複数辞典一括検索+![]()
![]()
てん【纏】🔗⭐🔉
てん【纏】
〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。
てん‐じょう【纏繞】‥ゼウ🔗⭐🔉
てん‐じょう【纏繞】‥ゼウ
まといつくこと。まきつくこと。
⇒てんじょう‐けい【纏繞茎】
てんじょう‐けい【纏繞茎】‥ゼウ‥🔗⭐🔉
てんじょう‐けい【纏繞茎】‥ゼウ‥
蔓になって他のものにまといつく茎。朝顔・藤などの茎の類。
⇒てん‐じょう【纏繞】
てん‐そく【纏足】🔗⭐🔉
てん‐そく【纏足】
中国で、女児が4〜5歳になった頃、足指に長い布帛を巻き、第1指(親指)以外の指を足裏に折り込むように固く縛って、大きくしないようにした風俗。唐末の頃から起こり、南宋頃から盛行。清の康 帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。
帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。
 帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。
帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。
てん‐ちゃく【纏着】🔗⭐🔉
てん‐ちゃく【纏着】
まといつくこと。纏繞てんじょう。
てん‐とう【纏頭】🔗⭐🔉
てん‐とう【纏頭】
(古くはテンドウ)
①歌舞・演芸などをした者に、褒美ほうびとして与えるもの。もとは衣服をぬいで与え、その頭に纏まとわせた。かずけもの。古今著聞集6「今夜の―は他の人に及ぶべからず、用枝一人にあるべし」
②当座の祝儀として与える金銭。はな。祝儀。
てん‐ばく【纏縛】🔗⭐🔉
てん‐ばく【纏縛】
①からみしばること。
②足手まとい。係累。
③〔仏〕衆生しゅじょうを迷いの世界につなぎとめるもの。煩悩のこと。
てん‐めん【纏綿】🔗⭐🔉
てん‐めん【纏綿】
①からみつくこと。まといつくこと。
②情緒が深く、こまやかで離れにくいさま。「情緒―」
はな【花・華】🔗⭐🔉
はな【花・華】
①
㋐被子植物の生殖器官で、雌しべ(子房)をもつことが特徴である。広義には種子植物の有性生殖にかかわる器官をいう。花は葉の変形である花葉と、茎の変形である花軸から成る。花被(萼と花冠)は形・色とも多様で、合弁花・離弁花があり、全く花被を欠くもの(裸花)もある。雄しべ・雌しべのそろった花を両性花、いずれか一方を欠くものを単性花という。なお、俗にコケなどの生殖器官を花ということもある。万葉集5「青柳梅との―を折りかざし」
花の構造
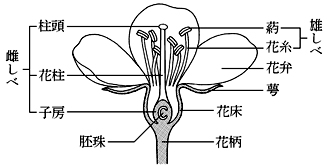 雌蕊
柱頭
花柱
子房
胚珠
雄蕊
葯
花糸
花弁
萼
花床
花柄
㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」
㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。
②1のようであること。また、そういうもの。
㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」
㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」
㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」
㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」
③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」
㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」
④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。
㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。
⑤いけばな。
⑥㋐「花合せ」の略。
㋑花札の略。
◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。
⇒花が咲く
⇒花と散る
⇒花に嵐
⇒花に風
⇒花は折りたし梢は高し
⇒花は桜木、人は武士
⇒花は根に鳥は故巣に
⇒花も恥じらう
⇒花も実も有る
⇒花より団子
⇒花を折る
⇒花を持たす
⇒花をやる
雌蕊
柱頭
花柱
子房
胚珠
雄蕊
葯
花糸
花弁
萼
花床
花柄
㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」
㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。
②1のようであること。また、そういうもの。
㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」
㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」
㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」
㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」
③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」
㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」
④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。
㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。
⑤いけばな。
⑥㋐「花合せ」の略。
㋑花札の略。
◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。
⇒花が咲く
⇒花と散る
⇒花に嵐
⇒花に風
⇒花は折りたし梢は高し
⇒花は桜木、人は武士
⇒花は根に鳥は故巣に
⇒花も恥じらう
⇒花も実も有る
⇒花より団子
⇒花を折る
⇒花を持たす
⇒花をやる
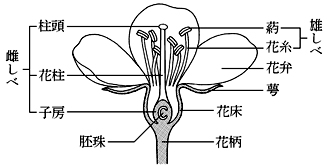 雌蕊
柱頭
花柱
子房
胚珠
雄蕊
葯
花糸
花弁
萼
花床
花柄
㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」
㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。
②1のようであること。また、そういうもの。
㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」
㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」
㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」
㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」
③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」
㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」
④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。
㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。
⑤いけばな。
⑥㋐「花合せ」の略。
㋑花札の略。
◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。
⇒花が咲く
⇒花と散る
⇒花に嵐
⇒花に風
⇒花は折りたし梢は高し
⇒花は桜木、人は武士
⇒花は根に鳥は故巣に
⇒花も恥じらう
⇒花も実も有る
⇒花より団子
⇒花を折る
⇒花を持たす
⇒花をやる
雌蕊
柱頭
花柱
子房
胚珠
雄蕊
葯
花糸
花弁
萼
花床
花柄
㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」
㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。
②1のようであること。また、そういうもの。
㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」
㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」
㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」
㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」
③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」
㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」
④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。
㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。
⑤いけばな。
⑥㋐「花合せ」の略。
㋑花札の略。
◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。
⇒花が咲く
⇒花と散る
⇒花に嵐
⇒花に風
⇒花は折りたし梢は高し
⇒花は桜木、人は武士
⇒花は根に鳥は故巣に
⇒花も恥じらう
⇒花も実も有る
⇒花より団子
⇒花を折る
⇒花を持たす
⇒花をやる
まき・ぬ【纏き寝】🔗⭐🔉
まき・ぬ【纏き寝】
〔自下二〕
互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」
まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥🔗⭐🔉
まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥
奈良盆地南東部、桜井市にある3〜4世紀の集落・墳墓遺跡。出土した多くの土器から東海・山陰・山陽地方との交流が推定される。
まきむく‐やま【巻向山・纏向山】🔗⭐🔉
まきむく‐やま【巻向山・纏向山】
奈良県中部、桜井市北部の山。標高567メートル。痛足あなし山。(歌枕)
まき‐も・つ【纏き持つ】🔗⭐🔉
まき‐も・つ【纏き持つ】
〔他四〕
手にまきつけて持つ。手にもつ。万葉集13「―・てる小鈴もゆらに」
ま・く【枕く・婚く・纏く】🔗⭐🔉
ま・く【枕く・婚く・纏く】
〔他四〕
①枕とする。古事記上「玉手さし―・きもも長に寝いをし寝なせ」
②(後にマグとも)抱いて寝る。共寝をする。結婚する。古事記中「誰をし―・かむ」。宇治拾遺物語9「人の妻―・くものあり」
まつ・う【纏ふ】マツフ🔗⭐🔉
まつ・う【纏ふ】マツフ
〔他四〕
「まとう」に同じ。
まつ・べる【集べる・纏べる】🔗⭐🔉
まつ・べる【集べる・纏べる】
〔他下一〕
一つにまとめる。あつめる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「沓見―・べて腰に付け」
まつ・む【集む・纏む】🔗⭐🔉
まつ・む【集む・纏む】
〔他下二〕
ひとところに集めそろえる。まとめる。〈日葡辞書〉
まつり‐ぐけ【纏り絎】🔗⭐🔉
まつり‐ぐけ【纏り絎】
布端の始末の方法。三つ折りにした布の折り山部分を、表布は小さくすくって針目が目立たないように絎縫いする。まつり縫い。
まつり‐ぬい【纏り縫い】‥ヌヒ🔗⭐🔉
まつり‐ぬい【纏り縫い】‥ヌヒ
(→)「まつりぐけ」に同じ。
まつ・る【纏る】🔗⭐🔉
まつ・る【纏る】
〔他五〕
布の端を折って、内側から外側に糸を回しながら縫いつける。
まつわ・す【纏はす】マツハス🔗⭐🔉
まつわ・す【纏はす】マツハス
〔他四〕
①まつわるようにする。源氏物語明石「ただ同じさまなる物のみ来つつ―・し聞ゆと見給ふ」
②絶えずつきまとわせる。栄華物語初花「たびたびよび―・し聞えたまひつつ」
まつわり‐つ・く【纏わり付く】マツハリ‥🔗⭐🔉
まつわり‐つ・く【纏わり付く】マツハリ‥
〔自五〕
物にからみつく。また、からむようにつきまとう。まといつく。まとわりつく。「クモの巣が体中に―・く」「母親に―・いて離れない」「脳裏に―・く」
まつわ・る【纏わる】マツハル🔗⭐🔉
まつわ・る【纏わる】マツハル
〔自五〕
(下二段にも活用)
①物にからみつく。まきつく。源氏物語夕顔「軒のつまなどに這ひ―・れたるを」。古今和歌集恋「唐衣なれば身にこそ―・れめ」。「裾が―・る」
②絶えずくっついていて離れない。まとわる。つきまとう。万葉集13「藤波の思ひ―・り」。「あの一件が頭に―・って眠れない」
③(からみついてほぐれない意から)筋が通らなくなる。わけがわからなくなる。日葡辞書「マツワッタコトヲイウ」
④関係する。関連する。「それに―・る話」
まとい【纏】マトヒ🔗⭐🔉
まとい【纏】マトヒ
①まとうこと。
②馬標うまじるしの一種。竿の頭に種々の飾りをつけ、多くはその下に馬簾ばれんを垂れた。
③江戸中期以降、纏2に模して作り、火消組の標しるしとしたもの。
纏
 ④纏持まといもちの略。
⇒まとい‐もち【纏持】
④纏持まといもちの略。
⇒まとい‐もち【纏持】
 ④纏持まといもちの略。
⇒まとい‐もち【纏持】
④纏持まといもちの略。
⇒まとい‐もち【纏持】
まとい‐つ・く【纏い付く】マトヒ‥🔗⭐🔉
まとい‐つ・く【纏い付く】マトヒ‥
〔自五〕
からまりつく。まつわりつく。
まとい‐もち【纏持】マトヒ‥🔗⭐🔉
まとい‐もち【纏持】マトヒ‥
火消し2のうち、纏を持つ役を勤めるもの。消し口の要路に立つのが普通。
⇒まとい【纏】
まと・う【纏う】マトフ🔗⭐🔉
まと・う【纏う】マトフ
[一]〔他五〕
①巻きつくようにする。巻きつかせる。からみつかせる。法華経天喜頃点「手・脚繚マトハれ戻もとれらむ」。宇治拾遺物語14「経頼が足を三返四返ばかり―・ひけり」
②身につける。「晴着を身に―・う」
[二]〔自四〕
巻きつく。からまる。からみつく。平家物語6「法衣自然に身に―・つて肩にかかり」
まとまり【纏り】🔗⭐🔉
まとまり【纏り】
まとまること。まとまったぐあい。「―のない話」「―がない集団」「―をつける」
まとま・る【纏まる】🔗⭐🔉
まとま・る【纏まる】
〔自五〕
①ばらばらだったものが、一つの整った状態のものになる。ひとかたまりになる。「意見が―・る」「―・って歩いて下さい」「―・った金を用意する」
②望ましい状態で成就する。決着がつく。完成する。「論文が―・る」「縁談が―・る」
まとめ‐やく【纏め役】🔗⭐🔉
まとめ‐やく【纏め役】
利害などの調整をして、事をスムーズに進行させる立場の人。「―に徹する」
まと・める【纏める】🔗⭐🔉
まと・める【纏める】
〔他下一〕[文]まと・む(下二)
①ばらばらだったものを一つの整った状態にする。「荷物を―・める」「意見を―・める」
②望ましい状態に成就させる。決着をつける。完成させる。「交渉を―・める」「考えを―・める」
まとわ・す【纏わす】マトハス🔗⭐🔉
まとわ・す【纏わす】マトハス
〔他五〕
①からまりつくようにする。
②馴れ親しんで付きまとうようにする。宇津保物語楼上上「この殿をば父こそとて睦まじう―・し奉り給ふ」
まとわり‐つ・く【纏わり付く】マトハリ‥🔗⭐🔉
まとわり‐つ・く【纏わり付く】マトハリ‥
〔自五〕
(→)「まつわりつく」に同じ。「足に―・く猫」
まとわ・る【纏はる】マトハル🔗⭐🔉
まとわ・る【纏はる】マトハル
〔自下二〕
①まきつく。からみつく。沙石集2「在世の蛇、池の中より出て仏の説法し給ふを草の根に―・れて聞く時に」
②絶えずくっついていて離れない。まつわる。元真集「秋霧のはれぬおもひに―・れて」
○的を射るまとをいる
物事の肝心な点を確実にとらえる。「的を射た発言」
⇒まと【的】
[漢]纏🔗⭐🔉
纏 字形
 〔糸部15画/21画/3727・453B〕
〔音〕テン(漢)
〔訓〕まとう・まとい
[意味]
①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」
②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。
▷[纒]は異体字。
〔糸部15画/21画/3727・453B〕
〔音〕テン(漢)
〔訓〕まとう・まとい
[意味]
①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」
②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。
▷[纒]は異体字。
 〔糸部15画/21画/3727・453B〕
〔音〕テン(漢)
〔訓〕まとう・まとい
[意味]
①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」
②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。
▷[纒]は異体字。
〔糸部15画/21画/3727・453B〕
〔音〕テン(漢)
〔訓〕まとう・まとい
[意味]
①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」
②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。
▷[纒]は異体字。
広辞苑に「纏」で始まるの検索結果 1-36。