複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (50)
おおやけ【公】オホ‥🔗⭐🔉
おおやけ【公】オホ‥
(「大宅」「大家」の意)
①天皇。皇后。中宮。伊勢物語「―思おぼして使う給ふ女」
②朝廷。政府。官庁。官事。蜻蛉日記下「―は八幡の祭のこととののしる」
③国家・社会または世間。孝徳紀「―の民とすべし」
④表だったこと。公然。「事が―になる」「―にする」
⑤私有でないこと。公共。公有。「―の施設」
⑥私心のないこと。公明。公正。難波物語「詞うるはしく、論―なり」
⑦金持。財産家。狂言、米市「こなたは―な事でござれば、少しばかりは出たのが無いと申す事はござるまい」
↔私わたくし。
⇒おおやけ‐がた【公方】
⇒おおやけ‐ごころ【公心】
⇒おおやけ‐ごと【公事】
⇒おおやけ‐ざた【公沙汰】
⇒おおやけ‐ざま【公様】
⇒おおやけ‐づかい【公使】
⇒おおやけ‐どころ【公所】
⇒おおやけ‐の‐しせつ【公の施設】
⇒おおやけ‐の‐わたくし【公の私】
⇒おおやけ‐ばら【公腹】
⇒おおやけ‐びと【公人】
⇒おおやけ‐もの【公物】
⇒おおやけ‐わざ【公業】
⇒おおやけ‐わたくし【公私】
おおやけ‐おおやけ・し【公公し】オホ‥オホ‥🔗⭐🔉
おおやけ‐おおやけ・し【公公し】オホ‥オホ‥
〔形シク〕
「おおやけし」を強めていう語。
おおやけ・し【公し】オホ‥🔗⭐🔉
おおやけ・し【公し】オホ‥
〔形シク〕
表だっている。格式ばっている。枕草子104「これはた―・しう唐めきてをかし」
おおやけ‐の‐しせつ【公の施設】オホ‥🔗⭐🔉
おおやけ‐の‐しせつ【公の施設】オホ‥
地方公共団体が、福祉増進の目的で住民のために設ける公共施設。運動場・公民館・図書館・公園など。
⇒おおやけ【公】
おおやけ‐の‐わたくし【公の私】オホ‥🔗⭐🔉
おおやけ‐の‐わたくし【公の私】オホ‥
公の事の中にも多少の私情を加える意。謡曲、俊寛「―といふことのあれば、せめては向ひの地までなりとも情にのせてたび給へ」
⇒おおやけ【公】
きみ【君・公】🔗⭐🔉
きみ【君・公】
[一]〔名〕
➊人のかみに立って支配する者。
①国家の元首。帝王。君主。万葉集18「天の日嗣と知らし来る―の御代御代」。源氏物語若菜下「次の―とならせ給ふべき御子」
②自分が仕える人。主人。主君。竹取物語「命を捨てても、おのが―の仰せ事をばかなへむ」
➋人を敬って言う語。
①自分に優越する人。(古語で男から女をいう時には、多くはこの意)古事記上「白玉の―が装ひしたふとくありけり」。万葉集8「わが―にわけは恋ふらし」
②女から男を、親しみをこめて言う語。古事記下「わがせの―は涙ぐましも」。古今和歌集序「―にけさあしたの霜のおきていなば」
③(「…の君」の形で)敬称的に使う。源氏物語紅葉賀「中将の―」。源氏物語若菜上「内侍のかんの―には」
➌古代の姓かばねの一つ。主として継体天皇以後の諸天皇の後裔と称する「公」姓の13氏は、天武天皇の時に真人まひとと賜姓され、八色姓やくさのかばねの第一等となった。「君」姓の者は多く朝臣あそみと賜姓。
➍遊女の異称。遊君。
[二]〔代〕
男の話し手が同輩以下の相手を指すのに使う語。あなた。おまえ。
⇒君君たらずとも、臣臣たらざるべからず
⇒君君たり、臣臣たり
⇒君辱めらるれば臣死す
⇒君は舟、臣は水
くえい‐でん【公営田】🔗⭐🔉
くえい‐でん【公営田】
平安初期の823年(弘仁14)、大宰府管内の諸国で試みられた国営の農場。口分田・剰田の良田の一部を、一般農民に種子・農具・食料などを支給して耕作させ、調・庸を免除するかわりに、全収穫を国家が収めた。石見・上総などでも行われた。↔私営田
く‐えん【公宴】🔗⭐🔉
く‐えん【公宴】
朝廷で行われる宴会。おおやけの宴会。平家物語1「それ雄剣を帯して―に列し」
く‐げ【公家】🔗⭐🔉
く‐げ【公家】
①おおやけ。朝廷。朝家。また、主上。天皇。保元物語(金刀比羅本)「―もつぱら日吉山王に御祈誓有りけるとかや」
②朝臣。公家衆。↔武家。
③(→)公卿くぎょう1に同じ。〈伊呂波字類抄〉
くげ‐あく【公家悪】🔗⭐🔉
くげ‐あく【公家悪】
歌舞伎の役柄。公家の悪役。「車引」の時平しへいなど。
くげ‐がた【公家方】🔗⭐🔉
くげ‐がた【公家方】
①(→)公家衆くげしゅうに同じ。
②朝廷に味方する人々。宮方。↔武家方
くげ‐こじつ【公家故実】🔗⭐🔉
くげ‐こじつ【公家故実】
公家に関する故実。↔武家故実
くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ🔗⭐🔉
くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ
公家に仕える侍。
くげ‐しゅう【公家衆】🔗⭐🔉
くげ‐しゅう【公家衆】
(クゲシュとも)幕府出仕の人に対して、朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。↔武家衆
くげ‐しょはっと【公家諸法度】🔗⭐🔉
くげ‐しょはっと【公家諸法度】
禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。
くげ‐はっと【公家法度】🔗⭐🔉
くげ‐はっと【公家法度】
禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。
くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン🔗⭐🔉
くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン
(コウケレツエイズカンとも)13世紀制作の絵巻。1巻。平安末期から鎌倉時代にかけての公家の姿を似絵にせえの技法で描いた肖像画集。
こう【公】🔗⭐🔉
こう【公】
(呉音はク)
①おおやけ。朝廷。官府。国家。
②社会。世間または衆人。おもてむき。
③主君。諸侯。貴人。
④周の五等の爵の第1位。方100里の地を領有。
⑤華族制度の五等爵の第1位。公爵。
⑥昔の大臣の称。また、大臣となった人につける敬称。「菅―」
⑦もと王公家軌範による公家を襲ついだ皇族待遇者。→公族。
⑧貴人などへの敬称。代名詞的にも用いる。
⑨名などの下につけて親しみまたはさげすみの意を表す。「忠犬ハチ―」
こう‐あん【公安】🔗⭐🔉
こう‐あん【公安】
公共の安寧。社会が安らかに治まること。
⇒こうあん‐いいんかい【公安委員会】
⇒こうあん‐じょうれい【公安条例】
⇒こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】
⇒こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】
こう‐あん【公案】🔗⭐🔉
こう‐あん【公案】
①公文書の下書。官府の調書。訴訟の目安めやす。
②禅宗で、参禅者に対して言葉で与える課題。先人の言行などを内容とする難問を与え、それを思考させることを通じて、とらわれの心から脱却させ悟りの世界に入らせることを目的とする。
③(転じて)工夫。思案。風姿花伝「―して思ふべし」
⇒こうあん‐ぜん【公案禅】
こうあん‐いいんかい【公安委員会】‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
こうあん‐いいんかい【公安委員会】‥ヰヰンクワイ
①(Comité de salut public フランス)フランス革命の際、1793年4月、国民公会が設けた執行機関。強大な権限をもち、恐怖政治を推進した一方、外敵の侵入を防ぐのに功があった。95年廃止。
②日本で、警察の民主的な運営を管理するため、1947年の警察法によって設置された機関。公安委員は国および各自治体の首長が議会の同意を得て民間人を任命する。→国家公安委員会→都道府県公安委員会→市町村公安委員会。
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐じょうれい【公安条例】‥デウ‥🔗⭐🔉
こうあん‐じょうれい【公安条例】‥デウ‥
地方公共団体の条例で、治安保持などの必要を理由に集会・集団行進・集団示威運動などを事前に規制する行政警察法規。1950年前後に大阪・京都・東京などで制定され違憲論をひきおこした。
東京都公安条例反対デモ(1949年)
提供:東京都
 ⇒こう‐あん【公安】
⇒こう‐あん【公安】
 ⇒こう‐あん【公安】
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‥ヰヰンクワイ
法務省の外局の一つ。破壊活動防止法の規定により、破壊的団体の規制に関する審査と決定を行う。
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐ぜん【公案禅】🔗⭐🔉
こうあん‐ぜん【公案禅】
公案を用いて正覚しょうがくに至らせようとする禅。主に臨済宗で用いられる。
⇒こう‐あん【公案】
こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】‥テウ‥チヤウ🔗⭐🔉
こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】‥テウ‥チヤウ
法務省の外局の一つ。破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査および処分の請求等に関する事務を行う。
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐は【公安派】🔗⭐🔉
こうあん‐は【公安派】
明末の文学流派。湖北公安県出身の袁宏道ら3兄弟が中心。李贄りしの影響を受け、当時流行していた古文辞派の復古主義に反対し、性霊の発露を重んじた。→竟陵きょうりょう派
こう‐いん【公印】🔗⭐🔉
こう‐いん【公印】
おおやけの印。官庁公署の印。「―偽造」
こう‐えい【公営】🔗⭐🔉
こう‐えい【公営】
公の機関が経営すること。特に、地方公共団体が経営または設置・管理すること。「―競馬」
⇒こうえい‐きぎょう【公営企業】
⇒こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ【公営企業金融公庫】
⇒こうえい‐きょうぎ【公営競技】
⇒こうえい‐じゅうたく【公営住宅】
⇒こうえい‐でん【公営田】
こうえい‐きぎょう【公営企業】‥ゲフ🔗⭐🔉
こうえい‐きぎょう【公営企業】‥ゲフ
(→)地方公営企業に同じ。
⇒こう‐えい【公営】
こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ【公営企業金融公庫】‥ゲフ‥🔗⭐🔉
こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ【公営企業金融公庫】‥ゲフ‥
政府保証付きの公営企業債券を発行し、公営事業のための資金調達が困難な地方公共団体に対して貸付を行う公庫。1957年設立。
⇒こう‐えい【公営】
こうえい‐きょうぎ【公営競技】‥キヤウ‥🔗⭐🔉
こうえい‐きょうぎ【公営競技】‥キヤウ‥
地方自治体が運営できる競技である競馬・自転車競走(競輪)・小型自動車競走(オートレース)・競艇の総称。
⇒こう‐えい【公営】
こうえい‐じゅうたく【公営住宅】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉
こうえい‐じゅうたく【公営住宅】‥ヂユウ‥
公営住宅法に基づき、地方公共団体が建設して、その住民に賃貸する住宅。
⇒こう‐えい【公営】
こうえい‐でん【公営田】🔗⭐🔉
こうえい‐でん【公営田】
⇒くえいでん
⇒こう‐えい【公営】
こう‐えき【公益】🔗⭐🔉
こう‐えき【公益】
国家または社会公共の利益。広く世人を益すること。↔私益。
⇒こうえき‐いいん【公益委員】
⇒こうえき‐さいりょう‐かいじ【公益裁量開示】
⇒こうえき‐じぎょう【公益事業】
⇒こうえき‐しちや【公益質屋】
⇒こうえき‐しんたく【公益信託】
⇒こうえき‐ほうじん【公益法人】
⇒こうえき‐りん【公益林】
こうえき‐いいん【公益委員】‥ヰヰン🔗⭐🔉
こうえき‐いいん【公益委員】‥ヰヰン
①労働委員会で公益を代表する委員。労働者委員および使用者委員の同意を得た候補者の中から一定数を任命する。
②一般に、各種の審議会等において、公益を代表する委員。
⇒こう‐えき【公益】
こうえき‐さいりょう‐かいじ【公益裁量開示】‥リヤウ‥🔗⭐🔉
こうえき‐さいりょう‐かいじ【公益裁量開示】‥リヤウ‥
情報公開法で、行政機関の長が公益上特に必要があると認めるときには、不開示情報についても裁量的に開示できるとする制度。
⇒こう‐えき【公益】
こうえき‐じぎょう【公益事業】‥ゲフ🔗⭐🔉
こうえき‐じぎょう【公益事業】‥ゲフ
公共の利益に関係し、公衆の日常生活に不可欠の事業。交通・電話・ガス・電気などの事業。
⇒こう‐えき【公益】
こうえき‐しちや【公益質屋】🔗⭐🔉
こうえき‐しちや【公益質屋】
市町村または社会福祉法人が公益のために経営する質屋。2000年廃止。
⇒こう‐えき【公益】
こうえき‐しんたく【公益信託】🔗⭐🔉
こうえき‐しんたく【公益信託】
福祉・教育・学術研究など公益的目的で設定される信託。公益財団法人と同じ作用を営む。
⇒こう‐えき【公益】
こうえき‐ほうじん【公益法人】‥ハフ‥🔗⭐🔉
こうえき‐ほうじん【公益法人】‥ハフ‥
民法上、慈善・学術・技芸その他の公益事業を目的とする社団や財団で、主務官庁の許可を得て法人となったもの。↔営利法人。
⇒こう‐えき【公益】
こうえき‐りん【公益林】🔗⭐🔉
こうえき‐りん【公益林】
国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全など公益的機能の確保を目的とする森林。水土保全林と、森林と人との共生林からなる。
⇒こう‐えき【公益】
こう‐えん【公宴】🔗⭐🔉
こう‐えん【公宴】
宮中で催される詩歌・管弦の会や宴。
こう‐えん【公園】‥ヱン🔗⭐🔉
こう‐えん【公園】‥ヱン
公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するため一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)とがある。
こう‐えん【公演】🔗⭐🔉
こう‐えん【公演】
公衆の面前で演劇・舞踊・音楽などを演ずること。「歌舞伎の―」「正月―」
こう‐とう【公稲】‥タウ🔗⭐🔉
こう‐とう【公稲】‥タウ
公有の稲。律令制で、田租その他の名目で徴収した稲を出挙すいこなどにあてるため国郡の倉に貯えたもの。
[漢]公🔗⭐🔉
公 字形
 筆順
筆順
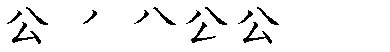 〔八部2画/4画/教育/2488・3878〕
〔音〕コウ(漢) ク(呉)
〔訓〕おおやけ・きみ (名)たか・いさお・きん・ただし
[意味]
①おおやけ。パブリック。(対)私。
㋐おもてむき。おおっぴら。「公然・公表・公言」
㋑(個人的でなく)社会一般。「公共・公衆・公器・公教育」
㋒朝廷。官庁。「義勇、公に奉じ」「公職・公家くげ・公文書」。特に、地方自治体。「公吏・公立」
②特定のものにかたよらない。「公平・公正・至公」
③おしなべて通じている。「公理・公約数」
④きみ。諸侯。国君。大臣。「公
〔八部2画/4画/教育/2488・3878〕
〔音〕コウ(漢) ク(呉)
〔訓〕おおやけ・きみ (名)たか・いさお・きん・ただし
[意味]
①おおやけ。パブリック。(対)私。
㋐おもてむき。おおっぴら。「公然・公表・公言」
㋑(個人的でなく)社会一般。「公共・公衆・公器・公教育」
㋒朝廷。官庁。「義勇、公に奉じ」「公職・公家くげ・公文書」。特に、地方自治体。「公吏・公立」
②特定のものにかたよらない。「公平・公正・至公」
③おしなべて通じている。「公理・公約数」
④きみ。諸侯。国君。大臣。「公 くぎょう・こうけい・桓公かんこう」
⑤五等爵の最上位。公爵。「公侯伯子男・西園寺さいおんじ公」
⑥他人に対する敬称。「貴公・尊公・楠公なんこう」
⑦人や動物の名前の下につけて、親しみや軽蔑けいべつを示す語。「熊くま公・雷公・ずべ公」
[解字]
会意。「八」(=左右に開く)+「厶」(=腕でかかえこむ。「私」の原字)。かかえこんだものを開いて見せる意。
[下ツキ
王公・郭公・貴公・愚公・君公・至公至平・十八公・主人公・相公・諸公・尊公・太公・乃公・土公・尼公・奉公・雷公・老公
[難読]
公孫樹いちょう・公達きんだち・公羊伝くようでん・公魚わかさぎ・公司コンス
くぎょう・こうけい・桓公かんこう」
⑤五等爵の最上位。公爵。「公侯伯子男・西園寺さいおんじ公」
⑥他人に対する敬称。「貴公・尊公・楠公なんこう」
⑦人や動物の名前の下につけて、親しみや軽蔑けいべつを示す語。「熊くま公・雷公・ずべ公」
[解字]
会意。「八」(=左右に開く)+「厶」(=腕でかかえこむ。「私」の原字)。かかえこんだものを開いて見せる意。
[下ツキ
王公・郭公・貴公・愚公・君公・至公至平・十八公・主人公・相公・諸公・尊公・太公・乃公・土公・尼公・奉公・雷公・老公
[難読]
公孫樹いちょう・公達きんだち・公羊伝くようでん・公魚わかさぎ・公司コンス
 筆順
筆順
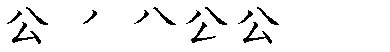 〔八部2画/4画/教育/2488・3878〕
〔音〕コウ(漢) ク(呉)
〔訓〕おおやけ・きみ (名)たか・いさお・きん・ただし
[意味]
①おおやけ。パブリック。(対)私。
㋐おもてむき。おおっぴら。「公然・公表・公言」
㋑(個人的でなく)社会一般。「公共・公衆・公器・公教育」
㋒朝廷。官庁。「義勇、公に奉じ」「公職・公家くげ・公文書」。特に、地方自治体。「公吏・公立」
②特定のものにかたよらない。「公平・公正・至公」
③おしなべて通じている。「公理・公約数」
④きみ。諸侯。国君。大臣。「公
〔八部2画/4画/教育/2488・3878〕
〔音〕コウ(漢) ク(呉)
〔訓〕おおやけ・きみ (名)たか・いさお・きん・ただし
[意味]
①おおやけ。パブリック。(対)私。
㋐おもてむき。おおっぴら。「公然・公表・公言」
㋑(個人的でなく)社会一般。「公共・公衆・公器・公教育」
㋒朝廷。官庁。「義勇、公に奉じ」「公職・公家くげ・公文書」。特に、地方自治体。「公吏・公立」
②特定のものにかたよらない。「公平・公正・至公」
③おしなべて通じている。「公理・公約数」
④きみ。諸侯。国君。大臣。「公 くぎょう・こうけい・桓公かんこう」
⑤五等爵の最上位。公爵。「公侯伯子男・西園寺さいおんじ公」
⑥他人に対する敬称。「貴公・尊公・楠公なんこう」
⑦人や動物の名前の下につけて、親しみや軽蔑けいべつを示す語。「熊くま公・雷公・ずべ公」
[解字]
会意。「八」(=左右に開く)+「厶」(=腕でかかえこむ。「私」の原字)。かかえこんだものを開いて見せる意。
[下ツキ
王公・郭公・貴公・愚公・君公・至公至平・十八公・主人公・相公・諸公・尊公・太公・乃公・土公・尼公・奉公・雷公・老公
[難読]
公孫樹いちょう・公達きんだち・公羊伝くようでん・公魚わかさぎ・公司コンス
くぎょう・こうけい・桓公かんこう」
⑤五等爵の最上位。公爵。「公侯伯子男・西園寺さいおんじ公」
⑥他人に対する敬称。「貴公・尊公・楠公なんこう」
⑦人や動物の名前の下につけて、親しみや軽蔑けいべつを示す語。「熊くま公・雷公・ずべ公」
[解字]
会意。「八」(=左右に開く)+「厶」(=腕でかかえこむ。「私」の原字)。かかえこんだものを開いて見せる意。
[下ツキ
王公・郭公・貴公・愚公・君公・至公至平・十八公・主人公・相公・諸公・尊公・太公・乃公・土公・尼公・奉公・雷公・老公
[難読]
公孫樹いちょう・公達きんだち・公羊伝くようでん・公魚わかさぎ・公司コンス
大辞林の検索結果 (49)
おお-やけ【公】🔗⭐🔉
おお-やけ オホ― [0] 【公】
〔「大家(オオヤケ)」「大宅(オオヤケ)」が原義〕
■一■ (名)
(1)政治や行政にたずさわる組織・機関。国・政府・地方公共団体など。古くは朝廷・幕府などをさす。「―の場で白黒をつける」「―の機関で管理する」
(2)個人ではなく,組織あるいは広く世間一般の人にかかわっていること。「土地を―の用に供する」「市長としての―の任務」
(3)事柄が外部に表れ出ること。表ざた。表むき。「目的は―にできない」
(4)天皇。また,皇后や中宮。「―も行幸せしめ給ふ/大鏡(時平)」
■二■ (形動ナリ)
私心がなく,公平であるさま。「詞うるはしく,論―なり/仮名草子・難波物語」
おおやけ=に する🔗⭐🔉
する🔗⭐🔉
――に する
世間一般に知らせる。公表する。また,表ざたにする。「新構想はまだ―
する
世間一般に知らせる。公表する。また,表ざたにする。「新構想はまだ― する段階ではない」
する段階ではない」
 する
世間一般に知らせる。公表する。また,表ざたにする。「新構想はまだ―
する
世間一般に知らせる。公表する。また,表ざたにする。「新構想はまだ― する段階ではない」
する段階ではない」
おおやけ=の秩序と善良の風俗🔗⭐🔉
――の秩序と善良の風俗
⇒公序良俗(コウジヨリヨウゾク)
おおやけ-の-うしろみ【公の後ろ見】🔗⭐🔉
おおやけ-の-うしろみ オホ― 【公の後ろ見】
天皇の政治を助けること。また,その人。摂政。関白。
おおやけ-の-わたくし【公の私】🔗⭐🔉
おおやけ-の-わたくし オホ― 【公の私】
公的なことにも,どうしても多少の私情をまじえてしまうこと。「うたてやな,―といふことのあれば/謡曲・俊寛」
おおやけ・し【公し】🔗⭐🔉
おおやけ・し オホヤケシ 【公し】 (形シク)
公式的である。公的で定まった型にはまっている。「さもありぬべき事ぞかしと,―・しう仰せられ/浜松中納言 4」
くえい-でん【公営田】🔗⭐🔉
くえい-でん [2] 【公営田】
〔「こうえいでん」とも〕
律令体制の弛緩(シカン)に対処して財源を確保するためにとられた国営の田制。班田農民の徭役(ヨウエキ)労働で耕作し,農民の調・庸を免除するかわりに全収穫を国家におさめた。のちには他国でも行われた。823年,大宰府管内に設定されたのが最初。
⇔私営田
く-げ【公家】🔗⭐🔉
く-げ [0] 【公家】
(1)朝廷に仕える身分の高い者。武家に対して朝臣一般をいう。公家衆。「お―さん」
→公卿(クギヨウ)
(2)おおやけ。朝廷。また,主上や天皇をもいう。「大乗妙経を―にさづけ奉り/平家 2」
くげ-あく【公家悪】🔗⭐🔉
くげ-あく [0] 【公家悪】
歌舞伎の役柄の一。公家の敵(カタキ)役。藍色(アイイロ)を主調とする隈(クマ)をとり,超人的で冷酷な性格をもつ。「暫(シバラク)」のウケなど。
くげ-かぞく【公家華族】🔗⭐🔉
くげ-かぞく ―クワゾク [3] 【公家華族】
もと公家で,明治維新後に華族になったもの。大名華族・武家華族に対していう。
くげ-がた【公家方】🔗⭐🔉
くげ-がた [0] 【公家方】
(1)「公家衆(クゲシユウ)」に同じ。
(2)朝廷の味方。公家側。大内方。
⇔武家方
くげ-こじつ【公家故実】🔗⭐🔉
くげ-こじつ [3] 【公家故実】
公家に関する故実。
⇔武家故実
くげ-ざむらい【公家侍】🔗⭐🔉
くげ-ざむらい ―ザムラヒ [3] 【公家侍】
公家に仕える侍。
くげ-しゅう【公家衆】🔗⭐🔉
くげ-しゅう [2] 【公家衆】
〔「くげしゅ」とも〕
武家に対し,朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。
くげ-しょはっと【公家諸法度】🔗⭐🔉
くげ-しょはっと 【公家諸法度】
「禁中並公家諸法度(キンチユウナラビニクゲシヨハツト)」の略。
こう【公】🔗⭐🔉
こう [1] 【公】
■一■ (名)
(1)おおやけ。おもてむき。官府。個人に対するもの。「―と私(シ)の別をわきまえる」「義勇,―に奉ずる」
(2)五等爵の第一位。公爵。
■二■ (代)
二人称。封建領主・大臣・身分の高い人など,また一般に他人を敬っていう語。また,同輩の者にも用いる。貴公。「―もっていかんとなす」
■三■ (接尾)
(1)身分の高い人の名に付けて,敬意を表す。「家康―」
(2)人や動物の名前に付けて,親しみ,あるいはやや軽んずる気持ちを表す。「忠犬ハチ―」「熊―」
こう-あん【公安】🔗⭐🔉
こう-あん [0] 【公安】
公共の安寧(アンネイ)。国家や社会の秩序が保たれていること。
こうあん-いいんかい【公安委員会】🔗⭐🔉
こうあん-いいんかい ―
 ンクワイ [6] 【公安委員会】
(1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし,1947年(昭和22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。
(2)フランス革命中の1793年4月,国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後,革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。
ンクワイ [6] 【公安委員会】
(1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし,1947年(昭和22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。
(2)フランス革命中の1793年4月,国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後,革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。

 ンクワイ [6] 【公安委員会】
(1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし,1947年(昭和22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。
(2)フランス革命中の1793年4月,国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後,革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。
ンクワイ [6] 【公安委員会】
(1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし,1947年(昭和22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。
(2)フランス革命中の1793年4月,国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後,革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。
こうあん-けいさつ【公安警察】🔗⭐🔉
こうあん-けいさつ [5] 【公安警察】
国家の秩序維持と安全のために,反体制的運動や組織を取り締まる警察活動。
→政治警察
こうあん-じょうれい【公安条例】🔗⭐🔉
こうあん-じょうれい ―デウ― [5] 【公安条例】
公共の秩序を維持する名目で,集会・デモなどの規制・取り締まりに関して地方公共団体が制定する条例の通称。事前の届け出または許可などを規制の内容とする。
こうあん-しょく【公安職】🔗⭐🔉
こうあん-しょく [3] 【公安職】
一般職公務員のうち,警察官・皇宮警察官・入国警備官および検察庁・公安調査庁・海上保安庁・刑務所・少年院に勤務する職員のこと。
こうあん-ちょうさ-ちょう【公安調査庁】🔗⭐🔉
こうあん-ちょうさ-ちょう ―テウサチヤウ [7] 【公安調査庁】
1952年(昭和27),破壊活動防止法により設けられた法務省の外局。暴力的破壊活動を行う団体の調査や解散指定の請求などを行う。その請求を審査・決定する機関として,公安審査委員会がある。
こう-あん【公案】🔗⭐🔉
こう-あん [0] 【公案】
(1)中国の役所の文書。調書。裁判記録。
(2)禅宗で,修行者が悟りを開くため,研究課題として与えられる問題。優れた修行者の言葉や事績から取られており,日常的思考を超えた世界に修行者を導くもの。
こう-いん【公印】🔗⭐🔉
こう-いん [0] 【公印】
官庁公署の印。おおやけの印。
こうえい-きぎょう【公営企業】🔗⭐🔉
こうえい-きぎょう ―ゲフ [5] 【公営企業】
地方公共団体の経営する企業。水道・鉄道・バスなどがある。
こうえい-けいば【公営競馬】🔗⭐🔉
こうえい-けいば [5] 【公営競馬】
⇒ちほうけいば(地方競馬)
こうえい-じゅうたく【公営住宅】🔗⭐🔉
こうえい-じゅうたく ―ヂユウ― [5] 【公営住宅】
地方公共団体が建設し,所得制限などの入居資格により住民に賃貸する住宅。1951年(昭和26)公布の公営住宅法に基づく。
こうえい-でん【公営田】🔗⭐🔉
こうえい-でん [3] 【公営田】
⇒くえいでん(公営田)
こうえい-とばく【公営賭博】🔗⭐🔉
こうえい-とばく [5] 【公営賭博】
地方公共団体が施行する競馬・競輪・競艇・オート-レース・宝くじの通称。それぞれに特別法がある。公営ギャンブル。
こうえき-いいん【公益委員】🔗⭐🔉
こうえき-いいん ―
 ン [5] 【公益委員】
(1)労働委員会で公益を代表する委員。労働大臣または都道府県知事が提示した候補者の中から,労使を代表する委員の同意を得て一定数が選ばれる。
(2)各種の審議会における公益を代表する委員。
ン [5] 【公益委員】
(1)労働委員会で公益を代表する委員。労働大臣または都道府県知事が提示した候補者の中から,労使を代表する委員の同意を得て一定数が選ばれる。
(2)各種の審議会における公益を代表する委員。

 ン [5] 【公益委員】
(1)労働委員会で公益を代表する委員。労働大臣または都道府県知事が提示した候補者の中から,労使を代表する委員の同意を得て一定数が選ばれる。
(2)各種の審議会における公益を代表する委員。
ン [5] 【公益委員】
(1)労働委員会で公益を代表する委員。労働大臣または都道府県知事が提示した候補者の中から,労使を代表する委員の同意を得て一定数が選ばれる。
(2)各種の審議会における公益を代表する委員。
こうえき-じぎょう【公益事業】🔗⭐🔉
こうえき-じぎょう ―ゲフ [5] 【公益事業】
公衆の日常生活に不可欠な,鉄道・電話・水道・ガス・電気・医療など,公共の利益に関する事業。
こうえき-しせつ【公益施設】🔗⭐🔉
こうえき-しせつ [5] 【公益施設】
公益事業として運営される施設。電気・ガス・水道・電信・鉄道・医療などの施設。
こうえき-しちや【公益質屋】🔗⭐🔉
こうえき-しちや [6] 【公益質屋】
市町村または社会福祉法人が庶民金融の便宜のために経営する質屋。公益質屋法の規制を受け,国庫の補助がある。公設質屋。
こうえき-しんたく【公益信託】🔗⭐🔉
こうえき-しんたく [5] 【公益信託】
個人や法人が財産を一定の公益目的に使うため信託すること。信託法に規定。
こうえき-ほうじん【公益法人】🔗⭐🔉
こうえき-ほうじん ―ハフ― [5] 【公益法人】
祭祀(サイシ)・宗教・学術・技芸その他の公益を目的とする非営利法人。社団法人と財団法人とがある。
⇔営利法人
こう-えん【公園】🔗⭐🔉
こう-えん ― ン [0] 【公園】
(1)〔「公苑」と書く施設もある〕
主に市街地またはその周辺に設けられ,市民が休息したり散歩したりできる公共の庭園。
(2)観光や自然保護のために指定されている地域。国立公園や県立自然公園など。
ン [0] 【公園】
(1)〔「公苑」と書く施設もある〕
主に市街地またはその周辺に設けられ,市民が休息したり散歩したりできる公共の庭園。
(2)観光や自然保護のために指定されている地域。国立公園や県立自然公園など。
 ン [0] 【公園】
(1)〔「公苑」と書く施設もある〕
主に市街地またはその周辺に設けられ,市民が休息したり散歩したりできる公共の庭園。
(2)観光や自然保護のために指定されている地域。国立公園や県立自然公園など。
ン [0] 【公園】
(1)〔「公苑」と書く施設もある〕
主に市街地またはその周辺に設けられ,市民が休息したり散歩したりできる公共の庭園。
(2)観光や自然保護のために指定されている地域。国立公園や県立自然公園など。
こう-えん【公演】🔗⭐🔉
こう-えん [0] 【公演】 (名)スル
多数の観客の前で,演芸・音楽などを演ずること。
こう-か【公家】🔗⭐🔉
こう-か [1] 【公家】
おおやけ。朝廷。朝家。こうけ。
こう-とう【公稲】🔗⭐🔉
こう-とう ―タウ [0] 【公稲】
官に納める稲。律令制で,租税として徴収した稲を出挙(スイコ)などにあてるために貯えたもの。官稲。
くげ【公家】(和英)🔗⭐🔉
くげ【公家】
a court noble.
こうあん【公安】(和英)🔗⭐🔉
こうあん【公安】
public peace[safety].‖公安委員(会) a public safety commissioner (commission).公安官《鉄道》a public security officer.公安条令 the Public Safety Regulations.
こうえき【公益】(和英)🔗⭐🔉
こうえき【公益】
the public good[interest,benefit].‖公益事業 public utilities.公益法人 a public service corporation.
こうえん【公園】(和英)🔗⭐🔉
こうえん【公演】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「公」で始まるの検索結果。もっと読み込む