複数辞典一括検索+![]()
![]()
們 たち🔗⭐🔉
【們】
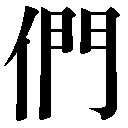 10画 人部
区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC
《音読み》 モン
10画 人部
区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC
《音読み》 モン /ボン
/ボン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 たち/ら
《意味》
{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」
《解字》
形声。「人+音符門」。
n〉
《訓読み》 たち/ら
《意味》
{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」
《解字》
形声。「人+音符門」。
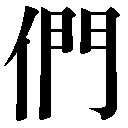 10画 人部
区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC
《音読み》 モン
10画 人部
区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC
《音読み》 モン /ボン
/ボン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 たち/ら
《意味》
{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」
《解字》
形声。「人+音符門」。
n〉
《訓読み》 たち/ら
《意味》
{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」
《解字》
形声。「人+音符門」。
太刀 タチ🔗⭐🔉
【太刀】
タチ〔国〕 刀剣の総称。
刀剣の総称。 腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。
腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。
 刀剣の総称。
刀剣の総称。 腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。
腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。
資 たち🔗⭐🔉
【資】
 13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
 {名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
 {名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
 {名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
 シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
 シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ)
シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ) 茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
 {名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
 {名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
 {名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
 シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
 シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ)
シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ) 茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
質 たち🔗⭐🔉
【質】
 15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
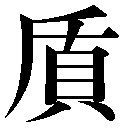 11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》
11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》  シツ
シツ /シチ
/シチ 〈zh
〈zh 〉/
〉/ チ
チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》

 {名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
 {名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
 {名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
 シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕
シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

 {名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
 チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ)
チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ) 緻チ(きめ細かくなかみがつまる)
緻チ(きめ細かくなかみがつまる) 室シツ(つまったへや)
室シツ(つまったへや) 窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
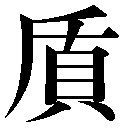 11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》
11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》  シツ
シツ /シチ
/シチ 〈zh
〈zh 〉/
〉/ チ
チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》

 {名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
 {名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
 {名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
 シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕
シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

 {名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
 チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ)
チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ) 緻チ(きめ細かくなかみがつまる)
緻チ(きめ細かくなかみがつまる) 室シツ(つまったへや)
室シツ(つまったへや) 窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
館 たち🔗⭐🔉
【館】
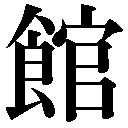 16画 食部 [三年]
区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9
【舘】異体字異体字
16画 食部 [三年]
区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9
【舘】異体字異体字
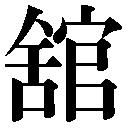 16画 舌部
区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク
16画 舌部
区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク ン)
ン)
 〈gu
〈gu n〉
《訓読み》 やかた/たち/たて
《名付け》 いえ・たて
《意味》
n〉
《訓読み》 やかた/たち/たて
《名付け》 いえ・たて
《意味》
 {名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕
{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕
 {名}やど。やどや。「旅館」
{名}やど。やどや。「旅館」
 {名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」
{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」
 {名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」
{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」
 カンス{動}やかたや役所を設ける。
カンス{動}やかたや役所を設ける。
 カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕
〔国〕
カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕
〔国〕 やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。
やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。 やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。
やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。 たち・たて。小規模な城。とりで。
《解字》
会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。
《単語家族》
完カン(まるく囲む)
たち・たて。小規模な城。とりで。
《解字》
会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。
《単語家族》
完カン(まるく囲む) 院(へいで囲んだ家)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
院(へいで囲んだ家)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
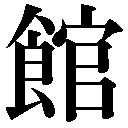 16画 食部 [三年]
区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9
【舘】異体字異体字
16画 食部 [三年]
区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9
【舘】異体字異体字
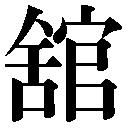 16画 舌部
区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク
16画 舌部
区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク ン)
ン)
 〈gu
〈gu n〉
《訓読み》 やかた/たち/たて
《名付け》 いえ・たて
《意味》
n〉
《訓読み》 やかた/たち/たて
《名付け》 いえ・たて
《意味》
 {名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕
{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕
 {名}やど。やどや。「旅館」
{名}やど。やどや。「旅館」
 {名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」
{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」
 {名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」
{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」
 カンス{動}やかたや役所を設ける。
カンス{動}やかたや役所を設ける。
 カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕
〔国〕
カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕
〔国〕 やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。
やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。 やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。
やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。 たち・たて。小規模な城。とりで。
《解字》
会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。
《単語家族》
完カン(まるく囲む)
たち・たて。小規模な城。とりで。
《解字》
会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。
《単語家族》
完カン(まるく囲む) 院(へいで囲んだ家)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
院(へいで囲んだ家)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「たち」で完全一致するの検索結果 1-5。