複数辞典一括検索+![]()
![]()
亜 つぐ🔗⭐🔉
【亜】
 7画 二部 [常用漢字]
区点=1601 16進=3021 シフトJIS=889F
【亞】旧字人名に使える旧字
7画 二部 [常用漢字]
区点=1601 16進=3021 シフトJIS=889F
【亞】旧字人名に使える旧字
 8画 二部
区点=4819 16進=5033 シフトJIS=98B1
《常用音訓》ア
《音読み》 ア
8画 二部
区点=4819 16進=5033 シフトJIS=98B1
《常用音訓》ア
《音読み》 ア /エ
/エ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 つぎ・つぐ
《意味》
〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 つぎ・つぐ
《意味》
 {動}つぐ。表面に出ずに下になる。
{動}つぐ。表面に出ずに下になる。
 {形}主たるものの下になり、それにつぐ地位にある。第二位である。「亜流」「亜聖」
{形}主たるものの下になり、それにつぐ地位にある。第二位である。「亜流」「亜聖」
 {助}人の称呼につく接頭辞。〈同義語〉→阿。「亜父アフ/アホ」「亜母アボ」
{助}人の称呼につく接頭辞。〈同義語〉→阿。「亜父アフ/アホ」「亜母アボ」
 {名}アジアのこと。▽「亜細亜」の略。「東亜」
《解字》
{名}アジアのこと。▽「亜細亜」の略。「東亜」
《解字》
 象形。建物や墓をつくるために地下に四角く掘った土台を描いたもので、表に出ない下のささえの意から、転じて、つぐことを意味する。堊ア(建物の土台となる粘土)の原字。また、下でつかえるの意を派生し、唖ア(のどがつかえてしゃべることが出来ない。)・惡アク・オ(=悪。胸がつかえるいやな気持ち)に含まれる。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。建物や墓をつくるために地下に四角く掘った土台を描いたもので、表に出ない下のささえの意から、転じて、つぐことを意味する。堊ア(建物の土台となる粘土)の原字。また、下でつかえるの意を派生し、唖ア(のどがつかえてしゃべることが出来ない。)・惡アク・オ(=悪。胸がつかえるいやな気持ち)に含まれる。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 二部 [常用漢字]
区点=1601 16進=3021 シフトJIS=889F
【亞】旧字人名に使える旧字
7画 二部 [常用漢字]
区点=1601 16進=3021 シフトJIS=889F
【亞】旧字人名に使える旧字
 8画 二部
区点=4819 16進=5033 シフトJIS=98B1
《常用音訓》ア
《音読み》 ア
8画 二部
区点=4819 16進=5033 シフトJIS=98B1
《常用音訓》ア
《音読み》 ア /エ
/エ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 つぎ・つぐ
《意味》
〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 つぎ・つぐ
《意味》
 {動}つぐ。表面に出ずに下になる。
{動}つぐ。表面に出ずに下になる。
 {形}主たるものの下になり、それにつぐ地位にある。第二位である。「亜流」「亜聖」
{形}主たるものの下になり、それにつぐ地位にある。第二位である。「亜流」「亜聖」
 {助}人の称呼につく接頭辞。〈同義語〉→阿。「亜父アフ/アホ」「亜母アボ」
{助}人の称呼につく接頭辞。〈同義語〉→阿。「亜父アフ/アホ」「亜母アボ」
 {名}アジアのこと。▽「亜細亜」の略。「東亜」
《解字》
{名}アジアのこと。▽「亜細亜」の略。「東亜」
《解字》
 象形。建物や墓をつくるために地下に四角く掘った土台を描いたもので、表に出ない下のささえの意から、転じて、つぐことを意味する。堊ア(建物の土台となる粘土)の原字。また、下でつかえるの意を派生し、唖ア(のどがつかえてしゃべることが出来ない。)・惡アク・オ(=悪。胸がつかえるいやな気持ち)に含まれる。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。建物や墓をつくるために地下に四角く掘った土台を描いたもので、表に出ない下のささえの意から、転じて、つぐことを意味する。堊ア(建物の土台となる粘土)の原字。また、下でつかえるの意を派生し、唖ア(のどがつかえてしゃべることが出来ない。)・惡アク・オ(=悪。胸がつかえるいやな気持ち)に含まれる。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
嗣 つぐ🔗⭐🔉
【嗣】
 13画 口部 [常用漢字]
区点=2744 16進=3B4C シフトJIS=8E6B
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
13画 口部 [常用漢字]
区点=2744 16進=3B4C シフトJIS=8E6B
《常用音訓》シ
《音読み》 シ /ジ
/ジ 〈s
〈s 〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 さね・つぎ・つぐ・ひで
《意味》
〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 さね・つぎ・つぐ・ひで
《意味》
 {動}つぐ。なくなった人のあとをつぐ。家系や家業を相続する。「継嗣」「今吾嗣為之十二年=今吾嗣イデコレヲ為スコト十二年ナリ」〔→柳宗元〕
{動}つぐ。なくなった人のあとをつぐ。家系や家業を相続する。「継嗣」「今吾嗣為之十二年=今吾嗣イデコレヲ為スコト十二年ナリ」〔→柳宗元〕
 {名}あとつぎ。「後嗣」「太子君嗣也、不可施刑=太子ハ君ノ嗣ナリ、刑ヲ施スベカラズ」〔→史記〕
《解字》
形声。左側は「口+册(たけふだ)」から成り、あとつぎをたてるいきさつを短冊に記し、神前に口で報告することを示す。嗣は、それに音をあらわすだけの司をそえたもの。
《単語家族》
子(こども)と同系。また、司(つかさどる)と同系のことばと考えれば、先人の遺業をつかさどることとも解せられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}あとつぎ。「後嗣」「太子君嗣也、不可施刑=太子ハ君ノ嗣ナリ、刑ヲ施スベカラズ」〔→史記〕
《解字》
形声。左側は「口+册(たけふだ)」から成り、あとつぎをたてるいきさつを短冊に記し、神前に口で報告することを示す。嗣は、それに音をあらわすだけの司をそえたもの。
《単語家族》
子(こども)と同系。また、司(つかさどる)と同系のことばと考えれば、先人の遺業をつかさどることとも解せられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 口部 [常用漢字]
区点=2744 16進=3B4C シフトJIS=8E6B
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
13画 口部 [常用漢字]
区点=2744 16進=3B4C シフトJIS=8E6B
《常用音訓》シ
《音読み》 シ /ジ
/ジ 〈s
〈s 〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 さね・つぎ・つぐ・ひで
《意味》
〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 さね・つぎ・つぐ・ひで
《意味》
 {動}つぐ。なくなった人のあとをつぐ。家系や家業を相続する。「継嗣」「今吾嗣為之十二年=今吾嗣イデコレヲ為スコト十二年ナリ」〔→柳宗元〕
{動}つぐ。なくなった人のあとをつぐ。家系や家業を相続する。「継嗣」「今吾嗣為之十二年=今吾嗣イデコレヲ為スコト十二年ナリ」〔→柳宗元〕
 {名}あとつぎ。「後嗣」「太子君嗣也、不可施刑=太子ハ君ノ嗣ナリ、刑ヲ施スベカラズ」〔→史記〕
《解字》
形声。左側は「口+册(たけふだ)」から成り、あとつぎをたてるいきさつを短冊に記し、神前に口で報告することを示す。嗣は、それに音をあらわすだけの司をそえたもの。
《単語家族》
子(こども)と同系。また、司(つかさどる)と同系のことばと考えれば、先人の遺業をつかさどることとも解せられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}あとつぎ。「後嗣」「太子君嗣也、不可施刑=太子ハ君ノ嗣ナリ、刑ヲ施スベカラズ」〔→史記〕
《解字》
形声。左側は「口+册(たけふだ)」から成り、あとつぎをたてるいきさつを短冊に記し、神前に口で報告することを示す。嗣は、それに音をあらわすだけの司をそえたもの。
《単語家族》
子(こども)と同系。また、司(つかさどる)と同系のことばと考えれば、先人の遺業をつかさどることとも解せられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
接 つぐ🔗⭐🔉
【接】
 11画
11画  部 [五年]
区点=3260 16進=405C シフトJIS=90DA
《常用音訓》セツ/つ…ぐ
《音読み》 セツ
部 [五年]
区点=3260 16進=405C シフトJIS=90DA
《常用音訓》セツ/つ…ぐ
《音読み》 セツ /ショウ(セフ)
/ショウ(セフ)
 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 まじわる(まじはる)/つぐ/うける(うく)
《名付け》 つぎ・つぐ・つら・もち
《意味》
〉
《訓読み》 まじわる(まじはる)/つぐ/うける(うく)
《名付け》 つぎ・つぐ・つら・もち
《意味》
 セッス{動}くっつく。「直接」「首尾相接=首尾相ヒ接ス」「兵刃既接=兵刃既ニ接ス」〔→孟子〕
セッス{動}くっつく。「直接」「首尾相接=首尾相ヒ接ス」「兵刃既接=兵刃既ニ接ス」〔→孟子〕
 セッス{動}人と会う。交わる。ふれあう。「接待」「其接也以礼=ソノ接スルヤ礼ヲモッテス」〔→孟子〕
セッス{動}人と会う。交わる。ふれあう。「接待」「其接也以礼=ソノ接スルヤ礼ヲモッテス」〔→孟子〕
 セッス{動}まじわる(マジハル)。おすとめすとが交接する。
セッス{動}まじわる(マジハル)。おすとめすとが交接する。
 セッス{動}つぐ。つなぐ。また、後者が前者にくっついてつながる。〈類義語〉→続。「接続」「接踵而至=踵ヲ接イデ至ル」
セッス{動}つぐ。つなぐ。また、後者が前者にくっついてつながる。〈類義語〉→続。「接続」「接踵而至=踵ヲ接イデ至ル」
 セッス{動}うける(ウク)。ひきとる。やって来るものをうけとる。また、うけつぐ。「接受」「仰手接飛鳶=手ヲ仰ケテ飛鳶ヲ接ク」〔→曹植〕
セッス{動}うける(ウク)。ひきとる。やって来るものをうけとる。また、うけつぐ。「接受」「仰手接飛鳶=手ヲ仰ケテ飛鳶ヲ接ク」〔→曹植〕
 {動}〔俗〕出迎えて人と会う。「迎接」
《解字》
会意兼形声。妾ショウは「辛(はもの)+女」からなる会意文字で、刃物で入れ墨をした女どれいのこと。もっぱら男と交接し接待する女であった。接は「手+音符妾」で、相手とくっつく動作を示す。▽セツは、促音語尾pをツと書きあらわしたためのなまり。
《類義》
→継
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動}〔俗〕出迎えて人と会う。「迎接」
《解字》
会意兼形声。妾ショウは「辛(はもの)+女」からなる会意文字で、刃物で入れ墨をした女どれいのこと。もっぱら男と交接し接待する女であった。接は「手+音符妾」で、相手とくっつく動作を示す。▽セツは、促音語尾pをツと書きあらわしたためのなまり。
《類義》
→継
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 11画
11画  部 [五年]
区点=3260 16進=405C シフトJIS=90DA
《常用音訓》セツ/つ…ぐ
《音読み》 セツ
部 [五年]
区点=3260 16進=405C シフトJIS=90DA
《常用音訓》セツ/つ…ぐ
《音読み》 セツ /ショウ(セフ)
/ショウ(セフ)
 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 まじわる(まじはる)/つぐ/うける(うく)
《名付け》 つぎ・つぐ・つら・もち
《意味》
〉
《訓読み》 まじわる(まじはる)/つぐ/うける(うく)
《名付け》 つぎ・つぐ・つら・もち
《意味》
 セッス{動}くっつく。「直接」「首尾相接=首尾相ヒ接ス」「兵刃既接=兵刃既ニ接ス」〔→孟子〕
セッス{動}くっつく。「直接」「首尾相接=首尾相ヒ接ス」「兵刃既接=兵刃既ニ接ス」〔→孟子〕
 セッス{動}人と会う。交わる。ふれあう。「接待」「其接也以礼=ソノ接スルヤ礼ヲモッテス」〔→孟子〕
セッス{動}人と会う。交わる。ふれあう。「接待」「其接也以礼=ソノ接スルヤ礼ヲモッテス」〔→孟子〕
 セッス{動}まじわる(マジハル)。おすとめすとが交接する。
セッス{動}まじわる(マジハル)。おすとめすとが交接する。
 セッス{動}つぐ。つなぐ。また、後者が前者にくっついてつながる。〈類義語〉→続。「接続」「接踵而至=踵ヲ接イデ至ル」
セッス{動}つぐ。つなぐ。また、後者が前者にくっついてつながる。〈類義語〉→続。「接続」「接踵而至=踵ヲ接イデ至ル」
 セッス{動}うける(ウク)。ひきとる。やって来るものをうけとる。また、うけつぐ。「接受」「仰手接飛鳶=手ヲ仰ケテ飛鳶ヲ接ク」〔→曹植〕
セッス{動}うける(ウク)。ひきとる。やって来るものをうけとる。また、うけつぐ。「接受」「仰手接飛鳶=手ヲ仰ケテ飛鳶ヲ接ク」〔→曹植〕
 {動}〔俗〕出迎えて人と会う。「迎接」
《解字》
会意兼形声。妾ショウは「辛(はもの)+女」からなる会意文字で、刃物で入れ墨をした女どれいのこと。もっぱら男と交接し接待する女であった。接は「手+音符妾」で、相手とくっつく動作を示す。▽セツは、促音語尾pをツと書きあらわしたためのなまり。
《類義》
→継
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動}〔俗〕出迎えて人と会う。「迎接」
《解字》
会意兼形声。妾ショウは「辛(はもの)+女」からなる会意文字で、刃物で入れ墨をした女どれいのこと。もっぱら男と交接し接待する女であった。接は「手+音符妾」で、相手とくっつく動作を示す。▽セツは、促音語尾pをツと書きあらわしたためのなまり。
《類義》
→継
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
更 つぐ🔗⭐🔉
【更】
 7画 曰部 [常用漢字]
区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58
《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける
《音読み》 コウ(カウ)
7画 曰部 [常用漢字]
区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58
《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける
《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)
/キョウ(キャウ) 〈g
〈g ng・g
ng・g ng〉
《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)
《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ
《意味》
ng〉
《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)
《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ
《意味》
 {動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕
{動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕
 {動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」
{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」
 {動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」
{動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」
 {副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」
{副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」
 {副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕
{副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕
 {副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。
{副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。
 {動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」
{動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」
 {名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕
{名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕
 {名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj
{名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj ngと読む。
ngと読む。
 {名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。
〔国〕
{名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。
〔国〕 さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」
さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」 いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」
いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」 ふける(フク)。夜がおそくなる。
《解字》
ふける(フク)。夜がおそくなる。
《解字》
 会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。
《類義》
→代
《異字同訓》
ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。
《類義》
→代
《異字同訓》
ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 7画 曰部 [常用漢字]
区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58
《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける
《音読み》 コウ(カウ)
7画 曰部 [常用漢字]
区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58
《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける
《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)
/キョウ(キャウ) 〈g
〈g ng・g
ng・g ng〉
《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)
《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ
《意味》
ng〉
《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)
《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ
《意味》
 {動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕
{動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕
 {動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」
{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」
 {動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」
{動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」
 {副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」
{副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」
 {副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕
{副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕
 {副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。
{副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。
 {動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」
{動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」
 {名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕
{名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕
 {名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj
{名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj ngと読む。
ngと読む。
 {名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。
〔国〕
{名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。
〔国〕 さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」
さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」 いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」
いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」 ふける(フク)。夜がおそくなる。
《解字》
ふける(フク)。夜がおそくなる。
《解字》
 会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。
《類義》
→代
《異字同訓》
ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。
《類義》
→代
《異字同訓》
ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
椄 つぐ🔗⭐🔉
【椄】
 12画 木部
区点=6006 16進=5C26 シフトJIS=9EA4
《音読み》 ショウ(セフ)
12画 木部
区点=6006 16進=5C26 シフトJIS=9EA4
《音読み》 ショウ(セフ)
 /セツ
/セツ 《訓読み》 つぐ/つぎき
《意味》
{動・名}つぐ。つぎき。木をつぎ合わせる。また、つぎ合わせた木。
《解字》
会意兼形声。「木+音符妾ショウ」。妾は男の性器をさしこむあいて、女奴隷。椄は、木に枝をさしこんでつなぐこと。
《訓読み》 つぐ/つぎき
《意味》
{動・名}つぐ。つぎき。木をつぎ合わせる。また、つぎ合わせた木。
《解字》
会意兼形声。「木+音符妾ショウ」。妾は男の性器をさしこむあいて、女奴隷。椄は、木に枝をさしこんでつなぐこと。
 12画 木部
区点=6006 16進=5C26 シフトJIS=9EA4
《音読み》 ショウ(セフ)
12画 木部
区点=6006 16進=5C26 シフトJIS=9EA4
《音読み》 ショウ(セフ)
 /セツ
/セツ 《訓読み》 つぐ/つぎき
《意味》
{動・名}つぐ。つぎき。木をつぎ合わせる。また、つぎ合わせた木。
《解字》
会意兼形声。「木+音符妾ショウ」。妾は男の性器をさしこむあいて、女奴隷。椄は、木に枝をさしこんでつなぐこと。
《訓読み》 つぐ/つぎき
《意味》
{動・名}つぐ。つぎき。木をつぎ合わせる。また、つぎ合わせた木。
《解字》
会意兼形声。「木+音符妾ショウ」。妾は男の性器をさしこむあいて、女奴隷。椄は、木に枝をさしこんでつなぐこと。
次 つぐ🔗⭐🔉
【次】
 6画 欠部 [三年]
区点=2801 16進=3C21 シフトJIS=8E9F
《常用音訓》シ/ジ/つぎ/つ…ぐ
《音読み》 ジ
6画 欠部 [三年]
区点=2801 16進=3C21 シフトJIS=8E9F
《常用音訓》シ/ジ/つぎ/つ…ぐ
《音読み》 ジ /シ
/シ
 〈c
〈c 〉
《訓読み》 つぎ/つぐ/つぎに/ついで/やどる/とまる
《名付け》 ちか・つぎ・つぐ・ひで・やどる
《意味》
〉
《訓読み》 つぎ/つぐ/つぎに/ついで/やどる/とまる
《名付け》 ちか・つぎ・つぐ・ひで・やどる
《意味》
 {名}つぎ。並んだもののうち、はじめのもののつぎ。「次年」「敢問其次=アヘテソノ次ヲ問フ」〔→論語〕
{名}つぎ。並んだもののうち、はじめのもののつぎ。「次年」「敢問其次=アヘテソノ次ヲ問フ」〔→論語〕
 {動}つぐ。第一のものの下に位する。また、第一のもののあとに続く。「君又次之=君マタコレニ次グ」「相次去世=アヒ次イデ世ヲ去ル」
{動}つぐ。第一のものの下に位する。また、第一のもののあとに続く。「君又次之=君マタコレニ次グ」「相次去世=アヒ次イデ世ヲ去ル」
 {副}つぎに。ついで。そのあとに続いて。「次叙病心=次ニ病ム心ヲ叙ス」〔→白居易〕
{副}つぎに。ついで。そのあとに続いて。「次叙病心=次ニ病ム心ヲ叙ス」〔→白居易〕
 {名}順序。「序次」「班次(並べた順序)」「以次進至陛=次ヲモッテ進ミ陛ニ至ル」〔→史記〕
{名}順序。「序次」「班次(並べた順序)」「以次進至陛=次ヲモッテ進ミ陛ニ至ル」〔→史記〕
 {単位}物事の回数・度数を数えるときのことば。また、物事の順序をあらわすことば。「数次(数回)」
{単位}物事の回数・度数を数えるときのことば。また、物事の順序をあらわすことば。「数次(数回)」
 {名}ある行為をしたとき。そのさい。「参内之次サンダイノジ(宮中にまいったとき)」
{名}ある行為をしたとき。そのさい。「参内之次サンダイノジ(宮中にまいったとき)」
 ジス{動}やどる。とまる。もと、軍隊がざっと部署をととのえて宿営する。また、旅の間に一日だけとまる。「旅次(宿屋。また、旅の途上)」「師退次于召陵=師退キテ召陵ニ次ル」〔→左伝〕
ジス{動}やどる。とまる。もと、軍隊がざっと部署をととのえて宿営する。また、旅の間に一日だけとまる。「旅次(宿屋。また、旅の途上)」「師退次于召陵=師退キテ召陵ニ次ル」〔→左伝〕
 {名}星のとまる星座。また広く物のやどる場所。「胸次(むねのところ)」「席次(席のある所)」
{名}星のとまる星座。また広く物のやどる場所。「胸次(むねのところ)」「席次(席のある所)」
 「造次」とは、そそくさと物をかたづけたり、あつらえたりすることから、あわただしい短時間のこと。
《解字》
「造次」とは、そそくさと物をかたづけたり、あつらえたりすることから、あわただしい短時間のこと。
《解字》
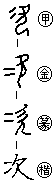 会意。「二(並べる)+欠(人が体をかがめたさま)」で、ざっと身のまわりを整理しておいて休むこと。軍隊の小休止の意。のち、物をざっと順序づけて並べる意に用い、次第に順序をあらわすことばになった。
《単語家族》
茨シ(かや草をざっと並べる)
会意。「二(並べる)+欠(人が体をかがめたさま)」で、ざっと身のまわりを整理しておいて休むこと。軍隊の小休止の意。のち、物をざっと順序づけて並べる意に用い、次第に順序をあらわすことばになった。
《単語家族》
茨シ(かや草をざっと並べる) 資(ざっと並べて整えた材料)などと同系。
《類義》
→番
《異字同訓》
つぐ。 次ぐ「事件が相次ぐ。富士山に次ぐ山。取り次ぐ。次の間」継ぐ「布を継ぐ。跡を継ぐ。引き継ぐ。継ぎ目。継ぎを当てる」接ぐ「木を接ぐ。骨を接ぐ。接ぎ木」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
資(ざっと並べて整えた材料)などと同系。
《類義》
→番
《異字同訓》
つぐ。 次ぐ「事件が相次ぐ。富士山に次ぐ山。取り次ぐ。次の間」継ぐ「布を継ぐ。跡を継ぐ。引き継ぐ。継ぎ目。継ぎを当てる」接ぐ「木を接ぐ。骨を接ぐ。接ぎ木」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画 欠部 [三年]
区点=2801 16進=3C21 シフトJIS=8E9F
《常用音訓》シ/ジ/つぎ/つ…ぐ
《音読み》 ジ
6画 欠部 [三年]
区点=2801 16進=3C21 シフトJIS=8E9F
《常用音訓》シ/ジ/つぎ/つ…ぐ
《音読み》 ジ /シ
/シ
 〈c
〈c 〉
《訓読み》 つぎ/つぐ/つぎに/ついで/やどる/とまる
《名付け》 ちか・つぎ・つぐ・ひで・やどる
《意味》
〉
《訓読み》 つぎ/つぐ/つぎに/ついで/やどる/とまる
《名付け》 ちか・つぎ・つぐ・ひで・やどる
《意味》
 {名}つぎ。並んだもののうち、はじめのもののつぎ。「次年」「敢問其次=アヘテソノ次ヲ問フ」〔→論語〕
{名}つぎ。並んだもののうち、はじめのもののつぎ。「次年」「敢問其次=アヘテソノ次ヲ問フ」〔→論語〕
 {動}つぐ。第一のものの下に位する。また、第一のもののあとに続く。「君又次之=君マタコレニ次グ」「相次去世=アヒ次イデ世ヲ去ル」
{動}つぐ。第一のものの下に位する。また、第一のもののあとに続く。「君又次之=君マタコレニ次グ」「相次去世=アヒ次イデ世ヲ去ル」
 {副}つぎに。ついで。そのあとに続いて。「次叙病心=次ニ病ム心ヲ叙ス」〔→白居易〕
{副}つぎに。ついで。そのあとに続いて。「次叙病心=次ニ病ム心ヲ叙ス」〔→白居易〕
 {名}順序。「序次」「班次(並べた順序)」「以次進至陛=次ヲモッテ進ミ陛ニ至ル」〔→史記〕
{名}順序。「序次」「班次(並べた順序)」「以次進至陛=次ヲモッテ進ミ陛ニ至ル」〔→史記〕
 {単位}物事の回数・度数を数えるときのことば。また、物事の順序をあらわすことば。「数次(数回)」
{単位}物事の回数・度数を数えるときのことば。また、物事の順序をあらわすことば。「数次(数回)」
 {名}ある行為をしたとき。そのさい。「参内之次サンダイノジ(宮中にまいったとき)」
{名}ある行為をしたとき。そのさい。「参内之次サンダイノジ(宮中にまいったとき)」
 ジス{動}やどる。とまる。もと、軍隊がざっと部署をととのえて宿営する。また、旅の間に一日だけとまる。「旅次(宿屋。また、旅の途上)」「師退次于召陵=師退キテ召陵ニ次ル」〔→左伝〕
ジス{動}やどる。とまる。もと、軍隊がざっと部署をととのえて宿営する。また、旅の間に一日だけとまる。「旅次(宿屋。また、旅の途上)」「師退次于召陵=師退キテ召陵ニ次ル」〔→左伝〕
 {名}星のとまる星座。また広く物のやどる場所。「胸次(むねのところ)」「席次(席のある所)」
{名}星のとまる星座。また広く物のやどる場所。「胸次(むねのところ)」「席次(席のある所)」
 「造次」とは、そそくさと物をかたづけたり、あつらえたりすることから、あわただしい短時間のこと。
《解字》
「造次」とは、そそくさと物をかたづけたり、あつらえたりすることから、あわただしい短時間のこと。
《解字》
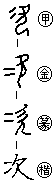 会意。「二(並べる)+欠(人が体をかがめたさま)」で、ざっと身のまわりを整理しておいて休むこと。軍隊の小休止の意。のち、物をざっと順序づけて並べる意に用い、次第に順序をあらわすことばになった。
《単語家族》
茨シ(かや草をざっと並べる)
会意。「二(並べる)+欠(人が体をかがめたさま)」で、ざっと身のまわりを整理しておいて休むこと。軍隊の小休止の意。のち、物をざっと順序づけて並べる意に用い、次第に順序をあらわすことばになった。
《単語家族》
茨シ(かや草をざっと並べる) 資(ざっと並べて整えた材料)などと同系。
《類義》
→番
《異字同訓》
つぐ。 次ぐ「事件が相次ぐ。富士山に次ぐ山。取り次ぐ。次の間」継ぐ「布を継ぐ。跡を継ぐ。引き継ぐ。継ぎ目。継ぎを当てる」接ぐ「木を接ぐ。骨を接ぐ。接ぎ木」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
資(ざっと並べて整えた材料)などと同系。
《類義》
→番
《異字同訓》
つぐ。 次ぐ「事件が相次ぐ。富士山に次ぐ山。取り次ぐ。次の間」継ぐ「布を継ぐ。跡を継ぐ。引き継ぐ。継ぎ目。継ぎを当てる」接ぐ「木を接ぐ。骨を接ぐ。接ぎ木」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
注 つぐ🔗⭐🔉
【注】
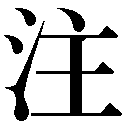 8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ
8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ /ス
/ス /シュ
/シュ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
 {動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
 {動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
 {動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
 チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
 {動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
 チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
 {名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ)
{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ) 柱(はしら)
柱(はしら) 住(一か所にとどまる→すむ)
住(一か所にとどまる→すむ) 駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
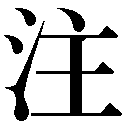 8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ
8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ /ス
/ス /シュ
/シュ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
 {動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
 {動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
 {動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
 チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
 {動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
 チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
 {名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ)
{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ) 柱(はしら)
柱(はしら) 住(一か所にとどまる→すむ)
住(一か所にとどまる→すむ) 駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
紹 つぐ🔗⭐🔉
【紹】
 11画 糸部 [常用漢字]
区点=3050 16進=3E52 シフトJIS=8FD0
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ)
11画 糸部 [常用漢字]
区点=3050 16進=3E52 シフトJIS=8FD0
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ) /ジョウ(ゼウ)
/ジョウ(ゼウ) 〈sh
〈sh o〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 あき・つぎ・つぐ
《意味》
o〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 あき・つぎ・つぐ
《意味》
 {動}つぐ。糸の端と端とをまわしてきてつなぐ。また、絶えぬように物事を受けつぐ。〈類義語〉→継。「紹継」「紹其業=ソノ業ヲ紹グ」
{動}つぐ。糸の端と端とをまわしてきてつなぐ。また、絶えぬように物事を受けつぐ。〈類義語〉→継。「紹継」「紹其業=ソノ業ヲ紹グ」
 「紹介」とは、間にたって両者をまねきよせ、縁をつなぐこと。仲立ち。「勝請為紹介而見之於先生=勝紹介ヲ為サンコトヲ請ヒテコレヲ先生ニ見エシム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀(半円の形をしたかたな)」の会意兼形声文字で、半円を描いてまねきよせること。紹は「糸+音符召」で、糸の端と端とを半円を描いてまねきよせ、つなぐこと。
《単語家族》
招(まねきよせる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「紹介」とは、間にたって両者をまねきよせ、縁をつなぐこと。仲立ち。「勝請為紹介而見之於先生=勝紹介ヲ為サンコトヲ請ヒテコレヲ先生ニ見エシム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀(半円の形をしたかたな)」の会意兼形声文字で、半円を描いてまねきよせること。紹は「糸+音符召」で、糸の端と端とを半円を描いてまねきよせ、つなぐこと。
《単語家族》
招(まねきよせる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 糸部 [常用漢字]
区点=3050 16進=3E52 シフトJIS=8FD0
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ)
11画 糸部 [常用漢字]
区点=3050 16進=3E52 シフトJIS=8FD0
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ) /ジョウ(ゼウ)
/ジョウ(ゼウ) 〈sh
〈sh o〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 あき・つぎ・つぐ
《意味》
o〉
《訓読み》 つぐ
《名付け》 あき・つぎ・つぐ
《意味》
 {動}つぐ。糸の端と端とをまわしてきてつなぐ。また、絶えぬように物事を受けつぐ。〈類義語〉→継。「紹継」「紹其業=ソノ業ヲ紹グ」
{動}つぐ。糸の端と端とをまわしてきてつなぐ。また、絶えぬように物事を受けつぐ。〈類義語〉→継。「紹継」「紹其業=ソノ業ヲ紹グ」
 「紹介」とは、間にたって両者をまねきよせ、縁をつなぐこと。仲立ち。「勝請為紹介而見之於先生=勝紹介ヲ為サンコトヲ請ヒテコレヲ先生ニ見エシム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀(半円の形をしたかたな)」の会意兼形声文字で、半円を描いてまねきよせること。紹は「糸+音符召」で、糸の端と端とを半円を描いてまねきよせ、つなぐこと。
《単語家族》
招(まねきよせる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「紹介」とは、間にたって両者をまねきよせ、縁をつなぐこと。仲立ち。「勝請為紹介而見之於先生=勝紹介ヲ為サンコトヲ請ヒテコレヲ先生ニ見エシム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀(半円の形をしたかたな)」の会意兼形声文字で、半円を描いてまねきよせること。紹は「糸+音符召」で、糸の端と端とを半円を描いてまねきよせ、つなぐこと。
《単語家族》
招(まねきよせる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
継 つぐ🔗⭐🔉
【継】
 13画 糸部 [常用漢字]
区点=2349 16進=3751 シフトJIS=8C70
【繼】旧字旧字
13画 糸部 [常用漢字]
区点=2349 16進=3751 シフトJIS=8C70
【繼】旧字旧字
 20画 糸部
区点=6975 16進=656B シフトJIS=E38B
《常用音訓》ケイ/つ…ぐ
《音読み》 ケイ
20画 糸部
区点=6975 16進=656B シフトJIS=E38B
《常用音訓》ケイ/つ…ぐ
《音読み》 ケイ /ケ
/ケ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 つぐ/ついで
《名付け》 つぎ・つぐ・つね・ひで
《意味》
〉
《訓読み》 つぐ/ついで
《名付け》 つぎ・つぐ・つね・ひで
《意味》
 {動・形}つぐ。切れた糸をつなぐ。糸でつなぐように、前人の位・仕事・物などを受けて行う。あとをつぐ。あとをついだ。〈対語〉→絶。〈類義語〉→続。「継続」「後継」「継室」「継絶世=絶世ヲ継グ」〔→論語〕
{動・形}つぐ。切れた糸をつなぐ。糸でつなぐように、前人の位・仕事・物などを受けて行う。あとをつぐ。あとをついだ。〈対語〉→絶。〈類義語〉→続。「継続」「後継」「継室」「継絶世=絶世ヲ継グ」〔→論語〕
 {動}つぐ。あとに続ける。つぎ足す。「以夜継日=夜モッテ日ニ継グ」「君子周急、不継富=君子ハ急ナルヲ周ケテ、富ミタルヲ継ガズ」〔→論語〕
{動}つぐ。あとに続ける。つぎ足す。「以夜継日=夜モッテ日ニ継グ」「君子周急、不継富=君子ハ急ナルヲ周ケテ、富ミタルヲ継ガズ」〔→論語〕
 {接続}ついで。そのあとに続いて。▽「継而…」という形で用いることが多い。「継而有師命=継イデ師命有リ」〔→孟子〕
《解字》
会意。斷(=断)の字の左側の部分は、糸をばらばらに切ることを示す。繼は「糸+斷の字の左側の部分」で、切れた糸をつなぐこと。
《単語家族》
繋ケイ(つなぐ)
{接続}ついで。そのあとに続いて。▽「継而…」という形で用いることが多い。「継而有師命=継イデ師命有リ」〔→孟子〕
《解字》
会意。斷(=断)の字の左側の部分は、糸をばらばらに切ることを示す。繼は「糸+斷の字の左側の部分」で、切れた糸をつなぐこと。
《単語家族》
繋ケイ(つなぐ) 系(つながる)
系(つながる) 綮ケイ(つながったひも)などと同系。
《類義》
続は、断絶しないように糸でつないで、後から後からつづくこと。接は、一点でくっついてつながること。
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
綮ケイ(つながったひも)などと同系。
《類義》
続は、断絶しないように糸でつないで、後から後からつづくこと。接は、一点でくっついてつながること。
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 糸部 [常用漢字]
区点=2349 16進=3751 シフトJIS=8C70
【繼】旧字旧字
13画 糸部 [常用漢字]
区点=2349 16進=3751 シフトJIS=8C70
【繼】旧字旧字
 20画 糸部
区点=6975 16進=656B シフトJIS=E38B
《常用音訓》ケイ/つ…ぐ
《音読み》 ケイ
20画 糸部
区点=6975 16進=656B シフトJIS=E38B
《常用音訓》ケイ/つ…ぐ
《音読み》 ケイ /ケ
/ケ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 つぐ/ついで
《名付け》 つぎ・つぐ・つね・ひで
《意味》
〉
《訓読み》 つぐ/ついで
《名付け》 つぎ・つぐ・つね・ひで
《意味》
 {動・形}つぐ。切れた糸をつなぐ。糸でつなぐように、前人の位・仕事・物などを受けて行う。あとをつぐ。あとをついだ。〈対語〉→絶。〈類義語〉→続。「継続」「後継」「継室」「継絶世=絶世ヲ継グ」〔→論語〕
{動・形}つぐ。切れた糸をつなぐ。糸でつなぐように、前人の位・仕事・物などを受けて行う。あとをつぐ。あとをついだ。〈対語〉→絶。〈類義語〉→続。「継続」「後継」「継室」「継絶世=絶世ヲ継グ」〔→論語〕
 {動}つぐ。あとに続ける。つぎ足す。「以夜継日=夜モッテ日ニ継グ」「君子周急、不継富=君子ハ急ナルヲ周ケテ、富ミタルヲ継ガズ」〔→論語〕
{動}つぐ。あとに続ける。つぎ足す。「以夜継日=夜モッテ日ニ継グ」「君子周急、不継富=君子ハ急ナルヲ周ケテ、富ミタルヲ継ガズ」〔→論語〕
 {接続}ついで。そのあとに続いて。▽「継而…」という形で用いることが多い。「継而有師命=継イデ師命有リ」〔→孟子〕
《解字》
会意。斷(=断)の字の左側の部分は、糸をばらばらに切ることを示す。繼は「糸+斷の字の左側の部分」で、切れた糸をつなぐこと。
《単語家族》
繋ケイ(つなぐ)
{接続}ついで。そのあとに続いて。▽「継而…」という形で用いることが多い。「継而有師命=継イデ師命有リ」〔→孟子〕
《解字》
会意。斷(=断)の字の左側の部分は、糸をばらばらに切ることを示す。繼は「糸+斷の字の左側の部分」で、切れた糸をつなぐこと。
《単語家族》
繋ケイ(つなぐ) 系(つながる)
系(つながる) 綮ケイ(つながったひも)などと同系。
《類義》
続は、断絶しないように糸でつないで、後から後からつづくこと。接は、一点でくっついてつながること。
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
綮ケイ(つながったひも)などと同系。
《類義》
続は、断絶しないように糸でつないで、後から後からつづくこと。接は、一点でくっついてつながること。
《異字同訓》
つぐ。 →次
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
緝 つぐ🔗⭐🔉
【緝】
 15画 糸部
区点=6941 16進=6549 シフトJIS=E368
《音読み》 シュウ(シフ)
15画 糸部
区点=6941 16進=6549 シフトJIS=E368
《音読み》 シュウ(シフ)
 〈q
〈q ・j
・j 〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/つぐ/あつめる(あつむ)/とらえる(とらふ)
《意味》
〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/つぐ/あつめる(あつむ)/とらえる(とらふ)
《意味》
 {動}つむぐ。繊維を寄せあわせてより糸にする。〈類義語〉→紡(つむぐ)。
{動}つむぐ。繊維を寄せあわせてより糸にする。〈類義語〉→紡(つむぐ)。
 {動}うむ。麻の長い繊維をよりながらつぎたして長い糸にする。麻糸をつくる。
{動}うむ。麻の長い繊維をよりながらつぎたして長い糸にする。麻糸をつくる。
 {動}つぐ。衣服のへりを寄せあわせてかがる。衣服のへりを横に縫いあわせて止める。「緝辺シュウヘン(衣のへりをかがる)」「緝綴シュウテイ・シュウテツ」
{動}つぐ。衣服のへりを寄せあわせてかがる。衣服のへりを横に縫いあわせて止める。「緝辺シュウヘン(衣のへりをかがる)」「緝綴シュウテイ・シュウテツ」
 {動}つぐ。あつめる(アツム)。寄せあわす。また、原稿をつづりあわせる。〈同義語〉→輯。「編緝ヘンシュウ(=編輯、編集)」
{動}つぐ。あつめる(アツム)。寄せあわす。また、原稿をつづりあわせる。〈同義語〉→輯。「編緝ヘンシュウ(=編輯、編集)」
 {動}とらえる(トラフ)。「緝私シュウシ(密輸者をとらえる)」「緝盗シュウトウ(盗賊をとらえる)」
{動}とらえる(トラフ)。「緝私シュウシ(密輸者をとらえる)」「緝盗シュウトウ(盗賊をとらえる)」
 「緝緝シュウシュウ」とは、べちゃべちゃとしゃべる声。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュウ)は「口+耳」の会意文字で、耳に口を寄せあわせることを示す。緝はそれを音符とし、糸を加えた字で、繊維を寄せあわせてより糸をつむぐこと。
《単語家族》
葺シュウ(草を寄せあわせて屋根をふく)
「緝緝シュウシュウ」とは、べちゃべちゃとしゃべる声。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュウ)は「口+耳」の会意文字で、耳に口を寄せあわせることを示す。緝はそれを音符とし、糸を加えた字で、繊維を寄せあわせてより糸をつむぐこと。
《単語家族》
葺シュウ(草を寄せあわせて屋根をふく) 輯シュウ(寄せあわせる)
輯シュウ(寄せあわせる) 集(寄せあわせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
集(寄せあわせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 糸部
区点=6941 16進=6549 シフトJIS=E368
《音読み》 シュウ(シフ)
15画 糸部
区点=6941 16進=6549 シフトJIS=E368
《音読み》 シュウ(シフ)
 〈q
〈q ・j
・j 〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/つぐ/あつめる(あつむ)/とらえる(とらふ)
《意味》
〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/つぐ/あつめる(あつむ)/とらえる(とらふ)
《意味》
 {動}つむぐ。繊維を寄せあわせてより糸にする。〈類義語〉→紡(つむぐ)。
{動}つむぐ。繊維を寄せあわせてより糸にする。〈類義語〉→紡(つむぐ)。
 {動}うむ。麻の長い繊維をよりながらつぎたして長い糸にする。麻糸をつくる。
{動}うむ。麻の長い繊維をよりながらつぎたして長い糸にする。麻糸をつくる。
 {動}つぐ。衣服のへりを寄せあわせてかがる。衣服のへりを横に縫いあわせて止める。「緝辺シュウヘン(衣のへりをかがる)」「緝綴シュウテイ・シュウテツ」
{動}つぐ。衣服のへりを寄せあわせてかがる。衣服のへりを横に縫いあわせて止める。「緝辺シュウヘン(衣のへりをかがる)」「緝綴シュウテイ・シュウテツ」
 {動}つぐ。あつめる(アツム)。寄せあわす。また、原稿をつづりあわせる。〈同義語〉→輯。「編緝ヘンシュウ(=編輯、編集)」
{動}つぐ。あつめる(アツム)。寄せあわす。また、原稿をつづりあわせる。〈同義語〉→輯。「編緝ヘンシュウ(=編輯、編集)」
 {動}とらえる(トラフ)。「緝私シュウシ(密輸者をとらえる)」「緝盗シュウトウ(盗賊をとらえる)」
{動}とらえる(トラフ)。「緝私シュウシ(密輸者をとらえる)」「緝盗シュウトウ(盗賊をとらえる)」
 「緝緝シュウシュウ」とは、べちゃべちゃとしゃべる声。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュウ)は「口+耳」の会意文字で、耳に口を寄せあわせることを示す。緝はそれを音符とし、糸を加えた字で、繊維を寄せあわせてより糸をつむぐこと。
《単語家族》
葺シュウ(草を寄せあわせて屋根をふく)
「緝緝シュウシュウ」とは、べちゃべちゃとしゃべる声。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュウ)は「口+耳」の会意文字で、耳に口を寄せあわせることを示す。緝はそれを音符とし、糸を加えた字で、繊維を寄せあわせてより糸をつむぐこと。
《単語家族》
葺シュウ(草を寄せあわせて屋根をふく) 輯シュウ(寄せあわせる)
輯シュウ(寄せあわせる) 集(寄せあわせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
集(寄せあわせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
繹 つぐ🔗⭐🔉
【繹】
 19画 糸部
区点=6972 16進=6568 シフトJIS=E388
《音読み》 エキ
19画 糸部
区点=6972 16進=6568 シフトJIS=E388
《音読み》 エキ /ヤク
/ヤク 〈y
〈y 〉
《訓読み》 ぬく/たずねる(たづぬ)/つぐ/つづく
《意味》
〉
《訓読み》 ぬく/たずねる(たづぬ)/つぐ/つづく
《意味》
 {動}ぬく。たずねる(タヅヌ)。つづいたものをずるずると一つずつ引き出す。つぎつぎと引き出して吟味する。「繹理=理ヲ繹ヌ」「演繹エンエキ(ある理論をもとにして、一つずつ例にあてはめていく)」「繹之為貴=コレヲ繹ヌルヲ貴シト為ス」〔→論語〕
{動}ぬく。たずねる(タヅヌ)。つづいたものをずるずると一つずつ引き出す。つぎつぎと引き出して吟味する。「繹理=理ヲ繹ヌ」「演繹エンエキ(ある理論をもとにして、一つずつ例にあてはめていく)」「繹之為貴=コレヲ繹ヌルヲ貴シト為ス」〔→論語〕
 {動}つぐ。つづく。つらなる。一つずつ出て来て、ずるずると絶えずにつづく。「絡繹不絶=絡繹トシテ絶エズ」「繹繹エキエキ(後から後からつづくさま)」
{動}つぐ。つづく。つらなる。一つずつ出て来て、ずるずると絶えずにつづく。「絡繹不絶=絡繹トシテ絶エズ」「繹繹エキエキ(後から後からつづくさま)」
 {名}祭りの名。祖先をまつる正祭の翌日行う。「繹祭エキサイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ)は「目+幸(手かせの形)」の会意文字で、ひとりずつ出てくる手かせをはめた罪人を目で選び出すさま。擇タク(=択。えらぶ)の原字。繹はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をたぐって一つずつ引き出すこと。・―・―・の形につづくの意を含む。
《単語家族》
驛エキ(=駅。一つ一つとつづいて並ぶ宿場)
{名}祭りの名。祖先をまつる正祭の翌日行う。「繹祭エキサイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ)は「目+幸(手かせの形)」の会意文字で、ひとりずつ出てくる手かせをはめた罪人を目で選び出すさま。擇タク(=択。えらぶ)の原字。繹はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をたぐって一つずつ引き出すこと。・―・―・の形につづくの意を含む。
《単語家族》
驛エキ(=駅。一つ一つとつづいて並ぶ宿場) 擇タク(=択。一つずつ引き出して吟味する)
擇タク(=択。一つずつ引き出して吟味する) 澤タク(=沢。つぎつぎとつづく湿地)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
澤タク(=沢。つぎつぎとつづく湿地)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 19画 糸部
区点=6972 16進=6568 シフトJIS=E388
《音読み》 エキ
19画 糸部
区点=6972 16進=6568 シフトJIS=E388
《音読み》 エキ /ヤク
/ヤク 〈y
〈y 〉
《訓読み》 ぬく/たずねる(たづぬ)/つぐ/つづく
《意味》
〉
《訓読み》 ぬく/たずねる(たづぬ)/つぐ/つづく
《意味》
 {動}ぬく。たずねる(タヅヌ)。つづいたものをずるずると一つずつ引き出す。つぎつぎと引き出して吟味する。「繹理=理ヲ繹ヌ」「演繹エンエキ(ある理論をもとにして、一つずつ例にあてはめていく)」「繹之為貴=コレヲ繹ヌルヲ貴シト為ス」〔→論語〕
{動}ぬく。たずねる(タヅヌ)。つづいたものをずるずると一つずつ引き出す。つぎつぎと引き出して吟味する。「繹理=理ヲ繹ヌ」「演繹エンエキ(ある理論をもとにして、一つずつ例にあてはめていく)」「繹之為貴=コレヲ繹ヌルヲ貴シト為ス」〔→論語〕
 {動}つぐ。つづく。つらなる。一つずつ出て来て、ずるずると絶えずにつづく。「絡繹不絶=絡繹トシテ絶エズ」「繹繹エキエキ(後から後からつづくさま)」
{動}つぐ。つづく。つらなる。一つずつ出て来て、ずるずると絶えずにつづく。「絡繹不絶=絡繹トシテ絶エズ」「繹繹エキエキ(後から後からつづくさま)」
 {名}祭りの名。祖先をまつる正祭の翌日行う。「繹祭エキサイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ)は「目+幸(手かせの形)」の会意文字で、ひとりずつ出てくる手かせをはめた罪人を目で選び出すさま。擇タク(=択。えらぶ)の原字。繹はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をたぐって一つずつ引き出すこと。・―・―・の形につづくの意を含む。
《単語家族》
驛エキ(=駅。一つ一つとつづいて並ぶ宿場)
{名}祭りの名。祖先をまつる正祭の翌日行う。「繹祭エキサイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ)は「目+幸(手かせの形)」の会意文字で、ひとりずつ出てくる手かせをはめた罪人を目で選び出すさま。擇タク(=択。えらぶ)の原字。繹はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をたぐって一つずつ引き出すこと。・―・―・の形につづくの意を含む。
《単語家族》
驛エキ(=駅。一つ一つとつづいて並ぶ宿場) 擇タク(=択。一つずつ引き出して吟味する)
擇タク(=択。一つずつ引き出して吟味する) 澤タク(=沢。つぎつぎとつづく湿地)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
澤タク(=沢。つぎつぎとつづく湿地)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
纉 つぐ🔗⭐🔉
【纉】
 21画 糸部
区点=6983 16進=6573 シフトJIS=E393
《音読み》 サン
21画 糸部
区点=6983 16進=6573 シフトJIS=E393
《音読み》 サン
 〈zu
〈zu n〉
《訓読み》 つぐ
《意味》
{動}つぐ。受けつぐ。また、前の人のやり方にあわせて続ける。「纉業=業ヲ纉グ」「纉継サンケイ」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符賛サン(力をあわす、そろえる)」。前の人に力をあわせて、仕事を受けつぐこと。
《熟語》
→熟語
n〉
《訓読み》 つぐ
《意味》
{動}つぐ。受けつぐ。また、前の人のやり方にあわせて続ける。「纉業=業ヲ纉グ」「纉継サンケイ」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符賛サン(力をあわす、そろえる)」。前の人に力をあわせて、仕事を受けつぐこと。
《熟語》
→熟語
 21画 糸部
区点=6983 16進=6573 シフトJIS=E393
《音読み》 サン
21画 糸部
区点=6983 16進=6573 シフトJIS=E393
《音読み》 サン
 〈zu
〈zu n〉
《訓読み》 つぐ
《意味》
{動}つぐ。受けつぐ。また、前の人のやり方にあわせて続ける。「纉業=業ヲ纉グ」「纉継サンケイ」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符賛サン(力をあわす、そろえる)」。前の人に力をあわせて、仕事を受けつぐこと。
《熟語》
→熟語
n〉
《訓読み》 つぐ
《意味》
{動}つぐ。受けつぐ。また、前の人のやり方にあわせて続ける。「纉業=業ヲ纉グ」「纉継サンケイ」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符賛サン(力をあわす、そろえる)」。前の人に力をあわせて、仕事を受けつぐこと。
《熟語》
→熟語
襲 つぐ🔗⭐🔉
【襲】
 22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ)
22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)
/ジュウ(ジフ) 〈x
〈x 〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
 {動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
 {単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
 {動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
 {動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる)
{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる) 習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ)
22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)
/ジュウ(ジフ) 〈x
〈x 〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
 {動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
 {単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
 {動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
 {動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる)
{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる) 習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
踵 つぐ🔗⭐🔉
【踵】
 16画 足部
区点=7691 16進=6C7B シフトJIS=E6F9
《音読み》 ショウ
16画 足部
区点=7691 16進=6C7B シフトJIS=E6F9
《音読み》 ショウ /シュ
/シュ 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 くびす/つぐ/いたる/しきりに/ついで
《意味》
ng〉
《訓読み》 くびす/つぐ/いたる/しきりに/ついで
《意味》
 {名}くびす。かかと。体重のかかる足のかかと。〈類義語〉→踝カ(くるぶし)。「旋踵=踵ヲ旋ラス」「摩頂放踵、利天下為之=頂ヲ摩シ踵ヲ放ツモ、天下ヲ利セントシテコレヲ為ス」〔→孟子〕
{名}くびす。かかと。体重のかかる足のかかと。〈類義語〉→踝カ(くるぶし)。「旋踵=踵ヲ旋ラス」「摩頂放踵、利天下為之=頂ヲ摩シ踵ヲ放ツモ、天下ヲ利セントシテコレヲ為ス」〔→孟子〕
 {動}つぐ。すぐあとに続く。あとを追う。「踵武ショウブ」
{動}つぐ。すぐあとに続く。あとを追う。「踵武ショウブ」
 {動}いたる。あとをたどっていく。また、たずねていく。「踵門而告文公曰=門ニ踵リテ文公ニ告ゲテ曰ハク」〔→孟子〕
{動}いたる。あとをたどっていく。また、たずねていく。「踵門而告文公曰=門ニ踵リテ文公ニ告ゲテ曰ハク」〔→孟子〕
 {副}しきりに。ついで。あとからあとから。引き続いて。「踵見仲尼=踵イデ仲尼ニ見ユ」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。「足+音符重(おもみがかかる)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}しきりに。ついで。あとからあとから。引き続いて。「踵見仲尼=踵イデ仲尼ニ見ユ」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。「足+音符重(おもみがかかる)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画 足部
区点=7691 16進=6C7B シフトJIS=E6F9
《音読み》 ショウ
16画 足部
区点=7691 16進=6C7B シフトJIS=E6F9
《音読み》 ショウ /シュ
/シュ 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 くびす/つぐ/いたる/しきりに/ついで
《意味》
ng〉
《訓読み》 くびす/つぐ/いたる/しきりに/ついで
《意味》
 {名}くびす。かかと。体重のかかる足のかかと。〈類義語〉→踝カ(くるぶし)。「旋踵=踵ヲ旋ラス」「摩頂放踵、利天下為之=頂ヲ摩シ踵ヲ放ツモ、天下ヲ利セントシテコレヲ為ス」〔→孟子〕
{名}くびす。かかと。体重のかかる足のかかと。〈類義語〉→踝カ(くるぶし)。「旋踵=踵ヲ旋ラス」「摩頂放踵、利天下為之=頂ヲ摩シ踵ヲ放ツモ、天下ヲ利セントシテコレヲ為ス」〔→孟子〕
 {動}つぐ。すぐあとに続く。あとを追う。「踵武ショウブ」
{動}つぐ。すぐあとに続く。あとを追う。「踵武ショウブ」
 {動}いたる。あとをたどっていく。また、たずねていく。「踵門而告文公曰=門ニ踵リテ文公ニ告ゲテ曰ハク」〔→孟子〕
{動}いたる。あとをたどっていく。また、たずねていく。「踵門而告文公曰=門ニ踵リテ文公ニ告ゲテ曰ハク」〔→孟子〕
 {副}しきりに。ついで。あとからあとから。引き続いて。「踵見仲尼=踵イデ仲尼ニ見ユ」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。「足+音符重(おもみがかかる)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}しきりに。ついで。あとからあとから。引き続いて。「踵見仲尼=踵イデ仲尼ニ見ユ」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。「足+音符重(おもみがかかる)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「つぐ」で完全一致するの検索結果 1-14。