複数辞典一括検索+![]()
![]()
害 そこなう🔗⭐🔉
【害】
 10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ
10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ /カイ
/カイ 〈h
〈h i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
 ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
 ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
 ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
 {名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
 「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
 {副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
 会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ)
会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)
割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ
10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ /カイ
/カイ 〈h
〈h i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
 ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
 ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
 ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
 {名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
 「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
 {副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
 会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ)
会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)
割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
底 そこ🔗⭐🔉
【底】
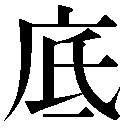 8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ
8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
 {名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
 {名}文書の下書き。「底稿」
{名}文書の下書き。「底稿」
 {動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
 「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
 {疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
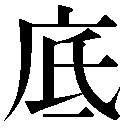 8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ
8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
 {名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
 {名}文書の下書き。「底稿」
{名}文書の下書き。「底稿」
 {動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
 「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
 {疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
払底 ソコヲハラウ🔗⭐🔉
【払底】
フッテイ・ソコヲハラウ〔国〕 入れ物の底を払う。
入れ物の底を払う。 品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。
品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。
 入れ物の底を払う。
入れ物の底を払う。 品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。
品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。
損 そこなう🔗⭐🔉
【損】
 13画
13画  部 [五年]
区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9
《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる
《音読み》 ソン
部 [五年]
区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9
《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる
《音読み》 ソン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)
《名付け》 ちか
《意味》
n〉
《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)
《名付け》 ちか
《意味》
 ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」
ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」
 ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕
ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕
 ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」
ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」
 {名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」
{名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。
〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」
《解字》
会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員
《単語家族》
遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。
〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」
《解字》
会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員
《単語家族》
遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画
13画  部 [五年]
区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9
《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる
《音読み》 ソン
部 [五年]
区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9
《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる
《音読み》 ソン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)
《名付け》 ちか
《意味》
n〉
《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)
《名付け》 ちか
《意味》
 ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」
ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」
 ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕
ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕
 ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」
ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」
 {名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」
{名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。
〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」
《解字》
会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員
《単語家族》
遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。
〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」
《解字》
会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員
《単語家族》
遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
楚江 ソコウ🔗⭐🔉
【楚江】
ソコウ 川名。長江の中・下流域での別名。湖南・湖北省一帯を指して楚の国ということから。
殃 そこなう🔗⭐🔉
【殃】
 9画 歹部
区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69
《音読み》 オウ(アウ)
9画 歹部
区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69
《音読み》 オウ(アウ) /ヨウ(ヤウ)
/ヨウ(ヤウ) 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)
《意味》
 {名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」
{名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」
 {動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於
{動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於 舜之世=民ヲ殃フ者ハ
舜之世=民ヲ殃フ者ハ 舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。
《類義》
→災
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。
《類義》
→災
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 9画 歹部
区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69
《音読み》 オウ(アウ)
9画 歹部
区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69
《音読み》 オウ(アウ) /ヨウ(ヤウ)
/ヨウ(ヤウ) 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)
《意味》
 {名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」
{名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」
 {動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於
{動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於 舜之世=民ヲ殃フ者ハ
舜之世=民ヲ殃フ者ハ 舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。
《類義》
→災
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。
《類義》
→災
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
残 そこなう🔗⭐🔉
【残】
 10画 歹部 [四年]
区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63
【殘】旧字旧字
10画 歹部 [四年]
区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63
【殘】旧字旧字
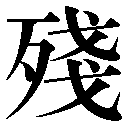 12画 歹部
区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B
《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る
《音読み》 ザン
12画 歹部
区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B
《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る
《音読み》 ザン /サン
/サン 〈c
〈c n〉
《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)
《意味》
n〉
《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)
《意味》
 {動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」
{動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」
 {形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」
{形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」
 {動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕
{動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕
 ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔
《単語家族》
盞セン(小さい皿サラ)
ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔
《単語家族》
盞セン(小さい皿サラ) 錢(=銭。小ぜに)
錢(=銭。小ぜに) 淺セン(=浅。水が少ない)
淺セン(=浅。水が少ない) 賤セン(財が少ない)などと同系。
《類義》
遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
賤セン(財が少ない)などと同系。
《類義》
遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 歹部 [四年]
区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63
【殘】旧字旧字
10画 歹部 [四年]
区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63
【殘】旧字旧字
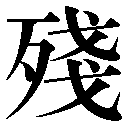 12画 歹部
区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B
《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る
《音読み》 ザン
12画 歹部
区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B
《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る
《音読み》 ザン /サン
/サン 〈c
〈c n〉
《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)
《意味》
n〉
《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)
《意味》
 {動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」
{動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」
 {形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」
{形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」
 {動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕
{動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕
 ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔
《単語家族》
盞セン(小さい皿サラ)
ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔
《単語家族》
盞セン(小さい皿サラ) 錢(=銭。小ぜに)
錢(=銭。小ぜに) 淺セン(=浅。水が少ない)
淺セン(=浅。水が少ない) 賤セン(財が少ない)などと同系。
《類義》
遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
賤セン(財が少ない)などと同系。
《類義》
遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
狙候 ソコウ🔗⭐🔉
【狙候】
ソコウ ねらいうかがう。
疎忽 ソコツ🔗⭐🔉
【疎忽】
ソコツ  そそっかしい。
そそっかしい。 不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。
不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。
 そそっかしい。
そそっかしい。 不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。
不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。
疎広 ソコウ🔗⭐🔉
【疎広】
ソコウ〈人名〉漢代の学者。蘭陵ランリョウ(山東省蒼山ソウザン県)の人。字アザナは仲翁。『春秋』の学に詳しく太子傅タイシフとなる。
祖考 ソコウ🔗⭐🔉
【祖考】
ソコウ  死んだ祖父。
死んだ祖父。 遠い祖先。
遠い祖先。
 死んだ祖父。
死んだ祖父。 遠い祖先。
遠い祖先。
祖国 ソコク🔗⭐🔉
【祖国】
ソコク  先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。
先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。 民族がわかれた、もとの国。本国。
民族がわかれた、もとの国。本国。
 先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。
先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。 民族がわかれた、もとの国。本国。
民族がわかれた、もとの国。本国。
粗肴 ソコウ🔗⭐🔉
【粗肴】
ソコウ そまつな料理。
粗忽 ソコツ🔗⭐🔉
【粗忽】
ソコツ〔国〕 軽はずみで、そそっかしい。
軽はずみで、そそっかしい。 不注意の結果生じた失敗。
不注意の結果生じた失敗。
 軽はずみで、そそっかしい。
軽はずみで、そそっかしい。 不注意の結果生じた失敗。
不注意の結果生じた失敗。
素交 ソコウ🔗⭐🔉
【素交】
ソコウ 日ごろの交わり。
素行 ソコウ🔗⭐🔉
【素行】
ソコウ  日ごろの行い。
日ごろの行い。 現在の身分に応じた正しい行い。
現在の身分に応じた正しい行い。
 日ごろの行い。
日ごろの行い。 現在の身分に応じた正しい行い。
現在の身分に応じた正しい行い。
素光 ソコウ🔗⭐🔉
【素光】
ソコウ 白い光。月の光、また、月光に照らされた露・霜・雪などの光をいう。
組甲 ソコウ🔗⭐🔉
【組甲】
ソコウ くみひもでつづってつくった鎧ヨロイ。
賊 そこなう🔗⭐🔉
【賊】
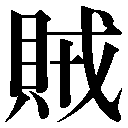 13画 貝部 [常用漢字]
区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF
《常用音訓》ゾク
《音読み》 ゾク
13画 貝部 [常用漢字]
区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF
《常用音訓》ゾク
《音読み》 ゾク /ソク
/ソク 〈z
〈z i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ
《意味》
i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ
《意味》
 {動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕
{動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕
 {動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」
{動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」
 {名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」
{名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」
 {名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」
《解字》
会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」
《解字》
会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
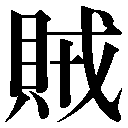 13画 貝部 [常用漢字]
区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF
《常用音訓》ゾク
《音読み》 ゾク
13画 貝部 [常用漢字]
区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF
《常用音訓》ゾク
《音読み》 ゾク /ソク
/ソク 〈z
〈z i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ
《意味》
i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ
《意味》
 {動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕
{動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕
 {動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」
{動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」
 {名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」
{名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」
 {名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」
《解字》
会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」
《解字》
会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遡行 ソコウ🔗⭐🔉
【遡行】
ソコウ =溯行。水の流れをさかのぼっていく。
鼠姑 ソコ🔗⭐🔉
【鼠婦】
ソフ 虫の名。わらじむし。『鼠負ソフ・鼠姑ソコ』
漢字源に「そこ」で始まるの検索結果 1-23。