複数辞典一括検索+![]()
![]()
令 しむ🔗⭐🔉
【令】
 5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ
5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
 {名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
 {名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
 {形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
 {名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
 {名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
 レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
 {助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
 {助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
 「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
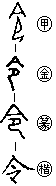 会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷)
会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)
玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)
伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ
5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
 {名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
 {名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
 {形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
 {名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
 {名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
 レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
 {助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
 {助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
 「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
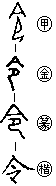 会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷)
会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)
玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)
伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
使 しむ🔗⭐🔉
【使】
 8画 人部 [三年]
区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67
《常用音訓》シ/つか…う
《音読み》 シ
8画 人部 [三年]
区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67
《常用音訓》シ/つか…う
《音読み》 シ
 〈sh
〈sh ・sh
・sh 〉
《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば
《意味》
〉
《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば
《意味》
 {動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕
{動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕
 {名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」
{名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」
 {動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕
{動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕
 {助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕
{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕
 {助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕
《解字》
会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏
《単語家族》
仕
{助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕
《解字》
会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏
《単語家族》
仕 事と同系。
《類義》
→遣
《異字同訓》
つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
事と同系。
《類義》
→遣
《異字同訓》
つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 人部 [三年]
区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67
《常用音訓》シ/つか…う
《音読み》 シ
8画 人部 [三年]
区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67
《常用音訓》シ/つか…う
《音読み》 シ
 〈sh
〈sh ・sh
・sh 〉
《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば
《意味》
〉
《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば
《意味》
 {動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕
{動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕
 {名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」
{名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」
 {動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕
{動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕
 {助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕
{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕
 {助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕
《解字》
会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏
《単語家族》
仕
{助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕
《解字》
会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏
《単語家族》
仕 事と同系。
《類義》
→遣
《異字同訓》
つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
事と同系。
《類義》
→遣
《異字同訓》
つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
俾 しむ🔗⭐🔉
【俾】
 10画 人部
区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA
《音読み》
10画 人部
区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA
《音読み》  ヒ
ヒ
 〈b
〈b 〉/
〉/ ヘイ
ヘイ /ハイ
/ハイ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)
《意味》
〉
《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)
《意味》

 {助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕
{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕
 {動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」
{動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」
 「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。
「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。
 「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。
《解字》
会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。
《熟語》
→熟語
「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。
《解字》
会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。
《熟語》
→熟語
 10画 人部
区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA
《音読み》
10画 人部
区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA
《音読み》  ヒ
ヒ
 〈b
〈b 〉/
〉/ ヘイ
ヘイ /ハイ
/ハイ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)
《意味》
〉
《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)
《意味》

 {助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕
{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕
 {動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」
{動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」
 「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。
「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。
 「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。
《解字》
会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。
《熟語》
→熟語
「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。
《解字》
会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。
《熟語》
→熟語
徇 しむ🔗⭐🔉
【徇】
 9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン
9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
 ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
 {動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
 {動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
 {形}あまねし。全部に行き渡っている。
{形}あまねし。全部に行き渡っている。
 {形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
 {助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン
9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
 ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
 {動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
 {動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
 {形}あまねし。全部に行き渡っている。
{形}あまねし。全部に行き渡っている。
 {形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
 {助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
教 しむ🔗⭐🔉
【教】
 11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ)
11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)
/コウ(カウ) 〈ji
〈ji o・ji
o・ji o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
 {動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
 {名}領主の命令。「教令」
{名}領主の命令。「教令」
 {名}宗教。「回教」
{名}宗教。「回教」
 {助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
 会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる)
会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)
較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ)
11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)
/コウ(カウ) 〈ji
〈ji o・ji
o・ji o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
 {動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
 {名}領主の命令。「教令」
{名}領主の命令。「教令」
 {名}宗教。「回教」
{名}宗教。「回教」
 {助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
 会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる)
会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)
較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「シム」で始まるの検索結果 1-6。
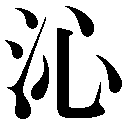 7画 水部
区点=6178 16進=5D6E シフトJIS=9F8E
《音読み》
7画 水部
区点=6178 16進=5D6E シフトJIS=9F8E
《音読み》  n〉/
n〉/