複数辞典一括検索+![]()
![]()
充 あてる🔗⭐🔉
【充】
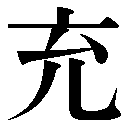 6画 儿部 [常用漢字]
区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B
《常用音訓》ジュウ/あ…てる
《音読み》 ジュウ
6画 儿部 [常用漢字]
区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B
《常用音訓》ジュウ/あ…てる
《音読み》 ジュウ /シュ
/シュ /シュウ
/シュウ 〈ch
〈ch ng〉
《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる
《意味》
ng〉
《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる
《意味》
 {動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕
{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕
 {動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育
《類義》
→実
《異字同訓》
あたる/あてる。 →当
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育
《類義》
→実
《異字同訓》
あたる/あてる。 →当
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
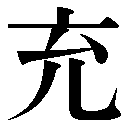 6画 儿部 [常用漢字]
区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B
《常用音訓》ジュウ/あ…てる
《音読み》 ジュウ
6画 儿部 [常用漢字]
区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B
《常用音訓》ジュウ/あ…てる
《音読み》 ジュウ /シュ
/シュ /シュウ
/シュウ 〈ch
〈ch ng〉
《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる
《意味》
ng〉
《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる
《意味》
 {動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕
{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕
 {動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育
《類義》
→実
《異字同訓》
あたる/あてる。 →当
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育
《類義》
→実
《異字同訓》
あたる/あてる。 →当
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
宛 あて🔗⭐🔉
【宛】
 8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン(
8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン( ン)
ン) /オン(ヲン)
/オン(ヲン) 〈yu
〈yu n・w
n・w n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
 {動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
 エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
 {副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
 「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕
「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕 あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」
あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」 ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
 会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる)
会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる) 円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン(
8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン( ン)
ン) /オン(ヲン)
/オン(ヲン) 〈yu
〈yu n・w
n・w n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
 {動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
 エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
 {副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
 「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕
「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕 あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」
あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」 ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
 会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる)
会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる) 円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
射 あてる🔗⭐🔉
【射】
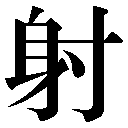 10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》
10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》  シャ
シャ /ジャ
/ジャ 〈sh
〈sh 〉/
〉/ ヤ
ヤ
 〈y
〈y 〉/
〉/ エキ
エキ /ヤク
/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》
《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》

 {動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
 {名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
 {動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
 「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。
「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

 {動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
 「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
 会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる)
会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
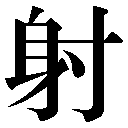 10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》
10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》  シャ
シャ /ジャ
/ジャ 〈sh
〈sh 〉/
〉/ ヤ
ヤ
 〈y
〈y 〉/
〉/ エキ
エキ /ヤク
/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》
《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》

 {動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
 {名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
 {動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
 「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。
「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

 {動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
 「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
 会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる)
会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
当 あてる🔗⭐🔉
【当】
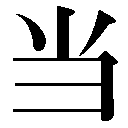 6画 小部 [二年]
区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396
【當】旧字旧字
6画 小部 [二年]
区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396
【當】旧字旧字
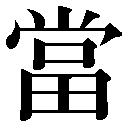 13画 田部
区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163
《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる
《音読み》 トウ(タウ)
13画 田部
区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163
《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる
《音読み》 トウ(タウ)
 〈d
〈d ng・d
ng・d ng〉
《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし
《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし
《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ
《意味》
 {動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」
{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」
 {動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」
{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」
 {動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕
{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕
 {動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」
{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」
 {助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕
{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕
 {名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」
{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」
 {名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」
《解字》
形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚
《単語家族》
賞(それに相当する礼を払う)
{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」
《解字》
形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚
《単語家族》
賞(それに相当する礼を払う) 傷(面をぶちあてこわす)などと同系。
《類義》
→可・→衝
《異字同訓》
あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
傷(面をぶちあてこわす)などと同系。
《類義》
→可・→衝
《異字同訓》
あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
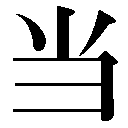 6画 小部 [二年]
区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396
【當】旧字旧字
6画 小部 [二年]
区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396
【當】旧字旧字
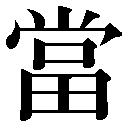 13画 田部
区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163
《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる
《音読み》 トウ(タウ)
13画 田部
区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163
《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる
《音読み》 トウ(タウ)
 〈d
〈d ng・d
ng・d ng〉
《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし
《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし
《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ
《意味》
 {動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」
{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」
 {動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」
{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」
 {動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕
{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕
 {動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」
{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」
 {助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕
{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕
 {名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」
{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」
 {名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」
《解字》
形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚
《単語家族》
賞(それに相当する礼を払う)
{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」
《解字》
形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚
《単語家族》
賞(それに相当する礼を払う) 傷(面をぶちあてこわす)などと同系。
《類義》
→可・→衝
《異字同訓》
あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
傷(面をぶちあてこわす)などと同系。
《類義》
→可・→衝
《異字同訓》
あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
抵 あてる🔗⭐🔉
【抵】
 8画
8画  部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
 {動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
 {動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
 {動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
 {動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
 「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
 {動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く)
{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画
8画  部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
 {動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
 {動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
 {動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
 {動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
 「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
 {動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く)
{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
椹 あてぎ🔗⭐🔉
【椹】
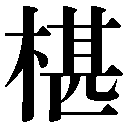 13画 木部
区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9
《音読み》
13画 木部
区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9
《音読み》  チン(チム)
チン(チム)
 〈zh
〈zh n〉/
n〉/ ジン(ジム)
ジン(ジム) /シン(シム)
/シン(シム) 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)
《意味》
n〉
《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)
《意味》

 {名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。
{名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。
 {名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。
{名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。
 {名}くわの実。
〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。
《単語家族》
沈
{名}くわの実。
〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。
《単語家族》
沈 枕(下におくまくら)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枕(下におくまくら)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
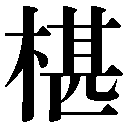 13画 木部
区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9
《音読み》
13画 木部
区点=6027 16進=5C3B シフトJIS=9EB9
《音読み》  チン(チム)
チン(チム)
 〈zh
〈zh n〉/
n〉/ ジン(ジム)
ジン(ジム) /シン(シム)
/シン(シム) 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)
《意味》
n〉
《訓読み》 あてぎ/きぬた/さわら(さはら)
《意味》

 {名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。
{名}あてぎ。木をわるとき、下におく台。
 {名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。
{名}きぬた。衣料をたたくとき、下にしく石の台。▽碪チン・砧チンに当てた用法。
 {名}くわの実。
〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。
《単語家族》
沈
{名}くわの実。
〔国〕さわら(サハラ)。木の名。ひのき科の常緑高木。葉はひのきに似ている。材は桶オケなどをつくるのに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符甚シン・チン(下に沈む、下におく)」で、下におく木の台。
《単語家族》
沈 枕(下におくまくら)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枕(下におくまくら)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「あて」で始まるの検索結果 1-6。