複数辞典一括検索+![]()
![]()
俘 とりこ🔗⭐🔉
【俘】
 9画 人部
区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8
《音読み》 フ
9画 人部
区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)
《意味》
〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)
《意味》
 {名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕
{名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕
 {動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。
《解字》
会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ)
{動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。
《解字》
会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ) 抱(だきこむ)
抱(だきこむ) 保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚
《類義》
→虜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚
《類義》
→虜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 人部
区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8
《音読み》 フ
9画 人部
区点=4858 16進=505A シフトJIS=98D8
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)
《意味》
〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)
《意味》
 {名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕
{名}とりこ。逃げないように囲んだ捕虜。「俘虜フリョ」「諸侯不相遺俘=諸侯ハ俘ヲ相ヒ遺ラズ」〔→左伝〕
 {動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。
《解字》
会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ)
{動}とりこにする(トリコニス)。捕らえて、わくの中へ入れる。
《解字》
会意兼形声。孚フは「爪(手の形)+子」の会意文字で、手で子どもを包むさまを示す。包(つつむ) 抱(だきこむ)
抱(だきこむ) 保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚
《類義》
→虜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
保(外を包んで中の物を保有する)と同系のことば。俘は「人+音符孚」で、捕らえた人間を外から囲んで、逃げないように、また、とらわれないように保有することを示す。→孚
《類義》
→虜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
取次 トリツギ🔗⭐🔉
取得 トリエ🔗⭐🔉
【取得】
 シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。
シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。 トリエ〔国〕長所。取り柄。
トリエ〔国〕長所。取り柄。
 シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。
シュトク(権利や資格などを)自分のものとすること。手に入れること。 トリエ〔国〕長所。取り柄。
トリエ〔国〕長所。取り柄。
堡 とりで🔗⭐🔉
【堡】
 12画 土部
区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6
《音読み》 ホウ
12画 土部
区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6
《音読み》 ホウ /ホ
/ホ 〈b
〈b o・b
o・b 〉
《訓読み》 とりで
《意味》
〉
《訓読み》 とりで
《意味》
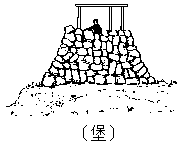 {名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」
《解字》
会意兼形声。「土+音符保」。
《熟語》
→下付・中付語
{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」
《解字》
会意兼形声。「土+音符保」。
《熟語》
→下付・中付語
 12画 土部
区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6
《音読み》 ホウ
12画 土部
区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6
《音読み》 ホウ /ホ
/ホ 〈b
〈b o・b
o・b 〉
《訓読み》 とりで
《意味》
〉
《訓読み》 とりで
《意味》
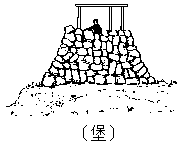 {名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」
《解字》
会意兼形声。「土+音符保」。
《熟語》
→下付・中付語
{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」
《解字》
会意兼形声。「土+音符保」。
《熟語》
→下付・中付語
塁 とりで🔗⭐🔉
【塁】
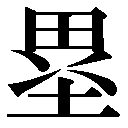 12画 土部 [常用漢字]
区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB
【壘】旧字人名に使える旧字
12画 土部 [常用漢字]
区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB
【壘】旧字人名に使える旧字
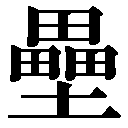 18画 土部
区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
18画 土部
区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
 〈l
〈l i〉
《訓読み》 とりで/るい
《名付け》 かさ・たか
《意味》
i〉
《訓読み》 とりで/るい
《名付け》 かさ・たか
《意味》
 {名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」
{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」
 {動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。
{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。
 「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。
〔国〕るい。野球のベース。「二塁」
《解字》
「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。
〔国〕るい。野球のベース。「二塁」
《解字》
 会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。
《単語家族》
磊ライ(重ねた石)
会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。
《単語家族》
磊ライ(重ねた石) 累(いくつも重ねてつらねる)
累(いくつも重ねてつらねる) 類(同じ物の集まり)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
類(同じ物の集まり)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
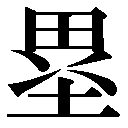 12画 土部 [常用漢字]
区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB
【壘】旧字人名に使える旧字
12画 土部 [常用漢字]
区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB
【壘】旧字人名に使える旧字
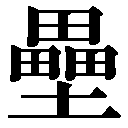 18画 土部
区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
18画 土部
区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
 〈l
〈l i〉
《訓読み》 とりで/るい
《名付け》 かさ・たか
《意味》
i〉
《訓読み》 とりで/るい
《名付け》 かさ・たか
《意味》
 {名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」
{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」
 {動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。
{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。
 「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。
〔国〕るい。野球のベース。「二塁」
《解字》
「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。
〔国〕るい。野球のベース。「二塁」
《解字》
 会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。
《単語家族》
磊ライ(重ねた石)
会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。
《単語家族》
磊ライ(重ねた石) 累(いくつも重ねてつらねる)
累(いくつも重ねてつらねる) 類(同じ物の集まり)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
類(同じ物の集まり)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
塞 とりで🔗⭐🔉
【塞】
 13画 土部
区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7
《音読み》
13画 土部
区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7
《音読み》  ソク
ソク
 〈s
〈s 〉/
〉/ サイ
サイ
 〈s
〈s i・s
i・s i〉
《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで
《意味》
i〉
《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで
《意味》

 {動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕
{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕
 {動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕
{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕
 {名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。
{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

 {名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」
{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」
 {名}地形の険しい要害の地。
{名}地形の険しい要害の地。
 {名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕
《解字》
{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕
《解字》
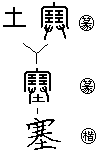 会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。
《単語家族》
即(そばにひっつく)
会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。
《単語家族》
即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
則(ぴったりとひっつく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 土部
区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7
《音読み》
13画 土部
区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7
《音読み》  ソク
ソク
 〈s
〈s 〉/
〉/ サイ
サイ
 〈s
〈s i・s
i・s i〉
《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで
《意味》
i〉
《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで
《意味》

 {動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕
{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕
 {動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕
{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕
 {名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。
{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

 {名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」
{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」
 {名}地形の険しい要害の地。
{名}地形の険しい要害の地。
 {名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕
《解字》
{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕
《解字》
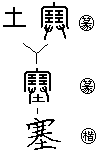 会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。
《単語家族》
即(そばにひっつく)
会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。
《単語家族》
即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
則(ぴったりとひっつく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
壁 とりで🔗⭐🔉
【壁】
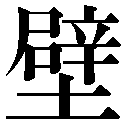 16画 土部 [常用漢字]
区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7
《常用音訓》ヘキ/かべ
《音読み》 ヘキ
16画 土部 [常用漢字]
区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7
《常用音訓》ヘキ/かべ
《音読み》 ヘキ /ヒャク
/ヒャク 〈b
〈b 〉
《訓読み》 かべ/とりで
《名付け》 かべ
《意味》
〉
《訓読み》 かべ/とりで
《名付け》 かべ
《意味》
 {名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」
{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」
 {名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。
{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。
 ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕
ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕
 {名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」
{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。
《単語家族》
碑(平らな石)
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。
《単語家族》
碑(平らな石) 屏ヘイ(平らなついたて)と同系。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
屏ヘイ(平らなついたて)と同系。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
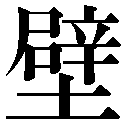 16画 土部 [常用漢字]
区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7
《常用音訓》ヘキ/かべ
《音読み》 ヘキ
16画 土部 [常用漢字]
区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7
《常用音訓》ヘキ/かべ
《音読み》 ヘキ /ヒャク
/ヒャク 〈b
〈b 〉
《訓読み》 かべ/とりで
《名付け》 かべ
《意味》
〉
《訓読み》 かべ/とりで
《名付け》 かべ
《意味》
 {名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」
{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」
 {名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。
{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。
 ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕
ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕
 {名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」
{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。
《単語家族》
碑(平らな石)
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。
《単語家族》
碑(平らな石) 屏ヘイ(平らなついたて)と同系。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
屏ヘイ(平らなついたて)と同系。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
寨 とりで🔗⭐🔉
屠竜之技 トリョウノギ🔗⭐🔉
【屠竜之技】
トリョウノギ〈故事〉竜を殺す技術。巧みではあるが実際の役にたたないわざのたとえ。〔→荘子〕
屠戮 トリク🔗⭐🔉
【屠戮】
トリク 牛・羊などを殺すようにむざんに殺す。
廓 とりで🔗⭐🔉
【廓】
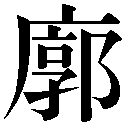 14画 广部
区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66
《音読み》 カク(ク
14画 广部
区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66
《音読み》 カク(ク ク)
ク)
 〈ku
〈ku 〉
《訓読み》 くるわ/とりで
《意味》
〉
《訓読み》 くるわ/とりで
《意味》
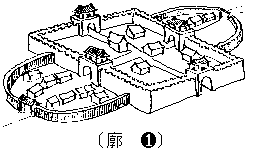
 {名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」
{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」
 {名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」
{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」
 {形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕
{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕
 {動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕
《解字》
会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭
《単語家族》
槨カク(棺おけの外わく)
{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕
《解字》
会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭
《単語家族》
槨カク(棺おけの外わく) 拡(外わくをはって中を広げる)
拡(外わくをはって中を広げる) 画カク(区切って囲む)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
画カク(区切って囲む)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
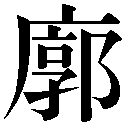 14画 广部
区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66
《音読み》 カク(ク
14画 广部
区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66
《音読み》 カク(ク ク)
ク)
 〈ku
〈ku 〉
《訓読み》 くるわ/とりで
《意味》
〉
《訓読み》 くるわ/とりで
《意味》
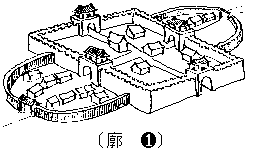
 {名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」
{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」
 {名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」
{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」
 {形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕
{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕
 {動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕
《解字》
会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭
《単語家族》
槨カク(棺おけの外わく)
{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕
《解字》
会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭
《単語家族》
槨カク(棺おけの外わく) 拡(外わくをはって中を広げる)
拡(外わくをはって中を広げる) 画カク(区切って囲む)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
画カク(区切って囲む)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
擒 とりこ🔗⭐🔉
【擒】
 16画
16画  部
区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0
《音読み》 キン(キム)
部
区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0
《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)
/ゴン(ゴム) 〈q
〈q n〉
《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
n〉
《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
 {動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕
{動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕
 {名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ
{名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ ンナリ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。
《単語家族》
陰(ふさがる)
ンナリ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。
《単語家族》
陰(ふさがる) 禁(行動をふさぎ止める)
禁(行動をふさぎ止める) 含(ふさぐ)などと同系。
《類義》
→捕
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
含(ふさぐ)などと同系。
《類義》
→捕
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画
16画  部
区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0
《音読み》 キン(キム)
部
区点=5802 16進=5A22 シフトJIS=9DA0
《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)
/ゴン(ゴム) 〈q
〈q n〉
《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
n〉
《訓読み》 とらえる(とらふ)/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
 {動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕
{動}とらえる(トラフ)。とりこにする(トリコニス)。網や包囲網の中に閉じこめて、とらえる。行動を封じて、いけどりにする。〈同義語〉→禽キン。〈類義語〉→捉ソク・→捕。「悉擒就戮=悉ク擒ヘラレテ戮ニ就ク」〔→謝小娥〕
 {名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ
{名}とりこ。とらえられた人。また、とりこにすること。〈類義語〉→虜リョ。「就擒=擒ニ就ク」「此乃信之所以為陛下禽(=擒)也=コレスナハチ信ノ陛下ノ擒トナリシユ ンナリ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。
《単語家族》
陰(ふさがる)
ンナリ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。禽キンの原字は「柄つきの網+音符今」からなり、鳥獣を網で押さえて、とらえることを示す。擒キンは「手+音符禽」で、禽キンが網でとらえた鳥獣の意となったため、擒がその原義である動詞の意味をあらわすようになった。
《単語家族》
陰(ふさがる) 禁(行動をふさぎ止める)
禁(行動をふさぎ止める) 含(ふさぐ)などと同系。
《類義》
→捕
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
含(ふさぐ)などと同系。
《類義》
→捕
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
斗量 トリョウ🔗⭐🔉
【斗量】
トリョウ ますではかる。分量の多いことのたとえ。
斗糧 トリョウ🔗⭐🔉
【斗糧】
トリョウ わずかな食糧。『斗粮トリョウ』
柵 とりで🔗⭐🔉
【柵】
 9画 木部
区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2
《音読み》 サク
9画 木部
区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2
《音読み》 サク /シャク
/シャク /セン
/セン /サン
/サン 〈zh
〈zh 〉〈sh
〉〈sh n〉
《訓読み》 しがらみ/とりで
《意味》
n〉
《訓読み》 しがらみ/とりで
《意味》
 {名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」
{名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」
 {名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。
{名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。
 {名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」
《解字》
会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。
{名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」
《解字》
会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。
 9画 木部
区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2
《音読み》 サク
9画 木部
区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2
《音読み》 サク /シャク
/シャク /セン
/セン /サン
/サン 〈zh
〈zh 〉〈sh
〉〈sh n〉
《訓読み》 しがらみ/とりで
《意味》
n〉
《訓読み》 しがらみ/とりで
《意味》
 {名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」
{名}竹や木を長短ふぞろいに結び、それを立て並べて人が通れないようにしたもの。矢来ヤライ。「柵門サクモン」
 {名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。
{名}しがらみ。流れをせきとめるために、水中につくったさく。
 {名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」
《解字》
会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。
{名}とりで。規模の小さなしろ。さくをめぐらした根拠地。〈類義語〉→寨サイ。「柵塁サクルイ(木の矢来を立てたとりで)」
《解字》
会意兼形声。「木+音符册サク(長短ふぞろいな木簡を並べた短冊)」。じぐざぐした木のさく。
砦 とりで🔗⭐🔉
禽 とり🔗⭐🔉
【禽】
 13画
13画  部
区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7
《音読み》 キン(キム)
部
区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7
《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)
/ゴン(ゴム) 〈q
〈q n〉
《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
n〉
《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
 {名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕
{名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕
 {動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕
《解字》
{動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕
《解字》
 会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に
会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に (動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。
《単語家族》
吟(口をふさいでうなる)
(動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。
《単語家族》
吟(口をふさいでうなる) 禁(ふさぎとめる)
禁(ふさぎとめる) 陰(とじこめる)などと同系。
《類義》
鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
陰(とじこめる)などと同系。
《類義》
鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画
13画  部
区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7
《音読み》 キン(キム)
部
区点=2257 16進=3659 シフトJIS=8BD7
《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)
/ゴン(ゴム) 〈q
〈q n〉
《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
n〉
《訓読み》 とり/とりこにする(とりこにす)/とりこ
《意味》
 {名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕
{名}とり。網やわなで捕らえる動物。また、のち、猟をして捕らえるとりのこと。「禽獣キンジュウ(とりやけもの)」「君子之於禽獣也=君子ノ禽獣ニオケルヤ」〔→孟子〕
 {動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕
《解字》
{動・名}とりこにする(トリコニス)。とりこ。捕らえる。また、捕らえられたもの。〈同義語〉→擒キン。「何為為我禽=何スレゾ我ガ禽ト為ルヤ」〔→史記〕
《解字》
 会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に
会意兼形声。もと「柄つきの網+音符今キン(ふさぐ)」の会意兼形声文字。のち、下部に (動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。
《単語家族》
吟(口をふさいでうなる)
(動物の尻)を加えたもので、動物を網でおさえて逃げられぬようにふさぎとめること。擒キン(とらえる)の原字。
《単語家族》
吟(口をふさいでうなる) 禁(ふさぎとめる)
禁(ふさぎとめる) 陰(とじこめる)などと同系。
《類義》
鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
陰(とじこめる)などと同系。
《類義》
鳥は、吊チョウと同系で、長く尾をつり下げたとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
肚裏涙落 トリナミダオツ🔗⭐🔉
【肚裏涙落】
トリナミダオツ 心の中で泣く。表情にあらわさないで悲しみ嘆くこと。
虜 とりこ🔗⭐🔉
【虜】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 13画 虍部 [常用漢字]
区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8
《常用音訓》リョ
《音読み》 リョ
13画 虍部 [常用漢字]
区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8
《常用音訓》リョ
《音読み》 リョ /ル
/ル /ロ
/ロ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)
《意味》
〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)
《意味》
 {名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」
{名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」
 {動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」
{動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」
 {名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕
{名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕
 {名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」
{名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」
 {形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。
《解字》
形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。
《単語家族》
旅リョ(並んだ人々)
{形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。
《解字》
形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。
《単語家族》
旅リョ(並んだ人々) 侶リョ(並んだ仲間)
侶リョ(並んだ仲間) 呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。
《類義》
俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。
《類義》
俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 13画 虍部 [常用漢字]
区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8
《常用音訓》リョ
《音読み》 リョ
13画 虍部 [常用漢字]
区点=4626 16進=4E3A シフトJIS=97B8
《常用音訓》リョ
《音読み》 リョ /ル
/ル /ロ
/ロ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)
《意味》
〉
《訓読み》 とりこ/とりこにする(とりこにす)/つよい(つよし)
《意味》
 {名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」
{名}とりこ。何人もじゅずつなぎにしたとりこ。広く、いけどりにした人。〈類義語〉→獲カク・→俘フ。「捕虜」「虜囚(とりこ)」
 {動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」
{動}とりこにする(トリコニス)。いけどりにする。「虜之=コレヲ虜ニス」
 {名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕
{名・形}どれい。また、どれいのようにこき使うさま。▽昔、捕虜をどれいにして使ったことから。〈類義語〉→奴。「厳家無格虜=厳シキ家ニハ格虜無シ」〔→史記〕
 {名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」
{名}敵をののしっていうことば。「胡虜コリョ(敵である西北の遊牧民族、えびす)」
 {形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。
《解字》
形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。
《単語家族》
旅リョ(並んだ人々)
{形}つよい(ツヨシ)。あらっぽい。▽鹵ロに当てた用法。
《解字》
形声。「力+音符盧の略体」で、力ずくで捕らえ、じゅずつなぎにしたとりこのこと。
《単語家族》
旅リョ(並んだ人々) 侶リョ(並んだ仲間)
侶リョ(並んだ仲間) 呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。
《類義》
俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
呂リョ(じゅずつなぎに並んだ脊柱セキチュウ)などと同系。
《類義》
俘フは、逃げないようにおさえたとりこ。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
酉 とり🔗⭐🔉
【酉】
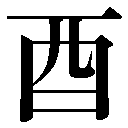 7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ)
7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
 象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
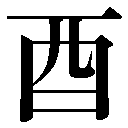 7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ)
7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
 象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
隹 とり🔗⭐🔉
【隹】
 8画 隹部
区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0
《音読み》 スイ
8画 隹部
区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0
《音読み》 スイ
 〈zhu
〈zhu 〉
《訓読み》 とり
《意味》
{名}とり。尾の短いとりの総称。
《解字》
〉
《訓読み》 とり
《意味》
{名}とり。尾の短いとりの総称。
《解字》
 象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。
《類義》
→鳥
象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。
《類義》
→鳥
 8画 隹部
区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0
《音読み》 スイ
8画 隹部
区点=8018 16進=7032 シフトJIS=E8B0
《音読み》 スイ
 〈zhu
〈zhu 〉
《訓読み》 とり
《意味》
{名}とり。尾の短いとりの総称。
《解字》
〉
《訓読み》 とり
《意味》
{名}とり。尾の短いとりの総称。
《解字》
 象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。
《類義》
→鳥
象形。尾の短いとりを描いたもの。▽ずんぐりと太いの意を含む。雀(すずめ)・隼(はやぶさ)・雉(きじ)などの字に含まれるが、鳥とともに、広く、とりを意味することばになった。
《類義》
→鳥
鳥 とり🔗⭐🔉
【鳥】
 11画 鳥部 [二年]
区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9
《常用音訓》チョウ/とり
《音読み》 チョウ(テウ)
11画 鳥部 [二年]
区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9
《常用音訓》チョウ/とり
《音読み》 チョウ(テウ)
 〈di
〈di o・ni
o・ni o〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり
《意味》
o〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり
《意味》
 {名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」
{名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」
 {形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」
{形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」
 {名}星の名。
《解字》
{名}星の名。
《解字》
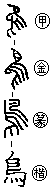 象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。
《単語家族》
蔦チョウ(ぶらさがるつた)
象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。
《単語家族》
蔦チョウ(ぶらさがるつた) 吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。
《類義》
隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。
《類義》
隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 鳥部 [二年]
区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9
《常用音訓》チョウ/とり
《音読み》 チョウ(テウ)
11画 鳥部 [二年]
区点=3627 16進=443B シフトJIS=92B9
《常用音訓》チョウ/とり
《音読み》 チョウ(テウ)
 〈di
〈di o・ni
o・ni o〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり
《意味》
o〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり
《意味》
 {名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」
{名}とり。尾のたれさがったとり。のち広くとりの総称に用いる。〈類義語〉→隹スイ・→禽キン。「鳥跡」「草木鳥獣」
 {形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」
{形}とりのごとく。人や物が、集まるさま。「鳥集」
 {名}星の名。
《解字》
{名}星の名。
《解字》
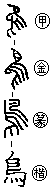 象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。
《単語家族》
蔦チョウ(ぶらさがるつた)
象形。尾のぶらさがったとりを描いたもの。北京語のniauは、ぶらりとたれた男性性器(diau)と同音であるのをさけた忌みことば。
《単語家族》
蔦チョウ(ぶらさがるつた) 吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。
《類義》
隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
吊チョウ(ぶらさがる)などと同系。
《類義》
隹スイは、ずんぐりとしたとり。禽キンは、あみでとらえて飼うとり。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
鳥之将死其鳴也哀 トリノマサニシセントスルヤソノナクコトカナシ🔗⭐🔉
【鳥之将死其鳴也哀】
トリノマサニシセントスルヤソノナクコトカナシ〈故事〉死にかかっている鳥は悲しい声で鳴くものだ。死に臨んだ人は、正しいことをいうということ。「鳥之将死其鳴也哀、人之将死其言也善=鳥ノマサニ死セントスルヤソノ鳴クコト哀シ、人ノマサニ死セントスルヤソノ言ヤ善シ」〔→論語〕
鳥目 トリメ🔗⭐🔉
【鳥目】
 チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。
チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。 トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。
トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。
 チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。
チョウモク〔国〕昔の銭。▽中央に穴があいていて、その形が鳥の目に似ていることからいう。 トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。
トリメ〔国〕夜、目が見えない病気。夜盲症。
鶏 とり🔗⭐🔉
【鶏】
 19画 鳥部 [常用漢字]
区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B
【鷄】旧字人名に使える旧字
19画 鳥部 [常用漢字]
区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B
【鷄】旧字人名に使える旧字
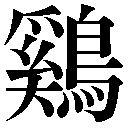 21画 鳥部
区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50
《常用音訓》ケイ/にわとり
《音読み》 ケイ
21画 鳥部
区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50
《常用音訓》ケイ/にわとり
《音読み》 ケイ /ケ
/ケ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり
《名付け》 とり
《意味》
{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。
《解字》
会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
〉
《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり
《名付け》 とり
《意味》
{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。
《解字》
会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 19画 鳥部 [常用漢字]
区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B
【鷄】旧字人名に使える旧字
19画 鳥部 [常用漢字]
区点=2360 16進=375C シフトJIS=8C7B
【鷄】旧字人名に使える旧字
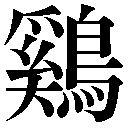 21画 鳥部
区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50
《常用音訓》ケイ/にわとり
《音読み》 ケイ
21画 鳥部
区点=8317 16進=7331 シフトJIS=EA50
《常用音訓》ケイ/にわとり
《音読み》 ケイ /ケ
/ケ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり
《名付け》 とり
《意味》
{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。
《解字》
会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
〉
《訓読み》 にわとり(にはとり)/とり
《名付け》 とり
《意味》
{名}にわとり(ニハトリ)。とり。家禽カキンの一種で、おんどりは、ときをつくる。肉・卵を食用にする。
《解字》
会意兼形声。奚ケイは「爪(手)+糸(ひも)」の会意文字で、系(ひもでつなぐ)の異体字。鷄は「鳥+音符奚」で、ひもでつないで飼った鳥のこと。また、たんなる形声文字と解して、けいけいと鳴く声をまねた擬声語と考えることもできる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「とり」で始まるの検索結果 1-26。
 次々に。順番に。「酔把花枝取次吟=酔フテ花枝ヲ把リ取次ニ吟ズ」〔
次々に。順番に。「酔把花枝取次吟=酔フテ花枝ヲ把リ取次ニ吟ズ」〔 あわただしい。また、ちょっとの間であるさま。「年光取次須偸賞=年光ハ取次ナリスベカラク偸ミ賞スベシ」〔
あわただしい。また、ちょっとの間であるさま。「年光取次須偸賞=年光ハ取次ナリスベカラク偸ミ賞スベシ」〔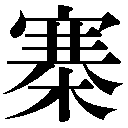 14画 宀部
区点=6045 16進=5C4D シフトJIS=9ECB
《音読み》 サイ
14画 宀部
区点=6045 16進=5C4D シフトJIS=9ECB
《音読み》 サイ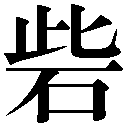 10画 石部
区点=2654 16進=3A56 シフトJIS=8DD4
《音読み》 サイ
10画 石部
区点=2654 16進=3A56 シフトJIS=8DD4
《音読み》 サイ