複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (11)
おお‐ごしょう【大小姓】オホ‥シヤウ🔗⭐🔉
おお‐ごしょう【大小姓】オホ‥シヤウ
身分が重く、奥勤めや使者役などをする年嵩としかさの小姓。元服した小姓。↔小小姓
だい‐しょう【大小】‥セウ🔗⭐🔉
だい‐しょう【大小】‥セウ
①大きいことと小さいこと。大きいものと小さいもの。大きいか、小さいか。「―を問わぬ」
②打刀うちがたなと脇差の小刀ちいさがたな。桃山時代から2尺以上の打刀と脇差とを併せ帯用するようになり、これを大小と呼んだ。江戸時代には武士の正式のものとなり、大小ともに拵こしらえの形式、塗・鐔つばなど外装をすべて揃えるようになった。
③大鼓おおつづみと小鼓こつづみ。
④大の月と小の月。
⑤陰暦を用いた頃、大小の月を、いろいろの趣向をこらして示した印刷物。大小暦。黄表紙、長生見度記ながいきみたいき「ここへ―を百枚下され」
⇒だいしょう‐いり【大小入り】
⇒だいしょう‐じ【大小事】
⇒だいしょう‐たいとう【大小対当】
⇒だいしょう‐の‐がく【大小の額】
⇒だいしょう‐の‐じんぎ【大小の神祇】
⇒だいしょう‐べん【大小便】
⇒だいしょう‐まえ【大小前】
⇒大小は武士の魂
だいしょう‐いり【大小入り】‥セウ‥🔗⭐🔉
だいしょう‐いり【大小入り】‥セウ‥
下座音楽の一つ。三味線に合わせて大鼓おおつづみ・小鼓こつづみの音を入れるもの。時代狂言の立回りに用いる。
⇒だい‐しょう【大小】
だいしょう‐じ【大小事】‥セウ‥🔗⭐🔉
だいしょう‐じ【大小事】‥セウ‥
大事と小事。大小の事柄。平治物語「紀伊二位の夫たるに依て、天下の―を執行ひ」
⇒だい‐しょう【大小】
だいしょう‐たいとう【大小対当】‥セウ‥タウ🔗⭐🔉
だいしょう‐たいとう【大小対当】‥セウ‥タウ
〔論〕(subalternatio ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称肯定命題(I)との対当関係および全称否定命題(E)と特称否定命題(O)との対当関係。
⇒だい‐しょう【大小】
だいしょう‐の‐がく【大小の額】‥セウ‥🔗⭐🔉
だいしょう‐の‐がく【大小の額】‥セウ‥
大の字を表に、小の字を裏に書いた額。大の月、小の月によって月々かけかえる。風俗文選「其の時の心に随ひ行くは、―見る心にや侍りけむ」
⇒だい‐しょう【大小】
だいしょう‐の‐じんぎ【大小の神祇】‥セウ‥🔗⭐🔉
だいしょう‐の‐じんぎ【大小の神祇】‥セウ‥
大社・小社の神祇。誓詞の末に用いる語。
⇒だい‐しょう【大小】
○大小は武士の魂だいしょうはぶしのたましい
大小の刀は武士の精神が宿っているもので、武士にとってはかけがえのないものである。
⇒だい‐しょう【大小】
○大小は武士の魂だいしょうはぶしのたましい🔗⭐🔉
○大小は武士の魂だいしょうはぶしのたましい
大小の刀は武士の精神が宿っているもので、武士にとってはかけがえのないものである。
⇒だい‐しょう【大小】
だいじょう‐ひぶっせつ‐ろん【大乗非仏説論】
大乗経典は仏説ではないとする論。古くインドにあり、日本では江戸中期の富永仲基が「出定後語」を著して非仏説を唱えた。近代、ヨーロッパにおける原典研究の立場から再提起され、明治期には村上専精らが歴史的立場からとの限定付きで主張。
⇒だい‐じょう【大乗】
だい‐じょうぶ【大丈夫】‥ヂヤウ‥
①(ダイジョウフとも)立派な男子。寂室録「参禅は実に―のことにして」
②しっかりしているさま。ごく堅固なさま。あぶなげのないさま。浮世床初「息子もよくかせいで利口者だから身上は―だ」。「強い地震にも―な建物」
③間違いなく。たしかに。「―、勘定は払うよ」
だいじょう‐ぶっきょう【大乗仏教】‥ケウ
紀元前後頃からインドに起こった改革派の仏教。従来の仏教が出家者中心・自利中心であったのを小乗仏教として批判し、それに対し、自分たちを菩薩と呼び利他中心の立場をとった。東アジアやチベットなどの北伝仏教はいずれも大乗仏教の流れを受けている。
⇒だい‐じょう【大乗】
だいしょう‐べん【大小便】‥セウ‥
大便と小便。
⇒だい‐しょう【大小】
たいしょう‐ほう【対照法】‥セウハフ
(antithesis)修辞法の一つ。相反した事物または程度のちがった事物を並べて、両者をいっそう鮮明にする技法。「提灯に釣鐘」の類。
⇒たい‐しょう【対照】
だいじょう‐ほうおう【太上法皇】‥ジヤウホフワウ
太上天皇が出家して後の称。法皇。
たいじょう‐ほうしん【帯状疱疹】‥ジヤウハウ‥
ヘルペス‐ウイルスによる帯状の有痛性発疹。肋間・頸・顔面・坐骨部など一定の末梢知覚神経に沿っておこり、小水疱が群生し周囲が発赤、所属リンパ節が腫はれる。約3週間で消退するが、神経痛を残すことがある。
⇒たい‐じょう【帯状】
たいしょうほうたい‐び【大詔奉戴日】‥セウ‥
「興亜奉公日」参照。
⇒たい‐しょう【大詔】
だいしょう‐まえ【大小前】‥セウマヘ
能舞台で大鼓おおつづみ方と小鼓こつづみ方の座席の中間前方をいう。→能舞台(図)
⇒だい‐しょう【大小】
だい‐じょうみゃく【大静脈】‥ジヤウ‥
体の各部からの血液を集めて心臓の右房に注ぐ静脈の本管。上下の二つから成り、上大静脈は上半身、下大静脈は下半身の血液を集め、心臓に入る。→内臓(図)
たいしょう‐めん【対称面】
「対称1㋐」参照。
⇒たい‐しょう【対称】
だい‐しょうり【大勝利】
おおきな勝利。大勝。大捷。
たいしょう‐りつ【対称律】
〔数〕ある集合の任意の2元に対して定義された関係〜について、a〜bならばb〜aという関係。反射律・推移律とともに同値の概念を規定する。
⇒たい‐しょう【対称】
たいしょう‐りょうほう【対症療法】‥シヤウレウハフ
患者の症状に対応して行う療法。高熱に解熱剤を用い、疼痛に鎮痛剤を用いる類。比喩的に、根本的な解決にならない当面の方策の意にも使う。「―で収支を合わせる」
⇒たい‐しょう【対症】
たいじょう‐ろうくん【太上老君】‥ジヤウラウ‥
(老君は老子の敬称)老子を神格化して呼ぶ称。道教の三尊の一つ。「魏書」釈老志などに見える。
⇒たい‐じょう【太上】
たいしょかん【大職冠】‥クワン
浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1711年(正徳1)初演。能の「海士あま」や幸若舞の「大織冠」などをもとに、蘇我入鹿と藤原鎌足のことを脚色。古浄瑠璃にもある。
たい‐しょく【大食】
①たくさん食うこと。おおぐい。「無芸―」
②〔史〕(→)タージに同じ。
⇒たいしょく‐かん【大食漢】
⇒たいしょく‐さいぼう【大食細胞】
⇒大食は命の取り越し
⇒大食腹に満つれば学問腹に入らず
たい‐しょく【体色】
生物体の表面の色。主に色素によるが、タマムシの甲など反射光線の干渉に起因する場合もある。
⇒たいしょく‐へんか【体色変化】
たい‐しょく【耐蝕・耐食】
腐食しにくいこと。「―性」
たい‐しょく【退色・褪色】
色がさめること。また、さめた色。「―しやすい色」
たい‐しょく【退食】
(朝廷から退いて、家に帰って食事する意)官吏が朝廷から退出すること。退朝。
たい‐しょく【退職】
現職を退くこと。「60歳で―する」↔就職。
⇒たいしょく‐きん【退職金】
⇒たいしょくしゃ‐いりょうせいど【退職者医療制度】
⇒たいしょく‐ねんきん【退職年金】
たい‐しょく【帯食】
〔天〕太陽または月が食のまま地平線に出現したり没したりすること。
たい‐しょく【黛色】
①まゆずみの色。
②山または樹木などの青ぐろい色。黛青。
たいしょく‐かん【大食漢】
おおぐらいの男。
⇒たい‐しょく【大食】
たいしょく‐きん【退職金】
退職に際して、雇主から退職者に支給される金銭の総称。退職手当・退職一時金の類。
⇒たい‐しょく【退職】
たいしょく‐さいぼう【大食細胞】‥バウ
(→)マクロファージに同じ。
⇒たい‐しょく【大食】
たいしょくしゃ‐いりょうせいど【退職者医療制度】‥レウ‥
医療保険制度の一種。対象は、老人保健法の適用が始まる75歳までの被用者年金保険の老齢退職年金受給者とその被扶養家族。
⇒たい‐しょく【退職】
たいしょく‐ねんきん【退職年金】
退職者に対して各種退職給付制度に基づいて支給される年金。在職期間や退職前の平均賃金・業績などに基づいて計算される。
⇒たい‐しょく【退職】
だいしょう‐べん【大小便】‥セウ‥🔗⭐🔉
だいしょう‐べん【大小便】‥セウ‥
大便と小便。
⇒だい‐しょう【大小】
だいしょう‐まえ【大小前】‥セウマヘ🔗⭐🔉
だいしょう‐まえ【大小前】‥セウマヘ
能舞台で大鼓おおつづみ方と小鼓こつづみ方の座席の中間前方をいう。→能舞台(図)
⇒だい‐しょう【大小】
○大は小を兼ねるだいはしょうをかねる🔗⭐🔉
○大は小を兼ねるだいはしょうをかねる
[春秋繁露度制]大きいものは小さいものの代りにも用いることができる。
⇒だい【大】
だいばだった【提婆達多】
(梵語Devadatta)釈尊の従弟で、斛飯王こくぼんのうの子。阿難の兄弟。出家して釈尊の弟子となり、後に背いて師に危害を加えようとしたが失敗し、死後無間地獄に堕ちたという。デーヴァダッタ。天授。調達。
⇒だいばだった‐ぼん【提婆達多品】
だいばだった‐ぼん【提婆達多品】
法華経二十八品中の第12。提婆達多の成仏、8歳の竜女が成仏することなどを説く。悪人成仏・女人成仏などの根拠として重視された。提婆品。
⇒だいばだった【提婆達多】
だい‐はち【大八】
大八車の略。代八。子孫鑑「―とて重宝なる車出来たり」
⇒だいはち‐ぐるま【大八車・代八車】
だい‐はち【第八】
8番目。8回目。
⇒だいはち‐げいじゅつ【第八芸術】
⇒だいはち‐こうとう‐がっこう【第八高等学校】
だいはち‐ぐるま【大八車・代八車】
(8人分の仕事の代りをする意)荷物運搬用の大きな二輪車で、2〜3人でひくもの。江戸前期から使用された。浄瑠璃、伽羅先代萩「坂道を押す―」
⇒だい‐はち【大八】
だいはち‐げいじゅつ【第八芸術】
(文芸・音楽・絵画・演劇・建築・彫刻・舞踊に次いで第8番目に現れた芸術の意)映画。1920年(大正9)半ばごろ流布。絵画・彫刻を美術として一括し、映画を第七芸術とすることもある。
⇒だい‐はち【第八】
だいはち‐こうとう‐がっこう【第八高等学校】‥カウ‥ガクカウ
旧制官立高等学校の一つ。1908年(明治41)名古屋市に設立。49年新制名古屋大学に統合。略称、八高。→名古屋大学
⇒だい‐はち【第八】
だい‐はちもんじ【大八文字】
「八文字」の足取りを大きくふむこと。
だいはちよう‐の‐くるま【大八葉の車】‥エフ‥
「八葉の車」の一種。小八葉に対し、高位の乗用。大八葉。
たい‐ばつ【体罰】
身体に直接に苦痛を与える罰。「―を加える」
だい‐はつ【大発】
大型の発動機を搭載した舟。
だい‐ばつ【題跋】
①題と跋。題辞と跋文。
②書物の末につける文章。跋文。
だい‐はっかい【大発会】‥クワイ
取引所で、新年最初の立会たちあい。初立会。↔大納会だいのうかい
だい‐はっせい【大発生】
ある種の生物が突発的に急激な増殖をすること。バッタが天日を被い大群をなして移動する、いわゆる飛蝗ひこうはその例。
だいはつねはん‐ぎょう【大般涅槃経】‥ギヤウ
①原始仏典の一つ。法顕訳。3巻。釈尊入滅の前後を歴史的に描いたもの。対応するものがパーリ語長部経典にあり、また、漢訳には「長阿含経」所収の「遊行ゆぎょう経」などの異訳がある。
②大乗仏典の一つ。北本(曇無讖どんむしん訳、40巻)と南本(慧観・謝霊運ら再治、36巻)とがある。釈尊の入滅を機縁として、法身の常住と一切衆生の成仏を説いたもの。涅槃経。
だいば‐ぼん【提婆品】
〔仏〕提婆達多品だいばだったぼんの略称。
⇒だいば【提婆】
たい‐はん【大凡】
おおよそ。あらまし。大略。大概。
たい‐はん【大半】
半分以上。過半。大部分。おおかた。「―を占める」「仕事は―片づいた」
たい‐はん【大藩】
①領知の石高の大きい藩。
②1868年(明治1)に、石高で諸藩を3等に分けたものの一つ。草高くさだか40万石以上のもの。70年には改めて物成ものなり15万石以上とした。
たい‐はん【退帆】
(明治期の語)船が帆をあげて帰っていくこと。
たい‐ばん【胎盤】
哺乳動物が妊娠した時、母体の子宮内壁と胎児との間にあって両者の栄養・呼吸・排泄などの機能を媒介・結合する盤状器官。母体と胎児の血液がこの部で接触し物質交換を行う。胎児とは臍帯さいたいで連絡。胎児の分娩後、胎盤も続いて排出されるが、これを俗に後産あとざん、排出された胎盤を胞衣えなという。
だい‐はん【台飯】
台盤の上にのせてある食物。源平盛衰記7「雀といふ小鳥になりて…―をめしけるこそいとあはれなれ」
だい‐ばん【代番】
本人に代わって勤番すること。
だい‐ばん【台盤】
(ダイハンとも)食物を盛った器をのせる台。4脚、横長の机状で、朱または黒の漆塗り、上面は縁が高くなっている。
台盤
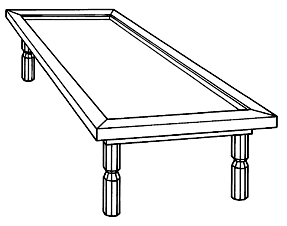 ⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【大判事】
①律令制の刑部省の上級の判事。
②1869年(明治2)に置いた最上級の判事。
だい‐ばんじゃく【大盤石】
①大きな岩。平家物語9「見下せば、―の苔むしたるが、つるべおとしに十四五丈ぞ」
②物事の基礎が堅固で、ゆるぎないこと。百座法談聞書抄「かれにくらぶれば―のやうになむあるべき」
だいばん‐どころ【台盤所】
①台盤を置く所。宮中では、清涼殿内の一室で、女房の詰所。貴人の家で、食物を調える所。紫式部日記「内の―にもてまゐるべき」→清涼殿(図)。
②大臣・大将の奥方の称。みだいどころ。平家物語1「花山院の左大臣の御み―にならせ給ひて」
⇒だい‐ばん【台盤】
だいはんにゃ【大般若】
狂言。僧が祈祷に来て大般若経の転読をしている時に、巫女みこが来て神楽を奏し、いつか僧の読経の調子が神楽の調子に釣りこまれる。
だいはんにゃ‐きょう【大般若経】‥キヤウ
最大の仏典。玄奘げんじょうの訳。600巻。般若波羅蜜(智慧・到彼岸)の義を説く諸経典を集大成したもの。般若(智慧)の立場から一切の存在はすべて空であるという空思想を説く。詳しくは「大般若波羅蜜多経だいはんにゃはらみったきょう」。
⇒だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】
だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】‥キヤウヱ
大般若経を真読または転読して除災招福や護国を祈る法会。般若会。大般若供養。
⇒だいはんにゃ‐きょう【大般若経】
たい‐ひ【対比】
①二つのものを突き合わせてくらべること。比較すること。「両案を―する」
②〔心〕(contrast)二つの相対立する感覚や感情などが空間的あるいは時間的に相接して現れる時、その差異が強調され、あるいは際立つ現象。例、明るさの対比、色の対比など。
③〔地〕(correlation)離れた地域にある地層が互いに同時代のものかどうかを決めること。化石や地層(例えば火山灰層)などによって行う。
たい‐ひ【待避】
わきにさけて事の過ぎるのを待つこと。「特急の通過を―する」
⇒たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】
⇒たいひ‐せん【待避線】
たい‐ひ【苔碑】
苔こけのむした石碑。
たい‐ひ【退避】
しりぞいて危険を避けること。「高台に―する」「―命令」
たい‐ひ【堆肥】
藁わら・ごみ・落葉・排泄物などを積み重ね、自然に発酵・腐熟させて作った肥料。つみごえ。
たい‐ひ【貸費】
学資などの、費用を貸すこと。森鴎外、半日「博士が其頃の―生といふものになりおふせる迄にしたのは」
たい‐び【大尾】
おわり。しまい。終局。結末。
たい‐び【黛眉】
まゆずみでかいた眉。
だい‐ひ【大悲】
〔仏〕
①衆生しゅじょうを苦しみから救い出す仏・菩薩の大きな慈悲の心。→大慈大悲。
②観世音の別名。
⇒だいひ‐かく【大悲閣】
⇒だいひ‐かんのん【大悲観音】
⇒だいひ‐さ【大悲者】
⇒だいひ‐じゅ【大悲呪】
⇒だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
⇒だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
だいひ‐かく【大悲閣】
観世音菩薩の像を安置した仏堂。特に、1614年(慶長19)角倉了以が京都嵐山に建立した千光寺をいう。観音堂。
⇒だい‐ひ【大悲】
だいひ‐かんのん【大悲観音】‥クワンオン
①六観音の一つ。千手観音の別称。
②観世音のこと。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びき【台引】
①宴会の膳などに敷く紙。
②本膳料理に添える引物。
だい‐びき【代引き】
「代金引換え」の略。
だい‐ひきもの【台引物】
膳部に添え台に載せて出す肴・菓子の類。客に持ち帰らせるもの。
たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】‥ガウ
その中に身を隠し、弾丸などを避けるための穴。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐さ【大悲者】
大慈悲者の意で、諸仏・菩薩、特に観世音の称。だいひしゃ。源氏物語玉鬘「―には、こと事も申さじ」
⇒だい‐ひ【大悲】
たいひ‐さん【玳皮盞】
中国江西省吉州窯産で、釉うわぐすりをかけた茶碗の外部に、玳瑁たいまいすなわち鼈甲べっこうのような文様が現れたもの。
たい‐びしお【鯛醤】タヒビシホ
タイの身で製したひしお。→ししびしお
だいひ‐じゅ【大悲呪】
千手陀羅尼せんじゅだらにの別称。平家物語3「心をいたして―を称誦せば」
⇒だい‐ひ【大悲】
タイピスト【typist】
タイプライターを打つのを職業とする人。
たいひ‐せん【待避線】
鉄道で、列車の行き違いまたは追い越しのさい、一方が避けるために設けた線路。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
多聞天すなわち毘沙門天びしゃもんてんの別称。
⇒だい‐ひ【大悲】
たい‐ひつ【大筆】
筆跡・詩文などの傑作。
だい‐ひつ【大弼】
①紫微中台しびちゅうだいの次官。
②律令制の弾正台だんじょうだいの次官。少弼の上位。明治官制でも弾正台の次官。
だい‐ひつ【代筆】
本人に代わって書くこと。また、その書いたもの。代書。「手紙を―する」↔直筆↔自筆
だいひのせんろっぽん【大悲千禄本】‥ロク‥
黄表紙。1巻。芝全交作、山東京伝画。1785年(天明5)刊。不景気で千手観音が千の手を損料貸しにするという滑稽を描いた作。
→文献資料[大悲千禄本]
だいびばしゃろん【大毘婆沙論】
説一切有部うぶの理論を総合した仏教論書。200巻。玄奘げんじょう訳。2世紀前半頃カシミールで成立。婆沙論。詳しくは「阿毘達磨大毘婆沙論」。
だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
①観世音菩薩の異称。
②鎌倉時代の律宗の僧、覚盛かくじょうの諡号しごう。唐招提寺中興の開山。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びゃく【大百】
(→)大百日おおびゃくにちに同じ。
だい‐びゃくえ【大白衣】
①大白衣法の略。
②(→)白衣観音に同じ。三十三観音の一つ。
⇒だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】
だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】‥ホフ
〔仏〕台密で、大白衣観音を本尊として修する秘法。
⇒だい‐びゃくえ【大白衣】
だいびゃくご‐しゃ【大白牛車】
〔仏〕大きな白牛の引く車。法華経譬喩品に説く。すべての人が成仏できるという一乗・仏乗のたとえに用いられる。日本霊異記下「―を得むが為に、願を発し、仏を造り」→牛の車
たい‐ひょう【体表】‥ヘウ
からだの表面。
たい‐びょう【大病】‥ビヤウ
重い病気。重病。大患。重患。〈文明本節用集〉。「―を病む」
⇒大病に薬無し
たい‐びょう【大廟】‥ベウ
①君主の祖先をまつったみたまや。宗廟。
②伊勢大神宮の称。
だい‐ひょう【大兵】‥ヒヤウ
体の大きく、たくましいこと。また、そういう男。「―肥満」↔小兵こひょう
だい‐ひょう【代表】‥ヘウ
①法人・団体または一個人に代わってその意思を外部に表示すること。また、その人。「親族を―して挨拶する」「―者」
②全体を示すものとなるような、一つのものまたは一部分。「日本文学を―する作品」「輸出品の―格」
⇒だいひょう‐けん【代表権】
⇒だいひょう‐さく【代表作】
⇒だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】
⇒だいひょう‐しつもん【代表質問】
⇒だいひょう‐しゃいん【代表社員】
⇒だいひょう‐ち【代表値】
⇒だいひょう‐てき【代表的】
⇒だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】
⇒だいひょう‐みんしゅせい【代表民主制】
だいひょう‐けん【代表権】‥ヘウ‥
代表することができる権限。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐さく【代表作】‥ヘウ‥
その作者の特色を最もよく表した作品。また、その作者の作品のうち最もすぐれたもの。
⇒だい‐ひょう【代表】
だい‐びょうし【大拍子】‥ビヤウ‥
①里神楽に用いる、一種の締太鼓。
②歌舞伎囃子の一つ。1に大太鼓を打ち合わせ、それに篠笛・三味線の入るものもある。神社の場などに用いる。
だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】‥ヘウ‥カウ‥
委員会設置会社を代表する権限をもつ執行役。取締役会に選任された執行役の中から選定する。委員会設置会社以外の株式会社における代表取締役に相当。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しつもん【代表質問】‥ヘウ‥
国会で、政府演説に対する各党の代表者からの質問。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しゃいん【代表社員】‥ヘウ‥ヰン
①合名会社・合資会社・合同会社の社員のうち、会社を代表する権限をもつ者。
②弁護士法人・監査法人・税理士法人・中間法人などの社員を代表する者。
⇒だい‐ひょう【代表】
たいびょう‐せい【耐病性】‥ビヤウ‥
病害に対する生物、特に作物・家畜などの抵抗性。
だいひょう‐ち【代表値】‥ヘウ‥
統計で、資料の客観的尺度とする数値。平均値・中央値など。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐てき【代表的】‥ヘウ‥
一つのもので全体の性質や特徴を表しているさま。「―な作品」
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】‥ヘウ‥
取締役会で選定され、会社を代表する権限をもつ取締役。通常は社長のほか、副社長・専務取締役なども代表権をもつ。
⇒だい‐ひょう【代表】
⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【大判事】
①律令制の刑部省の上級の判事。
②1869年(明治2)に置いた最上級の判事。
だい‐ばんじゃく【大盤石】
①大きな岩。平家物語9「見下せば、―の苔むしたるが、つるべおとしに十四五丈ぞ」
②物事の基礎が堅固で、ゆるぎないこと。百座法談聞書抄「かれにくらぶれば―のやうになむあるべき」
だいばん‐どころ【台盤所】
①台盤を置く所。宮中では、清涼殿内の一室で、女房の詰所。貴人の家で、食物を調える所。紫式部日記「内の―にもてまゐるべき」→清涼殿(図)。
②大臣・大将の奥方の称。みだいどころ。平家物語1「花山院の左大臣の御み―にならせ給ひて」
⇒だい‐ばん【台盤】
だいはんにゃ【大般若】
狂言。僧が祈祷に来て大般若経の転読をしている時に、巫女みこが来て神楽を奏し、いつか僧の読経の調子が神楽の調子に釣りこまれる。
だいはんにゃ‐きょう【大般若経】‥キヤウ
最大の仏典。玄奘げんじょうの訳。600巻。般若波羅蜜(智慧・到彼岸)の義を説く諸経典を集大成したもの。般若(智慧)の立場から一切の存在はすべて空であるという空思想を説く。詳しくは「大般若波羅蜜多経だいはんにゃはらみったきょう」。
⇒だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】
だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】‥キヤウヱ
大般若経を真読または転読して除災招福や護国を祈る法会。般若会。大般若供養。
⇒だいはんにゃ‐きょう【大般若経】
たい‐ひ【対比】
①二つのものを突き合わせてくらべること。比較すること。「両案を―する」
②〔心〕(contrast)二つの相対立する感覚や感情などが空間的あるいは時間的に相接して現れる時、その差異が強調され、あるいは際立つ現象。例、明るさの対比、色の対比など。
③〔地〕(correlation)離れた地域にある地層が互いに同時代のものかどうかを決めること。化石や地層(例えば火山灰層)などによって行う。
たい‐ひ【待避】
わきにさけて事の過ぎるのを待つこと。「特急の通過を―する」
⇒たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】
⇒たいひ‐せん【待避線】
たい‐ひ【苔碑】
苔こけのむした石碑。
たい‐ひ【退避】
しりぞいて危険を避けること。「高台に―する」「―命令」
たい‐ひ【堆肥】
藁わら・ごみ・落葉・排泄物などを積み重ね、自然に発酵・腐熟させて作った肥料。つみごえ。
たい‐ひ【貸費】
学資などの、費用を貸すこと。森鴎外、半日「博士が其頃の―生といふものになりおふせる迄にしたのは」
たい‐び【大尾】
おわり。しまい。終局。結末。
たい‐び【黛眉】
まゆずみでかいた眉。
だい‐ひ【大悲】
〔仏〕
①衆生しゅじょうを苦しみから救い出す仏・菩薩の大きな慈悲の心。→大慈大悲。
②観世音の別名。
⇒だいひ‐かく【大悲閣】
⇒だいひ‐かんのん【大悲観音】
⇒だいひ‐さ【大悲者】
⇒だいひ‐じゅ【大悲呪】
⇒だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
⇒だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
だいひ‐かく【大悲閣】
観世音菩薩の像を安置した仏堂。特に、1614年(慶長19)角倉了以が京都嵐山に建立した千光寺をいう。観音堂。
⇒だい‐ひ【大悲】
だいひ‐かんのん【大悲観音】‥クワンオン
①六観音の一つ。千手観音の別称。
②観世音のこと。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びき【台引】
①宴会の膳などに敷く紙。
②本膳料理に添える引物。
だい‐びき【代引き】
「代金引換え」の略。
だい‐ひきもの【台引物】
膳部に添え台に載せて出す肴・菓子の類。客に持ち帰らせるもの。
たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】‥ガウ
その中に身を隠し、弾丸などを避けるための穴。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐さ【大悲者】
大慈悲者の意で、諸仏・菩薩、特に観世音の称。だいひしゃ。源氏物語玉鬘「―には、こと事も申さじ」
⇒だい‐ひ【大悲】
たいひ‐さん【玳皮盞】
中国江西省吉州窯産で、釉うわぐすりをかけた茶碗の外部に、玳瑁たいまいすなわち鼈甲べっこうのような文様が現れたもの。
たい‐びしお【鯛醤】タヒビシホ
タイの身で製したひしお。→ししびしお
だいひ‐じゅ【大悲呪】
千手陀羅尼せんじゅだらにの別称。平家物語3「心をいたして―を称誦せば」
⇒だい‐ひ【大悲】
タイピスト【typist】
タイプライターを打つのを職業とする人。
たいひ‐せん【待避線】
鉄道で、列車の行き違いまたは追い越しのさい、一方が避けるために設けた線路。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
多聞天すなわち毘沙門天びしゃもんてんの別称。
⇒だい‐ひ【大悲】
たい‐ひつ【大筆】
筆跡・詩文などの傑作。
だい‐ひつ【大弼】
①紫微中台しびちゅうだいの次官。
②律令制の弾正台だんじょうだいの次官。少弼の上位。明治官制でも弾正台の次官。
だい‐ひつ【代筆】
本人に代わって書くこと。また、その書いたもの。代書。「手紙を―する」↔直筆↔自筆
だいひのせんろっぽん【大悲千禄本】‥ロク‥
黄表紙。1巻。芝全交作、山東京伝画。1785年(天明5)刊。不景気で千手観音が千の手を損料貸しにするという滑稽を描いた作。
→文献資料[大悲千禄本]
だいびばしゃろん【大毘婆沙論】
説一切有部うぶの理論を総合した仏教論書。200巻。玄奘げんじょう訳。2世紀前半頃カシミールで成立。婆沙論。詳しくは「阿毘達磨大毘婆沙論」。
だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
①観世音菩薩の異称。
②鎌倉時代の律宗の僧、覚盛かくじょうの諡号しごう。唐招提寺中興の開山。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びゃく【大百】
(→)大百日おおびゃくにちに同じ。
だい‐びゃくえ【大白衣】
①大白衣法の略。
②(→)白衣観音に同じ。三十三観音の一つ。
⇒だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】
だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】‥ホフ
〔仏〕台密で、大白衣観音を本尊として修する秘法。
⇒だい‐びゃくえ【大白衣】
だいびゃくご‐しゃ【大白牛車】
〔仏〕大きな白牛の引く車。法華経譬喩品に説く。すべての人が成仏できるという一乗・仏乗のたとえに用いられる。日本霊異記下「―を得むが為に、願を発し、仏を造り」→牛の車
たい‐ひょう【体表】‥ヘウ
からだの表面。
たい‐びょう【大病】‥ビヤウ
重い病気。重病。大患。重患。〈文明本節用集〉。「―を病む」
⇒大病に薬無し
たい‐びょう【大廟】‥ベウ
①君主の祖先をまつったみたまや。宗廟。
②伊勢大神宮の称。
だい‐ひょう【大兵】‥ヒヤウ
体の大きく、たくましいこと。また、そういう男。「―肥満」↔小兵こひょう
だい‐ひょう【代表】‥ヘウ
①法人・団体または一個人に代わってその意思を外部に表示すること。また、その人。「親族を―して挨拶する」「―者」
②全体を示すものとなるような、一つのものまたは一部分。「日本文学を―する作品」「輸出品の―格」
⇒だいひょう‐けん【代表権】
⇒だいひょう‐さく【代表作】
⇒だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】
⇒だいひょう‐しつもん【代表質問】
⇒だいひょう‐しゃいん【代表社員】
⇒だいひょう‐ち【代表値】
⇒だいひょう‐てき【代表的】
⇒だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】
⇒だいひょう‐みんしゅせい【代表民主制】
だいひょう‐けん【代表権】‥ヘウ‥
代表することができる権限。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐さく【代表作】‥ヘウ‥
その作者の特色を最もよく表した作品。また、その作者の作品のうち最もすぐれたもの。
⇒だい‐ひょう【代表】
だい‐びょうし【大拍子】‥ビヤウ‥
①里神楽に用いる、一種の締太鼓。
②歌舞伎囃子の一つ。1に大太鼓を打ち合わせ、それに篠笛・三味線の入るものもある。神社の場などに用いる。
だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】‥ヘウ‥カウ‥
委員会設置会社を代表する権限をもつ執行役。取締役会に選任された執行役の中から選定する。委員会設置会社以外の株式会社における代表取締役に相当。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しつもん【代表質問】‥ヘウ‥
国会で、政府演説に対する各党の代表者からの質問。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しゃいん【代表社員】‥ヘウ‥ヰン
①合名会社・合資会社・合同会社の社員のうち、会社を代表する権限をもつ者。
②弁護士法人・監査法人・税理士法人・中間法人などの社員を代表する者。
⇒だい‐ひょう【代表】
たいびょう‐せい【耐病性】‥ビヤウ‥
病害に対する生物、特に作物・家畜などの抵抗性。
だいひょう‐ち【代表値】‥ヘウ‥
統計で、資料の客観的尺度とする数値。平均値・中央値など。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐てき【代表的】‥ヘウ‥
一つのもので全体の性質や特徴を表しているさま。「―な作品」
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】‥ヘウ‥
取締役会で選定され、会社を代表する権限をもつ取締役。通常は社長のほか、副社長・専務取締役なども代表権をもつ。
⇒だい‐ひょう【代表】
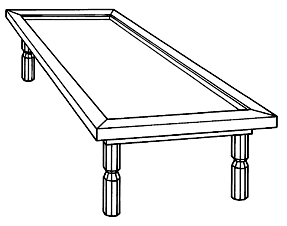 ⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【大判事】
①律令制の刑部省の上級の判事。
②1869年(明治2)に置いた最上級の判事。
だい‐ばんじゃく【大盤石】
①大きな岩。平家物語9「見下せば、―の苔むしたるが、つるべおとしに十四五丈ぞ」
②物事の基礎が堅固で、ゆるぎないこと。百座法談聞書抄「かれにくらぶれば―のやうになむあるべき」
だいばん‐どころ【台盤所】
①台盤を置く所。宮中では、清涼殿内の一室で、女房の詰所。貴人の家で、食物を調える所。紫式部日記「内の―にもてまゐるべき」→清涼殿(図)。
②大臣・大将の奥方の称。みだいどころ。平家物語1「花山院の左大臣の御み―にならせ給ひて」
⇒だい‐ばん【台盤】
だいはんにゃ【大般若】
狂言。僧が祈祷に来て大般若経の転読をしている時に、巫女みこが来て神楽を奏し、いつか僧の読経の調子が神楽の調子に釣りこまれる。
だいはんにゃ‐きょう【大般若経】‥キヤウ
最大の仏典。玄奘げんじょうの訳。600巻。般若波羅蜜(智慧・到彼岸)の義を説く諸経典を集大成したもの。般若(智慧)の立場から一切の存在はすべて空であるという空思想を説く。詳しくは「大般若波羅蜜多経だいはんにゃはらみったきょう」。
⇒だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】
だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】‥キヤウヱ
大般若経を真読または転読して除災招福や護国を祈る法会。般若会。大般若供養。
⇒だいはんにゃ‐きょう【大般若経】
たい‐ひ【対比】
①二つのものを突き合わせてくらべること。比較すること。「両案を―する」
②〔心〕(contrast)二つの相対立する感覚や感情などが空間的あるいは時間的に相接して現れる時、その差異が強調され、あるいは際立つ現象。例、明るさの対比、色の対比など。
③〔地〕(correlation)離れた地域にある地層が互いに同時代のものかどうかを決めること。化石や地層(例えば火山灰層)などによって行う。
たい‐ひ【待避】
わきにさけて事の過ぎるのを待つこと。「特急の通過を―する」
⇒たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】
⇒たいひ‐せん【待避線】
たい‐ひ【苔碑】
苔こけのむした石碑。
たい‐ひ【退避】
しりぞいて危険を避けること。「高台に―する」「―命令」
たい‐ひ【堆肥】
藁わら・ごみ・落葉・排泄物などを積み重ね、自然に発酵・腐熟させて作った肥料。つみごえ。
たい‐ひ【貸費】
学資などの、費用を貸すこと。森鴎外、半日「博士が其頃の―生といふものになりおふせる迄にしたのは」
たい‐び【大尾】
おわり。しまい。終局。結末。
たい‐び【黛眉】
まゆずみでかいた眉。
だい‐ひ【大悲】
〔仏〕
①衆生しゅじょうを苦しみから救い出す仏・菩薩の大きな慈悲の心。→大慈大悲。
②観世音の別名。
⇒だいひ‐かく【大悲閣】
⇒だいひ‐かんのん【大悲観音】
⇒だいひ‐さ【大悲者】
⇒だいひ‐じゅ【大悲呪】
⇒だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
⇒だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
だいひ‐かく【大悲閣】
観世音菩薩の像を安置した仏堂。特に、1614年(慶長19)角倉了以が京都嵐山に建立した千光寺をいう。観音堂。
⇒だい‐ひ【大悲】
だいひ‐かんのん【大悲観音】‥クワンオン
①六観音の一つ。千手観音の別称。
②観世音のこと。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びき【台引】
①宴会の膳などに敷く紙。
②本膳料理に添える引物。
だい‐びき【代引き】
「代金引換え」の略。
だい‐ひきもの【台引物】
膳部に添え台に載せて出す肴・菓子の類。客に持ち帰らせるもの。
たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】‥ガウ
その中に身を隠し、弾丸などを避けるための穴。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐さ【大悲者】
大慈悲者の意で、諸仏・菩薩、特に観世音の称。だいひしゃ。源氏物語玉鬘「―には、こと事も申さじ」
⇒だい‐ひ【大悲】
たいひ‐さん【玳皮盞】
中国江西省吉州窯産で、釉うわぐすりをかけた茶碗の外部に、玳瑁たいまいすなわち鼈甲べっこうのような文様が現れたもの。
たい‐びしお【鯛醤】タヒビシホ
タイの身で製したひしお。→ししびしお
だいひ‐じゅ【大悲呪】
千手陀羅尼せんじゅだらにの別称。平家物語3「心をいたして―を称誦せば」
⇒だい‐ひ【大悲】
タイピスト【typist】
タイプライターを打つのを職業とする人。
たいひ‐せん【待避線】
鉄道で、列車の行き違いまたは追い越しのさい、一方が避けるために設けた線路。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
多聞天すなわち毘沙門天びしゃもんてんの別称。
⇒だい‐ひ【大悲】
たい‐ひつ【大筆】
筆跡・詩文などの傑作。
だい‐ひつ【大弼】
①紫微中台しびちゅうだいの次官。
②律令制の弾正台だんじょうだいの次官。少弼の上位。明治官制でも弾正台の次官。
だい‐ひつ【代筆】
本人に代わって書くこと。また、その書いたもの。代書。「手紙を―する」↔直筆↔自筆
だいひのせんろっぽん【大悲千禄本】‥ロク‥
黄表紙。1巻。芝全交作、山東京伝画。1785年(天明5)刊。不景気で千手観音が千の手を損料貸しにするという滑稽を描いた作。
→文献資料[大悲千禄本]
だいびばしゃろん【大毘婆沙論】
説一切有部うぶの理論を総合した仏教論書。200巻。玄奘げんじょう訳。2世紀前半頃カシミールで成立。婆沙論。詳しくは「阿毘達磨大毘婆沙論」。
だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
①観世音菩薩の異称。
②鎌倉時代の律宗の僧、覚盛かくじょうの諡号しごう。唐招提寺中興の開山。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びゃく【大百】
(→)大百日おおびゃくにちに同じ。
だい‐びゃくえ【大白衣】
①大白衣法の略。
②(→)白衣観音に同じ。三十三観音の一つ。
⇒だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】
だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】‥ホフ
〔仏〕台密で、大白衣観音を本尊として修する秘法。
⇒だい‐びゃくえ【大白衣】
だいびゃくご‐しゃ【大白牛車】
〔仏〕大きな白牛の引く車。法華経譬喩品に説く。すべての人が成仏できるという一乗・仏乗のたとえに用いられる。日本霊異記下「―を得むが為に、願を発し、仏を造り」→牛の車
たい‐ひょう【体表】‥ヘウ
からだの表面。
たい‐びょう【大病】‥ビヤウ
重い病気。重病。大患。重患。〈文明本節用集〉。「―を病む」
⇒大病に薬無し
たい‐びょう【大廟】‥ベウ
①君主の祖先をまつったみたまや。宗廟。
②伊勢大神宮の称。
だい‐ひょう【大兵】‥ヒヤウ
体の大きく、たくましいこと。また、そういう男。「―肥満」↔小兵こひょう
だい‐ひょう【代表】‥ヘウ
①法人・団体または一個人に代わってその意思を外部に表示すること。また、その人。「親族を―して挨拶する」「―者」
②全体を示すものとなるような、一つのものまたは一部分。「日本文学を―する作品」「輸出品の―格」
⇒だいひょう‐けん【代表権】
⇒だいひょう‐さく【代表作】
⇒だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】
⇒だいひょう‐しつもん【代表質問】
⇒だいひょう‐しゃいん【代表社員】
⇒だいひょう‐ち【代表値】
⇒だいひょう‐てき【代表的】
⇒だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】
⇒だいひょう‐みんしゅせい【代表民主制】
だいひょう‐けん【代表権】‥ヘウ‥
代表することができる権限。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐さく【代表作】‥ヘウ‥
その作者の特色を最もよく表した作品。また、その作者の作品のうち最もすぐれたもの。
⇒だい‐ひょう【代表】
だい‐びょうし【大拍子】‥ビヤウ‥
①里神楽に用いる、一種の締太鼓。
②歌舞伎囃子の一つ。1に大太鼓を打ち合わせ、それに篠笛・三味線の入るものもある。神社の場などに用いる。
だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】‥ヘウ‥カウ‥
委員会設置会社を代表する権限をもつ執行役。取締役会に選任された執行役の中から選定する。委員会設置会社以外の株式会社における代表取締役に相当。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しつもん【代表質問】‥ヘウ‥
国会で、政府演説に対する各党の代表者からの質問。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しゃいん【代表社員】‥ヘウ‥ヰン
①合名会社・合資会社・合同会社の社員のうち、会社を代表する権限をもつ者。
②弁護士法人・監査法人・税理士法人・中間法人などの社員を代表する者。
⇒だい‐ひょう【代表】
たいびょう‐せい【耐病性】‥ビヤウ‥
病害に対する生物、特に作物・家畜などの抵抗性。
だいひょう‐ち【代表値】‥ヘウ‥
統計で、資料の客観的尺度とする数値。平均値・中央値など。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐てき【代表的】‥ヘウ‥
一つのもので全体の性質や特徴を表しているさま。「―な作品」
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】‥ヘウ‥
取締役会で選定され、会社を代表する権限をもつ取締役。通常は社長のほか、副社長・専務取締役なども代表権をもつ。
⇒だい‐ひょう【代表】
⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【大判事】
①律令制の刑部省の上級の判事。
②1869年(明治2)に置いた最上級の判事。
だい‐ばんじゃく【大盤石】
①大きな岩。平家物語9「見下せば、―の苔むしたるが、つるべおとしに十四五丈ぞ」
②物事の基礎が堅固で、ゆるぎないこと。百座法談聞書抄「かれにくらぶれば―のやうになむあるべき」
だいばん‐どころ【台盤所】
①台盤を置く所。宮中では、清涼殿内の一室で、女房の詰所。貴人の家で、食物を調える所。紫式部日記「内の―にもてまゐるべき」→清涼殿(図)。
②大臣・大将の奥方の称。みだいどころ。平家物語1「花山院の左大臣の御み―にならせ給ひて」
⇒だい‐ばん【台盤】
だいはんにゃ【大般若】
狂言。僧が祈祷に来て大般若経の転読をしている時に、巫女みこが来て神楽を奏し、いつか僧の読経の調子が神楽の調子に釣りこまれる。
だいはんにゃ‐きょう【大般若経】‥キヤウ
最大の仏典。玄奘げんじょうの訳。600巻。般若波羅蜜(智慧・到彼岸)の義を説く諸経典を集大成したもの。般若(智慧)の立場から一切の存在はすべて空であるという空思想を説く。詳しくは「大般若波羅蜜多経だいはんにゃはらみったきょう」。
⇒だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】
だいはんにゃきょう‐え【大般若経会】‥キヤウヱ
大般若経を真読または転読して除災招福や護国を祈る法会。般若会。大般若供養。
⇒だいはんにゃ‐きょう【大般若経】
たい‐ひ【対比】
①二つのものを突き合わせてくらべること。比較すること。「両案を―する」
②〔心〕(contrast)二つの相対立する感覚や感情などが空間的あるいは時間的に相接して現れる時、その差異が強調され、あるいは際立つ現象。例、明るさの対比、色の対比など。
③〔地〕(correlation)離れた地域にある地層が互いに同時代のものかどうかを決めること。化石や地層(例えば火山灰層)などによって行う。
たい‐ひ【待避】
わきにさけて事の過ぎるのを待つこと。「特急の通過を―する」
⇒たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】
⇒たいひ‐せん【待避線】
たい‐ひ【苔碑】
苔こけのむした石碑。
たい‐ひ【退避】
しりぞいて危険を避けること。「高台に―する」「―命令」
たい‐ひ【堆肥】
藁わら・ごみ・落葉・排泄物などを積み重ね、自然に発酵・腐熟させて作った肥料。つみごえ。
たい‐ひ【貸費】
学資などの、費用を貸すこと。森鴎外、半日「博士が其頃の―生といふものになりおふせる迄にしたのは」
たい‐び【大尾】
おわり。しまい。終局。結末。
たい‐び【黛眉】
まゆずみでかいた眉。
だい‐ひ【大悲】
〔仏〕
①衆生しゅじょうを苦しみから救い出す仏・菩薩の大きな慈悲の心。→大慈大悲。
②観世音の別名。
⇒だいひ‐かく【大悲閣】
⇒だいひ‐かんのん【大悲観音】
⇒だいひ‐さ【大悲者】
⇒だいひ‐じゅ【大悲呪】
⇒だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
⇒だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
だいひ‐かく【大悲閣】
観世音菩薩の像を安置した仏堂。特に、1614年(慶長19)角倉了以が京都嵐山に建立した千光寺をいう。観音堂。
⇒だい‐ひ【大悲】
だいひ‐かんのん【大悲観音】‥クワンオン
①六観音の一つ。千手観音の別称。
②観世音のこと。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びき【台引】
①宴会の膳などに敷く紙。
②本膳料理に添える引物。
だい‐びき【代引き】
「代金引換え」の略。
だい‐ひきもの【台引物】
膳部に添え台に載せて出す肴・菓子の類。客に持ち帰らせるもの。
たいひ‐ごう【待避壕・退避壕】‥ガウ
その中に身を隠し、弾丸などを避けるための穴。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐さ【大悲者】
大慈悲者の意で、諸仏・菩薩、特に観世音の称。だいひしゃ。源氏物語玉鬘「―には、こと事も申さじ」
⇒だい‐ひ【大悲】
たいひ‐さん【玳皮盞】
中国江西省吉州窯産で、釉うわぐすりをかけた茶碗の外部に、玳瑁たいまいすなわち鼈甲べっこうのような文様が現れたもの。
たい‐びしお【鯛醤】タヒビシホ
タイの身で製したひしお。→ししびしお
だいひ‐じゅ【大悲呪】
千手陀羅尼せんじゅだらにの別称。平家物語3「心をいたして―を称誦せば」
⇒だい‐ひ【大悲】
タイピスト【typist】
タイプライターを打つのを職業とする人。
たいひ‐せん【待避線】
鉄道で、列車の行き違いまたは追い越しのさい、一方が避けるために設けた線路。
⇒たい‐ひ【待避】
だいひ‐たもんてん【大悲多聞天】
多聞天すなわち毘沙門天びしゃもんてんの別称。
⇒だい‐ひ【大悲】
たい‐ひつ【大筆】
筆跡・詩文などの傑作。
だい‐ひつ【大弼】
①紫微中台しびちゅうだいの次官。
②律令制の弾正台だんじょうだいの次官。少弼の上位。明治官制でも弾正台の次官。
だい‐ひつ【代筆】
本人に代わって書くこと。また、その書いたもの。代書。「手紙を―する」↔直筆↔自筆
だいひのせんろっぽん【大悲千禄本】‥ロク‥
黄表紙。1巻。芝全交作、山東京伝画。1785年(天明5)刊。不景気で千手観音が千の手を損料貸しにするという滑稽を描いた作。
→文献資料[大悲千禄本]
だいびばしゃろん【大毘婆沙論】
説一切有部うぶの理論を総合した仏教論書。200巻。玄奘げんじょう訳。2世紀前半頃カシミールで成立。婆沙論。詳しくは「阿毘達磨大毘婆沙論」。
だいひ‐ぼさつ【大悲菩薩】
①観世音菩薩の異称。
②鎌倉時代の律宗の僧、覚盛かくじょうの諡号しごう。唐招提寺中興の開山。
⇒だい‐ひ【大悲】
だい‐びゃく【大百】
(→)大百日おおびゃくにちに同じ。
だい‐びゃくえ【大白衣】
①大白衣法の略。
②(→)白衣観音に同じ。三十三観音の一つ。
⇒だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】
だいびゃくえ‐ほう【大白衣法】‥ホフ
〔仏〕台密で、大白衣観音を本尊として修する秘法。
⇒だい‐びゃくえ【大白衣】
だいびゃくご‐しゃ【大白牛車】
〔仏〕大きな白牛の引く車。法華経譬喩品に説く。すべての人が成仏できるという一乗・仏乗のたとえに用いられる。日本霊異記下「―を得むが為に、願を発し、仏を造り」→牛の車
たい‐ひょう【体表】‥ヘウ
からだの表面。
たい‐びょう【大病】‥ビヤウ
重い病気。重病。大患。重患。〈文明本節用集〉。「―を病む」
⇒大病に薬無し
たい‐びょう【大廟】‥ベウ
①君主の祖先をまつったみたまや。宗廟。
②伊勢大神宮の称。
だい‐ひょう【大兵】‥ヒヤウ
体の大きく、たくましいこと。また、そういう男。「―肥満」↔小兵こひょう
だい‐ひょう【代表】‥ヘウ
①法人・団体または一個人に代わってその意思を外部に表示すること。また、その人。「親族を―して挨拶する」「―者」
②全体を示すものとなるような、一つのものまたは一部分。「日本文学を―する作品」「輸出品の―格」
⇒だいひょう‐けん【代表権】
⇒だいひょう‐さく【代表作】
⇒だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】
⇒だいひょう‐しつもん【代表質問】
⇒だいひょう‐しゃいん【代表社員】
⇒だいひょう‐ち【代表値】
⇒だいひょう‐てき【代表的】
⇒だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】
⇒だいひょう‐みんしゅせい【代表民主制】
だいひょう‐けん【代表権】‥ヘウ‥
代表することができる権限。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐さく【代表作】‥ヘウ‥
その作者の特色を最もよく表した作品。また、その作者の作品のうち最もすぐれたもの。
⇒だい‐ひょう【代表】
だい‐びょうし【大拍子】‥ビヤウ‥
①里神楽に用いる、一種の締太鼓。
②歌舞伎囃子の一つ。1に大太鼓を打ち合わせ、それに篠笛・三味線の入るものもある。神社の場などに用いる。
だいひょう‐しっこうやく【代表執行役】‥ヘウ‥カウ‥
委員会設置会社を代表する権限をもつ執行役。取締役会に選任された執行役の中から選定する。委員会設置会社以外の株式会社における代表取締役に相当。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しつもん【代表質問】‥ヘウ‥
国会で、政府演説に対する各党の代表者からの質問。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐しゃいん【代表社員】‥ヘウ‥ヰン
①合名会社・合資会社・合同会社の社員のうち、会社を代表する権限をもつ者。
②弁護士法人・監査法人・税理士法人・中間法人などの社員を代表する者。
⇒だい‐ひょう【代表】
たいびょう‐せい【耐病性】‥ビヤウ‥
病害に対する生物、特に作物・家畜などの抵抗性。
だいひょう‐ち【代表値】‥ヘウ‥
統計で、資料の客観的尺度とする数値。平均値・中央値など。
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐てき【代表的】‥ヘウ‥
一つのもので全体の性質や特徴を表しているさま。「―な作品」
⇒だい‐ひょう【代表】
だいひょう‐とりしまりやく【代表取締役】‥ヘウ‥
取締役会で選定され、会社を代表する権限をもつ取締役。通常は社長のほか、副社長・専務取締役なども代表権をもつ。
⇒だい‐ひょう【代表】
大辞林の検索結果 (11)
おお-ごしょう【大小姓】🔗⭐🔉
おお-ごしょう オホゴシヤウ [3] 【大小姓】
元服した小姓。
⇔小小姓
だい-しょう【大小】🔗⭐🔉
だい-しょう ―セウ [1] 【大小】
(1)大きいことと小さいこと。大きいものと小さいもの。「―とりまぜる」「―を問わない」
(2)大刀と小刀(脇差(ワキザシ))。「―をたばさむ」
(3)大鼓(オオツヅミ)と小鼓。
(4)大の月と小の月。「ツキノ―/ロドリゲス」
だいしょう=は武士の魂(タマシイ)🔗⭐🔉
――は武士の魂(タマシイ)
大刀・小刀は武士にとって自分の魂と同様に大切なものである。
だいしょう-いり【大小入り】🔗⭐🔉
だいしょう-いり ―セウ― [0] 【大小入り】
歌舞伎の下座音楽の一。三味線のほかに大鼓・小鼓の音を入れたもの。時代物の立ち回りなどに用いる。
だいしょう-じ【大小事】🔗⭐🔉
だいしょう-じ ―セウ― 【大小事】
大小のことがら。「天下の―を執行(トリオコナ)ひ/平治(上)」
だいしょう-たいとう【大小対当】🔗⭐🔉
だいしょう-たいとう ―セウ―タウ [1][5] 【大小対当】
〔論〕 対当関係の一。主語・述語を同じくする全称肯定判断と特称肯定判断,または全称否定判断と特称否定判断との論理的関係。
→対当関係
だいしょう-の-じんぎ【大小の神祇】🔗⭐🔉
だいしょう-の-じんぎ ―セウ― 【大小の神祇】
大社・小社の神々。もろもろの神々。
だいしょう-まえ【大小前】🔗⭐🔉
だいしょう-まえ ―セウマヘ [3] 【大小前】
能舞台で,正面奥の大鼓方と小鼓方の前あたりの場所をいう。
→能舞台
だい-しょうべん【大小便】🔗⭐🔉
だい-しょうべん ―セウベン [3][5] 【大小便】
大便と小便。
だい-しょうみょう【大小名】🔗⭐🔉
だい-しょうみょう ―セウミヤウ [3] 【大小名】
大名と小名。
だいしょう【大小様々の】(和英)🔗⭐🔉
だいしょう【大小様々の】
large and small;of all[various]sizes.
広辞苑+大辞林に「大小」で始まるの検索結果。