複数辞典一括検索+![]()
![]()
うじ【氏】🔗⭐🔉
うじ ウヂ [1] 【氏】
■一■ (名)
(1)家々の系統を表す名称。名字。姓。(ア)民法旧規定において,家の名称。(イ)現行法上,名とともに個人の呼称となるもの。原則として,夫婦と未婚の子は同じ氏を称する。
(2)家柄。
(3)事実上あるいは系譜上,同祖から出たものとされる家の集団。古代において支配階級の構成単位をなしていたもの。族長的地位に立つ家の家長が氏の上(カミ)となり,氏の共有財産(大化の改新以前の部民(ベノタミ)の田荘(タドコロ),律令制下の氏の賤(セン))を管理し,氏神を奉祀(ホウシ)して氏人(ウジビト)を統率した。氏には姓(カバネ)があり,社会における氏の政治的地位はこれによって秩序づけられた。律令制の解体とともに氏の名は次第に消え,源・平・藤・橘など少数のもののみが残った。
■二■ (接尾)
名字・姓名につけて,敬意を表す。「山田―」
〔現在では「し(氏)」という〕
うじ【蛆】🔗⭐🔉
うじ [2] 【蛆】
ハエやハチなどの幼虫。体は円筒形ないし紡錘形で脚を欠く。全身が白色を帯び,体表の毛は不明瞭。俗に,不潔な場所にわいて出ると信じられていた。[季]夏。
うじ【宇治】🔗⭐🔉
うし-あわせ【牛合(わ)せ】🔗⭐🔉
うし-あわせ ―アハセ [3] 【牛合(わ)せ】
牛と牛とを角を突き合わせて戦わせ,その勝負を見る遊び。闘牛。牛の角突き合い。
うじい【雲林院】🔗⭐🔉
うじい ウジ 【雲林院】
⇒うりんいん(雲林院)
【雲林院】
⇒うりんいん(雲林院)
 【雲林院】
⇒うりんいん(雲林院)
【雲林院】
⇒うりんいん(雲林院)
うじいえ【氏家】🔗⭐🔉
うじいえ ウジイヘ 【氏家】
栃木県中部,塩谷郡の町。近世,奥州街道の宿駅。
うじ-いし【宇治石】🔗⭐🔉
うじ-いし ウヂ― [2] 【宇治石】
京都府宇治市に産する濃緑色のかたい岩。茶臼(チヤウス)などを作る。
うし-いち【牛市】🔗⭐🔉
うし-いち [2][3][0] 【牛市】
牛を売買する市。牛のせり市。
うじ-うじ🔗⭐🔉
うじ-うじ ウヂウヂ [1] (副)スル
決断力がなく,思いためらうさま。「―(した)煮えきらない奴だ」
うし-うま【牛馬】🔗⭐🔉
うし-うま [0] 【牛馬】
小形のウマ。肩高1.3メートル内外。皮膚病のためとされるが,体毛が少なく,たてがみや尾の長い毛を欠き,尾は棒状。一見すると牛のように見えることからこの名がある。文禄・慶長の役のときに,朝鮮から持ち帰ったものといわれる。種子島に生き残っていたが,1947年(昭和22)頃絶滅。
うし-おい【牛追い】🔗⭐🔉
うし-おい ―オヒ [0][3] 【牛追い】
牛をあとから追って歩かせる人。うしかた。牛飼い。
うしおい-うた【牛追い唄】🔗⭐🔉
うしおい-うた ―オヒ― [3] 【牛追い唄】
民謡。牛方が牛を追うときに唄う唄。岩手県の「南部牛追い唄」が有名。牛方節(ウシカタブシ)。
うし-おうもの【牛追物】🔗⭐🔉
うし-おうもの ―オフモノ 【牛追物】
騎射の一。小牛を馬で追って蟇目(ヒキメ)の矢で射るもの。鎌倉時代に流行。
うし-かい【牛飼い】🔗⭐🔉
うし-かい ―カヒ [0][3] 【牛飼い】
(1)牛を飼う人。うしかた。
(2)「牛飼い童(ワラワ)」の略。
うしかい-わらわ【牛飼い童】🔗⭐🔉
うしかい-わらわ ―カヒワラハ 【牛飼い童】
牛車(ギツシヤ)の牛を扱う者。成人でも狩衣(カリギヌ)を着,もとどりを放った童形(ドウギヨウ)でいる。
うじ-かがのじょう【宇治加賀掾】🔗⭐🔉
うじ-かがのじょう ウヂ― 【宇治加賀掾】
(1635-1711) 上方(カミガタ)古浄瑠璃最後の太夫。嘉太夫(カダユウ)節の流祖。紀伊国の人。前名は宇治嘉太夫。謡曲・平曲などから曲節や題材を摂取して一派を開いた。近松門左衛門の作品を脚色して上演。のち,初世竹本義太夫と競演して敗れたが,義太夫節に対する影響は大きい。
うし-かけ【牛駈け】🔗⭐🔉
うし-かけ 【牛駈け】
昔,陰暦五月五日に大坂北野あたりで牛を川の堤へ引き出し放ち遊ばせた行事。牛のやぶ入り。
うし-かた【牛方】🔗⭐🔉
うし-かた [0] 【牛方】
牛を扱う人。牛を使って,荷物を運ぶことを業とする人。
うじ-がみ【氏神】🔗⭐🔉
うじ-がみ ウヂ― [0][3] 【氏神】
(1)古代の氏族が共同でまつった祖先神,あるいはその氏と特に縁故のある守護神。また,それをまつった神社。藤原氏の祖先神としての天児屋根命(アマノコヤネノミコト),守護神としての鹿島神宮・香取神宮,忌部氏の太玉命(フトタマノミコト),源氏の八幡宮など。
(2)室町時代以降,同一の地域内に居住する人々が共同でまつる神。産土神(ウブスナガミ)。
(3)屋敷神のこと。
うし-かもしか【牛羚羊】🔗⭐🔉
うし-かもしか [3] 【牛羚羊】
⇒ヌー
うじ-かわ🔗⭐🔉
うじ-かわ ウヂカハ (副)
ためらうさま。うじうじ。もじもじ。「恥かしかつたか門口で,― ―/浄瑠璃・一谷嫩軍記」
うじ-がわ【宇治川】🔗⭐🔉
うじ-がわ ウヂガハ 【宇治川】
京都府南部を流れる川。水源は琵琶湖。上流は瀬田川,宇治市で宇治川となり木津川・桂川と合流して淀川となる。古来,網代(アジロ)・川霧・柴舟などとともに歌によまれた。((歌枕))
うじがわ-の-せんじん【宇治川の先陣】🔗⭐🔉
うじがわ-の-せんじん ウヂガハ―センヂン 【宇治川の先陣】
1184年の宇治川の戦いで,源義経側の佐々木高綱と梶原景季が源頼朝から与えられた名馬生 (イケズキ)・磨墨(スルスミ)に乗って,宇治川を渡る先陣争いをしたこと。「平家物語」や「源平盛衰記」にみえる。
(イケズキ)・磨墨(スルスミ)に乗って,宇治川を渡る先陣争いをしたこと。「平家物語」や「源平盛衰記」にみえる。
 (イケズキ)・磨墨(スルスミ)に乗って,宇治川を渡る先陣争いをしたこと。「平家物語」や「源平盛衰記」にみえる。
(イケズキ)・磨墨(スルスミ)に乗って,宇治川を渡る先陣争いをしたこと。「平家物語」や「源平盛衰記」にみえる。
うじがわ-の-たたかい【宇治川の戦い】🔗⭐🔉
うじがわ-の-たたかい ウヂガハ―タタカヒ 【宇治川の戦い】
(1)1184年1月,源義経と木曾義仲の軍勢による宇治川をはさんでの戦い。佐々木高綱と梶原景季の先陣争いで有名。
(2)1221年6月,承久の乱のとき,朝廷軍が北条泰時の率いる幕府軍に大敗した戦い。
う-じく【羽軸】🔗⭐🔉
う-じく ―ヂク [0][1] 【羽軸】
羽毛の中央の軸。
うじ-くさ【蛆草】🔗⭐🔉
うじ-くさ [2][0] 【蛆草】
〔葉を,味噌の蛆を殺すのに用いたので〕
ミソナオシの別名。
うし-くよう【牛供養】🔗⭐🔉
うし-くよう ―クヤウ [3] 【牛供養】
中国地方で,花田植えのとき,美しく飾った牛に田の代掻(シロカ)きをさせる行事。
うじ-くろうど【氏蔵人】🔗⭐🔉
うじ-くろうど ウヂクラウド 【氏蔵人】
六位の蔵人の第三席にいるもの。藤原氏であれば藤(トウ)蔵人,源氏であれば源蔵人などと氏の名を冠して称する。
うじ-けいず【氏系図】🔗⭐🔉
うじ-けいず ウヂケイヅ [1] 【氏系図】
(1)氏の祖先から代々の続きを表した図。
(2)家筋。家系。家柄。家門。
うしけ-のり【牛毛苔】🔗⭐🔉
うしけ-のり [3] 【牛毛苔】
紅藻類ウシケノリ目の海藻。高潮線に近い岩上などに着生。分布は全世界的。藻体は紫褐色で細糸状,叢生したところは獣毛を思わせる。
うじ-こ【氏子】🔗⭐🔉
うじ-こ ウヂ― [0] 【氏子】
(1)共同の祖先神をまつる人々。氏の子。氏人。
(2)共通の氏神{(2)}をまつる人々。氏神が守護する地域に住む人々。
うじこ-いり【氏子入り】🔗⭐🔉
うじこ-いり ウヂ― [0] 【氏子入り】
新生児が初めて氏神{(2)}に参り,その氏子に加わる儀礼。嫁・婿が婚礼の際に婚家の氏神に参って氏子入りをする所も多い。
うじこ-じゅう【氏子中】🔗⭐🔉
うじこ-じゅう ウヂ―ヂユウ [3] 【氏子中】
同じ氏神{(2)}をまつる人々。氏子の仲間。氏子一同。
うじこ-そうだい【氏子総代】🔗⭐🔉
うじこ-そうだい ウヂ― [4] 【氏子総代】
氏子中の総代に選ばれた者。その神社の神職と協力して神社を維持する。氏子代表。
うじこ-ふだ【氏子札】🔗⭐🔉
うじこ-ふだ ウヂ― [3] 【氏子札】
新生児の宮参りのとき,氏神社が与える札。氏子であることを証する札。
うし-ころし【牛殺し】🔗⭐🔉
うし-ころし [3][0] 【牛殺し】
(1)牛を殺すことを職業とする人。
(2)〔牛の鼻木としたのでいう〕
植物カマツカの別名。
うし-さわら【牛鰆】🔗⭐🔉
うし-さわら ―サハラ [3] 【牛鰆】
スズキ目の海魚。全長2メートルに達する。体は紡錘形でやや長く,吻(フン)はとがり,尾びれは半月状となる。体色は背面が青緑色で腹面は白色。体側に淡い二列の斑点が並ぶ。味はサワラより劣る。南日本以南に分布。オキサワラ。
うじ-しちえん【宇治七園】🔗⭐🔉
うじ-しちえん ウヂシチ ン 【宇治七園】
足利義満が指定した宇治の茶園。森・川下・朝日・祝(井)・奥の山・宇文字・琵琶(または上林(カンバヤシ))の七か所。宇治茶発展の基礎となった。
ン 【宇治七園】
足利義満が指定した宇治の茶園。森・川下・朝日・祝(井)・奥の山・宇文字・琵琶(または上林(カンバヤシ))の七か所。宇治茶発展の基礎となった。
 ン 【宇治七園】
足利義満が指定した宇治の茶園。森・川下・朝日・祝(井)・奥の山・宇文字・琵琶(または上林(カンバヤシ))の七か所。宇治茶発展の基礎となった。
ン 【宇治七園】
足利義満が指定した宇治の茶園。森・川下・朝日・祝(井)・奥の山・宇文字・琵琶(または上林(カンバヤシ))の七か所。宇治茶発展の基礎となった。
うじしゅういものがたり【宇治拾遺物語】🔗⭐🔉
うじしゅういものがたり ウヂシフ ― 【宇治拾遺物語】
説話集。二巻。流布本一五巻。編者未詳。1212〜21年頃成立(のちに増補されたか)。仏教説話・滑稽談・民話・説話など一九七話を収録。軽妙な和文脈で民衆の生活感情や人間性を語る。
― 【宇治拾遺物語】
説話集。二巻。流布本一五巻。編者未詳。1212〜21年頃成立(のちに増補されたか)。仏教説話・滑稽談・民話・説話など一九七話を収録。軽妙な和文脈で民衆の生活感情や人間性を語る。
 ― 【宇治拾遺物語】
説話集。二巻。流布本一五巻。編者未詳。1212〜21年頃成立(のちに増補されたか)。仏教説話・滑稽談・民話・説話など一九七話を収録。軽妙な和文脈で民衆の生活感情や人間性を語る。
― 【宇治拾遺物語】
説話集。二巻。流布本一五巻。編者未詳。1212〜21年頃成立(のちに増補されたか)。仏教説話・滑稽談・民話・説話など一九七話を収録。軽妙な和文脈で民衆の生活感情や人間性を語る。
うじ-じゅうじょう【宇治十帖】🔗⭐🔉
うじ-じゅうじょう ウヂジフデフ 【宇治十帖】
源氏物語五四帖のうちの最後の一〇帖。薫大将を主人公に山城国宇治を舞台とする。橋姫・椎本(シイガモト)・総角(アゲマキ)・早蕨(サワラビ)・宿木・東屋・浮舟・蜻蛉・手習・夢浮橋の一〇帖。
うじ-すじょう【氏素性・氏素姓】🔗⭐🔉
うじ-すじょう ウヂスジヤウ [1] 【氏素性・氏素姓】
生まれや家柄。家系。
うじだいなごんものがたり【宇治大納言物語】🔗⭐🔉
うじだいなごんものがたり ウヂダイナゴン― 【宇治大納言物語】
散逸説話集。源隆国作と伝えられる。平安後期成立。多くの書にその書名が引用され,「今昔物語集」「宇治拾遺物語」をはじめ,後代への影響が非常に大きい。また,「今昔物語集」「宇治拾遺物語」「世継物語」などの別称としても呼ばれ,相互の混同を引き起こした。
う-しち【烏瑟】🔗⭐🔉
う-しち 【烏瑟】
「烏瑟膩沙(ウシチニシヤ)」に同じ。うしつ。「―みどりこまやかに,慈悲の御眼,蓮の如く開けたり/栄花(鳥の舞)」
うじ-ちゃ【宇治茶】🔗⭐🔉
うじ-ちゃ ウヂ― [2] 【宇治茶】
京都府宇治市周辺から産出される茶。古来良質の茶として賞美される。
うじ-つ・く🔗⭐🔉
うじ-つ・く ウヂ― (動カ四)
気後れして,ぐずぐずする。ためらう。「いや盗人のすつぱのと言ひちらされて,きよろりつと―・いてゐる人ぢやない/浄瑠璃・八百屋お七」
うし-つつき【牛突】🔗⭐🔉
うし-つつき [3] 【牛突】
スズメ目の鳥。ムクドリの類。サイ・キリン・ウシなどの背中にたかったダニを食べる。
うじ-でら【氏寺】🔗⭐🔉
うじ-でら ウヂ― [2][0] 【氏寺】
一家一門で建立し代々帰依する寺。藤原氏の興福寺,和気(ワケ)氏の神護寺などの類。
うし-とら【丑寅・艮】🔗⭐🔉
うし-とら [0] 【丑寅・艮】
方角を十二支にあてていうときの丑と寅との中間の方角。北東の方角。鬼門(キモン)にあたる。
うしとら-よけ【丑寅除け】🔗⭐🔉
うしとら-よけ [0] 【丑寅除け】
⇒鬼門除(キモンヨ)け
うじな【狢】🔗⭐🔉
うじな 【狢】
ムジナの古名。「陸奥国に―有りて/日本書紀(推古訓)」
うじ-な【氏名】🔗⭐🔉
うじ-な ウヂ― [1] 【氏名】
名字。姓。
うじな【宇品】🔗⭐🔉
うじな 【宇品】
広島市南部の港湾地区。広島港の通称。
うしなわれたときをもとめて【失われた時を求めて】🔗⭐🔉
うしなわれたときをもとめて ウシナハレタ― 【失われた時を求めて】
〔原題 (フランス)  la recherche du temps perdu〕
プルーストの長編小説。全七巻。1913〜27年刊行。話者(私)の人生と恋愛の遍歴を複雑な時間構成でたどり,無意志的記憶の喚起によって意識の深層に光をあてた作品で,小説の概念に新規な局面を与えた。
la recherche du temps perdu〕
プルーストの長編小説。全七巻。1913〜27年刊行。話者(私)の人生と恋愛の遍歴を複雑な時間構成でたどり,無意志的記憶の喚起によって意識の深層に光をあてた作品で,小説の概念に新規な局面を与えた。
 la recherche du temps perdu〕
プルーストの長編小説。全七巻。1913〜27年刊行。話者(私)の人生と恋愛の遍歴を複雑な時間構成でたどり,無意志的記憶の喚起によって意識の深層に光をあてた作品で,小説の概念に新規な局面を与えた。
la recherche du temps perdu〕
プルーストの長編小説。全七巻。1913〜27年刊行。話者(私)の人生と恋愛の遍歴を複雑な時間構成でたどり,無意志的記憶の喚起によって意識の深層に光をあてた作品で,小説の概念に新規な局面を与えた。
うじ-にんぎょう【宇治人形】🔗⭐🔉
うじ-にんぎょう ウヂニンギヤウ [3] 【宇治人形】
宇治の名物人形。茶の木を材料にして主として茶摘み女などを作る。刀法・彩色とも奈良人形に似ている。茶の木人形。
うじのあじろ-の-しょうじ【宇治の網代の障子】🔗⭐🔉
うじのあじろ-の-しょうじ ウヂ―シヤウジ 【宇治の網代の障子】
清涼殿の東の広庇(ヒロビサシ)の北にあった衝立(ツイタテ)。裏面に墨絵で宇治川の網代が描いてあった。
→荒海の障子(ソウジ)
うじ-の-いん【氏の院】🔗⭐🔉
うじ-の-いん ウヂ― ン 【氏の院】
(1)平安初期,同じ氏族の子弟の教育機関として設置された大学別曹。藤原氏の勧学院,橘氏の学館院など。
(2)平安中期,勧学院のこと。
ン 【氏の院】
(1)平安初期,同じ氏族の子弟の教育機関として設置された大学別曹。藤原氏の勧学院,橘氏の学館院など。
(2)平安中期,勧学院のこと。
 ン 【氏の院】
(1)平安初期,同じ氏族の子弟の教育機関として設置された大学別曹。藤原氏の勧学院,橘氏の学館院など。
(2)平安中期,勧学院のこと。
ン 【氏の院】
(1)平安初期,同じ氏族の子弟の教育機関として設置された大学別曹。藤原氏の勧学院,橘氏の学館院など。
(2)平安中期,勧学院のこと。
うじ-の-おおいぎみ【宇治の大君】🔗⭐🔉
うじ-の-おおいぎみ ウヂ―オホイギミ 【宇治の大君】
源氏物語の作中人物。宇治の八の宮の長女。薫を愛しながらその求愛を拒み,「総角(アゲマキ)」の巻で薫にみとられて死ぬ。宇治の姫君。八の宮の姫君。
うじ-の-かみ【氏の上】🔗⭐🔉
うじ-の-かみ ウヂ― 【氏の上】
古代における氏族の首長。一族を統率して朝廷に仕え,氏人の訴訟を裁く権限をもち,氏神の祭祀をつかさどった。大化の改新によって制度化され,氏の宗(ソウ)(氏族の本家)の官位の最も高い者が任命された。氏の長(オサ)。うじのこのかみ。
→氏の長者
うじ-の-かんぱく【宇治の関白】🔗⭐🔉
うじ-の-かんぱく ウヂ―クワンパク 【宇治の関白】
藤原頼通(ヨリミチ)の通称。
うじ-の-きょ【氏の挙】🔗⭐🔉
うじ-の-きょ ウヂ― 【氏の挙】
平安時代,毎年正月六日の叙位のとき,氏の長者が,その氏人の叙爵(ジヨシヤク)を申請したこと。
→氏の爵
うし-の-くるま【牛の車】🔗⭐🔉
うし-の-くるま [0] 【牛の車】
〔仏〕 小乗の教えを羊や鹿の車というのに対して,大乗の妙法のたとえ。
→三車
うし-の-こく【丑の刻】🔗⭐🔉
うし-の-こく [4] 【丑の刻】
丑(ウシ){(2)}の時刻。
うしのこく-まいり【丑の刻参り】🔗⭐🔉
うしのこく-まいり ―マ リ [6] 【丑の刻参り】
⇒うしのときまいり(丑時参)
リ [6] 【丑の刻参り】
⇒うしのときまいり(丑時参)
 リ [6] 【丑の刻参り】
⇒うしのときまいり(丑時参)
リ [6] 【丑の刻参り】
⇒うしのときまいり(丑時参)
うし-の-した【牛の舌】🔗⭐🔉
うし-の-した [5][0] 【牛の舌】
カレイ目ウシノシタ科とササウシノシタ科の海魚の総称。全長10〜35センチメートル。体は平たくて長楕円形,目が小さく口は鉤(カギ)状に曲がる。アカシタビラメ・クロウシノシタなどウシノシタ科では両眼が体の左側にあり,大形のものが多く食用とされる。シマウシノシタ・ササウシノシタなどササウシノシタ科では両眼が体の右側にある。北日本以南の沿岸海底に分布。クツゾコ。ベタ。
→シタビラメ
うじ-の-しゃく【氏の爵】🔗⭐🔉
うじ-の-しゃく ウヂ― 【氏の爵】
平安時代,氏の挙(キヨ)により,正六位上の者のうちから一人ずつ五位に叙すること。
→氏の挙
うじ-の-そう【氏の宗】🔗⭐🔉
うじ-の-そう ウヂ― 【氏の宗】
同じ氏の中の嫡流の家。本家。
うし-の-そうめん【牛の素麺】🔗⭐🔉
うし-の-そうめん ―サウメン [4] 【牛の素麺】
根無葛(ネナシカズラ)の異名。
うし-の-たま【牛の玉】🔗⭐🔉
うし-の-たま [5] 【牛の玉】
(1)牛の額に生える毛の固まったようなもの。中にかたい芯(シン)があり,牛王(ゴオウ)と称して寺院などの宝物とした。
(2)
⇒牛黄(ゴオウ)
うじ-の-ちょうじゃ【氏の長者】🔗⭐🔉
うじ-の-ちょうじゃ ウヂ―チヤウジヤ 【氏の長者】
平安時代以後,氏族の首長の呼称。奈良時代以前の氏の上(カミ)にあたる。氏の中で最高官位の者がなり,氏を統率した。氏人の叙爵(ジヨシヤク)の推挙,氏神・氏社の祭祀(サイシ),氏の大学別曹の管理運営などをつかさどった。藤原氏では一三世紀以後,摂関の地位にあるものがなった。
うし-の-つのつきあい【牛の角突(き)合い】🔗⭐🔉
うし-の-つのつきあい ―ツノツキアヒ [6] 【牛の角突(き)合い】
(1)「牛合わせ」に同じ。
(2)言い争うこと。押し問答すること。
うし-の-とき【丑の時】🔗⭐🔉
うし-の-とき [5] 【丑の時】
「丑{(2)}」に同じ。丑の刻(コク)。
うしのとき-まいり【丑の時参り】🔗⭐🔉
うしのとき-まいり ―マ リ [6] 【丑の時参り】
憎いと思う人をのろい殺すために,丑の刻(午前二時頃)に神社や寺に参詣すること。七日目満願の日に,のろわれた人は死ぬと信じられた。白衣を着て,頭に五徳をのせ,その足に蝋燭(ロウソク)を挿して火をともし,胸に鏡をさげ,手に金づちと釘を持ち,相手をかたどった人形を鳥居や神木に打ちつける。その姿を人に見られると効果がなくなると信じられた。主に嫉妬深い女のすることとされた。丑の刻参り。丑の時詣(モウ)で。丑参り。
丑の時参り
リ [6] 【丑の時参り】
憎いと思う人をのろい殺すために,丑の刻(午前二時頃)に神社や寺に参詣すること。七日目満願の日に,のろわれた人は死ぬと信じられた。白衣を着て,頭に五徳をのせ,その足に蝋燭(ロウソク)を挿して火をともし,胸に鏡をさげ,手に金づちと釘を持ち,相手をかたどった人形を鳥居や神木に打ちつける。その姿を人に見られると効果がなくなると信じられた。主に嫉妬深い女のすることとされた。丑の刻参り。丑の時詣(モウ)で。丑参り。
丑の時参り
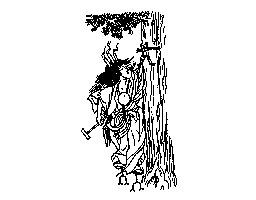 [図]
[図]
 リ [6] 【丑の時参り】
憎いと思う人をのろい殺すために,丑の刻(午前二時頃)に神社や寺に参詣すること。七日目満願の日に,のろわれた人は死ぬと信じられた。白衣を着て,頭に五徳をのせ,その足に蝋燭(ロウソク)を挿して火をともし,胸に鏡をさげ,手に金づちと釘を持ち,相手をかたどった人形を鳥居や神木に打ちつける。その姿を人に見られると効果がなくなると信じられた。主に嫉妬深い女のすることとされた。丑の刻参り。丑の時詣(モウ)で。丑参り。
丑の時参り
リ [6] 【丑の時参り】
憎いと思う人をのろい殺すために,丑の刻(午前二時頃)に神社や寺に参詣すること。七日目満願の日に,のろわれた人は死ぬと信じられた。白衣を着て,頭に五徳をのせ,その足に蝋燭(ロウソク)を挿して火をともし,胸に鏡をさげ,手に金づちと釘を持ち,相手をかたどった人形を鳥居や神木に打ちつける。その姿を人に見られると効果がなくなると信じられた。主に嫉妬深い女のすることとされた。丑の刻参り。丑の時詣(モウ)で。丑参り。
丑の時参り
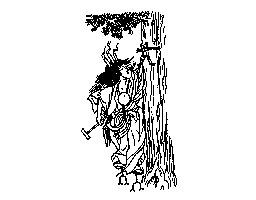 [図]
[図]
うしのと-やき【牛戸焼】🔗⭐🔉
うしのと-やき 【牛戸焼】
鳥取県八頭(ヤズ)郡河原(カワハラ)町牛戸産の焼き物。天保年間(1830-1844),陶工金河藤七が開窯,のち石見国の陶工小林梅五郎が受け継いだ。現在は水がめ・鉢(ハチ)・すり鉢など民具の生産が盛ん。
うじ-の-はしひめ【宇治の橋姫】🔗⭐🔉
うじ-の-はしひめ ウヂ― 【宇治の橋姫】
〔「うじのはしびめ」とも〕
(1)宇治橋のたもとの橋姫神社にまつられているとされる伝説上の女性。橋を守る神といい,また巫子(ミコ)・遊女・愛人などの意味をこめて和歌に多く詠まれた。
(2)嵯峨天皇の代,嫉妬のために宇治川に身を投げ,鬼形(キギヨウ)と化して京中の人に害をなしたと伝えられる女性。「平家物語」「太平記」「橋姫物語」などにみえる。
うし-の-ひ【丑の日】🔗⭐🔉
うし-の-ひ [4][3] 【丑の日】
(1)十二支をあてはめて,丑にあたる日。
(2)夏の土用の丑の日,または冬の寒中の丑の日。夏は鰻(ウナギ)を食べ,灸(キユウ)をすえ,冬は女性が紅を買う風習がある。
うしのひ-まつり【丑の日祭(り)】🔗⭐🔉
うしのひ-まつり [5] 【丑の日祭(り)】
丑の日に田の神をまつる行事。特に,和歌山県西牟婁(ムロ)郡周辺で,陰暦六月丑の日に行われる祭りが有名で,稲の生育を願って神社のお札を田の上で振り回す。青祈祷(アオギトウ)。
うし-の-ひたい【牛の額】🔗⭐🔉
うし-の-ひたい ―ヒタヒ [0] 【牛の額】
植物ミゾソバの別名。
うし-の-ほね【牛の骨】🔗⭐🔉
うし-の-ほね 【牛の骨】
素性のわからないものをののしっていう語。馬の骨。「どこの―やらしらいで/浮世草子・胸算用 3」
うじ-の-わきいらつこ【菟道稚郎子】🔗⭐🔉
うじ-の-わきいらつこ ウヂ― 【菟道稚郎子】
応神天皇の皇子。記紀によれば天皇に寵愛(チヨウアイ)されて皇太子となったが,兄の大鷦鷯尊(オオサザキノミコト)(仁徳天皇)に皇位を譲るために自殺したという。
うし-は・く【領く】🔗⭐🔉
うし-は・く 【領く】 (動カ四)
〔上代語。うし(大人)として領有するの意〕
統治する。支配する。「汝(イマシ)が,―・ける葦原の中つ国は我が御子の知らす国ぞと/古事記(上訓)」
うじ-ばし【宇治橋】🔗⭐🔉
うじ-ばし ウヂ― 【宇治橋】
(1)京都府宇治市にあって宇治川に架かる橋。橋姫の伝説がある。((歌枕))
(2)三重県伊勢市の五十鈴(イスズ)川に架かって,伊勢神宮内宮の表参道に通じる橋。
うじばし-だんぴ【宇治橋断碑】🔗⭐🔉
うじばし-だんぴ ウヂ― 【宇治橋断碑】
京都府宇治市放生院常光寺(橋寺)にある宇治橋碑の上部約三分の一の部分。646年に僧道登が宇治川に橋を架けたことを記す碑。早く失われたが,江戸時代に原碑の断片が発見され記録によって下部が復元された。
うじはや・し【阻し】🔗⭐🔉
うじはや・し ウヂハヤシ 【阻し】 (形ク)
(1)情勢が険悪である。切迫している。「かく―・き時に身命を惜しまずして/続紀(天平神護一宣命)」
(2)地勢が険しい。「経途(ミチ)―・く寒風(カゼハヤ)くして雪を飛ばす/大唐西域記(長寛点)」
うしはら【牛原】🔗⭐🔉
うしはら 【牛原】
姓氏の一。
うしはら-きよひこ【牛原虚彦】🔗⭐🔉
うしはら-きよひこ 【牛原虚彦】
(1897-1985) 映画監督。熊本県生まれ。松竹入社後,渡米してチャップリンの薫陶を受ける。帰国後,「彼と東京」「彼と田園」「彼と人生」三部作などで一時代を画した。
うじ-びと【氏人】🔗⭐🔉
うじ-びと ウヂ― [2] 【氏人】
古代,氏を構成した人。氏の上(カミ)を中心に血縁的関係による集団を形成,同一の氏と姓(カバネ)を称した。
うじ-ぶみ【氏文】🔗⭐🔉
うじ-ぶみ ウヂ― [0][2] 【氏文】
古代,一族の由緒や祖先の功績などを記した文書。「高橋―」
うし-へん【牛偏】🔗⭐🔉
うし-へん [0] 【牛偏】
漢字の偏の一。「牡」「物」「特」などの「牛」の部分。
うし-まいり【丑参り】🔗⭐🔉
うし-まいり ―マ リ [3] 【丑参り】
「丑(ウシ)の時参(トキマイ)り」に同じ。
リ [3] 【丑参り】
「丑(ウシ)の時参(トキマイ)り」に同じ。
 リ [3] 【丑参り】
「丑(ウシ)の時参(トキマイ)り」に同じ。
リ [3] 【丑参り】
「丑(ウシ)の時参(トキマイ)り」に同じ。
うし-まつり【牛祭】🔗⭐🔉
うし-まつり 【牛祭】
京都市太秦(ウズマサ)の広隆寺で行われる祭り。一〇月一〇日に行われる。魔多羅神(マタラジン)の仮面をかぶった男が牛に乗り,赤鬼・青鬼に扮した四天王を従えて境内を回ったのちに祭壇に至って祭文を読み上げる。[季]秋。《松明にむせぶ鬼あり―/田畑比古》
うじ-まる【宇治丸】🔗⭐🔉
うじ-まる ウヂ― [2] 【宇治丸】
京都府宇治市の特産である鰻鮨(ウナギズシ)の異名。また,かば焼きにもいう。うじのまる。
うし-みせ【牛店】🔗⭐🔉
うし-みせ [0] 【牛店】
明治時代,牛鍋など牛肉の料理を食べさせた店。うしや。ぎゅうや。
うし-みつ【丑三つ】🔗⭐🔉
うし-みつ [0] 【丑三つ】
(1)丑の刻を四つに分けた第三番目の時刻。今の午前二時から二時半頃,または午前三時から三時半。うしみつどき。
(2)真夜中。深更。
うじ-むし【蛆虫】🔗⭐🔉
うじ-むし [2] 【蛆虫】
(1)ハエ・ハチなどの幼虫。うじ。
(2)〔蛆のようにつまらない嫌な奴,の意〕
人をののしっていう語。「この―どもめ」
うじ【氏】(和英)🔗⭐🔉
うじ【蛆(虫)】(和英)🔗⭐🔉
うじうじ(和英)🔗⭐🔉
うじうじ
〜している be unduely hesitant.
うじがみ【氏神】(和英)🔗⭐🔉
うじがみ【氏神】
a guardian god.
うじこ【氏子】(和英)🔗⭐🔉
うじこ【氏子】
a parishioner.→英和
大辞林に「うじ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む