複数辞典一括検索+![]()
![]()
こ🔗⭐🔉
こ
(1)五十音図カ行第五段の仮名。軟口蓋破裂音の無声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。
(2)平仮名「こ」は「己」の草体。片仮名「コ」は「己」の初二画。
〔奈良時代までは上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕
こ【子・児】🔗⭐🔉
こ 【子・児】
■一■ [0] (名)
(1)人間や動物から,生まれ出るもの。特に,生まれ出て間もないもの。
⇔親
「―を生む」「腹に―を持った鮭」「犬の―」
〔動物の場合「仔」とも書く〕
(2)まだ一人前になっていない人間。年少の男女。「都会の―は体力が劣る」「小さな女の―」
(3)両親の間に生まれた人。また,縁組により,その間に生まれたものと同じように養われている人。
⇔親
「―を思う親の心」「伯父夫婦の―になる」
(4)(親しみの気持ちで)若い女性をいう語。芸子をさす場合もある。「会社の女の―」「あの店はいい―がそろっている」
(5)キリスト教で,キリストのこと。みこ。
(6)もととなるものから分かれ出たもの。また,従属的なもの。「竹の―」「元も―もない」「―会社」
(7)愛する人。また,親しみを感ずる人。「はしきやし逢はぬ―故にいたづらに宇治川の瀬に裳裾濡らしつ/万葉 2429」「熊白檮(クマカシ)が葉を髻華(ウズ)に挿せその―/古事記(中)」
(8)鳥の卵。「あてなるもの…かりの―/枕草子 42」
■二■ (接尾)
上の語との間に促音が入ることもある。
(1)名詞や動詞の連用形に付いて,その仕事をしている人,そのことに当たる人,そのような状態の人,そのためのものなどの意を表す。「売り―」「売れっ―」「馬―」「振り―」「背負(シヨイ)―」
(2)特に女性のする動作や仕事に付けて,それをする人が若い娘であることを表す。「踊り―」「お針―」
(3)名詞に付いて,そのような状態・性質の子供である意を表す。「ひとりっ―」「いじめっ―」「だだっ―」
(4)小さなものに付けて,愛称とする。「ひよ―」「ひよっ―」「砂―」
(5)その場所や時代に生まれ育った人であることを表す。「江戸っ―」「団地っ―」「大正っ―」
(6)女性の名に付けて,それが女子であることを表す。平安時代以降,明治の頃までは身分の高い女性の名に用いた。「花―」「春―」
(7)人に対する親愛の気持ちを表す。古く人名や人を表す語に付けて,男女ともに用いた。「小野妹―」「我妹(ワギモ)―」「背―」
こ【木】🔗⭐🔉
こ 【木】
〔「木(キ)」の交替形〕
き(木)。多く他の語と複合して用いられる。「―立ち」「―の葉」「―の根の根ばふ宮/古事記(下)」
こ【海鼠】🔗⭐🔉
こ 【海鼠】
ナマコの古名。[和名抄]
こ【格】🔗⭐🔉
こ [1][0] 【格】
(1)障子や格子の桟。子(コ)。
(2)格天井(ゴウテンジヨウ)の竿材。また,それぞれの格子。
(3)梯子(ハシゴ)の横木。「階(ハシ)の―をななめにおりくだりて/著聞 14」
こ【粉】🔗⭐🔉
こ [1] 【粉】
固体が砕けて細かになったもの。こな。「米の―」「身を―にして働く」
こ【蚕】🔗⭐🔉
こ 【蚕】
かいこ。「母が養(カ)ふ―の繭隠(マヨゴモ)り/万葉 2495」
こ【籠】🔗⭐🔉
こ 【籠】
(1)かご。「―もよ,み―持ち/万葉 1」
(2)「伏(フ)せ籠(ゴ)」に同じ。「なえたる衣(キヌ)どもの厚肥えたる,大いなる―にうちかけて/源氏(帚木)」
こ【戸】🔗⭐🔉
こ 【戸】
■一■ [1] (名)
(1)家の出入り口。戸口。また,とびら。と。
(2)家。家屋。また,一家。
(3)律令制で,地方行政における社会組織の最小単位。戸籍記載・賦課の単位でもあり,里や郷を構成する。
→郷戸(ゴウコ)
■二■ (接尾)
助数詞。家や世帯の数を数えるのに用いる。「戸数百―」
こ【呼】🔗⭐🔉
こ [1] 【呼】
〔call〕
通信網を流れるひとまとまりの情報。
こ【孤】🔗⭐🔉
こ [1] 【孤】 (名・形動)[文]ナリ
ひとりぼっちである・こと(さま)。「寒樹の夕空に倚(ヨ)りて―なる風情/金色夜叉(紅葉)」
こ【弧】🔗⭐🔉
こ [1] 【弧】
円周の一部分。また,放物線などの曲線の一部分。「―を描いて飛ぶ」
こ【個】🔗⭐🔉
こ 【個】
■一■ [1] (名)
ひとりの人。自分自身。「―としての認識」
■二■ (接尾)
助数詞。物の数を数えるのに用いる。「みかん三―」
こ【壺】🔗⭐🔉
こ [1] 【壺】
中国,古代のつぼ形の盛酒器。殷周時代の青銅製の祭器がよく知られる。
壺
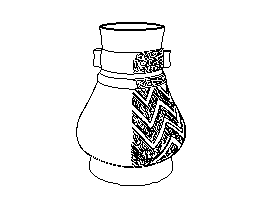 [図]
[図]
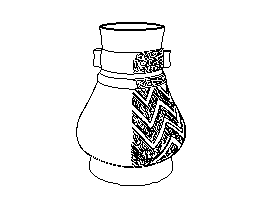 [図]
[図]
こ【鈷】🔗⭐🔉
こ [1] 【鈷】
古代インドの武器を形象化した,仏教で煩悩(ボンノウ)を打ちくだく意味で用いる法具。
→金剛杵(コンゴウシヨ)
こ【鉤】🔗⭐🔉
こ 【鉤】
巻き上げた簾(スダレ)を掛けて置くかぎ形の金物。「御簾の帽額(モコウ),総角(アゲマキ)などにあげたる―のきはやかなるも/枕草子 201」
こ【此・是】🔗⭐🔉
こ 【此・是】 (代)
近称の指示代名詞。その場にある,また話題の場所・物・事柄などを指し示す。ここ。これ。「明日よりは恋ひかも行かむ―ゆ別れなば/万葉 1728」「風吹けば浪の花さへ色見えて―や名にたてる山吹の崎/源氏(胡蝶)」「さば,―は誰がしわざにか/枕草子 138」
こ【来】🔗⭐🔉
こ 【来】
カ行変格活用動詞「く」の命令形の古形。こい。「旅にても喪なくはや〈こ〉と我妹子が結びし紐はなれにけるかも/万葉 3717」「こち〈こ〉,と言ひて/大和 103」
〔平安中期以降には,「かしこに物して整へむ,装束(ソウズク)して〈こよ〉/蜻蛉(中)」「こち〈こよ〉,と呼びよせて/宇治拾遺 5」のように間投助詞「よ」を添えた「こよ」の形も用いられるようになり,以後「こよ」が次第に優勢になってゆく〕
→来る
こ【小】🔗⭐🔉
こ 【小】 (接頭)
名詞・形容詞・形容動詞,まれに動詞に付く。
(1)形や規模が小さい,量が少ない,程度が軽いなどの意を表す。「―山」「―皿」「―銭(ゼニ)」「―降(ブ)り」「―ぜり合い」「―高い」「―突く」
(2)意味を和らげたり,親愛感を加えたりして,主観的な感じ,印象を添える。どことなく…の感じだ。「―粋」「―憎らしい」「―ざっぱり」「―しゃく」
(3)一人前ではない,大したものではないの意を表す。また,卑しめる意を表す。「―坊主」「―ざかしい」「―才(ザイ)」「―面(ヅラ)」「―役人」
(4)体の一部分を表す名詞に付いて,表現が露骨にならないようにする。「―鬢(ビン)」「―首をかしげる」「―膝を打つ」「―腰をかがめる」
(5)数量を表す名詞または数詞に付いて,それよりすこし少ないがほぼそのくらいの意を表す。「―一里」「―一畳」「―半日」「―一倍」
→こっ(接頭)
こ【濃】🔗⭐🔉
こ 【濃】 (接頭)
名詞に付いて,色の濃いことを表す。こい。「―紫」
こ【故】🔗⭐🔉
こ 【故】 (接頭)
(1)人名や官職名などに付けて,その人がすでに死亡していることを表す。「―右大将殿」
(2)官職名に付けて,それが以前の官職であることを表す。前の。「大夫には―中宮の大夫/栄花(暮待つ星)」
こ🔗⭐🔉
こ (接尾)
(1)名詞・動詞の連用形に付いて,「こと」の意を表す。「うそっ―」「慣れっ―」「知りっ―ない」「泣きっ―なしよ」
(2)動詞の連用形に付いて,互いに…する,互いに…して競争するなどの意を表す。「背中の流しっ―」「駆けっ―」「にらめっ―」
(3)擬声語・擬態語に付いて,語調を整えたり,意味を強めたりする。「ぎっちら―」「ぎい―ぎい―」「ぺちゃん―」「ごっつん―」
(4)名詞に付いて,親しみの気持ちを添える。「あん―」「隅っ―」「根っ―」
〔上の語との間に促音が入ることが多い〕
こ【処】🔗⭐🔉
こ 【処】 (接尾)
名詞・代名詞に付いて,その場所を表す。「こ―」「そ―」「あそ―」
コア core
core 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コア [1]  core
core (1)物の中心部。核。
(2)地球の核。
(3)コイルなどの鉄心。
(4)鋳物の中子(ナカゴ)。
(5)原子炉の炉心。
(6)建物で,共用施設をまとめて設置した所。
→コア-システム
(1)物の中心部。核。
(2)地球の核。
(3)コイルなどの鉄心。
(4)鋳物の中子(ナカゴ)。
(5)原子炉の炉心。
(6)建物で,共用施設をまとめて設置した所。
→コア-システム
 core
core (1)物の中心部。核。
(2)地球の核。
(3)コイルなどの鉄心。
(4)鋳物の中子(ナカゴ)。
(5)原子炉の炉心。
(6)建物で,共用施設をまとめて設置した所。
→コア-システム
(1)物の中心部。核。
(2)地球の核。
(3)コイルなどの鉄心。
(4)鋳物の中子(ナカゴ)。
(5)原子炉の炉心。
(6)建物で,共用施設をまとめて設置した所。
→コア-システム
こ-あい【濃藍】🔗⭐🔉
こ-あい ―ア [0] 【濃藍】
濃い藍色。
[0] 【濃藍】
濃い藍色。
 [0] 【濃藍】
濃い藍色。
[0] 【濃藍】
濃い藍色。
こ-あおい【小葵】🔗⭐🔉
こ-あおい ―アフヒ [2] 【小葵】
(1)銭葵(ゼニアオイ)の異名。
(2)模様の名。銭葵の花を模様化したもの。有職文様の一つで,天皇や貴族の下襲(シタガサネ)などに用いた。
小葵(2)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
こ-あかえ【古赤絵】🔗⭐🔉
こ-あかえ ―アカ [2] 【古赤絵】
中国明代の赤絵のうち,景徳鎮民窯で万暦以前のものの総称。下地に染付を用いない。一六世紀前半が最盛期。
[2] 【古赤絵】
中国明代の赤絵のうち,景徳鎮民窯で万暦以前のものの総称。下地に染付を用いない。一六世紀前半が最盛期。
 [2] 【古赤絵】
中国明代の赤絵のうち,景徳鎮民窯で万暦以前のものの総称。下地に染付を用いない。一六世紀前半が最盛期。
[2] 【古赤絵】
中国明代の赤絵のうち,景徳鎮民窯で万暦以前のものの総称。下地に染付を用いない。一六世紀前半が最盛期。
こ-あがり【小上(が)り】🔗⭐🔉
こ-あがり [2] 【小上(が)り】
小料理屋などで,いす席と通路をはさんで設けられた座敷。
コア-カリキュラム core curriculum
core curriculum 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コア-カリキュラム [5][3]  core curriculum
core curriculum 学習者の現実生活の問題解決の学習を中核におき,その周辺に基礎的な知識・技術を学習する課程を配する教育課程。
学習者の現実生活の問題解決の学習を中核におき,その周辺に基礎的な知識・技術を学習する課程を配する教育課程。
 core curriculum
core curriculum 学習者の現実生活の問題解決の学習を中核におき,その周辺に基礎的な知識・技術を学習する課程を配する教育課程。
学習者の現実生活の問題解決の学習を中核におき,その周辺に基礎的な知識・技術を学習する課程を配する教育課程。
こ-あきない【小商い】🔗⭐🔉
こ-あきない ―アキナヒ [2][3] 【小商い】
小規模な商売。また,取引額の小さい売買。
⇔大商い
こ-あきんど【小商人】🔗⭐🔉
こ-あきんど [3] 【小商人】
わずかな資本で商売をしている人。こあきゅうど。
こ-あご【小顎】🔗⭐🔉
こ-あご [0] 【小顎】
節足動物の口器の一部で,大あごに続く部分。付属肢が変形したもの。甲殻類・多足類では二対,昆虫類では一対ある。小鰓(シヨウサイ)。
こ-あし【小足】🔗⭐🔉
こ-あし [0] 【小足】
歩幅を狭くして速く歩くこと。刻み足。
こ-あじ【小味】🔗⭐🔉
こ-あじ ―アヂ [0] 【小味】 (名・形動)[文]ナリ
(1)微妙でこまやかな・味や趣(さま)。「―のきいた料理」
(2)取引相場で,値動きは小さいが,売買に面白みのある・こと(さま)。
⇔大味
こアジア-しょご【古―諸語】🔗⭐🔉
こアジア-しょご [1]-[4] 【古―諸語】
〔Paleo-Asiatic〕
沿海州から北東アジアにかけて孤立的に分布するギリヤーク語・ユカギール語・チュクチ語など少数民族の言語の総称。少数の同系言語から成るいくつかの語族と,全く孤立した言語とがある。旧アジア諸語。旧シベリア諸語。極北諸語。
こ-あじさし【小鰺刺】🔗⭐🔉
こ-あじさし ―アヂサシ [2] 【小鰺刺】
チドリ目カモメ科の水鳥。全長28センチメートル内外。背面は淡灰色,腹面は白色で,頭上は黒く,尾は燕尾状で白い。日本には夏鳥として南方から渡来し,海岸・河原などの砂礫地で営巣する。
コア-システム core system
core system 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コア-システム [3]  core system
core system 建築計画の一方式。階段・エレベーター・便所などの共用施設を建物の各階の同じ位置にまとめて設置し,その周囲に事務室または居住室を配置する方式。
建築計画の一方式。階段・エレベーター・便所などの共用施設を建物の各階の同じ位置にまとめて設置し,その周囲に事務室または居住室を配置する方式。
 core system
core system 建築計画の一方式。階段・エレベーター・便所などの共用施設を建物の各階の同じ位置にまとめて設置し,その周囲に事務室または居住室を配置する方式。
建築計画の一方式。階段・エレベーター・便所などの共用施設を建物の各階の同じ位置にまとめて設置し,その周囲に事務室または居住室を配置する方式。
コアセルベート coacervate
coacervate 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コアセルベート [5]  coacervate
coacervate 溶液中で,親水性コロイドの粒子が集合し,小液滴として周囲と境界をもち,溶液との間に一定の平衡状態を保っているもの。地球上での生命の起源の最初の段階と考える説がある。
溶液中で,親水性コロイドの粒子が集合し,小液滴として周囲と境界をもち,溶液との間に一定の平衡状態を保っているもの。地球上での生命の起源の最初の段階と考える説がある。
 coacervate
coacervate 溶液中で,親水性コロイドの粒子が集合し,小液滴として周囲と境界をもち,溶液との間に一定の平衡状態を保っているもの。地球上での生命の起源の最初の段階と考える説がある。
溶液中で,親水性コロイドの粒子が集合し,小液滴として周囲と境界をもち,溶液との間に一定の平衡状態を保っているもの。地球上での生命の起源の最初の段階と考える説がある。
コア-タイム core time
core time 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コア-タイム [3]  core time
core time フレックス-タイム制で,必ず就労していなければならない時間帯。
フレックス-タイム制で,必ず就労していなければならない時間帯。
 core time
core time フレックス-タイム制で,必ず就労していなければならない時間帯。
フレックス-タイム制で,必ず就労していなければならない時間帯。
こ-あたり【小当(た)り】🔗⭐🔉
こ-あたり [2] 【小当(た)り】 (名)スル
それとなく他人の気持ちを探ってみること。「―に当たってみる」
こ-あて【小宛】🔗⭐🔉
こ-あて [0] 【小宛】
連歌で,前句の持つ意味・情趣の本質・核心のこと。付句のときに必ず押さえておかなければならない急所。二条良基の所論。心の小宛。詞の小宛。
こ-あほうどり【小信天翁】🔗⭐🔉
こ-あほうどり ―アハウドリ [3] 【小信天翁】
ミズナギドリ目アホウドリ科の鳥。アホウドリよりやや小形。体と翼下面は白色で,背と翼上面は黒色。冬はハワイ・小笠原などの亜熱帯の島々で集団繁殖し,夏に日本近海でよく見られる。
こ-あま・い【小甘い】🔗⭐🔉
こ-あま・い [0] 【小甘い】 (形)
取引用語。相場がやや下がり気味である。
こ-あみがさ【小編み笠】🔗⭐🔉
こ-あみがさ [2] 【小編み笠】
江戸時代,槍持ちなどのかぶった丈(タケ)の高い,饅頭(マンジユウ)のような形の編み笠。
こ-あめ【小雨】🔗⭐🔉
こ-あめ [0] 【小雨】
こさめ。
こ-あゆ【小鮎】🔗⭐🔉
こ-あゆ [0] 【小鮎】
(1)アユの幼魚。若鮎。[季]春。
(2)湖に陸封され,成長しても全長10センチメートル前後にしかならないアユ。琵琶湖・池田湖などにすむ。稚魚のうちに他の河川に放流すれば普通のアユと同程度の大きさに育つ。湖産アユ。
コアラ koala
koala 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コアラ [1]  koala
koala 有袋類の一種。体長70センチメートルほどで,尾は痕跡的に残るのみ。子グマに似た姿をしている。雌の腹部には育児嚢がある。樹上生活をし,ユーカリの葉だけを食べる。性質は温和で,動作は緩慢。オーストラリア東部に分布。コモリグマ。
有袋類の一種。体長70センチメートルほどで,尾は痕跡的に残るのみ。子グマに似た姿をしている。雌の腹部には育児嚢がある。樹上生活をし,ユーカリの葉だけを食べる。性質は温和で,動作は緩慢。オーストラリア東部に分布。コモリグマ。
 koala
koala 有袋類の一種。体長70センチメートルほどで,尾は痕跡的に残るのみ。子グマに似た姿をしている。雌の腹部には育児嚢がある。樹上生活をし,ユーカリの葉だけを食べる。性質は温和で,動作は緩慢。オーストラリア東部に分布。コモリグマ。
有袋類の一種。体長70センチメートルほどで,尾は痕跡的に残るのみ。子グマに似た姿をしている。雌の腹部には育児嚢がある。樹上生活をし,ユーカリの葉だけを食べる。性質は温和で,動作は緩慢。オーストラリア東部に分布。コモリグマ。
こ-あんこく【胡安国】🔗⭐🔉
こ-あんこく 【胡安国】
(1074-1138) 中国,宋代の学者。字(アザナ)は康侯,号は武夷。高宗のとき中書舎人となり,侍講を兼ねた。著「春秋伝」など。
コアントロー (フランス) Cointreau
(フランス) Cointreau 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コアントロー [2]  (フランス) Cointreau
(フランス) Cointreau キュラソーの一種。食後酒のほか,健胃薬としても用いられている。商標名。
キュラソーの一種。食後酒のほか,健胃薬としても用いられている。商標名。
 (フランス) Cointreau
(フランス) Cointreau キュラソーの一種。食後酒のほか,健胃薬としても用いられている。商標名。
キュラソーの一種。食後酒のほか,健胃薬としても用いられている。商標名。
こい【恋】🔗⭐🔉
こい コヒ [1] 【恋】
(1)異性に強く惹(ヒ)かれ,会いたい,ひとりじめにしたい,一緒になりたいと思う気持ち。「―に落ちる」
(2)古くは,異性に限らず,植物・土地・古都・季節・過去の時など,目の前にない対象を慕う心にいう。「明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき―にあらなくに/万葉 325」
こい【請い・乞い】🔗⭐🔉
こい コヒ [1] 【請い・乞い】
相手にこいねがうこと。頼み。「―を入れる」「二人は自分の―に応じて/あめりか物語(荷風)」
こい【鯉】🔗⭐🔉
こい コヒ [1] 【鯉】
コイ目コイ科コイ属の淡水魚。普通は全長60センチメートルぐらいになり,二対の口ひげがある。野生種はノゴイともいい,体高が低くてほぼ円筒形で体色は黒褐色。飼育品種はヤマトゴイ・ドイツゴイ・ニシキゴイなどがあり,一般に体高がやや高くて側扁し,色彩や鱗(ウロコ)に変化がある。日本では古くから食用とされ,観賞用の品種も多い。
鯉
 [図]
[図]
 [図]
[図]
こ-い【古意】🔗⭐🔉
こ-い [1] 【古意】
(1)もともとの意義。
(2)昔をなつかしむ心。
こ-い【虎威】🔗⭐🔉
こ-い ― [1] 【虎威】
虎(トラ)が他の獣を恐れさせる威力。権勢の力。「―を張る」
[1] 【虎威】
虎(トラ)が他の獣を恐れさせる威力。権勢の力。「―を張る」
 [1] 【虎威】
虎(トラ)が他の獣を恐れさせる威力。権勢の力。「―を張る」
[1] 【虎威】
虎(トラ)が他の獣を恐れさせる威力。権勢の力。「―を張る」
こ-い【故意】🔗⭐🔉
こ-い [1] 【故意】
(1)ことさらにたくらむこと。わざとすること。「―に負ける」
(2)〔法〕 自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて,あえてその行為をする意思。刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう。
⇔過失
「未必の―」
コイ Khoi
Khoi 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
コイ [1]  Khoi
Khoi アフリカ南西部に住む民族。体は全体に小柄。主に牛・羊を遊牧して生活する。ヨーロッパ人によって,ホッテントットと呼ばれてきた。
アフリカ南西部に住む民族。体は全体に小柄。主に牛・羊を遊牧して生活する。ヨーロッパ人によって,ホッテントットと呼ばれてきた。
 Khoi
Khoi アフリカ南西部に住む民族。体は全体に小柄。主に牛・羊を遊牧して生活する。ヨーロッパ人によって,ホッテントットと呼ばれてきた。
アフリカ南西部に住む民族。体は全体に小柄。主に牛・羊を遊牧して生活する。ヨーロッパ人によって,ホッテントットと呼ばれてきた。
こ・い【濃い】🔗⭐🔉
こ・い [1] 【濃い】 (形)[文]ク こ・し
(1)物の濃度・密度が大きい。
⇔薄い
(ア)色が深い。
⇔淡い
「―・い緑」「夕闇が―・い」(イ)味・匂い・化粧などが強い。
⇔淡い
「―・い味つけにする」「ジャスミンの―・い香り」「おしろいが―・い」(ウ)生えているものの密度が高い。「―・いひげ」「髪の毛が―・い」(エ)液状のものについて,溶けている物質の水に対する割合が大きい。「小麦粉を―・くとく」「―・い粥(カユ)」(オ)霧やもやなどの濃度が大きい。「―・いもや」「ガスが―・く立ち込める」
(2)物事の程度が強い。(ア)何かの様子が強く表れている。「疲労の色が―・い」「敗色が―・い」(イ)可能性の度合が大きい。「犯罪の疑いが―・い」(ウ)情愛が濃厚である。「情が―・い」
(3)特に,紅色・紫色が深い。「かのしるしの扇は,桜の三重がさねにて,―・き方に,霞める月を書きて/源氏(花宴)」
(4)人間関係が密接である。交わりが深い。「などてかくはひあひがたき紫を心に深く思ひそめけむ,―・くなりはつまじきにや/源氏(真木柱)」
[派生] ――さ(名)
[慣用] 血は水よりも―
こ・い🔗⭐🔉
こ・い (接尾)
〔形容詞型活用([文]ク こ・し)〕〔形容詞「濃い」から〕
上の語との間に促音が入って「っこい」の形をとることが多い。名詞・形容詞の語幹などに付いて,その成文・要素が強く感じられる。その程度・状態がはなはだしいなどの意を表す。「油っ―・い」「ひやっ―・い」「まだるっ―・い」「しつ―・い」「ねばっ―・い」「ひとなつっ―・い」
こい-あま・る【恋ひ余る】🔗⭐🔉
こい-あま・る コヒ― 【恋ひ余る】 (動ラ四)
恋するあまり,それが表に現れでる。「隠(コモ)り沼(ヌ)の下ゆ―・り白波のいちしろく出でぬ人の知るべく/万葉 3935」
こい-う・ける【請い受ける・乞い受ける】🔗⭐🔉
こい-う・ける コヒ― [4] 【請い受ける・乞い受ける】 (動カ下一)[文]カ下二 こひう・く
頼みこんで,それをもらう。「有能な人物を―・ける」「懸りたる首を敵に―・く/太平記 32」
こいおしえ-どり【恋教へ鳥】🔗⭐🔉
こいおしえ-どり コヒヲシヘ― [5] 【恋教へ鳥】
〔伊弉諾(イザナキ)・伊弉冉(イザナミ)二神が,セキレイの動作を見て夫婦の道を知ったという説話から〕
セキレイの異名。こいしりどり。
こい-がき【濃柿】🔗⭐🔉
こい-がき [2][1] 【濃柿】
染め色の名。濃い柿色。
こい-かぜ【恋風】🔗⭐🔉
こい-かぜ コヒ― 【恋風】
恋の思いにとらえられて自由にならないさまを風に悩まされるさまにたとえた語。「―が来ては袂にかいもとれてなう,袖の重さよ/閑吟集」
こい-がたき【恋敵】🔗⭐🔉
こい-がたき コヒ― [3] 【恋敵】
恋愛の競争相手。同じ人を恋している相手。ライバル。
こいかわ-はるまち【恋川春町】🔗⭐🔉
こいかわ-はるまち コヒカハ― 【恋川春町】
(1744-1789) 江戸中期の黄表紙作者・狂歌師。本名,倉橋格。別号,狂号,酒上不埒(サケノウエノフラチ)。駿河小島の松平家の家臣。江戸小石川春日町に住む。黄表紙の鼻祖。作「金々先生栄花夢」「鸚鵡返文武二道」など。
こ-いき【小意気・小粋】🔗⭐🔉
こ-いき [0] 【小意気・小粋】 (名・形動)[文]ナリ
(1)どことなく気がきいて,しゃれている・こと(さま)。「―な店」「―な女将」
(2)(「こいきすぎる」の形で)こ生意気なこと。「―過ぎたる小坊主めと/浄瑠璃・八百屋お七」
[派生] ――さ(名)
こい-くち【濃い口】🔗⭐🔉
こい-くち [0] 【濃い口】
醤油などの味や色が濃いこと。また,そのもの。
⇔薄口(1)
こいくち-しょうゆ【濃い口醤油】🔗⭐🔉
こいくち-しょうゆ ―シヤウ― [5] 【濃い口醤油】
醤油のこと。薄口醤油に対応しての名称。
こい-ぐち【鯉口】🔗⭐🔉
こい-ぐち コヒ― [0][2] 【鯉口】
〔形が鯉の口に似ているところからいう〕
(1)刀のさやの口。
(2)口の小さい筒袖。また,その袖をつけて水仕事のときなどに羽織った衣服。
こい-げしょう【濃い化粧】🔗⭐🔉
こい-げしょう ―ゲシヤウ [3] 【濃い化粧】
厚化粧。
こい-こが・れる【恋(い)焦がれる】🔗⭐🔉
こい-こが・れる コヒ― [5] 【恋(い)焦がれる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 こひこが・る
恋しくて,心が乱れ苦しむ。「一目見ただけの人に―・れる」[日葡]
こい-こく【鯉濃】🔗⭐🔉
こい-こく コヒ― [0] 【鯉濃】
〔鯉の濃漿(コクシヨウ)の意〕
鯉を筒切りにして,濃いめの味噌汁で煮込んだ料理。
こい-ごころ【恋心】🔗⭐🔉
こい-ごころ コヒ― [3] 【恋心】
恋しいと思う心。「―が芽生える」
こい-ごろも【恋衣】🔗⭐🔉
こい-ごろも コヒ― 【恋衣】
心から離れない恋の思いを衣にたとえた語。「―着奈良の山に鳴く鳥の/万葉 3088」
こ【子[児]】(和英)🔗⭐🔉
こい【請い】(和英)🔗⭐🔉
こい【請い】
a request.→英和
〜をいれる comply with a person's request.…の〜により at a person's request.
こい【濃い】(和英)🔗⭐🔉
こいがたき【恋敵】(和英)🔗⭐🔉
こいがたき【恋敵】
a rival in love.
大辞林に「こ」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む