複数辞典一括検索+![]()
![]()
たる【垂】🔗⭐🔉
たる 【垂】
〔「垂水(タルミ)」の略〕
滝のこと。
たる【樽】🔗⭐🔉
たる [0] 【樽】
酒・醤油・味噌,あるいは漬物などを入れる木製の容器。「漬物―」「一斗―」
た・る【足る】🔗⭐🔉
た・る [0] 【足る】 (動ラ五[四])
(1)不足や欠けたところがない状態になる。たりる。「お金が―・らない」「努力が―・らない」「望月の―・れる面わに/万葉 1807」
(2)それにふさわしい資格や価値がある。たりる。「将となすに―・る人物」「論ずるに―・らぬこと」「とるに―・らぬこと」「頼むに―・らぬ」
(3)満足する。「―・ることを知れ」
(4)「たらぬ」の形で,頭の働きが悪いの意を表す。「すこし―・らぬ人を賭にして/浮世草子・一代男 8」
(5)一定の数量に達する。「御年まだ六十にも―・らせ給はねば/大鏡(師輔)」
〔現代語では,慣用的用法のほかは,上一段活用の「足りる」が一般に用いられる〕
た・る【垂る】🔗⭐🔉
た・る 【垂る】
■一■ (動ラ四)
(1)水滴がしたたり落ちる。たれる。「白ひげの上ゆ涙―・り/万葉 4408」
(2)ものの一端が下に垂れ下がる。「(鼻ハ)先の方少し―・りて色つきたる事/源氏(末摘花)」
■二■ (動ラ下二)
⇒たれる
たる🔗⭐🔉
たる (助動)
〔古語の断定の助動詞「たり」の連体形から〕
(1)資格を表す場合に用い,「…である」の意を表す。「師〈たる〉に値しない」「かりにも大学生〈たる〉者のなすべきことではない」「荀(イヤシク)も男児〈たる〉者が零落したのを恥づるとは何んだ/浮雲(四迷)」
(2)「…たるや」の形で,特筆に値すると思われる事柄などを話題にする時に用いる。「その風体〈たる〉やさながら弁慶の如く…」
→たり(助動)
たるい【垂井】🔗⭐🔉
たるい タル 【垂井】
岐阜県南西部,揖斐(イビ)川支流の相川扇状地上にある町。中山道の旧宿場町。
【垂井】
岐阜県南西部,揖斐(イビ)川支流の相川扇状地上にある町。中山道の旧宿場町。
 【垂井】
岐阜県南西部,揖斐(イビ)川支流の相川扇状地上にある町。中山道の旧宿場町。
【垂井】
岐阜県南西部,揖斐(イビ)川支流の相川扇状地上にある町。中山道の旧宿場町。
たるい【樽井】🔗⭐🔉
たるい タル 【樽井】
姓氏の一。
【樽井】
姓氏の一。
 【樽井】
姓氏の一。
【樽井】
姓氏の一。
たるい-とうきち【樽井藤吉】🔗⭐🔉
たるい-とうきち タル ― 【樽井藤吉】
(1850-1922) 政治家。奈良県生まれ。自由民権運動に参加。1882年(明治15)東洋社会党を結成。のち,衆議院議員。「大東合邦論」を著し,大アジア主義を主張した。
― 【樽井藤吉】
(1850-1922) 政治家。奈良県生まれ。自由民権運動に参加。1882年(明治15)東洋社会党を結成。のち,衆議院議員。「大東合邦論」を著し,大アジア主義を主張した。
 ― 【樽井藤吉】
(1850-1922) 政治家。奈良県生まれ。自由民権運動に参加。1882年(明治15)東洋社会党を結成。のち,衆議院議員。「大東合邦論」を著し,大アジア主義を主張した。
― 【樽井藤吉】
(1850-1922) 政治家。奈良県生まれ。自由民権運動に参加。1882年(明治15)東洋社会党を結成。のち,衆議院議員。「大東合邦論」を著し,大アジア主義を主張した。
たる-いり【樽入り】🔗⭐🔉
たる-いり [0] 【樽入り】
樽にはいっていること。また,そのもの。
たる-いれ【樽入れ】🔗⭐🔉
たる-いれ [0] 【樽入れ】 (名)スル
(1)不漁の時,ほかの大漁のあった所へ樽酒を贈って一緒に酒宴し,大漁にあやかること。
(2)婚約が成立した時,かためとして婿の方から嫁の方へ,仲人が柳樽をいれること。きまりざけ。
たる-かいせん【樽廻船】🔗⭐🔉
たる-かいせん ―クワイセン [3] 【樽廻船】
1730年,菱垣(ヒガキ)廻船から独立して関西の酒荷を専門に江戸へ輸送した廻船仲間の船。江戸後期では年間一〇〇万樽の酒を運び,また菱垣廻船の荷物の一部も輸送して,船も千五百石から二千石積みの大型船を使用した。たるぶね。
樽廻船
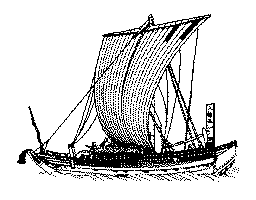 [図]
[図]
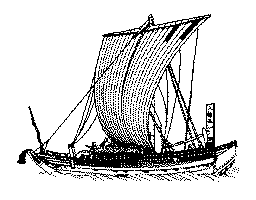 [図]
[図]
たる-かがみ【樽鏡】🔗⭐🔉
たる-かがみ [3] 【樽鏡】
酒樽の蓋(フタ)。かがみ。
たる-がき【樽柿】🔗⭐🔉
たる-がき [0][2] 【樽柿】
あいた酒樽に渋柿をつめ,樽に残るアルコール分によって渋をぬき,甘くしたもの。
たる-き【垂木・ ・椽・架】🔗⭐🔉
・椽・架】🔗⭐🔉
たる-き [0] 【垂木・ ・椽・架】
屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。
・椽・架】
屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。
 ・椽・架】
屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。
・椽・架】
屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材。はえき。たりき。
たるき-がた【垂木形】🔗⭐🔉
たるき-がた [0] 【垂木形】
垂木に平行に取り付ける幅の狭い簡略な破風板。
たるき-さき-がわら【垂木先瓦】🔗⭐🔉
たるき-さき-がわら ―ガハラ [6] 【垂木先瓦】
垂木の先端に装飾物として釘で打ちつける瓦。円形・方形のものが多く,平安末期以後は金具にかわる。垂木瓦。
たるき-だけ【垂木竹】🔗⭐🔉
たるき-だけ [3] 【垂木竹】
竹を垂木としたもの。また,その竹。さらし竹,すす竹などを用いる。
たるき-ばな【垂木鼻】🔗⭐🔉
たるき-ばな [3] 【垂木鼻】
垂木の端。また,その装飾。こじり。
たるき-わり【垂木割(り)】🔗⭐🔉
たるき-わり [0] 【垂木割(り)】
垂木の配置法。垂木の間隔によって繁(シゲ)割り・まばら割り・吹き寄せ割りなどがあり,並べ方によって平行垂木と扇垂木がある。
タルク talc
talc 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルク [1]  talc
talc (1)滑石(カツセキ)。
(2)滑石の粉末にホウ酸末・香料などを加えた化粧用の打ち粉。タルカム-パウダー。
(1)滑石(カツセキ)。
(2)滑石の粉末にホウ酸末・香料などを加えた化粧用の打ち粉。タルカム-パウダー。
 talc
talc (1)滑石(カツセキ)。
(2)滑石の粉末にホウ酸末・香料などを加えた化粧用の打ち粉。タルカム-パウダー。
(1)滑石(カツセキ)。
(2)滑石の粉末にホウ酸末・香料などを加えた化粧用の打ち粉。タルカム-パウダー。
タルコフスキー Andrei Arsen'evich Tarkovskii
Andrei Arsen'evich Tarkovskii 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルコフスキー  Andrei Arsen'evich Tarkovskii
Andrei Arsen'evich Tarkovskii (1932-1986) ソ連の映画監督。検閲と戦いながら,独自の映像の世界を追求。監督作品「アンドレイ=ルブリョフ」「惑星ソラリス」「鏡」「ストーカー」など。亡命してパリで没。
(1932-1986) ソ連の映画監督。検閲と戦いながら,独自の映像の世界を追求。監督作品「アンドレイ=ルブリョフ」「惑星ソラリス」「鏡」「ストーカー」など。亡命してパリで没。
 Andrei Arsen'evich Tarkovskii
Andrei Arsen'evich Tarkovskii (1932-1986) ソ連の映画監督。検閲と戦いながら,独自の映像の世界を追求。監督作品「アンドレイ=ルブリョフ」「惑星ソラリス」「鏡」「ストーカー」など。亡命してパリで没。
(1932-1986) ソ連の映画監督。検閲と戦いながら,独自の映像の世界を追求。監督作品「アンドレイ=ルブリョフ」「惑星ソラリス」「鏡」「ストーカー」など。亡命してパリで没。
たる-ざかな【樽魚】🔗⭐🔉
たる-ざかな [3] 【樽魚】
進物用の酒樽と酒のさかな。
たる-ざけ【樽酒】🔗⭐🔉
たる-ざけ [0][2] 【樽酒】
樽に入れた酒。そんしゅ。
タルスキ Alfred Tarski
Alfred Tarski 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルスキ  Alfred Tarski
Alfred Tarski (1902- ) アメリカの論理学者・数学者。ポーランド生まれ。真理概念の論理的分析を通じて意味論の方法を確立し,現代の記号論理学の展開に多大な貢献をなした。著「形式言語における真理概念」など。
(1902- ) アメリカの論理学者・数学者。ポーランド生まれ。真理概念の論理的分析を通じて意味論の方法を確立し,現代の記号論理学の展開に多大な貢献をなした。著「形式言語における真理概念」など。
 Alfred Tarski
Alfred Tarski (1902- ) アメリカの論理学者・数学者。ポーランド生まれ。真理概念の論理的分析を通じて意味論の方法を確立し,現代の記号論理学の展開に多大な貢献をなした。著「形式言語における真理概念」など。
(1902- ) アメリカの論理学者・数学者。ポーランド生まれ。真理概念の論理的分析を通じて意味論の方法を確立し,現代の記号論理学の展開に多大な貢献をなした。著「形式言語における真理概念」など。
たる-だい【樽代】🔗⭐🔉
たる-だい [0] 【樽代】
酒の代わりに贈る金。結納・転宅などの場合にいうことが多い。酒代。樽料。
タルタリア Niccolo Tartaglia
Niccolo Tartaglia 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルタリア  Niccolo Tartaglia
Niccolo Tartaglia (1500頃-1557) イタリアの数学者。本名ニコロ=フォンタナ。三次方程式の一般的解法を発見,のちカルダーノによって発表された。また,弾道の理論を研究。ユークリッドの「原論」を翻訳。
(1500頃-1557) イタリアの数学者。本名ニコロ=フォンタナ。三次方程式の一般的解法を発見,のちカルダーノによって発表された。また,弾道の理論を研究。ユークリッドの「原論」を翻訳。
 Niccolo Tartaglia
Niccolo Tartaglia (1500頃-1557) イタリアの数学者。本名ニコロ=フォンタナ。三次方程式の一般的解法を発見,のちカルダーノによって発表された。また,弾道の理論を研究。ユークリッドの「原論」を翻訳。
(1500頃-1557) イタリアの数学者。本名ニコロ=フォンタナ。三次方程式の一般的解法を発見,のちカルダーノによって発表された。また,弾道の理論を研究。ユークリッドの「原論」を翻訳。
タルタル Tartar
Tartar 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルタル  Tartar
Tartar 「タタール(の)」「タタール人(の)」「韃靼(ダツタン)(の)」の意。
「タタール(の)」「タタール人(の)」「韃靼(ダツタン)(の)」の意。
 Tartar
Tartar 「タタール(の)」「タタール人(の)」「韃靼(ダツタン)(の)」の意。
「タタール(の)」「タタール人(の)」「韃靼(ダツタン)(の)」の意。
タルタル-ステーキ tartar steak
tartar steak 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルタル-ステーキ [6]  tartar steak
tartar steak 肉料理の一。細かく挽いた牛肉に塩・胡椒をし,玉ネギ・パセリなどの薬味を加え,オリーブ油・生の卵黄を入れてペースト状に練ったもの。
肉料理の一。細かく挽いた牛肉に塩・胡椒をし,玉ネギ・パセリなどの薬味を加え,オリーブ油・生の卵黄を入れてペースト状に練ったもの。
 tartar steak
tartar steak 肉料理の一。細かく挽いた牛肉に塩・胡椒をし,玉ネギ・パセリなどの薬味を加え,オリーブ油・生の卵黄を入れてペースト状に練ったもの。
肉料理の一。細かく挽いた牛肉に塩・胡椒をし,玉ネギ・パセリなどの薬味を加え,オリーブ油・生の卵黄を入れてペースト状に練ったもの。
タルタル-ソース tartar sauce
tartar sauce 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルタル-ソース [5]  tartar sauce
tartar sauce ソースの一。ピクルス・タマネギ・パセリ・ゆで卵などを刻んで,マヨネーズと混ぜ合わせたもの。魚・貝・鶏肉などに添える。
ソースの一。ピクルス・タマネギ・パセリ・ゆで卵などを刻んで,マヨネーズと混ぜ合わせたもの。魚・貝・鶏肉などに添える。
 tartar sauce
tartar sauce ソースの一。ピクルス・タマネギ・パセリ・ゆで卵などを刻んで,マヨネーズと混ぜ合わせたもの。魚・貝・鶏肉などに添える。
ソースの一。ピクルス・タマネギ・パセリ・ゆで卵などを刻んで,マヨネーズと混ぜ合わせたもの。魚・貝・鶏肉などに添える。
タルタロス Tartaros
Tartaros 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルタロス [3]  Tartaros
Tartaros ギリシャ神話で地下の最奥にあるとされた仕置きの地。冥府よりも下にあり,ティタン神族がオリュンポス神族との戦いに敗れてここに幽閉され,タンタロスなど罪人が落とされた。
ギリシャ神話で地下の最奥にあるとされた仕置きの地。冥府よりも下にあり,ティタン神族がオリュンポス神族との戦いに敗れてここに幽閉され,タンタロスなど罪人が落とされた。
 Tartaros
Tartaros ギリシャ神話で地下の最奥にあるとされた仕置きの地。冥府よりも下にあり,ティタン神族がオリュンポス神族との戦いに敗れてここに幽閉され,タンタロスなど罪人が落とされた。
ギリシャ神話で地下の最奥にあるとされた仕置きの地。冥府よりも下にあり,ティタン神族がオリュンポス神族との戦いに敗れてここに幽閉され,タンタロスなど罪人が落とされた。
タルチュフ Le Tartuffe
Le Tartuffe 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルチュフ  Le Tartuffe
Le Tartuffe モリエールの喜劇。五幕。1664年初演。ぺてん師タルチュフが熱心な信仰家を装って富裕な商家に入りこみ財産乗っ取りを企てるが,失敗に終わる。
モリエールの喜劇。五幕。1664年初演。ぺてん師タルチュフが熱心な信仰家を装って富裕な商家に入りこみ財産乗っ取りを企てるが,失敗に終わる。
 Le Tartuffe
Le Tartuffe モリエールの喜劇。五幕。1664年初演。ぺてん師タルチュフが熱心な信仰家を装って富裕な商家に入りこみ財産乗っ取りを企てるが,失敗に終わる。
モリエールの喜劇。五幕。1664年初演。ぺてん師タルチュフが熱心な信仰家を装って富裕な商家に入りこみ財産乗っ取りを企てるが,失敗に終わる。
たる-づめ【樽詰(め)】🔗⭐🔉
たる-づめ [0] 【樽詰(め)】
樽に詰めること。また,詰めた物。
タルティーニ Giuseppe Tartini
Giuseppe Tartini 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルティーニ  Giuseppe Tartini
Giuseppe Tartini (1692-1770) イタリアのバイオリン奏者・作曲家。音響学理論・音楽教育などにも貢献。イタリアのバロック音楽の発展に寄与。作品は協奏曲,室内ソナタ・シンフォニアなど約三五〇曲がある。「悪魔のトリル」は有名。
(1692-1770) イタリアのバイオリン奏者・作曲家。音響学理論・音楽教育などにも貢献。イタリアのバロック音楽の発展に寄与。作品は協奏曲,室内ソナタ・シンフォニアなど約三五〇曲がある。「悪魔のトリル」は有名。
 Giuseppe Tartini
Giuseppe Tartini (1692-1770) イタリアのバイオリン奏者・作曲家。音響学理論・音楽教育などにも貢献。イタリアのバロック音楽の発展に寄与。作品は協奏曲,室内ソナタ・シンフォニアなど約三五〇曲がある。「悪魔のトリル」は有名。
(1692-1770) イタリアのバイオリン奏者・作曲家。音響学理論・音楽教育などにも貢献。イタリアのバロック音楽の発展に寄与。作品は協奏曲,室内ソナタ・シンフォニアなど約三五〇曲がある。「悪魔のトリル」は有名。
タルト (オランダ) taart
(オランダ) taart 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルト [1]  (オランダ) taart
(オランダ) taart 南蛮菓子の一。ゆずあんをカステラで巻いた生菓子。松山名産。
南蛮菓子の一。ゆずあんをカステラで巻いた生菓子。松山名産。
 (オランダ) taart
(オランダ) taart 南蛮菓子の一。ゆずあんをカステラで巻いた生菓子。松山名産。
南蛮菓子の一。ゆずあんをカステラで巻いた生菓子。松山名産。
タルト (フランス) tarte
(フランス) tarte 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルト [1]  (フランス) tarte
(フランス) tarte パイ生地またはビスケット生地を型に入れて焼き,クリームや果物をのせた菓子。
パイ生地またはビスケット生地を型に入れて焼き,クリームや果物をのせた菓子。
 (フランス) tarte
(フランス) tarte パイ生地またはビスケット生地を型に入れて焼き,クリームや果物をのせた菓子。
パイ生地またはビスケット生地を型に入れて焼き,クリームや果物をのせた菓子。
タルド Jean-Gabriel de Tarde
Jean-Gabriel de Tarde 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルド  Jean-Gabriel de Tarde
Jean-Gabriel de Tarde (1843-1904) フランスの社会学者。社会の成立を成員間の相互の模倣に求め,デュルケームの社会実在論に反対。また,ル=ボンを批判し,群集に対する「公衆」の概念を提唱。著「模倣の法則」「世論と群集」
(1843-1904) フランスの社会学者。社会の成立を成員間の相互の模倣に求め,デュルケームの社会実在論に反対。また,ル=ボンを批判し,群集に対する「公衆」の概念を提唱。著「模倣の法則」「世論と群集」
 Jean-Gabriel de Tarde
Jean-Gabriel de Tarde (1843-1904) フランスの社会学者。社会の成立を成員間の相互の模倣に求め,デュルケームの社会実在論に反対。また,ル=ボンを批判し,群集に対する「公衆」の概念を提唱。著「模倣の法則」「世論と群集」
(1843-1904) フランスの社会学者。社会の成立を成員間の相互の模倣に求め,デュルケームの社会実在論に反対。また,ル=ボンを批判し,群集に対する「公衆」の概念を提唱。著「模倣の法則」「世論と群集」
タルトゥー-がくは【―学派】🔗⭐🔉
タルトゥー-がくは 【―学派】
エストニアのタルトゥー(Tartu)大学を中心としたロシアの文化記号論の学派。ロトマン・イワーノフらが中心。ミハイル=バフチンの影響を受ける。
タルトレット (フランス) tartelette
(フランス) tartelette 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルトレット [1][4]  (フランス) tartelette
(フランス) tartelette 〔タートレットとも〕
一人用に小さくつくった洋菓子のタルト。
〔タートレットとも〕
一人用に小さくつくった洋菓子のタルト。
 (フランス) tartelette
(フランス) tartelette 〔タートレットとも〕
一人用に小さくつくった洋菓子のタルト。
〔タートレットとも〕
一人用に小さくつくった洋菓子のタルト。
たる-にんぎょう【樽人形】🔗⭐🔉
たる-にんぎょう ―ニンギヤウ [3] 【樽人形】
江戸時代,寛文・延宝(1661-1681)頃,柄のついた酒樽に着物を着せ編み笠などをかぶせて人形に仕立て,宴席などで,手で差し持って踊らせたもの。
たる-ぬき【樽抜き】🔗⭐🔉
たる-ぬき [0] 【樽抜き】
渋柿を酒の空樽に入れておいて,アルコールによって渋みを抜くこと。また,その柿。
タルバガン tarbagan
tarbagan 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルバガン [3]  tarbagan
tarbagan リス科の哺乳類。マーモットの一種。頭胴長60センチメートル,尾長12センチメートル内外で,足は短い。体はベージュまたは黄褐色。地中にトンネルを掘り,群れで生活。草食で,寒くなると冬眠する。ハンガリーからモンゴルまで分布。ステップ-マーモット。ボバック。
リス科の哺乳類。マーモットの一種。頭胴長60センチメートル,尾長12センチメートル内外で,足は短い。体はベージュまたは黄褐色。地中にトンネルを掘り,群れで生活。草食で,寒くなると冬眠する。ハンガリーからモンゴルまで分布。ステップ-マーモット。ボバック。
 tarbagan
tarbagan リス科の哺乳類。マーモットの一種。頭胴長60センチメートル,尾長12センチメートル内外で,足は短い。体はベージュまたは黄褐色。地中にトンネルを掘り,群れで生活。草食で,寒くなると冬眠する。ハンガリーからモンゴルまで分布。ステップ-マーモット。ボバック。
リス科の哺乳類。マーモットの一種。頭胴長60センチメートル,尾長12センチメートル内外で,足は短い。体はベージュまたは黄褐色。地中にトンネルを掘り,群れで生活。草食で,寒くなると冬眠する。ハンガリーからモンゴルまで分布。ステップ-マーモット。ボバック。
たる-ひ【足る日】🔗⭐🔉
たる-ひ 【足る日】
物事の満ち足りるよい日。充実した日。「今日の生日(イクヒ)の―に/祝詞(出雲国造神賀詞)」
たる-ひ【垂氷】🔗⭐🔉
たる-ひ 【垂氷】
雨・雪などの水が,軒・岩角などから,したたりながら凍って垂れ下がったもの。つらら。[季]冬。「滝の白糸―となり/平家 5」
たるひと-しんのう【熾仁親王】🔗⭐🔉
たるひと-しんのう ―シンワウ 【熾仁親王】
⇒有栖川宮熾仁親王(アリスガワノミヤタルヒトシンノウ)
たる-ひろい【樽拾い】🔗⭐🔉
たる-ひろい ―ヒロヒ [3] 【樽拾い】
酒屋の小僧が得意先から空樽や空徳利を集めて歩くこと。また,その小僧。
たる-ぶね【樽船】🔗⭐🔉
たる-ぶね [0][3] 【樽船】
⇒樽廻船(タルカイセン)
たるまえ-さん【樽前山】🔗⭐🔉
たるまえ-さん タルマヘ― 【樽前山】
北海道南西部,支笏(シコツ)湖の東方にそびえる活火山。海抜103メートル。江戸初期から近年までに三〇回余噴火。
たる-まる【樽丸】🔗⭐🔉
たる-まる [0] 【樽丸】
酒樽用の木材。杉でつくる。
たるみ【弛み】🔗⭐🔉
たるみ [0] 【弛み】
(1)たるむこと。気のゆるみ。「精神の―」「―事故」
(2)たるんでいる度合。「―の大きさ」
たる-み【垂水】🔗⭐🔉
たる-み 【垂水】
垂れ落ちる水。滝。「石(イワ)走る―の上のさわらびの萌(モ)え出づる春になりにけるかも/万葉 1418」
たるみ【垂水】🔗⭐🔉
たるみ 【垂水】
兵庫県神戸市西端の区名。明石海峡に臨む景勝地。
たる-みこし【樽御輿】🔗⭐🔉
たる-みこし [3] 【樽御輿】
酒樽を御輿に仕立てたもの。お神酒(ミキ)を神に捧(ササ)げたもので,今は主に子供が担ぐ。[季]夏。
たるみず【垂水】🔗⭐🔉
たるみず タルミヅ 【垂水】
鹿児島県大隅半島西部,鹿児島湾に面する市。ポンカン・ビワ・エンドウなどの栽培,ハマチ養殖,観光が産業の中心。
たる・む【弛む】🔗⭐🔉
たる・む [0] 【弛む】
■一■ (動マ五[四])
(1)張っていたものがゆるくなる。ゆるむ。「皮膚が―・む」「電線が―・む」
(2)心・気持ちにしまりがなくなる。だらしがなくなる。「精神が―・んでいる」「心ガ―・ム/日葡」
■二■ (動マ下二)
⇒たるめる
タルムード (ヘブライ) Talmud
(ヘブライ) Talmud 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
タルムード [3]  (ヘブライ) Talmud
(ヘブライ) Talmud 〔教訓の意〕
四〜六世紀に編まれたユダヤ教の口伝律法(ミシュナ)とその注解(ゲマラ)の集大成。トーラーとともにユダヤ人の生活規範・精神文化の基盤となった。
〔教訓の意〕
四〜六世紀に編まれたユダヤ教の口伝律法(ミシュナ)とその注解(ゲマラ)の集大成。トーラーとともにユダヤ人の生活規範・精神文化の基盤となった。
 (ヘブライ) Talmud
(ヘブライ) Talmud 〔教訓の意〕
四〜六世紀に編まれたユダヤ教の口伝律法(ミシュナ)とその注解(ゲマラ)の集大成。トーラーとともにユダヤ人の生活規範・精神文化の基盤となった。
〔教訓の意〕
四〜六世紀に編まれたユダヤ教の口伝律法(ミシュナ)とその注解(ゲマラ)の集大成。トーラーとともにユダヤ人の生活規範・精神文化の基盤となった。
たる・める【弛める】🔗⭐🔉
たる・める [0] 【弛める】 (動マ下一)[文]マ下二 たる・む
(1)強く張られていたものをゆるめる。たるませる。「ナワヲ―・メル/ヘボン」
(2)気をゆるめる。油断させる。
たる-や🔗⭐🔉
たる-や (連語)
〔助動詞「たり」の連体形に助詞「や」の付いたもの〕
(特筆すべき事柄に関して)…と言えば。…に至っては。「その怒り―大変なものだった」
たるや-おせん【樽屋おせん】🔗⭐🔉
たるや-おせん 【樽屋おせん】
不義をして自害した天満の樽屋の女房。1685年の事件という。歌謡や井原西鶴の「好色五人女」に脚色されて広まり,のち浄瑠璃・歌舞伎でも上演。
たる【足る】(和英)🔗⭐🔉
タルカム・パウダー(和英)🔗⭐🔉
タルカム・パウダー
talcum powder.
たるき【垂木】(和英)🔗⭐🔉
たるき【垂木】
a rafter.→英和
タルタル・ソース(和英)🔗⭐🔉
タルタル・ソース
tartar sauce.
たるみ【弛み】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「たる」で始まるの検索結果 1-66。