複数辞典一括検索+![]()
![]()
うな-さか【海境・海界・海坂】🔗⭐🔉
うな-さか 【海境・海界・海坂】
〔舟が水平線の彼方に見えなくなるのは,海に傾斜があって他界に至ると考えたからという〕
神話における海神の国と人の国との境界。「―を過ぎて漕ぎ行くに海神(ワタツミ)の神の娘子(オトメ)に/万葉 1740」「即ち―を塞(サ)へて返り入りましき/古事記(上)」
うみ【海】🔗⭐🔉
うみ [1] 【海】
(1)地球の表面のうち,海水をたたえた部分。総面積は約3億6千万平方キロメートルで,地球表面積の約四分の三を占める。最深はマリアナ海溝の約1万1千メートル。平均深度は3千8百メートル。海洋。
⇔陸
〔一般に外海をいうが,カスピ海のように周囲を陸で囲まれた大きな湖などをもいう〕
(2)みずうみ。湖。「鳰(ニオ)の―」
(3)月面の,比較的凹凸少なく広々している所。「嵐の―」
(4)あたり一面がその物でおおわれていること。「あたりは火の―だった」
(5)硯(スズリ)の,水をためておく部分。池。
うみ=が湧(ワ)・く🔗⭐🔉
――が湧(ワ)・く
魚の群れが海面に集まることをいう。
〔漁師の用いる語〕
うみ=に千年山に千年🔗⭐🔉
――に千年山に千年
「海千山千(ウミセンヤマセン)」に同じ。
うみ=の物とも山の物ともつかぬ🔗⭐🔉
――の物とも山の物ともつかぬ
物事の正体・本質がつかめず,どっちとも決めかねたり,将来を予測できなかったりすることのたとえ。
うみ=を山にする🔗⭐🔉
――を山にする
無理なことをするたとえ。
うみ=を渡・る🔗⭐🔉
――を渡・る
外国へ行く。また,外国から来る。
うみ【海】🔗⭐🔉
うみ 【海】
文部省唱歌。作詞作曲者とも不明。1913年(大正2)刊の「尋常小学唱歌(五)」に発表。「松原遠く消ゆるところ…」
うみ-イグアナ【海―】🔗⭐🔉
うみ-イグアナ [3] 【海―】
⇒海蜥蜴(ウミトカゲ)
うみ-う【海鵜】🔗⭐🔉
うみ-う [0] 【海鵜】
ペリカン目ウ科の海鳥。くちばしは長く,先はかぎ状。四本の指の間に発達した水掻きがある。体は光沢のある黒緑色で,全長90センチメートル内外。シベリア東部・朝鮮,北海道から九州までの海岸や小島の岩壁に集団で営巣する。若鳥を捕らえて訓練し,鵜飼いに使う。
海鵜
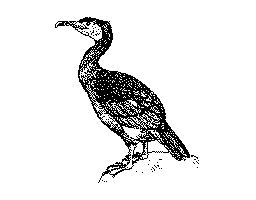 [図]
[図]
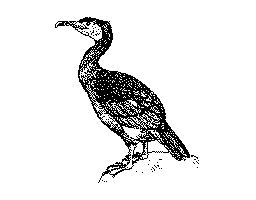 [図]
[図]
うみ-うし【海牛】🔗⭐🔉
うみ-うし [2] 【海牛】
〔触角を振って歩くのを牛に見たてた名〕
軟体動物腹足綱後鰓亜綱に属する一群の海産動物の総称。体形・体色は変化に富み,美しい色彩や模様をもつものが多い。足は幅広く,背面の前方に一対の触角をもつ。雌雄同体で草食性。暖海に生息し,種類が多い。
海牛
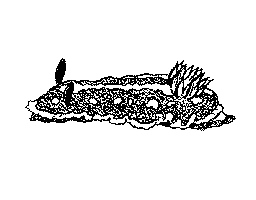 [図]
[図]
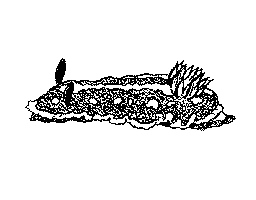 [図]
[図]
うみ-うなぎ【海鰻】🔗⭐🔉
うみ-うなぎ [3] 【海鰻】
体形がウナギに似て細長い,ウミヘビ・アナゴ・ウツボなどの俗称。
うみ-がめ【海亀】🔗⭐🔉
うみ-がめ [0] 【海亀】
ウミガメ科とオサガメ科の海産のカメの総称。一般に大形。前後肢はひれ状で海洋生活に適する。産卵は夏期,砂浜に上陸して行う。オサガメ・アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイなど。[季]夏。
うみ-がも【海鴨】🔗⭐🔉
うみ-がも [0][2][3] 【海鴨】
主として海上で暮らし,潜水して魚や貝などをとるカモ類をいう。ハジロガモ類・クロガモ類・ケワタガモ類など。
うみ-がらす【海烏】🔗⭐🔉
うみ-がらす [3] 【海烏】
チドリ目ウミスズメ科の海鳥。全長約45センチメートル。背面は黒色,腹面は白色。西洋梨形の大形卵を一個産む。北半球の寒冷海域に分布。日本では,1970年代以後に激減し,現在は北海道天売島のみで繁殖。絶滅危惧種。ロッペンガモ。ロッペン鳥。オロロン鳥。
うみ-ぎく【海菊】🔗⭐🔉
うみ-ぎく [2] 【海菊】
海産の二枚貝。片方の殻は深い椀形で殻頂を岩に付着し,他方の殻は平たく椀の蓋(フタ)状に合わさり,表面に多数の細い突起をもつ。貝殻の色は赤褐色・赤橙色・赤紫色など変化に富む。貝柱は食用。房総以南の浅海の岩礁にすむ。
うみ-つ-じ【海つ路】🔗⭐🔉
うみ-つ-じ ―ヂ 【海つ路】
〔「つ」は格助詞。「うみつち」とも〕
「うみじ」に同じ。「―のなぎなむ時も渡らなむ/万葉 1781」
うみ-つばめ【海燕】🔗⭐🔉
うみ-つばめ [3] 【海燕】
ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。黒みを帯びた翼は細長く,尾はふたまたに分かれる。全長13〜25センチメートル。水かきが発達し巧みに泳ぐ。離島の地中や岩の間に営巣する。ハイイロウミツバメ・コシジロウミツバメ・オーストンウミツバメなど。
うみにいくるひとびと【海に生くる人々】🔗⭐🔉
うみにいくるひとびと 【海に生くる人々】
小説。葉山嘉樹作。1926年(大正15)刊。石炭貨物船に働く海上労働者の階級的な目覚めを,自然描写を背景に描く。プロレタリア文学の記念碑的な作品。
うみ-の-いえ【海の家】🔗⭐🔉
うみ-の-いえ ―イヘ [1] 【海の家】
(1)浜辺にある海水浴客相手の更衣室を備え,軽食などを供するよしず張りなどの簡易な店。[季]夏。
(2)海岸近くに避暑・保養・海水浴などの客のために建てた宿泊施設。[季]夏。
うみ-の-さち【海の幸】🔗⭐🔉
うみ-の-さち [1] 【海の幸】
⇒うみさち(海幸)(1)
うみのひ【海の日】🔗⭐🔉
うみのひ 【海の日】
国民の祝日の一。七月二〇日。海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願うという主旨で1996年(平成8)より実施。
うみ-の-みや【海の宮】🔗⭐🔉
うみ-の-みや 【海の宮】
海中にあって竜神や乙姫(オトヒメ)の住むという宮殿。竜宮。うみのみやこ。「鼇海(ゴウカイ)の西には―/今鏡(すべらぎ下)」
うみ-びらき【海開き】🔗⭐🔉
うみ-びらき [3] 【海開き】
海水浴場を,その年初めて一般に公開すること。また,その日。浜開き。[季]夏。
うみやまのあいだ【海やまのあひだ】🔗⭐🔉
うみやまのあいだ ―アヒダ 【海やまのあひだ】
歌集。釈迢空(折口信夫)の最初の歌集。1925年(大正14)刊。民俗採訪旅行時の海や山での詠作が中心。四句詩形式が特色で,自由な詩型創出を試みている。
かい-い【海尉】🔗⭐🔉
かい-い ― [1] 【海尉】
海上自衛隊の自衛官の階級名。海佐の下,准海尉の上。一・二・三等に分かれる。
[1] 【海尉】
海上自衛隊の自衛官の階級名。海佐の下,准海尉の上。一・二・三等に分かれる。
 [1] 【海尉】
海上自衛隊の自衛官の階級名。海佐の下,准海尉の上。一・二・三等に分かれる。
[1] 【海尉】
海上自衛隊の自衛官の階級名。海佐の下,准海尉の上。一・二・三等に分かれる。
かい-いき【海域】🔗⭐🔉
かい-いき ― キ [0] 【海域】
ある区切られた範囲内の海面。「バーミューダ―」
キ [0] 【海域】
ある区切られた範囲内の海面。「バーミューダ―」
 キ [0] 【海域】
ある区切られた範囲内の海面。「バーミューダ―」
キ [0] 【海域】
ある区切られた範囲内の海面。「バーミューダ―」
かい-いん【海印】🔗⭐🔉
かい-いん [0] 【海印】
〔仏〕 海が万物を映すように,仏の智慧(チエ)の海に一切の事物が映し出されること。
かいいん-ざんまい【海印三昧】🔗⭐🔉
かいいん-ざんまい [5] 【海印三昧】
〔仏〕 釈迦が華厳経を説く時に入った禅定(ゼンジヨウ)。静かな海面に四方一切のものが映るように,煩悩や妄想のない仏の心鏡に,万象すべてが映ること。海印定。大海印三昧。
かいいん-じ【海印寺】🔗⭐🔉
かいいん-じ 【海印寺】
(1)韓国南部,慶尚南道伽 山(カヤサン)にある寺。通度寺・松広寺とともに,韓国三大寺の一。802年新羅(シラギ)哀荘王代に創建。高麗版大蔵経の印板を所蔵。
(2)京都府長岡京市にある寺。もと華厳宗に属していたが,江戸時代に真言宗に転宗。819年道雄の開基。応仁の乱後,荒廃して現在は寂照院を残すのみ。木上(コノカミ)山寂照院。
山(カヤサン)にある寺。通度寺・松広寺とともに,韓国三大寺の一。802年新羅(シラギ)哀荘王代に創建。高麗版大蔵経の印板を所蔵。
(2)京都府長岡京市にある寺。もと華厳宗に属していたが,江戸時代に真言宗に転宗。819年道雄の開基。応仁の乱後,荒廃して現在は寂照院を残すのみ。木上(コノカミ)山寂照院。
 山(カヤサン)にある寺。通度寺・松広寺とともに,韓国三大寺の一。802年新羅(シラギ)哀荘王代に創建。高麗版大蔵経の印板を所蔵。
(2)京都府長岡京市にある寺。もと華厳宗に属していたが,江戸時代に真言宗に転宗。819年道雄の開基。応仁の乱後,荒廃して現在は寂照院を残すのみ。木上(コノカミ)山寂照院。
山(カヤサン)にある寺。通度寺・松広寺とともに,韓国三大寺の一。802年新羅(シラギ)哀荘王代に創建。高麗版大蔵経の印板を所蔵。
(2)京都府長岡京市にある寺。もと華厳宗に属していたが,江戸時代に真言宗に転宗。819年道雄の開基。応仁の乱後,荒廃して現在は寂照院を残すのみ。木上(コノカミ)山寂照院。
かい-う【海宇】🔗⭐🔉
かい-う [1] 【海宇】
〔「宇」は天地四方の意〕
一国内。国中。海内(カイダイ)。
かい-う【海芋】🔗⭐🔉
かい-う [1] 【海芋】
植物,カラーの別名。[季]夏。
かいうん-どうめい【海運同盟】🔗⭐🔉
かいうん-どうめい [5] 【海運同盟】
同一の航路に定期船を就航させている海運業者どうしが,過当競争を回避する目的で,運賃・運送条件などを協定した国際的なカルテル。運賃の協定が中心なので運賃同盟ともいわれる。
かい-うん【海雲】🔗⭐🔉
かい-うん [0] 【海雲】
海と雲。また,海上の雲。
かい-えん【海燕】🔗⭐🔉
かい-えん [0] 【海燕】
(1)ウミツバメ。
(2)タコノマクラの異名。
(3)イトマキヒトデの異名。
かいえん-たい【海援隊】🔗⭐🔉
かいえん-たい カイ ン― 【海援隊】
幕末,坂本竜馬らが長崎で組織し,貿易・海運に従事しながら倒幕を企図した政治集団。1864年創設。西国諸藩,特に薩長両藩のために物資の輸送や西洋の武器・船舶の輸入などに当たった。
ン― 【海援隊】
幕末,坂本竜馬らが長崎で組織し,貿易・海運に従事しながら倒幕を企図した政治集団。1864年創設。西国諸藩,特に薩長両藩のために物資の輸送や西洋の武器・船舶の輸入などに当たった。
 ン― 【海援隊】
幕末,坂本竜馬らが長崎で組織し,貿易・海運に従事しながら倒幕を企図した政治集団。1864年創設。西国諸藩,特に薩長両藩のために物資の輸送や西洋の武器・船舶の輸入などに当たった。
ン― 【海援隊】
幕末,坂本竜馬らが長崎で組織し,貿易・海運に従事しながら倒幕を企図した政治集団。1864年創設。西国諸藩,特に薩長両藩のために物資の輸送や西洋の武器・船舶の輸入などに当たった。
かいおう-せい【海王星】🔗⭐🔉
かいおう-せい カイワウ― [0][3] 【海王星】
〔Neptune〕
太陽系の第八惑星。天王星の位置の予測値と観測値のずれから J = C =アダムズとル=ベリエが理論的位置を推算し,それに基づいて1846年にベルリン天文台のガレ(J.G. Galle 1812-1910)が発見。太陽からの平均距離約45億キロメートル。公転周期約165年。赤道半径2万4800キロメートル。質量は地球の約一七倍。衛星は八個が知られている。
かいおんじ-ちょうごろう【海音寺潮五郎】🔗⭐🔉
かいおんじ-ちょうごろう ―テウゴラウ 【海音寺潮五郎】
(1901-1977) 小説家。鹿児島県生まれ。本名,末富東作。国学院大卒。歴史に取材した作品が多い。作「平将門」「西郷隆盛」「天と地と」など。
かい-がい【海外】🔗⭐🔉
かい-がい ―グワイ [1] 【海外】
海を隔てた外国。外地。「―旅行」
かいがい-けいざいきょうりょく-ききん【海外経済協力基金】🔗⭐🔉
かいがい-けいざいきょうりょく-ききん ―グワイ―ケフリヨク― 【海外経済協力基金】
発展途上国の開発事業のうち資金供給の困難なものに対し,日本輸出入銀行などから投資や融資を行う政府関係金融機関。海外経済協力基金法により,1961年(昭和36)3月発足。
かいがい-けいじょうよじょう【海外経常余剰】🔗⭐🔉
かいがい-けいじょうよじょう ―グワイケイジヤウ― [9] 【海外経常余剰】
経常収支から移転収支を除いたもの。
かいがい-じじょう【海外事情】🔗⭐🔉
かいがい-じじょう ―グワイ―ジヤウ [5] 【海外事情】
海を隔てた外国のようす。
かいがい-とうしほけん【海外投資保険】🔗⭐🔉
かいがい-とうしほけん ―グワイ― [8] 【海外投資保険】
輸出保険法に基づき,海外投資における非常危険や信用危険により発生する損失を最高90パーセントまで補填する保険制度。
かいがい-とこう【海外渡航】🔗⭐🔉
かいがい-とこう ―グワイ―カウ [5] 【海外渡航】
船や航空機で海を渡り,外国に行くこと。
かいがい-とこう-きんしれい【海外渡航禁止令】🔗⭐🔉
かいがい-とこう-きんしれい ―グワイトカウ― [10] 【海外渡航禁止令】
江戸幕府の鎖国政策の一環をなす法令。1633年朱印船以外の日本船の海外渡航を禁止,次いで35年日本人の渡航を禁止。また外国より帰国した日本人の死罪を規定。
→鎖国
かいがい-ぼうえき【海外貿易】🔗⭐🔉
かいがい-ぼうえき ―グワイ― [5] 【海外貿易】
⇒対外(タイガイ)貿易
かいがい-ほうそう【海外放送】🔗⭐🔉
かいがい-ほうそう ―グワイハウ― [5] 【海外放送】
外国で受信されることを目的とする放送。多くは短波を使用。国際放送。
かいがい-しんぶん【海外新聞】🔗⭐🔉
かいがい-しんぶん カイグワイ― 【海外新聞】
浜田彦蔵が,民間で最初に発行した邦字新聞。海外の事情を翻訳紹介した。
かい-かく【海角】🔗⭐🔉
かい-かく [0] 【海角】
海に突き出た陸地の先端部。みさき。さき。はな。
かい-がく【海岳】🔗⭐🔉
かい-がく [1] 【海岳】
海と山。大恩のたとえにいう。「法花経一部七巻を写し奉つて,―に答し奉る/性霊集」
かい-かん【海関】🔗⭐🔉
かい-かん ―クワン [0] 【海関】
中国で,開港場に設けた税関。清朝が1685年に外国貿易のため設置。1859年以後イギリスなど諸外国による管理が1949年まで続いた。
かい-がん【海岸】🔗⭐🔉
かい-がん [0] 【海岸】
陸地が海に接する部分。海べ。なぎさ。
かいがん-きこう【海岸気候】🔗⭐🔉
かいがん-きこう [5] 【海岸気候】
海岸沿いの陸地にみられる気候。海洋の影響を受けるため,内陸に比べて一般に穏和,また海陸風が発達しやすい。塩風,場所によっては海霧の侵入がある。
⇔内陸気候
かいがん-こうがく【海岸工学】🔗⭐🔉
かいがん-こうがく [5] 【海岸工学】
海岸の保全と開発とを扱う土木工学の一分野。高潮・津波・波浪・流れなどによる海岸災害や海岸浸食を防ぐための堤防・護岸・突堤・離岸堤などの構築,人工海浜の造成などの方法・技術の研究を行う。
かいがん-さきゅう【海岸砂丘】🔗⭐🔉
かいがん-さきゅう ―キウ [5] 【海岸砂丘】
砂浜海岸で風に吹き飛ばされた砂が堆積してできる小高い丘。鳥取・新潟や遠州灘の沿岸に大規模なものが見られる。
かいがん-しょくぶつ【海岸植物】🔗⭐🔉
かいがん-しょくぶつ [6] 【海岸植物】
⇒海浜植物(カイヒンシヨクブツ)
かいがん-せん【海岸線】🔗⭐🔉
かいがん-せん [0] 【海岸線】
(1)陸と海との境界を連ねた線。汀線(テイセン)。
〔地形図では満潮面と陸地との境界線〕
(2)海岸に沿った一帯の地域。
(3)海岸ぞいの鉄道線路。
かいがん-だんきゅう【海岸段丘】🔗⭐🔉
かいがん-だんきゅう ―キウ [5] 【海岸段丘】
海岸に沿って分布する階段状地形。地盤の隆起や海水面の低下によってできる。海成段丘。
かいがん-へいや【海岸平野】🔗⭐🔉
かいがん-へいや [5] 【海岸平野】
(1)浅海底が,海水面の低下や地盤の隆起によって陸化した,低平な地域。砂礫・粘土などの浅海底堆積物で構成されている。
(2)海岸沿いにひろがる平坦地や低平地の総称。海に臨む三角州や扇状地,干潟などを含む。
かいがん-ぼうふうりん【海岸防風林】🔗⭐🔉
かいがん-ぼうふうりん ―バウ― [8] 【海岸防風林】
飛砂・風害・高潮などを防ぐため海岸沿いに設けられた保安林。
かいがん-りゅう【海岸流】🔗⭐🔉
かいがん-りゅう ―リウ [3] 【海岸流】
⇒沿岸流(エンガンリユウ)
かいがん-りん【海岸林】🔗⭐🔉
かいがん-りん [3] 【海岸林】
塩分の多い海岸の砂地・岩石地などに発達する林。クロマツ・アカマツ・トベラ・シャリンバイなどで構成される。
かい-き【海気】🔗⭐🔉
かい-き [1] 【海気】
(1)海の気。海辺の空気。
(2)海洋と大気。「―相互作用」
かい-き【海気・海黄】🔗⭐🔉
かい-き [0] 【海気・海黄】
〔のちに「甲斐絹」とも当てる〕
練り糸を用いて細かく目をつめて織った平織りの絹布。光沢があり絹鳴りがする。本来,慶長以前に輸入された中国産絹織物をいったが,甲斐国郡内で模して織るようになり「郡内海気」ともいわれた。
かい-ぎ【海技】🔗⭐🔉
かい-ぎ [1] 【海技】
船舶職員として必要な技術。
かいぎ-し【海技士】🔗⭐🔉
かいぎ-し [3] 【海技士】
海技従事者国家試験に合格し,指定の講習を受けた者に与えられる免許の区分。航海・機関・通信・電子通信に分けられ,それぞれ等級があり乗船履歴により受験できる免許の種類が限定される。
かいぎ-だいがっこう【海技大学校】🔗⭐🔉
かいぎ-だいがっこう ―ダイガクカウ 【海技大学校】
実務経験のある船員に,船舶運航に関する学理と技術を教授する運輸省所管の学校。1949年(昭和24)設立。本校は兵庫県芦屋市,81年岡山県倉敷市に分校を開設。
かい-きゅう【海丘】🔗⭐🔉
かい-きゅう ―キウ [0] 【海丘】
海山(カイザン)のうち,周りの海底からの比高が1000メートル未満のもの。
→海山
かい-ぎゅう【海牛】🔗⭐🔉
かい-ぎゅう ―ギウ [0] 【海牛】
海牛目の水生哺乳類の総称。全長約2.5メートルで紫灰色。後肢は退化し,前肢と尾はひれ状。浅瀬で水生植物を食う。ジュゴン科一種とマナティー科三種が含まれ,前者はインド洋・太平洋南西部に,後者は大西洋沿岸にすむ。人魚のモデルとされる。
かい-きょ【海渠】🔗⭐🔉
かい-きょ [1] 【海渠】
海岸線とほぼ直角をなして走る海底の裂溝。
かい-ぎょ【海魚】🔗⭐🔉
かい-ぎょ [1] 【海魚】
海産の魚。近海魚・遠海魚・深海魚などがある。海水魚。鹹水(カンスイ)魚。
かい-きょう【海況】🔗⭐🔉
かい-きょう ―キヤウ [0] 【海況】
海の状況。水温・塩分・海流・プランクトンの分布状態などを総合した海洋の状況。
かい-きょう【海峡】🔗⭐🔉
かい-きょう ―ケフ [0] 【海峡】
両側から陸地にはさまれ,二つの海をつなぐせまい海。瀬戸。水道。
かいきょう-しょくみんち【海峡植民地】🔗⭐🔉
かいきょう-しょくみんち ―ケフ― 【海峡植民地】
1826年以後イギリスがマレー半島に設けた植民地の総称。マラッカ・ペナン・シンガポールからなる。ベンガル州政府の管轄下にあったが,1867年イギリス直轄領となった。
かいきょう-せん【海峡線】🔗⭐🔉
かいきょう-せん ―ケフ― 【海峡線】
JR 北海道の鉄道線。青森県中小国・北海道木古内間,87.8キロメートル。青函トンネルで津軽海峡を渡る線区。
かい-ふ【海釜】🔗⭐🔉
かい-ふ [0][1] 【海釜】
潮流の浸食によって海底が削られてできる窪地(クボチ)。
たこ-の-まくら【蛸の枕・海燕】🔗⭐🔉
たこ-の-まくら [1]-[1] 【蛸の枕・海燕】
ウニ綱の棘皮動物。体はやや平たい饅頭(マンジユウ)形で,長径10センチメートル内外。上面に五つの花弁状の紋がある。褐色で,一面に短い棘(トゲ)が生える。本州中部以南の浅海の砂底にすむ。饅頭貝。
蛸の枕
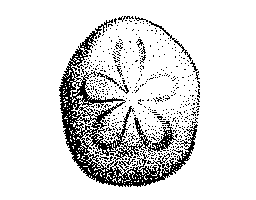 [図]
[図]
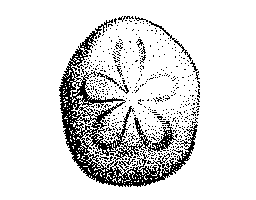 [図]
[図]
み【海】🔗⭐🔉
み 【海】
〔「うみ」の「う」が脱落した形〕
うみ。「淡海(オウミ)の―瀬田のわたりに潜(カズ)く鳥/日本書紀(神功)」
もずく【水雲・海雲・海蘊】🔗⭐🔉
もずく モヅク [0][1] 【水雲・海雲・海蘊】
(1)褐藻類ナガマツモ目の海藻。北海道南部以南の沿岸に分布。ホンダワラ類にからまり,春から初夏にかけよく育つ。体はきわめて細く,密に分枝し,粘質で柔らかい。食用。モゾコ。モクズ。[季]春。
(2){(1)}に似た,食用としている褐藻類の総称。
水雲(1)
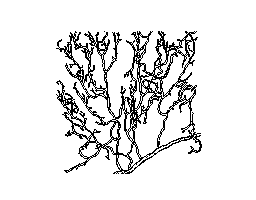 [図]
[図]
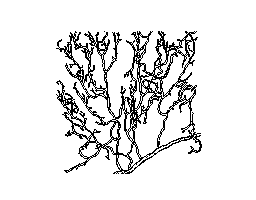 [図]
[図]
わた【海】🔗⭐🔉
わた 【海】
うみ。「―の底沖つ深江の/万葉 813」
わた-の-かみ【海の神】🔗⭐🔉
わた-の-かみ 【海の神】
うみの神。海神。わたつみ。
わた-の-そこ【海の底】🔗⭐🔉
わた-の-そこ 【海の底】 (枕詞)
海の底の奥深い意から「沖」「奥(オキ)」にかかる。「―沖つ白波竜田山/万葉 83」「―沖なる玉を手に巻(マ)くまでに/万葉 1327」
わた-の-はら【海の原】🔗⭐🔉
わた-の-はら 【海の原】
海。うなばら。大海。「―やそしまかけて漕ぎ出でぬと/古今(羇旅)」
うみ【海】(和英)🔗⭐🔉
うみがめ【海亀】(和英)🔗⭐🔉
うみがめ【海亀】
a (sea) turtle.
うみつばめ【海燕】(和英)🔗⭐🔉
うみつばめ【海燕】
a (stormy) petrel.
かいい【海尉】(和英)🔗⭐🔉
かいい【海尉】
[海上自衛隊] ‖一等海尉 a lieutenant.二等海尉 a lieutenant junior grade.三等海尉 an ensign.
かいいん【海員】(和英)🔗⭐🔉
かいうん【海運】(和英)🔗⭐🔉
かいうん【海運】
marine[sea]transportation;(merchant) shipping.→英和
‖海運界 shipping circles.海運業 shipping trade.海運業者 a shipping agent;shipping interests (総称).
かいおうせい【海王星】(和英)🔗⭐🔉
かいおうせい【海王星】
Neptune.→英和
かいがい【海外】(和英)🔗⭐🔉
かいがん【海岸】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「海」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む