複数辞典一括検索+![]()
![]()
いろ【色】🔗⭐🔉
いろ【色】
 [名]
[名]
 光の波長の違い(色相)によって目の受ける種々の感じ。原色のほか、それらの中間色があり、また、明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)によっても異なって感じる。色彩。「―が薄い」「暗い―」「落ち着いた―」
光の波長の違い(色相)によって目の受ける種々の感じ。原色のほか、それらの中間色があり、また、明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)によっても異なって感じる。色彩。「―が薄い」「暗い―」「落ち着いた―」 染料。絵の具。「―を塗る」「―がさめる」
染料。絵の具。「―を塗る」「―がさめる」 印刷・写真で、白・黒以外の色彩。「―刷り」
印刷・写真で、白・黒以外の色彩。「―刷り」 人の肌の色。人の顔の色つや。「抜けるように―の白い人」
人の肌の色。人の顔の色つや。「抜けるように―の白い人」
 表情としての顔色。「驚きの―が見える」「不満が―に出る」
表情としての顔色。「驚きの―が見える」「不満が―に出る」 目つき。目の光。「目の―を変えて怒りだす」
目つき。目の光。「目の―を変えて怒りだす」
 それらしい態度・そぶり。「反省の―が見られない」
それらしい態度・そぶり。「反省の―が見られない」 それらしく感じられる趣・気配。「秋の―の感じられる昨今」「敗北の―が濃い」
それらしく感じられる趣・気配。「秋の―の感じられる昨今」「敗北の―が濃い」 愛想。「―よい返事」
愛想。「―よい返事」 (「種」とも書く)種類。「―とりどり」「三(み)―選び出す」
(「種」とも書く)種類。「―とりどり」「三(み)―選び出す」 華やかさ。華美。「大会に―をそえる」
華やかさ。華美。「大会に―をそえる」 音・声などの響き。調子。「琴の音(ね)の―」「声(こわ)―」
音・声などの響き。調子。「琴の音(ね)の―」「声(こわ)―」
 情事。色事。「―を好む」「―に溺れる」
情事。色事。「―を好む」「―に溺れる」 女性の美しい容貌。「―に迷う」
女性の美しい容貌。「―に迷う」 情人。恋人。いい人。「―をつくる」
情人。恋人。いい人。「―をつくる」 古代・中世、位階によって定められた衣服の色。特に、禁色(きんじき)。「昔、公おぼして使う給ふ女の、―許されたるありけり」〈伊勢・六五〉
古代・中世、位階によって定められた衣服の色。特に、禁色(きんじき)。「昔、公おぼして使う給ふ女の、―許されたるありけり」〈伊勢・六五〉 喪服のねずみ色。にび色。「女房なども、かの御形見の―変へぬもあり」〈源・幻〉
喪服のねずみ色。にび色。「女房なども、かの御形見の―変へぬもあり」〈源・幻〉 婚礼や葬式のとき上に着る白衣。「葬礼に―を着て供して見せ」〈浄・博多小女郎〉
婚礼や葬式のとき上に着る白衣。「葬礼に―を着て供して見せ」〈浄・博多小女郎〉 人情。情愛。「東人(あづまうど)は…げには心の―なく、情おくれ」〈徒然・一四一〉
人情。情愛。「東人(あづまうど)は…げには心の―なく、情おくれ」〈徒然・一四一〉 [形動ナリ]
[形動ナリ] 女性の髪などがつややかで美しいさま。「髪、―に、こまごまとうるはしう」〈枕・二〇〇〉
女性の髪などがつややかで美しいさま。「髪、―に、こまごまとうるはしう」〈枕・二〇〇〉 好色なさま。「この宮の、いとさわがしきまで―におはしますなれば」〈源・浮舟〉
[類語]
好色なさま。「この宮の、いとさわがしきまで―におはしますなれば」〈源・浮舟〉
[類語] (
( )色彩・色調・色相(しきそう)・色合い・色目(いろめ)・彩り・あや・彩色・カラー
)色彩・色調・色相(しきそう)・色合い・色目(いろめ)・彩り・あや・彩色・カラー
 [名]
[名]
 光の波長の違い(色相)によって目の受ける種々の感じ。原色のほか、それらの中間色があり、また、明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)によっても異なって感じる。色彩。「―が薄い」「暗い―」「落ち着いた―」
光の波長の違い(色相)によって目の受ける種々の感じ。原色のほか、それらの中間色があり、また、明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)によっても異なって感じる。色彩。「―が薄い」「暗い―」「落ち着いた―」 染料。絵の具。「―を塗る」「―がさめる」
染料。絵の具。「―を塗る」「―がさめる」 印刷・写真で、白・黒以外の色彩。「―刷り」
印刷・写真で、白・黒以外の色彩。「―刷り」 人の肌の色。人の顔の色つや。「抜けるように―の白い人」
人の肌の色。人の顔の色つや。「抜けるように―の白い人」
 表情としての顔色。「驚きの―が見える」「不満が―に出る」
表情としての顔色。「驚きの―が見える」「不満が―に出る」 目つき。目の光。「目の―を変えて怒りだす」
目つき。目の光。「目の―を変えて怒りだす」
 それらしい態度・そぶり。「反省の―が見られない」
それらしい態度・そぶり。「反省の―が見られない」 それらしく感じられる趣・気配。「秋の―の感じられる昨今」「敗北の―が濃い」
それらしく感じられる趣・気配。「秋の―の感じられる昨今」「敗北の―が濃い」 愛想。「―よい返事」
愛想。「―よい返事」 (「種」とも書く)種類。「―とりどり」「三(み)―選び出す」
(「種」とも書く)種類。「―とりどり」「三(み)―選び出す」 華やかさ。華美。「大会に―をそえる」
華やかさ。華美。「大会に―をそえる」 音・声などの響き。調子。「琴の音(ね)の―」「声(こわ)―」
音・声などの響き。調子。「琴の音(ね)の―」「声(こわ)―」
 情事。色事。「―を好む」「―に溺れる」
情事。色事。「―を好む」「―に溺れる」 女性の美しい容貌。「―に迷う」
女性の美しい容貌。「―に迷う」 情人。恋人。いい人。「―をつくる」
情人。恋人。いい人。「―をつくる」 古代・中世、位階によって定められた衣服の色。特に、禁色(きんじき)。「昔、公おぼして使う給ふ女の、―許されたるありけり」〈伊勢・六五〉
古代・中世、位階によって定められた衣服の色。特に、禁色(きんじき)。「昔、公おぼして使う給ふ女の、―許されたるありけり」〈伊勢・六五〉 喪服のねずみ色。にび色。「女房なども、かの御形見の―変へぬもあり」〈源・幻〉
喪服のねずみ色。にび色。「女房なども、かの御形見の―変へぬもあり」〈源・幻〉 婚礼や葬式のとき上に着る白衣。「葬礼に―を着て供して見せ」〈浄・博多小女郎〉
婚礼や葬式のとき上に着る白衣。「葬礼に―を着て供して見せ」〈浄・博多小女郎〉 人情。情愛。「東人(あづまうど)は…げには心の―なく、情おくれ」〈徒然・一四一〉
人情。情愛。「東人(あづまうど)は…げには心の―なく、情おくれ」〈徒然・一四一〉 [形動ナリ]
[形動ナリ] 女性の髪などがつややかで美しいさま。「髪、―に、こまごまとうるはしう」〈枕・二〇〇〉
女性の髪などがつややかで美しいさま。「髪、―に、こまごまとうるはしう」〈枕・二〇〇〉 好色なさま。「この宮の、いとさわがしきまで―におはしますなれば」〈源・浮舟〉
[類語]
好色なさま。「この宮の、いとさわがしきまで―におはしますなれば」〈源・浮舟〉
[類語] (
( )色彩・色調・色相(しきそう)・色合い・色目(いろめ)・彩り・あや・彩色・カラー
)色彩・色調・色相(しきそう)・色合い・色目(いろめ)・彩り・あや・彩色・カラー
色改ま・る🔗⭐🔉
色改ま・る
喪が明けて、喪服からふだんの衣服に着替える。「宮の御果ても過ぎぬれば、世の中―・りて」〈源・少女〉
色に出(い)・ず🔗⭐🔉
色に出(い)・ず
 心の中の思いが表情や態度に現れる。「忍ぶれど―・でにけりわが恋は物や思ふと人の問ふまで」〈拾遺・恋一〉
心の中の思いが表情や態度に現れる。「忍ぶれど―・でにけりわが恋は物や思ふと人の問ふまで」〈拾遺・恋一〉 色がつく。「わが袖の涙にもあらぬ露にだに萩の下葉は―・でにけり」〈金槐集〉
色がつく。「わが袖の涙にもあらぬ露にだに萩の下葉は―・でにけり」〈金槐集〉
 心の中の思いが表情や態度に現れる。「忍ぶれど―・でにけりわが恋は物や思ふと人の問ふまで」〈拾遺・恋一〉
心の中の思いが表情や態度に現れる。「忍ぶれど―・でにけりわが恋は物や思ふと人の問ふまで」〈拾遺・恋一〉 色がつく。「わが袖の涙にもあらぬ露にだに萩の下葉は―・でにけり」〈金槐集〉
色がつく。「わが袖の涙にもあらぬ露にだに萩の下葉は―・でにけり」〈金槐集〉
色の白いは七難(しちなん)隠す🔗⭐🔉
色の白いは七難(しちなん)隠す
肌の色が白ければ、少しくらいの欠点は隠れて、美しく見える。
色は思案の外(ほか)🔗⭐🔉
色は思案の外(ほか)
男女間の恋情というものは常識では判断しきれないということ。恋は思案の外。
色も香(か)もあ・る🔗⭐🔉
色も香(か)もあ・る
美しい容色も、ゆかしい情愛もある。名実、または情理を兼ね備えている。花も実もある。「人情判事の―・る裁き」
色を失・う🔗⭐🔉
色を失・う
心配や恐れなどで顔が真っ青になる。意外な事態に対処しきれないようす。「悲報に接し愕然(がくぜん)として―・う」
色を売・る🔗⭐🔉
色を売・る
売春をする。色を鬻(ひさ)ぐ。
色を替え品を替・える🔗⭐🔉
色を替え品を替・える
あらゆる手段を用いる。手を替え品を替える。「―・えて説得する」
色を損(そん)・ずる🔗⭐🔉
色を損(そん)・ずる
不機嫌な顔色になる。怒る。
色を正(ただ)・す🔗⭐🔉
色を正(ただ)・す
あらたまった顔つきをする。ようすをきちんと正す。「―・して陳謝する」
色を作・る🔗⭐🔉
色を作・る
 化粧をする。なまめかしく装う。「それぞれに身代ほどの―・りてをかし」〈浮・胸算用・二〉
化粧をする。なまめかしく装う。「それぞれに身代ほどの―・りてをかし」〈浮・胸算用・二〉 人の気を引くようなようすをする。「色つくりたる男の、人待ち顔にて」〈浮・五人女・二〉
人の気を引くようなようすをする。「色つくりたる男の、人待ち顔にて」〈浮・五人女・二〉
 化粧をする。なまめかしく装う。「それぞれに身代ほどの―・りてをかし」〈浮・胸算用・二〉
化粧をする。なまめかしく装う。「それぞれに身代ほどの―・りてをかし」〈浮・胸算用・二〉 人の気を引くようなようすをする。「色つくりたる男の、人待ち顔にて」〈浮・五人女・二〉
人の気を引くようなようすをする。「色つくりたる男の、人待ち顔にて」〈浮・五人女・二〉
色を付・ける🔗⭐🔉
色を付・ける
物事の扱いに情を加える。値引きしたり、割り増ししたりする。「謝礼に―・ける」
色を作(な)・す🔗⭐🔉
色を作(な)・す
怒って顔色を変える。「―・して抗議する」
いろ‐あい【色合(い)】‐あひ🔗⭐🔉
いろ‐あい【色合(い)】‐あひ
 色彩のぐあい。色の加減。色調。「着物の―」
色彩のぐあい。色の加減。色調。「着物の―」 物事の感じやぐあい。傾向。「事件は迷宮入りの―をおびてきた」
物事の感じやぐあい。傾向。「事件は迷宮入りの―をおびてきた」 顔の色つや。顔色。「―心地よげに、声いたう枯れてさへづりゐたり」〈源・玉鬘〉
顔の色つや。顔色。「―心地よげに、声いたう枯れてさへづりゐたり」〈源・玉鬘〉
 色彩のぐあい。色の加減。色調。「着物の―」
色彩のぐあい。色の加減。色調。「着物の―」 物事の感じやぐあい。傾向。「事件は迷宮入りの―をおびてきた」
物事の感じやぐあい。傾向。「事件は迷宮入りの―をおびてきた」 顔の色つや。顔色。「―心地よげに、声いたう枯れてさへづりゐたり」〈源・玉鬘〉
顔の色つや。顔色。「―心地よげに、声いたう枯れてさへづりゐたり」〈源・玉鬘〉
いろ‐あく【色悪】🔗⭐🔉
いろ‐あく【色悪】
 歌舞伎の役柄の一つで、外見は二枚目で性根は悪人の役。「累(かさね)」の与右衛門、「四谷怪談」の伊右衛門など。いろがたき。
歌舞伎の役柄の一つで、外見は二枚目で性根は悪人の役。「累(かさね)」の与右衛門、「四谷怪談」の伊右衛門など。いろがたき。 女性を迷わせてもてあそぶ男。色魔(しきま)。「中々の―で…、
女性を迷わせてもてあそぶ男。色魔(しきま)。「中々の―で…、
 店(カフエー)の女を誑(たら)して」〈魯庵・社会百面相〉
店(カフエー)の女を誑(たら)して」〈魯庵・社会百面相〉
 歌舞伎の役柄の一つで、外見は二枚目で性根は悪人の役。「累(かさね)」の与右衛門、「四谷怪談」の伊右衛門など。いろがたき。
歌舞伎の役柄の一つで、外見は二枚目で性根は悪人の役。「累(かさね)」の与右衛門、「四谷怪談」の伊右衛門など。いろがたき。 女性を迷わせてもてあそぶ男。色魔(しきま)。「中々の―で…、
女性を迷わせてもてあそぶ男。色魔(しきま)。「中々の―で…、
 店(カフエー)の女を誑(たら)して」〈魯庵・社会百面相〉
店(カフエー)の女を誑(たら)して」〈魯庵・社会百面相〉
いろ‐あわせ【色合(わ)せ】‐あはせ🔗⭐🔉
いろ‐あわせ【色合(わ)せ】‐あはせ
[名]スル見本と色とを照らし合わせること。また、同じ色になるように色を調整すること。
いろ‐いと【色糸】🔗⭐🔉
いろ‐いと【色糸】
 種々の色に染めた糸。
種々の色に染めた糸。 三味線の糸。また、三味線。
三味線の糸。また、三味線。
 種々の色に染めた糸。
種々の色に染めた糸。 三味線の糸。また、三味線。
三味線の糸。また、三味線。
いろ・う【色ふ・△彩ふ・×艶ふ】いろふ🔗⭐🔉
いろ・う【色ふ・△彩ふ・×艶ふ】いろふ
 [動ハ四]
[動ハ四] 美しいいろどりをしている。映える。「いかばかり思ひおくとも見えざりし露に―・へる撫子(なでしこ)の花」〈和泉式部集・下〉
美しいいろどりをしている。映える。「いかばかり思ひおくとも見えざりし露に―・へる撫子(なでしこ)の花」〈和泉式部集・下〉 色が美しく交じる。「かざしの花の色々は秋の草に異なるけぢめ分かれで、何事にも目のみ紛ひ―・ふ」〈源・若菜下〉
色が美しく交じる。「かざしの花の色々は秋の草に異なるけぢめ分かれで、何事にも目のみ紛ひ―・ふ」〈源・若菜下〉 [動ハ下二]
[動ハ下二] 美しくいろどる。「大領(おほくび)端袖(はたそで)―・へたる直垂(ひたたれ)に」〈平家・一一〉
美しくいろどる。「大領(おほくび)端袖(はたそで)―・へたる直垂(ひたたれ)に」〈平家・一一〉 金や宝石などをちりばめて飾る。「くさぐさのうるはしき瑠璃を―・へて作れり」〈竹取〉
金や宝石などをちりばめて飾る。「くさぐさのうるはしき瑠璃を―・へて作れり」〈竹取〉 文章などを飾る。潤色する。「詞を―・へて云ふ程に綺語と云ふぞ」〈四河入海・一九〉
文章などを飾る。潤色する。「詞を―・へて云ふ程に綺語と云ふぞ」〈四河入海・一九〉
 [動ハ四]
[動ハ四] 美しいいろどりをしている。映える。「いかばかり思ひおくとも見えざりし露に―・へる撫子(なでしこ)の花」〈和泉式部集・下〉
美しいいろどりをしている。映える。「いかばかり思ひおくとも見えざりし露に―・へる撫子(なでしこ)の花」〈和泉式部集・下〉 色が美しく交じる。「かざしの花の色々は秋の草に異なるけぢめ分かれで、何事にも目のみ紛ひ―・ふ」〈源・若菜下〉
色が美しく交じる。「かざしの花の色々は秋の草に異なるけぢめ分かれで、何事にも目のみ紛ひ―・ふ」〈源・若菜下〉 [動ハ下二]
[動ハ下二] 美しくいろどる。「大領(おほくび)端袖(はたそで)―・へたる直垂(ひたたれ)に」〈平家・一一〉
美しくいろどる。「大領(おほくび)端袖(はたそで)―・へたる直垂(ひたたれ)に」〈平家・一一〉 金や宝石などをちりばめて飾る。「くさぐさのうるはしき瑠璃を―・へて作れり」〈竹取〉
金や宝石などをちりばめて飾る。「くさぐさのうるはしき瑠璃を―・へて作れり」〈竹取〉 文章などを飾る。潤色する。「詞を―・へて云ふ程に綺語と云ふぞ」〈四河入海・一九〉
文章などを飾る。潤色する。「詞を―・へて云ふ程に綺語と云ふぞ」〈四河入海・一九〉
いろ‐うるし【色漆・△彩漆】🔗⭐🔉
いろ‐うるし【色漆・△彩漆】
顔料を加えて色をつけた漆。朱漆・黒漆・青漆など。
いろ‐え【色絵】‐ヱ🔗⭐🔉
いろ‐え【色絵】‐ヱ
 彩色した絵。着色画。
彩色した絵。着色画。 墨絵。
墨絵。 金銀などの薄い板を他の金属の彫刻した部分に焼きつける技法。
金銀などの薄い板を他の金属の彫刻した部分に焼きつける技法。 本焼きした陶磁器の釉(うわぐすり)の上に軟質の顔料で絵や文様を彩色し、低い火度で焼きつけたもの。上絵付け。
本焼きした陶磁器の釉(うわぐすり)の上に軟質の顔料で絵や文様を彩色し、低い火度で焼きつけたもの。上絵付け。
 彩色した絵。着色画。
彩色した絵。着色画。 墨絵。
墨絵。 金銀などの薄い板を他の金属の彫刻した部分に焼きつける技法。
金銀などの薄い板を他の金属の彫刻した部分に焼きつける技法。 本焼きした陶磁器の釉(うわぐすり)の上に軟質の顔料で絵や文様を彩色し、低い火度で焼きつけたもの。上絵付け。
本焼きした陶磁器の釉(うわぐすり)の上に軟質の顔料で絵や文様を彩色し、低い火度で焼きつけたもの。上絵付け。
いろ‐えんぴつ【色鉛筆】🔗⭐🔉
いろ‐えんぴつ【色鉛筆】
赤・青などの色の鉛筆。蝋(ろう)・粘土・ゴムなどに着色顔料をまぜて芯を作る。
いろ‐おんど【色温度】‐ヲンド🔗⭐🔉
いろ‐おんど【色温度】‐ヲンド
高温の物体の放射する光の色から求める温度。黒体がそれと等しい色を出すときの温度で表す。
いろ‐か【色香】🔗⭐🔉
いろ‐か【色香】
 色と香り。
色と香り。 女のあでやかな顔と姿。女の色気。「―に惑う」
女のあでやかな顔と姿。女の色気。「―に惑う」
 色と香り。
色と香り。 女のあでやかな顔と姿。女の色気。「―に惑う」
女のあでやかな顔と姿。女の色気。「―に惑う」
いろ‐がみ【色紙】🔗⭐🔉
いろ‐がみ【色紙】
 種々の色に染めた紙。染め紙。また、折り紙用の着色した紙。
種々の色に染めた紙。染め紙。また、折り紙用の着色した紙。 鳥の子紙を五色に染め分けた畳紙(たとうがみ)。
鳥の子紙を五色に染め分けた畳紙(たとうがみ)。
 種々の色に染めた紙。染め紙。また、折り紙用の着色した紙。
種々の色に染めた紙。染め紙。また、折り紙用の着色した紙。 鳥の子紙を五色に染め分けた畳紙(たとうがみ)。
鳥の子紙を五色に染め分けた畳紙(たとうがみ)。
いろ‐ガラス【色ガラス】🔗⭐🔉
いろ‐ガラス【色ガラス】
着色ガラス。
いろ‐がわ【色革】‐がは🔗⭐🔉
いろ‐がわ【色革】‐がは
着色したなめし革。染め革。
いろ‐がわら【色河‐原】‐がはら🔗⭐🔉
いろ‐がわら【色河‐原】‐がはら
近世、京都四条河原のこと。芝居小屋があり、男色を売る者がいたところからいう。
いろ‐きちがい【色気違い】‐キちがひ🔗⭐🔉
いろ‐きちがい【色気違い】‐キちがひ
 色情狂(しきじようきよう)。
色情狂(しきじようきよう)。 ひどく好色なこと。また、その人。好色家。
ひどく好色なこと。また、その人。好色家。
 色情狂(しきじようきよう)。
色情狂(しきじようきよう)。 ひどく好色なこと。また、その人。好色家。
ひどく好色なこと。また、その人。好色家。
いろ‐ぐるい【色狂ひ】‐ぐるひ🔗⭐🔉
いろ‐ぐるい【色狂ひ】‐ぐるひ
女色におぼれ、放蕩(ほうとう)すること。女狂い。「人間一生のうちに、一たびは―に取り乱さぬといふ事一人もなし」〈浮・子息気質・一〉
いろ‐ぐろ【色黒】🔗⭐🔉
いろ‐ぐろ【色黒】
[名・形動]色、特に肌の色が黒いこと。また、そのさま。「―な(の)人」
いろ‐け【色気】🔗⭐🔉
いろ‐け【色気】
 色の加減。色の調子。色合い。「青の―が薄い」
色の加減。色の調子。色合い。「青の―が薄い」 異性に対する関心や欲求。色情。「―がつく」
異性に対する関心や欲求。色情。「―がつく」 人をひきつける性的魅力。「―たっぷりの目つき」
人をひきつける性的魅力。「―たっぷりの目つき」 愛嬌(あいきよう)。愛想。おもしろみ。風情。「―のないあいさつ」
愛嬌(あいきよう)。愛想。おもしろみ。風情。「―のないあいさつ」 女性の存在。女っ気。「―抜きの宴席」
女性の存在。女っ気。「―抜きの宴席」 社会的地位などに対する興味・関心。「大臣の椅子に―を示す」
社会的地位などに対する興味・関心。「大臣の椅子に―を示す」
 色の加減。色の調子。色合い。「青の―が薄い」
色の加減。色の調子。色合い。「青の―が薄い」 異性に対する関心や欲求。色情。「―がつく」
異性に対する関心や欲求。色情。「―がつく」 人をひきつける性的魅力。「―たっぷりの目つき」
人をひきつける性的魅力。「―たっぷりの目つき」 愛嬌(あいきよう)。愛想。おもしろみ。風情。「―のないあいさつ」
愛嬌(あいきよう)。愛想。おもしろみ。風情。「―のないあいさつ」 女性の存在。女っ気。「―抜きの宴席」
女性の存在。女っ気。「―抜きの宴席」 社会的地位などに対する興味・関心。「大臣の椅子に―を示す」
社会的地位などに対する興味・関心。「大臣の椅子に―を示す」
色気より食い気(け)🔗⭐🔉
色気より食い気(け)
色欲よりも食欲のほうが先であること。転じて、見えを捨てて実利をとること。
いろけ‐づ・く【色気付く】🔗⭐🔉
いろけ‐づ・く【色気付く】
[動カ五(四)] 異性に関心をもちはじめる。性に目覚める。「息子もそろそろ―・いてきた」
異性に関心をもちはじめる。性に目覚める。「息子もそろそろ―・いてきた」 花や果物などが色づいてくる。「ミカンが―・く」
花や果物などが色づいてくる。「ミカンが―・く」
 異性に関心をもちはじめる。性に目覚める。「息子もそろそろ―・いてきた」
異性に関心をもちはじめる。性に目覚める。「息子もそろそろ―・いてきた」 花や果物などが色づいてくる。「ミカンが―・く」
花や果物などが色づいてくる。「ミカンが―・く」
いろ‐ごと【色事】🔗⭐🔉
いろ‐ごと【色事】
 男女間の恋愛や情事。「―には縁遠い生活」
男女間の恋愛や情事。「―には縁遠い生活」 芝居で、男女間の情事のしぐさ。
芝居で、男女間の情事のしぐさ。 情人。愛人。いろ。「あの花紫は幡随長兵衛が―だとのこと」〈伎・吾嬬鑑〉
情人。愛人。いろ。「あの花紫は幡随長兵衛が―だとのこと」〈伎・吾嬬鑑〉
 男女間の恋愛や情事。「―には縁遠い生活」
男女間の恋愛や情事。「―には縁遠い生活」 芝居で、男女間の情事のしぐさ。
芝居で、男女間の情事のしぐさ。 情人。愛人。いろ。「あの花紫は幡随長兵衛が―だとのこと」〈伎・吾嬬鑑〉
情人。愛人。いろ。「あの花紫は幡随長兵衛が―だとのこと」〈伎・吾嬬鑑〉
いろごと‐し【色事師】🔗⭐🔉
いろごと‐し【色事師】
 歌舞伎で、色事を演じるのを得意とする役者。濡(ぬ)れ事師。
歌舞伎で、色事を演じるのを得意とする役者。濡(ぬ)れ事師。 情事の巧みな男。女たらし。
情事の巧みな男。女たらし。
 歌舞伎で、色事を演じるのを得意とする役者。濡(ぬ)れ事師。
歌舞伎で、色事を演じるのを得意とする役者。濡(ぬ)れ事師。 情事の巧みな男。女たらし。
情事の巧みな男。女たらし。
いろ‐ごのみ【色好み】🔗⭐🔉
いろ‐ごのみ【色好み】
 情事を好むこと。また、その人。好色漢。
情事を好むこと。また、その人。好色漢。 恋愛の情趣をよく解すること。また、その人。「―といはるるかぎり、五人」〈竹取〉
恋愛の情趣をよく解すること。また、その人。「―といはるるかぎり、五人」〈竹取〉 風流・風雅な方面に関心や理解があること。また、その人。「かの賢き―に仰せ合はせ給ひて、筑波集とていみじき様々の姿を尽くして集め置き給へる」〈ささめごと〉
風流・風雅な方面に関心や理解があること。また、その人。「かの賢き―に仰せ合はせ給ひて、筑波集とていみじき様々の姿を尽くして集め置き給へる」〈ささめごと〉 遊女などを買うこと。また、その遊女。「主なき女をよびて、料足を取らせて逢ふ事を―といふなり」〈伽・物くさ太郎〉
遊女などを買うこと。また、その遊女。「主なき女をよびて、料足を取らせて逢ふ事を―といふなり」〈伽・物くさ太郎〉
 情事を好むこと。また、その人。好色漢。
情事を好むこと。また、その人。好色漢。 恋愛の情趣をよく解すること。また、その人。「―といはるるかぎり、五人」〈竹取〉
恋愛の情趣をよく解すること。また、その人。「―といはるるかぎり、五人」〈竹取〉 風流・風雅な方面に関心や理解があること。また、その人。「かの賢き―に仰せ合はせ給ひて、筑波集とていみじき様々の姿を尽くして集め置き給へる」〈ささめごと〉
風流・風雅な方面に関心や理解があること。また、その人。「かの賢き―に仰せ合はせ給ひて、筑波集とていみじき様々の姿を尽くして集め置き給へる」〈ささめごと〉 遊女などを買うこと。また、その遊女。「主なき女をよびて、料足を取らせて逢ふ事を―といふなり」〈伽・物くさ太郎〉
遊女などを買うこと。また、その遊女。「主なき女をよびて、料足を取らせて逢ふ事を―といふなり」〈伽・物くさ太郎〉
いろ‐ざし【色差(し)】🔗⭐🔉
いろ‐ざし【色差(し)】
《「いろさし」とも》 色をつけること。彩色。着色。
色をつけること。彩色。着色。 顔などの色つや。色のぐあい。「御―まことにめでたく御心地よげに見えさせ給ひけるが」〈沙石集・一〉
顔などの色つや。色のぐあい。「御―まことにめでたく御心地よげに見えさせ給ひけるが」〈沙石集・一〉
 色をつけること。彩色。着色。
色をつけること。彩色。着色。 顔などの色つや。色のぐあい。「御―まことにめでたく御心地よげに見えさせ給ひけるが」〈沙石集・一〉
顔などの色つや。色のぐあい。「御―まことにめでたく御心地よげに見えさせ給ひけるが」〈沙石集・一〉
いろ‐じかけ【色仕掛(け)】🔗⭐🔉
いろ‐じかけ【色仕掛(け)】
ある目的を達成するために、色情を利用して異性をだましたり、誘惑したりすること。「―で承知させる」
いろ‐しすう【色指数】🔗⭐🔉
いろ‐しすう【色指数】
 星の色を数量的に示す尺度。写真等級から実視等級を引いた差で表す。赤い星ほど大きい値となる。
星の色を数量的に示す尺度。写真等級から実視等級を引いた差で表す。赤い星ほど大きい値となる。 火成岩分類の基準の一。岩石中に含まれる有色鉱物の割合を百分率で表す。
火成岩分類の基準の一。岩石中に含まれる有色鉱物の割合を百分率で表す。
 星の色を数量的に示す尺度。写真等級から実視等級を引いた差で表す。赤い星ほど大きい値となる。
星の色を数量的に示す尺度。写真等級から実視等級を引いた差で表す。赤い星ほど大きい値となる。 火成岩分類の基準の一。岩石中に含まれる有色鉱物の割合を百分率で表す。
火成岩分類の基準の一。岩石中に含まれる有色鉱物の割合を百分率で表す。
いろ‐すな【色砂】🔗⭐🔉
いろ‐すな【色砂】
和室の砂壁の上塗りに用いる、色のついた砂。
いろ‐ずり【色刷(り)・色×摺り】🔗⭐🔉
いろ‐ずり【色刷(り)・色×摺り】
 種々の色彩を用いて印刷物や版画などを刷ること。また、そのもの。
種々の色彩を用いて印刷物や版画などを刷ること。また、そのもの。 衣服などに、色彩で模様をすり出すこと。
衣服などに、色彩で模様をすり出すこと。
 種々の色彩を用いて印刷物や版画などを刷ること。また、そのもの。
種々の色彩を用いて印刷物や版画などを刷ること。また、そのもの。 衣服などに、色彩で模様をすり出すこと。
衣服などに、色彩で模様をすり出すこと。
いろ‐だか【色高】🔗⭐🔉
いろ‐だか【色高】
江戸時代の雑税の一。クワ・コウゾ・ウルシなどの栽培によって、田畑以外の山野・河海などからの収益があるとき、これを高に算定して村高に組み入れたもの。
いろ‐だま【色玉】🔗⭐🔉
いろ‐だま【色玉】
ザクロの別名。
いろ‐チョーク【色チョーク】🔗⭐🔉
いろ‐チョーク【色チョーク】
赤・青・黄などの色をつけた白墨。特に、普通の白墨と区別していう。
いろっ‐ぽ・い【色っぽい】🔗⭐🔉
いろっ‐ぽ・い【色っぽい】
[形]異性を引きつけるような魅力にあふれているさま。なまめかしい。多く女性にいう。「―・い年増」「―・いしぐさ」
[派生]いろっぽさ[名]
いろ‐つや【色×艶】🔗⭐🔉
いろ‐つや【色×艶】
 光沢のある色合い。特に、肌の色とつや。「顔の―がいい」
光沢のある色合い。特に、肌の色とつや。「顔の―がいい」 話や文章に付加されるおもしろみ。興趣。「話に―を添える」
話や文章に付加されるおもしろみ。興趣。「話に―を添える」 話や態度に感じられる愛想。情愛。「―のない応対ぶり」
話や態度に感じられる愛想。情愛。「―のない応対ぶり」
 光沢のある色合い。特に、肌の色とつや。「顔の―がいい」
光沢のある色合い。特に、肌の色とつや。「顔の―がいい」 話や文章に付加されるおもしろみ。興趣。「話に―を添える」
話や文章に付加されるおもしろみ。興趣。「話に―を添える」 話や態度に感じられる愛想。情愛。「―のない応対ぶり」
話や態度に感じられる愛想。情愛。「―のない応対ぶり」
いろ‐どめ【色止め】🔗⭐🔉
いろ‐どめ【色止め】
染め物の色が、さめたり落ちたりしないように固着剤などで処理すること。
いろ‐どり【彩り・色取り】🔗⭐🔉
いろ‐どり【彩り・色取り】
 色をつけること。彩色。
色をつけること。彩色。 色の配合。配色。「美しい―の秋の山々」
色の配合。配色。「美しい―の秋の山々」 おもしろみや風情、華やかさなどを付け加えること。「パレードが式典に―を添える」
おもしろみや風情、華やかさなどを付け加えること。「パレードが式典に―を添える」
 色をつけること。彩色。
色をつけること。彩色。 色の配合。配色。「美しい―の秋の山々」
色の配合。配色。「美しい―の秋の山々」 おもしろみや風情、華やかさなどを付け加えること。「パレードが式典に―を添える」
おもしろみや風情、華やかさなどを付け加えること。「パレードが式典に―を添える」
いろどり‐づき【色取り月】🔗⭐🔉
いろどり‐づき【色取り月】
《木の葉が色づく意から》陰暦九月の異称。
いろ‐とりどり【色取り取り】🔗⭐🔉
いろ‐とりどり【色取り取り】
種類がいろいろであること。「―の草花」「―の催し」
いろ‐ど・る【彩る・色取る】🔗⭐🔉
いろ‐ど・る【彩る・色取る】
[動ラ五(四)] 色をつける。彩色する。「壁を薄い緑に―・る」
色をつける。彩色する。「壁を薄い緑に―・る」 化粧する。「ほお紅で―・る」
化粧する。「ほお紅で―・る」 さまざまの色や物を取り合わせて飾る。「花で食卓を―・る」
さまざまの色や物を取り合わせて飾る。「花で食卓を―・る」 おもしろみや趣などを付け加える。「数々の逸話で―・られた人物」
おもしろみや趣などを付け加える。「数々の逸話で―・られた人物」
 色をつける。彩色する。「壁を薄い緑に―・る」
色をつける。彩色する。「壁を薄い緑に―・る」 化粧する。「ほお紅で―・る」
化粧する。「ほお紅で―・る」 さまざまの色や物を取り合わせて飾る。「花で食卓を―・る」
さまざまの色や物を取り合わせて飾る。「花で食卓を―・る」 おもしろみや趣などを付け加える。「数々の逸話で―・られた人物」
おもしろみや趣などを付け加える。「数々の逸話で―・られた人物」
いろ‐のり【色×糊】🔗⭐🔉
いろ‐のり【色×糊】
染料を加えた捺染(なつせん)用の糊。
いろ‐まち【色町・色街】🔗⭐🔉
いろ‐まち【色町・色街】
花柳街。特に、遊郭。遊里。色里。
いろ‐みほん【色見本】🔗⭐🔉
いろ‐みほん【色見本】
布地・染料・印刷などの色の見本。また、それを分類、整理したもの。
いろ‐めか・し【色めかし】🔗⭐🔉
いろ‐めか・し【色めかし】
[形シク]恋の情趣を好むようにみえるさま。色好みらしい。「―・しうなよび給へるを、女にて見むはをかしかりぬべく」〈源・紅葉賀〉
いろ‐めがね【色眼‐鏡】🔗⭐🔉
いろ‐めがね【色眼‐鏡】
 着色したレンズをはめた眼鏡。サングラスなど。
着色したレンズをはめた眼鏡。サングラスなど。 偏った物の見方。先入観にとらわれた物の見方。「―で人を見る」
偏った物の見方。先入観にとらわれた物の見方。「―で人を見る」
 着色したレンズをはめた眼鏡。サングラスなど。
着色したレンズをはめた眼鏡。サングラスなど。 偏った物の見方。先入観にとらわれた物の見方。「―で人を見る」
偏った物の見方。先入観にとらわれた物の見方。「―で人を見る」
いろめき‐た・つ【色めき立つ】🔗⭐🔉
いろめき‐た・つ【色めき立つ】
[動タ五(四)]緊張や興奮で落ち着かなくなる。動揺しはじめる。「緊急動議に議場は―・った」
いろ‐め・く【色めく】🔗⭐🔉
いろ‐め・く【色めく】
[動カ五(四)] その時節が来て色が美しくなる。華やかになる。「春になって公園の木々が―・く」
その時節が来て色が美しくなる。華やかになる。「春になって公園の木々が―・く」 色っぽく見える。「ほんのりとほおを染めて―・いた風情」
色っぽく見える。「ほんのりとほおを染めて―・いた風情」 緊張や興奮のために落ち着かない状態になる。活気づく。騒然となる。動揺する。「犯人逮捕の知らせに報道陣が―・いた」
緊張や興奮のために落ち着かない状態になる。活気づく。騒然となる。動揺する。「犯人逮捕の知らせに報道陣が―・いた」 戦いに敗れるようすが見え始める。「すはや敵は―・きたるは、と胡
戦いに敗れるようすが見え始める。「すはや敵は―・きたるは、と胡 (えびら)を叩き、勝時を作って」〈太平記・八〉
(えびら)を叩き、勝時を作って」〈太平記・八〉
 その時節が来て色が美しくなる。華やかになる。「春になって公園の木々が―・く」
その時節が来て色が美しくなる。華やかになる。「春になって公園の木々が―・く」 色っぽく見える。「ほんのりとほおを染めて―・いた風情」
色っぽく見える。「ほんのりとほおを染めて―・いた風情」 緊張や興奮のために落ち着かない状態になる。活気づく。騒然となる。動揺する。「犯人逮捕の知らせに報道陣が―・いた」
緊張や興奮のために落ち着かない状態になる。活気づく。騒然となる。動揺する。「犯人逮捕の知らせに報道陣が―・いた」 戦いに敗れるようすが見え始める。「すはや敵は―・きたるは、と胡
戦いに敗れるようすが見え始める。「すはや敵は―・きたるは、と胡 (えびら)を叩き、勝時を作って」〈太平記・八〉
(えびら)を叩き、勝時を作って」〈太平記・八〉
いろ‐ゆるし【色許し・色△聴し】🔗⭐🔉
いろ‐ゆるし【色許し・色△聴し】
禁色(きんじき)を許されること。
いろ‐よ・い【色△好い】🔗⭐🔉
いろ‐よ・い【色△好い】
[形] いろよ・し[ク]
いろよ・し[ク] こちらの望みにそうようなさま。都合がよい。好ましい。主に連体形が用いられる。「―・い返事」
こちらの望みにそうようなさま。都合がよい。好ましい。主に連体形が用いられる。「―・い返事」 容姿が美しい。「―・き人を見そめて」〈浮・好色袖鑑〉
容姿が美しい。「―・き人を見そめて」〈浮・好色袖鑑〉
 いろよ・し[ク]
いろよ・し[ク] こちらの望みにそうようなさま。都合がよい。好ましい。主に連体形が用いられる。「―・い返事」
こちらの望みにそうようなさま。都合がよい。好ましい。主に連体形が用いられる。「―・い返事」 容姿が美しい。「―・き人を見そめて」〈浮・好色袖鑑〉
容姿が美しい。「―・き人を見そめて」〈浮・好色袖鑑〉
いろん‐な【色んな】🔗⭐🔉
いろん‐な【色んな】
[連体]《「いろいろな」の音変化》さまざまの。種々の。「―話をする」
くり‐いろ【×涅色・× 色】🔗⭐🔉
色】🔗⭐🔉
くり‐いろ【×涅色・× 色】
色】

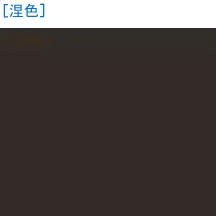 染め色の名。黒色。または、黒色に褐色のまじった色。くり。
染め色の名。黒色。または、黒色に褐色のまじった色。くり。
 色】
色】

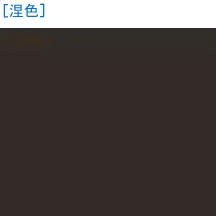 染め色の名。黒色。または、黒色に褐色のまじった色。くり。
染め色の名。黒色。または、黒色に褐色のまじった色。くり。
しき【色】🔗⭐🔉
しき【色】
仏語。 五蘊(ごうん)の一。五感によって認識される、物質や肉体。存在物。もの。
五蘊(ごうん)の一。五感によって認識される、物質や肉体。存在物。もの。 五境の一。目でとらえられるもの。色や形のあるもの。
五境の一。目でとらえられるもの。色や形のあるもの。
 五蘊(ごうん)の一。五感によって認識される、物質や肉体。存在物。もの。
五蘊(ごうん)の一。五感によって認識される、物質や肉体。存在物。もの。 五境の一。目でとらえられるもの。色や形のあるもの。
五境の一。目でとらえられるもの。色や形のあるもの。
しき‐え【色△衣】🔗⭐🔉
しき‐え【色△衣】
墨染めの衣以外の法衣。紫・緋・黄・青などの色があり、高位の僧が着る。
しき‐か【色価】🔗⭐🔉
しき‐か【色価】
《(フランス)valeur》絵画の画面を構成する色相・明度・彩度の相関関係。バルール。
しき‐かい【色界】🔗⭐🔉
しき‐かい【色界】
仏語。三界の一。欲界の上、無色界の下にある世界。欲界のように欲や煩悩(ぼんのう)はないが、無色界ほど物質や肉体の束縛から脱却していない世界。色界天。色天。四禅を修めた者の生まれる天界で、初禅天から第四禅天の四禅天よりなり、さらに一七天に分ける。
しき‐かく【色覚】🔗⭐🔉
しき‐かく【色覚】
視覚の一。光の波長の違いを色彩として識別する感覚。色神。
しきかく‐いじょう【色覚異常】‐イジヤウ🔗⭐🔉
しきかく‐いじょう【色覚異常】‐イジヤウ
色を見分ける視覚の異常。色盲・色弱などのこと。
しき‐かん【色感】🔗⭐🔉
しき‐かん【色感】
 色彩から受ける感じ。
色彩から受ける感じ。 色を見分ける感覚。色彩感覚。
色を見分ける感覚。色彩感覚。
 色彩から受ける感じ。
色彩から受ける感じ。 色を見分ける感覚。色彩感覚。
色を見分ける感覚。色彩感覚。
しき‐かん【色環】‐クワン🔗⭐🔉
しき‐かん【色環】‐クワン
色相をスペクトルの順序に環状に配列したもの。向かいあった二つの色は互いに補色の関係にある。色相環。カラーサークル。
しき‐さい【色彩】🔗⭐🔉
しき‐さい【色彩】
 いろ。いろどりや色合い。「―が美しい」
いろ。いろどりや色合い。「―が美しい」 物事にあらわれている、あるようすや傾向。「保守的―が強い」
物事にあらわれている、あるようすや傾向。「保守的―が強い」
 いろ。いろどりや色合い。「―が美しい」
いろ。いろどりや色合い。「―が美しい」 物事にあらわれている、あるようすや傾向。「保守的―が強い」
物事にあらわれている、あるようすや傾向。「保守的―が強い」
しきさい‐かんかく【色彩感覚】🔗⭐🔉
しきさい‐かんかく【色彩感覚】
色を感じとる能力。また、色を使いこなす能力。色感。
しきさい‐ちょうせつ【色彩調節】‐テウセツ🔗⭐🔉
しきさい‐ちょうせつ【色彩調節】‐テウセツ
色彩が人間に与える心理的な効果を利用して、疲労防止・能率向上・災害防止などに役立たせるため、色を選んで用いること。カラーコンディショニング。
しき‐し【色紙】🔗⭐🔉
しき‐し【色紙】
 和歌・俳句・書画などを書き記す四角い厚紙。五色の模様や金・銀の砂子などを施すものもある。寸法に二種類あり、大は縦六寸四分(約二〇センチ)・横五寸六分(約一七センチ)、小は縦六寸(約一八センチ)・横五寸三分(約一六センチ)。
和歌・俳句・書画などを書き記す四角い厚紙。五色の模様や金・銀の砂子などを施すものもある。寸法に二種類あり、大は縦六寸四分(約二〇センチ)・横五寸六分(約一七センチ)、小は縦六寸(約一八センチ)・横五寸三分(約一六センチ)。 衣服の弱った部分に裏打ちをする布地。
衣服の弱った部分に裏打ちをする布地。
 和歌・俳句・書画などを書き記す四角い厚紙。五色の模様や金・銀の砂子などを施すものもある。寸法に二種類あり、大は縦六寸四分(約二〇センチ)・横五寸六分(約一七センチ)、小は縦六寸(約一八センチ)・横五寸三分(約一六センチ)。
和歌・俳句・書画などを書き記す四角い厚紙。五色の模様や金・銀の砂子などを施すものもある。寸法に二種類あり、大は縦六寸四分(約二〇センチ)・横五寸六分(約一七センチ)、小は縦六寸(約一八センチ)・横五寸三分(約一六センチ)。 衣服の弱った部分に裏打ちをする布地。
衣服の弱った部分に裏打ちをする布地。
しきし‐がた【色紙形】🔗⭐🔉
しきし‐がた【色紙形】
 短冊形に対して、正方形に近い四角形。
短冊形に対して、正方形に近い四角形。 屏風(びようぶ)や障子に色紙の形を貼ったり輪郭を施したりして、そこに詩歌などを書いたもの。
屏風(びようぶ)や障子に色紙の形を貼ったり輪郭を施したりして、そこに詩歌などを書いたもの。
 短冊形に対して、正方形に近い四角形。
短冊形に対して、正方形に近い四角形。 屏風(びようぶ)や障子に色紙の形を貼ったり輪郭を施したりして、そこに詩歌などを書いたもの。
屏風(びようぶ)や障子に色紙の形を貼ったり輪郭を施したりして、そこに詩歌などを書いたもの。
しきし‐しょう【色視症】‐シヤウ🔗⭐🔉
しきし‐しょう【色視症】‐シヤウ
無色のものに色がついて見える症状。水晶体の摘出手術後の赤視症や青視症、サントニン中毒による黄視症などがある。
しきし‐だて【色紙△点】🔗⭐🔉
しきし‐だて【色紙△点】
茶の湯で、茶箱点(ちやばこだて)の一。道具や古袱紗(こぶくさ)などを置き合わせた形が、色紙を散らしたようになるところからいう。裏千家一一世淡々斎の考案になる。
しきし‐ばこ【色紙箱】🔗⭐🔉
しきし‐ばこ【色紙箱】
蒔絵(まきえ)などで彩色された、色紙を納める箱。
しきし‐まど【色紙窓】🔗⭐🔉
しきし‐まど【色紙窓】
茶室の窓の一種。二つの窓を上下にずらして配置したもの。色紙を散らしてはりつけたのに似ているところからいう。
しき‐じゃく【色弱】🔗⭐🔉
しき‐じゃく【色弱】
色覚に異常のある状態。色盲よりは程度が軽く、色の区別がしにくいもの。
しょく【色】🔗⭐🔉
しょく【色】
〔接尾〕助数詞。色数(いろかず)を数えるのに用いる。「三―かけ合わせ」「二四―の色鉛筆」「三―刷り」
れい‐しょく【× 色】🔗⭐🔉
色】🔗⭐🔉
れい‐しょく【× 色】
血相を変えること。
色】
血相を変えること。
 色】
血相を変えること。
色】
血相を変えること。
色🔗⭐🔉
色
 [音]ショク
シキ
[訓]いろ
[部首]色
[総画数]6
[コード]区点 3107
JIS 3F27
S‐JIS 9046
[分類]常用漢字
[難読語]
→あ‐いろ【文色】
→あかがね‐いろ【銅色】
→あきのいろくさ【秋色種】
→いろ‐ぐすり【色釉】
→うん‐しょく【慍色】
→え‐しき【壊色】
→かち‐いろ【褐色・搗色】
→き‐そく【気色】
→くり‐いろ【涅色・
[音]ショク
シキ
[訓]いろ
[部首]色
[総画数]6
[コード]区点 3107
JIS 3F27
S‐JIS 9046
[分類]常用漢字
[難読語]
→あ‐いろ【文色】
→あかがね‐いろ【銅色】
→あきのいろくさ【秋色種】
→いろ‐ぐすり【色釉】
→うん‐しょく【慍色】
→え‐しき【壊色】
→かち‐いろ【褐色・搗色】
→き‐そく【気色】
→くり‐いろ【涅色・ 色】
→くれない‐いろ【紅色】
→け‐しき【化色】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しきし‐だて【色紙点】
→しこたん【色丹】
→しろがね‐いろ【銀色】
→たい‐しょく【退色・褪色】
→チン‐イーソー【清一色】
→ツーイーソー【字一色】
→にな‐いろ【蜷色】
→にび‐いろ【鈍色】
→ひ‐じき【非色】
→ひ‐そく【秘色】
→ホンイーソー【混一色】
→ゆう‐しょく【油色】
→ゆば‐いろ【柚葉色】
→リュー‐イーソー【緑一色】
→れい‐しょく【
色】
→くれない‐いろ【紅色】
→け‐しき【化色】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しきし‐だて【色紙点】
→しこたん【色丹】
→しろがね‐いろ【銀色】
→たい‐しょく【退色・褪色】
→チン‐イーソー【清一色】
→ツーイーソー【字一色】
→にな‐いろ【蜷色】
→にび‐いろ【鈍色】
→ひ‐じき【非色】
→ひ‐そく【秘色】
→ホンイーソー【混一色】
→ゆう‐しょく【油色】
→ゆば‐いろ【柚葉色】
→リュー‐イーソー【緑一色】
→れい‐しょく【 色】
→ろ‐いろ【蝋色・呂色】
色】
→ろ‐いろ【蝋色・呂色】
 [音]ショク
シキ
[訓]いろ
[部首]色
[総画数]6
[コード]区点 3107
JIS 3F27
S‐JIS 9046
[分類]常用漢字
[難読語]
→あ‐いろ【文色】
→あかがね‐いろ【銅色】
→あきのいろくさ【秋色種】
→いろ‐ぐすり【色釉】
→うん‐しょく【慍色】
→え‐しき【壊色】
→かち‐いろ【褐色・搗色】
→き‐そく【気色】
→くり‐いろ【涅色・
[音]ショク
シキ
[訓]いろ
[部首]色
[総画数]6
[コード]区点 3107
JIS 3F27
S‐JIS 9046
[分類]常用漢字
[難読語]
→あ‐いろ【文色】
→あかがね‐いろ【銅色】
→あきのいろくさ【秋色種】
→いろ‐ぐすり【色釉】
→うん‐しょく【慍色】
→え‐しき【壊色】
→かち‐いろ【褐色・搗色】
→き‐そく【気色】
→くり‐いろ【涅色・ 色】
→くれない‐いろ【紅色】
→け‐しき【化色】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しきし‐だて【色紙点】
→しこたん【色丹】
→しろがね‐いろ【銀色】
→たい‐しょく【退色・褪色】
→チン‐イーソー【清一色】
→ツーイーソー【字一色】
→にな‐いろ【蜷色】
→にび‐いろ【鈍色】
→ひ‐じき【非色】
→ひ‐そく【秘色】
→ホンイーソー【混一色】
→ゆう‐しょく【油色】
→ゆば‐いろ【柚葉色】
→リュー‐イーソー【緑一色】
→れい‐しょく【
色】
→くれない‐いろ【紅色】
→け‐しき【化色】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しきし‐だて【色紙点】
→しこたん【色丹】
→しろがね‐いろ【銀色】
→たい‐しょく【退色・褪色】
→チン‐イーソー【清一色】
→ツーイーソー【字一色】
→にな‐いろ【蜷色】
→にび‐いろ【鈍色】
→ひ‐じき【非色】
→ひ‐そく【秘色】
→ホンイーソー【混一色】
→ゆう‐しょく【油色】
→ゆば‐いろ【柚葉色】
→リュー‐イーソー【緑一色】
→れい‐しょく【 色】
→ろ‐いろ【蝋色・呂色】
色】
→ろ‐いろ【蝋色・呂色】
大辞泉に「色」で始まるの検索結果 1-86。もっと読み込む