複数辞典一括検索+![]()
![]()
かがみ【鏡・△鑑・×鑒】🔗⭐🔉
かがみ【鏡・△鑑・×鑒】
 人の姿や物の形を映し見る道具。古くは青銅・白銅・鉄などの表面に水銀に錫(すず)をまぜたものを塗って磨いて作った。形は方円・八つ花形などがある。現在のものは、ガラス板の裏面に水銀を塗ってある。
人の姿や物の形を映し見る道具。古くは青銅・白銅・鉄などの表面に水銀に錫(すず)をまぜたものを塗って磨いて作った。形は方円・八つ花形などがある。現在のものは、ガラス板の裏面に水銀を塗ってある。 (鑑・鑒)人の手本。模範。「人の―」
(鑑・鑒)人の手本。模範。「人の―」 「鏡餅(かがみもち)」の略。
「鏡餅(かがみもち)」の略。 《形が古鏡に似ているところから》酒樽のふた。「―を抜く」
《形が古鏡に似ているところから》酒樽のふた。「―を抜く」 「鏡物(かがみもの)」の略。
「鏡物(かがみもの)」の略。 茶碗の茶だまりで、丸く一段くぼんでいる部分。高麗茶碗によく見られるもので、熊川(こもがい)茶碗の約束事の一。
[下接語]合わせ鏡・岩鏡・自惚(うぬぼ)れ鏡・衣紋(えもん)鏡・御(お)鏡・懐中鏡・浄玻璃(じようはり)の鏡・空の鏡・智慧(ちえ)の鏡・月の鏡・手鏡・共鏡・野守(のもり)の鏡・初鏡・ビードロ鏡・鬢(びん)鏡・懐鏡・丸鏡・水鏡・八咫(やた)の鏡
茶碗の茶だまりで、丸く一段くぼんでいる部分。高麗茶碗によく見られるもので、熊川(こもがい)茶碗の約束事の一。
[下接語]合わせ鏡・岩鏡・自惚(うぬぼ)れ鏡・衣紋(えもん)鏡・御(お)鏡・懐中鏡・浄玻璃(じようはり)の鏡・空の鏡・智慧(ちえ)の鏡・月の鏡・手鏡・共鏡・野守(のもり)の鏡・初鏡・ビードロ鏡・鬢(びん)鏡・懐鏡・丸鏡・水鏡・八咫(やた)の鏡
 人の姿や物の形を映し見る道具。古くは青銅・白銅・鉄などの表面に水銀に錫(すず)をまぜたものを塗って磨いて作った。形は方円・八つ花形などがある。現在のものは、ガラス板の裏面に水銀を塗ってある。
人の姿や物の形を映し見る道具。古くは青銅・白銅・鉄などの表面に水銀に錫(すず)をまぜたものを塗って磨いて作った。形は方円・八つ花形などがある。現在のものは、ガラス板の裏面に水銀を塗ってある。 (鑑・鑒)人の手本。模範。「人の―」
(鑑・鑒)人の手本。模範。「人の―」 「鏡餅(かがみもち)」の略。
「鏡餅(かがみもち)」の略。 《形が古鏡に似ているところから》酒樽のふた。「―を抜く」
《形が古鏡に似ているところから》酒樽のふた。「―を抜く」 「鏡物(かがみもの)」の略。
「鏡物(かがみもの)」の略。 茶碗の茶だまりで、丸く一段くぼんでいる部分。高麗茶碗によく見られるもので、熊川(こもがい)茶碗の約束事の一。
[下接語]合わせ鏡・岩鏡・自惚(うぬぼ)れ鏡・衣紋(えもん)鏡・御(お)鏡・懐中鏡・浄玻璃(じようはり)の鏡・空の鏡・智慧(ちえ)の鏡・月の鏡・手鏡・共鏡・野守(のもり)の鏡・初鏡・ビードロ鏡・鬢(びん)鏡・懐鏡・丸鏡・水鏡・八咫(やた)の鏡
茶碗の茶だまりで、丸く一段くぼんでいる部分。高麗茶碗によく見られるもので、熊川(こもがい)茶碗の約束事の一。
[下接語]合わせ鏡・岩鏡・自惚(うぬぼ)れ鏡・衣紋(えもん)鏡・御(お)鏡・懐中鏡・浄玻璃(じようはり)の鏡・空の鏡・智慧(ちえ)の鏡・月の鏡・手鏡・共鏡・野守(のもり)の鏡・初鏡・ビードロ鏡・鬢(びん)鏡・懐鏡・丸鏡・水鏡・八咫(やた)の鏡
かがみ‐あぶみ【鏡×鐙】🔗⭐🔉
かがみ‐あぶみ【鏡×鐙】
鏡鞍(かがみぐら)に用いる鐙。表面を錫(すず)と銅の合金による鏡地(かがみじ)とするときには銀・金・銅で張り包んだものもある。
かがみ‐いけ【鏡池】🔗⭐🔉
かがみ‐いけ【鏡池】
昔の貴人・英雄などが、水面に姿を映したとか、持っていた鏡を落としたとかの伝説がある池。
かがみ‐いし【鏡石】🔗⭐🔉
かがみ‐いし【鏡石】
 表面が滑らかでつやがあり、ものの影がよく映る石。鏡岩。
表面が滑らかでつやがあり、ものの影がよく映る石。鏡岩。 手水鉢(ちようずばち)の前に置く石。
手水鉢(ちようずばち)の前に置く石。
 表面が滑らかでつやがあり、ものの影がよく映る石。鏡岩。
表面が滑らかでつやがあり、ものの影がよく映る石。鏡岩。 手水鉢(ちようずばち)の前に置く石。
手水鉢(ちようずばち)の前に置く石。
かがみ‐いた【鏡板】🔗⭐🔉
かがみ‐いた【鏡板】
 壁・天井などに張る、平らで滑らかな一枚板。
壁・天井などに張る、平らで滑らかな一枚板。 能舞台の後方正面の羽目板。ふつう、大きく一本の老松を描く。
能舞台の後方正面の羽目板。ふつう、大きく一本の老松を描く。 轡(くつわ)の部分の名。はみの両端に付いて馬の口脇をおさえる金具。
轡(くつわ)の部分の名。はみの両端に付いて馬の口脇をおさえる金具。
 壁・天井などに張る、平らで滑らかな一枚板。
壁・天井などに張る、平らで滑らかな一枚板。 能舞台の後方正面の羽目板。ふつう、大きく一本の老松を描く。
能舞台の後方正面の羽目板。ふつう、大きく一本の老松を描く。 轡(くつわ)の部分の名。はみの両端に付いて馬の口脇をおさえる金具。
轡(くつわ)の部分の名。はみの両端に付いて馬の口脇をおさえる金具。
かがみ‐いわ【鏡岩】‐いは🔗⭐🔉
かがみ‐いわ【鏡岩】‐いは
「鏡石 」に同じ。
」に同じ。
 」に同じ。
」に同じ。
かがみ‐おび【鏡帯】🔗⭐🔉
かがみ‐おび【鏡帯】
裏布を表に、または表布を裏に折り返して、額縁のように仕立てた帯。
かがみ‐がい【鏡貝】‐がひ🔗⭐🔉
かがみ‐がい【鏡貝】‐がひ
マルスダレガイ科の二枚貝。浅海の砂泥底にすむ。貝殻は円形で平たく、殻長七センチくらい。殻表は白色で、細かい成長脈がある。北海道南部から南に分布。食用。餅貝。白貝(しらがい)。文珠貝(もんじゆがい)。
かがみ‐がわ【鏡川】‐がは🔗⭐🔉
かがみ‐がわ【鏡川】‐がは
高知県中部を流れる川。工石山(くいしやま)に源を発し、高知市を流れて、浦戸湾に注ぐ。長さ三一キロ。
かがみ‐ぐさ【鏡草】🔗⭐🔉
かがみ‐ぐさ【鏡草】
 昔、宮中で、正月元日に鏡餅(かがみもち)の上にのせた大根の輪切り。また、大根の別名。
昔、宮中で、正月元日に鏡餅(かがみもち)の上にのせた大根の輪切り。また、大根の別名。 ビャクレンの別名。
ビャクレンの別名。
 昔、宮中で、正月元日に鏡餅(かがみもち)の上にのせた大根の輪切り。また、大根の別名。
昔、宮中で、正月元日に鏡餅(かがみもち)の上にのせた大根の輪切り。また、大根の別名。 ビャクレンの別名。
ビャクレンの別名。
かがみ‐ぐつわ【鏡×轡】🔗⭐🔉
かがみ‐ぐつわ【鏡×轡】
鏡板(かがみいた)の部分を鏡のように円形にし、彫り透かしを入れないでつくった轡。
かがみ‐ぐら【鏡×鞍】🔗⭐🔉
かがみ‐ぐら【鏡×鞍】
前輪と後輪に金、銀などの薄板を張り、さらに山形の部分に覆輪(ふくりん)をかけた鞍。
かがみ‐ごい【鏡×鯉】‐ごひ🔗⭐🔉
かがみ‐ごい【鏡×鯉】‐ごひ
ドイツゴイの一品種。うろこは退化しているが、大形のものが背びれとしりびれの付け根や側線に沿って残っている。
かがみじし【鏡獅子】🔗⭐🔉
かがみじし【鏡獅子】
新歌舞伎十八番の一。舞踊劇。長唄。本名題「春興(しゆんきよう)鏡獅子」。福地桜痴作詞、三世杵屋正次郎(きねやしようじろう)作曲、二世藤間勘右衛門・九世市川団十郎振り付け。明治二六年(一八九三)歌舞伎座初演。
かがみ‐せん【鏡銑】🔗⭐🔉
かがみ‐せん【鏡銑】
マンガン一〇〜三五パーセント、炭素四〜五パーセントを含む銑鉄。破面が鏡状であるところからいわれる。転炉での製鋼で脱酸剤として用いる。鏡鉄(きようてつ)。
かがみ‐だい【鏡台】🔗⭐🔉
かがみ‐だい【鏡台】
「鏡立て」に同じ。
かがみ‐だい【鏡×鯛】‐だひ🔗⭐🔉
かがみ‐だい【鏡×鯛】‐だひ
マトウダイ科の海水魚。全長約五〇センチ。体は卵形で側扁が著しく、うろこはない。背びれの棘条(きよくじよう)間の皮膜が糸状に伸びている。体色は青みを帯びた銀白色。南日本に産し、主に練り製品の原料とされる。
かがみ‐たて【鏡立て】🔗⭐🔉
かがみ‐たて【鏡立て】
鏡を立てかける木製の枠、または台。かがみかけ。かがみだい。きょうだい。
かがみつくり‐べ【鏡作△部】🔗⭐🔉
かがみつくり‐べ【鏡作△部】
律令制以前、朝廷や豪族に属して鏡を製作した部民(べみん)。律令制では雑工戸(ざつこうこ)がこれを担当した。
かがみ‐てんじょう【鏡天井】‐テンジヤウ🔗⭐🔉
かがみ‐てんじょう【鏡天井】‐テンジヤウ
(ンジヤウ)格縁(ごうぶち)などをもたず、鏡のように平面に板を張って仕上げた天井。禅宗様建築に多くみられる。
かがみ‐ど【鏡戸】🔗⭐🔉
かがみ‐ど【鏡戸】
枠の中に一枚板をはめ込んだ戸。
かがみ‐とぎ【鏡△磨ぎ】🔗⭐🔉
かがみ‐とぎ【鏡△磨ぎ】
金属性の鏡をみがいて曇りをとり、光沢を出すこと。また、それを職業とする者。
かがみ‐なす【鏡なす】🔗⭐🔉
かがみ‐なす【鏡なす】
〔枕〕 古代の貴重品である鏡のように大切に思うの意から、「思ふ」にかかる。「―我(あ)が思ふ妹(いも)もありといはばこそ」〈万・三二六三〉
古代の貴重品である鏡のように大切に思うの意から、「思ふ」にかかる。「―我(あ)が思ふ妹(いも)もありといはばこそ」〈万・三二六三〉 鏡を見るように見るの意から、「見る」およびそれと同音の「み」を含む地名「み津」にかかる。「―我が見し君を」〈万・一四〇四〉
鏡を見るように見るの意から、「見る」およびそれと同音の「み」を含む地名「み津」にかかる。「―我が見し君を」〈万・一四〇四〉
 古代の貴重品である鏡のように大切に思うの意から、「思ふ」にかかる。「―我(あ)が思ふ妹(いも)もありといはばこそ」〈万・三二六三〉
古代の貴重品である鏡のように大切に思うの意から、「思ふ」にかかる。「―我(あ)が思ふ妹(いも)もありといはばこそ」〈万・三二六三〉 鏡を見るように見るの意から、「見る」およびそれと同音の「み」を含む地名「み津」にかかる。「―我が見し君を」〈万・一四〇四〉
鏡を見るように見るの意から、「見る」およびそれと同音の「み」を含む地名「み津」にかかる。「―我が見し君を」〈万・一四〇四〉
かがみ‐の‐おおきみ【鏡王女】‐おほきみ🔗⭐🔉
かがみ‐の‐おおきみ【鏡王女】‐おほきみ
[?〜六八三]万葉集の女流歌人。舒明(じよめい)天皇の皇女・皇妹とも、鏡王の娘で額田王(ぬかたのおおきみ)の姉ともいわれる。天智天皇に愛され、のち藤原鎌足(ふじわらのかまたり)の妻。鏡女王。鏡姫王。
かがみ‐の‐ま【鏡の間】🔗⭐🔉
かがみ‐の‐ま【鏡の間】
 能舞台で、橋懸かりの奥の揚げ幕のすぐ内にある板敷きの部屋。姿見鏡を置き、役者は登場直前にここで面(おもて)をつけ、気を統一する。
能舞台で、橋懸かりの奥の揚げ幕のすぐ内にある板敷きの部屋。姿見鏡を置き、役者は登場直前にここで面(おもて)をつけ、気を統一する。 江戸時代、歌舞伎舞台で大臣柱と大臣柱の間の本舞台になるところ。
江戸時代、歌舞伎舞台で大臣柱と大臣柱の間の本舞台になるところ。 四方に鏡を張りめぐらしてある部屋。特に、ベルサイユ宮殿のその一室。
四方に鏡を張りめぐらしてある部屋。特に、ベルサイユ宮殿のその一室。
 能舞台で、橋懸かりの奥の揚げ幕のすぐ内にある板敷きの部屋。姿見鏡を置き、役者は登場直前にここで面(おもて)をつけ、気を統一する。
能舞台で、橋懸かりの奥の揚げ幕のすぐ内にある板敷きの部屋。姿見鏡を置き、役者は登場直前にここで面(おもて)をつけ、気を統一する。 江戸時代、歌舞伎舞台で大臣柱と大臣柱の間の本舞台になるところ。
江戸時代、歌舞伎舞台で大臣柱と大臣柱の間の本舞台になるところ。 四方に鏡を張りめぐらしてある部屋。特に、ベルサイユ宮殿のその一室。
四方に鏡を張りめぐらしてある部屋。特に、ベルサイユ宮殿のその一室。
かがみ‐の‐まつ【鏡の松】🔗⭐🔉
かがみ‐の‐まつ【鏡の松】
能舞台で、鏡板(かがみいた)に描かれる老松の絵。奈良春日(かすが)神社の影向(ようごう)の松を写すという。
かがみ‐は【鏡葉】🔗⭐🔉
かがみ‐は【鏡葉】
カシワなどの、表面が広くてつやのある葉。
かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡×匣・鏡×筥】🔗⭐🔉
かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡×匣・鏡×筥】

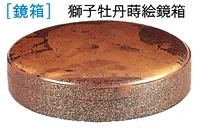 平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。
平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。

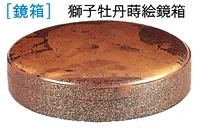 平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。
平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。
かがみ‐はだ【鏡肌】🔗⭐🔉
かがみ‐はだ【鏡肌】
断層面に沿って岩盤がずれ動いたときの摩擦で生じた、鏡のような光沢のある面。
かがみ‐ばり【鏡張り】🔗⭐🔉
かがみ‐ばり【鏡張り】
鏡板 を張ること。また、張ったもの。
を張ること。また、張ったもの。
 を張ること。また、張ったもの。
を張ること。また、張ったもの。
かがみ‐びらき【鏡開き】🔗⭐🔉
かがみ‐びらき【鏡開き】
《「開き」は「割り」の忌み詞》正月一一日(もと二〇日)に鏡餅(かがみもち)を下ろし、雑煮や汁粉にして食べること。武家では、男子は具足に、女子は鏡台に供えた鏡餅を手や槌(つち)で割り砕いた。町家でもこの風習をまねて行うようになった。鏡割り。《季 新年》「伊勢海老の―や具足櫃(ぐそくびつ)/許六」
かがみ‐ぶとん【鏡布団】🔗⭐🔉
かがみ‐ぶとん【鏡布団】
裏布を表の方に折り返して、額縁のように縫い上げた布団。鏡の形に似ているところからいう。
かがみ‐もじ【鏡文字】🔗⭐🔉
かがみ‐もじ【鏡文字】
鏡にうつったように、左右が逆になった文字。
かがみ‐もち【鏡×餅】🔗⭐🔉
かがみ‐もち【鏡×餅】
平たく円形に作った餅。大小二個をひと重ねにし、正月や祝いのとき、神仏に供える。おそなえ。おかがみ。《季 新年》「―暗きところに割れて坐す/三鬼」
かがみ‐もの【鏡物】🔗⭐🔉
かがみ‐もの【鏡物】
書名に「鏡」のつく、和文の歴史物語の総称。「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」など。鏡類。
かがみ‐やま【鏡山】🔗⭐🔉
かがみ‐やま【鏡山】
 滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉
滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉 佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。
佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。 広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
 滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉
滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉 佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。
佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。 広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
かがみ‐わり【鏡割(り)】🔗⭐🔉
かがみ‐わり【鏡割(り)】
「鏡開き」に同じ。《季 新年》
きょう‐えい【鏡映】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐えい【鏡映】キヤウ‐
[名]スル空間内の図形を、ある平面に関して鏡に映すような面対称に移すこと。
きょう‐か【鏡架】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐か【鏡架】キヤウ‐
鏡立て。鏡台。
きょうか‐すいげつ【鏡花水月】キヤウクワ‐🔗⭐🔉
きょうか‐すいげつ【鏡花水月】キヤウクワ‐
鏡に映った花や水に映った月のように、目には見えながら手にとることができないもの。また、言葉では表現できず、ただ心に感知するしかない物事。
きょうかすいげつ‐ほう【鏡花水月法】キヤウクワスイゲツハフ🔗⭐🔉
きょうかすいげつ‐ほう【鏡花水月法】キヤウクワスイゲツハフ
漢文で、直接その物事を説明せずに、はっきりその姿を感じとらせる表現法。
きょう‐けい【鏡径】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐けい【鏡径】キヤウ‐
円形の鏡やレンズの口径。
きょうしんめいち‐りゅう【鏡新明智流】キヤウシンメイチリウ🔗⭐🔉
きょうしんめいち‐りゅう【鏡新明智流】キヤウシンメイチリウ
剣術の一派。安永年間(一七七二〜一七八一)桃井直由(ももいなおよし)が創始。
きょう‐ぞう【鏡像】キヤウザウ🔗⭐🔉
きょう‐ぞう【鏡像】キヤウザウ
 鏡に映る像。一般に、平面に関して対称をなす点や物体の像。
鏡に映る像。一般に、平面に関して対称をなす点や物体の像。 中心O、半径rの球で、その空間にO以外の点Pをとり、その半直線OP上にOP・OQ=r2となる点Qをとったとき、P・Qを相互にその鏡像であるという。→反転
中心O、半径rの球で、その空間にO以外の点Pをとり、その半直線OP上にOP・OQ=r2となる点Qをとったとき、P・Qを相互にその鏡像であるという。→反転
 鏡に映る像。一般に、平面に関して対称をなす点や物体の像。
鏡に映る像。一般に、平面に関して対称をなす点や物体の像。 中心O、半径rの球で、その空間にO以外の点Pをとり、その半直線OP上にOP・OQ=r2となる点Qをとったとき、P・Qを相互にその鏡像であるという。→反転
中心O、半径rの球で、その空間にO以外の点Pをとり、その半直線OP上にOP・OQ=r2となる点Qをとったとき、P・Qを相互にその鏡像であるという。→反転
きょう‐だい【鏡台】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐だい【鏡台】キヤウ‐
鏡を立てる台。多く箱造りで引き出しなどがある。
きょう‐てつ【鏡鉄】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐てつ【鏡鉄】キヤウ‐
 鏡銑(かがみせん)
鏡銑(かがみせん)
 鏡銑(かがみせん)
鏡銑(かがみせん)
きょう‐どう【鏡胴】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐どう【鏡胴】キヤウ‐
望遠鏡・カメラなどで、レンズを支持し、焦点の調節、外光の遮断などをする筒形の胴。
きょう‐どう【鏡銅】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐どう【鏡銅】キヤウ‐
銅三分の二、錫(すず)三分の一からなる青銅合金。古く鏡として利用された。
きょう‐めん【鏡面】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐めん【鏡面】キヤウ‐
鏡やレンズなどの表面。
きょう‐り【鏡裏・鏡×裡】キヤウ‐🔗⭐🔉
きょう‐り【鏡裏・鏡×裡】キヤウ‐
像の映る鏡の中。
鏡🔗⭐🔉
鏡
 [音]ケイ
キョウ
[訓]かがみ
[部首]金
[総画数]19
[コード]区点 2232
JIS 3640
S‐JIS 8BBE
[分類]常用漢字
[難読語]
→かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡匣・鏡筥】
→き‐けい【亀鏡】
→きほう‐きょう【
[音]ケイ
キョウ
[訓]かがみ
[部首]金
[総画数]19
[コード]区点 2232
JIS 3640
S‐JIS 8BBE
[分類]常用漢字
[難読語]
→かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡匣・鏡筥】
→き‐けい【亀鏡】
→きほう‐きょう【 鳳鏡】
→しん‐けい【神鏡】
→つきひ‐がい【月日貝・海鏡】
→ます‐かがみ【真澄鏡・十寸鏡】
→まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】
→むすめひょうばんぜんあくかがみ【処女評判善悪鏡】
→め‐がね【眼鏡】
→らん‐きょう【鸞鏡】
→らん‐けい【鸞鏡】
鳳鏡】
→しん‐けい【神鏡】
→つきひ‐がい【月日貝・海鏡】
→ます‐かがみ【真澄鏡・十寸鏡】
→まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】
→むすめひょうばんぜんあくかがみ【処女評判善悪鏡】
→め‐がね【眼鏡】
→らん‐きょう【鸞鏡】
→らん‐けい【鸞鏡】
 [音]ケイ
キョウ
[訓]かがみ
[部首]金
[総画数]19
[コード]区点 2232
JIS 3640
S‐JIS 8BBE
[分類]常用漢字
[難読語]
→かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡匣・鏡筥】
→き‐けい【亀鏡】
→きほう‐きょう【
[音]ケイ
キョウ
[訓]かがみ
[部首]金
[総画数]19
[コード]区点 2232
JIS 3640
S‐JIS 8BBE
[分類]常用漢字
[難読語]
→かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡匣・鏡筥】
→き‐けい【亀鏡】
→きほう‐きょう【 鳳鏡】
→しん‐けい【神鏡】
→つきひ‐がい【月日貝・海鏡】
→ます‐かがみ【真澄鏡・十寸鏡】
→まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】
→むすめひょうばんぜんあくかがみ【処女評判善悪鏡】
→め‐がね【眼鏡】
→らん‐きょう【鸞鏡】
→らん‐けい【鸞鏡】
鳳鏡】
→しん‐けい【神鏡】
→つきひ‐がい【月日貝・海鏡】
→ます‐かがみ【真澄鏡・十寸鏡】
→まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】
→むすめひょうばんぜんあくかがみ【処女評判善悪鏡】
→め‐がね【眼鏡】
→らん‐きょう【鸞鏡】
→らん‐けい【鸞鏡】
大辞泉に「鏡」で始まるの検索結果 1-52。