複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぜん‐ご【前後】🔗⭐🔉
ぜん‐ご【前後】
①まえとうしろ。さきとあと。物の順序。「―の見境」
②大体そのくらい。あたり。付近。「千円―の品」
③順序が逆になること。「話が―する」
④あいだをおかずに続くこと。「―して訪れる」
⇒ぜんご‐さゆう【前後左右】
⇒ぜんご‐しょう【前後賞】
⇒ぜんご‐ふかく【前後不覚】
⇒前後に暮れる
⇒前後も知らず
⇒前後を失う
⇒前後を忘れる
ぜんご‐さゆう【前後左右】‥イウ🔗⭐🔉
ぜんご‐さゆう【前後左右】‥イウ
前と後と左と右。四方。
⇒ぜん‐ご【前後】
ぜんご‐しょう【前後賞】‥シヤウ🔗⭐🔉
ぜんご‐しょう【前後賞】‥シヤウ
当選番号の前後の番号に与える賞。
⇒ぜん‐ご【前後】
○前後に暮れるぜんごにくれる🔗⭐🔉
○前後に暮れるぜんごにくれる
前後をわきまえないようになる。途方にくれる。浄瑠璃、国性爺合戦「はつとばかり、前後に暮れて立ちたりしが」
⇒ぜん‐ご【前後】
せんご‐は【戦後派】
①(→)アプレゲールに同じ。
②第二次大戦後に育った世代。
⇒せん‐ご【戦後】
せんごは‐ぶんがく【戦後派文学】
第二次大戦後の主要な文学流派。雑誌「近代文学」の同人などを中心に政治と文学、マルクス主義と実存主義、主体性論、世代論等を共通の主題とし、野間宏・中村真一郎・埴谷雄高・梅崎春生・椎名麟三・武田泰淳らの創作活動がその実質を形づくった。
⇒せん‐ご【戦後】
せんごひゃくばんうたあわせ【千五百番歌合】‥アハセ
歌合。20巻。1201年(建仁1)新古今集撰進の院宣に先立ち、後鳥羽上皇が発企して上皇以下30人の歌人がおのおの百首を詠じて千五百番とした最大規模の歌合。判者は上皇以下10名。各様の形式をもって新古今時代の歌論の実際上における適用を示した。
せんこ‐ふえき【千古不易】
永久にかわらないこと。
⇒せん‐こ【千古】
ぜんご‐ふかく【前後不覚】
前後の区別もつかないほど正体のないさま。「―に陥る」
⇒ぜん‐ご【前後】
ぜんこ‐みぞう【前古未曾有】
昔からまだ一度もないこと。古今未曾有。
⇒ぜん‐こ【前古】
ぜんご‐ふかく【前後不覚】🔗⭐🔉
ぜんご‐ふかく【前後不覚】
前後の区別もつかないほど正体のないさま。「―に陥る」
⇒ぜん‐ご【前後】
○前後も知らずぜんごもしらず🔗⭐🔉
○前後も知らずぜんごもしらず
正体がないさまにいう。前後不覚。宇津保物語蔵開中「酒をしひてたびたりつるに、前後も知らでなむ」
⇒ぜん‐ご【前後】
せん‐ごり【川垢離】
神仏に祈願するため、川水にひたって身を清めること。浮世風呂4「湯の中は花火と―がねへばつかりだ」
せん‐ころ【先頃】
さきごろ。
○前後を失うぜんごをうしなう🔗⭐🔉
○前後を失うぜんごをうしなう
①ことの順序をあやまる。前後を失す。
②(→)「前後を忘れる」に同じ。
⇒ぜん‐ご【前後】
○前後を忘れるぜんごをわすれる🔗⭐🔉
○前後を忘れるぜんごをわすれる
①前後の方角もわからなくなる。また、どうすればよいか、処置に苦しむ。途方にくれる。前後を忘ぼうず。謡曲、船弁慶「眼もくらみ心も乱れて、前後を忘ずるばかりなり」
②前後不覚におちいる。
⇒ぜん‐ご【前後】
せん‐こん【剪根】
過度の生育を抑えるため、根の一部をきること。
ぜん‐こん【前根】
脊髄の前外側溝から出る脊髄神経の根幹部。後外側溝から出るものは後根こうこんという。
ぜん‐こん【善根】
〔仏〕
①安楽な果報を招くべき善因。「―を積む」
②諸善を生み出す根本。無貪・無瞋・無痴をいう。
⇒ぜんこん‐しゃ【善根者】
⇒ぜんこん‐やど【善根宿】
ぜんこん‐しゃ【善根者】
善根を積んだ人。
⇒ぜん‐こん【善根】
ぜんこん‐やど【善根宿】
漂泊の信徒または行き暮れた旅行者を宿泊させる無料の施行宿せぎょうやど。
⇒ぜん‐こん【善根】
せん‐ざ【遷座】
天皇または神仏の座を他所へうつすこと。また、うつること。
⇒せんざ‐さい【遷座祭】
ぜん‐さ【善作】
善い行い。よい所行。こんてむつすむん地「―をなして身を卑下する事」
ぜん‐ざ【前座】
①講談・落語などで真打しんうちの前に出演すること。また、その人。「―をつとめる」
②落語家などの格付の最下級。→二つ目→真打
センサー【sensor】
温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子、または装置。さらに検出量を適切な信号に変換して計測系に入力する装置を指す場合もある。検知器。
せん‐さい【先妻・前妻】
後妻に対して、前の妻。もとの妻。前妻ぜんさい。色葉字類抄「前妻、センサイ、コナミ」
せん‐さい【浅才】
あさはかな才。あさぢえ。主に自分について謙遜していう。せんざい。徒然草「異説を好むは、―の人の必ずある事なり」
せん‐さい【剪裁】
①布などを裁ち切ること。
②文章に手を入れて直すこと。文章をねること。
せん‐さい【剪綵】
色糸や絹布などを用いた造花などの細工物。
せん‐さい【戦災】
戦争によって受けた災害。「―にあう」
⇒せんさい‐こじ【戦災孤児】
せん‐さい【戦債】
戦費にあてるために発行する国債。
せん‐さい【繊細】
①かぼそく優美なさま。「―な指」
②ちょっとしたことにも感じやすいこと。デリケート。「―な感覚」
⇒せんさい‐の‐せいしん【繊細の精神】
せん‐さい【鮮菜】
あたらしい野菜。
せん‐ざい【千歳】
①千年。ちとせ。長い年月。今昔物語集4「―の契を期しつれども」
②「式三番しきさんば」参照。
⇒せんざい‐し【千歳紙】
⇒せんざい‐らく【千歳楽】
せん‐ざい【千載】
千年。千歳。長い年月。太平記3「名誉は―に留まつて」
⇒せんざい‐いちぐう【千載一遇】
⇒せんざい‐ふま【千載不磨】
せん‐ざい【前栽】
①庭前の花木・草花の植込み。また、その草木。せざい。伊勢物語「人の―に菊うゑけるに」
②前栽物の略。
⇒せんざい‐あわせ【前栽合】
⇒せんざい‐うり【前栽売】
⇒せんざい‐もの【前栽物】
せん‐ざい【洗剤】
衣服・器物などを洗うために、湯・水にとかして用いるもの。石鹸・合成洗剤の類で、一般に界面活性剤が用いられる。洗浄剤。
せん‐ざい【煎剤】
生薬しょうやくを煎じ出した薬液。
せん‐ざい【銭財】
①ぜにや宝物。
②ぜに。かね。金銭。
せん‐ざい【潜在】
表面に現れず、ひそみかくれていること。↔顕在。
⇒せんざい‐いしき【潜在意識】
⇒せんざい‐しつぎょう【潜在失業】
⇒せんざい‐しゅけん【潜在主権】
⇒せんざい‐じゅよう【潜在需要】
⇒せんざい‐てき【潜在的】
せん‐ざい【線材】
直径5〜9ミリメートルの丸鋼。鋼索・針金などに用いる。
ぜん‐さい【前妻】
(→)先妻せんさいに同じ。
ぜん‐さい【前菜】
食前または酒の肴に食べるつまみもの。オードブル。
ぜん‐さい【前債】
以前の債務。前の借り。
ぜん‐ざい【前罪】
以前に犯した罪。
ぜん‐ざい【善哉】
①善いと感じてほめ、または喜び祝う語。よいかな。謡曲、白髭「明神も御声をあげ、―、―、と感じ給へば」
②関西では、つぶし餡あんの汁粉。関東では、粟餅・道明寺餅・白玉餅などに濃い餡をかけたもの。
⇒ぜんざい‐もち【善哉餅】
せんざい‐あわせ【前栽合】‥アハセ
左右に組を分けて、前栽やそれを詠んだ歌の優劣を競う遊戯。歌合の一形式ともされた。栄華物語くれ待星「中宮には、―菊あはせなどせさせ給ひて」
⇒せん‐ざい【前栽】
せんざい‐いしき【潜在意識】
自覚されないまま潜んでいる意識。二重人格などの場合の分離意識。
⇒せん‐ざい【潜在】
せんざい‐いちぐう【千載一遇】
千年に1回しかあえないようなめったにないこと。「―のチャンス」
⇒せん‐ざい【千載】
せんざい‐うり【前栽売】
前栽物を商う人。やおや。
⇒せん‐ざい【前栽】
せんざいかく【千載佳句】
漢詩。2巻。大江維時編。天暦(947〜957)頃成立。唐の詩人153人の七言詩1083首から2句ずつ抜き出し、部門ごとに分類したもの。「和漢朗詠集」成立の先駆けとなった。
せんさい‐こじ【戦災孤児】
戦災によってみなし児となった子。
⇒せん‐さい【戦災】
せんざい‐し【千歳紙】
若松の葉や牡蠣殻灰かきがらばいを、楮こうぞ皮の紙料に混ぜて漉すいた和紙。襖の下張りに用いる。千年紙。
⇒せん‐ざい【千歳】
せんざい‐しつぎょう【潜在失業】‥ゲフ
統計に現れる失業(顕在失業)に対し、希望する職業につけないで主として農業および都市小商工業などに潜在的な過剰人口の形で存在する失業。→失業→不完全就業。
⇒せん‐ざい【潜在】
せんざいしゅう【千載集】‥シフ
「千載和歌集」の略称。
せんざい‐しゅけん【潜在主権】
外国の統治・支配下にある地域に潜在的に存在する主権。対日講和条約でアメリカの信託統治下に置かれ、同国の施政権はあるが、最終処分権は日本に属するといわれた、かつての沖縄などについていう。残存主権。
⇒せん‐ざい【潜在】
せんざい‐じゅよう【潜在需要】‥エウ
価格が高すぎたり情報が不足したりして現実の消費活動には現れていない需要。
⇒せん‐ざい【潜在】
せんさい‐ちゃ【仙斎茶】
染色の名。黒ずんだ緑。誹風柳多留73「―後の女房が染直し」
Munsell color system: 5GY3/1
せんざい‐てき【潜在的】
外面にははっきり現れず、内面に存在するさま。「―能力」
⇒せん‐ざい【潜在】
ぜんざい‐どうじ【善財童子】
(梵語Sudhana Śreṣṭhi-dāraka)[華厳経入法界品]求道ぐどうの童子で、菩薩の名。福城の長者の子で、文殊菩薩の説法を聞いて発心ほっしんし、53人の善知識を歴訪、最後に普賢菩薩に遇い、その十大願を聞き、法界に入ろうと願うに至った。仏道修行の階梯かいていを示したものとされ、絵画・偈賛に表される。東海道五十三次はこれに因んだものという。
せんさい‐の‐せいしん【繊細の精神】
(esprit de finesse フランス)パスカルの用語。複雑な事象を、論証によらず、直観的・全体的に把握する柔軟性に富む認識能力。↔幾何学的精神
⇒せん‐さい【繊細】
せんざい‐ふま【千載不磨】
千年も消えないこと。いつまでも不朽なこと。
⇒せん‐ざい【千載】
ぜんざい‐もち【善哉餅】
(→)「ぜんざい」2に同じ。
⇒ぜん‐ざい【善哉】
せんざい‐もの【前栽物】
あおもの。野菜。せんざい。
⇒せん‐ざい【前栽】
せんざい‐らく【千歳楽】
(→)千秋楽せんしゅうらく3に同じ。
⇒せん‐ざい【千歳】
ぜんさい‐るい【前鰓類】
軟体動物腹足綱の一亜綱。海産の典型的な巻貝のほとんどがこれに入る。巻いた貝殻の中で体が反転し、体の前方に肛門も鰓えらも位置するため、この名がある。タニシ・カワニナなどの淡水巻貝類のほかに、ヤマタニシなど少数の陸貝もあるが、有肺類の陸貝と異なり角質の蓋ふたがある。→後鰓類→有肺類
せんざいろう
福岡県博多で、正月の子供の行事。祝言を唱えて家々を歩き、銭をもらう。
せんざいわかしゅう【千載和歌集】‥シフ
勅撰和歌集。八代集の一つ。20巻。1183年(寿永2)後白河法皇の院宣により、87年(文治3)藤原俊成(釈阿)撰。一条天皇以後200年間の、後拾遺集に洩れた歌より撰修。温雅妖艶な中に幽寂な境地を表す。千載集。
→文献資料[千載和歌集]
せん‐さき【先先】
先さきの意を強めていう語。狂言、鴈大名「それがしが―ぢや」
せん‐さく【穿鑿】
(センザクとも)
①うがちほること。ほじくり返すこと。
②手を尽くしてたずね求めること。狂言、鱸庖丁「方々と―致いて、淀一番の大鯉を求めましてござる」
③究明すること。どこまでも調べ立てること。天草本伊曾保物語「色々の―の後、板に開かるるなり」
④問題。事項。浮世草子、浮世親仁形気「貸借の―はわきにして」
⑤事の次第。なりゆき。黄表紙、御存商売物「あのいちやつきを見やれ、けたいの悪い―だ」
⇒せんさく‐じょ【穿鑿所】
せん‐さく【詮索】
細かいところまで、調べもとめること。たずねさがすこと。「根掘り葉掘り―する」
ぜん‐さく【前作】
①この前の作品。以前の制作。
②同一地に2種以上の作物を前後して栽培する場合に、前に栽培する作物。サツマイモのあとに、油菜・蚕豆そらまめなどを栽培する時のサツマイモの類。まえさく。↔後作あとさく
せんさく‐じょ【穿鑿所】
罪人を取り調べる所。白洲しらす。
⇒せん‐さく【穿鑿】
せんざ‐さい【遷座祭】
(→)遷宮祭せんぐうさいに同じ。
⇒せん‐ざ【遷座】
センサス【census】
①人口調査。人口国勢調査。
②国勢の種々の側面に対して国が行う統計調査。「工業―」
ぜん‐さつ【禅刹】
①禅宗の寺院。
②寺院。
せんさつ‐きょう【占察経】‥キヤウ
仏書。2巻。中国で撰述された偽経と考えられるが、朝鮮半島において重視され、日本でも地蔵信仰を説く経典として流布。戒律の自誓受戒を認める唯一の経典としても著名。占察善悪業報経。
せんさ‐ばんべつ【千差万別】
種々様々に変わっていること。せんさまんべつ。「人の顔は―」
せん‐さま【先様】
さきに来たお客様。先客。
ぜん‐ざん【全山】
①すべての山。
②山全体。
せんざん‐こう【穿山甲】‥カフ
(中国名から)センザンコウ目(有鱗類)の哺乳類の総称。1科1属7種が現存。体長30〜90センチメートル、体の外側は角質の鱗に覆われ、鱗の色は黒褐色から黄褐色。東南アジアとアフリカに分布。前足に鋭いかぎ爪があり、木に登ることもできる。歯はない。昼は穴に隠れ、夜出て、アリやシロアリを食べる。敵に会えば体を丸めて身を守る。鯪鯉りょうり。ラーリー。石鯉。
せんざんこう
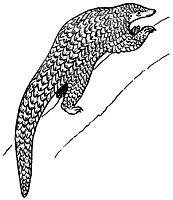 ミミセンザンコウ
提供:東京動物園協会
ミミセンザンコウ
提供:東京動物園協会
 せんざん‐ごりょう【泉山御陵】
京都市東山区の泉涌寺せんにゅうじにある四条天皇・後水尾天皇などの陵。
せんざん‐ばんすい【千山万水】
多くの山と多くの川。山また山、川また川。「―を越えて旅する」
せん‐し【先史】
文字史料の登場に先立つこと。また、その歴史。史前。
⇒せんし‐がく【先史学】
⇒せんし‐こうこがく【先史考古学】
⇒せんし‐じだい【先史時代】
せん‐し【先祀】
先祖のまつり。
せん‐し【先師】
(センジとも)
①死んだ師匠。
②前代の賢人。先賢。
せん‐し【宣示】
人に明らかにしめすこと。広く天下に告げしめすこと。公示。明示。
せん‐し【宣紙】
中国安徽省宣州に産する紙。白く平滑で大判であり、書画に適する。もと青檀せいたんの皮を原料としたが、近年稲藁を混ぜたものが多い。
せん‐し【宣賜】
勅宣によって賜ること。
せん‐し【専使】
ある事のために特に遣わす使者。特使。
せん‐し【専恣・擅恣】
わがまま。ほしいまま。きまま。
せん‐し【穿刺】
血管・体腔・臓器に中空の細い針を刺すこと。胸水・腹水・脳脊髄液を取る場合や治療のため薬物を注入する場合など。
せん‐し【栓子】
〔医〕(→)塞栓そくせんに同じ。
せん‐し【剪枝】
枝をきること。
せん‐し【剪紙】
切り紙細工。切り絵。
せん‐し【戦士】
戦場でたたかう兵士。比喩的にも使う。「企業―」
せん‐し【戦史】
戦争の歴史。
せん‐し【戦死】
戦闘で死ぬこと。うちじに。
せん‐し【撰糸】
羽二重はぶたえに類する薄地の絹織物。
せん‐し【潜思】
心を落ち着けて深く考えること。潜考。
せん‐し【選士】
①選抜された人。
②平安時代、軍団兵士に代わり、大宰府に属し辺境警備に任じた兵士。土豪の子弟から選抜され、統領が指揮した。
せん‐し【遷徙】
(「徙」も、うつる意)うつること。うつすこと。
せん‐し【繊指】
ほそくしなやかな指。美人の指。
せん‐し【瞻視】
(「瞻」も視の意)視ること。見やること。また、その目つき。
せんじ【煎じ】
①せんじ出すこと。「―かす」「―がら」
②鰹節製造の際、鰹を煮る釜の底に沈殿した飴状の汁を漉して煎じつめたエキス。調味料とする。煎汁。煮取り。
⇒せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
⇒せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
⇒せんじ‐もの【煎じ物】
せん‐じ【宣旨】
①古代〜中世、上級者の口頭による命令を受命者が書き記したもの。
②(1が文書化したもの)平安末期以降、天皇の命を伝える公文書。その本来の形である詔勅は発布にきわめて複雑な手続を要したのに対し、宣旨は内侍から蔵人くろうどに、蔵人から太政官の上卿しょうけいに伝え、上卿は少納言または弁官をして外記げきまたは大史に命じて文書に作らせ発行した。
③天皇の口勅を蔵人に伝えた女房。転じて、宮中の女房。後に女官の称。源氏物語槿「―を迎へつつ語らひ給ふ」
⇒せんじ‐がき【宣旨書】
⇒せんじ‐がみ【宣旨紙】
⇒せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】
⇒せんじ‐ます【宣旨升】
せん‐じ【戦事】
戦争に関する事柄。兵事。
せん‐じ【戦時】
戦争の行われている時期。戦争中。「―色を強める」↔平時。
⇒せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
⇒せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
⇒せんじ‐こうさい【戦時公債】
⇒せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】
⇒せんじ‐たいせい【戦時体制】
⇒せんじ‐ひょうじゅん‐せん【戦時標準船】
⇒せんじ‐ふっきゅう【戦時復仇】
⇒せんじ‐へんせい【戦時編制】
⇒せんじ‐ほけん【戦時保険】
せん‐じ【潜時】
(→)潜伏期2に同じ。
ぜん‐し【全市】
①市中全体。
②全部の市。
ぜん‐し【全姿】
全体のすがた。
ぜん‐し【全紙】
①和紙で、漉いたままの大きさの紙。
②洋紙で、A判・B判などの規格判に裁断された紙。全判。
③紙面の全体。
④写真感光材料の大きさの一つ。45.7センチメートル×55.9センチメートル(18インチ×22インチ)の大きさのものに対する慣用名。
⑤すべての新聞。
ぜん‐し【前史】
①当面の対象となっている時代の歴史の起因を説明するために書かれる、それ以前の歴史。「明治維新―」
②歴史以前。先史。
ぜん‐し【前志】
①以前のこころざし。
②昔の書籍または記録。
ぜん‐し【前肢】
①四肢ある動物の前方の二肢。まえあし。
②昆虫の前胸部の付属肢。
ぜん‐し【前翅】
昆虫の翅のうち前部の一対。中胸部につく。甲虫類では上翅ともいう。
ぜん‐し【前歯】
まえば。
ぜん‐じ【全治】‥ヂ
⇒ぜんち
ぜん‐じ【前司】
前任の国司。源氏物語宿木「常陸の―殿の姫君」
ぜん‐じ【前事】
以前にあった事。
⇒前事の忘れざるは後事の師なり
ぜん‐じ【善事】
よいこと。また、めでたいこと。
ぜん‐じ【禅師】
①禅定ぜんじょうに通達した師僧。
②中国・日本で、智徳の高い禅僧に朝廷から賜る称号。「一休―」
③一般に、法師の称。伊勢物語「山科の―のみこおはします」
ぜん‐じ【漸次】
〔副〕
だんだん。次第次第に。「研究は―進展しつつある」
せんじ‐かき【千字書】
江戸時代、習字の練習に1日に千字を書いたこと。冬至または毎月25日に行なった。
せんじ‐がき【宣旨書】
①宣旨の文書。おおせがき。せじがき。
②(宣旨書は代書したから)代書すること。また、その書状。宇津保物語蔵開中「大将見給ひて、あぢきなの―やとひとりごちて」
⇒せん‐じ【宣旨】
せんし‐がく【先史学】
(prehistory)先史時代のことを研究する学問。先史考古学とほぼ同義であるが、より広く人類学などの研究をも含む。史前学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐がみ【宣旨紙】
宣旨を書くための紙。かみやがみ。
⇒せん‐じ【宣旨】
せん‐しき【浅識】
あさはかな知識または識見。日本霊異記中「行基沙弥は―の人にして」
ぜん‐しきもう【全色盲】‥マウ
「色覚異常」参照。
せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
1918〜21年、ロシア革命直後の内戦の中で共産党政府が行なった、農民からの穀物強制徴発などの強力な統制経済。外国の干渉と内戦への危機対策として採用。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
戦時国際法上、敵国に輸送されれば敵国の交戦能力を増加させる可能性あるものとして、一方の交戦国が、中立国から他方の交戦国への輸送を防止し得る貨物。絶対禁制品(兵器・弾薬など)と条件付禁制品との別がある。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
煎じ出して服用する薬。煎剤。
⇒せんじ【煎じ】
せんし‐こうこがく【先史考古学】‥カウ‥
先史時代を遺物・遺跡によって考究する学問。↔歴史考古学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐こうさい【戦時公債】
戦時に、国家が軍事費調達のために発行する公債。軍事公債。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】‥ハフ
戦時における国際間の法律関係の規準を規定した法律の総称。交戦法規と中立法規とに分ける。戦時公法。戦時国際法。
⇒せん‐じ【戦時】
せんし‐じだい【先史時代】
(prehistoric age)考古学上の時代区分の一つ。人類が登場して以来、文献的史料によって歴史が解明できる時代になるまでを指す。日本では主に旧石器時代・縄文時代に当たる。→原史時代
⇒せん‐し【先史】
せんじしょう【撰時抄】‥セウ
日蓮の著書。5巻。1275年(建治1)成る。五綱教判の一つである時じを中心に、法華経への帰依を説いた書。蒙古襲来の危機に関連して書かれた。→日蓮宗
せんじ‐たいせい【戦時体制】
戦争時に、それに対応してしかれる国内体制。
⇒せん‐じ【戦時】
ぜんじだい‐てき【前時代的】
旧態依然として、今の時代に合わないさま。前近代的。「―な思考」
せんじ‐だ・す【煎じ出す】
〔他五〕
茶または薬を煮出す。
せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
煎じ出して飲む茶。
⇒せんじ【煎じ】
せん‐しつ【泉質】
温泉・鉱泉の水の化学的性質。旧来は「食塩泉」のように塩類名を用いたが、現在では「ナトリウム塩化物泉」のように含有する主要イオン名を並べて表現する。
せん‐しつ【船室】
船舶で、乗船客の使用にあてる室。キャビン。
せん‐じつ【先日】
近い過去の或る日。このあいだ。過日。「―は失礼」
せん‐じつ【専日】
暦で、十干と十二支に配する五行ごぎょうが同性となる日。すなわち、戊辰・己丑・戊戌・丙午・壬子・甲寅・乙卯・丁巳・己未・庚申・辛酉・癸亥の12日。→八専
せん‐じつ【選日】
暦注の干支・十二直・二十八宿・六輝などを見て吉日を選ぶこと。また、選ばれた日。
ぜん‐しつ【前失】
以前のあやまち。
ぜん‐しつ【禅室】
①禅を修する室。また、仏道を修する室。
②禅僧の居室。
③禅宗で住持の称。
④出家した貴人の尊敬語。
ぜん‐じつ【全日】
①まる1日。
②すべての日。毎日。
⇒ぜんじつ‐せい【全日制】
ぜん‐じつ【前日】
①当日のすぐ前の日。
②先日。以前のある日。
ぜんじつ‐せい【全日制】
⇒ぜんにちせい
⇒ぜん‐じつ【全日】
せんじ‐つ・める【煎じ詰める】
〔他下一〕[文]せんじつ・む(下二)
①成分が出つくすまで煎じる。
②行きつくところまで論じきわめる。とことんまで考える。「―・めると結局こうなる」
センシティブ【sensitive】
①感じやすいさま。鋭敏なさま。「―な感性」
②慎重に扱われるべきであるさま。「―な問題」
ぜん‐じどう【全自動】
起動すれば、何段階かの作業のすべてを人手をかけず機械が行うこと。「―洗濯機」
センシトメトリー【sensitometry】
(写真用語)感光材料の感度・コントラストなどの性質を測定すること。
せんし‐ないしんのう【選子内親王】‥ワウ
平安中期の歌人。村上天皇の皇女。円融天皇から5代57年の間、賀茂斎院となり、大斎院と称せられた。和歌に精進し、「大斎院前の御集」「大斎院御集」を残す。また仏道への帰依深く、家集「発心和歌集」がある。(964〜1035)
せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】‥ツカヒ
①勅旨を伝える使。枕草子128「―とて斉信の宰相の中将の」
②検非違使けびいしの命令書を持った使。平家物語4「いかに宣旨の御使をばかうはするぞ」
⇒せん‐じ【宣旨】
せんざん‐ごりょう【泉山御陵】
京都市東山区の泉涌寺せんにゅうじにある四条天皇・後水尾天皇などの陵。
せんざん‐ばんすい【千山万水】
多くの山と多くの川。山また山、川また川。「―を越えて旅する」
せん‐し【先史】
文字史料の登場に先立つこと。また、その歴史。史前。
⇒せんし‐がく【先史学】
⇒せんし‐こうこがく【先史考古学】
⇒せんし‐じだい【先史時代】
せん‐し【先祀】
先祖のまつり。
せん‐し【先師】
(センジとも)
①死んだ師匠。
②前代の賢人。先賢。
せん‐し【宣示】
人に明らかにしめすこと。広く天下に告げしめすこと。公示。明示。
せん‐し【宣紙】
中国安徽省宣州に産する紙。白く平滑で大判であり、書画に適する。もと青檀せいたんの皮を原料としたが、近年稲藁を混ぜたものが多い。
せん‐し【宣賜】
勅宣によって賜ること。
せん‐し【専使】
ある事のために特に遣わす使者。特使。
せん‐し【専恣・擅恣】
わがまま。ほしいまま。きまま。
せん‐し【穿刺】
血管・体腔・臓器に中空の細い針を刺すこと。胸水・腹水・脳脊髄液を取る場合や治療のため薬物を注入する場合など。
せん‐し【栓子】
〔医〕(→)塞栓そくせんに同じ。
せん‐し【剪枝】
枝をきること。
せん‐し【剪紙】
切り紙細工。切り絵。
せん‐し【戦士】
戦場でたたかう兵士。比喩的にも使う。「企業―」
せん‐し【戦史】
戦争の歴史。
せん‐し【戦死】
戦闘で死ぬこと。うちじに。
せん‐し【撰糸】
羽二重はぶたえに類する薄地の絹織物。
せん‐し【潜思】
心を落ち着けて深く考えること。潜考。
せん‐し【選士】
①選抜された人。
②平安時代、軍団兵士に代わり、大宰府に属し辺境警備に任じた兵士。土豪の子弟から選抜され、統領が指揮した。
せん‐し【遷徙】
(「徙」も、うつる意)うつること。うつすこと。
せん‐し【繊指】
ほそくしなやかな指。美人の指。
せん‐し【瞻視】
(「瞻」も視の意)視ること。見やること。また、その目つき。
せんじ【煎じ】
①せんじ出すこと。「―かす」「―がら」
②鰹節製造の際、鰹を煮る釜の底に沈殿した飴状の汁を漉して煎じつめたエキス。調味料とする。煎汁。煮取り。
⇒せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
⇒せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
⇒せんじ‐もの【煎じ物】
せん‐じ【宣旨】
①古代〜中世、上級者の口頭による命令を受命者が書き記したもの。
②(1が文書化したもの)平安末期以降、天皇の命を伝える公文書。その本来の形である詔勅は発布にきわめて複雑な手続を要したのに対し、宣旨は内侍から蔵人くろうどに、蔵人から太政官の上卿しょうけいに伝え、上卿は少納言または弁官をして外記げきまたは大史に命じて文書に作らせ発行した。
③天皇の口勅を蔵人に伝えた女房。転じて、宮中の女房。後に女官の称。源氏物語槿「―を迎へつつ語らひ給ふ」
⇒せんじ‐がき【宣旨書】
⇒せんじ‐がみ【宣旨紙】
⇒せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】
⇒せんじ‐ます【宣旨升】
せん‐じ【戦事】
戦争に関する事柄。兵事。
せん‐じ【戦時】
戦争の行われている時期。戦争中。「―色を強める」↔平時。
⇒せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
⇒せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
⇒せんじ‐こうさい【戦時公債】
⇒せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】
⇒せんじ‐たいせい【戦時体制】
⇒せんじ‐ひょうじゅん‐せん【戦時標準船】
⇒せんじ‐ふっきゅう【戦時復仇】
⇒せんじ‐へんせい【戦時編制】
⇒せんじ‐ほけん【戦時保険】
せん‐じ【潜時】
(→)潜伏期2に同じ。
ぜん‐し【全市】
①市中全体。
②全部の市。
ぜん‐し【全姿】
全体のすがた。
ぜん‐し【全紙】
①和紙で、漉いたままの大きさの紙。
②洋紙で、A判・B判などの規格判に裁断された紙。全判。
③紙面の全体。
④写真感光材料の大きさの一つ。45.7センチメートル×55.9センチメートル(18インチ×22インチ)の大きさのものに対する慣用名。
⑤すべての新聞。
ぜん‐し【前史】
①当面の対象となっている時代の歴史の起因を説明するために書かれる、それ以前の歴史。「明治維新―」
②歴史以前。先史。
ぜん‐し【前志】
①以前のこころざし。
②昔の書籍または記録。
ぜん‐し【前肢】
①四肢ある動物の前方の二肢。まえあし。
②昆虫の前胸部の付属肢。
ぜん‐し【前翅】
昆虫の翅のうち前部の一対。中胸部につく。甲虫類では上翅ともいう。
ぜん‐し【前歯】
まえば。
ぜん‐じ【全治】‥ヂ
⇒ぜんち
ぜん‐じ【前司】
前任の国司。源氏物語宿木「常陸の―殿の姫君」
ぜん‐じ【前事】
以前にあった事。
⇒前事の忘れざるは後事の師なり
ぜん‐じ【善事】
よいこと。また、めでたいこと。
ぜん‐じ【禅師】
①禅定ぜんじょうに通達した師僧。
②中国・日本で、智徳の高い禅僧に朝廷から賜る称号。「一休―」
③一般に、法師の称。伊勢物語「山科の―のみこおはします」
ぜん‐じ【漸次】
〔副〕
だんだん。次第次第に。「研究は―進展しつつある」
せんじ‐かき【千字書】
江戸時代、習字の練習に1日に千字を書いたこと。冬至または毎月25日に行なった。
せんじ‐がき【宣旨書】
①宣旨の文書。おおせがき。せじがき。
②(宣旨書は代書したから)代書すること。また、その書状。宇津保物語蔵開中「大将見給ひて、あぢきなの―やとひとりごちて」
⇒せん‐じ【宣旨】
せんし‐がく【先史学】
(prehistory)先史時代のことを研究する学問。先史考古学とほぼ同義であるが、より広く人類学などの研究をも含む。史前学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐がみ【宣旨紙】
宣旨を書くための紙。かみやがみ。
⇒せん‐じ【宣旨】
せん‐しき【浅識】
あさはかな知識または識見。日本霊異記中「行基沙弥は―の人にして」
ぜん‐しきもう【全色盲】‥マウ
「色覚異常」参照。
せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
1918〜21年、ロシア革命直後の内戦の中で共産党政府が行なった、農民からの穀物強制徴発などの強力な統制経済。外国の干渉と内戦への危機対策として採用。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
戦時国際法上、敵国に輸送されれば敵国の交戦能力を増加させる可能性あるものとして、一方の交戦国が、中立国から他方の交戦国への輸送を防止し得る貨物。絶対禁制品(兵器・弾薬など)と条件付禁制品との別がある。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
煎じ出して服用する薬。煎剤。
⇒せんじ【煎じ】
せんし‐こうこがく【先史考古学】‥カウ‥
先史時代を遺物・遺跡によって考究する学問。↔歴史考古学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐こうさい【戦時公債】
戦時に、国家が軍事費調達のために発行する公債。軍事公債。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】‥ハフ
戦時における国際間の法律関係の規準を規定した法律の総称。交戦法規と中立法規とに分ける。戦時公法。戦時国際法。
⇒せん‐じ【戦時】
せんし‐じだい【先史時代】
(prehistoric age)考古学上の時代区分の一つ。人類が登場して以来、文献的史料によって歴史が解明できる時代になるまでを指す。日本では主に旧石器時代・縄文時代に当たる。→原史時代
⇒せん‐し【先史】
せんじしょう【撰時抄】‥セウ
日蓮の著書。5巻。1275年(建治1)成る。五綱教判の一つである時じを中心に、法華経への帰依を説いた書。蒙古襲来の危機に関連して書かれた。→日蓮宗
せんじ‐たいせい【戦時体制】
戦争時に、それに対応してしかれる国内体制。
⇒せん‐じ【戦時】
ぜんじだい‐てき【前時代的】
旧態依然として、今の時代に合わないさま。前近代的。「―な思考」
せんじ‐だ・す【煎じ出す】
〔他五〕
茶または薬を煮出す。
せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
煎じ出して飲む茶。
⇒せんじ【煎じ】
せん‐しつ【泉質】
温泉・鉱泉の水の化学的性質。旧来は「食塩泉」のように塩類名を用いたが、現在では「ナトリウム塩化物泉」のように含有する主要イオン名を並べて表現する。
せん‐しつ【船室】
船舶で、乗船客の使用にあてる室。キャビン。
せん‐じつ【先日】
近い過去の或る日。このあいだ。過日。「―は失礼」
せん‐じつ【専日】
暦で、十干と十二支に配する五行ごぎょうが同性となる日。すなわち、戊辰・己丑・戊戌・丙午・壬子・甲寅・乙卯・丁巳・己未・庚申・辛酉・癸亥の12日。→八専
せん‐じつ【選日】
暦注の干支・十二直・二十八宿・六輝などを見て吉日を選ぶこと。また、選ばれた日。
ぜん‐しつ【前失】
以前のあやまち。
ぜん‐しつ【禅室】
①禅を修する室。また、仏道を修する室。
②禅僧の居室。
③禅宗で住持の称。
④出家した貴人の尊敬語。
ぜん‐じつ【全日】
①まる1日。
②すべての日。毎日。
⇒ぜんじつ‐せい【全日制】
ぜん‐じつ【前日】
①当日のすぐ前の日。
②先日。以前のある日。
ぜんじつ‐せい【全日制】
⇒ぜんにちせい
⇒ぜん‐じつ【全日】
せんじ‐つ・める【煎じ詰める】
〔他下一〕[文]せんじつ・む(下二)
①成分が出つくすまで煎じる。
②行きつくところまで論じきわめる。とことんまで考える。「―・めると結局こうなる」
センシティブ【sensitive】
①感じやすいさま。鋭敏なさま。「―な感性」
②慎重に扱われるべきであるさま。「―な問題」
ぜん‐じどう【全自動】
起動すれば、何段階かの作業のすべてを人手をかけず機械が行うこと。「―洗濯機」
センシトメトリー【sensitometry】
(写真用語)感光材料の感度・コントラストなどの性質を測定すること。
せんし‐ないしんのう【選子内親王】‥ワウ
平安中期の歌人。村上天皇の皇女。円融天皇から5代57年の間、賀茂斎院となり、大斎院と称せられた。和歌に精進し、「大斎院前の御集」「大斎院御集」を残す。また仏道への帰依深く、家集「発心和歌集」がある。(964〜1035)
せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】‥ツカヒ
①勅旨を伝える使。枕草子128「―とて斉信の宰相の中将の」
②検非違使けびいしの命令書を持った使。平家物語4「いかに宣旨の御使をばかうはするぞ」
⇒せん‐じ【宣旨】
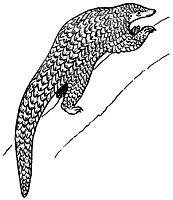 ミミセンザンコウ
提供:東京動物園協会
ミミセンザンコウ
提供:東京動物園協会
 せんざん‐ごりょう【泉山御陵】
京都市東山区の泉涌寺せんにゅうじにある四条天皇・後水尾天皇などの陵。
せんざん‐ばんすい【千山万水】
多くの山と多くの川。山また山、川また川。「―を越えて旅する」
せん‐し【先史】
文字史料の登場に先立つこと。また、その歴史。史前。
⇒せんし‐がく【先史学】
⇒せんし‐こうこがく【先史考古学】
⇒せんし‐じだい【先史時代】
せん‐し【先祀】
先祖のまつり。
せん‐し【先師】
(センジとも)
①死んだ師匠。
②前代の賢人。先賢。
せん‐し【宣示】
人に明らかにしめすこと。広く天下に告げしめすこと。公示。明示。
せん‐し【宣紙】
中国安徽省宣州に産する紙。白く平滑で大判であり、書画に適する。もと青檀せいたんの皮を原料としたが、近年稲藁を混ぜたものが多い。
せん‐し【宣賜】
勅宣によって賜ること。
せん‐し【専使】
ある事のために特に遣わす使者。特使。
せん‐し【専恣・擅恣】
わがまま。ほしいまま。きまま。
せん‐し【穿刺】
血管・体腔・臓器に中空の細い針を刺すこと。胸水・腹水・脳脊髄液を取る場合や治療のため薬物を注入する場合など。
せん‐し【栓子】
〔医〕(→)塞栓そくせんに同じ。
せん‐し【剪枝】
枝をきること。
せん‐し【剪紙】
切り紙細工。切り絵。
せん‐し【戦士】
戦場でたたかう兵士。比喩的にも使う。「企業―」
せん‐し【戦史】
戦争の歴史。
せん‐し【戦死】
戦闘で死ぬこと。うちじに。
せん‐し【撰糸】
羽二重はぶたえに類する薄地の絹織物。
せん‐し【潜思】
心を落ち着けて深く考えること。潜考。
せん‐し【選士】
①選抜された人。
②平安時代、軍団兵士に代わり、大宰府に属し辺境警備に任じた兵士。土豪の子弟から選抜され、統領が指揮した。
せん‐し【遷徙】
(「徙」も、うつる意)うつること。うつすこと。
せん‐し【繊指】
ほそくしなやかな指。美人の指。
せん‐し【瞻視】
(「瞻」も視の意)視ること。見やること。また、その目つき。
せんじ【煎じ】
①せんじ出すこと。「―かす」「―がら」
②鰹節製造の際、鰹を煮る釜の底に沈殿した飴状の汁を漉して煎じつめたエキス。調味料とする。煎汁。煮取り。
⇒せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
⇒せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
⇒せんじ‐もの【煎じ物】
せん‐じ【宣旨】
①古代〜中世、上級者の口頭による命令を受命者が書き記したもの。
②(1が文書化したもの)平安末期以降、天皇の命を伝える公文書。その本来の形である詔勅は発布にきわめて複雑な手続を要したのに対し、宣旨は内侍から蔵人くろうどに、蔵人から太政官の上卿しょうけいに伝え、上卿は少納言または弁官をして外記げきまたは大史に命じて文書に作らせ発行した。
③天皇の口勅を蔵人に伝えた女房。転じて、宮中の女房。後に女官の称。源氏物語槿「―を迎へつつ語らひ給ふ」
⇒せんじ‐がき【宣旨書】
⇒せんじ‐がみ【宣旨紙】
⇒せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】
⇒せんじ‐ます【宣旨升】
せん‐じ【戦事】
戦争に関する事柄。兵事。
せん‐じ【戦時】
戦争の行われている時期。戦争中。「―色を強める」↔平時。
⇒せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
⇒せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
⇒せんじ‐こうさい【戦時公債】
⇒せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】
⇒せんじ‐たいせい【戦時体制】
⇒せんじ‐ひょうじゅん‐せん【戦時標準船】
⇒せんじ‐ふっきゅう【戦時復仇】
⇒せんじ‐へんせい【戦時編制】
⇒せんじ‐ほけん【戦時保険】
せん‐じ【潜時】
(→)潜伏期2に同じ。
ぜん‐し【全市】
①市中全体。
②全部の市。
ぜん‐し【全姿】
全体のすがた。
ぜん‐し【全紙】
①和紙で、漉いたままの大きさの紙。
②洋紙で、A判・B判などの規格判に裁断された紙。全判。
③紙面の全体。
④写真感光材料の大きさの一つ。45.7センチメートル×55.9センチメートル(18インチ×22インチ)の大きさのものに対する慣用名。
⑤すべての新聞。
ぜん‐し【前史】
①当面の対象となっている時代の歴史の起因を説明するために書かれる、それ以前の歴史。「明治維新―」
②歴史以前。先史。
ぜん‐し【前志】
①以前のこころざし。
②昔の書籍または記録。
ぜん‐し【前肢】
①四肢ある動物の前方の二肢。まえあし。
②昆虫の前胸部の付属肢。
ぜん‐し【前翅】
昆虫の翅のうち前部の一対。中胸部につく。甲虫類では上翅ともいう。
ぜん‐し【前歯】
まえば。
ぜん‐じ【全治】‥ヂ
⇒ぜんち
ぜん‐じ【前司】
前任の国司。源氏物語宿木「常陸の―殿の姫君」
ぜん‐じ【前事】
以前にあった事。
⇒前事の忘れざるは後事の師なり
ぜん‐じ【善事】
よいこと。また、めでたいこと。
ぜん‐じ【禅師】
①禅定ぜんじょうに通達した師僧。
②中国・日本で、智徳の高い禅僧に朝廷から賜る称号。「一休―」
③一般に、法師の称。伊勢物語「山科の―のみこおはします」
ぜん‐じ【漸次】
〔副〕
だんだん。次第次第に。「研究は―進展しつつある」
せんじ‐かき【千字書】
江戸時代、習字の練習に1日に千字を書いたこと。冬至または毎月25日に行なった。
せんじ‐がき【宣旨書】
①宣旨の文書。おおせがき。せじがき。
②(宣旨書は代書したから)代書すること。また、その書状。宇津保物語蔵開中「大将見給ひて、あぢきなの―やとひとりごちて」
⇒せん‐じ【宣旨】
せんし‐がく【先史学】
(prehistory)先史時代のことを研究する学問。先史考古学とほぼ同義であるが、より広く人類学などの研究をも含む。史前学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐がみ【宣旨紙】
宣旨を書くための紙。かみやがみ。
⇒せん‐じ【宣旨】
せん‐しき【浅識】
あさはかな知識または識見。日本霊異記中「行基沙弥は―の人にして」
ぜん‐しきもう【全色盲】‥マウ
「色覚異常」参照。
せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
1918〜21年、ロシア革命直後の内戦の中で共産党政府が行なった、農民からの穀物強制徴発などの強力な統制経済。外国の干渉と内戦への危機対策として採用。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
戦時国際法上、敵国に輸送されれば敵国の交戦能力を増加させる可能性あるものとして、一方の交戦国が、中立国から他方の交戦国への輸送を防止し得る貨物。絶対禁制品(兵器・弾薬など)と条件付禁制品との別がある。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
煎じ出して服用する薬。煎剤。
⇒せんじ【煎じ】
せんし‐こうこがく【先史考古学】‥カウ‥
先史時代を遺物・遺跡によって考究する学問。↔歴史考古学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐こうさい【戦時公債】
戦時に、国家が軍事費調達のために発行する公債。軍事公債。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】‥ハフ
戦時における国際間の法律関係の規準を規定した法律の総称。交戦法規と中立法規とに分ける。戦時公法。戦時国際法。
⇒せん‐じ【戦時】
せんし‐じだい【先史時代】
(prehistoric age)考古学上の時代区分の一つ。人類が登場して以来、文献的史料によって歴史が解明できる時代になるまでを指す。日本では主に旧石器時代・縄文時代に当たる。→原史時代
⇒せん‐し【先史】
せんじしょう【撰時抄】‥セウ
日蓮の著書。5巻。1275年(建治1)成る。五綱教判の一つである時じを中心に、法華経への帰依を説いた書。蒙古襲来の危機に関連して書かれた。→日蓮宗
せんじ‐たいせい【戦時体制】
戦争時に、それに対応してしかれる国内体制。
⇒せん‐じ【戦時】
ぜんじだい‐てき【前時代的】
旧態依然として、今の時代に合わないさま。前近代的。「―な思考」
せんじ‐だ・す【煎じ出す】
〔他五〕
茶または薬を煮出す。
せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
煎じ出して飲む茶。
⇒せんじ【煎じ】
せん‐しつ【泉質】
温泉・鉱泉の水の化学的性質。旧来は「食塩泉」のように塩類名を用いたが、現在では「ナトリウム塩化物泉」のように含有する主要イオン名を並べて表現する。
せん‐しつ【船室】
船舶で、乗船客の使用にあてる室。キャビン。
せん‐じつ【先日】
近い過去の或る日。このあいだ。過日。「―は失礼」
せん‐じつ【専日】
暦で、十干と十二支に配する五行ごぎょうが同性となる日。すなわち、戊辰・己丑・戊戌・丙午・壬子・甲寅・乙卯・丁巳・己未・庚申・辛酉・癸亥の12日。→八専
せん‐じつ【選日】
暦注の干支・十二直・二十八宿・六輝などを見て吉日を選ぶこと。また、選ばれた日。
ぜん‐しつ【前失】
以前のあやまち。
ぜん‐しつ【禅室】
①禅を修する室。また、仏道を修する室。
②禅僧の居室。
③禅宗で住持の称。
④出家した貴人の尊敬語。
ぜん‐じつ【全日】
①まる1日。
②すべての日。毎日。
⇒ぜんじつ‐せい【全日制】
ぜん‐じつ【前日】
①当日のすぐ前の日。
②先日。以前のある日。
ぜんじつ‐せい【全日制】
⇒ぜんにちせい
⇒ぜん‐じつ【全日】
せんじ‐つ・める【煎じ詰める】
〔他下一〕[文]せんじつ・む(下二)
①成分が出つくすまで煎じる。
②行きつくところまで論じきわめる。とことんまで考える。「―・めると結局こうなる」
センシティブ【sensitive】
①感じやすいさま。鋭敏なさま。「―な感性」
②慎重に扱われるべきであるさま。「―な問題」
ぜん‐じどう【全自動】
起動すれば、何段階かの作業のすべてを人手をかけず機械が行うこと。「―洗濯機」
センシトメトリー【sensitometry】
(写真用語)感光材料の感度・コントラストなどの性質を測定すること。
せんし‐ないしんのう【選子内親王】‥ワウ
平安中期の歌人。村上天皇の皇女。円融天皇から5代57年の間、賀茂斎院となり、大斎院と称せられた。和歌に精進し、「大斎院前の御集」「大斎院御集」を残す。また仏道への帰依深く、家集「発心和歌集」がある。(964〜1035)
せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】‥ツカヒ
①勅旨を伝える使。枕草子128「―とて斉信の宰相の中将の」
②検非違使けびいしの命令書を持った使。平家物語4「いかに宣旨の御使をばかうはするぞ」
⇒せん‐じ【宣旨】
せんざん‐ごりょう【泉山御陵】
京都市東山区の泉涌寺せんにゅうじにある四条天皇・後水尾天皇などの陵。
せんざん‐ばんすい【千山万水】
多くの山と多くの川。山また山、川また川。「―を越えて旅する」
せん‐し【先史】
文字史料の登場に先立つこと。また、その歴史。史前。
⇒せんし‐がく【先史学】
⇒せんし‐こうこがく【先史考古学】
⇒せんし‐じだい【先史時代】
せん‐し【先祀】
先祖のまつり。
せん‐し【先師】
(センジとも)
①死んだ師匠。
②前代の賢人。先賢。
せん‐し【宣示】
人に明らかにしめすこと。広く天下に告げしめすこと。公示。明示。
せん‐し【宣紙】
中国安徽省宣州に産する紙。白く平滑で大判であり、書画に適する。もと青檀せいたんの皮を原料としたが、近年稲藁を混ぜたものが多い。
せん‐し【宣賜】
勅宣によって賜ること。
せん‐し【専使】
ある事のために特に遣わす使者。特使。
せん‐し【専恣・擅恣】
わがまま。ほしいまま。きまま。
せん‐し【穿刺】
血管・体腔・臓器に中空の細い針を刺すこと。胸水・腹水・脳脊髄液を取る場合や治療のため薬物を注入する場合など。
せん‐し【栓子】
〔医〕(→)塞栓そくせんに同じ。
せん‐し【剪枝】
枝をきること。
せん‐し【剪紙】
切り紙細工。切り絵。
せん‐し【戦士】
戦場でたたかう兵士。比喩的にも使う。「企業―」
せん‐し【戦史】
戦争の歴史。
せん‐し【戦死】
戦闘で死ぬこと。うちじに。
せん‐し【撰糸】
羽二重はぶたえに類する薄地の絹織物。
せん‐し【潜思】
心を落ち着けて深く考えること。潜考。
せん‐し【選士】
①選抜された人。
②平安時代、軍団兵士に代わり、大宰府に属し辺境警備に任じた兵士。土豪の子弟から選抜され、統領が指揮した。
せん‐し【遷徙】
(「徙」も、うつる意)うつること。うつすこと。
せん‐し【繊指】
ほそくしなやかな指。美人の指。
せん‐し【瞻視】
(「瞻」も視の意)視ること。見やること。また、その目つき。
せんじ【煎じ】
①せんじ出すこと。「―かす」「―がら」
②鰹節製造の際、鰹を煮る釜の底に沈殿した飴状の汁を漉して煎じつめたエキス。調味料とする。煎汁。煮取り。
⇒せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
⇒せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
⇒せんじ‐もの【煎じ物】
せん‐じ【宣旨】
①古代〜中世、上級者の口頭による命令を受命者が書き記したもの。
②(1が文書化したもの)平安末期以降、天皇の命を伝える公文書。その本来の形である詔勅は発布にきわめて複雑な手続を要したのに対し、宣旨は内侍から蔵人くろうどに、蔵人から太政官の上卿しょうけいに伝え、上卿は少納言または弁官をして外記げきまたは大史に命じて文書に作らせ発行した。
③天皇の口勅を蔵人に伝えた女房。転じて、宮中の女房。後に女官の称。源氏物語槿「―を迎へつつ語らひ給ふ」
⇒せんじ‐がき【宣旨書】
⇒せんじ‐がみ【宣旨紙】
⇒せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】
⇒せんじ‐ます【宣旨升】
せん‐じ【戦事】
戦争に関する事柄。兵事。
せん‐じ【戦時】
戦争の行われている時期。戦争中。「―色を強める」↔平時。
⇒せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
⇒せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
⇒せんじ‐こうさい【戦時公債】
⇒せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】
⇒せんじ‐たいせい【戦時体制】
⇒せんじ‐ひょうじゅん‐せん【戦時標準船】
⇒せんじ‐ふっきゅう【戦時復仇】
⇒せんじ‐へんせい【戦時編制】
⇒せんじ‐ほけん【戦時保険】
せん‐じ【潜時】
(→)潜伏期2に同じ。
ぜん‐し【全市】
①市中全体。
②全部の市。
ぜん‐し【全姿】
全体のすがた。
ぜん‐し【全紙】
①和紙で、漉いたままの大きさの紙。
②洋紙で、A判・B判などの規格判に裁断された紙。全判。
③紙面の全体。
④写真感光材料の大きさの一つ。45.7センチメートル×55.9センチメートル(18インチ×22インチ)の大きさのものに対する慣用名。
⑤すべての新聞。
ぜん‐し【前史】
①当面の対象となっている時代の歴史の起因を説明するために書かれる、それ以前の歴史。「明治維新―」
②歴史以前。先史。
ぜん‐し【前志】
①以前のこころざし。
②昔の書籍または記録。
ぜん‐し【前肢】
①四肢ある動物の前方の二肢。まえあし。
②昆虫の前胸部の付属肢。
ぜん‐し【前翅】
昆虫の翅のうち前部の一対。中胸部につく。甲虫類では上翅ともいう。
ぜん‐し【前歯】
まえば。
ぜん‐じ【全治】‥ヂ
⇒ぜんち
ぜん‐じ【前司】
前任の国司。源氏物語宿木「常陸の―殿の姫君」
ぜん‐じ【前事】
以前にあった事。
⇒前事の忘れざるは後事の師なり
ぜん‐じ【善事】
よいこと。また、めでたいこと。
ぜん‐じ【禅師】
①禅定ぜんじょうに通達した師僧。
②中国・日本で、智徳の高い禅僧に朝廷から賜る称号。「一休―」
③一般に、法師の称。伊勢物語「山科の―のみこおはします」
ぜん‐じ【漸次】
〔副〕
だんだん。次第次第に。「研究は―進展しつつある」
せんじ‐かき【千字書】
江戸時代、習字の練習に1日に千字を書いたこと。冬至または毎月25日に行なった。
せんじ‐がき【宣旨書】
①宣旨の文書。おおせがき。せじがき。
②(宣旨書は代書したから)代書すること。また、その書状。宇津保物語蔵開中「大将見給ひて、あぢきなの―やとひとりごちて」
⇒せん‐じ【宣旨】
せんし‐がく【先史学】
(prehistory)先史時代のことを研究する学問。先史考古学とほぼ同義であるが、より広く人類学などの研究をも含む。史前学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐がみ【宣旨紙】
宣旨を書くための紙。かみやがみ。
⇒せん‐じ【宣旨】
せん‐しき【浅識】
あさはかな知識または識見。日本霊異記中「行基沙弥は―の人にして」
ぜん‐しきもう【全色盲】‥マウ
「色覚異常」参照。
せんじ‐きょうさんしゅぎ【戦時共産主義】
1918〜21年、ロシア革命直後の内戦の中で共産党政府が行なった、農民からの穀物強制徴発などの強力な統制経済。外国の干渉と内戦への危機対策として採用。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐きんせいひん【戦時禁制品】
戦時国際法上、敵国に輸送されれば敵国の交戦能力を増加させる可能性あるものとして、一方の交戦国が、中立国から他方の交戦国への輸送を防止し得る貨物。絶対禁制品(兵器・弾薬など)と条件付禁制品との別がある。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐ぐすり【煎じ薬】
煎じ出して服用する薬。煎剤。
⇒せんじ【煎じ】
せんし‐こうこがく【先史考古学】‥カウ‥
先史時代を遺物・遺跡によって考究する学問。↔歴史考古学。
⇒せん‐し【先史】
せんじ‐こうさい【戦時公債】
戦時に、国家が軍事費調達のために発行する公債。軍事公債。
⇒せん‐じ【戦時】
せんじ‐こくさいこうほう【戦時国際公法】‥ハフ
戦時における国際間の法律関係の規準を規定した法律の総称。交戦法規と中立法規とに分ける。戦時公法。戦時国際法。
⇒せん‐じ【戦時】
せんし‐じだい【先史時代】
(prehistoric age)考古学上の時代区分の一つ。人類が登場して以来、文献的史料によって歴史が解明できる時代になるまでを指す。日本では主に旧石器時代・縄文時代に当たる。→原史時代
⇒せん‐し【先史】
せんじしょう【撰時抄】‥セウ
日蓮の著書。5巻。1275年(建治1)成る。五綱教判の一つである時じを中心に、法華経への帰依を説いた書。蒙古襲来の危機に関連して書かれた。→日蓮宗
せんじ‐たいせい【戦時体制】
戦争時に、それに対応してしかれる国内体制。
⇒せん‐じ【戦時】
ぜんじだい‐てき【前時代的】
旧態依然として、今の時代に合わないさま。前近代的。「―な思考」
せんじ‐だ・す【煎じ出す】
〔他五〕
茶または薬を煮出す。
せんじ‐ちゃ【煎じ茶】
煎じ出して飲む茶。
⇒せんじ【煎じ】
せん‐しつ【泉質】
温泉・鉱泉の水の化学的性質。旧来は「食塩泉」のように塩類名を用いたが、現在では「ナトリウム塩化物泉」のように含有する主要イオン名を並べて表現する。
せん‐しつ【船室】
船舶で、乗船客の使用にあてる室。キャビン。
せん‐じつ【先日】
近い過去の或る日。このあいだ。過日。「―は失礼」
せん‐じつ【専日】
暦で、十干と十二支に配する五行ごぎょうが同性となる日。すなわち、戊辰・己丑・戊戌・丙午・壬子・甲寅・乙卯・丁巳・己未・庚申・辛酉・癸亥の12日。→八専
せん‐じつ【選日】
暦注の干支・十二直・二十八宿・六輝などを見て吉日を選ぶこと。また、選ばれた日。
ぜん‐しつ【前失】
以前のあやまち。
ぜん‐しつ【禅室】
①禅を修する室。また、仏道を修する室。
②禅僧の居室。
③禅宗で住持の称。
④出家した貴人の尊敬語。
ぜん‐じつ【全日】
①まる1日。
②すべての日。毎日。
⇒ぜんじつ‐せい【全日制】
ぜん‐じつ【前日】
①当日のすぐ前の日。
②先日。以前のある日。
ぜんじつ‐せい【全日制】
⇒ぜんにちせい
⇒ぜん‐じつ【全日】
せんじ‐つ・める【煎じ詰める】
〔他下一〕[文]せんじつ・む(下二)
①成分が出つくすまで煎じる。
②行きつくところまで論じきわめる。とことんまで考える。「―・めると結局こうなる」
センシティブ【sensitive】
①感じやすいさま。鋭敏なさま。「―な感性」
②慎重に扱われるべきであるさま。「―な問題」
ぜん‐じどう【全自動】
起動すれば、何段階かの作業のすべてを人手をかけず機械が行うこと。「―洗濯機」
センシトメトリー【sensitometry】
(写真用語)感光材料の感度・コントラストなどの性質を測定すること。
せんし‐ないしんのう【選子内親王】‥ワウ
平安中期の歌人。村上天皇の皇女。円融天皇から5代57年の間、賀茂斎院となり、大斎院と称せられた。和歌に精進し、「大斎院前の御集」「大斎院御集」を残す。また仏道への帰依深く、家集「発心和歌集」がある。(964〜1035)
せんじ‐の‐つかい【宣旨の使】‥ツカヒ
①勅旨を伝える使。枕草子128「―とて斉信の宰相の中将の」
②検非違使けびいしの命令書を持った使。平家物語4「いかに宣旨の御使をばかうはするぞ」
⇒せん‐じ【宣旨】
まえ‐うしろ【前後ろ】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐うしろ【前後ろ】マヘ‥
①まえとうしろ。あとさき。ぜんご。
②衣服などの、前後の位置があべこべになっていること。うしろまえ。
まえ‐しりえ【前後】マヘシリヘ🔗⭐🔉
まえ‐しりえ【前後】マヘシリヘ
前方と後方。ぜんご。源氏物語絵合「上の女房―とさうぞきわけたり」
広辞苑に「前後」で始まるの検索結果 1-10。