複数辞典一括検索+![]()
![]()
址 あと🔗⭐🔉
墟 あと🔗⭐🔉
【墟】
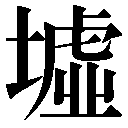 15画 土部
区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0
《音読み》 キョ
15画 土部
区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 あと
《意味》
〉
《訓読み》 あと
《意味》
 {名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」
{名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」
 {名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」
{名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」
 {名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。
《解字》
会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。
《単語家族》
虚(何もないくぼみ→むなしい)
{名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。
《解字》
会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。
《単語家族》
虚(何もないくぼみ→むなしい) 去(へこむ)
去(へこむ) 却(くぼむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
却(くぼむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
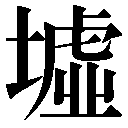 15画 土部
区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0
《音読み》 キョ
15画 土部
区点=5250 16進=5452 シフトJIS=9AD0
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 あと
《意味》
〉
《訓読み》 あと
《意味》
 {名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」
{名}あと。昔あったものが朽ち果てて、くぼみだけが残った所。「廃墟」「殷墟インキョ(三千年前に殷の都のあったあと。今の河南省安陽県にある)」
 {名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」
{名}山頂の中央部がくぼんだ大きな丘。「崑崙墟コンロンキョ」
 {名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。
《解字》
会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。
《単語家族》
虚(何もないくぼみ→むなしい)
{名}中国の中部・南部で、市のたつ小さな町のこと。▽町の名につけて「…墟」と呼ぶ。北部では「…集」という。
《解字》
会意兼形声。虚キョは「くぼみ+音符虍コ」の形声文字。墟は「土+音符虚(くぼみ)」で、地上に残った廃墟。
《単語家族》
虚(何もないくぼみ→むなしい) 去(へこむ)
去(へこむ) 却(くぼむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
却(くぼむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
後 あと🔗⭐🔉
【後】
 9画 彳部 [二年]
区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3
《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち
《音読み》 ゴ
9画 彳部 [二年]
区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3
《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち
《音読み》 ゴ /コウ
/コウ /グ
/グ 〈h
〈h u〉
《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)
《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち
《意味》
u〉
《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)
《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち
《意味》
 {名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」
{名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」
 {名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕
{名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕
 {形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕
{形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕
 {名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕
{名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕
 {動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕
{動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕
 {動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕
《解字》
{動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕
《解字》
 会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。
《異字同訓》
あと。 →跡 おくれる。→遅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。
《異字同訓》
あと。 →跡 おくれる。→遅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 9画 彳部 [二年]
区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3
《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち
《音読み》 ゴ
9画 彳部 [二年]
区点=2469 16進=3865 シフトJIS=8CE3
《常用音訓》コウ/ゴ/あと/うし…ろ/おく…れる/のち
《音読み》 ゴ /コウ
/コウ /グ
/グ 〈h
〈h u〉
《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)
《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち
《意味》
u〉
《訓読み》 のち/あと/うしろ/しりえ(しりへ)/あとにする(あとにす)/のちにする(のちにす)/おくれる(おくる)
《名付け》 しつ・ちか・のち・のり・もち
《意味》
 {名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」
{名}のち。あと。ある起点よりみて、あとの方。▽場所についても、時間についても用いる。〈対語〉→前・→先。「事後」「落人後=人後ニ落ツ」
 {名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕
{名}うしろ。しりえ(シリヘ)。しり。▽もと、人体後部のしりの穴のこと。〈同義語〉→后ゴ/コウ。「是夕也、恵王之後而蛭出=コノ夕ニ、恵王ノ後ヨリ蛭出ヅ」〔→新書〕
 {形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕
{形}のち。あと。のちの。あとの。〈対語〉→先・→初・→前。「後世」「後生」「後必有災=後必ズ災アリ」〔→孟子〕
 {名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕
{名}のち。あと。あとつぎの人。また、子孫。〈対語〉→先(祖先)。「三代之後(三王朝の子孫)」「其無後乎=ソレ後ナカランカ」〔→孟子〕
 {動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕
{動}あとにする(アトニス)。のちにする(ノチニス)。あと回しにする。「絵事後素=絵事ハ、素ヲ後ニス」〔→論語〕
 {動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕
《解字》
{動}おくれる(オクル)。あとになる。〈類義語〉→遅。「非敢後也=アヘテ後レシニアラザルナリ」〔→論語〕
《解字》
 会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。
《異字同訓》
あと。 →跡 おくれる。→遅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
会意。「幺(わずか)+夂(あしをひきずる)+彳(いく)」で、足をひいてわずかしか進めず、あとにおくれるさまをあらわす。のち、后コウ・ゴ(うしろ、しりの穴)と通じて用いられる。
《異字同訓》
あと。 →跡 おくれる。→遅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
後月 アトゲツ🔗⭐🔉
【後月】
 コウゲツ
コウゲツ  翌月。来月。
翌月。来月。 〔俗〕来々月。
〔俗〕来々月。 アトゲツ〔国〕前の月。先月。
アトゲツ〔国〕前の月。先月。 ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。
ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。
 コウゲツ
コウゲツ  翌月。来月。
翌月。来月。 〔俗〕来々月。
〔俗〕来々月。 アトゲツ〔国〕前の月。先月。
アトゲツ〔国〕前の月。先月。 ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。
ノチノツキ〔国〕陰暦八月十五日の月(中秋の名月)に対して、九月十三日の月。十三夜。
斂迹 アトヲオサム🔗⭐🔉
【斂迹】
レンセキ・アトヲオサム 挙動を引きしめてつつしむ。
痕 あと🔗⭐🔉
瘢 あと🔗⭐🔉
趾 あと🔗⭐🔉
【趾】
 11画 足部
区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4
《音読み》 シ
11画 足部
区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 あし/あと
《意味》
〉
《訓読み》 あし/あと
《意味》
 {名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕
{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕
 {名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」
《解字》
会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。
《類義》
→足
《熟語》
→下付・中付語
{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」
《解字》
会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。
《類義》
→足
《熟語》
→下付・中付語
 11画 足部
区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4
《音読み》 シ
11画 足部
区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 あし/あと
《意味》
〉
《訓読み》 あし/あと
《意味》
 {名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕
{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕
 {名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」
《解字》
会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。
《類義》
→足
《熟語》
→下付・中付語
{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」
《解字》
会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。
《類義》
→足
《熟語》
→下付・中付語
跡 あと🔗⭐🔉
【跡】
 13画 足部 [常用漢字]
区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5
《常用音訓》セキ/あと
《音読み》 セキ
13画 足部 [常用漢字]
区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5
《常用音訓》セキ/あと
《音読み》 セキ /シヤク
/シヤク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 あと
《名付け》 あと・ただ・と・みち
《意味》
〉
《訓読み》 あと
《名付け》 あと・ただ・と・みち
《意味》
 {名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」
{名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」
 {名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」
《解字》
会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。
《類義》
痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。
《異字同訓》
あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【迹】を見よ。
{名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」
《解字》
会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。
《類義》
痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。
《異字同訓》
あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【迹】を見よ。
 13画 足部 [常用漢字]
区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5
《常用音訓》セキ/あと
《音読み》 セキ
13画 足部 [常用漢字]
区点=3255 16進=4057 シフトJIS=90D5
《常用音訓》セキ/あと
《音読み》 セキ /シヤク
/シヤク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 あと
《名付け》 あと・ただ・と・みち
《意味》
〉
《訓読み》 あと
《名付け》 あと・ただ・と・みち
《意味》
 {名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」
{名}あと。次々と、同じ間をおいて点々と続く歩いたあと。転じて、足あと。〈同義語〉→迹セキ・→蹟セキ。「足跡」「踪跡ソウセキ(たてに長く続く足あと→ゆくえ)」
 {名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」
《解字》
会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。
《類義》
痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。
《異字同訓》
あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【迹】を見よ。
{名}あと。物があったあと。また、物事が行われたあと。〈同義語〉→蹟・→迹。「筆跡(=筆蹟)」
《解字》
会意。亦は、胸幅の間をおいて、両わきにあるわきの下を示す指事文字。腋エキの原字。跡は「足+亦」で、次々と間隔をおいて同じ形の続く足あと。
《類義》
痕コンは、根を残す傷あと。蹤ショウは、縦に細長く続く足あと。址シは建造物の土台が残ったもの。
《異字同訓》
あと。 跡「足の跡。苦心の跡が見える。容疑者の跡を追う。跡目を継ぐ」後「後の祭り。後を頼んで行く。後から行く。後になり先になり」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【迹】を見よ。
蹤 あと🔗⭐🔉
蹟 あと🔗⭐🔉
躅 あと🔗⭐🔉
迹 あと🔗⭐🔉
不践迹 アトヲフマズ🔗⭐🔉
【不践迹】
アトヲフマズ〈故事〉先人のやり方に従わず、全く自分独自のやり方で事を行う。〔→論語〕
阿堵 アト🔗⭐🔉
【阿堵】
アト  晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。
晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。 〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。
〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。 =阿睹。ひとみ。眼。
=阿睹。ひとみ。眼。
 晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。
晋シン代の代名詞。これ。この。このもの。 〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。
〈故事〉銭のこと。『阿堵物アトブツ』▽晋の王衍オウエンが銭ということばをきらって「このもの」といった故事から。 =阿睹。ひとみ。眼。
=阿睹。ひとみ。眼。
漢字源に「あと」で始まるの検索結果 1-17。
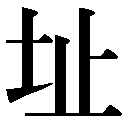 7画 土部
区点=5214 16進=542E シフトJIS=9AAC
【阯】異体字異体字
7画 土部
区点=5214 16進=542E シフトJIS=9AAC
【阯】異体字異体字
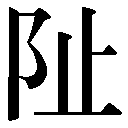 7画 阜部
区点=7987 16進=6F77 シフトJIS=E897
《音読み》 シ
7画 阜部
区点=7987 16進=6F77 シフトJIS=E897
《音読み》 シ 11画
11画  部
区点=2615 16進=3A2F シフトJIS=8DAD
《音読み》 コン
部
区点=2615 16進=3A2F シフトJIS=8DAD
《音読み》 コン n〉
《訓読み》 あと
《意味》
n〉
《訓読み》 あと
《意味》
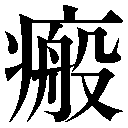 15画
15画  n〉
《訓読み》 あと
《意味》
n〉
《訓読み》 あと
《意味》
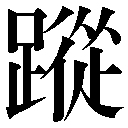 18画 足部
区点=7707 16進=6D27 シフトJIS=E746
《音読み》 ショウ
18画 足部
区点=7707 16進=6D27 シフトJIS=E746
《音読み》 ショウ ng〉
《訓読み》 あと/はなつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 あと/はなつ
《意味》
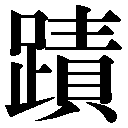 18画 足部
区点=3256 16進=4058 シフトJIS=90D6
《音読み》 セキ
18画 足部
区点=3256 16進=4058 シフトJIS=90D6
《音読み》 セキ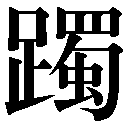 20画 足部
区点=7717 16進=6D31 シフトJIS=E750
《音読み》
20画 足部
区点=7717 16進=6D31 シフトJIS=E750
《音読み》  〉/
〉/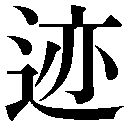 10画
10画  部
区点=7781 16進=6D71 シフトJIS=E791
《音読み》 セキ
部
区点=7781 16進=6D71 シフトJIS=E791
《音読み》 セキ