複数辞典一括検索+![]()
![]()
以 ゆえ🔗⭐🔉
【以】
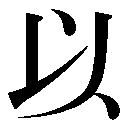 5画 人部 [四年]
区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8
《常用音訓》イ
《音読み》 イ
5画 人部 [四年]
区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8
《常用音訓》イ
《音読み》 イ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より
《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より
《意味》
〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より
《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より
《意味》
 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕
ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕
 {動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕
{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕
 {前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕
{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕
 {前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕
{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕
 {接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕
{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕
 {動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用
{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用 ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕
ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕
 {動}ひきいる(ヒキ
{動}ひきいる(ヒキ ル)。〈類義語〉→率・→将。
ル)。〈類義語〉→率・→将。
 {名}ゆえ(ユ
{名}ゆえ(ユ )。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕
)。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕
 {前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」
《解字》
{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」
《解字》
 会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
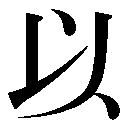 5画 人部 [四年]
区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8
《常用音訓》イ
《音読み》 イ
5画 人部 [四年]
区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8
《常用音訓》イ
《音読み》 イ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より
《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より
《意味》
〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より
《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より
《意味》
 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕
ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕
 {動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕
{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕
 {前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕
{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕
 {前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕
{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕
 {接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕
{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕
 {動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用
{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用 ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕
ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕
 {動}ひきいる(ヒキ
{動}ひきいる(ヒキ ル)。〈類義語〉→率・→将。
ル)。〈類義語〉→率・→将。
 {名}ゆえ(ユ
{名}ゆえ(ユ )。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕
)。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕
 {前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」
《解字》
{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」
《解字》
 会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
兪蔭甫 ユエツ🔗⭐🔉
【兪蔭甫】
ユインホ・ユエツ〈人名〉[エツ]は本名。1821〜1906 清シン代の考証学者。浙江セッコウ省徳清県の人。蔭甫は字アザナ、号は曲園。著に『春在堂全書』がある。
愉悦 ユエツ🔗⭐🔉
【愉楽】
ユラク なんのしこりもなくたのしむ。また、たのしみ。『愉悦ユエツ』
故 ゆえ🔗⭐🔉
【故】
 9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ
9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ /ク
/ク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
 {名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
 {形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
 {名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
 {名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
 {名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
 {動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
 {名}ゆえ(ユ
{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
 {接続}ゆえに(ユ
{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
 「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
 {副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい)
{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ
9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ /ク
/ク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
 {名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
 {形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
 {名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
 {名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
 {名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
 {動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
 {名}ゆえ(ユ
{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
 {接続}ゆえに(ユ
{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
 「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
 {副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい)
{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
由縁 ユエン🔗⭐🔉
【由縁】
ユエン  事物の由来。わけ。
事物の由来。わけ。 手がかり。方法。
手がかり。方法。
 事物の由来。わけ。
事物の由来。わけ。 手がかり。方法。
手がかり。方法。
肆 ゆえに🔗⭐🔉
【肆】
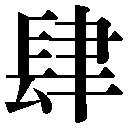 13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
 {動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
 {名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
 「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
 シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
 シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
 {助}ゆえに(ユ
{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
 {数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
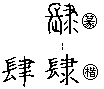 会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
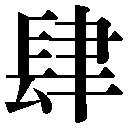 13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
 {動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
 {名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
 「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
 シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
 シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
 {助}ゆえに(ユ
{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
 {数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
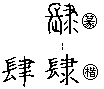 会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
諛悦 ユエツ🔗⭐🔉
【諛悦】
ユエツ 人に気に入られようとしてこびへつらう。こびへつらって喜ばせる。
輸贏 ユエイ🔗⭐🔉
【輸贏】
ユエイ・シュエイ まけることと勝つこと。勝敗。
漢字源に「ユエ」で始まるの検索結果 1-9。