複数辞典一括検索+![]()
![]()
墨🔗⭐🔉
【墨】
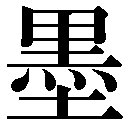 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 土部 [常用漢字]
区点=4347 16進=4B4F シフトJIS=966E
《常用音訓》ボク/すみ
《音読み》 ボク
14画 土部 [常用漢字]
区点=4347 16進=4B4F シフトJIS=966E
《常用音訓》ボク/すみ
《音読み》 ボク /モク
/モク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 すみ/くろい(くろし)
《名付け》 すみ
《意味》
〉
《訓読み》 すみ/くろい(くろし)
《名付け》 すみ
《意味》
 {名}すみ。毛筆で文字を書くのに用いるくろい液。また、すずりですってこの液をつくるために用いるくろいかたまり。松根やなたねなどの油をくすべ、そのすすを固めてつくる。
{名}すみ。毛筆で文字を書くのに用いるくろい液。また、すずりですってこの液をつくるために用いるくろいかたまり。松根やなたねなどの油をくすべ、そのすすを固めてつくる。
 {名}すみで書いた物。「芳墨」
{名}すみで書いた物。「芳墨」
 {名}すみのように、物を書くのに使う物。「石墨」「白墨」
{名}すみのように、物を書くのに使う物。「石墨」「白墨」
 {形}くろい(クロシ)。「面深墨=面、深墨ナリ」〔→孟子〕
{形}くろい(クロシ)。「面深墨=面、深墨ナリ」〔→孟子〕
 {名}入れ墨。「墨刑」
{名}入れ墨。「墨刑」
 {名}なわや、ひもにすみをつけて、材木の上に張り、ぴんとはねて直線を引く大工道具。すみなわ。「縄墨ジョウボク」
{名}なわや、ひもにすみをつけて、材木の上に張り、ぴんとはねて直線を引く大工道具。すみなわ。「縄墨ジョウボク」
 {単位}周代の、長さの単位。一墨は、五尺(一尺は二二・五センチメートル)。
{単位}周代の、長さの単位。一墨は、五尺(一尺は二二・五センチメートル)。
 {名}墨子ボクシのこと。また、その学派。「楊墨ヨウボク(楊朱と墨子)」「天下之言、不帰楊、則帰墨=天下ノ言、楊ニ帰セザレバ、スナハチ墨ニ帰ス」〔→孟子〕
〔国〕隅田川のこと。▽墨田川とも書いたことから。「墨堤」
《解字》
会意兼形声。
{名}墨子ボクシのこと。また、その学派。「楊墨ヨウボク(楊朱と墨子)」「天下之言、不帰楊、則帰墨=天下ノ言、楊ニ帰セザレバ、スナハチ墨ニ帰ス」〔→孟子〕
〔国〕隅田川のこと。▽墨田川とも書いたことから。「墨堤」
《解字》
会意兼形声。 コク(=黒)は「煙突+炎」の会意文字で、煙突のふちに点々とすすのたまったさまを示す。墨は、「土+音符
コク(=黒)は「煙突+炎」の会意文字で、煙突のふちに点々とすすのたまったさまを示す。墨は、「土+音符 」で、土状をなしたすすの塊のこと。くろい意を含む。→黒
《単語家族》
」で、土状をなしたすすの塊のこと。くろい意を含む。→黒
《単語家族》
 (=黒。くろいすす)
(=黒。くろいすす) 煤バイ(すす)
煤バイ(すす) 晦カイ(日のない暗い夜)
晦カイ(日のない暗い夜) 海(うすぐろい色のうみ)
海(うすぐろい色のうみ) 灰(すす→はい)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
灰(すす→はい)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
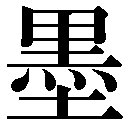 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 土部 [常用漢字]
区点=4347 16進=4B4F シフトJIS=966E
《常用音訓》ボク/すみ
《音読み》 ボク
14画 土部 [常用漢字]
区点=4347 16進=4B4F シフトJIS=966E
《常用音訓》ボク/すみ
《音読み》 ボク /モク
/モク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 すみ/くろい(くろし)
《名付け》 すみ
《意味》
〉
《訓読み》 すみ/くろい(くろし)
《名付け》 すみ
《意味》
 {名}すみ。毛筆で文字を書くのに用いるくろい液。また、すずりですってこの液をつくるために用いるくろいかたまり。松根やなたねなどの油をくすべ、そのすすを固めてつくる。
{名}すみ。毛筆で文字を書くのに用いるくろい液。また、すずりですってこの液をつくるために用いるくろいかたまり。松根やなたねなどの油をくすべ、そのすすを固めてつくる。
 {名}すみで書いた物。「芳墨」
{名}すみで書いた物。「芳墨」
 {名}すみのように、物を書くのに使う物。「石墨」「白墨」
{名}すみのように、物を書くのに使う物。「石墨」「白墨」
 {形}くろい(クロシ)。「面深墨=面、深墨ナリ」〔→孟子〕
{形}くろい(クロシ)。「面深墨=面、深墨ナリ」〔→孟子〕
 {名}入れ墨。「墨刑」
{名}入れ墨。「墨刑」
 {名}なわや、ひもにすみをつけて、材木の上に張り、ぴんとはねて直線を引く大工道具。すみなわ。「縄墨ジョウボク」
{名}なわや、ひもにすみをつけて、材木の上に張り、ぴんとはねて直線を引く大工道具。すみなわ。「縄墨ジョウボク」
 {単位}周代の、長さの単位。一墨は、五尺(一尺は二二・五センチメートル)。
{単位}周代の、長さの単位。一墨は、五尺(一尺は二二・五センチメートル)。
 {名}墨子ボクシのこと。また、その学派。「楊墨ヨウボク(楊朱と墨子)」「天下之言、不帰楊、則帰墨=天下ノ言、楊ニ帰セザレバ、スナハチ墨ニ帰ス」〔→孟子〕
〔国〕隅田川のこと。▽墨田川とも書いたことから。「墨堤」
《解字》
会意兼形声。
{名}墨子ボクシのこと。また、その学派。「楊墨ヨウボク(楊朱と墨子)」「天下之言、不帰楊、則帰墨=天下ノ言、楊ニ帰セザレバ、スナハチ墨ニ帰ス」〔→孟子〕
〔国〕隅田川のこと。▽墨田川とも書いたことから。「墨堤」
《解字》
会意兼形声。 コク(=黒)は「煙突+炎」の会意文字で、煙突のふちに点々とすすのたまったさまを示す。墨は、「土+音符
コク(=黒)は「煙突+炎」の会意文字で、煙突のふちに点々とすすのたまったさまを示す。墨は、「土+音符 」で、土状をなしたすすの塊のこと。くろい意を含む。→黒
《単語家族》
」で、土状をなしたすすの塊のこと。くろい意を含む。→黒
《単語家族》
 (=黒。くろいすす)
(=黒。くろいすす) 煤バイ(すす)
煤バイ(すす) 晦カイ(日のない暗い夜)
晦カイ(日のない暗い夜) 海(うすぐろい色のうみ)
海(うすぐろい色のうみ) 灰(すす→はい)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
灰(すす→はい)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
墨子泣糸 ボクシイトニナク🔗⭐🔉
【墨子泣糸】
ボクシイトニナク〈故事〉人は環境や教育次第で、性質の善悪が決まってしまうことのたとえ。墨子が、白い練り糸が黄色にも黒色にも染まるのを知って泣いた故事から。「墨子悲染=ボクシセンをかなしむ」とも。〔→淮南子〕
墨汁 ボクジュウ🔗⭐🔉
【墨水】
ボクスイ  墨をすってできた汁。『墨汁ボクジュウ』
墨をすってできた汁。『墨汁ボクジュウ』 〔国〕隅田川のこと。
〔国〕隅田川のこと。
 墨をすってできた汁。『墨汁ボクジュウ』
墨をすってできた汁。『墨汁ボクジュウ』 〔国〕隅田川のこと。
〔国〕隅田川のこと。
墨刑 ボッケイ🔗⭐🔉
【墨刑】
ボッケイ 入れ墨の刑。〈類義語〉黥刑ゲイケイ。入れ墨の刑。『墨黥ボクゲイ』
墨守 ボクシュ🔗⭐🔉
【墨守】
ボクシュ〈故事〉かたく自分の説や態度を守ること。▽墨子ボクシがよく城を守った故事から出たことば。
墨池 ボクチ🔗⭐🔉
【墨池】
ボクチ  すずりの、水をためるためのくぼんだ部分。
すずりの、水をためるためのくぼんだ部分。 墨つぼ。〈類義語〉翰池カンチ。
墨つぼ。〈類義語〉翰池カンチ。
 すずりの、水をためるためのくぼんだ部分。
すずりの、水をためるためのくぼんだ部分。 墨つぼ。〈類義語〉翰池カンチ。
墨つぼ。〈類義語〉翰池カンチ。
墨君 ボックン🔗⭐🔉
【墨竹】
ボクチク  墨で描かれた竹の絵。▽竹を此君シクンと呼ぶのに基づく。
墨で描かれた竹の絵。▽竹を此君シクンと呼ぶのに基づく。 竹の一種。くろだけ。『墨君ボックン』
竹の一種。くろだけ。『墨君ボックン』
 墨で描かれた竹の絵。▽竹を此君シクンと呼ぶのに基づく。
墨で描かれた竹の絵。▽竹を此君シクンと呼ぶのに基づく。 竹の一種。くろだけ。『墨君ボックン』
竹の一種。くろだけ。『墨君ボックン』
墨花 ボッカ🔗⭐🔉
【墨花】
ボッカ  墨で描かれた花の絵。
墨で描かれた花の絵。 墨の色つやのしみこんだすずり。
墨の色つやのしみこんだすずり。 つややかで美しい墨色のさま。
つややかで美しい墨色のさま。
 墨で描かれた花の絵。
墨で描かれた花の絵。 墨の色つやのしみこんだすずり。
墨の色つやのしみこんだすずり。 つややかで美しい墨色のさま。
つややかで美しい墨色のさま。
墨者 ボクシャ🔗⭐🔉
【墨者】
ボクシャ  「墨家」と同じ。
「墨家」と同じ。 墨刑を受けた人。
墨刑を受けた人。
 「墨家」と同じ。
「墨家」と同じ。 墨刑を受けた人。
墨刑を受けた人。
墨突不黔 ボクトツクロマズ🔗⭐🔉
【墨突不黔】
ボクトツクロマズ〈故事〉かまどのけむ出しが黒くならない。忙しくて家にいる暇もないこと。墨子が自分の教えを広めるのに忙しく、自分の家で炊事するひまもなかったので、かまどのけむ出しが黒くならなかったという故事から。「孔席不暇暖、而墨突不得黔=孔席暖マルニ暇アラズ、墨突黔ムヲ得ズ」〔→韓愈〕→「孔席不暇暖コウセキアタタマルニイトマアラズ」
墨林 ボクリン🔗⭐🔉
【墨林】
ボクリン 書画家の仲間。
墨海 ボッカイ🔗⭐🔉
【墨海】
ボッカイ すずりのこと。
墨客 ボッカク🔗⭐🔉
【墨客】
ボッカク 書道家や画家など。「文人墨客」
墨家 ボッカ🔗⭐🔉
【墨家】
ボッカ 墨子の学派に属する人。『墨者ボクシャ』
墨痕 ボッコン🔗⭐🔉
【墨迹】
ボクセキ =墨跡。 墨でかいた筆の跡。『墨蹟ボクセキ・墨蹤ボクショウ・墨痕ボッコン』
墨でかいた筆の跡。『墨蹟ボクセキ・墨蹤ボクショウ・墨痕ボッコン』 毛筆でかいた字や絵。
毛筆でかいた字や絵。
 墨でかいた筆の跡。『墨蹟ボクセキ・墨蹤ボクショウ・墨痕ボッコン』
墨でかいた筆の跡。『墨蹟ボクセキ・墨蹤ボクショウ・墨痕ボッコン』 毛筆でかいた字や絵。
毛筆でかいた字や絵。
墨堤 ボクテイ🔗⭐🔉
【墨堤】
ボクテイ〔国〕隅田川の土手。
墨罪 ボクザイ🔗⭐🔉
【墨罪】
ボクザイ 墨刑に当たる罪。『墨辟ボクヘキ』
墨子 ボクシ🔗⭐🔉
【墨子】
ボクシ〈書物〉一五巻。戦国時代初期(前五世紀ごろ)の墨家の著作の集大成。成立年代不明。墨子ボクシの著と伝えられてはいるが、その門弟や後人が、墨子の考え方や言行を書き記したもの。たとえば尚賢篇では商人の身分からも賢者をあげ用いるべきであると説き、兼愛篇では、社会の混乱のもとは弱肉強食にあるとして、それを救うため、血縁や身分差を無視した博愛を説き、非攻篇では、弱国に対する侵略を非難し、節用篇・節葬篇では、君主のぜいたくや、手厚すぎる葬礼が、人民を苦しめることを指摘してその簡素化を説いている。その他、論理学や、幾何学・光学・力学にわたる科学的内容を含む部分、墨家の集団がその主たる目的とした防御戦術の知識をのべた部分などから成る。その思想の主要な点が、血縁の愛を重んじ、礼を重んずる儒家の考えとまっこうから対立するため、本書は久しく支配階級から無視されてきたが、清シン朝になって研究するものがふえ、さらに民国から革命後にかけて、多く庶民の立場にたって説く進歩性と、論理学的、科学的内容をふくむ本書は、ますます高く評価されつつある。
墨池編 ボクチヘン🔗⭐🔉
【墨池編】
ボクチヘン〈書物〉二〇巻。北宋ホクソウの朱長文シュチョウブン(1039〜98)の編。成立年代不明。歴史の書論を系統的に編集した書。宋代までの書論を集大成した書として、また、それを分類して編集した最初の試みとしてその後の書論集に大きな影響を与えた。
墨子 ボクシ🔗⭐🔉
【墨子】
ボクシ〈人名〉戦国時代の思想家。諸子百家の一つである墨家の始祖といわれる。その思想は、人を平等に愛し、戦争に反対し、勤労をすすめ、一面、科学的でさえあったので、漢代のはじめまで大いに流行した。しかし、儒教が国教となって以後は弾圧されておとろえた。学説を集めた書『墨子』がある。→「糸路シロ」・→「悲練糸レンシヲカナシム」
漢字源に「墨」で始まるの検索結果 1-22。