複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (86)
くさ【種】🔗⭐🔉
くさ【種】
①(多く、動詞の連用形に付いてグサと濁る)物事を起こすたね。もと。材料。万葉集17「よろづ代の語らひぐさ」。「お笑い―」「質しち―」
②種類。しな。たぐい。源氏物語紅葉賀「唐土もろこし・高麗こまと尽したる舞ども―多かり」
③種々。いろいろ。万葉集19「秋の時花―にありと」
くさ‐ぐさ【種種】🔗⭐🔉
くさ‐ぐさ【種種】
物事の品数・種類の多いさま。いろいろ。さまざま。源氏物語絵合「―の御たきものども」
くさわい【種はひ】クサハヒ🔗⭐🔉
くさわい【種はひ】クサハヒ
①物事の原因。たね。もと。源氏物語帚木「難ずべき―まぜぬ人は」
②種類。仁徳紀「種種雑物くさわいのもの」
③おもむき。風情ふぜい。源氏物語末摘花「何の―もなくあはれげなる」
しゅ【種】🔗⭐🔉
しゅ【種】
①同じなかま。分類した一つ。「ある―の才能」
②〔生〕(species)生物分類の基本的単位。互いに同類と認識しあう個体の集合であり、形態・生態などの諸特徴の共通性や分布域、相互に生殖が可能であることや遺伝子組成などによって、他種と区別しうるもの。生物種。いくつかの特徴により、さらに亜種・変種・品種に分けることもある。化石についてはさらに時間の経過に伴う変化(すなわち進化)を加味して定義し、進化学的種という。→階級(表)。
③〔論〕種概念の略。
しゅ‐がいねん【種概念】🔗⭐🔉
しゅ‐がいねん【種概念】
〔論〕(specific concept)一概念と他概念とが上位と下位の従属関係に立つ時、その下位の方の概念をいう。例えば、人間は動物の種概念。但し、この関係は相対的である。→類概念
しゅ‐ぎゅう【種牛】‥ギウ🔗⭐🔉
しゅ‐ぎゅう【種牛】‥ギウ
たねうし。
しゅ‐ぎょく【種玉】🔗⭐🔉
しゅ‐ぎょく【種玉】
(孝行な楊伯雍が玉を種うえて美婦を得た「捜神記」中の故事から)美人を妻とすること。
しゅ‐げい【種芸】🔗⭐🔉
しゅ‐げい【種芸】
草木や作物の植えつけ。
しゅ‐こん【種根】🔗⭐🔉
しゅ‐こん【種根】
①植物の種子の発芽に際してはじめに出る根。種子根。
②たね。すじょう。
しゅ‐さ【種差】🔗⭐🔉
しゅ‐さ【種差】
〔論〕(differentia specifica ラテン)同位概念(同一の類概念に属する2個以上の種概念)のうち、特定の種に固有な性質で、それを他の種から区別する規準となる徴表。例えば、人間を他の動物から区別する場合、人間における「理性的」という徴表。
しゅ‐し【種子】🔗⭐🔉
しゅ‐し【種子】
(古くはシュジ)
①植物の胚珠が受精し成熟したもの。種皮に包まれ、その中に胚および胚乳がある。成熟後に散布され、発芽したものは新しい個体となる。たね。
②〔仏〕
⇒しゅうじ。
③〔仏〕
⇒しゅじ。
⇒しゅし‐しょくぶつ【種子植物】
しゅ‐じ【種子】🔗⭐🔉
しゅじ‐げさ【種子袈裟】🔗⭐🔉
しゅじ‐げさ【種子袈裟】
梵字を織りこんだ袈裟。種子衣。
⇒しゅ‐じ【種子】
しゅし‐しょくぶつ【種子植物】🔗⭐🔉
しゅし‐しょくぶつ【種子植物】
種子を形成する植物。植物の大きな分類単位で、最も進化した群とされる。裸子植物と被子植物とに分ける。顕花植物。
⇒しゅ‐し【種子】
しゅ‐しゃかい【種社会】‥クワイ🔗⭐🔉
しゅ‐しゃかい【種社会】‥クワイ
種の存在様式に関する動物社会学・生態学の用語。同種の動物の全個体、同種間および他種との相互関係の一切を含む生物界の基本的構成単位。
しゅ‐じゅ【種種】🔗⭐🔉
しゅ‐じゅ【種種】
種類の多いさま。いろいろ。さまざま。くさぐさ。保元物語「―の神変を現じて後」。「―あります」
⇒しゅじゅ‐ざった【種種雑多】
⇒しゅじゅ‐そう【種種相】
しゅじゅ‐ざった【種種雑多】🔗⭐🔉
しゅじゅ‐ざった【種種雑多】
いろいろまじっていること。
⇒しゅ‐じゅ【種種】
しゅじゅ‐そう【種種相】‥サウ🔗⭐🔉
しゅじゅ‐そう【種種相】‥サウ
さまざまな姿・ありさま。
⇒しゅ‐じゅ【種種】
しゅ‐しょう【種姓・種性】‥シヤウ🔗⭐🔉
しゅ‐しょう【種姓・種性】‥シヤウ
〔仏〕(梵語gotra)人が本来持っている性質。もともと家系・家柄・血統の意。法相教学では人間のありようを声聞種姓・独覚種姓・菩薩種姓・不定種姓・無姓の五種姓に分類し、悟りの可能性のない者(無姓)を認める(五姓各別)。
しゅ‐しょうめい【種小名】‥セウ‥🔗⭐🔉
しゅ‐しょうめい【種小名】‥セウ‥
生物の学名を二名法で表す際、属名に続く第2語で、その種を示す特徴を表す語。ラテン語で、形容詞または関係する地名・人名・土語などを形容詞化した形をもちいる。Homo sapiens(ヒト)のsapiensの類。
しゅ‐ぞく【種族】🔗⭐🔉
しゅ‐ぞく【種族】
①同一種類のもの。ともがら。今昔物語集1「此の夫人の胎の中の御子は…釈迦の―也」
②[史記高祖本紀「事の就ならざる後に、秦の其の家を種族せんことを恐る」](誅が種族に及ぶ意)一族を皆殺しにすること。族殺。族滅。
③エスニック‐グループ。部族(tribe)や民族と同義に用いることもある。
しゅ‐ちく【種畜】🔗⭐🔉
しゅ‐ちく【種畜】
繁殖用家畜。乳牛や馬では、特に改良の目的にかなった種雄をいう。
⇒しゅちく‐ぼくじょう【種畜牧場】
しゅちく‐ぼくじょう【種畜牧場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
しゅちく‐ぼくじょう【種畜牧場】‥ヂヤウ
家畜改良のため優秀な種畜を飼養する牧場。
⇒しゅ‐ちく【種畜】
しゅ‐とう【種痘】🔗⭐🔉
しゅ‐とう【種痘】
(vaccination)痘苗とうびょうを人体に接種し、天然痘に対する免疫性を得させ、感染を予防する方法。牛痘種痘法はジェンナーの発明。植え疱瘡ぼうそう。
⇒しゅとう‐じょ【種痘所】
しゅとう‐じょ【種痘所】🔗⭐🔉
しゅとう‐じょ【種痘所】
江戸末期、江戸の神田お玉が池に創設された牛痘種痘法を施す施設。1857年(安政4)伊東玄朴ら蘭方医の願い出により、翌年開設。60年(万延1)幕府直轄。61年(文久1)西洋医学所、63年医学所と改称。東大医学部の前身の一つ。種痘館。
⇒しゅ‐とう【種痘】
しゅのきげん【種の起原】🔗⭐🔉
しゅのきげん【種の起原】
(On the Origin of Species by Means of Natural Selection)ダーウィンが、自然淘汰を主たる要因として生物進化論を唱えた書。1859年初版。→進化論
しゅ‐ば【種馬】🔗⭐🔉
しゅ‐ば【種馬】
種つけ用の牡馬。たねうま。
しゅ‐ひ【種皮】🔗⭐🔉
しゅ‐ひ【種皮】
種子の皮。珠皮の変化したもの。一般に、裸子植物と被子植物合弁花類では1枚、離弁花類では2枚から成り、後者の場合は外種皮と内種皮とに区別される。
しゅ‐ぼば【種牡馬】🔗⭐🔉
しゅ‐ぼば【種牡馬】
種馬。特に、サラブレッドにいう。スタリオン。
す‐じょう【素生・素性・素姓・種姓】‥ジヤウ🔗⭐🔉
す‐じょう【素生・素性・素姓・種姓】‥ジヤウ
①血すじ。家すじ。家がら。筋目。椿説弓張月続編「氏も―も知らぬ身が」
②生まれ育った境遇。また、本来の性質。生れつき。「―を明かす」
③伝来の由緒。「―のはっきりした茶器」
たな‐い【種井】‥ヰ🔗⭐🔉
たな‐い【種井】‥ヰ
(一説に「田な井」)稲の種をひたしておくために、苗代の傍に掘る井戸または池。たないけ。拾遺和歌集恋「我がためは―の清水ぬるけれど」
たな‐おろし【種下ろし】🔗⭐🔉
たな‐おろし【種下ろし】
穀物の種を田畑に蒔くこと。たねおろし。〈日葡辞書〉
たな‐しね【種稲】🔗⭐🔉
たな‐しね【種稲】
(タナはタネの古形。シネはイネに同じ)いねのたね。種子用のもみ。いなだね。天智紀「稲種たなしね三千斛」
たな‐つ‐もの【種子・穀】🔗⭐🔉
たな‐つ‐もの【種子・穀】
(タナは種たね)稲。また、穀類の総称。神代紀上「稲を以ては水田種子たなつものとす」
たな‐どき【種時】🔗⭐🔉
たな‐どき【種時】
稲の種まきの時期。苗代なわしろをつくる季節。苗代時。
たな‐はつほ【種初穂】🔗⭐🔉
たな‐はつほ【種初穂】
(タナバツオとも)蒔まき残した種籾たねもみの余分でつくった炒米いりごめ。田の神に供え、人も食する。たないりごめ。
たな‐ふて【種浸】🔗⭐🔉
たな‐ふて【種浸】
(フテはヒタシの訛)稲の種を水に浸すこと。
たな‐まつり【種祭】🔗⭐🔉
たな‐まつり【種祭】
苗代に播種はしゅする日の祝い。種畑祭たなばたまつりとも。
たね【種】🔗⭐🔉
たね【種】
①植物の発芽するもととなるもの。特に、種子植物の種子。万葉集12「水を多み高田あげに―蒔き」
②動物の発生するもと。
③(「胤」とも書く)血すじ。また、血統を伝えるものとしての子。源氏物語常夏「あなめでたの我が親や。かかりける―ながら、あやしき小家に生ひいでけること」。「一粒―ひとつぶだね」
④物事の発生する、または成り立つもと。原因。また、資本。日本永代蔵5「その―なくて長者になれるは一人もなかりき」。「争いの―」「悩みの―」「―を明かす」「―も仕掛けもない」
⑤料理などの材料。汁の実。「おでんの―」「すしの―」
⑥転じて、物事を行うてがかり。よりどころ。根拠。好色五人女4「又さもあらば吉三良殿にあひ見ることの―ともなりなん」
⇒種が割れる
⇒種を宿す
たね‐い【種井】‥ヰ🔗⭐🔉
たね‐い【種井】‥ヰ
⇒たない
たね‐いた【種板】🔗⭐🔉
たね‐いた【種板】
写真の原板。乾板。
たね‐いも【種芋】🔗⭐🔉
たね‐いも【種芋】
種とする芋。甘藷・馬鈴薯などの、土中に埋めて発芽させるもの。春、温床に入れて発芽させる。〈[季]春〉。泊船集「―や花の盛りを売りありく」(芭蕉)
たね‐うし【種牛】🔗⭐🔉
たね‐うし【種牛】
畜牛の繁殖・改良のために飼う牡牛。
たね‐うま【種馬】🔗⭐🔉
たね‐うま【種馬】
馬の繁殖・改良のために飼う牡馬。
たね‐えらび【種選び】🔗⭐🔉
たね‐えらび【種選び】
春の彼岸前後、苗代に蒔まく種籾たねもみを塩水に浸けるなどして選別すること。たねより。〈[季]春〉
たね‐おじ【種叔父】‥ヲヂ🔗⭐🔉
たね‐おじ【種叔父】‥ヲヂ
(関東地方で)相続者の欠けた場合にそなえて、次男・三男の一人を家に留めておくこと。→用心子ようじんこ
たね‐おろし【種卸し・種下ろし】🔗⭐🔉
たね‐おろし【種卸し・種下ろし】
たねまき。特に、八十八夜の前後に、稲の種籾たねもみを苗代にまくこと。たなおろし。〈[季]春〉
たね‐かかし【種案山子】🔗⭐🔉
たね‐かかし【種案山子】
苗代に種をまいたあとに立てる案山子。〈[季]春〉
たね‐がき【種牡蠣】🔗⭐🔉
たね‐がき【種牡蠣】
カキの稚貝。貝殻に付着させて採取し、内湾の波の静かな所に移して育成する。宮城県の松島湾・万石まんごく浦などが主産地。
たね‐かし【種貸し】🔗⭐🔉
たね‐かし【種貸し】
江戸時代、種籾たねもみの蓄えのない農民に、領主が種籾を貸し付けたこと。
たね‐が‐しま【種子島】(地名他)🔗⭐🔉
たね‐が‐しま【種子島】
①薩南諸島の一島。鹿児島県南部大隅諸島の主島。大隅海峡で大隅半島と隔たる。面積445平方キロメートル。鉄砲伝来の地として有名。甘蔗栽培・牧牛が盛ん。宇宙センターがある。
②火縄銃の異称。
たねがしま【種子島】(姓氏)🔗⭐🔉
たねがしま【種子島】
姓氏の一つ。
⇒たねがしま‐ときたか【種子島時尭】
たねがしま‐ときたか【種子島時尭】🔗⭐🔉
たねがしま‐ときたか【種子島時尭】
戦国時代の種子島の領主。1543年(天文12)漂着したポルトガル人から小銃2梃を買い、家臣にその製法を学ばせた。鉄匠八板金兵衛清定が製造に成功。(1528〜1579)
⇒たねがしま【種子島】
たね‐かす【種粕】🔗⭐🔉
たね‐かす【種粕】
(→)油粕あぶらかすに同じ。
たね‐がみ【種紙】🔗⭐🔉
たね‐がみ【種紙】
蚕が卵を産みつける紙。蚕卵台紙。蚕紙。〈[季]春〉
たね‐かわ【種川】‥カハ🔗⭐🔉
たね‐かわ【種川】‥カハ
江戸時代、主に鮭の産卵を保護してその繁殖を図った川の施設およびその制度。越後三面みおもて川の一区域を限って行なった村上藩の種川が著名で、以後、同藩士の士族授産事業として継承。
○種が割れるたねがわれる🔗⭐🔉
○種が割れるたねがわれる
隠しておいた仕掛けやたくらみが明らかになる。
⇒たね【種】
たね‐ぎれ【種切れ】
材料が尽きること。品が尽きること。
たね‐ご【種子】
子の無い人が、もらい子して育てているうちに、実子が生まれた場合、そのもらい子の称。
たね‐こうじ【種麹】‥カウジ
粗白米または玄米に麹菌を繁殖させたもの。
たね‐ごえ【種肥】
種子に肥料を施すこと。種子の発芽や発芽後の生育を促進するため、種子を下肥・厩肥などで処理する。肌肥はだごえ。合肥あわせごえ。
たね‐ず【種酢】
食酢醸造の際、酢酸さくさん菌を供給するため添加するもの。すでに発酵している酢醪すもろみなど。
た‐ねずみ【田鼠】
クマネズミの別称。
たね‐せん【種銭】
銭を鋳造するとき、鋳型を作るのに用いる模型。母銭。
たねだ【種田】
姓氏の一つ。
⇒たねだ‐さんとうか【種田山頭火】
たねだ‐さんとうか【種田山頭火】‥クワ
俳人。本名、正一。山口県生れ。早大中退。荻原井泉水に師事。のち出家して全国を漂泊、自由律の句を詠む。句集「草木塔」など。(1882〜1940)
種田山頭火
提供:毎日新聞社
 ⇒たねだ【種田】
たね‐たまご【種卵】
繁殖用に雛ひなに孵かえすため取っておく卵。
たね‐だわら【種俵】‥ダハラ
種籾たねもみを入れて、種井たないにひたす俵。〈[季]春〉。「夜もすがら音なき雨や―」(蕪村)
たね‐ちがい【種違い・胤違い】‥チガヒ
(→)「たねがわり」に同じ。
たね‐つけ【種付け】
家畜などの優良種を繁殖させるために、良種の牡を牝に交配すること。
たねつけ‐ばな【種漬け花】
(種籾たねもみを水につけるころ花が咲くことから)(→)田芥たがらし2の異名。〈[季]春〉
たね‐つち【種土】
「敲たたき土」の原料とする土。花崗岩が風化してできたもの。
たね‐つぼ【種壺】
古陶器の一種。伊賀・信楽しがらき・備前・常滑とこなめ・瀬戸などの古窯から出る無釉のまま焼き締めた壺類。もと農具用で、古来茶人が水指みずさしなどに利用。
たね‐とり【種取り】
①種子を採取すること。〈[季]秋〉
②子を生ませるために養っておくもの。
③新聞・雑誌などの記事の材料を探りあるくこと。また、その人。
たね‐なし【種無し】
①果実に種子の無いこと。また、その果実。「―西瓜」
②物事をするための材料の無いこと。歌舞伎、お染久松色読販「まんざら貴様に―で無心も言ふまい」
たね‐なす【種茄子】
種子をとるために残しておく茄子。
たね‐のこし【種残し】
種子をとるために残しておく果実。狂言、瓜盗人「―の無い事は有るまい」
たね‐はら【種腹・胤腹】
父と母。両親。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「知つての通り、―一つの兄も有り、妹もあれど」
たね‐ばん【種板】
⇒たねいた
たね‐び【種火】
(→)火種ひだねに同じ。
たね‐ふくべ【種瓢】
種子をとるために残しておくヒョウタン。〈[季]秋〉
たね‐ほん【種本】
著作・書画または講義などのよりどころとする他人の著作。
たね‐まき【種蒔き・種播き】
種をまくこと。播種はしゅ。特に、八十八夜の前後に、稲の種を苗代にまくこと。〈[季]春〉
⇒たねまき‐ざくら【種播き桜】
⇒たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
⇒たねまき‐どり【種蒔鳥】
たねまき‐ざくら【種播き桜】
(東北地方で、苗代に種をまく季節に咲くからいう)コブシの花の異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
歌舞伎舞踊の曲。長唄。本名題「翁草恋種蒔」。6世杵屋喜三郎作曲。1775年(安永4)初演。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐どり【種蒔鳥】
(苗代に種をまく頃来て鳴くからいう)カッコウの異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまくひと【種蒔く人】
文芸雑誌。1921年(大正10)小牧近江・金子洋文らの創刊。23年廃刊。「文芸戦線」の前身で、社会主義文学の萌芽。
たね‐まゆ【種繭】
糸繭用の普通蚕種(一代雑種)をつくるための繭。
たねむら【種村】
姓氏の一つ。
⇒たねむら‐すえひろ【種村季弘】
たねむら‐すえひろ【種村季弘】‥スヱ‥
独文学者・評論家。東京生れ。東大卒。怪奇・幻想・異端などをめぐる独得の評論や翻訳活動を展開。作「吸血鬼幻想」「ぺてん師列伝」など。(1933〜2004)
⇒たねむら【種村】
たね‐もの【種物】
①草木のたね。種子。〈[季]春〉。「―屋」
②てんぷら・玉子とじなど、他の材料の入っている汁蕎麦しるそばまたは汁饂飩しるうどん。
③氷水に果汁などを加えたもの。
たね‐もみ【種籾】
種子として蒔まくために、選んで保存するもみ。
たね‐わた【種綿】
種子が入っているままの綿。
⇒たねだ【種田】
たね‐たまご【種卵】
繁殖用に雛ひなに孵かえすため取っておく卵。
たね‐だわら【種俵】‥ダハラ
種籾たねもみを入れて、種井たないにひたす俵。〈[季]春〉。「夜もすがら音なき雨や―」(蕪村)
たね‐ちがい【種違い・胤違い】‥チガヒ
(→)「たねがわり」に同じ。
たね‐つけ【種付け】
家畜などの優良種を繁殖させるために、良種の牡を牝に交配すること。
たねつけ‐ばな【種漬け花】
(種籾たねもみを水につけるころ花が咲くことから)(→)田芥たがらし2の異名。〈[季]春〉
たね‐つち【種土】
「敲たたき土」の原料とする土。花崗岩が風化してできたもの。
たね‐つぼ【種壺】
古陶器の一種。伊賀・信楽しがらき・備前・常滑とこなめ・瀬戸などの古窯から出る無釉のまま焼き締めた壺類。もと農具用で、古来茶人が水指みずさしなどに利用。
たね‐とり【種取り】
①種子を採取すること。〈[季]秋〉
②子を生ませるために養っておくもの。
③新聞・雑誌などの記事の材料を探りあるくこと。また、その人。
たね‐なし【種無し】
①果実に種子の無いこと。また、その果実。「―西瓜」
②物事をするための材料の無いこと。歌舞伎、お染久松色読販「まんざら貴様に―で無心も言ふまい」
たね‐なす【種茄子】
種子をとるために残しておく茄子。
たね‐のこし【種残し】
種子をとるために残しておく果実。狂言、瓜盗人「―の無い事は有るまい」
たね‐はら【種腹・胤腹】
父と母。両親。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「知つての通り、―一つの兄も有り、妹もあれど」
たね‐ばん【種板】
⇒たねいた
たね‐び【種火】
(→)火種ひだねに同じ。
たね‐ふくべ【種瓢】
種子をとるために残しておくヒョウタン。〈[季]秋〉
たね‐ほん【種本】
著作・書画または講義などのよりどころとする他人の著作。
たね‐まき【種蒔き・種播き】
種をまくこと。播種はしゅ。特に、八十八夜の前後に、稲の種を苗代にまくこと。〈[季]春〉
⇒たねまき‐ざくら【種播き桜】
⇒たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
⇒たねまき‐どり【種蒔鳥】
たねまき‐ざくら【種播き桜】
(東北地方で、苗代に種をまく季節に咲くからいう)コブシの花の異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
歌舞伎舞踊の曲。長唄。本名題「翁草恋種蒔」。6世杵屋喜三郎作曲。1775年(安永4)初演。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐どり【種蒔鳥】
(苗代に種をまく頃来て鳴くからいう)カッコウの異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまくひと【種蒔く人】
文芸雑誌。1921年(大正10)小牧近江・金子洋文らの創刊。23年廃刊。「文芸戦線」の前身で、社会主義文学の萌芽。
たね‐まゆ【種繭】
糸繭用の普通蚕種(一代雑種)をつくるための繭。
たねむら【種村】
姓氏の一つ。
⇒たねむら‐すえひろ【種村季弘】
たねむら‐すえひろ【種村季弘】‥スヱ‥
独文学者・評論家。東京生れ。東大卒。怪奇・幻想・異端などをめぐる独得の評論や翻訳活動を展開。作「吸血鬼幻想」「ぺてん師列伝」など。(1933〜2004)
⇒たねむら【種村】
たね‐もの【種物】
①草木のたね。種子。〈[季]春〉。「―屋」
②てんぷら・玉子とじなど、他の材料の入っている汁蕎麦しるそばまたは汁饂飩しるうどん。
③氷水に果汁などを加えたもの。
たね‐もみ【種籾】
種子として蒔まくために、選んで保存するもみ。
たね‐わた【種綿】
種子が入っているままの綿。
 ⇒たねだ【種田】
たね‐たまご【種卵】
繁殖用に雛ひなに孵かえすため取っておく卵。
たね‐だわら【種俵】‥ダハラ
種籾たねもみを入れて、種井たないにひたす俵。〈[季]春〉。「夜もすがら音なき雨や―」(蕪村)
たね‐ちがい【種違い・胤違い】‥チガヒ
(→)「たねがわり」に同じ。
たね‐つけ【種付け】
家畜などの優良種を繁殖させるために、良種の牡を牝に交配すること。
たねつけ‐ばな【種漬け花】
(種籾たねもみを水につけるころ花が咲くことから)(→)田芥たがらし2の異名。〈[季]春〉
たね‐つち【種土】
「敲たたき土」の原料とする土。花崗岩が風化してできたもの。
たね‐つぼ【種壺】
古陶器の一種。伊賀・信楽しがらき・備前・常滑とこなめ・瀬戸などの古窯から出る無釉のまま焼き締めた壺類。もと農具用で、古来茶人が水指みずさしなどに利用。
たね‐とり【種取り】
①種子を採取すること。〈[季]秋〉
②子を生ませるために養っておくもの。
③新聞・雑誌などの記事の材料を探りあるくこと。また、その人。
たね‐なし【種無し】
①果実に種子の無いこと。また、その果実。「―西瓜」
②物事をするための材料の無いこと。歌舞伎、お染久松色読販「まんざら貴様に―で無心も言ふまい」
たね‐なす【種茄子】
種子をとるために残しておく茄子。
たね‐のこし【種残し】
種子をとるために残しておく果実。狂言、瓜盗人「―の無い事は有るまい」
たね‐はら【種腹・胤腹】
父と母。両親。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「知つての通り、―一つの兄も有り、妹もあれど」
たね‐ばん【種板】
⇒たねいた
たね‐び【種火】
(→)火種ひだねに同じ。
たね‐ふくべ【種瓢】
種子をとるために残しておくヒョウタン。〈[季]秋〉
たね‐ほん【種本】
著作・書画または講義などのよりどころとする他人の著作。
たね‐まき【種蒔き・種播き】
種をまくこと。播種はしゅ。特に、八十八夜の前後に、稲の種を苗代にまくこと。〈[季]春〉
⇒たねまき‐ざくら【種播き桜】
⇒たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
⇒たねまき‐どり【種蒔鳥】
たねまき‐ざくら【種播き桜】
(東北地方で、苗代に種をまく季節に咲くからいう)コブシの花の異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
歌舞伎舞踊の曲。長唄。本名題「翁草恋種蒔」。6世杵屋喜三郎作曲。1775年(安永4)初演。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐どり【種蒔鳥】
(苗代に種をまく頃来て鳴くからいう)カッコウの異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまくひと【種蒔く人】
文芸雑誌。1921年(大正10)小牧近江・金子洋文らの創刊。23年廃刊。「文芸戦線」の前身で、社会主義文学の萌芽。
たね‐まゆ【種繭】
糸繭用の普通蚕種(一代雑種)をつくるための繭。
たねむら【種村】
姓氏の一つ。
⇒たねむら‐すえひろ【種村季弘】
たねむら‐すえひろ【種村季弘】‥スヱ‥
独文学者・評論家。東京生れ。東大卒。怪奇・幻想・異端などをめぐる独得の評論や翻訳活動を展開。作「吸血鬼幻想」「ぺてん師列伝」など。(1933〜2004)
⇒たねむら【種村】
たね‐もの【種物】
①草木のたね。種子。〈[季]春〉。「―屋」
②てんぷら・玉子とじなど、他の材料の入っている汁蕎麦しるそばまたは汁饂飩しるうどん。
③氷水に果汁などを加えたもの。
たね‐もみ【種籾】
種子として蒔まくために、選んで保存するもみ。
たね‐わた【種綿】
種子が入っているままの綿。
⇒たねだ【種田】
たね‐たまご【種卵】
繁殖用に雛ひなに孵かえすため取っておく卵。
たね‐だわら【種俵】‥ダハラ
種籾たねもみを入れて、種井たないにひたす俵。〈[季]春〉。「夜もすがら音なき雨や―」(蕪村)
たね‐ちがい【種違い・胤違い】‥チガヒ
(→)「たねがわり」に同じ。
たね‐つけ【種付け】
家畜などの優良種を繁殖させるために、良種の牡を牝に交配すること。
たねつけ‐ばな【種漬け花】
(種籾たねもみを水につけるころ花が咲くことから)(→)田芥たがらし2の異名。〈[季]春〉
たね‐つち【種土】
「敲たたき土」の原料とする土。花崗岩が風化してできたもの。
たね‐つぼ【種壺】
古陶器の一種。伊賀・信楽しがらき・備前・常滑とこなめ・瀬戸などの古窯から出る無釉のまま焼き締めた壺類。もと農具用で、古来茶人が水指みずさしなどに利用。
たね‐とり【種取り】
①種子を採取すること。〈[季]秋〉
②子を生ませるために養っておくもの。
③新聞・雑誌などの記事の材料を探りあるくこと。また、その人。
たね‐なし【種無し】
①果実に種子の無いこと。また、その果実。「―西瓜」
②物事をするための材料の無いこと。歌舞伎、お染久松色読販「まんざら貴様に―で無心も言ふまい」
たね‐なす【種茄子】
種子をとるために残しておく茄子。
たね‐のこし【種残し】
種子をとるために残しておく果実。狂言、瓜盗人「―の無い事は有るまい」
たね‐はら【種腹・胤腹】
父と母。両親。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「知つての通り、―一つの兄も有り、妹もあれど」
たね‐ばん【種板】
⇒たねいた
たね‐び【種火】
(→)火種ひだねに同じ。
たね‐ふくべ【種瓢】
種子をとるために残しておくヒョウタン。〈[季]秋〉
たね‐ほん【種本】
著作・書画または講義などのよりどころとする他人の著作。
たね‐まき【種蒔き・種播き】
種をまくこと。播種はしゅ。特に、八十八夜の前後に、稲の種を苗代にまくこと。〈[季]春〉
⇒たねまき‐ざくら【種播き桜】
⇒たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
⇒たねまき‐どり【種蒔鳥】
たねまき‐ざくら【種播き桜】
(東北地方で、苗代に種をまく季節に咲くからいう)コブシの花の異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
歌舞伎舞踊の曲。長唄。本名題「翁草恋種蒔」。6世杵屋喜三郎作曲。1775年(安永4)初演。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐どり【種蒔鳥】
(苗代に種をまく頃来て鳴くからいう)カッコウの異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまくひと【種蒔く人】
文芸雑誌。1921年(大正10)小牧近江・金子洋文らの創刊。23年廃刊。「文芸戦線」の前身で、社会主義文学の萌芽。
たね‐まゆ【種繭】
糸繭用の普通蚕種(一代雑種)をつくるための繭。
たねむら【種村】
姓氏の一つ。
⇒たねむら‐すえひろ【種村季弘】
たねむら‐すえひろ【種村季弘】‥スヱ‥
独文学者・評論家。東京生れ。東大卒。怪奇・幻想・異端などをめぐる独得の評論や翻訳活動を展開。作「吸血鬼幻想」「ぺてん師列伝」など。(1933〜2004)
⇒たねむら【種村】
たね‐もの【種物】
①草木のたね。種子。〈[季]春〉。「―屋」
②てんぷら・玉子とじなど、他の材料の入っている汁蕎麦しるそばまたは汁饂飩しるうどん。
③氷水に果汁などを加えたもの。
たね‐もみ【種籾】
種子として蒔まくために、選んで保存するもみ。
たね‐わた【種綿】
種子が入っているままの綿。
たね‐ぎれ【種切れ】🔗⭐🔉
たね‐ぎれ【種切れ】
材料が尽きること。品が尽きること。
たね‐ご【種子】🔗⭐🔉
たね‐ご【種子】
子の無い人が、もらい子して育てているうちに、実子が生まれた場合、そのもらい子の称。
たね‐こうじ【種麹】‥カウジ🔗⭐🔉
たね‐こうじ【種麹】‥カウジ
粗白米または玄米に麹菌を繁殖させたもの。
たね‐ず【種酢】🔗⭐🔉
たね‐ず【種酢】
食酢醸造の際、酢酸さくさん菌を供給するため添加するもの。すでに発酵している酢醪すもろみなど。
たね‐せん【種銭】🔗⭐🔉
たね‐せん【種銭】
銭を鋳造するとき、鋳型を作るのに用いる模型。母銭。
たねだ【種田】🔗⭐🔉
たねだ【種田】
姓氏の一つ。
⇒たねだ‐さんとうか【種田山頭火】
たねだ‐さんとうか【種田山頭火】‥クワ🔗⭐🔉
たねだ‐さんとうか【種田山頭火】‥クワ
俳人。本名、正一。山口県生れ。早大中退。荻原井泉水に師事。のち出家して全国を漂泊、自由律の句を詠む。句集「草木塔」など。(1882〜1940)
種田山頭火
提供:毎日新聞社
 ⇒たねだ【種田】
⇒たねだ【種田】
 ⇒たねだ【種田】
⇒たねだ【種田】
たね‐ちがい【種違い・胤違い】‥チガヒ🔗⭐🔉
たね‐ちがい【種違い・胤違い】‥チガヒ
(→)「たねがわり」に同じ。
たねつけ‐ばな【種漬け花】🔗⭐🔉
たねつけ‐ばな【種漬け花】
(種籾たねもみを水につけるころ花が咲くことから)(→)田芥たがらし2の異名。〈[季]春〉
たね‐つち【種土】🔗⭐🔉
たね‐つち【種土】
「敲たたき土」の原料とする土。花崗岩が風化してできたもの。
たね‐つぼ【種壺】🔗⭐🔉
たね‐つぼ【種壺】
古陶器の一種。伊賀・信楽しがらき・備前・常滑とこなめ・瀬戸などの古窯から出る無釉のまま焼き締めた壺類。もと農具用で、古来茶人が水指みずさしなどに利用。
たね‐とり【種取り】🔗⭐🔉
たね‐とり【種取り】
①種子を採取すること。〈[季]秋〉
②子を生ませるために養っておくもの。
③新聞・雑誌などの記事の材料を探りあるくこと。また、その人。
たね‐なす【種茄子】🔗⭐🔉
たね‐なす【種茄子】
種子をとるために残しておく茄子。
たね‐のこし【種残し】🔗⭐🔉
たね‐のこし【種残し】
種子をとるために残しておく果実。狂言、瓜盗人「―の無い事は有るまい」
たね‐まき【種蒔き・種播き】🔗⭐🔉
たね‐まき【種蒔き・種播き】
種をまくこと。播種はしゅ。特に、八十八夜の前後に、稲の種を苗代にまくこと。〈[季]春〉
⇒たねまき‐ざくら【種播き桜】
⇒たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
⇒たねまき‐どり【種蒔鳥】
たねまき‐ざくら【種播き桜】🔗⭐🔉
たねまき‐ざくら【種播き桜】
(東北地方で、苗代に種をまく季節に咲くからいう)コブシの花の異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】🔗⭐🔉
たねまき‐さんばそう【種蒔三番叟】
歌舞伎舞踊の曲。長唄。本名題「翁草恋種蒔」。6世杵屋喜三郎作曲。1775年(安永4)初演。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまき‐どり【種蒔鳥】🔗⭐🔉
たねまき‐どり【種蒔鳥】
(苗代に種をまく頃来て鳴くからいう)カッコウの異称。
⇒たね‐まき【種蒔き・種播き】
たねまくひと【種蒔く人】🔗⭐🔉
たねまくひと【種蒔く人】
文芸雑誌。1921年(大正10)小牧近江・金子洋文らの創刊。23年廃刊。「文芸戦線」の前身で、社会主義文学の萌芽。
たねむら【種村】🔗⭐🔉
たねむら【種村】
姓氏の一つ。
⇒たねむら‐すえひろ【種村季弘】
たねむら‐すえひろ【種村季弘】‥スヱ‥🔗⭐🔉
たねむら‐すえひろ【種村季弘】‥スヱ‥
独文学者・評論家。東京生れ。東大卒。怪奇・幻想・異端などをめぐる独得の評論や翻訳活動を展開。作「吸血鬼幻想」「ぺてん師列伝」など。(1933〜2004)
⇒たねむら【種村】
○種を宿すたねをやどす🔗⭐🔉
○種を宿すたねをやどす
ある人の子をはらむ。夏目漱石、彼岸過迄「其小間使が須永の種を宿した時」
⇒たね【種】
た‐ねん【他年】
ほかの年。将来の年。後年。
た‐ねん【他念】
ほかのことをおもう心。ほかの心。余念。宇治拾遺物語8「この年ごろ―なく経を保ち奉りてあるしるしやらん」
た‐ねん【多年】
多くの年月。長年ながねん。「―の苦労」
⇒たねん‐せい【多年生】
⇒たねんせい‐しょくぶつ【多年生植物】
⇒たねん‐そう【多年草】
たねん‐ぎ【多念義】
浄土宗で、法然の門下、長楽寺隆寛を祖とする一派の教義。往生の因たる念仏を終生唱え続けることによって極楽に往生できると説く。↔一念義
たねん‐せい【多年生】
〔生〕同じ場所で何年も継続して生育可能なこと。
⇒た‐ねん【多年】
たねんせい‐しょくぶつ【多年生植物】
3年以上の生育期間をもつ植物をいう。すべての木本植物が含まれる。→多年草。
⇒た‐ねん【多年】
たねん‐そう【多年草】‥サウ
多年生で、冬期地上部が枯れても春に芽を出す草本。キク・ユリ・オモトなどの類。
⇒た‐ねん【多年】
だ‐の
(指定の助動詞ダに並立助詞ノが付いてできた語)物事を列挙するのに用いる。「赤―青―」
た‐のう【多能】
①多方面にわたっての才能を身に具えていること。多芸。「―を誇る」
②性能や機能が多方面にわたっていること。
⇒たのう‐こうさくきかい【多能工作機械】
だ‐のう【惰農】
なまけ百姓。↔精農
たのう‐こうさくきかい【多能工作機械】
1台で数種の工作を行う機能を有する機械。
⇒た‐のう【多能】
たのうだ‐ひと【頼うだ人】
我が主人と頼んだ人。主人。頼うだ御方。頼うだ者。狂言、末広がり「こちの―のやうに」
た‐の‐かみ【田の神】
田を守護する神。農業の神。
⇒たのかみ‐おくり【田の神送り】
たのかみ‐おくり【田の神送り】
田の神が山へ帰るのを送る農村行事。9月30日、10月・11月の初丑はつうしの日など地方によって異なる。
⇒た‐の‐かみ【田の神】
た‐の‐くさ【田の草】
稲田の雑草。はぐさ。「―取り」
⇒たのくさ‐やすみ【田の草休み】
たのくさ‐やすみ【田の草休み】
田の草を取る労を休めること。また、その日。
⇒た‐の‐くさ【田の草】
た‐のごい【手拭】‥ノゴヒ
(タはテ、ノゴヒはヌグヒの古形)てぬぐい。〈日本霊異記下訓釈〉
たのし・い【楽しい】
〔形〕[文]たの・し(シク)
①満足で愉快な気分である。快い。万葉集18「今日の日は―・しく遊べ言ひつぎにせむ」。「―・い一日を過ごす」
②豊かである。富んでいる。大鏡道長「この年ごろはいとこそ―・しけれ。人の取らぬをばさるものにて、馬・牛だにぞはまぬ」。日葡辞書「ケナイフッキ(家内富貴)シテタノシイコトカギリナカッタ」
たのしび【楽しび】
(→)「たのしみ」に同じ。武烈紀(図書寮本)永和点「樹本をきり倒たふして昇れる者を落し死ころすを快タノシヒとす」
たのし・ぶ【楽しぶ】
〔自他四〕
(→)「たのしむ」に同じ。今昔物語集1「道に老人を見て憂への心有りて―・ぶ心無し」
た‐の‐しま【田の島】
水田の間に挟まった畑地。全国各地にある地名。
たのしみ【楽しみ】
たのしむこと。たのしむ対象。また、趣味や娯楽。三教治道篇保安点「恒屋に巣くふ娯タノシミを識らむや」。「釣を―にしている」「将来が―な青年」
⇒たのしみ‐ギセル【楽しみ煙管】
⇒たのしみ‐ざけ【楽しみ酒】
⇒たのしみ‐なべ【楽しみ鍋】
⇒楽しみ極まりて哀情多し
⇒楽しみ尽きて哀しみ来たる
たのしみ‐ギセル【楽しみ煙管】
楽しみながらのむ煙草。なぐさみに手にするキセル。
⇒たのしみ【楽しみ】
[漢]種🔗⭐🔉
種 字形
 筆順
筆順
 〔禾部9画/14画/教育/2879・3C6F〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕たね・うえる・くさ
[意味]
①植物のたね。物事を生ずるもと。「種子・種苗・播種はしゅ」
②たねをまく。植える。「種樹・種植・種痘・接種」
③同一のもとから生じ、ある共通性を有することによって他と区別されたなかま。たぐい。くさ。「ある種の本」「王侯将相いずくんぞ種(=血統の別)あらんや」〔史記〕「種類・種別・種種・職種・各種」▶論理学では、「類」と対比され、「類」の下位の分類概念。生物学では、分類上の基礎単位。「種名・雑種・変種」
[解字]
形声。「禾」(=作物)+音符「重」(=おもみをかける)。地面に作物をおしこんでうえる意。
[下ツキ
育種・異種・一種・機種・貴種・業種・下種・原種・採種・雑種・蚕種・職種・諸種・新種・人種・接種・多種・断種・同種・特種・播種・品種・兵種・別種・変種・芒種・薬種・洋種
〔禾部9画/14画/教育/2879・3C6F〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕たね・うえる・くさ
[意味]
①植物のたね。物事を生ずるもと。「種子・種苗・播種はしゅ」
②たねをまく。植える。「種樹・種植・種痘・接種」
③同一のもとから生じ、ある共通性を有することによって他と区別されたなかま。たぐい。くさ。「ある種の本」「王侯将相いずくんぞ種(=血統の別)あらんや」〔史記〕「種類・種別・種種・職種・各種」▶論理学では、「類」と対比され、「類」の下位の分類概念。生物学では、分類上の基礎単位。「種名・雑種・変種」
[解字]
形声。「禾」(=作物)+音符「重」(=おもみをかける)。地面に作物をおしこんでうえる意。
[下ツキ
育種・異種・一種・機種・貴種・業種・下種・原種・採種・雑種・蚕種・職種・諸種・新種・人種・接種・多種・断種・同種・特種・播種・品種・兵種・別種・変種・芒種・薬種・洋種
 筆順
筆順
 〔禾部9画/14画/教育/2879・3C6F〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕たね・うえる・くさ
[意味]
①植物のたね。物事を生ずるもと。「種子・種苗・播種はしゅ」
②たねをまく。植える。「種樹・種植・種痘・接種」
③同一のもとから生じ、ある共通性を有することによって他と区別されたなかま。たぐい。くさ。「ある種の本」「王侯将相いずくんぞ種(=血統の別)あらんや」〔史記〕「種類・種別・種種・職種・各種」▶論理学では、「類」と対比され、「類」の下位の分類概念。生物学では、分類上の基礎単位。「種名・雑種・変種」
[解字]
形声。「禾」(=作物)+音符「重」(=おもみをかける)。地面に作物をおしこんでうえる意。
[下ツキ
育種・異種・一種・機種・貴種・業種・下種・原種・採種・雑種・蚕種・職種・諸種・新種・人種・接種・多種・断種・同種・特種・播種・品種・兵種・別種・変種・芒種・薬種・洋種
〔禾部9画/14画/教育/2879・3C6F〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕たね・うえる・くさ
[意味]
①植物のたね。物事を生ずるもと。「種子・種苗・播種はしゅ」
②たねをまく。植える。「種樹・種植・種痘・接種」
③同一のもとから生じ、ある共通性を有することによって他と区別されたなかま。たぐい。くさ。「ある種の本」「王侯将相いずくんぞ種(=血統の別)あらんや」〔史記〕「種類・種別・種種・職種・各種」▶論理学では、「類」と対比され、「類」の下位の分類概念。生物学では、分類上の基礎単位。「種名・雑種・変種」
[解字]
形声。「禾」(=作物)+音符「重」(=おもみをかける)。地面に作物をおしこんでうえる意。
[下ツキ
育種・異種・一種・機種・貴種・業種・下種・原種・採種・雑種・蚕種・職種・諸種・新種・人種・接種・多種・断種・同種・特種・播種・品種・兵種・別種・変種・芒種・薬種・洋種
大辞林の検索結果 (98)
くさ【種】🔗⭐🔉
くさ 【種】
■一■ [2] (名)
(1)(「草」とも書く)何かを生ずる原因・材料。たね。多く「ぐさ」と濁り,複合語として用いる。「質―」「語り―」「お笑い―」
(2)種類。たぐい。「唐土・高麗と尽したる舞ども―多かり/源氏(紅葉賀)」
■二■ (接尾)
助数詞。物の種類を数えるのに用いる。「三―ある中に,梅花ははなやかに今めかしう/源氏(梅枝)」
くさ-ぐさ【種種】🔗⭐🔉
くさ-ぐさ [2][0] 【種種】
物事の種類や品数などの多いこと。いろいろ。さまざま。「―の品」「やかましい名を―作り設けて/夜明け前(藤村)」
くさぐさ-の-うた【種種の歌】🔗⭐🔉
くさぐさ-の-うた [2] 【種種の歌】
和歌集部立ての一である雑歌(ゾウカ)の別名。賀茂真淵の「万葉考」における用語。
くさ-わい【種】🔗⭐🔉
くさ-わい ―ハヒ 【種】
(1)物事のたね。原因。「思ひ沈むべき―なきとき/源氏(梅枝)」
(2)種類。たぐい。「物の―はならびたれば/落窪 1」
(3)趣。面白み。「何の―もなくあはれげなるを/源氏(末摘花)」
しゅ【種】🔗⭐🔉
しゅ [1] 【種】
(1)植物のたね。種子。
(2)種類。たぐい。「この―のカメラは他にない」
(3)〔species〕
(ア)生物分類上の基本単位。属の下位で,形態的に他と不連続な特徴をもち,原則として,相互に正常な有性生殖を行い得る個体群をいう。種はさらに主として形態的特徴から,亜種・変種・品種などに分ける。(イ)〔論〕「種概念」に同じ。
しゅう-じ【種子】🔗⭐🔉
しゅうじ-しき【種子識】🔗⭐🔉
しゅうじ-しき [3] 【種子識】
〔仏〕 阿頼耶識(アラヤシキ)の別名。
しゅ-がいねん【種概念】🔗⭐🔉
しゅ-がいねん [2] 【種概念】
〔論〕 二つの概念の間に従属関係が成り立つ場合,下位の概念をいう。例えば,「動物」に対する「人間」の類。種。
⇔類概念
しゅかん-ざっしゅ【種間雑種】🔗⭐🔉
しゅかん-ざっしゅ [4] 【種間雑種】
同属異種間の交雑によって生じた子孫。
しゅ-ぎょく【種玉】🔗⭐🔉
しゅ-ぎょく [1][0] 【種玉】
〔漢の楊伯雍が石を種(ウ)えて美玉と好妻を得たという「捜神記」の故事から〕
美人を妻とすること。
しゅ-げい【種芸】🔗⭐🔉
しゅ-げい [0] 【種芸】
〔「芸」は植える意〕
農作物の植えつけ。樹芸。
しゅ-こん【種根】🔗⭐🔉
しゅ-こん [0] 【種根】
(1)種から芽が出る時,初めに出る根。幼根の発達したもの。種子根。
(2)生まれ。すじょう。
しゅ-さ【種差】🔗⭐🔉
しゅ-さ [1] 【種差】
〔論〕
〔specific difference〕
同一類に属するある種を他のすべての種から区別する特定の徴表。例えば,「動物」という類において,「人間」を他のすべての動物から区別している「理性」など。
しゅ-し【種子】🔗⭐🔉
しゅし-しょくぶつ【種子植物】🔗⭐🔉
しゅし-しょくぶつ [4] 【種子植物】
植物界の一門。花が咲き,種子を生じる一群をいう。裸子植物と被子植物とに分ける。旧称,顕花植物。
しゅ-じ【種子】🔗⭐🔉
しゅじ-げさ【種子袈裟】🔗⭐🔉
しゅじ-げさ [2] 【種子袈裟】
梵字や真言を縫い込めた袈裟。種子衣。
しゅ-しゃかい【種社会】🔗⭐🔉
しゅ-しゃかい ―シヤクワイ [2] 【種社会】
生物の一つ一つの種が構成するその種固有の社会。それぞれの種社会がすみわけによって共存し,生物全体の社会が形成される。1949年,今西錦司によって提唱された。
しゅ-じゅ【種種】🔗⭐🔉
しゅ-じゅ [1] 【種種】 (名・形動)[文]ナリ
いろいろのものがあること。また,種類・方法などの多いさま。いろいろ。さまざま。副詞的にも用いる。「―の産物」「―な方策」「―さまざま」「対策を―考える」
しゅじゅ-ざった【種種雑多】🔗⭐🔉
しゅじゅ-ざった [1] 【種種雑多】 (名・形動)[文]ナリ
いろいろのものが入り交じっている・こと(さま)。「―な人間が集まる」
しゅじゅ-そう【種種相】🔗⭐🔉
しゅじゅ-そう ―サウ [2] 【種種相】
さまざまの状態・姿。「人の世の―」
しゅ-しょう【種性】🔗⭐🔉
しゅ-しょう ―シヤウ [0] 【種性】
〔仏〕
〔「種」は種子,「性」は性分の意〕
悟りを開く素質。また,生まれつき。
しゅ-しょうめい【種小名】🔗⭐🔉
しゅ-しょうめい ―セウメイ [2] 【種小名】
〔生〕 二名法に基づく学名表記の際,属名に続いて表される一語。
しゅ-ぞく【種族】🔗⭐🔉
しゅ-ぞく [1] 【種族】
(1)人種的特徴を同じくし,言語・文化を共有する人間の集団。民族。
(2)同じ種類に属する生物。「―保存の本能」
(3)同じ種類のもの。たぐい。「農と工とは固より貧困の―にして/日本開化小史(卯吉)」
しゅちいん-だいがく【種智院大学】🔗⭐🔉
しゅちいん-だいがく シユチ ン― 【種智院大学】
私立大学の一。空海の開いた綜芸種智院を源とし,1905年(明治38)創立の京都専門学校を母体に,49年(昭和24)設立。本部は京都市南区。
ン― 【種智院大学】
私立大学の一。空海の開いた綜芸種智院を源とし,1905年(明治38)創立の京都専門学校を母体に,49年(昭和24)設立。本部は京都市南区。
 ン― 【種智院大学】
私立大学の一。空海の開いた綜芸種智院を源とし,1905年(明治38)創立の京都専門学校を母体に,49年(昭和24)設立。本部は京都市南区。
ン― 【種智院大学】
私立大学の一。空海の開いた綜芸種智院を源とし,1905年(明治38)創立の京都専門学校を母体に,49年(昭和24)設立。本部は京都市南区。
しゅ-ちく【種畜】🔗⭐🔉
しゅ-ちく [0] 【種畜】
品種改良のためや,繁殖させるための家畜。種牛・種馬など。
しゅちく-ぼくじょう【種畜牧場】🔗⭐🔉
しゅちく-ぼくじょう ―ヂヤウ [4] 【種畜牧場】
家畜の飼育管理・改良増殖・種付け事業の指導などを行う牧場。種畜場。
しゅ-ちゅう【種虫】🔗⭐🔉
しゅ-ちゅう [0] 【種虫】
マラリア病原虫などの胞子虫類の胞子殻内で,分裂の結果できた細胞が胞子殻外へ出たもの。これにより新しい感染が起きる。スポロゾイト。
しゅ-とう【種痘】🔗⭐🔉
しゅ-とう [0] 【種痘】
天然痘を予防するため,痘苗(トウビヨウ)を人体の皮膚に接種すること。1796年,ジェンナーが牛痘ウイルスによる人工的免疫法を発見。植え疱瘡。
しゅとう-しょ【種痘所】🔗⭐🔉
しゅとう-しょ 【種痘所】
1858年,江戸の蘭方医により神田お玉が池に設けられた天然痘の予防接種施設。牛痘による種痘の実施と西洋医療技術の教育を行なった。のち幕府の西洋医学所となった。
しゅのきげん【種の起原】🔗⭐🔉
しゅのきげん 【種の起原】
〔原題 On the Origin of Species by Means of Natural Selection〕
進化のしくみとして自然選択説を唱えたダーウィンの著。1859年刊。
しゅ-ひ【種皮】🔗⭐🔉
しゅ-ひ [1] 【種皮】
種子の周囲をおおっている膜。胚・胚乳を保護する。
しゅ-びょう【種苗】🔗⭐🔉
しゅ-びょう ―ベウ [0] 【種苗】
種(タネ)と苗(ナエ)。農林産物だけでなく,水産物の繁殖・養殖などに用いられる卵・稚魚などもいう。
しゅびょう-ほう【種苗法】🔗⭐🔉
しゅびょう-ほう ―ベウハフ 【種苗法】
植物の種苗のうち農林水産省令で指定するものについて販売の際の品種などの表示を規制し,品種登録制度などについて定める法律。1947年(昭和22)制定。
しゅ-ぼば【種牡馬】🔗⭐🔉
しゅ-ぼば [2] 【種牡馬】
繁殖用の雄馬。サイヤー。スタリオン。
⇔種牝馬(シユヒンバ)
す-じょう【素性・素姓・種姓】🔗⭐🔉
す-じょう ―ジヤウ [0] 【素性・素姓・種姓】
(1)人の生まれた家柄や血筋。生まれや育ち。「―が知れない」「氏(ウジ)―」
(2)人の生まれ育った境遇や歩んできた道すじ。「―を明かす」
(3)物の由緒や由来。「―のはっきりしない刀」
〔本来は「種姓」で,スは「種」の呉音〕
たね【種】🔗⭐🔉
たね [1] 【種】
(1)(ア)(植物で)発芽のもととなるもの。種子(シユシ)。「―をまく」
→種子
(イ)動物の誕生のもととなるもの。「―つけ」「―うま」
(2)(「胤」とも書く)血統また,血統を受け継ぎ伝えていくもの。子。子孫。「落とし―」「一粒―」「―を絶やす」
(3)ある事の原因となる物事。「心配の―」「癪(シヤク)の―」「喧嘩の―をまく」
(4)手品・奇術などの仕掛け。「手品の―を明かす」
(5)材料となるもの。(ア)料理に用いる材料。「おでん―」「すし―」(イ)話・物語・記事などの材料。「新聞―」「うわさの―」(ウ)もととなるもの。よりどころ。「飯の―とする」「生活の―」(エ)元金。もとで。「―銭」
(6)性質。階級。「客―」
たね=が割・れる🔗⭐🔉
――が割・れる
からくりや真実が明らかになる。仕掛け・たくらみがわかる。
たね=を宿(ヤド)・す🔗⭐🔉
――を宿(ヤド)・す
子をはらむ。妊娠する。
たね-いた【種板】🔗⭐🔉
たね-いた [0] 【種板】
写真の原板。乾板。たねばん。
たねいち【種市】🔗⭐🔉
たねいち 【種市】
岩手県北東部,九戸(クノヘ)郡の町。太平洋に臨み,南部もぐりの発祥地。
たね-いも【種芋】🔗⭐🔉
たね-いも [0] 【種芋】
種にするための芋。そのまま植えて繁殖させるものと,苗をとるためのものとがある。[季]春。
たね-うし【種牛】🔗⭐🔉
たね-うし [0][2] 【種牛】
種付け用の血統のよい雄牛。しゅぎゅう。
たね-うま【種馬】🔗⭐🔉
たね-うま [0][2] 【種馬】
種付け用の血統のよい雄馬。種牡馬(シユボバ)。しゅば。
たね-おろし【種下ろし】🔗⭐🔉
たね-おろし [3] 【種下ろし】 (名)スル
田畑に種をまくこと。たねまき。[季]春。
たね-かかし【種案山子】🔗⭐🔉
たね-かかし [3] 【種案山子】
春,種をまいたあと鳥がついばむのを脅すために立てるかかし。[季]春。
たね-かし【種貸し】🔗⭐🔉
たね-かし [2][0] 【種貸し】
江戸時代,凶作などで種籾(タネモミ)のない領内の農民に,領主が種籾を貸し付けたこと。収穫後年貢とともに返済した。
たねがしま【種子島】🔗⭐🔉
たねがしま 【種子島】
姓氏の一。
たねがしま-ときたか【種子島時尭】🔗⭐🔉
たねがしま-ときたか 【種子島時尭】
(1528-1579) 戦国時代の種子島領主。1543年漂着したポルトガル人より鉄砲二挺を入手,その製法を研究,八板清定に鉄砲を作らせ普及の発端をつくった。
たねがしま-りゅう【種子島流】🔗⭐🔉
たねがしま-りゅう ―リウ 【種子島流】
砲術の一派。祖は種子島時尭の臣,笹川小四郎。主命により鉄砲・火薬の製法を学び,一派を成した。
たね-が-しま【種子島】🔗⭐🔉
たね-が-しま 【種子島】
(1)鹿児島県,大隅半島の南方にある南北に細長い島。鉄砲伝来の地。中心都市は,西之表。
(2) [3]
火縄銃の異名。1543年種子島に漂着したポルトガル人から領主種子島時尭(トキタカ)が入手し,その使用法・製法を家臣に学ばせて以来,新兵器として国内に普及したことによる。戦国大名は競ってこれを求め,戦法・築城法などに大転換をもたらした。
→火縄銃
たねがしま-うちゅう-センター【種子島宇宙―】🔗⭐🔉
たねがしま-うちゅう-センター ―ウチウ― 【種子島宇宙―】
気象・通信など各種の実用衛星を打ち上げる,我が国最大のロケット発射場。鹿児島県種子島の南東端,竹崎・大崎(南種子(ミナミタネ)町)にある。
たね-がみ【種紙】🔗⭐🔉
たね-がみ [0][2] 【種紙】
「蚕卵紙(サンランシ)」に同じ。[季]春。
たね-ぎれ【種切れ】🔗⭐🔉
たね-ぎれ [0] 【種切れ】 (名)スル
品物・材料・口実などがすっかりなくなること。「話が―になる」
たね-きん【種菌】🔗⭐🔉
たね-きん [0] 【種菌】
シイタケ栽培で使用する培養菌糸や胞子の塊。
たね-こうじ【種麹】🔗⭐🔉
たね-こうじ ―カウジ [3] 【種麹】
玄米などに麹黴(コウジカビ)を十分発育させたもの。また,その胞子のみを集めたもの。麹をつくる時,原料に混合して麹黴を発生させる元にする。
たね-ごえ【種肥】🔗⭐🔉
たね-ごえ [0] 【種肥】
発芽を早め,生育をよくするために種子に施す肥料。肌肥(ハダゴエ)。しゅひ。
たね-ず【種酢】🔗⭐🔉
たね-ず [2] 【種酢】
食酢の醸造で,酢酸菌を繁殖させる元にする酢酸発酵したもろみ。
たね-せん【種銭】🔗⭐🔉
たね-せん [0][2] 【種銭】
(1)銭貨鋳造の際,鋳型の模型となる銭。
(2)お金を殖やそうとする時,もととする金銭。
たねだ【種田】🔗⭐🔉
たねだ 【種田】
姓氏の一。
たねだ-さんとうか【種田山頭火】🔗⭐🔉
たねだ-さんとうか ―サントウクワ 【種田山頭火】
(1882-1940) 俳人。山口県生まれ。本名,正一。早大中退。「層雲」に参加。荻原井泉水門下。出家し托鉢生活をしながら自由律による句作をした。句集「草木塔」,日記紀行文集「愚を守る」など。
たね-だわら【種俵】🔗⭐🔉
たね-だわら ―ダハラ [3] 【種俵】
種籾(タネモミ)を入れた俵。まく前に俵のまま井戸や池に浸しておく。[季]春。
たね-ちがい【種違い・胤違い】🔗⭐🔉
たね-ちがい ―チガヒ [3] 【種違い・胤違い】
兄弟姉妹で,母は同じで父が異なること。たねがわり。異父。
→腹違い
たね-つけ【種付け】🔗⭐🔉
たね-つけ [0][4] 【種付け】 (名)スル
家畜などの繁殖や改良のために,優良種の雄を雌に交配させること。「―馬」
たね-つけ【種漬(け)】🔗⭐🔉
たね-つけ [0][2] 【種漬(け)】
発芽を促すため,苗代にまく前に種籾(タネモミ)を水に浸すこと。種浸し。
たねつけ-ばな【種漬花・種付花】🔗⭐🔉
たねつけ-ばな [4] 【種漬花・種付花】
アブラナ科の越年草。普通,田や道端に生える。高さ約25センチメートル。葉は互生し,羽状に全裂。春,枝頂に白色小花を総状につけ,長さ2センチメートル内外の細長い果実を結ぶ。若苗は食用になる。田芥(タガラシ)。
種漬花
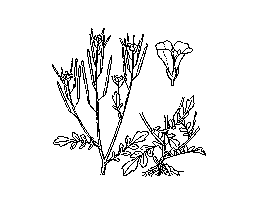 [図]
[図]
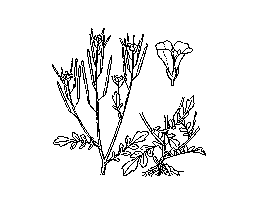 [図]
[図]
たね-つち【種土】🔗⭐🔉
たね-つち [2] 【種土】
叩土(タタキツチ)の原料にする土。花崗岩が風化したもの。
たね-とり【種取り】🔗⭐🔉
たね-とり [2][3] 【種取り】
(1)種子を採取すること。[季]秋。
(2)新聞・雑誌などの記事の材料をとること。また,その人。明治期の用語。
(3)子を生ませるために養っておく動物。
たね-び【種火】🔗⭐🔉
たね-び [2][0] 【種火】
いつでも火がおこせるように,またガス器具などですぐ着火できるように,用意しておく小さな火。「囲炉裏に―を残す」「ガス風呂の―」
たねひこ【種彦】🔗⭐🔉
たねひこ 【種彦】
⇒柳亭(リユウテイ)種彦
たね-ひたし【種浸し】🔗⭐🔉
たね-ひたし [3] 【種浸し】
「種漬(タネツ)け」に同じ。[季]春。
たね-ふくべ【種瓢】🔗⭐🔉
たね-ふくべ [4][3] 【種瓢】
種子をとるために残しておくヒョウタン。[季]秋。《誰彼にくれる印や―/虚子》
たね-まき【種蒔き】🔗⭐🔉
たね-まき [2] 【種蒔き】 (名)スル
(1)田畑に種をまくこと。特に,八十八夜の前後に,苗代に稲の種をまくこと。たねおろし。[季]春。「畑に―する」
(2)金もうけなどの材料・きっかけを作ること。「九郎助殿の留主を考へ何ぞ―にか/浄瑠璃・布引滝」
たねまき-ざくら【種蒔き桜】🔗⭐🔉
たねまき-ざくら [5] 【種蒔き桜】
東北地方で,コブシの異名。
たねまき-さんば【種蒔三番】🔗⭐🔉
たねまき-さんば 【種蒔三番】
「舌出し三番」の別名。
たねまき-どり【種蒔き鳥】🔗⭐🔉
たねまき-どり [4] 【種蒔き鳥】
カッコウの別名。
たねまくひと【種蒔く人】🔗⭐🔉
たねまくひと 【種蒔く人】
文芸雑誌。1921(大正10)〜23年発行。全二四冊。小牧近江・金子洋文らを同人として,反戦と被抑圧階級の解放を旗印に秋田県土崎で創刊,東京へ移り,プロレタリア文学運動の基礎を築いた。
たね-や【種屋】🔗⭐🔉
たね-や [2] 【種屋】
草木の種を商う家。また,その人。種物商。
しゅ【種】(和英)🔗⭐🔉
しゅし【種子】(和英)🔗⭐🔉
しゅし【種子】
a seed.→英和
⇒種(たね).
しゅぞく【種族】(和英)🔗⭐🔉
しゅちくじょう【種畜場】(和英)🔗⭐🔉
しゅちくじょう【種畜場】
a breeding stock farm.
しゅとう【種痘】(和英)🔗⭐🔉
しゅびょう【種苗】(和英)🔗⭐🔉
しゅびょう【種苗】
(seeds and) seedlings;a nursery tree.
たね【種】(和英)🔗⭐🔉
たね【種】
(1)[種子]a seed;→英和
a stone (梅などの);→英和
a pip (りんごなどの);→英和
a kernel (核・しん).→英和
(2)[牛・馬の]a breed;→英和
a stock.→英和
(3)[もと]the cause;→英和
the source.→英和
(4)[客の]good[bad]customers.(5)[話の]a topic.→英和
(6)[新聞の]news (matter).→英和
〜の多い(ない) seedy (seedless).→英和
〜をまく sow (seed).→英和
〜をあかす show the trick.→英和
〜も仕掛もない There is no trick (in it).
たねうし【種牛】(和英)🔗⭐🔉
たねうし【種牛】
a stud bull.
たねうま【種馬】(和英)🔗⭐🔉
たねうま【種馬】
a stud horse;a stallion.→英和
たねぎれ【種切れになる】(和英)🔗⭐🔉
たねぎれ【種切れになる】
[人が主語]run short of;[事物が主語]be exhausted.
たねつけ【種付け】(和英)🔗⭐🔉
たねつけ【種付け】
mating (家畜の).
たねとり【種取り】(和英)🔗⭐🔉
たねとり【種取り】
breeding (動物の);→英和
seed raising (植物の);news gathering (新聞の).
たねび【種火】(和英)🔗⭐🔉
たねび【種火】
a pilot-light.
たねまき【種蒔】(和英)🔗⭐🔉
たねまき【種蒔】
sowing;seeding.〜する sow (seed).→英和
広辞苑+大辞林に「種」で始まるの検索結果。もっと読み込む
 バク、阿弥陀如来は
バク、阿弥陀如来は キリクの類。種字。
キリクの類。種字。 ja〕
〔仏〕 唯識(ユイシキ)で,人間の心の根元である阿頼耶識(アラヤシキ)の中にあって,あらゆる現象を生じさせる原因。
ja〕
〔仏〕 唯識(ユイシキ)で,人間の心の根元である阿頼耶識(アラヤシキ)の中にあって,あらゆる現象を生じさせる原因。