複数辞典一括検索+![]()
![]()
アル【二】🔗⭐🔉
アル [1] 【二】
〔中国語〕
ふたつ。に。
に【二・弐】🔗⭐🔉
に [1] 【二・弐】
(1)数の名。一より一つ多い数。ふ。ふた。ふたつ。
(2)一の次の順序。二番目。第二位。つぎ。「―の矢をつがえる」「―の句」
(3)「二の糸」の略。「―上(アガ)り」
にいち-スト【二・一―】🔗⭐🔉
にいち-スト 【二・一―】
1947年(昭和22)2月1日を期して実行されようとした戦後最大のゼネラル-ストライキ。官公庁労組を中心に約六百万人の参加が予定されていたが,連合国軍最高司令官マッカーサーの命令により中止された。
にいち-てんさく-の-ご【二一天作の五】🔗⭐🔉
にいち-てんさく-の-ご 【二一天作の五】
(1)旧式珠算で,割り算九九の割り声。一(=一〇)を二で割ると五が立つという意。算盤(ソロバン)では桁(ケタ)の上の珠(タマ)を一つおろして五とおくこと。
(2)物を半分ずつに分けること。
(3)計算や勘定をすること。
にいにいろく-じけん【二・二六事件】🔗⭐🔉
にいにいろく-じけん 【二・二六事件】
⇒ににろくじけん
にい-の-あま【二位の尼】🔗⭐🔉
にい-の-あま ニ ― 【二位の尼】
平時子(タイラノトキコ)のこと。剃髪後,従二位に叙せられたのでいう。
― 【二位の尼】
平時子(タイラノトキコ)のこと。剃髪後,従二位に叙せられたのでいう。
 ― 【二位の尼】
平時子(タイラノトキコ)のこと。剃髪後,従二位に叙せられたのでいう。
― 【二位の尼】
平時子(タイラノトキコ)のこと。剃髪後,従二位に叙せられたのでいう。
に-いん【二院】🔗⭐🔉
に-いん ― ン [1] 【二院】
二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。両院。
ン [1] 【二院】
二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。両院。
 ン [1] 【二院】
二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。両院。
ン [1] 【二院】
二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。両院。
にいん-クラブ【二院―】🔗⭐🔉
にいん-クラブ ― ン― 【二院―】
⇒第二院(ダイニイン)クラブ
ン― 【二院―】
⇒第二院(ダイニイン)クラブ
 ン― 【二院―】
⇒第二院(ダイニイン)クラブ
ン― 【二院―】
⇒第二院(ダイニイン)クラブ
にいん-せい【二院制】🔗⭐🔉
にいん-せい ― ン― [0] 【二院制】
二つの独立した合議機関によって議会を構成し,原則として両者の意思の一致をもって議会の意思とする制度。通常,国民が直接的に選出した代表者からなる方を下院,その他の代表者からなる方を上院という。現憲法下の日本の国会は衆議院・参議院の二院から成るが,両者とも国民の直接的代表者で組織される。両院制。
→一院制
ン― [0] 【二院制】
二つの独立した合議機関によって議会を構成し,原則として両者の意思の一致をもって議会の意思とする制度。通常,国民が直接的に選出した代表者からなる方を下院,その他の代表者からなる方を上院という。現憲法下の日本の国会は衆議院・参議院の二院から成るが,両者とも国民の直接的代表者で組織される。両院制。
→一院制
 ン― [0] 【二院制】
二つの独立した合議機関によって議会を構成し,原則として両者の意思の一致をもって議会の意思とする制度。通常,国民が直接的に選出した代表者からなる方を下院,その他の代表者からなる方を上院という。現憲法下の日本の国会は衆議院・参議院の二院から成るが,両者とも国民の直接的代表者で組織される。両院制。
→一院制
ン― [0] 【二院制】
二つの独立した合議機関によって議会を構成し,原則として両者の意思の一致をもって議会の意思とする制度。通常,国民が直接的に選出した代表者からなる方を下院,その他の代表者からなる方を上院という。現憲法下の日本の国会は衆議院・参議院の二院から成るが,両者とも国民の直接的代表者で組織される。両院制。
→一院制
にえんき-さん【二塩基酸】🔗⭐🔉
にえんき-さん [4] 【二塩基酸】
電離して水素イオンとなることのできる水素原子を一分子あたり二個もつ酸。二価の酸。硫酸など。
に-おう【二王】🔗⭐🔉
に-おう ―ワウ [1] 【二王】
(1)二人の君主。
(2)中国の晋の書家,王羲之(オウギシ)とその子王献之の称。
に-おう【仁王・二王】🔗⭐🔉
に-おう ―ワウ [2][1] 【仁王・二王】
寺門あるいは須弥壇前面の両側に安置した一対の仏教護持の神像。忿怒(フンヌ)の相で,一体は口を開き,一体は口を閉じ両者で阿吽(アウン)の相をなす。その本来の性格については,金剛力士とするものなど諸説ある。
仁王
 [図]
[図]
 [図]
[図]
に-か【二化】🔗⭐🔉
に-か ―クワ [1] 【二化】
「二化性(ニカセイ)」に同じ。「―螟虫(メイチユウ)」
に-か【二家】🔗⭐🔉
に-か [1] 【二家】
⇒雌雄異株(シユウイシユ)
に-が【二河】🔗⭐🔉
に-が [1] 【二河】
〔仏〕 水の川と火の川。貪愛(トンアイ)と瞋憎(シンゾウ)の煩悩(ボンノウ)をそれぞれにたとえたもの。
→二河白道(ニガビヤクドウ)
にか-かい【二科会】🔗⭐🔉
にか-かい ニクワクワイ 【二科会】
美術団体。1914年(大正3)設立。文展洋画部に第二部設置を求めて入れられなかった石井柏亭・有島生馬らが結成。毎秋,公募展を開催。
にか-せい【二化性】🔗⭐🔉
にか-せい ニクワ― [0] 【二化性】
昆虫が,一年間に二世代繰り返す性質。多く夏と秋に現れる。二化。
→化性
にか-めいが【二化螟蛾】🔗⭐🔉
にか-めいが ニクワ― [3] 【二化螟蛾】
小形の蛾。前ばねの長さ10〜15ミリメートル。前ばねは黄褐色または暗褐色,後ろばねは白色。幼虫はニカメイチュウまたはズイムシと呼ばれ,イネの茎内を食害する大害虫。成虫は,田植え期と八,九月の二回発生する。日本全土のほか,アジア・ヨーロッパに広く分布。
にか-めいちゅう【二化螟虫】🔗⭐🔉
にか-めいちゅう ニクワ― [3] 【二化螟虫】
ニカメイガの幼虫。ズイムシ。
にクロム-さん【二―酸】🔗⭐🔉
にクロム-さん [0] 【二―酸】
クロム酸二分子から水一分子が脱水してできた縮合酸。
にクロムさん-カリウム【二―酸―】🔗⭐🔉
にクロムさん-カリウム [1]-[7] 【二―酸―】
橙赤色の板状結晶。化学式 K Cr
Cr O
O 強力な酸化剤として有機合成に用い,クロムめっき・分析試薬・染色用媒染剤・写真印刷など用途が広い。重クロム酸カリウム。
強力な酸化剤として有機合成に用い,クロムめっき・分析試薬・染色用媒染剤・写真印刷など用途が広い。重クロム酸カリウム。
 Cr
Cr O
O 強力な酸化剤として有機合成に用い,クロムめっき・分析試薬・染色用媒染剤・写真印刷など用途が広い。重クロム酸カリウム。
強力な酸化剤として有機合成に用い,クロムめっき・分析試薬・染色用媒染剤・写真印刷など用途が広い。重クロム酸カリウム。
にクロムさん-ナトリウム【二―酸―】🔗⭐🔉
にクロムさん-ナトリウム [1]-[8] 【二―酸―】
橙赤色の結晶。化学式 Na Cr
Cr O
O 二クロム酸カリウムに化学的性質はよく似るが,水に溶けやすい。革のなめし剤・クロムめっきなどに用いる。重クロム酸ナトリウム。
二クロム酸カリウムに化学的性質はよく似るが,水に溶けやすい。革のなめし剤・クロムめっきなどに用いる。重クロム酸ナトリウム。
 Cr
Cr O
O 二クロム酸カリウムに化学的性質はよく似るが,水に溶けやすい。革のなめし剤・クロムめっきなどに用いる。重クロム酸ナトリウム。
二クロム酸カリウムに化学的性質はよく似るが,水に溶けやすい。革のなめし剤・クロムめっきなどに用いる。重クロム酸ナトリウム。
にサイクル-きかん【二―機関】🔗⭐🔉
にサイクル-きかん ―キクワン [7][6] 【二―機関】
吸気・圧縮・(点火・爆発)・膨張・排気を二行程で行う内燃機関。小型ガソリン-エンジンやディーゼル-エンジンに用いる。二行程機関。
→四(ヨン)サイクル機関
ににはち-じけん【二・二八事件】🔗⭐🔉
ににはち-じけん 【二・二八事件】
1947年2月28日より台湾主要都市で起きた,台湾人による反中国・反国民党蜂起。官憲のタバコ密売者に対する暴行に端を発し,民衆は台湾の高度自治化を要求したが,軍に弾圧された。
ににろく-じけん【二・二六事件】🔗⭐🔉
ににろく-じけん 【二・二六事件】
陸軍皇道派青年将校が起こしたクーデター事件。1936年(昭和11)2月26日未明,首相官邸・警視庁などを千四百余名の部隊で襲撃,斎藤実内大臣・高橋是清蔵相・渡辺錠太郎教育総監らを殺害,永田町一帯を占領した。政府は翌日戒厳令を公布,二九日反乱は天皇の命令で鎮圧された。これにより岡田内閣にかわった広田内閣は陸軍の要求で軍部大臣現役武官制を復活,以後,軍の内閣介入の端緒となった。
に-の-あし【二の足】🔗⭐🔉
に-の-あし [0] 【二の足】
(1)二歩目。
(2)〔二の足を踏む意から〕
ためらうこと。しりごみ。「聞きおぢして―に成所を/浄瑠璃・国性爺合戦」
(3)太刀の鞘(サヤ)の帯取(オビトリ)を通す二つの足のうち鐺(コジリ)に近い方の称。
にのあし=を踏・む🔗⭐🔉
――を踏・む
〔一歩目は進むが,二歩目はためらって足踏みする意〕
決断がつかず実行をためらう。しりごみする。
に-の-いた【二の板】🔗⭐🔉
に-の-いた 【二の板】
兜(カブト)の錣(シコロ)や鎧(ヨロイ)の草摺(クサズリ)・袖などの,上から数えて二枚目の板。
に-の-いと【二の糸】🔗⭐🔉
に-の-いと 【二の糸】
三味線の三本の糸のうち一の糸より細く,三の糸より太い糸。
に-の-うで【二の腕】🔗⭐🔉
に-の-うで [0][4] 【二の腕】
(1)肩から肘(ヒジ)までの間の部分。上膊(ジヨウハク)部。
(2)肘と手首との間の腕。[日葡]
に-の-うま【二の午】🔗⭐🔉
に-の-うま [2][1] 【二の午】
二月の二回目の午の日。稲荷神社で祭礼が行われる。[季]春。《―や幟の外に何もなし/今井つる女》
→初午
に-の-うら【二の裏】🔗⭐🔉
に-の-うら 【二の裏】
連歌・俳諧で,二の折すなわち一巻の二枚目の懐紙の裏をいう。百韻では一四句,歌仙では六句を書く。歌仙では「名残の裏」にあたる。
に-の-おもて【二の表】🔗⭐🔉
に-の-おもて 【二の表】
連歌・俳諧で,二の折すなわち一巻の二枚目の懐紙の表のこと。百韻では一四句,歌仙では一二句を書く。歌仙では,「名残の表」にあたる。
に-の-おり【二の折】🔗⭐🔉
に-の-おり ―ヲリ [2][1] 【二の折】
連歌・俳諧に用いる二ないし四枚の半折懐紙の第二紙をいう。百韻ではその表と裏に各一四句,歌仙では表一二句,裏六句を書く。歌仙では「名残の折」にあたる。
に-の-かたな【二の刀】🔗⭐🔉
に-の-かたな [5][1] 【二の刀】
「二の太刀(タチ)」に同じ。
に-の-かわり【二の替(わ)り】🔗⭐🔉
に-の-かわり ―カハリ [0] 【二の替(わ)り】
〔「二の替わり狂言」の略〕
京坂で,歌舞伎の陰暦正月の狂言のこと。一一月の顔見世狂言が終わり,演目を一部差し替えて二度目の興行となるための称。[季]春。《さそはれし妻を遣りけり―/正岡子規》
→三の替わり
に-の-く【二の句】🔗⭐🔉
に-の-く [0] 【二の句】
(1)次に言い出す言葉。
(2)謡曲で,一声の詞章の第二句五・七五・七五に続く七五・七五の句。
(3)雅楽の朗詠の詩句を三段に分けて歌うとき,その第二段目の詩句。二段目は高音に歌うことから,続けて歌うと息が切れることが多い。
→二の句が継げない
にのく=が継げ ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
――が継げ ない
次に言い出す言葉が出てこない。あきれてあいた口がふさがらない。
ない
次に言い出す言葉が出てこない。あきれてあいた口がふさがらない。
 ない
次に言い出す言葉が出てこない。あきれてあいた口がふさがらない。
ない
次に言い出す言葉が出てこない。あきれてあいた口がふさがらない。
にのじ-てん【二の字点】🔗⭐🔉
にのじ-てん [3] 【二の字点】
漢字を重ねて訓読みにすることをしめす「 」のこと。「益
」のこと。「益 (マスマス)」「夫
(マスマス)」「夫 (ソレゾレ)」などの「
(ソレゾレ)」などの「 」。
」。
 」のこと。「益
」のこと。「益 (マスマス)」「夫
(マスマス)」「夫 (ソレゾレ)」などの「
(ソレゾレ)」などの「 」。
」。
に-の-ぜん【二の膳】🔗⭐🔉
に-の-ぜん [2][0] 【二の膳】
正式の日本料理で,本膳に次いで出される膳。「―付きの料理」
に-の-たい【二の対】🔗⭐🔉
に-の-たい 【二の対】
寝殿造りで,同一方角に対屋(タイノヤ)が複数設けられているとき,寝殿からより離れた方の対屋。
に-の-たち【二の太刀】🔗⭐🔉
に-の-たち [3] 【二の太刀】
二度目に斬りつけること。また,その太刀。「―をあびせる」
に-の-つぎ【二の次】🔗⭐🔉
に-の-つぎ [4] 【二の次】
二番目。あとまわし。「勉強は―にして遊び回っている」
に-の-つづみ【二の鼓】🔗⭐🔉
に-の-つづみ 【二の鼓】
雅楽に使う鼓。一の鼓より大きく,三の鼓より小さい細腰鼓。首にかけて桴(バチ)で打つ。現在は伝わっていない。
に-の-どう【二の胴】🔗⭐🔉
に-の-どう 【二の胴】
(1)人体の胴の一部。一の胴の少し下。
(2)和船の中腹にあたる艪床(ロドコ)の間の名称。
に-の-とり【二の酉】🔗⭐🔉
に-の-とり [0][2] 【二の酉】
一一月の第二の酉の日に行われる市。[季]冬。《―もとんと忘れて夜に入りし/星野立子》
に-の-ひと【二の人】🔗⭐🔉
に-の-ひと 【二の人】
宮中の席次が,一の人である摂政・関白に次ぐ人。「九条殿―にておはすれど/栄花(月の宴)」
に-の-ま【二の間】🔗⭐🔉
に-の-ま [1] 【二の間】
貴族の邸宅で,一の間に続く間。
に-の-まい【二の舞】🔗⭐🔉
に-の-まい ―マヒ 【二の舞】
(1)舞楽の一。右方の壱越(イチコツ)調の中曲。「安摩(アマ)」の答舞で,咲面(エミメン)をつけた老爺と腫面(ハレメン)をつけた老婆が安摩の舞を滑稽にまねる。
(2) [0]
人のまねをすること。特に,前の人と同じ失敗をすること。「―を演ずる」「色こそ見えねといふ歌の―のをこがましきに/義忠家歌合」
二の舞(1)
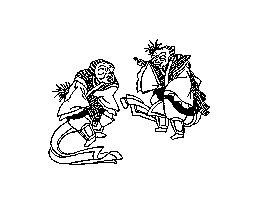 [図]
[図]
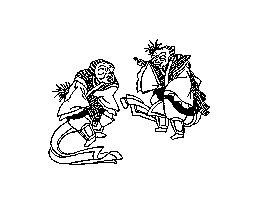 [図]
[図]
に-の-まち【二の町】🔗⭐🔉
に-の-まち 【二の町】
〔「町」は区分,等級の意〕
二級。二流。「これは―の心安きなるべし/源氏(帚木)」
→上(カミ)の町
に-の-まつ【二の松】🔗⭐🔉
に-の-まつ 【二の松】
能舞台の橋掛かりの白洲に植えられた三本の松のうち,中央の松。
→能舞台
に-の-まる【二の丸】🔗⭐🔉
に-の-まる [0] 【二の丸】
城の曲輪(クルワ)の名称。副郭の一。多くの場合二番目に重要な曲輪。城外から中心曲輪に至る道順に位置する。二の曲輪。
→本丸
に-の-みや【二の宮】🔗⭐🔉
に-の-みや [2] 【二の宮】
(1)二番目に生まれた親王。あるいは,内親王。
(2)一の宮に次ぐ社格の神社。
(3)地主権現(ジシユゴンゲン)の別名。
に-の-や【二の矢】🔗⭐🔉
に-の-や [1] 【二の矢】
(1)一の矢の次に放つ矢。二度目に射る矢。
(2)二番目・二度目にとる手段。「―が継げない」
にのや=を継・ぐ🔗⭐🔉
――を継・ぐ
一度目に続けて次の手段・行動をとる。「―・がんとするお霜を尻目に懸て/かくれんぼ(緑雨)」
に-よん-ディー【二、四-D】🔗⭐🔉
に-よん-ディー [4] 【二、四- D 】
2 ,4 -dichlorophenoxyacetic acid の略。合成オーキシンの一。広い葉をもつ植物に選択的に殺草効果を示すので,イネ科植物の栽培に除草剤として使う。水に溶けず乳剤として散布する。
ふ【二】🔗⭐🔉
ふ [1] 【二】
に。ふたつ。数をかぞえる時に用いる。「ひ,―,み」
ふう【二】🔗⭐🔉
ふう [1] 【二】
「ふ(二)」の長音化した語。に。ふたつ。「ひい,―,みい」
ふた【二】🔗⭐🔉
ふた [2] 【二】
に。ふたつ。名詞または動詞の上に付けて複合語を作る。「―親」「―心」「淡路島いや―並び/日本書紀(応神)」
ふた-つ【二つ】🔗⭐🔉
ふた-つ [3] 【二つ】
(1)数の名。ひとつより一多い数。
(2)物の数。二個。「りんごが―」「世論が―に割れる」
(3)二歳。「―になったばかり」
(4)二番目。第二。「一つには誠実,―には努力」
ふたつ=と無・い🔗⭐🔉
――と無・い
ただ一つしかない。かけがえがない。「世に―・い貴重な品」
ふたつ=に一つ🔗⭐🔉
――に一つ
二つのうちの,どちらか一つ。「イエスかノーか返事は―だ」
ふたつ-いろ【二つ色】🔗⭐🔉
ふたつ-いろ 【二つ色】
(1)「二藍(フタアイ)」に同じ。
(2)襲(カサネ)の色目の名。表は薄色または萌黄,裏は山吹色とも同色の衣を二枚ずつ重ねることともいう。
ふたつ-えり【二つ襟】🔗⭐🔉
ふたつ-えり [3] 【二つ襟】
重ね着の時に,二枚を交互に合わせないで,重ねて合わせること。
ふたつ-おり【二つ折り】🔗⭐🔉
ふたつ-おり ―ヲリ [0] 【二つ折り】
真ん中から折ること。「縦に―にする」
ふたつ-がわら【二つ瓦】🔗⭐🔉
ふたつ-がわら ―ガハラ [4] 【二つ瓦】
平安・鎌倉時代の大型船の構造。胴部の船瓦をたてに二材つなぐもの。また,その船。「―の三棟につくつたる舟にのり/平家 2」
ふたつ-ぎぬ【二つ衣】🔗⭐🔉
ふたつ-ぎぬ 【二つ衣】
袿(ウチキ)を二枚重ねたもの。ふたつおんぞ。「濃き色の―,単衣(ヒトエギヌ)着て/著聞 11」
ふたつ-ぐし【二つ櫛】🔗⭐🔉
ふたつ-ぐし [3] 【二つ櫛】
まげの前に二枚の櫛をさしたこと。また,その櫛。遊女などの風俗。
ふたつ-しろ【二つ白】🔗⭐🔉
ふたつ-しろ [3] 【二つ白】
「二白(ニハク)」に同じ。
ふたつ-しん【二つ真】🔗⭐🔉
ふたつ-しん [3] 【二つ真】
生け花の形式の一。立花(タテハナ)では木と木・草と草・木と草の二本を水際から梢まで間をあけてしん(心・真)に立てる。立華(リツカ)では花の右に竹,花の左に若松を用いる。たてわけ。さしわけ。
ふたつ-だま-ていきあつ【二つ玉低気圧】🔗⭐🔉
ふたつ-だま-ていきあつ [8] 【二つ玉低気圧】
南北に対になって現れる低気圧。本州を間に,日本海と太平洋に現れることが多い。
ふたつ-どもえ【二つ巴】🔗⭐🔉
ふたつ-どもえ ― [4] 【二つ巴】
巴紋の一。鞆(トモ)が二つ組み合わさった巴。
→巴
[4] 【二つ巴】
巴紋の一。鞆(トモ)が二つ組み合わさった巴。
→巴
 [4] 【二つ巴】
巴紋の一。鞆(トモ)が二つ組み合わさった巴。
→巴
[4] 【二つ巴】
巴紋の一。鞆(トモ)が二つ組み合わさった巴。
→巴
ふたつ-どり【二つ取り】🔗⭐🔉
ふたつ-どり 【二つ取り】
二つのうちどちらか一つを選ぶこと。どちらかといえば,の意。「―には婿には嫌なものなり/浮世草子・一代女 5」
ふたつ-ながら【二つ乍ら】🔗⭐🔉
ふたつ-ながら [4] 【二つ乍ら】 (副)
二つとも。双方どちらも。
ふたつ-の-みち【二つの道】🔗⭐🔉
ふたつ-の-みち 【二つの道】
(1)忠と孝の二道。「とにかくに―を思ふこそ世に仕ふるも苦しかりけり/続後拾遺(雑中)」
(2)〔白氏文集「秦中吟」から〕
貧と富の二つの道。「わが―うたふを聞け/源氏(帚木)」
ふたつ-ひき【二つ引き】🔗⭐🔉
ふたつ-ひき [0] 【二つ引き】
「二つ引両」に同じ。
ふたつ-ひきりょう【二つ引両】🔗⭐🔉
ふたつ-ひきりょう ―リヤウ [5] 【二つ引両】
家紋の一。輪の中に横に二本の線を引いたもの。足利氏の家紋。
ふたつ-ひとつ【二つ一つ】🔗⭐🔉
ふたつ-ひとつ 【二つ一つ】
二つのうちの,どちらか一つ。「すぐに芸者をやめるかあごをつるすか―だ/洒落本・船頭深話」
ふたつ-へんじ【二つ返事】🔗⭐🔉
ふたつ-へんじ [4] 【二つ返事】
「はい,はい」と重ねた返事。また,快く承知すること。「―で引き受ける」
ふたつ-まゆ【二つ繭】🔗⭐🔉
ふたつ-まゆ [3] 【二つ繭】
「二籠(フタゴモ)り{(2)}」に同じ。
ふたつ-め【二つ目】🔗⭐🔉
ふたつ-め [0] 【二つ目】
(1)同じものの第二番。「ひとつ食べ終わって,―に手を出す」
(2)東京の落語家の格。前座の上,真打ちの下。
(3)「二立目(フタタテメ)」に同じ。
ふたつ-もじ【二つ文字】🔗⭐🔉
ふたつ-もじ 【二つ文字】
平仮名の「こ」の字。「―牛の角文字直ぐな文字歪み文字とぞ君は覚ゆる/徒然 62」
ふたつ-ものがけ【二つ物掛け・二つ物賭】🔗⭐🔉
ふたつ-ものがけ 【二つ物掛け・二つ物賭】
二つのうちの,一方に運をかけること。一か八かの勝負。「ここの―せずしては一生替る事なし/浮世草子・胸算用 4」
ふたつ-もん【二つ紋】🔗⭐🔉
ふたつ-もん [3] 【二つ紋】
⇒比翼紋(ヒヨクモン)
ふたつ-わげ【二つ髷】🔗⭐🔉
ふたつ-わげ [3] 【二つ髷】
髻(モトドリ)を二つに分けて束ねること。後家や年配の女の髪形。
ふたつ-わり【二つ割り】🔗⭐🔉
ふたつ-わり [0] 【二つ割り】
(1)半分に分けること。また,二つに割ったもの。「西瓜を―にする」
(2)〔四斗樽の半分の意〕
二斗入りの酒樽。
(3)「半幅帯(ハンハバオビ)」に同じ。
ふたつ-な・し【二つ無し】🔗⭐🔉
ふたつ-な・し 【二つ無し】 (形ク)
(1)二つとない。かけがえがない。「―・きものと思ひしをみなそこに山のはならでいづる月かげ/古今(雑上)」
(2)比べるものがない。すぐれている。「世に―・き御ありさまながら/源氏(薄雲)」
にい【二位である】(和英)🔗⭐🔉
にい【二位である】
be[rank]second.
にいんせいど【二院制度】(和英)🔗⭐🔉
にいんせいど【二院制度】
the two-chamber[bicameral]system.
にかこく【二か国語放送】(和英)🔗⭐🔉
にかこく【二か国語放送】
bilingual broadcasting.
にのあし【二の足を踏む】(和英)🔗⭐🔉
にのあし【二の足を踏む】
hesitate.→英和
にのうで【二の腕】(和英)🔗⭐🔉
にのうで【二の腕】
the upper arm.
にのく【二の句がつげない】(和英)🔗⭐🔉
にのく【二の句がつげない】
be at a loss what to say;be speechless.
にのまい【二の舞を演じる】(和英)🔗⭐🔉
にのまい【二の舞を演じる】
repeat.→英和
ふたつ【二つ】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「二」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む