複数辞典一括検索+![]()
![]()
亶 ほしいままに🔗⭐🔉
【亶】
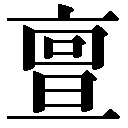 13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》
13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》  タン
タン
 〈d
〈d n〉/
n〉/ セン
セン /ゼン
/ゼン 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》
n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》

 {形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
 {接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
 {副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
 {形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
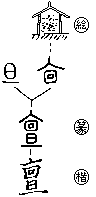 形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
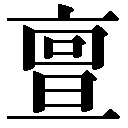 13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》
13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》  タン
タン
 〈d
〈d n〉/
n〉/ セン
セン /ゼン
/ゼン 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》
n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》

 {形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
 {接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
 {副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
 {形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
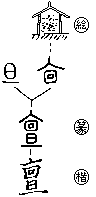 形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
宕 ほしいまま🔗⭐🔉
【宕】
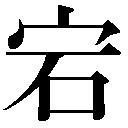 8画 宀部
区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386
《音読み》 トウ(タウ)
8画 宀部
区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま
《意味》
ng〉
《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま
《意味》
 {名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。
{名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。
 {形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」
{形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」
 {動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」
《解字》
会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」
《解字》
会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
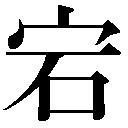 8画 宀部
区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386
《音読み》 トウ(タウ)
8画 宀部
区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま
《意味》
ng〉
《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま
《意味》
 {名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。
{名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。
 {形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」
{形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」
 {動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」
《解字》
会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」
《解字》
会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
恣 ほしいまま🔗⭐🔉
【恣】
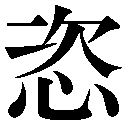 10画 心部
区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93
《音読み》 シ
10画 心部
区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93
《音読み》 シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)
《意味》
〉
《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)
《意味》
 {形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」
{形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。
《単語家族》
姿(ざっと身繕いする)
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。
《単語家族》
姿(ざっと身繕いする) 茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端)
茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端) 髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
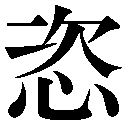 10画 心部
区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93
《音読み》 シ
10画 心部
区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93
《音読み》 シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)
《意味》
〉
《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)
《意味》
 {形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」
{形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。
《単語家族》
姿(ざっと身繕いする)
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。
《単語家族》
姿(ざっと身繕いする) 茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端)
茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端) 髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
擅 ほしいままにする🔗⭐🔉
放 ほしいままにする🔗⭐🔉
【放】
 8画 攴部 [三年]
区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA
《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる
《音読み》 ホウ(ハウ)
8画 攴部 [三年]
区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA
《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる
《音読み》 ホウ(ハウ)
 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)
《名付け》 おき・ゆき・ゆく
《意味》
ng〉
《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)
《名付け》 おき・ゆき・ゆく
《意味》
 {動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」
{動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」
 {動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」
{動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」
 {動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」
{動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」
 {動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕
{動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕
 {動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕
{動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕
 {動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」
{動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」
 {動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕
{動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕
 {動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」
{動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」
 {動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方
《単語家族》
房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや)
{動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方
《単語家族》
房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや) 妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。
《類義》
→啓・→肆
《異字同訓》
はなす/はなれる。 →離
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。
《類義》
→啓・→肆
《異字同訓》
はなす/はなれる。 →離
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 8画 攴部 [三年]
区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA
《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる
《音読み》 ホウ(ハウ)
8画 攴部 [三年]
区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA
《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる
《音読み》 ホウ(ハウ)
 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)
《名付け》 おき・ゆき・ゆく
《意味》
ng〉
《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)
《名付け》 おき・ゆき・ゆく
《意味》
 {動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」
{動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」
 {動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」
{動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」
 {動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」
{動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」
 {動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕
{動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕
 {動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕
{動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕
 {動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」
{動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」
 {動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕
{動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕
 {動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」
{動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」
 {動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方
《単語家族》
房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや)
{動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方
《単語家族》
房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや) 妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。
《類義》
→啓・→肆
《異字同訓》
はなす/はなれる。 →離
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。
《類義》
→啓・→肆
《異字同訓》
はなす/はなれる。 →離
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
縦 ほしいまま🔗⭐🔉
【縦】
 16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
 17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ
17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ /ショウ
/ショウ /シュ
/シュ 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
 {名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
 {形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
 {動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
 17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ
17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ /ショウ
/ショウ /シュ
/シュ 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
 {名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
 {形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
 {動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
肆 ほしいまま🔗⭐🔉
【肆】
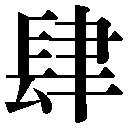 13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
 {動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
 {名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
 「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
 シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
 シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
 {助}ゆえに(ユ
{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
 {数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
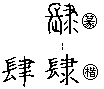 会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
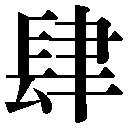 13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
13画 聿部
区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
〉
《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに
《意味》
 {動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕
 {名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕
 「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。
 シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕
 シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕
 {助}ゆえに(ユ
{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕
 {数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。
《解字》
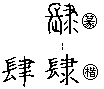 会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。
《類義》
縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「ほしいまま」で始まるの検索結果 1-7。
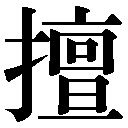 16画
16画  部
区点=5803 16進=5A23 シフトJIS=9DA1
《音読み》 セン
部
区点=5803 16進=5A23 シフトJIS=9DA1
《音読み》 セン