複数辞典一括検索+![]()
![]()
懐🔗⭐🔉
【懐】
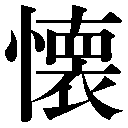 16画
16画  部 [常用漢字]
区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9
【懷】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9
【懷】旧字人名に使える旧字
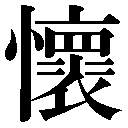 19画
19画  部
区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5
《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ
《音読み》 カイ(クワイ)
部
区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5
《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ
《音読み》 カイ(クワイ) /エ(
/エ( )
) 〈hu
〈hu i〉
《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ
《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす
《意味》
i〉
《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ
《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす
《意味》
 {動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕
{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕
 {名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」
{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」
 {動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕
{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕
 {名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕
{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕
 {動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕
{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕
 {名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」
〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。
《解字》
{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」
〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。
《単語家族》
回(取り囲む)
会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。
《単語家族》
回(取り囲む) 囲(かこむ)と同系。
《類義》
抱は、まるく包みこむこと。→思
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
囲(かこむ)と同系。
《類義》
抱は、まるく包みこむこと。→思
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
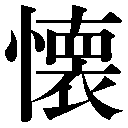 16画
16画  部 [常用漢字]
区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9
【懷】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9
【懷】旧字人名に使える旧字
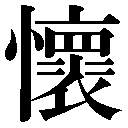 19画
19画  部
区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5
《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ
《音読み》 カイ(クワイ)
部
区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5
《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ
《音読み》 カイ(クワイ) /エ(
/エ( )
) 〈hu
〈hu i〉
《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ
《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす
《意味》
i〉
《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ
《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす
《意味》
 {動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕
{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕
 {名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」
{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」
 {動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕
{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕
 {名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕
{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕
 {動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕
{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕
 {名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」
〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。
《解字》
{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」
〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。
《単語家族》
回(取り囲む)
会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。
《単語家族》
回(取り囲む) 囲(かこむ)と同系。
《類義》
抱は、まるく包みこむこと。→思
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
囲(かこむ)と同系。
《類義》
抱は、まるく包みこむこと。→思
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
懐土 カイド🔗⭐🔉
懐中 カイチュウ🔗⭐🔉
【懐中】
カイチュウ  ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。
ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。 ウチニイダクふところに入れて持っていること。
ウチニイダクふところに入れて持っていること。 ふところの中にしまってある金銭。
ふところの中にしまってある金銭。
 ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。
ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。 ウチニイダクふところに入れて持っていること。
ウチニイダクふところに入れて持っていること。 ふところの中にしまってある金銭。
ふところの中にしまってある金銭。
懐旧 カイキユウ🔗⭐🔉
【懐旧】
カイキユウ 自分の生涯の過去のことをしのぶ。
懐古 イニシエヲオモウ🔗⭐🔉
懐石 カイセキ🔗⭐🔉
【懐石】
カイセキ〔国〕茶席で出す簡単な料理。▽温石オンジャク(温めた石)を懐にだいて腹をあたためると同じくらいに、腹をあたためて一時空腹をしのぐ意から。
懐胎 カイタイ🔗⭐🔉
【懐妊】
カイニン =懐姙。身ごもる。はらむ。妊娠。『懐胎カイタイ・懐孕カイヨウ』
懐附 カイフ🔗⭐🔉
【懐附】
カイフ なついてその人の側につく。
懐服 カイフク🔗⭐🔉
【懐服】
カイフク なついてつき従う。
懐柔 カイジュウ🔗⭐🔉
【懐柔】
カイジュウ  なつかせる。
なつかせる。 うまく手なずけて従わせる。
うまく手なずけて従わせる。
 なつかせる。
なつかせる。 うまく手なずけて従わせる。
うまく手なずけて従わせる。
懐郷 カイキョウ🔗⭐🔉
【懐郷】
カイキョウ(ク イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。
イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。
 イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。
イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。
懐羞 カイシュウ🔗⭐🔉
【懐羞】
カイシュウ はじらいの心をいだく。
懐想 カイソウ🔗⭐🔉
【懐想】
カイソウ なつかしくおもう。
懐疑 ウタガイヲイダク🔗⭐🔉
【懐疑】
カイギ・ウタガイヲイダク 疑いを持つ。疑わしいとおもう。
懐緬 カイメン🔗⭐🔉
【懐緬】
カイメン はるかに遠いものや、昔のことをおもう。
懐風藻 カイフウソウ🔗⭐🔉
【懐風藻】
カイフウソウ〔日〕〈書物〉現存する日本最古の漢詩集。撰者は淡海三船オウミノミフネ・石上宅嗣イソノカミノヤカツグ・葛井広成フジイノヒロナリなどの諸説があるが、未詳。751年成立。漢詩一二〇首(現行本は数首を欠く)を、作者別に集め年代順に配列している。作者は、文武天皇・大友皇子・大津皇子・藤原宇合フジワラノウマカイ・石上乙麻呂・葛井広成など六四人。大部分が上流階級の知識人。中国の儒教思想・老荘思想の影響を受けた発想によって、遊宴・応詔をうたった五言詩が大半で、類型的なものが多い。書名は、「先賢の遺風を懐オモう」の意から名づけられた。
懐王 カイオウ🔗⭐🔉
【懐王】
カイオウ(楚)〈人名〉戦国時代、楚ソの王。在位前328〜前298。威王の子。名は熊槐ユウカイ、懐は諡オクリナ。屈原の忠告をきかず秦シンの計略にのって斉セイとの同盟をやめ、斉が滅ぼされてから、秦王に会いにゆき殺された。→「巫山之夢フザンノユメ」
懐王 カイオウ🔗⭐🔉
【懐王】
カイオウ(秦)〈人名〉?〜前206?戦国時代の楚ソの懐王槐カイの孫で、項梁コウリョウにかつがれて楚の王になった。名は心。項羽が天下をとると義帝とされたが、すぐ暗殺された。
懐玉其罪 タマヲイダイテソレツミアリ🔗⭐🔉
【懐玉其罪】
タマヲイダイテソレツミアリ〈故事〉→「懐璧其罪タマヲイダイテソレツミアリ」
懐璧其罪 タマヲイダイテソレツミアリ🔗⭐🔉
【懐璧其罪】
タマヲイダイテソレツミアリ〈故事〉貴重なたまを持っているために、わざわいをうけ、罰せられる結果になる。身分不相応な物を持っているとかえって災いを招くこと。〔→左伝〕
懐荒 コウヲナツク🔗⭐🔉
【懐荒】
コウヲナツク 遠方の未開の地の人々をてなずけ従わせる。
漢字源に「懐」で始まるの検索結果 1-31。
