複数辞典一括検索+![]()
![]()
合口 アイクチ🔗⭐🔉
【合口】
 ゴウコウ
ゴウコウ  口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」
口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」 クチニアウ食べ物が、好みにあう。
クチニアウ食べ物が、好みにあう。 〔俗〕口論する。口争いをする。
〔俗〕口論する。口争いをする。 アイクチ〔国〕
アイクチ〔国〕 つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。
つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。 話しのあう人。
話しのあう人。
 ゴウコウ
ゴウコウ  口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」
口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」 クチニアウ食べ物が、好みにあう。
クチニアウ食べ物が、好みにあう。 〔俗〕口論する。口争いをする。
〔俗〕口論する。口争いをする。 アイクチ〔国〕
アイクチ〔国〕 つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。
つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。 話しのあう人。
話しのあう人。
哀叫 アイキョウ🔗⭐🔉
【哀号】
アイゴウ かなしみ、なき叫ぶ。『哀叫アイキョウ』
哀衣 アイイ🔗⭐🔉
【哀衣】
アイイ 喪中に着る着物。喪服。
哀哭 アイコク🔗⭐🔉
【哀哭】
アイコク かなしんで泣く。
哀艶 アイエン🔗⭐🔉
【哀婉】
アイエン あわれっぽくて、たおやかである。『哀艶アイエン』
哀毀骨立 アイキコツリツ🔗⭐🔉
【哀毀骨立】
アイキコツリツ 父母の喪などで、なげきかなしんで、やせおとろえる。〔→世説〕
哀歌 アイカ🔗⭐🔉
【哀歌】
アイカ  かなしげに歌う。また、その歌。
かなしげに歌う。また、その歌。 かなしみをこめて歌う。また、その歌。
かなしみをこめて歌う。また、その歌。
 かなしげに歌う。また、その歌。
かなしげに歌う。また、その歌。 かなしみをこめて歌う。また、その歌。
かなしみをこめて歌う。また、その歌。
哀歓 アイカン🔗⭐🔉
【哀歓】
アイカン かなしみと喜び。
哀願 アイガン🔗⭐🔉
【哀願】
アイガン あわれっぽく訴えて頼む。『哀請アイセイ』
哇咬 アイコウ🔗⭐🔉
【哇咬】
ワコウ・アイコウ  音が小刻みなさま。
音が小刻みなさま。 みだらな歌や音楽。
みだらな歌や音楽。
 音が小刻みなさま。
音が小刻みなさま。 みだらな歌や音楽。
みだらな歌や音楽。
噫噎 アイエツ🔗⭐🔉
【噫噎】
アイエツ 胸がつかえてむせぶ。
埃靄 アイアイ🔗⭐🔉
【埃靄】
アイアイ  もやのようにたちこめるほこり。
もやのようにたちこめるほこり。 この世のけがれ。
この世のけがれ。
 もやのようにたちこめるほこり。
もやのようにたちこめるほこり。 この世のけがれ。
この世のけがれ。
娃鬟 アイカン🔗⭐🔉
【娃鬟】
アイカン 美人。
愛育 アイイク🔗⭐🔉
【愛育】
アイイク かわいがってたいせつに育てる。『愛養アイヨウ』
愛玩 アイガン🔗⭐🔉
【愛玩】
アイガン =愛翫。 いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。
いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。 たいせつにしていつも観賞する。
たいせつにしていつも観賞する。
 いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。
いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。 たいせつにしていつも観賞する。
たいせつにしていつも観賞する。
愛狎 アイコウ🔗⭐🔉
【愛狎】
アイコウ なれ親しんでかわいがる。
愛国 アイコク🔗⭐🔉
【愛国】
アイコク・クニヲアイス 国を愛したいせつに思う。
愛敬 アイキョウ🔗⭐🔉
【愛敬】
 アイケイ 愛し敬う。
アイケイ 愛し敬う。 アイキョウ〔国〕
アイキョウ〔国〕 女性・子どもがかわいらしいこと。
女性・子どもがかわいらしいこと。 商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』
商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』
 アイケイ 愛し敬う。
アイケイ 愛し敬う。 アイキョウ〔国〕
アイキョウ〔国〕 女性・子どもがかわいらしいこと。
女性・子どもがかわいらしいこと。 商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』
商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』
愛悪 アイオ🔗⭐🔉
【愛憎】
アイゾウ  好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。
好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。 かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』
かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』
 好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。
好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。 かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』
かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』
愛嬌 アイキョウ🔗⭐🔉
【愛嬌】
アイキョウ  キョウヲアイスあでやかなものを好む。
キョウヲアイスあでやかなものを好む。 〔国〕「愛敬
〔国〕「愛敬 」と同じ。
」と同じ。
 キョウヲアイスあでやかなものを好む。
キョウヲアイスあでやかなものを好む。 〔国〕「愛敬
〔国〕「愛敬 」と同じ。
」と同じ。
愛護 アイゴ🔗⭐🔉
【愛護】
アイゴ たいせつに守る。かわいがって世話をすること。
敵娼 アイカタ🔗⭐🔉
【敵娼】
アイカタ〔国〕客の相手の遊女。
相 あい🔗⭐🔉
【相】
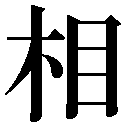 9画 目部 [三年]
区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A
《常用音訓》ショウ/ソウ/あい
《音読み》 ソウ(サウ)
9画 目部 [三年]
区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A
《常用音訓》ショウ/ソウ/あい
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈xi
〈xi ng・xi
ng・xi ng〉
《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)
《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる
《意味》
ng〉
《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)
《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる
《意味》
 {副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率
{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率 テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕
テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕
 {副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」
{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」
 {動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」
{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」
 {動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕
{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕
 {名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕
{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕
 {名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」
{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」
 ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕
ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕
 {名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」
{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」
 ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。
ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。
 ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」
〔国〕
ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」
〔国〕 あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」
あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」 文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」
《解字》
文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」
《解字》
 会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。
《単語家族》
爽ソウ(離れて対する)
会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。
《単語家族》
爽ソウ(離れて対する) 霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
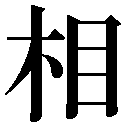 9画 目部 [三年]
区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A
《常用音訓》ショウ/ソウ/あい
《音読み》 ソウ(サウ)
9画 目部 [三年]
区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A
《常用音訓》ショウ/ソウ/あい
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈xi
〈xi ng・xi
ng・xi ng〉
《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)
《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる
《意味》
ng〉
《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)
《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる
《意味》
 {副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率
{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率 テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕
テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕
 {副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」
{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」
 {動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」
{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」
 {動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕
{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕
 {名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕
{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕
 {名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」
{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」
 ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕
ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕
 {名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」
{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」
 ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。
ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。
 ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」
〔国〕
ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」
〔国〕 あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」
あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」 文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」
《解字》
文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」
《解字》
 会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。
《単語家族》
爽ソウ(離れて対する)
会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。
《単語家族》
爽ソウ(離れて対する) 霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
相生 アイオイ🔗⭐🔉
【相生】
 ソウセイ・ソウショウ
ソウセイ・ソウショウ  互いに相手をうみだす。
互いに相手をうみだす。 五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。
五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。 アイオイ〔国〕
アイオイ〔国〕 同じ場所でいっしょに生ずること。
同じ場所でいっしょに生ずること。 一つの根から二本の木が生え出ること。
一つの根から二本の木が生え出ること。
 ソウセイ・ソウショウ
ソウセイ・ソウショウ  互いに相手をうみだす。
互いに相手をうみだす。 五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。
五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。 アイオイ〔国〕
アイオイ〔国〕 同じ場所でいっしょに生ずること。
同じ場所でいっしょに生ずること。 一つの根から二本の木が生え出ること。
一つの根から二本の木が生え出ること。
胥 あい🔗⭐🔉
【胥】
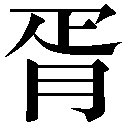 9画 肉部
区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF
《音読み》 ショ
9画 肉部
区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF
《音読み》 ショ /ソ
/ソ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ
《意味》
〉
《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ
《意味》
 {名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」
{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」
 {副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」
{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」
 {動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕
{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕
 {動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」
{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」
 {助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。
《単語家族》
疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる)
{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。
《単語家族》
疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる) 楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
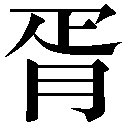 9画 肉部
区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF
《音読み》 ショ
9画 肉部
区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF
《音読み》 ショ /ソ
/ソ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ
《意味》
〉
《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ
《意味》
 {名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」
{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」
 {副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」
{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」
 {動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕
{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕
 {動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」
{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」
 {助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。
《単語家族》
疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる)
{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。
《単語家族》
疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる) 楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
藍 あい🔗⭐🔉
藹蔚 アイイ🔗⭐🔉
【藹蔚】
アイイ 樹木が茂るさま。
藹藹 アイアイ🔗⭐🔉
【藹藹】
アイアイ  元気いっぱいであるさま。
元気いっぱいであるさま。 草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕
草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕 いっぱいに満ちているさま。
いっぱいに満ちているさま。 =靄靄。月光が一面にたゆとうさま。
=靄靄。月光が一面にたゆとうさま。 =靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」
=靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」
 元気いっぱいであるさま。
元気いっぱいであるさま。 草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕
草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕 いっぱいに満ちているさま。
いっぱいに満ちているさま。 =靄靄。月光が一面にたゆとうさま。
=靄靄。月光が一面にたゆとうさま。 =靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」
=靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」
間 あい🔗⭐🔉
【間】
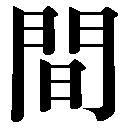 12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン
12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン /ケン
/ケン 〈ji
〈ji n・ji
n・ji n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
 {名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
 {名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
 {名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
 {名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
 {副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
 {単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
 {名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
 {名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
 {名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
 {名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
 {動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
 {形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
 {動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
 カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
 カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)
カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)
柬(よりわける) 界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
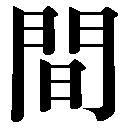 12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン
12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン /ケン
/ケン 〈ji
〈ji n・ji
n・ji n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
 {名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
 {名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
 {名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
 {名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
 {副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
 {単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
 {名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
 {名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
 {名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
 {名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
 {動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
 {形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
 {動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
 カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
 カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)
カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)
柬(よりわける) 界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
阨巷 アイコウ🔗⭐🔉
【阨巷】
アイコウ せまい通り。せまい路地。〈同義語〉隘巷。
阿姨 アイ🔗⭐🔉
【阿姨】
アイ  おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕
おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕 庶母をいうことば。
庶母をいうことば。 妻の姉妹をいうことば。
妻の姉妹をいうことば。 姉のこと。
姉のこと。 尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。
尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。
 おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕
おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕 庶母をいうことば。
庶母をいうことば。 妻の姉妹をいうことば。
妻の姉妹をいうことば。 姉のこと。
姉のこと。 尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。
尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。
姶 あい🔗⭐🔉
【姶】
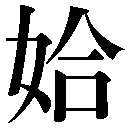 9画 女部
区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6
《音読み》 オウ
9画 女部
区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6
《音読み》 オウ
 《訓読み》 あい
《意味》
《訓読み》 あい
《意味》
 女の美しいようす。
女の美しいようす。 しずか。〔国〕あい。地名に使われる。
しずか。〔国〕あい。地名に使われる。
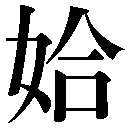 9画 女部
区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6
《音読み》 オウ
9画 女部
区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6
《音読み》 オウ
 《訓読み》 あい
《意味》
《訓読み》 あい
《意味》
 女の美しいようす。
女の美しいようす。 しずか。〔国〕あい。地名に使われる。
しずか。〔国〕あい。地名に使われる。
漢字源に「あい」で始まるの検索結果 1-44。もっと読み込む
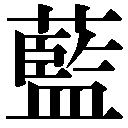 18画 艸部 [人名漢字]
区点=4585 16進=4D75 シフトJIS=9795
《音読み》 ラン(ラム)
18画 艸部 [人名漢字]
区点=4585 16進=4D75 シフトJIS=9795
《音読み》 ラン(ラム) n〉
《訓読み》 あい(あゐ)
《名付け》 あい
《意味》
n〉
《訓読み》 あい(あゐ)
《名付け》 あい
《意味》
 )。草の名。花から青色の染料をとる。あいぐさ。「青取之於藍、而青於藍=青ハコレヲ藍ヨリ取リテ、藍ヨリ青シ」〔
)。草の名。花から青色の染料をとる。あいぐさ。「青取之於藍、而青於藍=青ハコレヲ藍ヨリ取リテ、藍ヨリ青シ」〔