複数辞典一括検索+![]()
![]()
判 はん🔗⭐🔉
【判】
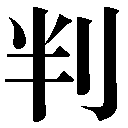 7画 リ部 [五年]
区点=4029 16進=483D シフトJIS=94BB
《常用音訓》ハン/バン
《音読み》 ハン
7画 リ部 [五年]
区点=4029 16進=483D シフトJIS=94BB
《常用音訓》ハン/バン
《音読み》 ハン
 /バン
/バン 〈p
〈p n〉
《訓読み》 わかつ/はん
《名付け》 さだ・ちか・なか・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 わかつ/はん
《名付け》 さだ・ちか・なか・ゆき
《意味》
 {動}わかつ。見わける。区別する。「判別」
{動}わかつ。見わける。区別する。「判別」
 ハンス{動}可否をきめる。答えを出す。「裁判」「判決」
ハンス{動}可否をきめる。答えを出す。「裁判」「判決」
 {形}けじめがはっきりしているさま。「判然」
〔国〕
{形}けじめがはっきりしているさま。「判然」
〔国〕 はん。印形のこと。▽転じて「大判」とは、大型の金貨のこと。「小判」とは、小型の金貨のこと。
はん。印形のこと。▽転じて「大判」とは、大型の金貨のこと。「小判」とは、小型の金貨のこと。 紙・書物のサイズ。「A5判」
《解字》
会意兼形声。半は「牛+八印(わける)」の会意文字で、牛のからだを両方にきりわける意を示す。判は「刀+音符半」で、半の後出の字。もと、刀で両分することを示すが、のち可否や黒白を区別し見わける意に用いる。→半
《単語家族》
半(二つにわける)
紙・書物のサイズ。「A5判」
《解字》
会意兼形声。半は「牛+八印(わける)」の会意文字で、牛のからだを両方にきりわける意を示す。判は「刀+音符半」で、半の後出の字。もと、刀で両分することを示すが、のち可否や黒白を区別し見わける意に用いる。→半
《単語家族》
半(二つにわける) 班ハン(わけた物)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
班ハン(わけた物)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
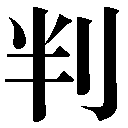 7画 リ部 [五年]
区点=4029 16進=483D シフトJIS=94BB
《常用音訓》ハン/バン
《音読み》 ハン
7画 リ部 [五年]
区点=4029 16進=483D シフトJIS=94BB
《常用音訓》ハン/バン
《音読み》 ハン
 /バン
/バン 〈p
〈p n〉
《訓読み》 わかつ/はん
《名付け》 さだ・ちか・なか・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 わかつ/はん
《名付け》 さだ・ちか・なか・ゆき
《意味》
 {動}わかつ。見わける。区別する。「判別」
{動}わかつ。見わける。区別する。「判別」
 ハンス{動}可否をきめる。答えを出す。「裁判」「判決」
ハンス{動}可否をきめる。答えを出す。「裁判」「判決」
 {形}けじめがはっきりしているさま。「判然」
〔国〕
{形}けじめがはっきりしているさま。「判然」
〔国〕 はん。印形のこと。▽転じて「大判」とは、大型の金貨のこと。「小判」とは、小型の金貨のこと。
はん。印形のこと。▽転じて「大判」とは、大型の金貨のこと。「小判」とは、小型の金貨のこと。 紙・書物のサイズ。「A5判」
《解字》
会意兼形声。半は「牛+八印(わける)」の会意文字で、牛のからだを両方にきりわける意を示す。判は「刀+音符半」で、半の後出の字。もと、刀で両分することを示すが、のち可否や黒白を区別し見わける意に用いる。→半
《単語家族》
半(二つにわける)
紙・書物のサイズ。「A5判」
《解字》
会意兼形声。半は「牛+八印(わける)」の会意文字で、牛のからだを両方にきりわける意を示す。判は「刀+音符半」で、半の後出の字。もと、刀で両分することを示すが、のち可否や黒白を区別し見わける意に用いる。→半
《単語家族》
半(二つにわける) 班ハン(わけた物)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
班ハン(わけた物)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
判押 ハンオウ🔗⭐🔉
【判押】
ハンオウ かきはん。〈類義語〉花押カオウ。
半 はん🔗⭐🔉
【半】
 5画 十部 [二年]
区点=4030 16進=483E シフトJIS=94BC
《常用音訓》ハン/なか…ば
《音読み》 ハン
5画 十部 [二年]
区点=4030 16進=483E シフトJIS=94BC
《常用音訓》ハン/なか…ば
《音読み》 ハン
 〈b
〈b n〉
《訓読み》 なかば/なかばする(なかばす)/わかつ/はん
《名付け》 なか・なかば・なからい
《意味》
n〉
《訓読み》 なかば/なかばする(なかばす)/わかつ/はん
《名付け》 なか・なかば・なからい
《意味》
 {名}なかば。二つに等分した片方。「夜半」「半入江風半入雲=半バハ江風ニ入リ、半バハ雲ニ入ル」〔→杜甫〕▽「〜有半」とは、二分の一はみ出ること。「長一身有半=長サ一身有半」〔→論語〕
{名}なかば。二つに等分した片方。「夜半」「半入江風半入雲=半バハ江風ニ入リ、半バハ雲ニ入ル」〔→杜甫〕▽「〜有半」とは、二分の一はみ出ること。「長一身有半=長サ一身有半」〔→論語〕
 {動}なかばする(ナカバス)。半分に達する。「相半=相ヒ半バス」
{動}なかばする(ナカバス)。半分に達する。「相半=相ヒ半バス」
 {動}わかつ。半分にわける。〈同義語〉→判。「折半」
〔国〕はん。さいころの目で、奇数。〈対語〉→丁。
《解字》
{動}わかつ。半分にわける。〈同義語〉→判。「折半」
〔国〕はん。さいころの目で、奇数。〈対語〉→丁。
《解字》
 会意。「牛+八印」で、牛は、物の代表、八印は、両方にわける意を示し、何かを二つにわけること。八(両分する)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たるから、「牛+音符八」の会意兼形声文字と考えてもよい。
《単語家族》
班(わける)
会意。「牛+八印」で、牛は、物の代表、八印は、両方にわける意を示し、何かを二つにわけること。八(両分する)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たるから、「牛+音符八」の会意兼形声文字と考えてもよい。
《単語家族》
班(わける) 判(わける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
判(わける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 5画 十部 [二年]
区点=4030 16進=483E シフトJIS=94BC
《常用音訓》ハン/なか…ば
《音読み》 ハン
5画 十部 [二年]
区点=4030 16進=483E シフトJIS=94BC
《常用音訓》ハン/なか…ば
《音読み》 ハン
 〈b
〈b n〉
《訓読み》 なかば/なかばする(なかばす)/わかつ/はん
《名付け》 なか・なかば・なからい
《意味》
n〉
《訓読み》 なかば/なかばする(なかばす)/わかつ/はん
《名付け》 なか・なかば・なからい
《意味》
 {名}なかば。二つに等分した片方。「夜半」「半入江風半入雲=半バハ江風ニ入リ、半バハ雲ニ入ル」〔→杜甫〕▽「〜有半」とは、二分の一はみ出ること。「長一身有半=長サ一身有半」〔→論語〕
{名}なかば。二つに等分した片方。「夜半」「半入江風半入雲=半バハ江風ニ入リ、半バハ雲ニ入ル」〔→杜甫〕▽「〜有半」とは、二分の一はみ出ること。「長一身有半=長サ一身有半」〔→論語〕
 {動}なかばする(ナカバス)。半分に達する。「相半=相ヒ半バス」
{動}なかばする(ナカバス)。半分に達する。「相半=相ヒ半バス」
 {動}わかつ。半分にわける。〈同義語〉→判。「折半」
〔国〕はん。さいころの目で、奇数。〈対語〉→丁。
《解字》
{動}わかつ。半分にわける。〈同義語〉→判。「折半」
〔国〕はん。さいころの目で、奇数。〈対語〉→丁。
《解字》
 会意。「牛+八印」で、牛は、物の代表、八印は、両方にわける意を示し、何かを二つにわけること。八(両分する)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たるから、「牛+音符八」の会意兼形声文字と考えてもよい。
《単語家族》
班(わける)
会意。「牛+八印」で、牛は、物の代表、八印は、両方にわける意を示し、何かを二つにわけること。八(両分する)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たるから、「牛+音符八」の会意兼形声文字と考えてもよい。
《単語家族》
班(わける) 判(わける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
判(わける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
半価 ハンカ🔗⭐🔉
【半直】
ハンチ =半値。半分のねだん。『半額ハンガク・半価ハンカ』▽「直」は、値。
半円 ハンエン🔗⭐🔉
【半規】
ハンキ 円の半分。『半円ハンエン』。▽「規」は、コンパス。
半解 ハンカイ🔗⭐🔉
【半解】
ハンカイ 半分だけ理解する。物事の一部分しか知らないこと。「一知半解」
反映 ハンエイ🔗⭐🔉
【反映】
ハンエイ  光や色が反射して映る。また、水面などに映る。
光や色が反射して映る。また、水面などに映る。 影響が他に及んであらわれる。また、影響を及ぼしてあらわす。
影響が他に及んであらわれる。また、影響を及ぼしてあらわす。
 光や色が反射して映る。また、水面などに映る。
光や色が反射して映る。また、水面などに映る。 影響が他に及んであらわれる。また、影響を及ぼしてあらわす。
影響が他に及んであらわれる。また、影響を及ぼしてあらわす。
反歌 ハンカ🔗⭐🔉
【反歌】
ハンカ〔国〕長歌のあとに添える短歌。長歌の意味を要約したり補足したりする。かえしうた。
反影 ハンエイ🔗⭐🔉
【反影】
ハンエイ =反景。光が反射して映る。また、反射した光。照りかえし。
帆影 ハンエイ🔗⭐🔉
【帆影】
ハンエイ  帆の姿。
帆の姿。 遠く見える舟。
遠く見える舟。
 帆の姿。
帆の姿。 遠く見える舟。
遠く見える舟。
攀縁 ハンエン🔗⭐🔉
【攀縁】
ハンエン  「攀援
「攀援 」と同じ。
」と同じ。 俗事に心がひかれる。
俗事に心がひかれる。
 「攀援
「攀援 」と同じ。
」と同じ。 俗事に心がひかれる。
俗事に心がひかれる。
搬運 ハンウン🔗⭐🔉
【搬運】
ハンウン 荷物を運ぶ。運搬。
樊於期 ハンオキ🔗⭐🔉
【樊於期】
ハンオキ〈人名〉戦国時代、秦シンの将軍。とがめを受けて燕エンに逃亡。燕の太子丹タンが秦王暗殺を企てたとき、その成就を願い自らの首を献上。
煩紆 ハンウ🔗⭐🔉
【煩紆】
ハンウ うれいが心の中にわだかまる。
煩苛 ハンカ🔗⭐🔉
【煩苛】
ハンカ わずらわしくてやかましい。法律や注意などがこまかすぎてわずらわしいこと。
版画 ハンガ🔗⭐🔉
【版画】
ハンガ 木版・銅版・石版などで刷った絵。
犯意 ハンイ🔗⭐🔉
【犯意】
ハンイ 罪をおかす意志。
班位 ハンイ🔗⭐🔉
【班位】
ハンイ  位。席次。列位。
位。席次。列位。 同列の地位。
同列の地位。
 位。席次。列位。
位。席次。列位。 同列の地位。
同列の地位。
瘢痍 ハンイ🔗⭐🔉
【瘢痍】
ハンイ 傷あと。『瘢痕ハンコン・瘢創ハンソウ』
繁育 ハンイク🔗⭐🔉
【繁育】
ハンイク しげりそだつ。人や家畜などがよく成長すること。〈同義語〉蕃育。
繁栄 ハンエイ🔗⭐🔉
【繁栄】
ハンエイ 勢力が盛んになって栄える。
繁衍 ハンエン🔗⭐🔉
【繁衍】
ハンエン  草木が盛んにのびて広がる。
草木が盛んにのびて広がる。 子孫や親戚などが栄える。
子孫や親戚などが栄える。
 草木が盛んにのびて広がる。
草木が盛んにのびて広がる。 子孫や親戚などが栄える。
子孫や親戚などが栄える。
繁苛 ハンカ🔗⭐🔉
【繁苛】
ハンカ 法律・規則がこまごまとしていて煩わしくてきびしい。
繁華 ハンカ🔗⭐🔉
繁陰 ハンイン🔗⭐🔉
【繁陰】
ハンイン よくしげった木のかげ。
繙閲 ハンエツ🔗⭐🔉
【繙閲】
ハンエツ 書物を読んでしらべる。
繙繹 ハンエキ🔗⭐🔉
【繙繹】
ハンエキ 書物を読み、その内容をたどって理解する。
般逸 ハンイツ🔗⭐🔉
范雲 ハンウン🔗⭐🔉
【范雲】
ハンウン〈人名〉451〜503 南北朝時代、斉セイの詩人。南郷舞陰(河南省泌陽ヒツヨウ県北)の人。字アザナは彦竜ゲンリュウ。斉の竟陵王キョウリョウオウ(蕭子良ショウシリョウ)をめぐる、竟陵の八友のひとり。
藩衛 ハンエイ🔗⭐🔉
【蕃衛】
ハンエイ =藩衛。 周囲をおおうかきねのように、王室を守ること。
周囲をおおうかきねのように、王室を守ること。 守り。特に、都の周囲にあって、天子を守る諸侯のこと。「外無諸侯以為蕃衛=外ニ諸侯ノモッテ蕃衛タル無シ」〔曹冏〕
守り。特に、都の周囲にあって、天子を守る諸侯のこと。「外無諸侯以為蕃衛=外ニ諸侯ノモッテ蕃衛タル無シ」〔曹冏〕
 周囲をおおうかきねのように、王室を守ること。
周囲をおおうかきねのように、王室を守ること。 守り。特に、都の周囲にあって、天子を守る諸侯のこと。「外無諸侯以為蕃衛=外ニ諸侯ノモッテ蕃衛タル無シ」〔曹冏〕
守り。特に、都の周囲にあって、天子を守る諸侯のこと。「外無諸侯以為蕃衛=外ニ諸侯ノモッテ蕃衛タル無シ」〔曹冏〕
藩 はん🔗⭐🔉
【藩】
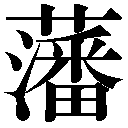 18画 艸部 [常用漢字]
区点=4045 16進=484D シフトJIS=94CB
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン
18画 艸部 [常用漢字]
区点=4045 16進=484D シフトJIS=94CB
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン /ホン
/ホン 〈f
〈f n〉
《訓読み》 まがき/はん
《名付け》 かき
《意味》
n〉
《訓読み》 まがき/はん
《名付け》 かき
《意味》
 {名}まがき。枝を逆方向にぐっとそらせてからませたいけがき。広く、かきね。「藩籬ハンリ」「羝羊触藩=羝羊藩ニ触ル」〔→易経〕
{名}まがき。枝を逆方向にぐっとそらせてからませたいけがき。広く、かきね。「藩籬ハンリ」「羝羊触藩=羝羊藩ニ触ル」〔→易経〕
 {名}王室を守るかきねの役をする諸侯。のち、地方を守る長官。「藩屏ハンペイ」
{名}王室を守るかきねの役をする諸侯。のち、地方を守る長官。「藩屏ハンペイ」
 {名}諸侯の領土。地域。「藩国」「吾、願游於其藩=吾、願ハクハソノ藩ニ游バン」〔→荘子〕
{名}諸侯の領土。地域。「藩国」「吾、願游於其藩=吾、願ハクハソノ藩ニ游バン」〔→荘子〕
 {動}かきねをつくって害敵から防衛する。「藩衛」
〔国〕はん。江戸時代、大名が領する土地・組織・人員の総称。「水戸藩」
《解字》
形声。「艸+音符潘ハン」。まがきをあらわす。攀は字の上部(林+爻)が本字であり、枝を逆方向にそらせてからませたいけがきのこと。藩はそれに当てた字。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かきねをつくって害敵から防衛する。「藩衛」
〔国〕はん。江戸時代、大名が領する土地・組織・人員の総称。「水戸藩」
《解字》
形声。「艸+音符潘ハン」。まがきをあらわす。攀は字の上部(林+爻)が本字であり、枝を逆方向にそらせてからませたいけがきのこと。藩はそれに当てた字。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
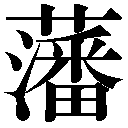 18画 艸部 [常用漢字]
区点=4045 16進=484D シフトJIS=94CB
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン
18画 艸部 [常用漢字]
区点=4045 16進=484D シフトJIS=94CB
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン /ホン
/ホン 〈f
〈f n〉
《訓読み》 まがき/はん
《名付け》 かき
《意味》
n〉
《訓読み》 まがき/はん
《名付け》 かき
《意味》
 {名}まがき。枝を逆方向にぐっとそらせてからませたいけがき。広く、かきね。「藩籬ハンリ」「羝羊触藩=羝羊藩ニ触ル」〔→易経〕
{名}まがき。枝を逆方向にぐっとそらせてからませたいけがき。広く、かきね。「藩籬ハンリ」「羝羊触藩=羝羊藩ニ触ル」〔→易経〕
 {名}王室を守るかきねの役をする諸侯。のち、地方を守る長官。「藩屏ハンペイ」
{名}王室を守るかきねの役をする諸侯。のち、地方を守る長官。「藩屏ハンペイ」
 {名}諸侯の領土。地域。「藩国」「吾、願游於其藩=吾、願ハクハソノ藩ニ游バン」〔→荘子〕
{名}諸侯の領土。地域。「藩国」「吾、願游於其藩=吾、願ハクハソノ藩ニ游バン」〔→荘子〕
 {動}かきねをつくって害敵から防衛する。「藩衛」
〔国〕はん。江戸時代、大名が領する土地・組織・人員の総称。「水戸藩」
《解字》
形声。「艸+音符潘ハン」。まがきをあらわす。攀は字の上部(林+爻)が本字であり、枝を逆方向にそらせてからませたいけがきのこと。藩はそれに当てた字。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かきねをつくって害敵から防衛する。「藩衛」
〔国〕はん。江戸時代、大名が領する土地・組織・人員の総称。「水戸藩」
《解字》
形声。「艸+音符潘ハン」。まがきをあらわす。攀は字の上部(林+爻)が本字であり、枝を逆方向にそらせてからませたいけがきのこと。藩はそれに当てた字。
《類義》
→垣
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
藩垣 ハンエン🔗⭐🔉
【藩垣】
ハンエン かきね。外側の守り。国家の守りとなる諸侯にたとえることもある。▽「詩経」大雅・板の「价人維藩、大師維垣=价人ハ維藩、大師ハ維垣」から。
返景 ハンエイ🔗⭐🔉
飯盂 ハンウ🔗⭐🔉
【飯盂】
ハンウ めしをもる容器。おはち。『飯鉢ハンハツ』
飯顆 ハンカ🔗⭐🔉
【飯粒】
ハンリュウ めしつぶ。ごはんつぶ。『飯顆ハンカ』
漢字源に「はん」で始まるの検索結果 1-46。もっと読み込む
 意味が反対であること。反義。「反意語」
意味が反対であること。反義。「反意語」
 互いに助けあう。また、たよりにする。〔
互いに助けあう。また、たよりにする。〔