複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (82)
は【破】🔗⭐🔉
は【破】
①雅楽で、序・破・急3楽章の一つ。拍節的リズムで、ゆったりと奏される楽章。曲によっては入破じゅはという。
②能楽では、楽章でなく、曲風で序・破・急を分け、破は変化をつけた部分。
は‐え【破壊】‥ヱ🔗⭐🔉
は‐え【破壊】‥ヱ
やぶれこわれること。やぶりこわすこと。はかい。日本霊異記下「僧の過を説く時は、多くの人の信を―し」
は‐おく【破屋】‥ヲク🔗⭐🔉
は‐おく【破屋】‥ヲク
こわれた家。あばらや。廃屋。
は‐か【破瓜】‥クワ🔗⭐🔉
は‐か【破瓜】‥クワ
①(「瓜」の字を二分すると、二つの「八」の字の形となるからいう)
㋐女性の16歳の称。思春期の年ごろ。「―期」
㋑(8の8倍は64であるからいう)男性の64歳の称。
②女性の処女膜の破れること。
は‐かい【破戒】🔗⭐🔉
は‐かい【破戒】
戒を破ること。受戒した者が戒法に違うこと。「―僧」↔持戒。
⇒はかい‐むざん【破戒無慙】
⇒破戒の出家は牛に生るる
はかい【破戒】(作品名)🔗⭐🔉
はかい【破戒】
長編小説。島崎藤村作。1906年(明治39)刊。被差別部落出身の小学校教師瀬川丑松うしまつが、父の戒めを破って自分の素姓を告白し、周囲の因襲と戦う苦悩を描く。日本自然主義文学の先駆。
→文献資料[破戒]
は‐かい【破壊】‥クワイ🔗⭐🔉
は‐かい【破壊】‥クワイ
うちこわすこと。うちこわされること。こわれること。「建物を―する」
⇒はかい‐おうりょく【破壊応力】
⇒はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】
⇒はかい‐しけん【破壊試験】
⇒はかい‐てき【破壊的】
⇒はかい‐りょく【破壊力】
はかい‐おうりょく【破壊応力】‥クワイ‥🔗⭐🔉
はかい‐おうりょく【破壊応力】‥クワイ‥
物体が破壊せずにもちこたえられる最大の応力。破壊強さ。極限強さ。
⇒は‐かい【破壊】
はかい‐しけん【破壊試験】‥クワイ‥🔗⭐🔉
はかい‐しけん【破壊試験】‥クワイ‥
①材料試験の一種。材料から採取した試験片または材料そのものに破壊するまで荷重を加え、材料の靱性・強度その他の機械的諸性質を検査するもの。
②機械などを、それが破壊するような厳しい条件で試験すること。
⇒は‐かい【破壊】
○破戒の出家は牛に生るるはかいのしゅっけはうしにうまるる🔗⭐🔉
○破戒の出家は牛に生るるはかいのしゅっけはうしにうまるる
破戒僧は次の世には牛になる意で、僧の品行をいましめていう語。狂言、骨皮「総じて―といふ」
⇒は‐かい【破戒】
はかい‐むざん【破戒無慙】
仏の定めた戒を破って良心に恥じないこと。
⇒は‐かい【破戒】
ばか‐いも【馬鹿芋】
(多産をあざけっていう)ジャガイモの異称。
はかい‐りょく【破壊力】‥クワイ‥
ものを破壊する力。比喩的に、その言動が相手を打ちのめす力。「―の強い爆薬」「―のある発言」
⇒は‐かい【破壊】
バガヴァッド‐ギーター【Bhagavad-gītā 梵】
(「聖なる神の歌」の意)古代インドの大叙事詩「マハーバーラタ」中の一詩編。正義の戦争、義務についてヴィシュヌ神の化身クリシュナが王子アルジュナに説く。ヒンドゥー教徒の最上の聖典。ギーター。
はかい‐むざん【破戒無慙】🔗⭐🔉
はかい‐むざん【破戒無慙】
仏の定めた戒を破って良心に恥じないこと。
⇒は‐かい【破戒】
はかい‐りょく【破壊力】‥クワイ‥🔗⭐🔉
はかい‐りょく【破壊力】‥クワイ‥
ものを破壊する力。比喩的に、その言動が相手を打ちのめす力。「―の強い爆薬」「―のある発言」
⇒は‐かい【破壊】
はか‐き【破瓜期】‥クワ‥🔗⭐🔉
はか‐き【破瓜期】‥クワ‥
月経の始まる年ごろ。思春期。
は‐かく【破格】🔗⭐🔉
は‐かく【破格】
①普通のきまりや先例を破ること。島崎藤村、夜明け前「あるひは―な外国使臣の参内に」
②普通以上のこと。特別。泉鏡花、歌行灯「―のお附合ひ、恐おそれ多いな」
はか‐びょう【破瓜病】‥クワビヤウ🔗⭐🔉
はか‐びょう【破瓜病】‥クワビヤウ
統合失調症の一型。10歳代後半から20歳代初めに不眠・憂鬱症・厭世的となり、幻視・幻聴・妄想などを起こす。破瓜期前後に起こることからいう。
は‐がん【破顔】🔗⭐🔉
は‐がん【破顔】
顔をほころばせて笑うこと。にこやかに笑うこと。
⇒はがん‐いっしょう【破顔一笑】
はがん‐いっしょう【破顔一笑】‥セウ🔗⭐🔉
はがん‐いっしょう【破顔一笑】‥セウ
顔をほころばせてにっこり笑うこと。「朗報に―する」
⇒は‐がん【破顔】
は‐き【破棄・破毀】🔗⭐🔉
は‐き【破棄・破毀】
①やぶりすてること。やぶりこわすこと。また、やぶれこわれること。
②取決めなどを一方的に取り消すこと。「契約を―する」
③〔法〕上訴裁判所が上訴に理由があるとして原判決を取り消すこと。民事では上告審にのみ用いる。
はき‐いそう【破棄移送】🔗⭐🔉
はき‐いそう【破棄移送】
破棄3して事件を原裁判所と同等の他の裁判所へ直接移すこと。
はき‐さしもどし【破棄差戻し】🔗⭐🔉
はき‐さしもどし【破棄差戻し】
上訴裁判所が原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻すこと。
はき‐じはん【破棄自判】🔗⭐🔉
はき‐じはん【破棄自判】
上訴裁判所が原判決を破棄して、事件について自ら裁判すること。
は‐きゃく【破却】🔗⭐🔉
は‐きゃく【破却】
やぶること。こわすこと。
○破鏡の嘆きはきょうのなげき🔗⭐🔉
○破鏡の嘆きはきょうのなげき
夫婦離別のなげき。
⇒は‐きょう【破鏡】
○破鏡再び照らさずはきょうふたたびてらさず🔗⭐🔉
○破鏡再び照らさずはきょうふたたびてらさず
[伝灯録17]夫婦の離別など、いったん破れた物事は再びもとのようにかえすことができないたとえ。破鏡重ねて照らさず。「覆水盆にかえらず」と同趣意。→落花枝に帰らず(「落花」成句)
⇒は‐きょう【破鏡】
は‐きょく【破局】
事の破れた局面。悲劇的な終末。「―を迎える」
は‐ぎり【葉桐】
江戸時代の金銀貨幣に極印ごくいんとして打った桐の葉の形。
は‐ぎり【歯切り】
①はがみ。はぎしり。好色一代男4「―して細腰もだえて」
②(ハキリとも)鋸・歯車などの歯を切るやすり。〈日葡辞書〉
⇒はぎり‐ばん【歯切り盤】
はぎり‐ばん【歯切り盤】
歯切りカッターを用いて歯車の歯を切る工作機械の総称。
⇒は‐ぎり【歯切り】
は‐ぎれ【刃切れ】
刀の刃先から地じに向かって真横に入っている割れ目。刃切れのある刀は差料さしりょうにならない。
は‐ぎれ【歯切れ】
①歯でかみ切るときの感じ。「―のよいたくあん」
②人の発言やしゃべり方の調子。「―のいい台詞せりふ」「―の悪い説明」
は‐ぎれ【端切れ】
裁ち残りの布地。はんぱのきれ。
はぎ‐わら【萩原】‥ハラ
⇒はぎはら
はぎわら【萩原】‥ハラ
姓氏の一つ。
⇒はぎわら‐さくたろう【萩原朔太郎】
⇒はぎわら‐ひろみち【萩原広道】
⇒はぎわら‐ゆうすけ【萩原雄祐】
はぎわら‐さくたろう【萩原朔太郎】‥ハラ‥ラウ
詩人。群馬県生れ。慶大中退。口語自由詩を芸術的に完成して新風を樹立。詩集「月に吠える」「青猫」「氷島」、詩論集「新しき欲情」「虚妄の正義」など。(1886〜1942)
萩原朔太郎
提供:毎日新聞社
 →作品:『月に吠える』
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ひろみち【萩原広道】‥ハラ‥
幕末の国学者。岡山の人。大国(野之口)隆正に学び、源氏物語に精通。著「源氏物語評釈」「本教提綱」など。(1815〜1863)
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ゆうすけ【萩原雄祐】‥ハライウ‥
天文学者。大阪生れ。東大卒。東京天文台長。天体力学、理論天体物理学を専攻。著「天体力学」など。文化勲章。(1897〜1979)
萩原雄祐
提供:毎日新聞社
→作品:『月に吠える』
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ひろみち【萩原広道】‥ハラ‥
幕末の国学者。岡山の人。大国(野之口)隆正に学び、源氏物語に精通。著「源氏物語評釈」「本教提綱」など。(1815〜1863)
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ゆうすけ【萩原雄祐】‥ハライウ‥
天文学者。大阪生れ。東大卒。東京天文台長。天体力学、理論天体物理学を専攻。著「天体力学」など。文化勲章。(1897〜1979)
萩原雄祐
提供:毎日新聞社
 ⇒はぎわら【萩原】
はきん【巴金】
(Ba Jin)(パキンとも)中国の小説家。本名、李尭棠ぎょうとう。四川の人。フランスに留学。アナーキズムの影響を強く受ける。文化大革命で迫害されたが、1977年に名誉回復。作「滅亡」「家」「第四病室」「憩園」「寒夜」など。「随想録」は文革批判の異色作。(1904〜2005)
は‐ぎん【端銀】
はしたがね。傾城禁短気「金二歩に―そへて」
はく【白】
(呉音はビャク)
①しろいこと。しろ。
②五行の一つ。西。秋。
③白耳義ベルギーの略。
はく【伯】
①兄弟中の年長者。長兄。
②神祇官の長官。
③五等爵の第3位。伯爵。
④伯耆国ほうきのくにの略。
⑤伯剌西爾ブラジルの略。
はく【帛】
きぬ。絹布。
はく【拍】
(慣用音はヒョウ)
①手のひらを打ち合わせること。手でうつこと。
②西洋音楽で、音の長さの基本単位。また、拍子の周期の中で繰り返される強弱の各部分。強拍と弱拍とより成る。→拍子ひょうし。
③〔言〕モーラ。
はく【泊】
宿をとること。宿泊の数をかぞえる語。「2―3日」
はく【陌】
「百」の大字。
はく【博】
①博士はくしの略。
②博覧会の略。
はく【箔】
①金・銀・銅・錫・真鍮などをたたいて、紙のように薄く平らに延ばしたもの。日葡辞書「ハクヲヲク」
②能装束の縫箔ぬいはくまたは摺箔すりはくの略。
⇒箔が付く
はく【魄】
たましい。この世にとどまるという陰いんの霊魂。↔魂こん
は・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
は・く【吐く】
〔他五〕
①口の中のものを外に出す。地蔵十輪経元慶点「咸ことごとく共に唾つはきをハキて言はく」。宇治拾遺物語11「川にざぶりと入る程に…くくみたる水―・きすてて」。日葡辞書「チヲハク」
②胃の中のものを口外に出す。もどす。「酔って―・く」
③言葉に出す。語る。口外する。天草本伊曾保物語「忠言をこそえ言はずとも、せめて讒言を―・くな」。「本音を―・く」
④内にあるものを外へ出す。「煙を―・く」
は・く【佩く・帯く・着く・穿く・履く】
〔他五・下二〕
①(多く「佩く」と書く)腰につける。さす。帯びる。古事記中「やつめさす出雲建いずもたけるが―・ける太刀つづら多纏さわまきさ身なしにあはれ」「一つ松人にありせば太刀―・けましを」
②《穿》腰から下の部分を覆う衣類を身につける。うがつ。「ズボンを―・く」
③《履》下駄・靴・足袋たび・靴下などを、足先につける。万葉集9「髪だにも掻きは梳らず履くつをだに―・かず行けども」。源氏物語浮舟「わが沓を―・かせて、自らは供なる人々のあやしきものを―・きたり」。天草本伊曾保物語「足袋を―・き」
④弦を弓にかける。万葉集14「陸奥の安太多良あだたら真弓はじき置きて反せらしめきなば弦つら―・かめかも」。万葉集2「梓弓弦緒つらお取り―・け引く人は」
は・く【捌く】
〔自下二〕
⇒はける(下一)
は・く【掃く】
〔他五〕
①箒などで払い清める。万葉集19「梳くしも見じ屋内やぬちも―・かじ草枕旅行く君を斎いわふと思ひて」。平家物語11「―・いたり拭のごうたり、塵拾ひ、手づから掃除せられけり」。「庭を―・く」
②祓はらい除く。万葉集20「ちはやぶる神をことむけまつろへぬ人をも和やわし―・き清め仕へまつりて」
③(「刷く」と書く)眉墨・白粉などを塗る。ぬりつける。「眉を―・く」
④孵化した毛蚕けごを蚕卵紙から取って蚕座へうつす。→掃立て2。
⑤上方の遊里語で、箒で女を掃く意から、多くの遊女を買い一人に定めないことをいう。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「わたしも大かたお―・きなさるのじやあろふナア」
⇒掃いて捨てるほど
は‐ぐ【爬具】
水底や砂泥をかきおこして、貝類を採取する道具の総称。
ハグ【hug】
抱きしめること。特に、欧米式の挨拶で抱き合うこと。
は・ぐ【禿ぐ】
〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【矧ぐ】
(古くはハク。「佩く」と同語か)
[一]〔他五〕
竹に羽をつけて矢をつくる。万葉集7「淡海おうみのや矢橋の小竹しのを矢―・かずて」
[二]〔他下二〕
弓に矢をつがえる。太平記3「弛はずせる弓に矢を―・げて射んとすれども」
は・ぐ【剥ぐ】
[一]〔他五〕
①表面をむきとる。はがす。へがす。神代紀上「真名鹿まなかの皮を全剥うつはぎに―・ぎて」。万葉集16「もむ楡を五百枝いおえ―・ぎ垂り」。「爪を―・ぐ」
②身につけたものをぬがせ取る。裸にする。宇津保物語祭使「賜はりたまふ司は、盗人のみ集ひて人の衣を―・ぎ取り、飯酒をさがし食む」
③官位などを取り上げる。奪う。「官を―・ぐ」
[二]〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【接ぐ】
〔他五〕
二つのものをつぎ合わす。「布を―・ぐ」
ばく【幕】
①幕府、特に徳川幕府の略。「―末」
②幕僚本部の略。
→まく(幕)
ばく【漠】
①ひろびろして何もないさま。
②とりとめのないさま。「―とした話」
ばく【縛】
①しばること。しばられること。なわめ。「―に就く」
②煩悩。「―の縄」「繋縛けばく」
ばく【貘・獏】
①ウマ目バク科の哺乳類の総称。中南米のアメリカバク・ヤマバク・ベアードバクの3種と東南アジアのマレーバクの1属4種がいる。体長1.5〜2メートル、体はずんぐりして、吻ふんが突き出ており、四肢は長くない。アメリカバクは毛色は暗褐色、マレーバクは前肢の後から腰にかけて白い。森林や水辺のやぶで単独か親子で生活し、薄明・暮時に活動、草や芋、果実を食べる。アメリカバク以外の3種は絶滅の危機にある。
マレーばく
⇒はぎわら【萩原】
はきん【巴金】
(Ba Jin)(パキンとも)中国の小説家。本名、李尭棠ぎょうとう。四川の人。フランスに留学。アナーキズムの影響を強く受ける。文化大革命で迫害されたが、1977年に名誉回復。作「滅亡」「家」「第四病室」「憩園」「寒夜」など。「随想録」は文革批判の異色作。(1904〜2005)
は‐ぎん【端銀】
はしたがね。傾城禁短気「金二歩に―そへて」
はく【白】
(呉音はビャク)
①しろいこと。しろ。
②五行の一つ。西。秋。
③白耳義ベルギーの略。
はく【伯】
①兄弟中の年長者。長兄。
②神祇官の長官。
③五等爵の第3位。伯爵。
④伯耆国ほうきのくにの略。
⑤伯剌西爾ブラジルの略。
はく【帛】
きぬ。絹布。
はく【拍】
(慣用音はヒョウ)
①手のひらを打ち合わせること。手でうつこと。
②西洋音楽で、音の長さの基本単位。また、拍子の周期の中で繰り返される強弱の各部分。強拍と弱拍とより成る。→拍子ひょうし。
③〔言〕モーラ。
はく【泊】
宿をとること。宿泊の数をかぞえる語。「2―3日」
はく【陌】
「百」の大字。
はく【博】
①博士はくしの略。
②博覧会の略。
はく【箔】
①金・銀・銅・錫・真鍮などをたたいて、紙のように薄く平らに延ばしたもの。日葡辞書「ハクヲヲク」
②能装束の縫箔ぬいはくまたは摺箔すりはくの略。
⇒箔が付く
はく【魄】
たましい。この世にとどまるという陰いんの霊魂。↔魂こん
は・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
は・く【吐く】
〔他五〕
①口の中のものを外に出す。地蔵十輪経元慶点「咸ことごとく共に唾つはきをハキて言はく」。宇治拾遺物語11「川にざぶりと入る程に…くくみたる水―・きすてて」。日葡辞書「チヲハク」
②胃の中のものを口外に出す。もどす。「酔って―・く」
③言葉に出す。語る。口外する。天草本伊曾保物語「忠言をこそえ言はずとも、せめて讒言を―・くな」。「本音を―・く」
④内にあるものを外へ出す。「煙を―・く」
は・く【佩く・帯く・着く・穿く・履く】
〔他五・下二〕
①(多く「佩く」と書く)腰につける。さす。帯びる。古事記中「やつめさす出雲建いずもたけるが―・ける太刀つづら多纏さわまきさ身なしにあはれ」「一つ松人にありせば太刀―・けましを」
②《穿》腰から下の部分を覆う衣類を身につける。うがつ。「ズボンを―・く」
③《履》下駄・靴・足袋たび・靴下などを、足先につける。万葉集9「髪だにも掻きは梳らず履くつをだに―・かず行けども」。源氏物語浮舟「わが沓を―・かせて、自らは供なる人々のあやしきものを―・きたり」。天草本伊曾保物語「足袋を―・き」
④弦を弓にかける。万葉集14「陸奥の安太多良あだたら真弓はじき置きて反せらしめきなば弦つら―・かめかも」。万葉集2「梓弓弦緒つらお取り―・け引く人は」
は・く【捌く】
〔自下二〕
⇒はける(下一)
は・く【掃く】
〔他五〕
①箒などで払い清める。万葉集19「梳くしも見じ屋内やぬちも―・かじ草枕旅行く君を斎いわふと思ひて」。平家物語11「―・いたり拭のごうたり、塵拾ひ、手づから掃除せられけり」。「庭を―・く」
②祓はらい除く。万葉集20「ちはやぶる神をことむけまつろへぬ人をも和やわし―・き清め仕へまつりて」
③(「刷く」と書く)眉墨・白粉などを塗る。ぬりつける。「眉を―・く」
④孵化した毛蚕けごを蚕卵紙から取って蚕座へうつす。→掃立て2。
⑤上方の遊里語で、箒で女を掃く意から、多くの遊女を買い一人に定めないことをいう。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「わたしも大かたお―・きなさるのじやあろふナア」
⇒掃いて捨てるほど
は‐ぐ【爬具】
水底や砂泥をかきおこして、貝類を採取する道具の総称。
ハグ【hug】
抱きしめること。特に、欧米式の挨拶で抱き合うこと。
は・ぐ【禿ぐ】
〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【矧ぐ】
(古くはハク。「佩く」と同語か)
[一]〔他五〕
竹に羽をつけて矢をつくる。万葉集7「淡海おうみのや矢橋の小竹しのを矢―・かずて」
[二]〔他下二〕
弓に矢をつがえる。太平記3「弛はずせる弓に矢を―・げて射んとすれども」
は・ぐ【剥ぐ】
[一]〔他五〕
①表面をむきとる。はがす。へがす。神代紀上「真名鹿まなかの皮を全剥うつはぎに―・ぎて」。万葉集16「もむ楡を五百枝いおえ―・ぎ垂り」。「爪を―・ぐ」
②身につけたものをぬがせ取る。裸にする。宇津保物語祭使「賜はりたまふ司は、盗人のみ集ひて人の衣を―・ぎ取り、飯酒をさがし食む」
③官位などを取り上げる。奪う。「官を―・ぐ」
[二]〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【接ぐ】
〔他五〕
二つのものをつぎ合わす。「布を―・ぐ」
ばく【幕】
①幕府、特に徳川幕府の略。「―末」
②幕僚本部の略。
→まく(幕)
ばく【漠】
①ひろびろして何もないさま。
②とりとめのないさま。「―とした話」
ばく【縛】
①しばること。しばられること。なわめ。「―に就く」
②煩悩。「―の縄」「繋縛けばく」
ばく【貘・獏】
①ウマ目バク科の哺乳類の総称。中南米のアメリカバク・ヤマバク・ベアードバクの3種と東南アジアのマレーバクの1属4種がいる。体長1.5〜2メートル、体はずんぐりして、吻ふんが突き出ており、四肢は長くない。アメリカバクは毛色は暗褐色、マレーバクは前肢の後から腰にかけて白い。森林や水辺のやぶで単独か親子で生活し、薄明・暮時に活動、草や芋、果実を食べる。アメリカバク以外の3種は絶滅の危機にある。
マレーばく
 アメリカバク
提供:東京動物園協会
アメリカバク
提供:東京動物園協会
 ベアードバク
提供:東京動物園協会
ベアードバク
提供:東京動物園協会
 マレーバク
提供:東京動物園協会
マレーバク
提供:東京動物園協会
 ②中国で想像上の動物。形は熊に、鼻は象に、目は犀に、尾は牛に、脚は虎に似、毛は黒白の斑で、頭が小さく、人の悪夢を食うと伝え、その皮を敷いて寝ると邪気を避けるという。
ばく【瀑】
高所から落ちる流水。たき。
ばく【爆】
爆弾・爆弾攻撃の略。
ば・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
ば‐ぐ【馬具】
馬の装具。鞍・轡くつわ・鐙あぶみ・手綱などの総称。
バグ【bug】
(虫の意)コンピューターのプログラムの誤り・欠陥。
パグ【pug】
イヌの一品種。体高約25センチメートル、短毛で、垂れ耳、巻尾。顔はチンのようにしゃくれ、皺だらけ。中国で愛玩用に作出。
パグ
②中国で想像上の動物。形は熊に、鼻は象に、目は犀に、尾は牛に、脚は虎に似、毛は黒白の斑で、頭が小さく、人の悪夢を食うと伝え、その皮を敷いて寝ると邪気を避けるという。
ばく【瀑】
高所から落ちる流水。たき。
ばく【爆】
爆弾・爆弾攻撃の略。
ば・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
ば‐ぐ【馬具】
馬の装具。鞍・轡くつわ・鐙あぶみ・手綱などの総称。
バグ【bug】
(虫の意)コンピューターのプログラムの誤り・欠陥。
パグ【pug】
イヌの一品種。体高約25センチメートル、短毛で、垂れ耳、巻尾。顔はチンのようにしゃくれ、皺だらけ。中国で愛玩用に作出。
パグ
 はく‐あ【白堊・白亜】
(ハクアクの慣用読み。「堊」は、白土の意)
①泥質の軟らかい石灰岩。ココリス・有孔虫などの遺骸や貝殻に由来する泥灰質粉末から成る浅海成層をつくる。白墨・石灰の原料、白壁の塗料とする。チョーク。
②白壁。「―の殿堂」
⇒はくあ‐かん【白堊館】
⇒はくあ‐き【白亜紀】
⇒はくあ‐けい【白亜系】
⇒はくあ‐しつ【白亜質】
はく‐あい【博愛】
[孝経三才章]ひろく愛すること。平等に愛すること。性霊集4「天仁慈を仮して―是を務む」。「―の精神」
⇒はくあい‐しゃ【博愛社】
⇒はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
はくあい‐しゃ【博愛社】
日本赤十字社の前身。1877年(明治10)佐野常民・大給恒おぎゅうゆずるらが西南戦争の両軍の死傷者救護を動機として創設。
⇒はく‐あい【博愛】
はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
個人的利己心、人種的偏見、国家的利益、宗教的またはイデオロギー的党派性を捨てて人類全体の福祉増進のために、全人類はすべて平等に相愛すべきものであるとする主張。→汎愛はんあい主義
⇒はく‐あい【博愛】
はくあ‐かん【白堊館】‥クワン
ホワイト‐ハウスの訳語。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐き【白亜紀】
(Cretaceous Period)地質年代のうち、中生代の最後の時代。約1億4000万年前から6500万年前まで。海が著しく広がり、ドーヴァー海峡などの白亜層が形成された。末期にはアルプス造山運動が起こった。アンモナイト・爬虫類(特に恐竜)などが栄えたが白亜紀末に絶滅。植物は羊歯しだ類・裸子植物が前半に多く、後半には被子植物が繁茂。→地質年代(表)。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐けい【白亜系】
白亜紀に形成された地層。日本では北海道や西日本の太平洋岸に多い。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐しつ【白亜質】
(→)セメント質に同じ。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあん【伯庵】
(江戸幕府の医師、曾谷そだに伯庵が愛蔵していたからという)桃山末期から江戸初期頃の作とされる大振りの茶碗。また、それと色・釉薬・形状その他特徴を同じくするもの。伯庵茶碗。
はく‐い【白衣】
①白い色の衣服。「―を着た医者」
②官位のない卑しいもの。布衣。庶人。
→びゃくえ。
⇒はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
はくい【羽咋】‥クヒ
石川県中部、能登半島西側基部にある市。邑知おうち潟干拓地と砂丘上に位置し、能登の中心都市。繊維工業が盛ん。千里浜ちりはま海水浴場がある。人口2万5千。
羽咋 千里浜なぎさドライブウェイ
撮影:新海良夫
はく‐あ【白堊・白亜】
(ハクアクの慣用読み。「堊」は、白土の意)
①泥質の軟らかい石灰岩。ココリス・有孔虫などの遺骸や貝殻に由来する泥灰質粉末から成る浅海成層をつくる。白墨・石灰の原料、白壁の塗料とする。チョーク。
②白壁。「―の殿堂」
⇒はくあ‐かん【白堊館】
⇒はくあ‐き【白亜紀】
⇒はくあ‐けい【白亜系】
⇒はくあ‐しつ【白亜質】
はく‐あい【博愛】
[孝経三才章]ひろく愛すること。平等に愛すること。性霊集4「天仁慈を仮して―是を務む」。「―の精神」
⇒はくあい‐しゃ【博愛社】
⇒はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
はくあい‐しゃ【博愛社】
日本赤十字社の前身。1877年(明治10)佐野常民・大給恒おぎゅうゆずるらが西南戦争の両軍の死傷者救護を動機として創設。
⇒はく‐あい【博愛】
はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
個人的利己心、人種的偏見、国家的利益、宗教的またはイデオロギー的党派性を捨てて人類全体の福祉増進のために、全人類はすべて平等に相愛すべきものであるとする主張。→汎愛はんあい主義
⇒はく‐あい【博愛】
はくあ‐かん【白堊館】‥クワン
ホワイト‐ハウスの訳語。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐き【白亜紀】
(Cretaceous Period)地質年代のうち、中生代の最後の時代。約1億4000万年前から6500万年前まで。海が著しく広がり、ドーヴァー海峡などの白亜層が形成された。末期にはアルプス造山運動が起こった。アンモナイト・爬虫類(特に恐竜)などが栄えたが白亜紀末に絶滅。植物は羊歯しだ類・裸子植物が前半に多く、後半には被子植物が繁茂。→地質年代(表)。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐けい【白亜系】
白亜紀に形成された地層。日本では北海道や西日本の太平洋岸に多い。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐しつ【白亜質】
(→)セメント質に同じ。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあん【伯庵】
(江戸幕府の医師、曾谷そだに伯庵が愛蔵していたからという)桃山末期から江戸初期頃の作とされる大振りの茶碗。また、それと色・釉薬・形状その他特徴を同じくするもの。伯庵茶碗。
はく‐い【白衣】
①白い色の衣服。「―を着た医者」
②官位のない卑しいもの。布衣。庶人。
→びゃくえ。
⇒はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
はくい【羽咋】‥クヒ
石川県中部、能登半島西側基部にある市。邑知おうち潟干拓地と砂丘上に位置し、能登の中心都市。繊維工業が盛ん。千里浜ちりはま海水浴場がある。人口2万5千。
羽咋 千里浜なぎさドライブウェイ
撮影:新海良夫
 はく‐い【伯夷】
「伯夷叔斉しゅくせい」参照。
⇒はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
はく・い【白い】
〔形〕
上等である、良い、美しいの意の隠語。滑稽本、妙竹林話七偏人「面の―・いのを一人よんで呉んなせへ」
ばく‐い【幕威】‥ヰ
幕府の威光。
はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
ともに殷いんの処士で、伯夷が兄、叔斉が弟。周の武王が殷の紂ちゅう王を討つに当たり、臣が君を弑しいする不可を説いていさめたが聞き入れられなかった。周が天下を統一すると、その禄を食むことを拒んで首陽山に隠れ、ともに餓死したと伝える。清廉潔白な人のたとえとする。
⇒はく‐い【伯夷】
はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
看護婦の美称。
⇒はく‐い【白衣】
はく‐いれ【箔入れ】
(→)「箔押し」に同じ。
はくいん【白隠】
江戸中期の臨済宗の僧。名は慧鶴えかく、号は鵠林。駿河の人。若くして各地で修行、京都妙心寺第一座となった後も諸国を遍歴教化、駿河の松蔭寺などを復興したほか多くの信者を集め、臨済宗中興の祖と称された。気魄ある禅画をよくした。諡号しごうは神機独妙禅師・正宗国師。著「荊叢毒蘂」「息耕録」「槐安国語」「遠羅天釜おらでがま」「夜船閑話」など。(1685〜1768)
はく‐いん【博引】
ひろく例を引用すること。
⇒はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】
はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】‥バウ‥
広範囲に多くの例を引き、証拠を示して説明すること。
⇒はく‐いん【博引】
はく‐う【白雨】
ゆうだち。にわかあめ。〈[季]夏〉
ばく‐う【麦雨】
麦の熟するころに降る雨。
バクー【Baku】
カスピ海に面したアゼルバイジャン共和国の首都。カスピ海に突出するアプシェロン半島の南岸にあり、近郊には油田地帯が展開。人口184万8千(2004)。
パグウォッシュ‐かいぎ【パグウォッシュ会議】‥クワイ‥
1955年の「ラッセル‐アインシュタイン宣言」に基づき、57年カナダのパグウォッシュ(Pugwash)で開かれた科学者の国際会議。核兵器廃絶を始めとして、科学と平和の問題を討議。以後、随時世界各地で開催。ノーベル平和賞。
はく‐うち【箔打ち】
金銀を箔にうちのばすこと。また、その職人。
バクーニン【Mikhail Aleksandrovich Bakunin】
ロシアの無政府主義者。1848〜49年ヨーロッパの革命運動に活躍。シベリア流刑中脱走し、亡命。第一インターナショナルに参加、のちマルクスと対立。主著「神と国家」。(1814〜1876)
はく‐うん【白雲】
白色のくも。しらくも。
⇒はくうん‐せき【白雲石】
⇒はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】
⇒はくうん‐ぼく【白雲木】
はく‐うん【薄運】
運にめぐまれないこと。ふしあわせ。不運。薄福。
はく‐うん【薄雲】
うすい雲。うすぐも。
はくうん‐せき【白雲石】
(→)苦灰石くかいせきに同じ。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】‥キヤウ
天帝のいるという所。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐ぼく【白雲木】
エゴノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ15メートルに達し、葉は広楕円形で大きく厚い。裏面は灰白色の細毛が密生。初夏、白色の合弁花を総状花序につけ下垂。種子から油を取り蝋燭を製し、材を挽物細工および薪炭料とする。庭園樹・街路樹とする。オオバヂシャ。
ハクウンボク(花)
撮影:関戸 勇
はく‐い【伯夷】
「伯夷叔斉しゅくせい」参照。
⇒はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
はく・い【白い】
〔形〕
上等である、良い、美しいの意の隠語。滑稽本、妙竹林話七偏人「面の―・いのを一人よんで呉んなせへ」
ばく‐い【幕威】‥ヰ
幕府の威光。
はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
ともに殷いんの処士で、伯夷が兄、叔斉が弟。周の武王が殷の紂ちゅう王を討つに当たり、臣が君を弑しいする不可を説いていさめたが聞き入れられなかった。周が天下を統一すると、その禄を食むことを拒んで首陽山に隠れ、ともに餓死したと伝える。清廉潔白な人のたとえとする。
⇒はく‐い【伯夷】
はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
看護婦の美称。
⇒はく‐い【白衣】
はく‐いれ【箔入れ】
(→)「箔押し」に同じ。
はくいん【白隠】
江戸中期の臨済宗の僧。名は慧鶴えかく、号は鵠林。駿河の人。若くして各地で修行、京都妙心寺第一座となった後も諸国を遍歴教化、駿河の松蔭寺などを復興したほか多くの信者を集め、臨済宗中興の祖と称された。気魄ある禅画をよくした。諡号しごうは神機独妙禅師・正宗国師。著「荊叢毒蘂」「息耕録」「槐安国語」「遠羅天釜おらでがま」「夜船閑話」など。(1685〜1768)
はく‐いん【博引】
ひろく例を引用すること。
⇒はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】
はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】‥バウ‥
広範囲に多くの例を引き、証拠を示して説明すること。
⇒はく‐いん【博引】
はく‐う【白雨】
ゆうだち。にわかあめ。〈[季]夏〉
ばく‐う【麦雨】
麦の熟するころに降る雨。
バクー【Baku】
カスピ海に面したアゼルバイジャン共和国の首都。カスピ海に突出するアプシェロン半島の南岸にあり、近郊には油田地帯が展開。人口184万8千(2004)。
パグウォッシュ‐かいぎ【パグウォッシュ会議】‥クワイ‥
1955年の「ラッセル‐アインシュタイン宣言」に基づき、57年カナダのパグウォッシュ(Pugwash)で開かれた科学者の国際会議。核兵器廃絶を始めとして、科学と平和の問題を討議。以後、随時世界各地で開催。ノーベル平和賞。
はく‐うち【箔打ち】
金銀を箔にうちのばすこと。また、その職人。
バクーニン【Mikhail Aleksandrovich Bakunin】
ロシアの無政府主義者。1848〜49年ヨーロッパの革命運動に活躍。シベリア流刑中脱走し、亡命。第一インターナショナルに参加、のちマルクスと対立。主著「神と国家」。(1814〜1876)
はく‐うん【白雲】
白色のくも。しらくも。
⇒はくうん‐せき【白雲石】
⇒はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】
⇒はくうん‐ぼく【白雲木】
はく‐うん【薄運】
運にめぐまれないこと。ふしあわせ。不運。薄福。
はく‐うん【薄雲】
うすい雲。うすぐも。
はくうん‐せき【白雲石】
(→)苦灰石くかいせきに同じ。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】‥キヤウ
天帝のいるという所。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐ぼく【白雲木】
エゴノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ15メートルに達し、葉は広楕円形で大きく厚い。裏面は灰白色の細毛が密生。初夏、白色の合弁花を総状花序につけ下垂。種子から油を取り蝋燭を製し、材を挽物細工および薪炭料とする。庭園樹・街路樹とする。オオバヂシャ。
ハクウンボク(花)
撮影:関戸 勇
 ⇒はく‐うん【白雲】
はく‐うんも【白雲母】
雲母の一種。真珠光沢をもち、無色または淡色のもの。電気絶縁体・耐熱保温材料とする。しろうんも。
白雲母
撮影:松原 聰
⇒はく‐うん【白雲】
はく‐うんも【白雲母】
雲母の一種。真珠光沢をもち、無色または淡色のもの。電気絶縁体・耐熱保温材料とする。しろうんも。
白雲母
撮影:松原 聰
 はく‐え【白衣】
⇒びゃくえ
はく‐え【箔絵】‥ヱ
漆工芸の加飾法の一種。箔をおいた絵。漆で模様を描き、上に金銀箔を貼り、乾いた後にぬぐうと模様だけに箔がつく。
ばく‐えい【幕営】
①幕を張りまわした陣営。
②天幕を張って野営すること。
はくえい‐ぐん【白衛軍】‥ヱイ‥
1917年のロシア革命およびその後の内乱に、赤軍に対抗して政権を奪回しようとした帝政派などにより組織された反革命軍。白軍。
ばく‐えき【博奕】
ばくち。
はく‐えん【白煙】
白色のけむり。しろけむり。また、靄もやなどがたなびく形容。
はく‐えん【白猿】‥ヱン
毛の白くなった老猿。
はくえん【栢莚】
2代市川団十郎の俳名。
はくえん‐こう【白鉛鉱】‥クワウ
炭酸鉛から成る鉱物。斜方晶系、結晶は卓状・柱状・錐状。金剛ないし真珠光沢、白色・灰色。
はく‐おう【白鴎】
羽の白いカモメ。
はく‐おき【箔置き】
箔がかぶせてあること。また、そのもの。また、それを作る職人。
はく‐おく【白屋】‥ヲク
白い茅でふいた家。貧しい人の住む家。また、そこに住む人。庶人。平家物語4「世の民なを―の種をかろんず」
はく‐おし【箔押し】
金・銀・色箔を器物などの表面に貼付すること。多く漆器の装飾に用い、また書物の製本で、表紙・背などの文字や図を表すのに用いる。箔入れ。
ばく‐おん【爆音】
①爆発する音。「砲弾の―」
②内燃機関で、混合気の爆発および排気の際に発する音。「飛行機の―」「―を立てる」
はく‐か【白化】‥クワ
⇒はっか
はく‐が【白画】‥グワ
白描はくびょうの技法を用いて描いた絵。素画そが。白描画。
はく‐が【帛画】‥グワ
絹地に描いた絵画。馬王堆まおうたい出土のものが有名。
はく‐が【博雅】
①ひろく物事を知っていること。また、その人。博識。天草本平家物語「―の君子これを読んで」。「―の士」
②博雅三位はくがのさんみの略。
ばく‐か【幕下】
⇒ばっか
ばく‐が【麦芽】
大麦を発芽させたもの。多量のアミラーゼを含み、ビール・ウィスキー・水飴の製造に用いる。モルト。
⇒ばくが‐とう【麦芽糖】
ばく‐が【麦蛾】
キバガ科のガ。開張は約15ミリメートルで灰褐色。幼虫はムギなどの貯蔵穀物を食い荒らす。世界各地に分布。
はく‐がい【迫害】
圧迫して害を加えること。くるしめ、しいたげること。「異教徒を―する」「―をこうむる」
はく‐がく【博学】
ひろく学問に通じていること。博識。「―な人」「―多識」
⇒はくがく‐たさい【博学多才】
はくがく‐たさい【博学多才】
幅広い知識を持ち、多くの才能に恵まれていること。「―を誇る」
⇒はく‐がく【博学】
はく‐え【白衣】
⇒びゃくえ
はく‐え【箔絵】‥ヱ
漆工芸の加飾法の一種。箔をおいた絵。漆で模様を描き、上に金銀箔を貼り、乾いた後にぬぐうと模様だけに箔がつく。
ばく‐えい【幕営】
①幕を張りまわした陣営。
②天幕を張って野営すること。
はくえい‐ぐん【白衛軍】‥ヱイ‥
1917年のロシア革命およびその後の内乱に、赤軍に対抗して政権を奪回しようとした帝政派などにより組織された反革命軍。白軍。
ばく‐えき【博奕】
ばくち。
はく‐えん【白煙】
白色のけむり。しろけむり。また、靄もやなどがたなびく形容。
はく‐えん【白猿】‥ヱン
毛の白くなった老猿。
はくえん【栢莚】
2代市川団十郎の俳名。
はくえん‐こう【白鉛鉱】‥クワウ
炭酸鉛から成る鉱物。斜方晶系、結晶は卓状・柱状・錐状。金剛ないし真珠光沢、白色・灰色。
はく‐おう【白鴎】
羽の白いカモメ。
はく‐おき【箔置き】
箔がかぶせてあること。また、そのもの。また、それを作る職人。
はく‐おく【白屋】‥ヲク
白い茅でふいた家。貧しい人の住む家。また、そこに住む人。庶人。平家物語4「世の民なを―の種をかろんず」
はく‐おし【箔押し】
金・銀・色箔を器物などの表面に貼付すること。多く漆器の装飾に用い、また書物の製本で、表紙・背などの文字や図を表すのに用いる。箔入れ。
ばく‐おん【爆音】
①爆発する音。「砲弾の―」
②内燃機関で、混合気の爆発および排気の際に発する音。「飛行機の―」「―を立てる」
はく‐か【白化】‥クワ
⇒はっか
はく‐が【白画】‥グワ
白描はくびょうの技法を用いて描いた絵。素画そが。白描画。
はく‐が【帛画】‥グワ
絹地に描いた絵画。馬王堆まおうたい出土のものが有名。
はく‐が【博雅】
①ひろく物事を知っていること。また、その人。博識。天草本平家物語「―の君子これを読んで」。「―の士」
②博雅三位はくがのさんみの略。
ばく‐か【幕下】
⇒ばっか
ばく‐が【麦芽】
大麦を発芽させたもの。多量のアミラーゼを含み、ビール・ウィスキー・水飴の製造に用いる。モルト。
⇒ばくが‐とう【麦芽糖】
ばく‐が【麦蛾】
キバガ科のガ。開張は約15ミリメートルで灰褐色。幼虫はムギなどの貯蔵穀物を食い荒らす。世界各地に分布。
はく‐がい【迫害】
圧迫して害を加えること。くるしめ、しいたげること。「異教徒を―する」「―をこうむる」
はく‐がく【博学】
ひろく学問に通じていること。博識。「―な人」「―多識」
⇒はくがく‐たさい【博学多才】
はくがく‐たさい【博学多才】
幅広い知識を持ち、多くの才能に恵まれていること。「―を誇る」
⇒はく‐がく【博学】
 →作品:『月に吠える』
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ひろみち【萩原広道】‥ハラ‥
幕末の国学者。岡山の人。大国(野之口)隆正に学び、源氏物語に精通。著「源氏物語評釈」「本教提綱」など。(1815〜1863)
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ゆうすけ【萩原雄祐】‥ハライウ‥
天文学者。大阪生れ。東大卒。東京天文台長。天体力学、理論天体物理学を専攻。著「天体力学」など。文化勲章。(1897〜1979)
萩原雄祐
提供:毎日新聞社
→作品:『月に吠える』
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ひろみち【萩原広道】‥ハラ‥
幕末の国学者。岡山の人。大国(野之口)隆正に学び、源氏物語に精通。著「源氏物語評釈」「本教提綱」など。(1815〜1863)
⇒はぎわら【萩原】
はぎわら‐ゆうすけ【萩原雄祐】‥ハライウ‥
天文学者。大阪生れ。東大卒。東京天文台長。天体力学、理論天体物理学を専攻。著「天体力学」など。文化勲章。(1897〜1979)
萩原雄祐
提供:毎日新聞社
 ⇒はぎわら【萩原】
はきん【巴金】
(Ba Jin)(パキンとも)中国の小説家。本名、李尭棠ぎょうとう。四川の人。フランスに留学。アナーキズムの影響を強く受ける。文化大革命で迫害されたが、1977年に名誉回復。作「滅亡」「家」「第四病室」「憩園」「寒夜」など。「随想録」は文革批判の異色作。(1904〜2005)
は‐ぎん【端銀】
はしたがね。傾城禁短気「金二歩に―そへて」
はく【白】
(呉音はビャク)
①しろいこと。しろ。
②五行の一つ。西。秋。
③白耳義ベルギーの略。
はく【伯】
①兄弟中の年長者。長兄。
②神祇官の長官。
③五等爵の第3位。伯爵。
④伯耆国ほうきのくにの略。
⑤伯剌西爾ブラジルの略。
はく【帛】
きぬ。絹布。
はく【拍】
(慣用音はヒョウ)
①手のひらを打ち合わせること。手でうつこと。
②西洋音楽で、音の長さの基本単位。また、拍子の周期の中で繰り返される強弱の各部分。強拍と弱拍とより成る。→拍子ひょうし。
③〔言〕モーラ。
はく【泊】
宿をとること。宿泊の数をかぞえる語。「2―3日」
はく【陌】
「百」の大字。
はく【博】
①博士はくしの略。
②博覧会の略。
はく【箔】
①金・銀・銅・錫・真鍮などをたたいて、紙のように薄く平らに延ばしたもの。日葡辞書「ハクヲヲク」
②能装束の縫箔ぬいはくまたは摺箔すりはくの略。
⇒箔が付く
はく【魄】
たましい。この世にとどまるという陰いんの霊魂。↔魂こん
は・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
は・く【吐く】
〔他五〕
①口の中のものを外に出す。地蔵十輪経元慶点「咸ことごとく共に唾つはきをハキて言はく」。宇治拾遺物語11「川にざぶりと入る程に…くくみたる水―・きすてて」。日葡辞書「チヲハク」
②胃の中のものを口外に出す。もどす。「酔って―・く」
③言葉に出す。語る。口外する。天草本伊曾保物語「忠言をこそえ言はずとも、せめて讒言を―・くな」。「本音を―・く」
④内にあるものを外へ出す。「煙を―・く」
は・く【佩く・帯く・着く・穿く・履く】
〔他五・下二〕
①(多く「佩く」と書く)腰につける。さす。帯びる。古事記中「やつめさす出雲建いずもたけるが―・ける太刀つづら多纏さわまきさ身なしにあはれ」「一つ松人にありせば太刀―・けましを」
②《穿》腰から下の部分を覆う衣類を身につける。うがつ。「ズボンを―・く」
③《履》下駄・靴・足袋たび・靴下などを、足先につける。万葉集9「髪だにも掻きは梳らず履くつをだに―・かず行けども」。源氏物語浮舟「わが沓を―・かせて、自らは供なる人々のあやしきものを―・きたり」。天草本伊曾保物語「足袋を―・き」
④弦を弓にかける。万葉集14「陸奥の安太多良あだたら真弓はじき置きて反せらしめきなば弦つら―・かめかも」。万葉集2「梓弓弦緒つらお取り―・け引く人は」
は・く【捌く】
〔自下二〕
⇒はける(下一)
は・く【掃く】
〔他五〕
①箒などで払い清める。万葉集19「梳くしも見じ屋内やぬちも―・かじ草枕旅行く君を斎いわふと思ひて」。平家物語11「―・いたり拭のごうたり、塵拾ひ、手づから掃除せられけり」。「庭を―・く」
②祓はらい除く。万葉集20「ちはやぶる神をことむけまつろへぬ人をも和やわし―・き清め仕へまつりて」
③(「刷く」と書く)眉墨・白粉などを塗る。ぬりつける。「眉を―・く」
④孵化した毛蚕けごを蚕卵紙から取って蚕座へうつす。→掃立て2。
⑤上方の遊里語で、箒で女を掃く意から、多くの遊女を買い一人に定めないことをいう。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「わたしも大かたお―・きなさるのじやあろふナア」
⇒掃いて捨てるほど
は‐ぐ【爬具】
水底や砂泥をかきおこして、貝類を採取する道具の総称。
ハグ【hug】
抱きしめること。特に、欧米式の挨拶で抱き合うこと。
は・ぐ【禿ぐ】
〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【矧ぐ】
(古くはハク。「佩く」と同語か)
[一]〔他五〕
竹に羽をつけて矢をつくる。万葉集7「淡海おうみのや矢橋の小竹しのを矢―・かずて」
[二]〔他下二〕
弓に矢をつがえる。太平記3「弛はずせる弓に矢を―・げて射んとすれども」
は・ぐ【剥ぐ】
[一]〔他五〕
①表面をむきとる。はがす。へがす。神代紀上「真名鹿まなかの皮を全剥うつはぎに―・ぎて」。万葉集16「もむ楡を五百枝いおえ―・ぎ垂り」。「爪を―・ぐ」
②身につけたものをぬがせ取る。裸にする。宇津保物語祭使「賜はりたまふ司は、盗人のみ集ひて人の衣を―・ぎ取り、飯酒をさがし食む」
③官位などを取り上げる。奪う。「官を―・ぐ」
[二]〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【接ぐ】
〔他五〕
二つのものをつぎ合わす。「布を―・ぐ」
ばく【幕】
①幕府、特に徳川幕府の略。「―末」
②幕僚本部の略。
→まく(幕)
ばく【漠】
①ひろびろして何もないさま。
②とりとめのないさま。「―とした話」
ばく【縛】
①しばること。しばられること。なわめ。「―に就く」
②煩悩。「―の縄」「繋縛けばく」
ばく【貘・獏】
①ウマ目バク科の哺乳類の総称。中南米のアメリカバク・ヤマバク・ベアードバクの3種と東南アジアのマレーバクの1属4種がいる。体長1.5〜2メートル、体はずんぐりして、吻ふんが突き出ており、四肢は長くない。アメリカバクは毛色は暗褐色、マレーバクは前肢の後から腰にかけて白い。森林や水辺のやぶで単独か親子で生活し、薄明・暮時に活動、草や芋、果実を食べる。アメリカバク以外の3種は絶滅の危機にある。
マレーばく
⇒はぎわら【萩原】
はきん【巴金】
(Ba Jin)(パキンとも)中国の小説家。本名、李尭棠ぎょうとう。四川の人。フランスに留学。アナーキズムの影響を強く受ける。文化大革命で迫害されたが、1977年に名誉回復。作「滅亡」「家」「第四病室」「憩園」「寒夜」など。「随想録」は文革批判の異色作。(1904〜2005)
は‐ぎん【端銀】
はしたがね。傾城禁短気「金二歩に―そへて」
はく【白】
(呉音はビャク)
①しろいこと。しろ。
②五行の一つ。西。秋。
③白耳義ベルギーの略。
はく【伯】
①兄弟中の年長者。長兄。
②神祇官の長官。
③五等爵の第3位。伯爵。
④伯耆国ほうきのくにの略。
⑤伯剌西爾ブラジルの略。
はく【帛】
きぬ。絹布。
はく【拍】
(慣用音はヒョウ)
①手のひらを打ち合わせること。手でうつこと。
②西洋音楽で、音の長さの基本単位。また、拍子の周期の中で繰り返される強弱の各部分。強拍と弱拍とより成る。→拍子ひょうし。
③〔言〕モーラ。
はく【泊】
宿をとること。宿泊の数をかぞえる語。「2―3日」
はく【陌】
「百」の大字。
はく【博】
①博士はくしの略。
②博覧会の略。
はく【箔】
①金・銀・銅・錫・真鍮などをたたいて、紙のように薄く平らに延ばしたもの。日葡辞書「ハクヲヲク」
②能装束の縫箔ぬいはくまたは摺箔すりはくの略。
⇒箔が付く
はく【魄】
たましい。この世にとどまるという陰いんの霊魂。↔魂こん
は・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
は・く【吐く】
〔他五〕
①口の中のものを外に出す。地蔵十輪経元慶点「咸ことごとく共に唾つはきをハキて言はく」。宇治拾遺物語11「川にざぶりと入る程に…くくみたる水―・きすてて」。日葡辞書「チヲハク」
②胃の中のものを口外に出す。もどす。「酔って―・く」
③言葉に出す。語る。口外する。天草本伊曾保物語「忠言をこそえ言はずとも、せめて讒言を―・くな」。「本音を―・く」
④内にあるものを外へ出す。「煙を―・く」
は・く【佩く・帯く・着く・穿く・履く】
〔他五・下二〕
①(多く「佩く」と書く)腰につける。さす。帯びる。古事記中「やつめさす出雲建いずもたけるが―・ける太刀つづら多纏さわまきさ身なしにあはれ」「一つ松人にありせば太刀―・けましを」
②《穿》腰から下の部分を覆う衣類を身につける。うがつ。「ズボンを―・く」
③《履》下駄・靴・足袋たび・靴下などを、足先につける。万葉集9「髪だにも掻きは梳らず履くつをだに―・かず行けども」。源氏物語浮舟「わが沓を―・かせて、自らは供なる人々のあやしきものを―・きたり」。天草本伊曾保物語「足袋を―・き」
④弦を弓にかける。万葉集14「陸奥の安太多良あだたら真弓はじき置きて反せらしめきなば弦つら―・かめかも」。万葉集2「梓弓弦緒つらお取り―・け引く人は」
は・く【捌く】
〔自下二〕
⇒はける(下一)
は・く【掃く】
〔他五〕
①箒などで払い清める。万葉集19「梳くしも見じ屋内やぬちも―・かじ草枕旅行く君を斎いわふと思ひて」。平家物語11「―・いたり拭のごうたり、塵拾ひ、手づから掃除せられけり」。「庭を―・く」
②祓はらい除く。万葉集20「ちはやぶる神をことむけまつろへぬ人をも和やわし―・き清め仕へまつりて」
③(「刷く」と書く)眉墨・白粉などを塗る。ぬりつける。「眉を―・く」
④孵化した毛蚕けごを蚕卵紙から取って蚕座へうつす。→掃立て2。
⑤上方の遊里語で、箒で女を掃く意から、多くの遊女を買い一人に定めないことをいう。洒落本、十界和尚話いかいおせわ「わたしも大かたお―・きなさるのじやあろふナア」
⇒掃いて捨てるほど
は‐ぐ【爬具】
水底や砂泥をかきおこして、貝類を採取する道具の総称。
ハグ【hug】
抱きしめること。特に、欧米式の挨拶で抱き合うこと。
は・ぐ【禿ぐ】
〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【矧ぐ】
(古くはハク。「佩く」と同語か)
[一]〔他五〕
竹に羽をつけて矢をつくる。万葉集7「淡海おうみのや矢橋の小竹しのを矢―・かずて」
[二]〔他下二〕
弓に矢をつがえる。太平記3「弛はずせる弓に矢を―・げて射んとすれども」
は・ぐ【剥ぐ】
[一]〔他五〕
①表面をむきとる。はがす。へがす。神代紀上「真名鹿まなかの皮を全剥うつはぎに―・ぎて」。万葉集16「もむ楡を五百枝いおえ―・ぎ垂り」。「爪を―・ぐ」
②身につけたものをぬがせ取る。裸にする。宇津保物語祭使「賜はりたまふ司は、盗人のみ集ひて人の衣を―・ぎ取り、飯酒をさがし食む」
③官位などを取り上げる。奪う。「官を―・ぐ」
[二]〔自下二〕
⇒はげる(下一)
は・ぐ【接ぐ】
〔他五〕
二つのものをつぎ合わす。「布を―・ぐ」
ばく【幕】
①幕府、特に徳川幕府の略。「―末」
②幕僚本部の略。
→まく(幕)
ばく【漠】
①ひろびろして何もないさま。
②とりとめのないさま。「―とした話」
ばく【縛】
①しばること。しばられること。なわめ。「―に就く」
②煩悩。「―の縄」「繋縛けばく」
ばく【貘・獏】
①ウマ目バク科の哺乳類の総称。中南米のアメリカバク・ヤマバク・ベアードバクの3種と東南アジアのマレーバクの1属4種がいる。体長1.5〜2メートル、体はずんぐりして、吻ふんが突き出ており、四肢は長くない。アメリカバクは毛色は暗褐色、マレーバクは前肢の後から腰にかけて白い。森林や水辺のやぶで単独か親子で生活し、薄明・暮時に活動、草や芋、果実を食べる。アメリカバク以外の3種は絶滅の危機にある。
マレーばく
 アメリカバク
提供:東京動物園協会
アメリカバク
提供:東京動物園協会
 ベアードバク
提供:東京動物園協会
ベアードバク
提供:東京動物園協会
 マレーバク
提供:東京動物園協会
マレーバク
提供:東京動物園協会
 ②中国で想像上の動物。形は熊に、鼻は象に、目は犀に、尾は牛に、脚は虎に似、毛は黒白の斑で、頭が小さく、人の悪夢を食うと伝え、その皮を敷いて寝ると邪気を避けるという。
ばく【瀑】
高所から落ちる流水。たき。
ばく【爆】
爆弾・爆弾攻撃の略。
ば・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
ば‐ぐ【馬具】
馬の装具。鞍・轡くつわ・鐙あぶみ・手綱などの総称。
バグ【bug】
(虫の意)コンピューターのプログラムの誤り・欠陥。
パグ【pug】
イヌの一品種。体高約25センチメートル、短毛で、垂れ耳、巻尾。顔はチンのようにしゃくれ、皺だらけ。中国で愛玩用に作出。
パグ
②中国で想像上の動物。形は熊に、鼻は象に、目は犀に、尾は牛に、脚は虎に似、毛は黒白の斑で、頭が小さく、人の悪夢を食うと伝え、その皮を敷いて寝ると邪気を避けるという。
ばく【瀑】
高所から落ちる流水。たき。
ばく【爆】
爆弾・爆弾攻撃の略。
ば・く【化く】
〔自下二〕
⇒ばける(下一)
ば‐ぐ【馬具】
馬の装具。鞍・轡くつわ・鐙あぶみ・手綱などの総称。
バグ【bug】
(虫の意)コンピューターのプログラムの誤り・欠陥。
パグ【pug】
イヌの一品種。体高約25センチメートル、短毛で、垂れ耳、巻尾。顔はチンのようにしゃくれ、皺だらけ。中国で愛玩用に作出。
パグ
 はく‐あ【白堊・白亜】
(ハクアクの慣用読み。「堊」は、白土の意)
①泥質の軟らかい石灰岩。ココリス・有孔虫などの遺骸や貝殻に由来する泥灰質粉末から成る浅海成層をつくる。白墨・石灰の原料、白壁の塗料とする。チョーク。
②白壁。「―の殿堂」
⇒はくあ‐かん【白堊館】
⇒はくあ‐き【白亜紀】
⇒はくあ‐けい【白亜系】
⇒はくあ‐しつ【白亜質】
はく‐あい【博愛】
[孝経三才章]ひろく愛すること。平等に愛すること。性霊集4「天仁慈を仮して―是を務む」。「―の精神」
⇒はくあい‐しゃ【博愛社】
⇒はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
はくあい‐しゃ【博愛社】
日本赤十字社の前身。1877年(明治10)佐野常民・大給恒おぎゅうゆずるらが西南戦争の両軍の死傷者救護を動機として創設。
⇒はく‐あい【博愛】
はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
個人的利己心、人種的偏見、国家的利益、宗教的またはイデオロギー的党派性を捨てて人類全体の福祉増進のために、全人類はすべて平等に相愛すべきものであるとする主張。→汎愛はんあい主義
⇒はく‐あい【博愛】
はくあ‐かん【白堊館】‥クワン
ホワイト‐ハウスの訳語。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐き【白亜紀】
(Cretaceous Period)地質年代のうち、中生代の最後の時代。約1億4000万年前から6500万年前まで。海が著しく広がり、ドーヴァー海峡などの白亜層が形成された。末期にはアルプス造山運動が起こった。アンモナイト・爬虫類(特に恐竜)などが栄えたが白亜紀末に絶滅。植物は羊歯しだ類・裸子植物が前半に多く、後半には被子植物が繁茂。→地質年代(表)。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐けい【白亜系】
白亜紀に形成された地層。日本では北海道や西日本の太平洋岸に多い。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐しつ【白亜質】
(→)セメント質に同じ。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあん【伯庵】
(江戸幕府の医師、曾谷そだに伯庵が愛蔵していたからという)桃山末期から江戸初期頃の作とされる大振りの茶碗。また、それと色・釉薬・形状その他特徴を同じくするもの。伯庵茶碗。
はく‐い【白衣】
①白い色の衣服。「―を着た医者」
②官位のない卑しいもの。布衣。庶人。
→びゃくえ。
⇒はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
はくい【羽咋】‥クヒ
石川県中部、能登半島西側基部にある市。邑知おうち潟干拓地と砂丘上に位置し、能登の中心都市。繊維工業が盛ん。千里浜ちりはま海水浴場がある。人口2万5千。
羽咋 千里浜なぎさドライブウェイ
撮影:新海良夫
はく‐あ【白堊・白亜】
(ハクアクの慣用読み。「堊」は、白土の意)
①泥質の軟らかい石灰岩。ココリス・有孔虫などの遺骸や貝殻に由来する泥灰質粉末から成る浅海成層をつくる。白墨・石灰の原料、白壁の塗料とする。チョーク。
②白壁。「―の殿堂」
⇒はくあ‐かん【白堊館】
⇒はくあ‐き【白亜紀】
⇒はくあ‐けい【白亜系】
⇒はくあ‐しつ【白亜質】
はく‐あい【博愛】
[孝経三才章]ひろく愛すること。平等に愛すること。性霊集4「天仁慈を仮して―是を務む」。「―の精神」
⇒はくあい‐しゃ【博愛社】
⇒はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
はくあい‐しゃ【博愛社】
日本赤十字社の前身。1877年(明治10)佐野常民・大給恒おぎゅうゆずるらが西南戦争の両軍の死傷者救護を動機として創設。
⇒はく‐あい【博愛】
はくあい‐しゅぎ【博愛主義】
個人的利己心、人種的偏見、国家的利益、宗教的またはイデオロギー的党派性を捨てて人類全体の福祉増進のために、全人類はすべて平等に相愛すべきものであるとする主張。→汎愛はんあい主義
⇒はく‐あい【博愛】
はくあ‐かん【白堊館】‥クワン
ホワイト‐ハウスの訳語。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐き【白亜紀】
(Cretaceous Period)地質年代のうち、中生代の最後の時代。約1億4000万年前から6500万年前まで。海が著しく広がり、ドーヴァー海峡などの白亜層が形成された。末期にはアルプス造山運動が起こった。アンモナイト・爬虫類(特に恐竜)などが栄えたが白亜紀末に絶滅。植物は羊歯しだ類・裸子植物が前半に多く、後半には被子植物が繁茂。→地質年代(表)。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐けい【白亜系】
白亜紀に形成された地層。日本では北海道や西日本の太平洋岸に多い。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあ‐しつ【白亜質】
(→)セメント質に同じ。
⇒はく‐あ【白堊・白亜】
はくあん【伯庵】
(江戸幕府の医師、曾谷そだに伯庵が愛蔵していたからという)桃山末期から江戸初期頃の作とされる大振りの茶碗。また、それと色・釉薬・形状その他特徴を同じくするもの。伯庵茶碗。
はく‐い【白衣】
①白い色の衣服。「―を着た医者」
②官位のない卑しいもの。布衣。庶人。
→びゃくえ。
⇒はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
はくい【羽咋】‥クヒ
石川県中部、能登半島西側基部にある市。邑知おうち潟干拓地と砂丘上に位置し、能登の中心都市。繊維工業が盛ん。千里浜ちりはま海水浴場がある。人口2万5千。
羽咋 千里浜なぎさドライブウェイ
撮影:新海良夫
 はく‐い【伯夷】
「伯夷叔斉しゅくせい」参照。
⇒はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
はく・い【白い】
〔形〕
上等である、良い、美しいの意の隠語。滑稽本、妙竹林話七偏人「面の―・いのを一人よんで呉んなせへ」
ばく‐い【幕威】‥ヰ
幕府の威光。
はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
ともに殷いんの処士で、伯夷が兄、叔斉が弟。周の武王が殷の紂ちゅう王を討つに当たり、臣が君を弑しいする不可を説いていさめたが聞き入れられなかった。周が天下を統一すると、その禄を食むことを拒んで首陽山に隠れ、ともに餓死したと伝える。清廉潔白な人のたとえとする。
⇒はく‐い【伯夷】
はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
看護婦の美称。
⇒はく‐い【白衣】
はく‐いれ【箔入れ】
(→)「箔押し」に同じ。
はくいん【白隠】
江戸中期の臨済宗の僧。名は慧鶴えかく、号は鵠林。駿河の人。若くして各地で修行、京都妙心寺第一座となった後も諸国を遍歴教化、駿河の松蔭寺などを復興したほか多くの信者を集め、臨済宗中興の祖と称された。気魄ある禅画をよくした。諡号しごうは神機独妙禅師・正宗国師。著「荊叢毒蘂」「息耕録」「槐安国語」「遠羅天釜おらでがま」「夜船閑話」など。(1685〜1768)
はく‐いん【博引】
ひろく例を引用すること。
⇒はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】
はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】‥バウ‥
広範囲に多くの例を引き、証拠を示して説明すること。
⇒はく‐いん【博引】
はく‐う【白雨】
ゆうだち。にわかあめ。〈[季]夏〉
ばく‐う【麦雨】
麦の熟するころに降る雨。
バクー【Baku】
カスピ海に面したアゼルバイジャン共和国の首都。カスピ海に突出するアプシェロン半島の南岸にあり、近郊には油田地帯が展開。人口184万8千(2004)。
パグウォッシュ‐かいぎ【パグウォッシュ会議】‥クワイ‥
1955年の「ラッセル‐アインシュタイン宣言」に基づき、57年カナダのパグウォッシュ(Pugwash)で開かれた科学者の国際会議。核兵器廃絶を始めとして、科学と平和の問題を討議。以後、随時世界各地で開催。ノーベル平和賞。
はく‐うち【箔打ち】
金銀を箔にうちのばすこと。また、その職人。
バクーニン【Mikhail Aleksandrovich Bakunin】
ロシアの無政府主義者。1848〜49年ヨーロッパの革命運動に活躍。シベリア流刑中脱走し、亡命。第一インターナショナルに参加、のちマルクスと対立。主著「神と国家」。(1814〜1876)
はく‐うん【白雲】
白色のくも。しらくも。
⇒はくうん‐せき【白雲石】
⇒はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】
⇒はくうん‐ぼく【白雲木】
はく‐うん【薄運】
運にめぐまれないこと。ふしあわせ。不運。薄福。
はく‐うん【薄雲】
うすい雲。うすぐも。
はくうん‐せき【白雲石】
(→)苦灰石くかいせきに同じ。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】‥キヤウ
天帝のいるという所。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐ぼく【白雲木】
エゴノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ15メートルに達し、葉は広楕円形で大きく厚い。裏面は灰白色の細毛が密生。初夏、白色の合弁花を総状花序につけ下垂。種子から油を取り蝋燭を製し、材を挽物細工および薪炭料とする。庭園樹・街路樹とする。オオバヂシャ。
ハクウンボク(花)
撮影:関戸 勇
はく‐い【伯夷】
「伯夷叔斉しゅくせい」参照。
⇒はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
はく・い【白い】
〔形〕
上等である、良い、美しいの意の隠語。滑稽本、妙竹林話七偏人「面の―・いのを一人よんで呉んなせへ」
ばく‐い【幕威】‥ヰ
幕府の威光。
はくい‐しゅくせい【伯夷叔斉】
ともに殷いんの処士で、伯夷が兄、叔斉が弟。周の武王が殷の紂ちゅう王を討つに当たり、臣が君を弑しいする不可を説いていさめたが聞き入れられなかった。周が天下を統一すると、その禄を食むことを拒んで首陽山に隠れ、ともに餓死したと伝える。清廉潔白な人のたとえとする。
⇒はく‐い【伯夷】
はくい‐の‐てんし【白衣の天使】
看護婦の美称。
⇒はく‐い【白衣】
はく‐いれ【箔入れ】
(→)「箔押し」に同じ。
はくいん【白隠】
江戸中期の臨済宗の僧。名は慧鶴えかく、号は鵠林。駿河の人。若くして各地で修行、京都妙心寺第一座となった後も諸国を遍歴教化、駿河の松蔭寺などを復興したほか多くの信者を集め、臨済宗中興の祖と称された。気魄ある禅画をよくした。諡号しごうは神機独妙禅師・正宗国師。著「荊叢毒蘂」「息耕録」「槐安国語」「遠羅天釜おらでがま」「夜船閑話」など。(1685〜1768)
はく‐いん【博引】
ひろく例を引用すること。
⇒はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】
はくいん‐ぼうしょう【博引旁証】‥バウ‥
広範囲に多くの例を引き、証拠を示して説明すること。
⇒はく‐いん【博引】
はく‐う【白雨】
ゆうだち。にわかあめ。〈[季]夏〉
ばく‐う【麦雨】
麦の熟するころに降る雨。
バクー【Baku】
カスピ海に面したアゼルバイジャン共和国の首都。カスピ海に突出するアプシェロン半島の南岸にあり、近郊には油田地帯が展開。人口184万8千(2004)。
パグウォッシュ‐かいぎ【パグウォッシュ会議】‥クワイ‥
1955年の「ラッセル‐アインシュタイン宣言」に基づき、57年カナダのパグウォッシュ(Pugwash)で開かれた科学者の国際会議。核兵器廃絶を始めとして、科学と平和の問題を討議。以後、随時世界各地で開催。ノーベル平和賞。
はく‐うち【箔打ち】
金銀を箔にうちのばすこと。また、その職人。
バクーニン【Mikhail Aleksandrovich Bakunin】
ロシアの無政府主義者。1848〜49年ヨーロッパの革命運動に活躍。シベリア流刑中脱走し、亡命。第一インターナショナルに参加、のちマルクスと対立。主著「神と国家」。(1814〜1876)
はく‐うん【白雲】
白色のくも。しらくも。
⇒はくうん‐せき【白雲石】
⇒はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】
⇒はくうん‐ぼく【白雲木】
はく‐うん【薄運】
運にめぐまれないこと。ふしあわせ。不運。薄福。
はく‐うん【薄雲】
うすい雲。うすぐも。
はくうん‐せき【白雲石】
(→)苦灰石くかいせきに同じ。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐の‐きょう【白雲の郷】‥キヤウ
天帝のいるという所。
⇒はく‐うん【白雲】
はくうん‐ぼく【白雲木】
エゴノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ15メートルに達し、葉は広楕円形で大きく厚い。裏面は灰白色の細毛が密生。初夏、白色の合弁花を総状花序につけ下垂。種子から油を取り蝋燭を製し、材を挽物細工および薪炭料とする。庭園樹・街路樹とする。オオバヂシャ。
ハクウンボク(花)
撮影:関戸 勇
 ⇒はく‐うん【白雲】
はく‐うんも【白雲母】
雲母の一種。真珠光沢をもち、無色または淡色のもの。電気絶縁体・耐熱保温材料とする。しろうんも。
白雲母
撮影:松原 聰
⇒はく‐うん【白雲】
はく‐うんも【白雲母】
雲母の一種。真珠光沢をもち、無色または淡色のもの。電気絶縁体・耐熱保温材料とする。しろうんも。
白雲母
撮影:松原 聰
 はく‐え【白衣】
⇒びゃくえ
はく‐え【箔絵】‥ヱ
漆工芸の加飾法の一種。箔をおいた絵。漆で模様を描き、上に金銀箔を貼り、乾いた後にぬぐうと模様だけに箔がつく。
ばく‐えい【幕営】
①幕を張りまわした陣営。
②天幕を張って野営すること。
はくえい‐ぐん【白衛軍】‥ヱイ‥
1917年のロシア革命およびその後の内乱に、赤軍に対抗して政権を奪回しようとした帝政派などにより組織された反革命軍。白軍。
ばく‐えき【博奕】
ばくち。
はく‐えん【白煙】
白色のけむり。しろけむり。また、靄もやなどがたなびく形容。
はく‐えん【白猿】‥ヱン
毛の白くなった老猿。
はくえん【栢莚】
2代市川団十郎の俳名。
はくえん‐こう【白鉛鉱】‥クワウ
炭酸鉛から成る鉱物。斜方晶系、結晶は卓状・柱状・錐状。金剛ないし真珠光沢、白色・灰色。
はく‐おう【白鴎】
羽の白いカモメ。
はく‐おき【箔置き】
箔がかぶせてあること。また、そのもの。また、それを作る職人。
はく‐おく【白屋】‥ヲク
白い茅でふいた家。貧しい人の住む家。また、そこに住む人。庶人。平家物語4「世の民なを―の種をかろんず」
はく‐おし【箔押し】
金・銀・色箔を器物などの表面に貼付すること。多く漆器の装飾に用い、また書物の製本で、表紙・背などの文字や図を表すのに用いる。箔入れ。
ばく‐おん【爆音】
①爆発する音。「砲弾の―」
②内燃機関で、混合気の爆発および排気の際に発する音。「飛行機の―」「―を立てる」
はく‐か【白化】‥クワ
⇒はっか
はく‐が【白画】‥グワ
白描はくびょうの技法を用いて描いた絵。素画そが。白描画。
はく‐が【帛画】‥グワ
絹地に描いた絵画。馬王堆まおうたい出土のものが有名。
はく‐が【博雅】
①ひろく物事を知っていること。また、その人。博識。天草本平家物語「―の君子これを読んで」。「―の士」
②博雅三位はくがのさんみの略。
ばく‐か【幕下】
⇒ばっか
ばく‐が【麦芽】
大麦を発芽させたもの。多量のアミラーゼを含み、ビール・ウィスキー・水飴の製造に用いる。モルト。
⇒ばくが‐とう【麦芽糖】
ばく‐が【麦蛾】
キバガ科のガ。開張は約15ミリメートルで灰褐色。幼虫はムギなどの貯蔵穀物を食い荒らす。世界各地に分布。
はく‐がい【迫害】
圧迫して害を加えること。くるしめ、しいたげること。「異教徒を―する」「―をこうむる」
はく‐がく【博学】
ひろく学問に通じていること。博識。「―な人」「―多識」
⇒はくがく‐たさい【博学多才】
はくがく‐たさい【博学多才】
幅広い知識を持ち、多くの才能に恵まれていること。「―を誇る」
⇒はく‐がく【博学】
はく‐え【白衣】
⇒びゃくえ
はく‐え【箔絵】‥ヱ
漆工芸の加飾法の一種。箔をおいた絵。漆で模様を描き、上に金銀箔を貼り、乾いた後にぬぐうと模様だけに箔がつく。
ばく‐えい【幕営】
①幕を張りまわした陣営。
②天幕を張って野営すること。
はくえい‐ぐん【白衛軍】‥ヱイ‥
1917年のロシア革命およびその後の内乱に、赤軍に対抗して政権を奪回しようとした帝政派などにより組織された反革命軍。白軍。
ばく‐えき【博奕】
ばくち。
はく‐えん【白煙】
白色のけむり。しろけむり。また、靄もやなどがたなびく形容。
はく‐えん【白猿】‥ヱン
毛の白くなった老猿。
はくえん【栢莚】
2代市川団十郎の俳名。
はくえん‐こう【白鉛鉱】‥クワウ
炭酸鉛から成る鉱物。斜方晶系、結晶は卓状・柱状・錐状。金剛ないし真珠光沢、白色・灰色。
はく‐おう【白鴎】
羽の白いカモメ。
はく‐おき【箔置き】
箔がかぶせてあること。また、そのもの。また、それを作る職人。
はく‐おく【白屋】‥ヲク
白い茅でふいた家。貧しい人の住む家。また、そこに住む人。庶人。平家物語4「世の民なを―の種をかろんず」
はく‐おし【箔押し】
金・銀・色箔を器物などの表面に貼付すること。多く漆器の装飾に用い、また書物の製本で、表紙・背などの文字や図を表すのに用いる。箔入れ。
ばく‐おん【爆音】
①爆発する音。「砲弾の―」
②内燃機関で、混合気の爆発および排気の際に発する音。「飛行機の―」「―を立てる」
はく‐か【白化】‥クワ
⇒はっか
はく‐が【白画】‥グワ
白描はくびょうの技法を用いて描いた絵。素画そが。白描画。
はく‐が【帛画】‥グワ
絹地に描いた絵画。馬王堆まおうたい出土のものが有名。
はく‐が【博雅】
①ひろく物事を知っていること。また、その人。博識。天草本平家物語「―の君子これを読んで」。「―の士」
②博雅三位はくがのさんみの略。
ばく‐か【幕下】
⇒ばっか
ばく‐が【麦芽】
大麦を発芽させたもの。多量のアミラーゼを含み、ビール・ウィスキー・水飴の製造に用いる。モルト。
⇒ばくが‐とう【麦芽糖】
ばく‐が【麦蛾】
キバガ科のガ。開張は約15ミリメートルで灰褐色。幼虫はムギなどの貯蔵穀物を食い荒らす。世界各地に分布。
はく‐がい【迫害】
圧迫して害を加えること。くるしめ、しいたげること。「異教徒を―する」「―をこうむる」
はく‐がく【博学】
ひろく学問に通じていること。博識。「―な人」「―多識」
⇒はくがく‐たさい【博学多才】
はくがく‐たさい【博学多才】
幅広い知識を持ち、多くの才能に恵まれていること。「―を誇る」
⇒はく‐がく【博学】
は‐きょく【破局】🔗⭐🔉
は‐きょく【破局】
事の破れた局面。悲劇的な終末。「―を迎える」
はぐん‐せい【破軍星】🔗⭐🔉
はぐん‐せい【破軍星】
北斗七星の第7星。剣の形をなし、陰陽道おんようどうでは、その剣先の指す方角を万事に不吉なりとして忌んだ。剣先けんさき。破軍。アルカイド。
は‐げ【破夏】🔗⭐🔉
は‐げ【破夏】
〔仏〕夏安居げあんごを中途でやめること。また、安居中の禁足を破って外出すること。
はこう‐だん【破甲弾】‥カフ‥🔗⭐🔉
はこう‐だん【破甲弾】‥カフ‥
(→)徹甲弾に同じ。
は‐ごく【破獄】🔗⭐🔉
は‐ごく【破獄】
囚人が牢獄を破ってぬけでること。ろうやぶり。破牢。
はこつ‐さいぼう【破骨細胞】‥バウ🔗⭐🔉
はこつ‐さいぼう【破骨細胞】‥バウ
骨の吸収を行う細胞。骨の再構築と血清カルシウム濃度の調節に関与する。
は‐こん【破婚】🔗⭐🔉
は‐こん【破婚】
結婚関係を解消すること。離縁。破鏡。
は‐さい【破砕・破摧】🔗⭐🔉
は‐さい【破砕・破摧】
やぶりくだくこと。また、やぶれくだけること。「岩石の―」「敵を―する」
⇒はさい‐き【破砕機】
はさい‐き【破砕機】🔗⭐🔉
はさい‐き【破砕機】
(→)クラッシャーに同じ。
⇒は‐さい【破砕・破摧】
はさつ‐おん【破擦音】🔗⭐🔉
はさつ‐おん【破擦音】
〔言〕(affricate)破裂音の直後に摩擦音がつづき、全体で一つの単音と見なされる音。〔ts〕〔dz〕〔tʃ〕〔dʒ〕など。
は‐さん【破産】🔗⭐🔉
は‐さん【破産】
①家産を破り失うこと。身代かぎり。胆大小心録「火にかかりて―した後は」
②〔法〕債務者がその債務を完済することができない状態に陥った場合に、総債権者に公平な弁済を受けさせようとする裁判上の手続。→会社更生法。
⇒はさん‐かんざいにん【破産管財人】
⇒はさん‐さいけん【破産債権】
⇒はさん‐ざいだん【破産財団】
⇒はさん‐せんこく【破産宣告】
⇒はさん‐ほう【破産法】
は‐さん【破算】🔗⭐🔉
は‐さん【破算】
⇒ごはさん(御破算)
はさん‐かんざいにん【破産管財人】‥クワン‥🔗⭐🔉
はさん‐かんざいにん【破産管財人】‥クワン‥
裁判所の選任により、裁判所の監督の下に破産財団に属する財産の管理と処分に当たる者。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐さいけん【破産債権】🔗⭐🔉
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続において、届出・確定を経て、破産財団から平等弁済すなわち配当を受け得る債権。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐ざいだん【破産財団】🔗⭐🔉
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続開始の決定を受けた債務者の財産。その管理処分権は破産管財人の手に移る。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐せんこく【破産宣告】🔗⭐🔉
はさん‐せんこく【破産宣告】
裁判所が破産手続を開始する旨を宣言する決定。1922年(大正2)制定の旧破産法のもとでの用語。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐ほう【破産法】‥ハフ🔗⭐🔉
はさん‐ほう【破産法】‥ハフ
裁判上の破産手続を定めた法律。1922年(大正11)制定、2004年新法制定。
⇒は‐さん【破産】
は・す【破す】🔗⭐🔉
は・す【破す】
〔他サ変〕
①破る。こわす。
②他の説を言いやぶる。説破する。
③(そろばんで)珠をくずす。御破算にする。〈日葡辞書〉
はっ・す【破す】🔗⭐🔉
はっ・す【破す】
〔他サ変〕
破門する。追放する。天草本伊曾保物語「今日より鳥類の一門を―・するぞ」
は‐の‐まい【破の舞】‥マヒ🔗⭐🔉
は‐の‐まい【破の舞】‥マヒ
能の舞事まいごとの一つ。序の舞・中の舞の後、謡一段を置き、再び舞う短い舞。
はりつ【破笠】🔗⭐🔉
はりつ【破笠】
⇒おがわはりつ(小川破笠)。
⇒はりつ‐ざいく【破笠細工】
はりつ‐ざいく【破笠細工】🔗⭐🔉
はりつ‐ざいく【破笠細工】
貝・陶片・角・牙・木片・板金などを蒔絵と併用して模様を表した漆器。江戸中期の漆工小川破笠が得意とした。
⇒はりつ【破笠】
は‐りゅう【破笠】‥リフ🔗⭐🔉
は‐りゅう【破笠】‥リフ
破れた笠。
やぶ・く【破く】🔗⭐🔉
やぶ・く【破く】
〔他五〕
(「破る」と「裂く」との混成語)破り裂く。やぶる。
やぶ・ける【破ける】🔗⭐🔉
やぶ・ける【破ける】
〔自下一〕
やぶれ裂ける。破れる。
やぶ・る【破る・敗る】🔗⭐🔉
やぶ・る【破る・敗る】
[一]〔他五〕
①固いものを突いてこわす。くだく。万葉集16「小螺しただみをい拾ひりひ持ち来て石もちつつき―・り」。「壁を―・る」
②(紙・布など平らなものを)裂く。やぶく。「障子を―・る」「証文を―・る」
③傷つける。そこなう。神代紀上「性かむさが残そこなひ害やぶることを好む」。沙石集3「身体髪膚を―・らずして」
④他人の心に反するようなことをする。源氏物語紅葉賀「まづくねくねしく恨むる人の心―・らじと思ひて」
⑤妨げて成り立たなくする。だめにする。平家物語3「青嵐夢を―・つて、その面影も見えざりけり」。「型を―・る」「静寂を―・る」
⑥守るべきことにそむき反する。犯す。源氏物語東屋「深き契りを―・りて」。徒然草「万の戒を―・りて、地獄に落つべし」。「約束を―・る」
⑦抵抗を排してつきぬける。突破する。平家物語9「そこを―・つて行く程に土肥次郎実平二千余騎で支へたり」
⑧戦いや勝負事で相手を負かす。(記録などを)更新する。「強敵を―・る」「世界記録を―・る」
[二]〔自下二〕
⇒やぶれる(下一)
やぶれ【破れ】🔗⭐🔉
やぶれ【破れ】
①破れること。破れたもの。また、破れた部分。東大寺諷誦文稿「尊きも卑しきも五竜の残ヤブレを脱まぬがれず」
②事が成立しないこと。破裂。破綻はたん。
③(「敗れ」とも書く)敗北。負け。
⇒やぶれ‐がさ【破れ傘】
⇒やぶれ‐かぶれ【破れかぶれ】
⇒やぶれ‐こもち【破れ子持】
⇒やぶれ‐そう【破れ僧】
⇒やぶれ‐そうぶ【破菖蒲】
⇒やぶれ‐ついじ【破れ築地】
⇒やぶれ‐め【破れ目】
⇒やぶれ‐や【破れ屋】
やぶれ‐がさ【破れ傘】🔗⭐🔉
やぶれ‐がさ【破れ傘】
①やぶれたからかさ。
②〔植〕キク科の多年草。山野に自生。高さ約1メートル。葉は大形で円形、深裂し、破れた傘に似る。夏、白色の頭状花を円錐花序に多数つける。〈[季]夏〉
やぶれがさ
 ヤブレガサ
提供:OPO
ヤブレガサ
提供:OPO
 ⇒やぶれ【破れ】
⇒やぶれ【破れ】
 ヤブレガサ
提供:OPO
ヤブレガサ
提供:OPO
 ⇒やぶれ【破れ】
⇒やぶれ【破れ】
やぶれ‐かぶれ【破れかぶれ】🔗⭐🔉
やぶれ‐かぶれ【破れかぶれ】
やけを起こし、自暴自棄であるさま。「―になってあばれる」
⇒やぶれ【破れ】
やぶれ‐こもち【破れ子持】🔗⭐🔉
やぶれ‐こもち【破れ子持】
子持の女をののしっていう語。宇津保物語蔵開上「あな見ぐるし、なぞの―か物は見るとて」
⇒やぶれ【破れ】
やぶれ‐そう【破れ僧】🔗⭐🔉
やぶれ‐そう【破れ僧】
有髪うはつの僧。また、破戒の僧。
⇒やぶれ【破れ】
やぶれ‐ついじ【破れ築地】‥ヂ🔗⭐🔉
やぶれ‐ついじ【破れ築地】‥ヂ
こわれた築地塀。
⇒やぶれ【破れ】
やぶれ‐め【破れ目】🔗⭐🔉
やぶれ‐め【破れ目】
破れたところ。やれめ。
⇒やぶれ【破れ】
やぶれ‐や【破れ屋】🔗⭐🔉
やぶれ‐や【破れ屋】
いたみこわれた家。むさくるしい家。
⇒やぶれ【破れ】
やぶ・れる【破れる・敗れる】🔗⭐🔉
やぶ・れる【破れる・敗れる】
〔自下一〕[文]やぶ・る(下二)
①形がこわれる。くだける。平家物語灌頂「甍いらか―・れては霧不断の香を焼たき」
②(紙・布など平らなものが)裂ける。やぶける。宇津保物語蔵開下「君はあや・かいねりの所々―・れたる一かさね、すすけたる白ぎぬ着て」。「襖が―・れる」
③害される。傷つく。十訓抄「―・れたる蛇を見て薬をつけて癒やす」
④失敗して心に痛手を受ける。「恋に―・れる」
⑤物事が成り立たなくなる。だめになる。源氏物語葵「除目の夜なりけれど、かくわりなき御さはりなれば、皆事―・れたるやうなり」。「交渉が―・れる」「均衡が―・れる」「夢が―・れる」
⑥戦いや勝負事に負ける。三宝絵詞「そのいくさ―・れぬ」。「試合に―・れる」
◇「敗れる」は、ふつう6で使う。
や・る【破る】🔗⭐🔉
や・る【破る】
[一]〔他四〕
やぶる。引きちぎる。土佐日記「とまれかうまれとく―・りてむ」
[二]〔自下二〕
やぶれる。ちぎれる。神楽歌、採物「笹分けば袖こそ―・れめ」
やれ【破れ】🔗⭐🔉
やれ【破れ】
①やぶれること。やぶれた所。やぶれたもの。「垣根の―をつくろう」
②印刷物のきずもの。
やれ‐がき【破れ垣】🔗⭐🔉
やれ‐がき【破れ垣】
やぶれた垣。
やれ‐がさ【破れ笠】🔗⭐🔉
やれ‐がさ【破れ笠】
やぶれた笠。
やれ‐ぐるま【破れ車】🔗⭐🔉
やれ‐ぐるま【破れ車】
こわれた車。
やれ‐こも【破れ薦】🔗⭐🔉
やれ‐こも【破れ薦】
やぶれた薦。万葉集13「かき棄うてむ―を敷きて」
やれ‐ごろも【破れ衣】🔗⭐🔉
やれ‐ごろも【破れ衣】
やぶれた衣服。
やれ‐ばしょう【破れ芭蕉】‥セウ🔗⭐🔉
やれ‐ばしょう【破れ芭蕉】‥セウ
風雨にたたかれて傷みやぶれた芭蕉の葉。〈[季]秋〉
やれ‐はす【破れ蓮・敗荷】🔗⭐🔉
やれ‐はす【破れ蓮・敗荷】
秋の深まりとともに破れて無残な姿となった蓮の葉。やれはちす。〈[季]秋〉
やれ‐ま【破れ間】🔗⭐🔉
やれ‐ま【破れ間】
やぶれたすきま。仁徳紀「星辰ほしのひかり壊やれまより漏りて」
やれ‐め【破れ目】🔗⭐🔉
やれ‐め【破れ目】
やぶれたところ。やぶれめ。
やれ‐やれ【破れ破れ】🔗⭐🔉
やれ‐やれ【破れ破れ】
ひどくやぶれているさま。ぼろぼろ。宇治拾遺物語8「果てには―と着なしてありけり」
わり‐ご【破子・破籠・樏】🔗⭐🔉
わり‐ご【破子・破籠・樏】
(割子・割籠とも書く)ヒノキの薄い白木で折箱のように造り、内部に仕切りを設けて、かぶせぶたにした弁当箱。また、それに入れた食物。土佐日記「今日―持たせてきたる人」。蜻蛉日記上「―などものして」
⇒わりご‐そば【破子蕎麦】
わりご‐そば【破子蕎麦】🔗⭐🔉
わりご‐そば【破子蕎麦】
段重ねにした漆塗の小さな破子に少しずつそばを入れ、薬味とつゆをかけて食べるもの。出雲地方の名物料理。出雲そば。割子そば。
⇒わり‐ご【破子・破籠・樏】
われ【割れ・破れ】🔗⭐🔉
われ【割れ・破れ】
①われること。われたもの。破片。かけら。
②勝負がつかないこと。わけ。「―相撲」
③相談などがまとまらないこと。
④相場が下落して、ある値段以下になること。→台割れ
われ‐ずもう【割相撲・破角力】‥ズマフ🔗⭐🔉
われ‐ずもう【割相撲・破角力】‥ズマフ
勝負のつかない相撲。われ。誹風柳多留3「―羽織の紐ひぼを結ばせる」
われ‐て【割れて・破れて】🔗⭐🔉
われ‐て【割れて・破れて】
〔副〕
しいて。無理に。ぜひ。伊勢物語「男―逢はむといふ」
わ・れる【割れる・破れる】🔗⭐🔉
わ・れる【割れる・破れる】
〔自下一〕[文]わ・る(下二)
固体に深いひびが入り、そこがはっきりした切れ目になって分かれ、元の形にもどらない状態となる意。
①一つのものが二つ以上に分かれる。裂ける。くだける。万葉集11「高山ゆ出で来る水の岩に触れ―・れてそ思ふ妹に逢はぬ夜は」。東大寺諷誦文稿「法を聞きつるのちは、卵かい破ワレて出でぬるがごとし」。詞花和歌集恋「瀬を早み岩にせかるる滝川の―・れても末にあはむとぞ思ふ」。永仁五年歌合「江に棄つる―・れたる船も身を海にうきて渡るもあはれとぞ見る」。日葡辞書「ツボ・チャワンガワルル」「タケガワルル」。「意見が―・れる」「―・れるような拍手」
②裂け目ができる。「大地が―・れる」「額が―・れる」
③決裂する。甲陽軍鑑2「公方家の諸侯、三善家の侍と二つに―・れ」。日葡辞書「クニガワルル」「ウチワ(内輪)ガワルル」
④秘密などがさらけ出される。浄瑠璃、栬狩剣本地「奥様に知らせ、いつそ―・れて出ようか」。「犯人ほしが―・れる」
⑤勝負事などで、勝負がつかないで終わる。引分けとなる。伊勢物語踊「―・れたるは半月の夜の相撲かな」
⑥今まで持ちこたえていた線が維持できなくなる。相場が下落して、ある値段以下になる。稲の穂「相場二匁五分で持ち合うて居る時…二匁以下に成つたを―・れると言ふ」
⑦野球で、真直ぐ進んで来た投球が急に下方に落ちる。「縦に―・れるカーブ」
われ‐われ【破破・割れ割れ】🔗⭐🔉
われ‐われ【破破・割れ割れ】
別れ別れ。てんでんばらばら。三河物語「一門の衆も―に成りて」
[漢]破🔗⭐🔉
破 字形
 筆順
筆順
 〔石部5画/10画/教育/3943・474B〕
〔音〕ハ(呉)(漢)
〔訓〕やぶる・やぶれる
[意味]
①こわす。くだく。こわれる。裂ける。「破損・破片・破裂・打破・爆破・難破船」
②だめにする。だめになる。「破約・破産・破談・破局」
③敵をやっつける。うちやぶる。「撃破・論破」
④やりとげる。果たす。「読破・看破・走破」
⑤楽曲で変化の多い部分。「序破急」
[解字]
形声。「石」+音符「皮」(=くだき割る音)。石で物をたたいてうち割る意。
[下ツキ
喝破・看破・撃破・小破・翔破・説破・走破・大破・打破・椎破・踏破・道破・読破・突破・難破・爆破・発破・連破・論破
[難読]
破落戸ごろつき・ならずもの・破子わりご・破籠わりご
〔石部5画/10画/教育/3943・474B〕
〔音〕ハ(呉)(漢)
〔訓〕やぶる・やぶれる
[意味]
①こわす。くだく。こわれる。裂ける。「破損・破片・破裂・打破・爆破・難破船」
②だめにする。だめになる。「破約・破産・破談・破局」
③敵をやっつける。うちやぶる。「撃破・論破」
④やりとげる。果たす。「読破・看破・走破」
⑤楽曲で変化の多い部分。「序破急」
[解字]
形声。「石」+音符「皮」(=くだき割る音)。石で物をたたいてうち割る意。
[下ツキ
喝破・看破・撃破・小破・翔破・説破・走破・大破・打破・椎破・踏破・道破・読破・突破・難破・爆破・発破・連破・論破
[難読]
破落戸ごろつき・ならずもの・破子わりご・破籠わりご
 筆順
筆順
 〔石部5画/10画/教育/3943・474B〕
〔音〕ハ(呉)(漢)
〔訓〕やぶる・やぶれる
[意味]
①こわす。くだく。こわれる。裂ける。「破損・破片・破裂・打破・爆破・難破船」
②だめにする。だめになる。「破約・破産・破談・破局」
③敵をやっつける。うちやぶる。「撃破・論破」
④やりとげる。果たす。「読破・看破・走破」
⑤楽曲で変化の多い部分。「序破急」
[解字]
形声。「石」+音符「皮」(=くだき割る音)。石で物をたたいてうち割る意。
[下ツキ
喝破・看破・撃破・小破・翔破・説破・走破・大破・打破・椎破・踏破・道破・読破・突破・難破・爆破・発破・連破・論破
[難読]
破落戸ごろつき・ならずもの・破子わりご・破籠わりご
〔石部5画/10画/教育/3943・474B〕
〔音〕ハ(呉)(漢)
〔訓〕やぶる・やぶれる
[意味]
①こわす。くだく。こわれる。裂ける。「破損・破片・破裂・打破・爆破・難破船」
②だめにする。だめになる。「破約・破産・破談・破局」
③敵をやっつける。うちやぶる。「撃破・論破」
④やりとげる。果たす。「読破・看破・走破」
⑤楽曲で変化の多い部分。「序破急」
[解字]
形声。「石」+音符「皮」(=くだき割る音)。石で物をたたいてうち割る意。
[下ツキ
喝破・看破・撃破・小破・翔破・説破・走破・大破・打破・椎破・踏破・道破・読破・突破・難破・爆破・発破・連破・論破
[難読]
破落戸ごろつき・ならずもの・破子わりご・破籠わりご
大辞林の検索結果 (97)
は-え【破壊】🔗⭐🔉
は-え ― 【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
 【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
は-おく【破屋】🔗⭐🔉
は-おく ―ヲク [0][1] 【破屋】
こわれ破れた家。あばらや。
は-か【破瓜】🔗⭐🔉
は-か ―クワ [1] 【破瓜】
〔「瓜」の字を縦に二分すると,八が二つになることから〕
(1)〔孫綽「情人碧玉歌」〕
(八の二倍で)女の一六歳。思春期の頃。「―期」
(2)〔通俗編(婦女)〕
(八の八倍で)男の六四歳。
(3)性交によって処女膜が破れること。
はかい-むざん【破戒無慚】🔗⭐🔉
はかい-むざん [4] 【破戒無慚】
僧が戒律を破りながら恥と思わないこと。
はかい【破戒】🔗⭐🔉
はかい 【破戒】
小説。島崎藤村作。1906年(明治39)刊。被差別部落出身の小学校教師瀬川丑松が,自己確立へ苦悩し,父の戒めを破って,自分の素性を告白し,周囲の偏見と闘う姿を描く。本格小説の誕生といわれた。
はかい-おうりょく【破壊応力】🔗⭐🔉
はかい-おうりょく ―クワイ― [4] 【破壊応力】
物体に外力を加えるとき,物体が破壊しない限界での応力。極限強さ。
はかい-かつどうぼうしほう【破壊活動防止法】🔗⭐🔉
はかい-かつどうぼうしほう ―クワイクワツドウバウシハフ 【破壊活動防止法】
暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する必要な規制措置を定め,暴力主義的破壊活動に関して刑法の罰則規定を補う法律。1952年(昭和27)制定。破防法。
はかい-しけん【破壊試験】🔗⭐🔉
はかい-しけん ―クワイ― [5][4] 【破壊試験】
材料または製品に荷重を加え,変形または破壊に至る強度を調べる試験。
はかい-しゃ【破壊者】🔗⭐🔉
はかい-しゃ ―クワイ― [2] 【破壊者】
こわす人。安定しているものや組織などをこわす人。「平和の―」
はかい-てき【破壊的】🔗⭐🔉
はかい-てき ―クワイ― [0] 【破壊的】 (形動)
物事をこわそうとするさま。物事の成立や進行を妨げようとするさま。
⇔建設的
「―な意見」
はかい-てん【破壊点】🔗⭐🔉
はかい-てん ―クワイ― [2] 【破壊点】
物体に加えられる外力とそれに抗する応力との釣り合いが破れ,物体が大きく変化して破壊されるその極限の点。
はかい-ぶんし【破壊分子】🔗⭐🔉
はかい-ぶんし ―クワイ― [4] 【破壊分子】
一つの国家・社会などの中にあって,その秩序を破壊しようとする一団の人々。組織の中で破壊的な活動をするメンバー。
はかい-りょく【破壊力】🔗⭐🔉
はかい-りょく ―クワイ― [2] 【破壊力】
物をうちこわす力。
はか-き【破瓜期】🔗⭐🔉
はか-き ハクワ― [2] 【破瓜期】
女子の一五,六歳の頃。思春期。
は-かく【破格】🔗⭐🔉
は-かく [0] 【破格】 (名・形動)[文]ナリ
(1)先例や基準にはずれる・こと(さま)。「―の昇進」「―の安値」
(2)詩や文章などで,きまりにはずれている・こと(さま)。また,その表現。「―な表現」
はか-びょう【破瓜病】🔗⭐🔉
はか-びょう ハクワビヤウ [0] 【破瓜病】
精神分裂病の型の一。特に思春期(破瓜期)に多いので,この名がある。
は-がん【破顔】🔗⭐🔉
は-がん [1][0] 【破顔】 (名)スル
顔をほころばせること。笑うこと。「深沈なる荒尾も已むを得ざらんやうに―しつ/金色夜叉(紅葉)」
はがん-いっしょう【破顔一笑】🔗⭐🔉
はがん-いっしょう ―セウ [1][0] 【破顔一笑】 (名)スル
顔をほころばせて,にっこり笑うこと。「吉報に―する」
はがん-みしょう【破顔微笑】🔗⭐🔉
はがん-みしょう ―セウ [1] 【破顔微笑】 (名)スル
〔仏〕
〔心に悟るところがあってにっこり笑う意〕
「拈華微笑(ネンゲミシヨウ)」に同じ。「爰(ココ)に摩訶迦葉(マカカシヨウ)一人―して,拈花(ネンゲ)瞬目の妙旨を心を以て心に伝へたり/太平記 24」
は-き【破棄・破毀】🔗⭐🔉
は-き [1] 【破棄・破毀】 (名)スル
(1)破って捨てること。「不要書類を―する」
(2)約束を一方的に破ること。「契約を―する」
(3)上級審裁判所が,上訴を理由ありと認め原判決を取り消すこと。
はき-いそう【破棄移送】🔗⭐🔉
はき-いそう [3] 【破棄移送】
事後審を行う裁判所が原判決を破棄し,原裁判所以外の裁判所に審理させること。
はき-さしもどし【破棄差(し)戻し】🔗⭐🔉
はき-さしもどし [1]-[0] 【破棄差(し)戻し】
事後審を行う裁判所が原判決を破棄し,再審理のために原裁判所へ差し戻すこと。
はき-じはん【破棄自判】🔗⭐🔉
はき-じはん [3] 【破棄自判】
事後審を行う裁判所が原判決を破棄し,事件について自ら判決をすること。
は-きゃく【破却】🔗⭐🔉
は-きゃく [0] 【破却】 (名)スル
こわすこと。めちゃめちゃにすること。「法を―する/民約論(徳)」
は-きょう【破鏡】🔗⭐🔉
は-きょう ―キヤウ [0] 【破鏡】
(1)こわれた鏡。
(2)欠けた月。
(3)離婚すること。
〔離れて暮らす夫婦が半分に割った鏡をそれぞれが持ち,他日再会の際の証としたが,妻が不義をはたらき,その一片がカササギとなって夫の所に飛来し,不義が発覚して離縁となったという中国の「神異経」の故事による〕
はきょう=の=嘆き(=嘆(タン))🔗⭐🔉
――の=嘆き(=嘆(タン))
夫婦が離婚しなければならない悲しみ。
はきょう=再び照らさず🔗⭐🔉
――再び照らさず
〔伝灯録〕
別れた夫婦のように,いったんこわれた関係はもとどおりにはならないことのたとえ。覆水盆にかえらず。
は-きょく【破局】🔗⭐🔉
は-きょく [0] 【破局】
今までの状態を維持できなくなること。悲惨な結末になること。「―を迎える」
はぐん-せい【破軍星】🔗⭐🔉
はぐん-せい [2] 【破軍星】
北斗七星の柄の先端の星,揺光(ヨウコウ)の別名。陰陽道(オンヨウドウ)では剣先に見たてこの星のさす方向を凶として忌んだ。破軍。
は-げ【破夏】🔗⭐🔉
は-げ [0] 【破夏】
〔仏〕 夏安居(ゲアンゴ)の期間に禁を破って外出すること。
はこう-だん【破甲弾】🔗⭐🔉
はこう-だん ハカフ― [2] 【破甲弾】
軍艦や戦車など堅固な装甲をもつ目標に対して使う砲弾。徹甲弾。
は-ごく【破獄】🔗⭐🔉
は-ごく [0] 【破獄】 (名)スル
囚人が牢獄を破って抜け出ること。ろうやぶり。脱獄。
は-こん【破婚】🔗⭐🔉
は-こん [0] 【破婚】 (名)スル
婚約・結婚を解消すること。
は-さい【破砕・破摧】🔗⭐🔉
は-さい [0] 【破砕・破摧】 (名)スル
こなごなにすること。「数艘の敵艦を―するとも/近世紀聞(延房)」
はさい-き【破砕機】🔗⭐🔉
はさい-き [2] 【破砕機】
岩石などを細かに砕く機械。クラッシャー。
はさい-たい【破砕帯】🔗⭐🔉
はさい-たい [0] 【破砕帯】
断層に沿って岩石が破壊された帯状の部分。断層角礫や断層粘土が,ある幅で一定の方向に分布する。大規模な断層には大規模な破砕帯を伴う場合が多い。
はさつ-おん【破擦音】🔗⭐🔉
はさつ-おん [3] 【破擦音】
破裂音を伴った摩擦音。ある調音点での閉鎖が開放されると同時に,同一調音点で摩擦音が行われ,その連続で一つの単音とみなされる音。普通 [t ][d
][d ][ts][dz]などの類。
][ts][dz]などの類。
 ][d
][d ][ts][dz]などの類。
][ts][dz]などの類。
は-さん【破産】🔗⭐🔉
は-さん [0] 【破産】 (名)スル
(1)財産をすべて失うこと。「事業に失敗して―する」
(2)債務者が債務の完済をできなくなった状態。また,そうなった場合に,債務者の総財産をすべての債権者に公平に分配できるようにする裁判上の手続き。
はさん-かんざいにん【破産管財人】🔗⭐🔉
はさん-かんざいにん ―クワンザイ― [0] 【破産管財人】
裁判所により選任され,破産財団の管理・処分,破産債権の調査・確定,財団債権の弁済などを行う者。
はさん-さいけん【破産債権】🔗⭐🔉
はさん-さいけん [4] 【破産債権】
破産手続において,破産財団からの公平な配当を要求することができる債権。破産債権は債権確定の手続きを経て確定された債権のみが配当にあずかることができる。
は・す【破す】🔗⭐🔉
は・す 【破す】 (動サ変)
破る。こわす。(論などを)うちやぶる。「埒(ラチ)のほか達磨(ダルマ)を―・する人をこそ法知らずとは云ふべかりけれ/沙石 5」
は-の-まい【破の舞】🔗⭐🔉
は-の-まい ―マヒ [1] 【破の舞】
能の舞の一。女性や天女の軽やかな短い舞。序の舞や中の舞の後,謡をはさんで舞う。「羽衣」「松風」「野宮」「右近」にある。
は-りつ【破笠】🔗⭐🔉
は-りつ [0] 【破笠】
破れた笠。はりゅう。
はりつ【破笠】🔗⭐🔉
はりつ 【破笠】
⇒小川(オガワ)破笠
はりつ-ざいく【破笠細工】🔗⭐🔉
はりつ-ざいく [4] 【破笠細工】
元禄(1688-1704)頃に破笠の創始した蒔絵(マキエ)細工。陶片・鉛・貝・堆朱(ツイシユ)などをはめ込んで文様を表すもの。
は-りゅう【破笠】🔗⭐🔉
は-りゅう ―リフ [0] 【破笠】
「はりつ(破笠)」に同じ。
やぶ・く【破く】🔗⭐🔉
やぶ・く [2] 【破く】 (動カ五[四])
〔「やぶる」と「さく」が混交した語〕
紙や布など薄いものをひきさく。やぶりさく。「手紙を―・く」
[可能] やぶける
やぶ・ける【破ける】🔗⭐🔉
やぶ・ける [3] 【破ける】 (動カ下一)
紙や布など薄いものがさける。やぶれる。「紙が―・ける」
〔「破く」の自動詞形〕
やぶる【破】🔗⭐🔉
やぶる [2] 【破】
暦注の十二直の一。訴訟談判・家屋の取り壊しなどに吉,約束相談に凶という日。
やぶ・る【破る】🔗⭐🔉
やぶ・る [2] 【破る】
■一■ (動ラ五[四])
(1)紙・布などを裂いたり穴をあけたりする。「手紙を―・る」「障子を―・る」
(2)(固い物を)傷をつけてこわす。また,砕く。「殻を―・ってひなが出る」
(3)相手側の備え・守りなどを打ちくだいて通過する。「警戒網を―・る」「関所を―・る」
(4)安定していた状態を乱す。「静寂を―・る」「記録を―・る」
(5)規則・約束などに背く行為をする。「誓いを―・る」
(6)相手を負かす。「優勝候補を―・る」
(7)人の体や心を傷つける。「額―・りて陀羅尼こめたるこそ/宇治拾遺 1」
〔「破れる」に対する他動詞〕
[可能] やぶれる
■二■ (動ラ下二)
⇒やぶれる
やぶれ【破れ】🔗⭐🔉
やぶれ [3] 【破れ】
(1)破れること。破れていること。また,破れたところや物。「靴下の―」「―太鼓」「―障子」
(2)事がうまくゆかないこと。破綻(ハタン)。「先のつまりたるは―に近き道なり/徒然 83」
(3)負け。敗北。
やぶれ-がさ【破れ傘】🔗⭐🔉
やぶれ-がさ [4] 【破れ傘】
(1)破れた傘。
(2)キク科の多年草。山地の林下に生える。茎は高さ約1メートルで,分枝しない。根葉は柄が長く,葉身は大きい円形で掌状に七〜九深裂し,裂片はさらに切れ込む。夏,茎頂に白色の頭花を円錐状につける。[季]夏。
破れ傘(2)
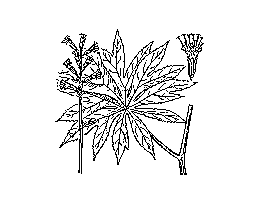 [図]
[図]
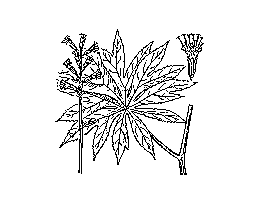 [図]
[図]
やぶれ-かぶれ【破れかぶれ】🔗⭐🔉
やぶれ-かぶれ [4] 【破れかぶれ】 (名・形動)
どうにでもなれとやけになる・こと(さま)。自暴自棄。捨て鉢。「こうなったら―だ」「―になる」「―な気持ち」
やぶれ-ごろも【破れ衣】🔗⭐🔉
やぶれ-ごろも [4] 【破れ衣】
破れた衣服。つづれ。
やぶれ-そう【破れ僧】🔗⭐🔉
やぶれ-そう 【破れ僧】
有髪の僧。また,破戒僧。「―烏帽子きたれば/七十一番職人歌合」
やぶれ-め【破れ目】🔗⭐🔉
やぶれ-め [0][4] 【破れ目】
破れたところ。やれめ。
やぶ・れる【破れる】🔗⭐🔉
やぶ・れる [3] 【破れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 やぶ・る
(1)紙・布などが裂けたり,穴があいたりする。やぶける。「―・れたシャツ」
(2)(固いものが)傷がついてこわれる。また,砕ける。「血管が―・れる」
(3)安定していた状態が失われる。「均衡が―・れる」
(4)事が成立しないで終わる。「夢が―・れる」「恋に―・れる」
(5)傷を負う。「―・れたる蛇を見て,薬をつけていやす/十訓 1」
〔「破る」に対する自動詞〕
やり-す・つ【破り捨つ】🔗⭐🔉
やり-す・つ 【破り捨つ】 (動タ下二)
破り捨てる。「残しおかじと思ふ反古(ホウゴ)など―・つる/徒然 29」
や・る【破る】🔗⭐🔉
や・る 【破る】
■一■ (動ラ四)
やぶる。裂く。「むつかしき反故など―・りて/源氏(浮舟)」
■二■ (動ラ下二)
裂ける。やぶれる。こわれる。「―・れたる草鞋に編笠着て/太平記 11」
やれ【破れ】🔗⭐🔉
やれ [2] 【破れ】
〔動詞「やる(破)」の連用形から〕
(1)破れること。また,破れたところ。やぶれ。「―穴」「―縁」「襖の―をつくろう」
(2)印刷の過程で刷り損じた紙。損紙。
やれ-あな【破れ穴】🔗⭐🔉
やれ-あな [0] 【破れ穴】
やぶれてできた穴。やぶれ穴。「浴衣(ユカタ)の肩に…大きな―があるを/当世書生気質(逍遥)」
やれ-えん【破れ縁】🔗⭐🔉
やれ-えん [2][0] 【破れ縁】
破れた濡れ縁。
やれ-がき【破れ垣】🔗⭐🔉
やれ-がき [2] 【破れ垣】
こわれた垣根。
やれ-がさ【破れ笠】🔗⭐🔉
やれ-がさ [3] 【破れ笠】
破れた笠。
やれ-ごろも【破れ衣】🔗⭐🔉
やれ-ごろも [3] 【破れ衣】
破れた衣服。
やれ-ぞうり【破れ草履】🔗⭐🔉
やれ-ぞうり ―ザウリ [3] 【破れ草履】
破れた草履。
やれ-ばしょう【破れ芭蕉】🔗⭐🔉
やれ-ばしょう ―バセウ [3] 【破れ芭蕉】
葉の破れたバショウ。[季]秋。《横にやれ終には縦に―/虚子》
やれ-はす【破れ蓮・敗荷】🔗⭐🔉
やれ-はす [0] 【破れ蓮・敗荷】
葉の破れたハス。やれはちす。はいか。[季]秋。
やれ-はちす【破れ蓮】🔗⭐🔉
やれ-はちす [3] 【破れ蓮】
「破(ヤ)れ蓮(ハス)」に同じ。[季]秋。
やれ-め【破れ目】🔗⭐🔉
やれ-め [0][3] 【破れ目】
破れた所。やぶれめ。
わり-ご【破り子・破り籠・ 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
わり-ご [0] 【破り子・破り籠・ 】
(1)ヒノキなどの薄板で作った容器。深いかぶせ蓋(ブタ)が付く。食物を携帯するのに用いた。めんぱ。
(2){(1)}に入れた食物。弁当。「道のほどの―などせさす/宇津保(吹上・上)」
破り子(1)
】
(1)ヒノキなどの薄板で作った容器。深いかぶせ蓋(ブタ)が付く。食物を携帯するのに用いた。めんぱ。
(2){(1)}に入れた食物。弁当。「道のほどの―などせさす/宇津保(吹上・上)」
破り子(1)
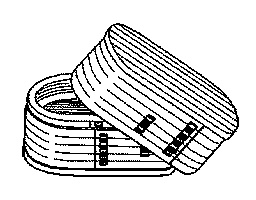 [図]
[図]
 】
(1)ヒノキなどの薄板で作った容器。深いかぶせ蓋(ブタ)が付く。食物を携帯するのに用いた。めんぱ。
(2){(1)}に入れた食物。弁当。「道のほどの―などせさす/宇津保(吹上・上)」
破り子(1)
】
(1)ヒノキなどの薄板で作った容器。深いかぶせ蓋(ブタ)が付く。食物を携帯するのに用いた。めんぱ。
(2){(1)}に入れた食物。弁当。「道のほどの―などせさす/宇津保(吹上・上)」
破り子(1)
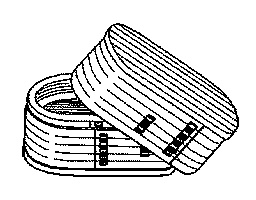 [図]
[図]
わりご-そば【破り子蕎麦】🔗⭐🔉
わりご-そば [4] 【破り子蕎麦】
破り子様の容器に蕎麦を入れ,つゆと薬味をかけて食べるもの。
われ-がね【破れ鐘・割れ鐘】🔗⭐🔉
われ-がね [0] 【破れ鐘・割れ鐘】
割れてひびの入った鐘。また,大きな濁った声のたとえ。「―のような声でどなる」
われ-ごえ【破れ声】🔗⭐🔉
われ-ごえ ―ゴ [3][0] 【破れ声】
太い濁った声。がらがら声。
[3][0] 【破れ声】
太い濁った声。がらがら声。
 [3][0] 【破れ声】
太い濁った声。がらがら声。
[3][0] 【破れ声】
太い濁った声。がらがら声。
われ-ぜに【破れ銭・割れ銭】🔗⭐🔉
われ-ぜに 【破れ銭・割れ銭】
室町時代,ひびが入ったり,破損したりしている銭。撰(エ)り銭の対象となった。
われ-て【破れて】🔗⭐🔉
われ-て 【破れて】 (副)
無理やりに。しいて。ぜひにも。「二日といふ夜,男,―あはむといふ/伊勢 69」
われ-なべ【破れ鍋・割れ鍋】🔗⭐🔉
われ-なべ [0] 【破れ鍋・割れ鍋】
割れてひびの入った鍋。
われなべ=に綴(ト)じ蓋(ブタ)🔗⭐🔉
――に綴(ト)じ蓋(ブタ)
破れ鍋にもふさわしい蓋があるように,どんな人にも相応の配偶者があること。また,配偶者は身分相応の者がよいことのたとえ。
われ-め【割れ目・破れ目】🔗⭐🔉
われ-め [0] 【割れ目・破れ目】
割れた所。さけめ。ひび。「コンクリートの―」「壁に―が入る」
われ-もの【割れ物・破れ物】🔗⭐🔉
われ-もの [0] 【割れ物・破れ物】
(1)割れやすい物。特に,ガラス器・陶磁器など。「―注意」
(2)割れた物。
わ・れる【割れる・破れる】🔗⭐🔉
わ・れる [0] 【割れる・破れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 わ・る
(1)力が加えられて,いくつかの部分に分かれる。くだける。「窓ガラスが―・れる」「卵が―・れた」
(2)切れ目や裂け目ができる。「大地震で地面が―・れた」「打たれて額が―・れる」
(3)まとまっていたものの,まとまりが失われる。分裂する。「党が二つに―・れる」「意見が―・れる」「票が―・れる」「ボリュームを上げると音が―・れる」「内輪ガ―・ルル/日葡」
(4)これまでわからなかったことが明らかになる。《割》「身元が―・れる」「話の筋が―・れる」「ほし(=犯人)が―・れる」「種が―・れる」
(5)(「割れるような」などの形で)(ア)声や音が非常に大きいの意を表す。「―・れるような拍手」「―・れんばかりの大歓声」(イ)頭痛がはげしい様子をいう。「頭が―・れそうに痛い」
(6)基準としていたある数値よりも小さくなる。《割》「一ドル一〇〇円の大台が―・れた」
(7)手形を割り引いてもらって現金になる。《割》
(8)あれやこれやと思って心が乱れる。「宵のまにいでて入りぬるみか月の―・れて物思ふころにもあるかな/古今(雑体)」
(9)分かれる。「瀬を早み岩にせかるる滝川の―・れても末に逢はむとぞ思ふ/詞花(恋上)」
〔「割る」に対する自動詞〕
[慣用] 尻が―・底が―・面が―
はかい【破壊】(和英)🔗⭐🔉
はかい【破戒】(和英)🔗⭐🔉
はかい【破戒】
violation of a commandment.‖破戒僧 a fallen priest.
はかく【破格の】(和英)🔗⭐🔉
はき【破棄】(和英)🔗⭐🔉
はきょく【破局】(和英)🔗⭐🔉
はきょく【破局】
a catastrophe;→英和
the sad end.
はさん【破産】(和英)🔗⭐🔉
やぶる【破る】(和英)🔗⭐🔉
やぶれ【破れ】(和英)🔗⭐🔉
やぶれる【破れる】(和英)🔗⭐🔉
やぶれる【破れる】
be broken (こわれる);be torn (裂ける);break up[off](交渉などが);be worn out (すり切れる);burst (破裂する).→英和
広辞苑+大辞林に「破」で始まるの検索結果。もっと読み込む