複数辞典一括検索+![]()
![]()
けん【見】🔗⭐🔉
けん【見】
①目のつけかた。見かた。考え。狂言、布施無経ふせないきょう「有ると思へば有の―、無いと思へば無の―」
②素見すけん。ひやかし。浮世草子、世間娘容気「遊女の―して帰るなど」
けん・ず【見ず】🔗⭐🔉
けん・ず【見ず】
〔他サ変〕
見る。見て察する。花鏡「為手しての感より―・ずる際きわなり」
ま‐み・える【見える】🔗⭐🔉
ま‐み・える【見える】
〔自下一〕[文]まみ・ゆ(下二)
(「目ま見える」の意)
①お目にかかる。謁見する。三蔵法師伝承徳点「更に天顔に見マミエざらむことを慮おもふ」
②会う。対面する。「敵に―・える」
③妻として夫につかえる。「貞女は二夫に―・えず」
み【見】🔗⭐🔉
み【見】
見ること。万葉集20「山見れば―のともしく川見れば―のさやけく」。「花―」
みえ【見え】🔗⭐🔉
みえ‐あ・う【見え逢ふ】‥アフ🔗⭐🔉
みえ‐あ・う【見え逢ふ】‥アフ
〔自四〕
出会う。宇治拾遺物語9「―・はばまた頭わらむともこそいへ」
みえ‐あた・る【見え当る】🔗⭐🔉
みえ‐あた・る【見え当る】
〔自四〕
見あたる。みつかる。狂言、連歌盗人「両人ともに見知つて居られます程に、自然―・りたりとも、別の事もござるまい」
みえ‐かえ・る【見え返る】‥カヘル🔗⭐🔉
みえ‐かえ・る【見え返る】‥カヘル
〔自四〕
くり返し見える。万葉集12「わがせこが夢いめに夢にし―・るらむ」
みえ‐がくれ【見え隠れ】🔗⭐🔉
みえ‐がくれ【見え隠れ】
①見えたり隠れたりすること。隠見。「―にあとをつける」
②建築の部材の隠れて見えない所。
みえ‐かわ・す【見え交す】‥カハス🔗⭐🔉
みえ‐かわ・す【見え交す】‥カハス
〔自四〕
互いに相手に見られる。顔を見合わせる。栄華物語布引滝「中に物引きなどして、―・さでぞありける」
みえ‐ぐる・し【見え苦し】🔗⭐🔉
みえ‐ぐる・し【見え苦し】
〔形シク〕
見られることが苦しい。会うことがきまりわるい。源氏物語東屋「すずろに―・しう恥かしくて」
みえ‐しらが・う【見えしらがふ】‥シラガフ🔗⭐🔉
みえ‐しらが・う【見えしらがふ】‥シラガフ
〔自四〕
わざと人目につくようにする。枕草子87「常に―・ひありく」
みえ‐す・く【見え透く】🔗⭐🔉
みえ‐す・く【見え透く】
〔自五〕
①底までとおって見える。内まで透いて見える。
②(人の言動の裏にかくれた意図などが)よくわかる。「―・いた嘘」
みえ‐た‐か【見えたか】🔗⭐🔉
みえ‐た‐か【見えたか】
「ざまをみろ」の意。狂言、舎弟「―勝たぞ勝たぞ勝たぞ」
みえ‐にく・い【見え難い】🔗⭐🔉
みえ‐にく・い【見え難い】
〔形〕[文]みえにく・し(ク)
①見ることが困難だ。見にくい。
②見られるのがきまりわるい。源氏物語総角「いたくすみたるけしきの―・く恥かしげなりしに」
みえぬ‐くに【見えぬ国】🔗⭐🔉
みえぬ‐くに【見えぬ国】
人目につかない国。他国。美人くらべ「此上は御命助け参らせん、何方へも―へ忍び候へ」
みえ‐まが・う【見え紛ふ】‥マガフ🔗⭐🔉
みえ‐まが・う【見え紛ふ】‥マガフ
〔自四〕
まぎらわしく見える。まちがって見える。後撰和歌集春「白雲とのみ―・ひつつ」
みえ‐みえ【見え見え】🔗⭐🔉
みえ‐みえ【見え見え】
本人の隠そうとしている魂胆・意図などが、他人にははっきりとわかってしまうさま。「―のうそをつく」
み・える【見える】🔗⭐🔉
み・える【見える】
〔自下一〕[文]み・ゆ(下二)
(動詞ミ(見)に自発の助動詞ユが付いた語)
①自然に目にうつる。目に入る。古事記中「千葉のかづ野を見ればももちだる家庭やにわも―・ゆ国の秀ほも―・ゆ」。土佐日記「月明ければいとよく有様―・ゆ」。「眼下に山が―・える」
②見る能力がある。「猫は夜でも物が―・える」
③(他から)見られる。万葉集15「物思ふと人には―・えじ下紐の下ゆ恋ふるに」。源氏物語少女「うち腫れたるまみも人に―・えむが恥かしきに」。徒然草「心おとりせらるる本性―・えんこそ口惜しかるべけれ」
④(他の人に見られる意から)見せる。万葉集18「月待ちて家にはゆかむわが挿せるあから橘影に―・えつつ」。源氏物語桐壺「はかなき花・紅葉につけても心ざしを―・え奉り」
⑤(見られる意から)妻となる。源氏物語若菜上「女は男に―・ゆるにつけてこそ、くやしげなる事も目ざましき思ひもおのづから打ちまじるものなめれど」
⑥会う。源氏物語葵「世の中のいと憂く覚ゆる程すぐしてなむ人にも―・え奉るべき」
⑦「来る」の尊敬語。源氏物語早蕨「時々も―・え給へ」。蜻蛉日記中「日暮るるほどに、文―・えたり」。「まだどなたも―・えません」
⑧見受けられる。思われる。徒然草「ただ人も、舎人など賜はるきはは、ゆゆしと―・ゆ」。「金持に―・える」
⑨見て、わかる。見てとれる。「先が―・える」
みえ‐わか・る【見え分る】🔗⭐🔉
みえ‐わか・る【見え分る】
〔自下二〕
見わけられる。源氏物語帚木「まことの物の上手は、さまことに―・れ侍り」
みえ‐わ・く【見え分く】🔗⭐🔉
みえ‐わ・く【見え分く】
〔自四〕
見分けがつく。栄華物語玉飾「さやかなる月とはいさや―・かず」
みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ🔗⭐🔉
みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ
(「見ケ〆料」とも書く)暴力団が、飲食店などから監督・保護の対価という名目で取る金銭。
み‐がてり【見がてり】🔗⭐🔉
み‐がてり【見がてり】
(ガテリは助詞)見ながら。みがてら。万葉集1「山のへのみ井を―神風の伊勢をとめども相見つるかも」
み‐が‐ほ・し【見が欲し】🔗⭐🔉
み‐が‐ほ・し【見が欲し】
〔形シク〕
(ガはもと助詞)見たい。万葉集6「山見れば山も―・し」
み‐こな・す【見こなす】🔗⭐🔉
み‐こな・す【見こなす】
〔他四〕
みくびる。軽蔑する。こなす。傾城禁短気「第一客を―・すは女郎の大疵」
み・す【見す】(自四)🔗⭐🔉
み・す【見す】
〔自四〕
(「見る」に尊敬の助動詞スの付いた語か)ごらんになる。継体紀「御諸みもろが上に登り立ち我が―・せば」→めす
み・す【見す】(他下二)🔗⭐🔉
み・す【見す】
〔他下二〕
⇒みせる(下一)
みず‐しらず【見ず知らず】🔗⭐🔉
みず‐しらず【見ず知らず】
一面識もないこと。また、その人。浄瑠璃、心中宵庚申「乗合の―にも可愛らしいと思ふ人もある」。「―の人」
みす‐みす【見す見す】🔗⭐🔉
みす‐みす【見す見す】
〔副〕
①目の前に見えて。それとはっきりわかって。紫式部日記「目に―あさましきものは人の心なりければ」
②目の前に見ていながら、あるいは、そうとわかっているにもかかわらず、どうにもならないさま。むざむざと。「―とり逃した」
みせ‐がお【見せ顔】‥ガホ🔗⭐🔉
みせ‐がお【見せ顔】‥ガホ
見せつけるような顔つき。拾遺和歌集愚草上「植ゑおきし昔を人に―にはるかになびく青柳の糸」
みせ‐かけ【見せ掛け】🔗⭐🔉
みせ‐かけ【見せ掛け】
見せ掛けること。うわべ。外見。「―だけの作り」
⇒みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】
みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】🔗⭐🔉
みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】
金持のように見せかけること。また、その人。
⇒みせ‐かけ【見せ掛け】
みせ‐か・ける【見せ掛ける】🔗⭐🔉
みせ‐か・ける【見せ掛ける】
〔他下一〕[文]みせか・く(下二)
本物でないものを本物のように思わせる。うわべをよく見せる。また、ある物を別の物のように思わせる。「新品に―・ける」
みせ‐がね【見せ金】🔗⭐🔉
みせ‐がね【見せ金】
商取引などで、信用を得るために相手に見せる金銭。みせきん。
みせ‐ぎぬ【見せ衣】🔗⭐🔉
みせ‐ぎぬ【見せ衣】
人に見せるために座敷などにかける衣裳。
みせ‐ぎょく【見せ玉】🔗⭐🔉
みせ‐ぎょく【見せ玉】
(取引用語)約定やくじょうする意思がないにもかかわらず、市場に売買注文を出して相場を変動させ、約定する前に注文を取り消すこと。金融商品取引法等により罰せられる。見せ板。
みせ‐きん【見せ金】🔗⭐🔉
みせ‐きん【見せ金】
⇒みせがね
みせ‐けち【見せ消ち】🔗⭐🔉
みせ‐けち【見せ消ち】
写本などで、字句の訂正をするのに、もとの文字が読めるようにした消し方。その文字に傍点または細い線などをしるす。
みせ‐ざや【見せ鞘】🔗⭐🔉
みせ‐ざや【見せ鞘】
腰刀の鞘を納める染革または錦製の袋。鞘尻より長く作り、余りを飾りとして折りさげるところから提鞘さげざやともいう。懸鞘かけざや。
見せ鞘
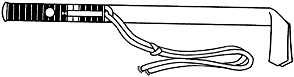
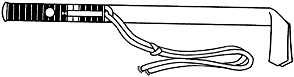
みせ‐しめ【見せしめ】🔗⭐🔉
みせ‐しめ【見せしめ】
他の者への今後の戒めとするため、ある者をこらしめて見せること。甲陽軍鑑2「勁を切て軍門にさらし、近辺の―に仕る」。「―のために厳重に罰する」
みせ‐ぜい【見せ勢】🔗⭐🔉
みせ‐ぜい【見せ勢】
見せかけの軍勢。〈日葡辞書〉
みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ🔗⭐🔉
みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ
虚勢を示して敵軍をあざむく陣立て。
みせ‐だま【見せ球】🔗⭐🔉
みせ‐だま【見せ球】
野球で、決め球を効果的に使うために投げる、決め球と球種やコースの異なる球。
みせ‐つ・ける【見せ付ける】🔗⭐🔉
みせ‐つ・ける【見せ付ける】
〔他下一〕[文]みせつ・く(下二)
人に自慢らしくみせる。これみよがしに見せる。「睦まじい仲を―・ける」
みせ‐どころ【見せ所】🔗⭐🔉
みせ‐どころ【見せ所】
自信があり人に見せたいところ。人が見る価値のあるところ。「ここが腕の―」
みせ‐ば【見せ場】🔗⭐🔉
みせ‐ば【見せ場】
演劇などで、役者の得意な芸が発揮される場面。転じて、見る価値のある場面。「―を作る」
みせ‐ばた【見せ旗】🔗⭐🔉
みせ‐ばた【見せ旗】
合戦で味方が大勢いるように見せかけるために立てる旗。
みせ‐ばや【見せばや】🔗⭐🔉
みせ‐ばや【見せばや】
ベンケイソウ科の多年草。高さ約30センチメートル、直立せず、たわんで垂れ下がる。全体やや紅色を帯びる。葉は3枚ずつ輪生、円形で多肉。秋、茎頂に多数の美しい淡紅色花を球状につける。観賞用に栽培。原産地は不明。小豆島しょうどしまの寒霞渓に同種が、東北の山地には近縁のツガルミセバヤが自生。タマノオ。〈[季]秋〉
みせばや
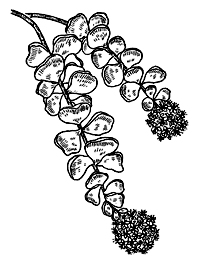
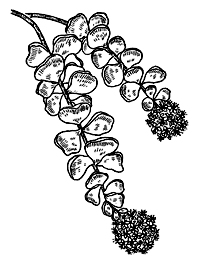
みせ‐びらか・す【見せびらかす】🔗⭐🔉
みせ‐びらか・す【見せびらかす】
〔他五〕
見せて自慢する。みせつける。「高価な品を―・す」
みせ‐やぐら【見せ櫓】🔗⭐🔉
みせ‐やぐら【見せ櫓】
(→)井楼せいろう1に同じ。
み・せる【見せる】🔗⭐🔉
み・せる【見せる】
〔他下一〕[文]み・す(下二)
①相手が見るようにする。見させる。「写真を―・せる」「人前に姿を―・せる」
②おもてに表す。「誠意を―・せる」「苦心のほどを―・せる」
③分からせる。思い知らせる。「目にもの―・せる」
④受けさせる。被らせる。経験させる。「憂き目を―・せる」
⑤診察を受ける。「医者に―・せる」
⑥占わせる。源氏物語明石「忍びてよろしき日―・せて」
⑦めあわせる。夫婦にさせる。源氏物語若菜下「かしづかんと思はん女子をば宮仕へにつぎては親王みこたちにこそは―・せたてまつらめ」
⑧(動詞連用形に助詞「て」「で」の伴ったものに付いて)
㋐(分からせるために)…して示す。「ピアノを弾いて―・せる」「うなずいて―・せる」
㋑故意に…する。(決意を示して)きっと…する。「やって―・せるぞ」
▷1では相手の心を魅了する意を利かせて、同音の当て字で「魅せる」と書くことがある。「―・せる演技」
○店を閉めるみせをしめる
①その日の営業を終了して閉店する。
②廃業する。
⇒みせ【店・見世】
○店をたたむみせをたたむ
商売をやめる。店じまいをする。
⇒みせ【店・見世】
○店を張るみせをはる
①商人が店を設けて商品を並べる。
②遊女が張見世に並んで客を待つ。
⇒みせ【店・見世】
○店を引くみせをひく
①店を片づける。店をしまう。狂言、鴈盗人「今代りを持て来う程に、店を引いておくりやれ」
②遊女が張見世に出ない。遊女が勤めを休む。
⇒みせ【店・見世】
○店を広げるみせをひろげる
①品物などを取り出していっぱいに並べる。
②店舗を拡張する。間口を広げる。比喩的に、扱う対象の範囲を広げる。
⇒みせ【店・見世】
みそこなわ・す【見そこなはす】ミソコナハス🔗⭐🔉
みそこなわ・す【見そこなはす】ミソコナハス
〔他四〕
(尊敬の意の「見す」の連用形「見し」と「行はす」との複合語)(→)「みそなわす」に同じ。万葉集1「天皇、昔日むかしより猶し存のこれる物を―・し」
みそな・う【見そなふ】ミソナフ🔗⭐🔉
みそな・う【見そなふ】ミソナフ
〔他四〕
(→)「みそなわす」に同じ。新古今和歌集釈教「神も仏も我を―・へ」
みそなわ・す【見そなはす】ミソナハス🔗⭐🔉
みそなわ・す【見そなはす】ミソナハス
〔他四〕
(ミソコナワスの約)「見る」の尊敬語。御覧になる。古今和歌集序「今も―・し、後の世にも伝はれとて」
みたく‐でも‐ない【見たくでもない】🔗⭐🔉
みたく‐でも‐ない【見たくでもない】
①(「見たくもない」を強めた語)見たいとも思わない。見るのもいやだ。浮世風呂2「酒なんざア、見たくでもねへ」
②見るにたえない。みっともない。体裁が悪い。東海道中膝栗毛2「ヤレチヤ、又―いさかいか。マアしづまりなさろ」
み‐だます【見だます】🔗⭐🔉
み‐だます【見だます】
(「たます」は分配の単位)地引網漁で網引を見ている者への魚の分配。
みたむ‐な・い【見たむない】🔗⭐🔉
みたむ‐な・い【見たむない】
〔形〕
(ミタクモナイの転)みたくない。体裁がよくない。みっともない。狂言、髭櫓「その髭が朝夕―・うてなりませぬ」
みた‐め【見た目】🔗⭐🔉
みた‐め【見た目】
他人の目にうつる様子・姿。「―が良い」
みた‐よう‐だ【見た様だ】‥ヤウ‥🔗⭐🔉
みた‐よう‐だ【見た様だ】‥ヤウ‥
(初め「…を見たようだ」の形で用いたが、後には「を」を伴わずに体言に直接した。明治期にさらに転じて「みたいだ」になった)…のようだ。…らしい。洒落本、辰巳之園「何だか、雨落のきしやご見たように、しやれのめすよ」
みて‐くれ【見て呉れ】🔗⭐🔉
みて‐くれ【見て呉れ】
①「見てくれ」と言わんばかりの、人目につくようなふるまいや身なり。洒落本、徒然睟が川「諸事―をもつぱらとして」
②みかけ。外見。みば。浮世床2「―は立派だが」。「―が悪い」
みて‐と・る【見て取る】🔗⭐🔉
みて‐と・る【見て取る】
〔他五〕
見て、まわりの情勢や相手の真意などをすばやく察知する。さとる。看取する。「形勢は不利だと―・る」
○見ての通りみてのとおり
見ればすぐ分かるとおり。見たまま。「―の落胆ぶりだ」
⇒みる【見る・視る・観る】
○見て見ぬ振りをするみてみぬふりをする
実際には見ても見なかったように振る舞う。また、きびしくとがめず見逃してやる。
⇒みる【見る・視る・観る】
○見ての通りみてのとおり🔗⭐🔉
○見ての通りみてのとおり
見ればすぐ分かるとおり。見たまま。「―の落胆ぶりだ」
⇒みる【見る・視る・観る】
○見て見ぬ振りをするみてみぬふりをする🔗⭐🔉
○見て見ぬ振りをするみてみぬふりをする
実際には見ても見なかったように振る舞う。また、きびしくとがめず見逃してやる。
⇒みる【見る・視る・観る】
み・てる
〔自下一〕
(中国地方で)尽きる。なくなる。
み‐と【水門・水戸】
(トは入口の意)
①海水の出入口。また、大河の海に入る所。みなと。土佐日記「阿波の―を渡る」
②堰いせき。すいもん。〈倭名類聚鈔10〉
みと【水戸】
茨城県中部の市。県庁所在地。那珂川の南に位置する、もと徳川氏35万石の城下町。城址には弘道館・孔子廟があり、偕楽園も有名。水府。人口26万3千。
みと‐あたわ・す【婚はす】‥アタハス
〔自四〕
(トは入口。陰部の意。アタハスはアタフの尊敬語)交合なさる。結婚なさる。古事記上「先の期ちぎりの如く―・しつ」
み‐とう【御灯】
①神仏・貴人の前にともす灯火。ごとう。みあかし。浄瑠璃、曾我会稽山「―の光しんしんと」
②平安時代、毎年3月3日・9月3日、天皇が京都北山の霊巌寺の北辰菩薩(妙見菩薩)に奉納した灯火。ごとう。
み‐とう【未到】‥タウ
まだ到達しないこと。「前人―の記録」
み‐とう【未踏】‥タフ
まだ足をふみ入れないこと。実地に歩いてみないこと。「人跡じんせき―の地」
み‐とう【味到】‥タウ
事柄の内容や情味などを十分に味わい知ること。味得。
み‐どう【御堂】‥ダウ
①仏像を安置した堂。源氏物語賢木「ことに建てられたる―の西の対の南にあたりて」
②法成寺ほうじょうじの異称。
⇒みどう‐かんぱく【御堂関白】
⇒みどう‐すじ【御堂筋】
みどう‐かんぱく【御堂関白】‥ダウクワン‥
(関白と称され法成寺を建立したところからいう)藤原道長の異称。
⇒み‐どう【御堂】
みどうかんぱくき【御堂関白記】‥ダウクワン‥
御堂関白と称される藤原道長の日記。998年(長徳4)から1021年(治安1)に至る。もと36巻。14巻の自筆本と12巻の古写本が現存する。具注暦ぐちゅうれきに記入したもの。
みどう‐すじ【御堂筋】‥ダウスヂ
大阪市北区の梅田から浪速区の難波なんばに至る通り。ビジネス街・繁華街。通りに沿う本願寺別院の北御堂・南御堂に因む名。
御堂筋(1)
撮影:的場 啓
 御堂筋(2)
撮影:的場 啓
御堂筋(2)
撮影:的場 啓
 ⇒み‐どう【御堂】
みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥
〔形ク〕
(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」
み‐とおし【見通し】‥トホシ
①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」
②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」
③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」
④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤
みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥
粟野膳あわのぜんの別称。
み‐とお・す【見通す】‥トホス
〔他五〕
①始めから終りまで目をとおす。
②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。
③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」
みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ
江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。
みと‐がく【水戸学】
江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。
み‐とが・める【見咎める】
〔他下一〕[文]みとが・む(下二)
①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」
②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」
み‐どき【見時】
見るによい時期。見頃。「桜の―」
み‐どきょう【御読経】‥キヤウ
①読経の尊敬語。
②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」
みとき‐よく【御時好く】
御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」
みとく【未得】
⇒いしだみとく(石田未得)
み‐とく【味得】
事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。
み‐と・く【見解く】
〔他四〕
見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」
み‐どく【味読】
内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」
みと‐け【水戸家】
徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。
みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥
(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。
み‐ところ【三所】
三つのところ。3点。
⇒みところ‐ぜめ【三所攻】
⇒みところ‐どう【三所籐】
⇒みところ‐もの【三所物】
み‐どころ【見所】
①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」
②将来の望み。みこみ。「―のある人物」
③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」
④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」
⑤能の見物席。けんしょ。
み‐どころ【身所】
魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」
みところ‐ぜめ【三所攻】
相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。
みところぜめ
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐どう【三所籐】
所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐もの【三所物】
刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。
⇒み‐ところ【三所】
ミトコンドリア【mitochondria】
細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。
⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】
ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ
ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。
⇒ミトコンドリア【mitochondria】
み‐とし【御年】
穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」
みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】
素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」
み‐としろ【御戸代・御刀代】
(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」
ミトス【mythos ギリシア】
⇒ミュトス
み‐とせ【三年・三歳】
3ねん。3さい。
み‐とど・ける【見届ける】
〔他下一〕[文]みとど・く(下二)
①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」
②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」
みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ
(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」
ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ
オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。
みと‐びらき【御戸開き】
神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」
みと‐ぼり【水戸彫】
彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。
みと‐まつり【水戸祭】
水口みなくち祭のこと。
みとみ【三富】
姓氏の一つ。
⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】
みとみ‐くちは【三富朽葉】
(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)
⇒みとみ【三富】
みと・む【認む】
〔他下二〕
⇒みとめる(下一)
みとむ‐な・い
〔形〕
(→)「みともない」に同じ。
みとめ【認め】
①認めること。
②認印みとめいんの略。
⇒みとめ‐いん【認印】
みとめ‐いん【認印】
①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。
②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。
⇒みとめ【認め】
みと・める【認める】
〔他下一〕[文]みと・む(下二)
(見留める意)
①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」
②目にとめる。「人影を―・める」
③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」
④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」
⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」
み‐ども【身共】
〔代〕
(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。
みとも‐がみ【御伴神】
(→)「みとものかみ」に同じ。
みとも‐な・い
〔形〕
(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」
みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】
尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。
みとよ【三豊】
香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。
ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。
⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】
ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ
(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。
⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
み‐とらし【御執】
(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」
み‐とり【見取り】
①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。
②見て写しとること。「―本」
③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。
④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。
⑤見取小作の略。
→みどり。
⇒みとり‐こさく【見取小作】
⇒みとり‐ざん【見取り算】
⇒みとり‐ず【見取図】
⇒みとり‐ば【見取場】
⇒みとり‐まい【見取米】
みどり
群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。
みどり【緑・翠】
(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)
①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」
②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」
Munsell color system: 2.5G5/10
③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」
⇒みどり‐いし【緑石】
⇒みどり‐がめ【緑亀】
⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】
⇒みどり‐ざる【緑猿】
⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】
⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】
⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】
⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】
⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】
⇒みどり‐の‐とう【緑の党】
⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】
⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】
⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】
⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
⇒みどり‐むし【緑虫】
み‐どり【見取り】
①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」
②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」
みどり‐いし【緑石】
ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐がめ【緑亀】
アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐ご【緑児・嬰児】
(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐こさく【見取小作】
江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐ざる【緑猿】
サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ざん【見取り算】
珠算で、数字を見ながら計算すること。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐ず【見取図】‥ヅ
①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。
②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥
学童擁護員の俗称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ
①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。
②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
つやのある美しい黒髪。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ころも【緑の衣】
六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐そで【緑の袖】
(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ダム【緑のダム】
森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ
(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐はやし【緑の林】
(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ひ【みどりの日】
国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ほら【緑の洞】
(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ば【見取場】
江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐まい【見取米】
江戸時代、見取場から上納させた年貢米。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐むし【緑虫】
ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。
⇒みどり【緑・翠】
み‐と・る【見取る】
〔他五〕
①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」
②見て写し取る。
③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」
ミドル【middle】
①中等。中級。中間。
②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」
⇒ミドル‐アイアン【middle iron】
⇒ミドル‐ウェア【middleware】
⇒ミドル‐エイジ【middle age】
⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】
⇒ミドル‐クラス【middle class】
⇒ミドル‐ショット【middle shot】
⇒ミドル‐スクール【middle school】
⇒ミドル‐ネーム【middle name】
⇒ミドル‐マネージメント【middle management】
ミドル‐アイアン【middle iron】
ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ウェア【middleware】
コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐エイジ【middle age】
中年。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ
(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐クラス【middle class】
中間層。中産階級。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ショット【middle shot】
写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐スクール【middle school】
アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ネーム【middle name】
欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐マネージメント【middle management】
(→)中間管理職のこと。
⇒ミドル【middle】
み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】
〔自下一〕[文]みと・る(下二)
我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」
みどろ【塗】
〔接尾〕
名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」
みどろ・し
〔形ク〕
まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」
ミトン【mitten】
親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。
みな【皆】
[一]〔名〕
全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」
[二]〔副〕
残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」
⇒皆にす
⇒皆になす
⇒皆になる
みな【蜷】
ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」
み‐な‐あい【水合】‥アヒ
水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」
み‐な‐うら【水占】
(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」
み‐なお・す【見直す】‥ナホス
[一]〔他五〕
①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」
②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」
[二]〔自五〕
病気または景気などが少しよい方に向かう。
み‐なか【真中】
まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」
み‐なが・す【見流す】
〔他五〕
見ても気にとめない。見すごす。
みなかた【南方】
姓氏の一つ。
⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)
南方熊楠
提供:毎日新聞社
⇒み‐どう【御堂】
みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥
〔形ク〕
(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」
み‐とおし【見通し】‥トホシ
①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」
②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」
③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」
④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤
みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥
粟野膳あわのぜんの別称。
み‐とお・す【見通す】‥トホス
〔他五〕
①始めから終りまで目をとおす。
②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。
③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」
みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ
江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。
みと‐がく【水戸学】
江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。
み‐とが・める【見咎める】
〔他下一〕[文]みとが・む(下二)
①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」
②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」
み‐どき【見時】
見るによい時期。見頃。「桜の―」
み‐どきょう【御読経】‥キヤウ
①読経の尊敬語。
②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」
みとき‐よく【御時好く】
御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」
みとく【未得】
⇒いしだみとく(石田未得)
み‐とく【味得】
事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。
み‐と・く【見解く】
〔他四〕
見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」
み‐どく【味読】
内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」
みと‐け【水戸家】
徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。
みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥
(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。
み‐ところ【三所】
三つのところ。3点。
⇒みところ‐ぜめ【三所攻】
⇒みところ‐どう【三所籐】
⇒みところ‐もの【三所物】
み‐どころ【見所】
①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」
②将来の望み。みこみ。「―のある人物」
③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」
④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」
⑤能の見物席。けんしょ。
み‐どころ【身所】
魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」
みところ‐ぜめ【三所攻】
相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。
みところぜめ
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐どう【三所籐】
所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐もの【三所物】
刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。
⇒み‐ところ【三所】
ミトコンドリア【mitochondria】
細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。
⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】
ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ
ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。
⇒ミトコンドリア【mitochondria】
み‐とし【御年】
穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」
みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】
素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」
み‐としろ【御戸代・御刀代】
(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」
ミトス【mythos ギリシア】
⇒ミュトス
み‐とせ【三年・三歳】
3ねん。3さい。
み‐とど・ける【見届ける】
〔他下一〕[文]みとど・く(下二)
①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」
②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」
みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ
(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」
ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ
オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。
みと‐びらき【御戸開き】
神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」
みと‐ぼり【水戸彫】
彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。
みと‐まつり【水戸祭】
水口みなくち祭のこと。
みとみ【三富】
姓氏の一つ。
⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】
みとみ‐くちは【三富朽葉】
(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)
⇒みとみ【三富】
みと・む【認む】
〔他下二〕
⇒みとめる(下一)
みとむ‐な・い
〔形〕
(→)「みともない」に同じ。
みとめ【認め】
①認めること。
②認印みとめいんの略。
⇒みとめ‐いん【認印】
みとめ‐いん【認印】
①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。
②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。
⇒みとめ【認め】
みと・める【認める】
〔他下一〕[文]みと・む(下二)
(見留める意)
①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」
②目にとめる。「人影を―・める」
③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」
④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」
⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」
み‐ども【身共】
〔代〕
(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。
みとも‐がみ【御伴神】
(→)「みとものかみ」に同じ。
みとも‐な・い
〔形〕
(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」
みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】
尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。
みとよ【三豊】
香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。
ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。
⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】
ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ
(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。
⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
み‐とらし【御執】
(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」
み‐とり【見取り】
①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。
②見て写しとること。「―本」
③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。
④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。
⑤見取小作の略。
→みどり。
⇒みとり‐こさく【見取小作】
⇒みとり‐ざん【見取り算】
⇒みとり‐ず【見取図】
⇒みとり‐ば【見取場】
⇒みとり‐まい【見取米】
みどり
群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。
みどり【緑・翠】
(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)
①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」
②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」
Munsell color system: 2.5G5/10
③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」
⇒みどり‐いし【緑石】
⇒みどり‐がめ【緑亀】
⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】
⇒みどり‐ざる【緑猿】
⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】
⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】
⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】
⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】
⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】
⇒みどり‐の‐とう【緑の党】
⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】
⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】
⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】
⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
⇒みどり‐むし【緑虫】
み‐どり【見取り】
①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」
②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」
みどり‐いし【緑石】
ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐がめ【緑亀】
アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐ご【緑児・嬰児】
(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐こさく【見取小作】
江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐ざる【緑猿】
サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ざん【見取り算】
珠算で、数字を見ながら計算すること。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐ず【見取図】‥ヅ
①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。
②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥
学童擁護員の俗称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ
①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。
②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
つやのある美しい黒髪。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ころも【緑の衣】
六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐そで【緑の袖】
(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ダム【緑のダム】
森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ
(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐はやし【緑の林】
(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ひ【みどりの日】
国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ほら【緑の洞】
(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ば【見取場】
江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐まい【見取米】
江戸時代、見取場から上納させた年貢米。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐むし【緑虫】
ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。
⇒みどり【緑・翠】
み‐と・る【見取る】
〔他五〕
①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」
②見て写し取る。
③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」
ミドル【middle】
①中等。中級。中間。
②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」
⇒ミドル‐アイアン【middle iron】
⇒ミドル‐ウェア【middleware】
⇒ミドル‐エイジ【middle age】
⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】
⇒ミドル‐クラス【middle class】
⇒ミドル‐ショット【middle shot】
⇒ミドル‐スクール【middle school】
⇒ミドル‐ネーム【middle name】
⇒ミドル‐マネージメント【middle management】
ミドル‐アイアン【middle iron】
ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ウェア【middleware】
コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐エイジ【middle age】
中年。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ
(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐クラス【middle class】
中間層。中産階級。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ショット【middle shot】
写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐スクール【middle school】
アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ネーム【middle name】
欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐マネージメント【middle management】
(→)中間管理職のこと。
⇒ミドル【middle】
み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】
〔自下一〕[文]みと・る(下二)
我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」
みどろ【塗】
〔接尾〕
名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」
みどろ・し
〔形ク〕
まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」
ミトン【mitten】
親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。
みな【皆】
[一]〔名〕
全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」
[二]〔副〕
残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」
⇒皆にす
⇒皆になす
⇒皆になる
みな【蜷】
ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」
み‐な‐あい【水合】‥アヒ
水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」
み‐な‐うら【水占】
(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」
み‐なお・す【見直す】‥ナホス
[一]〔他五〕
①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」
②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」
[二]〔自五〕
病気または景気などが少しよい方に向かう。
み‐なか【真中】
まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」
み‐なが・す【見流す】
〔他五〕
見ても気にとめない。見すごす。
みなかた【南方】
姓氏の一つ。
⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)
南方熊楠
提供:毎日新聞社
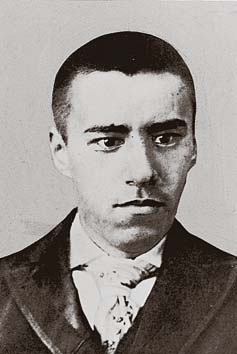 ⇒みなかた【南方】
み‐な‐かみ【水上】
①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。
②物事の起源。みなもと。
みなかみ【水上】
群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。
▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。
みなかみ【水上】
姓氏の一つ。
⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】
み‐な‐かみ【水神】
水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」
みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ
小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)
水上滝太郎
提供:岩波書店
⇒みなかた【南方】
み‐な‐かみ【水上】
①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。
②物事の起源。みなもと。
みなかみ【水上】
群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。
▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。
みなかみ【水上】
姓氏の一つ。
⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】
み‐な‐かみ【水神】
水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」
みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ
小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)
水上滝太郎
提供:岩波書店
 ⇒みなかみ【水上】
みな‐が‐みな【皆が皆】
残らず。ことごとく。
みな‐がら【皆がら】
〔副〕
残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」
みながわ【皆川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】
みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン
江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)
⇒みながわ【皆川】
みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ
〔自四〕
(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」
みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ
〔自四〕
(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」
みなぎ・る【漲る】
〔自五〕
①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」
②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」
み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ
みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」
み‐な・ぐ【見和ぐ】
〔自上二〕
見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」
みな‐くぐ・る【水潜る】
〔自四〕
水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」
み‐な‐くち【水口】
田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」
⇒みなくち‐だけ【水口竹】
⇒みなくち‐ばな【水口花】
⇒みなくち‐まつり【水口祭】
みなくち【水口】
滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。
⇒みなくち‐キセル【水口煙管】
⇒みなくち‐ざいく【水口細工】
みなくち‐キセル【水口煙管】
文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐ざいく【水口細工】
水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐だけ【水口竹】
田の水口に挿す竹。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐ばな【水口花】
播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐まつり【水口祭】
農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉
⇒み‐な‐くち【水口】
みな‐くま【皆熊】
全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)
みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ
全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」
⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】
みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ
真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」
⇒みな‐ぐれない【皆紅】
み‐なげ【身投げ】
水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。
みな‐ごろし【皆殺し・鏖】
一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。
みな‐さま【皆様】
多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」
みな‐さん【皆さん】
「みなさま」のややくだけた言い方。
み‐なし【見做し】
みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」
⇒みなし‐きてい【見做し規定】
⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】
⇒みなし‐はいとう【見做し配当】
⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】
⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】
みなし‐がわ【水無川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」
[二]〔枕〕
「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」
みなし‐きてい【見做し規定】
〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】
殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」
みなしぐり【虚栗】
俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。
みなし‐ご【孤・孤児】
(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉
みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン
公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。
⇒み‐なし【見做し】
みなしご‐ぐさ【白薇】
フナバラソウの異称。〈本草和名〉
みなした‐ふ【水下経】
〔枕〕
(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ
みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ
通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥
事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な‐しも【水下】
流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ
み‐なしろ【御名代】
(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ
みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥
実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な・す【見做す・看做す】
〔他五〕
①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」
②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」
③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」
④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。
みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ
全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」
ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】
ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。
みなせ【水無瀬】
摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。
⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】
⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)
水無瀬川
撮影:的場 啓
⇒みなかみ【水上】
みな‐が‐みな【皆が皆】
残らず。ことごとく。
みな‐がら【皆がら】
〔副〕
残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」
みながわ【皆川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】
みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン
江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)
⇒みながわ【皆川】
みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ
〔自四〕
(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」
みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ
〔自四〕
(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」
みなぎ・る【漲る】
〔自五〕
①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」
②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」
み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ
みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」
み‐な・ぐ【見和ぐ】
〔自上二〕
見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」
みな‐くぐ・る【水潜る】
〔自四〕
水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」
み‐な‐くち【水口】
田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」
⇒みなくち‐だけ【水口竹】
⇒みなくち‐ばな【水口花】
⇒みなくち‐まつり【水口祭】
みなくち【水口】
滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。
⇒みなくち‐キセル【水口煙管】
⇒みなくち‐ざいく【水口細工】
みなくち‐キセル【水口煙管】
文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐ざいく【水口細工】
水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐だけ【水口竹】
田の水口に挿す竹。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐ばな【水口花】
播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐まつり【水口祭】
農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉
⇒み‐な‐くち【水口】
みな‐くま【皆熊】
全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)
みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ
全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」
⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】
みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ
真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」
⇒みな‐ぐれない【皆紅】
み‐なげ【身投げ】
水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。
みな‐ごろし【皆殺し・鏖】
一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。
みな‐さま【皆様】
多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」
みな‐さん【皆さん】
「みなさま」のややくだけた言い方。
み‐なし【見做し】
みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」
⇒みなし‐きてい【見做し規定】
⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】
⇒みなし‐はいとう【見做し配当】
⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】
⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】
みなし‐がわ【水無川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」
[二]〔枕〕
「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」
みなし‐きてい【見做し規定】
〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】
殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」
みなしぐり【虚栗】
俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。
みなし‐ご【孤・孤児】
(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉
みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン
公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。
⇒み‐なし【見做し】
みなしご‐ぐさ【白薇】
フナバラソウの異称。〈本草和名〉
みなした‐ふ【水下経】
〔枕〕
(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ
みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ
通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥
事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な‐しも【水下】
流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ
み‐なしろ【御名代】
(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ
みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥
実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な・す【見做す・看做す】
〔他五〕
①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」
②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」
③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」
④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。
みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ
全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」
ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】
ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。
みなせ【水無瀬】
摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。
⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】
⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)
水無瀬川
撮影:的場 啓
 ⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」
[二]〔枕〕
「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」
みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。
→文献資料[水無瀬三吟]
⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。
水無瀬神宮
撮影:的場 啓
⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」
[二]〔枕〕
「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」
みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。
→文献資料[水無瀬三吟]
⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。
水無瀬神宮
撮影:的場 啓
 ⇒みなせ【水無瀬】
み‐な‐そこ【水底】
水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」
⇒みなそこ‐ふ【水底経】
みなそこ‐ふ【水底経】
〔枕〕
(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ
⇒み‐な‐そこ【水底】
みな‐そそく【水注く】
〔枕〕
「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」
み‐な‐づき【水無月・六月】
(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」
⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】
⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】
みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ
最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ
「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
み‐な‐と【港・湊】
(「水の門」の意)
①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」
②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉
⇒みなと‐え【港江】
⇒みなと‐かぜ【港風】
⇒みなと‐まち【港町】
みなと【港】
東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。
みなと‐え【港江】
港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐かぜ【港風】
港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐がみ【湊紙】
和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。
みなと‐がわ【湊川】‥ガハ
神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。
⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】
⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】
みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥
神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。
湊川神社
撮影:的場 啓
⇒みなせ【水無瀬】
み‐な‐そこ【水底】
水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」
⇒みなそこ‐ふ【水底経】
みなそこ‐ふ【水底経】
〔枕〕
(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ
⇒み‐な‐そこ【水底】
みな‐そそく【水注く】
〔枕〕
「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」
み‐な‐づき【水無月・六月】
(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」
⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】
⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】
みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ
最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ
「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
み‐な‐と【港・湊】
(「水の門」の意)
①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」
②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉
⇒みなと‐え【港江】
⇒みなと‐かぜ【港風】
⇒みなと‐まち【港町】
みなと【港】
東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。
みなと‐え【港江】
港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐かぜ【港風】
港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐がみ【湊紙】
和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。
みなと‐がわ【湊川】‥ガハ
神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。
⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】
⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】
みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥
神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。
湊川神社
撮影:的場 啓
 ⇒みなと‐がわ【湊川】
みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ
1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。
⇒みなと‐がわ【湊川】
みな‐とのだち【皆殿達】
殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」
みなと‐まち【港町】
港のある町。港によって発展した町。
⇒み‐な‐と【港・湊】
みな‐ながら【皆ながら】
〔副〕
ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」
⇒みなと‐がわ【湊川】
みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ
1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。
⇒みなと‐がわ【湊川】
みな‐とのだち【皆殿達】
殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」
みなと‐まち【港町】
港のある町。港によって発展した町。
⇒み‐な‐と【港・湊】
みな‐ながら【皆ながら】
〔副〕
ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」
 御堂筋(2)
撮影:的場 啓
御堂筋(2)
撮影:的場 啓
 ⇒み‐どう【御堂】
みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥
〔形ク〕
(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」
み‐とおし【見通し】‥トホシ
①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」
②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」
③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」
④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤
みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥
粟野膳あわのぜんの別称。
み‐とお・す【見通す】‥トホス
〔他五〕
①始めから終りまで目をとおす。
②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。
③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」
みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ
江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。
みと‐がく【水戸学】
江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。
み‐とが・める【見咎める】
〔他下一〕[文]みとが・む(下二)
①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」
②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」
み‐どき【見時】
見るによい時期。見頃。「桜の―」
み‐どきょう【御読経】‥キヤウ
①読経の尊敬語。
②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」
みとき‐よく【御時好く】
御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」
みとく【未得】
⇒いしだみとく(石田未得)
み‐とく【味得】
事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。
み‐と・く【見解く】
〔他四〕
見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」
み‐どく【味読】
内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」
みと‐け【水戸家】
徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。
みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥
(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。
み‐ところ【三所】
三つのところ。3点。
⇒みところ‐ぜめ【三所攻】
⇒みところ‐どう【三所籐】
⇒みところ‐もの【三所物】
み‐どころ【見所】
①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」
②将来の望み。みこみ。「―のある人物」
③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」
④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」
⑤能の見物席。けんしょ。
み‐どころ【身所】
魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」
みところ‐ぜめ【三所攻】
相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。
みところぜめ
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐どう【三所籐】
所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐もの【三所物】
刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。
⇒み‐ところ【三所】
ミトコンドリア【mitochondria】
細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。
⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】
ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ
ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。
⇒ミトコンドリア【mitochondria】
み‐とし【御年】
穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」
みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】
素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」
み‐としろ【御戸代・御刀代】
(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」
ミトス【mythos ギリシア】
⇒ミュトス
み‐とせ【三年・三歳】
3ねん。3さい。
み‐とど・ける【見届ける】
〔他下一〕[文]みとど・く(下二)
①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」
②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」
みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ
(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」
ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ
オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。
みと‐びらき【御戸開き】
神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」
みと‐ぼり【水戸彫】
彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。
みと‐まつり【水戸祭】
水口みなくち祭のこと。
みとみ【三富】
姓氏の一つ。
⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】
みとみ‐くちは【三富朽葉】
(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)
⇒みとみ【三富】
みと・む【認む】
〔他下二〕
⇒みとめる(下一)
みとむ‐な・い
〔形〕
(→)「みともない」に同じ。
みとめ【認め】
①認めること。
②認印みとめいんの略。
⇒みとめ‐いん【認印】
みとめ‐いん【認印】
①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。
②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。
⇒みとめ【認め】
みと・める【認める】
〔他下一〕[文]みと・む(下二)
(見留める意)
①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」
②目にとめる。「人影を―・める」
③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」
④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」
⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」
み‐ども【身共】
〔代〕
(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。
みとも‐がみ【御伴神】
(→)「みとものかみ」に同じ。
みとも‐な・い
〔形〕
(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」
みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】
尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。
みとよ【三豊】
香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。
ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。
⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】
ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ
(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。
⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
み‐とらし【御執】
(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」
み‐とり【見取り】
①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。
②見て写しとること。「―本」
③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。
④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。
⑤見取小作の略。
→みどり。
⇒みとり‐こさく【見取小作】
⇒みとり‐ざん【見取り算】
⇒みとり‐ず【見取図】
⇒みとり‐ば【見取場】
⇒みとり‐まい【見取米】
みどり
群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。
みどり【緑・翠】
(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)
①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」
②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」
Munsell color system: 2.5G5/10
③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」
⇒みどり‐いし【緑石】
⇒みどり‐がめ【緑亀】
⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】
⇒みどり‐ざる【緑猿】
⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】
⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】
⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】
⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】
⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】
⇒みどり‐の‐とう【緑の党】
⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】
⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】
⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】
⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
⇒みどり‐むし【緑虫】
み‐どり【見取り】
①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」
②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」
みどり‐いし【緑石】
ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐がめ【緑亀】
アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐ご【緑児・嬰児】
(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐こさく【見取小作】
江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐ざる【緑猿】
サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ざん【見取り算】
珠算で、数字を見ながら計算すること。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐ず【見取図】‥ヅ
①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。
②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥
学童擁護員の俗称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ
①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。
②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
つやのある美しい黒髪。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ころも【緑の衣】
六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐そで【緑の袖】
(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ダム【緑のダム】
森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ
(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐はやし【緑の林】
(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ひ【みどりの日】
国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ほら【緑の洞】
(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ば【見取場】
江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐まい【見取米】
江戸時代、見取場から上納させた年貢米。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐むし【緑虫】
ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。
⇒みどり【緑・翠】
み‐と・る【見取る】
〔他五〕
①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」
②見て写し取る。
③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」
ミドル【middle】
①中等。中級。中間。
②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」
⇒ミドル‐アイアン【middle iron】
⇒ミドル‐ウェア【middleware】
⇒ミドル‐エイジ【middle age】
⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】
⇒ミドル‐クラス【middle class】
⇒ミドル‐ショット【middle shot】
⇒ミドル‐スクール【middle school】
⇒ミドル‐ネーム【middle name】
⇒ミドル‐マネージメント【middle management】
ミドル‐アイアン【middle iron】
ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ウェア【middleware】
コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐エイジ【middle age】
中年。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ
(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐クラス【middle class】
中間層。中産階級。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ショット【middle shot】
写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐スクール【middle school】
アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ネーム【middle name】
欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐マネージメント【middle management】
(→)中間管理職のこと。
⇒ミドル【middle】
み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】
〔自下一〕[文]みと・る(下二)
我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」
みどろ【塗】
〔接尾〕
名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」
みどろ・し
〔形ク〕
まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」
ミトン【mitten】
親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。
みな【皆】
[一]〔名〕
全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」
[二]〔副〕
残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」
⇒皆にす
⇒皆になす
⇒皆になる
みな【蜷】
ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」
み‐な‐あい【水合】‥アヒ
水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」
み‐な‐うら【水占】
(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」
み‐なお・す【見直す】‥ナホス
[一]〔他五〕
①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」
②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」
[二]〔自五〕
病気または景気などが少しよい方に向かう。
み‐なか【真中】
まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」
み‐なが・す【見流す】
〔他五〕
見ても気にとめない。見すごす。
みなかた【南方】
姓氏の一つ。
⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)
南方熊楠
提供:毎日新聞社
⇒み‐どう【御堂】
みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥
〔形ク〕
(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」
み‐とおし【見通し】‥トホシ
①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」
②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」
③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」
④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤
みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥
粟野膳あわのぜんの別称。
み‐とお・す【見通す】‥トホス
〔他五〕
①始めから終りまで目をとおす。
②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。
③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」
みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ
江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。
みと‐がく【水戸学】
江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。
み‐とが・める【見咎める】
〔他下一〕[文]みとが・む(下二)
①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」
②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」
み‐どき【見時】
見るによい時期。見頃。「桜の―」
み‐どきょう【御読経】‥キヤウ
①読経の尊敬語。
②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」
みとき‐よく【御時好く】
御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」
みとく【未得】
⇒いしだみとく(石田未得)
み‐とく【味得】
事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。
み‐と・く【見解く】
〔他四〕
見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」
み‐どく【味読】
内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」
みと‐け【水戸家】
徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。
みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥
(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。
み‐ところ【三所】
三つのところ。3点。
⇒みところ‐ぜめ【三所攻】
⇒みところ‐どう【三所籐】
⇒みところ‐もの【三所物】
み‐どころ【見所】
①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」
②将来の望み。みこみ。「―のある人物」
③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」
④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」
⑤能の見物席。けんしょ。
み‐どころ【身所】
魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」
みところ‐ぜめ【三所攻】
相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。
みところぜめ
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐どう【三所籐】
所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」
⇒み‐ところ【三所】
みところ‐もの【三所物】
刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。
⇒み‐ところ【三所】
ミトコンドリア【mitochondria】
細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。
⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】
ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ
ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。
⇒ミトコンドリア【mitochondria】
み‐とし【御年】
穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」
みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】
素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」
み‐としろ【御戸代・御刀代】
(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」
ミトス【mythos ギリシア】
⇒ミュトス
み‐とせ【三年・三歳】
3ねん。3さい。
み‐とど・ける【見届ける】
〔他下一〕[文]みとど・く(下二)
①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」
②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」
みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ
(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」
ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ
オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。
みと‐びらき【御戸開き】
神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」
みと‐ぼり【水戸彫】
彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。
みと‐まつり【水戸祭】
水口みなくち祭のこと。
みとみ【三富】
姓氏の一つ。
⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】
みとみ‐くちは【三富朽葉】
(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)
⇒みとみ【三富】
みと・む【認む】
〔他下二〕
⇒みとめる(下一)
みとむ‐な・い
〔形〕
(→)「みともない」に同じ。
みとめ【認め】
①認めること。
②認印みとめいんの略。
⇒みとめ‐いん【認印】
みとめ‐いん【認印】
①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。
②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。
⇒みとめ【認め】
みと・める【認める】
〔他下一〕[文]みと・む(下二)
(見留める意)
①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」
②目にとめる。「人影を―・める」
③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」
④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」
⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」
み‐ども【身共】
〔代〕
(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。
みとも‐がみ【御伴神】
(→)「みとものかみ」に同じ。
みとも‐な・い
〔形〕
(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」
みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】
尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。
みとよ【三豊】
香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。
ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。
⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】
ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ
(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。
⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】
み‐とらし【御執】
(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」
み‐とり【見取り】
①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。
②見て写しとること。「―本」
③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。
④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。
⑤見取小作の略。
→みどり。
⇒みとり‐こさく【見取小作】
⇒みとり‐ざん【見取り算】
⇒みとり‐ず【見取図】
⇒みとり‐ば【見取場】
⇒みとり‐まい【見取米】
みどり
群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。
みどり【緑・翠】
(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)
①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」
②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」
Munsell color system: 2.5G5/10
③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」
⇒みどり‐いし【緑石】
⇒みどり‐がめ【緑亀】
⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】
⇒みどり‐ざる【緑猿】
⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】
⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】
⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】
⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】
⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】
⇒みどり‐の‐とう【緑の党】
⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】
⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】
⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】
⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
⇒みどり‐むし【緑虫】
み‐どり【見取り】
①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」
②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」
みどり‐いし【緑石】
ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐がめ【緑亀】
アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐ご【緑児・嬰児】
(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐こさく【見取小作】
江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐ざる【緑猿】
サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ざん【見取り算】
珠算で、数字を見ながら計算すること。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐ず【見取図】‥ヅ
①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。
②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥
学童擁護員の俗称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ
①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。
②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐かくめい【緑の革命】
1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】
つやのある美しい黒髪。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ころも【緑の衣】
六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐そで【緑の袖】
(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ダム【緑のダム】
森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ
(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐はやし【緑の林】
(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ひ【みどりの日】
国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐ほら【緑の洞】
(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」
⇒みどり【緑・翠】
みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】
オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。
⇒みどり【緑・翠】
みとり‐ば【見取場】
江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。
⇒み‐とり【見取り】
みとり‐まい【見取米】
江戸時代、見取場から上納させた年貢米。
⇒み‐とり【見取り】
みどり‐むし【緑虫】
ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。
⇒みどり【緑・翠】
み‐と・る【見取る】
〔他五〕
①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」
②見て写し取る。
③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」
ミドル【middle】
①中等。中級。中間。
②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」
⇒ミドル‐アイアン【middle iron】
⇒ミドル‐ウェア【middleware】
⇒ミドル‐エイジ【middle age】
⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】
⇒ミドル‐クラス【middle class】
⇒ミドル‐ショット【middle shot】
⇒ミドル‐スクール【middle school】
⇒ミドル‐ネーム【middle name】
⇒ミドル‐マネージメント【middle management】
ミドル‐アイアン【middle iron】
ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ウェア【middleware】
コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐エイジ【middle age】
中年。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ
(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐クラス【middle class】
中間層。中産階級。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ショット【middle shot】
写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐スクール【middle school】
アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐ネーム【middle name】
欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。
⇒ミドル【middle】
ミドル‐マネージメント【middle management】
(→)中間管理職のこと。
⇒ミドル【middle】
み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】
〔自下一〕[文]みと・る(下二)
我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」
みどろ【塗】
〔接尾〕
名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」
みどろ・し
〔形ク〕
まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」
ミトン【mitten】
親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。
みな【皆】
[一]〔名〕
全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」
[二]〔副〕
残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」
⇒皆にす
⇒皆になす
⇒皆になる
みな【蜷】
ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」
み‐な‐あい【水合】‥アヒ
水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」
み‐な‐うら【水占】
(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」
み‐なお・す【見直す】‥ナホス
[一]〔他五〕
①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」
②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」
[二]〔自五〕
病気または景気などが少しよい方に向かう。
み‐なか【真中】
まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」
み‐なが・す【見流す】
〔他五〕
見ても気にとめない。見すごす。
みなかた【南方】
姓氏の一つ。
⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
みなかた‐くまぐす【南方熊楠】
民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)
南方熊楠
提供:毎日新聞社
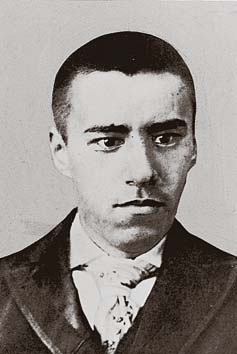 ⇒みなかた【南方】
み‐な‐かみ【水上】
①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。
②物事の起源。みなもと。
みなかみ【水上】
群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。
▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。
みなかみ【水上】
姓氏の一つ。
⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】
み‐な‐かみ【水神】
水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」
みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ
小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)
水上滝太郎
提供:岩波書店
⇒みなかた【南方】
み‐な‐かみ【水上】
①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。
②物事の起源。みなもと。
みなかみ【水上】
群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。
▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。
みなかみ【水上】
姓氏の一つ。
⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】
み‐な‐かみ【水神】
水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」
みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ
小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)
水上滝太郎
提供:岩波書店
 ⇒みなかみ【水上】
みな‐が‐みな【皆が皆】
残らず。ことごとく。
みな‐がら【皆がら】
〔副〕
残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」
みながわ【皆川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】
みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン
江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)
⇒みながわ【皆川】
みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ
〔自四〕
(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」
みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ
〔自四〕
(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」
みなぎ・る【漲る】
〔自五〕
①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」
②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」
み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ
みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」
み‐な・ぐ【見和ぐ】
〔自上二〕
見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」
みな‐くぐ・る【水潜る】
〔自四〕
水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」
み‐な‐くち【水口】
田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」
⇒みなくち‐だけ【水口竹】
⇒みなくち‐ばな【水口花】
⇒みなくち‐まつり【水口祭】
みなくち【水口】
滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。
⇒みなくち‐キセル【水口煙管】
⇒みなくち‐ざいく【水口細工】
みなくち‐キセル【水口煙管】
文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐ざいく【水口細工】
水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐だけ【水口竹】
田の水口に挿す竹。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐ばな【水口花】
播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐まつり【水口祭】
農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉
⇒み‐な‐くち【水口】
みな‐くま【皆熊】
全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)
みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ
全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」
⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】
みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ
真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」
⇒みな‐ぐれない【皆紅】
み‐なげ【身投げ】
水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。
みな‐ごろし【皆殺し・鏖】
一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。
みな‐さま【皆様】
多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」
みな‐さん【皆さん】
「みなさま」のややくだけた言い方。
み‐なし【見做し】
みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」
⇒みなし‐きてい【見做し規定】
⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】
⇒みなし‐はいとう【見做し配当】
⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】
⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】
みなし‐がわ【水無川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」
[二]〔枕〕
「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」
みなし‐きてい【見做し規定】
〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】
殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」
みなしぐり【虚栗】
俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。
みなし‐ご【孤・孤児】
(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉
みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン
公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。
⇒み‐なし【見做し】
みなしご‐ぐさ【白薇】
フナバラソウの異称。〈本草和名〉
みなした‐ふ【水下経】
〔枕〕
(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ
みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ
通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥
事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な‐しも【水下】
流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ
み‐なしろ【御名代】
(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ
みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥
実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な・す【見做す・看做す】
〔他五〕
①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」
②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」
③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」
④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。
みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ
全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」
ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】
ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。
みなせ【水無瀬】
摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。
⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】
⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)
水無瀬川
撮影:的場 啓
⇒みなかみ【水上】
みな‐が‐みな【皆が皆】
残らず。ことごとく。
みな‐がら【皆がら】
〔副〕
残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」
みながわ【皆川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】
みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン
江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)
⇒みながわ【皆川】
みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ
〔自四〕
(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」
みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ
〔自四〕
(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」
みなぎ・る【漲る】
〔自五〕
①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」
②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」
み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ
みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」
み‐な・ぐ【見和ぐ】
〔自上二〕
見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」
みな‐くぐ・る【水潜る】
〔自四〕
水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」
み‐な‐くち【水口】
田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」
⇒みなくち‐だけ【水口竹】
⇒みなくち‐ばな【水口花】
⇒みなくち‐まつり【水口祭】
みなくち【水口】
滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。
⇒みなくち‐キセル【水口煙管】
⇒みなくち‐ざいく【水口細工】
みなくち‐キセル【水口煙管】
文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐ざいく【水口細工】
水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。
⇒みなくち【水口】
みなくち‐だけ【水口竹】
田の水口に挿す竹。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐ばな【水口花】
播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。
⇒み‐な‐くち【水口】
みなくち‐まつり【水口祭】
農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉
⇒み‐な‐くち【水口】
みな‐くま【皆熊】
全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)
みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ
全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」
⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】
みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ
真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」
⇒みな‐ぐれない【皆紅】
み‐なげ【身投げ】
水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。
みな‐ごろし【皆殺し・鏖】
一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。
みな‐さま【皆様】
多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」
みな‐さん【皆さん】
「みなさま」のややくだけた言い方。
み‐なし【見做し】
みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」
⇒みなし‐きてい【見做し規定】
⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】
⇒みなし‐はいとう【見做し配当】
⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】
⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】
みなし‐がわ【水無川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」
[二]〔枕〕
「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」
みなし‐きてい【見做し規定】
〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】
殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」
みなしぐり【虚栗】
俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。
みなし‐ご【孤・孤児】
(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉
みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン
公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。
⇒み‐なし【見做し】
みなしご‐ぐさ【白薇】
フナバラソウの異称。〈本草和名〉
みなした‐ふ【水下経】
〔枕〕
(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ
みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ
通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。
⇒み‐なし【見做し】
みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥
事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な‐しも【水下】
流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ
み‐なしろ【御名代】
(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ
みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥
実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。
⇒み‐なし【見做し】
み‐な・す【見做す・看做す】
〔他五〕
①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」
②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」
③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」
④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。
みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ
全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」
ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】
ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。
みなせ【水無瀬】
摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。
⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】
⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)
水無瀬川
撮影:的場 啓
 ⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」
[二]〔枕〕
「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」
みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。
→文献資料[水無瀬三吟]
⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。
水無瀬神宮
撮影:的場 啓
⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ
[一]〔名〕
水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」
[二]〔枕〕
「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」
みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】
百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。
→文献資料[水無瀬三吟]
⇒みなせ【水無瀬】
みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】
水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。
水無瀬神宮
撮影:的場 啓
 ⇒みなせ【水無瀬】
み‐な‐そこ【水底】
水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」
⇒みなそこ‐ふ【水底経】
みなそこ‐ふ【水底経】
〔枕〕
(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ
⇒み‐な‐そこ【水底】
みな‐そそく【水注く】
〔枕〕
「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」
み‐な‐づき【水無月・六月】
(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」
⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】
⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】
みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ
最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ
「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
み‐な‐と【港・湊】
(「水の門」の意)
①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」
②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉
⇒みなと‐え【港江】
⇒みなと‐かぜ【港風】
⇒みなと‐まち【港町】
みなと【港】
東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。
みなと‐え【港江】
港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐かぜ【港風】
港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐がみ【湊紙】
和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。
みなと‐がわ【湊川】‥ガハ
神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。
⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】
⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】
みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥
神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。
湊川神社
撮影:的場 啓
⇒みなせ【水無瀬】
み‐な‐そこ【水底】
水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」
⇒みなそこ‐ふ【水底経】
みなそこ‐ふ【水底経】
〔枕〕
(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ
⇒み‐な‐そこ【水底】
みな‐そそく【水注く】
〔枕〕
「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」
み‐な‐づき【水無月・六月】
(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」
⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】
⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】
みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ
最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ
「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉
⇒み‐な‐づき【水無月・六月】
み‐な‐と【港・湊】
(「水の門」の意)
①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」
②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉
⇒みなと‐え【港江】
⇒みなと‐かぜ【港風】
⇒みなと‐まち【港町】
みなと【港】
東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。
みなと‐え【港江】
港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐かぜ【港風】
港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」
⇒み‐な‐と【港・湊】
みなと‐がみ【湊紙】
和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。
みなと‐がわ【湊川】‥ガハ
神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。
⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】
⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】
みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥
神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。
湊川神社
撮影:的場 啓
 ⇒みなと‐がわ【湊川】
みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ
1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。
⇒みなと‐がわ【湊川】
みな‐とのだち【皆殿達】
殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」
みなと‐まち【港町】
港のある町。港によって発展した町。
⇒み‐な‐と【港・湊】
みな‐ながら【皆ながら】
〔副〕
ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」
⇒みなと‐がわ【湊川】
みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ
1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。
⇒みなと‐がわ【湊川】
みな‐とのだち【皆殿達】
殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」
みなと‐まち【港町】
港のある町。港によって発展した町。
⇒み‐な‐と【港・湊】
みな‐ながら【皆ながら】
〔副〕
ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」
みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥🔗⭐🔉
みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥
〔形ク〕
(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」
○見ぬうちが花みぬうちがはな🔗⭐🔉
○見ぬうちが花みぬうちがはな
ものごとは、実際に見ないで、あれこれ想像しているうちの方が楽しいという意。見ぬが花。
⇒みる【見る・視る・観る】
み‐ぬ・く【見抜く】
〔他五〕
奥底まで見とおす。表に現れない本質を知る。見すかす。洞見する。「うそを―・く」
み‐ぬけ【身抜け】
①ある状態から身を脱すること。責任・苦労などから逃れること。また、そのための言行。世間胸算用5「此の節季の―何とも分別能はず」
②遊女や芸妓がつとめをやめること。身請けされること。
み‐ぬま【水沼】
水をたたえた沼。万葉集19「水鳥のすだく―を都となしつ」
みぬよ‐の‐ひと【見ぬ世の人】
昔の人。古人。徒然草「―を友とするこそこよなうなぐさむわざなれ」
み‐ね【峰・嶺】
①山のいただきのとがった所。山頂。ね。〈倭名類聚鈔1〉「―続き」
②物の高くなった所。宇津保物語俊蔭「耳のはた、鼻の―」。「雲の―」
③刀剣の刃の背。棟むね。
④烏帽子えぼしの頂上。
⑤櫛くしの背。
みね【美祢】
山口県西部、秋吉台の西縁にある市。明治以降大嶺炭田を中心に発展し、現在も主産業は鉱業。人口1万8千。
み‐ね【御哭】
声を立てて泣くこと。葬儀の時に、弔意を表して泣き叫ぶこと。通例、3度行う。孝徳紀「諸もろもろの公卿悉くに随ひて哀哭みねたてまつる」→泣女なきめ
ミネアポリス【Minneapolis】
アメリカのミネソタ州、ミシシッピ川西岸の都市。東岸のセントポールとともに製粉・食品加工が盛ん。人口38万3千(2000)。
みね‐いり【峰入】
(→)大峰入おおみねいりに同じ。入峰にゅうぶ。〈[季]夏〉
みね‐うち【峰打ち・刀背打ち】
相手を刀の峰で打つこと。むねうち。
みねざき【峰崎】
姓氏の一つ。
⇒みねざき‐こうとう【峰崎勾当】
みねざき‐こうとう【峰崎勾当】‥タウ
江戸後期の地歌の演奏家・作曲家。寛政(1789〜1801)前後、大坂で活躍。「雪」「小簾こすの戸」「残月」「越後獅子」「東獅子」などを作曲し、大阪系の地歌の端歌・手事物てごとものの完成に功績を残す。生没年未詳。
⇒みねざき【峰崎】
みね‐ずおう【峰蘇芳】‥ハウ
ツツジ科の常緑小低木。本州中部以北と北海道の高山帯に群生する。北半球周極地方に広く分布。長い地下茎で群生し、しばしばクッション状の群落となる。長さ1センチメートルほどの線状の葉を密に対生、葉裏は白い。夏に枝端に淡紅色を帯びた小白花を数個ずつつけ、花冠の上半部は星形に開く。
ミネストローネ【minestrone イタリア】
イタリア料理の一つ。具の多い野菜スープ。人参・キャベツ・玉葱・ベーコンなどを炒め、パスタなどを加えて煮込む。
ミネソタ【Minnesota】
アメリカ合衆国中央北部の州。無数の湖が点在。酪農が盛ん。州都セントポール。→アメリカ合衆国(図)
みね‐つづき【峰続き】
峰がつづいていること。また、つづいた峰。
みね‐の‐たおり【峰の撓】‥タヲリ
峰の線のたわんで低くなったところ。万葉集13「高山の―に射目いめ立てて」
みね‐の‐やくし【峰の薬師】
愛知県南設楽したら郡の鳳来寺の通称。本尊は子授けの薬師如来として名高い。
みね‐ばり【峰榛】
〔植〕オノオレの別称。
みね‐べ【峰辺】
峰のあたり。
ミネラル【mineral】
①鉱物。無機物。
②栄養素として生理作用に必要な無機物。ふつう無機塩類の形で摂取される。カルシウム・鉄・亜鉛・コバルト・マンガンの類。
⇒ミネラル‐ウォーター【mineral water】
⇒ミネラル‐コルチコイド【mineral corticoid】
ミネラル‐ウォーター【mineral water】
カルシウム・マグネシウムなどの無機塩類を比較的多量に含んだ飲料となる天然水・地下水。また人工的に無機塩類を添加した天然水。
⇒ミネラル【mineral】
ミネラル‐コルチコイド【mineral corticoid】
水や電解質の代謝に関係する副腎皮質ホルモン。腎臓に作用し、ナトリウム‐イオンや水の再吸収を促す。鉱質コルチコイド。電解質コルチコイド。
⇒ミネラル【mineral】
ミネルヴァ【Minerva】
ローマ神話で、技術・職人の女神。ギリシア神話のアテナと同一視され、アテナの権能が後に加えられた。
⇒ミネルヴァ‐の‐ふくろう【ミネルヴァの梟】
ミネルヴァ‐の‐ふくろう【ミネルヴァの梟】‥フクロフ
ミネルヴァの連れている梟。知恵の象徴。
⇒ミネルヴァ【Minerva】
みの【蓑】
茅かやや菅すげなどの茎葉を編んで作った雨具。その末が乱れ髪のように垂れる。また、藁わら・棕櫚しゅろなどでも作る。〈倭名類聚鈔14〉
蓑
 蓑
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
蓑
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 蓑(裏)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
蓑(裏)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 み‐の【三幅・三布】
①並幅なみはばの布を3枚縫い合わせた幅。
②「みのぶとん」の略。
みの【美濃】
①旧国名。今の岐阜県の南部。濃州。
②岐阜県南部の市。長良川の上流に位置し風光明媚。和紙の産地として有名。人口2万3千。
③美濃紙の略。
④美濃絹の略。
ミノ
食用としての牛の第1胃(瘤胃)。ガツ。
ミノア‐ぶんめい【ミノア文明】
(クレタの伝説的な王ミノス(Minōs)の名に因んでいう)前20〜15世紀を極盛期としてクレタ島に栄えた文明で、エーゲ文明の一中心。ギリシア本土にも影響を及ぼし、ミュケナイ文明興隆の一因となった。20世紀初頭、エヴァンズによるクノッソス宮殿の発掘でその存在が知られた。クレタ文明。
みの‐いち【蓑市】
江戸時代、三社祭の翌日、陰暦3月19日(祭礼のない年は18日)と年の市の翌日に、江戸浅草雷門前で蓑笠などを売った市。
みの‐いも【蓑芋】
サトイモの異称。
みのう
(「耳納」と当て字)稜線の変化の少ない連嶺で、郡村の境界をなしているもの。九州地方などで「何何みのう」という名が多い。
み‐のう【未納】‥ナフ
納めるべきものをまだ納めていないこと。「授業料―」
み‐の‐うえ【身の上】‥ウヘ
①人の一身に関する事柄。境遇。しんじょう。「―相談」
②人の運命。一生の運命。「―判断」
⇒みのうえ‐ばなし【身の上話】
みのうえ‐ばなし【身の上話】‥ウヘ‥
一身上の事柄に関する打明け話。
⇒み‐の‐うえ【身の上】
みのお【箕面】
大阪府北部の市。大阪市の衛星都市。箕面川の渓谷を占め、秋は紅葉狩りの名所。箕面川中流に箕面滝がある。修験道の霊場として有名。人口12万7千。
箕面滝
撮影:的場 啓
み‐の【三幅・三布】
①並幅なみはばの布を3枚縫い合わせた幅。
②「みのぶとん」の略。
みの【美濃】
①旧国名。今の岐阜県の南部。濃州。
②岐阜県南部の市。長良川の上流に位置し風光明媚。和紙の産地として有名。人口2万3千。
③美濃紙の略。
④美濃絹の略。
ミノ
食用としての牛の第1胃(瘤胃)。ガツ。
ミノア‐ぶんめい【ミノア文明】
(クレタの伝説的な王ミノス(Minōs)の名に因んでいう)前20〜15世紀を極盛期としてクレタ島に栄えた文明で、エーゲ文明の一中心。ギリシア本土にも影響を及ぼし、ミュケナイ文明興隆の一因となった。20世紀初頭、エヴァンズによるクノッソス宮殿の発掘でその存在が知られた。クレタ文明。
みの‐いち【蓑市】
江戸時代、三社祭の翌日、陰暦3月19日(祭礼のない年は18日)と年の市の翌日に、江戸浅草雷門前で蓑笠などを売った市。
みの‐いも【蓑芋】
サトイモの異称。
みのう
(「耳納」と当て字)稜線の変化の少ない連嶺で、郡村の境界をなしているもの。九州地方などで「何何みのう」という名が多い。
み‐のう【未納】‥ナフ
納めるべきものをまだ納めていないこと。「授業料―」
み‐の‐うえ【身の上】‥ウヘ
①人の一身に関する事柄。境遇。しんじょう。「―相談」
②人の運命。一生の運命。「―判断」
⇒みのうえ‐ばなし【身の上話】
みのうえ‐ばなし【身の上話】‥ウヘ‥
一身上の事柄に関する打明け話。
⇒み‐の‐うえ【身の上】
みのお【箕面】
大阪府北部の市。大阪市の衛星都市。箕面川の渓谷を占め、秋は紅葉狩りの名所。箕面川中流に箕面滝がある。修験道の霊場として有名。人口12万7千。
箕面滝
撮影:的場 啓

 蓑
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
蓑
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 蓑(裏)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
蓑(裏)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 み‐の【三幅・三布】
①並幅なみはばの布を3枚縫い合わせた幅。
②「みのぶとん」の略。
みの【美濃】
①旧国名。今の岐阜県の南部。濃州。
②岐阜県南部の市。長良川の上流に位置し風光明媚。和紙の産地として有名。人口2万3千。
③美濃紙の略。
④美濃絹の略。
ミノ
食用としての牛の第1胃(瘤胃)。ガツ。
ミノア‐ぶんめい【ミノア文明】
(クレタの伝説的な王ミノス(Minōs)の名に因んでいう)前20〜15世紀を極盛期としてクレタ島に栄えた文明で、エーゲ文明の一中心。ギリシア本土にも影響を及ぼし、ミュケナイ文明興隆の一因となった。20世紀初頭、エヴァンズによるクノッソス宮殿の発掘でその存在が知られた。クレタ文明。
みの‐いち【蓑市】
江戸時代、三社祭の翌日、陰暦3月19日(祭礼のない年は18日)と年の市の翌日に、江戸浅草雷門前で蓑笠などを売った市。
みの‐いも【蓑芋】
サトイモの異称。
みのう
(「耳納」と当て字)稜線の変化の少ない連嶺で、郡村の境界をなしているもの。九州地方などで「何何みのう」という名が多い。
み‐のう【未納】‥ナフ
納めるべきものをまだ納めていないこと。「授業料―」
み‐の‐うえ【身の上】‥ウヘ
①人の一身に関する事柄。境遇。しんじょう。「―相談」
②人の運命。一生の運命。「―判断」
⇒みのうえ‐ばなし【身の上話】
みのうえ‐ばなし【身の上話】‥ウヘ‥
一身上の事柄に関する打明け話。
⇒み‐の‐うえ【身の上】
みのお【箕面】
大阪府北部の市。大阪市の衛星都市。箕面川の渓谷を占め、秋は紅葉狩りの名所。箕面川中流に箕面滝がある。修験道の霊場として有名。人口12万7千。
箕面滝
撮影:的場 啓
み‐の【三幅・三布】
①並幅なみはばの布を3枚縫い合わせた幅。
②「みのぶとん」の略。
みの【美濃】
①旧国名。今の岐阜県の南部。濃州。
②岐阜県南部の市。長良川の上流に位置し風光明媚。和紙の産地として有名。人口2万3千。
③美濃紙の略。
④美濃絹の略。
ミノ
食用としての牛の第1胃(瘤胃)。ガツ。
ミノア‐ぶんめい【ミノア文明】
(クレタの伝説的な王ミノス(Minōs)の名に因んでいう)前20〜15世紀を極盛期としてクレタ島に栄えた文明で、エーゲ文明の一中心。ギリシア本土にも影響を及ぼし、ミュケナイ文明興隆の一因となった。20世紀初頭、エヴァンズによるクノッソス宮殿の発掘でその存在が知られた。クレタ文明。
みの‐いち【蓑市】
江戸時代、三社祭の翌日、陰暦3月19日(祭礼のない年は18日)と年の市の翌日に、江戸浅草雷門前で蓑笠などを売った市。
みの‐いも【蓑芋】
サトイモの異称。
みのう
(「耳納」と当て字)稜線の変化の少ない連嶺で、郡村の境界をなしているもの。九州地方などで「何何みのう」という名が多い。
み‐のう【未納】‥ナフ
納めるべきものをまだ納めていないこと。「授業料―」
み‐の‐うえ【身の上】‥ウヘ
①人の一身に関する事柄。境遇。しんじょう。「―相談」
②人の運命。一生の運命。「―判断」
⇒みのうえ‐ばなし【身の上話】
みのうえ‐ばなし【身の上話】‥ウヘ‥
一身上の事柄に関する打明け話。
⇒み‐の‐うえ【身の上】
みのお【箕面】
大阪府北部の市。大阪市の衛星都市。箕面川の渓谷を占め、秋は紅葉狩りの名所。箕面川中流に箕面滝がある。修験道の霊場として有名。人口12万7千。
箕面滝
撮影:的場 啓

みぬよ‐の‐ひと【見ぬ世の人】🔗⭐🔉
みぬよ‐の‐ひと【見ぬ世の人】
昔の人。古人。徒然草「―を友とするこそこよなうなぐさむわざなれ」
み‐まうし【見まうし】🔗⭐🔉
み‐まうし【見まうし】
見ることが厭わしい。見ることがつらい。源氏物語葵「見まうくおぼし捨てむも」→まうし
み‐まく【見まく】🔗⭐🔉
み‐まく【見まく】
(見ムのク語法)見るだろうこと。見ようとすること。見ること。万葉集2「妹が光儀すがたを―苦しも」
み‐み・ゆ【見見ゆ】🔗⭐🔉
み‐み・ゆ【見見ゆ】
〔自下二〕
見もし見られもする。あい会う。まみえる。謡曲、柏崎「などや生きてある母に姿を―・えんと思ふ心のなかるらん」
みよ‐かし【見よかし】🔗⭐🔉
みよ‐かし【見よかし】
(ミヨガシとも。カシは助詞)「これ見よ」といって見せびらかすような態度。これみよがし。
⇒みよかし‐がお【見よかし顔】
みよかし‐がお【見よかし顔】‥ガホ🔗⭐🔉
みよかし‐がお【見よかし顔】‥ガホ
「これ見よ」といわぬばかりの顔付き。見せびらかす様子。
⇒みよ‐かし【見よかし】
○見られたものじゃないみられたものじゃない🔗⭐🔉
○見られたものじゃないみられたものじゃない
(→)「見るに堪たえない」に同じ。
⇒みる【見る・視る・観る】
ミランコヴィッチ‐かせつ【ミランコヴィッチ仮説】
旧ユーゴスラヴィアの地球物理学者ミランコヴィッチ(Milutin Milanković1879〜1958)が提唱した、氷期と間氷期の周期的な交代を説明する仮説。地球の自転・公転要素の周期的な変動により日射量が変化して交代が生じるとする。
ミリ【milli】
(ラテン語で1000の意のmilleから)
①1000分の1(10−3)を表す単位の接頭語。記号m
②特にミリメートルの略。
ミリアンペア【milliampere】
電流の単位。1アンペアの1000分の1。記号mA
ミリオネア【millionaire】
百万長者。大金持。
ミリオン【million】
百万。
⇒ミリオン‐セラー【million seller】
ミリオン‐セラー【million seller】
百万以上売れたレコード・CDや本など。
⇒ミリオン【million】
ミリカン‐の‐じっけん【ミリカンの実験】
油滴を用いて電子の電荷量の大きさを決定する精密実験。1909年アメリカの物理学者ミリカン(R. A. Millikan1868〜1953)が考案。
ミリグラム【milligramme・瓱】
質量の単位。1グラムの1000分の1。記号mg
ミリスチン‐さん【ミリスチン酸】
(myristic acid)飽和脂肪酸の一つ。分子式CH3(CH2)12COOH 無色の結晶。やし油などにグリセリン‐エステルとして含まれる。
ミリタリー【military】
軍隊。軍人。また、軍に関するさま。「―‐ルック」
⇒ミリタリー‐マーチ【military march】
ミリタリー‐マーチ【military march】
軍隊行進曲。
⇒ミリタリー【military】
ミリタリスト【militarist】
軍国主義者。
ミリタリズム【militarism】
(→)軍国主義。
ミリ‐は【ミリ波】
波長1〜10ミリメートルの電磁波。衛星通信・レーダー・電波望遠鏡などに利用。ミリメートル波。略号EHF →電磁波(図)
ミリバール【millibar】
圧力の単位。1バールの1000分の1。1ミリバールは1ヘクトパスカル。1気圧は1013ミリバール。記号mb →気圧
ミリボルト【millivolt】
電圧の単位。1ボルトの1000分の1。記号mV
ミリメートル【millimètre フランス・粍】
長さの単位。1メートルの1000分の1。曲尺かねじゃくの約3厘3毛に当たる。記号mm
ミリュー【milieu フランス】
環境。周囲。境遇。
ミリュコーフ【Pavel N. Milyukov】
ロシア自由主義の指導者。歴史家。1905年立憲民主党(カデット)を組織。国会議員となり、二月革命後は臨時政府の外相。十月革命後、亡命。(1859〜1943)
み‐りょう【未了】‥レウ
いまだおわらないこと。「審議―」
⇒みりょう‐の‐いん【未了の因】
み‐りょう【魅了】‥レウ
人の心をひきつけて夢中にさせること。「観衆を―する」
みりょう‐の‐いん【未了の因】‥レウ‥
〔仏〕現世においてまだ尽き果てない前世の因縁。
⇒み‐りょう【未了】
み‐りょく【魅力】
人の心をひきつける力。「―に富む」
⇒みりょく‐てき【魅力的】
みりょく‐てき【魅力的】
魅力のあるさま。「―な人」「―な話」
⇒み‐りょく【魅力】
ミリリットル【millilitre フランス・竓】
体積の単位。1リットルの1000分の1。記号ml
み‐りん【味醂・味淋】
蒸した糯米もちごめと米麹こめこうじとを焼酎またはアルコールに混和して醸造し、滓かすをしぼりとった酒。甘味があり、主に調味用。
⇒みりん‐づけ【味醂漬】
⇒みりん‐ぼし【味醂乾し】
ミリンダおうのとい【ミリンダ王の問】‥ワウ‥トヒ
(パーリ語Milindapañha)インドの仏教聖典の一つ。紀元前2世紀半ば、北西インドを支配したギリシア系の王メナンドロス(パーリ語でミリンダ)と仏教僧ナーガセーナ長老との仏教教理についての問答を記す。ミリンダ王問経。漢訳名、那先比丘経なせんびくきょう。
みりん‐づけ【味醂漬】
瓜・茄子なす・大根などの野菜、または魚を味醂粕に漬けること。また、その食品。
⇒み‐りん【味醂・味淋】
みりん‐ぼし【味醂乾し】
乾魚の一種。イワシ・アジ・フグ・キスなどの魚を開き、味醂・醤油・砂糖などの混和液に浸し味をつけて乾燥したもの。さくらぼし。すえひろぼし。
⇒み‐りん【味醂・味淋】
みる【海松・水松】
海産の緑藻。アオサ藻綱ミル目の一種。浅海の岩石に着生する。全体に濃緑色(梅松色)を呈し、直径3ミリメートルくらいの円柱形肉質の幹が多数に二股ふたまた分岐する。高さ約20センチメートル。ミル属には、他にナガミル・クロミル・タマミルなどがある。食用。みるめ。みるな。みるぶさ。またみる。〈[季]春〉。万葉集6「沖辺には深―採り」→みるいろ(海松色)
みる
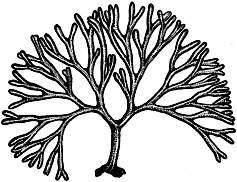 ミル【mil】
ヤード‐ポンド法の長さの単位。針金の直径などを測るのに用いる。1ミルは0.001インチで、0.0254ミリメートル。記号mil
ミル【James Mill】
イギリスの思想家・経済学者。ベンサムの功利主義を継承。主著「英領インド史」「経済学綱要」。(1773〜1836)
ミル【John Stuart Mill】
イギリスの哲学者・経済学者。父ジェームズから英才教育を受けた。イギリス経験論の立場から実証的社会科学の理論を基礎づけ、功利主義の社会倫理説を説く。経済学ではスミス・リカードを継ぎ、古典学派の最後の代表者。主著「経済学原理」「自由論」「自伝」。(1806〜1873)
みる【回る・廻る】
〔自上一〕
めぐる。まわる。古事記上「うち廻る島の崎崎」
みる【見る・視る・観る】
〔他上一〕
自分の目で実際に確かめる。転じて、自分の判断で処理する意。
➊目によって認識する。
①目によって物事の存在や動きを認識する。万葉集5「いつしかもみやこをみむと思ひつつ」。「みると聞くとは大違い」「芝居をみる」
②ながめる。望む。推古紀「我が大君の隠ります天の八十蔭出でたたす御空をみれば」。竹取物語「月をみてはいみじく泣き給ふ」。「窓から外をみる」
③人にあう。万葉集19「あをによし奈良人みむと」。源氏物語紅葉賀「み奉り給ふ時はうらみも忘れてかしづきいとなみ聞え給ふ」
④夫婦の契ちぎりをする。源氏物語帚木「多くはわが心も、みる人からをさまりもすべし」
⑤ある出来事に遭遇する。伊勢物語「物心細くすずろなる目をみることと思ふに」。源氏物語夕顔「何の契りにかかる目をみるらむ」。「馬鹿をみる」
⑥よく注意して観察する。竹取物語「あやしがりて寄りてみるに筒の中光りたり」。「様子をみる」「調子をみる」
⑦(「診る」とも書く)診察する。「病人をみる」
⑧調査する。しらべる。「答案をみる」
⑨試みる。ためす。
⑩(助詞「て」「で」を介して動詞連用形に付いて)
㋐ためしに…する。土佐日記「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」。「恐る恐るさわってみる」「やれるものならやってみな」
㋑(「…てみると」「…てみたら」「…てみれば」の形で)ある事実に気付く、またはある事実が成り立つ条件を示す。…すると。…したところが。「帰ってみると鍵がかかっていた」「親にしてみれば出来の悪い子ほどいとおしい」
➋判断する。
①物事を判断する。源氏物語桐壺「女もいといみじとみ奉りて」。「世のなりゆきをみる」「人をみる目」「甘くみる」
②占って判断する。源氏物語桐壺「朝廷のかためとなりて天の下を輔くる方にてみれば、又その相たがふべし」。「手相をみる」
③目にとめた文字の意味を知る。読む。源氏物語帚木「かかる御文みるべき人もなしと聞えよ」。日葡辞書「キャウ(経)ヲミアワスル」
④鑑定する。「古筆の専門家にみてもらう」
➌物事を調べ行う。
①取り扱う。行う。源氏物語若紫「かしこにいと切にみるべき事の侍るを思ひ給へ出でてなむ」。「政をみる」
②過ごして行けるよう力添えする。世話をする。面倒をみる。源氏物語玉鬘「かの御かはりにみ奉らん子も少なきがさうざうしきに」。「子供をみる」「勉強をみてやる」
③(「看る」とも書く)看病する。「付添が病人をみる」
➍(僧の忌詞)仏前に供える花を切る。
◇広く一般には「見」。「視」はまっすぐに目を向けてみる、また注意してみる場合、「観」は観察・見物などに多く使う。「診」は➊7に使う。
⇒見ての通り
⇒見て見ぬ振りをする
⇒見ぬうちが花
⇒見られたものじゃない
⇒見る影も無い
⇒見ると聞くとは大違い
⇒見るに忍びない
⇒見るに堪えない
⇒見るに見かねる
⇒見る間に
⇒見れば見るほど
みる【診る】
〔他上一〕
⇒みる(見)➊7
みる・い
〔形〕
(静岡県で)穀物などが、未熟で軟らかい。
みる‐いろ【海松色・水松色】
①黒みを帯びた萌葱もえぎ色。とくさいろ。
Munsell color system: 9Y4/3
②襲かさねの色目。山科流では表は萌葱、裏は青。または、表は黒萌葱、裏は白。
ミルウォーキー【Milwaukee】
アメリカ合衆国ウィスコンシン州の都市。同州最大の都市であり、ミシガン湖に臨む港湾都市で石炭・穀物などの積出しが多く、工業も盛ん。人口59万7千(2000)。
ミルカー【milker】
陰圧による吸引力を利用して牝牛の乳をしぼる器具。搾乳機。
みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ
(→)ミルクイガイの別称。
ミル【mil】
ヤード‐ポンド法の長さの単位。針金の直径などを測るのに用いる。1ミルは0.001インチで、0.0254ミリメートル。記号mil
ミル【James Mill】
イギリスの思想家・経済学者。ベンサムの功利主義を継承。主著「英領インド史」「経済学綱要」。(1773〜1836)
ミル【John Stuart Mill】
イギリスの哲学者・経済学者。父ジェームズから英才教育を受けた。イギリス経験論の立場から実証的社会科学の理論を基礎づけ、功利主義の社会倫理説を説く。経済学ではスミス・リカードを継ぎ、古典学派の最後の代表者。主著「経済学原理」「自由論」「自伝」。(1806〜1873)
みる【回る・廻る】
〔自上一〕
めぐる。まわる。古事記上「うち廻る島の崎崎」
みる【見る・視る・観る】
〔他上一〕
自分の目で実際に確かめる。転じて、自分の判断で処理する意。
➊目によって認識する。
①目によって物事の存在や動きを認識する。万葉集5「いつしかもみやこをみむと思ひつつ」。「みると聞くとは大違い」「芝居をみる」
②ながめる。望む。推古紀「我が大君の隠ります天の八十蔭出でたたす御空をみれば」。竹取物語「月をみてはいみじく泣き給ふ」。「窓から外をみる」
③人にあう。万葉集19「あをによし奈良人みむと」。源氏物語紅葉賀「み奉り給ふ時はうらみも忘れてかしづきいとなみ聞え給ふ」
④夫婦の契ちぎりをする。源氏物語帚木「多くはわが心も、みる人からをさまりもすべし」
⑤ある出来事に遭遇する。伊勢物語「物心細くすずろなる目をみることと思ふに」。源氏物語夕顔「何の契りにかかる目をみるらむ」。「馬鹿をみる」
⑥よく注意して観察する。竹取物語「あやしがりて寄りてみるに筒の中光りたり」。「様子をみる」「調子をみる」
⑦(「診る」とも書く)診察する。「病人をみる」
⑧調査する。しらべる。「答案をみる」
⑨試みる。ためす。
⑩(助詞「て」「で」を介して動詞連用形に付いて)
㋐ためしに…する。土佐日記「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」。「恐る恐るさわってみる」「やれるものならやってみな」
㋑(「…てみると」「…てみたら」「…てみれば」の形で)ある事実に気付く、またはある事実が成り立つ条件を示す。…すると。…したところが。「帰ってみると鍵がかかっていた」「親にしてみれば出来の悪い子ほどいとおしい」
➋判断する。
①物事を判断する。源氏物語桐壺「女もいといみじとみ奉りて」。「世のなりゆきをみる」「人をみる目」「甘くみる」
②占って判断する。源氏物語桐壺「朝廷のかためとなりて天の下を輔くる方にてみれば、又その相たがふべし」。「手相をみる」
③目にとめた文字の意味を知る。読む。源氏物語帚木「かかる御文みるべき人もなしと聞えよ」。日葡辞書「キャウ(経)ヲミアワスル」
④鑑定する。「古筆の専門家にみてもらう」
➌物事を調べ行う。
①取り扱う。行う。源氏物語若紫「かしこにいと切にみるべき事の侍るを思ひ給へ出でてなむ」。「政をみる」
②過ごして行けるよう力添えする。世話をする。面倒をみる。源氏物語玉鬘「かの御かはりにみ奉らん子も少なきがさうざうしきに」。「子供をみる」「勉強をみてやる」
③(「看る」とも書く)看病する。「付添が病人をみる」
➍(僧の忌詞)仏前に供える花を切る。
◇広く一般には「見」。「視」はまっすぐに目を向けてみる、また注意してみる場合、「観」は観察・見物などに多く使う。「診」は➊7に使う。
⇒見ての通り
⇒見て見ぬ振りをする
⇒見ぬうちが花
⇒見られたものじゃない
⇒見る影も無い
⇒見ると聞くとは大違い
⇒見るに忍びない
⇒見るに堪えない
⇒見るに見かねる
⇒見る間に
⇒見れば見るほど
みる【診る】
〔他上一〕
⇒みる(見)➊7
みる・い
〔形〕
(静岡県で)穀物などが、未熟で軟らかい。
みる‐いろ【海松色・水松色】
①黒みを帯びた萌葱もえぎ色。とくさいろ。
Munsell color system: 9Y4/3
②襲かさねの色目。山科流では表は萌葱、裏は青。または、表は黒萌葱、裏は白。
ミルウォーキー【Milwaukee】
アメリカ合衆国ウィスコンシン州の都市。同州最大の都市であり、ミシガン湖に臨む港湾都市で石炭・穀物などの積出しが多く、工業も盛ん。人口59万7千(2000)。
ミルカー【milker】
陰圧による吸引力を利用して牝牛の乳をしぼる器具。搾乳機。
みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ
(→)ミルクイガイの別称。
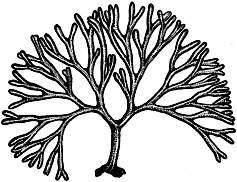 ミル【mil】
ヤード‐ポンド法の長さの単位。針金の直径などを測るのに用いる。1ミルは0.001インチで、0.0254ミリメートル。記号mil
ミル【James Mill】
イギリスの思想家・経済学者。ベンサムの功利主義を継承。主著「英領インド史」「経済学綱要」。(1773〜1836)
ミル【John Stuart Mill】
イギリスの哲学者・経済学者。父ジェームズから英才教育を受けた。イギリス経験論の立場から実証的社会科学の理論を基礎づけ、功利主義の社会倫理説を説く。経済学ではスミス・リカードを継ぎ、古典学派の最後の代表者。主著「経済学原理」「自由論」「自伝」。(1806〜1873)
みる【回る・廻る】
〔自上一〕
めぐる。まわる。古事記上「うち廻る島の崎崎」
みる【見る・視る・観る】
〔他上一〕
自分の目で実際に確かめる。転じて、自分の判断で処理する意。
➊目によって認識する。
①目によって物事の存在や動きを認識する。万葉集5「いつしかもみやこをみむと思ひつつ」。「みると聞くとは大違い」「芝居をみる」
②ながめる。望む。推古紀「我が大君の隠ります天の八十蔭出でたたす御空をみれば」。竹取物語「月をみてはいみじく泣き給ふ」。「窓から外をみる」
③人にあう。万葉集19「あをによし奈良人みむと」。源氏物語紅葉賀「み奉り給ふ時はうらみも忘れてかしづきいとなみ聞え給ふ」
④夫婦の契ちぎりをする。源氏物語帚木「多くはわが心も、みる人からをさまりもすべし」
⑤ある出来事に遭遇する。伊勢物語「物心細くすずろなる目をみることと思ふに」。源氏物語夕顔「何の契りにかかる目をみるらむ」。「馬鹿をみる」
⑥よく注意して観察する。竹取物語「あやしがりて寄りてみるに筒の中光りたり」。「様子をみる」「調子をみる」
⑦(「診る」とも書く)診察する。「病人をみる」
⑧調査する。しらべる。「答案をみる」
⑨試みる。ためす。
⑩(助詞「て」「で」を介して動詞連用形に付いて)
㋐ためしに…する。土佐日記「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」。「恐る恐るさわってみる」「やれるものならやってみな」
㋑(「…てみると」「…てみたら」「…てみれば」の形で)ある事実に気付く、またはある事実が成り立つ条件を示す。…すると。…したところが。「帰ってみると鍵がかかっていた」「親にしてみれば出来の悪い子ほどいとおしい」
➋判断する。
①物事を判断する。源氏物語桐壺「女もいといみじとみ奉りて」。「世のなりゆきをみる」「人をみる目」「甘くみる」
②占って判断する。源氏物語桐壺「朝廷のかためとなりて天の下を輔くる方にてみれば、又その相たがふべし」。「手相をみる」
③目にとめた文字の意味を知る。読む。源氏物語帚木「かかる御文みるべき人もなしと聞えよ」。日葡辞書「キャウ(経)ヲミアワスル」
④鑑定する。「古筆の専門家にみてもらう」
➌物事を調べ行う。
①取り扱う。行う。源氏物語若紫「かしこにいと切にみるべき事の侍るを思ひ給へ出でてなむ」。「政をみる」
②過ごして行けるよう力添えする。世話をする。面倒をみる。源氏物語玉鬘「かの御かはりにみ奉らん子も少なきがさうざうしきに」。「子供をみる」「勉強をみてやる」
③(「看る」とも書く)看病する。「付添が病人をみる」
➍(僧の忌詞)仏前に供える花を切る。
◇広く一般には「見」。「視」はまっすぐに目を向けてみる、また注意してみる場合、「観」は観察・見物などに多く使う。「診」は➊7に使う。
⇒見ての通り
⇒見て見ぬ振りをする
⇒見ぬうちが花
⇒見られたものじゃない
⇒見る影も無い
⇒見ると聞くとは大違い
⇒見るに忍びない
⇒見るに堪えない
⇒見るに見かねる
⇒見る間に
⇒見れば見るほど
みる【診る】
〔他上一〕
⇒みる(見)➊7
みる・い
〔形〕
(静岡県で)穀物などが、未熟で軟らかい。
みる‐いろ【海松色・水松色】
①黒みを帯びた萌葱もえぎ色。とくさいろ。
Munsell color system: 9Y4/3
②襲かさねの色目。山科流では表は萌葱、裏は青。または、表は黒萌葱、裏は白。
ミルウォーキー【Milwaukee】
アメリカ合衆国ウィスコンシン州の都市。同州最大の都市であり、ミシガン湖に臨む港湾都市で石炭・穀物などの積出しが多く、工業も盛ん。人口59万7千(2000)。
ミルカー【milker】
陰圧による吸引力を利用して牝牛の乳をしぼる器具。搾乳機。
みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ
(→)ミルクイガイの別称。
ミル【mil】
ヤード‐ポンド法の長さの単位。針金の直径などを測るのに用いる。1ミルは0.001インチで、0.0254ミリメートル。記号mil
ミル【James Mill】
イギリスの思想家・経済学者。ベンサムの功利主義を継承。主著「英領インド史」「経済学綱要」。(1773〜1836)
ミル【John Stuart Mill】
イギリスの哲学者・経済学者。父ジェームズから英才教育を受けた。イギリス経験論の立場から実証的社会科学の理論を基礎づけ、功利主義の社会倫理説を説く。経済学ではスミス・リカードを継ぎ、古典学派の最後の代表者。主著「経済学原理」「自由論」「自伝」。(1806〜1873)
みる【回る・廻る】
〔自上一〕
めぐる。まわる。古事記上「うち廻る島の崎崎」
みる【見る・視る・観る】
〔他上一〕
自分の目で実際に確かめる。転じて、自分の判断で処理する意。
➊目によって認識する。
①目によって物事の存在や動きを認識する。万葉集5「いつしかもみやこをみむと思ひつつ」。「みると聞くとは大違い」「芝居をみる」
②ながめる。望む。推古紀「我が大君の隠ります天の八十蔭出でたたす御空をみれば」。竹取物語「月をみてはいみじく泣き給ふ」。「窓から外をみる」
③人にあう。万葉集19「あをによし奈良人みむと」。源氏物語紅葉賀「み奉り給ふ時はうらみも忘れてかしづきいとなみ聞え給ふ」
④夫婦の契ちぎりをする。源氏物語帚木「多くはわが心も、みる人からをさまりもすべし」
⑤ある出来事に遭遇する。伊勢物語「物心細くすずろなる目をみることと思ふに」。源氏物語夕顔「何の契りにかかる目をみるらむ」。「馬鹿をみる」
⑥よく注意して観察する。竹取物語「あやしがりて寄りてみるに筒の中光りたり」。「様子をみる」「調子をみる」
⑦(「診る」とも書く)診察する。「病人をみる」
⑧調査する。しらべる。「答案をみる」
⑨試みる。ためす。
⑩(助詞「て」「で」を介して動詞連用形に付いて)
㋐ためしに…する。土佐日記「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」。「恐る恐るさわってみる」「やれるものならやってみな」
㋑(「…てみると」「…てみたら」「…てみれば」の形で)ある事実に気付く、またはある事実が成り立つ条件を示す。…すると。…したところが。「帰ってみると鍵がかかっていた」「親にしてみれば出来の悪い子ほどいとおしい」
➋判断する。
①物事を判断する。源氏物語桐壺「女もいといみじとみ奉りて」。「世のなりゆきをみる」「人をみる目」「甘くみる」
②占って判断する。源氏物語桐壺「朝廷のかためとなりて天の下を輔くる方にてみれば、又その相たがふべし」。「手相をみる」
③目にとめた文字の意味を知る。読む。源氏物語帚木「かかる御文みるべき人もなしと聞えよ」。日葡辞書「キャウ(経)ヲミアワスル」
④鑑定する。「古筆の専門家にみてもらう」
➌物事を調べ行う。
①取り扱う。行う。源氏物語若紫「かしこにいと切にみるべき事の侍るを思ひ給へ出でてなむ」。「政をみる」
②過ごして行けるよう力添えする。世話をする。面倒をみる。源氏物語玉鬘「かの御かはりにみ奉らん子も少なきがさうざうしきに」。「子供をみる」「勉強をみてやる」
③(「看る」とも書く)看病する。「付添が病人をみる」
➍(僧の忌詞)仏前に供える花を切る。
◇広く一般には「見」。「視」はまっすぐに目を向けてみる、また注意してみる場合、「観」は観察・見物などに多く使う。「診」は➊7に使う。
⇒見ての通り
⇒見て見ぬ振りをする
⇒見ぬうちが花
⇒見られたものじゃない
⇒見る影も無い
⇒見ると聞くとは大違い
⇒見るに忍びない
⇒見るに堪えない
⇒見るに見かねる
⇒見る間に
⇒見れば見るほど
みる【診る】
〔他上一〕
⇒みる(見)➊7
みる・い
〔形〕
(静岡県で)穀物などが、未熟で軟らかい。
みる‐いろ【海松色・水松色】
①黒みを帯びた萌葱もえぎ色。とくさいろ。
Munsell color system: 9Y4/3
②襲かさねの色目。山科流では表は萌葱、裏は青。または、表は黒萌葱、裏は白。
ミルウォーキー【Milwaukee】
アメリカ合衆国ウィスコンシン州の都市。同州最大の都市であり、ミシガン湖に臨む港湾都市で石炭・穀物などの積出しが多く、工業も盛ん。人口59万7千(2000)。
ミルカー【milker】
陰圧による吸引力を利用して牝牛の乳をしぼる器具。搾乳機。
みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ
(→)ミルクイガイの別称。
みる【見る・視る・観る】🔗⭐🔉
みる【見る・視る・観る】
〔他上一〕
自分の目で実際に確かめる。転じて、自分の判断で処理する意。
➊目によって認識する。
①目によって物事の存在や動きを認識する。万葉集5「いつしかもみやこをみむと思ひつつ」。「みると聞くとは大違い」「芝居をみる」
②ながめる。望む。推古紀「我が大君の隠ります天の八十蔭出でたたす御空をみれば」。竹取物語「月をみてはいみじく泣き給ふ」。「窓から外をみる」
③人にあう。万葉集19「あをによし奈良人みむと」。源氏物語紅葉賀「み奉り給ふ時はうらみも忘れてかしづきいとなみ聞え給ふ」
④夫婦の契ちぎりをする。源氏物語帚木「多くはわが心も、みる人からをさまりもすべし」
⑤ある出来事に遭遇する。伊勢物語「物心細くすずろなる目をみることと思ふに」。源氏物語夕顔「何の契りにかかる目をみるらむ」。「馬鹿をみる」
⑥よく注意して観察する。竹取物語「あやしがりて寄りてみるに筒の中光りたり」。「様子をみる」「調子をみる」
⑦(「診る」とも書く)診察する。「病人をみる」
⑧調査する。しらべる。「答案をみる」
⑨試みる。ためす。
⑩(助詞「て」「で」を介して動詞連用形に付いて)
㋐ためしに…する。土佐日記「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」。「恐る恐るさわってみる」「やれるものならやってみな」
㋑(「…てみると」「…てみたら」「…てみれば」の形で)ある事実に気付く、またはある事実が成り立つ条件を示す。…すると。…したところが。「帰ってみると鍵がかかっていた」「親にしてみれば出来の悪い子ほどいとおしい」
➋判断する。
①物事を判断する。源氏物語桐壺「女もいといみじとみ奉りて」。「世のなりゆきをみる」「人をみる目」「甘くみる」
②占って判断する。源氏物語桐壺「朝廷のかためとなりて天の下を輔くる方にてみれば、又その相たがふべし」。「手相をみる」
③目にとめた文字の意味を知る。読む。源氏物語帚木「かかる御文みるべき人もなしと聞えよ」。日葡辞書「キャウ(経)ヲミアワスル」
④鑑定する。「古筆の専門家にみてもらう」
➌物事を調べ行う。
①取り扱う。行う。源氏物語若紫「かしこにいと切にみるべき事の侍るを思ひ給へ出でてなむ」。「政をみる」
②過ごして行けるよう力添えする。世話をする。面倒をみる。源氏物語玉鬘「かの御かはりにみ奉らん子も少なきがさうざうしきに」。「子供をみる」「勉強をみてやる」
③(「看る」とも書く)看病する。「付添が病人をみる」
➍(僧の忌詞)仏前に供える花を切る。
◇広く一般には「見」。「視」はまっすぐに目を向けてみる、また注意してみる場合、「観」は観察・見物などに多く使う。「診」は➊7に使う。
⇒見ての通り
⇒見て見ぬ振りをする
⇒見ぬうちが花
⇒見られたものじゃない
⇒見る影も無い
⇒見ると聞くとは大違い
⇒見るに忍びない
⇒見るに堪えない
⇒見るに見かねる
⇒見る間に
⇒見れば見るほど
○見る影も無いみるかげもない🔗⭐🔉
○見る影も無いみるかげもない
以前の面影がすっかり変わって、見るに堪えないさまである。みすぼらしい。
⇒みる【見る・視る・観る】
みる‐から【見るから】
(→)「見るからに」に同じ。
⇒みるから‐に【見るからに】
みるから‐に【見るからに】
①見るとすぐ。見ればそのまま。後撰和歌集恋「いにしへの野中の清水―さしぐむものは涙なりけり」
②ちょっと見ただけでいかにもそれらしいように。見るから。「―嫌な奴」
⇒みる‐から【見るから】
ミルキー‐ハット【milky hat】
軽快な中折れ帽子。
ミルク【milk】
①牛乳。島崎藤村、春「四時頃スウプならびに牛乳ミルク等を食し」
②コンデンス‐ミルク(練乳)など加工乳の略。
③ミルク状のもの。乳液やココナッツ‐ミルクなど。
⇒ミルク‐いろ【ミルク色】
⇒ミルク‐キャラメル
⇒ミルク‐セーキ
⇒ミルク‐ティー【milk tea】
⇒ミルクのみ‐にんぎょう【ミルク飲み人形】
⇒ミルク‐パン【milk pan】
⇒ミルク‐プラント【milk plant】
⇒ミルク‐ホール
みる‐くい【海松食・水松食】‥クヒ
(→)ミルクイガイのこと。浄瑠璃、国性爺合戦「人の―わすれ貝」
⇒みるくい‐がい【海松食貝】
みるくい‐がい【海松食貝】‥クヒガヒ
バカガイ科の二枚貝。殻はやや長方形で、殻長約10センチメートル。黒褐色の殻皮をかぶり、それが長い水管をも覆う。水管の先にミルが着生し、それを食うように見えるので名づけられたという。日本各地の内湾浅海に広く産し、主に水管部を食用。特に鮨種すしだねとして好まれる。みる貝。ミルクイ。
⇒みる‐くい【海松食・水松食】
ミルク‐いろ【ミルク色】
乳白色。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐キャラメル
(milk caramel)ミルク風味のキャラメル。キャラメル。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐セーキ
(milk shake)牛乳に卵黄・砂糖を加えて攪拌した飲物。香料・果物などを加えたものもある。また卵と砂糖の代りにアイス‐クリームを使うこともある。
ミルクセーキ
撮影:関戸 勇
 ⇒ミルク【milk】
ミルク‐ティー【milk tea】
牛乳を加えた紅茶。また、牛乳でいれた紅茶。
⇒ミルク【milk】
ミルクのみ‐にんぎょう【ミルク飲み人形】‥ギヤウ
実際に水を飲ませることができる、セルロイドやビニール製の人形。1950年代に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐パン【milk pan】
小形の片手鍋。牛乳を沸かしたり、少量の材料をゆでたりするのに用いる。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐プラント【milk plant】
牛乳処理場。農家や牧場から供給される牛乳を濾過・殺菌して、一般消費者用に調製する施設。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐ホール
(和製語milk hall)牛乳を飲ませ、パンなども売る簡易な飲食店。明治末期から大正期に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルズ【Charles Wright Mills】
アメリカの社会学者。コロンビア大学教授。現代アメリカの大衆社会状況を批判的に分析。著「ホワイト‐カラー」「パワー‐エリート」「社会学的想像力」など。(1916〜1962)
みる‐ちゃ【海松茶】
海松みる色を帯びた茶色。日本永代蔵2「ひとつは―染にせし事」
ミルテ【Myrte ドイツ】
フトモモ科の常緑低木。ヨーロッパ原産で、高さ3メートルほど。先のとがった長楕円形の葉を密に対生する。夏から秋に5弁の白花を多数つけ、長い雄しべが目立つ。ギリシア神話で神木とされ、不死の象徴とされる。ミルトス。
ミルティアデス【Miltiadēs】
古代ギリシア、アテナイの将軍。マラトンの戦いでペルシア軍を破った。(前550頃〜前489)→マラトン
⇒ミルク【milk】
ミルク‐ティー【milk tea】
牛乳を加えた紅茶。また、牛乳でいれた紅茶。
⇒ミルク【milk】
ミルクのみ‐にんぎょう【ミルク飲み人形】‥ギヤウ
実際に水を飲ませることができる、セルロイドやビニール製の人形。1950年代に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐パン【milk pan】
小形の片手鍋。牛乳を沸かしたり、少量の材料をゆでたりするのに用いる。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐プラント【milk plant】
牛乳処理場。農家や牧場から供給される牛乳を濾過・殺菌して、一般消費者用に調製する施設。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐ホール
(和製語milk hall)牛乳を飲ませ、パンなども売る簡易な飲食店。明治末期から大正期に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルズ【Charles Wright Mills】
アメリカの社会学者。コロンビア大学教授。現代アメリカの大衆社会状況を批判的に分析。著「ホワイト‐カラー」「パワー‐エリート」「社会学的想像力」など。(1916〜1962)
みる‐ちゃ【海松茶】
海松みる色を帯びた茶色。日本永代蔵2「ひとつは―染にせし事」
ミルテ【Myrte ドイツ】
フトモモ科の常緑低木。ヨーロッパ原産で、高さ3メートルほど。先のとがった長楕円形の葉を密に対生する。夏から秋に5弁の白花を多数つけ、長い雄しべが目立つ。ギリシア神話で神木とされ、不死の象徴とされる。ミルトス。
ミルティアデス【Miltiadēs】
古代ギリシア、アテナイの将軍。マラトンの戦いでペルシア軍を破った。(前550頃〜前489)→マラトン
 ⇒ミルク【milk】
ミルク‐ティー【milk tea】
牛乳を加えた紅茶。また、牛乳でいれた紅茶。
⇒ミルク【milk】
ミルクのみ‐にんぎょう【ミルク飲み人形】‥ギヤウ
実際に水を飲ませることができる、セルロイドやビニール製の人形。1950年代に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐パン【milk pan】
小形の片手鍋。牛乳を沸かしたり、少量の材料をゆでたりするのに用いる。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐プラント【milk plant】
牛乳処理場。農家や牧場から供給される牛乳を濾過・殺菌して、一般消費者用に調製する施設。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐ホール
(和製語milk hall)牛乳を飲ませ、パンなども売る簡易な飲食店。明治末期から大正期に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルズ【Charles Wright Mills】
アメリカの社会学者。コロンビア大学教授。現代アメリカの大衆社会状況を批判的に分析。著「ホワイト‐カラー」「パワー‐エリート」「社会学的想像力」など。(1916〜1962)
みる‐ちゃ【海松茶】
海松みる色を帯びた茶色。日本永代蔵2「ひとつは―染にせし事」
ミルテ【Myrte ドイツ】
フトモモ科の常緑低木。ヨーロッパ原産で、高さ3メートルほど。先のとがった長楕円形の葉を密に対生する。夏から秋に5弁の白花を多数つけ、長い雄しべが目立つ。ギリシア神話で神木とされ、不死の象徴とされる。ミルトス。
ミルティアデス【Miltiadēs】
古代ギリシア、アテナイの将軍。マラトンの戦いでペルシア軍を破った。(前550頃〜前489)→マラトン
⇒ミルク【milk】
ミルク‐ティー【milk tea】
牛乳を加えた紅茶。また、牛乳でいれた紅茶。
⇒ミルク【milk】
ミルクのみ‐にんぎょう【ミルク飲み人形】‥ギヤウ
実際に水を飲ませることができる、セルロイドやビニール製の人形。1950年代に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐パン【milk pan】
小形の片手鍋。牛乳を沸かしたり、少量の材料をゆでたりするのに用いる。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐プラント【milk plant】
牛乳処理場。農家や牧場から供給される牛乳を濾過・殺菌して、一般消費者用に調製する施設。
⇒ミルク【milk】
ミルク‐ホール
(和製語milk hall)牛乳を飲ませ、パンなども売る簡易な飲食店。明治末期から大正期に流行。
⇒ミルク【milk】
ミルズ【Charles Wright Mills】
アメリカの社会学者。コロンビア大学教授。現代アメリカの大衆社会状況を批判的に分析。著「ホワイト‐カラー」「パワー‐エリート」「社会学的想像力」など。(1916〜1962)
みる‐ちゃ【海松茶】
海松みる色を帯びた茶色。日本永代蔵2「ひとつは―染にせし事」
ミルテ【Myrte ドイツ】
フトモモ科の常緑低木。ヨーロッパ原産で、高さ3メートルほど。先のとがった長楕円形の葉を密に対生する。夏から秋に5弁の白花を多数つけ、長い雄しべが目立つ。ギリシア神話で神木とされ、不死の象徴とされる。ミルトス。
ミルティアデス【Miltiadēs】
古代ギリシア、アテナイの将軍。マラトンの戦いでペルシア軍を破った。(前550頃〜前489)→マラトン
みる‐から【見るから】🔗⭐🔉
みる‐から【見るから】
(→)「見るからに」に同じ。
⇒みるから‐に【見るからに】
みるから‐に【見るからに】🔗⭐🔉
みるから‐に【見るからに】
①見るとすぐ。見ればそのまま。後撰和歌集恋「いにしへの野中の清水―さしぐむものは涙なりけり」
②ちょっと見ただけでいかにもそれらしいように。見るから。「―嫌な奴」
⇒みる‐から【見るから】
○見ると聞くとは大違いみるときくとはおおちがい🔗⭐🔉
○見ると聞くとは大違いみるときくとはおおちがい
実際に見たことと話に聞いていたこととでは大変な差違がある。下を略して「見ると聞くと」とも。歌舞伎、三十石艠始「家中には不義法度の固い掟と承つたが見ると聞くとは大違ひ」
⇒みる【見る・視る・観る】
ミルトン【John Milton】
イギリスの詩人。清教徒革命に参加、自由と民主制のために戦い、クロムウェルの共和政府にも関与。失明し、王政復古後は詩作に没頭。叙事詩「失楽園」「復楽園」、悲劇「闘士サムソン」の他に、言論の自由を論じた「アレオパジティカ」など多くの政治評論がある。(1608〜1674)
○見るに忍びないみるにしのびない🔗⭐🔉
○見るに忍びないみるにしのびない
気の毒で見ていられない。
⇒みる【見る・視る・観る】
○見るに堪えないみるにたえない🔗⭐🔉
○見るに堪えないみるにたえない
①体裁・内容などがいかにも粗末で、まともに見られない。見られたものじゃない。
②(→)「見るに忍びない」に同じ。
⇒みる【見る・視る・観る】
○見るに見かねるみるにみかねる🔗⭐🔉
○見るに見かねるみるにみかねる
当事者ではないが見て放っておけない。危なっかしくて任せておけない。「見るに見かねて手を出す」
⇒みる【見る・視る・観る】
ミル‐フィーユ【mille-feuille フランス】
(「千枚の葉」の意)フランス風菓子の一つ。層になるように作ったパイ生地を薄く伸ばして焼き、カスタード‐クリームや果物などを挟んで重ねたもの。ミルフィユ。
みる‐ぶさ【海松房・水松房】
枝が房になって生えた海松みる。髪そぎ・鬢びんそぎの儀に用いられた。〈[季]春〉
○見る間にみるまに🔗⭐🔉
○見る間にみるまに
見ている少しの間にも。またたく間に。「川の水位が―上昇した」
⇒みる【見る・視る・観る】
みる‐みる【見る見る】
①見ながらも。堤中納言物語「年ごろ行く方もなしと―、かく言ふよ」
②見ているうちに。たちまちに。「―血の気が失せる」
みる‐め【見る目】
①見ること。会うこと。源氏物語紅葉賀「―に飽くはまさなきことぞよ」
②見た様子。容姿。源氏物語若菜上「―は人よりけに若く、をかしげにて」。「―もなく落ちぶれた姿」
③様子をうかがう他人の目。他人の思惑。「人の―がうるさい」
④物・事柄の真偽・優劣などを見わける力。「―がない」
⇒みるめ‐の‐まえ【見る目の前】
⇒見る目嗅ぐ鼻
みる‐め【海松布・水松布】
(「め」は海藻の意)(→)海松みるに同じ。歌では多く「見る目」にかけて用いる。〈[季]春〉。古今和歌集恋「はやきせに―おひせば」
みる‐みる【見る見る】🔗⭐🔉
みる‐みる【見る見る】
①見ながらも。堤中納言物語「年ごろ行く方もなしと―、かく言ふよ」
②見ているうちに。たちまちに。「―血の気が失せる」
みる‐め【見る目】🔗⭐🔉
みる‐め【見る目】
①見ること。会うこと。源氏物語紅葉賀「―に飽くはまさなきことぞよ」
②見た様子。容姿。源氏物語若菜上「―は人よりけに若く、をかしげにて」。「―もなく落ちぶれた姿」
③様子をうかがう他人の目。他人の思惑。「人の―がうるさい」
④物・事柄の真偽・優劣などを見わける力。「―がない」
⇒みるめ‐の‐まえ【見る目の前】
⇒見る目嗅ぐ鼻
みるめ‐な・し【見る目なし】🔗⭐🔉
みるめ‐な・し【見る目なし】
〔形ク〕
①逢うことができない。後撰和歌集恋「―・きこと行きて怨みん」
②見どころがない。みすぼらしい。伊勢物語「―・き我が身を浦としらねばや」
め・す【召す・見す・看す】🔗⭐🔉
め・す【召す・見す・看す】
〔他五〕
(「見る」の尊敬語)
①御覧になる。万葉集1「埴安の堤の上にあり立たし―・したまへば」
②お治めになる。万葉集1「食おす国を―・し給はむと」
③お呼び寄せになる。万葉集2「東の滝たぎの御門にさもらへど昨日も今日も―・すこともなし」。源氏物語夕顔「―・せば御こたへして起きたれば」。「神に―・される」
④お取り寄せになる。古今和歌集秋「仁和寺に菊の花―・しける時に、歌そへて奉れと仰せられければ」。源氏物語空蝉「御硯いそぎ―・して」
⑤召し出して役につかせる。お命じになる。推古紀「僧正、僧都を任めして、仍りて僧尼を検校かむがふべし」。持統紀「撰善言司よきことえらぶつかさに拝めす」。古今和歌集雑「もろこしの判官に―・されて侍りける時に」
⑥結婚の相手となさる。寵愛なさる。神代紀上「奇稲田媛を幸めさむとして乞ひたまふ」。神代紀下「皇孫因て幸めす、即ち一夜にして有娠はらみぬ」
⑦上からの命によって捕らえる。囚人とする。「めしいましむ」「めしこむ」「めしとる」など複合語として使われることが多い。今昔物語集17「すみやかに、かの不調を致す男を―・し搦めて…殺すべし」。古今著聞集12「―・しすゑていかに汝程のやつがこれ程やすくは搦められたるぞと御たづね有りければ」
⑧上からの命令で…と呼ぶ。平家物語10「よしよし力及ばず。浪方なみかたとも―・せかし」
⑨「食う」「飲む」「買う」「取る」「(腹を)切る」「着る」「(風邪を)引く」などの尊敬語。物を身に受け入れる意。万葉集8「わけがためわが手もすまに春の野に抜ける茅花つばなそ―・して肥えませ」。続詞花和歌集戯咲「女のよき、つみや―・すと売りありきけるを聞きて」。大鏡道隆「さかづき取り給ひてあまたたび―・し常よりも乱れあそばせ給ひけるさま」。平治物語「叶はぬ所にて御腹―・されん事何の義か候ふべき」。平家物語3「御行水を―・さばやと思し召すはいかがせんずる」。平家物語9「田内左衛門をば物具―・されて、伊勢三郎に預けらる」。平家物語(延慶本)「速やかに命を―・して後世を助給へ」。建礼門院右京大夫集「青色の御唐衣、蝶を色々に織りたりし―・したりし」。中華若木詩抄「花を―・せ花を―・せと誰が所へもゆけども」。浮世風呂2「お風でも―・してはお悪うございますから」。「お年を―・す」「羽織を―・す」
⑩(自動詞的に)「乗る」「(気に)入る」などの尊敬語。平家物語4「それより御輿に―・して福原へいらせおはします」。「お気に―・したのをお持ち下さい」
⑪(多く尊敬の助動詞「る」を添えた形で使われる)広く「する」の尊敬語。なさる。狂言、花子「思ふやうにはなけれども、得心を―・されて満足した」。ロドリーゲス大文典「何事を―・すぞ」
⑫主に他の尊敬語動詞の連用形に付いて厚い尊敬の意を添える。万葉集15「遠くあれば一日一夜も思はずてあるらむものと思ほし―・すな」
[漢]見🔗⭐🔉
見 字形
 筆順
筆順
 〔見部0画/7画/教育/2411・382B〕
〔音〕ケン(呉)(漢) ゲン(呉)
〔訓〕みる・みえる・みせる・まみえる・あらわれる (名)あきら
[意味]
①みる。みえる。「見学・見物・見聞・発見・外見・散見」
②物のみかた。考え。「皮相の見」「見解・見識・意見・卓見・偏見」
③人にあう。対面する。まみえる。「会見・接見・朝見・見参げんざん」
④あらわれる。「露見・一見いちげん」。まのあたり。目の前に。「見在げんざい」。(同)現。
⑤受け身を表す助字。「る」「らる」と訓読する。「信而見疑=信にして疑わる」〔史記〕▶そういう目に会うの意から。
[解字]
会意。「目」+「人」。人が目にとめる意。
[下ツキ
意見・異見・一見・引見・隠見・謁見・延見・臆見・会見・外見・我見・管見・愚見・後見・高見・再見・細見・散見・私見・識見・実見・邪見・巡見・所見・書見・初見・素見・政見・接見・先見・浅見・創見・想見・総見・卓見・他見・達見・短見・知見・朝見・定見・洞見・拝見・発見・卑見・鄙見・披見・必見・謬見・膚見・僻見・瞥見・偏見・望見・未見・予見・了見・露見
[難読]
見栄みえ・見得みえ
〔見部0画/7画/教育/2411・382B〕
〔音〕ケン(呉)(漢) ゲン(呉)
〔訓〕みる・みえる・みせる・まみえる・あらわれる (名)あきら
[意味]
①みる。みえる。「見学・見物・見聞・発見・外見・散見」
②物のみかた。考え。「皮相の見」「見解・見識・意見・卓見・偏見」
③人にあう。対面する。まみえる。「会見・接見・朝見・見参げんざん」
④あらわれる。「露見・一見いちげん」。まのあたり。目の前に。「見在げんざい」。(同)現。
⑤受け身を表す助字。「る」「らる」と訓読する。「信而見疑=信にして疑わる」〔史記〕▶そういう目に会うの意から。
[解字]
会意。「目」+「人」。人が目にとめる意。
[下ツキ
意見・異見・一見・引見・隠見・謁見・延見・臆見・会見・外見・我見・管見・愚見・後見・高見・再見・細見・散見・私見・識見・実見・邪見・巡見・所見・書見・初見・素見・政見・接見・先見・浅見・創見・想見・総見・卓見・他見・達見・短見・知見・朝見・定見・洞見・拝見・発見・卑見・鄙見・披見・必見・謬見・膚見・僻見・瞥見・偏見・望見・未見・予見・了見・露見
[難読]
見栄みえ・見得みえ
 筆順
筆順
 〔見部0画/7画/教育/2411・382B〕
〔音〕ケン(呉)(漢) ゲン(呉)
〔訓〕みる・みえる・みせる・まみえる・あらわれる (名)あきら
[意味]
①みる。みえる。「見学・見物・見聞・発見・外見・散見」
②物のみかた。考え。「皮相の見」「見解・見識・意見・卓見・偏見」
③人にあう。対面する。まみえる。「会見・接見・朝見・見参げんざん」
④あらわれる。「露見・一見いちげん」。まのあたり。目の前に。「見在げんざい」。(同)現。
⑤受け身を表す助字。「る」「らる」と訓読する。「信而見疑=信にして疑わる」〔史記〕▶そういう目に会うの意から。
[解字]
会意。「目」+「人」。人が目にとめる意。
[下ツキ
意見・異見・一見・引見・隠見・謁見・延見・臆見・会見・外見・我見・管見・愚見・後見・高見・再見・細見・散見・私見・識見・実見・邪見・巡見・所見・書見・初見・素見・政見・接見・先見・浅見・創見・想見・総見・卓見・他見・達見・短見・知見・朝見・定見・洞見・拝見・発見・卑見・鄙見・披見・必見・謬見・膚見・僻見・瞥見・偏見・望見・未見・予見・了見・露見
[難読]
見栄みえ・見得みえ
〔見部0画/7画/教育/2411・382B〕
〔音〕ケン(呉)(漢) ゲン(呉)
〔訓〕みる・みえる・みせる・まみえる・あらわれる (名)あきら
[意味]
①みる。みえる。「見学・見物・見聞・発見・外見・散見」
②物のみかた。考え。「皮相の見」「見解・見識・意見・卓見・偏見」
③人にあう。対面する。まみえる。「会見・接見・朝見・見参げんざん」
④あらわれる。「露見・一見いちげん」。まのあたり。目の前に。「見在げんざい」。(同)現。
⑤受け身を表す助字。「る」「らる」と訓読する。「信而見疑=信にして疑わる」〔史記〕▶そういう目に会うの意から。
[解字]
会意。「目」+「人」。人が目にとめる意。
[下ツキ
意見・異見・一見・引見・隠見・謁見・延見・臆見・会見・外見・我見・管見・愚見・後見・高見・再見・細見・散見・私見・識見・実見・邪見・巡見・所見・書見・初見・素見・政見・接見・先見・浅見・創見・想見・総見・卓見・他見・達見・短見・知見・朝見・定見・洞見・拝見・発見・卑見・鄙見・披見・必見・謬見・膚見・僻見・瞥見・偏見・望見・未見・予見・了見・露見
[難読]
見栄みえ・見得みえ
広辞苑に「見」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む