複数辞典一括検索+![]()
![]()
与 と🔗⭐🔉
【与】
 3画 一部 [常用漢字]
区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E
【與】旧字人名に使える旧字
3画 一部 [常用漢字]
区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E
【與】旧字人名に使える旧字
 14画 臼部
区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F
《常用音訓》ヨ/あた…える
《音読み》 ヨ
14画 臼部
区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F
《常用音訓》ヨ/あた…える
《音読み》 ヨ
 〈y
〈y ・y
・y ・y
・y 〉
《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か
《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし
《意味》
〉
《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か
《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし
《意味》
 {動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」
{動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」
 {名}組。仲間。「与党」「与国」
{名}組。仲間。「与党」「与国」
 {動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕
{動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕
 {副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕
{副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕
 {前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕
{前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕
 {接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕
{接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕
 {前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕
{前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕
 {動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕
{動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕
 {助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕
《解字》
{助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕
《解字》
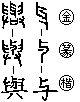 会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。
《単語家族》
舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる)
会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。
《単語家族》
舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる) 輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし)
輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし) 擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 3画 一部 [常用漢字]
区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E
【與】旧字人名に使える旧字
3画 一部 [常用漢字]
区点=4531 16進=4D3F シフトJIS=975E
【與】旧字人名に使える旧字
 14画 臼部
区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F
《常用音訓》ヨ/あた…える
《音読み》 ヨ
14画 臼部
区点=7148 16進=6750 シフトJIS=E46F
《常用音訓》ヨ/あた…える
《音読み》 ヨ
 〈y
〈y ・y
・y ・y
・y 〉
《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か
《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし
《意味》
〉
《訓読み》 くみする(くみす)/あずかる(あづかる)/ともに/と/…と…と/より/あたえる(あたふ)/か
《名付け》 あたう・あたえ・あと・あとう・くみ・すえ・ため・とも・のぶ・ひとし・もと・もろ・よし
《意味》
 {動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」
{動}くみする(クミス)。力をあわせる。広く、いっしょに物事をするために仲間になる。「易与=与シ易シ」
 {名}組。仲間。「与党」「与国」
{名}組。仲間。「与党」「与国」
 {動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕
{動}あずかる(アヅカル)。参加する。「参与」「而王天下、不与存焉=シカウシテ天下ニ王タルハ、与リ存セズ」〔→孟子〕
 {副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕
{副}ともに。いっしょに。「不可与言=トモニ言フベカラズ」〔→論語〕
 {前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕
{前}と。…と。「与朋友交=朋友ト交ハル」〔→論語〕
 {接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕
{接続}…と…と。 AとBと。「貧与賤=貧ト賤ト」〔→論語〕
 {前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕
{前}より。…とくらべて。▽「与其A寧B=其ノAナラン与リハ寧ロBナレ」という句型で用いる。「礼与其奢也寧倹=礼ハ其ノ奢ナラン与リハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕
 {動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕
{動}あたえる(アタフ)。▽賜予の予に当てた用法。「供与」「可以与、可以無与=以テ与フ可ク、以テ与フル無カル可シ」〔→孟子〕
 {助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕
《解字》
{助}か。歟カと同じく、文末につけて疑問や自問の気持ちをあらわすことば。▽平声に読む。「帰与、帰与=帰ランカ、帰ランカ」〔→論語〕
《解字》
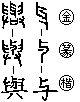 会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。
《単語家族》
舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる)
会意兼形声。与は牙ガの原字と同形で、かみあった姿を示す。與はさらに四本の手をそえて、二人が両手でいっしょに物を持ちあげるさまを示す。「二人の両手+音符与」で、かみあわす、力をあわせるなどの意を含む。
《単語家族》
舁ヨ(力をあわせてかつぎあげる) 輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし)
輿ヨ(力をあわせて持ちあげるみこし) 擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
擧キョ(=挙。力をあわせて持ちあげる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
十 と🔗⭐🔉
【十】
 2画 十部 [一年]
区点=2929 16進=3D3D シフトJIS=8F5C
《常用音訓》ジッ/ジュウ/と/とお
《音読み》 ジュウ(ジフ)
2画 十部 [一年]
区点=2929 16進=3D3D シフトJIS=8F5C
《常用音訓》ジッ/ジュウ/と/とお
《音読み》 ジュウ(ジフ) /ジッ
/ジッ /シュウ(シフ)
/シュウ(シフ) 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とお(とを)/と/とたび/とたびする(とたびす)
《名付け》 かず・しげ・じつ・そ・ただ・と・とお・とみ・ひさし・みつ・みつる
《意味》
〉
《訓読み》 とお(とを)/と/とたび/とたびする(とたびす)
《名付け》 かず・しげ・じつ・そ・ただ・と・とお・とみ・ひさし・みつ・みつる
《意味》
 {数}とお(トヲ)。「聞一以知十=一ヲ聞イテモッテ十ヲ知ル」〔→論語〕
{数}とお(トヲ)。「聞一以知十=一ヲ聞イテモッテ十ヲ知ル」〔→論語〕
 {数}と。順番の十番め。「十月十日」
{数}と。順番の十番め。「十月十日」
 {副・動}とたび。とたびする(トタビス)。十回。十回する。「人十能之、己千之=人十タビシテコレヲ能クスレバ、己コレヲ千タビス」〔→中庸〕
{副・動}とたび。とたびする(トタビス)。十回。十回する。「人十能之、己千之=人十タビシテコレヲ能クスレバ、己コレヲ千タビス」〔→中庸〕
 {形}すべて、まとまっているさま。十分なさま。「十全(完全)の備え」
《解字》
{形}すべて、まとまっているさま。十分なさま。「十全(完全)の備え」
《解字》
 指事。全部を一本に集めて一単位とすることを|印で示すもの。その中央がまるくふくれ、のち十の字体となった。多くのものを寄せ集めてまとめる意を含む。▽促音の語尾pがtに転じた場合はジツまたはジュツと読み、mに転じた場合はシン(シム)と読む。証文や契約書では改竄カイザンや誤解をさけるため、拾と書くことがある。
《単語家族》
拾シュウ(あわせ集める)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
指事。全部を一本に集めて一単位とすることを|印で示すもの。その中央がまるくふくれ、のち十の字体となった。多くのものを寄せ集めてまとめる意を含む。▽促音の語尾pがtに転じた場合はジツまたはジュツと読み、mに転じた場合はシン(シム)と読む。証文や契約書では改竄カイザンや誤解をさけるため、拾と書くことがある。
《単語家族》
拾シュウ(あわせ集める)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
 2画 十部 [一年]
区点=2929 16進=3D3D シフトJIS=8F5C
《常用音訓》ジッ/ジュウ/と/とお
《音読み》 ジュウ(ジフ)
2画 十部 [一年]
区点=2929 16進=3D3D シフトJIS=8F5C
《常用音訓》ジッ/ジュウ/と/とお
《音読み》 ジュウ(ジフ) /ジッ
/ジッ /シュウ(シフ)
/シュウ(シフ) 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とお(とを)/と/とたび/とたびする(とたびす)
《名付け》 かず・しげ・じつ・そ・ただ・と・とお・とみ・ひさし・みつ・みつる
《意味》
〉
《訓読み》 とお(とを)/と/とたび/とたびする(とたびす)
《名付け》 かず・しげ・じつ・そ・ただ・と・とお・とみ・ひさし・みつ・みつる
《意味》
 {数}とお(トヲ)。「聞一以知十=一ヲ聞イテモッテ十ヲ知ル」〔→論語〕
{数}とお(トヲ)。「聞一以知十=一ヲ聞イテモッテ十ヲ知ル」〔→論語〕
 {数}と。順番の十番め。「十月十日」
{数}と。順番の十番め。「十月十日」
 {副・動}とたび。とたびする(トタビス)。十回。十回する。「人十能之、己千之=人十タビシテコレヲ能クスレバ、己コレヲ千タビス」〔→中庸〕
{副・動}とたび。とたびする(トタビス)。十回。十回する。「人十能之、己千之=人十タビシテコレヲ能クスレバ、己コレヲ千タビス」〔→中庸〕
 {形}すべて、まとまっているさま。十分なさま。「十全(完全)の備え」
《解字》
{形}すべて、まとまっているさま。十分なさま。「十全(完全)の備え」
《解字》
 指事。全部を一本に集めて一単位とすることを|印で示すもの。その中央がまるくふくれ、のち十の字体となった。多くのものを寄せ集めてまとめる意を含む。▽促音の語尾pがtに転じた場合はジツまたはジュツと読み、mに転じた場合はシン(シム)と読む。証文や契約書では改竄カイザンや誤解をさけるため、拾と書くことがある。
《単語家族》
拾シュウ(あわせ集める)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
指事。全部を一本に集めて一単位とすることを|印で示すもの。その中央がまるくふくれ、のち十の字体となった。多くのものを寄せ集めてまとめる意を含む。▽促音の語尾pがtに転じた場合はジツまたはジュツと読み、mに転じた場合はシン(シム)と読む。証文や契約書では改竄カイザンや誤解をさけるため、拾と書くことがある。
《単語家族》
拾シュウ(あわせ集める)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
将 と🔗⭐🔉
【将】
 10画 寸部 [六年]
区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB
【將】旧字人名に使える旧字
10画 寸部 [六年]
区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB
【將】旧字人名に使える旧字
 11画 寸部
区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92
《常用音訓》ショウ
《音読み》
11画 寸部
区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92
《常用音訓》ショウ
《音読み》  ショウ(シャウ)
ショウ(シャウ) /ソウ(サウ)
/ソウ(サウ) 〈ji
〈ji ng〉/
ng〉/ ソウ(サウ)
ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈ji
〈ji ng〉
《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と
《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と
《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき
《意味》

 {名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕
{名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕
 ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕
ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕
 {動}ひきいる(ヒキ
{動}ひきいる(ヒキ ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将
ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将 テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕
テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕

 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕
ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕
 {前}もって。もちいて(モチ
{前}もって。もちいて(モチ テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕
テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕
 {動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕
{動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕
 {動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕
{動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕
 {助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕
{助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕
 {前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」
{前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」
 {助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕
{助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕
 {助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕
{助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕
 {接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。
{接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。
 {接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕
《解字》
{接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕
《解字》
 会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 寸部 [六年]
区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB
【將】旧字人名に使える旧字
10画 寸部 [六年]
区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB
【將】旧字人名に使える旧字
 11画 寸部
区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92
《常用音訓》ショウ
《音読み》
11画 寸部
区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92
《常用音訓》ショウ
《音読み》  ショウ(シャウ)
ショウ(シャウ) /ソウ(サウ)
/ソウ(サウ) 〈ji
〈ji ng〉/
ng〉/ ソウ(サウ)
ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈ji
〈ji ng〉
《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と
《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と
《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき
《意味》

 {名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕
{名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕
 ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕
ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕
 {動}ひきいる(ヒキ
{動}ひきいる(ヒキ ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将
ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将 テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕
テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕

 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕
ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕
 {前}もって。もちいて(モチ
{前}もって。もちいて(モチ テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕
テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕
 {動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕
{動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕
 {動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕
{動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕
 {助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕
{助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕
 {前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」
{前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」
 {助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕
{助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕
 {助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕
{助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕
 {接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。
{接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。
 {接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕
《解字》
{接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕
《解字》
 会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
戸 と🔗⭐🔉
【戸】
 4画 戸部 [二年]
区点=2445 16進=384D シフトJIS=8CCB
《常用音訓》コ/と
《音読み》 コ
4画 戸部 [二年]
区点=2445 16進=384D シフトJIS=8CCB
《常用音訓》コ/と
《音読み》 コ /グ/ゴ
/グ/ゴ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 と
《名付け》 いえ・かど・と・ど・ひろ・へ・べ・もり
《意味》
〉
《訓読み》 と
《名付け》 いえ・かど・と・ど・ひろ・へ・べ・もり
《意味》
 {名}と。家やへやの出入り口。また、出入り口にある片開きの一枚とびら。〈類義語〉→門・→扉ヒ。「門戸(入り口)」「外戸而不閉=外ニ戸アレドモ閉ヂズ」〔→礼記〕
{名}と。家やへやの出入り口。また、出入り口にある片開きの一枚とびら。〈類義語〉→門・→扉ヒ。「門戸(入り口)」「外戸而不閉=外ニ戸アレドモ閉ヂズ」〔→礼記〕
 {名・単位}人民の住む家。また、民家を数えることば。「戸口」「購我頭千金、邑万戸=我ガ頭ヲ、千金ト邑万戸トニ購フ」〔→史記〕
{名・単位}人民の住む家。また、民家を数えることば。「戸口」「購我頭千金、邑万戸=我ガ頭ヲ、千金ト邑万戸トニ購フ」〔→史記〕
 {名}家の意から転じて、大人の男の人。「大戸」「上戸」
《解字》
{名}家の意から転じて、大人の男の人。「大戸」「上戸」
《解字》
 象形。門は二枚とびらのもんを描いた象形文字。戸は、その左半部をとり、一枚とびらの入り口を描いたもので、かってに出入りしないようにふせぐとびら。
《単語家族》
護(中にはいらぬようふせぐ)
象形。門は二枚とびらのもんを描いた象形文字。戸は、その左半部をとり、一枚とびらの入り口を描いたもので、かってに出入りしないようにふせぐとびら。
《単語家族》
護(中にはいらぬようふせぐ) 禦ギョ(ふせぐ)などと同系。
《類義》
→門
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
禦ギョ(ふせぐ)などと同系。
《類義》
→門
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 4画 戸部 [二年]
区点=2445 16進=384D シフトJIS=8CCB
《常用音訓》コ/と
《音読み》 コ
4画 戸部 [二年]
区点=2445 16進=384D シフトJIS=8CCB
《常用音訓》コ/と
《音読み》 コ /グ/ゴ
/グ/ゴ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 と
《名付け》 いえ・かど・と・ど・ひろ・へ・べ・もり
《意味》
〉
《訓読み》 と
《名付け》 いえ・かど・と・ど・ひろ・へ・べ・もり
《意味》
 {名}と。家やへやの出入り口。また、出入り口にある片開きの一枚とびら。〈類義語〉→門・→扉ヒ。「門戸(入り口)」「外戸而不閉=外ニ戸アレドモ閉ヂズ」〔→礼記〕
{名}と。家やへやの出入り口。また、出入り口にある片開きの一枚とびら。〈類義語〉→門・→扉ヒ。「門戸(入り口)」「外戸而不閉=外ニ戸アレドモ閉ヂズ」〔→礼記〕
 {名・単位}人民の住む家。また、民家を数えることば。「戸口」「購我頭千金、邑万戸=我ガ頭ヲ、千金ト邑万戸トニ購フ」〔→史記〕
{名・単位}人民の住む家。また、民家を数えることば。「戸口」「購我頭千金、邑万戸=我ガ頭ヲ、千金ト邑万戸トニ購フ」〔→史記〕
 {名}家の意から転じて、大人の男の人。「大戸」「上戸」
《解字》
{名}家の意から転じて、大人の男の人。「大戸」「上戸」
《解字》
 象形。門は二枚とびらのもんを描いた象形文字。戸は、その左半部をとり、一枚とびらの入り口を描いたもので、かってに出入りしないようにふせぐとびら。
《単語家族》
護(中にはいらぬようふせぐ)
象形。門は二枚とびらのもんを描いた象形文字。戸は、その左半部をとり、一枚とびらの入り口を描いたもので、かってに出入りしないようにふせぐとびら。
《単語家族》
護(中にはいらぬようふせぐ) 禦ギョ(ふせぐ)などと同系。
《類義》
→門
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
禦ギョ(ふせぐ)などと同系。
《類義》
→門
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
砥 と🔗⭐🔉
【砥】
 10画 石部
区点=3754 16進=4556 シフトJIS=9375
《音読み》 シ
10画 石部
区点=3754 16進=4556 シフトJIS=9375
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh ・d
・d 〉
《訓読み》 と/といし/とぐ
《意味》
〉
《訓読み》 と/といし/とぐ
《意味》
 {名}と。といし。刃物をとぐための、きめのこまかな平らな石。あおと。〈類義語〉→礪レイ。「砥石シセキ」「剣待砥而後能利=剣ハ砥ヲ待チテノチヨク利ナリ」〔→淮南子〕「周道如砥、其直如矢=周道ハ砥ノゴトク、ソノ直ナルコト矢ノゴトシ」〔→詩経〕
{名}と。といし。刃物をとぐための、きめのこまかな平らな石。あおと。〈類義語〉→礪レイ。「砥石シセキ」「剣待砥而後能利=剣ハ砥ヲ待チテノチヨク利ナリ」〔→淮南子〕「周道如砥、其直如矢=周道ハ砥ノゴトク、ソノ直ナルコト矢ノゴトシ」〔→詩経〕
 {動・形}平らにする。平らにならす。また、平らで高低がない。「砥平シヘイ」
{動・形}平らにする。平らにならす。また、平らで高低がない。「砥平シヘイ」
 {動}とぐ。刃物をとぐ。刃物をみがく。「砥礪シレイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テイ)は、ひくい、平らの意を含む。砥はそれを音符とし、石を加えた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}とぐ。刃物をとぐ。刃物をみがく。「砥礪シレイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テイ)は、ひくい、平らの意を含む。砥はそれを音符とし、石を加えた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 石部
区点=3754 16進=4556 シフトJIS=9375
《音読み》 シ
10画 石部
区点=3754 16進=4556 シフトJIS=9375
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh ・d
・d 〉
《訓読み》 と/といし/とぐ
《意味》
〉
《訓読み》 と/といし/とぐ
《意味》
 {名}と。といし。刃物をとぐための、きめのこまかな平らな石。あおと。〈類義語〉→礪レイ。「砥石シセキ」「剣待砥而後能利=剣ハ砥ヲ待チテノチヨク利ナリ」〔→淮南子〕「周道如砥、其直如矢=周道ハ砥ノゴトク、ソノ直ナルコト矢ノゴトシ」〔→詩経〕
{名}と。といし。刃物をとぐための、きめのこまかな平らな石。あおと。〈類義語〉→礪レイ。「砥石シセキ」「剣待砥而後能利=剣ハ砥ヲ待チテノチヨク利ナリ」〔→淮南子〕「周道如砥、其直如矢=周道ハ砥ノゴトク、ソノ直ナルコト矢ノゴトシ」〔→詩経〕
 {動・形}平らにする。平らにならす。また、平らで高低がない。「砥平シヘイ」
{動・形}平らにする。平らにならす。また、平らで高低がない。「砥平シヘイ」
 {動}とぐ。刃物をとぐ。刃物をみがく。「砥礪シレイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テイ)は、ひくい、平らの意を含む。砥はそれを音符とし、石を加えた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}とぐ。刃物をとぐ。刃物をみがく。「砥礪シレイ」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テイ)は、ひくい、平らの意を含む。砥はそれを音符とし、石を加えた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
都 と🔗⭐🔉
【都】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 邑部 [三年]
区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373
《常用音訓》ツ/ト/みやこ
《音読み》 ト
11画 邑部 [三年]
区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373
《常用音訓》ツ/ト/みやこ
《音読み》 ト /ツ
/ツ 〈d
〈d ・d
・d u〉
《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と
《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ
《意味》
u〉
《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と
《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ
《意味》
 {名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕
{名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕
 {動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」
{動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」
 トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕
トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕
 {動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」
{動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」
 {副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd
{副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕
uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕
 {感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕
〔国〕と。東京都のこと。「都立」
《解字》
会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。
《単語家族》
睹ト(視線をあつめる)
{感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕
〔国〕と。東京都のこと。「都立」
《解字》
会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。
《単語家族》
睹ト(視線をあつめる) 堵ト(土をあつめてふさいだへい)
堵ト(土をあつめてふさいだへい) 貯チョ(あつめる)などと同系。
《類義》
市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
貯チョ(あつめる)などと同系。
《類義》
市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 邑部 [三年]
区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373
《常用音訓》ツ/ト/みやこ
《音読み》 ト
11画 邑部 [三年]
区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373
《常用音訓》ツ/ト/みやこ
《音読み》 ト /ツ
/ツ 〈d
〈d ・d
・d u〉
《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と
《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ
《意味》
u〉
《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と
《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ
《意味》
 {名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕
{名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕
 {動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」
{動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」
 トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕
トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕
 {動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」
{動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」
 {副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd
{副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕
uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕
 {感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕
〔国〕と。東京都のこと。「都立」
《解字》
会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。
《単語家族》
睹ト(視線をあつめる)
{感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕
〔国〕と。東京都のこと。「都立」
《解字》
会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。
《単語家族》
睹ト(視線をあつめる) 堵ト(土をあつめてふさいだへい)
堵ト(土をあつめてふさいだへい) 貯チョ(あつめる)などと同系。
《類義》
市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
貯チョ(あつめる)などと同系。
《類義》
市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
漢字源に「と」で完全一致するの検索結果 1-6。