複数辞典一括検索+![]()
![]()
下学上達 カガクジョウタツ🔗⭐🔉
【下学上達】
カガクジョウタツ〈故事〉手近なところから学んで、しだいに深い学問・道理に通ずること。〔→論語〕
下学集 カガクシュウ🔗⭐🔉
【下学集】
カガクシュウ〔日〕〈書物〉上下二巻。意味分類体の漢和辞典。著者未詳。1444年に成立。約三万の漢字および漢語を、天地・時節・神祇ジンギ・人倫など一八部門に分類し、片かなで読みを、漢文で意味をつけている。部門名と配列は、韻書として当時広く使われた『聚分韻略シュウブンインリャク』によっている。江戸時代には広く一般に用いられた。
価額 カガク🔗⭐🔉
【価額】
カガク『価格カカク』品物の値段に相当する金額。値段。
僂 かがめる🔗⭐🔉
光 かがやかす🔗⭐🔉
【光】
 6画 儿部 [二年]
区点=2487 16進=3877 シフトJIS=8CF5
《常用音訓》コウ/ひかり/ひか…る
《音読み》 コウ(ク
6画 儿部 [二年]
区点=2487 16進=3877 シフトJIS=8CF5
《常用音訓》コウ/ひかり/ひか…る
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ)
 〈gu
〈gu ng〉
《訓読み》 ひかる/ひかり/かがやく/かがやかす
《名付け》 あき・あきら・あり・かぬ・かね・さかえ・てる・ひかり・ひかる・ひこ・ひろ・ひろし・みつ・みつる
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひかる/ひかり/かがやく/かがやかす
《名付け》 あき・あきら・あり・かぬ・かね・さかえ・てる・ひかり・ひかる・ひこ・ひろ・ひろし・みつ・みつる
《意味》
 {動・名}ひかる。ひかり。明るくかがやく。また、明るくかがやくひかり。「光明」「髣髴若有光=髣髴トシテ光有ルガ若シ」〔→陶潜〕
{動・名}ひかる。ひかり。明るくかがやく。また、明るくかがやくひかり。「光明」「髣髴若有光=髣髴トシテ光有ルガ若シ」〔→陶潜〕
 {名}ひかり。外に照りはえるかがやき。目だつ才能や名声。「光彰」「和其光同其塵=其ノ光ヲ和ラゲ其ノ塵ニ同ジクス」〔→老子〕
{名}ひかり。外に照りはえるかがやき。目だつ才能や名声。「光彰」「和其光同其塵=其ノ光ヲ和ラゲ其ノ塵ニ同ジクス」〔→老子〕
 {動}かがやく。かがやかす。光を発散させる。みがきをかけて浮きだたせる。「以光先帝遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ光カス」〔→諸葛亮〕
{動}かがやく。かがやかす。光を発散させる。みがきをかけて浮きだたせる。「以光先帝遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ光カス」〔→諸葛亮〕
 {形}相手の行為を光栄とする意を添えることば。「光来」「光臨(おいでいただく)」
{形}相手の行為を光栄とする意を添えることば。「光来」「光臨(おいでいただく)」
 {名}つや。「光沢」
{名}つや。「光沢」
 {名}けしき。「風光」
{名}けしき。「風光」
 {形}〔俗〕発散し尽くす意から、全部尽き果てるさま。「用光(用い尽くす)」
《解字》
{形}〔俗〕発散し尽くす意から、全部尽き果てるさま。「用光(用い尽くす)」
《解字》
 会意。人が頭上に火を載せた姿を示す。四方に発散するの意を含む。
《単語家族》
晃コウ(ひかり)
会意。人が頭上に火を載せた姿を示す。四方に発散するの意を含む。
《単語家族》
晃コウ(ひかり) 煌コウ(ひかりが四方にかがやく)
煌コウ(ひかりが四方にかがやく) 黄(ほのおのひかり→きいろい)と同系。また、広・横(ひろがる)・往(どんどん進む)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
黄(ほのおのひかり→きいろい)と同系。また、広・横(ひろがる)・往(どんどん進む)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 6画 儿部 [二年]
区点=2487 16進=3877 シフトJIS=8CF5
《常用音訓》コウ/ひかり/ひか…る
《音読み》 コウ(ク
6画 儿部 [二年]
区点=2487 16進=3877 シフトJIS=8CF5
《常用音訓》コウ/ひかり/ひか…る
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ)
 〈gu
〈gu ng〉
《訓読み》 ひかる/ひかり/かがやく/かがやかす
《名付け》 あき・あきら・あり・かぬ・かね・さかえ・てる・ひかり・ひかる・ひこ・ひろ・ひろし・みつ・みつる
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひかる/ひかり/かがやく/かがやかす
《名付け》 あき・あきら・あり・かぬ・かね・さかえ・てる・ひかり・ひかる・ひこ・ひろ・ひろし・みつ・みつる
《意味》
 {動・名}ひかる。ひかり。明るくかがやく。また、明るくかがやくひかり。「光明」「髣髴若有光=髣髴トシテ光有ルガ若シ」〔→陶潜〕
{動・名}ひかる。ひかり。明るくかがやく。また、明るくかがやくひかり。「光明」「髣髴若有光=髣髴トシテ光有ルガ若シ」〔→陶潜〕
 {名}ひかり。外に照りはえるかがやき。目だつ才能や名声。「光彰」「和其光同其塵=其ノ光ヲ和ラゲ其ノ塵ニ同ジクス」〔→老子〕
{名}ひかり。外に照りはえるかがやき。目だつ才能や名声。「光彰」「和其光同其塵=其ノ光ヲ和ラゲ其ノ塵ニ同ジクス」〔→老子〕
 {動}かがやく。かがやかす。光を発散させる。みがきをかけて浮きだたせる。「以光先帝遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ光カス」〔→諸葛亮〕
{動}かがやく。かがやかす。光を発散させる。みがきをかけて浮きだたせる。「以光先帝遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ光カス」〔→諸葛亮〕
 {形}相手の行為を光栄とする意を添えることば。「光来」「光臨(おいでいただく)」
{形}相手の行為を光栄とする意を添えることば。「光来」「光臨(おいでいただく)」
 {名}つや。「光沢」
{名}つや。「光沢」
 {名}けしき。「風光」
{名}けしき。「風光」
 {形}〔俗〕発散し尽くす意から、全部尽き果てるさま。「用光(用い尽くす)」
《解字》
{形}〔俗〕発散し尽くす意から、全部尽き果てるさま。「用光(用い尽くす)」
《解字》
 会意。人が頭上に火を載せた姿を示す。四方に発散するの意を含む。
《単語家族》
晃コウ(ひかり)
会意。人が頭上に火を載せた姿を示す。四方に発散するの意を含む。
《単語家族》
晃コウ(ひかり) 煌コウ(ひかりが四方にかがやく)
煌コウ(ひかりが四方にかがやく) 黄(ほのおのひかり→きいろい)と同系。また、広・横(ひろがる)・往(どんどん進む)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
黄(ほのおのひかり→きいろい)と同系。また、広・横(ひろがる)・往(どんどん進む)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
化外 カガイ🔗⭐🔉
【化外】
カガイ 天子の政治・教化などの影響力の及ばない地域。中国文化圏の外。
夸娥 カガ🔗⭐🔉
【夸娥】
コガ・カガ〈人名〉古代、伝説上の仙人センニン。愚公が太行・王屋の二山を移そうとしたとき、天帝の命でその二子が山を移したという。→「愚公移山グコウヤマヲウツス」
宛 かがむ🔗⭐🔉
【宛】
 8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン(
8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン( ン)
ン) /オン(ヲン)
/オン(ヲン) 〈yu
〈yu n・w
n・w n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
 {動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
 エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
 {副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
 「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕
「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕 あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」
あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」 ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
 会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる)
会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる) 円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン(
8画 宀部
区点=1624 16進=3038 シフトJIS=88B6
《音読み》 エン( ン)
ン) /オン(ヲン)
/オン(ヲン) 〈yu
〈yu n・w
n・w n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
n〉
《訓読み》 まがる/かがむ/あたかも/あて/ずつ(づつ)
《意味》
 {動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
{動}まがる。かがむ。からだや姿をくねらせる。〈同義語〉→婉エン。「宛転エンテン」
 エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
エンタリ{形}くねくねとまがったさま。「宛曲エンキョク(相手に逆らわず、相手にあわせて調子をまげること)」「一水宛秋蛇=一水ハ宛トシテ秋蛇」〔→王安石〕
 {副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
{副}あたかも。原物のとおりに姿がまがっているの意から、まるで本物そっくりで、非常によく似ていることをあらわすことば。さながら。「宛如〜(あたかも〜のごとし)」「宛然エンゼン」
 「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕
「大宛ダイエン」とは、漢代、天山山脈中のフェルガナ地方にあった国の名。西域の代表国とみなされ、良馬の産出地として知られた。
〔国〕 あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」
あて。名ざし。また割り当て。「宛名アテナ」 ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
ずつ(ヅツ)。割り当て。「三つ宛」
《解字》
 会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる)
会意兼形声。下部の字(音エン)は、人がまるくからだをくねらせたさま。宛はそれを音符とし、宀(やね)を加えた字で、おおいの下でからだをまるくかがめることを示す。
《単語家族》
婉エン(女がからだをくねらせる) 円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
円(まるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
家学 カガク🔗⭐🔉
【家学】
カガク その家に代々伝わる学問。
屈 かがむ🔗⭐🔉
【屈】
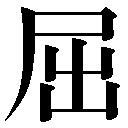 8画 尸部 [常用漢字]
区点=2294 16進=367E シフトJIS=8BFC
《常用音訓》クツ
《音読み》 クツ
8画 尸部 [常用漢字]
区点=2294 16進=367E シフトJIS=8BFC
《常用音訓》クツ
《音読み》 クツ /クチ
/クチ 〈q
〈q 〉
《訓読み》 かがむ/まげる(まぐ)
《意味》
〉
《訓読み》 かがむ/まげる(まぐ)
《意味》
 クッス{動}かがむ。まがってくぼむ。へこむ。〈対語〉→伸シン・→信(のびる)。「尺蠖之屈以求信也=尺蠖ノ屈スルハ、モッテ信ビンコトヲ求ムルナリ」〔→易経〕
クッス{動}かがむ。まがってくぼむ。へこむ。〈対語〉→伸シン・→信(のびる)。「尺蠖之屈以求信也=尺蠖ノ屈スルハ、モッテ信ビンコトヲ求ムルナリ」〔→易経〕
 クッス{動}まげる(マグ)。押さえてまげる。また、やりこめる。また、主義・主張をむりに押さえてかえる。「屈節=節ヲ屈グ」「常屈其座人=常ニソノ座人ヲ屈ス」〔→韓愈〕
クッス{動}まげる(マグ)。押さえてまげる。また、やりこめる。また、主義・主張をむりに押さえてかえる。「屈節=節ヲ屈グ」「常屈其座人=常ニソノ座人ヲ屈ス」〔→韓愈〕
 {形}ずんぐりとしてごつい。〈同義語〉→倔。「屈強(=倔強)」
《解字》
{形}ずんぐりとしてごつい。〈同義語〉→倔。「屈強(=倔強)」
《解字》
 会意。「尸(しり)+出」で、からだをまげてしりを後ろに突き出すことを示す。しりを出せばからだ全体はくぼんでまがることから、かがんで小さくなる、の意となる。出を音符と考える説もあるが従いがたい。
《単語家族》
掘クツ(穴をほってくぼみをつくる)
会意。「尸(しり)+出」で、からだをまげてしりを後ろに突き出すことを示す。しりを出せばからだ全体はくぼんでまがることから、かがんで小さくなる、の意となる。出を音符と考える説もあるが従いがたい。
《単語家族》
掘クツ(穴をほってくぼみをつくる) 窟クツ(くぼんだ穴)
窟クツ(くぼんだ穴) 堀(くぼんだほり)などと同系。
《類義》
→曲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堀(くぼんだほり)などと同系。
《類義》
→曲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
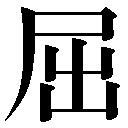 8画 尸部 [常用漢字]
区点=2294 16進=367E シフトJIS=8BFC
《常用音訓》クツ
《音読み》 クツ
8画 尸部 [常用漢字]
区点=2294 16進=367E シフトJIS=8BFC
《常用音訓》クツ
《音読み》 クツ /クチ
/クチ 〈q
〈q 〉
《訓読み》 かがむ/まげる(まぐ)
《意味》
〉
《訓読み》 かがむ/まげる(まぐ)
《意味》
 クッス{動}かがむ。まがってくぼむ。へこむ。〈対語〉→伸シン・→信(のびる)。「尺蠖之屈以求信也=尺蠖ノ屈スルハ、モッテ信ビンコトヲ求ムルナリ」〔→易経〕
クッス{動}かがむ。まがってくぼむ。へこむ。〈対語〉→伸シン・→信(のびる)。「尺蠖之屈以求信也=尺蠖ノ屈スルハ、モッテ信ビンコトヲ求ムルナリ」〔→易経〕
 クッス{動}まげる(マグ)。押さえてまげる。また、やりこめる。また、主義・主張をむりに押さえてかえる。「屈節=節ヲ屈グ」「常屈其座人=常ニソノ座人ヲ屈ス」〔→韓愈〕
クッス{動}まげる(マグ)。押さえてまげる。また、やりこめる。また、主義・主張をむりに押さえてかえる。「屈節=節ヲ屈グ」「常屈其座人=常ニソノ座人ヲ屈ス」〔→韓愈〕
 {形}ずんぐりとしてごつい。〈同義語〉→倔。「屈強(=倔強)」
《解字》
{形}ずんぐりとしてごつい。〈同義語〉→倔。「屈強(=倔強)」
《解字》
 会意。「尸(しり)+出」で、からだをまげてしりを後ろに突き出すことを示す。しりを出せばからだ全体はくぼんでまがることから、かがんで小さくなる、の意となる。出を音符と考える説もあるが従いがたい。
《単語家族》
掘クツ(穴をほってくぼみをつくる)
会意。「尸(しり)+出」で、からだをまげてしりを後ろに突き出すことを示す。しりを出せばからだ全体はくぼんでまがることから、かがんで小さくなる、の意となる。出を音符と考える説もあるが従いがたい。
《単語家族》
掘クツ(穴をほってくぼみをつくる) 窟クツ(くぼんだ穴)
窟クツ(くぼんだ穴) 堀(くぼんだほり)などと同系。
《類義》
→曲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堀(くぼんだほり)などと同系。
《類義》
→曲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
暉 かがやく🔗⭐🔉
【暉】
 13画 日部 [人名漢字]
区点=5886 16進=5A76 シフトJIS=9DF4
《音読み》 キ(ク
13画 日部 [人名漢字]
区点=5886 16進=5A76 シフトJIS=9DF4
《音読み》 キ(ク )
)
 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 ひかり/かがやく
《名付け》 あき・あきら・てらす・てる
《意味》
〉
《訓読み》 ひかり/かがやく
《名付け》 あき・あきら・てらす・てる
《意味》
 {名}ひかり。四方に広がるひかり。〈同義語〉→輝。「春暉シュンキ(春の日の輝き。転じて、子をはぐくむ父母の恩)」「報得三春暉=三春ノ暉ニ報ジ得ン」〔→孟郊〕
{名}ひかり。四方に広がるひかり。〈同義語〉→輝。「春暉シュンキ(春の日の輝き。転じて、子をはぐくむ父母の恩)」「報得三春暉=三春ノ暉ニ報ジ得ン」〔→孟郊〕
 {動}かがやく。まるくひかりが広がる。〈同義語〉→輝。「暉暉キキ」
《解字》
会意兼形声。「日+音符軍」。軍は、まるく取り巻く意を含む。暉は、光源からまるく輪をなして四方に広がるひかり。▽暈ウン(太陽のかさ)は、別字。
《単語家族》
揮(まるく円を描いて手を振る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かがやく。まるくひかりが広がる。〈同義語〉→輝。「暉暉キキ」
《解字》
会意兼形声。「日+音符軍」。軍は、まるく取り巻く意を含む。暉は、光源からまるく輪をなして四方に広がるひかり。▽暈ウン(太陽のかさ)は、別字。
《単語家族》
揮(まるく円を描いて手を振る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 日部 [人名漢字]
区点=5886 16進=5A76 シフトJIS=9DF4
《音読み》 キ(ク
13画 日部 [人名漢字]
区点=5886 16進=5A76 シフトJIS=9DF4
《音読み》 キ(ク )
)
 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 ひかり/かがやく
《名付け》 あき・あきら・てらす・てる
《意味》
〉
《訓読み》 ひかり/かがやく
《名付け》 あき・あきら・てらす・てる
《意味》
 {名}ひかり。四方に広がるひかり。〈同義語〉→輝。「春暉シュンキ(春の日の輝き。転じて、子をはぐくむ父母の恩)」「報得三春暉=三春ノ暉ニ報ジ得ン」〔→孟郊〕
{名}ひかり。四方に広がるひかり。〈同義語〉→輝。「春暉シュンキ(春の日の輝き。転じて、子をはぐくむ父母の恩)」「報得三春暉=三春ノ暉ニ報ジ得ン」〔→孟郊〕
 {動}かがやく。まるくひかりが広がる。〈同義語〉→輝。「暉暉キキ」
《解字》
会意兼形声。「日+音符軍」。軍は、まるく取り巻く意を含む。暉は、光源からまるく輪をなして四方に広がるひかり。▽暈ウン(太陽のかさ)は、別字。
《単語家族》
揮(まるく円を描いて手を振る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かがやく。まるくひかりが広がる。〈同義語〉→輝。「暉暉キキ」
《解字》
会意兼形声。「日+音符軍」。軍は、まるく取り巻く意を含む。暉は、光源からまるく輪をなして四方に広がるひかり。▽暈ウン(太陽のかさ)は、別字。
《単語家族》
揮(まるく円を描いて手を振る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
曄 かがやく🔗⭐🔉
【曄】
 14画 日部
区点=5901 16進=5B21 シフトJIS=9E40
《音読み》 ヨウ(エフ)
14画 日部
区点=5901 16進=5B21 シフトJIS=9E40
《音読み》 ヨウ(エフ)
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。赤々と燃えたつ。はなやかにかがやく。また、そのさま。「曄曄ヨウヨウ(赤々とかがやくさま)」
《解字》
会意。「日+華(はなやか)」。はなやかにかがやくこと。炎はその語尾が転じた語で曄と同系。また「白+華」の字でも書きあらわす。
〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。赤々と燃えたつ。はなやかにかがやく。また、そのさま。「曄曄ヨウヨウ(赤々とかがやくさま)」
《解字》
会意。「日+華(はなやか)」。はなやかにかがやくこと。炎はその語尾が転じた語で曄と同系。また「白+華」の字でも書きあらわす。
 14画 日部
区点=5901 16進=5B21 シフトJIS=9E40
《音読み》 ヨウ(エフ)
14画 日部
区点=5901 16進=5B21 シフトJIS=9E40
《音読み》 ヨウ(エフ)
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。赤々と燃えたつ。はなやかにかがやく。また、そのさま。「曄曄ヨウヨウ(赤々とかがやくさま)」
《解字》
会意。「日+華(はなやか)」。はなやかにかがやくこと。炎はその語尾が転じた語で曄と同系。また「白+華」の字でも書きあらわす。
〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。赤々と燃えたつ。はなやかにかがやく。また、そのさま。「曄曄ヨウヨウ(赤々とかがやくさま)」
《解字》
会意。「日+華(はなやか)」。はなやかにかがやくこと。炎はその語尾が転じた語で曄と同系。また「白+華」の字でも書きあらわす。
曜 かがやく🔗⭐🔉
【曜】
 18画 日部 [二年]
区点=4543 16進=4D4B シフトJIS=976A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(エウ)
18画 日部 [二年]
区点=4543 16進=4D4B シフトJIS=976A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 あきら・てらす・てる
《意味》
o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 あきら・てらす・てる
《意味》
 {動}かがやく。光が高く目だってかがやく。てかてかと光る。〈同義語〉→耀・→燿。〈類義語〉→灼シャク。
{動}かがやく。光が高く目だってかがやく。てかてかと光る。〈同義語〉→耀・→燿。〈類義語〉→灼シャク。
 {名}ひかり。目だってかがやくひかり。「日星隠曜=日星曜ヲ隠ス」〔→范仲淹〕
{名}ひかり。目だってかがやくひかり。「日星隠曜=日星曜ヲ隠ス」〔→范仲淹〕
 {名}日・月と火・水・木・金・土の星を七曜という。かがやく天体のこと。「七曜為之盈縮=七曜コレガ為ニ盈縮ス」
{名}日・月と火・水・木・金・土の星を七曜という。かがやく天体のこと。「七曜為之盈縮=七曜コレガ為ニ盈縮ス」
 {名}一週間を七曜に当てはめ、日曜・月曜などという。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、きじが高く目だって尾羽をたてること。擢テキ(高くぬき出す)
{名}一週間を七曜に当てはめ、日曜・月曜などという。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、きじが高く目だって尾羽をたてること。擢テキ(高くぬき出す) 躍(高くあがる)と同系。曜はそれを音符とし、日を加えた字で、光が目だって高くかがやくこと。掉トウ・チョウ(ぬき出す)や的(高く目だつまと)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
躍(高くあがる)と同系。曜はそれを音符とし、日を加えた字で、光が目だって高くかがやくこと。掉トウ・チョウ(ぬき出す)や的(高く目だつまと)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 18画 日部 [二年]
区点=4543 16進=4D4B シフトJIS=976A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(エウ)
18画 日部 [二年]
区点=4543 16進=4D4B シフトJIS=976A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 あきら・てらす・てる
《意味》
o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 あきら・てらす・てる
《意味》
 {動}かがやく。光が高く目だってかがやく。てかてかと光る。〈同義語〉→耀・→燿。〈類義語〉→灼シャク。
{動}かがやく。光が高く目だってかがやく。てかてかと光る。〈同義語〉→耀・→燿。〈類義語〉→灼シャク。
 {名}ひかり。目だってかがやくひかり。「日星隠曜=日星曜ヲ隠ス」〔→范仲淹〕
{名}ひかり。目だってかがやくひかり。「日星隠曜=日星曜ヲ隠ス」〔→范仲淹〕
 {名}日・月と火・水・木・金・土の星を七曜という。かがやく天体のこと。「七曜為之盈縮=七曜コレガ為ニ盈縮ス」
{名}日・月と火・水・木・金・土の星を七曜という。かがやく天体のこと。「七曜為之盈縮=七曜コレガ為ニ盈縮ス」
 {名}一週間を七曜に当てはめ、日曜・月曜などという。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、きじが高く目だって尾羽をたてること。擢テキ(高くぬき出す)
{名}一週間を七曜に当てはめ、日曜・月曜などという。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、きじが高く目だって尾羽をたてること。擢テキ(高くぬき出す) 躍(高くあがる)と同系。曜はそれを音符とし、日を加えた字で、光が目だって高くかがやくこと。掉トウ・チョウ(ぬき出す)や的(高く目だつまと)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
躍(高くあがる)と同系。曜はそれを音符とし、日を加えた字で、光が目だって高くかがやくこと。掉トウ・チョウ(ぬき出す)や的(高く目だつまと)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
歌楽 カガク🔗⭐🔉
【歌楽】
 カガク 歌謡と音楽。
カガク 歌謡と音楽。 カラク
カラク  歌をうたって楽しむこと。
歌をうたって楽しむこと。 詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
 カガク 歌謡と音楽。
カガク 歌謡と音楽。 カラク
カラク  歌をうたって楽しむこと。
歌をうたって楽しむこと。 詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
河岸 カガン🔗⭐🔉
【河岸】
 カガン 川岸。
カガン 川岸。 カシ〔国〕
カシ〔国〕 舟から人や荷物をあげる川岸。
舟から人や荷物をあげる川岸。 魚市場。魚河岸ウオガシ。
魚市場。魚河岸ウオガシ。
 カガン 川岸。
カガン 川岸。 カシ〔国〕
カシ〔国〕 舟から人や荷物をあげる川岸。
舟から人や荷物をあげる川岸。 魚市場。魚河岸ウオガシ。
魚市場。魚河岸ウオガシ。
炬 かがり🔗⭐🔉
【炬】
 9画 火部
区点=6357 16進=5F59 シフトJIS=E078
《音読み》 キョ
9画 火部
区点=6357 16進=5F59 シフトJIS=E078
《音読み》 キョ /コ
/コ /ゴ
/ゴ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 かがり/かがりび
《意味》
{名}かがり。かがりび。たいまつ。細い枝やあしを束ねてその先に油をぬり、火をつける。〈同義語〉→苣。「炬火キョカ」「蝋炬ロウキョ(ろうそく)」「挙炬=炬ヲ挙グ」
《解字》
会意兼形声。巨キョは、工印のものさしにコ型の手で持つ所のついた形を描いた象形文字。上の一線と下の一線とがへだたっている。距離の距(間がへだたる)と同系のことば。炬は「火+音符巨」で、長い束の先端に火をつけてもやし、ずっとへだたった下方を手に持つたいまつ。
《単語家族》
巨(間をへだてる→大きい)
〉
《訓読み》 かがり/かがりび
《意味》
{名}かがり。かがりび。たいまつ。細い枝やあしを束ねてその先に油をぬり、火をつける。〈同義語〉→苣。「炬火キョカ」「蝋炬ロウキョ(ろうそく)」「挙炬=炬ヲ挙グ」
《解字》
会意兼形声。巨キョは、工印のものさしにコ型の手で持つ所のついた形を描いた象形文字。上の一線と下の一線とがへだたっている。距離の距(間がへだたる)と同系のことば。炬は「火+音符巨」で、長い束の先端に火をつけてもやし、ずっとへだたった下方を手に持つたいまつ。
《単語家族》
巨(間をへだてる→大きい) 拒(間をへだてる→近づけない)
拒(間をへだてる→近づけない) 距(へだたる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
距(へだたる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 火部
区点=6357 16進=5F59 シフトJIS=E078
《音読み》 キョ
9画 火部
区点=6357 16進=5F59 シフトJIS=E078
《音読み》 キョ /コ
/コ /ゴ
/ゴ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 かがり/かがりび
《意味》
{名}かがり。かがりび。たいまつ。細い枝やあしを束ねてその先に油をぬり、火をつける。〈同義語〉→苣。「炬火キョカ」「蝋炬ロウキョ(ろうそく)」「挙炬=炬ヲ挙グ」
《解字》
会意兼形声。巨キョは、工印のものさしにコ型の手で持つ所のついた形を描いた象形文字。上の一線と下の一線とがへだたっている。距離の距(間がへだたる)と同系のことば。炬は「火+音符巨」で、長い束の先端に火をつけてもやし、ずっとへだたった下方を手に持つたいまつ。
《単語家族》
巨(間をへだてる→大きい)
〉
《訓読み》 かがり/かがりび
《意味》
{名}かがり。かがりび。たいまつ。細い枝やあしを束ねてその先に油をぬり、火をつける。〈同義語〉→苣。「炬火キョカ」「蝋炬ロウキョ(ろうそく)」「挙炬=炬ヲ挙グ」
《解字》
会意兼形声。巨キョは、工印のものさしにコ型の手で持つ所のついた形を描いた象形文字。上の一線と下の一線とがへだたっている。距離の距(間がへだたる)と同系のことば。炬は「火+音符巨」で、長い束の先端に火をつけてもやし、ずっとへだたった下方を手に持つたいまつ。
《単語家族》
巨(間をへだてる→大きい) 拒(間をへだてる→近づけない)
拒(間をへだてる→近づけない) 距(へだたる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
距(へだたる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
焜 かがやく🔗⭐🔉
煌 かがやく🔗⭐🔉
【煌】
 13画 火部
区点=6374 16進=5F6A シフトJIS=E08A
《音読み》 コウ(ク
13画 火部
区点=6374 16進=5F6A シフトJIS=E08A
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。光が四方に大きく広がる。明るいさま。〈類義語〉→晃コウ。「煌煌コウコウ」
《解字》
会意兼形声。皇は「自(はな)+音符王」からなり、偉大な鼻祖(開祖)のこと。大きく広がるの意を含む。煌は「火+音符皇」で、光が大きく広がること。
《単語家族》
晃コウ(光が広く発散する)
ng〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。光が四方に大きく広がる。明るいさま。〈類義語〉→晃コウ。「煌煌コウコウ」
《解字》
会意兼形声。皇は「自(はな)+音符王」からなり、偉大な鼻祖(開祖)のこと。大きく広がるの意を含む。煌は「火+音符皇」で、光が大きく広がること。
《単語家族》
晃コウ(光が広く発散する) 徨コウ(四方に広がっていく)などと同系。また光(四方に広がるひかり)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
徨コウ(四方に広がっていく)などと同系。また光(四方に広がるひかり)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 火部
区点=6374 16進=5F6A シフトJIS=E08A
《音読み》 コウ(ク
13画 火部
区点=6374 16進=5F6A シフトJIS=E08A
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。光が四方に大きく広がる。明るいさま。〈類義語〉→晃コウ。「煌煌コウコウ」
《解字》
会意兼形声。皇は「自(はな)+音符王」からなり、偉大な鼻祖(開祖)のこと。大きく広がるの意を含む。煌は「火+音符皇」で、光が大きく広がること。
《単語家族》
晃コウ(光が広く発散する)
ng〉
《訓読み》 かがやく/あきらか(あきらかなり)
《意味》
{動・形}かがやく。あきらか(アキラカナリ)。光が四方に大きく広がる。明るいさま。〈類義語〉→晃コウ。「煌煌コウコウ」
《解字》
会意兼形声。皇は「自(はな)+音符王」からなり、偉大な鼻祖(開祖)のこと。大きく広がるの意を含む。煌は「火+音符皇」で、光が大きく広がること。
《単語家族》
晃コウ(光が広く発散する) 徨コウ(四方に広がっていく)などと同系。また光(四方に広がるひかり)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
徨コウ(四方に広がっていく)などと同系。また光(四方に広がるひかり)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
燎 かがりび🔗⭐🔉
【燎】
 16画 火部 [人名漢字]
区点=6389 16進=5F79 シフトJIS=E099
《音読み》 リョウ(レウ)
16画 火部 [人名漢字]
区点=6389 16進=5F79 シフトJIS=E099
《音読み》 リョウ(レウ)
 〈li
〈li o・li
o・li o〉
《訓読み》 かがりび/にわび(にはび)/やく/あぶる
《意味》
o〉
《訓読み》 かがりび/にわび(にはび)/やく/あぶる
《意味》
 {名}かがりび。にわび(ニハビ)。たえまなくたくかがりび。ずるずると続いて燃える火。「庭燎テイリョウ」
{名}かがりび。にわび(ニハビ)。たえまなくたくかがりび。ずるずると続いて燃える火。「庭燎テイリョウ」
 リョウス{動}やく。たえまなくもえる。また、もえひろがる。延焼する。「火、燎眉毛=火、眉毛ヲ燎ク」「若火之燎于原=火ノ原ヲ燎スルガゴトシ」〔→書経〕
リョウス{動}やく。たえまなくもえる。また、もえひろがる。延焼する。「火、燎眉毛=火、眉毛ヲ燎ク」「若火之燎于原=火ノ原ヲ燎スルガゴトシ」〔→書経〕
 リョウタリ{形}かがりびをたいたように明るいさま。また、明るく美しいさま。「佼人燎兮=佼人燎タリ」〔→詩経〕
リョウタリ{形}かがりびをたいたように明るいさま。また、明るく美しいさま。「佼人燎兮=佼人燎タリ」〔→詩経〕
 リョウス{動}あぶる。火であたためる。「光武、対竃燎衣=光武、竃ニ対シテ衣ヲ燎ス」〔→後漢書〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、柴シバや骨をやぐらの形に組み、下から火でもやすさま。かがりびを意味する燎の原字。燎はそれを音符とし、火を加えた字で、ずるずるつづいて燃える意味を含む。▽また、かがりびの明るいことから、瞭(明るい)・寮(まど)などの意に当てて用いる。
《単語家族》
繚(まといついて、ずるずるつづく)
リョウス{動}あぶる。火であたためる。「光武、対竃燎衣=光武、竃ニ対シテ衣ヲ燎ス」〔→後漢書〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、柴シバや骨をやぐらの形に組み、下から火でもやすさま。かがりびを意味する燎の原字。燎はそれを音符とし、火を加えた字で、ずるずるつづいて燃える意味を含む。▽また、かがりびの明るいことから、瞭(明るい)・寮(まど)などの意に当てて用いる。
《単語家族》
繚(まといついて、ずるずるつづく) 僚(列をなす仲間)と同系。
《類義》
→焚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
僚(列をなす仲間)と同系。
《類義》
→焚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 16画 火部 [人名漢字]
区点=6389 16進=5F79 シフトJIS=E099
《音読み》 リョウ(レウ)
16画 火部 [人名漢字]
区点=6389 16進=5F79 シフトJIS=E099
《音読み》 リョウ(レウ)
 〈li
〈li o・li
o・li o〉
《訓読み》 かがりび/にわび(にはび)/やく/あぶる
《意味》
o〉
《訓読み》 かがりび/にわび(にはび)/やく/あぶる
《意味》
 {名}かがりび。にわび(ニハビ)。たえまなくたくかがりび。ずるずると続いて燃える火。「庭燎テイリョウ」
{名}かがりび。にわび(ニハビ)。たえまなくたくかがりび。ずるずると続いて燃える火。「庭燎テイリョウ」
 リョウス{動}やく。たえまなくもえる。また、もえひろがる。延焼する。「火、燎眉毛=火、眉毛ヲ燎ク」「若火之燎于原=火ノ原ヲ燎スルガゴトシ」〔→書経〕
リョウス{動}やく。たえまなくもえる。また、もえひろがる。延焼する。「火、燎眉毛=火、眉毛ヲ燎ク」「若火之燎于原=火ノ原ヲ燎スルガゴトシ」〔→書経〕
 リョウタリ{形}かがりびをたいたように明るいさま。また、明るく美しいさま。「佼人燎兮=佼人燎タリ」〔→詩経〕
リョウタリ{形}かがりびをたいたように明るいさま。また、明るく美しいさま。「佼人燎兮=佼人燎タリ」〔→詩経〕
 リョウス{動}あぶる。火であたためる。「光武、対竃燎衣=光武、竃ニ対シテ衣ヲ燎ス」〔→後漢書〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、柴シバや骨をやぐらの形に組み、下から火でもやすさま。かがりびを意味する燎の原字。燎はそれを音符とし、火を加えた字で、ずるずるつづいて燃える意味を含む。▽また、かがりびの明るいことから、瞭(明るい)・寮(まど)などの意に当てて用いる。
《単語家族》
繚(まといついて、ずるずるつづく)
リョウス{動}あぶる。火であたためる。「光武、対竃燎衣=光武、竃ニ対シテ衣ヲ燎ス」〔→後漢書〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、柴シバや骨をやぐらの形に組み、下から火でもやすさま。かがりびを意味する燎の原字。燎はそれを音符とし、火を加えた字で、ずるずるつづいて燃える意味を含む。▽また、かがりびの明るいことから、瞭(明るい)・寮(まど)などの意に当てて用いる。
《単語家族》
繚(まといついて、ずるずるつづく) 僚(列をなす仲間)と同系。
《類義》
→焚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
僚(列をなす仲間)と同系。
《類義》
→焚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
燿 かがやく🔗⭐🔉
【燿】
 18画 火部 [人名漢字]
区点=6402 16進=6022 シフトJIS=E0A0
《音読み》 ヨウ(エウ)
18画 火部 [人名漢字]
区点=6402 16進=6022 シフトJIS=E0A0
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 てる
《意味》
o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 てる
《意味》
 {動}かがやく。火が高く燃えあがってかがやく。〈同義語〉→曜。
{動}かがやく。火が高く燃えあがってかがやく。〈同義語〉→曜。
 {名}ひかり。高くかがやく火のひかり。〈同義語〉→曜。「流曜リュウヨウ(水にうつって流れるように見えるひかり)」
{名}ひかり。高くかがやく火のひかり。〈同義語〉→曜。「流曜リュウヨウ(水にうつって流れるように見えるひかり)」
 「燿燿ヨウヨウ」とは、高く目だってかがやくさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)とは「羽+隹(鳥)」の会意文字で、きじが尾羽を目だつように高くかかげること。擢テキ(高く抜きあげる)の原字。燿はそれを音符とし、火を加えた字で、火のひかりが高く目だってかがやくこと。
《単語家族》
曜(日光が高くかがやく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「燿燿ヨウヨウ」とは、高く目だってかがやくさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)とは「羽+隹(鳥)」の会意文字で、きじが尾羽を目だつように高くかかげること。擢テキ(高く抜きあげる)の原字。燿はそれを音符とし、火を加えた字で、火のひかりが高く目だってかがやくこと。
《単語家族》
曜(日光が高くかがやく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 18画 火部 [人名漢字]
区点=6402 16進=6022 シフトJIS=E0A0
《音読み》 ヨウ(エウ)
18画 火部 [人名漢字]
区点=6402 16進=6022 シフトJIS=E0A0
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 てる
《意味》
o〉
《訓読み》 かがやく/ひかり
《名付け》 てる
《意味》
 {動}かがやく。火が高く燃えあがってかがやく。〈同義語〉→曜。
{動}かがやく。火が高く燃えあがってかがやく。〈同義語〉→曜。
 {名}ひかり。高くかがやく火のひかり。〈同義語〉→曜。「流曜リュウヨウ(水にうつって流れるように見えるひかり)」
{名}ひかり。高くかがやく火のひかり。〈同義語〉→曜。「流曜リュウヨウ(水にうつって流れるように見えるひかり)」
 「燿燿ヨウヨウ」とは、高く目だってかがやくさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)とは「羽+隹(鳥)」の会意文字で、きじが尾羽を目だつように高くかかげること。擢テキ(高く抜きあげる)の原字。燿はそれを音符とし、火を加えた字で、火のひかりが高く目だってかがやくこと。
《単語家族》
曜(日光が高くかがやく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「燿燿ヨウヨウ」とは、高く目だってかがやくさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)とは「羽+隹(鳥)」の会意文字で、きじが尾羽を目だつように高くかかげること。擢テキ(高く抜きあげる)の原字。燿はそれを音符とし、火を加えた字で、火のひかりが高く目だってかがやくこと。
《単語家族》
曜(日光が高くかがやく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
禍害 カガイ🔗⭐🔉
【禍災】
カサイ 思いがけない災難。『禍殃カオウ・禍害カガイ・禍患カカン』
科学 カガク🔗⭐🔉
【科学】
カガク  学問。
学問。 事物・現象について、系統だてて研究する学問。
事物・現象について、系統だてて研究する学問。 自然科学のこと。
自然科学のこと。
 学問。
学問。 事物・現象について、系統だてて研究する学問。
事物・現象について、系統だてて研究する学問。 自然科学のこと。
自然科学のこと。
篝 かがり🔗⭐🔉
耀 かがやかす🔗⭐🔉
花街柳巷 カガイリュウコウ🔗⭐🔉
【花街柳巷】
カガイリュウコウ 遊女などが集まっているはなやかな地域。遊里。
華顔 カガン🔗⭐🔉
【華顔】
カガン 花のように美しい顔。花のかんばせ。
輝 かがやかしい🔗⭐🔉
【輝】
 15画 車部 [常用漢字]
区点=2117 16進=3531 シフトJIS=8B50
《常用音訓》キ/かがや…く
《音読み》 キ(ク
15画 車部 [常用漢字]
区点=2117 16進=3531 シフトJIS=8B50
《常用音訓》キ/かがや…く
《音読み》 キ(ク )
) /ケ
/ケ 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 かがやく/てる/かがやき/かがやかしい(かがやかし)
《名付け》 あきら・かがやき・てる・ひかる
《意味》
〉
《訓読み》 かがやく/てる/かがやき/かがやかしい(かがやかし)
《名付け》 あきら・かがやき・てる・ひかる
《意味》
 {動・名}かがやく。てる。かがやき。火の外をまるくとりまいてひかる。のちひろく、光が四方にひろがること。また、そのひかり。「光輝燦然コウキサンゼン(光ってあざやかなこと)」
{動・名}かがやく。てる。かがやき。火の外をまるくとりまいてひかる。のちひろく、光が四方にひろがること。また、そのひかり。「光輝燦然コウキサンゼン(光ってあざやかなこと)」
 {形}かがやかしい(カガヤカシ)。はでにかがやくさま。てりはえるさま。
{形}かがやかしい(カガヤカシ)。はでにかがやくさま。てりはえるさま。
 {動・名}はでにてりかがやく。はぶりがよいこと。「輝燿キヨウ(栄花)」
《解字》
会意兼形声。軍グンは、まるく円陣をえがいた軍営。輝は「光+音符軍」で、光の中心をまるくとりまいたひかり。軍の語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・名}はでにてりかがやく。はぶりがよいこと。「輝燿キヨウ(栄花)」
《解字》
会意兼形声。軍グンは、まるく円陣をえがいた軍営。輝は「光+音符軍」で、光の中心をまるくとりまいたひかり。軍の語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 車部 [常用漢字]
区点=2117 16進=3531 シフトJIS=8B50
《常用音訓》キ/かがや…く
《音読み》 キ(ク
15画 車部 [常用漢字]
区点=2117 16進=3531 シフトJIS=8B50
《常用音訓》キ/かがや…く
《音読み》 キ(ク )
) /ケ
/ケ 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 かがやく/てる/かがやき/かがやかしい(かがやかし)
《名付け》 あきら・かがやき・てる・ひかる
《意味》
〉
《訓読み》 かがやく/てる/かがやき/かがやかしい(かがやかし)
《名付け》 あきら・かがやき・てる・ひかる
《意味》
 {動・名}かがやく。てる。かがやき。火の外をまるくとりまいてひかる。のちひろく、光が四方にひろがること。また、そのひかり。「光輝燦然コウキサンゼン(光ってあざやかなこと)」
{動・名}かがやく。てる。かがやき。火の外をまるくとりまいてひかる。のちひろく、光が四方にひろがること。また、そのひかり。「光輝燦然コウキサンゼン(光ってあざやかなこと)」
 {形}かがやかしい(カガヤカシ)。はでにかがやくさま。てりはえるさま。
{形}かがやかしい(カガヤカシ)。はでにかがやくさま。てりはえるさま。
 {動・名}はでにてりかがやく。はぶりがよいこと。「輝燿キヨウ(栄花)」
《解字》
会意兼形声。軍グンは、まるく円陣をえがいた軍営。輝は「光+音符軍」で、光の中心をまるくとりまいたひかり。軍の語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・名}はでにてりかがやく。はぶりがよいこと。「輝燿キヨウ(栄花)」
《解字》
会意兼形声。軍グンは、まるく円陣をえがいた軍営。輝は「光+音符軍」で、光の中心をまるくとりまいたひかり。軍の語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
過雁 カガン🔗⭐🔉
【過雁】
カガン =過鴈。空を飛んでいくかり。
鏡 かがみ🔗⭐🔉
【鏡】
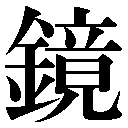 19画 金部 [四年]
区点=2232 16進=3640 シフトJIS=8BBE
《常用音訓》キョウ/かがみ
《音読み》 キョウ(キャウ)
19画 金部 [四年]
区点=2232 16進=3640 シフトJIS=8BBE
《常用音訓》キョウ/かがみ
《音読み》 キョウ(キャウ) /ケイ
/ケイ 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かがみ・かね・とし・み
《意味》
ng〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かがみ・かね・とし・み
《意味》
 {名}かがみ。光の反射を利用して姿をうつし出す道具。古くは、銅をみがいてつくり、今はガラスに、水銀・アルミニウムをめっきしてつくる。「銅鏡」
{名}かがみ。光の反射を利用して姿をうつし出す道具。古くは、銅をみがいてつくり、今はガラスに、水銀・アルミニウムをめっきしてつくる。「銅鏡」
 {名}かがみ。自分の姿を反省するいましめ。手本。模範。〈類義語〉→鑑。「鏡戒」
{名}かがみ。自分の姿を反省するいましめ。手本。模範。〈類義語〉→鑑。「鏡戒」
 {動}かんがみる。これまでの経験を手本にして考える。〈類義語〉→鑑。「鏡考」
{動}かんがみる。これまでの経験を手本にして考える。〈類義語〉→鑑。「鏡考」
 {名・形}かがみにうつされた姿や光。また、すみきったもののたとえ。あきらかな。「鏡水」
{名・形}かがみにうつされた姿や光。また、すみきったもののたとえ。あきらかな。「鏡水」
 {名}レンズ。めがね。レンズを使った器械。「顕微鏡」「老眼鏡」
《解字》
会意兼形声。竟は、楽章のさかいめ、くぎりめをあらわし、境の原字。鏡は「金+音符竟」。銅をみがいて、明暗のさかいめをはっきりうつし出すかがみ。
《単語家族》
景ケイ(明暗のくぎりめ)と同系。
《類義》
監カン・鑑カンは、顔を伏せて見るみずかがみのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}レンズ。めがね。レンズを使った器械。「顕微鏡」「老眼鏡」
《解字》
会意兼形声。竟は、楽章のさかいめ、くぎりめをあらわし、境の原字。鏡は「金+音符竟」。銅をみがいて、明暗のさかいめをはっきりうつし出すかがみ。
《単語家族》
景ケイ(明暗のくぎりめ)と同系。
《類義》
監カン・鑑カンは、顔を伏せて見るみずかがみのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
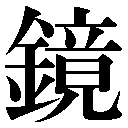 19画 金部 [四年]
区点=2232 16進=3640 シフトJIS=8BBE
《常用音訓》キョウ/かがみ
《音読み》 キョウ(キャウ)
19画 金部 [四年]
区点=2232 16進=3640 シフトJIS=8BBE
《常用音訓》キョウ/かがみ
《音読み》 キョウ(キャウ) /ケイ
/ケイ 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かがみ・かね・とし・み
《意味》
ng〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かがみ・かね・とし・み
《意味》
 {名}かがみ。光の反射を利用して姿をうつし出す道具。古くは、銅をみがいてつくり、今はガラスに、水銀・アルミニウムをめっきしてつくる。「銅鏡」
{名}かがみ。光の反射を利用して姿をうつし出す道具。古くは、銅をみがいてつくり、今はガラスに、水銀・アルミニウムをめっきしてつくる。「銅鏡」
 {名}かがみ。自分の姿を反省するいましめ。手本。模範。〈類義語〉→鑑。「鏡戒」
{名}かがみ。自分の姿を反省するいましめ。手本。模範。〈類義語〉→鑑。「鏡戒」
 {動}かんがみる。これまでの経験を手本にして考える。〈類義語〉→鑑。「鏡考」
{動}かんがみる。これまでの経験を手本にして考える。〈類義語〉→鑑。「鏡考」
 {名・形}かがみにうつされた姿や光。また、すみきったもののたとえ。あきらかな。「鏡水」
{名・形}かがみにうつされた姿や光。また、すみきったもののたとえ。あきらかな。「鏡水」
 {名}レンズ。めがね。レンズを使った器械。「顕微鏡」「老眼鏡」
《解字》
会意兼形声。竟は、楽章のさかいめ、くぎりめをあらわし、境の原字。鏡は「金+音符竟」。銅をみがいて、明暗のさかいめをはっきりうつし出すかがみ。
《単語家族》
景ケイ(明暗のくぎりめ)と同系。
《類義》
監カン・鑑カンは、顔を伏せて見るみずかがみのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}レンズ。めがね。レンズを使った器械。「顕微鏡」「老眼鏡」
《解字》
会意兼形声。竟は、楽章のさかいめ、くぎりめをあらわし、境の原字。鏡は「金+音符竟」。銅をみがいて、明暗のさかいめをはっきりうつし出すかがみ。
《単語家族》
景ケイ(明暗のくぎりめ)と同系。
《類義》
監カン・鑑カンは、顔を伏せて見るみずかがみのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
鏡餠 カガミモチ🔗⭐🔉
【鏡餠】
 キョウヘイ 麦と米をまぜてつくった、鏡型のもち。
キョウヘイ 麦と米をまぜてつくった、鏡型のもち。 カガミモチ〔国〕神前に供えたり、正月の飾りものにしたりする、まるく平たいもち。おそなえ。
カガミモチ〔国〕神前に供えたり、正月の飾りものにしたりする、まるく平たいもち。おそなえ。
 キョウヘイ 麦と米をまぜてつくった、鏡型のもち。
キョウヘイ 麦と米をまぜてつくった、鏡型のもち。 カガミモチ〔国〕神前に供えたり、正月の飾りものにしたりする、まるく平たいもち。おそなえ。
カガミモチ〔国〕神前に供えたり、正月の飾りものにしたりする、まるく平たいもち。おそなえ。
鑑 かがみ🔗⭐🔉
【鑑】
 23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
 23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム)
23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)
/ケン(ケム) 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
 {名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
 {名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
 {名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
 {動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
 {名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
 {動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める)
{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める) 覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
 23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム)
23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)
/ケン(ケム) 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
 {名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
 {名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
 {名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
 {動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
 {名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
 {動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める)
{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める) 覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
漢字源に「かが」で始まるの検索結果 1-34。
 13画 人部
区点=4904 16進=5124 シフトJIS=9943
《音読み》 ロウ
13画 人部
区点=4904 16進=5124 シフトJIS=9943
《音読み》 ロウ u〉〈l
u〉〈l 〉
《訓読み》 かがめる(かがむ)
《意味》
〉
《訓読み》 かがめる(かがむ)
《意味》
 12画 火部
区点=6367 16進=5F63 シフトJIS=E083
《音読み》 コン
12画 火部
区点=6367 16進=5F63 シフトJIS=E083
《音読み》 コン 16画 竹部
区点=6832 16進=6440 シフトJIS=E2BE
《音読み》 コウ
16画 竹部
区点=6832 16進=6440 シフトJIS=E2BE
《音読み》 コウ u〉
《訓読み》 かご/かがり/ふせご
《意味》
u〉
《訓読み》 かご/かがり/ふせご
《意味》
 20画 羽部 [人名漢字]
区点=4552 16進=4D54 シフトJIS=9773
《音読み》 ヨウ(エウ)
20画 羽部 [人名漢字]
区点=4552 16進=4D54 シフトJIS=9773
《音読み》 ヨウ(エウ)