複数辞典一括検索+![]()
![]()
冷 さます🔗⭐🔉
【冷】
 7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ
7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
 {動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
 {形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
 レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ
7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
 {動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
 {形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
 レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
妨 さまたげる🔗⭐🔉
彷 さまよう🔗⭐🔉
【彷】
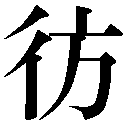 7画 彳部
区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66
《音読み》
7画 彳部
区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66
《音読み》  ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)
/ボウ(バウ) 〈p
〈p ng〉/
ng〉/ ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ)
 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
 {動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」
{動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」
 「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。
《解字》
会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋)
「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。
《解字》
会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋) 防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方
《類義》
徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方
《類義》
徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
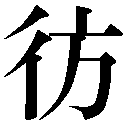 7画 彳部
区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66
《音読み》
7画 彳部
区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66
《音読み》  ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)
/ボウ(バウ) 〈p
〈p ng〉/
ng〉/ ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ)
 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
 {動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」
{動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」
 「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。
《解字》
会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋)
「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。
《解字》
会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋) 防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方
《類義》
徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方
《類義》
徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
徊 さまよう🔗⭐🔉
【徊】
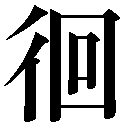 9画 彳部
区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A
《音読み》 カイ(ク
9画 彳部
区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A
《音読み》 カイ(ク イ)
イ) /エ(
/エ( )
) 〈hu
〈hu i〉
《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)
《意味》
i〉
《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)
《意味》
 {動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。
{動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。
 「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。
《解字》
会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。
《熟語》
→下付・中付語
「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。
《解字》
会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。
《熟語》
→下付・中付語
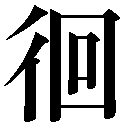 9画 彳部
区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A
《音読み》 カイ(ク
9画 彳部
区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A
《音読み》 カイ(ク イ)
イ) /エ(
/エ( )
) 〈hu
〈hu i〉
《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)
《意味》
i〉
《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)
《意味》
 {動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。
{動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。
 「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。
《解字》
会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。
《熟語》
→下付・中付語
「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。
《解字》
会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。
《熟語》
→下付・中付語
徘 さまよう🔗⭐🔉
【徘】
 11画 彳部
区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70
《音読み》 ハイ
11画 彳部
区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70
《音読み》 ハイ /バイ
/バイ 〈p
〈p i〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」
《解字》
会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。
《熟語》
→熟語
i〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」
《解字》
会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。
《熟語》
→熟語
 11画 彳部
区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70
《音読み》 ハイ
11画 彳部
区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70
《音読み》 ハイ /バイ
/バイ 〈p
〈p i〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」
《解字》
会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。
《熟語》
→熟語
i〉
《訓読み》 さまよう(さまよふ)
《意味》
{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」
《解字》
会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。
《熟語》
→熟語
徨 さまよう🔗⭐🔉
態 さま🔗⭐🔉
【態】
 14画 心部 [五年]
区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4
《常用音訓》タイ
《音読み》 タイ
14画 心部 [五年]
区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4
《常用音訓》タイ
《音読み》 タイ
 〈t
〈t i〉
《訓読み》 すがた/さま/わざと
《名付け》 かた
《意味》
i〉
《訓読み》 すがた/さま/わざと
《名付け》 かた
《意味》
 {名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕
{名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕
 {動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」
〔国〕わざと。ことさらに。
《解字》
会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」
〔国〕わざと。ことさらに。
《解字》
会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 14画 心部 [五年]
区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4
《常用音訓》タイ
《音読み》 タイ
14画 心部 [五年]
区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4
《常用音訓》タイ
《音読み》 タイ
 〈t
〈t i〉
《訓読み》 すがた/さま/わざと
《名付け》 かた
《意味》
i〉
《訓読み》 すがた/さま/わざと
《名付け》 かた
《意味》
 {名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕
{名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕
 {動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」
〔国〕わざと。ことさらに。
《解字》
会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」
〔国〕わざと。ことさらに。
《解字》
会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
様 さま🔗⭐🔉
【様】
 14画 木部 [三年]
区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C
【樣】旧字人名に使える旧字
14画 木部 [三年]
区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C
【樣】旧字人名に使える旧字
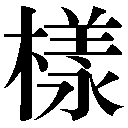 15画 木部
区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9
《常用音訓》ヨウ/さま
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
15画 木部
区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9
《常用音訓》ヨウ/さま
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 さま/くぬぎ
《意味》
ng〉
《訓読み》 さま/くぬぎ
《意味》
 {名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」
{名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」
 {名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」
{名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」
 {単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」
{単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」
 「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。
「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。
 {名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。
〔国〕
{名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。
〔国〕 やりかた。「仕様がない」「見様見まね」
やりかた。「仕様がない」「見様見まね」 さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」
さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」 さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」
《解字》
形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。
《単語家族》
像(すがた)と同系。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」
《解字》
形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。
《単語家族》
像(すがた)と同系。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 14画 木部 [三年]
区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C
【樣】旧字人名に使える旧字
14画 木部 [三年]
区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C
【樣】旧字人名に使える旧字
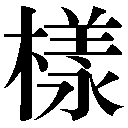 15画 木部
区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9
《常用音訓》ヨウ/さま
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
15画 木部
区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9
《常用音訓》ヨウ/さま
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 さま/くぬぎ
《意味》
ng〉
《訓読み》 さま/くぬぎ
《意味》
 {名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」
{名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」
 {名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」
{名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」
 {単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」
{単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」
 「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。
「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。
 {名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。
〔国〕
{名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。
〔国〕 やりかた。「仕様がない」「見様見まね」
やりかた。「仕様がない」「見様見まね」 さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」
さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」 さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」
《解字》
形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。
《単語家族》
像(すがた)と同系。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」
《解字》
形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。
《単語家族》
像(すがた)と同系。
《類義》
→状
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
無碍 サマタゲナシ🔗⭐🔉
【無碍】
 ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』
ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』 ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。
ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。
 ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』
ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』 ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。
ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。
瑣末 サマツ🔗⭐🔉
【瑣細】
ササイ こまかくて重要でないこと。『瑣小サショウ・瑣末サマツ』〈同義語〉些細。
碍 さまたげ🔗⭐🔉
礙 さまたげ🔗⭐🔉
【礙】
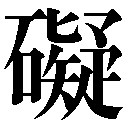 19画 石部
区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247
《音読み》 ガイ
19画 石部
区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247
《音読み》 ガイ /ゲ
/ゲ 〈
〈 i〉
《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ
《意味》
i〉
《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ
《意味》
 {動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕
{動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕
 {名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」
《解字》
会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。
《単語家族》
凝(かたまってとまる)
{名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」
《解字》
会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。
《単語家族》
凝(かたまってとまる) 擬(ためらわせる)と同系。
《類義》
障は、ついたてでとめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
擬(ためらわせる)と同系。
《類義》
障は、ついたてでとめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
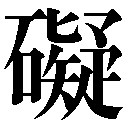 19画 石部
区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247
《音読み》 ガイ
19画 石部
区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247
《音読み》 ガイ /ゲ
/ゲ 〈
〈 i〉
《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ
《意味》
i〉
《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ
《意味》
 {動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕
{動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕
 {名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」
《解字》
会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。
《単語家族》
凝(かたまってとまる)
{名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」
《解字》
会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。
《単語家族》
凝(かたまってとまる) 擬(ためらわせる)と同系。
《類義》
障は、ついたてでとめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
擬(ためらわせる)と同系。
《類義》
障は、ついたてでとめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
覚 さます🔗⭐🔉
【覚】
 12画 見部 [四年]
区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F
【覺】旧字旧字
12画 見部 [四年]
区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F
【覺】旧字旧字
 20画 見部
区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653
《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める
《音読み》
20画 見部
区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653
《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める
《音読み》  カク
カク
 〈ju
〈ju 〉/
〉/ コウ(カウ)
コウ(カウ) /キョウ(ケウ)
/キョウ(ケウ) /カク
/カク 〈ji
〈ji o〉
《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ
《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし
《意味》
o〉
《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ
《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし
《意味》

 {動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」
{動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」
 {動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕
{動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕
 カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」
カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」
 {動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、
{動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、 と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕
〔国〕
と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕
〔国〕 おぼえる(オボユ)。記憶する。
おぼえる(オボユ)。記憶する。 おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」
おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」 「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」
《解字》
会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。
《単語家族》
交コウ(交差する)
「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」
《解字》
会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。
《単語家族》
交コウ(交差する) 較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。
《異字同訓》
さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。
《異字同訓》
さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 見部 [四年]
区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F
【覺】旧字旧字
12画 見部 [四年]
区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F
【覺】旧字旧字
 20画 見部
区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653
《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める
《音読み》
20画 見部
区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653
《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める
《音読み》  カク
カク
 〈ju
〈ju 〉/
〉/ コウ(カウ)
コウ(カウ) /キョウ(ケウ)
/キョウ(ケウ) /カク
/カク 〈ji
〈ji o〉
《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ
《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし
《意味》
o〉
《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ
《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし
《意味》

 {動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」
{動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」
 {動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕
{動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕
 カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」
カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」
 {動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、
{動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、 と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕
〔国〕
と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕
〔国〕 おぼえる(オボユ)。記憶する。
おぼえる(オボユ)。記憶する。 おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」
おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」 「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」
《解字》
会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。
《単語家族》
交コウ(交差する)
「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」
《解字》
会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。
《単語家族》
交コウ(交差する) 較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。
《異字同訓》
さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。
《異字同訓》
さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
醒 さます🔗⭐🔉
【醒】
 16画 酉部
区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1
《音読み》 セイ
16画 酉部
区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1
《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈x
〈x ng〉
《訓読み》 さめる(さむ)/さます
《意味》
ng〉
《訓読み》 さめる(さむ)/さます
《意味》
 {動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕
{動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕
 {動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」
《解字》
会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。
《単語家族》
清セイ(すみきった水)
{動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」
《解字》
会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。
《単語家族》
清セイ(すみきった水) 晶ショウ(すみきった光)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
晶ショウ(すみきった光)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画 酉部
区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1
《音読み》 セイ
16画 酉部
区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1
《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈x
〈x ng〉
《訓読み》 さめる(さむ)/さます
《意味》
ng〉
《訓読み》 さめる(さむ)/さます
《意味》
 {動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕
{動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕
 {動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」
《解字》
会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。
《単語家族》
清セイ(すみきった水)
{動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」
《解字》
会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。
《単語家族》
清セイ(すみきった水) 晶ショウ(すみきった光)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
晶ショウ(すみきった光)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「さま」で始まるの検索結果 1-15。
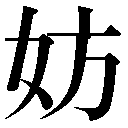 7画 女部 [常用漢字]
区点=4324 16進=4B38 シフトJIS=9657
《常用音訓》ボウ/さまた…げる
《音読み》 ボウ(バウ)
7画 女部 [常用漢字]
区点=4324 16進=4B38 シフトJIS=9657
《常用音訓》ボウ/さまた…げる
《音読み》 ボウ(バウ) ng〉
《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)
《意味》
 12画 彳部
区点=5551 16進=5753 シフトJIS=9C72
《音読み》 コウ(ク
12画 彳部
区点=5551 16進=5753 シフトJIS=9C72
《音読み》 コウ(ク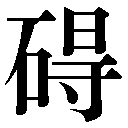 13画 石部
区点=1923 16進=3337 シフトJIS=8A56
《音読み》 ガイ
13画 石部
区点=1923 16進=3337 シフトJIS=8A56
《音読み》 ガイ