複数辞典一括検索+![]()
![]()
そ(音節)🔗⭐🔉
そ
①舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音〔s〕と母音〔o〕との結合した音節。〔so〕 上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔so〕乙〔sö〕2類の別があった。
②平仮名「そ」は「曾」の草体。片仮名「ソ」は「曾」の初2画。
そ【十】🔗⭐🔉
そ【十】
とお。じゅう。複合語として用いる。「―代しろ」「五―路いそじ」「三―一文字みそひともじ」
そ【衣】🔗⭐🔉
そ【衣】
ころも。きもの。神代紀上「神衣かむみそ」
そ【背】🔗⭐🔉
そ【背】
(セの古形)せ。せなか。うしろ。古事記上「黒き御衣みけしを…―に脱き棄うて」。万葉集14「筑波嶺ねに―向がいに見ゆる」
そ【麻】🔗⭐🔉
そ【麻】
「あさ」の古名。複合語として用いる。「夏―引く」「天つ菅―」
そ【磯】🔗⭐🔉
そ【磯】
「いそ」の「い」の脱落したもの。複合語に見られる。「―馴れ松」「荒―ありそ」
そ【阻】🔗⭐🔉
そ【阻】
山のけわしいこと。
そ【狙】🔗⭐🔉
そ【狙】
さる。
そ【俎】🔗⭐🔉
そ【俎】
①木製の平板の台で、2足または4足のついたもの。豆とうと共に中国の重要な祭器で、犠牲いけにえの肉をのせて供える。
俎
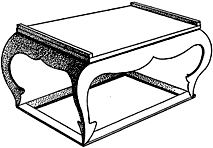 ②まないた。
②まないた。
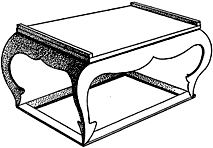 ②まないた。
②まないた。
そ【祖】🔗⭐🔉
そ【祖】
①家系の初代。また、父より前の直系血縁者。とおつおや。
②ある物事を開き始めた人。「中興の―」
③はじめ。もと。
そ【疽】🔗⭐🔉
そ【疽】
[正字通「癰ようの深き者を疽と曰いう、疽の深ければ悪、癰の浅ければ大なり」]悪性の腫物の一種。主に背部に生じ、筋骨を腐らす。癰の類。
そ【租】🔗⭐🔉
そ【租】
①年貢。税金。みつぎ。
②律令制の現物納租税の一種。口分田・位田・職田しきでんなど私的用益を許した田から収穫の一部を現物納させたもの。率は大化改新後おおむね田1段につき1束5把、すなわち収穫の約3パーセント。租の大半は諸国に納められて正税しょうぜいと呼び、毎年出挙すいこして利稲を国郡の費用とした。田租でんそ。
そ【疏】🔗⭐🔉
そ【疏】
(「疎」の本字。呉音はショ)
①箇条書にして陳述すること。また、その文書。官にたてまつる文書。上奏文。
②禅宗寺院における公文書。四六文が用いられ、五山文学の1ジャンルをなした。
③注釈。注に対してさらに注を加えたもの。しょ。「三経義―ぎしょ」
④「主典さかん」参照。
そ【粗】🔗⭐🔉
そ【粗】
①あらいこと。雑なこと。そまつなこと。
②贈物などに付ける謙称。
そ【組】🔗⭐🔉
そ【組】
組合の略。
そ【酥】🔗⭐🔉
そ【酥】
牛または羊の乳を煮つめて濃くしたもの。煉乳。酪。蘇そ。民部省式「凡そ諸国、―を貢る」
そ【楚】🔗⭐🔉
そ【楚】
①中国古代、春秋戦国時代の国。戦国七雄の一つ。長江中下流域を領有。戦国時代には、帝顓頊せんぎょくの子孫を自称。春秋の初め王号を称する。郢えいに都し、強大を誇ったが、秦のために滅ぼされた。中原諸国とは風俗言語も異なり、蛮夷の国と見なされた。( 〜前223)
②中国、隋末の617年林士弘が江南に建てた国。都は予章。(617〜622)
③中国、五代十国の一つ。許州の人、馬殷が湖南に建てた国。都は潭州。6世で南唐に滅ぼされた。(907〜951)
④中国、北宋滅亡の後、1127年金によって建てられた国。皇帝は北宋の宰相張邦昌。1カ月で滅亡。
そ【礎】🔗⭐🔉
そ【礎】
柱の基石。いしずえ。
ソ【sol イタリア】🔗⭐🔉
ソ【sol イタリア】
〔音〕
①七音音階の第5階名。
②ト(G)音のイタリア音名。
そ【其】🔗⭐🔉
そ【其】
〔代〕
①それ。そこ。その人。古事記中「臭韮かみら一もと―根がもと―根芽つなぎてうちてしやまむ」
②なにがし。某。伊勢物語「京に、―の人の御もとにとて、文書きてつく」
そ(副詞)🔗⭐🔉
そ
〔副〕
(副詞ソウの転)そう。そのよう。四河入海「―でもないことを―であるといひて」
そ(助詞)🔗⭐🔉
そ
〔助詞〕
➊(係助詞)
⇒ぞ。
➋(終助詞)サ変動詞「す」の古い命令形であるという。あるいは、清音であった係助詞「ぞ」と同源ともいう。動詞の連用形(カ変・サ変では未然形「こ」「せ」。「こ」「せ」は古い命令形とも)に付く。
①副詞「な」を伴い、「な…そ」の形で禁止を表す。「な」が禁止を表し、「そ」は添えられた語とする解釈もある。…するな。万葉集15「沖つ風いたくな吹き―妹もあらなくに」。竹取物語「胸痛きことなし給ひ―」。大鏡「荒涼して心しらざらむ人の前に夢語りな、この聞かせ給ふ人々、しおはしまされ―」
②平安後期から「そ」だけで禁止の意を表す例を生じた。…してくれるな。…なさるな。今昔物語集29「今はかく馴れぬれば、何ごとなりとも隠し―」。愚管抄4「世のならひに候へば、なげかせ給ひ―」。天草本伊曾保物語「少しもご気づかひあられ―」
そ(感動詞)🔗⭐🔉
そ
〔感〕
①馬を追う声。万葉集14「駒は食たぐとも吾わは―と追もはじ」
②掛け声。それ。義経記3「あとも―とも言はば、一定事も出で来なんと思ふ」
そ‐あく【粗悪】🔗⭐🔉
そ‐あく【粗悪】
粗末で質の悪いこと。「―な材料」「―品」
そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ🔗⭐🔉
そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ
平安時代、大臣の大饗たいきょうの時、蘇(酥)と干栗とを賜うため遣わされた勅使。そあまぐりのちょくし。→そ(酥)
ソアラー【soarer】🔗⭐🔉
ソアラー【soarer】
高性能のグライダー。上級滑空機。
ソアリング【soaring】🔗⭐🔉
ソアリング【soaring】
(→)滑空かっくう。
そ‐あん【素案】🔗⭐🔉
そ‐あん【素案】
練り上げてまとまった案にする前の、大もとになる案。
そい🔗⭐🔉
そい
①フサカサゴ科の魚の総称。
②メバル・ニゴイなどの地方名。
そい【添ひ・傍・副】ソヒ🔗⭐🔉
そい【添ひ・傍・副】ソヒ
かたわら。そば。枕草子245「―にさぶらひて」
そ‐い【所為】‥ヰ🔗⭐🔉
そ‐い【所為】‥ヰ
しわざ。しょい。せい。
そ‐い【素衣】🔗⭐🔉
そ‐い【素衣】
白色の衣服。しろぎぬ。
そ‐い【素意】🔗⭐🔉
そ‐い【素意】
かねてからの思い。素志。神皇正統記「―の末をもあらはさまほしくて」。「―を貫く」
そ‐い【粗衣】🔗⭐🔉
そ‐い【粗衣】
そまつな衣服。「―粗食」
そ‐い【疎意】🔗⭐🔉
そ‐い【疎意】
うとんずる心。隔意。〈日葡辞書〉
そい【候】🔗⭐🔉
そい【候】
〔助動〕
ソウ(候)の命令形「さうへ」が「そへ」→「そい」と転じたもの。狂言、鈍根草「いつもよりはやかつた、おたち―」
そい‐うま【副馬】ソヒ‥🔗⭐🔉
そい‐うま【副馬】ソヒ‥
(→)「そえうま」に同じ。〈類聚名義抄〉
そい‐ぐるま【副車】ソヒ‥🔗⭐🔉
そい‐ぐるま【副車】ソヒ‥
(→)「そえぐるま」に同じ。〈類聚名義抄〉
ソイ‐ソース【soy sauce】🔗⭐🔉
ソイ‐ソース【soy sauce】
醤油しょうゆ。
そい‐そしょく【粗衣粗食】🔗⭐🔉
そい‐そしょく【粗衣粗食】
粗末な衣服と粗末な食べ物。質素な生活をすること。↔暖衣飽食
そい‐た・つ【添ひ立つ】ソヒ‥🔗⭐🔉
そい‐た・つ【添ひ立つ】ソヒ‥
〔自四〕
付き添って世話をする。かしずく。後見する。能因本枕草子内裏は五節のほどこそ「いみじく―・ちたらむ人の心さわぎぬべし」
そ‐いつ【其奴】🔗⭐🔉
そ‐いつ【其奴】
〔代〕
(ソヤツの転)人を軽侮して、または無遠慮に呼ぶ語。その野郎。そのやつ。また、「それ」のぞんざいな言い方。「―が問題だ」
そい‐づかい【副使】ソヒヅカヒ🔗⭐🔉
そい‐づかい【副使】ソヒヅカヒ
副使ふくし。副官。顕宗紀「吉備臣を以て―として」
そい‐つ・く【添ひ付く】ソヒ‥🔗⭐🔉
そい‐つ・く【添ひ付く】ソヒ‥
〔自四〕
そばへ寄る。寄りそう。枕草子104「やがて御屏風に―・きてのぞくを」
そい‐と・げる【添い遂げる】ソヒ‥🔗⭐🔉
そい‐と・げる【添い遂げる】ソヒ‥
〔自下一〕[文]そひと・ぐ(下二)
①一生、夫婦としてくらす。
②困難を克服して、ついに夫婦となる。
広辞苑に「そ」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む