複数辞典一括検索+![]()
![]()
いぬ‐い【戌亥・乾】‥ヰ🔗⭐🔉
いぬ‐い【戌亥・乾】‥ヰ
十二支で表した方位で、戌と亥の間。北西の方角。→方位(図)。
⇒いぬい‐もん【乾門】
から【涸・乾】🔗⭐🔉
から【涸・乾】
(→)「かれ(涸)」に同じ。複合語に用いられる。「―井」「―咳」
から‐いり【乾煎り】🔗⭐🔉
から‐いり【乾煎り】
食物を水を加えずに煎ること。また、そうした食物。
から‐ざけ【乾鮭】🔗⭐🔉
から‐ざけ【乾鮭】
①サケの腸はらわたを去り、素乾しらぼしにしたもの。近世には冬の薬食いとすることがあった。〈[季]冬〉。今昔物語集28「―を太刀に帯はけて」
②人をののしる言葉。とるに足りない人間や老人などにいう。
⇒からざけ‐いろ【乾鮭色】
からざけ‐いろ【乾鮭色】🔗⭐🔉
からざけ‐いろ【乾鮭色】
古びくすんで乾鮭のようになった色。狂言、魚説法「すすけに煤けたる―の袈裟をかけ」
⇒から‐ざけ【乾鮭】
から‐せき【空咳・乾咳】🔗⭐🔉
から‐せき【空咳・乾咳】
(カラゼキとも)
①わざとするせきばらい。
②痰たんを伴わない、あるいは痰の切れない苦しい咳。
からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】🔗⭐🔉
からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】
カラカゼの促音化。〈[季]冬〉
から・びる【乾びる・涸びる・枯びる・嗄びる】🔗⭐🔉
から・びる【乾びる・涸びる・枯びる・嗄びる】
〔自上一〕[文]から・ぶ(上二)
①乾いて水気がなくなる。願経四分律平安初期点「樹通しかしながら身乾カラビつ」
②枯寂な趣を帯びる。狂言、連歌毘沙門「いやこれは人間とも見えず、―・びたるていにて御出現は」
③しわがれる。雨月物語5「―・びたる声」
から・ぶ【乾ぶ・涸ぶ・枯ぶ・嗄ぶ】🔗⭐🔉
から・ぶ【乾ぶ・涸ぶ・枯ぶ・嗄ぶ】
〔自上二〕
⇒からびる(上一)
から‐ぶき【乾拭き】🔗⭐🔉
から‐ぶき【乾拭き】
家具・縁側などのつやを出すため、かわいた布で拭くこと。艶拭つやぶき。
から‐ぼし【乾干し】🔗⭐🔉
から‐ぼし【乾干し】
魚・野菜などを日光で乾かすこと。また、その物。
かわか・す【乾かす】🔗⭐🔉
かわか・す【乾かす】
〔他五〕
日光や火で水分・湿気をのぞく。かわくようにする。干す。「洗濯物を―・す」
かわき【乾き・渇き】🔗⭐🔉
かわき【乾き・渇き】
①《乾》水分がなくなること。
②《渇》のどがかわくこと。また、比喩的に、欲求を満たす或るものを強く求めている心的状態。「心の―」
⇒かわき‐すなご【乾砂子】
⇒かわき‐の‐やまい【乾きの病】
⇒かわき‐もの【乾き物】
かわき‐すなご【乾砂子】🔗⭐🔉
かわき‐すなご【乾砂子】
朝儀の時、雨後のぬかるみを防ぐため庭に敷く砂。徒然草「庭の儀を奉行する人、―を設くるは、故実なりとぞ」
⇒かわき【乾き・渇き】
かわき‐の‐やまい【乾きの病】‥ヤマヒ🔗⭐🔉
かわき‐の‐やまい【乾きの病】‥ヤマヒ
①いくら食べても食べ足りない気持がする病気。のどがかわいて仕方のない病気。
②糖尿病の古名。燥病。渇病。
⇒かわき【乾き・渇き】
かわき‐もの【乾き物】🔗⭐🔉
かわき‐もの【乾き物】
豆類や干物など乾物の酒の肴さかな。
⇒かわき【乾き・渇き】
かわ・く【乾く・渇く】🔗⭐🔉
かわ・く【乾く・渇く】
〔自五〕
①《乾》熱などのために水分や湿気がなくなる。ひる。万葉集7「漁あさりする海未通女あまおとめらが袖とほり濡れにし衣干せど―・かず」。平家物語12「涙に袖はしほれつつ、塩くむあまの衣ならねども、―・くまなくぞ見え給ふ」。「洗濯物が―・く」「空気が―・く」「舌の根も―・かぬうちに」
②《渇》喉のどにうるおいがなくなって飲料を欲する。また、うるおいとなるものを欠いて、強く欲する。宇治拾遺物語7「喉の―・けば、水のませよ」。「音楽に―・く」
③うるおいがなくなる。感情がなく、冷淡な感じを与える。「―・き切った人の心」
かわら・ぐ【乾らぐ】🔗⭐🔉
かわら・ぐ【乾らぐ】
[一]〔自四〕
乾いてつやがなくなる。男色大鑑「前髪の風に―・ぎ」
[二]〔他下二〕
かわかす。水分・湿気をなくする。〈日葡辞書〉
かんえん‐ぴ【乾塩皮】🔗⭐🔉
かんえん‐ぴ【乾塩皮】
なまの獣皮を保存し、または輸送する便のために、塩を施して乾かしたもの。
かん‐か【乾果】‥クワ🔗⭐🔉
かん‐か【乾果】‥クワ
成熟後、果皮が乾燥して木質または革質となる果実。閉果と裂開果とがある。乾燥果。↔液果
かん‐き【乾季・乾期】🔗⭐🔉
かん‐き【乾季・乾期】
一年の中で雨の少ない季節。特に、東南アジア・インド・アフリカなどは、乾季と雨季とがはっきり分かれている。
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】🔗⭐🔉
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】
ほした魚。ひもの。ほしざかな。
かん‐げん【乾舷】🔗⭐🔉
かん‐げん【乾舷】
軍艦では喫水線きっすいせん、商船では満載喫水線から乾舷甲板までの垂直距離。
かん‐こ【乾固】🔗⭐🔉
かん‐こ【乾固】
かわきかたまること。
かん‐こ【乾枯】🔗⭐🔉
かん‐こ【乾枯】
かわきかれること。
かん‐こうげん【乾荒原】‥クワウ‥🔗⭐🔉
かん‐こうげん【乾荒原】‥クワウ‥
荒原の一種。厳しい乾燥気候のため植物が生育できないか、極めてまれにしかみられない。
かん‐さい【乾菜】🔗⭐🔉
かん‐さい【乾菜】
ほした野菜。ほしな。
かん‐しき【乾式】🔗⭐🔉
かん‐しき【乾式】
液体を用いない方式。または、液剤を蒸発させる方式。「―オフセット」↔湿式。
⇒かんしき‐へんあつき【乾式変圧器】
⇒かんしき‐やきん【乾式冶金】
かんしき‐へんあつき【乾式変圧器】🔗⭐🔉
かんしき‐へんあつき【乾式変圧器】
絶縁油を用いない変圧器。一般用の小型のものからビルディングなどで使用される大容量のものまで、広く用いられる。
⇒かん‐しき【乾式】
かんしき‐やきん【乾式冶金】🔗⭐🔉
かんしき‐やきん【乾式冶金】
鉱石に熱を加えて金属を還元する冶金法。還元剤には炭素・水素・金属などを用いる。硫化物の場合には焙焼を行なっていったん酸化物としてから還元を行う。↔湿式冶金
⇒かん‐しき【乾式】
かん‐しつ【乾湿】🔗⭐🔉
かん‐しつ【乾湿】
かわきとしめり。乾燥と湿気。
⇒かんしつきゅう‐しつどけい【乾湿球湿度計】
⇒かんしつ‐けい【乾湿計】
かん‐しつ【乾漆】🔗⭐🔉
かんしつきゅう‐しつどけい【乾湿球湿度計】‥キウ‥🔗⭐🔉
かんしつきゅう‐しつどけい【乾湿球湿度計】‥キウ‥
水の蒸発の程度を測って空気中の湿度を知る装置。同型の2個の温度計を並置し、その一方の球部を常に湿った布で包んだもの。両温度計の示度の差を読み、別の表によって湿度を知る。
⇒かん‐しつ【乾湿】
かんしつ‐けい【乾湿計】🔗⭐🔉
かんしつ‐けい【乾湿計】
(→)乾湿球湿度計に同じ。
⇒かん‐しつ【乾湿】
かんしつ‐ぞう【乾漆像】‥ザウ🔗⭐🔉
かんしつ‐ぞう【乾漆像】‥ザウ
乾漆で造った彫像。中国から伝えられ、奈良時代に最も盛行した。木心乾漆像(聖林寺十一面観音像など)と脱活乾漆(脱乾漆とも)像(興福寺阿修羅像など)とがあり、前者は心木を作り、その上に木屎こくそと漆液とをこね合わせたものを盛り上げ、麻布を薄く用いる。後者は塑土で原型を作り、その上に麻布を漆液で貼り固め、乾燥ののち内部の塑土を取り除く。
⇒かん‐しつ【乾漆】
かんしつ‐ふん【乾漆粉】🔗⭐🔉
かんしつ‐ふん【乾漆粉】
朱・黄・緑・黒などの彩漆をガラス面に塗って乾燥させ、剥はぎとって粉末にしたもの。蒔絵や変り塗に用いる。
⇒かん‐しつ【乾漆】
かん‐しょうが【乾生薑】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
かん‐しょうが【乾生薑】‥シヤウ‥
(→)乾薑かんきょうに同じ。
かん‐せい【乾性】🔗⭐🔉
かん‐せい【乾性】
乾燥する性質。また、水分をあまり必要としない性質。↔湿性。
⇒かんせい‐ゆ【乾性油】
かんせい‐しょくぶつ【乾生植物】🔗⭐🔉
かんせい‐しょくぶつ【乾生植物】
砂漠・荒原など水分に乏しい場所に生育し得る植物。多肉で貯水組織が発達しているものが多い。サボテン・ベンケイソウなど。→多肉植物
かんせい‐ゆ【乾性油】🔗⭐🔉
かんせい‐ゆ【乾性油】
空気中に放置すると、酸素と反応して固化・乾燥する脂肪油。リノール酸・リノレン酸のような不飽和度の高い高級脂肪酸のグリセリン‐エステルを多く含む。ヨウ素価130以上。ペンキ・印刷インク・油絵具などに用いる。桐油・亜麻仁油・荏油えのあぶらなどの類。乾油。乾燥油。↔不乾性油
⇒かん‐せい【乾性】
かん‐せんきょ【乾船渠】🔗⭐🔉
かん‐せんきょ【乾船渠】
(→)乾ドックに同じ。
かん‐そう【乾燥】‥サウ🔗⭐🔉
かん‐そう【乾燥】‥サウ
湿気や水分がなくなること、また、なくすこと。かわくこと。「空気が―する」「無味―」
⇒かんそう‐いも【乾燥芋】
⇒かんそう‐か【乾燥果】
⇒かんそう‐き【乾燥機】
⇒かんそう‐きこう【乾燥気候】
⇒かんそう‐けっしょう【乾燥血漿】
⇒かんそう‐こうぼ【乾燥酵母】
⇒かんそう‐ざい【乾燥剤】
⇒かんそう‐しつ【乾燥室】
⇒かんそう‐せんたく【乾燥洗濯】
⇒かんそう‐だんねつ‐げんりつ【乾燥断熱減率】
⇒かんそう‐むみ【乾燥無味】
⇒かんそう‐やさい【乾燥野菜】
⇒かんそう‐ゆ【乾燥油】
⇒かんそう‐らん【乾燥卵】
⇒かんそう‐りん【乾燥林】
かんそう‐いも【乾燥芋】‥サウ‥🔗⭐🔉
かんそう‐いも【乾燥芋】‥サウ‥
サツマイモを、生なまのまま、あるいは蒸したり茹でたりして、薄く切って干し上げた保存食品。干しいも。
⇒かん‐そう【乾燥】
かんそう‐か【乾燥果】‥サウクワ🔗⭐🔉
かんそう‐か【乾燥果】‥サウクワ
(→)乾果かんかに同じ。
⇒かん‐そう【乾燥】
かんそう‐き【乾燥機】‥サウ‥🔗⭐🔉
かんそう‐き【乾燥機】‥サウ‥
水分を取り除き、乾燥させる装置。ドライヤー。
⇒かん‐そう【乾燥】
かんそう‐きこう【乾燥気候】‥サウ‥🔗⭐🔉
かんそう‐きこう【乾燥気候】‥サウ‥
年間の降水量が蒸発量よりも少なく、樹木が生育しにくい気候。乾燥が厳しく草木の生育がほとんど不可能な砂漠気候と、若干の降水があり草や灌木が生育できるステップ気候とに大別。
⇒かん‐そう【乾燥】
かん‐ドック【乾ドック】🔗⭐🔉
かん‐ドック【乾ドック】
(dry dock)船体の建造・修理・塗装などのために、船を入れ、注排水のできる掘込み式ドック。乾船渠かんせんきょ。↔湿ドック
かん‐ば【乾場】🔗⭐🔉
かん‐ば【乾場】
採取した海藻を乾燥するための、海岸近くの広い土地。
かん‐パン【乾パン】🔗⭐🔉
かん‐パン【乾パン】
保存・携帯に便利なように水分を少なくして堅く作った小形のビスケット様のパン。旧日本陸軍では乾麺麭かんめんぽうと呼んだ。堅かたパン。
カンペイ【乾貝】🔗⭐🔉
カンペイ【乾貝】
(中国語)中国料理に用いるホタテガイなどの乾した貝柱。
けん【乾】🔗⭐🔉
けん【乾】
八卦はっけの一つ。☰で表す。陽の卦で、その徳は健、天にかたどる。方位では北西いぬいに配する。↔坤こん
⇒乾を旋らし坤を転ず
けん‐きん【乾金】🔗⭐🔉
けん‐きん【乾金】
(→)乾字金けんじきんに同じ。誹風柳多留拾遺10「姑婆々―などを一分持ち」
けんげん【乾元】🔗⭐🔉
けんげん【乾元】
鎌倉後期、後二条天皇朝の年号。正安4年11月21日(1302年12月10日)改元、乾元2年8月5日(1303年9月16日)嘉元に改元。
けん‐こう【乾綱】‥カウ🔗⭐🔉
けん‐こう【乾綱】‥カウ
①天の法則。
②君主の大権。
けん‐こん【乾坤】🔗⭐🔉
けん‐こん【乾坤】
①易えきの卦けの乾と坤。
②天地。
③陰陽。
④いぬい(北西)とひつじさる(南西)。
⑤二つで一組をなすものの順序を表す語。多く書物の上冊・下冊の意。
⇒けんこん‐いってき【乾坤一擲】
けんこん‐いってき【乾坤一擲】🔗⭐🔉
けんこん‐いってき【乾坤一擲】
運命を賭として、のるかそるかの勝負をすること。→一擲乾坤を賭とす(「一擲」成句)
⇒けん‐こん【乾坤】
けんざん【乾山】🔗⭐🔉
けんざん【乾山】
⇒おがたけんざん(尾形乾山)。
⇒けんざん‐やき【乾山焼】
けんざん‐やき【乾山焼】🔗⭐🔉
けんざん‐やき【乾山焼】
元禄(1688〜1704)の頃、尾形乾山が京都の鳴滝で始めた陶器。兄光琳こうりんが絵付に加わり、装飾性に優れた茶道具や懐石器などを製作。
⇒けんざん【乾山】
けんじ‐きん【乾字金】🔗⭐🔉
けんじ‐きん【乾字金】
(「乾」字の極印があるからいう)1710年(宝永7)江戸幕府の鋳造した小判金および一分判金。乾金けんきん。乾ノ字金。
○乾を旋らし坤を転ずけんをめぐらしこんをてんず🔗⭐🔉
○乾を旋らし坤を転ずけんをめぐらしこんをてんず
[韓愈、潮州刺史謝上表]天下の情勢を一新するのにいう。
⇒けん【乾】
こ
①後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音〔k〕と母音〔o〕との結合した音節。〔ko〕 上代特殊仮名遣では奈良時代には甲〔ko〕乙〔kö〕2類の別があり、その区別は平安初期まで残った。
②平仮名「こ」は「己」の草体。片仮名「コ」は「己」の初2画。
こ【子・児・仔】
[一]〔名〕
(「小こ」と同源か)
①親から生まれたもの。また、それに準ずる資格の者。実子・養子・まま子のいずれにもいい、人以外の動物にもいう。万葉集5「銀しろかねも金くがねも玉も何せむにまされる宝―にしかめやも」。宇津保物語蔵開中「そこを御―にして」。大鏡後一条「魚の―多かれど、まことの魚となること難し」
②生まれてまだ間のないもの。幼少のもの。まだ一人前でない者。こども。狂言、子盗人「まだ―が寝さしてある」。「―犬を拾う」
③一族の子弟。万葉集5「天の下奏まおしたまひし家の―と選び給ひて」
④(男女を問わず)人を親しんで呼ぶ語。古事記中「命のまたけむ人は…くまかしが葉をうずにさせその―」。古事記中「眉画まよがき濃こに描き垂れ遇はしし女人おみなかもがと我が見し―ら」
⑤抱えの若い芸者など。また広く、若い女。
⑥卵。古事記下「雁かり―産むと聞くや」
⑦蚕。万葉集12「たらちねの母が養かふ―の繭まよごもり」
⑧本もとから分かれて生じたもの。古事記下「一本菅は―持たず」。「竹の―」「―芋」
⑨子株こかぶの略。
⑩利息。利子。「元もとも―もない」
⑪従属的な位置にあるもの。
㋐それに所属し、支配下にあるもの。「―会社」
㋑麻雀・花札など勝負事で、親以外のもの。
㋒碇いかりに取りつけた石。日葡辞書「イカリノコ」
㋓はしごの横木。日葡辞書「ハシノコ」→格こ。
[二]〔接尾〕
①古くは男女ともに、今は女の名の下に添える語。大和物語「右馬允藤原千兼といふ人の妻めには、とし―といふ人なむありける」。「小野妹―」「花―」
②小さなもの、劣ったものの意で添える語。「ひよ―」「猿まし―」「娘っ―」
③人の意を表す語。多く、仕事をする人の意。万葉集3「網―あご」。「売り―」「お針―」「馬―」「江戸っ―」「売れっ―」
④ものを表すのに添える語。「振り―」「呼び―の笛」「鳴る―」
◇一般には「子」を使う。[一]1・2の人には「児」、人以外には「仔」も使う。
⇒子に優る宝なし
⇒子は親の鏡
⇒子は親の背中を見て育つ
⇒子は鎹
⇒子は三界の首枷
⇒子養わんと欲すれども親待たず
⇒子ゆえの闇
⇒子を棄つる藪はあれど身を棄つる藪はなし
⇒子を見ること親に如かず
⇒子を持って知る親の恩
こ【木】
(「き(木)」の古形。他の語に冠して複合語をつくる)
①樹木。古事記中「―の葉」
②木材。古事記中「―鍬くわ」
こ【格】
①障子の骨。
②梯子はしごの足をかける横木。古今著聞集14「階はしの―を斜におり下りて」
③格天井ごうてんじょうの竿材。
④碁盤・将棋盤の面に引いた縦横の線。め。
こ【粉】
①砕けてこまかくなったもの。すりつぶしてこまかくしたもの。こな。日本霊異記下「干飯ほしいいの―」。「身を―にする」「小麦―」
②薬味やくみ。三議一統大双紙「海苔のりの類、あをみ等を―におくなり」
③汁の実み。
⇒粉になる
⇒粉を吹く
こ【蚕】
(→)「かいこ」のこと。「春―」→こ(子・児・仔)[一]7
こ【濃】
(接頭語的に用いて)色や液のこいこと。華厳音義私記「漿、古美豆」。「―紫」
こ【籠】
①「かご」のこと。万葉集1「―もよ、み―持ち」
②(→)伏籠ふせごに同じ。源氏物語帚木「なえたる衣きぬどもの厚肥えたる大いなる―にうちかけて」
こ【海鼠】
ナマコのこと。古事記上「故かれ今に―の口析さけり」
こ【戸】
①家。家屋。「―を構える」
②家・住まいをかぞえる語。
③律令制で、行政上の単位とされた家。→郷戸ごうこ
こ【股】
〔数〕鈎股弦こうこげんの一つ。
こ【孤】
①両親のない子。みなしご。「六尺りくせきの―」
②ただ一人であること。同類のものがないこと。ひとりぼっち。「徳は―ならず」
こ【弧】
①木の弓。弓。また、弓なりの形。「―を描いて飛ぶ」
②〔数〕円周または曲線のつながった一部分。
こ【故】
①[易経雑卦「革は故ふるきを去る也」]古いものごと。
②死ぬこと。また、すでに死んだ人をよぶ場合に冠する語。源氏物語桐壺「―大納言今はとなるまで」
こ【胡】
(呉音はゴ。唐音はウ)
①中国で、異民族の称。秦代・漢代には匈奴、唐代には広く西域民族を指す。→五胡。
②中国で、一般に異民族・外国を指し、外来のものに冠する語。
③でたらめなこと。
こ【個・箇】
(唐音)
①ひとつの物。ひとりの人。「―の認識」
②ものを数える語。→か(箇)
こ【絇】
①⇒く(絇)。
②絇くの糸すじを数える語。
こ【袴】
①はかま。「着―の祝」
②もと陸軍で、ズボンのこと。
こ【湖】
①みずうみ。また、湖沼を数える語。
②中国で、特に洞庭湖。
こ【鈷】
(「股」の借字)仏具の一種。銛もりの変化したもので、密教でその形を象徴化し、悟りを妨げるものを払う意味を持つ。→金剛杵こんごうしょ
こ【鉤】
巻き上げた御簾みすをつるし懸けるかぎ。枕草子201「みすの帽額もこう、総角あげまきなどにあげたる―のきはやかなるも」
こ【滬】
(Hu)中国上海シャンハイ市の略称。市内を流れる蘇州河の下流部を古く滬涜ことくと呼んだことに因む。
こ【瞽】
目の見えないこと。
こ【是・此】
〔代〕
(空間的・時間的または心理的に)話し手の近くにあり、話し手に属すると認めたものを指し示す語。これ。ここ。古事記中「ああしやごしや、―は嘲咲あざわらふぞ」。万葉集8「ほととぎす―ゆ鳴き渡る」
こ【来】
カ変動詞「く」の未然形・命令形。命令形は後世、「こよ」とも。更級日記「いづら猫は。こちゐて―」
こ【小】
〔接頭〕
体言・形容詞などの上に付く。
①物の形・数量の小さい意を表す。万葉集4「佐保河の―石践ふみ渡り」。万葉集11「―菅の笠をきずて来にけり」。源氏物語松風「―鷹」。源氏物語若紫「―柴」。「―島」「―船」「―人数」
②事物の程度の少ない意を表す。万葉集11「―雨雰ふりしきしくしく思ほゆ」。「―太り」
③年が若い。幼い。枕草子300「陰陽師のもとなる―わらはべこそ」。「―犬」
④数量が足りないが、ややそれに近い意を表す。浮世床初「半年か―半年ゐる内には」。「―一里」「―一時間」
⑤半分の意を表す。「―半斤」「小半こなから」
⑥いうにいわれない、何となく、の意を表す。また、その状態を憎む意を表す。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「定めしゆふべ平様と手を引き合うてでござんせう。―にくいことや」。「―ぎれい」「―ざっぱり」「―ぎたない」「―うるさい」
⑦軽んじあなどる意を表す。日葡辞書「コセガレ」。歌舞伎、三十石艠始さんじっこくよふねのはじまり「―ざかしい青蠅めら」。浮世草子、御前義経記「―童わっぱなみの草履をつかみ」。「―利口」「―役人」
⑧(体の部分を表す語に付いて)その動作を軽く行う意を表す。「―耳にはさむ」「―腰を屈める」
⑨語調を整える。「夕焼け―焼け」「おお寒―寒」
こ
〔接尾〕
①「こと(事)」の下略。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「虚事うそっこにてめくりを始めても、互いに勝を人に譲り」
②互いにすること。相競うこと。くら。くらべ。浮世床2「是れは癖だからゆるしつ―」。「駆けっ―」
③さま。そういう状態。「どんぶら―」「ぺちゃん―」
④特に意味を持たず種々の語に付く。東北地方の方言などに多い。「牛べこ―の子っ―」「ちゃわん―」「ぜに―」
こ【処】
〔接尾〕
場所の意を表す。「そ―」「かし―」「あそ―」
こ【乎】
状態を表す語に付けて語調を強める語。「洋々―」
ご
後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音〔g〕と母音〔o〕との結合した音節。〔go〕 ただし、語頭以外では鼻音〔ŋo〕となることが多い。上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔go〕乙〔gö〕2類の別があり、その区別は平安初期まで残った。
ご
松の枯落葉。多くは掻き集めて焚物とするのをいう。こくば。こくぼ。落松葉を掻き寄せる熊手を「ごかき」という。近世は伊賀・尾張・三河地方に方言として残った。「―をたいて手拭あぶる寒さかな」(芭蕉)
ご【豆汁・豆油】
大豆を水にひたし、すりつぶした汁。豆腐の原料や染物または油絵の彩料に用いる。
ご【五】
数の名。いつつ。いつ。
ご【午】
①十二支の第7。うま。
②午うまの刻。昼の12時。「三井寺や日は―にせまる若楓」(蕪村)。
③南。
ご【伍】
①古代中国で、五人を一伍とする軍政上の単位。また、五戸を一伍とする行政上の単位。
②なかま。くみ。並んだ1組。列。
③「五」の大字。
ご【呉】
①中国古代、春秋時代の列国の一つ。周の文王の伯父太伯の建国と称する。長江河口地方を領有。楚を破り勢を張ったが、夫差の時、越王勾践に滅ぼされた。( 〜前473)
②中国、三国時代の三国の一つ。孫権が江南に建てた国。222年独立、229年国号を定めた。都は建業。4世で西晋に滅ぼされた。(222〜280)
③中国、五代十国の一つ。楊行密が淮南・江東に建てた国。都は揚州。4世で南唐に滅ぼされた。(902〜937)
④中国江蘇省の別称。
→くれ(呉)
ご【吾】
①われ。自分。
②友人などに冠する親称。
ご【後】
(慣用音。漢音はコウ)
時間的にあと。のち。「その―」
ご【御】
(呉音)
[一]〔名〕
(「御前ごぜん」の略)貴婦人の称呼の下に添えて敬称とする語。土佐日記「淡路の―の歌に劣れり」
[二]〔接頭〕
①主に漢語の体言に冠して尊敬の意を添える。源氏物語桐壺「十二にて―元服したまふ」。日葡辞書「ゴベウショ(御廟所)」
②主に漢語の体言に冠して丁寧の意を添える。「―飯にする」
③自分の行為を表す語に冠して謙譲の意を添える。「―説明いたします」
[三]〔接尾〕
人物を表す語の下に付けて尊敬の意を添える。日葡辞書「チチゴ」。浄瑠璃、伽羅先代萩「ゆうべ呼んだ花嫁―」
→ぎょ(御)
ご【期】
(呉音)
①とき。おり。また、期限。際限。大鏡道長「申すべきことは―もなく侍るを」。宇津保物語蔵開上「子生み給ふべき―近くなりぬれば」。「この―に及んで」
②死ぬ時。最期。謡曲、土蜘蛛「今は―を待つばかりなり」
③江戸時代、遊里で夜の九つ時。今の午後12時。
→き(期)
ご【碁・棊】
二人相対し、361の目を盛った盤上に交互に一つずつ黒・白の碁石を並べ、地を広く占めた方を勝ちとする遊戯。中国から伝来。囲碁。宇津保物語初秋「われこの御―に勝たむとも思はず」。「―を打つ」
⇒碁に凝ると親の死目に逢わぬ
⇒碁に負けたら将棋に勝て
ご【語】
(呉音)
①ことば。ことばづかい。はなし。「―をかわす」「24万―収録の辞典」
②物語の略。「源―」
⇒語塞がる
ご【誤】
うっかりまちがうこと。あやまち。「―を訂す」
コア【core】
①ものの中心部。中核。核心。
②建物の中央部で、共用施設・設備スペース・構造用耐力壁などが集められたところ。→コア‐システム。
③鋳物の中子なかご。
④(コイルなどの)鉄心てっしん。
⑤地球の核。→核
ゴア【Goa・臥亜】
①インド南西部、アラビア海に面する州。もとポルトガルの植民地で、1961年インドに接収された。ザビエルの墓所がある。安土桃山時代すでに日本との交通があった。
②江戸時代にオランダ人が日本にもたらしたインド産の織物。
ご‐あいさつ【御挨拶】
①「挨拶」を丁寧にいう語。
②相手の非礼などに対して、皮肉を込めて応える言葉。「これは―だね」
コア‐インフレーション【core inflation】
短期的な物価変動による影響を取り除いた、長期的な物価変動に基づくと考えられる物価上昇。コア‐インフレ。
こ‐あおい【小葵】‥アフヒ
①〔植〕(→)ゼニアオイの異称。
②唐花からはな唐草からくさ文様の一種で花がゼニアオイに似るもの。天皇・東宮の下襲したがさね・衵あこめ・半臂はんぴ・直衣のうしなどに用いた。
小葵
 こ‐あがり【小上がり】
小料理屋などで、客が気軽に上がれるよう、簡単な仕切りだけで土間と仕切られた座敷。
コア‐カリキュラム【core curriculum】
教科の枠にとらわれず、学習の核となる課題や教材を中心に編成した教育課程。それに取り組む経験の過程を共通必須とする。アメリカの進歩主義教育において実施し、日本でも第二次大戦後数年間試みた。
こ‐あきない【小商い】‥アキナヒ
わずかの資金で行う小規模のあきない。
こ‐あきんど【小商人】
少しの資金で、小規模の商いをする商人。
ご‐あく【五悪】
①〔仏〕五戒にそむくこと。殺生せっしょう・偸盗ちゅうとう・邪淫・妄語・飲酒おんじゅの五悪事。→五戒。
②仁・義・礼・智・信の五常にそむくこと。
ご‐あくしゅ【五悪趣】
〔仏〕衆生しゅじょうが善悪の業因によって趣おもむき住む五つの場所、すなわち天・人間・畜生・餓鬼・地獄の総称。五趣。五悪道。
こ‐あげ【小揚】
①船から河岸に荷揚げすること。また、その人夫。浄瑠璃、鎌倉三代記「お供先で、―がいるなら、われらを買うて貰ふぞや」
②客を乗せて遊郭に通った駕籠かごかき。浮世草子、好色敗毒散「足の駕のりものには―を雇ふ世話もなし」
③義太夫節で、端場はばの前、一場の冒頭の部分。
こ‐あざ【小字】
町村内の大字おおあざをさらに細かく分けた称。
ご‐あさって【五明後日】
(西日本で)明々々後日。しあさって1の次の日。
コア‐サンプラー【core sampler】
土壌や岩石の試料を採取するための筒状の標本採掘器具。
こ‐あし【小足】
足並を細かくきざんで歩くこと。きざみあし。日葡辞書「コアシニアユム」。浄瑠璃、大職冠「とどろとどろと―を使ひ」
こ‐あじ【小味】‥アヂ
①こまやかで、趣ある味。↔大味。
②(取引用語)相場が動き始めて、売買に面白みが湧いてくること。
こ‐アジア‐しょご【古アジア諸語】
(Paleo-Asiatic)アジア北東端部の言語のうち、アルタイ諸語・ウラル諸語以外の諸言語の総称。チュクチ・コリヤーク・カムチャダール・ユカギール・ニヴヒ・ケットなどの諸民族の言語を含むが、類縁関係は不明。旧アジア諸語。
こ‐あじさい【小紫陽花】‥アヂサヰ
ユキノシタ科の小低木。関東地方以西の各地の山地に多い。落葉性で高さ1メートル余。葉は対生し倒卵形、上半部に粗大な鋸歯がある。夏、茎頂に上部が平たい散房花序をつけ、淡青色の小花を密生。アジサイの仲間だが花序の外周部に装飾花はつかない。
コア‐システム【core system】
建築計画の一方式。通路や階段、台所・便所・浴室などサービス‐スペースを集中化し、建物の核とする方法。動線・配管などが能率的に配置できる。
コアセルベート【coacervate】
溶液中で親水コロイドの粒子が集合し、溶液との間に一定の平衡を保つ小さなコロイド液(液滴)となったもの。オパーリンは、細胞の原形質との類似性から、生命発生の一段階と考えた。
コア‐タイム【core time】
フレックス‐タイム制で、各人が共通して就労すべき基幹的な時間帯。
こ‐あたり【小当り】
①試みに他人の意中などを探ってみること。「―に当たってみる」
②蒔絵まきえで、直接器物に下絵を描くこと。
ゴア‐テックス【Gore-Tex】
テフロン系樹脂を布地にコーティングした衣料素材。撥水性・通気性に優れる。商標名。
コア‐ドリル【core drill】
中空の円筒状の刃を持つドリル。コンクリートや石材の穴あけ、地質・道路の試料採取、削り穴の仕上げ加工などに用いる。
こ‐あま・い【小甘い】
〔形〕
(取引用語)相場がやや下がり気味である。
こ‐あみがさ【小編笠】
饅頭形で腰高に編んだ編笠。江戸初期、槍持・ほおずき売・風車売などがかぶった。
小編笠
こ‐あがり【小上がり】
小料理屋などで、客が気軽に上がれるよう、簡単な仕切りだけで土間と仕切られた座敷。
コア‐カリキュラム【core curriculum】
教科の枠にとらわれず、学習の核となる課題や教材を中心に編成した教育課程。それに取り組む経験の過程を共通必須とする。アメリカの進歩主義教育において実施し、日本でも第二次大戦後数年間試みた。
こ‐あきない【小商い】‥アキナヒ
わずかの資金で行う小規模のあきない。
こ‐あきんど【小商人】
少しの資金で、小規模の商いをする商人。
ご‐あく【五悪】
①〔仏〕五戒にそむくこと。殺生せっしょう・偸盗ちゅうとう・邪淫・妄語・飲酒おんじゅの五悪事。→五戒。
②仁・義・礼・智・信の五常にそむくこと。
ご‐あくしゅ【五悪趣】
〔仏〕衆生しゅじょうが善悪の業因によって趣おもむき住む五つの場所、すなわち天・人間・畜生・餓鬼・地獄の総称。五趣。五悪道。
こ‐あげ【小揚】
①船から河岸に荷揚げすること。また、その人夫。浄瑠璃、鎌倉三代記「お供先で、―がいるなら、われらを買うて貰ふぞや」
②客を乗せて遊郭に通った駕籠かごかき。浮世草子、好色敗毒散「足の駕のりものには―を雇ふ世話もなし」
③義太夫節で、端場はばの前、一場の冒頭の部分。
こ‐あざ【小字】
町村内の大字おおあざをさらに細かく分けた称。
ご‐あさって【五明後日】
(西日本で)明々々後日。しあさって1の次の日。
コア‐サンプラー【core sampler】
土壌や岩石の試料を採取するための筒状の標本採掘器具。
こ‐あし【小足】
足並を細かくきざんで歩くこと。きざみあし。日葡辞書「コアシニアユム」。浄瑠璃、大職冠「とどろとどろと―を使ひ」
こ‐あじ【小味】‥アヂ
①こまやかで、趣ある味。↔大味。
②(取引用語)相場が動き始めて、売買に面白みが湧いてくること。
こ‐アジア‐しょご【古アジア諸語】
(Paleo-Asiatic)アジア北東端部の言語のうち、アルタイ諸語・ウラル諸語以外の諸言語の総称。チュクチ・コリヤーク・カムチャダール・ユカギール・ニヴヒ・ケットなどの諸民族の言語を含むが、類縁関係は不明。旧アジア諸語。
こ‐あじさい【小紫陽花】‥アヂサヰ
ユキノシタ科の小低木。関東地方以西の各地の山地に多い。落葉性で高さ1メートル余。葉は対生し倒卵形、上半部に粗大な鋸歯がある。夏、茎頂に上部が平たい散房花序をつけ、淡青色の小花を密生。アジサイの仲間だが花序の外周部に装飾花はつかない。
コア‐システム【core system】
建築計画の一方式。通路や階段、台所・便所・浴室などサービス‐スペースを集中化し、建物の核とする方法。動線・配管などが能率的に配置できる。
コアセルベート【coacervate】
溶液中で親水コロイドの粒子が集合し、溶液との間に一定の平衡を保つ小さなコロイド液(液滴)となったもの。オパーリンは、細胞の原形質との類似性から、生命発生の一段階と考えた。
コア‐タイム【core time】
フレックス‐タイム制で、各人が共通して就労すべき基幹的な時間帯。
こ‐あたり【小当り】
①試みに他人の意中などを探ってみること。「―に当たってみる」
②蒔絵まきえで、直接器物に下絵を描くこと。
ゴア‐テックス【Gore-Tex】
テフロン系樹脂を布地にコーティングした衣料素材。撥水性・通気性に優れる。商標名。
コア‐ドリル【core drill】
中空の円筒状の刃を持つドリル。コンクリートや石材の穴あけ、地質・道路の試料採取、削り穴の仕上げ加工などに用いる。
こ‐あま・い【小甘い】
〔形〕
(取引用語)相場がやや下がり気味である。
こ‐あみがさ【小編笠】
饅頭形で腰高に編んだ編笠。江戸初期、槍持・ほおずき売・風車売などがかぶった。
小編笠
 こあみ‐ざ【小網座】
〔天〕(→)レチクル座の別称。
こ‐あゆ【小鮎】
①鮎の幼魚。3〜4月ごろ、川をさかのぼる。〈[季]春〉
②湖中に陸封され、成魚の体形とならず小形のまま成熟した鮎。河川に放流すると普通の大きさの鮎となる。
コアラ【koala】
フクロネズミ目(有袋類)コアラ科の哺乳類。体長70センチメートルほどで、尾はほとんどない。体毛は灰色から黄褐色。耳は大きく、白く柔らかい毛に覆われる。オーストラリア東部の低地にのみ生息、ユーカリの葉しか食べない。動作は鈍く、ほとんど樹上で生活。毛皮利用とペットとするため乱獲され、絶滅しかかったが、保護が成功してかなり回復。フクログマ。コモリグマ。
コアラ
こあみ‐ざ【小網座】
〔天〕(→)レチクル座の別称。
こ‐あゆ【小鮎】
①鮎の幼魚。3〜4月ごろ、川をさかのぼる。〈[季]春〉
②湖中に陸封され、成魚の体形とならず小形のまま成熟した鮎。河川に放流すると普通の大きさの鮎となる。
コアラ【koala】
フクロネズミ目(有袋類)コアラ科の哺乳類。体長70センチメートルほどで、尾はほとんどない。体毛は灰色から黄褐色。耳は大きく、白く柔らかい毛に覆われる。オーストラリア東部の低地にのみ生息、ユーカリの葉しか食べない。動作は鈍く、ほとんど樹上で生活。毛皮利用とペットとするため乱獲され、絶滅しかかったが、保護が成功してかなり回復。フクログマ。コモリグマ。
コアラ
 コアラ
提供:東京動物園協会
コアラ
提供:東京動物園協会
 ご‐あ・る
〔自四〕
(ゴザルの転)「ある」の丁寧な言い方。主に「…でごある」の形で用いる。浄瑠璃、冥途飛脚「友達に損かける忠兵衛では―・らぬ」
こ‐あるき【小歩き】
①小足に歩くこと。
②使い走りをする者。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「粋方仲間の―、貰ひ喰ひで暮して居つたを引き上げて」
こ‐あん【孤鞍】
一人馬に乗って行くこと。単騎。
ごあん・す
〔自サ変〕
(遊里語。ゴザンスの転)「来る」の尊敬語、また、「(で)ある」を丁寧にいう語として用いる。いらっしゃる。ございます。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「前は再々―・して何が怖うて逃げさんす」。浄瑠璃、傾城反魂香「何の気随で―・しよ」
こ‐あんどの【小安殿】
⇒こやすみどの
こい【凍】
(コユの連用形から)こごえること。継体紀「天下其の―を受くることあり」
こい【恋】コヒ
①一緒に生活できない人や亡くなった人に強くひかれて、切なく思うこと。また、そのこころ。特に、男女間の思慕の情。恋慕。恋愛。万葉集20「常陸さし行かむ雁もが吾あが―を記して付けて妹に知らせむ」。「―に身を焼く」
②植物や土地などに寄せる思慕の情。万葉集10「桜花時は過ぎねど見る人の―の盛りと今し散るらむ」
⇒恋に上下の隔てなし
⇒恋は曲者
⇒恋は思案の外
⇒恋は盲目
⇒恋は闇
こい【尰】コヒ
膝から下が腫はれる病気。脚気かっけの類。おめあし。蜻蛉日記上「片足に―つきたるに」
こい【請い・乞い】コヒ
こうこと。ねがうこと。たのみ。「―に応ずる」
こい【鯉】コヒ
コイ科の淡水産の硬骨魚。側線鱗が36枚あるというので六六魚りくりくぎょとも呼ぶが、実際には31〜38枚ほどの変異が見られる。2対の口ひげがあり、急な流れのない泥底の川や池を好む。日本では食用・観賞用として珍重され、また立身出世の象徴とされる。変種に錦鯉やドイツから輸入した革鯉などがある。鯉魚。土佐日記「―はなくて、鮒ふなよりはじめて、川のも海のも」
コイ
提供:東京動物園協会
ご‐あ・る
〔自四〕
(ゴザルの転)「ある」の丁寧な言い方。主に「…でごある」の形で用いる。浄瑠璃、冥途飛脚「友達に損かける忠兵衛では―・らぬ」
こ‐あるき【小歩き】
①小足に歩くこと。
②使い走りをする者。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「粋方仲間の―、貰ひ喰ひで暮して居つたを引き上げて」
こ‐あん【孤鞍】
一人馬に乗って行くこと。単騎。
ごあん・す
〔自サ変〕
(遊里語。ゴザンスの転)「来る」の尊敬語、また、「(で)ある」を丁寧にいう語として用いる。いらっしゃる。ございます。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「前は再々―・して何が怖うて逃げさんす」。浄瑠璃、傾城反魂香「何の気随で―・しよ」
こ‐あんどの【小安殿】
⇒こやすみどの
こい【凍】
(コユの連用形から)こごえること。継体紀「天下其の―を受くることあり」
こい【恋】コヒ
①一緒に生活できない人や亡くなった人に強くひかれて、切なく思うこと。また、そのこころ。特に、男女間の思慕の情。恋慕。恋愛。万葉集20「常陸さし行かむ雁もが吾あが―を記して付けて妹に知らせむ」。「―に身を焼く」
②植物や土地などに寄せる思慕の情。万葉集10「桜花時は過ぎねど見る人の―の盛りと今し散るらむ」
⇒恋に上下の隔てなし
⇒恋は曲者
⇒恋は思案の外
⇒恋は盲目
⇒恋は闇
こい【尰】コヒ
膝から下が腫はれる病気。脚気かっけの類。おめあし。蜻蛉日記上「片足に―つきたるに」
こい【請い・乞い】コヒ
こうこと。ねがうこと。たのみ。「―に応ずる」
こい【鯉】コヒ
コイ科の淡水産の硬骨魚。側線鱗が36枚あるというので六六魚りくりくぎょとも呼ぶが、実際には31〜38枚ほどの変異が見られる。2対の口ひげがあり、急な流れのない泥底の川や池を好む。日本では食用・観賞用として珍重され、また立身出世の象徴とされる。変種に錦鯉やドイツから輸入した革鯉などがある。鯉魚。土佐日記「―はなくて、鮒ふなよりはじめて、川のも海のも」
コイ
提供:東京動物園協会
 ⇒鯉の滝登り
こ‐い【木居】‥ヰ
鷹狩の鷹が木の枝にとまっていること。また、その木。後拾遺和歌集冬「とやがへるしらふの鷹の―をなみ雪げの空にあはせつるかな」
こ‐い【古意】
①古い意義。昔の意味。
②昔をなつかしむ気持。
こ‐い【虎威】‥ヰ
虎が群獣を恐れさせる威力。
こ‐い【故意】
①ことさらにたくらむこと。心あってすること。「―に行う」
②〔法〕自己の行為が一定の結果を生ずることを認識して或る行為をした場合の心理状態。犯意。↔過失
コイ【Khoi】
(「本当の人」の意のコイコイに由来)アフリカ南部に住み、牛・羊の牧畜と採集狩猟を主な生業としていた諸民族の総称。19世紀以降キリスト教化し、農業などに従事。ホッテントットと呼ばれていたが、現在はコイ・コイコイの呼称が用いられる。→サン
こ・い【濃い】
〔形〕[文]こ・し(ク)
①色が深い。古今和歌集物名「花の色はただひとさかり―・けれども」。「―・い緑色」
②染色(特に、紫・紅)の度合が強い。土佐日記「船には紅―・く良き衣着ず」。源氏物語空蝉「―・き綾の単襲ひとえがさねなめり」
③密度が高い。
㋐液体の濃度が高い。宇治拾遺物語3「見れば沈・丁子を―・く煎じて入れたり」。「茶を―・くいれる」
㋑(味・香・化粧などが)淡泊でない。濃厚である。後撰和歌集春「なほざりに折りつるものを梅の花―・き香にわれや衣染めてむ」。西大寺本最勝王経平安初期点「滋コキ味無けむ」。「吸物の味が―・い」「―・い化粧」
㋒(分布状態などが)密である。厚い。西大寺本最勝王経平安初期点「果実も並に滋コク繁くして」。「―・い眉」「霧が―・い」
㋓男女間の交情がこまやかである。つながりが密接である。傾城禁短気「よくよく分別して―・うならぬ中に見事な事をして、止めるが至極の要なり」。「―・い仲に水をさす」
④可能性・必然性などの程度が大である。「敗色が―・い」「疲労の色が―・い」「詐欺の疑いが―・い」
ご‐い【五位】‥ヰ
①位階の第5番目のもの。すなわち正五位または従五位。律令制では五位以上は格段に優遇された。
②ゴイサギの略。
ご‐い【五噫】
(後漢の梁鴻が世を嘆いて作った詩の名から。「噫」は嘆く声)世にいれられないのを嘆くこと。太平記2「持明院殿方の人々、案に相違して―を歌ふ者のみ多かりけり」
ご‐い【呉偉】‥ヰ
明代中期の画家。字は士英・次翁。号は魯夫・小仙。江夏(湖北省)の人。浙派の大家。(1459〜1508)
ご‐い【唔咿】
読書の声。咿唔。
ご‐い【語彙】‥ヰ
(vocabulary)一つの言語の、あるいはその中の特定の範囲についての、単語の総体。また、ある範囲の単語を集めて一定の順序に並べた書物。「日本語の―」「親族―」「近松―」
ご‐い【語意】
ことばの意味。語義。
こい‐あか・す【恋ひ明かす】コヒ‥
〔自四〕
恋しさのあまり寝られないで夜をあかす。万葉集13「君が目に恋ひや明さむ長き此の夜を」
こい‐あきびと【恋商人】コヒ‥
遊女。女郎。
こい‐あま・る【恋ひ余る】コヒ‥
〔自四〕
恋心が包みきれず外にあらわれる。万葉集17「隠沼こもりぬの下ゆ―・り」
こい‐う・ける【請い受ける・乞い受ける】コヒ‥
〔他下一〕[文]こひう・く(下二)
頼み求めて譲り渡される。
こい‐うた【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐うら【恋占】コヒ‥
恋についてのうらない。月詣和歌集「なほざりの手ずさみにする―も」
こい‐うら・む【恋ひ恨む】コヒ‥
〔他四・上二〕
恋い慕うあまりにかえってうらめしく思う。風雅和歌集恋「―・み君に心はなりはててあらぬ思ひもまぜぬ頃かな」
こ‐いえ【小家】‥イヘ
小さいそまつな家。源氏物語常夏「かかりける種ながら、あやしき―におひいでけること」
⇒こいえ‐がち【小家勝ち】
⇒こいえ‐ぎんみ【小家吟味】
こいえ‐がち【小家勝ち】‥イヘ‥
小家の多く並んでいること。源氏物語夕顔「げにいと―にむつかしげなるわたりの」
⇒こ‐いえ【小家】
こいえ‐ぎんみ【小家吟味】‥イヘ‥
名主が五人組・大家立会で、不審なものの取締りに借屋・店借たながり人を戸別に調べたこと。
⇒こ‐いえ【小家】
こいおしえ‐どり【恋教え鳥】コヒヲシヘ‥
(伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神に夫婦の道を教えたという説話に基づく)セキレイの異称。恋知り鳥。道教え鳥。
こい‐か【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐がき【濃柿】
濃い柿色。浄瑠璃、女殺油地獄「揃ひ羽織の―に、知恵の輪の大紋」
こい‐かぜ【恋風】コヒ‥
恋心の切なさを、風が身にしみわたるのにたとえていう語。日本永代蔵5「何時を知らぬ―恐ろし」
こい‐がたき【恋敵】コヒ‥
同じ人を恋している、恋の競争相手。
こい‐かわ【恋河】コヒカハ
恋の心の深いのを川の深いのにたとえていう語。夫木和歌抄22「―に沈むにつけて思ふかな我が身も石になるにやあるらむ」
こいかわ‐はるまち【恋川春町】コヒカハ‥
江戸中期の狂歌師・黄表紙作者・浮世絵師。本名、倉橋格。別号、寿山人・酒上不埒さけのうえのふらち。駿河小島の松平家の臣。江戸小石川春日町に住み、恋川春町はそのもじり。「金々先生栄花夢」「高漫斉行脚日記」などにより黄表紙創始者の位置を占め、それらはすべて自画作。(1744〜1789)
→文献資料[金々先生栄花夢]
こ‐いき【小息】
小さく吐く息。古今著聞集6「御物の常にも吹かれざらむをば、まづ―にて心みるべきなり」
こ‐いき【小意気・小粋】
①(「―すぎる」の形で)生意気なこと。浄瑠璃、曾我虎が磨「愛敬のない―すぎた旦那ぶつた顔付き」
②ちょっと粋いきなこと。何となく粋なこと。ちょっとしゃれていること。浮世床初「友達の女房は―であだで」。「―に踊る」「―な身なり」
ご‐いぎょう【呉偉業】‥ヰゲフ
明末・清初の詩人。字は駿公。号は梅村。明滅亡後、一時、清の国子監祭酒。清初三大家の一人。絵画・戯曲もよくした。詩文集「梅村家蔵藁」など。(1609〜1671)
こ‐いきん【顧維鈞】‥ヰ‥
(Gu Weijun)中国の学者・外交官。渡米しコロンビア大学卒業。1919年パリ平和会議全権、のち中華民国国際連盟代表、駐米大使。57年国際司法裁判所判事。回想録がある。(1888〜1985)
こい‐ぐさ【恋草】コヒ‥
恋の思いの激しいことを、草の生い茂るのにたとえていう語。万葉集4「―を力車に七車積みて恋ふらくわが心から」
こい‐くち【濃口】
①濃口醤油の略。↔薄口。
②醤油・ソースなどの色や味が濃いこと。
⇒こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】
こい‐ぐち【鯉口】コヒ‥
(楕円形で鯉の口に似ているからいう)
①刀の鞘さや口。→腰刀(図)。
②水仕事などをする時、よごれを防ぐために着る筒袖のように仕立てた布子ぬのこ。→袖(図)
⇒鯉口を切る
こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】‥シヤウ‥
色が濃い、一般的な醤油。↔薄口醤油
⇒こい‐くち【濃口】
⇒鯉の滝登り
こ‐い【木居】‥ヰ
鷹狩の鷹が木の枝にとまっていること。また、その木。後拾遺和歌集冬「とやがへるしらふの鷹の―をなみ雪げの空にあはせつるかな」
こ‐い【古意】
①古い意義。昔の意味。
②昔をなつかしむ気持。
こ‐い【虎威】‥ヰ
虎が群獣を恐れさせる威力。
こ‐い【故意】
①ことさらにたくらむこと。心あってすること。「―に行う」
②〔法〕自己の行為が一定の結果を生ずることを認識して或る行為をした場合の心理状態。犯意。↔過失
コイ【Khoi】
(「本当の人」の意のコイコイに由来)アフリカ南部に住み、牛・羊の牧畜と採集狩猟を主な生業としていた諸民族の総称。19世紀以降キリスト教化し、農業などに従事。ホッテントットと呼ばれていたが、現在はコイ・コイコイの呼称が用いられる。→サン
こ・い【濃い】
〔形〕[文]こ・し(ク)
①色が深い。古今和歌集物名「花の色はただひとさかり―・けれども」。「―・い緑色」
②染色(特に、紫・紅)の度合が強い。土佐日記「船には紅―・く良き衣着ず」。源氏物語空蝉「―・き綾の単襲ひとえがさねなめり」
③密度が高い。
㋐液体の濃度が高い。宇治拾遺物語3「見れば沈・丁子を―・く煎じて入れたり」。「茶を―・くいれる」
㋑(味・香・化粧などが)淡泊でない。濃厚である。後撰和歌集春「なほざりに折りつるものを梅の花―・き香にわれや衣染めてむ」。西大寺本最勝王経平安初期点「滋コキ味無けむ」。「吸物の味が―・い」「―・い化粧」
㋒(分布状態などが)密である。厚い。西大寺本最勝王経平安初期点「果実も並に滋コク繁くして」。「―・い眉」「霧が―・い」
㋓男女間の交情がこまやかである。つながりが密接である。傾城禁短気「よくよく分別して―・うならぬ中に見事な事をして、止めるが至極の要なり」。「―・い仲に水をさす」
④可能性・必然性などの程度が大である。「敗色が―・い」「疲労の色が―・い」「詐欺の疑いが―・い」
ご‐い【五位】‥ヰ
①位階の第5番目のもの。すなわち正五位または従五位。律令制では五位以上は格段に優遇された。
②ゴイサギの略。
ご‐い【五噫】
(後漢の梁鴻が世を嘆いて作った詩の名から。「噫」は嘆く声)世にいれられないのを嘆くこと。太平記2「持明院殿方の人々、案に相違して―を歌ふ者のみ多かりけり」
ご‐い【呉偉】‥ヰ
明代中期の画家。字は士英・次翁。号は魯夫・小仙。江夏(湖北省)の人。浙派の大家。(1459〜1508)
ご‐い【唔咿】
読書の声。咿唔。
ご‐い【語彙】‥ヰ
(vocabulary)一つの言語の、あるいはその中の特定の範囲についての、単語の総体。また、ある範囲の単語を集めて一定の順序に並べた書物。「日本語の―」「親族―」「近松―」
ご‐い【語意】
ことばの意味。語義。
こい‐あか・す【恋ひ明かす】コヒ‥
〔自四〕
恋しさのあまり寝られないで夜をあかす。万葉集13「君が目に恋ひや明さむ長き此の夜を」
こい‐あきびと【恋商人】コヒ‥
遊女。女郎。
こい‐あま・る【恋ひ余る】コヒ‥
〔自四〕
恋心が包みきれず外にあらわれる。万葉集17「隠沼こもりぬの下ゆ―・り」
こい‐う・ける【請い受ける・乞い受ける】コヒ‥
〔他下一〕[文]こひう・く(下二)
頼み求めて譲り渡される。
こい‐うた【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐うら【恋占】コヒ‥
恋についてのうらない。月詣和歌集「なほざりの手ずさみにする―も」
こい‐うら・む【恋ひ恨む】コヒ‥
〔他四・上二〕
恋い慕うあまりにかえってうらめしく思う。風雅和歌集恋「―・み君に心はなりはててあらぬ思ひもまぜぬ頃かな」
こ‐いえ【小家】‥イヘ
小さいそまつな家。源氏物語常夏「かかりける種ながら、あやしき―におひいでけること」
⇒こいえ‐がち【小家勝ち】
⇒こいえ‐ぎんみ【小家吟味】
こいえ‐がち【小家勝ち】‥イヘ‥
小家の多く並んでいること。源氏物語夕顔「げにいと―にむつかしげなるわたりの」
⇒こ‐いえ【小家】
こいえ‐ぎんみ【小家吟味】‥イヘ‥
名主が五人組・大家立会で、不審なものの取締りに借屋・店借たながり人を戸別に調べたこと。
⇒こ‐いえ【小家】
こいおしえ‐どり【恋教え鳥】コヒヲシヘ‥
(伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神に夫婦の道を教えたという説話に基づく)セキレイの異称。恋知り鳥。道教え鳥。
こい‐か【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐がき【濃柿】
濃い柿色。浄瑠璃、女殺油地獄「揃ひ羽織の―に、知恵の輪の大紋」
こい‐かぜ【恋風】コヒ‥
恋心の切なさを、風が身にしみわたるのにたとえていう語。日本永代蔵5「何時を知らぬ―恐ろし」
こい‐がたき【恋敵】コヒ‥
同じ人を恋している、恋の競争相手。
こい‐かわ【恋河】コヒカハ
恋の心の深いのを川の深いのにたとえていう語。夫木和歌抄22「―に沈むにつけて思ふかな我が身も石になるにやあるらむ」
こいかわ‐はるまち【恋川春町】コヒカハ‥
江戸中期の狂歌師・黄表紙作者・浮世絵師。本名、倉橋格。別号、寿山人・酒上不埒さけのうえのふらち。駿河小島の松平家の臣。江戸小石川春日町に住み、恋川春町はそのもじり。「金々先生栄花夢」「高漫斉行脚日記」などにより黄表紙創始者の位置を占め、それらはすべて自画作。(1744〜1789)
→文献資料[金々先生栄花夢]
こ‐いき【小息】
小さく吐く息。古今著聞集6「御物の常にも吹かれざらむをば、まづ―にて心みるべきなり」
こ‐いき【小意気・小粋】
①(「―すぎる」の形で)生意気なこと。浄瑠璃、曾我虎が磨「愛敬のない―すぎた旦那ぶつた顔付き」
②ちょっと粋いきなこと。何となく粋なこと。ちょっとしゃれていること。浮世床初「友達の女房は―であだで」。「―に踊る」「―な身なり」
ご‐いぎょう【呉偉業】‥ヰゲフ
明末・清初の詩人。字は駿公。号は梅村。明滅亡後、一時、清の国子監祭酒。清初三大家の一人。絵画・戯曲もよくした。詩文集「梅村家蔵藁」など。(1609〜1671)
こ‐いきん【顧維鈞】‥ヰ‥
(Gu Weijun)中国の学者・外交官。渡米しコロンビア大学卒業。1919年パリ平和会議全権、のち中華民国国際連盟代表、駐米大使。57年国際司法裁判所判事。回想録がある。(1888〜1985)
こい‐ぐさ【恋草】コヒ‥
恋の思いの激しいことを、草の生い茂るのにたとえていう語。万葉集4「―を力車に七車積みて恋ふらくわが心から」
こい‐くち【濃口】
①濃口醤油の略。↔薄口。
②醤油・ソースなどの色や味が濃いこと。
⇒こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】
こい‐ぐち【鯉口】コヒ‥
(楕円形で鯉の口に似ているからいう)
①刀の鞘さや口。→腰刀(図)。
②水仕事などをする時、よごれを防ぐために着る筒袖のように仕立てた布子ぬのこ。→袖(図)
⇒鯉口を切る
こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】‥シヤウ‥
色が濃い、一般的な醤油。↔薄口醤油
⇒こい‐くち【濃口】
 こ‐あがり【小上がり】
小料理屋などで、客が気軽に上がれるよう、簡単な仕切りだけで土間と仕切られた座敷。
コア‐カリキュラム【core curriculum】
教科の枠にとらわれず、学習の核となる課題や教材を中心に編成した教育課程。それに取り組む経験の過程を共通必須とする。アメリカの進歩主義教育において実施し、日本でも第二次大戦後数年間試みた。
こ‐あきない【小商い】‥アキナヒ
わずかの資金で行う小規模のあきない。
こ‐あきんど【小商人】
少しの資金で、小規模の商いをする商人。
ご‐あく【五悪】
①〔仏〕五戒にそむくこと。殺生せっしょう・偸盗ちゅうとう・邪淫・妄語・飲酒おんじゅの五悪事。→五戒。
②仁・義・礼・智・信の五常にそむくこと。
ご‐あくしゅ【五悪趣】
〔仏〕衆生しゅじょうが善悪の業因によって趣おもむき住む五つの場所、すなわち天・人間・畜生・餓鬼・地獄の総称。五趣。五悪道。
こ‐あげ【小揚】
①船から河岸に荷揚げすること。また、その人夫。浄瑠璃、鎌倉三代記「お供先で、―がいるなら、われらを買うて貰ふぞや」
②客を乗せて遊郭に通った駕籠かごかき。浮世草子、好色敗毒散「足の駕のりものには―を雇ふ世話もなし」
③義太夫節で、端場はばの前、一場の冒頭の部分。
こ‐あざ【小字】
町村内の大字おおあざをさらに細かく分けた称。
ご‐あさって【五明後日】
(西日本で)明々々後日。しあさって1の次の日。
コア‐サンプラー【core sampler】
土壌や岩石の試料を採取するための筒状の標本採掘器具。
こ‐あし【小足】
足並を細かくきざんで歩くこと。きざみあし。日葡辞書「コアシニアユム」。浄瑠璃、大職冠「とどろとどろと―を使ひ」
こ‐あじ【小味】‥アヂ
①こまやかで、趣ある味。↔大味。
②(取引用語)相場が動き始めて、売買に面白みが湧いてくること。
こ‐アジア‐しょご【古アジア諸語】
(Paleo-Asiatic)アジア北東端部の言語のうち、アルタイ諸語・ウラル諸語以外の諸言語の総称。チュクチ・コリヤーク・カムチャダール・ユカギール・ニヴヒ・ケットなどの諸民族の言語を含むが、類縁関係は不明。旧アジア諸語。
こ‐あじさい【小紫陽花】‥アヂサヰ
ユキノシタ科の小低木。関東地方以西の各地の山地に多い。落葉性で高さ1メートル余。葉は対生し倒卵形、上半部に粗大な鋸歯がある。夏、茎頂に上部が平たい散房花序をつけ、淡青色の小花を密生。アジサイの仲間だが花序の外周部に装飾花はつかない。
コア‐システム【core system】
建築計画の一方式。通路や階段、台所・便所・浴室などサービス‐スペースを集中化し、建物の核とする方法。動線・配管などが能率的に配置できる。
コアセルベート【coacervate】
溶液中で親水コロイドの粒子が集合し、溶液との間に一定の平衡を保つ小さなコロイド液(液滴)となったもの。オパーリンは、細胞の原形質との類似性から、生命発生の一段階と考えた。
コア‐タイム【core time】
フレックス‐タイム制で、各人が共通して就労すべき基幹的な時間帯。
こ‐あたり【小当り】
①試みに他人の意中などを探ってみること。「―に当たってみる」
②蒔絵まきえで、直接器物に下絵を描くこと。
ゴア‐テックス【Gore-Tex】
テフロン系樹脂を布地にコーティングした衣料素材。撥水性・通気性に優れる。商標名。
コア‐ドリル【core drill】
中空の円筒状の刃を持つドリル。コンクリートや石材の穴あけ、地質・道路の試料採取、削り穴の仕上げ加工などに用いる。
こ‐あま・い【小甘い】
〔形〕
(取引用語)相場がやや下がり気味である。
こ‐あみがさ【小編笠】
饅頭形で腰高に編んだ編笠。江戸初期、槍持・ほおずき売・風車売などがかぶった。
小編笠
こ‐あがり【小上がり】
小料理屋などで、客が気軽に上がれるよう、簡単な仕切りだけで土間と仕切られた座敷。
コア‐カリキュラム【core curriculum】
教科の枠にとらわれず、学習の核となる課題や教材を中心に編成した教育課程。それに取り組む経験の過程を共通必須とする。アメリカの進歩主義教育において実施し、日本でも第二次大戦後数年間試みた。
こ‐あきない【小商い】‥アキナヒ
わずかの資金で行う小規模のあきない。
こ‐あきんど【小商人】
少しの資金で、小規模の商いをする商人。
ご‐あく【五悪】
①〔仏〕五戒にそむくこと。殺生せっしょう・偸盗ちゅうとう・邪淫・妄語・飲酒おんじゅの五悪事。→五戒。
②仁・義・礼・智・信の五常にそむくこと。
ご‐あくしゅ【五悪趣】
〔仏〕衆生しゅじょうが善悪の業因によって趣おもむき住む五つの場所、すなわち天・人間・畜生・餓鬼・地獄の総称。五趣。五悪道。
こ‐あげ【小揚】
①船から河岸に荷揚げすること。また、その人夫。浄瑠璃、鎌倉三代記「お供先で、―がいるなら、われらを買うて貰ふぞや」
②客を乗せて遊郭に通った駕籠かごかき。浮世草子、好色敗毒散「足の駕のりものには―を雇ふ世話もなし」
③義太夫節で、端場はばの前、一場の冒頭の部分。
こ‐あざ【小字】
町村内の大字おおあざをさらに細かく分けた称。
ご‐あさって【五明後日】
(西日本で)明々々後日。しあさって1の次の日。
コア‐サンプラー【core sampler】
土壌や岩石の試料を採取するための筒状の標本採掘器具。
こ‐あし【小足】
足並を細かくきざんで歩くこと。きざみあし。日葡辞書「コアシニアユム」。浄瑠璃、大職冠「とどろとどろと―を使ひ」
こ‐あじ【小味】‥アヂ
①こまやかで、趣ある味。↔大味。
②(取引用語)相場が動き始めて、売買に面白みが湧いてくること。
こ‐アジア‐しょご【古アジア諸語】
(Paleo-Asiatic)アジア北東端部の言語のうち、アルタイ諸語・ウラル諸語以外の諸言語の総称。チュクチ・コリヤーク・カムチャダール・ユカギール・ニヴヒ・ケットなどの諸民族の言語を含むが、類縁関係は不明。旧アジア諸語。
こ‐あじさい【小紫陽花】‥アヂサヰ
ユキノシタ科の小低木。関東地方以西の各地の山地に多い。落葉性で高さ1メートル余。葉は対生し倒卵形、上半部に粗大な鋸歯がある。夏、茎頂に上部が平たい散房花序をつけ、淡青色の小花を密生。アジサイの仲間だが花序の外周部に装飾花はつかない。
コア‐システム【core system】
建築計画の一方式。通路や階段、台所・便所・浴室などサービス‐スペースを集中化し、建物の核とする方法。動線・配管などが能率的に配置できる。
コアセルベート【coacervate】
溶液中で親水コロイドの粒子が集合し、溶液との間に一定の平衡を保つ小さなコロイド液(液滴)となったもの。オパーリンは、細胞の原形質との類似性から、生命発生の一段階と考えた。
コア‐タイム【core time】
フレックス‐タイム制で、各人が共通して就労すべき基幹的な時間帯。
こ‐あたり【小当り】
①試みに他人の意中などを探ってみること。「―に当たってみる」
②蒔絵まきえで、直接器物に下絵を描くこと。
ゴア‐テックス【Gore-Tex】
テフロン系樹脂を布地にコーティングした衣料素材。撥水性・通気性に優れる。商標名。
コア‐ドリル【core drill】
中空の円筒状の刃を持つドリル。コンクリートや石材の穴あけ、地質・道路の試料採取、削り穴の仕上げ加工などに用いる。
こ‐あま・い【小甘い】
〔形〕
(取引用語)相場がやや下がり気味である。
こ‐あみがさ【小編笠】
饅頭形で腰高に編んだ編笠。江戸初期、槍持・ほおずき売・風車売などがかぶった。
小編笠
 こあみ‐ざ【小網座】
〔天〕(→)レチクル座の別称。
こ‐あゆ【小鮎】
①鮎の幼魚。3〜4月ごろ、川をさかのぼる。〈[季]春〉
②湖中に陸封され、成魚の体形とならず小形のまま成熟した鮎。河川に放流すると普通の大きさの鮎となる。
コアラ【koala】
フクロネズミ目(有袋類)コアラ科の哺乳類。体長70センチメートルほどで、尾はほとんどない。体毛は灰色から黄褐色。耳は大きく、白く柔らかい毛に覆われる。オーストラリア東部の低地にのみ生息、ユーカリの葉しか食べない。動作は鈍く、ほとんど樹上で生活。毛皮利用とペットとするため乱獲され、絶滅しかかったが、保護が成功してかなり回復。フクログマ。コモリグマ。
コアラ
こあみ‐ざ【小網座】
〔天〕(→)レチクル座の別称。
こ‐あゆ【小鮎】
①鮎の幼魚。3〜4月ごろ、川をさかのぼる。〈[季]春〉
②湖中に陸封され、成魚の体形とならず小形のまま成熟した鮎。河川に放流すると普通の大きさの鮎となる。
コアラ【koala】
フクロネズミ目(有袋類)コアラ科の哺乳類。体長70センチメートルほどで、尾はほとんどない。体毛は灰色から黄褐色。耳は大きく、白く柔らかい毛に覆われる。オーストラリア東部の低地にのみ生息、ユーカリの葉しか食べない。動作は鈍く、ほとんど樹上で生活。毛皮利用とペットとするため乱獲され、絶滅しかかったが、保護が成功してかなり回復。フクログマ。コモリグマ。
コアラ
 コアラ
提供:東京動物園協会
コアラ
提供:東京動物園協会
 ご‐あ・る
〔自四〕
(ゴザルの転)「ある」の丁寧な言い方。主に「…でごある」の形で用いる。浄瑠璃、冥途飛脚「友達に損かける忠兵衛では―・らぬ」
こ‐あるき【小歩き】
①小足に歩くこと。
②使い走りをする者。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「粋方仲間の―、貰ひ喰ひで暮して居つたを引き上げて」
こ‐あん【孤鞍】
一人馬に乗って行くこと。単騎。
ごあん・す
〔自サ変〕
(遊里語。ゴザンスの転)「来る」の尊敬語、また、「(で)ある」を丁寧にいう語として用いる。いらっしゃる。ございます。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「前は再々―・して何が怖うて逃げさんす」。浄瑠璃、傾城反魂香「何の気随で―・しよ」
こ‐あんどの【小安殿】
⇒こやすみどの
こい【凍】
(コユの連用形から)こごえること。継体紀「天下其の―を受くることあり」
こい【恋】コヒ
①一緒に生活できない人や亡くなった人に強くひかれて、切なく思うこと。また、そのこころ。特に、男女間の思慕の情。恋慕。恋愛。万葉集20「常陸さし行かむ雁もが吾あが―を記して付けて妹に知らせむ」。「―に身を焼く」
②植物や土地などに寄せる思慕の情。万葉集10「桜花時は過ぎねど見る人の―の盛りと今し散るらむ」
⇒恋に上下の隔てなし
⇒恋は曲者
⇒恋は思案の外
⇒恋は盲目
⇒恋は闇
こい【尰】コヒ
膝から下が腫はれる病気。脚気かっけの類。おめあし。蜻蛉日記上「片足に―つきたるに」
こい【請い・乞い】コヒ
こうこと。ねがうこと。たのみ。「―に応ずる」
こい【鯉】コヒ
コイ科の淡水産の硬骨魚。側線鱗が36枚あるというので六六魚りくりくぎょとも呼ぶが、実際には31〜38枚ほどの変異が見られる。2対の口ひげがあり、急な流れのない泥底の川や池を好む。日本では食用・観賞用として珍重され、また立身出世の象徴とされる。変種に錦鯉やドイツから輸入した革鯉などがある。鯉魚。土佐日記「―はなくて、鮒ふなよりはじめて、川のも海のも」
コイ
提供:東京動物園協会
ご‐あ・る
〔自四〕
(ゴザルの転)「ある」の丁寧な言い方。主に「…でごある」の形で用いる。浄瑠璃、冥途飛脚「友達に損かける忠兵衛では―・らぬ」
こ‐あるき【小歩き】
①小足に歩くこと。
②使い走りをする者。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「粋方仲間の―、貰ひ喰ひで暮して居つたを引き上げて」
こ‐あん【孤鞍】
一人馬に乗って行くこと。単騎。
ごあん・す
〔自サ変〕
(遊里語。ゴザンスの転)「来る」の尊敬語、また、「(で)ある」を丁寧にいう語として用いる。いらっしゃる。ございます。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「前は再々―・して何が怖うて逃げさんす」。浄瑠璃、傾城反魂香「何の気随で―・しよ」
こ‐あんどの【小安殿】
⇒こやすみどの
こい【凍】
(コユの連用形から)こごえること。継体紀「天下其の―を受くることあり」
こい【恋】コヒ
①一緒に生活できない人や亡くなった人に強くひかれて、切なく思うこと。また、そのこころ。特に、男女間の思慕の情。恋慕。恋愛。万葉集20「常陸さし行かむ雁もが吾あが―を記して付けて妹に知らせむ」。「―に身を焼く」
②植物や土地などに寄せる思慕の情。万葉集10「桜花時は過ぎねど見る人の―の盛りと今し散るらむ」
⇒恋に上下の隔てなし
⇒恋は曲者
⇒恋は思案の外
⇒恋は盲目
⇒恋は闇
こい【尰】コヒ
膝から下が腫はれる病気。脚気かっけの類。おめあし。蜻蛉日記上「片足に―つきたるに」
こい【請い・乞い】コヒ
こうこと。ねがうこと。たのみ。「―に応ずる」
こい【鯉】コヒ
コイ科の淡水産の硬骨魚。側線鱗が36枚あるというので六六魚りくりくぎょとも呼ぶが、実際には31〜38枚ほどの変異が見られる。2対の口ひげがあり、急な流れのない泥底の川や池を好む。日本では食用・観賞用として珍重され、また立身出世の象徴とされる。変種に錦鯉やドイツから輸入した革鯉などがある。鯉魚。土佐日記「―はなくて、鮒ふなよりはじめて、川のも海のも」
コイ
提供:東京動物園協会
 ⇒鯉の滝登り
こ‐い【木居】‥ヰ
鷹狩の鷹が木の枝にとまっていること。また、その木。後拾遺和歌集冬「とやがへるしらふの鷹の―をなみ雪げの空にあはせつるかな」
こ‐い【古意】
①古い意義。昔の意味。
②昔をなつかしむ気持。
こ‐い【虎威】‥ヰ
虎が群獣を恐れさせる威力。
こ‐い【故意】
①ことさらにたくらむこと。心あってすること。「―に行う」
②〔法〕自己の行為が一定の結果を生ずることを認識して或る行為をした場合の心理状態。犯意。↔過失
コイ【Khoi】
(「本当の人」の意のコイコイに由来)アフリカ南部に住み、牛・羊の牧畜と採集狩猟を主な生業としていた諸民族の総称。19世紀以降キリスト教化し、農業などに従事。ホッテントットと呼ばれていたが、現在はコイ・コイコイの呼称が用いられる。→サン
こ・い【濃い】
〔形〕[文]こ・し(ク)
①色が深い。古今和歌集物名「花の色はただひとさかり―・けれども」。「―・い緑色」
②染色(特に、紫・紅)の度合が強い。土佐日記「船には紅―・く良き衣着ず」。源氏物語空蝉「―・き綾の単襲ひとえがさねなめり」
③密度が高い。
㋐液体の濃度が高い。宇治拾遺物語3「見れば沈・丁子を―・く煎じて入れたり」。「茶を―・くいれる」
㋑(味・香・化粧などが)淡泊でない。濃厚である。後撰和歌集春「なほざりに折りつるものを梅の花―・き香にわれや衣染めてむ」。西大寺本最勝王経平安初期点「滋コキ味無けむ」。「吸物の味が―・い」「―・い化粧」
㋒(分布状態などが)密である。厚い。西大寺本最勝王経平安初期点「果実も並に滋コク繁くして」。「―・い眉」「霧が―・い」
㋓男女間の交情がこまやかである。つながりが密接である。傾城禁短気「よくよく分別して―・うならぬ中に見事な事をして、止めるが至極の要なり」。「―・い仲に水をさす」
④可能性・必然性などの程度が大である。「敗色が―・い」「疲労の色が―・い」「詐欺の疑いが―・い」
ご‐い【五位】‥ヰ
①位階の第5番目のもの。すなわち正五位または従五位。律令制では五位以上は格段に優遇された。
②ゴイサギの略。
ご‐い【五噫】
(後漢の梁鴻が世を嘆いて作った詩の名から。「噫」は嘆く声)世にいれられないのを嘆くこと。太平記2「持明院殿方の人々、案に相違して―を歌ふ者のみ多かりけり」
ご‐い【呉偉】‥ヰ
明代中期の画家。字は士英・次翁。号は魯夫・小仙。江夏(湖北省)の人。浙派の大家。(1459〜1508)
ご‐い【唔咿】
読書の声。咿唔。
ご‐い【語彙】‥ヰ
(vocabulary)一つの言語の、あるいはその中の特定の範囲についての、単語の総体。また、ある範囲の単語を集めて一定の順序に並べた書物。「日本語の―」「親族―」「近松―」
ご‐い【語意】
ことばの意味。語義。
こい‐あか・す【恋ひ明かす】コヒ‥
〔自四〕
恋しさのあまり寝られないで夜をあかす。万葉集13「君が目に恋ひや明さむ長き此の夜を」
こい‐あきびと【恋商人】コヒ‥
遊女。女郎。
こい‐あま・る【恋ひ余る】コヒ‥
〔自四〕
恋心が包みきれず外にあらわれる。万葉集17「隠沼こもりぬの下ゆ―・り」
こい‐う・ける【請い受ける・乞い受ける】コヒ‥
〔他下一〕[文]こひう・く(下二)
頼み求めて譲り渡される。
こい‐うた【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐うら【恋占】コヒ‥
恋についてのうらない。月詣和歌集「なほざりの手ずさみにする―も」
こい‐うら・む【恋ひ恨む】コヒ‥
〔他四・上二〕
恋い慕うあまりにかえってうらめしく思う。風雅和歌集恋「―・み君に心はなりはててあらぬ思ひもまぜぬ頃かな」
こ‐いえ【小家】‥イヘ
小さいそまつな家。源氏物語常夏「かかりける種ながら、あやしき―におひいでけること」
⇒こいえ‐がち【小家勝ち】
⇒こいえ‐ぎんみ【小家吟味】
こいえ‐がち【小家勝ち】‥イヘ‥
小家の多く並んでいること。源氏物語夕顔「げにいと―にむつかしげなるわたりの」
⇒こ‐いえ【小家】
こいえ‐ぎんみ【小家吟味】‥イヘ‥
名主が五人組・大家立会で、不審なものの取締りに借屋・店借たながり人を戸別に調べたこと。
⇒こ‐いえ【小家】
こいおしえ‐どり【恋教え鳥】コヒヲシヘ‥
(伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神に夫婦の道を教えたという説話に基づく)セキレイの異称。恋知り鳥。道教え鳥。
こい‐か【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐がき【濃柿】
濃い柿色。浄瑠璃、女殺油地獄「揃ひ羽織の―に、知恵の輪の大紋」
こい‐かぜ【恋風】コヒ‥
恋心の切なさを、風が身にしみわたるのにたとえていう語。日本永代蔵5「何時を知らぬ―恐ろし」
こい‐がたき【恋敵】コヒ‥
同じ人を恋している、恋の競争相手。
こい‐かわ【恋河】コヒカハ
恋の心の深いのを川の深いのにたとえていう語。夫木和歌抄22「―に沈むにつけて思ふかな我が身も石になるにやあるらむ」
こいかわ‐はるまち【恋川春町】コヒカハ‥
江戸中期の狂歌師・黄表紙作者・浮世絵師。本名、倉橋格。別号、寿山人・酒上不埒さけのうえのふらち。駿河小島の松平家の臣。江戸小石川春日町に住み、恋川春町はそのもじり。「金々先生栄花夢」「高漫斉行脚日記」などにより黄表紙創始者の位置を占め、それらはすべて自画作。(1744〜1789)
→文献資料[金々先生栄花夢]
こ‐いき【小息】
小さく吐く息。古今著聞集6「御物の常にも吹かれざらむをば、まづ―にて心みるべきなり」
こ‐いき【小意気・小粋】
①(「―すぎる」の形で)生意気なこと。浄瑠璃、曾我虎が磨「愛敬のない―すぎた旦那ぶつた顔付き」
②ちょっと粋いきなこと。何となく粋なこと。ちょっとしゃれていること。浮世床初「友達の女房は―であだで」。「―に踊る」「―な身なり」
ご‐いぎょう【呉偉業】‥ヰゲフ
明末・清初の詩人。字は駿公。号は梅村。明滅亡後、一時、清の国子監祭酒。清初三大家の一人。絵画・戯曲もよくした。詩文集「梅村家蔵藁」など。(1609〜1671)
こ‐いきん【顧維鈞】‥ヰ‥
(Gu Weijun)中国の学者・外交官。渡米しコロンビア大学卒業。1919年パリ平和会議全権、のち中華民国国際連盟代表、駐米大使。57年国際司法裁判所判事。回想録がある。(1888〜1985)
こい‐ぐさ【恋草】コヒ‥
恋の思いの激しいことを、草の生い茂るのにたとえていう語。万葉集4「―を力車に七車積みて恋ふらくわが心から」
こい‐くち【濃口】
①濃口醤油の略。↔薄口。
②醤油・ソースなどの色や味が濃いこと。
⇒こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】
こい‐ぐち【鯉口】コヒ‥
(楕円形で鯉の口に似ているからいう)
①刀の鞘さや口。→腰刀(図)。
②水仕事などをする時、よごれを防ぐために着る筒袖のように仕立てた布子ぬのこ。→袖(図)
⇒鯉口を切る
こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】‥シヤウ‥
色が濃い、一般的な醤油。↔薄口醤油
⇒こい‐くち【濃口】
⇒鯉の滝登り
こ‐い【木居】‥ヰ
鷹狩の鷹が木の枝にとまっていること。また、その木。後拾遺和歌集冬「とやがへるしらふの鷹の―をなみ雪げの空にあはせつるかな」
こ‐い【古意】
①古い意義。昔の意味。
②昔をなつかしむ気持。
こ‐い【虎威】‥ヰ
虎が群獣を恐れさせる威力。
こ‐い【故意】
①ことさらにたくらむこと。心あってすること。「―に行う」
②〔法〕自己の行為が一定の結果を生ずることを認識して或る行為をした場合の心理状態。犯意。↔過失
コイ【Khoi】
(「本当の人」の意のコイコイに由来)アフリカ南部に住み、牛・羊の牧畜と採集狩猟を主な生業としていた諸民族の総称。19世紀以降キリスト教化し、農業などに従事。ホッテントットと呼ばれていたが、現在はコイ・コイコイの呼称が用いられる。→サン
こ・い【濃い】
〔形〕[文]こ・し(ク)
①色が深い。古今和歌集物名「花の色はただひとさかり―・けれども」。「―・い緑色」
②染色(特に、紫・紅)の度合が強い。土佐日記「船には紅―・く良き衣着ず」。源氏物語空蝉「―・き綾の単襲ひとえがさねなめり」
③密度が高い。
㋐液体の濃度が高い。宇治拾遺物語3「見れば沈・丁子を―・く煎じて入れたり」。「茶を―・くいれる」
㋑(味・香・化粧などが)淡泊でない。濃厚である。後撰和歌集春「なほざりに折りつるものを梅の花―・き香にわれや衣染めてむ」。西大寺本最勝王経平安初期点「滋コキ味無けむ」。「吸物の味が―・い」「―・い化粧」
㋒(分布状態などが)密である。厚い。西大寺本最勝王経平安初期点「果実も並に滋コク繁くして」。「―・い眉」「霧が―・い」
㋓男女間の交情がこまやかである。つながりが密接である。傾城禁短気「よくよく分別して―・うならぬ中に見事な事をして、止めるが至極の要なり」。「―・い仲に水をさす」
④可能性・必然性などの程度が大である。「敗色が―・い」「疲労の色が―・い」「詐欺の疑いが―・い」
ご‐い【五位】‥ヰ
①位階の第5番目のもの。すなわち正五位または従五位。律令制では五位以上は格段に優遇された。
②ゴイサギの略。
ご‐い【五噫】
(後漢の梁鴻が世を嘆いて作った詩の名から。「噫」は嘆く声)世にいれられないのを嘆くこと。太平記2「持明院殿方の人々、案に相違して―を歌ふ者のみ多かりけり」
ご‐い【呉偉】‥ヰ
明代中期の画家。字は士英・次翁。号は魯夫・小仙。江夏(湖北省)の人。浙派の大家。(1459〜1508)
ご‐い【唔咿】
読書の声。咿唔。
ご‐い【語彙】‥ヰ
(vocabulary)一つの言語の、あるいはその中の特定の範囲についての、単語の総体。また、ある範囲の単語を集めて一定の順序に並べた書物。「日本語の―」「親族―」「近松―」
ご‐い【語意】
ことばの意味。語義。
こい‐あか・す【恋ひ明かす】コヒ‥
〔自四〕
恋しさのあまり寝られないで夜をあかす。万葉集13「君が目に恋ひや明さむ長き此の夜を」
こい‐あきびと【恋商人】コヒ‥
遊女。女郎。
こい‐あま・る【恋ひ余る】コヒ‥
〔自四〕
恋心が包みきれず外にあらわれる。万葉集17「隠沼こもりぬの下ゆ―・り」
こい‐う・ける【請い受ける・乞い受ける】コヒ‥
〔他下一〕[文]こひう・く(下二)
頼み求めて譲り渡される。
こい‐うた【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐うら【恋占】コヒ‥
恋についてのうらない。月詣和歌集「なほざりの手ずさみにする―も」
こい‐うら・む【恋ひ恨む】コヒ‥
〔他四・上二〕
恋い慕うあまりにかえってうらめしく思う。風雅和歌集恋「―・み君に心はなりはててあらぬ思ひもまぜぬ頃かな」
こ‐いえ【小家】‥イヘ
小さいそまつな家。源氏物語常夏「かかりける種ながら、あやしき―におひいでけること」
⇒こいえ‐がち【小家勝ち】
⇒こいえ‐ぎんみ【小家吟味】
こいえ‐がち【小家勝ち】‥イヘ‥
小家の多く並んでいること。源氏物語夕顔「げにいと―にむつかしげなるわたりの」
⇒こ‐いえ【小家】
こいえ‐ぎんみ【小家吟味】‥イヘ‥
名主が五人組・大家立会で、不審なものの取締りに借屋・店借たながり人を戸別に調べたこと。
⇒こ‐いえ【小家】
こいおしえ‐どり【恋教え鳥】コヒヲシヘ‥
(伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ2神に夫婦の道を教えたという説話に基づく)セキレイの異称。恋知り鳥。道教え鳥。
こい‐か【恋歌】コヒ‥
⇒こいのうた
こい‐がき【濃柿】
濃い柿色。浄瑠璃、女殺油地獄「揃ひ羽織の―に、知恵の輪の大紋」
こい‐かぜ【恋風】コヒ‥
恋心の切なさを、風が身にしみわたるのにたとえていう語。日本永代蔵5「何時を知らぬ―恐ろし」
こい‐がたき【恋敵】コヒ‥
同じ人を恋している、恋の競争相手。
こい‐かわ【恋河】コヒカハ
恋の心の深いのを川の深いのにたとえていう語。夫木和歌抄22「―に沈むにつけて思ふかな我が身も石になるにやあるらむ」
こいかわ‐はるまち【恋川春町】コヒカハ‥
江戸中期の狂歌師・黄表紙作者・浮世絵師。本名、倉橋格。別号、寿山人・酒上不埒さけのうえのふらち。駿河小島の松平家の臣。江戸小石川春日町に住み、恋川春町はそのもじり。「金々先生栄花夢」「高漫斉行脚日記」などにより黄表紙創始者の位置を占め、それらはすべて自画作。(1744〜1789)
→文献資料[金々先生栄花夢]
こ‐いき【小息】
小さく吐く息。古今著聞集6「御物の常にも吹かれざらむをば、まづ―にて心みるべきなり」
こ‐いき【小意気・小粋】
①(「―すぎる」の形で)生意気なこと。浄瑠璃、曾我虎が磨「愛敬のない―すぎた旦那ぶつた顔付き」
②ちょっと粋いきなこと。何となく粋なこと。ちょっとしゃれていること。浮世床初「友達の女房は―であだで」。「―に踊る」「―な身なり」
ご‐いぎょう【呉偉業】‥ヰゲフ
明末・清初の詩人。字は駿公。号は梅村。明滅亡後、一時、清の国子監祭酒。清初三大家の一人。絵画・戯曲もよくした。詩文集「梅村家蔵藁」など。(1609〜1671)
こ‐いきん【顧維鈞】‥ヰ‥
(Gu Weijun)中国の学者・外交官。渡米しコロンビア大学卒業。1919年パリ平和会議全権、のち中華民国国際連盟代表、駐米大使。57年国際司法裁判所判事。回想録がある。(1888〜1985)
こい‐ぐさ【恋草】コヒ‥
恋の思いの激しいことを、草の生い茂るのにたとえていう語。万葉集4「―を力車に七車積みて恋ふらくわが心から」
こい‐くち【濃口】
①濃口醤油の略。↔薄口。
②醤油・ソースなどの色や味が濃いこと。
⇒こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】
こい‐ぐち【鯉口】コヒ‥
(楕円形で鯉の口に似ているからいう)
①刀の鞘さや口。→腰刀(図)。
②水仕事などをする時、よごれを防ぐために着る筒袖のように仕立てた布子ぬのこ。→袖(図)
⇒鯉口を切る
こいくち‐しょうゆ【濃口醤油】‥シヤウ‥
色が濃い、一般的な醤油。↔薄口醤油
⇒こい‐くち【濃口】
こ‐ぶん【子分】🔗⭐🔉
こ‐ぶん【子分】
①仮に子として取り扱うもの。義子。日本永代蔵5「是を―にして家を渡し、相応の娵よめを尋ねけるに」
②(「乾児」「乾分」とも書く)親分に従属する部下。てした。てか。↔親分。
③利息。〈日葡辞書〉
ひ【乾・干】🔗⭐🔉
ひ【乾・干】
ひること。かわき。「―のよい海苔」
ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】🔗⭐🔉
ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】
〔自五〕
①全くかわききる。「田が―・る」
②すっかり潮がひいてしまう。
③生計が立たなくなる。飢える。「あごが―・る」
ひ‐うお【干魚・乾魚】‥ウヲ🔗⭐🔉
ひ‐うお【干魚・乾魚】‥ウヲ
魚のひもの。魚の内臓を取りのぞいて乾したもの。ひいお。
ひ‐がし【干菓子・乾菓子】‥グワ‥🔗⭐🔉
ひ‐がし【干菓子・乾菓子】‥グワ‥
生菓子に対する、水分の少ない和菓子の総称。粔籹おこし・落雁らくがん・煎餅せんべいの類。
干菓子
撮影:関戸 勇


ひ‐ごえ【乾声・失声】‥ゴヱ🔗⭐🔉
ひ‐ごえ【乾声・失声】‥ゴヱ
音声がかれて出ないこと。かれごえ。〈倭名類聚鈔3〉
ひ‐ざかな【干魚・乾魚】🔗⭐🔉
ひ‐じに【乾死に・干死に】🔗⭐🔉
ひ‐じに【乾死に・干死に】
うえじに。餓死。平家物語3「頼豪はやがて―に死ににけり」
ひ‐し・ぬ【乾死ぬ・干死ぬ】🔗⭐🔉
ひ‐し・ぬ【乾死ぬ・干死ぬ】
〔自ナ変〕
餓えて死ぬ。餓死する。
ひる【干る・乾る】🔗⭐🔉
ひる【干る・乾る】
〔自上一〕
(奈良時代には終止形「ふ」で上二段活用)
①かわく。古今和歌集恋「夕さればいとどひがたき我が袖に」
②海・川の水が涸かれて底が現れる。古今和歌集物名「涙川沖ひむ時や底は知られん」
③終わる。果てる。尽きる。天草本伊曾保物語「我と身を大きにほむる者は、まだその言葉もひぬうちに面目を失ふものぢや」
ふ【乾】🔗⭐🔉
ふ【乾】
〔自上二〕
(上代語。平安時代以後は上一段活用)かわく。干る。
①水分が蒸発してなくなる。万葉集2「荒たへの衣の袖はふる時もなし」。万葉集5「わが泣く涙いまだひなくに」
②潮が退いて海底が現れる。万葉集15「潮ひなば」
ほし【乾し・干し】🔗⭐🔉
ほし【乾し・干し】
太陽熱や火熱にあてて水分をとり去ること。「かげ―」「物―」
ほし‐あ・げる【乾し上げる・干し上げる】🔗⭐🔉
ほし‐あ・げる【乾し上げる・干し上げる】
〔他下一〕[文]ほしあ・ぐ(下二)
①日光や火力で水分をとりさる。平家物語8「源氏の舟五百余艘を―・げたるを…おろしけり」
②食物を奪って飢えさせる。
③水や酒などを飲みほす。
ほし‐いお【乾魚・干魚】‥イヲ🔗⭐🔉
ほし‐いお【乾魚・干魚】‥イヲ
⇒ほしうお。〈倭名類聚鈔16〉
ほし‐いも【乾芋・干芋】🔗⭐🔉
ほし‐いも【乾芋・干芋】
(→)乾燥芋に同じ。
ほし‐うお【乾魚・干魚】‥ウヲ🔗⭐🔉
ほし‐うお【乾魚・干魚】‥ウヲ
背・腹を開き、または開かずにほした魚。ひうお。ひもの。
ほし‐うり【乾瓜】🔗⭐🔉
ほし‐うり【乾瓜】
シロウリを縦割りにして種を取り、塩をまぶして乾したもの。塩出しして食べる。〈[季]夏〉
ほし‐えび【乾蝦・干海老】🔗⭐🔉
ほし‐えび【乾蝦・干海老】
エビをゆでて乾したもの。
ほし‐か【乾鰯・干鰮】🔗⭐🔉
ほし‐か【乾鰯・干鰮】
脂をしぼったイワシをほしたもの。ニシンも用いる。江戸時代、乾燥肥料として農業の発展に役立った。
ほし‐がき【乾柿・干柿】🔗⭐🔉
ほし‐がき【乾柿・干柿】
渋柿の皮をむき、ほして甘くしたもの。ころがき。〈[季]秋〉。「―をつるす」
乾柿
撮影:関戸 勇


ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】🔗⭐🔉
ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】
〔他下一〕[文]ほしかた・む(下二)
ほして固くする。源平盛衰記47「一子の娘を先立てて、その身を―・めて頸に懸けて歩きけり」
ほし‐ぐり【乾栗・干栗】🔗⭐🔉
ほし‐ぐり【乾栗・干栗】
栗の実をゆで、ほし固めたもの。
ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】🔗⭐🔉
ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】
ナマコのはらわたを取り去り、茹ゆでてほしたもの。ほしなまこ。いりこ。
ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】🔗⭐🔉
ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】
〔他四〕
飢えさせて殺す。〈日葡辞書〉
ほしっ‐かえし【乾しっ返し】‥カヘシ🔗⭐🔉
ほしっ‐かえし【乾しっ返し】‥カヘシ
東京大森で海苔のりを製造する者が、越後・房総・諏訪などから雇ってくる女。乾海苔を裏返すのが主な仕事であるからいう。
ほし‐な【乾菜・干菜】🔗⭐🔉
ほし‐な【乾菜・干菜】
ほした菜。特に、大根の葉や蕪菜かぶらなを陰干しにしたもの。懸菜。〈[季]冬〉。西鶴織留5「―も細かに切つておいたり」
ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】🔗⭐🔉
ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】
(→)「ほしこ」に同じ。
ほし‐のり【乾海苔・干海苔】🔗⭐🔉
ほし‐のり【乾海苔・干海苔】
うすく漉すいてかわかした海苔。〈[季]春〉
乾海苔
撮影:関戸 勇
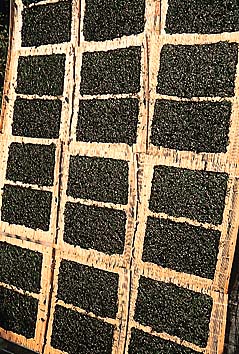
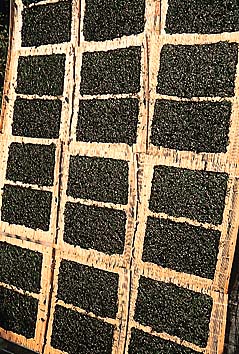
ほし‐もの【乾し物・干し物】🔗⭐🔉
ほし‐もの【乾し物・干し物】
日にほしてかわかすこと。また、そのもの。特に洗濯や染色の場合にいう。「―を取り込む」
ほ・す【乾す・干す】🔗⭐🔉
ほ・す【乾す・干す】
〔他五〕
①風や太陽に当てて水気を去る。かわかす。万葉集1「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣―・したり天の香具山」。「洗濯物を―・す」
②涙をかわかす。源氏物語椎本「二所うち語らひつつ―・す世もなくて過ぐし給ふに年も暮れにけり」
③中にあるものをすっかりとり去る。飲みつくす。「池の水を―・す」「杯を―・す」
④飲食物をとらずに空からにする。また、食物をとらせずにおく。落窪物語2「只今は―・させまほしくぞある」。日葡辞書「ハラヲホス」「ノドヲホス」
⑤仕事などを与えないでおく。「役を―・される」
[漢]乾🔗⭐🔉
乾 字形
 筆順
筆順
 〔
〔 部3画/11画/常用/2005・3425〕
〔音〕カン(呉)(漢) ケン(漢)
〔訓〕かわく・かわかす・ほす・いぬい
[意味]
[一]カンかわく。かわかす。ほす。水分がなくなる。ひる。(同)干。(対)湿。「乾燥・乾杯・乾物」
[二]ケン
①周易しゅうえきの八卦はっかの最初の卦。陽の卦、☰で表し、天・君主・男性など、強く盛んなものを象徴する。(対)坤こん。「乾坤けんこん・乾元」
②いぬい。西北の方角。
[解字]
もと、乙部10画。会意。「
部3画/11画/常用/2005・3425〕
〔音〕カン(呉)(漢) ケン(漢)
〔訓〕かわく・かわかす・ほす・いぬい
[意味]
[一]カンかわく。かわかす。ほす。水分がなくなる。ひる。(同)干。(対)湿。「乾燥・乾杯・乾物」
[二]ケン
①周易しゅうえきの八卦はっかの最初の卦。陽の卦、☰で表し、天・君主・男性など、強く盛んなものを象徴する。(対)坤こん。「乾坤けんこん・乾元」
②いぬい。西北の方角。
[解字]
もと、乙部10画。会意。「 」(=日がのぼる)+「乙」(=のびる)。日が高く昇る意。勢いがよい、高く明るい、かわくの意に転ずる。[
」(=日がのぼる)+「乙」(=のびる)。日が高く昇る意。勢いがよい、高く明るい、かわくの意に転ずる。[ ]は異体字。
[難読]
乾葉ひば・乾物ひもの・乾飯ほしいい・かれいい・乾鰯ほしか・乾海鼠ほしこ
]は異体字。
[難読]
乾葉ひば・乾物ひもの・乾飯ほしいい・かれいい・乾鰯ほしか・乾海鼠ほしこ
 筆順
筆順
 〔
〔 部3画/11画/常用/2005・3425〕
〔音〕カン(呉)(漢) ケン(漢)
〔訓〕かわく・かわかす・ほす・いぬい
[意味]
[一]カンかわく。かわかす。ほす。水分がなくなる。ひる。(同)干。(対)湿。「乾燥・乾杯・乾物」
[二]ケン
①周易しゅうえきの八卦はっかの最初の卦。陽の卦、☰で表し、天・君主・男性など、強く盛んなものを象徴する。(対)坤こん。「乾坤けんこん・乾元」
②いぬい。西北の方角。
[解字]
もと、乙部10画。会意。「
部3画/11画/常用/2005・3425〕
〔音〕カン(呉)(漢) ケン(漢)
〔訓〕かわく・かわかす・ほす・いぬい
[意味]
[一]カンかわく。かわかす。ほす。水分がなくなる。ひる。(同)干。(対)湿。「乾燥・乾杯・乾物」
[二]ケン
①周易しゅうえきの八卦はっかの最初の卦。陽の卦、☰で表し、天・君主・男性など、強く盛んなものを象徴する。(対)坤こん。「乾坤けんこん・乾元」
②いぬい。西北の方角。
[解字]
もと、乙部10画。会意。「 」(=日がのぼる)+「乙」(=のびる)。日が高く昇る意。勢いがよい、高く明るい、かわくの意に転ずる。[
」(=日がのぼる)+「乙」(=のびる)。日が高く昇る意。勢いがよい、高く明るい、かわくの意に転ずる。[ ]は異体字。
[難読]
乾葉ひば・乾物ひもの・乾飯ほしいい・かれいい・乾鰯ほしか・乾海鼠ほしこ
]は異体字。
[難読]
乾葉ひば・乾物ひもの・乾飯ほしいい・かれいい・乾鰯ほしか・乾海鼠ほしこ
広辞苑に「乾」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む
 そく
そく