複数辞典一括検索+![]()
![]()
か【化】クワ🔗⭐🔉
か【化】クワ
(呉音はケ)
①徳を以て教えみちびくこと。平家物語5「尭舜無為の―をうたひ」
②化学の略。「―繊」
か‐いく【化育】クワ‥🔗⭐🔉
か‐いく【化育】クワ‥
天地自然が万物を生じ育てること。
か‐がい【化外】クワグワイ🔗⭐🔉
か‐がい【化外】クワグワイ
⇒けがい
か‐がく【化学】クワ‥🔗⭐🔉
か‐がく【化学】クワ‥
(chemistry)諸物質の構造・性質並びにこれら物質相互間の反応を研究する自然科学の一部門。旧称、舎密セイミ。
⇒かがく‐エネルギー【化学エネルギー】
⇒かがく‐かせき【化学化石】
⇒かがく‐がん【化学岩】
⇒かがく‐きかい【化学機械】
⇒かがく‐きごう【化学記号】
⇒かがく‐けつごう【化学結合】
⇒かがく‐げんそ【化学元素】
⇒かがく‐こうがく【化学工学】
⇒かがく‐こうぎょう【化学工業】
⇒かがく‐ごうせい【化学合成】
⇒かがく‐こうぞう【化学構造】
⇒かがく‐さよう【化学作用】
⇒かがく‐しき【化学式】
⇒かがく‐じゅようき【化学受容器】
⇒かがく‐しょうぼうしゃ【化学消防車】
⇒かがく‐しんか【化学進化】
⇒かがく‐しんわりょく【化学親和力】
⇒かがく‐せいひん【化学製品】
⇒かがく‐せん【化学戦】
⇒かがく‐せんい【化学繊維】
⇒かがく‐たんこう【化学探鉱】
⇒かがく‐ちぢみ【化学縮】
⇒かがく‐ちょうみりょう【化学調味料】
⇒かがく‐てき【化学的】
⇒かがくてき‐かんかく【化学的感覚】
⇒かがくてき‐さんそようきゅうりょう【化学的酸素要求量】
⇒かがくてき‐たいせきがん【化学的堆積岩】
⇒かがくてき‐たいせきこうしょう【化学的堆積鉱床】
⇒かがくてき‐たいせきぶつ【化学的堆積物】
⇒かがくてき‐ぼうじょ【化学的防除】
⇒かがく‐てんびん【化学天秤】
⇒かがく‐とうりょう【化学当量】
⇒かがく‐ねつりきがく【化学熱力学】
⇒かがく‐パルプ【化学パルプ】
⇒かがく‐はんのう【化学反応】
⇒かがく‐はんのうしき【化学反応式】
⇒かがく‐ひりょう【化学肥料】
⇒かがく‐ぶっしつ【化学物質】
⇒かがく‐ぶつりがく【化学物理学】
⇒かがく‐ぶんせき【化学分析】
⇒かがく‐へいき【化学兵器】
⇒かがく‐へいき‐きんし‐じょうやく【化学兵器禁止条約】
⇒かがく‐へいこう【化学平衡】
⇒かがく‐へんか【化学変化】
⇒かがく‐ほうていしき【化学方程式】
⇒かがく‐ポテンシャル【化学ポテンシャル】
⇒かがく‐めっき【化学鍍金】
⇒かがく‐やくひん【化学薬品】
⇒かがく‐りょうほう【化学療法】
⇒かがく‐りょう‐ろん【化学量論】
かがく‐エネルギー【化学エネルギー】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐エネルギー【化学エネルギー】クワ‥
(chemical energy)原子間の化学結合によって物質内に保有されるエネルギーの形態の一つ。化学変化に伴い、熱・光・電気などのエネルギーに変わる。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐かせき【化学化石】クワ‥クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐かせき【化学化石】クワ‥クワ‥
地層や化石の中に残っている有機化合物で、古生物の生体に由来するもの。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐がん【化学岩】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐がん【化学岩】クワ‥
(chemical rocks)水溶液から化学的に沈殿してできた岩石の総称。岩塩・カリ塩・石膏・珪華など。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐きかい【化学機械】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐きかい【化学機械】クワ‥
化学工業用の器具・機械・装置の総称。大別して、粉砕機・混合機・攪拌かくはん機・分離機・濾過ろか機・蒸発器・乾燥機・蒸留器・熱交換器などに分ける。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐きごう【化学記号】クワ‥ガウ🔗⭐🔉
かがく‐きごう【化学記号】クワ‥ガウ
化学物質を示す記号。主として元素記号を指す。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐けつごう【化学結合】クワ‥ガフ🔗⭐🔉
かがく‐けつごう【化学結合】クワ‥ガフ
分子や結晶を構成する各原子間の結びつき。結びつける力の性質によって、イオン結合・共有結合・金属結合などに大別する。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐げんそ【化学元素】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐げんそ【化学元素】クワ‥
化学的手段(化学的反応)によっては、それ以上に分解し得ない物質。厳密には、同一原子番号の原子だけから成る物質。金・銀・銅・鉄・水素・酸素・炭素・窒素など。元素。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐こうがく【化学工学】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐こうがく【化学工学】クワ‥
化学工業における諸工程や機械・装置の設計及び運用などを研究する工学の一分科。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐こうぎょう【化学工業】クワ‥ゲフ🔗⭐🔉
かがく‐こうぎょう【化学工業】クワ‥ゲフ
化学反応を基礎とした製造工業。ガラス工業・陶磁器工業・セメント工業・ソーダ工業・製油工業・精錬工業・化学肥料工業・有機合成工業・石油化学工業の類。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐こうぞう【化学構造】クワ‥ザウ🔗⭐🔉
かがく‐こうぞう【化学構造】クワ‥ザウ
分子を構成する原子・官能基の配列。一般に構造式で表す。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐さよう【化学作用】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐さよう【化学作用】クワ‥
化学変化を起こす作用。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐しき【化学式】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐しき【化学式】クワ‥
元素記号を用いて物質を表示する式。実験式・分子式・示性式・構造式などを含む。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐じゅようき【化学受容器】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐じゅようき【化学受容器】クワ‥
化学物質を刺激として受け取る受容器。匂いを知覚する嗅上皮、味覚器である舌粘膜上皮など。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐しょうぼうしゃ【化学消防車】クワ‥セウバウ‥🔗⭐🔉
かがく‐しょうぼうしゃ【化学消防車】クワ‥セウバウ‥
化学消火剤を撒布する消防自動車。放水での消火が困難・危険な火災に対処する。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐しんわりょく【化学親和力】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐しんわりょく【化学親和力】クワ‥
化学反応のとき物質の間に働くと考えられる親和性を表す大きさ。今日では、熱力学的に定義されている。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐せいひん【化学製品】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐せいひん【化学製品】クワ‥
化学工業で製造される製品。工業薬品(硫酸・塩酸・硝酸など)・化学肥料・紙・パルプ・合成繊維・ゴム製品・プラスチック・医薬・染料・石鹸・化粧品の類。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐せん【化学戦】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐せん【化学戦】クワ‥
化学兵器による戦闘。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐せんい【化学繊維】クワ‥ヰ🔗⭐🔉
かがく‐せんい【化学繊維】クワ‥ヰ
天然繊維に対して人工的につくった繊維の総称。再生繊維(天然繊維を溶解し紡糸してつくったもの。ビスコース‐レーヨンの類)、半合成繊維(天然繊維の高分子を誘導体として溶解し紡糸してつくったもの。アセテート‐レーヨンの類)、および合成繊維(分子量の小さい化合物から合成したもの。ナイロン・ポリエステルの類)に分類される。人造繊維。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐たんこう【化学探鉱】クワ‥クワウ🔗⭐🔉
かがく‐たんこう【化学探鉱】クワ‥クワウ
岩石・土壌・地下水・河川の水や植物・堆積物中の特定元素の濃度を分析し、鉱床の存在位置を地球化学の知識を基礎に推定する方法。地化学探査。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ちぢみ【化学縮】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐ちぢみ【化学縮】クワ‥
化学薬品により収縮させた縮・縮緬皺ちりめんじわ。クラップ縮緬の類。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ちょうみりょう【化学調味料】クワ‥テウ‥レウ🔗⭐🔉
かがく‐ちょうみりょう【化学調味料】クワ‥テウ‥レウ
(→)「うま味調味料」に同じ。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐てき【化学的】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐てき【化学的】クワ‥
化学により認識されるさま。物質の組成・性質・変化に関するさま。「―変化」↔物理的。
⇒か‐がく【化学】
かがくてき‐かんかく【化学的感覚】クワ‥🔗⭐🔉
かがくてき‐かんかく【化学的感覚】クワ‥
化学的刺激によって起こる感覚。嗅覚・味覚はこれに属する。
⇒か‐がく【化学】
かがくてき‐さんそようきゅうりょう【化学的酸素要求量】クワ‥エウキウリヤウ🔗⭐🔉
かがくてき‐さんそようきゅうりょう【化学的酸素要求量】クワ‥エウキウリヤウ
(→)シー‐オー‐ディー(COD)に同じ。
⇒か‐がく【化学】
かがくてき‐たいせきがん【化学的堆積岩】クワ‥🔗⭐🔉
かがくてき‐たいせきがん【化学的堆積岩】クワ‥
化学的作用によって水溶液から沈殿してできた岩石の総称。岩塩・石膏などの蒸発岩のほかに、バクテリアなど微生物が関与してできた鉄鉱層など。石灰岩やチャートを含めることがある。
⇒か‐がく【化学】
かがくてき‐たいせきこうしょう【化学的堆積鉱床】クワ‥クワウシヤウ🔗⭐🔉
かがくてき‐たいせきこうしょう【化学的堆積鉱床】クワ‥クワウシヤウ
海水や地表水に溶けていた鉱物が、化学的条件の変化によって沈殿してできた鉱床。
⇒か‐がく【化学】
かがくてき‐たいせきぶつ【化学的堆積物】クワ‥🔗⭐🔉
かがくてき‐たいせきぶつ【化学的堆積物】クワ‥
(chemical sediments)化学的および生化学的作用が関与してできた堆積物。
⇒か‐がく【化学】
かがくてき‐ぼうじょ【化学的防除】クワ‥バウヂヨ🔗⭐🔉
かがくてき‐ぼうじょ【化学的防除】クワ‥バウヂヨ
化学物質を用いて有害動植物・微生物を防除すること。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐てんびん【化学天秤】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐てんびん【化学天秤】クワ‥
化学実験・分析に使用する天秤。秤量100〜200グラム、感度0.1〜1ミリグラム程度。化学はかり。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐とうりょう【化学当量】クワ‥タウリヤウ🔗⭐🔉
かがく‐とうりょう【化学当量】クワ‥タウリヤウ
化学反応性に基づいて定められた元素・化合物の一定量。水素原子の1モルまたは酸素原子の2分の1モルと化合または置換し得る他の元素の量をグラムで表し、元素の1当量とする。酸・塩基では、酸として作用する1当量の水素を含む酸の量およびこれを中和する塩基の量を、1当量とする。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ねつりきがく【化学熱力学】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐ねつりきがく【化学熱力学】クワ‥
気体・液体・溶液などの性質や相平衡・化学平衡などを取り扱う熱力学の一部門。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐はんのうしき【化学反応式】クワ‥オウ‥🔗⭐🔉
かがく‐はんのうしき【化学反応式】クワ‥オウ‥
化学式を用いて化学反応の内容を表した式。反応物質の化学式を左辺に、生成物質の化学式を右辺に書き、矢印・等号、2本の逆向きの矢印( )で結ぶ。例えば2H2+O2→2H2Oなど。量的関係を示したものは化学方程式ともいう。
⇒か‐がく【化学】
)で結ぶ。例えば2H2+O2→2H2Oなど。量的関係を示したものは化学方程式ともいう。
⇒か‐がく【化学】
 )で結ぶ。例えば2H2+O2→2H2Oなど。量的関係を示したものは化学方程式ともいう。
⇒か‐がく【化学】
)で結ぶ。例えば2H2+O2→2H2Oなど。量的関係を示したものは化学方程式ともいう。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ひりょう【化学肥料】クワ‥レウ🔗⭐🔉
かがく‐ひりょう【化学肥料】クワ‥レウ
化学的に製造する肥料。窒素・リン酸・カリウムの一種以上を水溶性の化合物として含む。硫安・過燐酸石灰の類。↔天然肥料。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ぶっしつ【化学物質】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐ぶっしつ【化学物質】クワ‥
物質のうち、特に化学の研究対象となるような物質を区別していう語。化学工業で合成される物質、あるいは人工の物質という意味で使われることがあるが、本来はそのような意味はない。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ぶつりがく【化学物理学】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐ぶつりがく【化学物理学】クワ‥
物質の分子構造や、化学反応の機構などの問題を、物理学の理論・実験を導入して研究する物理学の一分野。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ぶんせき【化学分析】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐ぶんせき【化学分析】クワ‥
物質の検出や化学的組成の決定のための操作。定性分析と定量分析とに大別される。近年は機器分析法が広く行われる。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐へいき‐きんし‐じょうやく【化学兵器禁止条約】クワ‥デウ‥🔗⭐🔉
かがく‐へいき‐きんし‐じょうやく【化学兵器禁止条約】クワ‥デウ‥
正式には「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」。化学兵器の使用のみならず開発・生産・貯蔵を全面的に禁止し、その廃棄を義務づけた国際条約。1993年採択、97年発効。日本は97年に批准。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐へいこう【化学平衡】クワ‥カウ🔗⭐🔉
かがく‐へいこう【化学平衡】クワ‥カウ
可逆反応において正反応の進行速度と逆反応の進行速度とが釣り合って、見かけ上反応が停止した状態。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐へんか【化学変化】クワ‥クワ🔗⭐🔉
かがく‐へんか【化学変化】クワ‥クワ
物質を構成する原子の結合の組換えを伴う変化。物体の位置・形状・大きさなどの変化に対して、物質自身の変化をいう。↔物理変化。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ほうていしき【化学方程式】クワ‥ハウ‥🔗⭐🔉
かがく‐ほうていしき【化学方程式】クワ‥ハウ‥
化学反応式のうち、反応の内容を定量的に示したもの。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐ポテンシャル【化学ポテンシャル】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐ポテンシャル【化学ポテンシャル】クワ‥
混合物中の各成分の1モルまたは1分子に割り当てられた定温・定圧下での自由エネルギー。多成分系の平衡を支配する因子で、平衡状態では各成分の化学ポテンシャルが等しくなる。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐めっき【化学鍍金】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐めっき【化学鍍金】クワ‥
電気を用いず、金属塩の水溶液に還元剤を加えて金属を析出させ、材料表面にめっきを施す方法。無電解めっき。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐やくひん【化学薬品】クワ‥🔗⭐🔉
かがく‐やくひん【化学薬品】クワ‥
医薬品に対して、化学的用途に用いられる薬品。工業薬品と区別する時には、比較的精製されたものをいう。
⇒か‐がく【化学】
かがく‐りょう‐ろん【化学量論】クワ‥リヤウ‥🔗⭐🔉
かがく‐りょう‐ろん【化学量論】クワ‥リヤウ‥
反応に関与する物質の数量的関係を研究する化学の一部門。初めは質量保存則、定比例の法則などが主な対象であったが、後に物質の組成と物理化学的性質との間の数量的関係を研究する物理化学の一部門を意味するようになった。現在では化学反応の数量的関係自体を指して用いることが多い。
⇒か‐がく【化学】
か‐ごう【化合】クワガフ🔗⭐🔉
か‐ごう【化合】クワガフ
(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。
⇒かごう‐ぶつ【化合物】
⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】
かごう‐ぶつ【化合物】クワガフ‥🔗⭐🔉
かごう‐ぶつ【化合物】クワガフ‥
(compound)2種以上の元素が結合している物質。
⇒か‐ごう【化合】
かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】クワガフ‥ダウ‥🔗⭐🔉
かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】クワガフ‥ダウ‥
半導体の性質を示す化合物の総称。砒化ガリウム・硫化カドミウムなど。発光ダイオード・レーザー素子などに用いる。
⇒か‐ごう【化合】
か‐こつ【化骨】クワ‥🔗⭐🔉
か‐こつ【化骨】クワ‥
(→)骨化に同じ。
か・する【化する】クワ‥🔗⭐🔉
か・する【化する】クワ‥
〔自他サ変〕[文]化す(サ変)
①形や性質が変わって別のものとなる。かわる。変化する。また、別のものに変える。「廃墟と―・する」
②感化をうけてかわる。また、教え導いて変わらせる。同化する。「徳を以て人を―・する」
げ‐えん【化縁】🔗⭐🔉
げ‐えん【化縁】
(ケエンとも)
①仏・菩薩が衆生しゅじょうを教化する因縁。
②教化をうけるべき衆生の側の機縁。
け‐がい【化外】‥グワイ🔗⭐🔉
け‐がい【化外】‥グワイ
王化の及ばない所。教化の外。「―の民」
け‐きょう【化教】‥ケウ🔗⭐🔉
け‐きょう【化教】‥ケウ
〔仏〕律宗で、精神的素質に応じて衆生しゅじょうを教化する教え。定じょう・慧え二学をいう。↔制教
け‐げん【化現】🔗⭐🔉
け‐げん【化現】
〔仏〕神仏などが姿をかえてこの世にあらわれること。化作けさ。今昔物語集17「この沙弥を地蔵菩薩の大悲の―なりとぞいひける」
け‐しゅ【化主】🔗⭐🔉
け‐しゅ【化主】
〔仏〕
①(化導の教主の意)仏の異称。阿弥陀を浄土の化主、釈尊を娑婆の化主という類。
②高徳の僧。
③(智積院など新義真言宗の)寺院の住職。
④市街に出て衆生に施物を乞い、結縁けちえんして法を説いたり、寺院の費用を弁じたりする僧。街坊。
け‐じょ【化女】‥ヂヨ🔗⭐🔉
け‐じょ【化女】‥ヂヨ
姿を変じて現れた女。ばけた女。
け‐しょう【化粧・仮粧】‥シヤウ🔗⭐🔉
け‐しょう【化粧・仮粧】‥シヤウ
①紅・白粉おしろいなどをつけて顔をよそおい飾ること。美しく見えるよう、表面を磨いたり飾ったりすること。おつくり。けそう。〈下学集〉。「美しく―する」
②(名詞に冠して)美しく飾った、体裁をつくろった、形式的な、などの意を表す語。「―金具」
③〔建〕外から見えるところ。外面にあらわれている部分。「―垂木だるき」↔野の。
⇒けしょう‐いくさ【化粧軍】
⇒けしょう‐いた【化粧板】
⇒けしょう‐がね【化粧金】
⇒けしょう‐がみ【化粧紙】
⇒けしょう‐がわ【化粧革】
⇒けしょう‐がわ【化粧側】
⇒けしょう‐ギセル【化粧煙管】
⇒けしょう‐くずれ【化粧崩れ】
⇒けしょう‐ごうはん【化粧合板】
⇒けしょう‐ごえ【化粧声】
⇒けしょう‐こまい【化粧木舞】
⇒けしょう‐じお【化粧塩】
⇒けしょう‐した【化粧下】
⇒けしょう‐しつ【化粧室】
⇒けしょう‐すい【化粧水】
⇒けしょう‐せっけん【化粧石鹸】
⇒けしょう‐だ【化粧田】
⇒けしょう‐だい【化粧台】
⇒けしょう‐だち【化粧立ち】
⇒けしょう‐だち【化粧裁ち】
⇒けしょう‐だな【化粧棚】
⇒けしょう‐だるき【化粧垂木】
⇒けしょう‐だんす【化粧箪笥】
⇒けしょう‐っけ【化粧っ気】
⇒けしょう‐つち【化粧土】
⇒けしょう‐づみ【化粧積み】
⇒けしょう‐なおし【化粧直し】
⇒けしょう‐なわ【化粧縄】
⇒けしょう‐の‐いた【化粧の板】
⇒けしょう‐ばえ【化粧映え】
⇒けしょう‐ばこ【化粧箱】
⇒けしょう‐ひん【化粧品】
⇒けしょう‐まく【化粧幕】
⇒けしょう‐まわし【化粧回し】
⇒けしょう‐みず【化粧水】
⇒けしょう‐めじ【化粧目地】
⇒けしょう‐もとゆい【化粧元結】
⇒けしょう‐やなぎ【化粧柳】
⇒けしょう‐やねうら【化粧屋根裏】
⇒けしょう‐ゆい【化粧結い】
⇒けしょう‐りょう【化粧料】
⇒けしょう‐わざ【化粧業】
けしょう‐ギセル【化粧煙管】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
けしょう‐ギセル【化粧煙管】‥シヤウ‥
美しい絵模様を施した陶製のキセル。
⇒け‐しょう【化粧・仮粧】
けしょう‐じお【化粧塩】‥シヤウジホ🔗⭐🔉
けしょう‐じお【化粧塩】‥シヤウジホ
魚を姿焼きにするとき、焼き上がりを美しくしたり、焦げないようにしたりするのに尾や鰭ひれなどにまぶす塩。貝類の殻にまぶすこともある。飾り塩。鰭塩。
⇒け‐しょう【化粧・仮粧】
けしょう‐っけ【化粧っ気】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
けしょう‐っけ【化粧っ気】‥シヤウ‥
化粧をしてある様子。「―がない顔」
⇒け‐しょう【化粧・仮粧】
けしょう‐の‐いた【化粧の板】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
けしょう‐の‐いた【化粧の板】‥シヤウ‥
鎧よろいの札頭さねがしらと金具廻かなぐまわりとをつなぎ、その間に入れる細い横板。染革で包み、金物を打つ。けしょういた。→大鎧おおよろい(図)。
⇒け‐しょう【化粧・仮粧】
けしょう‐ばえ【化粧映え】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
けしょう‐ばえ【化粧映え】‥シヤウ‥
化粧によって顔立ちが引き立って見えること。「―がする顔」
⇒け‐しょう【化粧・仮粧】
けしょう‐やねうら【化粧屋根裏】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
けしょう‐やねうら【化粧屋根裏】‥シヤウ‥
天井を張らないで、小屋組こやぐみを見せた屋根裏。
⇒け‐しょう【化粧・仮粧】
け・す【化す】🔗⭐🔉
け・す【化す】
〔自サ変〕
(→)「化かする」(自サ変)に同じ。今昔物語集6「―・して僧となり給ひぬ」
け‐そう【化粧・仮粧】‥サウ🔗⭐🔉
け‐そう【化粧・仮粧】‥サウ
⇒けしょう。竹取物語「御身の―いといたくして」
け‐ちぎり【仮契・化契】🔗⭐🔉
け‐ちぎり【仮契・化契】
下級の遊女。端はし女郎。けち。浮世草子、御前義経記「端女郎は鹿恋かこいより下、見世みせ女郎をいふなり。替名を―とも、火打とも」
け‐にょ【化女】🔗⭐🔉
け‐にょ【化女】
仏・菩薩が仮に女人の姿となって現れたもの。化人の女。古今著聞集2「かの糸をこの―に授け給ふ」
けらく‐てん【化楽天】🔗⭐🔉
けらく‐てん【化楽天】
〔仏〕六欲天の第5。ここに生まれたものは、自ら楽しい境遇を作り楽しみ、八千歳の寿命を保つという。楽変化天。化自楽天。化自在天。
けわい【化粧・仮粧】ケハヒ🔗⭐🔉
けわい【化粧・仮粧】ケハヒ
けしょう。おつくり。田植草紙「髪けづり―する」
⇒けわい‐がね【化粧金】
⇒けわい‐けしょう【化粧化粧】
⇒けわい‐でん【化粧田】
⇒けわい‐でん【化粧殿】
⇒けわい‐りょう【化粧料】
けわ・う【化粧ふ】ケハフ🔗⭐🔉
けわ・う【化粧ふ】ケハフ
〔自四〕
(「けわい」を活用させた語)
①身づくろいをする。六波羅殿御家訓「内にてはいかにもつくろひ―・ふべし」
②けしょうする。浄瑠璃、八百屋お七「幽霊が白仏程―・うての」
のぶ‐の‐き【化香樹】🔗⭐🔉
のぶ‐の‐き【化香樹】
〔植〕ノグルミの別称。
ばかし‐ばり【化かし鉤】🔗⭐🔉
ばかし‐ばり【化かし鉤】
(→)擬餌ぎじ鉤のこと。
はか・す【化かす・魅す】🔗⭐🔉
はか・す【化かす・魅す】
〔他四〕
⇒ばかす
ばか・す【化かす・魅す】🔗⭐🔉
ばか・す【化かす・魅す】
〔他五〕
(古くはハカスとも)人の心を迷わせる。だます。たぶらかす。玉葉集恋「さりともと頼む心に―・されて死なれぬものは命なりけり」。「狸は人を―・す」
ばけ【化け】🔗⭐🔉
ばけ【化け】
①ばけること。また、ばけたさま。宇治拾遺物語8「狸を射害いころし、其―をあらはしけるなり」
②だますこと。ごまかし。申楽談儀「下手の―の現はるること」
③魚釣り用の擬餌ぎじ。とっぱ。
④歌舞伎の所作事の一つ。浪花聞書「―。歌舞伎所作事七変化九変化を、七―九―と唱ふ」
ばけ‐がく【化学】🔗⭐🔉
ばけ‐がく【化学】
「化学かがく」を、同音の「科学かがく」と混同しないため、湯桶読みにした語。
ばけ‐く【化句】🔗⭐🔉
ばけ‐く【化句】
冠付かむりづけで、言おうとする言葉をことさら分かりにくい語で言いかえた句。
ばけ‐ねこ【化け猫】🔗⭐🔉
ばけ‐ねこ【化け猫】
魔力を持ち、人などに化けるといわれる猫。猫の化物。
ばけ‐の‐かわ【化けの皮】‥カハ🔗⭐🔉
ばけ‐の‐かわ【化けの皮】‥カハ
素姓・真相などを包みかくしているうわべの体裁。中村花痩、赤毛布「今日こそは―を引つ褫ぱいで呉れんづ」
⇒化けの皮を現す
○化けの皮を現すばけのかわをあらわす
つくろって包みかくしていた素姓・真相が露見する。「化けの皮が剥げる」とも。
⇒ばけ‐の‐かわ【化けの皮】
○化けの皮を現すばけのかわをあらわす🔗⭐🔉
○化けの皮を現すばけのかわをあらわす
つくろって包みかくしていた素姓・真相が露見する。「化けの皮が剥げる」とも。
⇒ばけ‐の‐かわ【化けの皮】
ばけ‐ばけ・し【化け化けし】
〔形シク〕
いかにもよくばけたようである。また、あざむく傾向がある。いつわりである。和歌秘伝抄「世の中皆―・しくなりて、飾りたる偽りにふけりて」
は‐けぶり【羽煙】
多くの鳥が塵煙じんえんの立ちあがるように飛び立つこと。また、そのために起こる塵煙。為忠集「田づらにぞ―たつるむら雀」
はげま・す【励ます】
〔他五〕
①はげむようにする。ふるいたたせる。気持をそそる。源氏物語玉鬘「まづ人の心―・さむことを先におぼすよ」。「選手を―・す」
②はげしくする。強める。「声を―・す」
はげみ【励み】
はげますもの。また、はげむこと。勉励。いさみ。「わが子の成長を―にする」
はけ‐みち【捌け道】
水などの自然に流れ出ていく道。はけぐち。
はげ・む【励む】
[一]〔自五〕
①気力をはげしくする。気を荒立てる。類聚名義抄「激、ハゲム」
②ある目的に向かって心を奮い立たす。つとめる。精を出す。源氏物語絵合「われ人に劣りなむや、と思し―・みてすぐれたる上手ども召し取りて」。「勉強に―・む」
[二]〔他四〕
①ふるい起こす。宇津保物語俊蔭「こはき力を―・みて」
②力を尽くして行う。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「心すずしく義兵をおこし、一戦を―・み申すべし」
はけ‐め【刷毛目】
①刷毛で塗ったり掃いたりしたあと。「―をつける」
②1に似た文様。特に、陶器の素地きじに白化粧土を刷毛で塗りつけ、この文様を表したもの。
③微塵縞みじんじまなどの織物に経糸たていと・緯糸よこいとを、濃淡2色1本おきに配列し、おのおの1糸ずつ交互に打ち込んで織り、表を縦縞、裏を横縞にしたもの。刷毛目縞。
ばけ‐もの【化物】
①狐・狸・猫などが化けて怪しい姿をしたもの。へんげ。妖怪。おばけ。
②素人しろうとから転じて玄人くろうとになった義太夫語り。
③普通ではできない図抜けた能力のある人のたとえ。「何でも記憶する―」
⇒ばけもの‐え【化物絵】
⇒ばけもの‐やしき【化物屋敷】
⇒ばけもの‐ろうそく【化物蝋燭】
ばけもの‐え【化物絵】‥ヱ
化物の姿をかいた絵。
⇒ばけ‐もの【化物】
ばけもの‐やしき【化物屋敷】
化物の現れるという屋敷。おばけ屋敷。
⇒ばけ‐もの【化物】
ばけもの‐ろうそく【化物蝋燭】‥ラフ‥
影絵の一種。紙を種々の人の形に切り、2枚を竹の串に挟んで裏返せば種々の形にかわるもの。(嬉遊笑覧)
⇒ばけ‐もの【化物】
はげ‐やま【禿山】
樹木の生えていない山。草木のない山。
は・ける【捌ける】
〔自下一〕[文]は・く(下二)
①流通する。とどこおらずに流れる。「水が―・ける」
②品物などがよく売れる。さばける。「新製品が―・ける」
は・げる【剥げる・禿げる】
〔自下一〕[文]は・ぐ(下二)
①表面がむけ離れる。はがれる。「めっきが―・げる」「塗りが―・げる」
②《禿》頭髪がぬけおちる。転じて、草木がなくなって山などの地肌が露出する。「心労で―・げる」
③色があせる。「着物の色が―・げる」
ば・ける【化ける】
〔自下一〕[文]ば・く(下二)
(古くはハクとも)
①形をかえる。異形のものに変わる。徒然草「未練の狐、―・け損じけるにこそ」
②素姓を隠して別人のさまをよそおう。「村人に―・けて潜入する」
③全く別のものに変わる。「学資が酒代に―・ける」
④目立つ所のなかった芸人・役者が予期しないほどに良く変わる。広く、思いもよらない大当りとなる。
はげ‐わし【禿鷲】
タカ目タカ科の鳥の一群。アフリカを中心に旧世界に分布。屍肉食の猛禽。約15種。多くは頭に羽毛がほとんどない。コンドル類とは別。日本に迷鳥として飛来記録のあるハゲワシは、地中海周辺からアジアに分布するクロハゲワシのみ。
くろはげわし
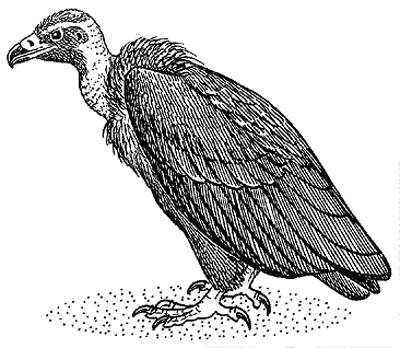 シロエリハゲワシ
撮影:小宮輝之
シロエリハゲワシ
撮影:小宮輝之
 ミミハゲワシ
撮影:小宮輝之
ミミハゲワシ
撮影:小宮輝之
 クロハゲワシ
提供:OPO
クロハゲワシ
提供:OPO
 は‐けん【派遣】
①諸方へ分けて送り遣わすこと。
②命じて出張させること。「視察団を―する」「人材―業」
⇒はけん‐ろうどう【派遣労働】
は‐けん【覇権】
①武力や権謀をもって競争者を抑えて得た権力。覇者としての権力。頭領の権力。「―主義」「―を握る」
②転じて、競技などで優勝者としての資格。「―をかけて争う」
ば‐けん【馬券】
競馬で、勝ち馬を予想して投票する券。勝馬投票券の通称。「―を買う」
ば‐げん【罵言】
ののしることば。悪口。「―を吐く」
は‐げんか【端喧嘩】‥クワ
取るに足りない小さいけんか。小ぜりあいのけんか。
ば‐けんちゅう【馬建忠】
清末の官僚。江蘇丹徒の人。フランスに留学。洋務派として外交に活躍。著「馬氏文通」「適可斎記言」。(1845〜1900)
はけん‐ろうどう【派遣労働】‥ラウ‥
派遣会社が雇っている労働者が、契約先の企業に派遣されて業務にあたる労働形態。
⇒は‐けん【派遣】
はこ【箱・函・筥・匣・筐】
①物を納めておく器。普通、角型で木・紙・竹などで作る。万葉集9「この―を開きて見てば」。「宝石―」
②便所で糞を受ける箱。おまる。おかわ。今昔物語集30「―洗ひに行かむを伺ひ」
③転じて、(人の)糞。
④挟箱はさみばこの略。
⑤三味線を入れる箱。転じて、三味線。また、三味線を入れた箱を持って芸者に従って行く男。はこや。
⑥牛車の屋形やかた。車箱。また、鉄道車両の車室やエレベーターのケージ。
⑦(東北地方で)岩壁で囲まれた渓谷の一部。
⑧(「箱入り」の略)とっておきの芸。得意芸。おはこ。譬喩尽「―じや。箱入との事、其の芸の手に入りし語なり」
はご【
は‐けん【派遣】
①諸方へ分けて送り遣わすこと。
②命じて出張させること。「視察団を―する」「人材―業」
⇒はけん‐ろうどう【派遣労働】
は‐けん【覇権】
①武力や権謀をもって競争者を抑えて得た権力。覇者としての権力。頭領の権力。「―主義」「―を握る」
②転じて、競技などで優勝者としての資格。「―をかけて争う」
ば‐けん【馬券】
競馬で、勝ち馬を予想して投票する券。勝馬投票券の通称。「―を買う」
ば‐げん【罵言】
ののしることば。悪口。「―を吐く」
は‐げんか【端喧嘩】‥クワ
取るに足りない小さいけんか。小ぜりあいのけんか。
ば‐けんちゅう【馬建忠】
清末の官僚。江蘇丹徒の人。フランスに留学。洋務派として外交に活躍。著「馬氏文通」「適可斎記言」。(1845〜1900)
はけん‐ろうどう【派遣労働】‥ラウ‥
派遣会社が雇っている労働者が、契約先の企業に派遣されて業務にあたる労働形態。
⇒は‐けん【派遣】
はこ【箱・函・筥・匣・筐】
①物を納めておく器。普通、角型で木・紙・竹などで作る。万葉集9「この―を開きて見てば」。「宝石―」
②便所で糞を受ける箱。おまる。おかわ。今昔物語集30「―洗ひに行かむを伺ひ」
③転じて、(人の)糞。
④挟箱はさみばこの略。
⑤三味線を入れる箱。転じて、三味線。また、三味線を入れた箱を持って芸者に従って行く男。はこや。
⑥牛車の屋形やかた。車箱。また、鉄道車両の車室やエレベーターのケージ。
⑦(東北地方で)岩壁で囲まれた渓谷の一部。
⑧(「箱入り」の略)とっておきの芸。得意芸。おはこ。譬喩尽「―じや。箱入との事、其の芸の手に入りし語なり」
はご【 ・黐
・黐 】
(→)「はが」に同じ。〈日葡辞書〉
は‐ご【羽子】
ムクロジの核に孔をうがち、彩色した鳥の小羽を数枚さしこんだもの。羽子板でこれをついて遊ぶ。はね。つくばね。おいばね。
はご‐いた【羽子板】
羽子をつくのに用いる長方形で柄のある板。桐・杉などで作り、表に絵を描き、または押絵を付けなどする。胡鬼板こぎいた。〈[季]新年〉
羽子板
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
】
(→)「はが」に同じ。〈日葡辞書〉
は‐ご【羽子】
ムクロジの核に孔をうがち、彩色した鳥の小羽を数枚さしこんだもの。羽子板でこれをついて遊ぶ。はね。つくばね。おいばね。
はご‐いた【羽子板】
羽子をつくのに用いる長方形で柄のある板。桐・杉などで作り、表に絵を描き、または押絵を付けなどする。胡鬼板こぎいた。〈[季]新年〉
羽子板
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(宮崎)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(宮崎)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(山梨)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(山梨)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(熊本)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(熊本)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(福島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(福島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(群馬)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(群馬)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(静岡)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(静岡)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(鹿児島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(鹿児島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒はごいた‐いち【羽子板市】
⇒はごいた‐かなもの【羽子板金物】
⇒はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
はごいた‐いち【羽子板市】
歳末に立つ、羽子板を売る市。〈[季]冬〉
羽子板市(浅草寺)
提供:東京都
⇒はごいた‐いち【羽子板市】
⇒はごいた‐かなもの【羽子板金物】
⇒はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
はごいた‐いち【羽子板市】
歳末に立つ、羽子板を売る市。〈[季]冬〉
羽子板市(浅草寺)
提供:東京都
 ⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐かなもの【羽子板金物】
(→)羽子板ボルトに同じ。
⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
一端が孔つきの平板になっているボルト。
⇒はご‐いた【羽子板】
はこ‐いり【箱入り】
①箱に入っていること。また、入っているもの。西鶴織留2「此丁銀―にして請取」
②大切にすること。また、そのもの。傾城禁短気「太夫さまを―にして」
③とっておきの芸。おはこ。
④箱入り娘の略。
⇒はこいり‐むすめ【箱入り娘】
はこいり‐むすめ【箱入り娘】
大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘。秘蔵娘。人情本、春色辰巳園「箱入娘はこいれむすめかなんぞのようにしたふ」
⇒はこ‐いり【箱入り】
は‐こう【八講】‥カウ
法華八講ほっけはっこうのこと。枕草子35「結縁の―し給ふ」
は‐こう【波光】‥クワウ
波のきらめく色。
は‐こう【波高】‥カウ
波の高さ。
は‐こう【爬行】‥カウ
はって行くこと。
は‐こう【跛行】‥カウ
①片足をひきずって行くこと。
②釣合のとれないこと。順調でないこと。「―景気」
⇒はこう‐ほんいせい【跛行本位制】
はこ・うハコフ
〔他下二〕
⇒はこゆ
ば‐こう【馬耕】‥カウ
馬を用いて田畑を耕すこと。
ば‐こうせん【場口銭】
(取引用語)市場で、取引所が取引員から徴収する手数料。
はこう‐だん【破甲弾】‥カフ‥
(→)徹甲弾に同じ。
はこう‐ほんいせい【跛行本位制】‥カウ‥ヰ‥
(limping standard)金貨および銀貨を無制限法貨と認め、そのうち一方(多くは銀貨)の自由鋳造を認めない本位制度。→複本位制→併行本位制
⇒は‐こう【跛行】
はこえ
(ハコユ(またはハコフ)の連用形からか)縫腋ほうえきの袍ほうの後身うしろみの腰の辺を引き上げて内側にたたみ、左右を折りこんで袋状にした部分。格袋かくぶくろ。→縫腋の袍(図)
はこおうまる【箱王丸】‥ワウ‥
曾我時致ときむねの幼名。
はこ‐おとし【箱落し】
主として小形の獣類を捕獲するのに用いる猟具。箱の中の餌を引くと、上からおもしが落ちる仕掛けのもの。
はこ‐がき【箱書】
①書画・器物などを収める箱の蓋ふたなどに、その名称や極書きわめがきを書き、署名・押印などしたもの。作者自身、またはその弟子・私淑者などが記すことが多い。箱書付。→ともばこ。
②シナリオ執筆の際、あらかじめ各シーンの要点を書きとめておくこと。
はこ‐かなもの【箱金物】
コの字形の建築用金物。小屋束こやづかと小屋梁こやばりとの結合などに用いる。
はこ‐がまえ【匚構え】‥ガマヘ
漢字の構えの一つ。「匡」「匠」などの構えの「匚」の称。→かくしがまえ
はこ‐がめ【箱亀】
カメの一群。腹甲に蝶番ちょうつがい状の部分があって、頭や四肢を甲羅に隠してから、腹甲で開口部に蓋をすることができるカメの総称。カメ科・ドロガメ科・ヨコクビガメ科などを含む。多くは陸生だが、一部淡水生。
は‐ごく【破獄】
囚人が牢獄を破ってぬけでること。ろうやぶり。破牢。
はごく・む【育む】
〔他四〕
(→)「はぐくむ」に同じ。重之集「―・みし君を雲ゐになしてより」
はこ‐ぐるま【箱車】
①屋形のある牛車ぎっしゃ。
②上に箱形の物入れを取り付けた荷車。
はこ‐げすい【箱下水】
蓋ふたで上部を覆った、断面が長方形の下水溝。
はこ‐さかな【箱肴】
祝儀・贈答用の箱入りの魚。多く干鯛が用いられた。日本永代蔵6「先づ銀百枚・真綿二十把、斗樽壱荷に―。思ひの外なる薬代」
はこざき‐ぐう【筥崎宮】
福岡市東区箱崎にある元官幣大社。祭神は応神天皇を主神とし、神功皇后・玉依姫命を合祀。筑前国一の宮。筥崎八幡宮。はこざきのみや。
はこ‐し【箱師】
電車などの乗物の中で掏摸すりを常習とする者。
は‐ごし【葉越し】
葉の間を通り越すこと。葉の隙間から透いて見えること。
はこしき‐せっかん【箱式石棺】‥セキクワン
弥生・古墳時代の棺の一型式。板石を長方形の箱のように組み合わせて作る。箱式棺。シスト。
はこ‐じゃく【箱尺】
水準測量で、水平視線の高さを測定する目盛り尺。2段または3段の入れ子になっており、最大5メートルまで伸びる。
はこ‐じょう【箱錠】‥ヂヤウ
扉等に用いる、箱型の錠。
はこ‐ずし【箱鮨】
(→)「おしずし」に同じ。
はこ‐スパナ【箱スパナ】
ボルト頭またはナットの上から覆うようにはめて締めるスパナ。ボックス‐スパナ。
箱スパナ
⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐かなもの【羽子板金物】
(→)羽子板ボルトに同じ。
⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
一端が孔つきの平板になっているボルト。
⇒はご‐いた【羽子板】
はこ‐いり【箱入り】
①箱に入っていること。また、入っているもの。西鶴織留2「此丁銀―にして請取」
②大切にすること。また、そのもの。傾城禁短気「太夫さまを―にして」
③とっておきの芸。おはこ。
④箱入り娘の略。
⇒はこいり‐むすめ【箱入り娘】
はこいり‐むすめ【箱入り娘】
大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘。秘蔵娘。人情本、春色辰巳園「箱入娘はこいれむすめかなんぞのようにしたふ」
⇒はこ‐いり【箱入り】
は‐こう【八講】‥カウ
法華八講ほっけはっこうのこと。枕草子35「結縁の―し給ふ」
は‐こう【波光】‥クワウ
波のきらめく色。
は‐こう【波高】‥カウ
波の高さ。
は‐こう【爬行】‥カウ
はって行くこと。
は‐こう【跛行】‥カウ
①片足をひきずって行くこと。
②釣合のとれないこと。順調でないこと。「―景気」
⇒はこう‐ほんいせい【跛行本位制】
はこ・うハコフ
〔他下二〕
⇒はこゆ
ば‐こう【馬耕】‥カウ
馬を用いて田畑を耕すこと。
ば‐こうせん【場口銭】
(取引用語)市場で、取引所が取引員から徴収する手数料。
はこう‐だん【破甲弾】‥カフ‥
(→)徹甲弾に同じ。
はこう‐ほんいせい【跛行本位制】‥カウ‥ヰ‥
(limping standard)金貨および銀貨を無制限法貨と認め、そのうち一方(多くは銀貨)の自由鋳造を認めない本位制度。→複本位制→併行本位制
⇒は‐こう【跛行】
はこえ
(ハコユ(またはハコフ)の連用形からか)縫腋ほうえきの袍ほうの後身うしろみの腰の辺を引き上げて内側にたたみ、左右を折りこんで袋状にした部分。格袋かくぶくろ。→縫腋の袍(図)
はこおうまる【箱王丸】‥ワウ‥
曾我時致ときむねの幼名。
はこ‐おとし【箱落し】
主として小形の獣類を捕獲するのに用いる猟具。箱の中の餌を引くと、上からおもしが落ちる仕掛けのもの。
はこ‐がき【箱書】
①書画・器物などを収める箱の蓋ふたなどに、その名称や極書きわめがきを書き、署名・押印などしたもの。作者自身、またはその弟子・私淑者などが記すことが多い。箱書付。→ともばこ。
②シナリオ執筆の際、あらかじめ各シーンの要点を書きとめておくこと。
はこ‐かなもの【箱金物】
コの字形の建築用金物。小屋束こやづかと小屋梁こやばりとの結合などに用いる。
はこ‐がまえ【匚構え】‥ガマヘ
漢字の構えの一つ。「匡」「匠」などの構えの「匚」の称。→かくしがまえ
はこ‐がめ【箱亀】
カメの一群。腹甲に蝶番ちょうつがい状の部分があって、頭や四肢を甲羅に隠してから、腹甲で開口部に蓋をすることができるカメの総称。カメ科・ドロガメ科・ヨコクビガメ科などを含む。多くは陸生だが、一部淡水生。
は‐ごく【破獄】
囚人が牢獄を破ってぬけでること。ろうやぶり。破牢。
はごく・む【育む】
〔他四〕
(→)「はぐくむ」に同じ。重之集「―・みし君を雲ゐになしてより」
はこ‐ぐるま【箱車】
①屋形のある牛車ぎっしゃ。
②上に箱形の物入れを取り付けた荷車。
はこ‐げすい【箱下水】
蓋ふたで上部を覆った、断面が長方形の下水溝。
はこ‐さかな【箱肴】
祝儀・贈答用の箱入りの魚。多く干鯛が用いられた。日本永代蔵6「先づ銀百枚・真綿二十把、斗樽壱荷に―。思ひの外なる薬代」
はこざき‐ぐう【筥崎宮】
福岡市東区箱崎にある元官幣大社。祭神は応神天皇を主神とし、神功皇后・玉依姫命を合祀。筑前国一の宮。筥崎八幡宮。はこざきのみや。
はこ‐し【箱師】
電車などの乗物の中で掏摸すりを常習とする者。
は‐ごし【葉越し】
葉の間を通り越すこと。葉の隙間から透いて見えること。
はこしき‐せっかん【箱式石棺】‥セキクワン
弥生・古墳時代の棺の一型式。板石を長方形の箱のように組み合わせて作る。箱式棺。シスト。
はこ‐じゃく【箱尺】
水準測量で、水平視線の高さを測定する目盛り尺。2段または3段の入れ子になっており、最大5メートルまで伸びる。
はこ‐じょう【箱錠】‥ヂヤウ
扉等に用いる、箱型の錠。
はこ‐ずし【箱鮨】
(→)「おしずし」に同じ。
はこ‐スパナ【箱スパナ】
ボルト頭またはナットの上から覆うようにはめて締めるスパナ。ボックス‐スパナ。
箱スパナ
 はこ‐せこ【筥迫・函迫】
(筥狭子の意という)女性がふところに挟んで持つ装身具。江戸時代、奥女中や武家中流以上の若い女性が紙入れとして使用。今は礼装の時などの装飾として用いる。
筥迫
はこ‐せこ【筥迫・函迫】
(筥狭子の意という)女性がふところに挟んで持つ装身具。江戸時代、奥女中や武家中流以上の若い女性が紙入れとして使用。今は礼装の時などの装飾として用いる。
筥迫
 筥迫
提供:ポーラ文化研究所
筥迫
提供:ポーラ文化研究所
 はこ‐ぜん【箱膳】
一人分の食器を入れておく箱。食事のときは膳とする。奉公人や家族の普段用に用いた。切溜きりだめ。
箱膳
はこ‐ぜん【箱膳】
一人分の食器を入れておく箱。食事のときは膳とする。奉公人や家族の普段用に用いた。切溜きりだめ。
箱膳
 はこ‐そ【箱訴】
江戸時代、庶民の直訴じきそを受けるため、評定所門前に目安箱めやすばこを置いて訴状を投入させた制度。
ば‐こそ
(接続助詞バに係助詞コソが付いた形)仮定条件を強調したり、反語的な意味をこめて強く否定したりするのに用いる。平家物語7「今は世の世にてもあら―」
パゴダ【pagoda】
東南アジアなどで、卒塔婆そとばの称。転じて、ヨーロッパ諸国で広く東洋の仏塔を指す。
は‐ごたえ【歯応え】‥ゴタヘ
①物をかむとき、かたくて歯に抵抗を感ずること。「―があって、うまい」
②転じて、反応。手ごたえ。「―のない人間」
はこだて【函館】
(古くは「箱館」と書いた)北海道渡島おしま半島の南東部に位置する市。港湾都市。渡島支庁所在地。もと江戸幕府の奉行所所在地。安政の仮条約により開港。1988年まで青函連絡船による北海道の玄関口。五稜郭・トラピスチヌ修道院がある。人口29万4千。
ハリストス正教会(函館)
撮影:新海良夫
はこ‐そ【箱訴】
江戸時代、庶民の直訴じきそを受けるため、評定所門前に目安箱めやすばこを置いて訴状を投入させた制度。
ば‐こそ
(接続助詞バに係助詞コソが付いた形)仮定条件を強調したり、反語的な意味をこめて強く否定したりするのに用いる。平家物語7「今は世の世にてもあら―」
パゴダ【pagoda】
東南アジアなどで、卒塔婆そとばの称。転じて、ヨーロッパ諸国で広く東洋の仏塔を指す。
は‐ごたえ【歯応え】‥ゴタヘ
①物をかむとき、かたくて歯に抵抗を感ずること。「―があって、うまい」
②転じて、反応。手ごたえ。「―のない人間」
はこだて【函館】
(古くは「箱館」と書いた)北海道渡島おしま半島の南東部に位置する市。港湾都市。渡島支庁所在地。もと江戸幕府の奉行所所在地。安政の仮条約により開港。1988年まで青函連絡船による北海道の玄関口。五稜郭・トラピスチヌ修道院がある。人口29万4千。
ハリストス正教会(函館)
撮影:新海良夫
 五稜郭
撮影:新海良夫
五稜郭
撮影:新海良夫
 ⇒はこだて‐せんそう【箱館戦争】
⇒はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】
⇒はこだて‐ほんせん【函館本線】
はこだて‐せんそう【箱館戦争】‥サウ
戊辰戦争の最後の戦い。榎本武揚ら旧幕軍の一部は、明治元年(1868)箱館五稜郭を占拠し、事実上の独立政権を作り新政府に抵抗したが、翌年攻撃を受け、5月に降伏。五稜郭の戦い。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。箱館に駐在して蝦夷地を支配し、また辺境防備の事にあたった。享和2年(1802)2月設置の蝦夷奉行を同年5月に改称。→松前奉行。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ほんせん【函館本線】
函館から小樽・札幌を経て旭川に至るJR線。迂回線を含み全長458.4キロメートル。
⇒はこだて【函館】
はこ‐だん【箱段】
①(→)箱梯子はこばしごに同じ。
②玄関の上がり台。
はこ‐ぢょうちん【箱提灯】‥ヂヤウ‥
上と下とに円く平たい蓋があって、たためば全部蓋の中に納まる構造の大形提灯。蓋には蝋燭ろうそくを出し入れする孔がある。
箱提灯
⇒はこだて‐せんそう【箱館戦争】
⇒はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】
⇒はこだて‐ほんせん【函館本線】
はこだて‐せんそう【箱館戦争】‥サウ
戊辰戦争の最後の戦い。榎本武揚ら旧幕軍の一部は、明治元年(1868)箱館五稜郭を占拠し、事実上の独立政権を作り新政府に抵抗したが、翌年攻撃を受け、5月に降伏。五稜郭の戦い。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。箱館に駐在して蝦夷地を支配し、また辺境防備の事にあたった。享和2年(1802)2月設置の蝦夷奉行を同年5月に改称。→松前奉行。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ほんせん【函館本線】
函館から小樽・札幌を経て旭川に至るJR線。迂回線を含み全長458.4キロメートル。
⇒はこだて【函館】
はこ‐だん【箱段】
①(→)箱梯子はこばしごに同じ。
②玄関の上がり台。
はこ‐ぢょうちん【箱提灯】‥ヂヤウ‥
上と下とに円く平たい蓋があって、たためば全部蓋の中に納まる構造の大形提灯。蓋には蝋燭ろうそくを出し入れする孔がある。
箱提灯
 はこつ‐さいぼう【破骨細胞】‥バウ
骨の吸収を行う細胞。骨の再構築と血清カルシウム濃度の調節に関与する。
はこ‐づめ【箱詰】
①箱に物を詰めること。また、その詰めたもの。「―の桃」
②ぎっしりと満たし詰めること。「―になった乗客」
はこ‐でっぽう【はこ鉄砲】‥パウ
(和歌山県などで)夜狙よねらいのこと。
はこ‐でんじゅ【箱伝授】
①古今集の秘伝に関する書類を箱に密封して相伝したこと。
②一般に、諸道の秘伝書や財宝などを箱入のまま相伝すること。
はこ‐どい【箱樋】‥ドヒ
⇒はこひ
はこ‐どこ【箱床】
(→)寝敷ねじき1に同じ。
はこ‐どめ【箱止】
(箱は三味線箱の意)料理屋・待合などに芸者の出入りするのを差し止めること。
はこ‐どり【箱鳥】
容鳥かおどりまたはカッコウの一名という。(和歌などで、「はこ(箱)」の縁で「あ(明)く」を導く。一説に、箱鳥は深山にすみ、夜来て塒ねぐらを求め朝早く山に帰るからという)源氏物語若菜上「み山木にねぐら定むる―もいかでか花の色にあくべき」
はこ‐にわ【箱庭】‥ニハ
箱の中に土砂を入れ、小さい木や陶器製の人形・家・橋・舟・水車などを配して、庭園・山水・名勝などを模したもの。江戸時代に流行。石台。〈[季]夏〉。→盆石。
⇒はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】
はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】‥ニハレウハフ
心理療法の一つ。砂を入れた箱とおもちゃの建物・人物・動物などを用意し、箱庭を作らせることで治療を試みるもの。
⇒はこ‐にわ【箱庭】
はこね【箱根】
神奈川県足柄下郡の町。箱根山一帯を含む。温泉・観光地。芦ノ湖南東岸の旧宿場町は東海道五十三次の一つで、江戸時代には関所があった。
⇒はこね‐うつぎ【箱根空木】
⇒はこね‐おんせん【箱根温泉】
⇒はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
⇒はこね‐ごんげん【箱根権現】
⇒はこね‐ざいく【箱根細工】
⇒はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】
⇒はこね‐じ【箱根路】
⇒はこね‐しだ【箱根羊歯】
⇒はこね‐しちとう【箱根七湯】
⇒はこね‐じんじゃ【箱根神社】
⇒はこね‐そう【箱根草】
⇒はこね‐だけ【箱根竹】
⇒はこね‐の‐せき【箱根の関】
⇒はこね‐はちり【箱根八里】
⇒はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
⇒はこね‐やま【箱根山】
⇒はこね‐ゆもと【箱根湯本】
⇒はこね‐ようすい【箱根用水】
⇒はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】
はこね‐うつぎ【箱根空木】
(箱根に多く産したとの誤認による)スイカズラ科の落葉低木。各地の海岸に自生。樹高2〜5メートル。太い髄がある。初夏、梢上や葉腋に多数の筒状花をつけ、花は初め白色、後に紅変。庭樹とする。錦帯花。〈[季]夏〉
はこねうつぎ
はこつ‐さいぼう【破骨細胞】‥バウ
骨の吸収を行う細胞。骨の再構築と血清カルシウム濃度の調節に関与する。
はこ‐づめ【箱詰】
①箱に物を詰めること。また、その詰めたもの。「―の桃」
②ぎっしりと満たし詰めること。「―になった乗客」
はこ‐でっぽう【はこ鉄砲】‥パウ
(和歌山県などで)夜狙よねらいのこと。
はこ‐でんじゅ【箱伝授】
①古今集の秘伝に関する書類を箱に密封して相伝したこと。
②一般に、諸道の秘伝書や財宝などを箱入のまま相伝すること。
はこ‐どい【箱樋】‥ドヒ
⇒はこひ
はこ‐どこ【箱床】
(→)寝敷ねじき1に同じ。
はこ‐どめ【箱止】
(箱は三味線箱の意)料理屋・待合などに芸者の出入りするのを差し止めること。
はこ‐どり【箱鳥】
容鳥かおどりまたはカッコウの一名という。(和歌などで、「はこ(箱)」の縁で「あ(明)く」を導く。一説に、箱鳥は深山にすみ、夜来て塒ねぐらを求め朝早く山に帰るからという)源氏物語若菜上「み山木にねぐら定むる―もいかでか花の色にあくべき」
はこ‐にわ【箱庭】‥ニハ
箱の中に土砂を入れ、小さい木や陶器製の人形・家・橋・舟・水車などを配して、庭園・山水・名勝などを模したもの。江戸時代に流行。石台。〈[季]夏〉。→盆石。
⇒はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】
はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】‥ニハレウハフ
心理療法の一つ。砂を入れた箱とおもちゃの建物・人物・動物などを用意し、箱庭を作らせることで治療を試みるもの。
⇒はこ‐にわ【箱庭】
はこね【箱根】
神奈川県足柄下郡の町。箱根山一帯を含む。温泉・観光地。芦ノ湖南東岸の旧宿場町は東海道五十三次の一つで、江戸時代には関所があった。
⇒はこね‐うつぎ【箱根空木】
⇒はこね‐おんせん【箱根温泉】
⇒はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
⇒はこね‐ごんげん【箱根権現】
⇒はこね‐ざいく【箱根細工】
⇒はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】
⇒はこね‐じ【箱根路】
⇒はこね‐しだ【箱根羊歯】
⇒はこね‐しちとう【箱根七湯】
⇒はこね‐じんじゃ【箱根神社】
⇒はこね‐そう【箱根草】
⇒はこね‐だけ【箱根竹】
⇒はこね‐の‐せき【箱根の関】
⇒はこね‐はちり【箱根八里】
⇒はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
⇒はこね‐やま【箱根山】
⇒はこね‐ゆもと【箱根湯本】
⇒はこね‐ようすい【箱根用水】
⇒はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】
はこね‐うつぎ【箱根空木】
(箱根に多く産したとの誤認による)スイカズラ科の落葉低木。各地の海岸に自生。樹高2〜5メートル。太い髄がある。初夏、梢上や葉腋に多数の筒状花をつけ、花は初め白色、後に紅変。庭樹とする。錦帯花。〈[季]夏〉
はこねうつぎ
 ハコネウツギ
提供:ネイチャー・プロダクション
ハコネウツギ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐おんせん【箱根温泉】‥ヲン‥
神奈川県南西部、箱根山中にある温泉の総称。いわゆる箱根七湯のほか、小涌谷こわくだに・強羅ごうら・仙石・湯ノ花沢・大平台など。酸性泉・硫黄泉・塩類泉・単純泉。泉量豊富。
箱根湯本温泉
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐おんせん【箱根温泉】‥ヲン‥
神奈川県南西部、箱根山中にある温泉の総称。いわゆる箱根七湯のほか、小涌谷こわくだに・強羅ごうら・仙石・湯ノ花沢・大平台など。酸性泉・硫黄泉・塩類泉・単純泉。泉量豊富。
箱根湯本温泉
撮影:関戸 勇
 塔ノ沢温泉
撮影:関戸 勇
塔ノ沢温泉
撮影:関戸 勇
 大平台温泉
撮影:関戸 勇
大平台温泉
撮影:関戸 勇
 宮ノ下温泉
撮影:関戸 勇
宮ノ下温泉
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
ツツジ科の小低木。箱根を中心に関東地方南西部に自生。葉は小形の倒卵形で、質厚く枝端に集まる。7月頃、葉腋に筒形白色の小花を付ける。盆栽用に栽植。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ごんげん【箱根権現】
箱根神社の別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ざいく【箱根細工】
箱根・小田原地方で土産物として発展した木工細工。とくに寄木細工や木象嵌に特色がある。
箱根細工
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
ツツジ科の小低木。箱根を中心に関東地方南西部に自生。葉は小形の倒卵形で、質厚く枝端に集まる。7月頃、葉腋に筒形白色の小花を付ける。盆栽用に栽植。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ごんげん【箱根権現】
箱根神社の別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ざいく【箱根細工】
箱根・小田原地方で土産物として発展した木工細工。とくに寄木細工や木象嵌に特色がある。
箱根細工
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】‥セウウヲ
サンショウウオの一種。全長12〜18センチメートル。体の背面は暗褐色か黒色で中央に幅広い1条のオレンジ色の帯がある。成体も肺を欠き、呼吸は皮膚で行うのが特徴。幼生は渓流中にすみ、指先に爪を持つ。本州・四国の山間にすむ。乾燥して民間薬として用いた。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じ【箱根路】‥ヂ
箱根山中を通ずる道路。小田原から箱根まで4里10町、箱根から三島まで3里20町、合わせて約8里あるところから箱根八里の称がある。
箱根路
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】‥セウウヲ
サンショウウオの一種。全長12〜18センチメートル。体の背面は暗褐色か黒色で中央に幅広い1条のオレンジ色の帯がある。成体も肺を欠き、呼吸は皮膚で行うのが特徴。幼生は渓流中にすみ、指先に爪を持つ。本州・四国の山間にすむ。乾燥して民間薬として用いた。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じ【箱根路】‥ヂ
箱根山中を通ずる道路。小田原から箱根まで4里10町、箱根から三島まで3里20町、合わせて約8里あるところから箱根八里の称がある。
箱根路
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐しだ【箱根羊歯】
(初め箱根山で採集されたことからの名)ホウライシダ科の常緑多年生シダ。山地の崖がけなどに生える。葉は羽状、葉柄は紫黒褐色で光沢がある。本州中南部以西に産し、観賞用にもする。全体を乾して去痰・利尿・通経剤とする。ハコネソウ。
はこねしだ
⇒はこね【箱根】
はこね‐しだ【箱根羊歯】
(初め箱根山で採集されたことからの名)ホウライシダ科の常緑多年生シダ。山地の崖がけなどに生える。葉は羽状、葉柄は紫黒褐色で光沢がある。本州中南部以西に産し、観賞用にもする。全体を乾して去痰・利尿・通経剤とする。ハコネソウ。
はこねしだ
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐しちとう【箱根七湯】‥タウ
箱根温泉郷にある湯本・塔ノ沢・宮ノ下・底倉・堂ヶ島・木賀きが・芦ノ湯の七温泉。木賀の代りに姥子うばこを入れることもある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じんじゃ【箱根神社】
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根、芦ノ湖東岸にある元国幣小社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと・木花開耶姫尊このはなさくやひめのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみこと。箱根権現。
⇒はこね【箱根】
はこね‐そう【箱根草】‥サウ
ハコネシダの別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐だけ【箱根竹】
アズマネザサの一品種。箱根山に多いのでこの名がある。花は春に開き緑紫色。地下茎で喫煙用のパイプを作る。
⇒はこね【箱根】
はこね‐の‐せき【箱根の関】
江戸時代初め設置された、東海道の箱根山中の関所。三島・小田原の両宿の中間にあり、箱根宿の東方の入口で、北は芦ノ湖に面し、南は山を負い、要害の地。小田原藩主が預かり、特に入鉄砲いりでっぽう出女でおんなの取締りが厳重であった。
箱根の関
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐しちとう【箱根七湯】‥タウ
箱根温泉郷にある湯本・塔ノ沢・宮ノ下・底倉・堂ヶ島・木賀きが・芦ノ湯の七温泉。木賀の代りに姥子うばこを入れることもある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じんじゃ【箱根神社】
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根、芦ノ湖東岸にある元国幣小社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと・木花開耶姫尊このはなさくやひめのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみこと。箱根権現。
⇒はこね【箱根】
はこね‐そう【箱根草】‥サウ
ハコネシダの別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐だけ【箱根竹】
アズマネザサの一品種。箱根山に多いのでこの名がある。花は春に開き緑紫色。地下茎で喫煙用のパイプを作る。
⇒はこね【箱根】
はこね‐の‐せき【箱根の関】
江戸時代初め設置された、東海道の箱根山中の関所。三島・小田原の両宿の中間にあり、箱根宿の東方の入口で、北は芦ノ湖に面し、南は山を負い、要害の地。小田原藩主が預かり、特に入鉄砲いりでっぽう出女でおんなの取締りが厳重であった。
箱根の関
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐はちり【箱根八里】
「箱根路はこねじ」参照。
⇒はこね【箱根】
はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
箱根街道などの馬子たちが歌った馬子唄。「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」とあり、大井川辺で歌われたともいう。別に「箱根駕籠かき唄」がある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐やま【箱根山】
伊豆半島の基部にあり、神奈川・静岡両県にまたがる三重式の火山。最高峰は中央火口丘の一つ、神山で標高1438メートル。火口原に芦ノ湖があり、また多数の温泉がある。交通網の整備により観光開発が進む。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ゆもと【箱根湯本】
箱根七湯の一つ。神奈川県箱根町、箱根温泉郷東部、早川渓谷に湧出する無色透明の単純泉。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ようすい【箱根用水】
箱根芦ノ湖から湖尻峠の下にトンネルを掘って西方の村々に引いた灌漑用水。1670年(寛文10)完成。深良用水。
⇒はこね【箱根】
はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】‥ヰザリ‥
浄瑠璃。司馬芝叟しばしそう作の時代物。通称「躄勝五郎」。1801年(享和1)初演。躄となった飯沼勝五郎が妻初花と共に方々を流浪するが、箱根権現の霊験によって足腰が立ち、忠僕筆助の助太刀で兄の仇佐藤剛助(滝口上野)を討ったことを脚色する。後に歌舞伎化。
⇒はこね【箱根】
はご‐の‐き【羽子の木】
〔植〕ツクバネの別称。〈[季]秋〉
はこ‐ばしご【箱梯子】
側面下部の空間を戸棚・押入・抽斗ひきだしなどに利用した梯子段。箱段。はこばし。
はこ‐ばしゃ【箱馬車】
座席の屋根をつくりつけにした箱型の馬車。島崎藤村、春「暗い―が其時門内へ引込まれた」
はこ‐ひ【箱樋・函樋】
箱形の樋。水車などの通水路として使うことが多い。はこどい。
はこび【運び】
①足をはこぶこと。歩くこと。「わざわざお―いただいて恐縮です」
②物事を進めること。また、その段取り。進み具合。「仕事の―が悪い」「近く開店の―となった」「―をつける」
⇒はこび‐でまえ【運び点前】
⇒はこび‐や【運び屋】
はこび‐こ・む【運び込む】
〔他五〕
運んで中に入れる。「家具を新居に―・む」「患者を病院に―・む」
はこび‐だ・す【運び出す】
〔他五〕
運んで外へ出す。
はこび‐でまえ【運び点前】‥マヘ
茶会で客が茶室に入ってから水指以下の茶道具を運び出して茶をたてる法。
⇒はこび【運び】
はこ‐ひばち【箱火鉢】
箱形をした木製の火鉢。
はこび‐や【運び屋】
店を構えず、小規模に物資の運搬を業とする者。特に、密輸組織の中の運搬人。
⇒はこび【運び】
はこ・ぶ【運ぶ】
[一]〔他五〕
①持ち、または積んで、送る。運送する。源氏物語若菜上「かの院よりも御調度など―・ばる」。「荷物を―・ぶ」
②そちらへ移し進める。古今著聞集2「其の外霊験の名地ごとに、あゆみを―・ばずといふ事なし」。日葡辞書「アシヲハコブ」
③推し進める。はかどらせる。徒然草「刹那覚えずといへども、是を―・びて止やまざれば、命を終ふる期忽ちにいたる」。「筆を―・ぶ」「裁縫の針を―・ぶ」
④その方へ向ける。よせる。日葡辞書「ヒトニココロザシヲハコブ」
[二]〔自五〕
①向く。寄る。拾玉集6「大寺の池の蓮はちすの花ざかり―・ぶ心にたむけてぞ見る」
②物事がうまく進む。はかどる。進捗しんちょくする。「議事が―・ぶ」
はこ‐ふぐ【箱河豚】
ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は固い骨板に包まれる。水深50メートル以浅の岩礁に生息する。肉は無毒だが、体表から粘液毒を出す。北海道南部から九州南部、台湾に分布。
はこ‐ぶね【箱船・方舟】
①長方形の船。
②ノアの方舟。神が悪に満ちた世界を絶滅しようとして洪水を起こした時、ノアが神の恩恵を得て製作し、家族や各動物種一つがいと共に乗って難を避け、アララト山に漂着したという方形の船。(旧約聖書創世記6〜8章)
はこ‐ぶみ【筥文】
叙位・除目じもくの時、硯箱の蓋に入れて御前に置く上申書。
はこ‐ぶろ【箱風呂】
風呂の一種。箱形の風呂。
はこべ【蘩蔞・繁縷】
ナデシコ科の越年草。山野・路傍に自生、しばしば群生する。高さ15〜50センチメートル、下部は地に臥す。葉は広卵形で柔らかい。春、白色の小5弁花を開く。鳥餌または食用に供し、利尿剤ともする。春の七草の一つ。あさしらげ。はこべら。
はこべ
⇒はこね【箱根】
はこね‐はちり【箱根八里】
「箱根路はこねじ」参照。
⇒はこね【箱根】
はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
箱根街道などの馬子たちが歌った馬子唄。「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」とあり、大井川辺で歌われたともいう。別に「箱根駕籠かき唄」がある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐やま【箱根山】
伊豆半島の基部にあり、神奈川・静岡両県にまたがる三重式の火山。最高峰は中央火口丘の一つ、神山で標高1438メートル。火口原に芦ノ湖があり、また多数の温泉がある。交通網の整備により観光開発が進む。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ゆもと【箱根湯本】
箱根七湯の一つ。神奈川県箱根町、箱根温泉郷東部、早川渓谷に湧出する無色透明の単純泉。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ようすい【箱根用水】
箱根芦ノ湖から湖尻峠の下にトンネルを掘って西方の村々に引いた灌漑用水。1670年(寛文10)完成。深良用水。
⇒はこね【箱根】
はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】‥ヰザリ‥
浄瑠璃。司馬芝叟しばしそう作の時代物。通称「躄勝五郎」。1801年(享和1)初演。躄となった飯沼勝五郎が妻初花と共に方々を流浪するが、箱根権現の霊験によって足腰が立ち、忠僕筆助の助太刀で兄の仇佐藤剛助(滝口上野)を討ったことを脚色する。後に歌舞伎化。
⇒はこね【箱根】
はご‐の‐き【羽子の木】
〔植〕ツクバネの別称。〈[季]秋〉
はこ‐ばしご【箱梯子】
側面下部の空間を戸棚・押入・抽斗ひきだしなどに利用した梯子段。箱段。はこばし。
はこ‐ばしゃ【箱馬車】
座席の屋根をつくりつけにした箱型の馬車。島崎藤村、春「暗い―が其時門内へ引込まれた」
はこ‐ひ【箱樋・函樋】
箱形の樋。水車などの通水路として使うことが多い。はこどい。
はこび【運び】
①足をはこぶこと。歩くこと。「わざわざお―いただいて恐縮です」
②物事を進めること。また、その段取り。進み具合。「仕事の―が悪い」「近く開店の―となった」「―をつける」
⇒はこび‐でまえ【運び点前】
⇒はこび‐や【運び屋】
はこび‐こ・む【運び込む】
〔他五〕
運んで中に入れる。「家具を新居に―・む」「患者を病院に―・む」
はこび‐だ・す【運び出す】
〔他五〕
運んで外へ出す。
はこび‐でまえ【運び点前】‥マヘ
茶会で客が茶室に入ってから水指以下の茶道具を運び出して茶をたてる法。
⇒はこび【運び】
はこ‐ひばち【箱火鉢】
箱形をした木製の火鉢。
はこび‐や【運び屋】
店を構えず、小規模に物資の運搬を業とする者。特に、密輸組織の中の運搬人。
⇒はこび【運び】
はこ・ぶ【運ぶ】
[一]〔他五〕
①持ち、または積んで、送る。運送する。源氏物語若菜上「かの院よりも御調度など―・ばる」。「荷物を―・ぶ」
②そちらへ移し進める。古今著聞集2「其の外霊験の名地ごとに、あゆみを―・ばずといふ事なし」。日葡辞書「アシヲハコブ」
③推し進める。はかどらせる。徒然草「刹那覚えずといへども、是を―・びて止やまざれば、命を終ふる期忽ちにいたる」。「筆を―・ぶ」「裁縫の針を―・ぶ」
④その方へ向ける。よせる。日葡辞書「ヒトニココロザシヲハコブ」
[二]〔自五〕
①向く。寄る。拾玉集6「大寺の池の蓮はちすの花ざかり―・ぶ心にたむけてぞ見る」
②物事がうまく進む。はかどる。進捗しんちょくする。「議事が―・ぶ」
はこ‐ふぐ【箱河豚】
ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は固い骨板に包まれる。水深50メートル以浅の岩礁に生息する。肉は無毒だが、体表から粘液毒を出す。北海道南部から九州南部、台湾に分布。
はこ‐ぶね【箱船・方舟】
①長方形の船。
②ノアの方舟。神が悪に満ちた世界を絶滅しようとして洪水を起こした時、ノアが神の恩恵を得て製作し、家族や各動物種一つがいと共に乗って難を避け、アララト山に漂着したという方形の船。(旧約聖書創世記6〜8章)
はこ‐ぶみ【筥文】
叙位・除目じもくの時、硯箱の蓋に入れて御前に置く上申書。
はこ‐ぶろ【箱風呂】
風呂の一種。箱形の風呂。
はこべ【蘩蔞・繁縷】
ナデシコ科の越年草。山野・路傍に自生、しばしば群生する。高さ15〜50センチメートル、下部は地に臥す。葉は広卵形で柔らかい。春、白色の小5弁花を開く。鳥餌または食用に供し、利尿剤ともする。春の七草の一つ。あさしらげ。はこべら。
はこべ
 ハコベ
撮影:関戸 勇
ハコベ
撮影:関戸 勇
 ⇒はこべ‐じお【蘩蔞塩】
はこべ‐じお【蘩蔞塩】‥ジホ
ハコベを青いまま炒いって、水気を去り、塩を交ぜて再び炒った粉。歯を磨くのに用いる。
⇒はこべ【蘩蔞・繁縷】
はこべ‐ら【蘩蔞】
ハコベの古名。〈[季]春〉
はこ‐べん【箱弁】
箱弁当の略。仕出し屋などが運んで来る、箱につめた弁当。
はこ‐ぼり【箱堀】
石垣で両岸を切立きったてにして箱のように造った堀。
は‐こぼれ【刃毀れ】
刃物の刃が欠けること。また、その箇所。
はこ‐まくら【箱枕】
箱形の木枕。箱の上に括枕くくりまくらをのせる。
はこ‐まわし【箱回し】‥マハシ
(→)箱屋2に同じ。
パコミオス【Pachōmios ギリシア】
エジプトのコプト教会の聖人。共住的修道制を創設、その規則はバシレイオスやベネディクトゥスに影響。パコミウス。(290頃〜346)
はこ‐むね【箱棟】
日本建築で、大棟を箱形にしておおったもの。普通は木で造る。
箱棟
⇒はこべ‐じお【蘩蔞塩】
はこべ‐じお【蘩蔞塩】‥ジホ
ハコベを青いまま炒いって、水気を去り、塩を交ぜて再び炒った粉。歯を磨くのに用いる。
⇒はこべ【蘩蔞・繁縷】
はこべ‐ら【蘩蔞】
ハコベの古名。〈[季]春〉
はこ‐べん【箱弁】
箱弁当の略。仕出し屋などが運んで来る、箱につめた弁当。
はこ‐ぼり【箱堀】
石垣で両岸を切立きったてにして箱のように造った堀。
は‐こぼれ【刃毀れ】
刃物の刃が欠けること。また、その箇所。
はこ‐まくら【箱枕】
箱形の木枕。箱の上に括枕くくりまくらをのせる。
はこ‐まわし【箱回し】‥マハシ
(→)箱屋2に同じ。
パコミオス【Pachōmios ギリシア】
エジプトのコプト教会の聖人。共住的修道制を創設、その規則はバシレイオスやベネディクトゥスに影響。パコミウス。(290頃〜346)
はこ‐むね【箱棟】
日本建築で、大棟を箱形にしておおったもの。普通は木で造る。
箱棟
 はこ‐めがね【箱眼鏡】
水面上から水中を透視しながら漁をするのに用いる箱形の眼鏡。底部はガラスまたは凸レンズ。覗眼鏡のぞきめがね。〈[季]夏〉
はこめじ‐したみ【箱目地下見】‥ヂ‥
下見2の一つ。板を垂直になるように張り、水平の目地を太い筋として現すもの。ドイツ下見。
は‐ごも【葉薦】
真菰まこもの葉を編んで作った薦。神前の案下あんかに敷く。散木奇歌集「柴の庵に―の囲ひそよめきて」
はこ‐もち【箱持】
(→)箱屋2に同じ。
はこ‐もの【箱物】
①箱形の物。箱類。
②建造物をいう語。多く十分に活用していない場合に用いる。
はこ‐もん【筥紋・箱紋】
全体を方形に描いた文様。↔円紋まるもん
はこ‐や【箱屋】
①箱を造り、またはそれを売る家。また、その人。
②御座敷に出る芸妓に従って、箱に入れた三味線を持って行く男。はこまわし。はこもち。はこ。成島柳北、柳橋新誌「妓及び酒楼船舗皆二戸けんを呼んで―と為す」
はこ‐やなぎ【箱柳】
ヤナギ科の落葉高木。ポプラと同属。山地に自生。高さ数メートル。葉は広楕円形で下面は灰白色。雌雄異株。4月頃、褐色の花穂を垂下する。街路樹などとして栽植し、軟材で、箱・マッチの軸木・製紙・経木真田用とする。ヤマナラシ。〈毛吹草〉
はこや‐の‐やま【藐姑射の山】
(「藐姑射」はバクコヤとも)
①[荘子逍遥遊]中国で不老不死の仙人が住むという山。姑射山こやさん。万葉集16「―を見まく近けむ」
②上皇の御所を祝していう称。仙洞せんとう。
はこ・ゆ
〔他下二〕
(「はこふ」とする説もある)衣服の裾をからげて箱のようにふくらませる意。裾をかかげる。枕草子144「ひき―・えたる男児」
パコ‐ラバンヌ【Paco Rabanne】
⇒ラバンヌ
は‐ごろも【羽衣】
①鳥の羽で作った薄く軽い衣。天人がこれを着て自由に空中を飛行するという。あまのはごろも。あまごろも。
②鳥・虫などの翅。
③カメムシ目ハゴロモ科の昆虫の総称。近縁なビワハゴロモ科、アオバハゴロモ科などを含めることもある。体に比して前翅が大きく、美しい色彩を呈するものが多い。(曲名別項)
⇒はごろも‐ぐさ【羽衣草】
⇒はごろも‐そう【羽衣草】
⇒はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
⇒はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
はごろも【羽衣】
能。鬘物。三保松原で漁夫白竜が羽衣をみつけたのを、天人が呼びとめて返してもらい、その礼に舞を舞って昇天する。長唄・常磐津・一中・箏曲にも作られる。→羽衣伝説
羽衣
はこ‐めがね【箱眼鏡】
水面上から水中を透視しながら漁をするのに用いる箱形の眼鏡。底部はガラスまたは凸レンズ。覗眼鏡のぞきめがね。〈[季]夏〉
はこめじ‐したみ【箱目地下見】‥ヂ‥
下見2の一つ。板を垂直になるように張り、水平の目地を太い筋として現すもの。ドイツ下見。
は‐ごも【葉薦】
真菰まこもの葉を編んで作った薦。神前の案下あんかに敷く。散木奇歌集「柴の庵に―の囲ひそよめきて」
はこ‐もち【箱持】
(→)箱屋2に同じ。
はこ‐もの【箱物】
①箱形の物。箱類。
②建造物をいう語。多く十分に活用していない場合に用いる。
はこ‐もん【筥紋・箱紋】
全体を方形に描いた文様。↔円紋まるもん
はこ‐や【箱屋】
①箱を造り、またはそれを売る家。また、その人。
②御座敷に出る芸妓に従って、箱に入れた三味線を持って行く男。はこまわし。はこもち。はこ。成島柳北、柳橋新誌「妓及び酒楼船舗皆二戸けんを呼んで―と為す」
はこ‐やなぎ【箱柳】
ヤナギ科の落葉高木。ポプラと同属。山地に自生。高さ数メートル。葉は広楕円形で下面は灰白色。雌雄異株。4月頃、褐色の花穂を垂下する。街路樹などとして栽植し、軟材で、箱・マッチの軸木・製紙・経木真田用とする。ヤマナラシ。〈毛吹草〉
はこや‐の‐やま【藐姑射の山】
(「藐姑射」はバクコヤとも)
①[荘子逍遥遊]中国で不老不死の仙人が住むという山。姑射山こやさん。万葉集16「―を見まく近けむ」
②上皇の御所を祝していう称。仙洞せんとう。
はこ・ゆ
〔他下二〕
(「はこふ」とする説もある)衣服の裾をからげて箱のようにふくらませる意。裾をかかげる。枕草子144「ひき―・えたる男児」
パコ‐ラバンヌ【Paco Rabanne】
⇒ラバンヌ
は‐ごろも【羽衣】
①鳥の羽で作った薄く軽い衣。天人がこれを着て自由に空中を飛行するという。あまのはごろも。あまごろも。
②鳥・虫などの翅。
③カメムシ目ハゴロモ科の昆虫の総称。近縁なビワハゴロモ科、アオバハゴロモ科などを含めることもある。体に比して前翅が大きく、美しい色彩を呈するものが多い。(曲名別項)
⇒はごろも‐ぐさ【羽衣草】
⇒はごろも‐そう【羽衣草】
⇒はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
⇒はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
はごろも【羽衣】
能。鬘物。三保松原で漁夫白竜が羽衣をみつけたのを、天人が呼びとめて返してもらい、その礼に舞を舞って昇天する。長唄・常磐津・一中・箏曲にも作られる。→羽衣伝説
羽衣
 『羽衣』
撮影:神田佳明(シテ:長島茂)
『羽衣』
撮影:神田佳明(シテ:長島茂)
 は‐ごろも【葉衣】
木の葉で作ったころも。
はごろも‐ぐさ【羽衣草】
(lady's-mantle)バラ科の多年草。日本を含む北半球高山帯に自生。高さ約30センチメートル。夏、淡黄緑色の小花を密生。
はごろもぐさ
は‐ごろも【葉衣】
木の葉で作ったころも。
はごろも‐ぐさ【羽衣草】
(lady's-mantle)バラ科の多年草。日本を含む北半球高山帯に自生。高さ約30センチメートル。夏、淡黄緑色の小花を密生。
はごろもぐさ
 ⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐そう【羽衣草】‥サウ
ノコギリソウの別称。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
天女が水浴中に羽衣を盗まれて天に帰れず人妻となって暮らすうち、羽衣を探し出して昇天するという伝説。駿河国三保松原(有度浜)、近江国伊香小江いかごのおえ、丹後国比治山(以上、風土記逸文)などにあるもののほか、全国に類似のものが多い。→白鳥処女説話。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
静岡市三保松原の御穂神社の南東にある松。能「羽衣」の松と伝える。
⇒は‐ごろも【羽衣】
は‐こん【波痕】
波のあと。
は‐こん【破婚】
結婚関係を解消すること。離縁。破鏡。
はさ【稲架】
(新潟・富山・福井・岐阜などで)稲掛け。稲架とうか。はざ。〈[季]秋〉
ば‐さ
(「婆娑」と当てる)
①舞う袖のひるがえるさま。
②歩きまわるさま。菅家文草2「孔肆に―たるはこれ査郎」
③影などの乱れ動くさま。蕪村句集「古傘の―と月夜の時雨かな」
④物の散り乱れるさま。
⑤竹の葉などの風にあたって鳴る音。
⑥琴などの音調の曲折あるさま。
バザー【baza(a)r】
(もとペルシア語で市場の意)社会事業などの資金を集める目的で催す市いち。慈善市。→バザール
ハザード【hazard】
(危険・障害物の意)ゴルフで、コースに設けたバンカーやウォーター‐ハザードのこと。
⇒ハザード‐マップ【hazard map】
⇒ハザード‐ランプ【hazard lamp】
ハザード‐マップ【hazard map】
(→)災害予測地図に同じ。
⇒ハザード【hazard】
ハザード‐ランプ【hazard lamp】
自動車の非常点滅表示灯。路肩停車時など、危険を他の車などに伝えるために点滅させるランプ。
⇒ハザード【hazard】
バザーリ【G. Vasari】
⇒ヴァザーリ
バザール【bāzār ペルシア】
①インド・中央アジア・中東諸国などの市場。
②種々雑多な品物を売る一群の小店。
③百貨店などの大売出し。→バザー
は‐さい【破砕・破摧】
やぶりくだくこと。また、やぶれくだけること。「岩石の―」「敵を―する」
⇒はさい‐き【破砕機】
はさい‐き【破砕機】
(→)クラッシャーに同じ。
⇒は‐さい【破砕・破摧】
は‐ざお【歯竿】‥ザヲ
(→)ラック(rack)1に同じ。
は‐ざかい【刃境】‥ザカヒ
刀の刃と地との境。
はざかい‐き【端境期】‥ザカヒ‥
古米に代わって新米が市場に出回ろうとする時期。9〜10月頃の称。転じて、果物・野菜などの市場に出回らなくなる時期、広義にはさまざまな移行期をもいう。
はさか・う【挟かふ】ハサカフ
〔自四〕
はさまる。猿蓑「塩魚の歯に―・ふや秋の暮」(荷兮)
はさ‐がた【夾形】
結髪用具。長さ約1尺、幅約5分ほどの羅うすものの紐。飾り紐に使う。
は‐さき【刃先】
刀などのきっさき。刀鋩とうぼう。
は‐さき【羽先】
はねの先端。
は‐さき【葉先】
①葉の先端。ようせん。
②(→)「かいさき(櫂先)」2に同じ。
は‐ざくら【葉桜】
①花が散って若葉が出はじめた頃の桜。〈[季]夏〉
②紋所の名。
ばさ・ける
〔自下一〕
ばさばさする。ちらばる。(嬉遊笑覧)
はささ・く【馳ささく】
〔他下二〕
馳せさせる。万葉集14「小お林に駒を―・け」
ハ‐ざし【ハ刺し】
洋裁のステッチの一種。片仮名のハの字型の針目が並ぶもの。主に芯地を表地に縫いつけるのに用いる。
は‐ざし【刃刺・羽差】
近世の沿岸鯨漁で、勢子船に乗った銛もり師。銛を打ち、捕った鯨を船に結びつけるなど、危険で熟練を要する仕事を受け持つ役。
は‐ざし【葉挿し】
挿木法の一つ。接穂つぎほに葉を用い、不定芽を出させるもの。
ば‐さし【馬刺】
馬肉の刺身。
はさ・す【馳さす】
〔他下二〕
馳せさせる。走らせる。万葉集14「さざれ石に駒を―・せて」
はさつ‐おん【破擦音】
〔言〕(affricate)破裂音の直後に摩擦音がつづき、全体で一つの単音と見なされる音。〔ts〕〔dz〕〔tʃ〕〔dʒ〕など。
ばさ‐つ・く
〔自五〕
ばさばさする。
ぱさ‐つ・く
〔自五〕
ぱさぱさになる。水分がなくなりぱさぱさした感じになる。「パンが―・く」「髪が―・く」
ばさっ‐と
〔副〕
①翼・小枝・紙の束などが触れ合ったり打ち当たったりしてたてる音、また、そのさま。「新聞を―置く」
②一気に、または大量に切断するさま。「髪を―切る」
パサデナ【Pasadena】
アメリカ合衆国南西部、ロサンゼルス市北東郊にある住宅都市。人口11万7千(2000)。
ばさ‐ばさ
①乾いた薄いものが繰り返し触れ合って発する音。また、そのさま。「鷲が―と舞い下りる」
②ものを思い切りよく大量に切り落とすさま。「枝を―と払う」
③ひとまとまりに整っているべきものが乱れているさま。「書類が―に散らかる」「―した髪」
ぱさ‐ぱさ
水分や脂肪分が抜けて乾いているさま。手触りや口当りが乾いた感じで味わいがないさま。「パンが―する」
はざ‐ま【狭間・迫間】
(古くはハサマ)
①物と物との間のせまいところ。あわい。伊勢物語「後涼殿の―を渡りければ」
②谷あい。谷。〈皇極紀訓注〉
③あいだ。ほど。おり。宇治拾遺物語11「その―は唇ばかり働くは念仏なめりと見ゆ」
④矢・鉄砲などを放つために、城壁に設けた穴。銃眼。
⑤鶯の籠につけた丸いすかし。
⇒はざま‐くばり【狭間配り】
はざま【間】
姓氏の一つ。
⇒はざま‐しげとみ【間重富】
はざま‐くばり【狭間配り】
籠城で、矢・弾丸を放つため、兵士を城壁の狭間に配置すること。
⇒はざ‐ま【狭間・迫間】
はざま‐しげとみ【間重富】
江戸後期の天文暦学者。長涯と号。大坂の質商。麻田剛立に入門、西洋の天文暦学を研究。望遠鏡や種々の観測機器を作り、天体観測上に画期をなした。のち幕府に召されて寛政改暦に当たった。(1756〜1816)
⇒はざま【間】
はさま・る【挟まる】
〔自五〕
物と物との間に入って動きがとれなくなる。宇治拾遺物語13「股に―・りてある折」。「扉に手が―・る」「二人の間に―・って苦労する」
はさみ【挟み・挿み】
はさむこと。→はさみ(鋏)。
⇒はさみ‐いた【挟板】
⇒はさみ‐うち【挟み撃ち】
⇒はさみ‐おび【挟み帯】
⇒はさみ‐かせ【挟械】
⇒はさみ‐がみ【挟み紙】
⇒はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
⇒はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
⇒はさみ‐ざかな【挟み肴】
⇒はさみ‐じょう【挟み状】
⇒はさみ‐しょうぎ【挟み将棋】
⇒はさみ‐だけ【挟み竹】
⇒はさみ‐ばこ【挟箱】
⇒はさみ‐むすび【挟み結び】
⇒はさみ‐もの【挟み物・挿み物】
はさみ【鋏・剪刀】
①2枚の刃で挟むようにして物を切る道具。切符などに穴をあけるパンチのこともいう。〈倭名類聚鈔15〉
②(「螯」「鉗」とも書く)節足動物のカニ・サソリなどの脚の(→)鋏1のような部分。これを持つ脚を特に鋏脚(鉗脚かんきゃくとも)という。
③(じゃんけんで)2本の指を伸ばした形。ちょき。「石、紙、―」
⇒はさみじょう‐かかくさ【鋏状価格差】
⇒はさみ‐ばん【鋏盤】
⇒はさみ‐むし【鋏虫・蠼螋】
⇒鋏を入れる
はさみ‐あ・げる【挟み上げる】
〔他下一〕[文]はさみあ・ぐ(下二)
箸などで、はさんで持ち上げる。
はさみ‐いた【挟板】
門の左右に取り付ける板作りの袖。はさいた。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐い・れる【挟み入れる】
〔他下一〕[文]はさみい・る(下二)
①物の間に入れこむ。はさみこむ。
②はさんで他へ移し入れる。
はさみ‐うち【挟み撃ち】
相手を両側から挟むようにして攻撃すること。「敵を―にする」
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐う・つ【挟み撃つ】
〔他五〕
敵を中に挟んで、左右または前後から攻撃する。
はさみ‐おび【挟み帯】
はさみ結びにすること。さしこみおび。つっこみおび。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐かせ【挟械】
掘建ほったて柱の根を固めるために、その左右に取り付ける根かせ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐がみ【挟み紙】
①書物の中の必要な箇所に注意のために挟む紙片。しおり。
②重ねてある物品の間に挟んで、傷がつかないようにする紙。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐き・る【剪み切る】
〔他四〕
鋏で切り取る。
はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
限界ゲージの一種。ゲージの口を工作物にあてがい、円筒形・球形の直径、直方体の厚さなどが許しうる上限と下限の間に入っているかどうか検査するのに用いる。スナップ‐ゲージ。
挟みゲージ
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐そう【羽衣草】‥サウ
ノコギリソウの別称。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
天女が水浴中に羽衣を盗まれて天に帰れず人妻となって暮らすうち、羽衣を探し出して昇天するという伝説。駿河国三保松原(有度浜)、近江国伊香小江いかごのおえ、丹後国比治山(以上、風土記逸文)などにあるもののほか、全国に類似のものが多い。→白鳥処女説話。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
静岡市三保松原の御穂神社の南東にある松。能「羽衣」の松と伝える。
⇒は‐ごろも【羽衣】
は‐こん【波痕】
波のあと。
は‐こん【破婚】
結婚関係を解消すること。離縁。破鏡。
はさ【稲架】
(新潟・富山・福井・岐阜などで)稲掛け。稲架とうか。はざ。〈[季]秋〉
ば‐さ
(「婆娑」と当てる)
①舞う袖のひるがえるさま。
②歩きまわるさま。菅家文草2「孔肆に―たるはこれ査郎」
③影などの乱れ動くさま。蕪村句集「古傘の―と月夜の時雨かな」
④物の散り乱れるさま。
⑤竹の葉などの風にあたって鳴る音。
⑥琴などの音調の曲折あるさま。
バザー【baza(a)r】
(もとペルシア語で市場の意)社会事業などの資金を集める目的で催す市いち。慈善市。→バザール
ハザード【hazard】
(危険・障害物の意)ゴルフで、コースに設けたバンカーやウォーター‐ハザードのこと。
⇒ハザード‐マップ【hazard map】
⇒ハザード‐ランプ【hazard lamp】
ハザード‐マップ【hazard map】
(→)災害予測地図に同じ。
⇒ハザード【hazard】
ハザード‐ランプ【hazard lamp】
自動車の非常点滅表示灯。路肩停車時など、危険を他の車などに伝えるために点滅させるランプ。
⇒ハザード【hazard】
バザーリ【G. Vasari】
⇒ヴァザーリ
バザール【bāzār ペルシア】
①インド・中央アジア・中東諸国などの市場。
②種々雑多な品物を売る一群の小店。
③百貨店などの大売出し。→バザー
は‐さい【破砕・破摧】
やぶりくだくこと。また、やぶれくだけること。「岩石の―」「敵を―する」
⇒はさい‐き【破砕機】
はさい‐き【破砕機】
(→)クラッシャーに同じ。
⇒は‐さい【破砕・破摧】
は‐ざお【歯竿】‥ザヲ
(→)ラック(rack)1に同じ。
は‐ざかい【刃境】‥ザカヒ
刀の刃と地との境。
はざかい‐き【端境期】‥ザカヒ‥
古米に代わって新米が市場に出回ろうとする時期。9〜10月頃の称。転じて、果物・野菜などの市場に出回らなくなる時期、広義にはさまざまな移行期をもいう。
はさか・う【挟かふ】ハサカフ
〔自四〕
はさまる。猿蓑「塩魚の歯に―・ふや秋の暮」(荷兮)
はさ‐がた【夾形】
結髪用具。長さ約1尺、幅約5分ほどの羅うすものの紐。飾り紐に使う。
は‐さき【刃先】
刀などのきっさき。刀鋩とうぼう。
は‐さき【羽先】
はねの先端。
は‐さき【葉先】
①葉の先端。ようせん。
②(→)「かいさき(櫂先)」2に同じ。
は‐ざくら【葉桜】
①花が散って若葉が出はじめた頃の桜。〈[季]夏〉
②紋所の名。
ばさ・ける
〔自下一〕
ばさばさする。ちらばる。(嬉遊笑覧)
はささ・く【馳ささく】
〔他下二〕
馳せさせる。万葉集14「小お林に駒を―・け」
ハ‐ざし【ハ刺し】
洋裁のステッチの一種。片仮名のハの字型の針目が並ぶもの。主に芯地を表地に縫いつけるのに用いる。
は‐ざし【刃刺・羽差】
近世の沿岸鯨漁で、勢子船に乗った銛もり師。銛を打ち、捕った鯨を船に結びつけるなど、危険で熟練を要する仕事を受け持つ役。
は‐ざし【葉挿し】
挿木法の一つ。接穂つぎほに葉を用い、不定芽を出させるもの。
ば‐さし【馬刺】
馬肉の刺身。
はさ・す【馳さす】
〔他下二〕
馳せさせる。走らせる。万葉集14「さざれ石に駒を―・せて」
はさつ‐おん【破擦音】
〔言〕(affricate)破裂音の直後に摩擦音がつづき、全体で一つの単音と見なされる音。〔ts〕〔dz〕〔tʃ〕〔dʒ〕など。
ばさ‐つ・く
〔自五〕
ばさばさする。
ぱさ‐つ・く
〔自五〕
ぱさぱさになる。水分がなくなりぱさぱさした感じになる。「パンが―・く」「髪が―・く」
ばさっ‐と
〔副〕
①翼・小枝・紙の束などが触れ合ったり打ち当たったりしてたてる音、また、そのさま。「新聞を―置く」
②一気に、または大量に切断するさま。「髪を―切る」
パサデナ【Pasadena】
アメリカ合衆国南西部、ロサンゼルス市北東郊にある住宅都市。人口11万7千(2000)。
ばさ‐ばさ
①乾いた薄いものが繰り返し触れ合って発する音。また、そのさま。「鷲が―と舞い下りる」
②ものを思い切りよく大量に切り落とすさま。「枝を―と払う」
③ひとまとまりに整っているべきものが乱れているさま。「書類が―に散らかる」「―した髪」
ぱさ‐ぱさ
水分や脂肪分が抜けて乾いているさま。手触りや口当りが乾いた感じで味わいがないさま。「パンが―する」
はざ‐ま【狭間・迫間】
(古くはハサマ)
①物と物との間のせまいところ。あわい。伊勢物語「後涼殿の―を渡りければ」
②谷あい。谷。〈皇極紀訓注〉
③あいだ。ほど。おり。宇治拾遺物語11「その―は唇ばかり働くは念仏なめりと見ゆ」
④矢・鉄砲などを放つために、城壁に設けた穴。銃眼。
⑤鶯の籠につけた丸いすかし。
⇒はざま‐くばり【狭間配り】
はざま【間】
姓氏の一つ。
⇒はざま‐しげとみ【間重富】
はざま‐くばり【狭間配り】
籠城で、矢・弾丸を放つため、兵士を城壁の狭間に配置すること。
⇒はざ‐ま【狭間・迫間】
はざま‐しげとみ【間重富】
江戸後期の天文暦学者。長涯と号。大坂の質商。麻田剛立に入門、西洋の天文暦学を研究。望遠鏡や種々の観測機器を作り、天体観測上に画期をなした。のち幕府に召されて寛政改暦に当たった。(1756〜1816)
⇒はざま【間】
はさま・る【挟まる】
〔自五〕
物と物との間に入って動きがとれなくなる。宇治拾遺物語13「股に―・りてある折」。「扉に手が―・る」「二人の間に―・って苦労する」
はさみ【挟み・挿み】
はさむこと。→はさみ(鋏)。
⇒はさみ‐いた【挟板】
⇒はさみ‐うち【挟み撃ち】
⇒はさみ‐おび【挟み帯】
⇒はさみ‐かせ【挟械】
⇒はさみ‐がみ【挟み紙】
⇒はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
⇒はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
⇒はさみ‐ざかな【挟み肴】
⇒はさみ‐じょう【挟み状】
⇒はさみ‐しょうぎ【挟み将棋】
⇒はさみ‐だけ【挟み竹】
⇒はさみ‐ばこ【挟箱】
⇒はさみ‐むすび【挟み結び】
⇒はさみ‐もの【挟み物・挿み物】
はさみ【鋏・剪刀】
①2枚の刃で挟むようにして物を切る道具。切符などに穴をあけるパンチのこともいう。〈倭名類聚鈔15〉
②(「螯」「鉗」とも書く)節足動物のカニ・サソリなどの脚の(→)鋏1のような部分。これを持つ脚を特に鋏脚(鉗脚かんきゃくとも)という。
③(じゃんけんで)2本の指を伸ばした形。ちょき。「石、紙、―」
⇒はさみじょう‐かかくさ【鋏状価格差】
⇒はさみ‐ばん【鋏盤】
⇒はさみ‐むし【鋏虫・蠼螋】
⇒鋏を入れる
はさみ‐あ・げる【挟み上げる】
〔他下一〕[文]はさみあ・ぐ(下二)
箸などで、はさんで持ち上げる。
はさみ‐いた【挟板】
門の左右に取り付ける板作りの袖。はさいた。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐い・れる【挟み入れる】
〔他下一〕[文]はさみい・る(下二)
①物の間に入れこむ。はさみこむ。
②はさんで他へ移し入れる。
はさみ‐うち【挟み撃ち】
相手を両側から挟むようにして攻撃すること。「敵を―にする」
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐う・つ【挟み撃つ】
〔他五〕
敵を中に挟んで、左右または前後から攻撃する。
はさみ‐おび【挟み帯】
はさみ結びにすること。さしこみおび。つっこみおび。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐かせ【挟械】
掘建ほったて柱の根を固めるために、その左右に取り付ける根かせ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐がみ【挟み紙】
①書物の中の必要な箇所に注意のために挟む紙片。しおり。
②重ねてある物品の間に挟んで、傷がつかないようにする紙。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐き・る【剪み切る】
〔他四〕
鋏で切り取る。
はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
限界ゲージの一種。ゲージの口を工作物にあてがい、円筒形・球形の直径、直方体の厚さなどが許しうる上限と下限の間に入っているかどうか検査するのに用いる。スナップ‐ゲージ。
挟みゲージ
 ⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
①文の中に挟み込むことば。
②(→)唐言からことに同じ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐こ・む【
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
①文の中に挟み込むことば。
②(→)唐言からことに同じ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐こ・む【
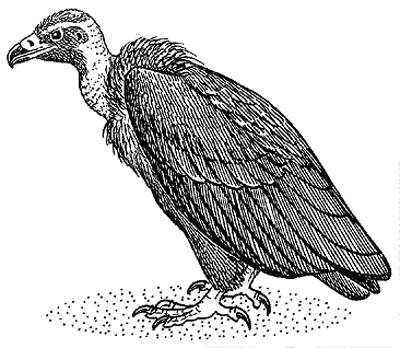 シロエリハゲワシ
撮影:小宮輝之
シロエリハゲワシ
撮影:小宮輝之
 ミミハゲワシ
撮影:小宮輝之
ミミハゲワシ
撮影:小宮輝之
 クロハゲワシ
提供:OPO
クロハゲワシ
提供:OPO
 は‐けん【派遣】
①諸方へ分けて送り遣わすこと。
②命じて出張させること。「視察団を―する」「人材―業」
⇒はけん‐ろうどう【派遣労働】
は‐けん【覇権】
①武力や権謀をもって競争者を抑えて得た権力。覇者としての権力。頭領の権力。「―主義」「―を握る」
②転じて、競技などで優勝者としての資格。「―をかけて争う」
ば‐けん【馬券】
競馬で、勝ち馬を予想して投票する券。勝馬投票券の通称。「―を買う」
ば‐げん【罵言】
ののしることば。悪口。「―を吐く」
は‐げんか【端喧嘩】‥クワ
取るに足りない小さいけんか。小ぜりあいのけんか。
ば‐けんちゅう【馬建忠】
清末の官僚。江蘇丹徒の人。フランスに留学。洋務派として外交に活躍。著「馬氏文通」「適可斎記言」。(1845〜1900)
はけん‐ろうどう【派遣労働】‥ラウ‥
派遣会社が雇っている労働者が、契約先の企業に派遣されて業務にあたる労働形態。
⇒は‐けん【派遣】
はこ【箱・函・筥・匣・筐】
①物を納めておく器。普通、角型で木・紙・竹などで作る。万葉集9「この―を開きて見てば」。「宝石―」
②便所で糞を受ける箱。おまる。おかわ。今昔物語集30「―洗ひに行かむを伺ひ」
③転じて、(人の)糞。
④挟箱はさみばこの略。
⑤三味線を入れる箱。転じて、三味線。また、三味線を入れた箱を持って芸者に従って行く男。はこや。
⑥牛車の屋形やかた。車箱。また、鉄道車両の車室やエレベーターのケージ。
⑦(東北地方で)岩壁で囲まれた渓谷の一部。
⑧(「箱入り」の略)とっておきの芸。得意芸。おはこ。譬喩尽「―じや。箱入との事、其の芸の手に入りし語なり」
はご【
は‐けん【派遣】
①諸方へ分けて送り遣わすこと。
②命じて出張させること。「視察団を―する」「人材―業」
⇒はけん‐ろうどう【派遣労働】
は‐けん【覇権】
①武力や権謀をもって競争者を抑えて得た権力。覇者としての権力。頭領の権力。「―主義」「―を握る」
②転じて、競技などで優勝者としての資格。「―をかけて争う」
ば‐けん【馬券】
競馬で、勝ち馬を予想して投票する券。勝馬投票券の通称。「―を買う」
ば‐げん【罵言】
ののしることば。悪口。「―を吐く」
は‐げんか【端喧嘩】‥クワ
取るに足りない小さいけんか。小ぜりあいのけんか。
ば‐けんちゅう【馬建忠】
清末の官僚。江蘇丹徒の人。フランスに留学。洋務派として外交に活躍。著「馬氏文通」「適可斎記言」。(1845〜1900)
はけん‐ろうどう【派遣労働】‥ラウ‥
派遣会社が雇っている労働者が、契約先の企業に派遣されて業務にあたる労働形態。
⇒は‐けん【派遣】
はこ【箱・函・筥・匣・筐】
①物を納めておく器。普通、角型で木・紙・竹などで作る。万葉集9「この―を開きて見てば」。「宝石―」
②便所で糞を受ける箱。おまる。おかわ。今昔物語集30「―洗ひに行かむを伺ひ」
③転じて、(人の)糞。
④挟箱はさみばこの略。
⑤三味線を入れる箱。転じて、三味線。また、三味線を入れた箱を持って芸者に従って行く男。はこや。
⑥牛車の屋形やかた。車箱。また、鉄道車両の車室やエレベーターのケージ。
⑦(東北地方で)岩壁で囲まれた渓谷の一部。
⑧(「箱入り」の略)とっておきの芸。得意芸。おはこ。譬喩尽「―じや。箱入との事、其の芸の手に入りし語なり」
はご【 ・黐
・黐 】
(→)「はが」に同じ。〈日葡辞書〉
は‐ご【羽子】
ムクロジの核に孔をうがち、彩色した鳥の小羽を数枚さしこんだもの。羽子板でこれをついて遊ぶ。はね。つくばね。おいばね。
はご‐いた【羽子板】
羽子をつくのに用いる長方形で柄のある板。桐・杉などで作り、表に絵を描き、または押絵を付けなどする。胡鬼板こぎいた。〈[季]新年〉
羽子板
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
】
(→)「はが」に同じ。〈日葡辞書〉
は‐ご【羽子】
ムクロジの核に孔をうがち、彩色した鳥の小羽を数枚さしこんだもの。羽子板でこれをついて遊ぶ。はね。つくばね。おいばね。
はご‐いた【羽子板】
羽子をつくのに用いる長方形で柄のある板。桐・杉などで作り、表に絵を描き、または押絵を付けなどする。胡鬼板こぎいた。〈[季]新年〉
羽子板
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(宮崎)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(宮崎)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(山梨)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(山梨)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(熊本)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(熊本)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(福島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(福島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(群馬)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(群馬)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(静岡)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(静岡)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 羽子板(鹿児島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
羽子板(鹿児島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒はごいた‐いち【羽子板市】
⇒はごいた‐かなもの【羽子板金物】
⇒はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
はごいた‐いち【羽子板市】
歳末に立つ、羽子板を売る市。〈[季]冬〉
羽子板市(浅草寺)
提供:東京都
⇒はごいた‐いち【羽子板市】
⇒はごいた‐かなもの【羽子板金物】
⇒はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
はごいた‐いち【羽子板市】
歳末に立つ、羽子板を売る市。〈[季]冬〉
羽子板市(浅草寺)
提供:東京都
 ⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐かなもの【羽子板金物】
(→)羽子板ボルトに同じ。
⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
一端が孔つきの平板になっているボルト。
⇒はご‐いた【羽子板】
はこ‐いり【箱入り】
①箱に入っていること。また、入っているもの。西鶴織留2「此丁銀―にして請取」
②大切にすること。また、そのもの。傾城禁短気「太夫さまを―にして」
③とっておきの芸。おはこ。
④箱入り娘の略。
⇒はこいり‐むすめ【箱入り娘】
はこいり‐むすめ【箱入り娘】
大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘。秘蔵娘。人情本、春色辰巳園「箱入娘はこいれむすめかなんぞのようにしたふ」
⇒はこ‐いり【箱入り】
は‐こう【八講】‥カウ
法華八講ほっけはっこうのこと。枕草子35「結縁の―し給ふ」
は‐こう【波光】‥クワウ
波のきらめく色。
は‐こう【波高】‥カウ
波の高さ。
は‐こう【爬行】‥カウ
はって行くこと。
は‐こう【跛行】‥カウ
①片足をひきずって行くこと。
②釣合のとれないこと。順調でないこと。「―景気」
⇒はこう‐ほんいせい【跛行本位制】
はこ・うハコフ
〔他下二〕
⇒はこゆ
ば‐こう【馬耕】‥カウ
馬を用いて田畑を耕すこと。
ば‐こうせん【場口銭】
(取引用語)市場で、取引所が取引員から徴収する手数料。
はこう‐だん【破甲弾】‥カフ‥
(→)徹甲弾に同じ。
はこう‐ほんいせい【跛行本位制】‥カウ‥ヰ‥
(limping standard)金貨および銀貨を無制限法貨と認め、そのうち一方(多くは銀貨)の自由鋳造を認めない本位制度。→複本位制→併行本位制
⇒は‐こう【跛行】
はこえ
(ハコユ(またはハコフ)の連用形からか)縫腋ほうえきの袍ほうの後身うしろみの腰の辺を引き上げて内側にたたみ、左右を折りこんで袋状にした部分。格袋かくぶくろ。→縫腋の袍(図)
はこおうまる【箱王丸】‥ワウ‥
曾我時致ときむねの幼名。
はこ‐おとし【箱落し】
主として小形の獣類を捕獲するのに用いる猟具。箱の中の餌を引くと、上からおもしが落ちる仕掛けのもの。
はこ‐がき【箱書】
①書画・器物などを収める箱の蓋ふたなどに、その名称や極書きわめがきを書き、署名・押印などしたもの。作者自身、またはその弟子・私淑者などが記すことが多い。箱書付。→ともばこ。
②シナリオ執筆の際、あらかじめ各シーンの要点を書きとめておくこと。
はこ‐かなもの【箱金物】
コの字形の建築用金物。小屋束こやづかと小屋梁こやばりとの結合などに用いる。
はこ‐がまえ【匚構え】‥ガマヘ
漢字の構えの一つ。「匡」「匠」などの構えの「匚」の称。→かくしがまえ
はこ‐がめ【箱亀】
カメの一群。腹甲に蝶番ちょうつがい状の部分があって、頭や四肢を甲羅に隠してから、腹甲で開口部に蓋をすることができるカメの総称。カメ科・ドロガメ科・ヨコクビガメ科などを含む。多くは陸生だが、一部淡水生。
は‐ごく【破獄】
囚人が牢獄を破ってぬけでること。ろうやぶり。破牢。
はごく・む【育む】
〔他四〕
(→)「はぐくむ」に同じ。重之集「―・みし君を雲ゐになしてより」
はこ‐ぐるま【箱車】
①屋形のある牛車ぎっしゃ。
②上に箱形の物入れを取り付けた荷車。
はこ‐げすい【箱下水】
蓋ふたで上部を覆った、断面が長方形の下水溝。
はこ‐さかな【箱肴】
祝儀・贈答用の箱入りの魚。多く干鯛が用いられた。日本永代蔵6「先づ銀百枚・真綿二十把、斗樽壱荷に―。思ひの外なる薬代」
はこざき‐ぐう【筥崎宮】
福岡市東区箱崎にある元官幣大社。祭神は応神天皇を主神とし、神功皇后・玉依姫命を合祀。筑前国一の宮。筥崎八幡宮。はこざきのみや。
はこ‐し【箱師】
電車などの乗物の中で掏摸すりを常習とする者。
は‐ごし【葉越し】
葉の間を通り越すこと。葉の隙間から透いて見えること。
はこしき‐せっかん【箱式石棺】‥セキクワン
弥生・古墳時代の棺の一型式。板石を長方形の箱のように組み合わせて作る。箱式棺。シスト。
はこ‐じゃく【箱尺】
水準測量で、水平視線の高さを測定する目盛り尺。2段または3段の入れ子になっており、最大5メートルまで伸びる。
はこ‐じょう【箱錠】‥ヂヤウ
扉等に用いる、箱型の錠。
はこ‐ずし【箱鮨】
(→)「おしずし」に同じ。
はこ‐スパナ【箱スパナ】
ボルト頭またはナットの上から覆うようにはめて締めるスパナ。ボックス‐スパナ。
箱スパナ
⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐かなもの【羽子板金物】
(→)羽子板ボルトに同じ。
⇒はご‐いた【羽子板】
はごいた‐ボルト【羽子板ボルト】
一端が孔つきの平板になっているボルト。
⇒はご‐いた【羽子板】
はこ‐いり【箱入り】
①箱に入っていること。また、入っているもの。西鶴織留2「此丁銀―にして請取」
②大切にすること。また、そのもの。傾城禁短気「太夫さまを―にして」
③とっておきの芸。おはこ。
④箱入り娘の略。
⇒はこいり‐むすめ【箱入り娘】
はこいり‐むすめ【箱入り娘】
大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘。秘蔵娘。人情本、春色辰巳園「箱入娘はこいれむすめかなんぞのようにしたふ」
⇒はこ‐いり【箱入り】
は‐こう【八講】‥カウ
法華八講ほっけはっこうのこと。枕草子35「結縁の―し給ふ」
は‐こう【波光】‥クワウ
波のきらめく色。
は‐こう【波高】‥カウ
波の高さ。
は‐こう【爬行】‥カウ
はって行くこと。
は‐こう【跛行】‥カウ
①片足をひきずって行くこと。
②釣合のとれないこと。順調でないこと。「―景気」
⇒はこう‐ほんいせい【跛行本位制】
はこ・うハコフ
〔他下二〕
⇒はこゆ
ば‐こう【馬耕】‥カウ
馬を用いて田畑を耕すこと。
ば‐こうせん【場口銭】
(取引用語)市場で、取引所が取引員から徴収する手数料。
はこう‐だん【破甲弾】‥カフ‥
(→)徹甲弾に同じ。
はこう‐ほんいせい【跛行本位制】‥カウ‥ヰ‥
(limping standard)金貨および銀貨を無制限法貨と認め、そのうち一方(多くは銀貨)の自由鋳造を認めない本位制度。→複本位制→併行本位制
⇒は‐こう【跛行】
はこえ
(ハコユ(またはハコフ)の連用形からか)縫腋ほうえきの袍ほうの後身うしろみの腰の辺を引き上げて内側にたたみ、左右を折りこんで袋状にした部分。格袋かくぶくろ。→縫腋の袍(図)
はこおうまる【箱王丸】‥ワウ‥
曾我時致ときむねの幼名。
はこ‐おとし【箱落し】
主として小形の獣類を捕獲するのに用いる猟具。箱の中の餌を引くと、上からおもしが落ちる仕掛けのもの。
はこ‐がき【箱書】
①書画・器物などを収める箱の蓋ふたなどに、その名称や極書きわめがきを書き、署名・押印などしたもの。作者自身、またはその弟子・私淑者などが記すことが多い。箱書付。→ともばこ。
②シナリオ執筆の際、あらかじめ各シーンの要点を書きとめておくこと。
はこ‐かなもの【箱金物】
コの字形の建築用金物。小屋束こやづかと小屋梁こやばりとの結合などに用いる。
はこ‐がまえ【匚構え】‥ガマヘ
漢字の構えの一つ。「匡」「匠」などの構えの「匚」の称。→かくしがまえ
はこ‐がめ【箱亀】
カメの一群。腹甲に蝶番ちょうつがい状の部分があって、頭や四肢を甲羅に隠してから、腹甲で開口部に蓋をすることができるカメの総称。カメ科・ドロガメ科・ヨコクビガメ科などを含む。多くは陸生だが、一部淡水生。
は‐ごく【破獄】
囚人が牢獄を破ってぬけでること。ろうやぶり。破牢。
はごく・む【育む】
〔他四〕
(→)「はぐくむ」に同じ。重之集「―・みし君を雲ゐになしてより」
はこ‐ぐるま【箱車】
①屋形のある牛車ぎっしゃ。
②上に箱形の物入れを取り付けた荷車。
はこ‐げすい【箱下水】
蓋ふたで上部を覆った、断面が長方形の下水溝。
はこ‐さかな【箱肴】
祝儀・贈答用の箱入りの魚。多く干鯛が用いられた。日本永代蔵6「先づ銀百枚・真綿二十把、斗樽壱荷に―。思ひの外なる薬代」
はこざき‐ぐう【筥崎宮】
福岡市東区箱崎にある元官幣大社。祭神は応神天皇を主神とし、神功皇后・玉依姫命を合祀。筑前国一の宮。筥崎八幡宮。はこざきのみや。
はこ‐し【箱師】
電車などの乗物の中で掏摸すりを常習とする者。
は‐ごし【葉越し】
葉の間を通り越すこと。葉の隙間から透いて見えること。
はこしき‐せっかん【箱式石棺】‥セキクワン
弥生・古墳時代の棺の一型式。板石を長方形の箱のように組み合わせて作る。箱式棺。シスト。
はこ‐じゃく【箱尺】
水準測量で、水平視線の高さを測定する目盛り尺。2段または3段の入れ子になっており、最大5メートルまで伸びる。
はこ‐じょう【箱錠】‥ヂヤウ
扉等に用いる、箱型の錠。
はこ‐ずし【箱鮨】
(→)「おしずし」に同じ。
はこ‐スパナ【箱スパナ】
ボルト頭またはナットの上から覆うようにはめて締めるスパナ。ボックス‐スパナ。
箱スパナ
 はこ‐せこ【筥迫・函迫】
(筥狭子の意という)女性がふところに挟んで持つ装身具。江戸時代、奥女中や武家中流以上の若い女性が紙入れとして使用。今は礼装の時などの装飾として用いる。
筥迫
はこ‐せこ【筥迫・函迫】
(筥狭子の意という)女性がふところに挟んで持つ装身具。江戸時代、奥女中や武家中流以上の若い女性が紙入れとして使用。今は礼装の時などの装飾として用いる。
筥迫
 筥迫
提供:ポーラ文化研究所
筥迫
提供:ポーラ文化研究所
 はこ‐ぜん【箱膳】
一人分の食器を入れておく箱。食事のときは膳とする。奉公人や家族の普段用に用いた。切溜きりだめ。
箱膳
はこ‐ぜん【箱膳】
一人分の食器を入れておく箱。食事のときは膳とする。奉公人や家族の普段用に用いた。切溜きりだめ。
箱膳
 はこ‐そ【箱訴】
江戸時代、庶民の直訴じきそを受けるため、評定所門前に目安箱めやすばこを置いて訴状を投入させた制度。
ば‐こそ
(接続助詞バに係助詞コソが付いた形)仮定条件を強調したり、反語的な意味をこめて強く否定したりするのに用いる。平家物語7「今は世の世にてもあら―」
パゴダ【pagoda】
東南アジアなどで、卒塔婆そとばの称。転じて、ヨーロッパ諸国で広く東洋の仏塔を指す。
は‐ごたえ【歯応え】‥ゴタヘ
①物をかむとき、かたくて歯に抵抗を感ずること。「―があって、うまい」
②転じて、反応。手ごたえ。「―のない人間」
はこだて【函館】
(古くは「箱館」と書いた)北海道渡島おしま半島の南東部に位置する市。港湾都市。渡島支庁所在地。もと江戸幕府の奉行所所在地。安政の仮条約により開港。1988年まで青函連絡船による北海道の玄関口。五稜郭・トラピスチヌ修道院がある。人口29万4千。
ハリストス正教会(函館)
撮影:新海良夫
はこ‐そ【箱訴】
江戸時代、庶民の直訴じきそを受けるため、評定所門前に目安箱めやすばこを置いて訴状を投入させた制度。
ば‐こそ
(接続助詞バに係助詞コソが付いた形)仮定条件を強調したり、反語的な意味をこめて強く否定したりするのに用いる。平家物語7「今は世の世にてもあら―」
パゴダ【pagoda】
東南アジアなどで、卒塔婆そとばの称。転じて、ヨーロッパ諸国で広く東洋の仏塔を指す。
は‐ごたえ【歯応え】‥ゴタヘ
①物をかむとき、かたくて歯に抵抗を感ずること。「―があって、うまい」
②転じて、反応。手ごたえ。「―のない人間」
はこだて【函館】
(古くは「箱館」と書いた)北海道渡島おしま半島の南東部に位置する市。港湾都市。渡島支庁所在地。もと江戸幕府の奉行所所在地。安政の仮条約により開港。1988年まで青函連絡船による北海道の玄関口。五稜郭・トラピスチヌ修道院がある。人口29万4千。
ハリストス正教会(函館)
撮影:新海良夫
 五稜郭
撮影:新海良夫
五稜郭
撮影:新海良夫
 ⇒はこだて‐せんそう【箱館戦争】
⇒はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】
⇒はこだて‐ほんせん【函館本線】
はこだて‐せんそう【箱館戦争】‥サウ
戊辰戦争の最後の戦い。榎本武揚ら旧幕軍の一部は、明治元年(1868)箱館五稜郭を占拠し、事実上の独立政権を作り新政府に抵抗したが、翌年攻撃を受け、5月に降伏。五稜郭の戦い。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。箱館に駐在して蝦夷地を支配し、また辺境防備の事にあたった。享和2年(1802)2月設置の蝦夷奉行を同年5月に改称。→松前奉行。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ほんせん【函館本線】
函館から小樽・札幌を経て旭川に至るJR線。迂回線を含み全長458.4キロメートル。
⇒はこだて【函館】
はこ‐だん【箱段】
①(→)箱梯子はこばしごに同じ。
②玄関の上がり台。
はこ‐ぢょうちん【箱提灯】‥ヂヤウ‥
上と下とに円く平たい蓋があって、たためば全部蓋の中に納まる構造の大形提灯。蓋には蝋燭ろうそくを出し入れする孔がある。
箱提灯
⇒はこだて‐せんそう【箱館戦争】
⇒はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】
⇒はこだて‐ほんせん【函館本線】
はこだて‐せんそう【箱館戦争】‥サウ
戊辰戦争の最後の戦い。榎本武揚ら旧幕軍の一部は、明治元年(1868)箱館五稜郭を占拠し、事実上の独立政権を作り新政府に抵抗したが、翌年攻撃を受け、5月に降伏。五稜郭の戦い。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ぶぎょう【箱館奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。箱館に駐在して蝦夷地を支配し、また辺境防備の事にあたった。享和2年(1802)2月設置の蝦夷奉行を同年5月に改称。→松前奉行。
⇒はこだて【函館】
はこだて‐ほんせん【函館本線】
函館から小樽・札幌を経て旭川に至るJR線。迂回線を含み全長458.4キロメートル。
⇒はこだて【函館】
はこ‐だん【箱段】
①(→)箱梯子はこばしごに同じ。
②玄関の上がり台。
はこ‐ぢょうちん【箱提灯】‥ヂヤウ‥
上と下とに円く平たい蓋があって、たためば全部蓋の中に納まる構造の大形提灯。蓋には蝋燭ろうそくを出し入れする孔がある。
箱提灯
 はこつ‐さいぼう【破骨細胞】‥バウ
骨の吸収を行う細胞。骨の再構築と血清カルシウム濃度の調節に関与する。
はこ‐づめ【箱詰】
①箱に物を詰めること。また、その詰めたもの。「―の桃」
②ぎっしりと満たし詰めること。「―になった乗客」
はこ‐でっぽう【はこ鉄砲】‥パウ
(和歌山県などで)夜狙よねらいのこと。
はこ‐でんじゅ【箱伝授】
①古今集の秘伝に関する書類を箱に密封して相伝したこと。
②一般に、諸道の秘伝書や財宝などを箱入のまま相伝すること。
はこ‐どい【箱樋】‥ドヒ
⇒はこひ
はこ‐どこ【箱床】
(→)寝敷ねじき1に同じ。
はこ‐どめ【箱止】
(箱は三味線箱の意)料理屋・待合などに芸者の出入りするのを差し止めること。
はこ‐どり【箱鳥】
容鳥かおどりまたはカッコウの一名という。(和歌などで、「はこ(箱)」の縁で「あ(明)く」を導く。一説に、箱鳥は深山にすみ、夜来て塒ねぐらを求め朝早く山に帰るからという)源氏物語若菜上「み山木にねぐら定むる―もいかでか花の色にあくべき」
はこ‐にわ【箱庭】‥ニハ
箱の中に土砂を入れ、小さい木や陶器製の人形・家・橋・舟・水車などを配して、庭園・山水・名勝などを模したもの。江戸時代に流行。石台。〈[季]夏〉。→盆石。
⇒はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】
はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】‥ニハレウハフ
心理療法の一つ。砂を入れた箱とおもちゃの建物・人物・動物などを用意し、箱庭を作らせることで治療を試みるもの。
⇒はこ‐にわ【箱庭】
はこね【箱根】
神奈川県足柄下郡の町。箱根山一帯を含む。温泉・観光地。芦ノ湖南東岸の旧宿場町は東海道五十三次の一つで、江戸時代には関所があった。
⇒はこね‐うつぎ【箱根空木】
⇒はこね‐おんせん【箱根温泉】
⇒はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
⇒はこね‐ごんげん【箱根権現】
⇒はこね‐ざいく【箱根細工】
⇒はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】
⇒はこね‐じ【箱根路】
⇒はこね‐しだ【箱根羊歯】
⇒はこね‐しちとう【箱根七湯】
⇒はこね‐じんじゃ【箱根神社】
⇒はこね‐そう【箱根草】
⇒はこね‐だけ【箱根竹】
⇒はこね‐の‐せき【箱根の関】
⇒はこね‐はちり【箱根八里】
⇒はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
⇒はこね‐やま【箱根山】
⇒はこね‐ゆもと【箱根湯本】
⇒はこね‐ようすい【箱根用水】
⇒はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】
はこね‐うつぎ【箱根空木】
(箱根に多く産したとの誤認による)スイカズラ科の落葉低木。各地の海岸に自生。樹高2〜5メートル。太い髄がある。初夏、梢上や葉腋に多数の筒状花をつけ、花は初め白色、後に紅変。庭樹とする。錦帯花。〈[季]夏〉
はこねうつぎ
はこつ‐さいぼう【破骨細胞】‥バウ
骨の吸収を行う細胞。骨の再構築と血清カルシウム濃度の調節に関与する。
はこ‐づめ【箱詰】
①箱に物を詰めること。また、その詰めたもの。「―の桃」
②ぎっしりと満たし詰めること。「―になった乗客」
はこ‐でっぽう【はこ鉄砲】‥パウ
(和歌山県などで)夜狙よねらいのこと。
はこ‐でんじゅ【箱伝授】
①古今集の秘伝に関する書類を箱に密封して相伝したこと。
②一般に、諸道の秘伝書や財宝などを箱入のまま相伝すること。
はこ‐どい【箱樋】‥ドヒ
⇒はこひ
はこ‐どこ【箱床】
(→)寝敷ねじき1に同じ。
はこ‐どめ【箱止】
(箱は三味線箱の意)料理屋・待合などに芸者の出入りするのを差し止めること。
はこ‐どり【箱鳥】
容鳥かおどりまたはカッコウの一名という。(和歌などで、「はこ(箱)」の縁で「あ(明)く」を導く。一説に、箱鳥は深山にすみ、夜来て塒ねぐらを求め朝早く山に帰るからという)源氏物語若菜上「み山木にねぐら定むる―もいかでか花の色にあくべき」
はこ‐にわ【箱庭】‥ニハ
箱の中に土砂を入れ、小さい木や陶器製の人形・家・橋・舟・水車などを配して、庭園・山水・名勝などを模したもの。江戸時代に流行。石台。〈[季]夏〉。→盆石。
⇒はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】
はこにわ‐りょうほう【箱庭療法】‥ニハレウハフ
心理療法の一つ。砂を入れた箱とおもちゃの建物・人物・動物などを用意し、箱庭を作らせることで治療を試みるもの。
⇒はこ‐にわ【箱庭】
はこね【箱根】
神奈川県足柄下郡の町。箱根山一帯を含む。温泉・観光地。芦ノ湖南東岸の旧宿場町は東海道五十三次の一つで、江戸時代には関所があった。
⇒はこね‐うつぎ【箱根空木】
⇒はこね‐おんせん【箱根温泉】
⇒はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
⇒はこね‐ごんげん【箱根権現】
⇒はこね‐ざいく【箱根細工】
⇒はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】
⇒はこね‐じ【箱根路】
⇒はこね‐しだ【箱根羊歯】
⇒はこね‐しちとう【箱根七湯】
⇒はこね‐じんじゃ【箱根神社】
⇒はこね‐そう【箱根草】
⇒はこね‐だけ【箱根竹】
⇒はこね‐の‐せき【箱根の関】
⇒はこね‐はちり【箱根八里】
⇒はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
⇒はこね‐やま【箱根山】
⇒はこね‐ゆもと【箱根湯本】
⇒はこね‐ようすい【箱根用水】
⇒はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】
はこね‐うつぎ【箱根空木】
(箱根に多く産したとの誤認による)スイカズラ科の落葉低木。各地の海岸に自生。樹高2〜5メートル。太い髄がある。初夏、梢上や葉腋に多数の筒状花をつけ、花は初め白色、後に紅変。庭樹とする。錦帯花。〈[季]夏〉
はこねうつぎ
 ハコネウツギ
提供:ネイチャー・プロダクション
ハコネウツギ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐おんせん【箱根温泉】‥ヲン‥
神奈川県南西部、箱根山中にある温泉の総称。いわゆる箱根七湯のほか、小涌谷こわくだに・強羅ごうら・仙石・湯ノ花沢・大平台など。酸性泉・硫黄泉・塩類泉・単純泉。泉量豊富。
箱根湯本温泉
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐おんせん【箱根温泉】‥ヲン‥
神奈川県南西部、箱根山中にある温泉の総称。いわゆる箱根七湯のほか、小涌谷こわくだに・強羅ごうら・仙石・湯ノ花沢・大平台など。酸性泉・硫黄泉・塩類泉・単純泉。泉量豊富。
箱根湯本温泉
撮影:関戸 勇
 塔ノ沢温泉
撮影:関戸 勇
塔ノ沢温泉
撮影:関戸 勇
 大平台温泉
撮影:関戸 勇
大平台温泉
撮影:関戸 勇
 宮ノ下温泉
撮影:関戸 勇
宮ノ下温泉
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
ツツジ科の小低木。箱根を中心に関東地方南西部に自生。葉は小形の倒卵形で、質厚く枝端に集まる。7月頃、葉腋に筒形白色の小花を付ける。盆栽用に栽植。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ごんげん【箱根権現】
箱根神社の別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ざいく【箱根細工】
箱根・小田原地方で土産物として発展した木工細工。とくに寄木細工や木象嵌に特色がある。
箱根細工
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐こめつつじ【箱根米躑躅】
ツツジ科の小低木。箱根を中心に関東地方南西部に自生。葉は小形の倒卵形で、質厚く枝端に集まる。7月頃、葉腋に筒形白色の小花を付ける。盆栽用に栽植。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ごんげん【箱根権現】
箱根神社の別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ざいく【箱根細工】
箱根・小田原地方で土産物として発展した木工細工。とくに寄木細工や木象嵌に特色がある。
箱根細工
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】‥セウウヲ
サンショウウオの一種。全長12〜18センチメートル。体の背面は暗褐色か黒色で中央に幅広い1条のオレンジ色の帯がある。成体も肺を欠き、呼吸は皮膚で行うのが特徴。幼生は渓流中にすみ、指先に爪を持つ。本州・四国の山間にすむ。乾燥して民間薬として用いた。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じ【箱根路】‥ヂ
箱根山中を通ずる道路。小田原から箱根まで4里10町、箱根から三島まで3里20町、合わせて約8里あるところから箱根八里の称がある。
箱根路
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐さんしょううお【箱根山椒魚】‥セウウヲ
サンショウウオの一種。全長12〜18センチメートル。体の背面は暗褐色か黒色で中央に幅広い1条のオレンジ色の帯がある。成体も肺を欠き、呼吸は皮膚で行うのが特徴。幼生は渓流中にすみ、指先に爪を持つ。本州・四国の山間にすむ。乾燥して民間薬として用いた。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じ【箱根路】‥ヂ
箱根山中を通ずる道路。小田原から箱根まで4里10町、箱根から三島まで3里20町、合わせて約8里あるところから箱根八里の称がある。
箱根路
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐しだ【箱根羊歯】
(初め箱根山で採集されたことからの名)ホウライシダ科の常緑多年生シダ。山地の崖がけなどに生える。葉は羽状、葉柄は紫黒褐色で光沢がある。本州中南部以西に産し、観賞用にもする。全体を乾して去痰・利尿・通経剤とする。ハコネソウ。
はこねしだ
⇒はこね【箱根】
はこね‐しだ【箱根羊歯】
(初め箱根山で採集されたことからの名)ホウライシダ科の常緑多年生シダ。山地の崖がけなどに生える。葉は羽状、葉柄は紫黒褐色で光沢がある。本州中南部以西に産し、観賞用にもする。全体を乾して去痰・利尿・通経剤とする。ハコネソウ。
はこねしだ
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐しちとう【箱根七湯】‥タウ
箱根温泉郷にある湯本・塔ノ沢・宮ノ下・底倉・堂ヶ島・木賀きが・芦ノ湯の七温泉。木賀の代りに姥子うばこを入れることもある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じんじゃ【箱根神社】
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根、芦ノ湖東岸にある元国幣小社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと・木花開耶姫尊このはなさくやひめのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみこと。箱根権現。
⇒はこね【箱根】
はこね‐そう【箱根草】‥サウ
ハコネシダの別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐だけ【箱根竹】
アズマネザサの一品種。箱根山に多いのでこの名がある。花は春に開き緑紫色。地下茎で喫煙用のパイプを作る。
⇒はこね【箱根】
はこね‐の‐せき【箱根の関】
江戸時代初め設置された、東海道の箱根山中の関所。三島・小田原の両宿の中間にあり、箱根宿の東方の入口で、北は芦ノ湖に面し、南は山を負い、要害の地。小田原藩主が預かり、特に入鉄砲いりでっぽう出女でおんなの取締りが厳重であった。
箱根の関
撮影:関戸 勇
⇒はこね【箱根】
はこね‐しちとう【箱根七湯】‥タウ
箱根温泉郷にある湯本・塔ノ沢・宮ノ下・底倉・堂ヶ島・木賀きが・芦ノ湯の七温泉。木賀の代りに姥子うばこを入れることもある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐じんじゃ【箱根神社】
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根、芦ノ湖東岸にある元国幣小社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと・木花開耶姫尊このはなさくやひめのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみこと。箱根権現。
⇒はこね【箱根】
はこね‐そう【箱根草】‥サウ
ハコネシダの別称。
⇒はこね【箱根】
はこね‐だけ【箱根竹】
アズマネザサの一品種。箱根山に多いのでこの名がある。花は春に開き緑紫色。地下茎で喫煙用のパイプを作る。
⇒はこね【箱根】
はこね‐の‐せき【箱根の関】
江戸時代初め設置された、東海道の箱根山中の関所。三島・小田原の両宿の中間にあり、箱根宿の東方の入口で、北は芦ノ湖に面し、南は山を負い、要害の地。小田原藩主が預かり、特に入鉄砲いりでっぽう出女でおんなの取締りが厳重であった。
箱根の関
撮影:関戸 勇
 ⇒はこね【箱根】
はこね‐はちり【箱根八里】
「箱根路はこねじ」参照。
⇒はこね【箱根】
はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
箱根街道などの馬子たちが歌った馬子唄。「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」とあり、大井川辺で歌われたともいう。別に「箱根駕籠かき唄」がある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐やま【箱根山】
伊豆半島の基部にあり、神奈川・静岡両県にまたがる三重式の火山。最高峰は中央火口丘の一つ、神山で標高1438メートル。火口原に芦ノ湖があり、また多数の温泉がある。交通網の整備により観光開発が進む。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ゆもと【箱根湯本】
箱根七湯の一つ。神奈川県箱根町、箱根温泉郷東部、早川渓谷に湧出する無色透明の単純泉。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ようすい【箱根用水】
箱根芦ノ湖から湖尻峠の下にトンネルを掘って西方の村々に引いた灌漑用水。1670年(寛文10)完成。深良用水。
⇒はこね【箱根】
はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】‥ヰザリ‥
浄瑠璃。司馬芝叟しばしそう作の時代物。通称「躄勝五郎」。1801年(享和1)初演。躄となった飯沼勝五郎が妻初花と共に方々を流浪するが、箱根権現の霊験によって足腰が立ち、忠僕筆助の助太刀で兄の仇佐藤剛助(滝口上野)を討ったことを脚色する。後に歌舞伎化。
⇒はこね【箱根】
はご‐の‐き【羽子の木】
〔植〕ツクバネの別称。〈[季]秋〉
はこ‐ばしご【箱梯子】
側面下部の空間を戸棚・押入・抽斗ひきだしなどに利用した梯子段。箱段。はこばし。
はこ‐ばしゃ【箱馬車】
座席の屋根をつくりつけにした箱型の馬車。島崎藤村、春「暗い―が其時門内へ引込まれた」
はこ‐ひ【箱樋・函樋】
箱形の樋。水車などの通水路として使うことが多い。はこどい。
はこび【運び】
①足をはこぶこと。歩くこと。「わざわざお―いただいて恐縮です」
②物事を進めること。また、その段取り。進み具合。「仕事の―が悪い」「近く開店の―となった」「―をつける」
⇒はこび‐でまえ【運び点前】
⇒はこび‐や【運び屋】
はこび‐こ・む【運び込む】
〔他五〕
運んで中に入れる。「家具を新居に―・む」「患者を病院に―・む」
はこび‐だ・す【運び出す】
〔他五〕
運んで外へ出す。
はこび‐でまえ【運び点前】‥マヘ
茶会で客が茶室に入ってから水指以下の茶道具を運び出して茶をたてる法。
⇒はこび【運び】
はこ‐ひばち【箱火鉢】
箱形をした木製の火鉢。
はこび‐や【運び屋】
店を構えず、小規模に物資の運搬を業とする者。特に、密輸組織の中の運搬人。
⇒はこび【運び】
はこ・ぶ【運ぶ】
[一]〔他五〕
①持ち、または積んで、送る。運送する。源氏物語若菜上「かの院よりも御調度など―・ばる」。「荷物を―・ぶ」
②そちらへ移し進める。古今著聞集2「其の外霊験の名地ごとに、あゆみを―・ばずといふ事なし」。日葡辞書「アシヲハコブ」
③推し進める。はかどらせる。徒然草「刹那覚えずといへども、是を―・びて止やまざれば、命を終ふる期忽ちにいたる」。「筆を―・ぶ」「裁縫の針を―・ぶ」
④その方へ向ける。よせる。日葡辞書「ヒトニココロザシヲハコブ」
[二]〔自五〕
①向く。寄る。拾玉集6「大寺の池の蓮はちすの花ざかり―・ぶ心にたむけてぞ見る」
②物事がうまく進む。はかどる。進捗しんちょくする。「議事が―・ぶ」
はこ‐ふぐ【箱河豚】
ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は固い骨板に包まれる。水深50メートル以浅の岩礁に生息する。肉は無毒だが、体表から粘液毒を出す。北海道南部から九州南部、台湾に分布。
はこ‐ぶね【箱船・方舟】
①長方形の船。
②ノアの方舟。神が悪に満ちた世界を絶滅しようとして洪水を起こした時、ノアが神の恩恵を得て製作し、家族や各動物種一つがいと共に乗って難を避け、アララト山に漂着したという方形の船。(旧約聖書創世記6〜8章)
はこ‐ぶみ【筥文】
叙位・除目じもくの時、硯箱の蓋に入れて御前に置く上申書。
はこ‐ぶろ【箱風呂】
風呂の一種。箱形の風呂。
はこべ【蘩蔞・繁縷】
ナデシコ科の越年草。山野・路傍に自生、しばしば群生する。高さ15〜50センチメートル、下部は地に臥す。葉は広卵形で柔らかい。春、白色の小5弁花を開く。鳥餌または食用に供し、利尿剤ともする。春の七草の一つ。あさしらげ。はこべら。
はこべ
⇒はこね【箱根】
はこね‐はちり【箱根八里】
「箱根路はこねじ」参照。
⇒はこね【箱根】
はこね‐まごうた【箱根馬子唄】
箱根街道などの馬子たちが歌った馬子唄。「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」とあり、大井川辺で歌われたともいう。別に「箱根駕籠かき唄」がある。
⇒はこね【箱根】
はこね‐やま【箱根山】
伊豆半島の基部にあり、神奈川・静岡両県にまたがる三重式の火山。最高峰は中央火口丘の一つ、神山で標高1438メートル。火口原に芦ノ湖があり、また多数の温泉がある。交通網の整備により観光開発が進む。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ゆもと【箱根湯本】
箱根七湯の一つ。神奈川県箱根町、箱根温泉郷東部、早川渓谷に湧出する無色透明の単純泉。
⇒はこね【箱根】
はこね‐ようすい【箱根用水】
箱根芦ノ湖から湖尻峠の下にトンネルを掘って西方の村々に引いた灌漑用水。1670年(寛文10)完成。深良用水。
⇒はこね【箱根】
はこねれいげん‐いざりのあだうち【箱根霊験躄仇討】‥ヰザリ‥
浄瑠璃。司馬芝叟しばしそう作の時代物。通称「躄勝五郎」。1801年(享和1)初演。躄となった飯沼勝五郎が妻初花と共に方々を流浪するが、箱根権現の霊験によって足腰が立ち、忠僕筆助の助太刀で兄の仇佐藤剛助(滝口上野)を討ったことを脚色する。後に歌舞伎化。
⇒はこね【箱根】
はご‐の‐き【羽子の木】
〔植〕ツクバネの別称。〈[季]秋〉
はこ‐ばしご【箱梯子】
側面下部の空間を戸棚・押入・抽斗ひきだしなどに利用した梯子段。箱段。はこばし。
はこ‐ばしゃ【箱馬車】
座席の屋根をつくりつけにした箱型の馬車。島崎藤村、春「暗い―が其時門内へ引込まれた」
はこ‐ひ【箱樋・函樋】
箱形の樋。水車などの通水路として使うことが多い。はこどい。
はこび【運び】
①足をはこぶこと。歩くこと。「わざわざお―いただいて恐縮です」
②物事を進めること。また、その段取り。進み具合。「仕事の―が悪い」「近く開店の―となった」「―をつける」
⇒はこび‐でまえ【運び点前】
⇒はこび‐や【運び屋】
はこび‐こ・む【運び込む】
〔他五〕
運んで中に入れる。「家具を新居に―・む」「患者を病院に―・む」
はこび‐だ・す【運び出す】
〔他五〕
運んで外へ出す。
はこび‐でまえ【運び点前】‥マヘ
茶会で客が茶室に入ってから水指以下の茶道具を運び出して茶をたてる法。
⇒はこび【運び】
はこ‐ひばち【箱火鉢】
箱形をした木製の火鉢。
はこび‐や【運び屋】
店を構えず、小規模に物資の運搬を業とする者。特に、密輸組織の中の運搬人。
⇒はこび【運び】
はこ・ぶ【運ぶ】
[一]〔他五〕
①持ち、または積んで、送る。運送する。源氏物語若菜上「かの院よりも御調度など―・ばる」。「荷物を―・ぶ」
②そちらへ移し進める。古今著聞集2「其の外霊験の名地ごとに、あゆみを―・ばずといふ事なし」。日葡辞書「アシヲハコブ」
③推し進める。はかどらせる。徒然草「刹那覚えずといへども、是を―・びて止やまざれば、命を終ふる期忽ちにいたる」。「筆を―・ぶ」「裁縫の針を―・ぶ」
④その方へ向ける。よせる。日葡辞書「ヒトニココロザシヲハコブ」
[二]〔自五〕
①向く。寄る。拾玉集6「大寺の池の蓮はちすの花ざかり―・ぶ心にたむけてぞ見る」
②物事がうまく進む。はかどる。進捗しんちょくする。「議事が―・ぶ」
はこ‐ふぐ【箱河豚】
ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長30センチメートル。体は固い骨板に包まれる。水深50メートル以浅の岩礁に生息する。肉は無毒だが、体表から粘液毒を出す。北海道南部から九州南部、台湾に分布。
はこ‐ぶね【箱船・方舟】
①長方形の船。
②ノアの方舟。神が悪に満ちた世界を絶滅しようとして洪水を起こした時、ノアが神の恩恵を得て製作し、家族や各動物種一つがいと共に乗って難を避け、アララト山に漂着したという方形の船。(旧約聖書創世記6〜8章)
はこ‐ぶみ【筥文】
叙位・除目じもくの時、硯箱の蓋に入れて御前に置く上申書。
はこ‐ぶろ【箱風呂】
風呂の一種。箱形の風呂。
はこべ【蘩蔞・繁縷】
ナデシコ科の越年草。山野・路傍に自生、しばしば群生する。高さ15〜50センチメートル、下部は地に臥す。葉は広卵形で柔らかい。春、白色の小5弁花を開く。鳥餌または食用に供し、利尿剤ともする。春の七草の一つ。あさしらげ。はこべら。
はこべ
 ハコベ
撮影:関戸 勇
ハコベ
撮影:関戸 勇
 ⇒はこべ‐じお【蘩蔞塩】
はこべ‐じお【蘩蔞塩】‥ジホ
ハコベを青いまま炒いって、水気を去り、塩を交ぜて再び炒った粉。歯を磨くのに用いる。
⇒はこべ【蘩蔞・繁縷】
はこべ‐ら【蘩蔞】
ハコベの古名。〈[季]春〉
はこ‐べん【箱弁】
箱弁当の略。仕出し屋などが運んで来る、箱につめた弁当。
はこ‐ぼり【箱堀】
石垣で両岸を切立きったてにして箱のように造った堀。
は‐こぼれ【刃毀れ】
刃物の刃が欠けること。また、その箇所。
はこ‐まくら【箱枕】
箱形の木枕。箱の上に括枕くくりまくらをのせる。
はこ‐まわし【箱回し】‥マハシ
(→)箱屋2に同じ。
パコミオス【Pachōmios ギリシア】
エジプトのコプト教会の聖人。共住的修道制を創設、その規則はバシレイオスやベネディクトゥスに影響。パコミウス。(290頃〜346)
はこ‐むね【箱棟】
日本建築で、大棟を箱形にしておおったもの。普通は木で造る。
箱棟
⇒はこべ‐じお【蘩蔞塩】
はこべ‐じお【蘩蔞塩】‥ジホ
ハコベを青いまま炒いって、水気を去り、塩を交ぜて再び炒った粉。歯を磨くのに用いる。
⇒はこべ【蘩蔞・繁縷】
はこべ‐ら【蘩蔞】
ハコベの古名。〈[季]春〉
はこ‐べん【箱弁】
箱弁当の略。仕出し屋などが運んで来る、箱につめた弁当。
はこ‐ぼり【箱堀】
石垣で両岸を切立きったてにして箱のように造った堀。
は‐こぼれ【刃毀れ】
刃物の刃が欠けること。また、その箇所。
はこ‐まくら【箱枕】
箱形の木枕。箱の上に括枕くくりまくらをのせる。
はこ‐まわし【箱回し】‥マハシ
(→)箱屋2に同じ。
パコミオス【Pachōmios ギリシア】
エジプトのコプト教会の聖人。共住的修道制を創設、その規則はバシレイオスやベネディクトゥスに影響。パコミウス。(290頃〜346)
はこ‐むね【箱棟】
日本建築で、大棟を箱形にしておおったもの。普通は木で造る。
箱棟
 はこ‐めがね【箱眼鏡】
水面上から水中を透視しながら漁をするのに用いる箱形の眼鏡。底部はガラスまたは凸レンズ。覗眼鏡のぞきめがね。〈[季]夏〉
はこめじ‐したみ【箱目地下見】‥ヂ‥
下見2の一つ。板を垂直になるように張り、水平の目地を太い筋として現すもの。ドイツ下見。
は‐ごも【葉薦】
真菰まこもの葉を編んで作った薦。神前の案下あんかに敷く。散木奇歌集「柴の庵に―の囲ひそよめきて」
はこ‐もち【箱持】
(→)箱屋2に同じ。
はこ‐もの【箱物】
①箱形の物。箱類。
②建造物をいう語。多く十分に活用していない場合に用いる。
はこ‐もん【筥紋・箱紋】
全体を方形に描いた文様。↔円紋まるもん
はこ‐や【箱屋】
①箱を造り、またはそれを売る家。また、その人。
②御座敷に出る芸妓に従って、箱に入れた三味線を持って行く男。はこまわし。はこもち。はこ。成島柳北、柳橋新誌「妓及び酒楼船舗皆二戸けんを呼んで―と為す」
はこ‐やなぎ【箱柳】
ヤナギ科の落葉高木。ポプラと同属。山地に自生。高さ数メートル。葉は広楕円形で下面は灰白色。雌雄異株。4月頃、褐色の花穂を垂下する。街路樹などとして栽植し、軟材で、箱・マッチの軸木・製紙・経木真田用とする。ヤマナラシ。〈毛吹草〉
はこや‐の‐やま【藐姑射の山】
(「藐姑射」はバクコヤとも)
①[荘子逍遥遊]中国で不老不死の仙人が住むという山。姑射山こやさん。万葉集16「―を見まく近けむ」
②上皇の御所を祝していう称。仙洞せんとう。
はこ・ゆ
〔他下二〕
(「はこふ」とする説もある)衣服の裾をからげて箱のようにふくらませる意。裾をかかげる。枕草子144「ひき―・えたる男児」
パコ‐ラバンヌ【Paco Rabanne】
⇒ラバンヌ
は‐ごろも【羽衣】
①鳥の羽で作った薄く軽い衣。天人がこれを着て自由に空中を飛行するという。あまのはごろも。あまごろも。
②鳥・虫などの翅。
③カメムシ目ハゴロモ科の昆虫の総称。近縁なビワハゴロモ科、アオバハゴロモ科などを含めることもある。体に比して前翅が大きく、美しい色彩を呈するものが多い。(曲名別項)
⇒はごろも‐ぐさ【羽衣草】
⇒はごろも‐そう【羽衣草】
⇒はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
⇒はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
はごろも【羽衣】
能。鬘物。三保松原で漁夫白竜が羽衣をみつけたのを、天人が呼びとめて返してもらい、その礼に舞を舞って昇天する。長唄・常磐津・一中・箏曲にも作られる。→羽衣伝説
羽衣
はこ‐めがね【箱眼鏡】
水面上から水中を透視しながら漁をするのに用いる箱形の眼鏡。底部はガラスまたは凸レンズ。覗眼鏡のぞきめがね。〈[季]夏〉
はこめじ‐したみ【箱目地下見】‥ヂ‥
下見2の一つ。板を垂直になるように張り、水平の目地を太い筋として現すもの。ドイツ下見。
は‐ごも【葉薦】
真菰まこもの葉を編んで作った薦。神前の案下あんかに敷く。散木奇歌集「柴の庵に―の囲ひそよめきて」
はこ‐もち【箱持】
(→)箱屋2に同じ。
はこ‐もの【箱物】
①箱形の物。箱類。
②建造物をいう語。多く十分に活用していない場合に用いる。
はこ‐もん【筥紋・箱紋】
全体を方形に描いた文様。↔円紋まるもん
はこ‐や【箱屋】
①箱を造り、またはそれを売る家。また、その人。
②御座敷に出る芸妓に従って、箱に入れた三味線を持って行く男。はこまわし。はこもち。はこ。成島柳北、柳橋新誌「妓及び酒楼船舗皆二戸けんを呼んで―と為す」
はこ‐やなぎ【箱柳】
ヤナギ科の落葉高木。ポプラと同属。山地に自生。高さ数メートル。葉は広楕円形で下面は灰白色。雌雄異株。4月頃、褐色の花穂を垂下する。街路樹などとして栽植し、軟材で、箱・マッチの軸木・製紙・経木真田用とする。ヤマナラシ。〈毛吹草〉
はこや‐の‐やま【藐姑射の山】
(「藐姑射」はバクコヤとも)
①[荘子逍遥遊]中国で不老不死の仙人が住むという山。姑射山こやさん。万葉集16「―を見まく近けむ」
②上皇の御所を祝していう称。仙洞せんとう。
はこ・ゆ
〔他下二〕
(「はこふ」とする説もある)衣服の裾をからげて箱のようにふくらませる意。裾をかかげる。枕草子144「ひき―・えたる男児」
パコ‐ラバンヌ【Paco Rabanne】
⇒ラバンヌ
は‐ごろも【羽衣】
①鳥の羽で作った薄く軽い衣。天人がこれを着て自由に空中を飛行するという。あまのはごろも。あまごろも。
②鳥・虫などの翅。
③カメムシ目ハゴロモ科の昆虫の総称。近縁なビワハゴロモ科、アオバハゴロモ科などを含めることもある。体に比して前翅が大きく、美しい色彩を呈するものが多い。(曲名別項)
⇒はごろも‐ぐさ【羽衣草】
⇒はごろも‐そう【羽衣草】
⇒はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
⇒はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
はごろも【羽衣】
能。鬘物。三保松原で漁夫白竜が羽衣をみつけたのを、天人が呼びとめて返してもらい、その礼に舞を舞って昇天する。長唄・常磐津・一中・箏曲にも作られる。→羽衣伝説
羽衣
 『羽衣』
撮影:神田佳明(シテ:長島茂)
『羽衣』
撮影:神田佳明(シテ:長島茂)
 は‐ごろも【葉衣】
木の葉で作ったころも。
はごろも‐ぐさ【羽衣草】
(lady's-mantle)バラ科の多年草。日本を含む北半球高山帯に自生。高さ約30センチメートル。夏、淡黄緑色の小花を密生。
はごろもぐさ
は‐ごろも【葉衣】
木の葉で作ったころも。
はごろも‐ぐさ【羽衣草】
(lady's-mantle)バラ科の多年草。日本を含む北半球高山帯に自生。高さ約30センチメートル。夏、淡黄緑色の小花を密生。
はごろもぐさ
 ⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐そう【羽衣草】‥サウ
ノコギリソウの別称。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
天女が水浴中に羽衣を盗まれて天に帰れず人妻となって暮らすうち、羽衣を探し出して昇天するという伝説。駿河国三保松原(有度浜)、近江国伊香小江いかごのおえ、丹後国比治山(以上、風土記逸文)などにあるもののほか、全国に類似のものが多い。→白鳥処女説話。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
静岡市三保松原の御穂神社の南東にある松。能「羽衣」の松と伝える。
⇒は‐ごろも【羽衣】
は‐こん【波痕】
波のあと。
は‐こん【破婚】
結婚関係を解消すること。離縁。破鏡。
はさ【稲架】
(新潟・富山・福井・岐阜などで)稲掛け。稲架とうか。はざ。〈[季]秋〉
ば‐さ
(「婆娑」と当てる)
①舞う袖のひるがえるさま。
②歩きまわるさま。菅家文草2「孔肆に―たるはこれ査郎」
③影などの乱れ動くさま。蕪村句集「古傘の―と月夜の時雨かな」
④物の散り乱れるさま。
⑤竹の葉などの風にあたって鳴る音。
⑥琴などの音調の曲折あるさま。
バザー【baza(a)r】
(もとペルシア語で市場の意)社会事業などの資金を集める目的で催す市いち。慈善市。→バザール
ハザード【hazard】
(危険・障害物の意)ゴルフで、コースに設けたバンカーやウォーター‐ハザードのこと。
⇒ハザード‐マップ【hazard map】
⇒ハザード‐ランプ【hazard lamp】
ハザード‐マップ【hazard map】
(→)災害予測地図に同じ。
⇒ハザード【hazard】
ハザード‐ランプ【hazard lamp】
自動車の非常点滅表示灯。路肩停車時など、危険を他の車などに伝えるために点滅させるランプ。
⇒ハザード【hazard】
バザーリ【G. Vasari】
⇒ヴァザーリ
バザール【bāzār ペルシア】
①インド・中央アジア・中東諸国などの市場。
②種々雑多な品物を売る一群の小店。
③百貨店などの大売出し。→バザー
は‐さい【破砕・破摧】
やぶりくだくこと。また、やぶれくだけること。「岩石の―」「敵を―する」
⇒はさい‐き【破砕機】
はさい‐き【破砕機】
(→)クラッシャーに同じ。
⇒は‐さい【破砕・破摧】
は‐ざお【歯竿】‥ザヲ
(→)ラック(rack)1に同じ。
は‐ざかい【刃境】‥ザカヒ
刀の刃と地との境。
はざかい‐き【端境期】‥ザカヒ‥
古米に代わって新米が市場に出回ろうとする時期。9〜10月頃の称。転じて、果物・野菜などの市場に出回らなくなる時期、広義にはさまざまな移行期をもいう。
はさか・う【挟かふ】ハサカフ
〔自四〕
はさまる。猿蓑「塩魚の歯に―・ふや秋の暮」(荷兮)
はさ‐がた【夾形】
結髪用具。長さ約1尺、幅約5分ほどの羅うすものの紐。飾り紐に使う。
は‐さき【刃先】
刀などのきっさき。刀鋩とうぼう。
は‐さき【羽先】
はねの先端。
は‐さき【葉先】
①葉の先端。ようせん。
②(→)「かいさき(櫂先)」2に同じ。
は‐ざくら【葉桜】
①花が散って若葉が出はじめた頃の桜。〈[季]夏〉
②紋所の名。
ばさ・ける
〔自下一〕
ばさばさする。ちらばる。(嬉遊笑覧)
はささ・く【馳ささく】
〔他下二〕
馳せさせる。万葉集14「小お林に駒を―・け」
ハ‐ざし【ハ刺し】
洋裁のステッチの一種。片仮名のハの字型の針目が並ぶもの。主に芯地を表地に縫いつけるのに用いる。
は‐ざし【刃刺・羽差】
近世の沿岸鯨漁で、勢子船に乗った銛もり師。銛を打ち、捕った鯨を船に結びつけるなど、危険で熟練を要する仕事を受け持つ役。
は‐ざし【葉挿し】
挿木法の一つ。接穂つぎほに葉を用い、不定芽を出させるもの。
ば‐さし【馬刺】
馬肉の刺身。
はさ・す【馳さす】
〔他下二〕
馳せさせる。走らせる。万葉集14「さざれ石に駒を―・せて」
はさつ‐おん【破擦音】
〔言〕(affricate)破裂音の直後に摩擦音がつづき、全体で一つの単音と見なされる音。〔ts〕〔dz〕〔tʃ〕〔dʒ〕など。
ばさ‐つ・く
〔自五〕
ばさばさする。
ぱさ‐つ・く
〔自五〕
ぱさぱさになる。水分がなくなりぱさぱさした感じになる。「パンが―・く」「髪が―・く」
ばさっ‐と
〔副〕
①翼・小枝・紙の束などが触れ合ったり打ち当たったりしてたてる音、また、そのさま。「新聞を―置く」
②一気に、または大量に切断するさま。「髪を―切る」
パサデナ【Pasadena】
アメリカ合衆国南西部、ロサンゼルス市北東郊にある住宅都市。人口11万7千(2000)。
ばさ‐ばさ
①乾いた薄いものが繰り返し触れ合って発する音。また、そのさま。「鷲が―と舞い下りる」
②ものを思い切りよく大量に切り落とすさま。「枝を―と払う」
③ひとまとまりに整っているべきものが乱れているさま。「書類が―に散らかる」「―した髪」
ぱさ‐ぱさ
水分や脂肪分が抜けて乾いているさま。手触りや口当りが乾いた感じで味わいがないさま。「パンが―する」
はざ‐ま【狭間・迫間】
(古くはハサマ)
①物と物との間のせまいところ。あわい。伊勢物語「後涼殿の―を渡りければ」
②谷あい。谷。〈皇極紀訓注〉
③あいだ。ほど。おり。宇治拾遺物語11「その―は唇ばかり働くは念仏なめりと見ゆ」
④矢・鉄砲などを放つために、城壁に設けた穴。銃眼。
⑤鶯の籠につけた丸いすかし。
⇒はざま‐くばり【狭間配り】
はざま【間】
姓氏の一つ。
⇒はざま‐しげとみ【間重富】
はざま‐くばり【狭間配り】
籠城で、矢・弾丸を放つため、兵士を城壁の狭間に配置すること。
⇒はざ‐ま【狭間・迫間】
はざま‐しげとみ【間重富】
江戸後期の天文暦学者。長涯と号。大坂の質商。麻田剛立に入門、西洋の天文暦学を研究。望遠鏡や種々の観測機器を作り、天体観測上に画期をなした。のち幕府に召されて寛政改暦に当たった。(1756〜1816)
⇒はざま【間】
はさま・る【挟まる】
〔自五〕
物と物との間に入って動きがとれなくなる。宇治拾遺物語13「股に―・りてある折」。「扉に手が―・る」「二人の間に―・って苦労する」
はさみ【挟み・挿み】
はさむこと。→はさみ(鋏)。
⇒はさみ‐いた【挟板】
⇒はさみ‐うち【挟み撃ち】
⇒はさみ‐おび【挟み帯】
⇒はさみ‐かせ【挟械】
⇒はさみ‐がみ【挟み紙】
⇒はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
⇒はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
⇒はさみ‐ざかな【挟み肴】
⇒はさみ‐じょう【挟み状】
⇒はさみ‐しょうぎ【挟み将棋】
⇒はさみ‐だけ【挟み竹】
⇒はさみ‐ばこ【挟箱】
⇒はさみ‐むすび【挟み結び】
⇒はさみ‐もの【挟み物・挿み物】
はさみ【鋏・剪刀】
①2枚の刃で挟むようにして物を切る道具。切符などに穴をあけるパンチのこともいう。〈倭名類聚鈔15〉
②(「螯」「鉗」とも書く)節足動物のカニ・サソリなどの脚の(→)鋏1のような部分。これを持つ脚を特に鋏脚(鉗脚かんきゃくとも)という。
③(じゃんけんで)2本の指を伸ばした形。ちょき。「石、紙、―」
⇒はさみじょう‐かかくさ【鋏状価格差】
⇒はさみ‐ばん【鋏盤】
⇒はさみ‐むし【鋏虫・蠼螋】
⇒鋏を入れる
はさみ‐あ・げる【挟み上げる】
〔他下一〕[文]はさみあ・ぐ(下二)
箸などで、はさんで持ち上げる。
はさみ‐いた【挟板】
門の左右に取り付ける板作りの袖。はさいた。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐い・れる【挟み入れる】
〔他下一〕[文]はさみい・る(下二)
①物の間に入れこむ。はさみこむ。
②はさんで他へ移し入れる。
はさみ‐うち【挟み撃ち】
相手を両側から挟むようにして攻撃すること。「敵を―にする」
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐う・つ【挟み撃つ】
〔他五〕
敵を中に挟んで、左右または前後から攻撃する。
はさみ‐おび【挟み帯】
はさみ結びにすること。さしこみおび。つっこみおび。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐かせ【挟械】
掘建ほったて柱の根を固めるために、その左右に取り付ける根かせ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐がみ【挟み紙】
①書物の中の必要な箇所に注意のために挟む紙片。しおり。
②重ねてある物品の間に挟んで、傷がつかないようにする紙。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐き・る【剪み切る】
〔他四〕
鋏で切り取る。
はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
限界ゲージの一種。ゲージの口を工作物にあてがい、円筒形・球形の直径、直方体の厚さなどが許しうる上限と下限の間に入っているかどうか検査するのに用いる。スナップ‐ゲージ。
挟みゲージ
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐そう【羽衣草】‥サウ
ノコギリソウの別称。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐でんせつ【羽衣伝説】
天女が水浴中に羽衣を盗まれて天に帰れず人妻となって暮らすうち、羽衣を探し出して昇天するという伝説。駿河国三保松原(有度浜)、近江国伊香小江いかごのおえ、丹後国比治山(以上、風土記逸文)などにあるもののほか、全国に類似のものが多い。→白鳥処女説話。
⇒は‐ごろも【羽衣】
はごろも‐の‐まつ【羽衣松】
静岡市三保松原の御穂神社の南東にある松。能「羽衣」の松と伝える。
⇒は‐ごろも【羽衣】
は‐こん【波痕】
波のあと。
は‐こん【破婚】
結婚関係を解消すること。離縁。破鏡。
はさ【稲架】
(新潟・富山・福井・岐阜などで)稲掛け。稲架とうか。はざ。〈[季]秋〉
ば‐さ
(「婆娑」と当てる)
①舞う袖のひるがえるさま。
②歩きまわるさま。菅家文草2「孔肆に―たるはこれ査郎」
③影などの乱れ動くさま。蕪村句集「古傘の―と月夜の時雨かな」
④物の散り乱れるさま。
⑤竹の葉などの風にあたって鳴る音。
⑥琴などの音調の曲折あるさま。
バザー【baza(a)r】
(もとペルシア語で市場の意)社会事業などの資金を集める目的で催す市いち。慈善市。→バザール
ハザード【hazard】
(危険・障害物の意)ゴルフで、コースに設けたバンカーやウォーター‐ハザードのこと。
⇒ハザード‐マップ【hazard map】
⇒ハザード‐ランプ【hazard lamp】
ハザード‐マップ【hazard map】
(→)災害予測地図に同じ。
⇒ハザード【hazard】
ハザード‐ランプ【hazard lamp】
自動車の非常点滅表示灯。路肩停車時など、危険を他の車などに伝えるために点滅させるランプ。
⇒ハザード【hazard】
バザーリ【G. Vasari】
⇒ヴァザーリ
バザール【bāzār ペルシア】
①インド・中央アジア・中東諸国などの市場。
②種々雑多な品物を売る一群の小店。
③百貨店などの大売出し。→バザー
は‐さい【破砕・破摧】
やぶりくだくこと。また、やぶれくだけること。「岩石の―」「敵を―する」
⇒はさい‐き【破砕機】
はさい‐き【破砕機】
(→)クラッシャーに同じ。
⇒は‐さい【破砕・破摧】
は‐ざお【歯竿】‥ザヲ
(→)ラック(rack)1に同じ。
は‐ざかい【刃境】‥ザカヒ
刀の刃と地との境。
はざかい‐き【端境期】‥ザカヒ‥
古米に代わって新米が市場に出回ろうとする時期。9〜10月頃の称。転じて、果物・野菜などの市場に出回らなくなる時期、広義にはさまざまな移行期をもいう。
はさか・う【挟かふ】ハサカフ
〔自四〕
はさまる。猿蓑「塩魚の歯に―・ふや秋の暮」(荷兮)
はさ‐がた【夾形】
結髪用具。長さ約1尺、幅約5分ほどの羅うすものの紐。飾り紐に使う。
は‐さき【刃先】
刀などのきっさき。刀鋩とうぼう。
は‐さき【羽先】
はねの先端。
は‐さき【葉先】
①葉の先端。ようせん。
②(→)「かいさき(櫂先)」2に同じ。
は‐ざくら【葉桜】
①花が散って若葉が出はじめた頃の桜。〈[季]夏〉
②紋所の名。
ばさ・ける
〔自下一〕
ばさばさする。ちらばる。(嬉遊笑覧)
はささ・く【馳ささく】
〔他下二〕
馳せさせる。万葉集14「小お林に駒を―・け」
ハ‐ざし【ハ刺し】
洋裁のステッチの一種。片仮名のハの字型の針目が並ぶもの。主に芯地を表地に縫いつけるのに用いる。
は‐ざし【刃刺・羽差】
近世の沿岸鯨漁で、勢子船に乗った銛もり師。銛を打ち、捕った鯨を船に結びつけるなど、危険で熟練を要する仕事を受け持つ役。
は‐ざし【葉挿し】
挿木法の一つ。接穂つぎほに葉を用い、不定芽を出させるもの。
ば‐さし【馬刺】
馬肉の刺身。
はさ・す【馳さす】
〔他下二〕
馳せさせる。走らせる。万葉集14「さざれ石に駒を―・せて」
はさつ‐おん【破擦音】
〔言〕(affricate)破裂音の直後に摩擦音がつづき、全体で一つの単音と見なされる音。〔ts〕〔dz〕〔tʃ〕〔dʒ〕など。
ばさ‐つ・く
〔自五〕
ばさばさする。
ぱさ‐つ・く
〔自五〕
ぱさぱさになる。水分がなくなりぱさぱさした感じになる。「パンが―・く」「髪が―・く」
ばさっ‐と
〔副〕
①翼・小枝・紙の束などが触れ合ったり打ち当たったりしてたてる音、また、そのさま。「新聞を―置く」
②一気に、または大量に切断するさま。「髪を―切る」
パサデナ【Pasadena】
アメリカ合衆国南西部、ロサンゼルス市北東郊にある住宅都市。人口11万7千(2000)。
ばさ‐ばさ
①乾いた薄いものが繰り返し触れ合って発する音。また、そのさま。「鷲が―と舞い下りる」
②ものを思い切りよく大量に切り落とすさま。「枝を―と払う」
③ひとまとまりに整っているべきものが乱れているさま。「書類が―に散らかる」「―した髪」
ぱさ‐ぱさ
水分や脂肪分が抜けて乾いているさま。手触りや口当りが乾いた感じで味わいがないさま。「パンが―する」
はざ‐ま【狭間・迫間】
(古くはハサマ)
①物と物との間のせまいところ。あわい。伊勢物語「後涼殿の―を渡りければ」
②谷あい。谷。〈皇極紀訓注〉
③あいだ。ほど。おり。宇治拾遺物語11「その―は唇ばかり働くは念仏なめりと見ゆ」
④矢・鉄砲などを放つために、城壁に設けた穴。銃眼。
⑤鶯の籠につけた丸いすかし。
⇒はざま‐くばり【狭間配り】
はざま【間】
姓氏の一つ。
⇒はざま‐しげとみ【間重富】
はざま‐くばり【狭間配り】
籠城で、矢・弾丸を放つため、兵士を城壁の狭間に配置すること。
⇒はざ‐ま【狭間・迫間】
はざま‐しげとみ【間重富】
江戸後期の天文暦学者。長涯と号。大坂の質商。麻田剛立に入門、西洋の天文暦学を研究。望遠鏡や種々の観測機器を作り、天体観測上に画期をなした。のち幕府に召されて寛政改暦に当たった。(1756〜1816)
⇒はざま【間】
はさま・る【挟まる】
〔自五〕
物と物との間に入って動きがとれなくなる。宇治拾遺物語13「股に―・りてある折」。「扉に手が―・る」「二人の間に―・って苦労する」
はさみ【挟み・挿み】
はさむこと。→はさみ(鋏)。
⇒はさみ‐いた【挟板】
⇒はさみ‐うち【挟み撃ち】
⇒はさみ‐おび【挟み帯】
⇒はさみ‐かせ【挟械】
⇒はさみ‐がみ【挟み紙】
⇒はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
⇒はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
⇒はさみ‐ざかな【挟み肴】
⇒はさみ‐じょう【挟み状】
⇒はさみ‐しょうぎ【挟み将棋】
⇒はさみ‐だけ【挟み竹】
⇒はさみ‐ばこ【挟箱】
⇒はさみ‐むすび【挟み結び】
⇒はさみ‐もの【挟み物・挿み物】
はさみ【鋏・剪刀】
①2枚の刃で挟むようにして物を切る道具。切符などに穴をあけるパンチのこともいう。〈倭名類聚鈔15〉
②(「螯」「鉗」とも書く)節足動物のカニ・サソリなどの脚の(→)鋏1のような部分。これを持つ脚を特に鋏脚(鉗脚かんきゃくとも)という。
③(じゃんけんで)2本の指を伸ばした形。ちょき。「石、紙、―」
⇒はさみじょう‐かかくさ【鋏状価格差】
⇒はさみ‐ばん【鋏盤】
⇒はさみ‐むし【鋏虫・蠼螋】
⇒鋏を入れる
はさみ‐あ・げる【挟み上げる】
〔他下一〕[文]はさみあ・ぐ(下二)
箸などで、はさんで持ち上げる。
はさみ‐いた【挟板】
門の左右に取り付ける板作りの袖。はさいた。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐い・れる【挟み入れる】
〔他下一〕[文]はさみい・る(下二)
①物の間に入れこむ。はさみこむ。
②はさんで他へ移し入れる。
はさみ‐うち【挟み撃ち】
相手を両側から挟むようにして攻撃すること。「敵を―にする」
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐う・つ【挟み撃つ】
〔他五〕
敵を中に挟んで、左右または前後から攻撃する。
はさみ‐おび【挟み帯】
はさみ結びにすること。さしこみおび。つっこみおび。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐かせ【挟械】
掘建ほったて柱の根を固めるために、その左右に取り付ける根かせ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐がみ【挟み紙】
①書物の中の必要な箇所に注意のために挟む紙片。しおり。
②重ねてある物品の間に挟んで、傷がつかないようにする紙。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐き・る【剪み切る】
〔他四〕
鋏で切り取る。
はさみ‐ゲージ【挟みゲージ】
限界ゲージの一種。ゲージの口を工作物にあてがい、円筒形・球形の直径、直方体の厚さなどが許しうる上限と下限の間に入っているかどうか検査するのに用いる。スナップ‐ゲージ。
挟みゲージ
 ⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
①文の中に挟み込むことば。
②(→)唐言からことに同じ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐こ・む【
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐ことば【挟み詞・挿語】
①文の中に挟み込むことば。
②(→)唐言からことに同じ。
⇒はさみ【挟み・挿み】
はさみ‐こ・む【ばけ‐ばけ・し【化け化けし】🔗⭐🔉
ばけ‐ばけ・し【化け化けし】
〔形シク〕
いかにもよくばけたようである。また、あざむく傾向がある。いつわりである。和歌秘伝抄「世の中皆―・しくなりて、飾りたる偽りにふけりて」
ば・ける【化ける】🔗⭐🔉
ば・ける【化ける】
〔自下一〕[文]ば・く(下二)
(古くはハクとも)
①形をかえる。異形のものに変わる。徒然草「未練の狐、―・け損じけるにこそ」
②素姓を隠して別人のさまをよそおう。「村人に―・けて潜入する」
③全く別のものに変わる。「学資が酒代に―・ける」
④目立つ所のなかった芸人・役者が予期しないほどに良く変わる。広く、思いもよらない大当りとなる。
[漢]化🔗⭐🔉
化 字形
 筆順
筆順
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部2画/4画/教育/1829・323D〕
[
)部2画/4画/教育/1829・323D〕
[ ] 字形
] 字形
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部2画/4画〕
〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)
〔訓〕ばける・ばかす
[意味]
①形や性質・状態があらたまって別のものになる。変わる。変える。ばける。「雲、竜と化す」「化合・化身けしん・変化へんか・へんげ・進化・映画化・画一化」
②万物を生成する(はたらき)。「陰陽の化」「化育・造化」
③影響を及ぼす。教えみちびく。「無為にして化す」「教化きょうか・きょうけ・徳化・感化・化外けがい」
[解字]
解字
)部2画/4画〕
〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)
〔訓〕ばける・ばかす
[意味]
①形や性質・状態があらたまって別のものになる。変わる。変える。ばける。「雲、竜と化す」「化合・化身けしん・変化へんか・へんげ・進化・映画化・画一化」
②万物を生成する(はたらき)。「陰陽の化」「化育・造化」
③影響を及ぼす。教えみちびく。「無為にして化す」「教化きょうか・きょうけ・徳化・感化・化外けがい」
[解字]
解字 会意。左右それぞれ人の立っている姿勢とすわっている姿勢。姿をかえる意を表す。もと、匕部2画。
[下ツキ
悪化・異化・羽化・液化・塩化・欧化・王化・応化・開化・感化・勧化・帰化・気化・強化・教化・劇化・激化・
会意。左右それぞれ人の立っている姿勢とすわっている姿勢。姿をかえる意を表す。もと、匕部2画。
[下ツキ
悪化・異化・羽化・液化・塩化・欧化・王化・応化・開化・感化・勧化・帰化・気化・強化・教化・劇化・激化・ 化・膠化・硬化・権化・酸化・磁化・時化・弱化・臭化物・純化・醇化・馴化・消化・浄化・所化・進化・深化・赤化・遷化・千変万化・造化・俗化・退化・脱化・炭化・転化・電化・同化・道化・徳化・鈍化・軟化・濃化・能化・美化・風化・孵化・普化僧・分化・文化・変化・沃化・硫化・緑化・劣化・老化・矮化
化・膠化・硬化・権化・酸化・磁化・時化・弱化・臭化物・純化・醇化・馴化・消化・浄化・所化・進化・深化・赤化・遷化・千変万化・造化・俗化・退化・脱化・炭化・転化・電化・同化・道化・徳化・鈍化・軟化・濃化・能化・美化・風化・孵化・普化僧・分化・文化・変化・沃化・硫化・緑化・劣化・老化・矮化
 筆順
筆順
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部2画/4画/教育/1829・323D〕
[
)部2画/4画/教育/1829・323D〕
[ ] 字形
] 字形
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部2画/4画〕
〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)
〔訓〕ばける・ばかす
[意味]
①形や性質・状態があらたまって別のものになる。変わる。変える。ばける。「雲、竜と化す」「化合・化身けしん・変化へんか・へんげ・進化・映画化・画一化」
②万物を生成する(はたらき)。「陰陽の化」「化育・造化」
③影響を及ぼす。教えみちびく。「無為にして化す」「教化きょうか・きょうけ・徳化・感化・化外けがい」
[解字]
解字
)部2画/4画〕
〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)
〔訓〕ばける・ばかす
[意味]
①形や性質・状態があらたまって別のものになる。変わる。変える。ばける。「雲、竜と化す」「化合・化身けしん・変化へんか・へんげ・進化・映画化・画一化」
②万物を生成する(はたらき)。「陰陽の化」「化育・造化」
③影響を及ぼす。教えみちびく。「無為にして化す」「教化きょうか・きょうけ・徳化・感化・化外けがい」
[解字]
解字 会意。左右それぞれ人の立っている姿勢とすわっている姿勢。姿をかえる意を表す。もと、匕部2画。
[下ツキ
悪化・異化・羽化・液化・塩化・欧化・王化・応化・開化・感化・勧化・帰化・気化・強化・教化・劇化・激化・
会意。左右それぞれ人の立っている姿勢とすわっている姿勢。姿をかえる意を表す。もと、匕部2画。
[下ツキ
悪化・異化・羽化・液化・塩化・欧化・王化・応化・開化・感化・勧化・帰化・気化・強化・教化・劇化・激化・ 化・膠化・硬化・権化・酸化・磁化・時化・弱化・臭化物・純化・醇化・馴化・消化・浄化・所化・進化・深化・赤化・遷化・千変万化・造化・俗化・退化・脱化・炭化・転化・電化・同化・道化・徳化・鈍化・軟化・濃化・能化・美化・風化・孵化・普化僧・分化・文化・変化・沃化・硫化・緑化・劣化・老化・矮化
化・膠化・硬化・権化・酸化・磁化・時化・弱化・臭化物・純化・醇化・馴化・消化・浄化・所化・進化・深化・赤化・遷化・千変万化・造化・俗化・退化・脱化・炭化・転化・電化・同化・道化・徳化・鈍化・軟化・濃化・能化・美化・風化・孵化・普化僧・分化・文化・変化・沃化・硫化・緑化・劣化・老化・矮化
広辞苑に「化」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む