複数辞典一括検索+![]()
![]()
安積艮斎 アサカゴンサイ🔗⭐🔉
【安積艮斎】
アサカゴンサイ〔日〕〈人名〉1791〜1860 江戸時代末期の漢学者。名は重信シゲノブ、字アザナは思順、艮斎は号。岩代イワシロ(福島県)の人。佐藤一斎に学び、のち昌平黌ショウヘイコウの教授。名文家として知られ、著に『艮斎閑話カンワ』『荀子ジュンシ略説』などがある。
旭 あさひ🔗⭐🔉
晁 あさ🔗⭐🔉
晨 あさ🔗⭐🔉
【晨】
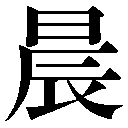 11画 日部 [人名漢字]
区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED
《音読み》 シン
11画 日部 [人名漢字]
区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED
《音読み》 シン /ジン
/ジン 〈ch
〈ch n〉
《訓読み》 あさ/あした/とき
《名付け》 あき・とき・とよ
《意味》
n〉
《訓読み》 あさ/あした/とき
《名付け》 あき・とき・とよ
《意味》
 {名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕
{名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕
 {名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕
{名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕
 {名}二十八宿の一つ。房星。
《解字》
会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。
《単語家族》
震(ふるう)
{名}二十八宿の一つ。房星。
《解字》
会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。
《単語家族》
震(ふるう) 振と同系。
《類義》
→朝
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
振と同系。
《類義》
→朝
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
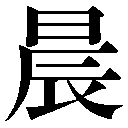 11画 日部 [人名漢字]
区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED
《音読み》 シン
11画 日部 [人名漢字]
区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED
《音読み》 シン /ジン
/ジン 〈ch
〈ch n〉
《訓読み》 あさ/あした/とき
《名付け》 あき・とき・とよ
《意味》
n〉
《訓読み》 あさ/あした/とき
《名付け》 あき・とき・とよ
《意味》
 {名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕
{名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕
 {名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕
{名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕
 {名}二十八宿の一つ。房星。
《解字》
会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。
《単語家族》
震(ふるう)
{名}二十八宿の一つ。房星。
《解字》
会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。
《単語家族》
震(ふるう) 振と同系。
《類義》
→朝
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
振と同系。
《類義》
→朝
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
朝 あさ🔗⭐🔉
【朝】
 12画 月部 [二年]
区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9
《常用音訓》チョウ/あさ
《音読み》
12画 月部 [二年]
区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9
《常用音訓》チョウ/あさ
《音読み》  チョウ(テウ)
チョウ(テウ)
 〈zh
〈zh o〉
o〉 チョウ(テウ)
チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)
《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ
《意味》
o〉
《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)
《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ
《意味》

 {名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」
{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」
 「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。
「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

 チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」
チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」
 チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」
チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」
 {名}天子が政治を行うところ。「朝廷」
{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」
 {名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」
《解字》
{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」
《解字》
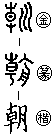 会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。
《単語家族》
抽(抜き出す)
会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。
《単語家族》
抽(抜き出す) 冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。
《類義》
旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。
《類義》
旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 12画 月部 [二年]
区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9
《常用音訓》チョウ/あさ
《音読み》
12画 月部 [二年]
区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9
《常用音訓》チョウ/あさ
《音読み》  チョウ(テウ)
チョウ(テウ)
 〈zh
〈zh o〉
o〉 チョウ(テウ)
チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)
《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ
《意味》
o〉
《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)
《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ
《意味》

 {名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」
{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」
 「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。
「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

 チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」
チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」
 チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」
チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」
 {名}天子が政治を行うところ。「朝廷」
{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」
 {名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」
《解字》
{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」
《解字》
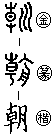 会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。
《単語家族》
抽(抜き出す)
会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。
《単語家族》
抽(抜き出す) 冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。
《類義》
旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。
《類義》
旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
浅 あさい🔗⭐🔉
【浅】
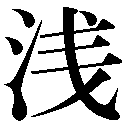 9画 水部 [四年]
区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3
【淺】旧字旧字
9画 水部 [四年]
区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3
【淺】旧字旧字
 11画 水部
区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7
《常用音訓》セン/あさ…い
《音読み》 セン
11画 水部
区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7
《常用音訓》セン/あさ…い
《音読み》 セン
 〈qi
〈qi n・ji
n・ji n〉
《訓読み》 あさい(あさし)
《名付け》 あさ
《意味》
n〉
《訓読み》 あさい(あさし)
《名付け》 あさ
《意味》
 {形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕
{形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕
 {形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」
《解字》
会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔
《単語家族》
賤セン(財貨が少ない→いやしい)
{形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」
《解字》
会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔
《単語家族》
賤セン(財貨が少ない→いやしい) 箋セン(小さい竹札)
箋セン(小さい竹札) 錢(=銭。小ぜに)
錢(=銭。小ぜに) 盞サン(小ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
盞サン(小ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
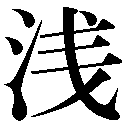 9画 水部 [四年]
区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3
【淺】旧字旧字
9画 水部 [四年]
区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3
【淺】旧字旧字
 11画 水部
区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7
《常用音訓》セン/あさ…い
《音読み》 セン
11画 水部
区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7
《常用音訓》セン/あさ…い
《音読み》 セン
 〈qi
〈qi n・ji
n・ji n〉
《訓読み》 あさい(あさし)
《名付け》 あさ
《意味》
n〉
《訓読み》 あさい(あさし)
《名付け》 あさ
《意味》
 {形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕
{形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕
 {形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」
《解字》
会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔
《単語家族》
賤セン(財貨が少ない→いやしい)
{形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」
《解字》
会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔
《単語家族》
賤セン(財貨が少ない→いやしい) 箋セン(小さい竹札)
箋セン(小さい竹札) 錢(=銭。小ぜに)
錢(=銭。小ぜに) 盞サン(小ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
盞サン(小ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
浅蜊 アサリ🔗⭐🔉
【浅蜊】
アサリ〔国〕二枚貝の名。浅い海の砂の中にすむ。
浅見絅斎 アサミケイサイ🔗⭐🔉
【浅見絅斎】
アサミケイサイ〔日〕〈人名〉1652〜1711 江戸時代の儒学者。名は安正、絅斎は号。近江オウミ(滋賀県)の人。山崎闇斎アンサイについて朱子学を学んだ。足利尊氏を乱臣としたり、赤穂四十七士を義士としたりして、尊皇思想・大義名分を唱えた。著に『靖献セイケン遺言』『中庸講義』など。
漁 あさる🔗⭐🔉
【漁】
 14画 水部 [四年]
区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99
《常用音訓》ギョ/リョウ
《音読み》 ギョ
14画 水部 [四年]
区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99
《常用音訓》ギョ/リョウ
《音読み》 ギョ /リョウ(レフ)
/リョウ(レフ) /ゴ
/ゴ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる
《意味》
〉
《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる
《意味》
 ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕
ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕
 {動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」
《解字》
会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」
《解字》
会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 14画 水部 [四年]
区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99
《常用音訓》ギョ/リョウ
《音読み》 ギョ
14画 水部 [四年]
区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99
《常用音訓》ギョ/リョウ
《音読み》 ギョ /リョウ(レフ)
/リョウ(レフ) /ゴ
/ゴ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる
《意味》
〉
《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる
《意味》
 ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕
ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕
 {動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」
《解字》
会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」
《解字》
会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
潮 あさしお🔗⭐🔉
【潮】
 15画 水部 [六年]
区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA
《常用音訓》チョウ/しお
《音読み》 チョウ(テウ)
15画 水部 [六年]
区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA
《常用音訓》チョウ/しお
《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)
《名付け》 うしお・しお
《意味》
o〉
《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)
《名付け》 うしお・しお
《意味》
 {名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕
{名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕
 {名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」
{名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」
 {動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」
{動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」
 {名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」
{名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」
 {名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。
〔国〕
{名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。
〔国〕 うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」
うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」 しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」
しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」 しお(シホ)。とき。おり。「潮時」
しお(シホ)。とき。おり。「潮時」 世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」
世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」 月経のこと。「初潮」
《解字》
会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。
《単語家族》
朝と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
月経のこと。「初潮」
《解字》
会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。
《単語家族》
朝と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 水部 [六年]
区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA
《常用音訓》チョウ/しお
《音読み》 チョウ(テウ)
15画 水部 [六年]
区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA
《常用音訓》チョウ/しお
《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)
《名付け》 うしお・しお
《意味》
o〉
《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)
《名付け》 うしお・しお
《意味》
 {名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕
{名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕
 {名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」
{名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」
 {動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」
{動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」
 {名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」
{名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」
 {名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。
〔国〕
{名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。
〔国〕 うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」
うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」 しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」
しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」 しお(シホ)。とき。おり。「潮時」
しお(シホ)。とき。おり。「潮時」 世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」
世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」 月経のこと。「初潮」
《解字》
会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。
《単語家族》
朝と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
月経のこと。「初潮」
《解字》
会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。
《単語家族》
朝と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
猟 あさる🔗⭐🔉
【猟】
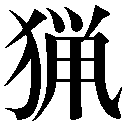 11画 犬部 [常用漢字]
区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2
【獵】旧字旧字
11画 犬部 [常用漢字]
区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2
【獵】旧字旧字
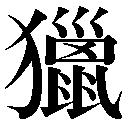 18画 犬部
区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(レフ)
18画 犬部
区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(レフ)
 〈li
〈li 〉
《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる
《意味》
〉
《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる
《意味》
 リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕
リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕
 {動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」
{動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」
 「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕
〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。
《解字》
会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。
《類義》
→狩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕
〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。
《解字》
会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。
《類義》
→狩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
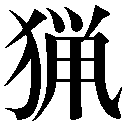 11画 犬部 [常用漢字]
区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2
【獵】旧字旧字
11画 犬部 [常用漢字]
区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2
【獵】旧字旧字
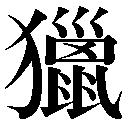 18画 犬部
区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(レフ)
18画 犬部
区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(レフ)
 〈li
〈li 〉
《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる
《意味》
〉
《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる
《意味》
 リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕
リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕
 {動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」
{動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」
 「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕
〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。
《解字》
会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。
《類義》
→狩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕
〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。
《解字》
会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。
《類義》
→狩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
苴 あさ🔗⭐🔉
苜 あさ🔗⭐🔉
【苜】
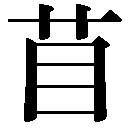 8画 艸部
区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C
《音読み》 ボク
8画 艸部
区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C
《音読み》 ボク /モク
/モク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 あさ
《意味》
「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。
《解字》
形声。「艸+音符目」。
〉
《訓読み》 あさ
《意味》
「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。
《解字》
形声。「艸+音符目」。
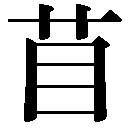 8画 艸部
区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C
《音読み》 ボク
8画 艸部
区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C
《音読み》 ボク /モク
/モク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 あさ
《意味》
「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。
《解字》
形声。「艸+音符目」。
〉
《訓読み》 あさ
《意味》
「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。
《解字》
形声。「艸+音符目」。
蕣 あさがお🔗⭐🔉
【蕣】
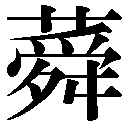 15画 艸部
区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA
《音読み》 シュン
15画 艸部
区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA
《音読み》 シュン
 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)
《意味》
{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。
〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。
《熟語》
→熟語
n〉
《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)
《意味》
{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。
〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。
《熟語》
→熟語
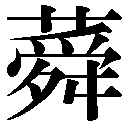 15画 艸部
区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA
《音読み》 シュン
15画 艸部
区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA
《音読み》 シュン
 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)
《意味》
{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。
〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。
《熟語》
→熟語
n〉
《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)
《意味》
{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。
〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。
《熟語》
→熟語
蜊 あさり🔗⭐🔉
【蜊】
 13画 虫部
区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D
《音読み》 リ
13画 虫部
区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D
《音読み》 リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 あさり
《意味》
「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。
〔国〕あさり。貝の名。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。
《熟語》
→下付・中付語
〉
《訓読み》 あさり
《意味》
「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。
〔国〕あさり。貝の名。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。
《熟語》
→下付・中付語
 13画 虫部
区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D
《音読み》 リ
13画 虫部
区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D
《音読み》 リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 あさり
《意味》
「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。
〔国〕あさり。貝の名。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。
《熟語》
→下付・中付語
〉
《訓読み》 あさり
《意味》
「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。
〔国〕あさり。貝の名。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。
《熟語》
→下付・中付語
鯏 あさり🔗⭐🔉
【鯏】
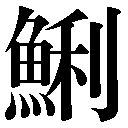 18画 魚部 〔国〕
区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3
《訓読み》 あさり
《意味》
あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。
《解字》
形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。
18画 魚部 〔国〕
区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3
《訓読み》 あさり
《意味》
あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。
《解字》
形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。
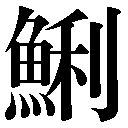 18画 魚部 〔国〕
区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3
《訓読み》 あさり
《意味》
あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。
《解字》
形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。
18画 魚部 〔国〕
区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3
《訓読み》 あさり
《意味》
あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。
《解字》
形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。
麻 あさ🔗⭐🔉
【麻】
 11画 麻部 [常用漢字]
区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683
《常用音訓》マ/あさ
《音読み》 マ
11画 麻部 [常用漢字]
区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683
《常用音訓》マ/あさ
《音読み》 マ /メ
/メ /バ
/バ 〈m
〈m 〉
《訓読み》 あさ
《名付け》 あさ・お・ぬさ
《意味》
〉
《訓読み》 あさ
《名付け》 あさ・お・ぬさ
《意味》
 {名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。
{名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。
 {名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」
{名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」
 {動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」
{動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」
 {名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。
《解字》
会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。
《単語家族》
摩(こする)
{名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。
《解字》
会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。
《単語家族》
摩(こする) 模(こする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
模(こする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 11画 麻部 [常用漢字]
区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683
《常用音訓》マ/あさ
《音読み》 マ
11画 麻部 [常用漢字]
区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683
《常用音訓》マ/あさ
《音読み》 マ /メ
/メ /バ
/バ 〈m
〈m 〉
《訓読み》 あさ
《名付け》 あさ・お・ぬさ
《意味》
〉
《訓読み》 あさ
《名付け》 あさ・お・ぬさ
《意味》
 {名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。
{名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。
 {名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」
{名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」
 {動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」
{動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」
 {名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。
《解字》
会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。
《単語家族》
摩(こする)
{名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。
《解字》
会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。
《単語家族》
摩(こする) 模(こする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
模(こする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
麻木 アサギ🔗⭐🔉
【麻木】
 マボク
マボク  「麻痺」と同じ。
「麻痺」と同じ。 ぼんやりして鈍い人。
ぼんやりして鈍い人。 アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。
アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。
 マボク
マボク  「麻痺」と同じ。
「麻痺」と同じ。 ぼんやりして鈍い人。
ぼんやりして鈍い人。 アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。
アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。
莇 あさがら🔗⭐🔉
【莇】
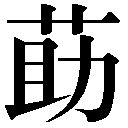 10画 艸部
区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4
《音読み》 チョ/ショ
10画 艸部
区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4
《音読み》 チョ/ショ /ジョ/ソ
/ジョ/ソ 《訓読み》 あさがら/あざみ
《意味》
《訓読み》 あさがら/あざみ
《意味》
 草の名。くこ。
草の名。くこ。 中国古代の税法の一。
〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。
中国古代の税法の一。
〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。
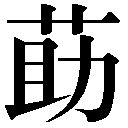 10画 艸部
区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4
《音読み》 チョ/ショ
10画 艸部
区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4
《音読み》 チョ/ショ /ジョ/ソ
/ジョ/ソ 《訓読み》 あさがら/あざみ
《意味》
《訓読み》 あさがら/あざみ
《意味》
 草の名。くこ。
草の名。くこ。 中国古代の税法の一。
〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。
中国古代の税法の一。
〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。
漢字源に「あさ」で始まるの検索結果 1-20。
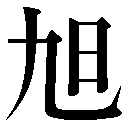 6画 日部 [人名漢字]
区点=1616 16進=3030 シフトJIS=88AE
《音読み》 キョク
6画 日部 [人名漢字]
区点=1616 16進=3030 シフトJIS=88AE
《音読み》 キョク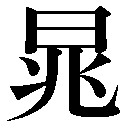 10画 日部
区点=5874 16進=5A6A シフトJIS=9DE8
《音読み》 チョウ(テウ)
10画 日部
区点=5874 16進=5A6A シフトJIS=9DE8
《音読み》 チョウ(テウ)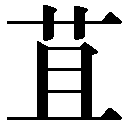 8画 艸部
区点=7183 16進=6773 シフトJIS=E493
《音読み》 ショ
8画 艸部
区点=7183 16進=6773 シフトJIS=E493
《音読み》 ショ 〉
《訓読み》 あさ
《意味》
〉
《訓読み》 あさ
《意味》