複数辞典一括検索+![]()
![]()
例 たとえ🔗⭐🔉
【例】
 8画 人部 [四年]
区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1
《常用音訓》レイ/たと…える
《音読み》 レイ
8画 人部 [四年]
区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1
《常用音訓》レイ/たと…える
《音読み》 レイ /レ
/レ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)
《名付け》 ただ・つね・とも・みち
《意味》
〉
《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)
《名付け》 ただ・つね・とも・みち
《意味》
 {名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」
{名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」
 レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」
レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」
 レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕
〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。
《解字》
会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕
〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。
《解字》
会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 人部 [四年]
区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1
《常用音訓》レイ/たと…える
《音読み》 レイ
8画 人部 [四年]
区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1
《常用音訓》レイ/たと…える
《音読み》 レイ /レ
/レ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)
《名付け》 ただ・つね・とも・みち
《意味》
〉
《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)
《名付け》 ただ・つね・とも・みち
《意味》
 {名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」
{名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」
 レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」
レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」
 レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕
〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。
《解字》
会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕
〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。
《解字》
会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
即 たとえ🔗⭐🔉
【即】
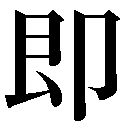 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 7画 卩部 [常用漢字]
区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6
《常用音訓》ソク
《音読み》 ソク
7画 卩部 [常用漢字]
区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6
《常用音訓》ソク
《音読み》 ソク /ショク
/ショク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)
《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より
《意味》
〉
《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)
《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より
《意味》
 ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕
ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕
 {副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕
{副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕
 {副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕
{副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕
 {接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕
{接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕
 {接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕
{接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。
《解字》
{接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。
《解字》
 会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。
《単語家族》
則(そばにくっつく)
会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。
《単語家族》
則(そばにくっつく) 側(そば)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
側(そば)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
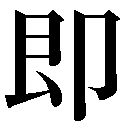 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 7画 卩部 [常用漢字]
区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6
《常用音訓》ソク
《音読み》 ソク
7画 卩部 [常用漢字]
区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6
《常用音訓》ソク
《音読み》 ソク /ショク
/ショク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)
《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より
《意味》
〉
《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)
《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より
《意味》
 ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕
ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕
 {副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕
{副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕
 {副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕
{副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕
 {接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕
{接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕
 {接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕
{接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。
《解字》
{接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。
《解字》
 会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。
《単語家族》
則(そばにくっつく)
会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。
《単語家族》
則(そばにくっつく) 側(そば)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
側(そば)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
取譬 タトエヲトル🔗⭐🔉
【取譬】
シュヒ・タトエヲトル  他のことをもってきてたとえる。
他のことをもってきてたとえる。 基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。
基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。
 他のことをもってきてたとえる。
他のことをもってきてたとえる。 基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。
基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。
向使 タトエ🔗⭐🔉
【向使】
モシ・タトエ 。・タトイかりに。もしも。
喩 たとえ🔗⭐🔉
【喩】
 12画 口部
区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67
《音読み》 ユ
12画 口部
区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67
《音読み》 ユ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
〉
《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
 {動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕
{動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕
 {動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕
{動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕
 {名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕
{名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕
 {名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」
{名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」
 「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。
「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。
 {動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 口部
区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67
《音読み》 ユ
12画 口部
区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67
《音読み》 ユ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
〉
《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
 {動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕
{動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕
 {動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕
{動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕
 {名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕
{名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕
 {名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」
{名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」
 「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。
「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。
 {動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕
《解字》
会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
引喩 タトエヲヒク🔗⭐🔉
【引喩】
インユ・タトエヲヒク たとえを引用する。『引比インピ』
況 たとえる🔗⭐🔉
【況】
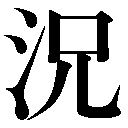 8画 水部 [常用漢字]
区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5
【况】異体字異体字
8画 水部 [常用漢字]
区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5
【况】異体字異体字
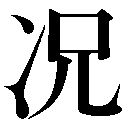 7画 冫部
区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ク
7画 冫部
区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ク ャウ)
ャウ) /コウ(ク
/コウ(ク ウ)
ウ) 〈ku
〈ku ng〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます
《意味》
ng〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます
《意味》
 {名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕
{名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕
 {動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」
{動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」
 {接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕
{接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕
 {副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。
《単語家族》
汪オウ(水が大きく広がる)
{副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。
《単語家族》
汪オウ(水が大きく広がる) 広(大きくひろがる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
広(大きくひろがる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
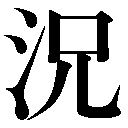 8画 水部 [常用漢字]
区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5
【况】異体字異体字
8画 水部 [常用漢字]
区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5
【况】異体字異体字
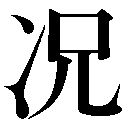 7画 冫部
区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ク
7画 冫部
区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ク ャウ)
ャウ) /コウ(ク
/コウ(ク ウ)
ウ) 〈ku
〈ku ng〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます
《意味》
ng〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます
《意味》
 {名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕
{名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕
 {動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」
{動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」
 {接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕
{接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕
 {副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。
《単語家族》
汪オウ(水が大きく広がる)
{副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。
《単語家族》
汪オウ(水が大きく広がる) 広(大きくひろがる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
広(大きくひろがる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縦 たとえ🔗⭐🔉
【縦】
 16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
 17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ
17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ /ショウ
/ショウ /シュ
/シュ 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
 {名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
 {形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
 {動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
 17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ
17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ /ショウ
/ショウ /シュ
/シュ 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
 {名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
 {形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
 {動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縦使 タトエ🔗⭐🔉
【縦令】
タトエ・タトイ かりに、…しても。『縦使タトエ・タトイ』「縦令然諾暫相許=縦令然諾シテ暫クアヒ許ストモ」〔張謂〕
諭 たとえ🔗⭐🔉
【諭】
 16画 言部 [常用漢字]
区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740
《常用音訓》ユ/さと…す
《音読み》 ユ
16画 言部 [常用漢字]
区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740
《常用音訓》ユ/さと…す
《音読み》 ユ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ
《意味》
〉
《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ
《意味》
 {動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕
{動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕
 {名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」
{名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」
 {動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕
{動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕
 {名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」
《解字》
会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。
《単語家族》
癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」
《解字》
会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。
《単語家族》
癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画 言部 [常用漢字]
区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740
《常用音訓》ユ/さと…す
《音読み》 ユ
16画 言部 [常用漢字]
区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740
《常用音訓》ユ/さと…す
《音読み》 ユ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ
《意味》
〉
《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ
《意味》
 {動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕
{動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕
 {名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」
{名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」
 {動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕
{動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕
 {名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」
《解字》
会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。
《単語家族》
癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」
《解字》
会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。
《単語家族》
癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
譬 たとえ🔗⭐🔉
【譬】
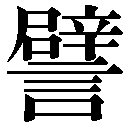 20画 言部
区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0
《音読み》 ヒ
20画 言部
区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0
《音読み》 ヒ
 〈p
〈p 〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。
《単語家族》
避ヒ(本すじから横にさける)
〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。
《単語家族》
避ヒ(本すじから横にさける) 僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
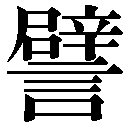 20画 言部
区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0
《音読み》 ヒ
20画 言部
区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0
《音読み》 ヒ
 〈p
〈p 〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。
《単語家族》
避ヒ(本すじから横にさける)
〉
《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)
《意味》
{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。
《単語家族》
避ヒ(本すじから横にさける) 僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。
《類義》
→並
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
辟若 タトエバ…ノゴトシ🔗⭐🔉
【辟若】
タトエバ…ノゴトシ たとえていうならば…のようである。「孟子曰、有為者辟若掘井=孟子曰ク、為スコト有ル者ハ、辟ヘバ井ヲ掘ルガゴトシ」〔→孟子〕
漢字源に「たとえ」で始まるの検索結果 1-13。