複数辞典一括検索+![]()
![]()
介 はさまる🔗⭐🔉
【介】
 4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ
4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》

 カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
 カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
 {動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
 {名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
 {形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
 {形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
 {名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。
{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。
四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
 会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界
会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界 堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ
4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》

 カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
 カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
 {動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
 {名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
 {形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
 {形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
 {名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。
{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。
四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
 会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界
会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界 堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
叉 はさむ🔗⭐🔉
【叉】
 3画 又部
区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3
《音読み》 サ
3画 又部
区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3
《音読み》 サ /シャ
/シャ 〈ch
〈ch ・ch
・ch ・ch
・ch 〉
《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす
《意味》
 {動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」
{動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」
 {名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」
{名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」
 {動}さす。さすまたでさす。
{動}さす。さすまたでさす。
 〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。
《解字》
〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。
《解字》
 象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。
《単語家族》
左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。
《単語家族》
左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 3画 又部
区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3
《音読み》 サ
3画 又部
区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3
《音読み》 サ /シャ
/シャ 〈ch
〈ch ・ch
・ch ・ch
・ch 〉
《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす
《意味》
 {動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」
{動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」
 {名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」
{名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」
 {動}さす。さすまたでさす。
{動}さす。さすまたでさす。
 〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。
《解字》
〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。
《解字》
 象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。
《単語家族》
左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。
《単語家族》
左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
夾 はさむ🔗⭐🔉
【夾】
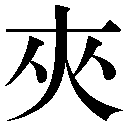 7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ)
7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
 {動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
 {形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
 {名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
 {名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
 会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ)
会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)
峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
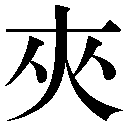 7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ)
7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
 {動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
 {形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
 {名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
 {名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
 会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ)
会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)
峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拑 はさむ🔗⭐🔉
挟 はさまる🔗⭐🔉
【挟】
 9画
9画  部 [常用漢字]
区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2
【挾】旧字旧字
部 [常用漢字]
区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2
【挾】旧字旧字
 10画
10画  部
区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70
《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む
《音読み》 キョウ(ケフ)
部
区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70
《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む
《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)
/ギョウ(ゲフ) 〈xi
〈xi ・ji
・ji 〉
《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ
《名付け》 さし・もち
《意味》
〉
《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ
《名付け》 さし・もち
《意味》
 {動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕
{動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕
 {動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕
{動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕
 {動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾
《単語家族》
狹キョウ(=狭。はさまれてせまい)
{動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾
《単語家族》
狹キョウ(=狭。はさまれてせまい) 峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷)
峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷) 脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画
9画  部 [常用漢字]
区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2
【挾】旧字旧字
部 [常用漢字]
区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2
【挾】旧字旧字
 10画
10画  部
区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70
《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む
《音読み》 キョウ(ケフ)
部
区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70
《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む
《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)
/ギョウ(ゲフ) 〈xi
〈xi ・ji
・ji 〉
《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ
《名付け》 さし・もち
《意味》
〉
《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ
《名付け》 さし・もち
《意味》
 {動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕
{動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕
 {動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕
{動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕
 {動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾
《単語家族》
狹キョウ(=狭。はさまれてせまい)
{動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾
《単語家族》
狹キョウ(=狭。はさまれてせまい) 峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷)
峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷) 脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
摂 はさまる🔗⭐🔉
【摂】
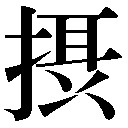 13画
13画  部 [常用漢字]
区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB
【攝】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB
【攝】旧字人名に使える旧字
 21画
21画  部
区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90
《常用音訓》セツ
《音読み》 セツ
部
区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90
《常用音訓》セツ
《音読み》 セツ /ショウ(セフ)
/ショウ(セフ)
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる
《名付け》 おさむ・かぬ・かね
《意味》
〉
《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる
《名付け》 おさむ・かぬ・かね
《意味》
 {動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕
{動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕
 {動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」
{動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」
 {動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕
{動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕
 セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「
セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「 老而舜摂也=
老而舜摂也= 老イテ舜摂ス」〔→孟子〕
老イテ舜摂ス」〔→孟子〕
 {動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕
{動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕
 ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。
《解字》
ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。
《解字》
 会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
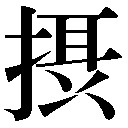 13画
13画  部 [常用漢字]
区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB
【攝】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB
【攝】旧字人名に使える旧字
 21画
21画  部
区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90
《常用音訓》セツ
《音読み》 セツ
部
区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90
《常用音訓》セツ
《音読み》 セツ /ショウ(セフ)
/ショウ(セフ)
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる
《名付け》 おさむ・かぬ・かね
《意味》
〉
《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる
《名付け》 おさむ・かぬ・かね
《意味》
 {動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕
{動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕
 {動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」
{動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」
 {動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕
{動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕
 セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「
セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「 老而舜摂也=
老而舜摂也= 老イテ舜摂ス」〔→孟子〕
老イテ舜摂ス」〔→孟子〕
 {動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕
{動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕
 ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。
《解字》
ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。
《解字》
 会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
破砕 ハサイ🔗⭐🔉
【破砕{摧}】
ハサイ こなごなにうちくだく。また、やぶれほろびる。
破算 ハサン🔗⭐🔉
【破算】
ハサン〔国〕 そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。
そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。 計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。
計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。
 そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。
そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。 計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。
計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。
筴 はさむ🔗⭐🔉
箝 はさむ🔗⭐🔉
漢字源に「はさ」で始まるの検索結果 1-12。
 8画
8画  〔俗〕すっかりだめになる。
〔俗〕すっかりだめになる。
 13画 竹部
区点=6809 16進=6429 シフトJIS=E2A7
《音読み》
13画 竹部
区点=6809 16進=6429 シフトJIS=E2A7
《音読み》  サク
サク キョウ(ケフ)
キョウ(ケフ)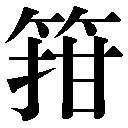 14画 竹部
区点=6815 16進=642F シフトJIS=E2AD
《音読み》 カン
14画 竹部
区点=6815 16進=642F シフトJIS=E2AD
《音読み》 カン 15画 金部
区点=7887 16進=6E77 シフトJIS=E7F5
《音読み》 キョウ(ケフ)
15画 金部
区点=7887 16進=6E77 シフトJIS=E7F5
《音読み》 キョウ(ケフ)