複数辞典一括検索+![]()
![]()
一生面 イツセイメン🔗⭐🔉
【一生面】
イツセイメン 新しいやり方。新機軸。
乙乙 イツイツ🔗⭐🔉
【乙乙】
 イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。
イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。 イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。
イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。
 イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。
イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。 イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。
イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。
乙夜 イツヤ🔗⭐🔉
【乙夜】
イツヤ 五夜の一つ。日没から夜明けまでの時間を五つにわけたその二番め。二更。二鼓。
乙夜之覧 イツヤノラン🔗⭐🔉
【乙夜之覧】
イツヤノラン『乙覧イツラン』〈故事〉天子の読書のこと。▽昔、中国で天子は昼間政治のことで忙しいので、乙夜になってはじめて読書をしたことから。
乙第 イツダイ🔗⭐🔉
【乙科】
イッカ・オツカ『乙第イツダイ』漢・唐時代、科挙(官吏登用試験)の成績の第二級。宋ソウ代、進士を甲科、挙人を乙科といった。
乙第 イツダイ🔗⭐🔉
【乙第】
イツダイ  別荘。別邸。
別荘。別邸。 「乙科」と同じ。
「乙科」と同じ。
 別荘。別邸。
別荘。別邸。 「乙科」と同じ。
「乙科」と同じ。
五 いつ🔗⭐🔉
【五】
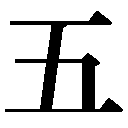 4画 二部 [一年]
区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC
《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ
《音読み》 ゴ
4画 二部 [一年]
区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC
《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ
《音読み》 ゴ
 〈w
〈w 〉
《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび
《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび
《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき
《意味》
 {数}いつつ。「五刑」
{数}いつつ。「五刑」
 {数}いつ。順番の五番め。「五月五日」
{数}いつ。順番の五番め。「五月五日」
 {副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕
〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
{副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕
〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
 指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。
《単語家族》
互ゴ(互いに交差する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。
《単語家族》
互ゴ(互いに交差する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
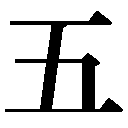 4画 二部 [一年]
区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC
《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ
《音読み》 ゴ
4画 二部 [一年]
区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC
《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ
《音読み》 ゴ
 〈w
〈w 〉
《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび
《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび
《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき
《意味》
 {数}いつつ。「五刑」
{数}いつつ。「五刑」
 {数}いつ。順番の五番め。「五月五日」
{数}いつ。順番の五番め。「五月五日」
 {副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕
〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
{副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕
〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
 指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。
《単語家族》
互ゴ(互いに交差する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。
《単語家族》
互ゴ(互いに交差する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
佚女 イツジョ🔗⭐🔉
【佚女】
イツジョ  美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。
美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。 道徳からはずれたみだらな女。
道徳からはずれたみだらな女。
 美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。
美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。 道徳からはずれたみだらな女。
道徳からはずれたみだらな女。
佚老 イツロウ🔗⭐🔉
【佚老】
イツロウ  世俗をのがれた老人。
世俗をのがれた老人。 老人をのんびりさせる。
老人をのんびりさせる。
 世俗をのがれた老人。
世俗をのがれた老人。 老人をのんびりさせる。
老人をのんびりさせる。
佚遊 イツユウ🔗⭐🔉
偽 いつわり🔗⭐🔉
【偽】
 11画 人部 [常用漢字]
区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55
【僞】旧字人名に使える旧字
11画 人部 [常用漢字]
区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55
【僞】旧字人名に使える旧字
 14画 人部
区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945
《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ
《音読み》 ギ(グ
14画 人部
区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945
《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ
《音読み》 ギ(グ )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)
《意味》
i〉
《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)
《意味》
 {動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕
{動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕
 {名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕
{名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕
 {名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕
{名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕
 {名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」
《解字》
会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、
{名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」
《解字》
会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、 の用法が為のもとの意味に近い。→為
《類義》
→欺
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
の用法が為のもとの意味に近い。→為
《類義》
→欺
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 人部 [常用漢字]
区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55
【僞】旧字人名に使える旧字
11画 人部 [常用漢字]
区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55
【僞】旧字人名に使える旧字
 14画 人部
区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945
《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ
《音読み》 ギ(グ
14画 人部
区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945
《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ
《音読み》 ギ(グ )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)
《意味》
i〉
《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)
《意味》
 {動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕
{動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕
 {名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕
{名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕
 {名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕
{名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕
 {名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」
《解字》
会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、
{名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」
《解字》
会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、 の用法が為のもとの意味に近い。→為
《類義》
→欺
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
の用法が為のもとの意味に近い。→為
《類義》
→欺
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
帰一 イツニキス🔗⭐🔉
【帰一】
キイツ・イツニキス 一つに落ち着く。わかれているものが一つにまとまること。
害 いつか🔗⭐🔉
【害】
 10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ
10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ /カイ
/カイ 〈h
〈h i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
 ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
 ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
 ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
 {名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
 「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
 {副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
 会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ)
会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)
割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ
10画 宀部 [四年]
区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51
《常用音訓》ガイ
《音読み》 ガイ /カイ
/カイ 〈h
〈h i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
i〉
《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか
《意味》
 ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕
 ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」
 ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕
 {名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕
 「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。
 {副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕
《解字》
 会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ)
会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。
《単語家族》
轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)
割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
恩 いつくしむ🔗⭐🔉
【恩】
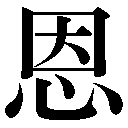 10画 心部 [五年]
区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6
《常用音訓》オン
《音読み》 オン
10画 心部 [五年]
区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6
《常用音訓》オン
《音読み》 オン
 〈
〈 n〉
《訓読み》 いつくしむ
《名付け》 おき・めぐみ
《意味》
n〉
《訓読み》 いつくしむ
《名付け》 おき・めぐみ
《意味》
 {名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕
{名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕
 {動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕
《解字》
会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕
《解字》
会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
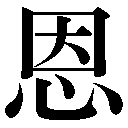 10画 心部 [五年]
区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6
《常用音訓》オン
《音読み》 オン
10画 心部 [五年]
区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6
《常用音訓》オン
《音読み》 オン
 〈
〈 n〉
《訓読み》 いつくしむ
《名付け》 おき・めぐみ
《意味》
n〉
《訓読み》 いつくしむ
《名付け》 おき・めぐみ
《意味》
 {名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕
{名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕
 {動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕
《解字》
会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕
《解字》
会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
慈 いつくしみ🔗⭐🔉
【慈】
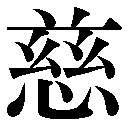 13画 心部 [常用漢字]
区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C
《常用音訓》ジ/いつく…しむ
《音読み》 ジ
13画 心部 [常用漢字]
区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C
《常用音訓》ジ/いつく…しむ
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈c
〈c 〉
《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ
《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ
《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし
《意味》
 {動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕
{動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕
 {動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕
{動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕
 {形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕
{形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕
 {名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕
{名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕
 {名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」
《解字》
会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。
《単語家族》
滋ジ(ふえる)
{名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」
《解字》
会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。
《単語家族》
滋ジ(ふえる) 孳ジ(子どもを育てる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
孳ジ(子どもを育てる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
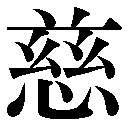 13画 心部 [常用漢字]
区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C
《常用音訓》ジ/いつく…しむ
《音読み》 ジ
13画 心部 [常用漢字]
区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C
《常用音訓》ジ/いつく…しむ
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈c
〈c 〉
《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ
《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ
《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし
《意味》
 {動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕
{動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕
 {動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕
{動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕
 {形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕
{形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕
 {名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕
{名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕
 {名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」
《解字》
会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。
《単語家族》
滋ジ(ふえる)
{名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」
《解字》
会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。
《単語家族》
滋ジ(ふえる) 孳ジ(子どもを育てる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
孳ジ(子どもを育てる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
曷 いつか🔗⭐🔉
【曷】
 9画 曰部
区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A
《音読み》 カツ
9画 曰部
区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A
《音読み》 カツ /ガチ
/ガチ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 なに/なんぞ/いつか
《意味》
〉
《訓読み》 なに/なんぞ/いつか
《意味》
 {副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕
{副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕
 {副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕
《解字》
{副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕
《解字》
 会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
 9画 曰部
区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A
《音読み》 カツ
9画 曰部
区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A
《音読み》 カツ /ガチ
/ガチ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 なに/なんぞ/いつか
《意味》
〉
《訓読み》 なに/なんぞ/いつか
《意味》
 {副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕
{副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕
 {副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕
《解字》
{副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕
《解字》
 会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
溢利 イツリ🔗⭐🔉
【溢利】
イツリ 余分の利益。
溢美 イツビ🔗⭐🔉
【溢美】
イツビ  非常に美しい。
非常に美しい。 ほめすぎること。
ほめすぎること。
 非常に美しい。
非常に美しい。 ほめすぎること。
ほめすぎること。
溢美溢悪 イツビイツアク🔗⭐🔉
【溢美溢悪】
イツビイツアク ほめすぎることと、けなしすぎること。▽「荘子」人間世篇の「両喜必多溢美之言、両怒必多溢悪之言=両喜ハカナラズ溢美ノ言多ク、両怒ハカナラズ溢悪ノ言多シ」から。
溢喜 イツキ🔗⭐🔉
【溢喜】
イツキ あふれるほどの喜び。
溢溢 イツイツ🔗⭐🔉
【溢溢】
イツイツ  みちあふれるさま。
みちあふれるさま。 鳥の鳴き声の形容。
鳥の鳴き声の形容。
 みちあふれるさま。
みちあふれるさま。 鳥の鳴き声の形容。
鳥の鳴き声の形容。
溢誉 イツヨ🔗⭐🔉
【溢誉】
イツヨ 過度の名誉。ほめすぎ。
逸才 イツサイ🔗⭐🔉
【逸才】
イツサイ『逸材イツザイ』通俗のわくをこえた才能。また、そのような才能のある人。〈同義語〉軼才。
逸文 イツブン🔗⭐🔉
【逸文】
イツブン  すぐれた文章。名文。
すぐれた文章。名文。 散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。
散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。 書き落とした文章。〈同義語〉佚文。
書き落とした文章。〈同義語〉佚文。
 すぐれた文章。名文。
すぐれた文章。名文。 散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。
散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。 書き落とした文章。〈同義語〉佚文。
書き落とした文章。〈同義語〉佚文。
逸言 イツゲン🔗⭐🔉
【逸言】
イツゲン  気らくなおしゃべり。
気らくなおしゃべり。 ルールをはずれた失言。
ルールをはずれた失言。
 気らくなおしゃべり。
気らくなおしゃべり。 ルールをはずれた失言。
ルールをはずれた失言。
逸労 イツロウ🔗⭐🔉
【逸労】
イツロウ すきかってにして楽しむことと、苦労すること。
逸事 イツジ🔗⭐🔉
【逸事】
イツジ  記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。
記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。 先人のすぐれた業績。
先人のすぐれた業績。
 記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。
記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。 先人のすぐれた業績。
先人のすぐれた業績。
逸美 イツビ🔗⭐🔉
【逸美】
イツビ 非常に美しい。
逸遊 イツユウ🔗⭐🔉
【逸遊】
イツユウ =逸游。かってきままに遊びくらす。〈同義語〉佚遊。
逸群 イツグン🔗⭐🔉
【逸群】
イツグン 普通の人からぬきんでてすぐれている。〈類義語〉抜群。
逸話 イツワ🔗⭐🔉
【逸話】
イツワ ある人物についての、一般には知られていない興味深い話。〈同義語〉佚話。
逸聞 イツブン🔗⭐🔉
【逸聞】
イツブン 世間に伝わっていない話。〈同義語〉佚聞・軼聞。
逸韻 イツイン🔗⭐🔉
【逸韻】
イツイン  世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。
世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。 韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。
韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。
 世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。
世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。 韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。
韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。
斎 いつき🔗⭐🔉
【斎】
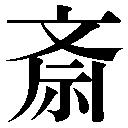 11画 齊部 [常用漢字]
区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6
【齋】旧字旧字
11画 齊部 [常用漢字]
区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6
【齋】旧字旧字
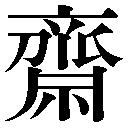 17画 齊部
区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ
17画 齊部
区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ /セ
/セ 〈zh
〈zh i〉
《訓読み》 とき/いつく/いつき
《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 とき/いつく/いつき
《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし
《意味》
 サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕
サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕 {名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」
{名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」 {名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」
{名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」 {名}とき。僧の食事。
〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。
《解字》
会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。
《単語家族》
齊(=斉。そろえる)
{名}とき。僧の食事。
〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。
《解字》
会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。
《単語家族》
齊(=斉。そろえる) 儕サイ(肩をそろえる仲間)
儕サイ(肩をそろえる仲間) 妻(夫とならぶつま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
妻(夫とならぶつま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
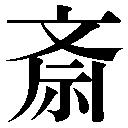 11画 齊部 [常用漢字]
区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6
【齋】旧字旧字
11画 齊部 [常用漢字]
区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6
【齋】旧字旧字
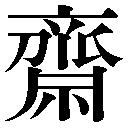 17画 齊部
区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ
17画 齊部
区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ /セ
/セ 〈zh
〈zh i〉
《訓読み》 とき/いつく/いつき
《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 とき/いつく/いつき
《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし
《意味》
 サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕
サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕 {名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」
{名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」 {名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」
{名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」 {名}とき。僧の食事。
〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。
《解字》
会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。
《単語家族》
齊(=斉。そろえる)
{名}とき。僧の食事。
〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。
《解字》
会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。
《単語家族》
齊(=斉。そろえる) 儕サイ(肩をそろえる仲間)
儕サイ(肩をそろえる仲間) 妻(夫とならぶつま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
妻(夫とならぶつま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
斎王 イツキノミコ🔗⭐🔉
【斎王】
サイオウ・イツキノミコ〔国〕昔、天皇即位のときに、伊勢イセ神宮および、京都の賀茂カモ神社に奉仕した、未婚の内親王、または皇女。斎宮と斎院。
漢字源に「いつ」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む