複数辞典一括検索+![]()
![]()
共己 オノレヲキョウス🔗⭐🔉
【共己】
キョウキ・オノレヲキョウス 自分の態度をうやうやしくする。「天子共己而已矣=天子ハ己ヲ共スルノミ」〔→荀子〕
利己 オノレヲリス🔗⭐🔉
【利己】
リコ・オノレヲリス 自分だけ利益を得ようとすること。自分本位であること。〈対語〉利他。「利己心」
各 おのおの🔗⭐🔉
【各】
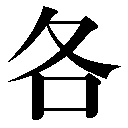 6画 口部 [四年]
区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65
《常用音訓》カク/おのおの
《音読み》 カク
6画 口部 [四年]
区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65
《常用音訓》カク/おのおの
《音読み》 カク
 〈g
〈g ・g
・g 〉
《訓読み》 おのおの
《名付け》 まさ
《意味》
〉
《訓読み》 おのおの
《名付け》 まさ
《意味》
 {指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
{指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
 {副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕
{副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕
 {動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」
《解字》
{動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」
《解字》
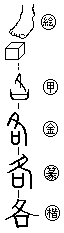 会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。
《単語家族》
格(つかえる枝→しん棒)
会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。
《単語家族》
格(つかえる枝→しん棒) 恪カク(かたい心)
恪カク(かたい心) 咯カク(のどがつかえる)
咯カク(のどがつかえる) 客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。
《類義》
毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。
《類義》
毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
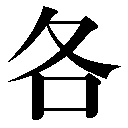 6画 口部 [四年]
区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65
《常用音訓》カク/おのおの
《音読み》 カク
6画 口部 [四年]
区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65
《常用音訓》カク/おのおの
《音読み》 カク
 〈g
〈g ・g
・g 〉
《訓読み》 おのおの
《名付け》 まさ
《意味》
〉
《訓読み》 おのおの
《名付け》 まさ
《意味》
 {指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
{指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
 {副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕
{副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕
 {動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」
《解字》
{動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」
《解字》
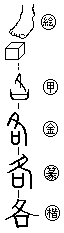 会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。
《単語家族》
格(つかえる枝→しん棒)
会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。
《単語家族》
格(つかえる枝→しん棒) 恪カク(かたい心)
恪カク(かたい心) 咯カク(のどがつかえる)
咯カク(のどがつかえる) 客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。
《類義》
毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。
《類義》
毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
小野妹子 オノノイモコ🔗⭐🔉
【小野妹子】
オノノイモコ〔日〕〈人名〉飛鳥アスカ時代の遣隋ズイ使。607・08年、聖徳太子の命で隋に渡った。
小野篁 オノノタカムラ🔗⭐🔉
【小野篁】
オノノタカムラ〔日〕〈人名〉802〜52 平安時代初期の学者・漢詩人・歌人。参議岑守ミネモリの子。『令義解リョウノギゲ』の編集に参加。遣唐副使に任ぜられたが、大使の藤原常嗣フジワラノツネツグと争い、渡航しなかったので、流罪となった。著に『野相公集』がある。
小野道風 オノノトウフウ🔗⭐🔉
【小野道風】
オノノトウフウ〔日〕〈人名〉894〜966 平安時代中期の書家。和様の基礎を築き、野蹟と呼ばれ、藤原佐理フジワラノサリ・行成コウゼイとともに三蹟とされる。
己 おのれ🔗⭐🔉
【己】
 3画 己部 [六年]
区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8
《常用音訓》キ/コ/おのれ
《音読み》 コ
3画 己部 [六年]
区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8
《常用音訓》キ/コ/おのれ
《音読み》 コ /キ
/キ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 おのれ/つちのと
《名付け》 おと・つちのと・な
《意味》
〉
《訓読み》 おのれ/つちのと
《名付け》 おと・つちのと・な
《意味》
 {名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕
{名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕
 {名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。
〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。
《解字》
{名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。
〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。
《解字》
 象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。
《単語家族》
起(はっとおきる)
象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。
《単語家族》
起(はっとおきる) 紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 3画 己部 [六年]
区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8
《常用音訓》キ/コ/おのれ
《音読み》 コ
3画 己部 [六年]
区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8
《常用音訓》キ/コ/おのれ
《音読み》 コ /キ
/キ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 おのれ/つちのと
《名付け》 おと・つちのと・な
《意味》
〉
《訓読み》 おのれ/つちのと
《名付け》 おと・つちのと・な
《意味》
 {名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕
{名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕
 {名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。
〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。
《解字》
{名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。
〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。
《解字》
 象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。
《単語家族》
起(はっとおきる)
象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。
《単語家族》
起(はっとおきる) 紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
行己 オノレヲオコナウ🔗⭐🔉
【行己】
オノレヲオコナウ 自分自身で行動する。「行己有恥=己ヲ行フニ恥有リ」〔→論語〕
克己復礼 オノレニカチテレイニカエル🔗⭐🔉
【克己復礼】
オノレニカチテレイニカエル〈故事〉自分のわがままにうち勝って、礼をふみ行う。〔→論語〕
虚己 オノレヲムナシクス🔗⭐🔉
【虚己】
オノレヲムナシクス 自分の考えを捨てて謙虚になる。
戚 おの🔗⭐🔉
【戚】
 11画 戈部
区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA
《音読み》 セキ
11画 戈部
区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA
《音読み》 セキ /シャク
/シャク 〈q
〈q 〉
《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり
《意味》
〉
《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり
《意味》
 {名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」
{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」
 {動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕
{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕
 {名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕
{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕
 {名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 戈部
区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA
《音読み》 セキ
11画 戈部
区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA
《音読み》 セキ /シャク
/シャク 〈q
〈q 〉
《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり
《意味》
〉
《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり
《意味》
 {名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」
{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」
 {動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕
{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕
 {名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕
{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕
 {名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
戦 おののく🔗⭐🔉
【戦】
 13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
 16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
 {動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
 {名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる)
{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる) 扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
 16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
 {動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
 {名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる)
{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる) 扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
斤 おの🔗⭐🔉
【斤】
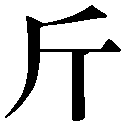 4画 斤部 [常用漢字]
区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2
《常用音訓》キン
《音読み》 キン
4画 斤部 [常用漢字]
区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2
《常用音訓》キン
《音読み》 キン /コン
/コン 〈j
〈j n〉
《訓読み》 おの(をの)
《名付け》 のり
《意味》
n〉
《訓読み》 おの(をの)
《名付け》 のり
《意味》
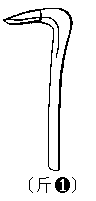
 {名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕
{名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕
 {単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。
{単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。
 「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。
〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。
《解字》
「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。
〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。
《解字》
 象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
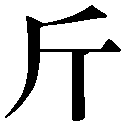 4画 斤部 [常用漢字]
区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2
《常用音訓》キン
《音読み》 キン
4画 斤部 [常用漢字]
区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2
《常用音訓》キン
《音読み》 キン /コン
/コン 〈j
〈j n〉
《訓読み》 おの(をの)
《名付け》 のり
《意味》
n〉
《訓読み》 おの(をの)
《名付け》 のり
《意味》
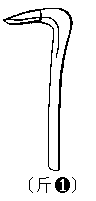
 {名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕
{名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕
 {単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。
{単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。
 「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。
〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。
《解字》
「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。
〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。
《解字》
 象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
斧 おの🔗⭐🔉
【斧】
 8画 斤部
区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580
《音読み》 フ
8画 斤部
区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 おの(をの)
《意味》
〉
《訓読み》 おの(をの)
《意味》
 {名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」
《解字》
会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。
《単語家族》
拍ハク(うつ)
{名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」
《解字》
会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。
《単語家族》
拍ハク(うつ) 搏ハク(うつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
搏ハク(うつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 斤部
区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580
《音読み》 フ
8画 斤部
区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 おの(をの)
《意味》
〉
《訓読み》 おの(をの)
《意味》
 {名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」
《解字》
会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。
《単語家族》
拍ハク(うつ)
{名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」
《解字》
会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。
《単語家族》
拍ハク(うつ) 搏ハク(うつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
搏ハク(うつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
自 おのずから🔗⭐🔉
【自】
 6画 自部 [二年]
区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9
《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら
《音読み》 ジ
6画 自部 [二年]
区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9
《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈z
〈z 〉
《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より
《名付け》 おの・これ・さだ・より
《意味》
〉
《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より
《名付け》 おの・これ・さだ・より
《意味》
 {副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」
{副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」
 {副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕
{副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕
 {副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕
{副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕
 {前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕
《解字》
{前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕
《解字》
 象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。
《類義》
親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。
《類義》
親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 自部 [二年]
区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9
《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら
《音読み》 ジ
6画 自部 [二年]
区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9
《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈z
〈z 〉
《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より
《名付け》 おの・これ・さだ・より
《意味》
〉
《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より
《名付け》 おの・これ・さだ・より
《意味》
 {副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」
{副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」
 {副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕
{副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕
 {副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕
{副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕
 {前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕
《解字》
{前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕
《解字》
 象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。
《類義》
親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。
《類義》
親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
虚己 オノレヲムナシクス🔗⭐🔉
【虚己】
キョキ・オノレヲムナシクス 私心・欲望をなくする。「人能虚己以遊世、其孰能害之=人ヨク己ヲ虚シクシテモッテ世ニ遊ベバ、ソレタレカヨクコレヲ害セン」〔→荘子〕
漢字源に「おの」で始まるの検索結果 1-19。
 自分の行いを慎むこと。「恭己正南面而已矣=己ヲ恭シクシテ正シク南面スルノミ」〔
自分の行いを慎むこと。「恭己正南面而已矣=己ヲ恭シクシテ正シク南面スルノミ」〔 天子がうやうやしく位についているだけで、実権を臣下に奪われていること。〔
天子がうやうやしく位についているだけで、実権を臣下に奪われていること。〔