複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (93)
かた【片】🔗⭐🔉
かた【片】
①揃えば対ついとなるものの一方。万葉集8「天飛ぶや領巾ひれ―敷き真玉手の玉手さしかへ」。万葉集11「磯貝の―恋のみに年は経につつ」。「―手」
②整わないこと。不完全。万葉集9「八年児やとせごの―生おいの時ゆ」。「―こと」
③わずか。竹取物語「―時の間ま」
④一方に偏し、中心部から離れていること。神代紀下「石川―淵、―淵に網張り渡し」。伊勢物語「―ゐなかに住みけり」。「―端」「―よる」
⇒片が付く
かた‐いお【片庵】‥イホ🔗⭐🔉
かた‐いお【片庵】‥イホ
粗末な家。自分の家の謙譲語。宇津保物語藤原君「おきなの―にゐてまして」
かた‐いじ【片意地】‥ヂ🔗⭐🔉
かた‐いじ【片意地】‥ヂ
頑固に自分の考えを立てとおすこと。また、その性質。「―を張る」
かた‐いっぽう【片一方】‥パウ🔗⭐🔉
かた‐いっぽう【片一方】‥パウ
二つの中の一方。片方。かたっぽ。
かた‐うた【片歌】🔗⭐🔉
かた‐うた【片歌】
雅楽寮で教習した大歌の一体。五・七・七または五・七・五の3句で1首をなす歌で、奈良時代以前には、多くは問答に用いた。江戸時代、建部綾足は俳諧の一体として、片歌の復興を志した。
かた‐おか【片岡】‥ヲカ🔗⭐🔉
かた‐おか【片岡】‥ヲカ
一方が切り立っている岡。また、孤立した岡。万葉集7「―の此の向つ峯おに」
かたおか【片岡】‥ヲカ(地名)🔗⭐🔉
かたおか【片岡】‥ヲカ
奈良県北葛城郡王寺町辺。片岡坐かたおかにます神社は式内社。(歌枕)
かたおか‐けんきち【片岡健吉】‥ヲカ‥🔗⭐🔉
かたおか‐けんきち【片岡健吉】‥ヲカ‥
政治家。土佐藩士。立志社を創設し、民撰議院設立建白に加わるなど自由民権運動の指導者。自由党・政友会の領袖。衆議院議長。(1843〜1903)
⇒かたおか【片岡】
かたおか‐ちえぞう【片岡千恵蔵】‥ヲカ‥ヱザウ🔗⭐🔉
かたおか‐ちえぞう【片岡千恵蔵】‥ヲカ‥ヱザウ
俳優。本名、植木正義。群馬県生れ。歌舞伎から映画界に転じ、「赤西蠣太」「国士無双」など時代劇の花形として活躍。第二次大戦後も「血槍富士」などに出演。(1903〜1983)
⇒かたおか【片岡】
かたおか‐てっぺい【片岡鉄兵】‥ヲカ‥🔗⭐🔉
かたおか‐てっぺい【片岡鉄兵】‥ヲカ‥
小説家。岡山県生れ。慶大中退。新感覚派からプロレタリア文学に転向、のち仏門に帰依した。作「綾里村快挙録」「花嫁学校」など。(1894〜1944)
⇒かたおか【片岡】
かたおか‐にざえもん【片岡仁左衛門】‥ヲカ‥ヱ‥🔗⭐🔉
かたおか‐にざえもん【片岡仁左衛門】‥ヲカ‥ヱ‥
歌舞伎俳優。京都の人。屋号、7代以降松島屋。
①(初代)実悪じつあくに長じた。(1656〜1715)
②(7代)化政期京坂劇壇の重鎮。名跡を再興。(1755〜1837)
③(11代)8代の4男。大阪で初代中村鴈治郎と対抗して活躍。(1857〜1934)
④(12代)10代の甥・養子。15代市村羽左衛門の女房役として活躍。(1882〜1946)
⑤(13代)11代の3男。長く関西歌舞伎を支える。当り役は由良之助・菅丞相・忠兵衛など。(1903〜1994)
⇒かたおか【片岡】
かた‐おさえ【片押え】‥オサヘ🔗⭐🔉
かた‐おさえ【片押え】‥オサヘ
江戸時代、大名行列で中間ちゅうげん・小者などを支配する足軽が片側に一人だけつくもの。二人つく両押えに対していう。
かた‐おし【片押し】🔗⭐🔉
かた‐おし【片押し】
一方に片寄ること。片方だけに負担をかけたりすること。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「ほんに意地の悪い天道様、コウ―に照つたり降つたりするのが」
かた‐おろし【片下ろし】🔗⭐🔉
かた‐おろし【片下ろし】
①上代の歌謡などで、本・末の両方に分かれて歌う場合に、その一方を調子を下げて低く歌うもの。古事記下「この歌は夷振ひなぶりの―なり」
②片下ろし1の歌い方で歌う平安時代の歌謡の一種。
かた‐がい【片貝】‥ガヒ🔗⭐🔉
かた‐がい【片貝】‥ガヒ
アワビのように、貝殻が一方だけの貝。
かた‐かお【片顔】‥カホ🔗⭐🔉
かた‐かお【片顔】‥カホ
顔の半面。かためん。
⇒かたかお‐なし【片顔無し】
かたかお‐なし【片顔無し】‥カホ‥🔗⭐🔉
かたかお‐なし【片顔無し】‥カホ‥
心が一徹で他方を顧みないこと。また、その人。源平盛衰記12「入道はさる―の人にて」
⇒かた‐かお【片顔】
かた‐か・く【片掛く】🔗⭐🔉
かた‐か・く【片掛く】
〔他下二〕
①片方を掛ける。ちょっと掛ける。よせかける。源氏物語手習「山に―・けたる家なれば」
②(自動詞的に)たよる。すがる。源氏物語松風「かの殿の御蔭に―・けてと思ふことありて」
かた‐かく・る【片隠る】🔗⭐🔉
かた‐かく・る【片隠る】
〔自下二〕
片方が隠れる。少し隠れる。続後撰和歌集恋「谷深み岩―・れ行く水のかげばかり見て袖濡らせとや」
かた‐かけ【片掛け】🔗⭐🔉
かた‐かけ【片掛け】
①片方をかけること。ちょっとかけること。
②船に片帆をかけること。大和物語「―の船にや乗れる」
⇒かたかけ‐おぶね【片掛け小舟】
かた‐かげ【片陰】🔗⭐🔉
かた‐かげ【片陰】
①一方が物の陰になっている所。
②日光のあたらない所。特に、夏の午後のひかげ。〈[季]夏〉
かたかけ‐おぶね【片掛け小舟】‥ヲ‥🔗⭐🔉
かたかけ‐おぶね【片掛け小舟】‥ヲ‥
片帆をかけた小さい舟。古今和歌集六帖3「塩瀬こぐ―流るとも」
⇒かた‐かけ【片掛け】
かた‐かずら【片葛】‥カヅラ🔗⭐🔉
かた‐かずら【片葛】‥カヅラ
「諸葛もろかずら」参照。
○片が付くかたがつく🔗⭐🔉
○片が付くかたがつく
物事が処理される。始末がつく。梅暦「おいらんのお身の上も、どうか手軽く方が付きませう」
⇒かた【片】
かた‐がっしょう【片合掌】‥シヤウ
片手でする合掌。
かた‐かど【片才】
少しの才能。一つの才芸。源氏物語帚木「その―もなき人はあらむやと」
かた‐かど【片角】
①一方のかど。ひとかど。
②少しの量。
かた‐かな【片仮名】
(「片」は一部分の意)仮名文字の一つ。阿→ア、伊→イ、宇→ウ、久→ク、己→コのように漢字の一部を取って作ったもの。平安初期、漢文訓点に使って様々の字体があったが、院政時代にほぼ現行に近い形になった。現在では主に外来語や擬音語などの表記に用いる。かたかんな。↔平仮名。→仮名。
⇒かたかな‐ご【片仮名語】
かたかな‐ご【片仮名語】
ふつう片仮名で表記する、主に欧米から入ってきた外来語。日本で外来語を模してつくられた語にもいう。
⇒かた‐かな【片仮名】
かた‐かま【片釜】
竈かまどに二つ並べて据えた釜の、その一つ。
かた‐かま【片鎌】
①鎌槍の一方の枝。
②片鎌槍の略。浄瑠璃、堀川波鼓「素鑓―十文字」
⇒かたかま‐やり【片鎌槍】
かたかま‐やり【片鎌槍】
槍の身の片方に鎌状の枝のあるもの。鎌槍の片方だけを加えたもの。片鎌。
片鎌槍
 ⇒かた‐かま【片鎌】
かたがみ【片上】
姓氏の一つ。
⇒かたがみ‐のぶる【片上伸】
かた‐がみ【型紙】
①模様を彫り抜いた厚紙。布帛ふはくにあてて模様を捺染なっせんするのに用いる。型付紙。
②洋裁や手芸などで、作ろうとするものの形を製図して切った紙。これを布などにあてて裁断する。「―を取る」
かたがみ【潟上】
秋田県西部、八郎潟・日本海に臨む市。南接する秋田市のベッドタウン化が進む。人口3万6千。
かたがみ‐のぶる【片上伸】
評論家・ロシア文学者。号、天弦。愛媛県生れ。早大卒、同教授。自然主義・理想主義を経て、文学の社会性を強調。著「文学評論」など。(1884〜1928)
⇒かたがみ【片上】
かた‐がゆ【固粥】
固く煮た粥。現在の普通の飯。〈倭名類聚鈔16〉↔汁粥
かた‐ガラス【片硝子】
懐中時計の、外蓋の一方にガラスをはめたもの。両蓋に対していう。
カタカリ【kathakali】
南インド西海岸、ケーララ地方の古典舞踊劇。隈取りをし、大きなスカート様の衣装をつけ、演劇的要素の濃い舞踊。
かたが・る【傾がる】
〔自五〕
かたむく。
かた‐かわ【片皮】‥カハ
行縢むかばきの、片方の足を入れる方。古今著聞集16「むかばき…―に左右の足を入れて」
かた‐がわ【片側】‥ガハ
一方のかわ。かたほう。「―通行止め」
⇒かたがわ‐まち【片側町】
⇒かたがわ‐やぶり【片側破り】
かた‐がわせ【片為替】‥ガハセ
銀行で売為替か買為替かの一方の額が他方を超過して、いずれかにかたよっている状態。
かたがわ‐まち【片側町】‥ガハ‥
道の片側だけ家の建ち並んだ町。片町。片通り。
⇒かた‐がわ【片側】
かたがわ‐やぶり【片側破り】‥ガハ‥
理非・善悪もかまわずに押し通そうとする性質。また、その人。よこがみやぶり。保元物語「―の猪武者」
⇒かた‐がわ【片側】
かた‐がわり【肩代り】‥ガハリ
①駕籠かごなどを舁かく者が交代すること。また、その代りの者。転じて、他人の負債・負担を代わって引き受けること。
②取引相場で、他人の建玉たてぎょくをその人に代わって引き受けること。
かた‐かんな【片仮名】
(カンナはカリナの転)(→)「かたかな」に同じ。宇津保物語蔵開中「一つには―一つは葦手」
かたき【敵】
①相手。競争相手。源氏物語宿木「碁盤召し出でて、御碁の―に召し寄す」。「商売―」
②戦争の相手。てき。平家物語5「げにもまことに野も山も海も河もみな―でありけり」
③(「仇」とも書く)恨みのある相手。あだ。仇敵きゅうてき。枕草子49「愛敬あいぎょうおくれたる人などは、あいなく―にして」。「親の―」
④配偶者。むこ。よめ。宇津保物語藤原君「―を得むずるやうは、比叡の中堂に常灯を奉り給へ」
⇒かたき‐うち【敵討】
⇒かたきうち‐もの【敵討物】
⇒かたき‐どうし【敵同士】
⇒かたき‐もち【敵持ち】
⇒かたき‐やく【敵役】
かたき【難き】
(カタシの連体形)むずかしいこと。たやすくないこと。「―を先にして獲うるを後にす」↔易やすき
かた‐き【片食】
カタケの転。「一ひと―」
かた‐ぎ【気質】
(「形木かたぎ」から転じて)
①物事のやり方。慣習。ならわし。天草本伊曾保物語「あるほどの宝を奉らるる―がござつた」
②顔やからだの様子。また、性質や気だて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「万人にも憎まれぬいとしらしい―」
③(「形気」「容気」「形儀」とも書く)身分・職業・年齢などに相応した特有の類型的な気風。日本永代蔵6「利発なる小判を長櫃の底に入れ置き、年久しく世間を見せ給はぬは商人の―にあらず」。「職人―」「昔―」
⇒かたぎ‐もの【気質物】
かた‐ぎ【形木・模】
①物の形を彫り刻んだ板。その形を布や紙にすって染め付けるのに用いる。枕草子90「いみじうやうじたる白き衣、―のかたは絵にかきたり」
②版木はんぎ。摺すり形木。
③(→)型板かたいた1の古称。
④一定の型。定型。規範。きまり。風姿花伝「格別の事なれば定めて稽古すべき―もなし」
かた‐ぎ【堅木】
①堅固な材木。カシ・クヌギ・ナラ・ケヤキのような薪炭とする木の称。宇津保物語貴宮「一尺三寸ばかりの―の盌もいに」
②(→)アカガシの異称。
かた‐ぎ【堅気】
①もの堅い性質。律儀りちぎ。
②まじめな職業。主に芸娼妓・ばくちうちなどに対していう。「―になる」
かたき‐うち【敵討】
①主君・近親・朋友などの仇あだを討ち果たすこと。江戸時代に最も多かった。仇討。復讐ふくしゅう。
②転じて一般に、恥辱をすすぐことをもいう。「このあいだの―だ」
⇒かたき【敵】
かたきうち‐もの【敵討物】
敵討を主題とした小説・浄瑠璃・脚本・講談などの称。仇討物。
⇒かたき【敵】
かた‐ぎき【片聞き】
一方の言い分だけを聞くこと。
⇒かた‐かま【片鎌】
かたがみ【片上】
姓氏の一つ。
⇒かたがみ‐のぶる【片上伸】
かた‐がみ【型紙】
①模様を彫り抜いた厚紙。布帛ふはくにあてて模様を捺染なっせんするのに用いる。型付紙。
②洋裁や手芸などで、作ろうとするものの形を製図して切った紙。これを布などにあてて裁断する。「―を取る」
かたがみ【潟上】
秋田県西部、八郎潟・日本海に臨む市。南接する秋田市のベッドタウン化が進む。人口3万6千。
かたがみ‐のぶる【片上伸】
評論家・ロシア文学者。号、天弦。愛媛県生れ。早大卒、同教授。自然主義・理想主義を経て、文学の社会性を強調。著「文学評論」など。(1884〜1928)
⇒かたがみ【片上】
かた‐がゆ【固粥】
固く煮た粥。現在の普通の飯。〈倭名類聚鈔16〉↔汁粥
かた‐ガラス【片硝子】
懐中時計の、外蓋の一方にガラスをはめたもの。両蓋に対していう。
カタカリ【kathakali】
南インド西海岸、ケーララ地方の古典舞踊劇。隈取りをし、大きなスカート様の衣装をつけ、演劇的要素の濃い舞踊。
かたが・る【傾がる】
〔自五〕
かたむく。
かた‐かわ【片皮】‥カハ
行縢むかばきの、片方の足を入れる方。古今著聞集16「むかばき…―に左右の足を入れて」
かた‐がわ【片側】‥ガハ
一方のかわ。かたほう。「―通行止め」
⇒かたがわ‐まち【片側町】
⇒かたがわ‐やぶり【片側破り】
かた‐がわせ【片為替】‥ガハセ
銀行で売為替か買為替かの一方の額が他方を超過して、いずれかにかたよっている状態。
かたがわ‐まち【片側町】‥ガハ‥
道の片側だけ家の建ち並んだ町。片町。片通り。
⇒かた‐がわ【片側】
かたがわ‐やぶり【片側破り】‥ガハ‥
理非・善悪もかまわずに押し通そうとする性質。また、その人。よこがみやぶり。保元物語「―の猪武者」
⇒かた‐がわ【片側】
かた‐がわり【肩代り】‥ガハリ
①駕籠かごなどを舁かく者が交代すること。また、その代りの者。転じて、他人の負債・負担を代わって引き受けること。
②取引相場で、他人の建玉たてぎょくをその人に代わって引き受けること。
かた‐かんな【片仮名】
(カンナはカリナの転)(→)「かたかな」に同じ。宇津保物語蔵開中「一つには―一つは葦手」
かたき【敵】
①相手。競争相手。源氏物語宿木「碁盤召し出でて、御碁の―に召し寄す」。「商売―」
②戦争の相手。てき。平家物語5「げにもまことに野も山も海も河もみな―でありけり」
③(「仇」とも書く)恨みのある相手。あだ。仇敵きゅうてき。枕草子49「愛敬あいぎょうおくれたる人などは、あいなく―にして」。「親の―」
④配偶者。むこ。よめ。宇津保物語藤原君「―を得むずるやうは、比叡の中堂に常灯を奉り給へ」
⇒かたき‐うち【敵討】
⇒かたきうち‐もの【敵討物】
⇒かたき‐どうし【敵同士】
⇒かたき‐もち【敵持ち】
⇒かたき‐やく【敵役】
かたき【難き】
(カタシの連体形)むずかしいこと。たやすくないこと。「―を先にして獲うるを後にす」↔易やすき
かた‐き【片食】
カタケの転。「一ひと―」
かた‐ぎ【気質】
(「形木かたぎ」から転じて)
①物事のやり方。慣習。ならわし。天草本伊曾保物語「あるほどの宝を奉らるる―がござつた」
②顔やからだの様子。また、性質や気だて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「万人にも憎まれぬいとしらしい―」
③(「形気」「容気」「形儀」とも書く)身分・職業・年齢などに相応した特有の類型的な気風。日本永代蔵6「利発なる小判を長櫃の底に入れ置き、年久しく世間を見せ給はぬは商人の―にあらず」。「職人―」「昔―」
⇒かたぎ‐もの【気質物】
かた‐ぎ【形木・模】
①物の形を彫り刻んだ板。その形を布や紙にすって染め付けるのに用いる。枕草子90「いみじうやうじたる白き衣、―のかたは絵にかきたり」
②版木はんぎ。摺すり形木。
③(→)型板かたいた1の古称。
④一定の型。定型。規範。きまり。風姿花伝「格別の事なれば定めて稽古すべき―もなし」
かた‐ぎ【堅木】
①堅固な材木。カシ・クヌギ・ナラ・ケヤキのような薪炭とする木の称。宇津保物語貴宮「一尺三寸ばかりの―の盌もいに」
②(→)アカガシの異称。
かた‐ぎ【堅気】
①もの堅い性質。律儀りちぎ。
②まじめな職業。主に芸娼妓・ばくちうちなどに対していう。「―になる」
かたき‐うち【敵討】
①主君・近親・朋友などの仇あだを討ち果たすこと。江戸時代に最も多かった。仇討。復讐ふくしゅう。
②転じて一般に、恥辱をすすぐことをもいう。「このあいだの―だ」
⇒かたき【敵】
かたきうち‐もの【敵討物】
敵討を主題とした小説・浄瑠璃・脚本・講談などの称。仇討物。
⇒かたき【敵】
かた‐ぎき【片聞き】
一方の言い分だけを聞くこと。
 ⇒かた‐かま【片鎌】
かたがみ【片上】
姓氏の一つ。
⇒かたがみ‐のぶる【片上伸】
かた‐がみ【型紙】
①模様を彫り抜いた厚紙。布帛ふはくにあてて模様を捺染なっせんするのに用いる。型付紙。
②洋裁や手芸などで、作ろうとするものの形を製図して切った紙。これを布などにあてて裁断する。「―を取る」
かたがみ【潟上】
秋田県西部、八郎潟・日本海に臨む市。南接する秋田市のベッドタウン化が進む。人口3万6千。
かたがみ‐のぶる【片上伸】
評論家・ロシア文学者。号、天弦。愛媛県生れ。早大卒、同教授。自然主義・理想主義を経て、文学の社会性を強調。著「文学評論」など。(1884〜1928)
⇒かたがみ【片上】
かた‐がゆ【固粥】
固く煮た粥。現在の普通の飯。〈倭名類聚鈔16〉↔汁粥
かた‐ガラス【片硝子】
懐中時計の、外蓋の一方にガラスをはめたもの。両蓋に対していう。
カタカリ【kathakali】
南インド西海岸、ケーララ地方の古典舞踊劇。隈取りをし、大きなスカート様の衣装をつけ、演劇的要素の濃い舞踊。
かたが・る【傾がる】
〔自五〕
かたむく。
かた‐かわ【片皮】‥カハ
行縢むかばきの、片方の足を入れる方。古今著聞集16「むかばき…―に左右の足を入れて」
かた‐がわ【片側】‥ガハ
一方のかわ。かたほう。「―通行止め」
⇒かたがわ‐まち【片側町】
⇒かたがわ‐やぶり【片側破り】
かた‐がわせ【片為替】‥ガハセ
銀行で売為替か買為替かの一方の額が他方を超過して、いずれかにかたよっている状態。
かたがわ‐まち【片側町】‥ガハ‥
道の片側だけ家の建ち並んだ町。片町。片通り。
⇒かた‐がわ【片側】
かたがわ‐やぶり【片側破り】‥ガハ‥
理非・善悪もかまわずに押し通そうとする性質。また、その人。よこがみやぶり。保元物語「―の猪武者」
⇒かた‐がわ【片側】
かた‐がわり【肩代り】‥ガハリ
①駕籠かごなどを舁かく者が交代すること。また、その代りの者。転じて、他人の負債・負担を代わって引き受けること。
②取引相場で、他人の建玉たてぎょくをその人に代わって引き受けること。
かた‐かんな【片仮名】
(カンナはカリナの転)(→)「かたかな」に同じ。宇津保物語蔵開中「一つには―一つは葦手」
かたき【敵】
①相手。競争相手。源氏物語宿木「碁盤召し出でて、御碁の―に召し寄す」。「商売―」
②戦争の相手。てき。平家物語5「げにもまことに野も山も海も河もみな―でありけり」
③(「仇」とも書く)恨みのある相手。あだ。仇敵きゅうてき。枕草子49「愛敬あいぎょうおくれたる人などは、あいなく―にして」。「親の―」
④配偶者。むこ。よめ。宇津保物語藤原君「―を得むずるやうは、比叡の中堂に常灯を奉り給へ」
⇒かたき‐うち【敵討】
⇒かたきうち‐もの【敵討物】
⇒かたき‐どうし【敵同士】
⇒かたき‐もち【敵持ち】
⇒かたき‐やく【敵役】
かたき【難き】
(カタシの連体形)むずかしいこと。たやすくないこと。「―を先にして獲うるを後にす」↔易やすき
かた‐き【片食】
カタケの転。「一ひと―」
かた‐ぎ【気質】
(「形木かたぎ」から転じて)
①物事のやり方。慣習。ならわし。天草本伊曾保物語「あるほどの宝を奉らるる―がござつた」
②顔やからだの様子。また、性質や気だて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「万人にも憎まれぬいとしらしい―」
③(「形気」「容気」「形儀」とも書く)身分・職業・年齢などに相応した特有の類型的な気風。日本永代蔵6「利発なる小判を長櫃の底に入れ置き、年久しく世間を見せ給はぬは商人の―にあらず」。「職人―」「昔―」
⇒かたぎ‐もの【気質物】
かた‐ぎ【形木・模】
①物の形を彫り刻んだ板。その形を布や紙にすって染め付けるのに用いる。枕草子90「いみじうやうじたる白き衣、―のかたは絵にかきたり」
②版木はんぎ。摺すり形木。
③(→)型板かたいた1の古称。
④一定の型。定型。規範。きまり。風姿花伝「格別の事なれば定めて稽古すべき―もなし」
かた‐ぎ【堅木】
①堅固な材木。カシ・クヌギ・ナラ・ケヤキのような薪炭とする木の称。宇津保物語貴宮「一尺三寸ばかりの―の盌もいに」
②(→)アカガシの異称。
かた‐ぎ【堅気】
①もの堅い性質。律儀りちぎ。
②まじめな職業。主に芸娼妓・ばくちうちなどに対していう。「―になる」
かたき‐うち【敵討】
①主君・近親・朋友などの仇あだを討ち果たすこと。江戸時代に最も多かった。仇討。復讐ふくしゅう。
②転じて一般に、恥辱をすすぐことをもいう。「このあいだの―だ」
⇒かたき【敵】
かたきうち‐もの【敵討物】
敵討を主題とした小説・浄瑠璃・脚本・講談などの称。仇討物。
⇒かたき【敵】
かた‐ぎき【片聞き】
一方の言い分だけを聞くこと。
⇒かた‐かま【片鎌】
かたがみ【片上】
姓氏の一つ。
⇒かたがみ‐のぶる【片上伸】
かた‐がみ【型紙】
①模様を彫り抜いた厚紙。布帛ふはくにあてて模様を捺染なっせんするのに用いる。型付紙。
②洋裁や手芸などで、作ろうとするものの形を製図して切った紙。これを布などにあてて裁断する。「―を取る」
かたがみ【潟上】
秋田県西部、八郎潟・日本海に臨む市。南接する秋田市のベッドタウン化が進む。人口3万6千。
かたがみ‐のぶる【片上伸】
評論家・ロシア文学者。号、天弦。愛媛県生れ。早大卒、同教授。自然主義・理想主義を経て、文学の社会性を強調。著「文学評論」など。(1884〜1928)
⇒かたがみ【片上】
かた‐がゆ【固粥】
固く煮た粥。現在の普通の飯。〈倭名類聚鈔16〉↔汁粥
かた‐ガラス【片硝子】
懐中時計の、外蓋の一方にガラスをはめたもの。両蓋に対していう。
カタカリ【kathakali】
南インド西海岸、ケーララ地方の古典舞踊劇。隈取りをし、大きなスカート様の衣装をつけ、演劇的要素の濃い舞踊。
かたが・る【傾がる】
〔自五〕
かたむく。
かた‐かわ【片皮】‥カハ
行縢むかばきの、片方の足を入れる方。古今著聞集16「むかばき…―に左右の足を入れて」
かた‐がわ【片側】‥ガハ
一方のかわ。かたほう。「―通行止め」
⇒かたがわ‐まち【片側町】
⇒かたがわ‐やぶり【片側破り】
かた‐がわせ【片為替】‥ガハセ
銀行で売為替か買為替かの一方の額が他方を超過して、いずれかにかたよっている状態。
かたがわ‐まち【片側町】‥ガハ‥
道の片側だけ家の建ち並んだ町。片町。片通り。
⇒かた‐がわ【片側】
かたがわ‐やぶり【片側破り】‥ガハ‥
理非・善悪もかまわずに押し通そうとする性質。また、その人。よこがみやぶり。保元物語「―の猪武者」
⇒かた‐がわ【片側】
かた‐がわり【肩代り】‥ガハリ
①駕籠かごなどを舁かく者が交代すること。また、その代りの者。転じて、他人の負債・負担を代わって引き受けること。
②取引相場で、他人の建玉たてぎょくをその人に代わって引き受けること。
かた‐かんな【片仮名】
(カンナはカリナの転)(→)「かたかな」に同じ。宇津保物語蔵開中「一つには―一つは葦手」
かたき【敵】
①相手。競争相手。源氏物語宿木「碁盤召し出でて、御碁の―に召し寄す」。「商売―」
②戦争の相手。てき。平家物語5「げにもまことに野も山も海も河もみな―でありけり」
③(「仇」とも書く)恨みのある相手。あだ。仇敵きゅうてき。枕草子49「愛敬あいぎょうおくれたる人などは、あいなく―にして」。「親の―」
④配偶者。むこ。よめ。宇津保物語藤原君「―を得むずるやうは、比叡の中堂に常灯を奉り給へ」
⇒かたき‐うち【敵討】
⇒かたきうち‐もの【敵討物】
⇒かたき‐どうし【敵同士】
⇒かたき‐もち【敵持ち】
⇒かたき‐やく【敵役】
かたき【難き】
(カタシの連体形)むずかしいこと。たやすくないこと。「―を先にして獲うるを後にす」↔易やすき
かた‐き【片食】
カタケの転。「一ひと―」
かた‐ぎ【気質】
(「形木かたぎ」から転じて)
①物事のやり方。慣習。ならわし。天草本伊曾保物語「あるほどの宝を奉らるる―がござつた」
②顔やからだの様子。また、性質や気だて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「万人にも憎まれぬいとしらしい―」
③(「形気」「容気」「形儀」とも書く)身分・職業・年齢などに相応した特有の類型的な気風。日本永代蔵6「利発なる小判を長櫃の底に入れ置き、年久しく世間を見せ給はぬは商人の―にあらず」。「職人―」「昔―」
⇒かたぎ‐もの【気質物】
かた‐ぎ【形木・模】
①物の形を彫り刻んだ板。その形を布や紙にすって染め付けるのに用いる。枕草子90「いみじうやうじたる白き衣、―のかたは絵にかきたり」
②版木はんぎ。摺すり形木。
③(→)型板かたいた1の古称。
④一定の型。定型。規範。きまり。風姿花伝「格別の事なれば定めて稽古すべき―もなし」
かた‐ぎ【堅木】
①堅固な材木。カシ・クヌギ・ナラ・ケヤキのような薪炭とする木の称。宇津保物語貴宮「一尺三寸ばかりの―の盌もいに」
②(→)アカガシの異称。
かた‐ぎ【堅気】
①もの堅い性質。律儀りちぎ。
②まじめな職業。主に芸娼妓・ばくちうちなどに対していう。「―になる」
かたき‐うち【敵討】
①主君・近親・朋友などの仇あだを討ち果たすこと。江戸時代に最も多かった。仇討。復讐ふくしゅう。
②転じて一般に、恥辱をすすぐことをもいう。「このあいだの―だ」
⇒かたき【敵】
かたきうち‐もの【敵討物】
敵討を主題とした小説・浄瑠璃・脚本・講談などの称。仇討物。
⇒かたき【敵】
かた‐ぎき【片聞き】
一方の言い分だけを聞くこと。
かた‐かど【片角】🔗⭐🔉
かた‐かど【片角】
①一方のかど。ひとかど。
②少しの量。
かた‐かな【片仮名】🔗⭐🔉
かた‐かな【片仮名】
(「片」は一部分の意)仮名文字の一つ。阿→ア、伊→イ、宇→ウ、久→ク、己→コのように漢字の一部を取って作ったもの。平安初期、漢文訓点に使って様々の字体があったが、院政時代にほぼ現行に近い形になった。現在では主に外来語や擬音語などの表記に用いる。かたかんな。↔平仮名。→仮名。
⇒かたかな‐ご【片仮名語】
かたかな‐ご【片仮名語】🔗⭐🔉
かたかな‐ご【片仮名語】
ふつう片仮名で表記する、主に欧米から入ってきた外来語。日本で外来語を模してつくられた語にもいう。
⇒かた‐かな【片仮名】
かた‐かま【片釜】🔗⭐🔉
かた‐かま【片釜】
竈かまどに二つ並べて据えた釜の、その一つ。
かた‐かま【片鎌】🔗⭐🔉
かた‐かま【片鎌】
①鎌槍の一方の枝。
②片鎌槍の略。浄瑠璃、堀川波鼓「素鑓―十文字」
⇒かたかま‐やり【片鎌槍】
かたかま‐やり【片鎌槍】🔗⭐🔉
かたかま‐やり【片鎌槍】
槍の身の片方に鎌状の枝のあるもの。鎌槍の片方だけを加えたもの。片鎌。
片鎌槍
 ⇒かた‐かま【片鎌】
⇒かた‐かま【片鎌】
 ⇒かた‐かま【片鎌】
⇒かた‐かま【片鎌】
かた‐がわせ【片為替】‥ガハセ🔗⭐🔉
かた‐がわせ【片為替】‥ガハセ
銀行で売為替か買為替かの一方の額が他方を超過して、いずれかにかたよっている状態。
かた‐かんな【片仮名】🔗⭐🔉
かた‐かんな【片仮名】
(カンナはカリナの転)(→)「かたかな」に同じ。宇津保物語蔵開中「一つには―一つは葦手」
かた‐きし【片岸】🔗⭐🔉
かた‐きし【片岸】
(カタギシとも)
①片方の岸。
②となり合せの場所。蜻蛉日記上「われは左近の馬場を―にしたれば」
③片一方が崖がけになっている所。断崖。栄華物語衣珠「山の嶺・谷の底と見上げ見下ろし給ふに、…―のくづれなどいと盛りにおもしろし」
かたぎり【片桐】🔗⭐🔉
かたぎり【片桐】
姓氏の一つ。
⇒かたぎり‐かつもと【片桐且元】
⇒かたぎり‐せきしゅう【片桐石州】
かたぎり‐かつもと【片桐且元】🔗⭐🔉
かたぎり‐かつもと【片桐且元】
安土桃山時代の武将。近江の人。豊臣秀吉に仕え、市正いちのかみと称。賤ヶ岳しずがたけ七本槍の一人。秀吉の没後、秀頼の後見となる。大坂落城後まもなく病没。(1556〜1615)
⇒かたぎり【片桐】
かたぎり‐せきしゅう【片桐石州】‥シウ🔗⭐🔉
かたぎり‐せきしゅう【片桐石州】‥シウ
江戸前期、石州流茶道の祖。名は貞昌。石見守。大和小泉城主。桑山宗仙に師事し、1665年(寛文5)徳川家綱の茶道師範。古器の鑑定に精通。(1605〜1673)
⇒かたぎり【片桐】
かた‐ぎん【片吟】🔗⭐🔉
かた‐ぎん【片吟】
(→)独吟どくぎん3に同じ。
かた‐くも【片雲】🔗⭐🔉
かた‐くも【片雲】
一片の雲。ちぎれ雲。へんうん。
かた‐ぐる・し【片苦し】🔗⭐🔉
かた‐ぐる・し【片苦し】
〔形シク〕
片思いで苦しい。自分を思わない人を思ってなやましい。蜻蛉日記上「―・しなるめな見せそ神」
かた‐こま【片駒】🔗⭐🔉
かた‐こま【片駒】
将棋で、(→)一枚落いちまいおちに同じ。
かた‐さがり【片下がり】🔗⭐🔉
かた‐さがり【片下がり】
着物を着たとき、一方の裾すそがさがること。
かた‐さ・る【片去る】🔗⭐🔉
かた‐さ・る【片去る】
〔自四〕
①片側に寄る。脇へ寄る。万葉集18「ぬばたまの夜床―・り朝寝髪かきもけづらず」
②遠慮する。源氏物語若菜上「いづかたも、みなこなたの御けはひには、―・りはばかるさまにて」
かた‐し【片し】🔗⭐🔉
かた‐し【片し】
対ついのものの片方。かたかた。片一方。宇津保物語貴宮「うへの袴をかへざまに着、―に足二つをさし入れて」
⇒かたし‐がい【片し貝】
⇒かたし‐がたし【片し片し】
⇒かたし‐めぬき【片し目貫】
かたし‐がい【片し貝】‥ガヒ🔗⭐🔉
かたし‐がい【片し貝】‥ガヒ
二枚貝の離れた一片。かたつがい。内裏名所百首「伊勢島や二見の浦の―あはで月日を待つぞつれなき」
⇒かた‐し【片し】
かたし‐がたし【片し片し】🔗⭐🔉
かたし‐がたし【片し片し】
対ついであるべきものが揃わないこと。ちぐはぐ。好色五人女4「―の草履をはき」
⇒かた‐し【片し】
かたし‐めぬき【片し目貫】🔗⭐🔉
かたし‐めぬき【片し目貫】
一対の目貫の半端になった片方。西鶴織留2「口のうちより虎の―を取り出し」
⇒かた‐し【片し】
かた‐しゃぎり【片しゃぎり】🔗⭐🔉
かた‐しゃぎり【片しゃぎり】
歌舞伎囃子はやしの一つ。松羽目物の幕開きや時代物の幕切れなどに、太鼓・能管・大小鼓ではやすもの。片砂切。
かた・す【片す】🔗⭐🔉
かた・す【片す】
〔他五〕
①移し変える。片寄せる。
②(東北・関東地方で)片付ける。
かた‐すみ【片隅】🔗⭐🔉
かた‐すみ【片隅】
中心から離れた一隅。片方の隅。かたわき。すみっこ。「都会の―」
かた‐ず・む【片ずむ】🔗⭐🔉
かた‐ず・む【片ずむ】
〔自四〕
(ズムのかなづかい未詳。一説に、「詰つむ」とも)かたよる。一方へ傾く。
○固唾を呑むかたずをのむ
事のなりゆきを案じなどして息をこらすさまにいう。沙石集9「光寂坊かたづのみて、云ひやりたる事なし」
⇒かた‐ず【固唾】
かた‐そら【片空】🔗⭐🔉
かた‐そら【片空】
片方の空。天の一方。
かた‐たがい【片違い】‥タガヒ🔗⭐🔉
かた‐たがい【片違い】‥タガヒ
物の順序・高低・方向などのそろわないこと。ふぞろい。参差しんし。かたちがい。欽明紀「前後さきのち次ついでを失ひて、兄弟あにおとと参差かたたがいなり」
かた‐ちがい【片違い】‥チガヒ🔗⭐🔉
かた‐ちがい【片違い】‥チガヒ
(→)「かたたがい(片違い)」に同じ。新撰六帖6「あふ事は―なる笹結び」
○形変わるかたちかわる
出家姿になる。剃髪する。源氏物語橋姫「御形も変りておはしますらむが」
⇒かたち【形・容】
かた‐ちぐ【片ちぐ】🔗⭐🔉
かた‐ちぐ【片ちぐ】
物が揃わないこと。ちぐはぐ。申楽談儀「帯などの先、―なる所、心得べし」
かた‐つ‐え【片つ枝】🔗⭐🔉
かた‐つ‐え【片つ枝】
片方の枝。片枝。
かた‐つ‐がい【片つ貝】‥ガヒ🔗⭐🔉
かた‐つ‐がい【片つ貝】‥ガヒ
二枚貝の片方の貝がら。かたしがい。
かた‐つ‐かた【片つ方】🔗⭐🔉
かた‐つ‐かた【片つ方】
①(二つあるものの)かたほう。片一方。源氏物語絵合「御櫛の箱の―を見給ふに」
②いま一つの方。他方。源氏物語夕顔「待ちきこえがほなる―人を」
③かたすみ。かたはし。源氏物語空蝉「この御たたう紙の―に」
かたっ‐ぱし【片っ端】🔗⭐🔉
かたっ‐ぱし【片っ端】
カタハシの促音化。
⇒かたっぱし‐から【片っ端から】
かたっぱし‐から【片っ端から】🔗⭐🔉
かたっぱし‐から【片っ端から】
端から。次々に。手当り次第に。
⇒かたっ‐ぱし【片っ端】
かたっ‐ぽ【片っ方】🔗⭐🔉
かたっ‐ぽ【片っ方】
(くだけた感じの語)(→)「かたほう」に同じ。
かた‐なき【片泣き・片鳴き】🔗⭐🔉
かた‐なき【片泣き・片鳴き】
①片方だけが泣くこと。独り泣き。允恭紀「―にわが泣く妻」
②半泣きに泣くこと。仁徳紀「―に道行く者も」
③鳥などの鳴き声の未熟で満足な鳴き方でないこと。新撰六帖6「おのづからまだ―のひな鳥の」
かた‐に【片荷】🔗⭐🔉
かた‐に【片荷】
天秤棒でかついだ荷の片方。半分の荷。
⇒かたに‐づ・る【片荷釣る】
かた‐は【片羽】🔗⭐🔉
かた‐は【片羽】
片方の翼。
かた‐はがい【片羽交】‥ガヒ🔗⭐🔉
かた‐はがい【片羽交】‥ガヒ
鳥の片方の翼。狂言、鴈礫「其雁は取るとも、―なり共置いて行け」
かた‐はずし【片外し】‥ハヅシ🔗⭐🔉
かた‐はずし【片外し】‥ハヅシ
①女の髪の結い方。下げ髪を輪に巻いて笄こうがいを横に貫き、毛先を笄の右下から左下また右下とまわしくぐらせ、余りを髱たぼの後ろへ流したもの。笄を抜けば、下げ髪となる。江戸時代の御殿女中の間に行われた。
片外し
 ②歌舞伎で、女形の鬘かつらの一つ。1の髪型による。政岡・尾上・岩藤・重の井など。
③(取引用語)(→)「片落し」2に同じ。
②歌舞伎で、女形の鬘かつらの一つ。1の髪型による。政岡・尾上・岩藤・重の井など。
③(取引用語)(→)「片落し」2に同じ。
 ②歌舞伎で、女形の鬘かつらの一つ。1の髪型による。政岡・尾上・岩藤・重の井など。
③(取引用語)(→)「片落し」2に同じ。
②歌舞伎で、女形の鬘かつらの一つ。1の髪型による。政岡・尾上・岩藤・重の井など。
③(取引用語)(→)「片落し」2に同じ。
かた‐はぶたえ【片羽二重】‥ヘ🔗⭐🔉
かた‐はぶたえ【片羽二重】‥ヘ
筬おさ一羽に経たて糸一本を入れた軽目の羽二重。
かた‐ひき【片引き・方引き】🔗⭐🔉
かた‐ひき【片引き・方引き】
(→)「かたびいき」に同じ。
かた‐ひ・く【片引く・方引く】🔗⭐🔉
かた‐ひ・く【片引く・方引く】
〔他四〕
一方だけをひいきにする。えこひいきをする。枕草子135「け近き人思ひ―・き、ほめ」
かた‐びらき【片開き】🔗⭐🔉
かた‐びらき【片開き】
扉が1枚で片側にだけ開くこと。「―の戸」
かたふた‐ばしら【片蓋柱】🔗⭐🔉
かたふた‐ばしら【片蓋柱】
壁に付けた長方形断面の装飾的な柱。片蓋。
かた‐ま【片間】🔗⭐🔉
かた‐ま【片間】
片方に添った部屋。
かた‐むすび【片掬び】🔗⭐🔉
かた‐むすび【片掬び】
片手で水などをすくうこと。夫木和歌抄9「岩もる清水―せむ」
かた‐や【方屋・片屋・形屋】🔗⭐🔉
かた‐や【方屋・片屋・形屋】
①相撲や競馬などの時、左右・東西に分けた競技者の控える所。今昔物語集28「埒より東の左の―の西のそばに立てて御覧じけり」
②相撲場の四本柱しほんばしらの内。土俵場。〈日葡辞書〉
⇒かたや‐いり【方屋入】
かた‐や【片や】🔗⭐🔉
かた‐や【片や】
一方は。片方は。「―大鵬、こなた柏戸」
かた‐や【片屋】(建築)🔗⭐🔉
かた‐や【片屋】
雨水が一方に多く落ちるように造った屋根。
かた‐よ・せる【片寄せる】🔗⭐🔉
かた‐よ・せる【片寄せる】
〔他下一〕[文]かたよ・す(下二)
①一方へ寄せる。
②一方へまとめる。かたづける。好色一代女6「口鼻かかは奥の一間を―・せて」
かた‐より【片寄り・偏り】🔗⭐🔉
かた‐より【片寄り・偏り】
①一方に寄ること。万葉集10「秋の田の穂向ほむきの寄れる―にわれは物思ふつれなきものを」
②一方に偏すること。また、その程度。「栄養の―」
かた‐よ・る【片寄る・偏る】🔗⭐🔉
かた‐よ・る【片寄る・偏る】
〔自五〕
①片方へ寄る。傾く。万葉集14「宇良野の山に月つく―・るも」。「―・った考え」
②一方に力を貸す。味方する。不公平になる。蜻蛉日記中「数々に君―・りて引くなれば柳のまゆも今ぞ開くる」
かた‐われ【片割れ】🔗⭐🔉
かたわれ‐づき【片割れ月】🔗⭐🔉
かたわれ‐づき【片割れ月】
半月。弦月。弓張月。拾遺和歌集恋「あふことは―の雲がくれおぼろけにやは人の恋しき」
⇒かた‐われ【片割れ】
かたわれ‐ぶね【片割れ舟】🔗⭐🔉
かたわれ‐ぶね【片割れ舟】
破損して役に立たない舟。千載和歌集雑「なぎさなる―のうづもれて」
⇒かた‐われ【片割れ】
かたわれ‐ぼし【片割れ星】🔗⭐🔉
かたわれ‐ぼし【片割れ星】
流星。走り星。よばいぼし。
⇒かた‐われ【片割れ】
○肩を怒らすかたをいからす
肩を高く張って、人を威圧する態度をする。
⇒かた【肩】
○肩を入れるかたをいれる
力を添える。ひいきをする。肩入れする。肩を持つ。
⇒かた【肩】
○肩を落とすかたをおとす
力が抜け両肩が下がった姿になる。ひどく落胆しているさま。
⇒かた【肩】
○肩を貸すかたをかす
力を添える。援助をする。
⇒かた【肩】
○肩をすくめるかたをすくめる
肩をちぢませる。やれやれという気持や落胆した気持を表す。
⇒かた【肩】
○肩をすぼめるかたをすぼめる
肩身が狭く意気があがらない様子をいう。
⇒かた【肩】
○肩を並べるかたをならべる
並んで立つ。並んで歩く。対等の地位で張り合う。
⇒かた【肩】
○肩を抜くかたをぬく
責任をのがれる。負担をまぬかれる。
⇒かた【肩】
○肩を持つかたをもつ
味方になって援助する。ひいきする。肩を入れる。
⇒かた【肩】
ひら【片・枚】🔗⭐🔉
ひら【片・枚】
うすくひらたいもの。すなわち、紙・葉・筵むしろなど。また、それを数えるのに用いる語。源氏物語梅枝「白き赤きなど、掲焉けちえんなる―は、筆取りなほし用意し給へるさまさへ」。枕草子36「あざやかなる畳一―うち敷きて」。「一―の雲」
へん【片】🔗⭐🔉
へん【片】
①ひときれ。きれはし。
②ペンスの当て字。
へん‐うん【片雲】🔗⭐🔉
へん‐うん【片雲】
一片の雲。ちぎれぐも。奥の細道「―の風にさそはれて漂泊の思ひやまず」
へん‐えい【片影】🔗⭐🔉
へん‐えい【片影】
わずかのかげ。わずかに見える物の姿。また、ある側面。「沖ゆく舟の―」「故人の―を物語る逸話」
へん‐かん【片簡】🔗⭐🔉
へん‐かん【片簡】
文書のきれはし。断簡。
へん‐がん【片岩】🔗⭐🔉
へん‐がん【片岩】
(→)結晶片岩けっしょうへんがんに同じ。
へん‐ぐう【片隅】🔗⭐🔉
へん‐ぐう【片隅】
かたすみ。すみ。
へん‐ぺん【片片】🔗⭐🔉
へん‐ぺん【片片】
①きれぎれなさま。
②断片の軽くひるがえるさま。「―として散る」
③取るに足りないさま。「―たる小事」
[漢]片🔗⭐🔉
片 字形
 筆順
筆順
 〔片部0画/4画/教育/4250・4A52〕
〔音〕ヘン(呉)(漢)
〔訓〕かた・きれ・ひら・ペンス
[意味]
①二つのうちの一方。かたわれ。「片務・片帆」
②きれはし。かけら。「木片・破片・片雲・断片」
③転じて、ごくわずか。ちょっと。「片言・片時」
④ペンス。イギリスの貨幣単位。▶pennyの複数形penceの音訳。
[解字]
解字
〔片部0画/4画/教育/4250・4A52〕
〔音〕ヘン(呉)(漢)
〔訓〕かた・きれ・ひら・ペンス
[意味]
①二つのうちの一方。かたわれ。「片務・片帆」
②きれはし。かけら。「木片・破片・片雲・断片」
③転じて、ごくわずか。ちょっと。「片言・片時」
④ペンス。イギリスの貨幣単位。▶pennyの複数形penceの音訳。
[解字]
解字 「木」を二つに割った右半部を描いた象形文字。木の切れはしの意。[
「木」を二つに割った右半部を描いた象形文字。木の切れはしの意。[ ]は異体字。
[下ツキ
阿片・鴉片・一片・花片・砕片・残片・紙片・小片・切片・雪片・断片・鉄片・肉片・薄片・破片・半片・氷片・木片・鱗片
[難読]
片方かたえ
]は異体字。
[下ツキ
阿片・鴉片・一片・花片・砕片・残片・紙片・小片・切片・雪片・断片・鉄片・肉片・薄片・破片・半片・氷片・木片・鱗片
[難読]
片方かたえ
 筆順
筆順
 〔片部0画/4画/教育/4250・4A52〕
〔音〕ヘン(呉)(漢)
〔訓〕かた・きれ・ひら・ペンス
[意味]
①二つのうちの一方。かたわれ。「片務・片帆」
②きれはし。かけら。「木片・破片・片雲・断片」
③転じて、ごくわずか。ちょっと。「片言・片時」
④ペンス。イギリスの貨幣単位。▶pennyの複数形penceの音訳。
[解字]
解字
〔片部0画/4画/教育/4250・4A52〕
〔音〕ヘン(呉)(漢)
〔訓〕かた・きれ・ひら・ペンス
[意味]
①二つのうちの一方。かたわれ。「片務・片帆」
②きれはし。かけら。「木片・破片・片雲・断片」
③転じて、ごくわずか。ちょっと。「片言・片時」
④ペンス。イギリスの貨幣単位。▶pennyの複数形penceの音訳。
[解字]
解字 「木」を二つに割った右半部を描いた象形文字。木の切れはしの意。[
「木」を二つに割った右半部を描いた象形文字。木の切れはしの意。[ ]は異体字。
[下ツキ
阿片・鴉片・一片・花片・砕片・残片・紙片・小片・切片・雪片・断片・鉄片・肉片・薄片・破片・半片・氷片・木片・鱗片
[難読]
片方かたえ
]は異体字。
[下ツキ
阿片・鴉片・一片・花片・砕片・残片・紙片・小片・切片・雪片・断片・鉄片・肉片・薄片・破片・半片・氷片・木片・鱗片
[難読]
片方かたえ
大辞林の検索結果 (99)
かた【片】🔗⭐🔉
かた 【片】 (接頭)
〔「かた(方)」と同源〕
名詞に付く。
(1)(ア)二つそろったものの一方の意を表す。「―親」「―思い」「―敷く」(イ)すくない,わずかである意を表す。「―時」(ウ)完全でない意を表す。「―言(コト)」(エ)中心より離れ,一方に寄っている,へんぴである意を表す。「―田舎」「―山里」
(2)〔上代の用法〕
動詞に付いて,ひたすらそれをするさまを表す。「―待つ」「―設(マ)く」
→片や
かた=が付・く🔗⭐🔉
――が付・く
「方が付く」に同じ。
〔「片付く」からの類推表記〕
かた=を付・ける🔗⭐🔉
――を付・ける
「方を付ける」に同じ。
〔「片付ける」からの類推表記〕
かた-あらし【片荒らし】🔗⭐🔉
かた-あらし 【片荒らし】
中世,地味が悪いため一年おきまたは数年おきに耕作した田。律令制下では易田(エキデン)と呼んだ。休田(ヤスミダ)。「山がつの外面の小田の―/新撰六帖 2」
かた-いじ【片意地】🔗⭐🔉
かた-いじ ―イヂ [0] 【片意地】 (名・形動)[文]ナリ
頑固に自分の考えを押し通す・こと(さま)。「―な男」「―を張る」
かた-いっぽう【片一方】🔗⭐🔉
かた-いっぽう ―イツパウ [3] 【片一方】
二つのうちの一つ。片方。
かた-うた【片歌】🔗⭐🔉
かた-うた [2][0] 【片歌】
〔二つ組み合って完全になる歌の片方の意〕
(1)古代歌謡の一体。五・七・七の三句で一首をなす歌で,多くは問答に用いた。二つ合わせると旋頭歌(セドウカ)の形となる。「はしけやし我家(ワギエ)の方よ雲居立ち来も/古事記(中)」の類。
(2)江戸時代の俳人建部綾足が,俳諧の起源を{(1)}に求めて提唱した一九音(五・七・七)の発句形式。
かた-おか【片岡】🔗⭐🔉
かた-おか ―ヲカ 【片岡】
一方が他方よりなだらかに傾斜している岡。また,孤立している岡。「―にしば移りしてなく雉子(キギス)/山家(春)」
かたおか【片岡】🔗⭐🔉
かたおか カタヲカ 【片岡】
(1)奈良県北葛城郡王寺町付近の丘陵。かたおかやま。((歌枕))「霧立ちて鴈(カリ)ぞなくなる―の朝(アシタ)の原はもみぢしぬらむ/古今(秋下)」
(2)京都市北区の上賀茂神社本殿の東にある小山。海抜170メートル。片岡の森。((歌枕))「郭公(ホトトギス)こゑ待つ程は―の杜のしづくに立ちやぬれまし/新古今(夏)」
かたおか【片岡】🔗⭐🔉
かたおか カタヲカ 【片岡】
姓氏の一。
かたおか-けんきち【片岡健吉】🔗⭐🔉
かたおか-けんきち カタヲカ― 【片岡健吉】
(1843-1903) 政治家。土佐藩出身。立志社を創立し,自由民権運動を指導した。また,国会期成同盟総代として活躍。国会開設後衆議院議員,同議長。
かたおか-ちえぞう【片岡千恵蔵】🔗⭐🔉
かたおか-ちえぞう カタヲカチ ザウ 【片岡千恵蔵】
(1903-1983) 映画俳優。本名,植木正義。群馬県生まれ。歌舞伎から映画に転じ,時代劇を中心に長く第一線のスターとして活躍。代表作「国士無双」「赤西蠣太」「血槍富士」など。
ザウ 【片岡千恵蔵】
(1903-1983) 映画俳優。本名,植木正義。群馬県生まれ。歌舞伎から映画に転じ,時代劇を中心に長く第一線のスターとして活躍。代表作「国士無双」「赤西蠣太」「血槍富士」など。
 ザウ 【片岡千恵蔵】
(1903-1983) 映画俳優。本名,植木正義。群馬県生まれ。歌舞伎から映画に転じ,時代劇を中心に長く第一線のスターとして活躍。代表作「国士無双」「赤西蠣太」「血槍富士」など。
ザウ 【片岡千恵蔵】
(1903-1983) 映画俳優。本名,植木正義。群馬県生まれ。歌舞伎から映画に転じ,時代劇を中心に長く第一線のスターとして活躍。代表作「国士無双」「赤西蠣太」「血槍富士」など。
かたおか-てっぺい【片岡鉄兵】🔗⭐🔉
かたおか-てっぺい カタヲカ― 【片岡鉄兵】
(1894-1944) 小説家。岡山県生まれ。横光利一らと「文芸時代」を創刊,新感覚派の提唱者となるが,プロレタリア文学に転じた。のち転向,以後大衆文学に進んだ。代表作「綱の上の少女」「綾里村快挙録」
かたおか-にざえもん【片岡仁左衛門】🔗⭐🔉
かたおか-にざえもん カタヲカニザ モン 【片岡仁左衛門】
上方の歌舞伎俳優。屋号,松島屋。
(1)(初世)(1656-1715) 元禄期(1688-1704)に敵役(カタキヤク)・実事・武道の名人といわれた。
(2)(七世)(1755-1837) 文化・文政期(1804-1830)に大坂を中心に活躍,幅広い芸風を示した。
(3)(一一世)(1857-1934) 大正・昭和初期の名優。晩年は東京に移り,和事や新作物の老け役を得意とした。
(4)(一三世)(1903-1994) 一一世の三男。上方歌舞伎の復興に貢献。
モン 【片岡仁左衛門】
上方の歌舞伎俳優。屋号,松島屋。
(1)(初世)(1656-1715) 元禄期(1688-1704)に敵役(カタキヤク)・実事・武道の名人といわれた。
(2)(七世)(1755-1837) 文化・文政期(1804-1830)に大坂を中心に活躍,幅広い芸風を示した。
(3)(一一世)(1857-1934) 大正・昭和初期の名優。晩年は東京に移り,和事や新作物の老け役を得意とした。
(4)(一三世)(1903-1994) 一一世の三男。上方歌舞伎の復興に貢献。
 モン 【片岡仁左衛門】
上方の歌舞伎俳優。屋号,松島屋。
(1)(初世)(1656-1715) 元禄期(1688-1704)に敵役(カタキヤク)・実事・武道の名人といわれた。
(2)(七世)(1755-1837) 文化・文政期(1804-1830)に大坂を中心に活躍,幅広い芸風を示した。
(3)(一一世)(1857-1934) 大正・昭和初期の名優。晩年は東京に移り,和事や新作物の老け役を得意とした。
(4)(一三世)(1903-1994) 一一世の三男。上方歌舞伎の復興に貢献。
モン 【片岡仁左衛門】
上方の歌舞伎俳優。屋号,松島屋。
(1)(初世)(1656-1715) 元禄期(1688-1704)に敵役(カタキヤク)・実事・武道の名人といわれた。
(2)(七世)(1755-1837) 文化・文政期(1804-1830)に大坂を中心に活躍,幅広い芸風を示した。
(3)(一一世)(1857-1934) 大正・昭和初期の名優。晩年は東京に移り,和事や新作物の老け役を得意とした。
(4)(一三世)(1903-1994) 一一世の三男。上方歌舞伎の復興に貢献。
かたおか-やすし【片岡安】🔗⭐🔉
かたおか-やすし カタヲカ― 【片岡安】
(1876-1946) 建築家。金沢生まれ。東京帝大卒。関西建築協会(現・日本建築協会)の初代理事長。大阪市中央公会堂,大阪毎日新聞社などを設計。
かた-おろし【片下ろし】🔗⭐🔉
かた-おろし [3] 【片下ろし】
古代歌謡のうたい方の一。本(モト)と末(スエ)に分かれてうたうとき,一方の調子を下げてうたうこと。また,そのようなうたい方をする歌謡の曲名。
かた-かお【片顔】🔗⭐🔉
かた-かお ―カホ 【片顔】
顔の半分。片面。「ほうかぶりはづれて―の少し見えたるを/太平記 29」
かたかお-なし【片顔無し】🔗⭐🔉
かたかお-なし ―カホ― 【片顔無し】
心が一徹で他を顧みないこと。また,そのような人。「入道はさる―の人にて/盛衰記 12」
かた-か・く【片掛く】🔗⭐🔉
かた-か・く 【片掛く】 (動カ下二)
(1)片方を寄せかける。「山に―・けたる家なれば/源氏(手習)」
(2)頼みにする。当てにする。「かの殿の御蔭に―・けて/源氏(松風)」
かた-かげ【片陰】🔗⭐🔉
かた-かげ [3] 【片陰】
(1)日陰。特に夏の夕方の日陰。[季]夏。
(2)何かに隠されて,ある方角からは見えない所。物かげ。「―へ呼んで,紙に包んだ物を手に握らせて/雁(鴎外)」
かた-がっしょう【片合掌】🔗⭐🔉
かた-がっしょう ―ガツシヤウ [3] 【片合掌】
片手だけで合掌のかっこうをすること。
かた-かど【片才】🔗⭐🔉
かた-かど 【片才】
わずかな才芸。「(女ノ)―を聞き伝へて(男ガ)心を動かすこともあめり/源氏(帚木)」
かた-かな【片仮名】🔗⭐🔉
かたかな-ご【片仮名語】🔗⭐🔉
かたかな-ご [0] 【片仮名語】
片仮名で表記される語。主として,外来語。
かた-かま【片鎌】🔗⭐🔉
かた-かま [3] 【片鎌】
(1)鎌槍の左右へ突き出た三日月形の枝のうちの一方の枝。
(2)「片鎌槍」の略。
かたかま-やり【片鎌槍】🔗⭐🔉
かたかま-やり [4] 【片鎌槍】
鎌槍のうち,穂の枝が片方のみのもの。かたかま。
片鎌槍
 [図]
[図]
 [図]
[図]
かた-がわせ【片為替】🔗⭐🔉
かた-がわせ ―ガハセ [3] 【片為替】
特定国との間で,貿易不均衡のため為替の受け払いが,一方に偏った状態。
かた-かんな【片仮名】🔗⭐🔉
かた-かんな 【片仮名】
「かたかな」に同じ。「一には―,ひとつは葦手/宇津保(蔵開中)」
かた-ぎし【片岸】🔗⭐🔉
かた-ぎし [0] 【片岸】
〔古くは「かたきし」とも〕
(1)川などの一方の岸。
(2)〔「岸」は崖(ガケ)の意〕
片方が高く切り立ってがけになった所。「遥なる―より馬を丸ばして落ちて/今昔 19」
(3)傍らの場所。隣。「左近の馬場を―にしたれば/蜻蛉(上)」
かたぎり【片桐】🔗⭐🔉
かたぎり 【片桐】
姓氏の一。
かたぎり-かつもと【片桐且元】🔗⭐🔉
かたぎり-かつもと 【片桐且元】
(1556-1615) 安土桃山・江戸初期の武将。通称市正(イチノカミ)。近江の人。豊臣秀吉に仕え,賤ヶ岳七本槍の一人。秀頼の後見役。方広寺鐘銘事件で大坂城を去る。大坂冬・夏の陣では徳川方についた。
かたぎり-せきしゅう【片桐石州】🔗⭐🔉
かたぎり-せきしゅう ―セキシウ 【片桐石州】
(1605-1673) 江戸初期の茶匠。名は貞昌。石州流茶道の開祖。大和国小泉城主。石見守(イワミノカミ)。千道安の高弟桑山宗仙に学び,小堀遠州の後継として将軍家の茶道師範となった。
かた-くち【片口】🔗⭐🔉
かた-くち [0] 【片口】
(1)鉢で,取っ手がなく一方に注ぎ口の突き出ているもの。
⇔両口(リヨウグチ)
(2)一方の人だけの言い分。「―の御裁断/浄瑠璃・反魂香」
(3)かたわら。片一方。「酒飲む―に案じつつ/義経記 4」
(4)馬の口取り縄の左右の一方だけを引くこと。
⇔諸口(モロクチ)
「或は―に引かせ/平家(一六・長門本)」
片口(1)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
かたくち-いわし【片口鰯】🔗⭐🔉
かたくち-いわし [5] 【片口鰯】
ニシン目の海魚。全長15センチメートル内外。下顎が小さい。体色は背側が青黒色,腹側が銀白色。しらす干し・煮干し・ごまめなどの材料とし,食用のほかカツオ釣りの生き餌とする。日本各地に分布。ヒシコイワシ。セグロイワシ。シコイワシ。シコ。タレクチ。
→イワシ
かた-くり【片栗】🔗⭐🔉
かた-くり [2] 【片栗】
(1)ユリ科の多年草。林下に生じ,早春,二葉を開く。葉は楕円形で厚く,紫斑がある。葉にやや後れて長い花茎の先に紫紅色のユリに似た花を一個下向きにつける。根茎は白色・多肉の棒状でデンプンを蓄え,片栗粉にする。古名,カタカゴ・カタカシ。カタコ。
〔「片栗の花」は[季]春。《―の一つの花の花盛り/高野素十》〕
(2)「片栗粉」の略。
片栗(1)
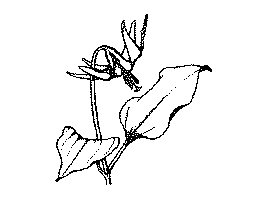 [図]
[図]
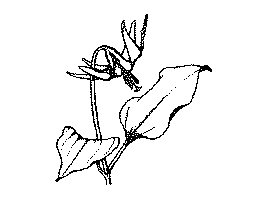 [図]
[図]
かたくり-こ【片栗粉】🔗⭐🔉
かたくり-こ [4][3] 【片栗粉】
カタクリの地下茎から製した白いデンプン。市販の多くはジャガイモから製し,葛(クズ)粉の代用として菓子・料理に用いる。
かた-ぐるし【片苦し】🔗⭐🔉
かた-ぐるし 【片苦し】 (形動ナリ)
片思いで,心ぐるしいさま。「―なるめな見せそ神/蜻蛉(上)」
かた-こと【片言】🔗⭐🔉
かた-こと [0] 【片言】
〔「かた」は不完全の意〕
(1)幼児や外国人などのたどたどしい話し方。「―の英語を話す」
(2)方言や俗語。「さるといふをはるといふ,すべて―はさつしたまへ/人情本・梅児誉美(初)」
かたこと-まじり【片言交じり】🔗⭐🔉
かたこと-まじり [5] 【片言交じり】
片言をまじえて話すこと。
かたこと【片言】🔗⭐🔉
かたこと 【片言】
方言集。安原貞室著。五巻。1650年刊。愛児に言葉遣いを教えるため,主に京都の方言・訛語(カゴ)を集めて正しい語と対比したもの。片言なおし。
かた-さがり【片下(が)り】🔗⭐🔉
かた-さがり [3] 【片下(が)り】
(1)片方が下がっていること。
(2)着物の裾の一方が下がっていること。
かた-さしなわ【片差縄】🔗⭐🔉
かた-さしなわ ―サシナハ 【片差縄】
馬の口に付けて引く差縄を,左右に付けず,片方(右)にだけ付けたもの。四位以下の者がこれを行なった。
⇔諸差縄(モロサシナワ)
かた-さ・る【片去る】🔗⭐🔉
かた-さ・る 【片去る】 (動ラ四)
(1)一方に寄る。よける。「枕―・る夢に見え来し/万葉 633」
(2)遠慮する。「いづ方も皆こなたの御けはひには,―・り憚るさまにて/源氏(若菜上)」
かたし【片足・片し】🔗⭐🔉
かたし 【片足・片し】
〔「かたあし」の転〕
(1)片方の足。「お里は踏脱(クツヌギ)へ―おろして/人情本・閑情末摘花」
(2)対になっているものの片方。また,半分。「くろ箱のふたも―落ちたる硯/枕草子(二一九・能因本)」
(3)ほんのわずかの物。少しの物。「食物等―なければ/四河入海 14」
かたし-がたし【片し片し】🔗⭐🔉
かたし-がたし 【片し片し】
履物など対になっているものの片方が違っていること。「―の奈良草履/浮世草子・五人女 3」
かたし-めぬき【片し目貫】🔗⭐🔉
かたし-めぬき [4] 【片し目貫】
(1)もともと,裏表一対あった目貫が片方だけになったもの。
(2)一対の目貫の片方が造りを異にしているもの。
かた-しゃぎり【片しゃぎり】🔗⭐🔉
かた-しゃぎり [3] 【片しゃぎり】
歌舞伎の下座の一。松羽目物や口上などの幕開き,大時代物の幕切れなどに用いる。太鼓・大鼓・小鼓・能管などを用い,太鼓を右ばちの片方で流す手法が特徴。
かた・す【片す】🔗⭐🔉
かた・す [2] 【片す】 (動サ五[四])
物を他の場所に移す。どける。また,かたづける。「おもちゃを―・す」「其所を―・して盥(タレイ)をあげろ/塩原多助一代記(円朝)」
かた-すみ【片隅】🔗⭐🔉
かた-すみ [3][0] 【片隅】
中央部から離れた目立たない所。すみっこ。「部屋の―」「大都会の―」
かた-そぎ【片削ぎ】🔗⭐🔉
かた-そぎ [0] 【片削ぎ】
(1)片方をそぎ落とすこと。また,そのもの。「―の月を昔の色と見て/新後撰(秋下)」
(2)神社の屋根に交わしてある千木(チギ)の両端を斜めにけずり落としたもの。
かた-ちぐ【片ちぐ】🔗⭐🔉
かた-ちぐ 【片ちぐ】 (名・形動)
対をなすものが,ふぞろいな・こと(さま)。ちぐはぐ。ふぞろい。「―に片枝は蕾,片枝は開きそめたる花衣/浄瑠璃・五十年忌(中)」
かた-つ-かた【片つ方】🔗⭐🔉
かた-つ-かた 【片つ方】
(1)二つ一組のもののどちらか一方。片一方。片側。「御手,―をばひろげたるやうに/更級」
(2)いま一つの方。他方。「きびしき―(=本妻)やありけむ/堤中納言(このついで)」
(3)かたすみ。かたはし。「御たたう紙の―に/源氏(空蝉)」
かた-つきみ【片月見】🔗⭐🔉
かた-つきみ [3][4] 【片月見】
八月十五夜と九月十三夜のどちらか一方だけ月見をすること。忌むべきこととされる。
かたっ-ぱし【片っ端】🔗⭐🔉
かたっ-ぱし [0] 【片っ端】
「かたはし」の促音添加。
かたっぱし-から【片っ端から】🔗⭐🔉
かたっぱし-から 【片っ端から】 (副)
はしから次々に。手当たり次第に。無差別に。かたはしから。「―投げつける」「―けちをつける」
かたっ-ぽう【片っ方】🔗⭐🔉
かたっ-ぽう ―パウ [2] 【片っ方】
「かたほう」の促音添加。かたっぽ。
かた-ど【片戸】🔗⭐🔉
かた-ど [0] 【片戸】
扉一枚の開き戸。片開きの戸。
かた-なき【片泣き・片鳴き】🔗⭐🔉
かた-なき 【片泣き・片鳴き】
(1)一人で泣くこと。ひたすらに泣くこと。「下泣きに我が泣く妻―に我が泣く妻/日本書紀(允恭)」
(2)鳥の鳴き声がまだ整わないこと。《片鳴》「おのづからまだ―のひなどりの/新撰六帖 6」
かた-に【片荷】🔗⭐🔉
かた-に [0] 【片荷】
(1)天秤棒(テンビンボウ)で前後に分けて担った荷物の片方。
(2)荷物が片方に寄ってしまうこと。
(3)船舶・トラックなどで,積み荷が往路または復路のどちらか一方しかないこと。
(4)責任の一半。「―を下ろす」
かた-は【片羽】🔗⭐🔉
かた-は [0] 【片羽】
(1)片一方の翼。かたはね。
(2)対になっているものの一方。転じて,不完全なさま。「鎮西八郎為朝の箭(ヤ)の根あり。…―の長さ八寸ばかり/読本・弓張月(残)」「名を知って物を知らぬ―になった/サフラン(鴎外)」
かた-ばかま【片袴】🔗⭐🔉
かた-ばかま 【片袴】
(1)袴の足の片方。
(2)山伏などがはく短い袴。また,袴の下にはく防寒用の袴とも。
かた-はずし【片外し】🔗⭐🔉
かた-はずし ―ハヅシ [3] 【片外し】
(1)江戸時代の女性の髪の結い方の一。束ねた髪を根の前に水平に挿した笄(コウガイ)に巻きつけ,片方を笄からはずし後ろへ垂れ下げたもの。笄を抜き取ると,下げ髪となる。諸侯の奥女中などが結った。
(2)歌舞伎の鬘の一。「伽羅先代萩(メイボクセンダイハギ)」の政岡,「鏡山」の尾上など御殿女中や武家の奥方に扮する女形が用いる。
片外し(1)
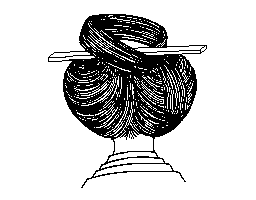 [図]
[図]
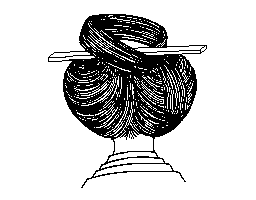 [図]
[図]
かた-はぶたえ【片羽二重】🔗⭐🔉
かた-はぶたえ ―ハブタヘ [3] 【片羽二重】
普通,筬(オサ)一羽にたて糸を二本入れるのに対して,たて糸一本で織った軽い羽二重。
かた-ひ・く【片引く・方引く】🔗⭐🔉
かた-ひ・く 【片引く・方引く】 (動カ四)
えこひいきする。「け近き人思ひ―・き/枕草子 135」
かた-ひじ【片肘・片肱】🔗⭐🔉
かた-ひじ ―ヒヂ [0] 【片肘・片肱】
片一方のひじ。
かた-びらき【片開き】🔗⭐🔉
かた-びらき [3] 【片開き】
開き戸が一枚で,一方だけに開くこと。
⇔両開き
かたふた-ばしら【片蓋柱】🔗⭐🔉
かたふた-ばしら [5] 【片蓋柱】
装飾として壁面に取り付けた柱。壁面より多少突き出ている。つけ柱。
かた-ぶり【偏降り・片降り】🔗⭐🔉
かた-ぶり [0] 【偏降り・片降り】
日照りのあと,雨降りばかり長く続くこと。
⇔偏照り
かた-べり【片減り】🔗⭐🔉
かた-べり [0] 【片減り】 (名)スル
片側または片一方だけが減ること。はき物の底や車のタイヤなどにいう。
かた-みせ【片見世・片店】🔗⭐🔉
かた-みせ [0] 【片見世・片店】
店の一部分で,本業とは違う商品を副業的に並べ商うこと。また,その店。
かた-むすび【片結び】🔗⭐🔉
かた-むすび [3] 【片結び】
帯やひもなどの結び方。一方に輪を作り,その輪に他方を輪にして入れ,はじめの輪を引き締めて結ぶもの。解けやすい結び方。
かた-や【片屋・傍屋】🔗⭐🔉
かた-や [0] 【片屋・傍屋】
(1)片流れの屋根。また,その造りの建物。片屋造り。
(2)母屋の傍らにある建物。
かた-や【片や】🔗⭐🔉
かた-や 【片や】 (連語)
(1)片一方は。「―五期連続の名人,―新進気鋭の四段」
(2)相撲で,行司が力士を土俵上で名を呼び上げて,名指す時に用いる語。
かた-よ・せる【片寄せる】🔗⭐🔉
かた-よ・せる [4] 【片寄せる】 (動サ下一)[文]サ下二 かたよ・す
一方へ寄せる。一方にまとめる。「四辺(アタリ)に散りたる雑籍を―・せつつ/社会百面相(魯庵)」
かた-より【片寄り・偏り】🔗⭐🔉
かた-より [0][4] 【片寄り・偏り】
(1)一方にかたよること。「栄養の―がひどい」
(2)〔物〕 偏光。
(3)(「かたよりに」の形で)ただ一方に寄って。ひたすら。「明日の夕(ヨイ)照らむ月夜は―に今夜(コヨイ)に寄りて/万葉 1072」
かた-よ・る【偏る・片寄る】🔗⭐🔉
かた-よ・る [3] 【偏る・片寄る】 (動ラ五[四])
(1)中心や標準からはずれて一方に寄る。「進路が東に―・る」「―・った考え方」「栄養が―・る」
(2)ある部分にだけ集まって,全体の釣り合いを欠く。「人口が都市に―・る」
(3)一方に味方をする。不公平な扱いをする。「―・った判定」
(4)あるものの方に近づき寄る。「浦野の山に月(ツク)―・るも/万葉 3565」
かた-われ【片割れ】🔗⭐🔉
かた-われ [0][4] 【片割れ】
(1)仲間の一部。「盗賊の―」
(2)器などの割れた一片。また,ひとそろいのものの一部。
(3)分身。「清をおれの―と思ふからだ/坊っちゃん(漱石)」
かたわれ-づき【片割れ月】🔗⭐🔉
かたわれ-づき [4] 【片割れ月】
半月。弓張り月。弦月。
ひら【片・枚】🔗⭐🔉
ひら 【片・枚】 (接尾)
〔「ひら(平)」と同源〕
助数詞。花弁・葉・紙などのような,薄くて幅広く,平らなものを数えるのに用いる。枚(マイ)。「一―の花弁」
へん【片】🔗⭐🔉
へん 【片】 (接尾)
〔促音・撥音のあとに付くときは「ぺん」となる〕
助数詞。物の切れはし,花びらなどを数えるのに用いる。「牡丹散て打かさなりぬ二三―/蕪村句集」
へん-うん【片雲】🔗⭐🔉
へん-うん [0] 【片雲】
ちぎれ雲。一片の雲。一かけらの雲。「―の風にさそはれて漂泊の思ひやまず/奥の細道」
へん-えい【片影】🔗⭐🔉
へん-えい [0] 【片影】
(1)物のわずかな影。姿のほんの一部分。
(2)人の性格などの一面。「父の―を伺わせる」
へん-がん【片岩】🔗⭐🔉
へん-がん [1] 【片岩】
⇒結晶片岩(ケツシヨウヘンガン)
へん-ぐう【片隅】🔗⭐🔉
へん-ぐう [0] 【片隅】
かたすみ。すみ。
へん-げつ【片月】🔗⭐🔉
へん-げつ [1] 【片月】
かたわれ月。弓張り月。弦月。
へん-げん【片言】🔗⭐🔉
へん-げん [0][3] 【片言】
(1)わずかな言葉。ちょっとした言葉。一言。「―隻句」
(2)一方の人の言い分。
へんげん-せきご【片言隻語】🔗⭐🔉
へんげん-せきご [5] 【片言隻語】
ほんのちょっとした言葉。片言隻句。
へん-ご【片語】🔗⭐🔉
へん-ご [1][0] 【片語】
ちょっとした言葉。片言。
かたかな【片仮名】(和英)🔗⭐🔉
かたかな【片仮名】
the square form of kana[the Japanese syllabary].
かたくりこ【片栗粉】(和英)🔗⭐🔉
かたくりこ【片栗粉】
(dogtooth violet) starch.→英和
かたすみ【片隅(に)】(和英)🔗⭐🔉
かたすみ【片隅(に)】
(in) a corner.→英和
かたっぱし【片っ端から】(和英)🔗⭐🔉
かたっぱし【片っ端から】
⇒片端(かたはし).
へんげんせきご【片言隻語】(和英)🔗⭐🔉
へんげんせきご【片言隻語】
a single[every]word;words.
広辞苑+大辞林に「片」で始まるの検索結果。もっと読み込む