複数辞典一括検索+![]()
![]()
いか‐いか・し【厳厳し】🔗⭐🔉
いか‐いか・し【厳厳し】
〔形シク〕
大層いかめしい。たけだけしく強い。
いか・し【厳し】(形ク)🔗⭐🔉
いかし‐ひ【厳し日】🔗⭐🔉
いかし‐ひ【厳し日】
おごそかな日。生日いくひ。
⇒いかし【厳し】
いかし‐ほ【厳し穂・茂し穂】🔗⭐🔉
いかし‐ほ【厳し穂・茂し穂】
よく実のついた稲穂。祝詞、祈年祭「八束穂の―」
⇒いかし【厳し】
いかし‐ほこ【厳し矛】🔗⭐🔉
いかし‐ほこ【厳し矛】
いかめしい矛。〈舒明紀訓注〉
⇒いかし【厳し】
いかし‐みよ【厳し御世】🔗⭐🔉
いかし‐みよ【厳し御世】
盛んな御代。祝詞、平野祭「―に幸さきはへまつりて」
⇒いかし【厳し】
いかつ・い【厳つい】🔗⭐🔉
いかつ・い【厳つい】
〔形〕
いかめしい。きびしい。ごつい。浄瑠璃、心中二つ腹帯「伯母御の―・い返礼に」。「―・い肩」
いかつ‐がま・し【厳つがまし】🔗⭐🔉
いかつ‐がま・し【厳つがまし】
〔形シク〕
いかにもいかめしい。鹿の巻筆「―・しく言へば」
いかつ‐ごえ【厳つ声】‥ゴヱ🔗⭐🔉
いかつ‐ごえ【厳つ声】‥ゴヱ
いかめしい声。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「片寄かたよれと雑色が―」
いかつ‐は・く【厳つ吐く】🔗⭐🔉
いかつ‐は・く【厳つ吐く】
〔自四〕
はげしく言いののしる。浄瑠璃、出世景清「侍畜生大たはけと、―・いてぞ申しける」
○厳つを出すいかつをだす🔗⭐🔉
○厳つを出すいかつをだす
いかめしく力み返す。傾城禁短気「臂捲ひじまくりして喧嘩眼になつていかつを出し」
⇒いか‐つ【厳つ】
いか‐で【如何で・争で】
〔副〕
(イカニテの転)
①(願望)何とかして。竹取物語「―このかぐや姫を得てしがな」
②(疑問)どのようにして。どういうわけで。源氏物語帚木「―、はた、かかりけむ」
③(反語)どうして。竹取物語「―さることなくてはおはしまさむ」
⇒いかで‐か【如何でか・争でか】
いか‐てい【如何体】
どのような様子。いかよう。幸若舞曲、烏帽子折「たとへ―の物なりとも」
いかで‐か【如何でか・争でか】
〔副〕
①(疑問)どうして。竹取物語「家に入り給ひぬるを―聞きけむ」
②(反語)どうして(…することがあろうか)。枕草子104「淑景舎は見たてまつりたりやと問はせ給へば、まだ―」
③(願望)何とかして。拾遺和歌集恋「―と思ふ心のある時はおぼめくさへぞうれしかりける」
⇒いか‐で【如何で・争で】
いかと‐いかと【厳と厳と】
〔副〕
広々と。一説に「如何と如何と」で、「どのようだろうか」の意。万葉集8「―あるわが宿に百枝ももえさし生ふる橘」
いが‐とうめ【伊賀専女】‥タウメ
①狐の異称。神に祭った狐の称。
②人をたばかる媒酌人を、狐にたとえていう語。源氏物語東屋「今更に―にやとつつましくてなむ」
いか‐どっくり【烏賊徳利】
イカの胴に型を入れて、とっくりの形に乾したもの。燗かんをした酒を入れ、イカの味と香りを酒に移す。
いか‐な【如何な】
[一]〔連体〕
どのような。どんな。中華若木詩抄「此の大雪には―園林も一様に白くなるべきぞ」
[二]〔副〕
(否定・反語の語にかかる)どうしても。何としても。いっかな。浮世草子、日本新永代蔵「鋳崩して売りはらふに、―此の銅を買ふ人なし」
⇒いかな‐いかな【如何な如何な】
⇒いかな‐こと【如何な事】
いかな‐いかな【如何な如何な】
「いかな」を強めていう語。決して。どうしてどうして。何の何の。狂言、悪太郎「誰殿がお止めやつても、―止る事では御座らぬ」
⇒いか‐な【如何な】
いかな‐ご【玉筋魚】
イカナゴ科の海産の硬骨魚。体は細長く槍形、全長約25センチメートル。背部は青褐色、下腹部は銀白色。春、小さいのを捕って煮干・佃煮つくだにとする。俗にカマスゴという。夏には砂の中に潜って休眠。北日本に多く、九州まで分布。小女子こうなご。〈[季]春〉
いかなご
 ⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】
いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥
イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。
⇒いかな‐ご【玉筋魚】
いかな‐こと【如何な事】
①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」
②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」
⇒いか‐な【如何な】
いかな・り【如何なり】
〔自ラ変〕
(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」
いかなる【如何なる】
〔連体〕
(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」
いか‐に【如何に】
[一]〔副〕
①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」
②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」
③限度の定めがたいさま。
㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」
㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」
[二]〔感〕
呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」
⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】
⇒いかに‐か【如何にか】
⇒いかに‐して【如何にして】
⇒いかに‐して‐も【如何にしても】
⇒いかに‐せん【如何にせん】
⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】
⇒いかに‐も【如何にも】
⇒いかに‐も‐して【如何にもして】
⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】
⇒如何に申し候
いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥
まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐か【如何にか】
①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」
②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して【如何にして】
①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」
②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して‐も【如何にしても】
①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」
②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐せん【如何にせん】
①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」
②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐ぞや【如何にぞや】
①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」
②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」
③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐も【如何にも】
〔副〕
①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」
②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」
③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」
④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」
⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」
⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」
⇒いか‐に【如何に】
⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】
いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥
イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。
⇒いかな‐ご【玉筋魚】
いかな‐こと【如何な事】
①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」
②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」
⇒いか‐な【如何な】
いかな・り【如何なり】
〔自ラ変〕
(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」
いかなる【如何なる】
〔連体〕
(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」
いか‐に【如何に】
[一]〔副〕
①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」
②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」
③限度の定めがたいさま。
㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」
㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」
[二]〔感〕
呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」
⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】
⇒いかに‐か【如何にか】
⇒いかに‐して【如何にして】
⇒いかに‐して‐も【如何にしても】
⇒いかに‐せん【如何にせん】
⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】
⇒いかに‐も【如何にも】
⇒いかに‐も‐して【如何にもして】
⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】
⇒如何に申し候
いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥
まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐か【如何にか】
①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」
②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して【如何にして】
①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」
②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して‐も【如何にしても】
①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」
②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐せん【如何にせん】
①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」
②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐ぞや【如何にぞや】
①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」
②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」
③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐も【如何にも】
〔副〕
①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」
②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」
③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」
④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」
⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」
⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」
⇒いか‐に【如何に】
 ⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】
いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥
イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。
⇒いかな‐ご【玉筋魚】
いかな‐こと【如何な事】
①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」
②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」
⇒いか‐な【如何な】
いかな・り【如何なり】
〔自ラ変〕
(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」
いかなる【如何なる】
〔連体〕
(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」
いか‐に【如何に】
[一]〔副〕
①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」
②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」
③限度の定めがたいさま。
㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」
㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」
[二]〔感〕
呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」
⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】
⇒いかに‐か【如何にか】
⇒いかに‐して【如何にして】
⇒いかに‐して‐も【如何にしても】
⇒いかに‐せん【如何にせん】
⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】
⇒いかに‐も【如何にも】
⇒いかに‐も‐して【如何にもして】
⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】
⇒如何に申し候
いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥
まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐か【如何にか】
①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」
②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して【如何にして】
①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」
②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して‐も【如何にしても】
①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」
②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐せん【如何にせん】
①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」
②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐ぞや【如何にぞや】
①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」
②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」
③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐も【如何にも】
〔副〕
①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」
②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」
③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」
④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」
⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」
⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」
⇒いか‐に【如何に】
⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】
いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥
イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。
⇒いかな‐ご【玉筋魚】
いかな‐こと【如何な事】
①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」
②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」
⇒いか‐な【如何な】
いかな・り【如何なり】
〔自ラ変〕
(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」
いかなる【如何なる】
〔連体〕
(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」
いか‐に【如何に】
[一]〔副〕
①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」
②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」
③限度の定めがたいさま。
㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」
㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」
[二]〔感〕
呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」
⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】
⇒いかに‐か【如何にか】
⇒いかに‐して【如何にして】
⇒いかに‐して‐も【如何にしても】
⇒いかに‐せん【如何にせん】
⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】
⇒いかに‐も【如何にも】
⇒いかに‐も‐して【如何にもして】
⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】
⇒如何に申し候
いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥
まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐か【如何にか】
①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」
②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して【如何にして】
①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」
②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐して‐も【如何にしても】
①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」
②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐せん【如何にせん】
①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」
②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐ぞや【如何にぞや】
①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」
②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」
③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」
⇒いか‐に【如何に】
いかに‐も【如何にも】
〔副〕
①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」
②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」
③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」
④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」
⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」
⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」
⇒いか‐に【如何に】
いかと‐いかと【厳と厳と】🔗⭐🔉
いかと‐いかと【厳と厳と】
〔副〕
広々と。一説に「如何と如何と」で、「どのようだろうか」の意。万葉集8「―あるわが宿に百枝ももえさし生ふる橘」
いか‐ぼし【厳星】🔗⭐🔉
いか‐ぼし【厳星】
かぶとの鉢の矧はぎ合せの鋲頭の、大形でいかめしいもの。
いか‐め【厳め】🔗⭐🔉
いか‐め【厳め】
いかめしいさま。いかつ。狂言、腰祈「―な、お山伏にならせられて御座るの」
いか‐めし・い【厳めしい】🔗⭐🔉
いか‐めし・い【厳めしい】
〔形〕[文]いかめ・し(シク)
①おごそかで重々しい。いかつい。源氏物語桐壺「いと―・しうその作法したるに」。「―・いお邸やしき」
②はげしい。あらあらしい。源氏物語明石「―・しき雨風いかづちの驚かし侍りつれば」
③盛大である。おおげさである。源氏物語真木柱「儀式いと―・しう二なくて参り給ふ」
④態度が儀式ばっている。堅苦しい。さゝめごと「―・しくも尋ね給ふものかな」
いかもの‐づくり【厳物作り】🔗⭐🔉
いかもの‐づくり【厳物作り】
いかめしく見える作りにした太刀。長覆輪ながふくりん・兵具鋂ひょうぐぐさりの太刀ごしらえなどをいう。
いか‐ら・し【厳らし】🔗⭐🔉
いか‐ら・し【厳らし】
〔形ク〕
いかめしい。たけだけしい。愚管抄3「若く―・き様なる人にて」
いこう【厳う】イカウ🔗⭐🔉
いこう【厳う】イカウ
(イカシの連用形イカクの音便)
⇒いかし3
いずはら【厳原】イヅ‥🔗⭐🔉
いずはら【厳原】イヅ‥
長崎県対馬つしま市の地名。もと宗氏10万石の城下町。対馬の中心地。
いつ【厳・稜威】🔗⭐🔉
いつ【厳・稜威】
①尊厳な威光。威勢の鋭いこと。古事記上「―のをたけび踏みたけびて」
②植物などが威勢よく繁茂すること。
③斎いみ浄められていること。祝詞、神賀詞「―幣の緒結び」
いつ‐かし【厳橿】🔗⭐🔉
いつ‐かし【厳橿】
神威のある、繁茂した樫かしの木。「斎橿」とも書く。古事記下「御諸みもろの―がもと」
いつか・し【厳し】🔗⭐🔉
いつか・し【厳し】
〔形シク〕
(動詞イツ(斎)クから)いかめしく立派である。たっとい。荘重である。源氏物語少女「内の儀式を移して…―・しき御有様なり」
いつく・し【厳し・慈し・美し】🔗⭐🔉
いつく・し【厳し・慈し・美し】
〔形シク〕
①神威がいかめしい。また、威儀がそなわっている。おごそかで立派である。万葉集5「すめ神の―・しき国」。源氏物語若菜上「つぎつぎの御ゆかり―・しきほど」
②神々しく気品があって、うつくしい。今昔物語集30「百日許になりたる女子のいと―・しげなれば」
③(室町時代以降ウツクシと混同)あいらしい。いとしい。日葡辞書「ギョクショク(玉色)。タマノイロ、即ち、イツクシイイロ」
いつくしま【厳島】🔗⭐🔉
いつくしま【厳島】
広島湾南西部の島。日本三景の一つ。面積約30平方キロメートル。その最高所は、標高530メートルの弥山みせん。廿日市はつかいち市に属し島全体が原始林で覆われる。北岸に厳島神社と門前町がある。伊都岐いつき島。宮島。
⇒いつくしま‐えんねん【厳島延年】
⇒いつくしま‐じんじゃ【厳島神社】
⇒いつくしま‐の‐たたかい【厳島の戦】
いつくしま‐えんねん【厳島延年】🔗⭐🔉
いつくしま‐えんねん【厳島延年】
旧暦7月14日、厳島神社で行う延年舞の神事。現在は玉取祭として8月に行う。
⇒いつくしま【厳島】
いつくしま‐じんじゃ【厳島神社】🔗⭐🔉
いつくしま‐じんじゃ【厳島神社】
厳島にある元官幣中社。市杵島姫命いちきしまひめのみことを主神とし、田心姫命たごりひめのみこと・湍津姫命たぎつひめのみことを合祀。社殿は海中に立ち、宝物類には平家寄進のものが多く、大鳥居・朱塗の殿堂・五重塔・千畳閣・能舞台など、国宝・史跡に富む。世界遺産。安芸国一の宮。
厳島神社
提供:NHK
 厳島神社
提供:NHK
⇒いつくしま【厳島】
厳島神社
提供:NHK
⇒いつくしま【厳島】
 厳島神社
提供:NHK
⇒いつくしま【厳島】
厳島神社
提供:NHK
⇒いつくしま【厳島】
いつくしま‐の‐たたかい【厳島の戦】‥タタカヒ🔗⭐🔉
いつくしま‐の‐たたかい【厳島の戦】‥タタカヒ
1555年(弘治1)毛利元就もうりもとなりが、大内義隆を滅ぼした陶晴賢すえはるかたを敗死させた戦い。以後、毛利氏は中国地方に威を振るうようになった。
⇒いつくしま【厳島】
いつ‐ぬさ【厳幣】🔗⭐🔉
いつ‐ぬさ【厳幣】
神事に奉仕する者が頭にかぶる木綿鬘ゆうかずら。祝詞、神賀詞「―の緒結び」
おご・し【厳し】🔗⭐🔉
おご・し【厳し】
〔形シク〕
おごそかである。威力が大きい。持統紀「三百みももはしらの―・しき大徳等ほうしたち」
おごそか【厳か】🔗⭐🔉
おごそか【厳か】
威儀正しく、近寄りにくいさま。いかめしいさま。厳粛。弥勒上生経賛平安初期点「身容、敦粛とオコソカにして」。「―に儀式を執り行う」
から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】🔗⭐🔉
から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】
[一]〔名〕
櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」
唐櫛笥
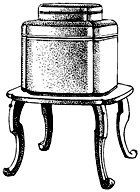 [二]〔枕〕
「明く」にかかる。
[二]〔枕〕
「明く」にかかる。
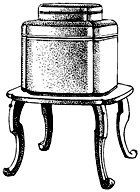 [二]〔枕〕
「明く」にかかる。
[二]〔枕〕
「明く」にかかる。
きびし・い【厳しい】🔗⭐🔉
きびし・い【厳しい】
〔形〕[文]きび・し(シク)
(平安初期にはク活用)
①厳重である。おごそかである。枕草子92「行事の蔵人のいと―・しうもてなして」。「警戒が―・い」
②激しく容赦ない。むごい。大鏡道長「王の―・しうなりなば、世の人いかが堪へむ」。「―・い訓練」「―・く叱る」
③傾斜が急で角だっている。けわしい。長秋詠藻「荒き海―・しき山の中なれど」
④物事の状態や人の表情などが緊張している。「―・い国際情勢」「―・い表情」
⑤はなはだしい。ひどい。「寒さが―・い」
⑥並一通りでない。たいしたものである。金々先生栄花夢「これは―・い。さつまやの源五兵衛ときて居る」
げん【厳】🔗⭐🔉
げん【厳】
(呉音はゴン)
①きびしいこと。「―に言い渡す」
②父に対する尊称。
げん‐い【厳威】‥ヰ🔗⭐🔉
げん‐い【厳威】‥ヰ
おごそかで威光のあること。おごそかな威儀。
げん‐か【厳科】‥クワ🔗⭐🔉
げん‐か【厳科】‥クワ
きびしい罰。
げん‐かい【厳戒】🔗⭐🔉
げん‐かい【厳戒】
厳重に警戒すること。「―を要する」
げん‐かく【厳格】🔗⭐🔉
げん‐かく【厳格】
きびしくただしいこと。ある規則をきびしく守り、いいかげんにしないこと。「―な家風」「―に審査する」
⇒げんかく‐しゅぎ【厳格主義】
げんかく‐しゅぎ【厳格主義】🔗⭐🔉
げんかく‐しゅぎ【厳格主義】
〔哲〕(→)厳粛主義に同じ。
⇒げん‐かく【厳格】
げん‐かん【厳寒】🔗⭐🔉
げん‐かん【厳寒】
冬のきびしい寒さ。〈[季]冬〉
げん‐がん【厳顔】🔗⭐🔉
げん‐がん【厳顔】
おごそかな顔つき。君主などの、いかめしい顔。太平記5「―を犯して道を以て諫め諍ふ」
げん‐ぎ【厳儀】🔗⭐🔉
げん‐ぎ【厳儀】
おごそかな儀式。立派な儀式。
げん‐きょう【厳教】‥ケウ🔗⭐🔉
げん‐きょう【厳教】‥ケウ
①きびしい教え。
②他人の教えの尊敬語。
げん‐きん【厳禁】🔗⭐🔉
げん‐きん【厳禁】
きびしくとめること。厳重な禁止。「火気―」
げん‐くん【厳君】🔗⭐🔉
げん‐くん【厳君】
他人の父の敬称。父君。
げん‐くん【厳訓】🔗⭐🔉
げん‐くん【厳訓】
きびしい訓戒。
げん‐けい【厳刑】🔗⭐🔉
げん‐けい【厳刑】
きびしい刑罰。
げん‐こく【厳酷・厳刻】🔗⭐🔉
げん‐こく【厳酷・厳刻】
むごいほどきびしいさま。「―なる処罰」
げん‐し【厳旨】🔗⭐🔉
げん‐し【厳旨】
①厳命の趣旨。
②他人の趣旨の尊敬語。
げん‐しゅ【厳守】🔗⭐🔉
げん‐しゅ【厳守】
きびしく守ること。「時間―」
げん‐じゅう【厳重】‥ヂユウ🔗⭐🔉
げん‐じゅう【厳重】‥ヂユウ
①⇒げんじょう。
②きびしいこと。「―な警戒」
げん‐しゅく【厳粛】🔗⭐🔉
げん‐しゅく【厳粛】
①おごそかで、心が引きしまるさま。厳格で静粛なこと。「式は―に執り行われた」「―な雰囲気」
②それを真剣に受け取らなければならないさま。厳として動かしがたいこと。「―に受けとめる」「―な事実」
⇒げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】
げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】🔗⭐🔉
げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】
〔哲〕(rigorism)道徳法則を厳格に守る態度。ストア学派のように、義務を至上として欲望をおさえ、快楽や幸福を拒む立場。カントの倫理学では、道徳的意志の動機として幸福や快楽を認めない。厳格主義。リゴリズム。
⇒げん‐しゅく【厳粛】
げん‐しゅん【厳峻】🔗⭐🔉
げん‐しゅん【厳峻】
おごそかできびしいこと。
げん‐しょ【厳暑】🔗⭐🔉
げん‐しょ【厳暑】
きびしい暑さ。
げん‐じょう【厳重】‥ヂヨウ🔗⭐🔉
げん‐じょう【厳重】‥ヂヨウ
おごそかなこと。いかめしいこと。増鏡「臨幸の―なる事も侍らんに参りあへらば」
げん‐しん【厳親】🔗⭐🔉
げん‐しん【厳親】
父親。厳君。厳父。
げん‐せい【厳正】🔗⭐🔉
げん‐せい【厳正】
厳格で公正なこと。「―な審査」
⇒げんせい‐ちゅうりつ【厳正中立】
げんせい‐ちゅうりつ【厳正中立】🔗⭐🔉
げんせい‐ちゅうりつ【厳正中立】
いずれにもかたよらずに、中立の立場を厳守すること。→中立2
⇒げん‐せい【厳正】
げん‐せき【厳責】🔗⭐🔉
げん‐せき【厳責】
きびしく責めること。
げん‐せん【厳選】🔗⭐🔉
げん‐せん【厳選】
厳重な基準によって選ぶこと。「―された商品」
げん‐ぜん【厳然・儼然】🔗⭐🔉
げん‐ぜん【厳然・儼然】
いかめしくおごそかなさま。「―とした態度」「―たる事実」
げん‐そん【厳存】🔗⭐🔉
げん‐そん【厳存】
厳然として存在すること。
げん‐たつ【厳達】🔗⭐🔉
げん‐たつ【厳達】
きびしく通達すること。また、その通達。
げん‐たん【厳探】🔗⭐🔉
げん‐たん【厳探】
きびしくさがすこと。
げん‐とう【厳冬】🔗⭐🔉
げん‐とう【厳冬】
冬の寒さがきびしい頃。〈[季]冬〉。「―期」
げん‐と‐して【厳として・儼として】🔗⭐🔉
げん‐と‐して【厳として・儼として】
おごそかに。犯しがたく。動かしがたく。「―動じない」「事実は―存在する」
げん‐ばつ【厳罰】🔗⭐🔉
げん‐ばつ【厳罰】
きびしい処罰。「―に処する」
げん‐ぴ【厳秘】🔗⭐🔉
げん‐ぴ【厳秘】
きびしく守らねばならない秘密。極秘。「―に付する」
げん‐ぷ【厳父】🔗⭐🔉
げん‐ぷ【厳父】
①きびしい父。
②他人の父の尊敬語。厳君。父君。
⇒げんぷ‐じぼ【厳父慈母】
げん‐ぷう【厳封】🔗⭐🔉
げん‐ぷう【厳封】
厳重に封をすること。厳緘げんかん。
げん‐ふく【厳復】🔗⭐🔉
げん‐ふく【厳復】
(Yan Fu)中国の思想家・学者。福建の人。字は又陵・幾道。清朝末期、英国に留学し、西欧近代思想を翻訳・紹介、知識層に大きな影響をあたえたが、のち伝統擁護を主張。「天演論」(T.H.ハックスリ「進化と倫理」)や「原富」(A.スミス「国富論」)などが代表的翻訳。(1854〜1921)
げんぷ‐じぼ【厳父慈母】🔗⭐🔉
げんぷ‐じぼ【厳父慈母】
厳しい父親と優しく守ってくれる慈しみ深い母親。他人の両親の敬称にも使う。
⇒げん‐ぷ【厳父】
げん‐ぼう【厳貌】‥バウ🔗⭐🔉
げん‐ぼう【厳貌】‥バウ
いかめしい容貌・姿。厳容。
げん‐ぽう【厳法】‥パフ🔗⭐🔉
げん‐ぽう【厳法】‥パフ
きびしいおきて。きびしい法律。
げん‐みつ【厳密】🔗⭐🔉
げん‐みつ【厳密】
こまかい点まで手落ちなくきびしく行うさま。「―な検査」「―に言えば」
げん‐めい【厳命】🔗⭐🔉
げん‐めい【厳命】
きびしい命令。きびしく命令すること。「―を下す」
げん‐めい【厳明】🔗⭐🔉
げん‐めい【厳明】
きびしくて道理に明らかなこと。
げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン🔗⭐🔉
げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン
徳川家綱の諡号しごう。
げん‐よう【厳容】🔗⭐🔉
げん‐よう【厳容】
いかめしいすがた。
げん‐りつ【厳律】🔗⭐🔉
げん‐りつ【厳律】
きびしいおきて。厳重な刑律。
げん‐れい【厳令】🔗⭐🔉
げん‐れい【厳令】
きびしく命令すること。厳命。
ごん‐じょう【厳浄】‥ジヤウ🔗⭐🔉
ごん‐じょう【厳浄】‥ジヤウ
おごそかで汚れのないこと。荘厳で清浄なこと。正法眼蔵辧道話「戒律を―すべしや」
みか・し【厳し】🔗⭐🔉
みか・し【厳し】
〔形ク〕
しおからい。塩分が多い。新撰字鏡4「醎、美加支阿地波比、又加良之」
[漢]厳🔗⭐🔉
厳 字形
 筆順
筆順
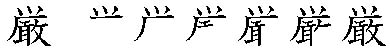 〔
〔 部14画/17画/教育/2423・3837〕
[嚴] 字形
部14画/17画/教育/2423・3837〕
[嚴] 字形
 〔口部17画/20画/5178・536E〕
〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)
〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし
[意味]
①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」
②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」
[解字]
形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。
[下ツキ
威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳
〔口部17画/20画/5178・536E〕
〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)
〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし
[意味]
①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」
②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」
[解字]
形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。
[下ツキ
威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳
 筆順
筆順
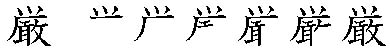 〔
〔 部14画/17画/教育/2423・3837〕
[嚴] 字形
部14画/17画/教育/2423・3837〕
[嚴] 字形
 〔口部17画/20画/5178・536E〕
〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)
〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし
[意味]
①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」
②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」
[解字]
形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。
[下ツキ
威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳
〔口部17画/20画/5178・536E〕
〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)
〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし
[意味]
①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」
②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」
[解字]
形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。
[下ツキ
威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳
広辞苑に「厳」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む