複数辞典一括検索+![]()
![]()
くわ【桑】クハ🔗⭐🔉
くわ【桑】クハ
①クワ科の落葉高木クワ類の総称。ヤマグワおよびその栽培品種がもっとも普通だが、別種のハチジョウグワ、中国産の魯桑ろそうなども栽培され、改良品種も多い。養蚕のために刈りとるから長大なものは少ない。樹皮は淡褐色、葉は深い切れ込みのあるものと全縁のものとある。春、淡黄緑色の単性花を穂状に綴る。雌雄異株、稀に同株。花後、小さい実を結び、熟すれば紫黒色を呈し、味は甘い。材は諸種の用に供し、特に自生樹は硬く、工芸用材として珍重。樹皮の繊維は製紙の原料。殊に葉は養蚕用として重要。四木の一つ。〈[季]春〉。「桑の実」は〈[季]夏〉。万葉集7「母が其の業なりの―すらに」
クワ
撮影:関戸 勇
 クワ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クワ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ②桑色の略。
⇒桑解く
②桑色の略。
⇒桑解く
 クワ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クワ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ②桑色の略。
⇒桑解く
②桑色の略。
⇒桑解く
くわ‐いし【桑石】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐いし【桑石】クハ‥
桑の木目のような文様のある石。
くわ‐いちご【桑苺】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐いちご【桑苺】クハ‥
桑の果実。くわのみ。〈[季]夏〉
くわ‐いろ【桑色】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐いろ【桑色】クハ‥
薄い黄色。桑。
くわ‐えだしゃく【桑枝尺】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐えだしゃく【桑枝尺】クハ‥
(桑枝尺蠖くわえだしゃくとりの略)シャクガ科のガ。翅は褐色で、黒い波のようなすじがある。中形で、開張3.5〜5.5センチメートル。6〜7月に現れる。幼虫は「くわしゃくとり」といい、桑の害虫。
くわ‐か【桑科】クハクワ🔗⭐🔉
くわ‐か【桑科】クハクワ
双子葉植物の一科。新旧両大陸の熱帯地方を中心に約55属1400種、日本に15種ほどが知られる。クワ・アサ・コウゾなどの繊維用植物のほか、ホップ・イチジク・パンノキなど有用植物が多い。
くわ‐かみきり【桑天牛】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐かみきり【桑天牛】クハ‥
カミキリムシ科の甲虫。体長約3〜4センチメートル。黄褐色で、前胸背板に横皺多く、体よりも長い鞭むち状の触角をもつ。幼虫は白色で、鉄砲虫といい、クワ・イチジク・リンゴなどの幹に孔を穿って食害する。
クワカミキリ
撮影:海野和男


くわかわ‐がみ【桑皮紙】クハカハ‥🔗⭐🔉
くわかわ‐がみ【桑皮紙】クハカハ‥
桑皮を原料として漉すいた紙。山梨・長野・静岡県などで産した。そうひし。
くわき【桑木】クハ‥🔗⭐🔉
くわき【桑木】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわき‐げんよく【桑木厳翼】
くわき‐げんよく【桑木厳翼】クハ‥🔗⭐🔉
くわき‐げんよく【桑木厳翼】クハ‥
哲学者。東京の人。京大・東大教授歴任。独・仏・英3国に留学。自由主義的啓蒙家として西洋哲学を普及した。著「哲学概論」「カントと現代の哲学」など。(1874〜1946)
⇒くわき【桑木】
くわ‐きじらみ【桑木虱】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐きじらみ【桑木虱】クハ‥
カメムシ目キジラミ科の昆虫。体長約4ミリメートル、体は黄緑ないし黄赤色、濃色の斑紋があり、翅は白色半透明で黒褐色の小紋がある。若虫は長さ約3ミリメートル、暗褐色で白い綿のような分泌物を被り、桑の葉の裏に寄生して大害を与える。クワノワタムシ。
くわきじらみ


くわ‐こ【桑子】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐こ【桑子】クハ‥
蚕をいう。〈[季]春〉。万葉集12「なかなかに人とあらずは―にもならましものを」
くわ‐ご【桑蚕・野蚕】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐ご【桑蚕・野蚕】クハ‥
①カイコガ科のガ。カイコガに似るが、幼虫は黄褐色。成虫は翅紋の色が濃い。家蚕の原種ともいう。桑の害虫。卵で越年、春季孵化し繭をつくって蛹化し、6〜7月頃羽化。ノガイコ。ヤマガイコ。桑繭。
くわご
 クワゴ
撮影:海野和男
クワゴ
撮影:海野和男
 クワゴ(幼虫)
撮影:海野和男
クワゴ(幼虫)
撮影:海野和男
 ②(→)桑子に同じ。
②(→)桑子に同じ。
 クワゴ
撮影:海野和男
クワゴ
撮影:海野和男
 クワゴ(幼虫)
撮影:海野和男
クワゴ(幼虫)
撮影:海野和男
 ②(→)桑子に同じ。
②(→)桑子に同じ。
くわ‐こき【桑扱き】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐こき【桑扱き】クハ‥
桑樹の枝から新梢および葉を取り去ること。
⇒くわこき‐き【桑扱き器】
くわこき‐き【桑扱き器】クハ‥🔗⭐🔉
くわこき‐き【桑扱き器】クハ‥
刈り取った桑から葉を扱きとる器具。足で台を踏み桑を手に持ち、扱きとる。
⇒くわ‐こき【桑扱き】
くわ‐こぶ【桑瘤】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐こぶ【桑瘤】クハ‥
桑の木に生じた木質の硬いきのこ。サルノコシカケなど。
くわ‐ざけ【桑酒】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐ざけ【桑酒】クハ‥
桑の実で醸造した酒。味醂みりんに似て芳烈。
くわ‐しゃくとり【桑尺蠖】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐しゃくとり【桑尺蠖】クハ‥
クワエダシャクの幼虫の称。桑の害虫。褐色で桑の小枝に類似。どびんわり。
くわ‐しゅ【桑酒】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐しゅ【桑酒】クハ‥
⇒くわざけ
くわ‐しろ【桑代】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐しろ【桑代】クハ‥
中世、桑畑に課した税。
くわ‐ぞめ【桑染】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐ぞめ【桑染】クハ‥
桑の樹の汁で染めること。また、その染めた薄黄色のもの。
⇒くわぞめ‐たび【桑染足袋】
くわぞめ‐たび【桑染足袋】クハ‥🔗⭐🔉
くわぞめ‐たび【桑染足袋】クハ‥
桑染の足袋。江戸前期、貞享・元禄に、もっぱら伊達者だてしゃがはいた。
⇒くわ‐ぞめ【桑染】
くわ‐だか【桑高】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐だか【桑高】クハ‥
江戸時代、桑畑の桑の収穫高に応じて結んだ石高。
くわ‐ちゃ【桑茶】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐ちゃ【桑茶】クハ‥
桑の葉を茶のように製したもの。
くわ‐づけ【桑付け】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐づけ【桑付け】クハ‥
眠りから起きた蚕に初めて桑を与えること。→眠みん
くわ‐つみ【桑摘み】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐つみ【桑摘み】クハ‥
養蚕用に桑の葉を摘みとること。また、その人。〈[季]春〉
⇒くわつみ‐うた【桑摘み唄】
くわつみ‐うた【桑摘み唄】クハ‥🔗⭐🔉
くわつみ‐うた【桑摘み唄】クハ‥
桑摘みの時にうたう唄。「桑は摘みたし梢は高し誰に負われて摘んで取る」の類。
⇒くわ‐つみ【桑摘み】
くわ‐どき【桑時】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐どき【桑時】クハ‥
桑を摘みとって蚕を飼うべき時期。養蚕期。こどき。
○桑解くくわとく
秋の末に株ごとに束ねておいた桑の枝を、春になってほどく。桑ほどく。〈[季]春〉
⇒くわ【桑】
○桑解くくわとく🔗⭐🔉
○桑解くくわとく
秋の末に株ごとに束ねておいた桑の枝を、春になってほどく。桑ほどく。〈[季]春〉
⇒くわ【桑】
くわ‐とり【鍬取り】クハ‥
鍬をとって耕作する人。百姓。
くわな【桑名】クハ‥
三重県北東部の市。もと松平氏10万石の城下町。旧東海道の宮(熱田)からの渡し場。焼蛤やきはまぐり・時雨しぐれ蛤で有名。人口13万9千。
⇒くわな‐の‐とのさま【桑名の殿様】
⇒くわな‐ぼん【桑名盆】
くわな‐の‐とのさま【桑名の殿様】クハ‥
三重県の民謡。江戸末期、木遣きやり歌からお座敷唄となったもの。
⇒くわな【桑名】
くわな‐ぼん【桑名盆】クハ‥
桑名に産する盆。表裏共に黒漆を塗り、錫粉と青漆の併用、または朱漆のみで蕪菁かぶらを描いたもの。
⇒くわな【桑名】
くわ‐の‐かど【桑の門】クハ‥
(「桑門そうもん」の訓読)僧。出家。世捨人。新撰六帖2「からくして入りしは何ぞ―みちの心よそのしるしあれ」
くわ‐の‐はし【桑の箸】クハ‥
桑の材で作った箸。これを常に食事に用いれば中風にかからないという。誹風柳多留拾遺8「遠くおもんぱかつて―で食ひ」
くわのみ‐でら【桑実寺】クハ‥
滋賀県蒲生郡安土町にある天台宗の寺。俗に桑峰薬師ともいう。678年(天武7)定恵の創立という。1576年(天正4)織田信長が再興。
くわ‐の‐ゆみ【桑弓】クハ‥
⇒くわゆみ。平家物語3「―・蓬の矢にて、天地四方を射させらる」
くわ‐はじめ【鍬初め・鍬始め】クハ‥
新年に耕作・土工などを始める儀式。くわぞめ。〈[季]新年〉
くわ‐ばら【桑原】クハ‥
①桑の樹を植えつけた畑。桑田。
②雷鳴の時、落雷を避ける呪文として用いる語。また、一般に忌わしいことを避けるためにも言う。雷神があやまって農家の井戸に落ちた時、農夫は蓋をして天に帰らせなかった。雷神は、自分は桑樹を嫌うから、桑原桑原と唱えるならば再び落ちまいと答えたとの伝説に基づくという。また、死して雷となったと伝える菅公の領地桑原には古来落雷した例がないのに因むともいう。狂言、雷「アア、――」
くわばら【桑原】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわばら‐じつぞう【桑原隲蔵】
⇒くわばら‐たけお【桑原武夫】
くわばら‐じつぞう【桑原隲蔵】クハ‥ザウ
東洋史学者。敦賀生れ。京大教授。東西交渉史・西域の研究に功績がある。著「蒲寿庚の事蹟」「東洋史説苑」など。(1870〜1931)
桑原隲蔵
提供:毎日新聞社
 ⇒くわばら【桑原】
くわばら‐たけお【桑原武夫】クハ‥ヲ
仏文学者・評論家。福井県生れ。隲蔵じつぞうの子。京大卒。スタンダールらの翻訳紹介と広範な評論活動で知られる。また、京大人文科学研究所教授として中江兆民その他の学際的な共同研究を主宰。著「ルソー研究」「文学理論の研究」など。文化勲章。(1904〜1988)→第二芸術
桑原武夫
撮影:田村 茂
⇒くわばら【桑原】
くわばら‐たけお【桑原武夫】クハ‥ヲ
仏文学者・評論家。福井県生れ。隲蔵じつぞうの子。京大卒。スタンダールらの翻訳紹介と広範な評論活動で知られる。また、京大人文科学研究所教授として中江兆民その他の学際的な共同研究を主宰。著「ルソー研究」「文学理論の研究」など。文化勲章。(1904〜1988)→第二芸術
桑原武夫
撮影:田村 茂
 ⇒くわばら【桑原】
くわ‐びら【鍬平】クハ‥
①鍬の、柄を除いた部分。また、そのような形。
②足の、くるぶしから先の部分。足首。東海道名所記「お―出しめされい」
③扁平で土ふまずのない足。鍬平足。扁平足。
くわ‐ぼうき【桑箒・鍬箒】クハバウキ
桑の切株から生える楚すわえを束ねて作った箒。浮世草子、好色産毛「久三郎も気を通り、―持て門はきに出る」
くわ‐まゆ【桑繭】クハ‥
野蚕くわご。また、その繭。〈倭名類聚鈔14〉
くわ‐まよ【桑繭】クハ‥
(上代東国方言)(→)「くわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の新にい―の衣きぬはあれど」
くわ‐むし【桑虫】クハ‥
カイコの異称。〈書言字考節用集〉
くわ‐やき【鍬焼】クハ‥
肉・野菜などを鉄板で焼き、たれで味をつけた料理。昔、野良仕事の合間、野鳥をつかまえ鍬で焼いたことによるという。
くわやま【桑山】クハ‥
近世、大坂天王寺の珊瑚寺から売り出した小粒の丸薬。小児の万病に効くとされた。豊臣の家臣桑山修理太夫が文禄・慶長の役の際に朝鮮から伝えたという。桑山小粒丸。浄瑠璃、心中天の網島「必ず―飲ませて下され」
くわやま【桑山】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】
くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】クハ‥シウ
江戸中期の文人画家。名は嗣燦しさん。字は明夫。和歌山の人。池大雅に兄事。山水画、特に真景図にすぐれる。「絵事鄙言かいじひげん」「玉洲画趣」などの画論書がある。(1746〜1799)
⇒くわやま【桑山】
くわ・ゆ【加ゆ】クハユ
〔他下二〕
⇒くわえる(下一)
くわ‐ゆみ【桑弓】クハ‥
桑で作った弓。男児誕生の時、この弓に蓬よもぎの茎ではいだ矢をつがえて四方を射て立身出世を祝った。くわのゆみ。→桑弧蓬矢そうこほうし
くわ‐よほろ【鍬丁・钁丁】クハ‥
古代、屯倉みやけを耕すために徴発された壮丁。安閑紀「郡こおり毎の―」
く‐わり【区割り】
ものをいくつかのまとまりに分けること。区分くぶん。
クヮルテット
⇒カルテット
くわわ・る【加わる】クハハル
〔自五〕
①ある事物の上に他の事物が添えられる。重なる。ふえる。はなはだしくなる。古今和歌集雑「わび人の住むべきやどと見るなへに嘆き―・る琴の音ぞする」。源氏物語藤裏葉「御封みふ―・り官爵つかさこうぶりなどみな添ひ給ふ」。「寒さが―・る」「圧力が―・る」
②参加する。その一員となる。源氏物語若菜下「―・りたる二人なむ、兵衛づかさの名高き限りを、召したりける」。日葡辞書「ニンジュ(人数)ニクワワル」。「一味に―・る」「打合せに―・る」
クワント【Mary Quant】
イギリスの服飾デザイナー。1961年ミニスカートを発表し、世界中にブームを巻き起こした。(1934〜)
くん
気息を鼻に通じて発する声。においを嗅ぎ、煙にむせびなどする時の声。
くん【君】
①統治者。天子・帝王・諸侯などをいう。
②敬称。
㋐尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。
㋑同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。「加藤―」
くん【訓】
①よむこと。字義を解釈すること。
②漢字を和語にあててよむこと。「人」を「ひと」とよむ類。↔音おん
くん【裙】
①もすそ。
②裙子くんずの略。
くん【葷】
ネギ・ニラ・ショウガなど、臭気の強い、または辛い蔬菜。「不入―酒」
くん【勲】
①君主または国家に尽くした功労。
②勲章の等級に冠して用いる語。「―一等」
くん【薫】
よいかおり。
⇒薫は香を以て自ら焼く
ぐん【軍】
①戦うための集団・組織。陸海空軍の汎称。古今著聞集9「―、野に伏す時は、飛雁列つらを破る」。「―の意向」「―を率いる」
②中国周代の軍隊編制の単位で、師(2500人)を五つ合わせたもの、すなわち1万2500人。天子は6軍、大国は3軍、中国は2軍、小国は1軍を置く。
③明治以後の兵制で、戦時に数個師団をもって構成された軍隊編制の単位。
④スポーツなどのチーム。
ぐん【郡】
①中国で、戦国時代以後、隋・唐まで行われた行政区画の一つ。県の上の単位。後世、府・州の雅称。→県。
②日本の地方行政区画の一つ。律令制では国の下、里(郷)の上の行政区画とし、1878年(明治11)明治政府下では府・県の下の行政単位とされたが、1923年(大正12)廃止。今は地理上の区画。こおり。→国郡里制
ぐん【群】
①むらがり。むれ。あつまり。「―をなす」
②〔数〕(group)一つの集合があって、これを構成する要素(元という)の間に次の四つの条件を満たす一つの算法
⇒くわばら【桑原】
くわ‐びら【鍬平】クハ‥
①鍬の、柄を除いた部分。また、そのような形。
②足の、くるぶしから先の部分。足首。東海道名所記「お―出しめされい」
③扁平で土ふまずのない足。鍬平足。扁平足。
くわ‐ぼうき【桑箒・鍬箒】クハバウキ
桑の切株から生える楚すわえを束ねて作った箒。浮世草子、好色産毛「久三郎も気を通り、―持て門はきに出る」
くわ‐まゆ【桑繭】クハ‥
野蚕くわご。また、その繭。〈倭名類聚鈔14〉
くわ‐まよ【桑繭】クハ‥
(上代東国方言)(→)「くわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の新にい―の衣きぬはあれど」
くわ‐むし【桑虫】クハ‥
カイコの異称。〈書言字考節用集〉
くわ‐やき【鍬焼】クハ‥
肉・野菜などを鉄板で焼き、たれで味をつけた料理。昔、野良仕事の合間、野鳥をつかまえ鍬で焼いたことによるという。
くわやま【桑山】クハ‥
近世、大坂天王寺の珊瑚寺から売り出した小粒の丸薬。小児の万病に効くとされた。豊臣の家臣桑山修理太夫が文禄・慶長の役の際に朝鮮から伝えたという。桑山小粒丸。浄瑠璃、心中天の網島「必ず―飲ませて下され」
くわやま【桑山】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】
くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】クハ‥シウ
江戸中期の文人画家。名は嗣燦しさん。字は明夫。和歌山の人。池大雅に兄事。山水画、特に真景図にすぐれる。「絵事鄙言かいじひげん」「玉洲画趣」などの画論書がある。(1746〜1799)
⇒くわやま【桑山】
くわ・ゆ【加ゆ】クハユ
〔他下二〕
⇒くわえる(下一)
くわ‐ゆみ【桑弓】クハ‥
桑で作った弓。男児誕生の時、この弓に蓬よもぎの茎ではいだ矢をつがえて四方を射て立身出世を祝った。くわのゆみ。→桑弧蓬矢そうこほうし
くわ‐よほろ【鍬丁・钁丁】クハ‥
古代、屯倉みやけを耕すために徴発された壮丁。安閑紀「郡こおり毎の―」
く‐わり【区割り】
ものをいくつかのまとまりに分けること。区分くぶん。
クヮルテット
⇒カルテット
くわわ・る【加わる】クハハル
〔自五〕
①ある事物の上に他の事物が添えられる。重なる。ふえる。はなはだしくなる。古今和歌集雑「わび人の住むべきやどと見るなへに嘆き―・る琴の音ぞする」。源氏物語藤裏葉「御封みふ―・り官爵つかさこうぶりなどみな添ひ給ふ」。「寒さが―・る」「圧力が―・る」
②参加する。その一員となる。源氏物語若菜下「―・りたる二人なむ、兵衛づかさの名高き限りを、召したりける」。日葡辞書「ニンジュ(人数)ニクワワル」。「一味に―・る」「打合せに―・る」
クワント【Mary Quant】
イギリスの服飾デザイナー。1961年ミニスカートを発表し、世界中にブームを巻き起こした。(1934〜)
くん
気息を鼻に通じて発する声。においを嗅ぎ、煙にむせびなどする時の声。
くん【君】
①統治者。天子・帝王・諸侯などをいう。
②敬称。
㋐尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。
㋑同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。「加藤―」
くん【訓】
①よむこと。字義を解釈すること。
②漢字を和語にあててよむこと。「人」を「ひと」とよむ類。↔音おん
くん【裙】
①もすそ。
②裙子くんずの略。
くん【葷】
ネギ・ニラ・ショウガなど、臭気の強い、または辛い蔬菜。「不入―酒」
くん【勲】
①君主または国家に尽くした功労。
②勲章の等級に冠して用いる語。「―一等」
くん【薫】
よいかおり。
⇒薫は香を以て自ら焼く
ぐん【軍】
①戦うための集団・組織。陸海空軍の汎称。古今著聞集9「―、野に伏す時は、飛雁列つらを破る」。「―の意向」「―を率いる」
②中国周代の軍隊編制の単位で、師(2500人)を五つ合わせたもの、すなわち1万2500人。天子は6軍、大国は3軍、中国は2軍、小国は1軍を置く。
③明治以後の兵制で、戦時に数個師団をもって構成された軍隊編制の単位。
④スポーツなどのチーム。
ぐん【郡】
①中国で、戦国時代以後、隋・唐まで行われた行政区画の一つ。県の上の単位。後世、府・州の雅称。→県。
②日本の地方行政区画の一つ。律令制では国の下、里(郷)の上の行政区画とし、1878年(明治11)明治政府下では府・県の下の行政単位とされたが、1923年(大正12)廃止。今は地理上の区画。こおり。→国郡里制
ぐん【群】
①むらがり。むれ。あつまり。「―をなす」
②〔数〕(group)一つの集合があって、これを構成する要素(元という)の間に次の四つの条件を満たす一つの算法 が規定されているとき、この集合を群という。(ア)この集合の二つの元aとbに対してa
が規定されているとき、この集合を群という。(ア)この集合の二つの元aとbに対してa bもまたこの集合の元である。(イ)結合律a
bもまたこの集合の元である。(イ)結合律a (b
(b c)=(a
c)=(a b)
b) cが成り立つ。(ウ)単位元(すべての元aに対してe
cが成り立つ。(ウ)単位元(すべての元aに対してe a=a
a=a e=aが成り立つような元e)が含まれている。(エ)逆元(元aに対しa
e=aが成り立つような元e)が含まれている。(エ)逆元(元aに対しa x=x
x=x a=eが成り立つような元x)が含まれている。
⇒群を抜く
くん‐い【君位】‥ヰ
天皇の位。君主の位。
くん‐い【勲位】‥ヰ
①勲等と位階。
②勲等。令制では12等、明治以降は8等に定められた。
ぐん‐い【軍医】
軍隊で、傷病兵の診察・治療および軍陣医学・軍陣衛生をつかさどる武官。桜井忠温、肉弾「―は死傷者収容の為に屡しばしば危険を冒して」
⇒ぐんい‐そうかん【軍医総監】
くん‐いく【訓育】
①教え育てること。「児童を―する」
②感情と意志とを陶冶とうやして望ましい性格を形成する教育作用。躾しつけ、または徳育と同義に解される場合も多い。
くんいく【葷粥・獯鬻】
周代における北狄ほくてきの名称。玁狁けんいんとも呼ばれ、戦国・秦・漢の匈奴きょうどの祖に当たるともいう。
くん‐いく【薫育】
徳をもって人を導き育てること。薫陶化育。
ぐんい‐そうかん【軍医総監】
旧陸海軍で、軍医の最高の階級。陸軍では1897年(明治30)以前は少将相当官、以後は中将相当官。1937年(昭和12)より軍医中将と改称。次位は軍医監(大佐のち少将相当官)、第3位は一等軍医正。
⇒ぐん‐い【軍医】
ぐん‐いん【郡院】‥ヰン
(→)郡家ぐうけに同じ。
ぐん‐えい【軍営】
軍隊の営所。兵営。陣営。
ぐん‐えき【軍役】
(グンヤクとも)
①封建制下、武士が主君に対して負う軍事上の負担。
②戦時における夫役ぶやく。軍隊の服役。
③戦争。戦役。
くんえ‐こう【薫衣香】‥カウ
⇒くのえこう
くん‐えん【薫煙】
たきもののよい香りの煙。
くん‐えん【燻煙】
いぶすこと。炎の出ないように物を燃やして煙を多く出すこと。
⇒くんえん‐ざい【燻煙剤】
くんえん‐ざい【燻煙剤】
加熱により有効成分を煙状に浮遊させ、病虫害を防除する薬剤。主に温室などの施設栽培や倉庫などで用いる。蚊取り線香もこの一種。
⇒くん‐えん【燻煙】
ぐん‐おう【郡王】‥ワウ
中国の封爵の名称。皇族に与えられることが多く、明・清では親王の下に位した爵位。
くん‐おん【君恩】
君主のめぐみ。君主の恩。
くん‐か【君家】
君主の家。主君の家。
くん‐か【訓化】‥クワ
教訓感化すること。教え導くこと。
くん‐か【薫化】‥クワ
徳をもってよい方に導くこと。
ぐん‐か【軍靴】‥クワ
軍人用の靴。「―に踏みにじられる」
ぐん‐か【軍歌】
軍隊で、兵の士気を高揚させるための歌。また俗に、軍隊生活を歌った歌謡曲。
ぐん‐か【群下】
多くの臣下。群臣。
ぐん‐が【軍衙】
軍務を取り扱う役所。
ぐん‐が【郡衙】
①郡司の庁。
②郡役所。
くん‐かい【訓戒・訓誡】
教えさとし、いましめること。「―を垂れる」
くん‐かい【訓解】
字句・文章をときあかすこと。
くん‐かい【訓誨】‥クワイ
さとし教えること。
ぐん‐かく【軍拡】‥クワク
軍備拡張の略。↔軍縮
ぐん‐かく【群鶴】
むれをなす鶴。「―文様」
ぐん‐がく【軍学】
用兵戦術を研究する学問。中国では六韜りくとう・三略・孫子・呉子の兵書を基礎とし、日本では近世に各派を生じ、甲州流を先駆とし、越後流・北条流・山鹿流・長沼流・楠木流などがあった。兵学。兵法。
⇒ぐんがく‐しゃ【軍学者】
ぐん‐がく【軍楽】
軍隊の士気をふるいたたせるためや式典の際に演奏する音楽。楽器編成は管楽器と打楽器とが主体。
⇒ぐんがく‐たい【軍楽隊】
ぐんがく‐しゃ【軍学者】
軍学に長じた人。兵法学者。
⇒ぐん‐がく【軍学】
ぐんがく‐たい【軍楽隊】
軍楽を奏する楽隊。
⇒ぐん‐がく【軍楽】
くん‐かだ【訓伽陀】
(訓読する偈げの意)仏教歌謡。声明しょうみょうのうち、和文の伽陀の総称。四句形式のものが多い。→偈
くん‐がな【訓仮名】
万葉仮名のうち、漢字本来の意味とは無関係に漢字の訓を日本語の音節に当てたもの。「懐なつかし」を「名津蚊為」「夏樫」と書く類。字訓仮名。↔音仮名
ぐん‐かん【軍官】‥クワン
軍事をつかさどる官吏。武官。
ぐん‐かん【軍監】
⇒ぐんげん
ぐん‐かん【軍艦】
①水上の戦闘に従事する艦艇。
②旧海軍における艦艇の類別の一つ。戦艦・巡洋艦・航空母艦・潜水母艦・海防艦・砲艦などで、駆逐艦・潜水艦・特務艦などとは区別する。
⇒ぐんかん‐き【軍艦旗】
⇒ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】
⇒ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
⇒ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】
⇒ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
⇒ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
ぐんかん‐き【軍艦旗】
軍艦が艦尾に掲揚する旗。旧海軍では16条の旭日旗。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐん‐かんく【軍管区】‥クワン‥
旧陸軍で、日本内地を分けた際の各管轄区域。1940年(昭和15)には東部・中部・西部・北部の4軍管区に分け、司令官の下に各師団を統轄。
ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】‥サウ‥
1857年(安政4)江戸幕府が軍艦操縦教授のため江戸の築地の講武所内に設置した機関。66年(慶応2)海軍所と改称。翌年横浜の海軍伝習所を吸収。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
ペリカン目グンカンドリ科の鳥の総称。鵜うに似た全体黒色の大きな海鳥。翼を広げると1メートルを超える。雄は喉の裸出部が赤い。尾羽は長く燕の尾のように二つに分かれる。飛ぶ力が強く、熱帯地方の海に群棲して魚類を捕食。オオグンカンドリなど世界に5種あり、日本には稀に迷いこむ。
おおぐんかんどり(雄)
a=eが成り立つような元x)が含まれている。
⇒群を抜く
くん‐い【君位】‥ヰ
天皇の位。君主の位。
くん‐い【勲位】‥ヰ
①勲等と位階。
②勲等。令制では12等、明治以降は8等に定められた。
ぐん‐い【軍医】
軍隊で、傷病兵の診察・治療および軍陣医学・軍陣衛生をつかさどる武官。桜井忠温、肉弾「―は死傷者収容の為に屡しばしば危険を冒して」
⇒ぐんい‐そうかん【軍医総監】
くん‐いく【訓育】
①教え育てること。「児童を―する」
②感情と意志とを陶冶とうやして望ましい性格を形成する教育作用。躾しつけ、または徳育と同義に解される場合も多い。
くんいく【葷粥・獯鬻】
周代における北狄ほくてきの名称。玁狁けんいんとも呼ばれ、戦国・秦・漢の匈奴きょうどの祖に当たるともいう。
くん‐いく【薫育】
徳をもって人を導き育てること。薫陶化育。
ぐんい‐そうかん【軍医総監】
旧陸海軍で、軍医の最高の階級。陸軍では1897年(明治30)以前は少将相当官、以後は中将相当官。1937年(昭和12)より軍医中将と改称。次位は軍医監(大佐のち少将相当官)、第3位は一等軍医正。
⇒ぐん‐い【軍医】
ぐん‐いん【郡院】‥ヰン
(→)郡家ぐうけに同じ。
ぐん‐えい【軍営】
軍隊の営所。兵営。陣営。
ぐん‐えき【軍役】
(グンヤクとも)
①封建制下、武士が主君に対して負う軍事上の負担。
②戦時における夫役ぶやく。軍隊の服役。
③戦争。戦役。
くんえ‐こう【薫衣香】‥カウ
⇒くのえこう
くん‐えん【薫煙】
たきもののよい香りの煙。
くん‐えん【燻煙】
いぶすこと。炎の出ないように物を燃やして煙を多く出すこと。
⇒くんえん‐ざい【燻煙剤】
くんえん‐ざい【燻煙剤】
加熱により有効成分を煙状に浮遊させ、病虫害を防除する薬剤。主に温室などの施設栽培や倉庫などで用いる。蚊取り線香もこの一種。
⇒くん‐えん【燻煙】
ぐん‐おう【郡王】‥ワウ
中国の封爵の名称。皇族に与えられることが多く、明・清では親王の下に位した爵位。
くん‐おん【君恩】
君主のめぐみ。君主の恩。
くん‐か【君家】
君主の家。主君の家。
くん‐か【訓化】‥クワ
教訓感化すること。教え導くこと。
くん‐か【薫化】‥クワ
徳をもってよい方に導くこと。
ぐん‐か【軍靴】‥クワ
軍人用の靴。「―に踏みにじられる」
ぐん‐か【軍歌】
軍隊で、兵の士気を高揚させるための歌。また俗に、軍隊生活を歌った歌謡曲。
ぐん‐か【群下】
多くの臣下。群臣。
ぐん‐が【軍衙】
軍務を取り扱う役所。
ぐん‐が【郡衙】
①郡司の庁。
②郡役所。
くん‐かい【訓戒・訓誡】
教えさとし、いましめること。「―を垂れる」
くん‐かい【訓解】
字句・文章をときあかすこと。
くん‐かい【訓誨】‥クワイ
さとし教えること。
ぐん‐かく【軍拡】‥クワク
軍備拡張の略。↔軍縮
ぐん‐かく【群鶴】
むれをなす鶴。「―文様」
ぐん‐がく【軍学】
用兵戦術を研究する学問。中国では六韜りくとう・三略・孫子・呉子の兵書を基礎とし、日本では近世に各派を生じ、甲州流を先駆とし、越後流・北条流・山鹿流・長沼流・楠木流などがあった。兵学。兵法。
⇒ぐんがく‐しゃ【軍学者】
ぐん‐がく【軍楽】
軍隊の士気をふるいたたせるためや式典の際に演奏する音楽。楽器編成は管楽器と打楽器とが主体。
⇒ぐんがく‐たい【軍楽隊】
ぐんがく‐しゃ【軍学者】
軍学に長じた人。兵法学者。
⇒ぐん‐がく【軍学】
ぐんがく‐たい【軍楽隊】
軍楽を奏する楽隊。
⇒ぐん‐がく【軍楽】
くん‐かだ【訓伽陀】
(訓読する偈げの意)仏教歌謡。声明しょうみょうのうち、和文の伽陀の総称。四句形式のものが多い。→偈
くん‐がな【訓仮名】
万葉仮名のうち、漢字本来の意味とは無関係に漢字の訓を日本語の音節に当てたもの。「懐なつかし」を「名津蚊為」「夏樫」と書く類。字訓仮名。↔音仮名
ぐん‐かん【軍官】‥クワン
軍事をつかさどる官吏。武官。
ぐん‐かん【軍監】
⇒ぐんげん
ぐん‐かん【軍艦】
①水上の戦闘に従事する艦艇。
②旧海軍における艦艇の類別の一つ。戦艦・巡洋艦・航空母艦・潜水母艦・海防艦・砲艦などで、駆逐艦・潜水艦・特務艦などとは区別する。
⇒ぐんかん‐き【軍艦旗】
⇒ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】
⇒ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
⇒ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】
⇒ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
⇒ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
ぐんかん‐き【軍艦旗】
軍艦が艦尾に掲揚する旗。旧海軍では16条の旭日旗。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐん‐かんく【軍管区】‥クワン‥
旧陸軍で、日本内地を分けた際の各管轄区域。1940年(昭和15)には東部・中部・西部・北部の4軍管区に分け、司令官の下に各師団を統轄。
ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】‥サウ‥
1857年(安政4)江戸幕府が軍艦操縦教授のため江戸の築地の講武所内に設置した機関。66年(慶応2)海軍所と改称。翌年横浜の海軍伝習所を吸収。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
ペリカン目グンカンドリ科の鳥の総称。鵜うに似た全体黒色の大きな海鳥。翼を広げると1メートルを超える。雄は喉の裸出部が赤い。尾羽は長く燕の尾のように二つに分かれる。飛ぶ力が強く、熱帯地方の海に群棲して魚類を捕食。オオグンカンドリなど世界に5種あり、日本には稀に迷いこむ。
おおぐんかんどり(雄)
 グンカンドリ
提供:OPO
グンカンドリ
提供:OPO
 ⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。若年寄(のち老中)に属し、海陸の警衛、艦船の製造、軍艦の操練などをつかさどった。1859年(安政6)設置。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
行進曲名。鳥山啓作詞・瀬戸口藤吉作曲の軍歌「軍艦」(1897年作)を、1900年、瀬戸口がさらに行進曲に編曲したもの。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
羅紗の一種。厚地で保温力に富むことから、外套、各種の制服などに用いられた。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
くん‐き【勲記】
叙勲者に勲章とともに与えられる証書。
くん‐ぎ【訓義】
漢字の読みと意味。「―未詳」
ぐん‐き【軍気】
軍隊の意気。士気。兵気。
ぐん‐き【軍紀】
軍隊の風紀と規律。
ぐん‐き【軍記】
①戦争の話を記した書物。軍書。
②軍記物・軍記物語の略。
⇒ぐんき‐もの【軍記物】
⇒ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
⇒ぐんき‐よみ【軍記読み】
ぐん‐き【軍旗】
①軍陣で主将の存在を示す旗。
②軍隊の表章とする旗。旧日本陸軍では歩兵と騎兵の連隊に天皇が親授し、大日章に16条の光線を描き、竿頭に3面の金色菊花章を飾り、紫の総ふさで3方を縁取ったもの。連隊旗。
⇒ぐんき‐さい【軍旗祭】
ぐん‐き【軍器】
軍用の器具。兵器。
ぐん‐き【軍毅】
軍団の将。続日本紀36「国司、―」
ぐん‐き【軍機】
軍事上の機密。「―漏洩ろうえい」
⇒ぐんき‐しょ【軍機処】
⇒ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
⇒ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】
ぐん‐き【群起】
むらがり立つこと。
ぐん‐ぎ【軍議】
軍事上の評議。
ぐん‐ぎ【群疑】
①多くの人の疑うこと。
②多くの疑問。
ぐん‐ぎ【群議】
多くの人の議論。衆議。
ぐんき‐さい【軍旗祭】
旧陸軍の連隊で、軍旗を親授された記念日に行なった祝典。
⇒ぐん‐き【軍旗】
ぐんき‐しょ【軍機処】
清朝しんちょうの最高政治機関。正式には弁理軍機処。軍事上の機務、後には一般行政上の枢機をも掌握した。内閣大学士および六部尚書侍郎の中から軍機大臣4〜6名を任命。1729年創設。もと臨時的機関であったが、19世紀初め法制化された。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
軍機処を構成する官僚。宰相に相当する。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】‥ハフ
軍事上の秘密保護を目的とした法律。秘密の種類・範囲は陸海軍大臣の命令で定めることができた。1899年(明治32)制定。1937年(昭和12)に大改正。45年廃止。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐もの【軍記物】
①(→)軍記物語に同じ。
②江戸時代に出た小説の一種。軍いくさに関する事跡を興味あるように実録と空想とをまじえて書いたもの。絵本太閤記など。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
合戦を主として時代の展開を写した叙事詩的文学。鎌倉時代に多く作られ、保元物語・平治物語・平家物語・太平記などがある。武将の個人的生活を主題とした義経記ぎけいきや曾我物語を含めることもある。主として和漢混淆体。軍記物。戦記物語。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐん‐きょ【群居】
むらがり集まっていること。群れをつくって住んでいること。「海辺に―する生物」
くん‐ぎょう【勲業】‥ゲフ
勲功ある事業。功業。
ぐんき‐よみ【軍記読み】
軍記物を講釈すること。また、その人。
⇒ぐん‐き【軍記】
クングール【Kungur】
中国、新疆ウイグル自治区の西部、パミール高原の東部に位置する高峰。1981年イギリス隊が初登頂。標高7719メートル。コングール。
くん‐くん
①においを嗅ぐために鼻で小刻みに息を吸う音。
②犬が甘えたり何事かを訴えたりする弱い鳴き声。「子犬が―と鳴く」
ぐん‐ぐん
〔副〕
力強く物事が行われるさま。変化してゆく度合が大きいさま。「背丈が―伸びる」「差を―縮める」
ぐん‐け【郡家】
⇒ぐうけ
ぐん‐けい【軍鶏】
シャモのこと。
ぐん‐けい【群系】
(formation)生態学で生物の群集、特に植物群落を分類する単位の一つ。気候や地形などが類似している所には、生活型の類似した生物から成る群集が見出されるので、植物の相観やおもな生物の種類を基準として群系を分類する。例えば中央アジアの草原の生物群集と北アメリカの草原の生物群集とは類似し、ともに温帯草原群系とされる。植物群系。
ぐん‐けいほう【軍刑法】‥ハフ
陸軍刑法と海軍刑法との併称。
くん‐けん【君権】
君主の権力。
くん‐げん【訓言】
いましめの言葉。訓辞。
ぐん‐けん【軍犬】
軍隊で、連絡・警戒・捜索などに使う犬。軍用犬。
ぐん‐げん【軍監】
古代、鎮守府および征夷使の第三等官。副将軍の次の官。ぐんかん。
ぐん‐げん【群言】
多くの人のことば。
ぐんけん‐せいど【郡県制度】
中国の地方行政制度。春秋戦国から秦代にかけて、全国を郡・県などの行政区画に分け、地方官を選任して行政を執行させた。↔封建制度1。→郡国制
くん‐こ【訓詁】
(「詁」は古言を解く意)字句の解釈。蒙求抄1「―は注をしたと云ふ心ぞ」
⇒くんこ‐がく【訓詁学】
ぐん‐こ【軍戸】
明代、軍籍に編入された戸。衛所制度により世襲的に軍務に服役させ、税役を免除した。
ぐん‐こ【軍袴】
(旧陸軍用語)軍服のズボン。
ぐん‐こ【軍鼓】
戦陣で用いる太鼓。陣太鼓など。
くん‐こう【君公】
きみ。主君。君主。
くん‐こう【君侯】
武士が、その仕える諸侯を呼ぶ称。
くん‐こう【焄蒿】‥カウ
(「焄」はこうばしくにおう意、「蒿」は蒸しのぼる意)香気のたちかおること。
⇒くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】
くん‐こう【勲功】
国家または君主に尽くした功労。いさお。てがら。「―を立てる」
くん‐こう【薫香】‥カウ
よいかおりを立てるため、くゆらす香料。たきもの。
ぐん‐こう【軍功】
戦争における功績。いくさの手柄。
ぐん‐こう【軍港】‥カウ
艦隊および軍艦の根拠地として、特別の設備のある港湾。日本では明治期に、横須賀・呉・佐世保・舞鶴を軍港とし、鎮守府が置かれた。国木田独歩、苦悶の叫「桟橋は流石さすが―丈けありて立派なものなり」→要港
ぐん‐こう【群口】
多くの人のことば。
ぐん‐こう【群行】‥カウ
①大勢集まって行くこと。
②斎宮いつきのみやが野の宮で潔斎を終えて9月に伊勢へ下向すること。
ぐん‐ごう【群豪】‥ガウ
多くの豪傑。群雄。
くんごう‐こく【君合国】‥ガフ‥
(→)同君連合に同じ。
くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】‥カウ‥サウ
香気がたちかおり、人の心を恐れおののかせる意。鬼神の気を形容する語。
⇒くん‐こう【焄蒿】
くんこ‐がく【訓詁学】
①漢代および唐代に、経けいの意義を解釈することを専らとした学問。漢代は経書の蒐集と訓詁とに力を入れ、唐代に大成。注疏学。
②一般に、経典けいてんの訓詁注釈を主とする学。
⇒くん‐こ【訓詁】
くん‐こく【君国】
①君主と国家。
②君主の統治する国。
くん‐こく【訓告】
教え告げること。いましめ告げること。「―処分」
ぐん‐こく【軍国】
①軍隊と国家。軍事と国政。
②戦争をしている国。
③軍事を主な政策とする国家。
⇒ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
国の政治・経済・法律・教育などの政策・組織を戦争のために準備し、対外進出で国威を高めようと考える立場。ミリタリズム。木下杢太郎、地下一尺集「―の外に衆生の心を統一せしむるに足る巨大なる磁石はないのかしらむ」
⇒ぐん‐こく【軍国】
ぐんこく‐せい【郡国制】
漢の高祖が採用した封建・郡県併用の地方制度。同族・功臣を分封した国を置く一方、直轄支配地には郡県を設けた。
くん‐さい【捃採】
(「捃」は拾う意)拾いとること。転じて、書物の要所を抜き集めること。捃摭くんせき。
くん‐さい【葷菜】
においの強い野菜。ネギ・ニラ・ニンニクの類。
くんさ・る
〔他四〕
「下さる」の訛。俚言集覧「一番とまつて―・るなら」
ぐん‐さん【群参】
むらがって伺候すること。群をなして参詣すること。源平盛衰記1「結縁―の道俗は歓喜の袖をしぼる」
ぐん‐ざん【群山】
多くの山。むらがりあつまる山々。むらやま。
ぐん‐さん‐ふくごうたい【軍産複合体】‥ガフ‥
(military-industry complex)一国の軍事力・軍部が国内の産業経済上の利益に大きく支えられている体制。一般に軍部と軍需産業との密接な結びつきをいう。アイゼンハワーの用語。産軍複合体。
くん‐し【君子】
①高い身分の人。
②人格が立派な人。徳が高くて品位のそなわった人。品位の高い人。人格者。「聖人―」
③梅・竹・蘭・菊の異称。四君子。
④[周敦頤「蓮、花之君子者也」](画題)文人画で蓮華を描くもの。君子花。
⑤妻が夫を指していう語。
⇒くんし‐こく【君子国】
⇒くんし‐じん【君子人】
⇒くんし‐ひょうへん【君子豹変】
⇒くんし‐らん【君子蘭】
⇒君子の過ちは日月の食の如し
⇒君子の九思
⇒君子の三畏
⇒君子の三楽
⇒君子の徳は風
⇒君子の交わりは淡きこと水の如し
⇒君子は危うきに近寄らず
⇒君子は器ならず
⇒君子は三端を避く
⇒君子は周して比せず、小人は比して周せず
⇒君子は人の美を成す
⇒君子は独を慎む
⇒君子は豹変す
⇒君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず
⇒君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
くん‐し【薫紙】
香料をしみこませた紙。
くん‐じ【訓示】
①教え示すこと。
②年齢・地位などの上の者が下の者に対して教え示すこと。また、その教え。「―を垂れる」
⇒くんじ‐きてい【訓示規定】
くん‐じ【訓辞】
教えいましめる言葉。「校長の―」
ぐん‐し【軍士】
①兵士。兵。
②(→)軍師1に同じ。
ぐん‐し【軍使】
戦闘継続中、一方の交戦者の命により敵軍に赴く使者。
ぐん‐し【軍師】
①主将に属して、軍機をつかさどり謀略をめぐらす人。軍士。軍司。
②(比喩的に)巧みに策略・手段をめぐらす人。
ぐん‐し【群司】
多くの役人。群吏。
ぐん‐じ【軍事】
軍隊・兵備・戦争などに関する事柄。軍務に関する事柄。「―大国」「―力」
⇒ぐんじ‐か【軍事化】
⇒ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】
⇒ぐんじ‐こうどう【軍事行動】
⇒ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
⇒ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】
⇒ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】
⇒ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
⇒ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
⇒ぐんじ‐ふうさ【軍事封鎖】
⇒ぐんじ‐もくひょう‐しゅぎ【軍事目標主義】
⇒ぐんじ‐ゆうびん【軍事郵便】
⇒ぐんじ‐ゆそう【軍事輸送】
ぐんじ【軍持】‥ヂ
〔仏〕(梵語kuṇḍikā)僧尼の持つ水瓶すいびょう。転じて、瓶かめの異称。太平記37「尋常の寒梅樹折れて―に上れば」
ぐん‐じ【郡司】
①律令時代の地方行政官。国司の下にあって郡を治めた。地方の有力者から任命し、大領・少領・主政・主帳の四等官から成る。こおりのみやつこ。
②郡司1のうち大領・少領をいう。→郡領。
⇒ぐんじ‐めし【郡司召】
ぐんじ【郡司】
姓氏の一つ。
⇒ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
⇒ぐんじ‐まさかつ【郡司正勝】
くんじ‐いた・し【屈じ甚し】
〔形ク〕
心が晴れずふさぐ。元気がない。くしいたし。くっしいたし。源氏物語少女「胸のみふたがりて物なども見入られず、―・くて文も読までながめ臥し給へるを」
ぐんじ‐か【軍事化】‥クワ
国が外交政策の立案・遂行に当たって、安全保障の見地から軍事力・軍事的手段に強く依拠する傾向。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんじ‐きてい【訓示規定】
〔法〕もっぱら裁判所または行政庁に対する命令の性質をもち、これに反してもその行為の法的効力に影響がないとされる規定。↔効力規定
⇒くん‐じ【訓示】
ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】‥ケウ‥
1925年(大正14)より中等程度以上の男子学校に陸軍現役将校を配属して行なった軍事に関する訓練。45年(昭和20)廃止。学校教練。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんし‐きん【軍資金】
①軍事に必要な資金。
②(比喩的に)計画遂行に要する資金。
ぐんじ‐こうどう【軍事行動】‥カウ‥
国家が兵力を以てする一切の行動。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんし‐こく【君子国】
[淮南子墜形訓「東方に君子の国有り」]風俗が善良で礼儀の正しい国。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
①(→)軍法会議に同じ。
②戦争犯罪人を裁くための法廷。→国際軍事裁判。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】‥ヰン
重要軍務について天皇の諮詢しじゅんに応じた機関。1903年(明治36)設置、45年(昭和20)廃止。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
軍人・開拓者。海軍大尉。江戸生れ。幕臣の子。幸田露伴・成友の兄。千島開拓のため、1893年(明治26)報効義会を組織し、占守島しゅむしゅとうに移住。日露戦争に従軍、のち義勇艦隊を組織して海事・国防思想を普及。(1860〜1924)
⇒ぐんじ【郡司】
くんし‐じん【君子人】
徳行高く、君子ともいうべき人。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】‥リヤウ
敵国または他国の領土を武力で占領すること。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
敵地に入り込んで軍事上の探偵をするもの。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くん‐しつ【燻室】
魚・獣肉の燻製を作るため燻蒸する室。
ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
2国またはそれ以上の諸国間に締結される軍事に関する同盟。→攻守同盟。
⇒ぐん‐じ【軍事】
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。若年寄(のち老中)に属し、海陸の警衛、艦船の製造、軍艦の操練などをつかさどった。1859年(安政6)設置。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
行進曲名。鳥山啓作詞・瀬戸口藤吉作曲の軍歌「軍艦」(1897年作)を、1900年、瀬戸口がさらに行進曲に編曲したもの。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
羅紗の一種。厚地で保温力に富むことから、外套、各種の制服などに用いられた。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
くん‐き【勲記】
叙勲者に勲章とともに与えられる証書。
くん‐ぎ【訓義】
漢字の読みと意味。「―未詳」
ぐん‐き【軍気】
軍隊の意気。士気。兵気。
ぐん‐き【軍紀】
軍隊の風紀と規律。
ぐん‐き【軍記】
①戦争の話を記した書物。軍書。
②軍記物・軍記物語の略。
⇒ぐんき‐もの【軍記物】
⇒ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
⇒ぐんき‐よみ【軍記読み】
ぐん‐き【軍旗】
①軍陣で主将の存在を示す旗。
②軍隊の表章とする旗。旧日本陸軍では歩兵と騎兵の連隊に天皇が親授し、大日章に16条の光線を描き、竿頭に3面の金色菊花章を飾り、紫の総ふさで3方を縁取ったもの。連隊旗。
⇒ぐんき‐さい【軍旗祭】
ぐん‐き【軍器】
軍用の器具。兵器。
ぐん‐き【軍毅】
軍団の将。続日本紀36「国司、―」
ぐん‐き【軍機】
軍事上の機密。「―漏洩ろうえい」
⇒ぐんき‐しょ【軍機処】
⇒ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
⇒ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】
ぐん‐き【群起】
むらがり立つこと。
ぐん‐ぎ【軍議】
軍事上の評議。
ぐん‐ぎ【群疑】
①多くの人の疑うこと。
②多くの疑問。
ぐん‐ぎ【群議】
多くの人の議論。衆議。
ぐんき‐さい【軍旗祭】
旧陸軍の連隊で、軍旗を親授された記念日に行なった祝典。
⇒ぐん‐き【軍旗】
ぐんき‐しょ【軍機処】
清朝しんちょうの最高政治機関。正式には弁理軍機処。軍事上の機務、後には一般行政上の枢機をも掌握した。内閣大学士および六部尚書侍郎の中から軍機大臣4〜6名を任命。1729年創設。もと臨時的機関であったが、19世紀初め法制化された。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
軍機処を構成する官僚。宰相に相当する。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】‥ハフ
軍事上の秘密保護を目的とした法律。秘密の種類・範囲は陸海軍大臣の命令で定めることができた。1899年(明治32)制定。1937年(昭和12)に大改正。45年廃止。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐もの【軍記物】
①(→)軍記物語に同じ。
②江戸時代に出た小説の一種。軍いくさに関する事跡を興味あるように実録と空想とをまじえて書いたもの。絵本太閤記など。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
合戦を主として時代の展開を写した叙事詩的文学。鎌倉時代に多く作られ、保元物語・平治物語・平家物語・太平記などがある。武将の個人的生活を主題とした義経記ぎけいきや曾我物語を含めることもある。主として和漢混淆体。軍記物。戦記物語。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐん‐きょ【群居】
むらがり集まっていること。群れをつくって住んでいること。「海辺に―する生物」
くん‐ぎょう【勲業】‥ゲフ
勲功ある事業。功業。
ぐんき‐よみ【軍記読み】
軍記物を講釈すること。また、その人。
⇒ぐん‐き【軍記】
クングール【Kungur】
中国、新疆ウイグル自治区の西部、パミール高原の東部に位置する高峰。1981年イギリス隊が初登頂。標高7719メートル。コングール。
くん‐くん
①においを嗅ぐために鼻で小刻みに息を吸う音。
②犬が甘えたり何事かを訴えたりする弱い鳴き声。「子犬が―と鳴く」
ぐん‐ぐん
〔副〕
力強く物事が行われるさま。変化してゆく度合が大きいさま。「背丈が―伸びる」「差を―縮める」
ぐん‐け【郡家】
⇒ぐうけ
ぐん‐けい【軍鶏】
シャモのこと。
ぐん‐けい【群系】
(formation)生態学で生物の群集、特に植物群落を分類する単位の一つ。気候や地形などが類似している所には、生活型の類似した生物から成る群集が見出されるので、植物の相観やおもな生物の種類を基準として群系を分類する。例えば中央アジアの草原の生物群集と北アメリカの草原の生物群集とは類似し、ともに温帯草原群系とされる。植物群系。
ぐん‐けいほう【軍刑法】‥ハフ
陸軍刑法と海軍刑法との併称。
くん‐けん【君権】
君主の権力。
くん‐げん【訓言】
いましめの言葉。訓辞。
ぐん‐けん【軍犬】
軍隊で、連絡・警戒・捜索などに使う犬。軍用犬。
ぐん‐げん【軍監】
古代、鎮守府および征夷使の第三等官。副将軍の次の官。ぐんかん。
ぐん‐げん【群言】
多くの人のことば。
ぐんけん‐せいど【郡県制度】
中国の地方行政制度。春秋戦国から秦代にかけて、全国を郡・県などの行政区画に分け、地方官を選任して行政を執行させた。↔封建制度1。→郡国制
くん‐こ【訓詁】
(「詁」は古言を解く意)字句の解釈。蒙求抄1「―は注をしたと云ふ心ぞ」
⇒くんこ‐がく【訓詁学】
ぐん‐こ【軍戸】
明代、軍籍に編入された戸。衛所制度により世襲的に軍務に服役させ、税役を免除した。
ぐん‐こ【軍袴】
(旧陸軍用語)軍服のズボン。
ぐん‐こ【軍鼓】
戦陣で用いる太鼓。陣太鼓など。
くん‐こう【君公】
きみ。主君。君主。
くん‐こう【君侯】
武士が、その仕える諸侯を呼ぶ称。
くん‐こう【焄蒿】‥カウ
(「焄」はこうばしくにおう意、「蒿」は蒸しのぼる意)香気のたちかおること。
⇒くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】
くん‐こう【勲功】
国家または君主に尽くした功労。いさお。てがら。「―を立てる」
くん‐こう【薫香】‥カウ
よいかおりを立てるため、くゆらす香料。たきもの。
ぐん‐こう【軍功】
戦争における功績。いくさの手柄。
ぐん‐こう【軍港】‥カウ
艦隊および軍艦の根拠地として、特別の設備のある港湾。日本では明治期に、横須賀・呉・佐世保・舞鶴を軍港とし、鎮守府が置かれた。国木田独歩、苦悶の叫「桟橋は流石さすが―丈けありて立派なものなり」→要港
ぐん‐こう【群口】
多くの人のことば。
ぐん‐こう【群行】‥カウ
①大勢集まって行くこと。
②斎宮いつきのみやが野の宮で潔斎を終えて9月に伊勢へ下向すること。
ぐん‐ごう【群豪】‥ガウ
多くの豪傑。群雄。
くんごう‐こく【君合国】‥ガフ‥
(→)同君連合に同じ。
くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】‥カウ‥サウ
香気がたちかおり、人の心を恐れおののかせる意。鬼神の気を形容する語。
⇒くん‐こう【焄蒿】
くんこ‐がく【訓詁学】
①漢代および唐代に、経けいの意義を解釈することを専らとした学問。漢代は経書の蒐集と訓詁とに力を入れ、唐代に大成。注疏学。
②一般に、経典けいてんの訓詁注釈を主とする学。
⇒くん‐こ【訓詁】
くん‐こく【君国】
①君主と国家。
②君主の統治する国。
くん‐こく【訓告】
教え告げること。いましめ告げること。「―処分」
ぐん‐こく【軍国】
①軍隊と国家。軍事と国政。
②戦争をしている国。
③軍事を主な政策とする国家。
⇒ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
国の政治・経済・法律・教育などの政策・組織を戦争のために準備し、対外進出で国威を高めようと考える立場。ミリタリズム。木下杢太郎、地下一尺集「―の外に衆生の心を統一せしむるに足る巨大なる磁石はないのかしらむ」
⇒ぐん‐こく【軍国】
ぐんこく‐せい【郡国制】
漢の高祖が採用した封建・郡県併用の地方制度。同族・功臣を分封した国を置く一方、直轄支配地には郡県を設けた。
くん‐さい【捃採】
(「捃」は拾う意)拾いとること。転じて、書物の要所を抜き集めること。捃摭くんせき。
くん‐さい【葷菜】
においの強い野菜。ネギ・ニラ・ニンニクの類。
くんさ・る
〔他四〕
「下さる」の訛。俚言集覧「一番とまつて―・るなら」
ぐん‐さん【群参】
むらがって伺候すること。群をなして参詣すること。源平盛衰記1「結縁―の道俗は歓喜の袖をしぼる」
ぐん‐ざん【群山】
多くの山。むらがりあつまる山々。むらやま。
ぐん‐さん‐ふくごうたい【軍産複合体】‥ガフ‥
(military-industry complex)一国の軍事力・軍部が国内の産業経済上の利益に大きく支えられている体制。一般に軍部と軍需産業との密接な結びつきをいう。アイゼンハワーの用語。産軍複合体。
くん‐し【君子】
①高い身分の人。
②人格が立派な人。徳が高くて品位のそなわった人。品位の高い人。人格者。「聖人―」
③梅・竹・蘭・菊の異称。四君子。
④[周敦頤「蓮、花之君子者也」](画題)文人画で蓮華を描くもの。君子花。
⑤妻が夫を指していう語。
⇒くんし‐こく【君子国】
⇒くんし‐じん【君子人】
⇒くんし‐ひょうへん【君子豹変】
⇒くんし‐らん【君子蘭】
⇒君子の過ちは日月の食の如し
⇒君子の九思
⇒君子の三畏
⇒君子の三楽
⇒君子の徳は風
⇒君子の交わりは淡きこと水の如し
⇒君子は危うきに近寄らず
⇒君子は器ならず
⇒君子は三端を避く
⇒君子は周して比せず、小人は比して周せず
⇒君子は人の美を成す
⇒君子は独を慎む
⇒君子は豹変す
⇒君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず
⇒君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
くん‐し【薫紙】
香料をしみこませた紙。
くん‐じ【訓示】
①教え示すこと。
②年齢・地位などの上の者が下の者に対して教え示すこと。また、その教え。「―を垂れる」
⇒くんじ‐きてい【訓示規定】
くん‐じ【訓辞】
教えいましめる言葉。「校長の―」
ぐん‐し【軍士】
①兵士。兵。
②(→)軍師1に同じ。
ぐん‐し【軍使】
戦闘継続中、一方の交戦者の命により敵軍に赴く使者。
ぐん‐し【軍師】
①主将に属して、軍機をつかさどり謀略をめぐらす人。軍士。軍司。
②(比喩的に)巧みに策略・手段をめぐらす人。
ぐん‐し【群司】
多くの役人。群吏。
ぐん‐じ【軍事】
軍隊・兵備・戦争などに関する事柄。軍務に関する事柄。「―大国」「―力」
⇒ぐんじ‐か【軍事化】
⇒ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】
⇒ぐんじ‐こうどう【軍事行動】
⇒ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
⇒ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】
⇒ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】
⇒ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
⇒ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
⇒ぐんじ‐ふうさ【軍事封鎖】
⇒ぐんじ‐もくひょう‐しゅぎ【軍事目標主義】
⇒ぐんじ‐ゆうびん【軍事郵便】
⇒ぐんじ‐ゆそう【軍事輸送】
ぐんじ【軍持】‥ヂ
〔仏〕(梵語kuṇḍikā)僧尼の持つ水瓶すいびょう。転じて、瓶かめの異称。太平記37「尋常の寒梅樹折れて―に上れば」
ぐん‐じ【郡司】
①律令時代の地方行政官。国司の下にあって郡を治めた。地方の有力者から任命し、大領・少領・主政・主帳の四等官から成る。こおりのみやつこ。
②郡司1のうち大領・少領をいう。→郡領。
⇒ぐんじ‐めし【郡司召】
ぐんじ【郡司】
姓氏の一つ。
⇒ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
⇒ぐんじ‐まさかつ【郡司正勝】
くんじ‐いた・し【屈じ甚し】
〔形ク〕
心が晴れずふさぐ。元気がない。くしいたし。くっしいたし。源氏物語少女「胸のみふたがりて物なども見入られず、―・くて文も読までながめ臥し給へるを」
ぐんじ‐か【軍事化】‥クワ
国が外交政策の立案・遂行に当たって、安全保障の見地から軍事力・軍事的手段に強く依拠する傾向。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんじ‐きてい【訓示規定】
〔法〕もっぱら裁判所または行政庁に対する命令の性質をもち、これに反してもその行為の法的効力に影響がないとされる規定。↔効力規定
⇒くん‐じ【訓示】
ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】‥ケウ‥
1925年(大正14)より中等程度以上の男子学校に陸軍現役将校を配属して行なった軍事に関する訓練。45年(昭和20)廃止。学校教練。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんし‐きん【軍資金】
①軍事に必要な資金。
②(比喩的に)計画遂行に要する資金。
ぐんじ‐こうどう【軍事行動】‥カウ‥
国家が兵力を以てする一切の行動。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんし‐こく【君子国】
[淮南子墜形訓「東方に君子の国有り」]風俗が善良で礼儀の正しい国。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
①(→)軍法会議に同じ。
②戦争犯罪人を裁くための法廷。→国際軍事裁判。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】‥ヰン
重要軍務について天皇の諮詢しじゅんに応じた機関。1903年(明治36)設置、45年(昭和20)廃止。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
軍人・開拓者。海軍大尉。江戸生れ。幕臣の子。幸田露伴・成友の兄。千島開拓のため、1893年(明治26)報効義会を組織し、占守島しゅむしゅとうに移住。日露戦争に従軍、のち義勇艦隊を組織して海事・国防思想を普及。(1860〜1924)
⇒ぐんじ【郡司】
くんし‐じん【君子人】
徳行高く、君子ともいうべき人。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】‥リヤウ
敵国または他国の領土を武力で占領すること。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
敵地に入り込んで軍事上の探偵をするもの。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くん‐しつ【燻室】
魚・獣肉の燻製を作るため燻蒸する室。
ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
2国またはそれ以上の諸国間に締結される軍事に関する同盟。→攻守同盟。
⇒ぐん‐じ【軍事】
 ⇒くわばら【桑原】
くわばら‐たけお【桑原武夫】クハ‥ヲ
仏文学者・評論家。福井県生れ。隲蔵じつぞうの子。京大卒。スタンダールらの翻訳紹介と広範な評論活動で知られる。また、京大人文科学研究所教授として中江兆民その他の学際的な共同研究を主宰。著「ルソー研究」「文学理論の研究」など。文化勲章。(1904〜1988)→第二芸術
桑原武夫
撮影:田村 茂
⇒くわばら【桑原】
くわばら‐たけお【桑原武夫】クハ‥ヲ
仏文学者・評論家。福井県生れ。隲蔵じつぞうの子。京大卒。スタンダールらの翻訳紹介と広範な評論活動で知られる。また、京大人文科学研究所教授として中江兆民その他の学際的な共同研究を主宰。著「ルソー研究」「文学理論の研究」など。文化勲章。(1904〜1988)→第二芸術
桑原武夫
撮影:田村 茂
 ⇒くわばら【桑原】
くわ‐びら【鍬平】クハ‥
①鍬の、柄を除いた部分。また、そのような形。
②足の、くるぶしから先の部分。足首。東海道名所記「お―出しめされい」
③扁平で土ふまずのない足。鍬平足。扁平足。
くわ‐ぼうき【桑箒・鍬箒】クハバウキ
桑の切株から生える楚すわえを束ねて作った箒。浮世草子、好色産毛「久三郎も気を通り、―持て門はきに出る」
くわ‐まゆ【桑繭】クハ‥
野蚕くわご。また、その繭。〈倭名類聚鈔14〉
くわ‐まよ【桑繭】クハ‥
(上代東国方言)(→)「くわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の新にい―の衣きぬはあれど」
くわ‐むし【桑虫】クハ‥
カイコの異称。〈書言字考節用集〉
くわ‐やき【鍬焼】クハ‥
肉・野菜などを鉄板で焼き、たれで味をつけた料理。昔、野良仕事の合間、野鳥をつかまえ鍬で焼いたことによるという。
くわやま【桑山】クハ‥
近世、大坂天王寺の珊瑚寺から売り出した小粒の丸薬。小児の万病に効くとされた。豊臣の家臣桑山修理太夫が文禄・慶長の役の際に朝鮮から伝えたという。桑山小粒丸。浄瑠璃、心中天の網島「必ず―飲ませて下され」
くわやま【桑山】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】
くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】クハ‥シウ
江戸中期の文人画家。名は嗣燦しさん。字は明夫。和歌山の人。池大雅に兄事。山水画、特に真景図にすぐれる。「絵事鄙言かいじひげん」「玉洲画趣」などの画論書がある。(1746〜1799)
⇒くわやま【桑山】
くわ・ゆ【加ゆ】クハユ
〔他下二〕
⇒くわえる(下一)
くわ‐ゆみ【桑弓】クハ‥
桑で作った弓。男児誕生の時、この弓に蓬よもぎの茎ではいだ矢をつがえて四方を射て立身出世を祝った。くわのゆみ。→桑弧蓬矢そうこほうし
くわ‐よほろ【鍬丁・钁丁】クハ‥
古代、屯倉みやけを耕すために徴発された壮丁。安閑紀「郡こおり毎の―」
く‐わり【区割り】
ものをいくつかのまとまりに分けること。区分くぶん。
クヮルテット
⇒カルテット
くわわ・る【加わる】クハハル
〔自五〕
①ある事物の上に他の事物が添えられる。重なる。ふえる。はなはだしくなる。古今和歌集雑「わび人の住むべきやどと見るなへに嘆き―・る琴の音ぞする」。源氏物語藤裏葉「御封みふ―・り官爵つかさこうぶりなどみな添ひ給ふ」。「寒さが―・る」「圧力が―・る」
②参加する。その一員となる。源氏物語若菜下「―・りたる二人なむ、兵衛づかさの名高き限りを、召したりける」。日葡辞書「ニンジュ(人数)ニクワワル」。「一味に―・る」「打合せに―・る」
クワント【Mary Quant】
イギリスの服飾デザイナー。1961年ミニスカートを発表し、世界中にブームを巻き起こした。(1934〜)
くん
気息を鼻に通じて発する声。においを嗅ぎ、煙にむせびなどする時の声。
くん【君】
①統治者。天子・帝王・諸侯などをいう。
②敬称。
㋐尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。
㋑同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。「加藤―」
くん【訓】
①よむこと。字義を解釈すること。
②漢字を和語にあててよむこと。「人」を「ひと」とよむ類。↔音おん
くん【裙】
①もすそ。
②裙子くんずの略。
くん【葷】
ネギ・ニラ・ショウガなど、臭気の強い、または辛い蔬菜。「不入―酒」
くん【勲】
①君主または国家に尽くした功労。
②勲章の等級に冠して用いる語。「―一等」
くん【薫】
よいかおり。
⇒薫は香を以て自ら焼く
ぐん【軍】
①戦うための集団・組織。陸海空軍の汎称。古今著聞集9「―、野に伏す時は、飛雁列つらを破る」。「―の意向」「―を率いる」
②中国周代の軍隊編制の単位で、師(2500人)を五つ合わせたもの、すなわち1万2500人。天子は6軍、大国は3軍、中国は2軍、小国は1軍を置く。
③明治以後の兵制で、戦時に数個師団をもって構成された軍隊編制の単位。
④スポーツなどのチーム。
ぐん【郡】
①中国で、戦国時代以後、隋・唐まで行われた行政区画の一つ。県の上の単位。後世、府・州の雅称。→県。
②日本の地方行政区画の一つ。律令制では国の下、里(郷)の上の行政区画とし、1878年(明治11)明治政府下では府・県の下の行政単位とされたが、1923年(大正12)廃止。今は地理上の区画。こおり。→国郡里制
ぐん【群】
①むらがり。むれ。あつまり。「―をなす」
②〔数〕(group)一つの集合があって、これを構成する要素(元という)の間に次の四つの条件を満たす一つの算法
⇒くわばら【桑原】
くわ‐びら【鍬平】クハ‥
①鍬の、柄を除いた部分。また、そのような形。
②足の、くるぶしから先の部分。足首。東海道名所記「お―出しめされい」
③扁平で土ふまずのない足。鍬平足。扁平足。
くわ‐ぼうき【桑箒・鍬箒】クハバウキ
桑の切株から生える楚すわえを束ねて作った箒。浮世草子、好色産毛「久三郎も気を通り、―持て門はきに出る」
くわ‐まゆ【桑繭】クハ‥
野蚕くわご。また、その繭。〈倭名類聚鈔14〉
くわ‐まよ【桑繭】クハ‥
(上代東国方言)(→)「くわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の新にい―の衣きぬはあれど」
くわ‐むし【桑虫】クハ‥
カイコの異称。〈書言字考節用集〉
くわ‐やき【鍬焼】クハ‥
肉・野菜などを鉄板で焼き、たれで味をつけた料理。昔、野良仕事の合間、野鳥をつかまえ鍬で焼いたことによるという。
くわやま【桑山】クハ‥
近世、大坂天王寺の珊瑚寺から売り出した小粒の丸薬。小児の万病に効くとされた。豊臣の家臣桑山修理太夫が文禄・慶長の役の際に朝鮮から伝えたという。桑山小粒丸。浄瑠璃、心中天の網島「必ず―飲ませて下され」
くわやま【桑山】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】
くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】クハ‥シウ
江戸中期の文人画家。名は嗣燦しさん。字は明夫。和歌山の人。池大雅に兄事。山水画、特に真景図にすぐれる。「絵事鄙言かいじひげん」「玉洲画趣」などの画論書がある。(1746〜1799)
⇒くわやま【桑山】
くわ・ゆ【加ゆ】クハユ
〔他下二〕
⇒くわえる(下一)
くわ‐ゆみ【桑弓】クハ‥
桑で作った弓。男児誕生の時、この弓に蓬よもぎの茎ではいだ矢をつがえて四方を射て立身出世を祝った。くわのゆみ。→桑弧蓬矢そうこほうし
くわ‐よほろ【鍬丁・钁丁】クハ‥
古代、屯倉みやけを耕すために徴発された壮丁。安閑紀「郡こおり毎の―」
く‐わり【区割り】
ものをいくつかのまとまりに分けること。区分くぶん。
クヮルテット
⇒カルテット
くわわ・る【加わる】クハハル
〔自五〕
①ある事物の上に他の事物が添えられる。重なる。ふえる。はなはだしくなる。古今和歌集雑「わび人の住むべきやどと見るなへに嘆き―・る琴の音ぞする」。源氏物語藤裏葉「御封みふ―・り官爵つかさこうぶりなどみな添ひ給ふ」。「寒さが―・る」「圧力が―・る」
②参加する。その一員となる。源氏物語若菜下「―・りたる二人なむ、兵衛づかさの名高き限りを、召したりける」。日葡辞書「ニンジュ(人数)ニクワワル」。「一味に―・る」「打合せに―・る」
クワント【Mary Quant】
イギリスの服飾デザイナー。1961年ミニスカートを発表し、世界中にブームを巻き起こした。(1934〜)
くん
気息を鼻に通じて発する声。においを嗅ぎ、煙にむせびなどする時の声。
くん【君】
①統治者。天子・帝王・諸侯などをいう。
②敬称。
㋐尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。
㋑同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。「加藤―」
くん【訓】
①よむこと。字義を解釈すること。
②漢字を和語にあててよむこと。「人」を「ひと」とよむ類。↔音おん
くん【裙】
①もすそ。
②裙子くんずの略。
くん【葷】
ネギ・ニラ・ショウガなど、臭気の強い、または辛い蔬菜。「不入―酒」
くん【勲】
①君主または国家に尽くした功労。
②勲章の等級に冠して用いる語。「―一等」
くん【薫】
よいかおり。
⇒薫は香を以て自ら焼く
ぐん【軍】
①戦うための集団・組織。陸海空軍の汎称。古今著聞集9「―、野に伏す時は、飛雁列つらを破る」。「―の意向」「―を率いる」
②中国周代の軍隊編制の単位で、師(2500人)を五つ合わせたもの、すなわち1万2500人。天子は6軍、大国は3軍、中国は2軍、小国は1軍を置く。
③明治以後の兵制で、戦時に数個師団をもって構成された軍隊編制の単位。
④スポーツなどのチーム。
ぐん【郡】
①中国で、戦国時代以後、隋・唐まで行われた行政区画の一つ。県の上の単位。後世、府・州の雅称。→県。
②日本の地方行政区画の一つ。律令制では国の下、里(郷)の上の行政区画とし、1878年(明治11)明治政府下では府・県の下の行政単位とされたが、1923年(大正12)廃止。今は地理上の区画。こおり。→国郡里制
ぐん【群】
①むらがり。むれ。あつまり。「―をなす」
②〔数〕(group)一つの集合があって、これを構成する要素(元という)の間に次の四つの条件を満たす一つの算法 が規定されているとき、この集合を群という。(ア)この集合の二つの元aとbに対してa
が規定されているとき、この集合を群という。(ア)この集合の二つの元aとbに対してa bもまたこの集合の元である。(イ)結合律a
bもまたこの集合の元である。(イ)結合律a (b
(b c)=(a
c)=(a b)
b) cが成り立つ。(ウ)単位元(すべての元aに対してe
cが成り立つ。(ウ)単位元(すべての元aに対してe a=a
a=a e=aが成り立つような元e)が含まれている。(エ)逆元(元aに対しa
e=aが成り立つような元e)が含まれている。(エ)逆元(元aに対しa x=x
x=x a=eが成り立つような元x)が含まれている。
⇒群を抜く
くん‐い【君位】‥ヰ
天皇の位。君主の位。
くん‐い【勲位】‥ヰ
①勲等と位階。
②勲等。令制では12等、明治以降は8等に定められた。
ぐん‐い【軍医】
軍隊で、傷病兵の診察・治療および軍陣医学・軍陣衛生をつかさどる武官。桜井忠温、肉弾「―は死傷者収容の為に屡しばしば危険を冒して」
⇒ぐんい‐そうかん【軍医総監】
くん‐いく【訓育】
①教え育てること。「児童を―する」
②感情と意志とを陶冶とうやして望ましい性格を形成する教育作用。躾しつけ、または徳育と同義に解される場合も多い。
くんいく【葷粥・獯鬻】
周代における北狄ほくてきの名称。玁狁けんいんとも呼ばれ、戦国・秦・漢の匈奴きょうどの祖に当たるともいう。
くん‐いく【薫育】
徳をもって人を導き育てること。薫陶化育。
ぐんい‐そうかん【軍医総監】
旧陸海軍で、軍医の最高の階級。陸軍では1897年(明治30)以前は少将相当官、以後は中将相当官。1937年(昭和12)より軍医中将と改称。次位は軍医監(大佐のち少将相当官)、第3位は一等軍医正。
⇒ぐん‐い【軍医】
ぐん‐いん【郡院】‥ヰン
(→)郡家ぐうけに同じ。
ぐん‐えい【軍営】
軍隊の営所。兵営。陣営。
ぐん‐えき【軍役】
(グンヤクとも)
①封建制下、武士が主君に対して負う軍事上の負担。
②戦時における夫役ぶやく。軍隊の服役。
③戦争。戦役。
くんえ‐こう【薫衣香】‥カウ
⇒くのえこう
くん‐えん【薫煙】
たきもののよい香りの煙。
くん‐えん【燻煙】
いぶすこと。炎の出ないように物を燃やして煙を多く出すこと。
⇒くんえん‐ざい【燻煙剤】
くんえん‐ざい【燻煙剤】
加熱により有効成分を煙状に浮遊させ、病虫害を防除する薬剤。主に温室などの施設栽培や倉庫などで用いる。蚊取り線香もこの一種。
⇒くん‐えん【燻煙】
ぐん‐おう【郡王】‥ワウ
中国の封爵の名称。皇族に与えられることが多く、明・清では親王の下に位した爵位。
くん‐おん【君恩】
君主のめぐみ。君主の恩。
くん‐か【君家】
君主の家。主君の家。
くん‐か【訓化】‥クワ
教訓感化すること。教え導くこと。
くん‐か【薫化】‥クワ
徳をもってよい方に導くこと。
ぐん‐か【軍靴】‥クワ
軍人用の靴。「―に踏みにじられる」
ぐん‐か【軍歌】
軍隊で、兵の士気を高揚させるための歌。また俗に、軍隊生活を歌った歌謡曲。
ぐん‐か【群下】
多くの臣下。群臣。
ぐん‐が【軍衙】
軍務を取り扱う役所。
ぐん‐が【郡衙】
①郡司の庁。
②郡役所。
くん‐かい【訓戒・訓誡】
教えさとし、いましめること。「―を垂れる」
くん‐かい【訓解】
字句・文章をときあかすこと。
くん‐かい【訓誨】‥クワイ
さとし教えること。
ぐん‐かく【軍拡】‥クワク
軍備拡張の略。↔軍縮
ぐん‐かく【群鶴】
むれをなす鶴。「―文様」
ぐん‐がく【軍学】
用兵戦術を研究する学問。中国では六韜りくとう・三略・孫子・呉子の兵書を基礎とし、日本では近世に各派を生じ、甲州流を先駆とし、越後流・北条流・山鹿流・長沼流・楠木流などがあった。兵学。兵法。
⇒ぐんがく‐しゃ【軍学者】
ぐん‐がく【軍楽】
軍隊の士気をふるいたたせるためや式典の際に演奏する音楽。楽器編成は管楽器と打楽器とが主体。
⇒ぐんがく‐たい【軍楽隊】
ぐんがく‐しゃ【軍学者】
軍学に長じた人。兵法学者。
⇒ぐん‐がく【軍学】
ぐんがく‐たい【軍楽隊】
軍楽を奏する楽隊。
⇒ぐん‐がく【軍楽】
くん‐かだ【訓伽陀】
(訓読する偈げの意)仏教歌謡。声明しょうみょうのうち、和文の伽陀の総称。四句形式のものが多い。→偈
くん‐がな【訓仮名】
万葉仮名のうち、漢字本来の意味とは無関係に漢字の訓を日本語の音節に当てたもの。「懐なつかし」を「名津蚊為」「夏樫」と書く類。字訓仮名。↔音仮名
ぐん‐かん【軍官】‥クワン
軍事をつかさどる官吏。武官。
ぐん‐かん【軍監】
⇒ぐんげん
ぐん‐かん【軍艦】
①水上の戦闘に従事する艦艇。
②旧海軍における艦艇の類別の一つ。戦艦・巡洋艦・航空母艦・潜水母艦・海防艦・砲艦などで、駆逐艦・潜水艦・特務艦などとは区別する。
⇒ぐんかん‐き【軍艦旗】
⇒ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】
⇒ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
⇒ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】
⇒ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
⇒ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
ぐんかん‐き【軍艦旗】
軍艦が艦尾に掲揚する旗。旧海軍では16条の旭日旗。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐん‐かんく【軍管区】‥クワン‥
旧陸軍で、日本内地を分けた際の各管轄区域。1940年(昭和15)には東部・中部・西部・北部の4軍管区に分け、司令官の下に各師団を統轄。
ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】‥サウ‥
1857年(安政4)江戸幕府が軍艦操縦教授のため江戸の築地の講武所内に設置した機関。66年(慶応2)海軍所と改称。翌年横浜の海軍伝習所を吸収。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
ペリカン目グンカンドリ科の鳥の総称。鵜うに似た全体黒色の大きな海鳥。翼を広げると1メートルを超える。雄は喉の裸出部が赤い。尾羽は長く燕の尾のように二つに分かれる。飛ぶ力が強く、熱帯地方の海に群棲して魚類を捕食。オオグンカンドリなど世界に5種あり、日本には稀に迷いこむ。
おおぐんかんどり(雄)
a=eが成り立つような元x)が含まれている。
⇒群を抜く
くん‐い【君位】‥ヰ
天皇の位。君主の位。
くん‐い【勲位】‥ヰ
①勲等と位階。
②勲等。令制では12等、明治以降は8等に定められた。
ぐん‐い【軍医】
軍隊で、傷病兵の診察・治療および軍陣医学・軍陣衛生をつかさどる武官。桜井忠温、肉弾「―は死傷者収容の為に屡しばしば危険を冒して」
⇒ぐんい‐そうかん【軍医総監】
くん‐いく【訓育】
①教え育てること。「児童を―する」
②感情と意志とを陶冶とうやして望ましい性格を形成する教育作用。躾しつけ、または徳育と同義に解される場合も多い。
くんいく【葷粥・獯鬻】
周代における北狄ほくてきの名称。玁狁けんいんとも呼ばれ、戦国・秦・漢の匈奴きょうどの祖に当たるともいう。
くん‐いく【薫育】
徳をもって人を導き育てること。薫陶化育。
ぐんい‐そうかん【軍医総監】
旧陸海軍で、軍医の最高の階級。陸軍では1897年(明治30)以前は少将相当官、以後は中将相当官。1937年(昭和12)より軍医中将と改称。次位は軍医監(大佐のち少将相当官)、第3位は一等軍医正。
⇒ぐん‐い【軍医】
ぐん‐いん【郡院】‥ヰン
(→)郡家ぐうけに同じ。
ぐん‐えい【軍営】
軍隊の営所。兵営。陣営。
ぐん‐えき【軍役】
(グンヤクとも)
①封建制下、武士が主君に対して負う軍事上の負担。
②戦時における夫役ぶやく。軍隊の服役。
③戦争。戦役。
くんえ‐こう【薫衣香】‥カウ
⇒くのえこう
くん‐えん【薫煙】
たきもののよい香りの煙。
くん‐えん【燻煙】
いぶすこと。炎の出ないように物を燃やして煙を多く出すこと。
⇒くんえん‐ざい【燻煙剤】
くんえん‐ざい【燻煙剤】
加熱により有効成分を煙状に浮遊させ、病虫害を防除する薬剤。主に温室などの施設栽培や倉庫などで用いる。蚊取り線香もこの一種。
⇒くん‐えん【燻煙】
ぐん‐おう【郡王】‥ワウ
中国の封爵の名称。皇族に与えられることが多く、明・清では親王の下に位した爵位。
くん‐おん【君恩】
君主のめぐみ。君主の恩。
くん‐か【君家】
君主の家。主君の家。
くん‐か【訓化】‥クワ
教訓感化すること。教え導くこと。
くん‐か【薫化】‥クワ
徳をもってよい方に導くこと。
ぐん‐か【軍靴】‥クワ
軍人用の靴。「―に踏みにじられる」
ぐん‐か【軍歌】
軍隊で、兵の士気を高揚させるための歌。また俗に、軍隊生活を歌った歌謡曲。
ぐん‐か【群下】
多くの臣下。群臣。
ぐん‐が【軍衙】
軍務を取り扱う役所。
ぐん‐が【郡衙】
①郡司の庁。
②郡役所。
くん‐かい【訓戒・訓誡】
教えさとし、いましめること。「―を垂れる」
くん‐かい【訓解】
字句・文章をときあかすこと。
くん‐かい【訓誨】‥クワイ
さとし教えること。
ぐん‐かく【軍拡】‥クワク
軍備拡張の略。↔軍縮
ぐん‐かく【群鶴】
むれをなす鶴。「―文様」
ぐん‐がく【軍学】
用兵戦術を研究する学問。中国では六韜りくとう・三略・孫子・呉子の兵書を基礎とし、日本では近世に各派を生じ、甲州流を先駆とし、越後流・北条流・山鹿流・長沼流・楠木流などがあった。兵学。兵法。
⇒ぐんがく‐しゃ【軍学者】
ぐん‐がく【軍楽】
軍隊の士気をふるいたたせるためや式典の際に演奏する音楽。楽器編成は管楽器と打楽器とが主体。
⇒ぐんがく‐たい【軍楽隊】
ぐんがく‐しゃ【軍学者】
軍学に長じた人。兵法学者。
⇒ぐん‐がく【軍学】
ぐんがく‐たい【軍楽隊】
軍楽を奏する楽隊。
⇒ぐん‐がく【軍楽】
くん‐かだ【訓伽陀】
(訓読する偈げの意)仏教歌謡。声明しょうみょうのうち、和文の伽陀の総称。四句形式のものが多い。→偈
くん‐がな【訓仮名】
万葉仮名のうち、漢字本来の意味とは無関係に漢字の訓を日本語の音節に当てたもの。「懐なつかし」を「名津蚊為」「夏樫」と書く類。字訓仮名。↔音仮名
ぐん‐かん【軍官】‥クワン
軍事をつかさどる官吏。武官。
ぐん‐かん【軍監】
⇒ぐんげん
ぐん‐かん【軍艦】
①水上の戦闘に従事する艦艇。
②旧海軍における艦艇の類別の一つ。戦艦・巡洋艦・航空母艦・潜水母艦・海防艦・砲艦などで、駆逐艦・潜水艦・特務艦などとは区別する。
⇒ぐんかん‐き【軍艦旗】
⇒ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】
⇒ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
⇒ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】
⇒ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
⇒ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
ぐんかん‐き【軍艦旗】
軍艦が艦尾に掲揚する旗。旧海軍では16条の旭日旗。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐん‐かんく【軍管区】‥クワン‥
旧陸軍で、日本内地を分けた際の各管轄区域。1940年(昭和15)には東部・中部・西部・北部の4軍管区に分け、司令官の下に各師団を統轄。
ぐんかん‐そうれんじょ【軍艦操練所】‥サウ‥
1857年(安政4)江戸幕府が軍艦操縦教授のため江戸の築地の講武所内に設置した機関。66年(慶応2)海軍所と改称。翌年横浜の海軍伝習所を吸収。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐どり【軍艦鳥】
ペリカン目グンカンドリ科の鳥の総称。鵜うに似た全体黒色の大きな海鳥。翼を広げると1メートルを超える。雄は喉の裸出部が赤い。尾羽は長く燕の尾のように二つに分かれる。飛ぶ力が強く、熱帯地方の海に群棲して魚類を捕食。オオグンカンドリなど世界に5種あり、日本には稀に迷いこむ。
おおぐんかんどり(雄)
 グンカンドリ
提供:OPO
グンカンドリ
提供:OPO
 ⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。若年寄(のち老中)に属し、海陸の警衛、艦船の製造、軍艦の操練などをつかさどった。1859年(安政6)設置。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
行進曲名。鳥山啓作詞・瀬戸口藤吉作曲の軍歌「軍艦」(1897年作)を、1900年、瀬戸口がさらに行進曲に編曲したもの。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
羅紗の一種。厚地で保温力に富むことから、外套、各種の制服などに用いられた。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
くん‐き【勲記】
叙勲者に勲章とともに与えられる証書。
くん‐ぎ【訓義】
漢字の読みと意味。「―未詳」
ぐん‐き【軍気】
軍隊の意気。士気。兵気。
ぐん‐き【軍紀】
軍隊の風紀と規律。
ぐん‐き【軍記】
①戦争の話を記した書物。軍書。
②軍記物・軍記物語の略。
⇒ぐんき‐もの【軍記物】
⇒ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
⇒ぐんき‐よみ【軍記読み】
ぐん‐き【軍旗】
①軍陣で主将の存在を示す旗。
②軍隊の表章とする旗。旧日本陸軍では歩兵と騎兵の連隊に天皇が親授し、大日章に16条の光線を描き、竿頭に3面の金色菊花章を飾り、紫の総ふさで3方を縁取ったもの。連隊旗。
⇒ぐんき‐さい【軍旗祭】
ぐん‐き【軍器】
軍用の器具。兵器。
ぐん‐き【軍毅】
軍団の将。続日本紀36「国司、―」
ぐん‐き【軍機】
軍事上の機密。「―漏洩ろうえい」
⇒ぐんき‐しょ【軍機処】
⇒ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
⇒ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】
ぐん‐き【群起】
むらがり立つこと。
ぐん‐ぎ【軍議】
軍事上の評議。
ぐん‐ぎ【群疑】
①多くの人の疑うこと。
②多くの疑問。
ぐん‐ぎ【群議】
多くの人の議論。衆議。
ぐんき‐さい【軍旗祭】
旧陸軍の連隊で、軍旗を親授された記念日に行なった祝典。
⇒ぐん‐き【軍旗】
ぐんき‐しょ【軍機処】
清朝しんちょうの最高政治機関。正式には弁理軍機処。軍事上の機務、後には一般行政上の枢機をも掌握した。内閣大学士および六部尚書侍郎の中から軍機大臣4〜6名を任命。1729年創設。もと臨時的機関であったが、19世紀初め法制化された。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
軍機処を構成する官僚。宰相に相当する。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】‥ハフ
軍事上の秘密保護を目的とした法律。秘密の種類・範囲は陸海軍大臣の命令で定めることができた。1899年(明治32)制定。1937年(昭和12)に大改正。45年廃止。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐もの【軍記物】
①(→)軍記物語に同じ。
②江戸時代に出た小説の一種。軍いくさに関する事跡を興味あるように実録と空想とをまじえて書いたもの。絵本太閤記など。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
合戦を主として時代の展開を写した叙事詩的文学。鎌倉時代に多く作られ、保元物語・平治物語・平家物語・太平記などがある。武将の個人的生活を主題とした義経記ぎけいきや曾我物語を含めることもある。主として和漢混淆体。軍記物。戦記物語。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐん‐きょ【群居】
むらがり集まっていること。群れをつくって住んでいること。「海辺に―する生物」
くん‐ぎょう【勲業】‥ゲフ
勲功ある事業。功業。
ぐんき‐よみ【軍記読み】
軍記物を講釈すること。また、その人。
⇒ぐん‐き【軍記】
クングール【Kungur】
中国、新疆ウイグル自治区の西部、パミール高原の東部に位置する高峰。1981年イギリス隊が初登頂。標高7719メートル。コングール。
くん‐くん
①においを嗅ぐために鼻で小刻みに息を吸う音。
②犬が甘えたり何事かを訴えたりする弱い鳴き声。「子犬が―と鳴く」
ぐん‐ぐん
〔副〕
力強く物事が行われるさま。変化してゆく度合が大きいさま。「背丈が―伸びる」「差を―縮める」
ぐん‐け【郡家】
⇒ぐうけ
ぐん‐けい【軍鶏】
シャモのこと。
ぐん‐けい【群系】
(formation)生態学で生物の群集、特に植物群落を分類する単位の一つ。気候や地形などが類似している所には、生活型の類似した生物から成る群集が見出されるので、植物の相観やおもな生物の種類を基準として群系を分類する。例えば中央アジアの草原の生物群集と北アメリカの草原の生物群集とは類似し、ともに温帯草原群系とされる。植物群系。
ぐん‐けいほう【軍刑法】‥ハフ
陸軍刑法と海軍刑法との併称。
くん‐けん【君権】
君主の権力。
くん‐げん【訓言】
いましめの言葉。訓辞。
ぐん‐けん【軍犬】
軍隊で、連絡・警戒・捜索などに使う犬。軍用犬。
ぐん‐げん【軍監】
古代、鎮守府および征夷使の第三等官。副将軍の次の官。ぐんかん。
ぐん‐げん【群言】
多くの人のことば。
ぐんけん‐せいど【郡県制度】
中国の地方行政制度。春秋戦国から秦代にかけて、全国を郡・県などの行政区画に分け、地方官を選任して行政を執行させた。↔封建制度1。→郡国制
くん‐こ【訓詁】
(「詁」は古言を解く意)字句の解釈。蒙求抄1「―は注をしたと云ふ心ぞ」
⇒くんこ‐がく【訓詁学】
ぐん‐こ【軍戸】
明代、軍籍に編入された戸。衛所制度により世襲的に軍務に服役させ、税役を免除した。
ぐん‐こ【軍袴】
(旧陸軍用語)軍服のズボン。
ぐん‐こ【軍鼓】
戦陣で用いる太鼓。陣太鼓など。
くん‐こう【君公】
きみ。主君。君主。
くん‐こう【君侯】
武士が、その仕える諸侯を呼ぶ称。
くん‐こう【焄蒿】‥カウ
(「焄」はこうばしくにおう意、「蒿」は蒸しのぼる意)香気のたちかおること。
⇒くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】
くん‐こう【勲功】
国家または君主に尽くした功労。いさお。てがら。「―を立てる」
くん‐こう【薫香】‥カウ
よいかおりを立てるため、くゆらす香料。たきもの。
ぐん‐こう【軍功】
戦争における功績。いくさの手柄。
ぐん‐こう【軍港】‥カウ
艦隊および軍艦の根拠地として、特別の設備のある港湾。日本では明治期に、横須賀・呉・佐世保・舞鶴を軍港とし、鎮守府が置かれた。国木田独歩、苦悶の叫「桟橋は流石さすが―丈けありて立派なものなり」→要港
ぐん‐こう【群口】
多くの人のことば。
ぐん‐こう【群行】‥カウ
①大勢集まって行くこと。
②斎宮いつきのみやが野の宮で潔斎を終えて9月に伊勢へ下向すること。
ぐん‐ごう【群豪】‥ガウ
多くの豪傑。群雄。
くんごう‐こく【君合国】‥ガフ‥
(→)同君連合に同じ。
くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】‥カウ‥サウ
香気がたちかおり、人の心を恐れおののかせる意。鬼神の気を形容する語。
⇒くん‐こう【焄蒿】
くんこ‐がく【訓詁学】
①漢代および唐代に、経けいの意義を解釈することを専らとした学問。漢代は経書の蒐集と訓詁とに力を入れ、唐代に大成。注疏学。
②一般に、経典けいてんの訓詁注釈を主とする学。
⇒くん‐こ【訓詁】
くん‐こく【君国】
①君主と国家。
②君主の統治する国。
くん‐こく【訓告】
教え告げること。いましめ告げること。「―処分」
ぐん‐こく【軍国】
①軍隊と国家。軍事と国政。
②戦争をしている国。
③軍事を主な政策とする国家。
⇒ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
国の政治・経済・法律・教育などの政策・組織を戦争のために準備し、対外進出で国威を高めようと考える立場。ミリタリズム。木下杢太郎、地下一尺集「―の外に衆生の心を統一せしむるに足る巨大なる磁石はないのかしらむ」
⇒ぐん‐こく【軍国】
ぐんこく‐せい【郡国制】
漢の高祖が採用した封建・郡県併用の地方制度。同族・功臣を分封した国を置く一方、直轄支配地には郡県を設けた。
くん‐さい【捃採】
(「捃」は拾う意)拾いとること。転じて、書物の要所を抜き集めること。捃摭くんせき。
くん‐さい【葷菜】
においの強い野菜。ネギ・ニラ・ニンニクの類。
くんさ・る
〔他四〕
「下さる」の訛。俚言集覧「一番とまつて―・るなら」
ぐん‐さん【群参】
むらがって伺候すること。群をなして参詣すること。源平盛衰記1「結縁―の道俗は歓喜の袖をしぼる」
ぐん‐ざん【群山】
多くの山。むらがりあつまる山々。むらやま。
ぐん‐さん‐ふくごうたい【軍産複合体】‥ガフ‥
(military-industry complex)一国の軍事力・軍部が国内の産業経済上の利益に大きく支えられている体制。一般に軍部と軍需産業との密接な結びつきをいう。アイゼンハワーの用語。産軍複合体。
くん‐し【君子】
①高い身分の人。
②人格が立派な人。徳が高くて品位のそなわった人。品位の高い人。人格者。「聖人―」
③梅・竹・蘭・菊の異称。四君子。
④[周敦頤「蓮、花之君子者也」](画題)文人画で蓮華を描くもの。君子花。
⑤妻が夫を指していう語。
⇒くんし‐こく【君子国】
⇒くんし‐じん【君子人】
⇒くんし‐ひょうへん【君子豹変】
⇒くんし‐らん【君子蘭】
⇒君子の過ちは日月の食の如し
⇒君子の九思
⇒君子の三畏
⇒君子の三楽
⇒君子の徳は風
⇒君子の交わりは淡きこと水の如し
⇒君子は危うきに近寄らず
⇒君子は器ならず
⇒君子は三端を避く
⇒君子は周して比せず、小人は比して周せず
⇒君子は人の美を成す
⇒君子は独を慎む
⇒君子は豹変す
⇒君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず
⇒君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
くん‐し【薫紙】
香料をしみこませた紙。
くん‐じ【訓示】
①教え示すこと。
②年齢・地位などの上の者が下の者に対して教え示すこと。また、その教え。「―を垂れる」
⇒くんじ‐きてい【訓示規定】
くん‐じ【訓辞】
教えいましめる言葉。「校長の―」
ぐん‐し【軍士】
①兵士。兵。
②(→)軍師1に同じ。
ぐん‐し【軍使】
戦闘継続中、一方の交戦者の命により敵軍に赴く使者。
ぐん‐し【軍師】
①主将に属して、軍機をつかさどり謀略をめぐらす人。軍士。軍司。
②(比喩的に)巧みに策略・手段をめぐらす人。
ぐん‐し【群司】
多くの役人。群吏。
ぐん‐じ【軍事】
軍隊・兵備・戦争などに関する事柄。軍務に関する事柄。「―大国」「―力」
⇒ぐんじ‐か【軍事化】
⇒ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】
⇒ぐんじ‐こうどう【軍事行動】
⇒ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
⇒ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】
⇒ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】
⇒ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
⇒ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
⇒ぐんじ‐ふうさ【軍事封鎖】
⇒ぐんじ‐もくひょう‐しゅぎ【軍事目標主義】
⇒ぐんじ‐ゆうびん【軍事郵便】
⇒ぐんじ‐ゆそう【軍事輸送】
ぐんじ【軍持】‥ヂ
〔仏〕(梵語kuṇḍikā)僧尼の持つ水瓶すいびょう。転じて、瓶かめの異称。太平記37「尋常の寒梅樹折れて―に上れば」
ぐん‐じ【郡司】
①律令時代の地方行政官。国司の下にあって郡を治めた。地方の有力者から任命し、大領・少領・主政・主帳の四等官から成る。こおりのみやつこ。
②郡司1のうち大領・少領をいう。→郡領。
⇒ぐんじ‐めし【郡司召】
ぐんじ【郡司】
姓氏の一つ。
⇒ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
⇒ぐんじ‐まさかつ【郡司正勝】
くんじ‐いた・し【屈じ甚し】
〔形ク〕
心が晴れずふさぐ。元気がない。くしいたし。くっしいたし。源氏物語少女「胸のみふたがりて物なども見入られず、―・くて文も読までながめ臥し給へるを」
ぐんじ‐か【軍事化】‥クワ
国が外交政策の立案・遂行に当たって、安全保障の見地から軍事力・軍事的手段に強く依拠する傾向。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんじ‐きてい【訓示規定】
〔法〕もっぱら裁判所または行政庁に対する命令の性質をもち、これに反してもその行為の法的効力に影響がないとされる規定。↔効力規定
⇒くん‐じ【訓示】
ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】‥ケウ‥
1925年(大正14)より中等程度以上の男子学校に陸軍現役将校を配属して行なった軍事に関する訓練。45年(昭和20)廃止。学校教練。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんし‐きん【軍資金】
①軍事に必要な資金。
②(比喩的に)計画遂行に要する資金。
ぐんじ‐こうどう【軍事行動】‥カウ‥
国家が兵力を以てする一切の行動。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんし‐こく【君子国】
[淮南子墜形訓「東方に君子の国有り」]風俗が善良で礼儀の正しい国。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
①(→)軍法会議に同じ。
②戦争犯罪人を裁くための法廷。→国際軍事裁判。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】‥ヰン
重要軍務について天皇の諮詢しじゅんに応じた機関。1903年(明治36)設置、45年(昭和20)廃止。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
軍人・開拓者。海軍大尉。江戸生れ。幕臣の子。幸田露伴・成友の兄。千島開拓のため、1893年(明治26)報効義会を組織し、占守島しゅむしゅとうに移住。日露戦争に従軍、のち義勇艦隊を組織して海事・国防思想を普及。(1860〜1924)
⇒ぐんじ【郡司】
くんし‐じん【君子人】
徳行高く、君子ともいうべき人。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】‥リヤウ
敵国または他国の領土を武力で占領すること。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
敵地に入り込んで軍事上の探偵をするもの。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くん‐しつ【燻室】
魚・獣肉の燻製を作るため燻蒸する室。
ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
2国またはそれ以上の諸国間に締結される軍事に関する同盟。→攻守同盟。
⇒ぐん‐じ【軍事】
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ぶぎょう【軍艦奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。若年寄(のち老中)に属し、海陸の警衛、艦船の製造、軍艦の操練などをつかさどった。1859年(安政6)設置。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐マーチ【軍艦マーチ】
行進曲名。鳥山啓作詞・瀬戸口藤吉作曲の軍歌「軍艦」(1897年作)を、1900年、瀬戸口がさらに行進曲に編曲したもの。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
ぐんかん‐ラシャ【軍艦羅紗】
羅紗の一種。厚地で保温力に富むことから、外套、各種の制服などに用いられた。
⇒ぐん‐かん【軍艦】
くん‐き【勲記】
叙勲者に勲章とともに与えられる証書。
くん‐ぎ【訓義】
漢字の読みと意味。「―未詳」
ぐん‐き【軍気】
軍隊の意気。士気。兵気。
ぐん‐き【軍紀】
軍隊の風紀と規律。
ぐん‐き【軍記】
①戦争の話を記した書物。軍書。
②軍記物・軍記物語の略。
⇒ぐんき‐もの【軍記物】
⇒ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
⇒ぐんき‐よみ【軍記読み】
ぐん‐き【軍旗】
①軍陣で主将の存在を示す旗。
②軍隊の表章とする旗。旧日本陸軍では歩兵と騎兵の連隊に天皇が親授し、大日章に16条の光線を描き、竿頭に3面の金色菊花章を飾り、紫の総ふさで3方を縁取ったもの。連隊旗。
⇒ぐんき‐さい【軍旗祭】
ぐん‐き【軍器】
軍用の器具。兵器。
ぐん‐き【軍毅】
軍団の将。続日本紀36「国司、―」
ぐん‐き【軍機】
軍事上の機密。「―漏洩ろうえい」
⇒ぐんき‐しょ【軍機処】
⇒ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
⇒ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】
ぐん‐き【群起】
むらがり立つこと。
ぐん‐ぎ【軍議】
軍事上の評議。
ぐん‐ぎ【群疑】
①多くの人の疑うこと。
②多くの疑問。
ぐん‐ぎ【群議】
多くの人の議論。衆議。
ぐんき‐さい【軍旗祭】
旧陸軍の連隊で、軍旗を親授された記念日に行なった祝典。
⇒ぐん‐き【軍旗】
ぐんき‐しょ【軍機処】
清朝しんちょうの最高政治機関。正式には弁理軍機処。軍事上の機務、後には一般行政上の枢機をも掌握した。内閣大学士および六部尚書侍郎の中から軍機大臣4〜6名を任命。1729年創設。もと臨時的機関であったが、19世紀初め法制化された。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐だいじん【軍機大臣】
軍機処を構成する官僚。宰相に相当する。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐ほご‐ほう【軍機保護法】‥ハフ
軍事上の秘密保護を目的とした法律。秘密の種類・範囲は陸海軍大臣の命令で定めることができた。1899年(明治32)制定。1937年(昭和12)に大改正。45年廃止。
⇒ぐん‐き【軍機】
ぐんき‐もの【軍記物】
①(→)軍記物語に同じ。
②江戸時代に出た小説の一種。軍いくさに関する事跡を興味あるように実録と空想とをまじえて書いたもの。絵本太閤記など。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐんき‐ものがたり【軍記物語】
合戦を主として時代の展開を写した叙事詩的文学。鎌倉時代に多く作られ、保元物語・平治物語・平家物語・太平記などがある。武将の個人的生活を主題とした義経記ぎけいきや曾我物語を含めることもある。主として和漢混淆体。軍記物。戦記物語。
⇒ぐん‐き【軍記】
ぐん‐きょ【群居】
むらがり集まっていること。群れをつくって住んでいること。「海辺に―する生物」
くん‐ぎょう【勲業】‥ゲフ
勲功ある事業。功業。
ぐんき‐よみ【軍記読み】
軍記物を講釈すること。また、その人。
⇒ぐん‐き【軍記】
クングール【Kungur】
中国、新疆ウイグル自治区の西部、パミール高原の東部に位置する高峰。1981年イギリス隊が初登頂。標高7719メートル。コングール。
くん‐くん
①においを嗅ぐために鼻で小刻みに息を吸う音。
②犬が甘えたり何事かを訴えたりする弱い鳴き声。「子犬が―と鳴く」
ぐん‐ぐん
〔副〕
力強く物事が行われるさま。変化してゆく度合が大きいさま。「背丈が―伸びる」「差を―縮める」
ぐん‐け【郡家】
⇒ぐうけ
ぐん‐けい【軍鶏】
シャモのこと。
ぐん‐けい【群系】
(formation)生態学で生物の群集、特に植物群落を分類する単位の一つ。気候や地形などが類似している所には、生活型の類似した生物から成る群集が見出されるので、植物の相観やおもな生物の種類を基準として群系を分類する。例えば中央アジアの草原の生物群集と北アメリカの草原の生物群集とは類似し、ともに温帯草原群系とされる。植物群系。
ぐん‐けいほう【軍刑法】‥ハフ
陸軍刑法と海軍刑法との併称。
くん‐けん【君権】
君主の権力。
くん‐げん【訓言】
いましめの言葉。訓辞。
ぐん‐けん【軍犬】
軍隊で、連絡・警戒・捜索などに使う犬。軍用犬。
ぐん‐げん【軍監】
古代、鎮守府および征夷使の第三等官。副将軍の次の官。ぐんかん。
ぐん‐げん【群言】
多くの人のことば。
ぐんけん‐せいど【郡県制度】
中国の地方行政制度。春秋戦国から秦代にかけて、全国を郡・県などの行政区画に分け、地方官を選任して行政を執行させた。↔封建制度1。→郡国制
くん‐こ【訓詁】
(「詁」は古言を解く意)字句の解釈。蒙求抄1「―は注をしたと云ふ心ぞ」
⇒くんこ‐がく【訓詁学】
ぐん‐こ【軍戸】
明代、軍籍に編入された戸。衛所制度により世襲的に軍務に服役させ、税役を免除した。
ぐん‐こ【軍袴】
(旧陸軍用語)軍服のズボン。
ぐん‐こ【軍鼓】
戦陣で用いる太鼓。陣太鼓など。
くん‐こう【君公】
きみ。主君。君主。
くん‐こう【君侯】
武士が、その仕える諸侯を呼ぶ称。
くん‐こう【焄蒿】‥カウ
(「焄」はこうばしくにおう意、「蒿」は蒸しのぼる意)香気のたちかおること。
⇒くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】
くん‐こう【勲功】
国家または君主に尽くした功労。いさお。てがら。「―を立てる」
くん‐こう【薫香】‥カウ
よいかおりを立てるため、くゆらす香料。たきもの。
ぐん‐こう【軍功】
戦争における功績。いくさの手柄。
ぐん‐こう【軍港】‥カウ
艦隊および軍艦の根拠地として、特別の設備のある港湾。日本では明治期に、横須賀・呉・佐世保・舞鶴を軍港とし、鎮守府が置かれた。国木田独歩、苦悶の叫「桟橋は流石さすが―丈けありて立派なものなり」→要港
ぐん‐こう【群口】
多くの人のことば。
ぐん‐こう【群行】‥カウ
①大勢集まって行くこと。
②斎宮いつきのみやが野の宮で潔斎を終えて9月に伊勢へ下向すること。
ぐん‐ごう【群豪】‥ガウ
多くの豪傑。群雄。
くんごう‐こく【君合国】‥ガフ‥
(→)同君連合に同じ。
くんこう‐せいそう【焄蒿悽愴】‥カウ‥サウ
香気がたちかおり、人の心を恐れおののかせる意。鬼神の気を形容する語。
⇒くん‐こう【焄蒿】
くんこ‐がく【訓詁学】
①漢代および唐代に、経けいの意義を解釈することを専らとした学問。漢代は経書の蒐集と訓詁とに力を入れ、唐代に大成。注疏学。
②一般に、経典けいてんの訓詁注釈を主とする学。
⇒くん‐こ【訓詁】
くん‐こく【君国】
①君主と国家。
②君主の統治する国。
くん‐こく【訓告】
教え告げること。いましめ告げること。「―処分」
ぐん‐こく【軍国】
①軍隊と国家。軍事と国政。
②戦争をしている国。
③軍事を主な政策とする国家。
⇒ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
ぐんこく‐しゅぎ【軍国主義】
国の政治・経済・法律・教育などの政策・組織を戦争のために準備し、対外進出で国威を高めようと考える立場。ミリタリズム。木下杢太郎、地下一尺集「―の外に衆生の心を統一せしむるに足る巨大なる磁石はないのかしらむ」
⇒ぐん‐こく【軍国】
ぐんこく‐せい【郡国制】
漢の高祖が採用した封建・郡県併用の地方制度。同族・功臣を分封した国を置く一方、直轄支配地には郡県を設けた。
くん‐さい【捃採】
(「捃」は拾う意)拾いとること。転じて、書物の要所を抜き集めること。捃摭くんせき。
くん‐さい【葷菜】
においの強い野菜。ネギ・ニラ・ニンニクの類。
くんさ・る
〔他四〕
「下さる」の訛。俚言集覧「一番とまつて―・るなら」
ぐん‐さん【群参】
むらがって伺候すること。群をなして参詣すること。源平盛衰記1「結縁―の道俗は歓喜の袖をしぼる」
ぐん‐ざん【群山】
多くの山。むらがりあつまる山々。むらやま。
ぐん‐さん‐ふくごうたい【軍産複合体】‥ガフ‥
(military-industry complex)一国の軍事力・軍部が国内の産業経済上の利益に大きく支えられている体制。一般に軍部と軍需産業との密接な結びつきをいう。アイゼンハワーの用語。産軍複合体。
くん‐し【君子】
①高い身分の人。
②人格が立派な人。徳が高くて品位のそなわった人。品位の高い人。人格者。「聖人―」
③梅・竹・蘭・菊の異称。四君子。
④[周敦頤「蓮、花之君子者也」](画題)文人画で蓮華を描くもの。君子花。
⑤妻が夫を指していう語。
⇒くんし‐こく【君子国】
⇒くんし‐じん【君子人】
⇒くんし‐ひょうへん【君子豹変】
⇒くんし‐らん【君子蘭】
⇒君子の過ちは日月の食の如し
⇒君子の九思
⇒君子の三畏
⇒君子の三楽
⇒君子の徳は風
⇒君子の交わりは淡きこと水の如し
⇒君子は危うきに近寄らず
⇒君子は器ならず
⇒君子は三端を避く
⇒君子は周して比せず、小人は比して周せず
⇒君子は人の美を成す
⇒君子は独を慎む
⇒君子は豹変す
⇒君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず
⇒君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
くん‐し【薫紙】
香料をしみこませた紙。
くん‐じ【訓示】
①教え示すこと。
②年齢・地位などの上の者が下の者に対して教え示すこと。また、その教え。「―を垂れる」
⇒くんじ‐きてい【訓示規定】
くん‐じ【訓辞】
教えいましめる言葉。「校長の―」
ぐん‐し【軍士】
①兵士。兵。
②(→)軍師1に同じ。
ぐん‐し【軍使】
戦闘継続中、一方の交戦者の命により敵軍に赴く使者。
ぐん‐し【軍師】
①主将に属して、軍機をつかさどり謀略をめぐらす人。軍士。軍司。
②(比喩的に)巧みに策略・手段をめぐらす人。
ぐん‐し【群司】
多くの役人。群吏。
ぐん‐じ【軍事】
軍隊・兵備・戦争などに関する事柄。軍務に関する事柄。「―大国」「―力」
⇒ぐんじ‐か【軍事化】
⇒ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】
⇒ぐんじ‐こうどう【軍事行動】
⇒ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
⇒ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】
⇒ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】
⇒ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
⇒ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
⇒ぐんじ‐ふうさ【軍事封鎖】
⇒ぐんじ‐もくひょう‐しゅぎ【軍事目標主義】
⇒ぐんじ‐ゆうびん【軍事郵便】
⇒ぐんじ‐ゆそう【軍事輸送】
ぐんじ【軍持】‥ヂ
〔仏〕(梵語kuṇḍikā)僧尼の持つ水瓶すいびょう。転じて、瓶かめの異称。太平記37「尋常の寒梅樹折れて―に上れば」
ぐん‐じ【郡司】
①律令時代の地方行政官。国司の下にあって郡を治めた。地方の有力者から任命し、大領・少領・主政・主帳の四等官から成る。こおりのみやつこ。
②郡司1のうち大領・少領をいう。→郡領。
⇒ぐんじ‐めし【郡司召】
ぐんじ【郡司】
姓氏の一つ。
⇒ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
⇒ぐんじ‐まさかつ【郡司正勝】
くんじ‐いた・し【屈じ甚し】
〔形ク〕
心が晴れずふさぐ。元気がない。くしいたし。くっしいたし。源氏物語少女「胸のみふたがりて物なども見入られず、―・くて文も読までながめ臥し給へるを」
ぐんじ‐か【軍事化】‥クワ
国が外交政策の立案・遂行に当たって、安全保障の見地から軍事力・軍事的手段に強く依拠する傾向。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんじ‐きてい【訓示規定】
〔法〕もっぱら裁判所または行政庁に対する命令の性質をもち、これに反してもその行為の法的効力に影響がないとされる規定。↔効力規定
⇒くん‐じ【訓示】
ぐんじ‐きょうれん【軍事教練】‥ケウ‥
1925年(大正14)より中等程度以上の男子学校に陸軍現役将校を配属して行なった軍事に関する訓練。45年(昭和20)廃止。学校教練。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんし‐きん【軍資金】
①軍事に必要な資金。
②(比喩的に)計画遂行に要する資金。
ぐんじ‐こうどう【軍事行動】‥カウ‥
国家が兵力を以てする一切の行動。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くんし‐こく【君子国】
[淮南子墜形訓「東方に君子の国有り」]風俗が善良で礼儀の正しい国。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
①(→)軍法会議に同じ。
②戦争犯罪人を裁くための法廷。→国際軍事裁判。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐さんぎいん【軍事参議院】‥ヰン
重要軍務について天皇の諮詢しじゅんに応じた機関。1903年(明治36)設置、45年(昭和20)廃止。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐しげただ【郡司成忠】
軍人・開拓者。海軍大尉。江戸生れ。幕臣の子。幸田露伴・成友の兄。千島開拓のため、1893年(明治26)報効義会を組織し、占守島しゅむしゅとうに移住。日露戦争に従軍、のち義勇艦隊を組織して海事・国防思想を普及。(1860〜1924)
⇒ぐんじ【郡司】
くんし‐じん【君子人】
徳行高く、君子ともいうべき人。
⇒くん‐し【君子】
ぐんじ‐せんりょう【軍事占領】‥リヤウ
敵国または他国の領土を武力で占領すること。
⇒ぐん‐じ【軍事】
ぐんじ‐たんてい【軍事探偵】
敵地に入り込んで軍事上の探偵をするもの。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くん‐しつ【燻室】
魚・獣肉の燻製を作るため燻蒸する室。
ぐんじ‐どうめい【軍事同盟】
2国またはそれ以上の諸国間に締結される軍事に関する同盟。→攻守同盟。
⇒ぐん‐じ【軍事】
くわな【桑名】クハ‥🔗⭐🔉
くわな【桑名】クハ‥
三重県北東部の市。もと松平氏10万石の城下町。旧東海道の宮(熱田)からの渡し場。焼蛤やきはまぐり・時雨しぐれ蛤で有名。人口13万9千。
⇒くわな‐の‐とのさま【桑名の殿様】
⇒くわな‐ぼん【桑名盆】
くわな‐の‐とのさま【桑名の殿様】クハ‥🔗⭐🔉
くわな‐の‐とのさま【桑名の殿様】クハ‥
三重県の民謡。江戸末期、木遣きやり歌からお座敷唄となったもの。
⇒くわな【桑名】
くわな‐ぼん【桑名盆】クハ‥🔗⭐🔉
くわな‐ぼん【桑名盆】クハ‥
桑名に産する盆。表裏共に黒漆を塗り、錫粉と青漆の併用、または朱漆のみで蕪菁かぶらを描いたもの。
⇒くわな【桑名】
くわ‐の‐かど【桑の門】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐の‐かど【桑の門】クハ‥
(「桑門そうもん」の訓読)僧。出家。世捨人。新撰六帖2「からくして入りしは何ぞ―みちの心よそのしるしあれ」
くわ‐の‐はし【桑の箸】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐の‐はし【桑の箸】クハ‥
桑の材で作った箸。これを常に食事に用いれば中風にかからないという。誹風柳多留拾遺8「遠くおもんぱかつて―で食ひ」
くわのみ‐でら【桑実寺】クハ‥🔗⭐🔉
くわのみ‐でら【桑実寺】クハ‥
滋賀県蒲生郡安土町にある天台宗の寺。俗に桑峰薬師ともいう。678年(天武7)定恵の創立という。1576年(天正4)織田信長が再興。
くわ‐の‐ゆみ【桑弓】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐の‐ゆみ【桑弓】クハ‥
⇒くわゆみ。平家物語3「―・蓬の矢にて、天地四方を射させらる」
くわ‐ばら【桑原】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐ばら【桑原】クハ‥
①桑の樹を植えつけた畑。桑田。
②雷鳴の時、落雷を避ける呪文として用いる語。また、一般に忌わしいことを避けるためにも言う。雷神があやまって農家の井戸に落ちた時、農夫は蓋をして天に帰らせなかった。雷神は、自分は桑樹を嫌うから、桑原桑原と唱えるならば再び落ちまいと答えたとの伝説に基づくという。また、死して雷となったと伝える菅公の領地桑原には古来落雷した例がないのに因むともいう。狂言、雷「アア、――」
くわばら【桑原】クハ‥(姓氏)🔗⭐🔉
くわばら【桑原】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわばら‐じつぞう【桑原隲蔵】
⇒くわばら‐たけお【桑原武夫】
くわばら‐じつぞう【桑原隲蔵】クハ‥ザウ🔗⭐🔉
くわばら‐じつぞう【桑原隲蔵】クハ‥ザウ
東洋史学者。敦賀生れ。京大教授。東西交渉史・西域の研究に功績がある。著「蒲寿庚の事蹟」「東洋史説苑」など。(1870〜1931)
桑原隲蔵
提供:毎日新聞社
 ⇒くわばら【桑原】
⇒くわばら【桑原】
 ⇒くわばら【桑原】
⇒くわばら【桑原】
くわ‐ぼうき【桑箒・鍬箒】クハバウキ🔗⭐🔉
くわ‐ぼうき【桑箒・鍬箒】クハバウキ
桑の切株から生える楚すわえを束ねて作った箒。浮世草子、好色産毛「久三郎も気を通り、―持て門はきに出る」
くわ‐まゆ【桑繭】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐まゆ【桑繭】クハ‥
野蚕くわご。また、その繭。〈倭名類聚鈔14〉
くわ‐まよ【桑繭】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐まよ【桑繭】クハ‥
(上代東国方言)(→)「くわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の新にい―の衣きぬはあれど」
くわ‐むし【桑虫】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐むし【桑虫】クハ‥
カイコの異称。〈書言字考節用集〉
くわやま【桑山】クハ‥🔗⭐🔉
くわやま【桑山】クハ‥
近世、大坂天王寺の珊瑚寺から売り出した小粒の丸薬。小児の万病に効くとされた。豊臣の家臣桑山修理太夫が文禄・慶長の役の際に朝鮮から伝えたという。桑山小粒丸。浄瑠璃、心中天の網島「必ず―飲ませて下され」
くわやま【桑山】クハ‥(姓氏)🔗⭐🔉
くわやま【桑山】クハ‥
姓氏の一つ。
⇒くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】
くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】クハ‥シウ🔗⭐🔉
くわやま‐ぎょくしゅう【桑山玉洲】クハ‥シウ
江戸中期の文人画家。名は嗣燦しさん。字は明夫。和歌山の人。池大雅に兄事。山水画、特に真景図にすぐれる。「絵事鄙言かいじひげん」「玉洲画趣」などの画論書がある。(1746〜1799)
⇒くわやま【桑山】
くわ‐ゆみ【桑弓】クハ‥🔗⭐🔉
くわ‐ゆみ【桑弓】クハ‥
桑で作った弓。男児誕生の時、この弓に蓬よもぎの茎ではいだ矢をつがえて四方を射て立身出世を祝った。くわのゆみ。→桑弧蓬矢そうこほうし
そう‐えん【桑園】サウヱン🔗⭐🔉
そう‐えん【桑園】サウヱン
桑を栽培する畑。くわばたけ。
そう‐か【桑果】サウクワ🔗⭐🔉
そう‐か【桑果】サウクワ
多花果の一種。クワ・パイナップルなどのように、花軸に多数の花がつき、多肉・多汁の果実の集まりになったもの。肉質聚合果。
そう‐かい【桑海】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐かい【桑海】サウ‥
(桑田変じて滄海となる意)世の中の移り変りのはげしいこと。滄桑。滄海桑田。
そう‐きゅう【桑弓】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐きゅう【桑弓】サウ‥
クワの木でつくったゆみ。狂言、弓矢「毎年上頭へ御弓始に―を捧げまする」→くわゆみ
そう‐こ【桑戸】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐こ【桑戸】サウ‥
桑の木で作った戸。転じて、貧者の家。
そう‐こ【桑弧】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐こ【桑弧】サウ‥
桑の木でつくった弓。
⇒そうこ‐ほうし【桑弧蓬矢】
そうこう【桑港】サウカウ🔗⭐🔉
そうこう【桑港】サウカウ
サン‐フランシスコの漢名。
そう‐こうよう【桑弘羊】サウ‥ヤウ🔗⭐🔉
そう‐こうよう【桑弘羊】サウ‥ヤウ
(ソウクヨウとも)前漢の武帝・昭帝に仕えた財務官僚。洛陽の人。塩と鉄の専売開始を受けて、均輸法・平準法を実施し、国家収益の増加を図った。(前152〜前80)
○相好を崩すそうごうをくずす
顔をほころばせて大いに笑い、または大いに喜ぶさまにいう。
⇒そう‐ごう【相好】
そうこ‐ほうし【桑弧蓬矢】サウ‥🔗⭐🔉
そうこ‐ほうし【桑弧蓬矢】サウ‥
[礼記内則]桑の弓に蓬よもぎの矢。中国の古俗で、男子が生まれた時、これで天地四方を射て将来の雄飛を祈った。転じて、男子が志を立てること。桑蓬之志。
⇒そう‐こ【桑弧】
そう‐し【桑梓】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐し【桑梓】サウ‥
[詩経小雅、小弁](昔、中国で戸ごとに桑と梓あずさとを垣に植え、養蚕と器具用として子孫に残したので、その父母の恩を敬っていう)ふるさと。故郷。
そうじつ‐はい【桑実胚】サウ‥🔗⭐🔉
そうじつ‐はい【桑実胚】サウ‥
動物の発生の初期にできる胚。割球のまだ腔所のできていないもの。形状が桑の実に似るところからいう。
そう‐ちゅう【桑中】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐ちゅう【桑中】サウ‥
[詩経鄘風、桑中](桑畑の中で密会する意から)男女の不義。淫事。
そう‐でん【桑田】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐でん【桑田】サウ‥
桑を植えた畑。くわばたけ。
⇒桑田変じて滄海となる
○桑田変じて滄海となるそうでんへんじてそうかいとなる🔗⭐🔉
○桑田変じて滄海となるそうでんへんじてそうかいとなる
[劉廷芝、白頭を悲しむ翁に代われる詩]桑畑が変わって青い海になる。世の変遷のはげしいことのたとえ。「滄海変じて桑田となる」とも。
⇒そう‐でん【桑田】
そうでん‐りょう【相伝領】サウ‥リヤウ
代々つたえつぐ領地。
⇒そう‐でん【相伝】
そう‐と【壮図】サウ‥
壮大な企て。「―を抱く」
そう‐と【壮途】サウ‥
さかんなかどで。「勇躍―につく」
そう‐と【僧徒】
僧のともがら。僧侶。
そう‐と
〔副〕
そっと。狂言、吃り「紅を―うついて」
そう‐とう【双頭】サウ‥
頭が二つ並んでついていること。両頭。
⇒そうとう‐の‐わし【双頭の鷲】
そう‐とう【争闘】サウ‥
あらそいたたかうこと。闘争。「リング上の―」
そう‐とう【相当】サウタウ
①程度や地位などが、そのものにふさわしいこと、つりあうこと、あてはまること。「国賓―の待遇」「死に―する罪」「それ―のお礼」
②(副詞的にも用いる)普通を超えているさま。かなりな程度であるさま。「―な自信家」「―ひどい傷」
⇒そうとう‐いんがかんけい【相当因果関係】
⇒そうとう‐うち【相当打】
⇒そうとう‐かん【相当官】
⇒そうとう‐かんり【相当官吏】
⇒そうとう‐すう【相当数】
そう‐とう【相等】サウ‥
あいひとしいこと。同等。
⇒そうとう‐せい【相等性】
そう‐とう【草頭】サウ‥
①くさかんむり。
②草の上。
そう‐とう【掃討・掃蕩・剿討】サウタウ
敵などを、すっかり払い除くこと。討ちほろぼすこと。「―作戦」
そうとう【曹洞】サウ‥
曹洞宗の略。
⇒そうとう‐しゅう【曹洞宗】
そう‐とう【窓頭】サウ‥
まどのほとり。まどぎわ。
そう‐とう【想到】サウタウ
考えが及ぶこと。考えつくこと。
そう‐とう【掻頭】サウ‥
①頭をかくこと。
②かんざし。
そう‐とう【層塔】‥タフ
層をなした塔。幾層もある塔。三重・五重・十三重の塔の類。
そう‐とう【総統】
①統すべくくること。また、その官職。
②中華民国政府の最高官職。大統領に当たる。元首として国家を代表、行政院長を任命、総統府を主宰する。→大総統。
③(Führer ドイツ)ナチス‐ドイツの最高官職。大統領・首相・党首の全権をもち、ヒトラーがこの地位を占めて独裁権をふるった。→ドゥーチェ
そう‐とう【蒼頭】サウ‥
①(中国で青色の頭巾をかぶっていたからいう)士卒。
②しもべ。めしつかい。
そう‐どう【相同】サウ‥
①異種の生物の器官で、外観上の相違はあるが、発生的および体制的に同一であること。例えば鳥の翼と獣の前肢。ホモロジー。↔相似。
②塩基配列やアミノ酸の一致によって検出される、二つまたはそれ以上の遺伝子間に見られる類縁性。ホモロジー。
⇒そうどう‐きかん【相同器官】
⇒そうどう‐くみかえ【相同組換え】
⇒そうどう‐せんしょくたい【相同染色体】
そう‐どう【草堂】サウダウ
①くさぶきの家。草屋。また、自分の家の謙譲語。
②いおり。草庵。
そう‐どう【僧堂】‥ダウ
禅宗寺院の建物の一つで、坐禅修行の根本道場。もとは坐禅を中心に食事から睡眠までの一切がなされた。禅堂。雲堂。撰仏場。
そう‐どう【騒動】サウ‥
①多人数が乱れさわぐこと。平家物語7「廿二日の夜半ばかり、六波羅の辺おびたゝしう―す」。「上を下への大―」
②非常の事態。事変。「米―」
③もめごと。あらそい。「お家―」
⇒そうどう‐うち【騒動打】
ぞう‐とう【造塔】ザウタフ
供養のために、遺骨または経文を納めて塔を建造すること。
ぞう‐とう【贈答】‥タフ
物をおくったり、そのお返しをしたりすること。「―品」
⇒ぞうとう‐か【贈答歌】
そう‐どういん【総動員】‥ヰン
ある目的のために全員をかり出すこと。「―をかける」「社員―」
そうとう‐いんがかんけい【相当因果関係】サウタウ‥グワクワン‥
法律で因果関係が問題となる場合に、相当と認められる範囲に限定された因果関係。不法行為による損害賠償の範囲、犯罪行為の結果を問題とする刑事責任の範囲などに関して主張される。
⇒そう‐とう【相当】
そうとう‐うち【相当打】サウタウ‥
(→)後妻打うわなりうちに同じ。
⇒そう‐とう【相当】
そうどう‐うち【騒動打】サウ‥
(→)後妻打うわなりうちに同じ。
⇒そう‐どう【騒動】
ぞうとう‐か【贈答歌】‥タフ‥
二人がその意中を言いあい、やりとりする和歌。
⇒ぞう‐とう【贈答】
そうとう‐かん【相当官】サウタウクワン
その階級が、ある本官に相当しているもの。
⇒そう‐とう【相当】
そうとう‐かんり【相当官吏】サウタウクワン‥
旧制で、官吏と同等の待遇を受けた職員。官幣社・国幣社の神職、公立学校職員など。
⇒そう‐とう【相当】
そうどう‐きかん【相同器官】サウ‥クワン
異種の生物で相同である器官。
⇒そう‐どう【相同】
そうどう‐くみかえ【相同組換え】サウ‥カヘ
ゲノム中のある遺伝子座の配列を、それと相同的な対立遺伝子座のものと交換すること。
⇒そう‐どう【相同】
そうとう‐しゅう【曹洞宗】サウ‥
禅宗の一派。中国で洞山良价とうざんりょうかいと弟子の曹山本寂によって開かれ、日本では、道元が入宋して如浄からこれを伝え受けた。只管打坐しかんたざを説く。永平寺・総持寺を大本山とする。→臨済宗
⇒そうとう【曹洞】
そうとう‐すう【相当数】サウタウ‥
①それにふさわしい数。
②かなり多い数。
⇒そう‐とう【相当】
そうとう‐せい【相等性】サウ‥
(equality)二つの事象の間に分量上または性質上差異が認められないこと。→同一性
⇒そう‐とう【相等】
そうどう‐せん【双胴船】サウ‥
二つの船体を横に並べて、水面上の甲板で結んだ船。安定性と推進性能がよいため、ヨット・高速船などに用いられる。カタマラン。
そうどう‐せんしょくたい【相同染色体】サウ‥
減数分裂の際に対合する染色体。一般に有性生殖をする生物の体細胞(二倍体)は2個ずつの相同染色体を持ち、片方は雄性に、片方は雌性に由来する。
⇒そう‐どう【相同】
そうとう‐の‐わし【双頭の鷲】サウ‥
(double-headed eagle)神聖ローマ・オーストリア・ロシア3皇帝の紋章。
⇒そう‐とう【双頭】
そう‐どうめい【総同盟】
①日本労働総同盟の略称。1921年友愛会を改称。36年全労1と合流して全日本労働総同盟となり、40年解散。→友愛会。
②日本労働組合総同盟の略称。46年旧総同盟系を中心に結集した全国組織。50年左派は総評へ参加、右派は全労会議・同盟会議を経て、64年同盟へ解消。
そう‐どうめいひぎょう【総同盟罷業】‥ゲフ
ゼネラル‐ストライキの訳語。
そう‐とく【総督】
①統すべひきいること。
②軍隊を統べひきいる最高の官。軍司令官。
③中国で、明・清代の最高地方長官。1省を管轄する巡撫に対して、数省(例外的に1省)の政務・軍務を統轄。
④植民地の政務統轄に当たる官。旧日本の朝鮮総督・台湾総督など。
⇒そうとく‐ふ【総督府】
そう‐どく【瘡毒】サウ‥
梅毒。かさ。
そうど・くサウドク
〔自四〕
(「騒動」を活用させた語か)さわぎ立てる。ざわつく。源氏物語空蝉「きはぎはしう―・けば」
ぞう‐とく【蔵匿】ザウ‥
人に知られないように隠しておくこと。隠匿。→犯人蔵匿罪
そうとく‐ふ【総督府】
植民地の総督が政務を統轄する役所。
⇒そう‐とく【総督】
そう‐どしより【惣年寄】
江戸時代、大坂・岡山などで町奉行の支配を受けて御触れの通達、町年寄・町役人の監督など民政に当たった町人。→町年寄
そうとめ【早少女】サウトメ
⇒さおとめ。〈日葡辞書〉
そう‐ともサウ‥
全くその通りである。ごもっとも。
そう‐とん【草墩】サウ‥
(墩は太鼓形の腰掛)平安時代、宮中で用いた腰掛の一種。菰まこもなどを芯として円筒形につくり、上面と周囲を錦で包む。
草墩
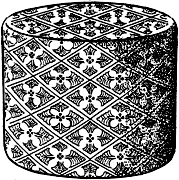 そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「
そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「 」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
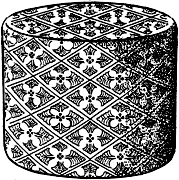 そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「
そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「 」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
そう‐もん【桑門】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐もん【桑門】サウ‥
(梵語śramaṇa 古い漢語仏典に出る語で、普通「沙門しゃもん」と音写)出家して仏道を修める人。僧侶。方丈記「―の蓮胤」
そう‐ゆ【桑楡】サウ‥🔗⭐🔉
そう‐ゆ【桑楡】サウ‥
①クワとニレ。
②[初学記天部上、日「日西に垂れ、景樹端に在り、之を桑楡と謂う」]夕日が樹木の上にかかっていること。転じて、くれがた。ゆうひ。
③晩年。老年。死期。
⇒桑楡且に迫らんとす
○桑楡且に迫らんとすそうゆまさにせまらんとす🔗⭐🔉
○桑楡且に迫らんとすそうゆまさにせまらんとす
[旧唐書太宗紀上]死期が近づいていることにいう。
⇒そう‐ゆ【桑楡】
ぞうよ【増誉】
平安後期の天台宗園城寺の僧。京都聖護院の開山。大峰・葛城山で修行、白河・堀河天皇の護持僧として活躍。熊野三山の検校。晩年天台座主に補せられたが、山門派の反対で辞退。(1032〜1116)
ぞう‐よ【贈与】
①金銭・物品などをおくり与えること。
②〔法〕民法上、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。
⇒ぞうよ‐ぜい【贈与税】
そう‐よう【掃葉】サウエフ
(誤字を落葉に見立てていう)校正のこと。
そう‐よう【掻痒】サウヤウ
かゆいところをかくこと。「隔靴かっか―の感」
そう‐よう【総容】
①その座の一同の人。
②書簡文などで、相手の家族一同を呼ぶ語。
そう‐よう【蒼蠅】サウ‥
①あおばえ。
②君側の讒者ざんしゃ・佞人ねいじんのたとえ。
⇒蒼蠅驥尾に付して千里を致す
そう‐よう【霜葉】サウエフ
霜にあたって紅葉した葉。しもば。
ぞう‐よう【雑用】ザフ‥
①雑多な用事。ざつよう。
②種々のこまごました費用。雑費。
ぞう‐よう【雑徭】ザフエウ
①律令制の徭役労働の一種。諸国で道路・堤防・官舎の建設・修理などのために公民に課した無償労働の義務。日数は正丁で当初、年60日を限度とし、時代が下るにつれてさらに減らされた。ざつよう。
②中国の唐代、地方官吏の使役による民衆の奉仕労働。
[漢]桑🔗⭐🔉
桑 字形
 筆順
筆順
 〔木部6画/10画/常用/2312・372C〕
〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)
〔訓〕くわ
[意味]
木の名。くわ。「桑園・蚕桑・扶桑・滄桑そうそう」
[解字]
象形。くわの木の形を描いたもの。[桒][
〔木部6画/10画/常用/2312・372C〕
〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)
〔訓〕くわ
[意味]
木の名。くわ。「桑園・蚕桑・扶桑・滄桑そうそう」
[解字]
象形。くわの木の形を描いたもの。[桒][ ]は異体字。
]は異体字。
 筆順
筆順
 〔木部6画/10画/常用/2312・372C〕
〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)
〔訓〕くわ
[意味]
木の名。くわ。「桑園・蚕桑・扶桑・滄桑そうそう」
[解字]
象形。くわの木の形を描いたもの。[桒][
〔木部6画/10画/常用/2312・372C〕
〔音〕ソウ〈サウ〉(呉)(漢)
〔訓〕くわ
[意味]
木の名。くわ。「桑園・蚕桑・扶桑・滄桑そうそう」
[解字]
象形。くわの木の形を描いたもの。[桒][ ]は異体字。
]は異体字。
広辞苑に「桑」で始まるの検索結果 1-66。