複数辞典一括検索+![]()
![]()
あや‐うじ【漢氏】‥ウヂ🔗⭐🔉
あや‐うじ【漢氏】‥ウヂ
古代の渡来系の有力な氏族。もと直あたい姓。応神天皇の時渡来した後漢霊帝の曾孫阿知使主あちのおみの子孫と称する東漢直やまとのあやのあたいと、後漢献帝の子孫と称する西漢直かわちのあやのあたいとがあった。天武天皇の時、連むらじ姓・忌寸いみき姓となる。子孫は坂上氏ら。
あや‐はとり【漢織】🔗⭐🔉
あや‐はとり【漢織】
(アヤハタオリ(漢機織)の約)大和政権に仕えた渡来系の機織技術者。雄略朝に漢土から来たという。雄略紀「―・呉織くれはとり…を将いて」→呉織
あや‐ひと【漢人】🔗⭐🔉
あや‐ひと【漢人】
①古代の渡来系氏族。東漢直やまとのあやのあたいの祖阿知使主あちのおみに率いられて渡来したと称する。東漢氏の配下にあって、錦・綾の生産、武具・革具などの手工業を職とした。
②古代の中国系と称する渡来人の通称。
→漢氏あやうじ
あや‐め【漢女】🔗⭐🔉
あや‐め【漢女】
古代の渡来人のうちで大陸系統の技術による裁縫に従事した女。万葉集7「―をすゑて縫へる衣ぞ」
エッチ‐エス‐ケー【HSK】🔗⭐🔉
エッチ‐エス‐ケー【HSK】
(「漢語水平考試」の拼音ピンイン表記Hanyu Shuiping Kaoshiの略)中国教育部(文部科学省に相当)認定の中国語(漢語)検定試験。中国語を母語としない人を対象とする。
カグナミ【江南・漢南】🔗⭐🔉
カグナミ【江南・漢南】
(「江南」の朝鮮音から)刀の鍔つばの一種。江戸時代、中国の江南地方から南蛮船で舶載された鍔。また、それを日本で模して作った鍔。
から【韓・唐・漢】🔗⭐🔉
から【韓・唐・漢】
①(朝鮮南部の古国の名に基づく)朝鮮の古称。万葉集16「―国の虎とふ神を生取いけどりに」
②中国の古称。また中国から渡来の物事に添えていう語。源氏物語葵「あはれなるふる事ども、―のも大和のも書きけがしつつ」。「―物」「―歌」
③転じて、ひろく外国の称。また、外国から渡来の物事に添えていう語。徒然草「―の大和の、珍しくえならぬ調度ども」。「―犬」
④唐織の略。源氏物語花宴「桜の―の綺きの御直衣」
⇒唐へ投銀
から‐ごえ【漢音】‥ゴヱ🔗⭐🔉
から‐ごえ【漢音】‥ゴヱ
「漢音かんおん」の訓読。呉音ごおんを「やまとごえ」というのに対していう語。
から‐ごころ【漢心・漢意】🔗⭐🔉
から‐ごころ【漢心・漢意】
漢籍を学んで中国の国風に心酔、感化された心。近世の国学者が用いた語。↔やまとごころ
から‐ざえ【漢才】🔗⭐🔉
から‐ざえ【漢才】
漢籍に通じ漢詩文に巧みな才。単に「ざえ」ともいう。愚管抄3「―はよくて詩などいみじく作られけれど」
から‐たけ【漢竹・唐竹】🔗⭐🔉
から‐たけ【漢竹・唐竹】
中国渡来の竹。笛などをつくった。寒竹かんちく。新撰六帖6「―の笛にまくてふかばざくら春面白く風ぞふくなる」
から‐ぶみ【漢書】🔗⭐🔉
から‐ぶみ【漢書】
中国の書籍。漢文の書物。漢籍。もろこしぶみ。かんしょ。
⇒からぶみ‐よみ【漢書読み】
からぶみ‐よみ【漢書読み】🔗⭐🔉
からぶみ‐よみ【漢書読み】
漢書の読み方。また、漢書を読む人。
⇒から‐ぶみ【漢書】
かん【漢】🔗⭐🔉
かん【漢】
①中国本土、また、民族の名。中国に関すること。「―文学」→漢族。
②男子。おとこ。
③中国の王朝名。
㋐秦につづく統一王朝。前漢(西漢)・後漢ごかん(東漢)に分ける。
㋑三国の蜀漢。
㋒五胡十六国の成漢・漢(前趙)。
㋓五代の後漢こうかん・北漢・南漢。
かん‐い【漢医】🔗⭐🔉
かん‐い【漢医】
漢方医。
かん‐おん【漢音】🔗⭐🔉
かん‐か【漢家】🔗⭐🔉
かん‐か【漢家】
①漢朝の帝室。また、中国の称。平家物語1「―本朝是やはじめならむ」
②漢方医。
かん‐が【漢画】‥グワ🔗⭐🔉
かん‐が【漢画】‥グワ
①漢代の絵画。
②中国絵画の汎称。
③鎌倉後期以後に興った宋元風の絵画。→唐絵。
⇒かんが‐は【漢画派】
かん‐がく【漢学】🔗⭐🔉
かん‐がく【漢学】
①日本で、一般に中国の儒学または中国の学問の総称。奈良・平安時代には特に盛んで、日本の礼楽・諸制度にも少なからぬ影響を与えた。江戸時代に漢学派として再興。「―の素養」↔国学。
②中国で、宋・明の性理の学に対して漢・唐の訓詁くんこの学。清の恵棟・戴震らが称え、考証学の基礎をなした。
⇒かんがく‐しゃ【漢学者】
⇒かんがく‐は【漢学派】
かんがく‐しゃ【漢学者】🔗⭐🔉
かんがく‐しゃ【漢学者】
漢学を修める人。漢学に造詣の深い人。
⇒かん‐がく【漢学】
かんがく‐は【漢学派】🔗⭐🔉
かんがく‐は【漢学派】
清代の学派の一つ。漢の儒者の注を尊重・継承する学派。日本では、江戸時代の新注・古義学・古文辞学などに抗して起こった吉田篁墩こうとん・大田錦城・狩谷棭斎えきさいらの学派。
⇒かん‐がく【漢学】
かんが‐は【漢画派】‥グワ‥🔗⭐🔉
かんが‐は【漢画派】‥グワ‥
中国の宋元画にならった日本の中世・近世の画家たちの汎称。鎌倉末期〜室町中期は禅林の画僧、室町後期以降は狩野派など専門の画家が中心となる。江戸時代に興った明清画風を指すこともある。
⇒かん‐が【漢画】
かん‐かん【漢奸】🔗⭐🔉
かん‐かん【漢奸】
中国で、敵に通じる者。裏切者。売国奴。
かん‐きょう【漢鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉
かん‐きょう【漢鏡】‥キヤウ
漢代の鏡。ほとんどが円盤形の青銅製品。草葉文鏡・連弧文鏡・四神鏡・神獣鏡・画像鏡などが代表的。→漢式鏡
かん‐げつ【漢月】🔗⭐🔉
かん‐げつ【漢月】
天漢あまのがわと明月。
かん‐ご【漢語】🔗⭐🔉
かん‐ご【漢語】
①漢字音から成る語。漢字の熟語。↔和語。
②漢民族の言語。中国語。
かんこう【漢口】🔗⭐🔉
かんこう【漢口】
(Hankou)中国湖北省東部の都市。長江と漢水の合流地点の北西に位置し、古代には夏口と呼ばれた。対岸の武昌、漢陽と合わせ武漢三鎮と称したが、中華人民共和国の成立後、合併して武漢市を形成。日中戦争初期、南京撤退後の国民政府所在地。水陸交通の要地。ハンカオ。
かん‐こう【漢江】‥カウ🔗⭐🔉
かん‐こう【漢江】‥カウ
①(Han-gang)朝鮮半島屈指の大河。太白山脈中の五台山に発源、春川江・臨津江などの支流を合わせ、ソウルの中央を流れて京畿湾に注ぐ。流域は工業地帯として発展し、1970年代の韓国の経済急成長を「漢江の奇跡」と呼ぶ。長さ514キロメートル。漢水。ハンガン。
②(Han Jiang)中国の漢水の別称。
かんごおんず【漢呉音図】‥ヅ🔗⭐🔉
かんごおんず【漢呉音図】‥ヅ
音韻書。太田全斎著。3巻。1815年(文化12)刊。韻鏡の四十三転図の各文字に漢呉音を傍記し、またその徴証を示して漢呉音と韻鏡に説くところとを比較考証し詳説する。
かん‐ざい【漢才】🔗⭐🔉
かん‐ざい【漢才】
中国の学問。漢学。また、それにくわしいこと。からざえ。古今著聞集13「成佐―に長じて」
かん‐さく【漢作】🔗⭐🔉
かん‐さく【漢作】
中国渡来の茶入ちゃいれ中、最も古いもの。
かんざん‐じょう【漢山城】‥ジヤウ🔗⭐🔉
かんざん‐じょう【漢山城】‥ジヤウ
百済くだらの都の一つ。371〜475年まで置かれる。今の韓国京畿道広州とする説が有力。
かん‐し【漢子】🔗⭐🔉
かん‐し【漢子】
男。おのこ。
かん‐し【漢詩】🔗⭐🔉
かん‐し【漢詩】
中国の古典詩。一句四言・五言または七言を主とし、平仄ひょうそく・押韻などの規則があり、古詩・楽府がふ・絶句・律詩・排律などの種類がある。からうた。
かん‐じ【漢字】🔗⭐🔉
かん‐じ【漢字】
古代中国で作られた、漢語2を表記する文字体系。現在は中国・日本・朝鮮で使用。象形・指事から発達した表意文字で、表音的にも用いる。紀元前十数世紀の殷いんの時代にすでに用いられた。篆書てんしょ・隷書・楷書・草書等の書体がある。日本では一般に、「峠」「榊」「辻」等の、いわゆる国字を含めて漢字と称する。真名まな。
⇒かんじ‐おん【漢字音】
⇒かんじ‐コード【漢字コード】
⇒かんじ‐ごはいし‐の‐ぎ【漢字御廃止之儀】
⇒かんじ‐せいげん【漢字制限】
かんじ‐おん【漢字音】🔗⭐🔉
かんしき‐きょう【漢式鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉
かんしき‐きょう【漢式鏡】‥キヤウ
漢・三国・六朝時代の鏡の総称。日本の古墳時代にそれらを模して作られた仿製鏡ぼうせいきょうを含めることもある。→漢鏡
かんじ‐コード【漢字コード】🔗⭐🔉
かんじ‐コード【漢字コード】
文字コード体系のうち、漢字に割り当てられたコード。また、文字コードの俗称。
⇒かん‐じ【漢字】
かんじ‐ごはいし‐の‐ぎ【漢字御廃止之儀】🔗⭐🔉
かんじ‐ごはいし‐の‐ぎ【漢字御廃止之儀】
前島密が慶応2年(1866)12月に将軍慶喜に出した建白書。漢字をやめ仮名を使用すべきことを説いたもので、国字改良論の先駆。
⇒かん‐じ【漢字】
かんじさんおんこう【漢字三音考】‥カウ🔗⭐🔉
かんじさんおんこう【漢字三音考】‥カウ
音韻書。本居宣長著。1巻。1785年(天明5)刊。漢音・呉音・唐音の3音を論じ、併せて日本語が万国語に卓絶することを説く。
かんじ‐せいげん【漢字制限】🔗⭐🔉
かんじ‐せいげん【漢字制限】
漢字学習の負担を軽くするため、使用する漢字の種類を一定の字数の範囲におさえること。
⇒かん‐じ【漢字】
かん‐じゅ【漢儒】🔗⭐🔉
かん‐じゅ【漢儒】
①漢時代の儒者。
②中国の儒者。
かん‐しょ【漢書】🔗⭐🔉
かん‐しょ【漢書】
①漢文の書物。中国の書物。漢籍。からぶみ。
②⇒かんじょ。
⇒かんしょ‐よみ【漢書読み】
かんじょ【漢書】🔗⭐🔉
かんじょ【漢書】
二十四史の一つ。前漢の歴史を記した紀伝体の書。後漢の班固の撰。本紀12巻、表8巻、志10巻、列伝70巻。計100巻(現行120巻)。82年頃成立。妹班昭が兄の死後、表および天文志を補う。紀伝体の断代史という形式は後世史家の範となる。前漢書。西漢書。
かんしょ‐よみ【漢書読み】🔗⭐🔉
かんしょ‐よみ【漢書読み】
(→)「かんせきよみ」に同じ。
⇒かん‐しょ【漢書】
かん‐じん【漢人】🔗⭐🔉
かん‐じん【漢人】
①漢族の人。漢民族。また、ひろく中国の人をいう。
②元代、旧金朝治下の漢人・契丹人・女真人などの称。旧南宋下の南人と区別された。
かん‐すい【漢水】🔗⭐🔉
かん‐すい【漢水】
(Han Shui)長江の最大の支流。全長1532キロメートル。中国陝西省南西隅に発源、漢中を経て湖北省に入り、曲流をかさねて武漢で長江に注ぐ。漢江。
かん‐すうじ【漢数字】🔗⭐🔉
かん‐すうじ【漢数字】
数を表す漢字。漢字の数字。「一・五・十・百・千」など。和数字。
かん‐せき【漢籍】🔗⭐🔉
かん‐せき【漢籍】
中国の書物。(中国人が)漢文で書いた書物。からぶみ。漢書かんしょ。仏典に対して外典げてんを指すことがある。
⇒かんせき‐か【漢籍家】
⇒かんせき‐よみ【漢籍読み】
かんせき‐か【漢籍家】🔗⭐🔉
かんせき‐か【漢籍家】
漢籍に通じた人。漢学者。
⇒かん‐せき【漢籍】
かんせき‐よみ【漢籍読み】🔗⭐🔉
かんせき‐よみ【漢籍読み】
①漢文に返り点・送り仮名などをつけ、字順を変えて読む法。漢文訓読法。漢書読み。
②漢学者。
⇒かん‐せき【漢籍】
かん‐ぞく【漢族】🔗⭐🔉
かん‐ぞく【漢族】
中国文化と中国国家を形成してきた主要民族。現在中国全人口の約9割を占める。その祖は人種的には新石器時代にさかのぼるが、共通の民族意識が成立するのは、春秋時代に自らを諸夏・華夏とよぶようになって以降。それらを漢人・漢族と称するのは、漢王朝成立以後。その後も漢化政策により多くの非漢族が漢族に同化した。
かんちゅう【漢中】🔗⭐🔉
かんちゅう【漢中】
中国陝西省の南西隅、漢水上流の盆地。四川・湖北両省に至る要地。劉邦(漢の高祖)が封ぜられて漢王と称した所。南鄭。
かん‐ちょう【漢朝】‥テウ🔗⭐🔉
かん‐ちょう【漢朝】‥テウ
①中国の漢の朝廷。漢の時代。
②中国。漢土。
かん‐てん【漢天】🔗⭐🔉
かん‐てん【漢天】
天あまの川の見える空。平家物語7「―既にひらきて雲東嶺にたなびき」
かん‐ど【漢土】🔗⭐🔉
かん‐ど【漢土】
中国。もろこし。
かん‐な【漢和】‥ワ🔗⭐🔉
かん‐な【漢和】‥ワ
(カンワの連声)漢和聯句の略。
⇒かんな‐れんく【漢和聯句】
かんな‐さん【漢拏山】🔗⭐🔉
かんな‐さん【漢拏山】
⇒ハルラサン
かんな‐れんく【漢和聯句】‥ワ‥🔗⭐🔉
かんな‐れんく【漢和聯句】‥ワ‥
聯句の一体。五・七・五の17音または七・七の14音の和句と、五言の漢句とをまじえる形式のもののうち、発句が漢句で始まるもの。鎌倉時代以来行われた。漢和。↔和漢聯句
⇒かん‐な【漢和】
かんのわのな‐の‐こくおう‐の‐いん【漢委奴国王印】‥ワウ‥🔗⭐🔉
かんのわのな‐の‐こくおう‐の‐いん【漢委奴国王印】‥ワウ‥
⇒わのなのこくおうのいん
かん‐ぶ【漢武】🔗⭐🔉
かん‐ぶ【漢武】
前漢の武帝。
かん‐ぶん【漢文】🔗⭐🔉
かん‐ぶん【漢文】
①中国古来の文章・文学。現代中国語文に対していう。
②日本で、1にならって書いた、漢字だけの文章。変体漢文を含んでもいう。
⇒かんぶん‐くずし【漢文崩し】
⇒かんぶん‐たい【漢文体】
かん‐ぶんがく【漢文学】🔗⭐🔉
かん‐ぶんがく【漢文学】
中国古来の文学。経書・史書・詩文など。また、日本漢詩文も含めてそれらを研究する学問。
かんぶん‐くずし【漢文崩し】‥クヅシ🔗⭐🔉
かんぶん‐くずし【漢文崩し】‥クヅシ
漢文を和読した体裁の読み方または書き方。
⇒かん‐ぶん【漢文】
かんぶん‐たい【漢文体】🔗⭐🔉
かんぶん‐たい【漢文体】
文章が漢文になっていること。また、漢文訓読の口調にならった文体。
⇒かん‐ぶん【漢文】
かん‐ぶんてん【漢文典】🔗⭐🔉
かん‐ぶんてん【漢文典】
漢文法を説いた書物。
かん‐ぶんぽう【漢文法】‥パフ🔗⭐🔉
かん‐ぶんぽう【漢文法】‥パフ
漢文の文法。
かん‐ぽう【漢方】‥パウ🔗⭐🔉
かんぽう‐い【漢方医】‥パウ‥🔗⭐🔉
かんぽう‐い【漢方医】‥パウ‥
漢方の医師。漢医。
⇒かん‐ぽう【漢方】
かんぽう‐しょうやく【漢方生薬】‥パウシヤウ‥🔗⭐🔉
かんぽう‐しょうやく【漢方生薬】‥パウシヤウ‥
漢方方剤を構成する生薬。
⇒かん‐ぽう【漢方】
かんぽう‐ほうざい【漢方方剤】‥パウハウ‥🔗⭐🔉
かんぽう‐ほうざい【漢方方剤】‥パウハウ‥
漢方医学で用いる処方。複数の和漢薬を約束の分量で調合したもの。
⇒かん‐ぽう【漢方】
かんぽう‐やく【漢方薬】‥パウ‥🔗⭐🔉
かんぽう‐やく【漢方薬】‥パウ‥
漢方で用いる薬。おもに草根・木皮の類。
⇒かん‐ぽう【漢方】
かん‐みょう【漢名】‥ミヤウ🔗⭐🔉
かん‐みょう【漢名】‥ミヤウ
⇒かんめい
かん‐みんぞく【漢民族】🔗⭐🔉
かん‐みんぞく【漢民族】
(→)漢族に同じ。
かん‐やく【漢訳】🔗⭐🔉
かん‐やく【漢訳】
外国語を漢文に訳すこと。「―聖書」
かん‐やく【漢薬】🔗⭐🔉
かん‐やく【漢薬】
漢方医の用いる薬。
かんやひょう‐コンス【漢冶萍公司】‥ヒヤウ‥🔗⭐🔉
かんやひょう‐コンス【漢冶萍公司】‥ヒヤウ‥
中国、湖北省の大冶鉄山、江西省の萍郷炭田の採掘事業と、漢陽鉄廠の製鉄事業とを総合して経営した会社。1907年に成立。日本資本の発言権が強かった。
かん‐よう【漢洋】‥ヤウ🔗⭐🔉
かん‐よう【漢洋】‥ヤウ
(明治期の語)東洋(日本を除く)と西洋。大槻文彦、ことばのうみのおくがき「近藤君は―の学に通明におはするものから」
かんよう【漢陽】‥ヤウ🔗⭐🔉
かんよう【漢陽】‥ヤウ
(Hanyang)中国湖北省、長江と漢水の合流地点の南西にある都市。対岸の漢口・武昌と合併して武漢市を形成。清末に製鉄所や兵器廠が建設されて以来の重工業基地。→漢冶萍かんやひょう公司
かん‐よう【漢窯】‥エウ🔗⭐🔉
かん‐よう【漢窯】‥エウ
漢代の陶窯。また、それで製した陶器。
かん‐わ【漢和】🔗⭐🔉
かん‐わ【漢和】
①中国と日本。
②漢語と日本語。
③漢和字典の略。
④漢和聯句の略。
⇒かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】
⇒かんわ‐れんく【漢和聯句】
かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】🔗⭐🔉
かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】
漢字・漢語の意義を日本語で解説した字典。
⇒かん‐わ【漢和】
かんわ‐れんく【漢和聯句】🔗⭐🔉
かんわ‐れんく【漢和聯句】
⇒かんなれんく
⇒かん‐わ【漢和】
○巻を追うかんをおう
書物を読み進めて行く。「巻を追って面白くなる」
⇒かん【巻】
○棺を蓋いて事定まるかんをおおいてことさだまる
[晋書劉毅伝]死んでこの世を去った後、初めてその人の生前の事業や性行の真価が定まる。「人事は棺を蓋いて定まる」とも。
⇒かん【棺】
○願を起こすがんをおこす
(→)「願を懸ける」に同じ。
⇒がん【願】
○願を懸けるがんをかける
神仏に事の成就を祈願する。
⇒がん【願】
○官をすかんをす
官位につく。狂言、丼礑どぶかっちり「官をせねば平家を語る事が成らぬ程に」
⇒かん【官】
○館を捐つかんをすつ
[史記范雎伝]「館舎を捐つ」に同じ。→館舎(成句)
⇒かん【館】
○願を立てるがんをたてる
(→)「願を懸ける」に同じ。
⇒がん【願】
○款を通ずかんをつうず
[北史盧柔伝]よしみを結ぶ。また、敵に内通する。
⇒かん【款】
○眼を付けるがんをつける
相手の顔や眼をじっとみる意の俗語。言いがかりをつける口実として用いる表現。
⇒がん【眼】
ハルラ‐サン【漢拏山】🔗⭐🔉
ハルラ‐サン【漢拏山】
(Halla-san)韓国済州島の主峰。標高1950メートルで、韓国最高峰。火山活動により形成され、火口湖・寄生火山など特異な景観をなす。
ハンブルク【Hamburg・漢堡】🔗⭐🔉
ハンブルク【Hamburg・漢堡】
ドイツ北部の工業都市。エルベ川の下流部に位置する大貿易港。中世、ハンザ同盟の中心都市の一つ。人口170万5千(1999)。
[漢]漢🔗⭐🔉
漢 字形
 筆順
筆順
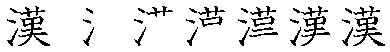 〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2033・3441〕
[
〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2033・3441〕
[ ] 字形
] 字形
 〔水(氵・氺)部11画/14画〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕あや
[意味]
①(特に日本から見た)中国(本土)。から。「漢土・漢民族・漢学・漢籍・漢方・和漢洋」
②おとこ。男子。「好漢・酔漢・痴漢・熱血漢」
③あまのがわ。「忽ちに漢を隔つる恋を成し」〔万葉集〕「天漢・銀漢」
④中国の王朝の名。
㋐前二〇二年劉邦りゅうほうが項羽を倒して建てた国。前漢。「漢書」
㋑西紀二五年劉秀(=光武帝)が再興した国。後漢。
㋒三国の一つ。劉備の建てた国。蜀漢しょくかん。▶このほか、五胡十六国、五代十国の中にもある。
[解字]
形声。「水」+音符「
〔水(氵・氺)部11画/14画〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕あや
[意味]
①(特に日本から見た)中国(本土)。から。「漢土・漢民族・漢学・漢籍・漢方・和漢洋」
②おとこ。男子。「好漢・酔漢・痴漢・熱血漢」
③あまのがわ。「忽ちに漢を隔つる恋を成し」〔万葉集〕「天漢・銀漢」
④中国の王朝の名。
㋐前二〇二年劉邦りゅうほうが項羽を倒して建てた国。前漢。「漢書」
㋑西紀二五年劉秀(=光武帝)が再興した国。後漢。
㋒三国の一つ。劉備の建てた国。蜀漢しょくかん。▶このほか、五胡十六国、五代十国の中にもある。
[解字]
形声。「水」+音符「 」(=水がない)。天の川の意。古く揚子江の支流の名とし、その川の流れる地方の名となった。唐代以後、中国人がみずからの国・民族を称していう語となった。
[下ツキ
悪漢・雲漢・怪漢・凶漢・巨漢・銀漢・好漢・皇漢・酔漢・星漢・痴漢・天漢・暴漢・木強漢・羅漢・和漢
[難読]
漢織あやはとり
」(=水がない)。天の川の意。古く揚子江の支流の名とし、その川の流れる地方の名となった。唐代以後、中国人がみずからの国・民族を称していう語となった。
[下ツキ
悪漢・雲漢・怪漢・凶漢・巨漢・銀漢・好漢・皇漢・酔漢・星漢・痴漢・天漢・暴漢・木強漢・羅漢・和漢
[難読]
漢織あやはとり
 筆順
筆順
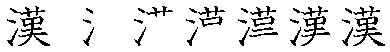 〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2033・3441〕
[
〔水(氵・氺)部10画/13画/教育/2033・3441〕
[ ] 字形
] 字形
 〔水(氵・氺)部11画/14画〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕あや
[意味]
①(特に日本から見た)中国(本土)。から。「漢土・漢民族・漢学・漢籍・漢方・和漢洋」
②おとこ。男子。「好漢・酔漢・痴漢・熱血漢」
③あまのがわ。「忽ちに漢を隔つる恋を成し」〔万葉集〕「天漢・銀漢」
④中国の王朝の名。
㋐前二〇二年劉邦りゅうほうが項羽を倒して建てた国。前漢。「漢書」
㋑西紀二五年劉秀(=光武帝)が再興した国。後漢。
㋒三国の一つ。劉備の建てた国。蜀漢しょくかん。▶このほか、五胡十六国、五代十国の中にもある。
[解字]
形声。「水」+音符「
〔水(氵・氺)部11画/14画〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕あや
[意味]
①(特に日本から見た)中国(本土)。から。「漢土・漢民族・漢学・漢籍・漢方・和漢洋」
②おとこ。男子。「好漢・酔漢・痴漢・熱血漢」
③あまのがわ。「忽ちに漢を隔つる恋を成し」〔万葉集〕「天漢・銀漢」
④中国の王朝の名。
㋐前二〇二年劉邦りゅうほうが項羽を倒して建てた国。前漢。「漢書」
㋑西紀二五年劉秀(=光武帝)が再興した国。後漢。
㋒三国の一つ。劉備の建てた国。蜀漢しょくかん。▶このほか、五胡十六国、五代十国の中にもある。
[解字]
形声。「水」+音符「 」(=水がない)。天の川の意。古く揚子江の支流の名とし、その川の流れる地方の名となった。唐代以後、中国人がみずからの国・民族を称していう語となった。
[下ツキ
悪漢・雲漢・怪漢・凶漢・巨漢・銀漢・好漢・皇漢・酔漢・星漢・痴漢・天漢・暴漢・木強漢・羅漢・和漢
[難読]
漢織あやはとり
」(=水がない)。天の川の意。古く揚子江の支流の名とし、その川の流れる地方の名となった。唐代以後、中国人がみずからの国・民族を称していう語となった。
[下ツキ
悪漢・雲漢・怪漢・凶漢・巨漢・銀漢・好漢・皇漢・酔漢・星漢・痴漢・天漢・暴漢・木強漢・羅漢・和漢
[難読]
漢織あやはとり
広辞苑に「漢」で始まるの検索結果 1-91。