複数辞典一括検索+![]()
![]()
つがい【番】ツガヒ🔗⭐🔉
つがい【番】ツガヒ
(動詞ツガウの連用形から)
①二つ組むこと。また、そのもの。くみ。法華義疏長保点「此の六瑞を束つかねて三の霍ツガヒとす」
②動物の雄おすと雌めすとの一対。「一―」
③めおと。夫婦。
④つがいめ。関節。日葡辞書「ツガイガハナレタ」
⑤機会。折。きっかけ。醒睡笑「剃りはてんとする―にふと立ち」
⑥都合。具合。狂言、瓜盗人「当年は日和続きもよし、雨の―も良いによつて」
⇒つがい‐ごもの【番小者】
⇒つがい‐どり【番鳥】
⇒つがい‐なわ【番縄】
⇒つがい‐ば【番葉】
⇒つがい‐まい【番舞】
⇒つがい‐むすび【番結び】
⇒つがい‐め【番目】
つがい‐ごもの【番小者】ツガヒ‥🔗⭐🔉
つがい‐ごもの【番小者】ツガヒ‥
馬や輿こしの先に立って随行する二人の小者。〈日葡辞書〉
⇒つがい【番】
つがい‐どり【番鳥】ツガヒ‥🔗⭐🔉
つがい‐どり【番鳥】ツガヒ‥
雌雄そろった鳥。
⇒つがい【番】
つがい‐なわ【番縄】ツガヒナハ🔗⭐🔉
つがい‐なわ【番縄】ツガヒナハ
柱と横木とのつがいめを結ぶ縄。
⇒つがい【番】
つがい‐ば【番葉】ツガヒ‥🔗⭐🔉
つがい‐ば【番葉】ツガヒ‥
互いに向き合っている葉。
⇒つがい【番】
つがい‐むすび【番結び】ツガヒ‥🔗⭐🔉
つがい‐むすび【番結び】ツガヒ‥
左右で一対をなす結び方。
⇒つがい【番】
つがい‐め【番目】ツガヒ‥🔗⭐🔉
つがい‐め【番目】ツガヒ‥
組み合う部分。関節。
⇒つがい【番】
つが・う【番う】ツガフ🔗⭐🔉
つが・う【番う】ツガフ
[一]〔自五〕
(「継ぎ合う」の意)
①二つのものが組み合う。対ついになる。千載和歌集恋「独り寝る我にて知りぬ池水に―・はぬ鴛鴦おしのおもふ心を」
②雌雄が交尾する。「鳥が―・う」
[二]〔他四・下二〕
⇒つがえる(下一)
つが・える【番える】ツガヘル🔗⭐🔉
つが・える【番える】ツガヘル
〔他下一〕[文]つが・ふ(四・下二)
①二つ以上を組み合わす。日葡辞書「アシヲツガウテヌル」
②弓の弦に矢をあてる。平家物語4「大鏑おおかぶらを取つて―・ひ、鵼ぬえの声しつる内裏の上へぞ射上げたる」
③言いかためる。固く約束する。浄瑠璃、井筒業平河内通「使者に向ひ、―・ひし詞は取りかへされず」
ばん【番】🔗⭐🔉
ばん【番】
(交替で勤務する人々の集まりの意)
①順にたがいに入れ替わること。また、入れ替わってする役目。今昔物語集11「―を結びて、此の経を守り」。「今度は君の―だ」
②見張ること。見張る人。竹取物語「女どもを―にをりて守らす」。「―をする」
③(多数備えて番号を付けておく意から)常用の粗末なものに冠する語。「―茶」
④順序。等級。「―外」
⑤つがい。組合せ。「結びの一―」
⑥舞曲の数を数える語。
ばん‐いし【番医師】🔗⭐🔉
ばん‐いし【番医師】
江戸幕府の医師の職名。若年寄の支配に属し、城中の表方で医療をつかさどり、また桔梗ききょうの間に宿直して不時の治療をした。
ばん‐いち【番一】🔗⭐🔉
ばん‐いち【番一】
①「一番」を反対に言った語。江戸末期の通言で、一番の意。
②賭博用語で、1のこと。
ばん‐いり【番入】🔗⭐🔉
ばん‐いり【番入】
江戸幕府で、旗本の部屋住の者や非役の者が採用されて大番・両番に入ること。
ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ🔗⭐🔉
ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ
1番の謡曲全部をうたうこと。素謡すうたいと番囃子ばんばやしとある。→小謡こうたい
ばん‐がい【番外】‥グワイ🔗⭐🔉
ばん‐がい【番外】‥グワイ
①定められた番数ばんかずや番組のほか。予定以外。「―の余興」
②会議の正式の構成員でなくて、その席に列するもの。「―委員」
③普通とはかけ離れて違っていること。「彼は―だ」
⇒ばんがい‐ち【番外地】
ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥🔗⭐🔉
ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥
番地のない土地。
⇒ばん‐がい【番外】
ばん‐がく【番楽】🔗⭐🔉
ばん‐がく【番楽】
秋田・山形両県で、秋に行われる神楽かぐらの一種。能楽の古い形を残している。
ばん‐がさ【番傘】🔗⭐🔉
ばん‐がさ【番傘】
竹骨に紙を張り油をひいた、粗末な雨傘。
ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ🔗⭐🔉
ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ
鎌倉前期、後鳥羽上皇から召し出されて1カ月交替で院の鍛冶場に勤番した備前・備中・山城などの刀鍛冶。備前の則宗・延房、粟田口の国安・国友など。御番鍛冶。
ばん‐がしら【番頭】🔗⭐🔉
ばん‐がしら【番頭】
①武家の番衆ばんしゅうの長。
②江戸時代、大番衆・小姓組番衆・書院番衆などの長。
ばん‐かず【番数】🔗⭐🔉
ばん‐かず【番数】
番のかず。番組・取組のかず。
ばん‐かた【番方】🔗⭐🔉
ばん‐かた【番方】
①(→)番衆ばんしゅうに同じ。
②番衆2の役職を以て仕える家臣の系列。
ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ🔗⭐🔉
ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ
当番をかわること。かわりばん。交代。
ばん‐きしゃ【番記者】🔗⭐🔉
ばん‐きしゃ【番記者】
特定の政治家などの担当として、常にそばにいて取材する記者。
ばん‐ギセル【番煙管】🔗⭐🔉
ばん‐ギセル【番煙管】
ふだん用いる粗末な長キセル。煙草入に入れて携帯するものと区別していう。
ばん‐ぐそく【番具足】🔗⭐🔉
ばん‐ぐそく【番具足】
一般に警備の番人の使用する粗末な具足。〈日葡辞書〉
ばん‐ぐみ【番組】🔗⭐🔉
ばん‐ぐみ【番組】
①番衆の組。交替勤務のために編成された各組。〈日葡辞書〉
②演芸・勝負事・放送などの組合せ。それを記したもの。プログラム。また、放送などの種目。「娯楽―」
ばん‐くるわせ【番狂わせ】‥クルハセ🔗⭐🔉
ばん‐くるわせ【番狂わせ】‥クルハセ
①予想外の出来事で順番の狂うこと。
②勝負事で予想外の結果が出ること。
ばん‐けん【番犬】🔗⭐🔉
ばん‐けん【番犬】
番をする犬。ばんいぬ。
ばん‐こ【番子】🔗⭐🔉
ばん‐こ【番子】
①「散手」や「貴徳」などの舞楽で、鉾ほこを持って出て舞人に渡すなどする、舞人の下役。人従。
②警備に従う下役。請負辻番などの夜番人。
③番太の異称。
ばん‐こ【番戸】🔗⭐🔉
ばん‐こ【番戸】
もと居住地を区別するためにつけた番号。今は番地に統一。
ばん‐こ【番個】🔗⭐🔉
ばん‐こ【番個】
花札で、12回ずつをまとめて数える語。1年。
ばん‐ごう【番号】‥ガウ🔗⭐🔉
ばん‐ごう【番号】‥ガウ
一つ一つを区別するために順番に付した数字や符号。ナンバー。「出席―」「電話―」「―をつける」
⇒ばんごう‐いんじき【番号印字器】
⇒ばんごう‐ふだ【番号札】
ばんごう‐いんじき【番号印字器】‥ガウ‥🔗⭐🔉
ばんごう‐いんじき【番号印字器】‥ガウ‥
番号を押捺する器械。ナンバリング‐マシン。
⇒ばん‐ごう【番号】
ばんこう‐か【番紅花】‥クワ🔗⭐🔉
ばんこう‐か【番紅花】‥クワ
サフランの漢名。
ばんごう‐ふだ【番号札】‥ガウ‥🔗⭐🔉
ばんごう‐ふだ【番号札】‥ガウ‥
順番を示す数字を書いた札。
⇒ばん‐ごう【番号】
ばん‐ごや【番小屋】🔗⭐🔉
ばん‐ごや【番小屋】
①番人のいる小屋。番をするために造った小屋。
②江戸各町の自身番に属した詰所。町民が交替で夜番した。番屋。
ばん‐ざい【番菜】🔗⭐🔉
ばん‐ざい【番菜】
ふだんの日の食事の副食物。おかず。おばんざい。関東の惣菜そうざいに対して、主に京阪地方でいう。守貞漫稿「平日の菜を京阪にては―と云、江戸にて惣ざいと云」
ばん‐し【番士】🔗⭐🔉
ばん‐し【番士】
①組々に分けられた兵士。
②番に当たって守る兵士。
③(→)番衆ばんしゅう2に同じ。
ばん‐しゅう【番衆】🔗⭐🔉
ばん‐しゅう【番衆】
①番をする人。番人。番方。
②武家時代、番頭ばんがしらに率いられ、殿中・営中に宿直勤番して雑務・警衛をつかさどった者。番方。番士。
ばん‐しょ【番所】🔗⭐🔉
ばん‐しょ【番所】
①番人の詰める所。見張り所。
②江戸時代、交通の要所に設けて通行人や船舶などを見張り、徴税などを行なった所。御番所。
③江戸町奉行所の称。
ばん‐しょう【番匠】‥シヤウ🔗⭐🔉
ばん‐しょう【番匠】‥シヤウ
⇒ばんじょう
ばん‐じょう【番上】‥ジヤウ🔗⭐🔉
ばん‐じょう【番上】‥ジヤウ
順番に交替して勤務すること。また、宿直すること。その方式で勤務する下級職員(雑任など)をもいう。分番。→長上
ばん‐じょう【番匠】‥ジヤウ🔗⭐🔉
ばん‐じょう【番匠】‥ジヤウ
①(正しくはバンショウ。番上の工匠の意)古代、交替で都に上り、木工もく寮で労務に服した木工。
②(→)大工だいくに同じ。〈日葡辞書〉
⇒ばんじょう‐がさ【番匠笠】
⇒ばんじょう‐つち【番匠槌】
⇒ばんじょう‐ばこ【番匠箱】
⇒ばんじょう‐や【番匠屋】
ばんじょう‐がさ【番匠笠】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
ばんじょう‐がさ【番匠笠】‥ジヤウ‥
(大工が用いたからいう)竹の皮でつくったやや大形の笠。ばっちょう笠。ばっち笠。たこらばっちょう。たころばち。
⇒ばん‐じょう【番匠】
ばんじょう‐つち【番匠槌】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
ばんじょう‐つち【番匠槌】‥ジヤウ‥
「さいづち」のこと。(物類称呼)
⇒ばん‐じょう【番匠】
ばんじょう‐ばこ【番匠箱】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
ばんじょう‐ばこ【番匠箱】‥ジヤウ‥
大工の道具箱。
⇒ばん‐じょう【番匠】
ばんじょう‐や【番匠屋】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
ばんじょう‐や【番匠屋】‥ジヤウ‥
(→)大工に同じ。
⇒ばん‐じょう【番匠】
ばん‐じょうゆ【番醤油】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
ばん‐じょうゆ【番醤油】‥ジヤウ‥
醤油粕に食塩水または水を加えて浸出させ、これに食塩を加えて製した下等の醤油。赤黒色で塩味が強い。ばん。番水。
ばん‐しん【番新】🔗⭐🔉
ばん‐しん【番新】
番頭新造の略。梅暦「おりから―障子をあけて」
ばん‐すい【番水】🔗⭐🔉
ばん‐すい【番水】
①中世以降、灌漑用水を順番で使用したこと。
②(→)番醤油ばんじょうゆに同じ。
ばん‐ぜい【番勢】🔗⭐🔉
ばん‐ぜい【番勢】
警備の軍隊。〈日葡辞書〉
ばん‐せん【番船】🔗⭐🔉
ばん‐せん【番船】
(バンブネとも)
①海上警備の船。折たく柴の記下「―これに近づけば、大炮を発して劫おびやかす」
②江戸時代、江戸入港の順番を争った廻船。上方から新綿・新酒を送るのを競った新綿番船・新酒番船の略。
ばん‐せん【番銭】🔗⭐🔉
ばん‐せん【番銭】
背に数字を記した古銭。寛永通宝には一から十六まで、元和通宝には一から三十までの背文がある。
ばん‐せん【番線】🔗⭐🔉
ばん‐せん【番線】
①針金の太さを示した語。番号が大きいほど線径が小さい。現在はミリメートルで示す。
②駅のプラットホームに面した線路を番号で区別していう語。
③映画や出版などの業界で、物流あるいは地域などの系統を分類していう語。
ばん‐そう【番僧】🔗⭐🔉
ばん‐そう【番僧】
輪番に仏堂を守護する僧。堂守どうもり。
ばん‐ぞう【番匠】‥ザウ🔗⭐🔉
ばん‐ぞう【番匠】‥ザウ
⇒ばんじょう
ばん‐そつ【番卒】🔗⭐🔉
ばん‐そつ【番卒】
番をする兵卒。番兵。
ばん‐た【番太】🔗⭐🔉
ばん‐た【番太】
江戸時代、町村に召し抱えられて火の番や盗人の番に当たった者。非人身分の者が多く、番非人ともいわれた。江戸では番太郎といい、平民がなり、町内の番小屋に住んで駄菓子・雑貨などを売りながら、その任をつとめた。好色五人女1「―が拍子木」
ばん‐だい【番代】🔗⭐🔉
ばん‐だい【番代】
番を追って交代すること。また、代りをする者。かわりばん。
ばん‐だい【番台】🔗⭐🔉
ばん‐だい【番台】
公衆浴場などで、入口に高く設けた見張台。また、その番人。
ばん‐だち【番立】🔗⭐🔉
ばん‐だち【番立】
江戸時代の歌舞伎劇場で、午前3時か4時頃、序幕の開く前に、下級俳優が「三番叟さんばそう」の揉もみの段を舞って舞台を浄きよめ、大入りを祈る儀式。また、その囃子。「翁渡し」を略式にしたもの。
ばん‐たろう【番太郎】‥ラウ🔗⭐🔉
ばん‐たろう【番太郎】‥ラウ
「番太ばんた」参照。
○番茶も出花ばんちゃもでばな🔗⭐🔉
○番茶も出花ばんちゃもでばな
番茶も入れたてはおいしい意から、器量のよくない娘でも娘ざかりは美しいというたとえ。「鬼も十八―」
⇒ばん‐ちゃ【番茶】
はん‐ちゅう【範疇】‥チウ
(category)(書経の洪範九疇という語から西周にしあまねがつくった訳語)ギリシア語のカテゴリア。述語の意。述語はいろいろな意味で存在(ある)を表すところから、多義的な存在の基本的構造を表す術語となった。そこからさらに認識の基本的構造を表すことにもなった。
①存在のもっとも基本的な概念(例えば実体・因果関係・量・質など)。これを存在の基本的な在り方と考えるもの(アリストテレス)、悟性の先天的概念と見るもの(カント)など、さまざまな考え方がある。
②個々の科学での基礎となる観念。数学における数の観念、自然諸科学における因果律などの観念。
③同じ種類のものの所属する部類・部門の意。
はん‐ちゅう【藩中】
藩のうち。藩内。同藩。
⇒はんちゅう‐もの【藩中者】
はん‐ちゅうえん【范仲淹】
北宋の文章家・政治家。字は希文。蘇州呉県(江蘇蘇州)の人。士大夫の気節に富み、軍事でも活躍。諡は文正。「岳陽楼記」が有名。著「范文正公集」など。(989〜1052)
はん‐ちゅうせいし【反中性子】
〔理〕中性子の反粒子。→反粒子
はんちゅう‐ぶし【半中節】
「豊後節ぶんごぶし1」参照。
はんちゅう‐もの【藩中者】
①同藩の武士。
②大名の家臣。藩士。藩臣。
⇒はん‐ちゅう【藩中】
はん‐ちょう【班長】‥チヤウ
一班の指揮に当たる長。
はん‐ちょう【班超】‥テウ
後漢の将軍。字は仲升。班彪はんぴょうの子。班固の弟。西域諸国を鎮撫し西域都護となり、定遠侯に封ぜられた。97年、部下の甘英かんえいを大秦たいしんに派遣した。(32〜102)→甘英
はん‐ちょう【藩庁】‥チヤウ
知藩事が事務を執った役所。
ばん‐ちょう【晩潮】‥テウ
夕方にさして来る潮。暮潮。夕汐。
ばん‐ちょう【番長】‥チヤウ
(古くはバンジョウ。交代勤務のために編成された各集団の統率者の意)
①古代、諸衛府の下級幹部。府生ふしょうの下位。はじめ律令制で、兵衛400人の上番ごとの長。のち近衛府などの舎人の長。随身になると騎馬で前駆。「上臈の随身ずいじん」とも呼ぶ。古今著聞集10「院の左―秦頼次」
②学校の非行少年少女仲間の長。
ばん‐ちょう【番帳】‥チヤウ
武家時代、幕府への出仕・宿直の番組をそのつど掲示するのに用いた帳簿。とのい番帳。番文ばんぶみ。
ばんちょうさらやしき【番町皿屋敷】‥チヤウ‥
岡本綺堂作の戯曲。1916年(大正5)初演。家宝の皿を割って真情をためした恋仲の腰元お菊を、青山播磨が殺す。新歌舞伎の代表作。
はん‐ちょくせん【半直線】
直線上の一点で直線を半分に分けたとき、そのおのおの。
はん‐ちん【判賃】
江戸時代、奉公人の保証人となって判を押した者の受ける賃銭。
はん‐ちん【板賃・版賃】
(→)「いたちん」に同じ。
はん‐ちん【藩鎮】
①地方のしずめとして駐屯した軍隊。
②王室の藩屏はんぺいたる諸侯。
③唐・五代の節度使の異称。特に、観察使を兼ねて中央政府から半ば独立し、軍閥化したもの。方鎮。
ハンチング
(ハンチング‐キャップ(hunting cap)の略)(→)鳥打帽。→ハンティング
パンチング【punching】
サッカーで、ゴール‐キーパーが拳こぶしでボールをはじき返すこと。
ハンチントン‐びょう【ハンチントン病】‥ビヤウ
舞踏運動・知能障害・性格障害・パーキンソン症状などを来す慢性進行性の疾患。優性遺伝病の一つ。1872年にハンチントン(George Huntington1850〜1916)よって最初に記録された。
パンツ【pants】
①(→)ズボンに同じ。
②運動する時などにはく短いズボン。
③ズボン風の下ばき。ズロース・ブリーフなど。
バンツー【Bantu】
(人類の意)アフリカのウガンダ・ケニア・カメルーン以南に広く分布するバンツーの言語を話す諸民族の総称。共通の「バンツー人」意識などはもたない。
⇒バンツー‐ごは【バンツー語派】
バンツー‐ごは【バンツー語派】
ニジェール‐コルドファン語族の一語派。スワヒリ語など300以上の言語から成る。
⇒バンツー【Bantu】
はん‐つき【半月】
1カ月の半分。はんげつ。
はん‐つき【半搗き】
米を半ばつきしらげること。また、その米。
⇒はんつき‐まい【半搗き米】
はんつき‐まい【半搗き米】
(→)「五分搗き」に同じ。
⇒はん‐つき【半搗き】
ばん‐づけ【番付】
①歌舞伎俳優・力士その他について、位付けしてその名を順に記したもの。「長者―」「名所―」
②演芸・相撲などの番組を記したもの。
はん‐つや【半通夜】
「通夜2」参照。
はん‐づら【版面】
⇒はんめん
ハンデ
ハンディキャップの訛略。「―をつける」
ばん‐て【番手】
①城に在番する警固の武士。城番。
②陣立で、隊伍の順序をいう語。「一―」
③順番を定めて交代ですること。かわりばんこ。好色一代女5「―に板の間を勤めける」
④糸の太さを表す単位。日本では多く英国式を採用し、重さ1ポンドで1綛かせ(綿糸では長さ840ヤード)のものを1番手といい、番手が多くなるほど糸が細くなる。また、毛糸などでは、重さ1キログラムの長さをキロメートル単位で表したものをいう。
はん‐てい【判定】
①判別して定めること。「写真―」「―を下す」
②ボクシング・柔道などで、規定時間内に勝敗がつかない場合、審判員が優劣を点数などで評価して勝敗を決めること。また、その決定。「―勝ち」
はん‐てい【藩邸】
藩の所有する邸宅。
ハンディー【handy】
大きさが手ごろで取り扱いやすいさま。
パンティー【panties】
女性用の短い下ばき。ショーツ。
⇒パンティー‐ストッキング
パンティー‐ストッキング
(和製語)腰部までをおおう、タイツ風のストッキング。パンスト。
⇒パンティー【panties】
ハンディキャップ【handicap】
①競技などで、力量の差を平均するために、優秀な者に課する負担条件。ハンデ。
②不利な条件。「―を克服する」「―を負う」
⇒ハンディキャップ‐レース【handicap race】
ハンディキャップ‐レース【handicap race】
競技や競馬で、能力に応じて負担に差をつけて行うレース。
⇒ハンディキャップ【handicap】
ハンディクラフト【handicraft】
手作りの製品。手工芸品。また、それを作る作業。
はんていこくしゅぎ‐うんどう【反帝国主義運動】
帝国主義による戦争または植民地化政策に対し反対する運動。反帝運動。
はん‐ていりつ【反定立】
〔哲〕アンチテーゼの訳語。
ハンティング【hunting】
狩り。狩猟。
バンティング【Frederick Grant Banting】
カナダの薬理学者。マクラウド(J. J. R. Macleod1876〜1935)・ベスト(C. H. Best1899〜1978)らとともにインシュリンを発見し、糖尿病治療に応用。ノーベル賞。(1891〜1941)
バンデージ【bandage】
包帯。特にボクシングで、手に巻く包帯。
ばん‐ておけ【番手桶】‥ヲケ
掃除の時などに用いる粗製の手桶。
ばん‐ちょう【番長】‥チヤウ🔗⭐🔉
ばん‐ちょう【番長】‥チヤウ
(古くはバンジョウ。交代勤務のために編成された各集団の統率者の意)
①古代、諸衛府の下級幹部。府生ふしょうの下位。はじめ律令制で、兵衛400人の上番ごとの長。のち近衛府などの舎人の長。随身になると騎馬で前駆。「上臈の随身ずいじん」とも呼ぶ。古今著聞集10「院の左―秦頼次」
②学校の非行少年少女仲間の長。
ばん‐ちょう【番帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
ばん‐ちょう【番帳】‥チヤウ
武家時代、幕府への出仕・宿直の番組をそのつど掲示するのに用いた帳簿。とのい番帳。番文ばんぶみ。
ばんちょうさらやしき【番町皿屋敷】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
ばんちょうさらやしき【番町皿屋敷】‥チヤウ‥
岡本綺堂作の戯曲。1916年(大正5)初演。家宝の皿を割って真情をためした恋仲の腰元お菊を、青山播磨が殺す。新歌舞伎の代表作。
ばん‐づけ【番付】🔗⭐🔉
ばん‐づけ【番付】
①歌舞伎俳優・力士その他について、位付けしてその名を順に記したもの。「長者―」「名所―」
②演芸・相撲などの番組を記したもの。
ばん‐て【番手】🔗⭐🔉
ばん‐て【番手】
①城に在番する警固の武士。城番。
②陣立で、隊伍の順序をいう語。「一―」
③順番を定めて交代ですること。かわりばんこ。好色一代女5「―に板の間を勤めける」
④糸の太さを表す単位。日本では多く英国式を採用し、重さ1ポンドで1綛かせ(綿糸では長さ840ヤード)のものを1番手といい、番手が多くなるほど糸が細くなる。また、毛糸などでは、重さ1キログラムの長さをキロメートル単位で表したものをいう。
ばん‐ておけ【番手桶】‥ヲケ🔗⭐🔉
ばん‐ておけ【番手桶】‥ヲケ
掃除の時などに用いる粗製の手桶。
○判で押したようはんでおしたよう
形式的に同じことをくりかえすさま。いつもきまっているさま。はんこで押したよう。「―な返事」
⇒はん【判】
ばん‐とう【番頭】🔗⭐🔉
ばん‐とう【番頭】
①広く、番を結んで勤務する職にある者の頭のこと。荘園における下級荘官や武家の警護役などの称。ばんがしら。
②商家の雇人の頭で、店の万事を預かる者。手代の上位。
③銭湯で、番台にいる者。また、広く三助なども指した。浮世風呂2「この流しの男は来年頃―に抜けやうといふ人物」
⇒ばんとう‐かぶ【番頭株】
⇒ばんとう‐しんぞう【番頭新造】
ばんとう‐かぶ【番頭株】🔗⭐🔉
ばんとう‐かぶ【番頭株】
商家の雇人で、やがて番頭になるべき地位にある者。金々先生栄花夢「なんでも江戸へ出で―とこぎつけ」
⇒ばん‐とう【番頭】
ばんとう‐しんぞう【番頭新造】‥ザウ🔗⭐🔉
ばんとう‐しんぞう【番頭新造】‥ザウ
江戸新吉原の遊郭で、上位の遊女の諸事世話をする新造の位の女郎。普通の年若い新造とは違って、世事に長じた年輩の女郎。番新ばんしん。番頭女郎。世話女郎。
⇒ばん‐とう【番頭】
ばん‐どころ【番所】🔗⭐🔉
ばん‐どころ【番所】
番人の詰所。ばんしょ。
ばん‐どり【番鳥】🔗⭐🔉
ばん‐どり【番鳥】
鳥の群れの中で、番をする鳥。〈日葡辞書〉
ばん‐にん【番人】🔗⭐🔉
ばん‐にん【番人】
番をする人。見張りをする人。
ばんば【番場】🔗⭐🔉
ばんば【番場】
滋賀県米原まいばら市の町。中山道の宿場。磨針峠すりはりとうげの北方、鳥居本と醒ヶ井との間。
ばん‐ばやし【番囃子】🔗⭐🔉
ばん‐ばやし【番囃子】
能の略式演奏の一つ。一番全部を舞なしに囃子をつけてすわったまま演奏すること。
ばんばん‐しゅっせ【番番出世】🔗⭐🔉
ばんばん‐しゅっせ【番番出世】
①〔仏〕順序を追って諸仏がこの世に現れること。
②年功の順に世に顕れること。
ばん‐ぶくろ【番袋】🔗⭐🔉
ばん‐ぶくろ【番袋】
宿直物とのいものを入れる袋。また、雑多な物を入れる大きな袋。狂言、舎弟「母親をおふくろなりとも―なりともおしやれ」
ばん‐ぶみ【番文】🔗⭐🔉
ばん‐ぶみ【番文】
(→)番帳ばんちょうに同じ。
ばん‐ぺい【番兵】🔗⭐🔉
ばん‐ぺい【番兵】
兵営・陣地の番をする兵。番卒。哨兵。
ばん‐や【番屋】🔗⭐🔉
ばん‐や【番屋】
①番人の詰所。
②江戸時代、番太がいた小屋。好色一代女6「―の行灯の影につれ行き」
③北海道でニシン・サケ漁などの漁夫の泊まる小屋。
ばん‐やく【番役】🔗⭐🔉
ばん‐やく【番役】
交替で順番にあたる勤務。
ばん‐やり【番槍】🔗⭐🔉
ばん‐やり【番槍】
①当直当番の者のために備えておく粗末な槍。
②歌舞伎の小道具。下回りの軍兵の持つ槍。
ばん‐ろんぎ【番論義】🔗⭐🔉
ばん‐ろんぎ【番論義】
順番に一番ずつ問者と答者とを組み合わせて論義すること。つがいろんぎ。今昔物語集12「―をせしめて其の義理を談ず」
ペンキ【番瀝青】🔗⭐🔉
ペンキ【番瀝青】
(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。
⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】
⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】
マチン【馬銭・番木鼈】🔗⭐🔉
マチン【馬銭・番木鼈】
(中国語)フジウツギ科の常緑高木。インドなどの原産。葉は対生し革質、広楕円形。枝端の集散花序に緑白色で円筒状の小花を開く。液果は蜜柑大、その種子は馬銭子またはホミカと呼ばれ、アルカロイドを含み猛毒。殺鼠剤とし、また興奮剤などを製する。ストリキニーネの木。〈日葡辞書〉
[漢]番🔗⭐🔉
番 字形
 筆順
筆順
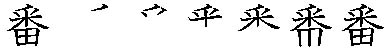 〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕
〔音〕バン(慣) ハン(漢)
〔訓〕つがう・つがい
[意味]
①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」
②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」
③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」
④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」
⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」
⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」
[解字]
会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。
[下ツキ
一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番
〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕
〔音〕バン(慣) ハン(漢)
〔訓〕つがう・つがい
[意味]
①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」
②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」
③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」
④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」
⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」
⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」
[解字]
会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。
[下ツキ
一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番
 筆順
筆順
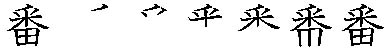 〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕
〔音〕バン(慣) ハン(漢)
〔訓〕つがう・つがい
[意味]
①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」
②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」
③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」
④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」
⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」
⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」
[解字]
会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。
[下ツキ
一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番
〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕
〔音〕バン(慣) ハン(漢)
〔訓〕つがう・つがい
[意味]
①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」
②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」
③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」
④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」
⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」
⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」
[解字]
会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。
[下ツキ
一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番
広辞苑に「番」で始まるの検索結果 1-95。