複数辞典一括検索+![]()
![]()
かざ【風】🔗⭐🔉
かざ【風】
「かぜ」の古形。他語に冠して複合語を作る。「―かみ」「―ぐるま」「―あな」
かざ‐おさえ【風押え】‥オサヘ🔗⭐🔉
かざ‐おさえ【風押え】‥オサヘ
風に吹かれて飛散するのを防ぐためのおもし。
かざ‐がくれ【風隠れ】🔗⭐🔉
かざ‐がくれ【風隠れ】
防風のために作る物陰。また、風の当たらない物陰。玉葉集春「木立をばつくろはずして桜花―にぞ植うべかりける」
かざ‐ぐも【風雲】🔗⭐🔉
かざ‐ぐも【風雲】
風が吹き始める前兆としての雲。かぜくも。義経記4「これこそ―よと申しも果てねば」
かざ‐ごし【風越】🔗⭐🔉
かざ‐ごし【風越】
①風の吹きこすところ。
②「風越の峰」の略。
かざごし‐の‐みね【風越の峰】🔗⭐🔉
かざごし‐の‐みね【風越の峰】
(→)風越山に同じ。(歌枕)
かざこし‐やま【風越山】🔗⭐🔉
かざこし‐やま【風越山】
長野県飯田市の西部にある山。標高1535メートル。白山権現がある。風越の峰。権現山。ふうえつざん。
かざ‐しも【風下】🔗⭐🔉
かざ‐しも【風下】
風の吹き進む方角。かざした。かざじり。かざさき。↔かざかみ
⇒風下に居る
○風下に居るかざしもにいる
人の影響下、支配下に居る。人の風儀を見習う。「風下に立つ」とも。
⇒かざ‐しも【風下】
○風下に居るかざしもにいる🔗⭐🔉
○風下に居るかざしもにいる
人の影響下、支配下に居る。人の風儀を見習う。「風下に立つ」とも。
⇒かざ‐しも【風下】
かざし‐もんく【翳文句】
謡曲中に言うのをはばかる文句がある時、他の文句にかえて謡うもの。一種の忌詞。「鉢の木」の「松はもとより煙にて薪となるはことわりや」の句を、徳川氏の松平をはばかって「松はもとより常磐にて薪となるは梅・桜」と謡う類。
⇒かざし【翳し】
かざ‐じり【風後】
(→)「かざしも」に同じ。
かさ‐じるし【笠標・笠符】
①戦陣で味方の目じるしに兜かぶとなどにつけた標識。多くは小旗を用いた。太平記9「その旗の文、―に皆一番と云ふ文字を書いたりける」
笠標
 ②目じるし。標的。
⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】
かざ‐じるし【風標】
(→)風見かざみに同じ。
かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】‥クワン
兜かぶとの鉢の後の中央の鐶。これに総角あげまきや笠標をつけた。高勝鐶こうしょうかん。
⇒かさ‐じるし【笠標・笠符】
かざ・す【翳す】
〔他五〕
手または手に持った物を上げて、あるものにさしかける。頭上にかかげる。おおうようにする。また、目をおおって光をさえぎる。平家物語9「盛長もさすがに恥づかしげにて、扇を顔に―・しけるぞと聞えし」。「校旗を―・す」「火鉢に手を―・す」「小手を―・して空を見上げる」
かざ・す【挿頭す】
〔他五〕
(髪挿スの転)
①花・枝・造花を髪または冠にさす。万葉集17「春の花今は盛りに匂ふらむ折りて―・さむ」
②飾りつける。頼政集「つくりたる桜をまぜくだものの上に―・してつかはしたりけるを」
かさ‐すげ【笠菅】
スゲの一種。水田に栽培。高さ約1メートル。茎は三稜形、葉は細く堅く、手などを切りやすい。夏、長大な花穂を出す。秋、刈り乾して笠・蓑みのを作るのに用いる。ミノスゲ。
かさ‐だか【嵩高】
①嵩の多いこと。かさばること。「―な荷物」
②相手を見下して横柄おうへいなさま。浄瑠璃、冥途飛脚「手代めが―な返事した」。「―に物を言う」
かざ‐たち【飾太刀】
(→)「かざりたち」に同じ。
かさ‐たて【傘立】
玄関などで外から持ち込んだ傘を立てておくための家具。
か‐さつ【苛察】
細事にわたって、きびしくせんさくすること。苛酷な観察。
がさつ
言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
かさ‐つ・く
〔自五〕
①乾いた音がする。「落葉が―・く」
②水気を失って表面が乾く。「肌が―・く」
カザック【Kazak ロシア】
⇒カザーク
がさ‐つ・く
〔自五〕
①がさがさと音がする。
②おちつかない態度・挙動をする。
かさ‐づけ【笠付】
〔文〕(→)冠付かむりづけに同じ。
かざ‐と【風戸】
①風の吹きこむ戸口。
②煙道の内部に設けた簡単な仕切り口。
かざ‐とおし【風通し】‥トホシ
⇒かぜとおし
かさ‐とがめ【笠咎め】
途中で行きあった者が笠をかぶったままで通り過ぎたり、また、人の笠が自分の笠に触れたのを無礼としてとがめること。
かさ‐どころ【瘡処】
できもののあと。〈倭名類聚鈔3〉
かさとり‐やま【笠取山】
京都府宇治市にある山。紅葉の名所。(歌枕)
かさ‐ど・る【嵩取る】
〔自四〕
①横柄おうへいに構える。得意になる。調子に乗る。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「中にも総兵衛―・つて」
②広く場所をとる。かさばる。
かざ‐ながれ【風流れ】
鷹狩の時、放った鷹が風に吹かれて他へそれて行くこと。散木奇歌集「みかり野に―するはし鷹の声にもつかぬ恨みをぞする」
かざ‐なぎ【風和ぎ・風凪ぎ】
風がやんで波の静まること。
かざ‐なみ【風波】
風と波。また、風のために立つ波。かぜなみ。ふうは。神代紀下「―を冒して海辺うみへたに来到る」
かざ‐なみ【風並】
風の吹く方角。転じて、物事のなりゆき。大勢。かざむき。
かさなり【重なり】
かさなること。また、かさなった状態。
かさなり‐あ・う【重なり合う】‥アフ
〔自五〕
二つ以上のものが互いに重なる。
かさな・る【重なる】
〔自五〕
①物の上に別の同じような物が乗る。源氏物語橋姫「いとど山―・れる御すみかに」。平家物語7「馬には人、人には馬、落ち―・り落ち―・り」。「―・って倒れる」「時計の針が―・る」
②事の上に事が増し加わる。同時に起こる。「不幸が―・る」「日曜と祝日が―・る」
③月日・年齢が積もる。万葉集18「雨降らず日の―・れば」
②目じるし。標的。
⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】
かざ‐じるし【風標】
(→)風見かざみに同じ。
かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】‥クワン
兜かぶとの鉢の後の中央の鐶。これに総角あげまきや笠標をつけた。高勝鐶こうしょうかん。
⇒かさ‐じるし【笠標・笠符】
かざ・す【翳す】
〔他五〕
手または手に持った物を上げて、あるものにさしかける。頭上にかかげる。おおうようにする。また、目をおおって光をさえぎる。平家物語9「盛長もさすがに恥づかしげにて、扇を顔に―・しけるぞと聞えし」。「校旗を―・す」「火鉢に手を―・す」「小手を―・して空を見上げる」
かざ・す【挿頭す】
〔他五〕
(髪挿スの転)
①花・枝・造花を髪または冠にさす。万葉集17「春の花今は盛りに匂ふらむ折りて―・さむ」
②飾りつける。頼政集「つくりたる桜をまぜくだものの上に―・してつかはしたりけるを」
かさ‐すげ【笠菅】
スゲの一種。水田に栽培。高さ約1メートル。茎は三稜形、葉は細く堅く、手などを切りやすい。夏、長大な花穂を出す。秋、刈り乾して笠・蓑みのを作るのに用いる。ミノスゲ。
かさ‐だか【嵩高】
①嵩の多いこと。かさばること。「―な荷物」
②相手を見下して横柄おうへいなさま。浄瑠璃、冥途飛脚「手代めが―な返事した」。「―に物を言う」
かざ‐たち【飾太刀】
(→)「かざりたち」に同じ。
かさ‐たて【傘立】
玄関などで外から持ち込んだ傘を立てておくための家具。
か‐さつ【苛察】
細事にわたって、きびしくせんさくすること。苛酷な観察。
がさつ
言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
かさ‐つ・く
〔自五〕
①乾いた音がする。「落葉が―・く」
②水気を失って表面が乾く。「肌が―・く」
カザック【Kazak ロシア】
⇒カザーク
がさ‐つ・く
〔自五〕
①がさがさと音がする。
②おちつかない態度・挙動をする。
かさ‐づけ【笠付】
〔文〕(→)冠付かむりづけに同じ。
かざ‐と【風戸】
①風の吹きこむ戸口。
②煙道の内部に設けた簡単な仕切り口。
かざ‐とおし【風通し】‥トホシ
⇒かぜとおし
かさ‐とがめ【笠咎め】
途中で行きあった者が笠をかぶったままで通り過ぎたり、また、人の笠が自分の笠に触れたのを無礼としてとがめること。
かさ‐どころ【瘡処】
できもののあと。〈倭名類聚鈔3〉
かさとり‐やま【笠取山】
京都府宇治市にある山。紅葉の名所。(歌枕)
かさ‐ど・る【嵩取る】
〔自四〕
①横柄おうへいに構える。得意になる。調子に乗る。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「中にも総兵衛―・つて」
②広く場所をとる。かさばる。
かざ‐ながれ【風流れ】
鷹狩の時、放った鷹が風に吹かれて他へそれて行くこと。散木奇歌集「みかり野に―するはし鷹の声にもつかぬ恨みをぞする」
かざ‐なぎ【風和ぎ・風凪ぎ】
風がやんで波の静まること。
かざ‐なみ【風波】
風と波。また、風のために立つ波。かぜなみ。ふうは。神代紀下「―を冒して海辺うみへたに来到る」
かざ‐なみ【風並】
風の吹く方角。転じて、物事のなりゆき。大勢。かざむき。
かさなり【重なり】
かさなること。また、かさなった状態。
かさなり‐あ・う【重なり合う】‥アフ
〔自五〕
二つ以上のものが互いに重なる。
かさな・る【重なる】
〔自五〕
①物の上に別の同じような物が乗る。源氏物語橋姫「いとど山―・れる御すみかに」。平家物語7「馬には人、人には馬、落ち―・り落ち―・り」。「―・って倒れる」「時計の針が―・る」
②事の上に事が増し加わる。同時に起こる。「不幸が―・る」「日曜と祝日が―・る」
③月日・年齢が積もる。万葉集18「雨降らず日の―・れば」
 ②目じるし。標的。
⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】
かざ‐じるし【風標】
(→)風見かざみに同じ。
かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】‥クワン
兜かぶとの鉢の後の中央の鐶。これに総角あげまきや笠標をつけた。高勝鐶こうしょうかん。
⇒かさ‐じるし【笠標・笠符】
かざ・す【翳す】
〔他五〕
手または手に持った物を上げて、あるものにさしかける。頭上にかかげる。おおうようにする。また、目をおおって光をさえぎる。平家物語9「盛長もさすがに恥づかしげにて、扇を顔に―・しけるぞと聞えし」。「校旗を―・す」「火鉢に手を―・す」「小手を―・して空を見上げる」
かざ・す【挿頭す】
〔他五〕
(髪挿スの転)
①花・枝・造花を髪または冠にさす。万葉集17「春の花今は盛りに匂ふらむ折りて―・さむ」
②飾りつける。頼政集「つくりたる桜をまぜくだものの上に―・してつかはしたりけるを」
かさ‐すげ【笠菅】
スゲの一種。水田に栽培。高さ約1メートル。茎は三稜形、葉は細く堅く、手などを切りやすい。夏、長大な花穂を出す。秋、刈り乾して笠・蓑みのを作るのに用いる。ミノスゲ。
かさ‐だか【嵩高】
①嵩の多いこと。かさばること。「―な荷物」
②相手を見下して横柄おうへいなさま。浄瑠璃、冥途飛脚「手代めが―な返事した」。「―に物を言う」
かざ‐たち【飾太刀】
(→)「かざりたち」に同じ。
かさ‐たて【傘立】
玄関などで外から持ち込んだ傘を立てておくための家具。
か‐さつ【苛察】
細事にわたって、きびしくせんさくすること。苛酷な観察。
がさつ
言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
かさ‐つ・く
〔自五〕
①乾いた音がする。「落葉が―・く」
②水気を失って表面が乾く。「肌が―・く」
カザック【Kazak ロシア】
⇒カザーク
がさ‐つ・く
〔自五〕
①がさがさと音がする。
②おちつかない態度・挙動をする。
かさ‐づけ【笠付】
〔文〕(→)冠付かむりづけに同じ。
かざ‐と【風戸】
①風の吹きこむ戸口。
②煙道の内部に設けた簡単な仕切り口。
かざ‐とおし【風通し】‥トホシ
⇒かぜとおし
かさ‐とがめ【笠咎め】
途中で行きあった者が笠をかぶったままで通り過ぎたり、また、人の笠が自分の笠に触れたのを無礼としてとがめること。
かさ‐どころ【瘡処】
できもののあと。〈倭名類聚鈔3〉
かさとり‐やま【笠取山】
京都府宇治市にある山。紅葉の名所。(歌枕)
かさ‐ど・る【嵩取る】
〔自四〕
①横柄おうへいに構える。得意になる。調子に乗る。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「中にも総兵衛―・つて」
②広く場所をとる。かさばる。
かざ‐ながれ【風流れ】
鷹狩の時、放った鷹が風に吹かれて他へそれて行くこと。散木奇歌集「みかり野に―するはし鷹の声にもつかぬ恨みをぞする」
かざ‐なぎ【風和ぎ・風凪ぎ】
風がやんで波の静まること。
かざ‐なみ【風波】
風と波。また、風のために立つ波。かぜなみ。ふうは。神代紀下「―を冒して海辺うみへたに来到る」
かざ‐なみ【風並】
風の吹く方角。転じて、物事のなりゆき。大勢。かざむき。
かさなり【重なり】
かさなること。また、かさなった状態。
かさなり‐あ・う【重なり合う】‥アフ
〔自五〕
二つ以上のものが互いに重なる。
かさな・る【重なる】
〔自五〕
①物の上に別の同じような物が乗る。源氏物語橋姫「いとど山―・れる御すみかに」。平家物語7「馬には人、人には馬、落ち―・り落ち―・り」。「―・って倒れる」「時計の針が―・る」
②事の上に事が増し加わる。同時に起こる。「不幸が―・る」「日曜と祝日が―・る」
③月日・年齢が積もる。万葉集18「雨降らず日の―・れば」
②目じるし。標的。
⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】
かざ‐じるし【風標】
(→)風見かざみに同じ。
かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】‥クワン
兜かぶとの鉢の後の中央の鐶。これに総角あげまきや笠標をつけた。高勝鐶こうしょうかん。
⇒かさ‐じるし【笠標・笠符】
かざ・す【翳す】
〔他五〕
手または手に持った物を上げて、あるものにさしかける。頭上にかかげる。おおうようにする。また、目をおおって光をさえぎる。平家物語9「盛長もさすがに恥づかしげにて、扇を顔に―・しけるぞと聞えし」。「校旗を―・す」「火鉢に手を―・す」「小手を―・して空を見上げる」
かざ・す【挿頭す】
〔他五〕
(髪挿スの転)
①花・枝・造花を髪または冠にさす。万葉集17「春の花今は盛りに匂ふらむ折りて―・さむ」
②飾りつける。頼政集「つくりたる桜をまぜくだものの上に―・してつかはしたりけるを」
かさ‐すげ【笠菅】
スゲの一種。水田に栽培。高さ約1メートル。茎は三稜形、葉は細く堅く、手などを切りやすい。夏、長大な花穂を出す。秋、刈り乾して笠・蓑みのを作るのに用いる。ミノスゲ。
かさ‐だか【嵩高】
①嵩の多いこと。かさばること。「―な荷物」
②相手を見下して横柄おうへいなさま。浄瑠璃、冥途飛脚「手代めが―な返事した」。「―に物を言う」
かざ‐たち【飾太刀】
(→)「かざりたち」に同じ。
かさ‐たて【傘立】
玄関などで外から持ち込んだ傘を立てておくための家具。
か‐さつ【苛察】
細事にわたって、きびしくせんさくすること。苛酷な観察。
がさつ
言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
かさ‐つ・く
〔自五〕
①乾いた音がする。「落葉が―・く」
②水気を失って表面が乾く。「肌が―・く」
カザック【Kazak ロシア】
⇒カザーク
がさ‐つ・く
〔自五〕
①がさがさと音がする。
②おちつかない態度・挙動をする。
かさ‐づけ【笠付】
〔文〕(→)冠付かむりづけに同じ。
かざ‐と【風戸】
①風の吹きこむ戸口。
②煙道の内部に設けた簡単な仕切り口。
かざ‐とおし【風通し】‥トホシ
⇒かぜとおし
かさ‐とがめ【笠咎め】
途中で行きあった者が笠をかぶったままで通り過ぎたり、また、人の笠が自分の笠に触れたのを無礼としてとがめること。
かさ‐どころ【瘡処】
できもののあと。〈倭名類聚鈔3〉
かさとり‐やま【笠取山】
京都府宇治市にある山。紅葉の名所。(歌枕)
かさ‐ど・る【嵩取る】
〔自四〕
①横柄おうへいに構える。得意になる。調子に乗る。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「中にも総兵衛―・つて」
②広く場所をとる。かさばる。
かざ‐ながれ【風流れ】
鷹狩の時、放った鷹が風に吹かれて他へそれて行くこと。散木奇歌集「みかり野に―するはし鷹の声にもつかぬ恨みをぞする」
かざ‐なぎ【風和ぎ・風凪ぎ】
風がやんで波の静まること。
かざ‐なみ【風波】
風と波。また、風のために立つ波。かぜなみ。ふうは。神代紀下「―を冒して海辺うみへたに来到る」
かざ‐なみ【風並】
風の吹く方角。転じて、物事のなりゆき。大勢。かざむき。
かさなり【重なり】
かさなること。また、かさなった状態。
かさなり‐あ・う【重なり合う】‥アフ
〔自五〕
二つ以上のものが互いに重なる。
かさな・る【重なる】
〔自五〕
①物の上に別の同じような物が乗る。源氏物語橋姫「いとど山―・れる御すみかに」。平家物語7「馬には人、人には馬、落ち―・り落ち―・り」。「―・って倒れる」「時計の針が―・る」
②事の上に事が増し加わる。同時に起こる。「不幸が―・る」「日曜と祝日が―・る」
③月日・年齢が積もる。万葉集18「雨降らず日の―・れば」
かざ‐はな【風花】🔗⭐🔉
かざ‐はな【風花】
(カザバナとも)
①初冬の風が立って雪または雨のちらちらと降ること。〈[季]冬〉。誹風柳多留7「―の内は居つづけ煮えきらず」
②晴天にちらつく雪。風上かざかみの降雪地から風に送られてまばらに飛来する雪。〈[季]冬〉
③「かざほろし」の異称。
かぜ【風】🔗⭐🔉
かぜ【風】
①空気の流れ。気流。特に、肌で感じるもの。古事記中「畝火山木の葉騒ぎぬ―吹かむとす」。「―が出る」「―で流される」「世間の冷たい―に当たる」
②なりゆき。形勢。風向き。人情本、春色辰巳園「サアサアでへぶ―の悪わりい請うけだ。行かう行かう」
③ならわし。風習。しきたり。流儀。新勅撰和歌集雑「大和島根の―として」
④(接尾語的に)そのようなそぶり。様子。「先輩―を吹かす」
⑤㋐風の病やまい。
㋑(「風邪」と書く)感冒。〈[季]冬〉。「―をひく」
⇒風枝を鳴らさず
⇒風薫る
⇒風が吹けば桶屋が儲かる
⇒風冴ゆる
⇒風死す
⇒風に櫛り雨に沐う
⇒風に順いて呼ぶ
⇒風に付く
⇒風に靡く草
⇒風に柳
⇒風の吹きまわし
⇒風の前の塵
⇒風破窓を射る
⇒風は吹けども山は動かず
⇒風邪は万病の元
⇒風光る
⇒風を切る
⇒風を食らう
⇒風を吸い露を飲む
⇒風を掴む
⇒風を結ぶ
かぜ‐おと【風音】🔗⭐🔉
かぜ‐おと【風音】
風の音。かざおと。
○風が吹けば桶屋が儲かるかぜがふけばおけやがもうかる🔗⭐🔉
○風が吹けば桶屋が儲かるかぜがふけばおけやがもうかる
風が吹くと砂ぼこりが出て盲人がふえ、盲人は三味線をひくのでそれに張る猫の皮が必要で猫が減り、そのため鼠がふえて桶をかじるので桶屋が繁盛する。思わぬ結果が生じる、あるいは、あてにならぬ期待をすることのたとえ。「大風が吹けば桶屋が喜ぶ」「風が吹けば箱屋が儲かる」などとも。
⇒かぜ【風】
か‐せき【化石】クワ‥
①(fossil)地質時代の生命の記録の総称。生物の遺骸あるいはその一部(体化石)、および足あと、這いあと、巣穴、糞などの生活の痕跡(生痕化石)を指す。一般に硬い部分が残り、石化することが多いが、石化していなくても(氷づけのマンモスなど)化石と呼ぶ。
②比喩的に、現在に残る古い物や制度。
⇒かせき‐じんるい【化石人類】
⇒かせき‐そうじょ‐がく【化石層序学】
⇒かせき‐ねんりょう【化石燃料】
⇒かせき‐りん【化石林】
か‐せき【家跡】
家の名跡。家督。家名。
か‐せき【家籍】
戸籍。
かせぎ【枷】
防ぐもの。浄瑠璃、善光寺御堂供養「岩の―に身をひそめ」
かせぎ【稼ぎ】
①励み働くこと。はたらき。
②世渡りのわざ。生業。「―にありつく」
③「稼ぎ高」の略。「―が少ない」
④有利な状態を作り出すこと。「時間―」「点数―」
⇒かせぎ‐だか【稼ぎ高】
⇒かせぎ‐て【稼ぎ手】
⇒かせぎ‐にん【稼ぎ人】
かせ‐ぎ【鹿】
(角が桛木かせぎに似ていることから)鹿の異称。赤染衛門集「朝ぼらけ蔀しとみをあぐと見えつるは―の近く立てるなりけり」
かせ‐ぎ【桛木】
①(→)桛かせ1に同じ。
②木のまたで造り、傾く物を支え、または高い所へ物を押しあげるのに用いる具。
③紋所の名。桛にかたどったもの。
が‐せき【瓦石】グワ‥
瓦と石。転じて、無価値なもの。
かぜきき‐ぐさ【風聞草】
(→)荻おぎの異称。
かせき‐こ【河跡湖】
蛇行の甚だしい河川の一部が河道から断たれて生じた湖。三日月形のものが多い。石狩川流域にその例が見られる。三日月湖。
か‐せきさい【過積載】クワ‥
トラックなどに定められた重量を超える荷物を積み載せること。
かせき‐じんるい【化石人類】クワ‥
第三紀末の鮮新世から第四紀の更新世に生きた人類。出土人骨がすべて化石化していることからこの名がある。
港川人の骨格
提供:国立科学博物館
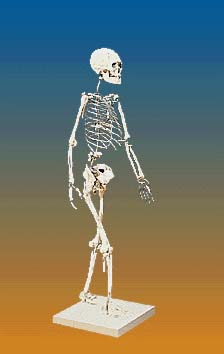 ⇒か‐せき【化石】
かせき‐そうじょ‐がく【化石層序学】クワ‥
(biostratigraphy)地質学の一分野。地層中に含まれる化石の特徴・分布によって地層を区分し体系化する。生層序学。化石層位学。
⇒か‐せき【化石】
かせぎ‐だか【稼ぎ高】
働いて得る金額。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐だ・す【稼ぎ出す】
〔他五〕
①かせぎ始める。
②かせいで金銭をこしらえる。
かせぎ‐て【稼ぎ手】
稼ぎ人。「一家の―」
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐どり
(岩手県で)(→)「かせどり」に同じ。
かせぎ‐にん【稼ぎ人】
①よく働く人。
②かせいで一家を養う人。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせき‐ねんりょう【化石燃料】クワ‥レウ
石炭・石油・天然ガスなど、太古の動植物の残骸が地下で変化して生成され、埋蔵されている燃料の総称。
⇒か‐せき【化石】
かぜ‐ぎみ【風邪気味】
かぜをひいたような様子であること。
かぜ‐きり【風切り】
①風を切ること。風を断つこと。
②風切羽の略。
⇒かぜきり‐がま【風切鎌】
⇒かぜきり‐ばね【風切羽】
かぜきり‐がま【風切鎌】
風除けの呪まじないに屋の棟または竿の先につけて立てる鎌や木製の鎌形あるいは古鎌。
⇒かぜ‐きり【風切り】
かぜきり‐ばね【風切羽】
⇒かざきりばね
⇒かぜ‐きり【風切り】
かせき‐りん【化石林】クワ‥
かつて存在した森林の一部が化石状態で保存されたもの。珪化木の森林など。
⇒か‐せき【化石】
かぜきる‐ひれ【風切る領巾】
風を止め鎮める呪力を持ったひれ。一説に、風を切って進む呪力を持ったひれ。古事記中「天之日矛あめのひぼこの持ち渡り来し物は…風振るひれ、―」
かせ・ぐ【枷ぐ】
〔他四〕
支えとめる。支える。防ぐ。保元物語「しばしは矢に―・がれて、たまるやうにぞ見えし」
かせ・ぐ【桛ぐ】
〔他四〕
桛かせにつむいだ糸を巻く。
かせ・ぐ【稼ぐ】
〔自五〕
①生業に励む。精出して働く。日葡辞書「シゴト、フシン(普請)ナドヲカセグ」
②力をつくす。心を砕く。申楽談儀「水鳥のやうに、下をば―・ぎて、拍子を持つて、上を美しく言ふを」
③得ようと心を砕く。探し求める。浮世物語「奉公を勤めばやと思ひ、方々の御大名方を―・ぐ所に」
④(他動詞として)働いて金を得る。努力して、価値あるものや有利な状況を手に入れる。もうける。「手間賃を―・ぐ」「点を―・ぐ」「時間を―・ぐ」
⇒稼ぐに追いつく貧乏なし
かせ‐ぐい【枷杭】‥グヒ
行動を束縛するもの。ほだし。浄瑠璃、新版歌祭文「義理の柵しがらみ、情の―」
かぜ‐くさ【風草】
イネ科の多年草。路傍などに群生。葉は細長く、平らな茎から伸び、花は大きな円錐花序をなす。ミチシバ。風知草。
カゼクサ
撮影:関戸 勇
⇒か‐せき【化石】
かせき‐そうじょ‐がく【化石層序学】クワ‥
(biostratigraphy)地質学の一分野。地層中に含まれる化石の特徴・分布によって地層を区分し体系化する。生層序学。化石層位学。
⇒か‐せき【化石】
かせぎ‐だか【稼ぎ高】
働いて得る金額。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐だ・す【稼ぎ出す】
〔他五〕
①かせぎ始める。
②かせいで金銭をこしらえる。
かせぎ‐て【稼ぎ手】
稼ぎ人。「一家の―」
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐どり
(岩手県で)(→)「かせどり」に同じ。
かせぎ‐にん【稼ぎ人】
①よく働く人。
②かせいで一家を養う人。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせき‐ねんりょう【化石燃料】クワ‥レウ
石炭・石油・天然ガスなど、太古の動植物の残骸が地下で変化して生成され、埋蔵されている燃料の総称。
⇒か‐せき【化石】
かぜ‐ぎみ【風邪気味】
かぜをひいたような様子であること。
かぜ‐きり【風切り】
①風を切ること。風を断つこと。
②風切羽の略。
⇒かぜきり‐がま【風切鎌】
⇒かぜきり‐ばね【風切羽】
かぜきり‐がま【風切鎌】
風除けの呪まじないに屋の棟または竿の先につけて立てる鎌や木製の鎌形あるいは古鎌。
⇒かぜ‐きり【風切り】
かぜきり‐ばね【風切羽】
⇒かざきりばね
⇒かぜ‐きり【風切り】
かせき‐りん【化石林】クワ‥
かつて存在した森林の一部が化石状態で保存されたもの。珪化木の森林など。
⇒か‐せき【化石】
かぜきる‐ひれ【風切る領巾】
風を止め鎮める呪力を持ったひれ。一説に、風を切って進む呪力を持ったひれ。古事記中「天之日矛あめのひぼこの持ち渡り来し物は…風振るひれ、―」
かせ・ぐ【枷ぐ】
〔他四〕
支えとめる。支える。防ぐ。保元物語「しばしは矢に―・がれて、たまるやうにぞ見えし」
かせ・ぐ【桛ぐ】
〔他四〕
桛かせにつむいだ糸を巻く。
かせ・ぐ【稼ぐ】
〔自五〕
①生業に励む。精出して働く。日葡辞書「シゴト、フシン(普請)ナドヲカセグ」
②力をつくす。心を砕く。申楽談儀「水鳥のやうに、下をば―・ぎて、拍子を持つて、上を美しく言ふを」
③得ようと心を砕く。探し求める。浮世物語「奉公を勤めばやと思ひ、方々の御大名方を―・ぐ所に」
④(他動詞として)働いて金を得る。努力して、価値あるものや有利な状況を手に入れる。もうける。「手間賃を―・ぐ」「点を―・ぐ」「時間を―・ぐ」
⇒稼ぐに追いつく貧乏なし
かせ‐ぐい【枷杭】‥グヒ
行動を束縛するもの。ほだし。浄瑠璃、新版歌祭文「義理の柵しがらみ、情の―」
かぜ‐くさ【風草】
イネ科の多年草。路傍などに群生。葉は細長く、平らな茎から伸び、花は大きな円錐花序をなす。ミチシバ。風知草。
カゼクサ
撮影:関戸 勇
 カセクシス【cathexis】
〔心〕ある人を愛する、ある物を嫌う、というような、対象へのプラスまたはマイナスの関心がいつまでも続くこと。一般的には対象・観念・行為のもつ情的価値、あるいは動機と目標との結びつきを意味する。
かぜ‐ぐすり【風邪薬】
①風邪をなおすための薬。
②酒の異称。
カセクシス【cathexis】
〔心〕ある人を愛する、ある物を嫌う、というような、対象へのプラスまたはマイナスの関心がいつまでも続くこと。一般的には対象・観念・行為のもつ情的価値、あるいは動機と目標との結びつきを意味する。
かぜ‐ぐすり【風邪薬】
①風邪をなおすための薬。
②酒の異称。
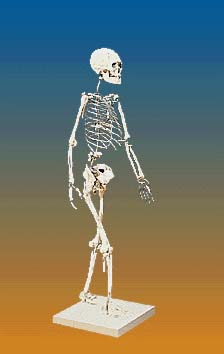 ⇒か‐せき【化石】
かせき‐そうじょ‐がく【化石層序学】クワ‥
(biostratigraphy)地質学の一分野。地層中に含まれる化石の特徴・分布によって地層を区分し体系化する。生層序学。化石層位学。
⇒か‐せき【化石】
かせぎ‐だか【稼ぎ高】
働いて得る金額。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐だ・す【稼ぎ出す】
〔他五〕
①かせぎ始める。
②かせいで金銭をこしらえる。
かせぎ‐て【稼ぎ手】
稼ぎ人。「一家の―」
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐どり
(岩手県で)(→)「かせどり」に同じ。
かせぎ‐にん【稼ぎ人】
①よく働く人。
②かせいで一家を養う人。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせき‐ねんりょう【化石燃料】クワ‥レウ
石炭・石油・天然ガスなど、太古の動植物の残骸が地下で変化して生成され、埋蔵されている燃料の総称。
⇒か‐せき【化石】
かぜ‐ぎみ【風邪気味】
かぜをひいたような様子であること。
かぜ‐きり【風切り】
①風を切ること。風を断つこと。
②風切羽の略。
⇒かぜきり‐がま【風切鎌】
⇒かぜきり‐ばね【風切羽】
かぜきり‐がま【風切鎌】
風除けの呪まじないに屋の棟または竿の先につけて立てる鎌や木製の鎌形あるいは古鎌。
⇒かぜ‐きり【風切り】
かぜきり‐ばね【風切羽】
⇒かざきりばね
⇒かぜ‐きり【風切り】
かせき‐りん【化石林】クワ‥
かつて存在した森林の一部が化石状態で保存されたもの。珪化木の森林など。
⇒か‐せき【化石】
かぜきる‐ひれ【風切る領巾】
風を止め鎮める呪力を持ったひれ。一説に、風を切って進む呪力を持ったひれ。古事記中「天之日矛あめのひぼこの持ち渡り来し物は…風振るひれ、―」
かせ・ぐ【枷ぐ】
〔他四〕
支えとめる。支える。防ぐ。保元物語「しばしは矢に―・がれて、たまるやうにぞ見えし」
かせ・ぐ【桛ぐ】
〔他四〕
桛かせにつむいだ糸を巻く。
かせ・ぐ【稼ぐ】
〔自五〕
①生業に励む。精出して働く。日葡辞書「シゴト、フシン(普請)ナドヲカセグ」
②力をつくす。心を砕く。申楽談儀「水鳥のやうに、下をば―・ぎて、拍子を持つて、上を美しく言ふを」
③得ようと心を砕く。探し求める。浮世物語「奉公を勤めばやと思ひ、方々の御大名方を―・ぐ所に」
④(他動詞として)働いて金を得る。努力して、価値あるものや有利な状況を手に入れる。もうける。「手間賃を―・ぐ」「点を―・ぐ」「時間を―・ぐ」
⇒稼ぐに追いつく貧乏なし
かせ‐ぐい【枷杭】‥グヒ
行動を束縛するもの。ほだし。浄瑠璃、新版歌祭文「義理の柵しがらみ、情の―」
かぜ‐くさ【風草】
イネ科の多年草。路傍などに群生。葉は細長く、平らな茎から伸び、花は大きな円錐花序をなす。ミチシバ。風知草。
カゼクサ
撮影:関戸 勇
⇒か‐せき【化石】
かせき‐そうじょ‐がく【化石層序学】クワ‥
(biostratigraphy)地質学の一分野。地層中に含まれる化石の特徴・分布によって地層を区分し体系化する。生層序学。化石層位学。
⇒か‐せき【化石】
かせぎ‐だか【稼ぎ高】
働いて得る金額。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐だ・す【稼ぎ出す】
〔他五〕
①かせぎ始める。
②かせいで金銭をこしらえる。
かせぎ‐て【稼ぎ手】
稼ぎ人。「一家の―」
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせぎ‐どり
(岩手県で)(→)「かせどり」に同じ。
かせぎ‐にん【稼ぎ人】
①よく働く人。
②かせいで一家を養う人。
⇒かせぎ【稼ぎ】
かせき‐ねんりょう【化石燃料】クワ‥レウ
石炭・石油・天然ガスなど、太古の動植物の残骸が地下で変化して生成され、埋蔵されている燃料の総称。
⇒か‐せき【化石】
かぜ‐ぎみ【風邪気味】
かぜをひいたような様子であること。
かぜ‐きり【風切り】
①風を切ること。風を断つこと。
②風切羽の略。
⇒かぜきり‐がま【風切鎌】
⇒かぜきり‐ばね【風切羽】
かぜきり‐がま【風切鎌】
風除けの呪まじないに屋の棟または竿の先につけて立てる鎌や木製の鎌形あるいは古鎌。
⇒かぜ‐きり【風切り】
かぜきり‐ばね【風切羽】
⇒かざきりばね
⇒かぜ‐きり【風切り】
かせき‐りん【化石林】クワ‥
かつて存在した森林の一部が化石状態で保存されたもの。珪化木の森林など。
⇒か‐せき【化石】
かぜきる‐ひれ【風切る領巾】
風を止め鎮める呪力を持ったひれ。一説に、風を切って進む呪力を持ったひれ。古事記中「天之日矛あめのひぼこの持ち渡り来し物は…風振るひれ、―」
かせ・ぐ【枷ぐ】
〔他四〕
支えとめる。支える。防ぐ。保元物語「しばしは矢に―・がれて、たまるやうにぞ見えし」
かせ・ぐ【桛ぐ】
〔他四〕
桛かせにつむいだ糸を巻く。
かせ・ぐ【稼ぐ】
〔自五〕
①生業に励む。精出して働く。日葡辞書「シゴト、フシン(普請)ナドヲカセグ」
②力をつくす。心を砕く。申楽談儀「水鳥のやうに、下をば―・ぎて、拍子を持つて、上を美しく言ふを」
③得ようと心を砕く。探し求める。浮世物語「奉公を勤めばやと思ひ、方々の御大名方を―・ぐ所に」
④(他動詞として)働いて金を得る。努力して、価値あるものや有利な状況を手に入れる。もうける。「手間賃を―・ぐ」「点を―・ぐ」「時間を―・ぐ」
⇒稼ぐに追いつく貧乏なし
かせ‐ぐい【枷杭】‥グヒ
行動を束縛するもの。ほだし。浄瑠璃、新版歌祭文「義理の柵しがらみ、情の―」
かぜ‐くさ【風草】
イネ科の多年草。路傍などに群生。葉は細長く、平らな茎から伸び、花は大きな円錐花序をなす。ミチシバ。風知草。
カゼクサ
撮影:関戸 勇
 カセクシス【cathexis】
〔心〕ある人を愛する、ある物を嫌う、というような、対象へのプラスまたはマイナスの関心がいつまでも続くこと。一般的には対象・観念・行為のもつ情的価値、あるいは動機と目標との結びつきを意味する。
かぜ‐ぐすり【風邪薬】
①風邪をなおすための薬。
②酒の異称。
カセクシス【cathexis】
〔心〕ある人を愛する、ある物を嫌う、というような、対象へのプラスまたはマイナスの関心がいつまでも続くこと。一般的には対象・観念・行為のもつ情的価値、あるいは動機と目標との結びつきを意味する。
かぜ‐ぐすり【風邪薬】
①風邪をなおすための薬。
②酒の異称。
かぜとともにさりぬ【風と共に去りぬ】🔗⭐🔉
かぜとともにさりぬ【風と共に去りぬ】
(Gone with the Wind)
①ミッチェルの長編小説。1936年刊。勝気で情熱的な女スカーレット=オハラの生き方を、南北戦争時代の変転する社会を背景に描く。
②1の映画化作品。1939年公開。主演ヴィヴィアン=リー・クラーク=ゲーブル。
○風に櫛り雨に沐うかぜにくしけずりあめにかみあらう🔗⭐🔉
○風に櫛り雨に沐うかぜにくしけずりあめにかみあらう
[晋書文帝紀]風雨にさらされて辛苦奔走すること。さまざまな苦労を体験するたとえ。櫛風沐雨しっぷうもくう。
⇒かぜ【風】
○風に順いて呼ぶかぜにしたがいてよぶ🔗⭐🔉
○風に順いて呼ぶかぜにしたがいてよぶ
[荀子勧学]風下に向かって呼べば、風力によって声がよく達するように、勢いに乗じて事をなせば、速く容易に成功する意。
⇒かぜ【風】
○風に付くかぜにつく🔗⭐🔉
○風に付くかぜにつく
①風にまかせる。風にのせる。源氏物語須磨「琴きんのこゑ、風につきてはるかに聞ゆるに」
②風のたよりにことづけする。千載和歌集雑「言の葉しげくちりぢりの風に付けつつ聞ゆれど」
⇒かぜ【風】
かぜにつれなきものがたり【風につれなき物語】
鎌倉時代の物語。初めの1巻のみ現存。作者未詳。1271年(文永8)成立の風葉和歌集に歌46首収載。恋愛と人生のつれなさを叙する。
○風に靡く草かぜになびくくさ🔗⭐🔉
○風に靡く草かぜになびくくさ
[論語顔淵「君子の徳は風なり。小人の徳は草なり。草之これに風を上くわうれば必ず偃ふす」]権力者・有徳者になびき従う者のたとえ。
⇒かぜ【風】
○風に柳かぜにやなぎ🔗⭐🔉
○風に柳かぜにやなぎ
程よくあしらって逆らわないさま。柳に風。
⇒かぜ【風】
かせ‐にん【悴人】
身分の賤しい者。仮名草子、夫婦宗論物語「都辺土に貧なる―一人おはしけるが」→かせもの
かぜ‐ぬき【風抜き】
⇒かざぬき
かぜ‐の‐あし【風の脚】
風の吹いてゆく動き。また、その速さ。
かぜ‐の‐いき【風の息】
〔気〕風速・風向の不規則な変動。地表付近の風に生じる。上層の風では比較的小さい。→突風→スコール→陣風
かぜ‐の‐いろ【風の色】
(草木などの動きで知られる)風の動き。また、その趣。かぜいろ。玉葉集秋「八重葎むぐら秋の分け入る―を」
かぜ‐の‐おとずれ【風の訪れ】‥オトヅレ
風の吹いてくることを人の訪れてくることにたとえていう語。謡曲、景清「―いづちとも、知らぬ迷ひのはかなさを」
かぜ‐の‐かみ【風の神】
①風を支配する神。級長津彦命しなつひこのみことをいう。
②風邪をはやらせる疫神。〈[季]冬〉。好色二代男「―をおくると色町子共さはぎて」
③江戸時代、風邪がはやる時、その疫神を追い払うと称して、仮面をかぶり太鼓を打って門付けして歩いた乞食。
⇒かぜのかみ‐おくり【風の神送り】
⇒かぜのかみ‐まつり【風の神祭】
かぜのかみ‐おくり【風の神送り】
風邪がはやる時、その疫神を送り出す呪まじないの行事。大勢が風の神に擬した人形をかつぎ、提灯をともし、鉦・太鼓ではやし立てて練りあるき、町送りになどする。
⇒かぜ‐の‐かみ【風の神】
かぜのかみ‐まつり【風の神祭】
風災を免れ豊作を祈る祭。7月4日(今は7月第1日曜)まで1週間、奈良の竜田神社で行われる。風鎮祭。→風祭かざまつり
⇒かぜ‐の‐かみ【風の神】
かぜ‐の‐きこえ【風の聞え】
ほのかに聞くこと。うわさ。風聞ふうぶん。風のたより。
かぜ‐の‐け【風邪の気】
風邪の気味。かぜけ。
かぜ‐の‐こ【風の子】
子供が寒風の中でも元気に遊び楽しむことを言う語。「子供は―」
かぜ‐の‐さき【風の先】
風の吹き行く方向。かぜさき。かぜのすえ。
かぜ‐の‐したみず【風の下水】‥ミヅ
風に吹かれて落ちるしずく。夫木和歌抄9「山里の松より落つる―」
かぜ‐の‐すえ【風の末】‥スヱ
風の吹き行く方向。かぜのさき。新千載和歌集恋「をちこちの―なる葛かづらいづ方よりか思ひ絶えなむ」
かぜ‐の‐すがた【風の姿】
①風に吹かれて草木のなびくさま。
②(「風姿ふうし」の訓読)うるわしい姿。尭孝集「高き世に―もたちかくれ富士の烟の絶えぬ道とて」
かぜ‐の‐たまくら【風の手枕】
風に吹かれながら寝ること。拾遺和歌集愚草員外「―月のさむしろ」
かぜ‐の‐たより【風の便り】
①風が吹きおくること。風の使い。古今和歌集春「花の香を―にたぐへてぞ鶯さそふしるべにはやる」
②どこから来たとも分からぬほのかな便り。うわさ。風のつて。風聞ふうぶん。拾遺和歌集哀傷「君まさばまづぞ折らまし桜花―に聞くぞ悲しき」
かぜ‐の‐つかい【風の使】‥ツカヒ
(→)「かぜのたより」1に同じ。
かぜ‐の‐つて【風の伝】
(→)「かぜのたより」2に同じ。
かぜのと‐の【風の音の】
〔枕〕
(風の音のように遠くの意で)「遠き」にかかる。
かぜ‐の‐ながれ【風の流れ】
「風流ふうりゅう」を訓読した語。古今著聞集5「色深き君が心の花散りて身にしむ―とぞ見し」
かぜ‐の‐はふり【風の祝】
風をしずめるために、風神を祭る神官。風の祝子はふりこ。
かぜ‐の‐あし【風の脚】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐あし【風の脚】
風の吹いてゆく動き。また、その速さ。
かぜ‐の‐いき【風の息】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐いろ【風の色】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐いろ【風の色】
(草木などの動きで知られる)風の動き。また、その趣。かぜいろ。玉葉集秋「八重葎むぐら秋の分け入る―を」
かぜ‐の‐おとずれ【風の訪れ】‥オトヅレ🔗⭐🔉
かぜ‐の‐おとずれ【風の訪れ】‥オトヅレ
風の吹いてくることを人の訪れてくることにたとえていう語。謡曲、景清「―いづちとも、知らぬ迷ひのはかなさを」
かぜ‐の‐かみ【風の神】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐かみ【風の神】
①風を支配する神。級長津彦命しなつひこのみことをいう。
②風邪をはやらせる疫神。〈[季]冬〉。好色二代男「―をおくると色町子共さはぎて」
③江戸時代、風邪がはやる時、その疫神を追い払うと称して、仮面をかぶり太鼓を打って門付けして歩いた乞食。
⇒かぜのかみ‐おくり【風の神送り】
⇒かぜのかみ‐まつり【風の神祭】
かぜのかみ‐おくり【風の神送り】🔗⭐🔉
かぜのかみ‐おくり【風の神送り】
風邪がはやる時、その疫神を送り出す呪まじないの行事。大勢が風の神に擬した人形をかつぎ、提灯をともし、鉦・太鼓ではやし立てて練りあるき、町送りになどする。
⇒かぜ‐の‐かみ【風の神】
かぜのかみ‐まつり【風の神祭】🔗⭐🔉
かぜのかみ‐まつり【風の神祭】
風災を免れ豊作を祈る祭。7月4日(今は7月第1日曜)まで1週間、奈良の竜田神社で行われる。風鎮祭。→風祭かざまつり
⇒かぜ‐の‐かみ【風の神】
かぜ‐の‐きこえ【風の聞え】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐きこえ【風の聞え】
ほのかに聞くこと。うわさ。風聞ふうぶん。風のたより。
かぜ‐の‐こ【風の子】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐こ【風の子】
子供が寒風の中でも元気に遊び楽しむことを言う語。「子供は―」
かぜ‐の‐さき【風の先】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐さき【風の先】
風の吹き行く方向。かぜさき。かぜのすえ。
かぜ‐の‐したみず【風の下水】‥ミヅ🔗⭐🔉
かぜ‐の‐したみず【風の下水】‥ミヅ
風に吹かれて落ちるしずく。夫木和歌抄9「山里の松より落つる―」
かぜ‐の‐すえ【風の末】‥スヱ🔗⭐🔉
かぜ‐の‐すえ【風の末】‥スヱ
風の吹き行く方向。かぜのさき。新千載和歌集恋「をちこちの―なる葛かづらいづ方よりか思ひ絶えなむ」
かぜ‐の‐すがた【風の姿】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐すがた【風の姿】
①風に吹かれて草木のなびくさま。
②(「風姿ふうし」の訓読)うるわしい姿。尭孝集「高き世に―もたちかくれ富士の烟の絶えぬ道とて」
かぜ‐の‐たまくら【風の手枕】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐たまくら【風の手枕】
風に吹かれながら寝ること。拾遺和歌集愚草員外「―月のさむしろ」
かぜ‐の‐たより【風の便り】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐たより【風の便り】
①風が吹きおくること。風の使い。古今和歌集春「花の香を―にたぐへてぞ鶯さそふしるべにはやる」
②どこから来たとも分からぬほのかな便り。うわさ。風のつて。風聞ふうぶん。拾遺和歌集哀傷「君まさばまづぞ折らまし桜花―に聞くぞ悲しき」
かぜ‐の‐つかい【風の使】‥ツカヒ🔗⭐🔉
かぜ‐の‐つかい【風の使】‥ツカヒ
(→)「かぜのたより」1に同じ。
かぜ‐の‐つて【風の伝】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐つて【風の伝】
(→)「かぜのたより」2に同じ。
かぜのと‐の【風の音の】🔗⭐🔉
かぜのと‐の【風の音の】
〔枕〕
(風の音のように遠くの意で)「遠き」にかかる。
かぜ‐の‐ながれ【風の流れ】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐ながれ【風の流れ】
「風流ふうりゅう」を訓読した語。古今著聞集5「色深き君が心の花散りて身にしむ―とぞ見し」
かぜ‐の‐はふり【風の祝】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐はふり【風の祝】
風をしずめるために、風神を祭る神官。風の祝子はふりこ。
○風の吹きまわしかぜのふきまわし
その時のなりゆき。「どういう―か、今日は早起きだ」
⇒かぜ【風】
○風の吹きまわしかぜのふきまわし🔗⭐🔉
○風の吹きまわしかぜのふきまわし
その時のなりゆき。「どういう―か、今日は早起きだ」
⇒かぜ【風】
かぜ‐の‐ぼん【風の盆】
風の神を鎮め、豊年を祈る行事。富山市八尾やつお町で毎年二百十日の9月1日から3日間行われる。町中の男女が越中おわら節を三味線・胡弓・太鼓の伴奏で唄い、夜を徹して踊り歩く。おわらまつり。〈[季]秋〉
かぜ‐の‐ま【風の間】
風のやんでいる間。かざま。新勅撰和歌集雑「―に誰結びけん花すすき」
かぜ‐の‐ぼん【風の盆】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐ぼん【風の盆】
風の神を鎮め、豊年を祈る行事。富山市八尾やつお町で毎年二百十日の9月1日から3日間行われる。町中の男女が越中おわら節を三味線・胡弓・太鼓の伴奏で唄い、夜を徹して踊り歩く。おわらまつり。〈[季]秋〉
かぜ‐の‐ま【風の間】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐ま【風の間】
風のやんでいる間。かざま。新勅撰和歌集雑「―に誰結びけん花すすき」
○風の前の塵かぜのまえのちり
物事のはかなく不安定なことのたとえ。「風の前の灯火ともしび」とも。平家物語1「たけき者も遂にはほろびぬ。ひとへに―に同じ」
⇒かぜ【風】
○風の前の塵かぜのまえのちり🔗⭐🔉
○風の前の塵かぜのまえのちり
物事のはかなく不安定なことのたとえ。「風の前の灯火ともしび」とも。平家物語1「たけき者も遂にはほろびぬ。ひとへに―に同じ」
⇒かぜ【風】
かぜのまたさぶろう【風の又三郎】‥ラウ
宮沢賢治作の童話。1934年(昭和9)刊。東北の小学校に転校してきた不思議な少年と、村の子供たちとの交流を描く。
かぜ‐の‐やどり【風の宿】
風を人と見なして、その宿るところ。古今和歌集春「花散らす―は誰か知る」
かぜ‐の‐やなぎ【風の柳】
①柳の枝が風に吹かれた時のように、ゆらゆらと動くさま。
②さからわずに受け流すさま。柳に風。風に柳。
かぜ‐の‐やまい【風の病】‥ヤマヒ
①邪気にあたって受けるという病気。
②神経系統の病気、すなわち頭痛・骨節疼痛などの俗称。
③感冒。
かぜのまたさぶろう【風の又三郎】‥ラウ🔗⭐🔉
かぜのまたさぶろう【風の又三郎】‥ラウ
宮沢賢治作の童話。1934年(昭和9)刊。東北の小学校に転校してきた不思議な少年と、村の子供たちとの交流を描く。
かぜ‐の‐やどり【風の宿】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐やどり【風の宿】
風を人と見なして、その宿るところ。古今和歌集春「花散らす―は誰か知る」
かぜ‐の‐やなぎ【風の柳】🔗⭐🔉
かぜ‐の‐やなぎ【風の柳】
①柳の枝が風に吹かれた時のように、ゆらゆらと動くさま。
②さからわずに受け流すさま。柳に風。風に柳。
かぜ‐の‐やまい【風の病】‥ヤマヒ🔗⭐🔉
かぜ‐の‐やまい【風の病】‥ヤマヒ
①邪気にあたって受けるという病気。
②神経系統の病気、すなわち頭痛・骨節疼痛などの俗称。
③感冒。
○風破窓を射るかぜはそうをいる
[百聯抄解]風が窓の破れから吹き込む。貧しいわび住まいにいう。
⇒かぜ【風】
○風は吹けども山は動かずかぜはふけどもやまはうごかず
まわりが騒がしく混乱していても、自若じじゃくとして少しも動じないたとえ。
⇒かぜ【風】
○風邪は万病の元かぜはまんびょうのもと
風邪はあらゆる病気の元であるから用心すべきであるということ。「風邪は百病の長」とも。
⇒かぜ【風】
○風光るかぜひかる
春の陽光の中をそよそよと風が吹きわたるのをいう。〈[季]春〉
⇒かぜ【風】
○風は吹けども山は動かずかぜはふけどもやまはうごかず🔗⭐🔉
○風は吹けども山は動かずかぜはふけどもやまはうごかず
まわりが騒がしく混乱していても、自若じじゃくとして少しも動じないたとえ。
⇒かぜ【風】
かぜ‐ほろし【風ほろし】🔗⭐🔉
かぜ‐ほろし【風ほろし】
⇒かざほろし
○風を切るかぜをきる🔗⭐🔉
○風を切るかぜをきる
速い速度で進むさま。
⇒かぜ【風】
○風を食らうかぜをくらう🔗⭐🔉
○風を食らうかぜをくらう
様子に感づいてすばやく逃げ去る。
⇒かぜ【風】
○風を吸い露を飲むかぜをすいつゆをのむ🔗⭐🔉
○風を吸い露を飲むかぜをすいつゆをのむ
[荘子逍遥遊]仙人が食を絶って命をつないでいること。
⇒かぜ【風】
○風を掴むかぜをつかむ🔗⭐🔉
○風を掴むかぜをつかむ
てがかりなくつかまえどころのないことにいう。「風を結ぶ」「雲をつかむ」とも。
⇒かぜ【風】
○風を結ぶかぜをむすぶ🔗⭐🔉
○風を結ぶかぜをむすぶ
(→)「風を掴つかむ」に同じ。
⇒かぜ【風】
か‐せん【下線】
(→)アンダー‐ラインに同じ。
か‐せん【化繊】クワ‥
化学繊維の略。「―の服」
か‐せん【戈船】クワ‥
いくさぶね。兵船。
か‐せん【火船】クワ‥
①藁・薪などを積んで点火し風上から流して敵船を焼討ちにする船や筏いかだ。
②火輪船かりんせん。
か‐せん【火戦】クワ‥
(→)火兵戦かへいせんに同じ。
か‐せん【火箭】クワ‥
①⇒ひや(火矢)。
②艦船の非常信号用の火具。空中に打ち上げると彩火・彩煙・音響を放つもの。
か‐せん【火線】クワ‥
①戦闘の最前線で、敵軍と銃・砲火をまじえるところ。
②〔理〕平行光線が凹面鏡によって反射される時、反射光線が正確に一点(焦点)に集まらないで、相互に交わってできる包絡線ほうらくせん。
か‐せん【火氈】クワ‥
燃え立つような緋色の毛氈。
か‐せん【加線】
五線譜で、五線以外に、その上または下に引く短い補助の線。
か‐せん【花仙】クワ‥
〔植〕(花中神仙の略)(→)海棠かいどうの異称。
か‐せん【佳饌・嘉饌】
立派な料理。
か‐せん【河川】
河かわ。多く、大きい河と小さい川とを総称していう。
⇒かせん‐こうがく【河川工学】
⇒かせん‐しき【河川敷】
⇒かせん‐ほう【河川法】
か‐せん【河船】
かわぶね。
か‐せん【河戦】
河の中で船を用いないでする戦闘。
か‐せん【科銭】クワ‥
科料の金銭。罰金。
か‐せん【架線】
①送電線・電話線などをかけわたすこと。また、かけわたされた線。がせん。「―工事」
②電化された鉄道で電力を車両に供給する電線。
か‐せん【夏癬】
夏期、小疹を生ずる馬の皮膚病。
か‐せん【華箋】クワ‥
他人の手紙の尊敬語。華翰。華墨。
か‐せん【華氈】クワ‥
美しい毛氈。
か‐せん【貨泉】クワ‥
中国、新の王莽おうもうが西暦14年に鋳造した銅銭。円形方孔で、方孔の右左に「貨泉」の2字を表す。日本でも弥生土器に伴って出土。
か‐せん【過銭】クワ‥
過料の金銭。罰金。
か‐せん【靴氈】クワ‥
靴かのくつおよび半靴ほうかの立挙たてあげにめぐらした赤地または青地の錦。花仙。もと毛氈を用いたことからの名。
か‐せん【寡占】クワ‥
(oligopoly)少数の供給者が市場を支配し互いに競争している状態。広義の独占に含まれる。競争者が二者の場合を複占という。
か‐せん【歌仙】
①和歌に秀でた人。六歌仙・三十六歌仙など。
②和歌の三十六歌仙に因んで36句から成る連歌・俳諧の形式。最初は連歌で三十六歌仙の名を句ごとに詠みこんだが、後には単に句数36あるものを指し、蕉風以来俳諧の代表的形態となった。懐紙2折4面に記し、初表しょおもて6句、同裏12句、名残なごりの表12句、同裏6句から成る。四九吟しくぎん。
③素謡すうたい・仕舞などの会で36番を演ずること。
⇒かせん‐え【歌仙絵】
⇒かせん‐ぶげん【歌仙分限】
か‐せん【蝸涎】クワ‥
蝸牛かたつむりの這い歩いた跡に残る、涎よだれのような粘液。
か‐ぜん【可染】
〔仏〕銀の異称。↔生色しょうしき
か‐ぜん【果然】クワ‥
予想どおりであること。案のとおり。はたして。
が‐せん【牙銭】
手数料。口銭。
が‐せん【牙籤】
⇒げせん
が‐せん【画仙】グワ‥
技量のすぐれたえかき。画聖。
⇒がせん‐し【画仙紙】
が‐ぜん【瓦全】グワ‥
[北斉書元景安伝「大丈夫は寧むしろ玉砕す可きも、瓦全する能あたわず」]何もしないでいたずらに身の安全を保つこと。甎全せんぜん。↔玉砕
が‐ぜん【俄然】
にわかなさま。だしぬけなさま。急に。突然。近世紀聞「―相整ひがたきは必定の理」。「―勇気が出た」
かせん‐え【歌仙絵】‥ヱ
三十六歌仙などの像を描き、これに和歌・略歴を書き添えたもの。鎌倉時代から盛行。
⇒か‐せん【歌仙】
かせん‐こうがく【河川工学】
土木工学の一分野。主として河川の改修・保全と利用に関する問題を扱う。
⇒か‐せん【河川】
がせん‐し【画仙紙】グワ‥
(「画箋紙」「雅仙紙」とも書く)中国安徽省宣州原産の宣紙で、白色大判の書画用の紙の称。これを模して日本で製したものを「和画仙」と呼ぶ。
⇒が‐せん【画仙】
かせん‐しき【河川敷】
河川法によって規定された河川の敷地。水位によって高水敷・低水敷に分けられる。
⇒か‐せん【河川】
かせんねん【迦旃延】
(梵語Mahākātyāyana摩訶まか迦旃延)釈尊十大弟子の一人。論義第一と称された。インド西部の布教に尽力。マハーカッチャーヤナ。
がせん‐ぶ【画線部】グワ‥
印刷の版で、印刷インクが付く部分。画像部分。
かせん‐ぶげん【歌仙分限】
江戸前期、京都の富者36人を、三十六歌仙に擬した称。
⇒か‐せん【歌仙】
かせん‐ほう【河川法】‥ハフ
公共の利害に重大な関係があると認定された河川について、その管理・工事・使用制限・費用負担関係などを規定した法律。1964年制定。
⇒か‐せん【河川】
かせんろく【何羨録】
江戸湾を中心とした釣りの技術書。吉良義央の女婿で陸奥黒石藩主の津軽采女正著。1723年(享保8)成る。河羨録とも。
か‐そ【火鼠】クワ‥
⇒ひねずみ
か‐そ【果蔬】クワ‥
くだものとやさい。
か‐そ【家祖】
①家の祖先。
②祖父の謙称。
か‐そ【家鼠】
⇒いえねずみ
か‐そ【過所・過書】クワ‥
⇒かしょ
か‐そ【過疎】クワ‥
まばらすぎること。ある地域の人口などが少なすぎること。「―地帯」「―化」↔過密
か‐そ【課租】クワ‥
租税を賦課すること。課税。
かぞ【父】
(奈良時代はカソ)父ちち。推古紀(岩崎本)平安初期点「君父カゾに順はず」
かぞ【楮】
⇒こうぞ。〈書言字考節用集〉
かぞ【加須】
埼玉県北東部の市。江戸時代、脇往還の宿場町。特産は鯉幟こいのぼり・剣道具・柔道着・うどんなど。人口6万8千。
が‐そ【画素】グワ‥
(picture element)画像を構成している最小単位。テレビや電送写真では、走査線の幅を1辺とする正方形。ピクセル。
かぞ‐いろ【父母】
(古くは清音)父母。両親。かぞいろは。堀河百首雑「―の住み荒らしたる宿なれば」
かぞ‐いろは【父母】
(古くは清音)(→)「かぞいろ」に同じ。
か‐そう【下層】
幾重にも重なったものの、下の方の部分。下の層。下の階層。
⇒かそう‐うん【下層雲】
⇒かそう‐かいきゅう【下層階級】
⇒かそう‐しゃかい【下層社会】
か‐そう【火葬】クワサウ
死体を焼き、骨を拾って葬ること。荼毘だび。続日本紀1「(文武)四年…遺教を奉じて粟原に―す。天下の―これよりして始まる」。「―に付す」
⇒かそう‐ば【火葬場】
か‐そう【禾草】クワサウ
①イネ科の草本の総称。
②イネ科草本中、牧草として栽培するもの。
か‐そう【仮相】‥サウ
仮のすがた。仮象。
か‐そう【仮葬】‥サウ
仮に葬ること。↔本葬
か‐そう【仮装】‥サウ
①仮の扮装。
②相手をあざむくため、いつわりよそおうこと。「―空母」
⇒かそう‐ぎょうれつ【仮装行列】
⇒かそう‐こうい【仮装行為】
⇒かそう‐ばいばい【仮装売買】
⇒かそう‐ぶとうかい【仮装舞踏会】
か‐そう【仮想】‥サウ
仮に考えること。仮に想定すること。
⇒かそう‐きおく【仮想記憶】
⇒かそう‐げんじつ【仮想現実】
⇒かそう‐てきこく【仮想敵国】
か‐そう【家相】‥サウ
吉凶に関係があるとされる家の位置・方向・間取りなどのあり方。中国から伝来した俗信で、陰陽五行説に基づく。
かそ・う【掠ふ】カソフ
〔他四〕
(古くはカソブ)
①掠かすめる。盗む。奪い取る。かすぶ。古事記中「その母王ははみこをも―・び取れ」
②人目をくらます。あざむく。狂言、二千石じせんせき「―・うで京うち参りをいたして御ざる」
か‐ぞう【加増】
加え増すこと。特に、禄高や領地の増加。
か‐ぞう【仮像】‥ザウ
鉱物の変化で、仮晶かしょうに同じ。
か‐ぞう【架蔵】‥ザウ
棚に所蔵すること。主に本にいう。
か‐ぞう【家蔵】‥ザウ
家に納めておくこと。また、その物。
か‐ぞう【萱草】クワザウ
(→)「かんぞう」に同じ。
かぞ・う【数ふ】カゾフ
〔他下二〕
⇒かぞえる(下一)
が‐そう【我相】‥サウ
〔仏〕
①自我の観念。また、自我への執着。
②自らおごって他を軽蔑すること。我慢の相。
が‐そう【画僧】グワ‥
画技に長じ、あるいは絵画制作を専門とする鎌倉・室町時代の禅僧。水墨の道釈画・山水画などを盛んに描いた。→絵仏師
が‐ぞう【画像】グワザウ
①えすがた。絵像。
②機械的処理により、感光材料・紙・スクリーン・テレビ‐ブラウン管などの上にうつし出された像。「鮮明な―」
⇒がぞう‐きょう【画像鏡】
⇒がぞう‐こうがく【画像工学】
⇒がぞう‐しょり【画像処理】
⇒がぞう‐しんだん【画像診断】
⇒がぞう‐せき【画像石】
⇒がぞう‐つうしん【画像通信】
かそう‐うん【下層雲】
大気の下層、地上から約2000メートルに生じる雲。層積雲・層雲など。→雲級(表)。
⇒か‐そう【下層】
かそう‐かい【可想界】‥サウ‥
〔哲〕(mundus intelligibilis ラテン)最高の認識能力である知性によってだけとらえられる超感覚的な世界。叡知界。↔感性界
かそう‐かいきゅう【下層階級】‥キフ
下層社会。
⇒か‐そう【下層】
かそう‐きおく【仮想記憶】‥サウ‥
(virtual memory)コンピューターで、プログラム上の論理的なアドレスと記憶装置上の物理的なアドレスとを分離独立させる記憶方式。プログラムに対するメモリーの物理的制約が緩和されるため、多くのコンピューターで採用されている。
⇒か‐そう【仮想】
がぞう‐きょう【画像鏡】グワザウキヤウ
漢式鏡の一つ。後漢〜三国時代に盛行し、背面に神人・竜虎・車馬などの絵画的な文様を持つ。文様が後漢の画像石に似ているところからいう。
⇒が‐ぞう【画像】
かそう‐ぎょうれつ【仮装行列】‥サウギヤウ‥
興を添えるため、思い思いの変装をして練り歩く行列。
⇒か‐そう【仮装】
かそう‐げんじつ【仮想現実】‥サウ‥
(→)バーチャル‐リアリティーに同じ。
⇒か‐そう【仮想】
かそう‐こうい【仮装行為】‥サウカウヰ
〔法〕第三者を欺くために、相手方と通謀してなす虚偽の意思表示から成立している法律行為。例えば実は贈与であるのに売買としておく類。
⇒か‐そう【仮装】
がぞう‐こうがく【画像工学】グワザウ‥
画像の伝送・記録・変換・処理・発生などを扱う工学。光学・写真・印刷・テレビジョン・ファクシミリなど、個々の応用分野として発達した学問・技術を包括する。
⇒が‐ぞう【画像】
かそう‐しゃかい【下層社会】‥クワイ
無財産または地位も低く、生活水準の低い社会階級またはその人々。
⇒か‐そう【下層】
がぞう‐しょり【画像処理】グワザウ‥
画像の含む情報を有効に利用する目的で、画像の変形、変換、特徴の抽出、分類、符号化、あるいは画像の発生などの処理を行うこと。
⇒が‐ぞう【画像】
がぞう‐しんだん【画像診断】グワザウ‥
病変に関する情報を画像にして診断すること。X線診断・超音波診断・核医学画像診断・磁気共鳴画像診断の総称。
⇒が‐ぞう【画像】
がぞう‐せき【画像石】グワザウ‥
おもに後漢時代に、墓室・祠堂・門柱の構築に用いた浮彫りのある石材。その画題は歴史的説話から日常生活全般に及び、当時の芸術資料として重要。
⇒が‐ぞう【画像】
がぞう‐つうしん【画像通信】グワザウ‥
主として画像を伝送対象とする通信の一形態。ファクシミリ・テレビジョン・テレビ電話など。
⇒が‐ぞう【画像】
かそう‐てきこく【仮想敵国】‥サウ‥
近い将来に戦争の発生する危険が予想され、国防上作戦計画を立案しておく必要のある相手国。
⇒か‐そう【仮想】
かぞう‐なます【和雑膾】クワザフ‥
キス・サヨリ・カレイなど、数種の魚の刺身さしみをまぜて蓼酢たでずで和えたもの。かんぞうなます。かんじょうなます。夏の料理。
かそう‐ば【火葬場】クワサウ‥
火葬を行う所。やきば。荼毘所だびしょ。かそうじょう。
⇒か‐そう【火葬】
かそう‐ばいばい【仮装売買】‥サウ‥
①売買する意思がないのに売買したように見せかけること。
②第三者に誤解を与える目的で、同一人物が同時期に、同価格で株式の売りと買いの注文を行うこと。
⇒か‐そう【仮装】
かそう‐ぶとうかい【仮装舞踏会】‥サウ‥タフクワイ
仮装した人が集まって行う舞踏会。
⇒か‐そう【仮装】
かぞえ【数え】カゾヘ
①かぞえること。
②「数え年」の略。
⇒かぞえ‐うた【数え歌】
⇒かぞえ‐づき【数え月】
⇒かぞえ‐どし【数え年】
⇒かぞえ‐び【数え日】
かぞえ‐あ・げる【数え上げる】カゾヘ‥
〔他下一〕[文]かぞへあ・ぐ(下二)
一つ一つとりあげて言う。列挙する。数え立てる。「悪事の数々を―・げる」
かぞえ‐うた【数え歌】カゾヘ‥
①古今集序に、詩経の六義りくぎになぞらえて設けた和歌の一体。「賦」にあたる。その意味内容は明らかでない。
②歌謡で、「一つとや…二つとや…」などと数え立てる歌。多く頭韻を利用。
⇒かぞえ【数え】
かぞえ‐た・てる【数え立てる】カゾヘ‥
〔他下一〕[文]かぞへた・つ(下二)
(→)「かぞえあげる」に同じ。源氏物語宿木「くはしうは、えぞ―・てざりけるとや」
かぞえ‐づき【数え月】カゾヘ‥
12月のこと。
⇒かぞえ【数え】
かぞえ‐どし【数え年】カゾヘ‥
生まれた年を1歳とし、以後正月になると1歳を加えて数える年齢。
⇒かぞえ【数え】
かぞえ‐な・す【数へなす】カゾヘ‥
〔他四〕
数え終える。玉葉集雑「つひにはいかが―・すべき」
かぞえ‐び【数え日】カゾヘ‥
①その年内の残りの日を指折り数えること。また、その残り少ない日。誹風柳多留7「―は親のと子のは大違ひ」
②利益の多い日。書入れ日。
⇒かぞえ【数え】
かぞ・える【数える】カゾヘル
〔他下一〕[文]かぞ・ふ(下二)
(カズ(数)と同源)五指を折って勘定する。従って、基本的には限定された数量を表現する。
①(指を折り)数を勘定する。万葉集5「出で行きし日を―・へつつ今日今日と吾あを待たすらむ父母らはも」。土佐日記「日の経ぬる数を今日いくか二十日三十日と―・ふれば指およびも損はれぬべし」。「参加者の数を―・える」
②列挙する。かぞえあげる。源氏物語夕顔「御随身どももありし。何がしこれがしと―・へしは」。「長所を―・える」
③数に入れる。考慮に入れる。源氏物語関屋「なほ、親しき家人のうちには―・へ給ひけり」。源氏物語胡蝶「そのきはより下は、…哀をもわき給へ。労をも―・へ給へ」。「代表作の一つに―・えられる」
④あまり節をつけないで歌う。白拍子のような無伴奏の歌謡を拍子をとって歌う歌い方にいう。平家物語10「白拍子を誠に面白く―・へすましたりければ」→かずう
⇒数える程
し【風】🔗⭐🔉
し【風】
(複合語として用いる)「かぜ」の古語。万葉集13「荒風あらしの吹けば」。山家集「風巻しまき横切る」
ふう【風】🔗⭐🔉
ふう【風】
①慣習。ならわし。また、物事のしかた。やり方。「昔の―を守る」
②おもむき。あじわい。いかにもそれらしい様子。また、それらしいふり。「君子の―がある」「何気ない―を装う」「フランス―」
③なりふり。すがた。日葡辞書「フウノヨイヒト」
④詩経の国風。一国の風化の有様を詠じた詩。その国その国の民謡。また、漢詩の六義りくぎの一つ。→六義。
⑤仏教で、四大しだいの一つ。
ふう‐あつ【風圧】🔗⭐🔉
ふう‐あつ【風圧】
風が物体に与える圧力。風速の2乗に比例して増加する。
ふう‐い【風位】‥ヰ🔗⭐🔉
ふう‐い【風位】‥ヰ
風の吹いてくる方向。風向。
ふう‐い【風威】‥ヰ🔗⭐🔉
ふう‐い【風威】‥ヰ
はげしい風の威力。
ふう‐いん【風韻】‥ヰン🔗⭐🔉
ふう‐いん【風韻】‥ヰン
おもむきのあること。雅致。風趣。風致。
ふう‐う【風雨】🔗⭐🔉
ふう‐う【風雨】
①風と雨。
②風の加わった強い雨。あめかぜ。あらし。暴風雨。
⇒ふうう‐みつ【風雨密】
ふうう‐みつ【風雨密】🔗⭐🔉
ふうう‐みつ【風雨密】
雨や風を通さないこと。水密よりは密閉性が劣る。
⇒ふう‐う【風雨】
ふう‐うん【風雲】🔗⭐🔉
ふう‐うん【風雲】
①風と雲。自然。
②竜が風と雲とを得て天に昇るように、英雄豪傑などが世に頭角を表す好い機会。また、世が大きく動こうとする気運。「―に乗ずる」
⇒ふううん‐じ【風雲児】
⇒ふううん‐の‐かい【風雲の会】
⇒ふううん‐の‐こころざし【風雲の志】
⇒ふううん‐の‐じょう【風雲の情】
⇒風雲急を告げる
○風雲急を告げるふううんきゅうをつげる
事態が急変し、大事件が起きそうな様子となる。
⇒ふう‐うん【風雲】
○風雲急を告げるふううんきゅうをつげる🔗⭐🔉
○風雲急を告げるふううんきゅうをつげる
事態が急変し、大事件が起きそうな様子となる。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐じ【風雲児】
風雲に際会した人。好機に乗じて世に頭角を表した人。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐の‐かい【風雲の会】‥クワイ
①竜が風雲を得て勢いを得るように、英主と賢臣とが出会うこと。
②英傑などが時機に乗じて志を遂げる好機。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐の‐こころざし【風雲の志】
風雲に乗じて大事をなそうとする志。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐の‐じょう【風雲の情】‥ジヤウ
自然の山野をさすらう旅に出たいという心。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふう‐えい【諷詠】
詩歌をつくること。詩歌を吟ずること。
ふう‐えん【風炎】
〔気〕(→)フェーンのこと。
ふう‐えん【風鳶】
凧たこ。いかのぼり。紙鳶しえん。
ふう‐か【風化】‥クワ
①徳によって教化すること。性霊集3「君臣―の道」
②地表およびその近くの岩石が、空気・水などの物理的・化学的作用で次第にくずされること。岩石が土に変わる変化の過程。比喩的に、心にきざまれたものが弱くなって行くこと。「戦争体験が―する」
③硫酸ナトリウムの十水和物すいわぶつ、炭酸ナトリウムの十水和物などのように結晶水を含んだ結晶が、空気中で漸次水分を失って、粉末状の物質に変わる現象。風解。
⇒ふうか‐せっかい【風化石灰】
ふう‐か【富家】
財貨の多い家。かねもち。ふか。ふけ。
ふう‐が【風雅】
①詩経大序にいう六義りくぎ中の、風と雅。→六義。
②詩歌・文章の道。文芸。太平記1「慈鎮和尚の―にもこえたり」
③蕉門で、俳諧をいう。広義には詩歌・連俳・絵・茶などにわたっていう。芭蕉、柴門の辞「予が―は夏炉冬扇のごとし」
④みやびたこと。俗でないこと。風流。文雅。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―でもなく洒落でなく、せう事なしの山科に、由良之助が侘住居」。「―な暮し」
⇒ふうが‐じん【風雅人】
フーガ【fuga イタリア】
(「逃げる」意のラテン語fugereに由来)楽曲形式の一つ。ある声部の主題で始まり、これに第2声部が模倣的に応答、以後も声部が加わるごとに主題と応答が繰り返される対位法的な楽曲。声部数に応じて3声フーガ・4声フーガ、複数の主題による場合はその数によって2重フーガ・3重フーガなどという。ルネサンスに始まり、バロック時代に本格的な発展をみ、古典派時代以降も使われた。遁走曲。フューグ。
ふう‐かい【風解】
(→)風化ふうか3に同じ。
ふう‐かい【風懐】‥クワイ
心に考えていること。心の中。
ふう‐かい【諷戒】
遠回しにいましめること。それとなくいましめること。
ふう‐がい【風害】
強い風による被害。
ふう‐がい【風概】
①風格。
②風光。
ふう‐かく【風格】
①その人の風貌・態度・言行などにあらわれた品格。ひとがら。人品。「大人たいじんの―」
②味わい。おもむき。「―のある字」
ふうがしゅう【風雅集】‥シフ
(→)風雅和歌集の略称。
ふうが‐じん【風雅人】
風雅を楽しむ人。風流人。
⇒ふう‐が【風雅】
ふうか‐せっかい【風化石灰】‥クワセキクワイ
空気中に長くさらした生石灰が、空気中の水を吸収して崩壊した白色の粉末、すなわち消石灰。ふけばい。
⇒ふう‐か【風化】
ふう‐がら【風柄】
①すがた。容姿。男色大鑑「よそにはふらぬ時雨と眺めし主の―」
②人柄。人品。
ふうがわかしゅう【風雅和歌集】‥シフ
勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。和漢両序がある。花園法皇の監修、光厳上皇が1344年(康永3)着手し、49年(貞和5)頃完成。歌数約2200首。玉葉集を受け京極派歌風を発展。風雅集。
ふう‐がわり【風変り】‥ガハリ
おもむき・ありさま・性格・行動などが普通とはちがっていること。「―な服装」
ふう‐かん【封緘】
封をとじること。封。
⇒ふうかん‐し【封緘紙】
⇒ふうかん‐はがき【封緘葉書】
ふう‐かん【風乾】
加熱・真空などの操作を加えず、空気中に放置するか風を送るかして物を乾燥させること。
ふう‐かん【風寒】
①風と寒さ。また、風が寒いこと。
②陰暦11月の異称。
ふう‐かん【風鑑】
①識見。見識。
②容貌・風采を見て、その人の性質を鑑定すること。
ふう‐かん【諷諫】
遠回しにいさめること。諷規。
ふう‐がん【風眼】
(→)膿漏のうろう眼の俗称。東海道中膝栗毛3「十年ばかしもあとに―とやらを患ひおりまして」
ふうかん‐し【封緘紙】
封のとじ目に貼る小さな紙片。シール。
⇒ふう‐かん【封緘】
ふうかん‐はがき【封緘葉書】
郵便書簡の旧称。
⇒ふう‐かん【封緘】
ふう‐き【風気】
①気候。
②風の吹くけはい。
③感冒。風邪。保元物語「春宮大夫宗能卿は…―とて参内せられず」
④風俗。
⑤気風。気性。
⑥ガスの腸内にたまるもの。
⑦中風ちゅうぶう。中気。
⇒ふうき‐せん【風気疝】
⇒ふうき‐せんつう【風気疝痛】
ふう‐き【風紀】
風俗・風習についての道徳上の節度や規律。日常生活のきまり。特に、男女間の交際の節度。「―を乱す」
⇒ふうき‐びんらん【風紀紊乱】
ふう‐き【風鬼】
①風の神。
②〔仏〕八風(利欲・名誉・苦楽など8種の誘惑)が人心を動揺させ正法しょうぼうに安住させないことをたとえていう。
ふう‐き【富貴】
富んで貴いこと。財貨が多く位の高いこと。ふっき。本朝文粋「―を浮雲に喩ふ」。「―の家柄」↔貧賤。
⇒ふうき‐ぐさ【富貴草】
⇒ふうき‐らん【富貴蘭】
⇒富貴天にあり
ふう‐ぎ【風儀】
①ならわし。風習。行儀。作法。黄表紙、高漫斉行脚日記「俳諧の―もはなはだあしくなり」。「昔の―がすたれる」
②作法にかなったなり・姿。型どおりの姿。好色一代男5「遊女も昔にまさりて、―もさのみ大坂にかはらずといふ」
③能楽で、(→)風体ふうていに同じ。花鏡「その時々の―を、し捨てし捨て忘るれば」
ふうき‐ぐさ【富貴草】
(→)牡丹ぼたんの異称。
⇒ふう‐き【富貴】
ふうき‐せん【風気疝】
(→)風気疝痛の略。
⇒ふう‐き【風気】
ふうき‐せんつう【風気疝痛】
鼓腸こちょうによって生じる疼痛。
⇒ふう‐き【風気】
ふううん‐じ【風雲児】🔗⭐🔉
ふううん‐じ【風雲児】
風雲に際会した人。好機に乗じて世に頭角を表した人。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐の‐かい【風雲の会】‥クワイ🔗⭐🔉
ふううん‐の‐かい【風雲の会】‥クワイ
①竜が風雲を得て勢いを得るように、英主と賢臣とが出会うこと。
②英傑などが時機に乗じて志を遂げる好機。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐の‐こころざし【風雲の志】🔗⭐🔉
ふううん‐の‐こころざし【風雲の志】
風雲に乗じて大事をなそうとする志。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふううん‐の‐じょう【風雲の情】‥ジヤウ🔗⭐🔉
ふううん‐の‐じょう【風雲の情】‥ジヤウ
自然の山野をさすらう旅に出たいという心。
⇒ふう‐うん【風雲】
ふう‐か【風化】‥クワ🔗⭐🔉
ふう‐か【風化】‥クワ
①徳によって教化すること。性霊集3「君臣―の道」
②地表およびその近くの岩石が、空気・水などの物理的・化学的作用で次第にくずされること。岩石が土に変わる変化の過程。比喩的に、心にきざまれたものが弱くなって行くこと。「戦争体験が―する」
③硫酸ナトリウムの十水和物すいわぶつ、炭酸ナトリウムの十水和物などのように結晶水を含んだ結晶が、空気中で漸次水分を失って、粉末状の物質に変わる現象。風解。
⇒ふうか‐せっかい【風化石灰】
ふうか‐せっかい【風化石灰】‥クワセキクワイ🔗⭐🔉
ふうか‐せっかい【風化石灰】‥クワセキクワイ
空気中に長くさらした生石灰が、空気中の水を吸収して崩壊した白色の粉末、すなわち消石灰。ふけばい。
⇒ふう‐か【風化】
ふり【振り・風】🔗⭐🔉
ふり【振り・風】
[一]〔名〕
①振ること。振り動くこと。振りぐあい。「振子の―」「バットの―が大きい」
②外形。すがた。なり。浄瑠璃、凱陣八島「色よし、―よし」
③習慣。しきたり。ふう。甲陽軍鑑3「大方家の―になるなり」
④ふるまい。動作。挙動。「人の―見てわが―直せ」
⑤それらしくよそおうこと。ふう。「知らぬ―をする」
⑥舞踊の仕草しぐさ。また、歌詞の意味する所を形に現すこと。「富士の山」という歌詞に対して、両手で富士の山を描く類。また、舞台で、俳優の動作全部を指す。所作しょさ。科しぐさ。「―をつける」
⑦(通りすがりで)なじみでないこと。「―の客」
⑧褌ふんどしや腰巻を着けないこと。
⑨女物の和服で、袖付から袖下までのあいた部分。また、振袖の略。→和服(図)。
⑩ゆがみ。ずれ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「ちつくり笠に―がある」
⑪やりくり。ふりまわし。日本永代蔵6「借銀かさみ、次第に―に詰まり」
⑫振袖新造の略。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「片町の―を内へ呼び入れ」
⑬振り売りの略。冬の日「荻織る笠を市に―する」
[二]〔接尾〕
①刀剣を数えるのに用いる語。
②⇒ぶり(振り・風)
ぶり【振り・風】🔗⭐🔉
ぶり【振り・風】
〔接尾〕
①名詞や動詞連用形に付いて、形・姿・様子を表す。「身―」「人形―」「男―を上げる」「小―な体」
▷「っぷり」と変化する場合もある。「飲みっぷり」
②時間を表す語に付いて、時日の経過の程度を表す。「久し―」「1年―」
③数量を表す語に付いて、その量に相当する意を表す。「二人―の大盛」
④歌のふしを名づけるのに、歌詞の最初の語に付ける語。「みずぐき―」
[漢]風🔗⭐🔉
風 字形
 筆順
筆順
 〔風部0画/9画/教育/4187・4977〕
〔音〕フウ(漢) フ(呉)
〔訓〕かぜ・かざ=
[意味]
①かぜ。「風雨・風車・暴風・扇風機」
②かぜのようにそれとなく伝わる。「風聞・風評」
③かぜになびかせる。教化する。「風教」
④かぜになびくように自然に形成されたしきたり。ならわし。「土地の風に染まる」「風俗・風習・家風」。特に、『詩経』の六義りくぎの一つで、諸国のおくにぶりを歌った民謡。「国風」
⑤それとなく現れた様子。
㋐すがた。様式。「風采ふうさい・風格・洋風・現代風」
㋑自然のけしき。おもむき。「風景・風情ふぜい・風流」
⑥寒気・邪気・ウイルスによる病気。「風邪・中風ちゅうぶう」
⑦遠まわしに言う。ほのめかす。(同)諷。「風刺・風喩ふうゆ」
[解字]
もと、「鳳ほう」の字をおおとりがはばたいて起こすかぜの意味に用いた。「風」は、「鳳」の「鳥」を「虫」に変えた文字。「
〔風部0画/9画/教育/4187・4977〕
〔音〕フウ(漢) フ(呉)
〔訓〕かぜ・かざ=
[意味]
①かぜ。「風雨・風車・暴風・扇風機」
②かぜのようにそれとなく伝わる。「風聞・風評」
③かぜになびかせる。教化する。「風教」
④かぜになびくように自然に形成されたしきたり。ならわし。「土地の風に染まる」「風俗・風習・家風」。特に、『詩経』の六義りくぎの一つで、諸国のおくにぶりを歌った民謡。「国風」
⑤それとなく現れた様子。
㋐すがた。様式。「風采ふうさい・風格・洋風・現代風」
㋑自然のけしき。おもむき。「風景・風情ふぜい・風流」
⑥寒気・邪気・ウイルスによる病気。「風邪・中風ちゅうぶう」
⑦遠まわしに言う。ほのめかす。(同)諷。「風刺・風喩ふうゆ」
[解字]
もと、「鳳ほう」の字をおおとりがはばたいて起こすかぜの意味に用いた。「風」は、「鳳」の「鳥」を「虫」に変えた文字。「 」が音符で、風の音を表すとも、風を受ける舟の帆を表すとも説かれる。[
」が音符で、風の音を表すとも、風を受ける舟の帆を表すとも説かれる。[ ][
][ ]は異体字。
[下ツキ
悪風・一風・威風・遺風・異風・陰風・淫風・横風・欧風・海風・凱風・学風・下風・家風・画風・棋風・気風・逆風・強風・狂風・矯風・驚風・金風・颶風・薫風・芸風・黄雀風・校風・光風・高風・業風・国風・古風・五風十雨・作風・朔風・疾風・櫛風沐雨・士風・秋風・春風・順風・嘯風・蕉風・書風・新風・腥風・清風・整風・旋風・扇風機・送風・台風・颱風・大風・中風・通風・痛風・唐風・東風・突風・南風・軟風・熱風・俳風・爆風・破傷風・破風・蛮風・半風子・微風・美風・屛風・弊風・偏西風・辺風・貿易風・防風・暴風・無風・洋風・陸風・涼風・良風・緑風・厲風・烈風・和風
[難読]
風邪かぜ・風信子ヒヤシンス
]は異体字。
[下ツキ
悪風・一風・威風・遺風・異風・陰風・淫風・横風・欧風・海風・凱風・学風・下風・家風・画風・棋風・気風・逆風・強風・狂風・矯風・驚風・金風・颶風・薫風・芸風・黄雀風・校風・光風・高風・業風・国風・古風・五風十雨・作風・朔風・疾風・櫛風沐雨・士風・秋風・春風・順風・嘯風・蕉風・書風・新風・腥風・清風・整風・旋風・扇風機・送風・台風・颱風・大風・中風・通風・痛風・唐風・東風・突風・南風・軟風・熱風・俳風・爆風・破傷風・破風・蛮風・半風子・微風・美風・屛風・弊風・偏西風・辺風・貿易風・防風・暴風・無風・洋風・陸風・涼風・良風・緑風・厲風・烈風・和風
[難読]
風邪かぜ・風信子ヒヤシンス
 筆順
筆順
 〔風部0画/9画/教育/4187・4977〕
〔音〕フウ(漢) フ(呉)
〔訓〕かぜ・かざ=
[意味]
①かぜ。「風雨・風車・暴風・扇風機」
②かぜのようにそれとなく伝わる。「風聞・風評」
③かぜになびかせる。教化する。「風教」
④かぜになびくように自然に形成されたしきたり。ならわし。「土地の風に染まる」「風俗・風習・家風」。特に、『詩経』の六義りくぎの一つで、諸国のおくにぶりを歌った民謡。「国風」
⑤それとなく現れた様子。
㋐すがた。様式。「風采ふうさい・風格・洋風・現代風」
㋑自然のけしき。おもむき。「風景・風情ふぜい・風流」
⑥寒気・邪気・ウイルスによる病気。「風邪・中風ちゅうぶう」
⑦遠まわしに言う。ほのめかす。(同)諷。「風刺・風喩ふうゆ」
[解字]
もと、「鳳ほう」の字をおおとりがはばたいて起こすかぜの意味に用いた。「風」は、「鳳」の「鳥」を「虫」に変えた文字。「
〔風部0画/9画/教育/4187・4977〕
〔音〕フウ(漢) フ(呉)
〔訓〕かぜ・かざ=
[意味]
①かぜ。「風雨・風車・暴風・扇風機」
②かぜのようにそれとなく伝わる。「風聞・風評」
③かぜになびかせる。教化する。「風教」
④かぜになびくように自然に形成されたしきたり。ならわし。「土地の風に染まる」「風俗・風習・家風」。特に、『詩経』の六義りくぎの一つで、諸国のおくにぶりを歌った民謡。「国風」
⑤それとなく現れた様子。
㋐すがた。様式。「風采ふうさい・風格・洋風・現代風」
㋑自然のけしき。おもむき。「風景・風情ふぜい・風流」
⑥寒気・邪気・ウイルスによる病気。「風邪・中風ちゅうぶう」
⑦遠まわしに言う。ほのめかす。(同)諷。「風刺・風喩ふうゆ」
[解字]
もと、「鳳ほう」の字をおおとりがはばたいて起こすかぜの意味に用いた。「風」は、「鳳」の「鳥」を「虫」に変えた文字。「 」が音符で、風の音を表すとも、風を受ける舟の帆を表すとも説かれる。[
」が音符で、風の音を表すとも、風を受ける舟の帆を表すとも説かれる。[ ][
][ ]は異体字。
[下ツキ
悪風・一風・威風・遺風・異風・陰風・淫風・横風・欧風・海風・凱風・学風・下風・家風・画風・棋風・気風・逆風・強風・狂風・矯風・驚風・金風・颶風・薫風・芸風・黄雀風・校風・光風・高風・業風・国風・古風・五風十雨・作風・朔風・疾風・櫛風沐雨・士風・秋風・春風・順風・嘯風・蕉風・書風・新風・腥風・清風・整風・旋風・扇風機・送風・台風・颱風・大風・中風・通風・痛風・唐風・東風・突風・南風・軟風・熱風・俳風・爆風・破傷風・破風・蛮風・半風子・微風・美風・屛風・弊風・偏西風・辺風・貿易風・防風・暴風・無風・洋風・陸風・涼風・良風・緑風・厲風・烈風・和風
[難読]
風邪かぜ・風信子ヒヤシンス
]は異体字。
[下ツキ
悪風・一風・威風・遺風・異風・陰風・淫風・横風・欧風・海風・凱風・学風・下風・家風・画風・棋風・気風・逆風・強風・狂風・矯風・驚風・金風・颶風・薫風・芸風・黄雀風・校風・光風・高風・業風・国風・古風・五風十雨・作風・朔風・疾風・櫛風沐雨・士風・秋風・春風・順風・嘯風・蕉風・書風・新風・腥風・清風・整風・旋風・扇風機・送風・台風・颱風・大風・中風・通風・痛風・唐風・東風・突風・南風・軟風・熱風・俳風・爆風・破傷風・破風・蛮風・半風子・微風・美風・屛風・弊風・偏西風・辺風・貿易風・防風・暴風・無風・洋風・陸風・涼風・良風・緑風・厲風・烈風・和風
[難読]
風邪かぜ・風信子ヒヤシンス
広辞苑に「風」で始まるの検索結果 1-78。もっと読み込む