複数辞典一括検索+![]()
![]()
不退転 フタイテン🔗⭐🔉
【不退転】
フタイテン  〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。
〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。 一歩も退かないこと。
一歩も退かないこと。
 〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。
〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。 一歩も退かないこと。
一歩も退かないこと。
両 ふたつ🔗⭐🔉
【両】
 6画 一部 [三年]
区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC
【兩】旧字旧字
6画 一部 [三年]
区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC
【兩】旧字旧字
 8画 入部
区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(リャウ)
8画 入部
区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(リャウ)
 〈li
〈li ng〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)
《名付け》 ふた・ふる・もろ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)
《名付け》 ふた・ふる・もろ
《意味》
 {名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕
{名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕
 {副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕
{副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕
 {単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」
{単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」
 {単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。
〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。
《解字》
{単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。
〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。
《解字》
 象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。
《単語家族》
輛リョウ(両輪の車)
象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。
《単語家族》
輛リョウ(両輪の車) 梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 一部 [三年]
区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC
【兩】旧字旧字
6画 一部 [三年]
区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC
【兩】旧字旧字
 8画 入部
区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(リャウ)
8画 入部
区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F
《常用音訓》リョウ
《音読み》 リョウ(リャウ)
 〈li
〈li ng〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)
《名付け》 ふた・ふる・もろ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)
《名付け》 ふた・ふる・もろ
《意味》
 {名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕
{名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕
 {副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕
{副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕
 {単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」
{単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」
 {単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。
〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。
《解字》
{単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。
〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。
《解字》
 象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。
《単語家族》
輛リョウ(両輪の車)
象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。
《単語家族》
輛リョウ(両輪の車) 梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
二 ふた🔗⭐🔉
【二】
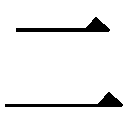 2画 二部 [一年]
区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1
【弍】異体字異体字
2画 二部 [一年]
区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1
【弍】異体字異体字
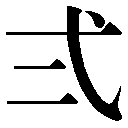 5画 弋部
区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF
《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ
《音読み》 ニ
5画 弋部
区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF
《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ
《音読み》 ニ /ジ
/ジ 〈
〈 r〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび
《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた
《意味》
r〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび
《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた
《意味》
 {数}ふたつ。
{数}ふたつ。
 {動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」
{動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」
 {数}ふた。順番の二番め。
{数}ふた。順番の二番め。
 {副}ふたたび。二度。二回。
{副}ふたたび。二度。二回。
 {形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」
{形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」
 {数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕
《解字》
{数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕
《解字》
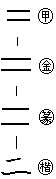 指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。
《単語家族》
二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞)
指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。
《単語家族》
二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞) 膩ニ・ジ(ねばってくっつく油)
膩ニ・ジ(ねばってくっつく油) 泥ナイ・デイ(くっつくどろ)
泥ナイ・デイ(くっつくどろ) 人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人)
人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人) 昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。
《類義》
両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。
《異字同訓》
ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。
《類義》
両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。
《異字同訓》
ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
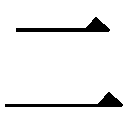 2画 二部 [一年]
区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1
【弍】異体字異体字
2画 二部 [一年]
区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1
【弍】異体字異体字
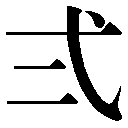 5画 弋部
区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF
《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ
《音読み》 ニ
5画 弋部
区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF
《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ
《音読み》 ニ /ジ
/ジ 〈
〈 r〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび
《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた
《意味》
r〉
《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび
《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた
《意味》
 {数}ふたつ。
{数}ふたつ。
 {動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」
{動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」
 {数}ふた。順番の二番め。
{数}ふた。順番の二番め。
 {副}ふたたび。二度。二回。
{副}ふたたび。二度。二回。
 {形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」
{形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」
 {数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕
《解字》
{数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕
《解字》
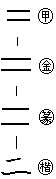 指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。
《単語家族》
二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞)
指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。
《単語家族》
二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞) 膩ニ・ジ(ねばってくっつく油)
膩ニ・ジ(ねばってくっつく油) 泥ナイ・デイ(くっつくどろ)
泥ナイ・デイ(くっつくどろ) 人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人)
人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人) 昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。
《類義》
両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。
《異字同訓》
ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。
《類義》
両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。
《異字同訓》
ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
付帯 フタイ🔗⭐🔉
【付帯】
フタイ =附帯。おもな物事に伴っていること。
付託 フタク🔗⭐🔉
【付託】
フタク =附託。物事を他に任せる。委託。
再 ふたたび🔗⭐🔉
【再】
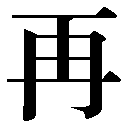 6画 冂部 [五年]
区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4
《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び
《音読み》 サイ
6画 冂部 [五年]
区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4
《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び
《音読み》 サイ
 /サ
/サ 〈z
〈z i〉
《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)
《意味》
i〉
《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)
《意味》
 {副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕
{副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕
 {動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕
《解字》
指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕
《解字》
指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
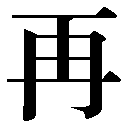 6画 冂部 [五年]
区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4
《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び
《音読み》 サイ
6画 冂部 [五年]
区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4
《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び
《音読み》 サイ
 /サ
/サ 〈z
〈z i〉
《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)
《意味》
i〉
《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)
《意味》
 {副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕
{副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕
 {動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕
《解字》
指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕
《解字》
指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓
《類義》
→二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
再斯可 フタタビスレバココニカナリ🔗⭐🔉
【再斯可】
フタタビスレバココニカナリ〈故事〉あまり考えすぎると惑いを生じるから、二度くりかえして考えれば、それでよい。〔→論語〕
双 ふた🔗⭐🔉
【双】
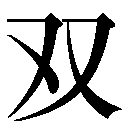 4画 又部 [常用漢字]
区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F
【雙】旧字旧字
4画 又部 [常用漢字]
区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F
【雙】旧字旧字
 18画 隹部
区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4
《常用音訓》ソウ/ふた
《音読み》 ソウ(サウ)
18画 隹部
区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4
《常用音訓》ソウ/ふた
《音読み》 ソウ(サウ)
 〈shu
〈shu ng〉
《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび
《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび
《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ
《意味》
 {名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕
{名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕
 {単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」
{単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」
 {動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕
《解字》
{動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕
《解字》
 会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。
《類義》
→二・→並
《異字同訓》
ふた。 →二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。
《類義》
→二・→並
《異字同訓》
ふた。 →二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
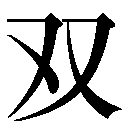 4画 又部 [常用漢字]
区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F
【雙】旧字旧字
4画 又部 [常用漢字]
区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F
【雙】旧字旧字
 18画 隹部
区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4
《常用音訓》ソウ/ふた
《音読み》 ソウ(サウ)
18画 隹部
区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4
《常用音訓》ソウ/ふた
《音読み》 ソウ(サウ)
 〈shu
〈shu ng〉
《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび
《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび
《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ
《意味》
 {名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕
{名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕
 {単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」
{単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」
 {動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕
《解字》
{動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕
《解字》
 会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。
《類義》
→二・→並
《異字同訓》
ふた。 →二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。
《類義》
→二・→並
《異字同訓》
ふた。 →二
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
布袋 フタイ🔗⭐🔉
【布袋】
 フタイ 布の袋。
フタイ 布の袋。 ホテイ
ホテイ  幹が短く節の多い竹。ほてい竹。
幹が短く節の多い竹。ほてい竹。 〔国〕七福神の一。
〔国〕七福神の一。
 フタイ 布の袋。
フタイ 布の袋。 ホテイ
ホテイ  幹が短く節の多い竹。ほてい竹。
幹が短く節の多い竹。ほてい竹。 〔国〕七福神の一。
〔国〕七福神の一。
弐 ふたつ🔗⭐🔉
【弐】
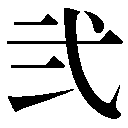 6画 弋部 [常用漢字]
区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3
【貳】旧字旧字
6画 弋部 [常用漢字]
区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3
【貳】旧字旧字
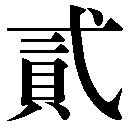 12画 貝部
区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6
【貮】異体字異体字
12画 貝部
区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6
【貮】異体字異体字
 11画 貝部
区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7
《常用音訓》ニ
《音読み》 ニ
11画 貝部
区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7
《常用音訓》ニ
《音読み》 ニ /ジ
/ジ 〈
〈 r〉
《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ
《名付け》 すけ
《意味》
r〉
《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ
《名付け》 すけ
《意味》
 {数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。
{数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。
 {動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕
{動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕
 {動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」
{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」
 {動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」
〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。
《解字》
会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」
〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。
《解字》
会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
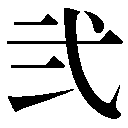 6画 弋部 [常用漢字]
区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3
【貳】旧字旧字
6画 弋部 [常用漢字]
区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3
【貳】旧字旧字
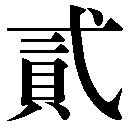 12画 貝部
区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6
【貮】異体字異体字
12画 貝部
区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6
【貮】異体字異体字
 11画 貝部
区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7
《常用音訓》ニ
《音読み》 ニ
11画 貝部
区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7
《常用音訓》ニ
《音読み》 ニ /ジ
/ジ 〈
〈 r〉
《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ
《名付け》 すけ
《意味》
r〉
《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ
《名付け》 すけ
《意味》
 {数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。
{数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。
 {動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕
{動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕
 {動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」
{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」
 {動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」
〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。
《解字》
会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」
〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。
《解字》
会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
復 ふたたびする🔗⭐🔉
【復】
 12画 彳部 [五年]
区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C
《常用音訓》フク
《音読み》
12画 彳部 [五年]
区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C
《常用音訓》フク
《音読み》  フク
フク /ブク
/ブク 〈f
〈f 〉/
〉/ ブ
ブ /フウ
/フウ /フク
/フク 〈f
〈f 〉
《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)
《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち
《意味》
〉
《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)
《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち
《意味》

 {動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」
{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」
 フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕
フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕
 フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕
フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕
 {副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕
{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕
 {副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕
{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕
 「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕
「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕
 「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕
「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕
 {名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。
{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。
 {動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」
《解字》
{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。
《類義》
→二・→反
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。
《類義》
→二・→反
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 彳部 [五年]
区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C
《常用音訓》フク
《音読み》
12画 彳部 [五年]
区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C
《常用音訓》フク
《音読み》  フク
フク /ブク
/ブク 〈f
〈f 〉/
〉/ ブ
ブ /フウ
/フウ /フク
/フク 〈f
〈f 〉
《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)
《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち
《意味》
〉
《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)
《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち
《意味》

 {動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」
{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」
 フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕
フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕
 フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕
フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕
 {副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕
{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕
 {副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕
{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕
 「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕
「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕
 「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕
「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕
 {名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。
{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。
 {動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」
《解字》
{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。
《類義》
→二・→反
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。
《類義》
→二・→反
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
盍 ふた🔗⭐🔉
【盍】
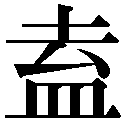 10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ)
10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) 〈h
〈h 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
 {動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
 {疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
 {疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ
{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
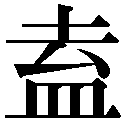 10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ)
10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) 〈h
〈h 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
 {動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
 {疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
 {疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ
{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
盒 ふたもの🔗⭐🔉
蓋 ふた🔗⭐🔉
【蓋】
 13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
 12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
 11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》
11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》  ガイ
ガイ /カイ
/カイ
 〈g
〈g i〉/
i〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)
/ゴウ(ガフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》

 {動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
 {名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
 {単位}傘カサなどを数えることば。
{単位}傘カサなどを数えることば。
 {動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
 {動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
 {副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕
{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

 {名}草ぶきの屋根。とま。
{名}草ぶきの屋根。とま。
 {疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる)
{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
 12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
 11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》
11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》  ガイ
ガイ /カイ
/カイ
 〈g
〈g i〉/
i〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)
/ゴウ(ガフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》

 {動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
 {名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
 {単位}傘カサなどを数えることば。
{単位}傘カサなどを数えることば。
 {動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
 {動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
 {副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕
{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

 {名}草ぶきの屋根。とま。
{名}草ぶきの屋根。とま。
 {疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる)
{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
負担 フタン🔗⭐🔉
【負担】
フタン  荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。
荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。 仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。
仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。 〔国〕能力以上でつらい事がら。
〔国〕能力以上でつらい事がら。
 荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。
荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。 仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。
仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。 〔国〕能力以上でつらい事がら。
〔国〕能力以上でつらい事がら。
漢字源に「ふた」で始まるの検索結果 1-16。
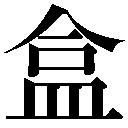 11画 皿部
区点=6622 16進=6236 シフトJIS=E1B4
《音読み》 ゴウ(ゴフ)
11画 皿部
区点=6622 16進=6236 シフトJIS=E1B4
《音読み》 ゴウ(ゴフ) {名}ふたもの。みとふたをあわせてとじる容器。「飯盒ハンゴウ」「墨盒ボクゴウ」「盒子ゴウシ(ふたもの)」
《解字》
会意兼形声。合は「あわせるしるし+口」からなり、器などの口をふたしてふさぐこと。盒は「皿(さら)+音符合」で、ふたとみとをあわせる容器のこと。
《単語家族》
盍コウ
{名}ふたもの。みとふたをあわせてとじる容器。「飯盒ハンゴウ」「墨盒ボクゴウ」「盒子ゴウシ(ふたもの)」
《解字》
会意兼形声。合は「あわせるしるし+口」からなり、器などの口をふたしてふさぐこと。盒は「皿(さら)+音符合」で、ふたとみとをあわせる容器のこと。
《単語家族》
盍コウ