複数辞典一括検索+![]()
![]()
下 しも🔗⭐🔉
【下】
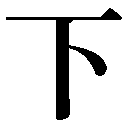 3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ
3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ /ゲ
/ゲ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
 {名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
 {名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
 {名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
 {名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
 {動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
 {動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
 {動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
 {動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
 {動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
 {助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
 {助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
 {形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
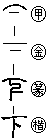 指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す)
指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す) 仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
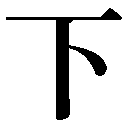 3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ
3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ /ゲ
/ゲ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
 {名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
 {名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
 {名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
 {名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
 {動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
 {動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
 {動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
 {動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
 {動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
 {助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
 {助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
 {形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
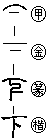 指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す)
指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す) 仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
下手 シモテ🔗⭐🔉
【下手】
 ゲシュ・テヲクダス 自分で直接行う。
ゲシュ・テヲクダス 自分で直接行う。 ヘタ〔国〕技芸などが未熟なこと。〈対語〉上手ジョウズ。
ヘタ〔国〕技芸などが未熟なこと。〈対語〉上手ジョウズ。 シタテ〔国〕才能・地位が相手より劣ること。また、そのような人。〈対語〉上手ウワテ。
シタテ〔国〕才能・地位が相手より劣ること。また、そのような人。〈対語〉上手ウワテ。 シモテ〔国〕
シモテ〔国〕 下のほう。
下のほう。 客席から見て舞台の左のほう。〈対語〉上手カミテ。
客席から見て舞台の左のほう。〈対語〉上手カミテ。
 ゲシュ・テヲクダス 自分で直接行う。
ゲシュ・テヲクダス 自分で直接行う。 ヘタ〔国〕技芸などが未熟なこと。〈対語〉上手ジョウズ。
ヘタ〔国〕技芸などが未熟なこと。〈対語〉上手ジョウズ。 シタテ〔国〕才能・地位が相手より劣ること。また、そのような人。〈対語〉上手ウワテ。
シタテ〔国〕才能・地位が相手より劣ること。また、そのような人。〈対語〉上手ウワテ。 シモテ〔国〕
シモテ〔国〕 下のほう。
下のほう。 客席から見て舞台の左のほう。〈対語〉上手カミテ。
客席から見て舞台の左のほう。〈対語〉上手カミテ。
下座 シモザ🔗⭐🔉
【下座】
ゲザ・シモザ 座敷などで、身分・地位のひくい人がすわる座席。末席。〈対語〉上座。
四門 シモン🔗⭐🔉
【四門】
シモン  四方の門。
四方の門。 北魏ホクギの時、一般人のためにつくられた学校。国子学(貴族のための学校)の四方の門のところに設けられた。元ゲン代に廃止。『四門学シモンガク』
北魏ホクギの時、一般人のためにつくられた学校。国子学(貴族のための学校)の四方の門のところに設けられた。元ゲン代に廃止。『四門学シモンガク』 四つの部門・分野。
四つの部門・分野。
 四方の門。
四方の門。 北魏ホクギの時、一般人のためにつくられた学校。国子学(貴族のための学校)の四方の門のところに設けられた。元ゲン代に廃止。『四門学シモンガク』
北魏ホクギの時、一般人のためにつくられた学校。国子学(貴族のための学校)の四方の門のところに設けられた。元ゲン代に廃止。『四門学シモンガク』 四つの部門・分野。
四つの部門・分野。
奚 しもべ🔗⭐🔉
【奚】
 10画 大部
区点=5288 16進=5478 シフトJIS=9AF6
《音読み》 ケイ
10画 大部
区点=5288 16進=5478 シフトJIS=9AF6
《音読み》 ケイ /ゲ
/ゲ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 しもべ/なに/なんぞ
《意味》
〉
《訓読み》 しもべ/なに/なんぞ
《意味》
 {名}しもべ。どれいや召使。「奚奴ケイド」「俄而小奚来報曰=俄ニシテ小奚来タリ報ジテ曰ハク」〔→斎藤拙堂〕
{名}しもべ。どれいや召使。「奚奴ケイド」「俄而小奚来報曰=俄ニシテ小奚来タリ報ジテ曰ハク」〔→斎藤拙堂〕
 {疑}なに。なにごと。どういうこと。〈類義語〉→何。「楽夫天命、復奚疑=カノ天命ヲ楽シミテ、マタナニヲカ疑ハン」〔→陶潜〕
{疑}なに。なにごと。どういうこと。〈類義語〉→何。「楽夫天命、復奚疑=カノ天命ヲ楽シミテ、マタナニヲカ疑ハン」〔→陶潜〕
 {副}なんぞ。どうして。〈類義語〉→何。「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
《解字》
会意。「爪(て)+糸(ひも)+大(ひと)」で、なわをつけて使役するどれいのこと。転じて、召使のこと。またその音を借りて、何・胡・害などとともに「なに、なぜ」を意味する疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
{副}なんぞ。どうして。〈類義語〉→何。「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
《解字》
会意。「爪(て)+糸(ひも)+大(ひと)」で、なわをつけて使役するどれいのこと。転じて、召使のこと。またその音を借りて、何・胡・害などとともに「なに、なぜ」を意味する疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
 10画 大部
区点=5288 16進=5478 シフトJIS=9AF6
《音読み》 ケイ
10画 大部
区点=5288 16進=5478 シフトJIS=9AF6
《音読み》 ケイ /ゲ
/ゲ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 しもべ/なに/なんぞ
《意味》
〉
《訓読み》 しもべ/なに/なんぞ
《意味》
 {名}しもべ。どれいや召使。「奚奴ケイド」「俄而小奚来報曰=俄ニシテ小奚来タリ報ジテ曰ハク」〔→斎藤拙堂〕
{名}しもべ。どれいや召使。「奚奴ケイド」「俄而小奚来報曰=俄ニシテ小奚来タリ報ジテ曰ハク」〔→斎藤拙堂〕
 {疑}なに。なにごと。どういうこと。〈類義語〉→何。「楽夫天命、復奚疑=カノ天命ヲ楽シミテ、マタナニヲカ疑ハン」〔→陶潜〕
{疑}なに。なにごと。どういうこと。〈類義語〉→何。「楽夫天命、復奚疑=カノ天命ヲ楽シミテ、マタナニヲカ疑ハン」〔→陶潜〕
 {副}なんぞ。どうして。〈類義語〉→何。「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
《解字》
会意。「爪(て)+糸(ひも)+大(ひと)」で、なわをつけて使役するどれいのこと。転じて、召使のこと。またその音を借りて、何・胡・害などとともに「なに、なぜ」を意味する疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
{副}なんぞ。どうして。〈類義語〉→何。「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
《解字》
会意。「爪(て)+糸(ひも)+大(ひと)」で、なわをつけて使役するどれいのこと。転じて、召使のこと。またその音を借りて、何・胡・害などとともに「なに、なぜ」を意味する疑問詞に当てる。
《熟語》
→熟語
肆目 シモク🔗⭐🔉
【肆目】
シモク  けしきなどを自由にながめまわす。
けしきなどを自由にながめまわす。 目の力の極限まで使う。
目の力の極限まで使う。
 けしきなどを自由にながめまわす。
けしきなどを自由にながめまわす。 目の力の極限まで使う。
目の力の極限まで使う。
試問 シモン🔗⭐🔉
【試問】
シモン 人がら・知識・能力などを知るために質問する。
諮問 シモン🔗⭐🔉
隷 しもべ🔗⭐🔉
【隷】
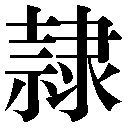 16画 隶部 [常用漢字]
区点=4676 16進=4E6C シフトJIS=97EA
【隸】旧字旧字
16画 隶部 [常用漢字]
区点=4676 16進=4E6C シフトJIS=97EA
【隸】旧字旧字
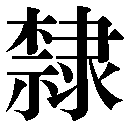 17画 隶部
区点=8017 16進=7031 シフトJIS=E8AF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ
17画 隶部
区点=8017 16進=7031 シフトJIS=E8AF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ /ライ
/ライ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 つける(つく)/したがう(したがふ)/しもべ
《意味》
〉
《訓読み》 つける(つく)/したがう(したがふ)/しもべ
《意味》
 レイス{動}つける(ツク)。したがう(シタガフ)。手もとに並べてくっつける。所属する。「名不隷征伐=名ハ征伐ニ隷セズ」〔→杜甫〕
レイス{動}つける(ツク)。したがう(シタガフ)。手もとに並べてくっつける。所属する。「名不隷征伐=名ハ征伐ニ隷セズ」〔→杜甫〕
 {名}しもべ。人に使われる、身分のいやしい者。また、雑務係の下級役人。「隷臣」「奴隷」
{名}しもべ。人に使われる、身分のいやしい者。また、雑務係の下級役人。「隷臣」「奴隷」
 {名}漢字の書体の名。隷書。▽漢代の書記や庶務係が、メモに用いた書体。篆書テンショに比べて、直線的で書きやすい。
《解字》
会意。もと「からなし(木+示)+隶(手がとどく)」で、果実を手でもぎとって並べることをあらわす。つないで並べる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}漢字の書体の名。隷書。▽漢代の書記や庶務係が、メモに用いた書体。篆書テンショに比べて、直線的で書きやすい。
《解字》
会意。もと「からなし(木+示)+隶(手がとどく)」で、果実を手でもぎとって並べることをあらわす。つないで並べる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
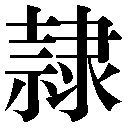 16画 隶部 [常用漢字]
区点=4676 16進=4E6C シフトJIS=97EA
【隸】旧字旧字
16画 隶部 [常用漢字]
区点=4676 16進=4E6C シフトJIS=97EA
【隸】旧字旧字
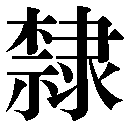 17画 隶部
区点=8017 16進=7031 シフトJIS=E8AF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ
17画 隶部
区点=8017 16進=7031 シフトJIS=E8AF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ /ライ
/ライ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 つける(つく)/したがう(したがふ)/しもべ
《意味》
〉
《訓読み》 つける(つく)/したがう(したがふ)/しもべ
《意味》
 レイス{動}つける(ツク)。したがう(シタガフ)。手もとに並べてくっつける。所属する。「名不隷征伐=名ハ征伐ニ隷セズ」〔→杜甫〕
レイス{動}つける(ツク)。したがう(シタガフ)。手もとに並べてくっつける。所属する。「名不隷征伐=名ハ征伐ニ隷セズ」〔→杜甫〕
 {名}しもべ。人に使われる、身分のいやしい者。また、雑務係の下級役人。「隷臣」「奴隷」
{名}しもべ。人に使われる、身分のいやしい者。また、雑務係の下級役人。「隷臣」「奴隷」
 {名}漢字の書体の名。隷書。▽漢代の書記や庶務係が、メモに用いた書体。篆書テンショに比べて、直線的で書きやすい。
《解字》
会意。もと「からなし(木+示)+隶(手がとどく)」で、果実を手でもぎとって並べることをあらわす。つないで並べる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}漢字の書体の名。隷書。▽漢代の書記や庶務係が、メモに用いた書体。篆書テンショに比べて、直線的で書きやすい。
《解字》
会意。もと「からなし(木+示)+隶(手がとどく)」で、果実を手でもぎとって並べることをあらわす。つないで並べる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
霜 しも🔗⭐🔉
【霜】
 17画 雨部 [常用漢字]
区点=3390 16進=417A シフトJIS=919A
《常用音訓》ソウ/しも
《音読み》 ソウ(サウ)
17画 雨部 [常用漢字]
区点=3390 16進=417A シフトJIS=919A
《常用音訓》ソウ/しも
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈shu
〈shu ng〉
《訓読み》 しも
《名付け》 しも
《意味》
ng〉
《訓読み》 しも
《名付け》 しも
《意味》
 {名}しも。空気ちゅうの水蒸気が、夜間、地上で凍ったもの。「霜花」「霜天」
{名}しも。空気ちゅうの水蒸気が、夜間、地上で凍ったもの。「霜花」「霜天」
 {名}としつき。「星霜」「客舎并州已十霜=并州ニ客舎シテスデニ十霜」〔→賈島〕
{名}としつき。「星霜」「客舎并州已十霜=并州ニ客舎シテスデニ十霜」〔→賈島〕
 {形}しものように白い。「霜毛」「霜刃」
{形}しものように白い。「霜毛」「霜刃」
 {名}冷たいもののたとえ。また、法律などの厳しいことのたとえ。「秋霜烈日」
{名}冷たいもののたとえ。また、法律などの厳しいことのたとえ。「秋霜烈日」
 {名}白いこな。薬の白い粉末。また、柿カキなどの表面にふきでる白い粉。「砒霜ヒソウ(砒素ヒソを含む白い粉)」
《解字》
会意兼形声。「雨+音符相(たてにむかいあう、別々に並びたつ)」。霜柱がたてに並びたつことに着目したもの。
《単語家族》
相
{名}白いこな。薬の白い粉末。また、柿カキなどの表面にふきでる白い粉。「砒霜ヒソウ(砒素ヒソを含む白い粉)」
《解字》
会意兼形声。「雨+音符相(たてにむかいあう、別々に並びたつ)」。霜柱がたてに並びたつことに着目したもの。
《単語家族》
相 疎(別々に並ぶ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
疎(別々に並ぶ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 17画 雨部 [常用漢字]
区点=3390 16進=417A シフトJIS=919A
《常用音訓》ソウ/しも
《音読み》 ソウ(サウ)
17画 雨部 [常用漢字]
区点=3390 16進=417A シフトJIS=919A
《常用音訓》ソウ/しも
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈shu
〈shu ng〉
《訓読み》 しも
《名付け》 しも
《意味》
ng〉
《訓読み》 しも
《名付け》 しも
《意味》
 {名}しも。空気ちゅうの水蒸気が、夜間、地上で凍ったもの。「霜花」「霜天」
{名}しも。空気ちゅうの水蒸気が、夜間、地上で凍ったもの。「霜花」「霜天」
 {名}としつき。「星霜」「客舎并州已十霜=并州ニ客舎シテスデニ十霜」〔→賈島〕
{名}としつき。「星霜」「客舎并州已十霜=并州ニ客舎シテスデニ十霜」〔→賈島〕
 {形}しものように白い。「霜毛」「霜刃」
{形}しものように白い。「霜毛」「霜刃」
 {名}冷たいもののたとえ。また、法律などの厳しいことのたとえ。「秋霜烈日」
{名}冷たいもののたとえ。また、法律などの厳しいことのたとえ。「秋霜烈日」
 {名}白いこな。薬の白い粉末。また、柿カキなどの表面にふきでる白い粉。「砒霜ヒソウ(砒素ヒソを含む白い粉)」
《解字》
会意兼形声。「雨+音符相(たてにむかいあう、別々に並びたつ)」。霜柱がたてに並びたつことに着目したもの。
《単語家族》
相
{名}白いこな。薬の白い粉末。また、柿カキなどの表面にふきでる白い粉。「砒霜ヒソウ(砒素ヒソを含む白い粉)」
《解字》
会意兼形声。「雨+音符相(たてにむかいあう、別々に並びたつ)」。霜柱がたてに並びたつことに着目したもの。
《単語家族》
相 疎(別々に並ぶ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
疎(別々に並ぶ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
霜月 シモツキ🔗⭐🔉
【霜月】
 ソウゲツ
ソウゲツ  霜のおりた寒い夜の月。
霜のおりた寒い夜の月。 陰暦七月の別名。
陰暦七月の別名。 シモツキ〔国〕陰暦十一月の別名。
シモツキ〔国〕陰暦十一月の別名。
 ソウゲツ
ソウゲツ  霜のおりた寒い夜の月。
霜のおりた寒い夜の月。 陰暦七月の別名。
陰暦七月の別名。 シモツキ〔国〕陰暦十一月の別名。
シモツキ〔国〕陰暦十一月の別名。
霜降 シモフリ🔗⭐🔉
【霜降】
 ソウコウ
ソウコウ  霜がおりること。
霜がおりること。 二十四気の一つ。寒露と立冬の間。陽暦の十月二十三日ごろ。「去年霜降斫秋荻=去年ノ霜降ニ秋荻ヲ斫リキ」〔→蘇軾〕
二十四気の一つ。寒露と立冬の間。陽暦の十月二十三日ごろ。「去年霜降斫秋荻=去年ノ霜降ニ秋荻ヲ斫リキ」〔→蘇軾〕 シモフリ〔国〕
シモフリ〔国〕 布地などで、黒色・灰色の地に、白い細かい点が一面にある模様。
布地などで、黒色・灰色の地に、白い細かい点が一面にある模様。 牛肉で、白い脂肪が不規則な網の目のように入りこんでいるもの。
牛肉で、白い脂肪が不規則な網の目のように入りこんでいるもの。 魚肉・鳥肉などを熱湯に通し、白くしてつくった刺身。
魚肉・鳥肉などを熱湯に通し、白くしてつくった刺身。
 ソウコウ
ソウコウ  霜がおりること。
霜がおりること。 二十四気の一つ。寒露と立冬の間。陽暦の十月二十三日ごろ。「去年霜降斫秋荻=去年ノ霜降ニ秋荻ヲ斫リキ」〔→蘇軾〕
二十四気の一つ。寒露と立冬の間。陽暦の十月二十三日ごろ。「去年霜降斫秋荻=去年ノ霜降ニ秋荻ヲ斫リキ」〔→蘇軾〕 シモフリ〔国〕
シモフリ〔国〕 布地などで、黒色・灰色の地に、白い細かい点が一面にある模様。
布地などで、黒色・灰色の地に、白い細かい点が一面にある模様。 牛肉で、白い脂肪が不規則な網の目のように入りこんでいるもの。
牛肉で、白い脂肪が不規則な網の目のように入りこんでいるもの。 魚肉・鳥肉などを熱湯に通し、白くしてつくった刺身。
魚肉・鳥肉などを熱湯に通し、白くしてつくった刺身。
履霜堅氷至 シモヲフミテケンピョウイタル🔗⭐🔉
【履霜堅氷至】
シモヲフミテケンピョウイタル〈故事〉霜をふむ時節を経ると、やがてかたい氷の張る時節になる。災いなどがはじめは目だたないが、だんだんとはっきりあらわれてくること。〔→易経〕
駟不及舌 シモシタニオヨバズ🔗⭐🔉
【駟不及舌】
シモシタニオヨバズ〈故事〉いったん口外したことばは、速度のはやい四頭だての馬車で追っても追いつけない。ことばをつつしむべきことのたとえ。「惜乎、夫子之説君子也、駟不及舌=惜シイカナ、夫子ノ君子ヲ説クヤ、駟モ舌ニ及バズ」〔→論語〕
鴟目虎吻 シモクコフン🔗⭐🔉
【鴟目虎吻】
シモクコフン〈故事〉鴟(ふくろう)の目つきと、虎トラの口もと。残忍で、あくまでもむさぼりとろうとする態度・容貌を形容することば。〔→漢書〕
鷙猛 シモウ🔗⭐🔉
【鷙勇】
シユウ たけだけしい。勇猛である。『鷙悍シカン・鷙猛シモウ・鷙強シキョウ』
漢字源に「シモ」で始まるの検索結果 1-17。