複数辞典一括検索+![]()
![]()
丈 たけ🔗⭐🔉
【丈】
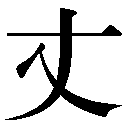 3画 一部 [常用漢字]
区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4
《常用音訓》ジョウ/たけ
《音読み》 ジョウ(ヂャウ)
3画 一部 [常用漢字]
区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4
《常用音訓》ジョウ/たけ
《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)
/チョウ(チャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます
《意味》
ng〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます
《意味》
 {単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。
{単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。
 {形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」
{形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」
 {名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」
{名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」
 {名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。
〔国〕
{名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。
〔国〕 長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」
長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」 たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」
《解字》
たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」
《解字》
 会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。
《単語家族》
長チョウ
会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。
《単語家族》
長チョウ 暢チョウ(のびる)
暢チョウ(のびる) 裳ショウ(長いスカート)
裳ショウ(長いスカート) 杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
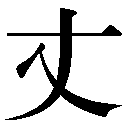 3画 一部 [常用漢字]
区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4
《常用音訓》ジョウ/たけ
《音読み》 ジョウ(ヂャウ)
3画 一部 [常用漢字]
区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4
《常用音訓》ジョウ/たけ
《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)
/チョウ(チャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます
《意味》
ng〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます
《意味》
 {単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。
{単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。
 {形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」
{形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」
 {名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」
{名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」
 {名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。
〔国〕
{名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。
〔国〕 長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」
長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」 たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」
《解字》
たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」
《解字》
 会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。
《単語家族》
長チョウ
会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。
《単語家族》
長チョウ 暢チョウ(のびる)
暢チョウ(のびる) 裳ショウ(長いスカート)
裳ショウ(長いスカート) 杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
健 たけし🔗⭐🔉
【健】
 11画 人部 [四年]
区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92
《常用音訓》ケン/すこ…やか
《音読み》 ケン
11画 人部 [四年]
区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92
《常用音訓》ケン/すこ…やか
《音読み》 ケン /ゴン
/ゴン 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし
《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす
《意味》
n〉
《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし
《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす
《意味》
 ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕
ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕
 ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕
ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕
 ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」
《解字》
会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建
《単語家族》
乾ケン(高く強い)
ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」
《解字》
会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建
《単語家族》
乾ケン(高く強い) 軒ケン(高いのき)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
軒ケン(高いのき)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 人部 [四年]
区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92
《常用音訓》ケン/すこ…やか
《音読み》 ケン
11画 人部 [四年]
区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92
《常用音訓》ケン/すこ…やか
《音読み》 ケン /ゴン
/ゴン 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし
《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす
《意味》
n〉
《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし
《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす
《意味》
 ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕
ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕
 ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕
ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕
 ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」
《解字》
会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建
《単語家族》
乾ケン(高く強い)
ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」
《解字》
会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建
《単語家族》
乾ケン(高く強い) 軒ケン(高いのき)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
軒ケン(高いのき)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
威 たけし🔗⭐🔉
【威】
 9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ(
9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ( )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
 {名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
 イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
 イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく)
「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)
熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ(
9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ( )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
 {名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
 イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
 イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく)
「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)
熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
岳 たけ🔗⭐🔉
【岳】
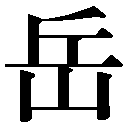 8画 山部 [常用漢字]
区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78
【嶽】旧字旧字
8画 山部 [常用漢字]
区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78
【嶽】旧字旧字
 17画 山部
区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4
《常用音訓》ガク/たけ
《音読み》 ガク
17画 山部
区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4
《常用音訓》ガク/たけ
《音読み》 ガク
 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 おか・たか・たかし・たけ
《意味》
〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 おか・たか・たかし・たけ
《意味》
 {名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」
{名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」
 {名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。
{名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。
 {形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」
《解字》
〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。
《単語家族》
確カク(かたい)
{形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」
《解字》
〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。
《単語家族》
確カク(かたい) 玉(かたいぎょく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
玉(かたいぎょく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
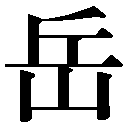 8画 山部 [常用漢字]
区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78
【嶽】旧字旧字
8画 山部 [常用漢字]
区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78
【嶽】旧字旧字
 17画 山部
区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4
《常用音訓》ガク/たけ
《音読み》 ガク
17画 山部
区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4
《常用音訓》ガク/たけ
《音読み》 ガク
 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 おか・たか・たかし・たけ
《意味》
〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 おか・たか・たかし・たけ
《意味》
 {名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」
{名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」
 {名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。
{名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。
 {形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」
《解字》
〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。
《単語家族》
確カク(かたい)
{形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」
《解字》
〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。
《単語家族》
確カク(かたい) 玉(かたいぎょく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
玉(かたいぎょく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
梟帥 タケル🔗⭐🔉
【梟帥】
 キョウスイ 荒々しい大将。
キョウスイ 荒々しい大将。 タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」
タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」
 キョウスイ 荒々しい大将。
キョウスイ 荒々しい大将。 タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」
タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」
武 たけだけしい🔗⭐🔉
【武】
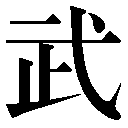 8画 止部 [五年]
区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590
《常用音訓》ブ/ム
《音読み》 ブ
8画 止部 [五年]
区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590
《常用音訓》ブ/ム
《音読み》 ブ /ム
/ム 〈w
〈w 〉
《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)
《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん
《意味》
〉
《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)
《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん
《意味》
 {形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」
{形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」
 {名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」
{名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」
 {名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」
{名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」
 {名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。
{名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。
 {名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。
{名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。
 {名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」
{名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」
 {名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕
《解字》
{名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕
《解字》
 会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。
《単語家族》
賦(求める)
会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。
《単語家族》
賦(求める) 慕(求める)
慕(求める) 摸ボ(さぐる)
摸ボ(さぐる) 驀バク(馬がむやみに前進する)
驀バク(馬がむやみに前進する) 罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
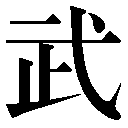 8画 止部 [五年]
区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590
《常用音訓》ブ/ム
《音読み》 ブ
8画 止部 [五年]
区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590
《常用音訓》ブ/ム
《音読み》 ブ /ム
/ム 〈w
〈w 〉
《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)
《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん
《意味》
〉
《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)
《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん
《意味》
 {形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」
{形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」
 {名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」
{名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」
 {名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」
{名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」
 {名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。
{名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。
 {名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。
{名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。
 {名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」
{名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」
 {名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕
《解字》
{名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕
《解字》
 会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。
《単語家族》
賦(求める)
会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。
《単語家族》
賦(求める) 慕(求める)
慕(求める) 摸ボ(さぐる)
摸ボ(さぐる) 驀バク(馬がむやみに前進する)
驀バク(馬がむやみに前進する) 罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
猛 たけし🔗⭐🔉
【猛】
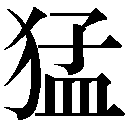 11画 犬部 [常用漢字]
区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2
《常用音訓》モウ
《音読み》 モウ(マウ)
11画 犬部 [常用漢字]
区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2
《常用音訓》モウ
《音読み》 モウ(マウ) /ミョウ(ミャウ)
/ミョウ(ミャウ) 《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)
《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし
《意味》
《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)
《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし
《意味》
 {動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕
{動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕
 {形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。
《単語家族》
萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。
《単語家族》
萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
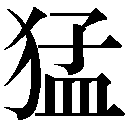 11画 犬部 [常用漢字]
区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2
《常用音訓》モウ
《音読み》 モウ(マウ)
11画 犬部 [常用漢字]
区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2
《常用音訓》モウ
《音読み》 モウ(マウ) /ミョウ(ミャウ)
/ミョウ(ミャウ) 《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)
《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし
《意味》
《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)
《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし
《意味》
 {動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕
{動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕
 {形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。
《単語家族》
萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。
《単語家族》
萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
竹 たけ🔗⭐🔉
【竹】
 6画 竹部 [一年]
区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C
《常用音訓》チク/たけ
《音読み》 チク
6画 竹部 [一年]
区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C
《常用音訓》チク/たけ
《音読み》 チク
 /シツ
/シツ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たか・たけ
《意味》
〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たか・たけ
《意味》
 {名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」
{名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」
 「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕
「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕
 {名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」
《解字》
{名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」
《解字》
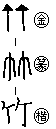 象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。
《単語家族》
蓄(外をかこんで中に入れる)
象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。
《単語家族》
蓄(外をかこんで中に入れる) 畜(外をかこんで中に入れる)
畜(外をかこんで中に入れる) 周(まわりをかこむ)などと同系。
《類義》
篠ショウは、細いしのだけ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
周(まわりをかこむ)などと同系。
《類義》
篠ショウは、細いしのだけ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 6画 竹部 [一年]
区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C
《常用音訓》チク/たけ
《音読み》 チク
6画 竹部 [一年]
区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C
《常用音訓》チク/たけ
《音読み》 チク
 /シツ
/シツ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たか・たけ
《意味》
〉
《訓読み》 たけ
《名付け》 たか・たけ
《意味》
 {名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」
{名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」
 「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕
「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕
 {名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」
《解字》
{名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」
《解字》
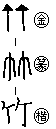 象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。
《単語家族》
蓄(外をかこんで中に入れる)
象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。
《単語家族》
蓄(外をかこんで中に入れる) 畜(外をかこんで中に入れる)
畜(外をかこんで中に入れる) 周(まわりをかこむ)などと同系。
《類義》
篠ショウは、細いしのだけ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
周(まわりをかこむ)などと同系。
《類義》
篠ショウは、細いしのだけ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
竹光 タケミツ🔗⭐🔉
【竹光】
 チクコウ
チクコウ  竹の色。
竹の色。 竹林の風光。
竹林の風光。 タケミツ〔国〕
タケミツ〔国〕 竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。
竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。 なまくら刀をあざけっていうことば。
なまくら刀をあざけっていうことば。
 チクコウ
チクコウ  竹の色。
竹の色。 竹林の風光。
竹林の風光。 タケミツ〔国〕
タケミツ〔国〕 竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。
竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。 なまくら刀をあざけっていうことば。
なまくら刀をあざけっていうことば。
竹篦 タケベラ🔗⭐🔉
【竹篦】
 チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。
チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。 チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。
チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。 タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。
タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。
 チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。
チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。 チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。
チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。 タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。
タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。
竹添井井 タケゾエセイセイ🔗⭐🔉
【竹添井井】
タケゾエセイセイ〔日〕〈人名〉1842〜1917 明治時代の漢学者。名は光鴻ミツヒロ、字アザナは漸郷、井井は号。著に『左氏会箋カイセン』『毛詩会箋』『桟雲峡雨日記』などがある。
竺 たけ🔗⭐🔉
筍 たけのこ🔗⭐🔉
【筍】
 12画 竹部
区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1
【笋】異体字異体字
12画 竹部
区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1
【笋】異体字異体字
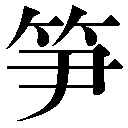 10画 竹部
区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2
《音読み》 ジュン
10画 竹部
区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)
《意味》
n〉
《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)
《意味》
 {名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。
{名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。
 {名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。
{名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。
 {名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 竹部
区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1
【笋】異体字異体字
12画 竹部
区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1
【笋】異体字異体字
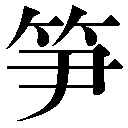 10画 竹部
区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2
《音読み》 ジュン
10画 竹部
区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)
《意味》
n〉
《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)
《意味》
 {名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。
{名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。
 {名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。
{名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。
 {名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
篁 たけ🔗⭐🔉
茸 たけ🔗⭐🔉
【茸】
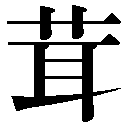 9画 艸部
区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9
《音読み》 ジョウ
9画 艸部
区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9
《音読み》 ジョウ /ニョウ
/ニョウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ
《意味》
ng〉
《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ
《意味》
 {動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」
{動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」
 {名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」
{名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」
 {形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。
{形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。
 {形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。
{形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。
 「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。
〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」
《解字》
会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。
〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」
《解字》
会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
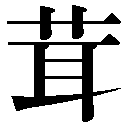 9画 艸部
区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9
《音読み》 ジョウ
9画 艸部
区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9
《音読み》 ジョウ /ニョウ
/ニョウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ
《意味》
ng〉
《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ
《意味》
 {動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」
{動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」
 {名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」
{名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」
 {形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。
{形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。
 {形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。
{形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。
 「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。
〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」
《解字》
会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。
〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」
《解字》
会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
酣 たけなわ🔗⭐🔉
【酣】
 12画 酉部
区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5
《音読み》 カン(カム)
12画 酉部
区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5
《音読み》 カン(カム) /ガン(ガム)
/ガン(ガム) 〈h
〈h n〉
《訓読み》 たけなわ(たけなは)
《意味》
n〉
《訓読み》 たけなわ(たけなは)
《意味》
 {形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕
{形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕
 {形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 酉部
区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5
《音読み》 カン(カム)
12画 酉部
区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5
《音読み》 カン(カム) /ガン(ガム)
/ガン(ガム) 〈h
〈h n〉
《訓読み》 たけなわ(たけなは)
《意味》
n〉
《訓読み》 たけなわ(たけなは)
《意味》
 {形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕
{形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕
 {形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
長 たけ🔗⭐🔉
【長】
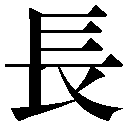 8画 長部 [二年]
区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7
《常用音訓》チョウ/なが…い
《音読み》
8画 長部 [二年]
区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7
《常用音訓》チョウ/なが…い
《音読み》  チョウ(チャウ)
チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)
/ジョウ(ヂャウ) 〈ch
〈ch ng〉/
ng〉/ チョウ(チャウ)
チョウ(チャウ)
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます
《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち
《意味》
ng〉
《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます
《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち
《意味》

 {形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕
{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕
 {形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕
{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕
 {名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕
{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕
 {形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」
{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

 {名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」
{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」
 {名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕
{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕
 {形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」
{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」
 チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕
チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕
 チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕
チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕
 チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕
チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕
 チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと
チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕
《解字》
の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕
《解字》
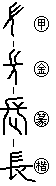 象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。
《単語家族》
帳チョウ(ながい布)
象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。
《単語家族》
帳チョウ(ながい布) 常ジョウ(ながい)
常ジョウ(ながい) 裳ショウ(ながいスカート)
裳ショウ(ながいスカート) 丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。
《類義》
永エイは、いつまでも断えず続くこと。
《異字同訓》
ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。
《類義》
永エイは、いつまでも断えず続くこと。
《異字同訓》
ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
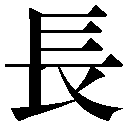 8画 長部 [二年]
区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7
《常用音訓》チョウ/なが…い
《音読み》
8画 長部 [二年]
区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7
《常用音訓》チョウ/なが…い
《音読み》  チョウ(チャウ)
チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)
/ジョウ(ヂャウ) 〈ch
〈ch ng〉/
ng〉/ チョウ(チャウ)
チョウ(チャウ)
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます
《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち
《意味》
ng〉
《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます
《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち
《意味》

 {形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕
{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕
 {形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕
{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕
 {名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕
{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕
 {形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」
{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

 {名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」
{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」
 {名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕
{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕
 {形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」
{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」
 チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕
チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕
 チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕
チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕
 チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕
チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕
 チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと
チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕
《解字》
の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕
《解字》
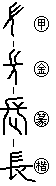 象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。
《単語家族》
帳チョウ(ながい布)
象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。
《単語家族》
帳チョウ(ながい布) 常ジョウ(ながい)
常ジョウ(ながい) 裳ショウ(ながいスカート)
裳ショウ(ながいスカート) 丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。
《類義》
永エイは、いつまでも断えず続くこと。
《異字同訓》
ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。
《類義》
永エイは、いつまでも断えず続くこと。
《異字同訓》
ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
闌 たけなわ🔗⭐🔉
【闌】
 17画 門部
区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C
《音読み》 ラン
17画 門部
区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C
《音読み》 ラン
 〈l
〈l n〉
《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに
《意味》
n〉
《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに
《意味》
 {名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。
{名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。
 {動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。
{動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。
 ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒
ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒 夜闌=月寒クシテ
夜闌=月寒クシテ 夜闌タリ」〔→黄庭堅〕
夜闌タリ」〔→黄庭堅〕
 {動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。
{動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。
 {副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」
{副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」
 「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。
《解字》
会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。
《解字》
会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 17画 門部
区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C
《音読み》 ラン
17画 門部
区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C
《音読み》 ラン
 〈l
〈l n〉
《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに
《意味》
n〉
《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに
《意味》
 {名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。
{名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。
 {動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。
{動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。
 ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒
ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒 夜闌=月寒クシテ
夜闌=月寒クシテ 夜闌タリ」〔→黄庭堅〕
夜闌タリ」〔→黄庭堅〕
 {動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。
{動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。
 {副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」
{副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」
 「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。
《解字》
会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。
《解字》
会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「たけ」で始まるの検索結果 1-19。
 8画 竹部
区点=2819 16進=3C33 シフトJIS=8EB1
《音読み》
8画 竹部
区点=2819 16進=3C33 シフトJIS=8EB1
《音読み》  15画 竹部
区点=6827 16進=643B シフトJIS=E2B9
《音読み》 コウ(クワウ)
15画 竹部
区点=6827 16進=643B シフトJIS=E2B9
《音読み》 コウ(クワウ)