複数辞典一括検索+![]()
![]()
から‐はじかみ【呉茱萸】🔗⭐🔉
から‐はじかみ【呉茱萸】
〔植〕ゴシュユの古名。〈本草和名〉
くりゃ・る【呉りゃる】🔗⭐🔉
くりゃ・る【呉りゃる】
〔他四〕
(クレヤルの転)
①(「くれる」に軽い尊敬の意を添える)くださる。
②(動詞の連用形に助詞「て」「で」の付いたものに接続して)…して下さる。狂言、萩大名「許いてお―・れ」
くれ【呉】🔗⭐🔉
くれ【呉】
①中国南北朝時代の南朝およびその支配した江南の地域を日本でいう称。また、広く中国の称。
②呉と通交して以来、中国伝来の事物に添えていう語。「―ない(呉の藍の意)」「―の母おも」「―楽」
くれ【呉】(地名(広島県))🔗⭐🔉
くれ【呉】
広島県南西部、広島市の南東にある市。江田島・能美島・倉橋島を望む。もと軍港・海軍工廠があり、現在は造船所がある。人口25万1千。
くれ【呉】(姓氏)🔗⭐🔉
くれ【呉】
姓氏の一つ。
⇒くれ‐しげいち【呉茂一】
⇒くれ‐しゅうぞう【呉秀三】
くれ‐がく【呉楽】🔗⭐🔉
くれ‐がく【呉楽】
(呉くれから伝来したからいう)伎楽の称。推古紀「呉に学びて―の儛まいを得たり」
くれ‐くぎ【呉釘】🔗⭐🔉
くれ‐くぎ【呉釘】
頭のない釘。切釘。新撰字鏡6「鐕、无盖釘也、久礼久疑也」
くれ‐ぐれ【呉呉】🔗⭐🔉
くれ‐ぐれ【呉呉】
〔副〕
(多くは「も」を伴って)
①念をいれるさま。くり返しくり返し。かえすがえす。毎月抄「先哲の―書きおける物にも」
②相手に念を押すさま。せつに。よくよく。「―もよろしく」「―もお大事に」
くれ‐しげいち【呉茂一】🔗⭐🔉
くれ‐しげいち【呉茂一】
西洋古典学者。東京生れ。秀三の子。東大・名古屋大教授。著「ギリシア神話」のほかギリシア・ローマ文学の邦訳多数。(1897〜1977)
呉茂一
撮影:田沼武能
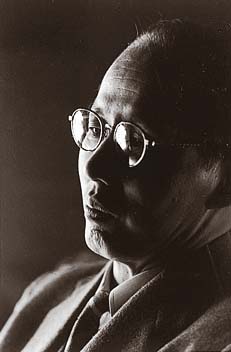 ⇒くれ【呉】
⇒くれ【呉】
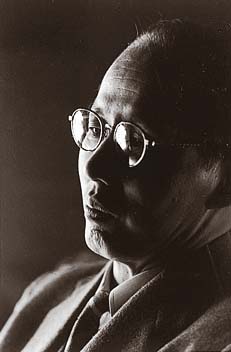 ⇒くれ【呉】
⇒くれ【呉】
くれ‐しゅうぞう【呉秀三】‥シウザウ🔗⭐🔉
くれ‐しゅうぞう【呉秀三】‥シウザウ
精神病学者。広島出身。東大教授。精神病学の発展に尽力。また、医学史・シーボルトの事績の研究がある。(1865〜1932)
⇒くれ【呉】
くれ‐たけ【呉竹】🔗⭐🔉
くれ‐たけ【呉竹】
①(呉くれから渡来した竹の意)淡竹はちくの異称。徒然草「―は葉ほそく、河竹は葉ひろし」
②真竹まだけの異称。
⇒くれたけ‐の【呉竹の】
⇒くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】
⇒くれたけ‐りょう【呉竹寮】
くれたけ‐の【呉竹の】🔗⭐🔉
くれたけ‐の【呉竹の】
〔枕〕
「ふし」「うきふし」「世」「夜」「むなし」「しげし」「端山」「末」にかかる。竹取物語「―よよの竹取り野山にもさやはわびしき節をのみ見し」
⇒くれ‐たけ【呉竹】
くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】🔗⭐🔉
くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】
内裏清涼殿の前庭の呉竹を植えたところ。
⇒くれ‐たけ【呉竹】
くれたけ‐りょう【呉竹寮】‥レウ🔗⭐🔉
くれたけ‐りょう【呉竹寮】‥レウ
もと宮中にあった皇子・皇女の住所。
⇒くれ‐たけ【呉竹】
くれ‐つづみ【呉鼓】🔗⭐🔉
くれ‐つづみ【呉鼓】
伎楽(呉楽くれがく)に用いた打楽器。腰鼓ようこのこと。くれのつづみ。→腰鼓
くれ‐どこ【呉床・牙床】🔗⭐🔉
くれ‐どこ【呉床・牙床】
中国の胡床こしょうにならって作った座臥の具。椅子いすの類。〈倭名類聚鈔14〉
くれ‐の‐あい【呉藍・紅藍】‥アヰ🔗⭐🔉
くれ‐の‐あい【呉藍・紅藍】‥アヰ
⇒くれない(紅)。〈倭名類聚鈔14〉
くれ‐の‐おも【呉の母・懐香】🔗⭐🔉
くれ‐の‐おも【呉の母・懐香】
茴香ういきょうの古名。〈倭名類聚鈔20〉
くれ‐の‐がく【呉の楽】🔗⭐🔉
くれ‐の‐がく【呉の楽】
伎楽の異称。くれがく。
くれ‐の‐つづみ【呉の鼓】🔗⭐🔉
くれ‐の‐つづみ【呉の鼓】
(→)「くれつづみ」に同じ。
くれ‐の‐はじかみ【呉椒・乾薑】🔗⭐🔉
くれ‐の‐はじかみ【呉椒・乾薑】
ショウガの古名。〈倭名類聚鈔17〉
くれ‐の‐みみず【呉の蚯蚓】🔗⭐🔉
くれ‐の‐みみず【呉の蚯蚓】
蚕の古名。〈享和本新撰字鏡1〉
くれ‐はし【呉階・呉橋】🔗⭐🔉
くれ‐はし【呉階・呉橋】
はしごだん。階段のついた長廊下。宇津保物語楼上上「楼にのぼり給ふべきほどの―は」
くれ‐はとり【呉織】🔗⭐🔉
くれ‐はとり【呉織】
(ハトリはハタオリの約)
[一]〔名〕
①大和政権に仕えた渡来系の機織はたおり技術者。雄略天皇の時代に中国の呉から渡来したという。→あやはとり。
②呉の国の法を伝えて織った綾などの織物。後撰和歌集恋「―といふ綾を」
[二]〔枕〕
(呉織は綾があるからいう)「あや(綾)」にかかる。
く・れる【呉れる】🔗⭐🔉
く・れる【呉れる】
〔他下一〕[文]く・る(下二)
①(自分が相手に)物をあたえる。また、動作を加える。やる。くれてやる。土佐日記「このながびつのものはみな人わらはまでに―・れたれば」。「ほしければ―・れてやろう」「げんこつを―・れる」
②(相手が自分に)物をあたえる。徒然草「よき友三つあり。一つには物―・るる友」。「娘が―・れたネクタイ」
③(動詞の連用形に助詞「て」の付いたものに接続して)
㋐自分のために他人がその動作をし、それによって恩恵・利益を受ける意を表す。転じて、他人の行為が自分の迷惑となる意にも用いる。絶句鈔「我をも引たてて―・れらるる知音」。狂言、抜殻「そちへ行て―・れい」。「よく来て―・れたね」「助けて―・れ」「困ったことをして―・れた」
㋑他人に対して自分がその動作をしてやる意を表す。蒙求抄9「そちが一族をば亡ほろぼいて―・れうぞ」。「ちと締めて―・れよう」
ご【呉】🔗⭐🔉
ご【呉】
①中国古代、春秋時代の列国の一つ。周の文王の伯父太伯の建国と称する。長江河口地方を領有。楚を破り勢を張ったが、夫差の時、越王勾践に滅ぼされた。( 〜前473)
②中国、三国時代の三国の一つ。孫権が江南に建てた国。222年独立、229年国号を定めた。都は建業。4世で西晋に滅ぼされた。(222〜280)
③中国、五代十国の一つ。楊行密が淮南・江東に建てた国。都は揚州。4世で南唐に滅ぼされた。(902〜937)
④中国江蘇省の別称。
→くれ(呉)
ご‐い【呉偉】‥ヰ🔗⭐🔉
ご‐い【呉偉】‥ヰ
明代中期の画家。字は士英・次翁。号は魯夫・小仙。江夏(湖北省)の人。浙派の大家。(1459〜1508)
ご‐いぎょう【呉偉業】‥ヰゲフ🔗⭐🔉
ご‐いぎょう【呉偉業】‥ヰゲフ
明末・清初の詩人。字は駿公。号は梅村。明滅亡後、一時、清の国子監祭酒。清初三大家の一人。絵画・戯曲もよくした。詩文集「梅村家蔵藁」など。(1609〜1671)
ご‐えつ【呉越】‥ヱツ(春秋)🔗⭐🔉
ご‐えつ【呉越】‥ヱツ
①中国の春秋時代の、呉の国と越の国。
②(呉と越とが敵対したことから)仲のきわめて悪いこと。
⇒ごえつ‐しゅんじゅう【呉越春秋】
⇒ごえつ‐どうしゅう【呉越同舟】
ごえつ【呉越】‥ヱツ(五代)🔗⭐🔉
ごえつ【呉越】‥ヱツ
五代十国の一つ。唐の鎮海節度使銭鏐せんりゅうが浙江・江蘇に建てた国。都は杭州。5世で宋に降った。(907〜978)
ごえつ‐しゅんじゅう【呉越春秋】‥ヱツ‥ジウ🔗⭐🔉
ごえつ‐しゅんじゅう【呉越春秋】‥ヱツ‥ジウ
春秋時代の呉・越両国の興亡の顛末を記した書。10巻。後漢の趙曄撰。
⇒ご‐えつ【呉越】
ごえつ‐どうしゅう【呉越同舟】‥ヱツ‥シウ🔗⭐🔉
ごえつ‐どうしゅう【呉越同舟】‥ヱツ‥シウ
[孫子九地「夫れ呉人と越人と相悪にくむ也、其の舟を同じくして済わたり風に遇うに当りては、其の相救うや、左右の手の如し」]仲の悪い者どうしが同じ場所に居合わせること。また、敵味方が共通の困難や利害に対して協力すること。
⇒ご‐えつ【呉越】
ゴー‐チョクトン【Goh Chok Tong・呉作棟】🔗⭐🔉
ゴー‐チョクトン【Goh Chok Tong・呉作棟】
シンガポールの政治家。1990年第2代首相に就任。2004年上級相兼通貨監督庁議長に転じる。(1941〜)
ご‐おん【呉音】🔗⭐🔉
ごか‐の‐あもう【呉下の阿蒙】🔗⭐🔉
ごか‐の‐あもう【呉下の阿蒙】
[三国志呉志呂蒙伝、注](魯粛が呂蒙に会って談議し、「初めは君を単に武略に長じているだけの人だと思っていたが、今は学問が上達して、呉にいた時代の蒙君(阿蒙の「阿」は発語)ではない」といった故事から)昔のままで進歩のない人物。学問のないつまらない者。
ご‐き【呉器】🔗⭐🔉
ご‐き【呉器】
抹茶茶碗の一種。もとは朝鮮の飯茶碗(御器)であって、素朴な大振りの撥ばち形の高台がつく。
ご‐きさい【呉 載】🔗⭐🔉
載】🔗⭐🔉
ご‐きさい【呉 載】
清代後期の文人。儀徴(江蘇省)の人。同治(1862〜1874)以後、皇帝の諱を避け、字の譲之を名とする。書画・篆刻に優れ、印譜に「師慎軒印譜」「呉譲之印譜」がある。(1799〜1870)
○御器提げるごきさげる
(椀をもって食を乞う意)乞食こじきとなる。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「師直が口一つで御器提げうも知れぬあぶない身代」
⇒ご‐き【御器】
載】
清代後期の文人。儀徴(江蘇省)の人。同治(1862〜1874)以後、皇帝の諱を避け、字の譲之を名とする。書画・篆刻に優れ、印譜に「師慎軒印譜」「呉譲之印譜」がある。(1799〜1870)
○御器提げるごきさげる
(椀をもって食を乞う意)乞食こじきとなる。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「師直が口一つで御器提げうも知れぬあぶない身代」
⇒ご‐き【御器】
 載】
清代後期の文人。儀徴(江蘇省)の人。同治(1862〜1874)以後、皇帝の諱を避け、字の譲之を名とする。書画・篆刻に優れ、印譜に「師慎軒印譜」「呉譲之印譜」がある。(1799〜1870)
○御器提げるごきさげる
(椀をもって食を乞う意)乞食こじきとなる。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「師直が口一つで御器提げうも知れぬあぶない身代」
⇒ご‐き【御器】
載】
清代後期の文人。儀徴(江蘇省)の人。同治(1862〜1874)以後、皇帝の諱を避け、字の譲之を名とする。書画・篆刻に優れ、印譜に「師慎軒印譜」「呉譲之印譜」がある。(1799〜1870)
○御器提げるごきさげる
(椀をもって食を乞う意)乞食こじきとなる。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「師直が口一つで御器提げうも知れぬあぶない身代」
⇒ご‐き【御器】
ご‐ぎゅう【呉牛】‥ギウ🔗⭐🔉
ご‐ぎゅう【呉牛】‥ギウ
(呉の地に多く産したからいう)水牛すいぎゅうの異称。
⇒呉牛月に喘ぐ
○呉牛月に喘ぐごぎゅうつきにあえぐ🔗⭐🔉
○呉牛月に喘ぐごぎゅうつきにあえぐ
[世説新語言語](呉牛は、昼間太陽の暑さに苦しんでいるため、夜、月を見ても太陽と思って喘ぐ意から)過度に恐れること、取越し苦労をすることのたとえ。
▷しばしば「蜀犬日に吠ゆ」と対で使う。
⇒ご‐ぎゅう【呉牛】
こきゅう‐はくぶついん【故宮博物院】‥ヰン
中国の北京にある大博物館。明・清朝の紫禁城(故宮)内廷の遺構を利用して1925年開設。古書・美術工芸品を多数収蔵。内戦に伴い、精品は台北に運ばれ、65年同名の博物館を開設。
故宮博物院(北京)
撮影:小松義夫
 ⇒こ‐きゅう【故宮】
こきゅう‐りつ【呼吸率】‥キフ‥
生物が呼吸によって取り入れる酸素に対する同一時間内に放出する二酸化炭素の容積比。呼吸物質として燃焼される栄養物の種類によって異なり、炭水化物ならば1、脂肪や蛋白質ならば1以下となる。呼吸商。
⇒こ‐きゅう【呼吸】
⇒こ‐きゅう【故宮】
こきゅう‐りつ【呼吸率】‥キフ‥
生物が呼吸によって取り入れる酸素に対する同一時間内に放出する二酸化炭素の容積比。呼吸物質として燃焼される栄養物の種類によって異なり、炭水化物ならば1、脂肪や蛋白質ならば1以下となる。呼吸商。
⇒こ‐きゅう【呼吸】
 ⇒こ‐きゅう【故宮】
こきゅう‐りつ【呼吸率】‥キフ‥
生物が呼吸によって取り入れる酸素に対する同一時間内に放出する二酸化炭素の容積比。呼吸物質として燃焼される栄養物の種類によって異なり、炭水化物ならば1、脂肪や蛋白質ならば1以下となる。呼吸商。
⇒こ‐きゅう【呼吸】
⇒こ‐きゅう【故宮】
こきゅう‐りつ【呼吸率】‥キフ‥
生物が呼吸によって取り入れる酸素に対する同一時間内に放出する二酸化炭素の容積比。呼吸物質として燃焼される栄養物の種類によって異なり、炭水化物ならば1、脂肪や蛋白質ならば1以下となる。呼吸商。
⇒こ‐きゅう【呼吸】
ご‐ぎょくしょう【呉玉章】‥シヤウ🔗⭐🔉
ご‐ぎょくしょう【呉玉章】‥シヤウ
(Wu Yuzhang)中国の政治家・教育家。名は永珊えいさん。四川の人。辛亥革命に参加、人民共和国成立後は人民大学校長などを歴任。ラテン化新文字による中国語の文字改革に努める。(1878〜1966)
ご‐けいし【呉敬梓】🔗⭐🔉
ご‐けいし【呉敬梓】
中国、清初の文学者。安徽全椒の人。字は敏軒。号は文木。著「儒林外史」「文木山房集」「詩説」など。(1701〜1754)
ご‐こう【呉広】‥クワウ🔗⭐🔉
ご‐こう【呉広】‥クワウ
「陳勝ちんしょう」参照。
ご‐さんけい【呉三桂】🔗⭐🔉
ご‐さんけい【呉三桂】
明末・清初の武将。遼東の人。明末、山海関の守将であったが李自成が北京を陥れると清軍を入関させ、清朝より平西王(雲南)に封ぜられる。のち清朝にも叛き(三藩の乱)、病死。(1612〜1678)
ごし【呉子】🔗⭐🔉
ごし【呉子】
①中国、戦国時代の兵法家。名は起。衛の人。魯・魏・楚に仕え、楚の悼王の大臣となり国を強盛ならしめたが、王の没後殺された。(前440頃〜前385)
②呉起の著とされる兵法書。6編。「孫子」と並び称せられる。
ご‐しけん【呉師虔】🔗⭐🔉
ご‐しけん【呉師虔】
琉球王朝時代の画人。本名、山口宗季そうき。王命により中国に渡って画技を学ぶ。1710年、絵師主取ぬしとりとなり、王の肖像画制作に従事。(1672〜1743)
ご‐しゅゆ【呉茱萸】🔗⭐🔉
ご‐しゅゆ【呉茱萸】
ミカン科の落葉小高木。中国の原産。古くから日本でも栽培。高さ約3メートル。茎・葉に軟毛を密生。葉は羽状複葉、対生。雌雄異株。初夏、緑白色の小花をつける。紫赤色の果実は香気と辛味があり、生薬として漢方で健胃・利尿・駆風・鎮痛剤に用いる。川薑かわはじかみ。古名、からはじかみ。
ごしゅゆ
 ⇒ごしゅゆ‐とう【呉茱萸湯】
⇒ごしゅゆ‐とう【呉茱萸湯】
 ⇒ごしゅゆ‐とう【呉茱萸湯】
⇒ごしゅゆ‐とう【呉茱萸湯】
ごしゅゆ‐とう【呉茱萸湯】‥タウ🔗⭐🔉
ごしゅゆ‐とう【呉茱萸湯】‥タウ
呉茱萸・人参・大棗たいそう・生薑しょうきょうから成る漢方方剤。胃の冷えを伴う頭痛・嘔吐・下痢に用いる。
⇒ご‐しゅゆ【呉茱萸】
ご‐しゅん【呉春】🔗⭐🔉
ご‐しゅん【呉春】
松村月渓まつむらげっけいの別称。
ご‐しょうおん【呉承恩】🔗⭐🔉
ご‐しょうおん【呉承恩】
明代の文学者。字は汝忠、号は射陽山人。江蘇省淮安の人。狷介な性分で、諧謔を好んだ。官途に恵まれず、晩年は著述に専念。「西遊記」の作者とされる。(1500頃〜1582頃)
ご‐しょうずい【呉祥瑞】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
ご‐しょうずい【呉祥瑞】‥シヤウ‥
⇒しょんずい(祥瑞)
ご‐しょうせき【呉昌碩】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
ご‐しょうせき【呉昌碩】‥シヤウ‥
清末の書画家。名は俊卿。号は缶廬。安吉(浙江省)の人。石鼓文せっこぶん研究に基づく篆書てんしょ・篆刻の大家。絵は、花卉かき・山水を得意とした。(1844〜1927)
ご‐じる【呉汁・豆汁】🔗⭐🔉
ご‐じる【呉汁・豆汁】
(「醐汁」は当て字)水に浸して柔らかくした大豆をすりつぶした「ご」(豆汁)を入れた味噌汁。
ご‐す【呉須】🔗⭐🔉
ご‐す【呉須】
①磁器の染付に用いる藍色顔料。中国に天然に産する唐呉須という多量の酸化コバルト・マンガン・鉄などを含む黒褐色の粘土を用いたが、近来は合成呉須を使用。呉州。呉須土。
②呉須手の略。
ごす‐あおえ【呉須青絵】‥アヲヱ🔗⭐🔉
ごす‐あおえ【呉須青絵】‥アヲヱ
呉須赤絵で、赤絵具の代りに青を基本とした上絵付が施されたもの。青呉須。
ごす‐あかえ【呉須赤絵】‥ヱ🔗⭐🔉
ごす‐あかえ【呉須赤絵】‥ヱ
呉須手の一種。明末清初の頃に福建省漳州しょうしゅう付近で作られた、赤を基調とする色絵磁器。大皿など多くを輸出。赤絵呉須。
ごす‐そめつけ【呉須染付】🔗⭐🔉
ごす‐そめつけ【呉須染付】
呉須手の磁器で、白地に藍だけで文様を描いたもの。明末清初の頃、福建省漳州しょうしゅう付近から産出。
ごす‐で【呉須手】🔗⭐🔉
ごす‐で【呉須手】
中国南部、福建・広東地方で明末清初の頃に焼かれた磁器。粗製で奔放な絵模様を描くが、日本の茶人が呉須赤絵・呉須染付などと称し珍重。呉州手。呉須。
ごそしちこく‐の‐らん【呉楚七国の乱】🔗⭐🔉
ごそしちこく‐の‐らん【呉楚七国の乱】
前154年、前漢の景帝が封建諸王の領地を削ったのに対し、呉・楚・趙・膠西こうせい・膠東・ 川しせん・済南の七国の諸王が起こした反乱。直ちに鎮圧されて中央集権が強化された。
川しせん・済南の七国の諸王が起こした反乱。直ちに鎮圧されて中央集権が強化された。
 川しせん・済南の七国の諸王が起こした反乱。直ちに鎮圧されて中央集権が強化された。
川しせん・済南の七国の諸王が起こした反乱。直ちに鎮圧されて中央集権が強化された。
ご‐ちょう【呉澄】🔗⭐🔉
ご‐ちょう【呉澄】
元代の儒者。字は幼清。草廬先生と称。江西崇仁の人。南宋滅亡ののち元朝に召され、翰林学士となる。朱熹の後継者を自任し、心学・経学双方から朱子学を広めた。文正と諡おくりなす。(1249〜1333)
ご‐ちん【呉鎮】🔗⭐🔉
ご‐ちん【呉鎮】
画家。元末四大家の一人。字は仲圭。号は梅(梅花)道人。浙江嘉興の人。終生仕官せず、性孤潔。山水・墨竹に長じ、また、詩・書をもよくした。(1280〜1354)→四大家1
ゴ‐ディン‐ジェム【Ngo Dinh Diem・呉廷 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ゴ‐ディン‐ジェム【Ngo Dinh Diem・呉廷 】
ベトナム共和国(南ベトナム)初代大統領。1955年国民投票によりバオダイを破って大統領就任、親米反共主義の独裁を行う。クーデターにより暗殺。(1901〜1963)
ゴ‐ディン‐ジェム
提供:ullstein bild/APL
】
ベトナム共和国(南ベトナム)初代大統領。1955年国民投票によりバオダイを破って大統領就任、親米反共主義の独裁を行う。クーデターにより暗殺。(1901〜1963)
ゴ‐ディン‐ジェム
提供:ullstein bild/APL

 】
ベトナム共和国(南ベトナム)初代大統領。1955年国民投票によりバオダイを破って大統領就任、親米反共主義の独裁を行う。クーデターにより暗殺。(1901〜1963)
ゴ‐ディン‐ジェム
提供:ullstein bild/APL
】
ベトナム共和国(南ベトナム)初代大統領。1955年国民投票によりバオダイを破って大統領就任、親米反共主義の独裁を行う。クーデターにより暗殺。(1901〜1963)
ゴ‐ディン‐ジェム
提供:ullstein bild/APL

ご‐てん【呉天】🔗⭐🔉
ご‐てん【呉天】
(呉国の空の意)遠い異郷の地。
ご‐どうげん【呉道玄】‥ダウ‥🔗⭐🔉
ご‐どうげん【呉道玄】‥ダウ‥
呉道子ごどうしの別称。
ご‐どうし【呉道子】‥ダウ‥🔗⭐🔉
ご‐どうし【呉道子】‥ダウ‥
唐代の画家。初名、道子。玄宗のとき宮廷画家となり道玄と改名。主に山水・人物・鳥獣・仏像などを題材にとり、壁画の製作を中心に筆をふるい、唐代の画風を一変させた。特に大規模な構成力と雄渾な筆法とを謳われた。(680頃〜750頃)
ご‐ばいそん【呉梅村】🔗⭐🔉
ご‐ばいそん【呉梅村】
呉偉業ごいぎょうの別称。
ご‐はいふ【呉佩孚】🔗⭐🔉
ご‐はいふ【呉佩孚】
(Wu Peifu)中国の直隷派の軍閥。山東の人。1924年第2次奉直戦争に敗れ、26年春以来張作霖と提携、蒋介石の北伐に敗北、北京に隠棲。(1873〜1939)
ご‐ひん【呉彬】🔗⭐🔉
ご‐ひん【呉彬】
明末の画家。字は文中。福建莆田の人。白描はくびょうにすぐれる。生没年未詳。
ご‐ふく【呉服】🔗⭐🔉
ご‐ふく【呉服】
①呉の織り方によって織り出した布帛。くれはとり。宇津保物語田鶴群鳥「蔵司の―綾」
②織物の総称。反物たんもの。布帛。好色一代女4「―商売の若き者」
③(太物ふとものに対して)絹織物の称。
⇒ごふく‐ざし【呉服差】
⇒ごふく‐じゃく【呉服尺】
⇒ごふく‐じょ【呉服所】
⇒ごふく‐だな【呉服店】
⇒ごふく‐だな【呉服棚】
⇒ごふく‐の‐ま【呉服の間】
⇒ごふく‐ひじり【呉服聖】
⇒ごふく‐もの【呉服物】
⇒ごふく‐ものさし【呉服物差】
⇒ごふく‐や【呉服屋】
ごふく‐ざし【呉服差】🔗⭐🔉
ごふく‐じゃく【呉服尺】🔗⭐🔉
ごふく‐じょ【呉服所】🔗⭐🔉
ごふく‐じょ【呉服所】
大名高家の用をする呉服屋。御用商人として金銀の融通もした。日本永代蔵1「本町―京の出店」
⇒ご‐ふく【呉服】
ごふく‐だな【呉服店】🔗⭐🔉
ごふく‐だな【呉服棚】🔗⭐🔉
ごふく‐だな【呉服棚】
床の間・書院などの脇に設けた袋棚。呉服などを入れるのに用いたからいう。
⇒ご‐ふく【呉服】
ごふく‐の‐ま【呉服の間】🔗⭐🔉
ごふく‐の‐ま【呉服の間】
江戸幕府で、大奥に仕えて、将軍・御台所の衣服の裁縫の事をつかさどった奥女中。
⇒ご‐ふく【呉服】
ごふくばし‐もん【呉服橋門】🔗⭐🔉
ごふくばし‐もん【呉服橋門】
江戸城外濠の門の一つ。今の中央区八重洲にあった。→江戸城門(図)
ごふく‐ひじり【呉服聖】🔗⭐🔉
ごふく‐ひじり【呉服聖】
江戸時代に呉服を背負って売りあるいた行商人。もと、高野聖こうやひじりが諸国を巡行して衣服を売ったのに基づくという。せりごふく。
⇒ご‐ふく【呉服】
ごふく‐もの【呉服物】🔗⭐🔉
ごふく‐もの【呉服物】
織物。反物。きれ類。
⇒ご‐ふく【呉服】
ごふく‐や【呉服屋】🔗⭐🔉
ごふく‐や【呉服屋】
呉服、江戸時代には絹織物を売る店。また、その人。
⇒ご‐ふく【呉服】
ご‐れき【呉歴】🔗⭐🔉
ご‐れき【呉歴】
清初の画家。字は漁山。号は墨井。江蘇常熟の人。黄公望の法を学び、後に独自の表現力に富む山水画風を完成。四王ならびに惲寿平うんじゅへいとあわせて四王呉惲と称された。(1632〜1718)
ゴロ【呉羅・呉呂・呉絽】🔗⭐🔉
ゴロ【呉羅・呉呂・呉絽】
ゴロフクレンの略。
ゴロフク【呉絽服】🔗⭐🔉
ゴロフク【呉絽服】
ゴロフクレンの略。
ゴロフクレン【grofgrein オランダ・呉絽服連】🔗⭐🔉
ゴロフクレン【grofgrein オランダ・呉絽服連】
(grofは「粗い」「粗末な」の意)舶来の梳毛そもう織物。羊毛その他の粗剛な獣毛で織る。江戸ではゴロ、上方かみがたでフクリンと略した。ゴロフクリン。好色一代男7「羽織は―黒きに縞びろうどの裏をつけ」
[漢]呉🔗⭐🔉
呉 字形
 筆順
筆順
 〔口部4画/7画/常用/2466・3862〕
[
〔口部4画/7画/常用/2466・3862〕
[ ] 字形
] 字形
 〔口部4画/7画〕
〔音〕ゴ(漢)
〔訓〕くれ・くれる
[意味]
①中国の春秋時代・三国・五代にそれぞれ長江(=揚子江)下流の南に建てられた国の名。「呉楚ごそ七国・呉越同舟」
②古代日本で、中国、特に江南の地方の称。くれ。「呉服・呉音」▶「くれ」は、日の暮れる方角にある国の意の訓で、さらに、物を与える意の「くれる」にもこの字を当てるようになる。
③中国戦国時代の兵法家呉子。「孫呉の兵法」
[解字]
会意。下半部は、人が頭をかたむけたさま。「口」を加えて、人が頭をかたむけ大口をあけて笑う意。「娯」の原字。古くから国名に当てた。[
〔口部4画/7画〕
〔音〕ゴ(漢)
〔訓〕くれ・くれる
[意味]
①中国の春秋時代・三国・五代にそれぞれ長江(=揚子江)下流の南に建てられた国の名。「呉楚ごそ七国・呉越同舟」
②古代日本で、中国、特に江南の地方の称。くれ。「呉服・呉音」▶「くれ」は、日の暮れる方角にある国の意の訓で、さらに、物を与える意の「くれる」にもこの字を当てるようになる。
③中国戦国時代の兵法家呉子。「孫呉の兵法」
[解字]
会意。下半部は、人が頭をかたむけたさま。「口」を加えて、人が頭をかたむけ大口をあけて笑う意。「娯」の原字。古くから国名に当てた。[ ]は異体字。
]は異体字。
 筆順
筆順
 〔口部4画/7画/常用/2466・3862〕
[
〔口部4画/7画/常用/2466・3862〕
[ ] 字形
] 字形
 〔口部4画/7画〕
〔音〕ゴ(漢)
〔訓〕くれ・くれる
[意味]
①中国の春秋時代・三国・五代にそれぞれ長江(=揚子江)下流の南に建てられた国の名。「呉楚ごそ七国・呉越同舟」
②古代日本で、中国、特に江南の地方の称。くれ。「呉服・呉音」▶「くれ」は、日の暮れる方角にある国の意の訓で、さらに、物を与える意の「くれる」にもこの字を当てるようになる。
③中国戦国時代の兵法家呉子。「孫呉の兵法」
[解字]
会意。下半部は、人が頭をかたむけたさま。「口」を加えて、人が頭をかたむけ大口をあけて笑う意。「娯」の原字。古くから国名に当てた。[
〔口部4画/7画〕
〔音〕ゴ(漢)
〔訓〕くれ・くれる
[意味]
①中国の春秋時代・三国・五代にそれぞれ長江(=揚子江)下流の南に建てられた国の名。「呉楚ごそ七国・呉越同舟」
②古代日本で、中国、特に江南の地方の称。くれ。「呉服・呉音」▶「くれ」は、日の暮れる方角にある国の意の訓で、さらに、物を与える意の「くれる」にもこの字を当てるようになる。
③中国戦国時代の兵法家呉子。「孫呉の兵法」
[解字]
会意。下半部は、人が頭をかたむけたさま。「口」を加えて、人が頭をかたむけ大口をあけて笑う意。「娯」の原字。古くから国名に当てた。[ ]は異体字。
]は異体字。
広辞苑に「呉」で始まるの検索結果 1-88。もっと読み込む