複数辞典一括検索+![]()
![]()
き【酒】🔗⭐🔉
き【酒】
さけの古称。続日本紀26「黒くろ―白しろ―」。「み―」
くし‐の‐かみ【酒の司・酒の長】🔗⭐🔉
くし‐の‐かみ【酒の司・酒の長】
酒のことをつかさどる首長。古事記中「―常世とこよにいます、石立たす少名御神」
さか【酒】🔗⭐🔉
さか【酒】
「さけ」の古形。複合語に用いられる。「―樽」
さか‐あいさつ【酒挨拶】🔗⭐🔉
さか‐あいさつ【酒挨拶】
酒を供して客をもてなすこと。浄瑠璃、堀川波鼓「―の客振の、よきも過ぎては仇となる」
さか‐あぶら【酒膏・醪】🔗⭐🔉
さか‐あぶら【酒膏・醪】
濁り酒の上に浮かんだかす。一説に濁り酒ともいう。〈倭名類聚鈔16〉
さかい【酒井】‥ヰ🔗⭐🔉
さかい【酒井】‥ヰ
姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。
⇒さかい‐ただかつ【酒井忠勝】
⇒さかい‐ただきよ【酒井忠清】
⇒さかい‐ただつぐ【酒井忠次】
⇒さかい‐ただよ【酒井忠世】
⇒さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】
⇒さかい‐ほういつ【酒井抱一】
さかい‐ただかつ【酒井忠勝】‥ヰ‥🔗⭐🔉
さかい‐ただかつ【酒井忠勝】‥ヰ‥
江戸前期の若狭小浜藩主。徳川家光の側近より累進、老中・大老として幕政運営の中心となる。(1587〜1662)
⇒さかい【酒井】
さかい‐ただきよ【酒井忠清】‥ヰ‥🔗⭐🔉
さかい‐ただきよ【酒井忠清】‥ヰ‥
江戸前期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。忠世の孫。大老となり、徳川家綱を補佐して威権を振るい、世に下馬将軍げばしょうぐんと称された。(1624〜1681)
⇒さかい【酒井】
さかい‐ただつぐ【酒井忠次】‥ヰ‥🔗⭐🔉
さかい‐ただつぐ【酒井忠次】‥ヰ‥
安土桃山時代の武将。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。妻は家康の叔母。家康の幼時よりこれを補佐、三方ヶ原・長篠・小牧の戦に功を立てた。(1527〜1596)
⇒さかい【酒井】
さかい‐ただよ【酒井忠世】‥ヰ‥🔗⭐🔉
さかい‐ただよ【酒井忠世】‥ヰ‥
江戸初期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。徳川秀忠の年寄衆の一人。のち土井利勝らとともに3代将軍家光の補導役。幕政の中心となった。(1572〜1636)
⇒さかい【酒井】
さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】‥ヰ‥🔗⭐🔉
さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】‥ヰ‥
歌舞伎脚本「太鼓音智勇三略たいこのおとちゆうのさんりゃく」の通称。新歌舞伎十八番の一つ。4幕。河竹黙阿弥作の時代物。1873年(明治6)初演。酒井忠次が櫓やぐらの太鼓を打ち、寄せ手に城の囲みを解かせたことを脚色する。
⇒さかい【酒井】
さかい‐ほういつ【酒井抱一】‥ヰハウ‥🔗⭐🔉
さかい‐ほういつ【酒井抱一】‥ヰハウ‥
江戸後期の画家。抱一派の祖。名は忠因ただなお。鶯村・雨華庵と号した。姫路城主酒井忠以ただざねの弟。西本願寺で出家し権大僧都となったが、江戸に隠棲。絵画・俳諧に秀で、特に尾形光琳に私淑してその画風に一層の洒脱さを加えた江戸風琳派を完成させた。(1761〜1828)
⇒さかい【酒井】
さか‐きげん【酒機嫌】🔗⭐🔉
さか‐きげん【酒機嫌】
酒に酔った時の機嫌。ささ機嫌。好色一代女3「呑みかけて―」
さか‐ぐるい【酒狂い】‥グルヒ🔗⭐🔉
さか‐ぐるい【酒狂い】‥グルヒ
酒狂しゅきょう。義経記3「それは地体―するものにて候ぞ」
さか‐け【酒気】🔗⭐🔉
さか‐け【酒気】
酒の気け。酒の酔い。しゅき。浄瑠璃、浦島年代記「峠で飲んだ―がすつきりしやんとさめはてた」
さか‐ごと【酒事】🔗⭐🔉
さか‐ごと【酒事】
さかもり。ささごと。酒宴。傾城色三味線「あへばはや別れの旦あしたを思ひやりて、―やめて語る夜も」
さか‐しお【酒塩】‥シホ🔗⭐🔉
さか‐しお【酒塩】‥シホ
煮物の調味のために、酒を加えること。また、その酒。狂言、地蔵舞「この六条か若和布にひたして、―と申てたぶれば」
さか‐だね【酒種】🔗⭐🔉
さか‐だね【酒種】
日本酒の醸造に用いる酵母。
さか‐て【酒手】🔗⭐🔉
さか‐て【酒手】
①酒の代金。さかしろ。さかだい。狂言、千鳥「内々の―の算用が済みませぬに依つて」
②人夫・車夫などに与える心づけの金銭。「―をはずむ」
さか‐に【酒荷】🔗⭐🔉
さか‐に【酒荷】
酒を樽につめて荷造りしたもの。
⇒さかに‐くちきん【酒荷口金】
さかに‐くちきん【酒荷口金】🔗⭐🔉
さかに‐くちきん【酒荷口金】
江戸時代、関東の私領で課された酒造税。
⇒さか‐に【酒荷】
さか‐はずれ【酒外れ】‥ハヅレ🔗⭐🔉
さか‐はずれ【酒外れ】‥ハヅレ
酒席で、ひとり酒を飲まずにいること。狂言、右流左止うるさし「昔から―はせぬ事ぢや」
さか‐ばた【酒旗】🔗⭐🔉
さか‐ばた【酒旗】
①酒屋の看板にかかげる旗。酒旆しゅはい。
②(→)「さかばやし」1に同じ。
さか‐ほがい【酒寿・酒祝】‥ホガヒ🔗⭐🔉
さか‐ほがい【酒寿・酒祝】‥ホガヒ
(古くは清音)酒宴をして祝うこと。神功紀「觴みさかずきを挙ささげて太子に―したまふ」
さか‐むかい【坂迎ひ・酒迎ひ】‥ムカヒ🔗⭐🔉
さか‐むかい【坂迎ひ・酒迎ひ】‥ムカヒ
(→)「さかむかえ(坂迎)」2に同じ。好色五人女2「―に寝所ねどころをしてとらせ」
さか‐むろ【酒室】🔗⭐🔉
さか‐むろ【酒室】
酒を作るための室むろ。酒殿。
さか‐や【酒屋】🔗⭐🔉
さか‐や【酒屋】
①酒を造る建物。酒殿さかどの。万葉集16「梯立はしたての熊来くまき―に」
②酒を造り、または売る人。また、その店。さかみせ。さかだな。
③浄瑠璃「艶容女舞衣はですがたおんなまいぎぬ」酒屋の段のこと。また、歌舞伎での同場面の通称。
→文献資料[艶容女舞衣(酒屋の段)]
⇒さかや‐かいぎ【酒屋会議】
⇒さかや‐どそう【酒屋土倉】
⇒さかや‐やく【酒屋役】
⇒酒屋へ三里豆腐屋へ二里
さかや‐かいぎ【酒屋会議】‥クワイ‥🔗⭐🔉
さかや‐かいぎ【酒屋会議】‥クワイ‥
1882年(明治15)全国の酒造家代表が自由民権運動と結び、酒税軽減を要求して京阪間で開いた会議。
⇒さか‐や【酒屋】
○酒屋へ三里豆腐屋へ二里さかやへさんりとうふやへにり🔗⭐🔉
○酒屋へ三里豆腐屋へ二里さかやへさんりとうふやへにり
田舎いなかの不便な土地のたとえ。「ほととぎす自由自在に聞く里は―」(頭光)
⇒さか‐や【酒屋】
さか‐やまい【酒病】‥ヤマヒ
甚だしく酒に酔って病気となること。酒毒にあてられること。二日酔。さかやもい。
さかや‐やく【酒屋役】
室町時代に幕府が酒造家に課した税。酒役さかやく。酒壺銭。造酒役つくりざかやく。
⇒さか‐や【酒屋】
さか‐ゆ【酒湯】
(→)「ささゆ」に同じ。
さか・ゆ【栄ゆ】
〔自下二〕
⇒さかえる(下一)
さか‐ゆ・く【栄行く】
〔自四〕
ますます栄えていく。徒然草「子孫を愛して―・く末を見むまでの命をあらまし」
さか‐ゆめ【逆夢】
実際とは反対の事を見る夢。また、吉凶を占う時など、実際には逆の事が起こるとされる夢。浄瑠璃、天神記「夢は―と心で祝ひ」↔正夢まさゆめ
さが‐よう【嵯峨様】‥ヤウ
和様書道の一派。
さか‐よせ【逆寄せ】
攻め寄せる敵軍に対して、逆に自分の方から攻め返すこと。逆襲。太平記6「今夜―にして、打ち散らして捨て候はばや」
さか‐よみ【逆読み】
語句をさかさに読むこと。
さがら【相良】
姓氏の一つ。出身は遠江相良荘。中世、関東御家人で、肥後人吉地方の地頭領主。戦国時代には球磨・八代・葦北3郡の大名。
⇒さがらし‐はっと【相良氏法度】
ざ‐がら【座柄】
一座の客の様子。その場の雰囲気。
さから・う【逆らう】サカラフ
〔自五〕
順当な方向に反して、逆に進もうとする。反抗する。「風に―・う」「先生に―・う」「時流に―・う」
さがらし‐はっと【相良氏法度】
肥後人吉城主相良為続ためつぐ・長毎ながつね・晴広3代の1493年(明応2)より1555年(弘治1)に至る分国法。41カ条。
⇒さがら【相良】
さがら‐そうぞう【相楽総三】‥ザウ
尊攘派志士。小島四郎左衛門(将満)の変名。江戸生れ。父は下総の郷士。水戸天狗党の筑波山挙兵に参加。また西郷隆盛の指令を受け江戸で治安を攪乱。赤報隊を結成し年貢半減令を掲げて東山道を進軍途上、維新政府に偽官軍として捕らえられ、下諏訪で処刑。(1839〜1868)
さがら‐ぬい【相良繍】‥ヌヒ
日本刺繍ししゅうの一技法。布の表面に結び目を作って、立体的な点を表し、また、それを多数並べて面の充填に用いる。玉繍たまぬい。瘤繍こぶぬい。疣繍いぼぬい。ノット‐ステッチ。
さがら‐め【相良布】
静岡県相良地方に産する海草。カジメによく似る。
サカラメント【sacramento ポルトガル】
(キリシタン用語)秘跡。どちりなきりしたん目録「七の―の事」→サクラメント
さかり【盛り】
①勢いが盛んなこと。栄えているさま。隆盛。万葉集5「―に咲ける梅の花」。「暑い―」
②強壮な時。青壮年期。体力や気力が最も充実している時期。源氏物語葵「若く―の子におくれ奉りて」。「―を過ぎる」
③人が多く寄り集まり、商売などが盛んであること。繁昌。にぎわい。人情本、春色辰巳園「―の時は十や二十の金はなんのといふやうになるのも土地がら」
④獣類が一定の時期に発情すること。「―がつく」
⑤「…ざかり」の形で、接尾語的にも使う。「花―」「女―」「働き―」
⇒さかり‐うるし【盛り漆】
⇒さかり‐どき【盛り時】
⇒さかり‐ば【盛り場】
⇒さかり‐びと【盛り人】
さがり【下がり】
①上から下へ、または前から後へ位置のかわること。
②程度や価値の低くなること。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「たくさんの米の買置をして、―を見て売りはらひ」。「物価の上がり―に応じて」
③(「お―」の形で)神仏の前から下げた供え物。また、客に出した食べ物の残り。転じて、目上の者から譲り与えられた物。「お―を頂戴する」「兄のお―の服」
④掛買代金の支払いの済まないもの。さがりがね。文武二道万石通「三万両の―が出来」
⑤ある時刻を過ぎること。太平記31「日已に酉とりの―に成つて」。「昼―」
⑥「おくみ(衽)さがり」の略。
⑦相撲取りが褌みつの前に飾りに垂れさげるもの。
⑧和船で、舳みよしの先端に垂れさげる黒い縄の飾り。かもじ。たれ。→和船(図)。
⇒さがり‐がね【下がり銀】
⇒さがり‐くち【下がり口】
⇒さがり‐ぐも【下がり蜘蛛】
⇒さがり‐ごけ【下がり苔】
⇒さがり‐しお【下がり潮】
⇒さがり‐ねこ【下がり猫】
⇒さがり‐は【下破・下端】
⇒さがり‐ば【下がり端】
⇒さがり‐ばな【下がり花】
⇒さがり‐ばら【下がり腹】
⇒さがり‐ふじ【下がり藤】
⇒さがり‐ふすべ【懸疣】
⇒さがり‐まつ【下がり松】
⇒さがり‐め【下がり目】
⇒下がりを請く
さがり【鍑】
釣り下げて物を煮る、口の大きい釜。懸釜。〈倭名類聚鈔16〉
さがり‐いす【下がりいす】
(「下がります」の意)江戸吉原で、2階から杯盤などを階下に下げる時、禿かぶろなどがその合図として呼ぶ言葉。さがりんす。
さかり‐うるし【盛り漆】
ウルシの木から樹液を採集する際、初掻から20回までの間(7月中旬から9月初旬頃)に掻いた、上等の生漆きうるし。
⇒さかり【盛り】
さがり‐がね【下がり銀】
(→)「さがり」4に同じ。
⇒さがり【下がり】
さがり‐くち【下がり口】
物価が下落しかける時期。また、物事のおとろえかかる初め。さがりめ。
⇒さがり【下がり】
さがり‐ぐも【下がり蜘蛛】
天井などから糸を引いて垂れ下がった蜘蛛。俗に朝の下がり蜘蛛は吉兆という。
⇒さがり【下がり】
さがり‐ごけ【下がり苔】
〔植〕
①サルオガセの異称。
②ヒカゲノカズラの異称。
⇒さがり【下がり】
さがり‐しお【下がり潮】‥シホ
(→)引潮ひきしおに同じ。
⇒さがり【下がり】
さかり‐どき【盛り時】
①盛りの時期。旺盛な時。
②獣類の発情期。交尾期。
⇒さかり【盛り】
さがり‐ねこ【下がり猫】
尾が長くさがっている猫。不運を招くという。
⇒さがり【下がり】
さかり‐ば【盛り場】
人が多く寄り集まってにぎやかな場所。繁華街。
⇒さかり【盛り】
さがり‐は【下破・下端】
①能や狂言の囃子事はやしごとの一つ。能の天仙などの出、狂言の祭りの行列の出など、歌いはやしながら登場する趣に用いる。
②歌舞伎の囃子の一つ。
㋐能とは別曲で、貴人の出入などに用いる。
㋑能の下端から取り、天王立てんのうだちと呼んで、義太夫狂言の大序の幕開きに用いる。
㋒能に準じ、舞踊音楽に多く用いる。
⇒さがり【下がり】
さがり‐ば【下がり端】
平安時代以後、女性の垂髪の額髪を肩の辺で揃えて切った端はし。また、その髪のさま。源氏物語空蝉「髪は…―肩のほどいときよげに」
⇒さがり【下がり】
さがり‐ばな【下がり花】
サガリバナ科の常緑高木。旧大陸の熱帯・亜熱帯の海岸などに生える。日本では奄美大島以南の南西諸島に自生。高さ10メートルに達し、大きな楕円形の葉を互生。夏に長さ数十センチメートルの長い花穂を垂下して、淡紅色か白色の花を多数つける。多数の長い雄しべが目立つ。
⇒さがり【下がり】
さがり‐ばら【下がり腹】
正妻以外の女から生まれること。妾腹。
⇒さがり【下がり】
さかり‐びと【盛り人】
若くて元気な人。わかもの。古事記下「身の―羨ともしきろかも」
⇒さかり【盛り】
さがり‐ふじ【下がり藤】‥フヂ
紋所の名。二房の藤の花を組み合わせ、左右に垂らして輪を描いたもの。↔上がり藤。→藤(図)。
⇒さがり【下がり】
さがり‐ふすべ【懸疣】
垂れさがったいぼ。〈倭名類聚鈔3〉
⇒さがり【下がり】
さがり‐まつ【下がり松】
枝の垂れさがった松。
⇒さがり【下がり】
さがり‐め【下がり目】
①目尻のさがった目。たれめ。
②(→)「下がり口」に同じ。
↔上がり目
⇒さがり【下がり】
さが‐りゅう【嵯峨流】‥リウ
①和様書道の一派。本阿弥光悦の門人、嵯峨の人角倉すみのくら素庵の創始。角倉流。与一流。
②築庭の一派。夢窓疎石が創めたという。天竜寺の庭を範とするもの。
さかや‐やく【酒屋役】🔗⭐🔉
さかや‐やく【酒屋役】
室町時代に幕府が酒造家に課した税。酒役さかやく。酒壺銭。造酒役つくりざかやく。
⇒さか‐や【酒屋】
さけ【酒】🔗⭐🔉
さけ‐うんじょう【酒運上】‥ジヤウ🔗⭐🔉
さけ‐うんじょう【酒運上】‥ジヤウ
酒の消費抑制のため、江戸幕府が課した酒造税。1697年(元禄10)に設けられたが、酒価の高騰をまねき、1709年(宝永6)に廃止。→酒造冥加
○酒が酒を飲むさけがさけをのむ🔗⭐🔉
○酒が酒を飲むさけがさけをのむ
酒飲みは酔いがまわるに従ってますます大酒を飲む。
⇒さけ【酒】
さげ‐かじ【下げ舵】‥カヂ
潜水艦を下降させるかじの取り方。↔上げ舵
さけ‐かす【酒粕・酒糟】
清酒の醸造に際し、もろみをしぼったあとに残ったかす。蒸留して焼酎しょうちゅうを製し、また食用とし、奈良漬・魚肉漬などを作るのに用いる。さかかす。さけのかす。
さけ‐かた【酒方】
室町幕府で、酒の出納をつかさどった職。
さげ‐がたな【提げ刀】
刀を手にさげ持つこと。また、その刀。提太刀さげだち。
さげ‐かま【下鎌】
〔建〕貫ぬきを柱に取り付ける仕口しくちの一種。貫の端を鳩尾きゅうび形にし、柱の穴に差し込んで上にくさびを打つもの。↔上鎌あげかま
下鎌
 さげ‐がみ【下げ紙】
公文書などに貼り下げて意見・理由などを書きつけた紙。つけがみ。付箋ふせん。下札さげふだ。
さげ‐がみ【下げ髪・垂髪】
①女の髪型。髻もとどりをたばねて背後に垂れ下げたもの。江戸時代、貴婦人・宮女などが晴れの時などに結んだ。すべらかし。
②少女の髪型。髪を左右に分け、編んで垂らしたもの。おさげ。
③歌舞伎の鬘かつらの一つ。1の形にしたもの。
さけ‐がめ【酒甕】
⇒さかがめ
さけ‐きちがい【酒気違い・酒狂】‥キチガヒ
①酒に酔ってくるい乱れること。また、その人。酒乱しゅらん。
②甚だしく酒を好んで他事を顧みないこと。また、その人。
さげ‐ぎり【下げ斬り】
①上から斬りおろすこと。狂言、朝比奈「古郡が筒抜き・―」
②片手で宙にひっさげ、もう一方の手で斬ること。つるしぎり。提斬り。
さけく【幸く】
〔副〕
(上代東国方言)(→)「さきく」に同じ。万葉集20「もろもろは―と申す帰り来くまでに」
さけ‐くさ・い【酒臭い】
〔形〕[文]さけくさ・し(ク)
酒のにおいがする。
さけ‐くせ【酒癖】
(サケグセとも)酒に酔った時に出るくせ。さかくせ。「―が悪い」
さけ‐くらい【酒食らい】‥クラヒ
おおざけのみ。
さげ‐ごし【下げ輿】
轅ながえを腰のあたりに持ちあげて運ぶ輿。
さけ‐ごと【酒事】
⇒さかごと
さけ‐こわい【酒強飯】‥コハヒ
(サケコハイヒの約)酒造の際、水に漬けておいてから甑こしきで蒸した精白米。
さけ‐さかな【酒肴】
酒と酒のさかな。しゅこう。
さげ‐ざや【提げ鞘】
①(→)「みせざや」に同じ。
②僧の携える小刀・戒刀の類。
③茶人の携える小刀。
さけ‐じ【裂け痔】‥ヂ
(→)「きれ痔」に同じ。
さげ‐しお【下げ潮】‥シホ
(→)「ひきしお」1に同じ。↔上げ潮
さげ‐じきろう【提食籠】
手にさげて持ち歩けるようにした食籠。
さげ‐したじ【下げ下地】‥ヂ
女の髪の結い方。前髪をつくり、鬢びんをふくらませ、髱たぼを左右で二つに割り、髷まげを島田のようにし、髪の余りを笄こうがいに巻きつけたもの。笄を抜けば下げ髪になるのでいう。江戸幕府の奥女中や大名の妻などの髪型。
さげ‐しぶり【下げ渋り】
(取引用語)相場が下落しそうで下落しないこと。
さげ‐しまだ【下げ島田】
(→)「投げ島田」に同じ。
さげしみ【蔑み】
(→)「さげすみ」に同じ。
さげし・む【蔑む】
〔他四〕
(「下げし見る」の意とも、「下墨さげすむ」の転ともいう)
①見くだす。蔑視する。栂尾明恵上人伝記「いやしみ―・み給へば大罪弥いよいよ深し」
②批判する。とやかくいう。傾城禁短気「物日ものびが厭いやさに四の五のといふと、―・まるるが無念な」
さげ‐じゅう【提げ重】‥ヂユウ
①提重箱の略。
②江戸で、明和・安永(1764〜1781)ごろはやった私娼。提重箱をさげて物を売り歩くさまで徘徊し、売淫したもの。
さげ‐じゅうばこ【提重箱】‥ヂユウ‥
さげて携行するようにつくった組重箱。提げ重。
さけ‐ずし【酒鮨】
硬めの飯に土地特有の甘味の強い地酒をたっぷりかけ、山海の幸を取り合わせて鮨桶に数時間漬け込んだ料理。鹿児島の郷土料理。
さげすみ【蔑み・貶み】
さげすむこと。軽蔑。蔑視。さげしみ。
さげ‐すみ【下墨】
(サゲズミとも)
①柱などの傾きを見るために、大工が墨糸を垂直にたらして見定めること。下げ振り。垂準。談林俳諧
さげ‐がみ【下げ紙】
公文書などに貼り下げて意見・理由などを書きつけた紙。つけがみ。付箋ふせん。下札さげふだ。
さげ‐がみ【下げ髪・垂髪】
①女の髪型。髻もとどりをたばねて背後に垂れ下げたもの。江戸時代、貴婦人・宮女などが晴れの時などに結んだ。すべらかし。
②少女の髪型。髪を左右に分け、編んで垂らしたもの。おさげ。
③歌舞伎の鬘かつらの一つ。1の形にしたもの。
さけ‐がめ【酒甕】
⇒さかがめ
さけ‐きちがい【酒気違い・酒狂】‥キチガヒ
①酒に酔ってくるい乱れること。また、その人。酒乱しゅらん。
②甚だしく酒を好んで他事を顧みないこと。また、その人。
さげ‐ぎり【下げ斬り】
①上から斬りおろすこと。狂言、朝比奈「古郡が筒抜き・―」
②片手で宙にひっさげ、もう一方の手で斬ること。つるしぎり。提斬り。
さけく【幸く】
〔副〕
(上代東国方言)(→)「さきく」に同じ。万葉集20「もろもろは―と申す帰り来くまでに」
さけ‐くさ・い【酒臭い】
〔形〕[文]さけくさ・し(ク)
酒のにおいがする。
さけ‐くせ【酒癖】
(サケグセとも)酒に酔った時に出るくせ。さかくせ。「―が悪い」
さけ‐くらい【酒食らい】‥クラヒ
おおざけのみ。
さげ‐ごし【下げ輿】
轅ながえを腰のあたりに持ちあげて運ぶ輿。
さけ‐ごと【酒事】
⇒さかごと
さけ‐こわい【酒強飯】‥コハヒ
(サケコハイヒの約)酒造の際、水に漬けておいてから甑こしきで蒸した精白米。
さけ‐さかな【酒肴】
酒と酒のさかな。しゅこう。
さげ‐ざや【提げ鞘】
①(→)「みせざや」に同じ。
②僧の携える小刀・戒刀の類。
③茶人の携える小刀。
さけ‐じ【裂け痔】‥ヂ
(→)「きれ痔」に同じ。
さげ‐しお【下げ潮】‥シホ
(→)「ひきしお」1に同じ。↔上げ潮
さげ‐じきろう【提食籠】
手にさげて持ち歩けるようにした食籠。
さげ‐したじ【下げ下地】‥ヂ
女の髪の結い方。前髪をつくり、鬢びんをふくらませ、髱たぼを左右で二つに割り、髷まげを島田のようにし、髪の余りを笄こうがいに巻きつけたもの。笄を抜けば下げ髪になるのでいう。江戸幕府の奥女中や大名の妻などの髪型。
さげ‐しぶり【下げ渋り】
(取引用語)相場が下落しそうで下落しないこと。
さげ‐しまだ【下げ島田】
(→)「投げ島田」に同じ。
さげしみ【蔑み】
(→)「さげすみ」に同じ。
さげし・む【蔑む】
〔他四〕
(「下げし見る」の意とも、「下墨さげすむ」の転ともいう)
①見くだす。蔑視する。栂尾明恵上人伝記「いやしみ―・み給へば大罪弥いよいよ深し」
②批判する。とやかくいう。傾城禁短気「物日ものびが厭いやさに四の五のといふと、―・まるるが無念な」
さげ‐じゅう【提げ重】‥ヂユウ
①提重箱の略。
②江戸で、明和・安永(1764〜1781)ごろはやった私娼。提重箱をさげて物を売り歩くさまで徘徊し、売淫したもの。
さげ‐じゅうばこ【提重箱】‥ヂユウ‥
さげて携行するようにつくった組重箱。提げ重。
さけ‐ずし【酒鮨】
硬めの飯に土地特有の甘味の強い地酒をたっぷりかけ、山海の幸を取り合わせて鮨桶に数時間漬け込んだ料理。鹿児島の郷土料理。
さげすみ【蔑み・貶み】
さげすむこと。軽蔑。蔑視。さげしみ。
さげ‐すみ【下墨】
(サゲズミとも)
①柱などの傾きを見るために、大工が墨糸を垂直にたらして見定めること。下げ振り。垂準。談林俳諧 判「蚊柱の―なれや蜘くもの糸」→正直しょうじき3。
②物事をおしはかること。見積もること。甲陽軍鑑10「信玄公御―少しもちがはず候」
さげす・む【蔑む・貶む】
〔他五〕
みくだす。みさげる。軽蔑する。甲陽軍鑑10「信玄公の氏政を―・み給ふと」。「―・んだ目付き」
さげ‐す・む【下墨む】
〔他四〕
(「下墨さげすみ」を動詞化した語)
①下墨をする。測量する。七十一番職人尽歌合「をしなをす工たくみもいさや墨金すみかねに―・む月のかたぶきにけり」
②おしはかる。推察する。見積もる。醒睡笑「何にも余分をおきて―・むべきものなり」
さげ‐ぜに【下げ銭】
(緡ぜにさしや棒などに銭を通して腰にさげたからいう)日雇職人などが身につけているはした銭。誹風柳多留23「―でくどいたを下女憤り」
さげ‐そ【下苧】
漆喰しっくいなどの剥落を防ぐため、木摺きずり下地に打った釘の頭に結び下げて塗り込む麻あさ。さげお。
さげ‐だち【提太刀】
(→)「さげがたな」に同じ。
さげ‐だな【下げ棚】
つりさげた棚。
さげ‐タバコぼん【提煙草盆】
把手とってをつけ、さげて持ち運ぶようにつくったタバコ盆。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「肩荷の端に―折々休む道草の」
さげ‐づえ【下げ杖】‥ヅヱ
大田植おおたうえの総指揮者さげの携える竹杖。
さけ‐づくり【酒造り】
⇒さかづくり
さけ‐づけ【酒漬け】
酒に漬けること。また、その漬けたもの。
さげ‐づつ【提げ筒】
携帯できる鉄砲。小銃の旧称。
さげ‐づと【下げ髱】
女の髪の結い方。髱たぼを下げて結うもの。江戸時代、奥女中の使番つかいばん以下の間に行われた。
さけ‐どころ【酒所】
酒の生産地として有名な所。さかどころ。
さげ‐どまり【下げ止り】
物価・相場などが下がり続けて、これ以上下がらない水準になること。
さげ‐なわ【下げ縄】‥ナハ
①土蔵の木舞こまいに結び下げた縄。これを壁の中に塗り込んでその剥落を防ぐもの。
②(大工の隠語)上方で、うどん。江戸で、そば。
判「蚊柱の―なれや蜘くもの糸」→正直しょうじき3。
②物事をおしはかること。見積もること。甲陽軍鑑10「信玄公御―少しもちがはず候」
さげす・む【蔑む・貶む】
〔他五〕
みくだす。みさげる。軽蔑する。甲陽軍鑑10「信玄公の氏政を―・み給ふと」。「―・んだ目付き」
さげ‐す・む【下墨む】
〔他四〕
(「下墨さげすみ」を動詞化した語)
①下墨をする。測量する。七十一番職人尽歌合「をしなをす工たくみもいさや墨金すみかねに―・む月のかたぶきにけり」
②おしはかる。推察する。見積もる。醒睡笑「何にも余分をおきて―・むべきものなり」
さげ‐ぜに【下げ銭】
(緡ぜにさしや棒などに銭を通して腰にさげたからいう)日雇職人などが身につけているはした銭。誹風柳多留23「―でくどいたを下女憤り」
さげ‐そ【下苧】
漆喰しっくいなどの剥落を防ぐため、木摺きずり下地に打った釘の頭に結び下げて塗り込む麻あさ。さげお。
さげ‐だち【提太刀】
(→)「さげがたな」に同じ。
さげ‐だな【下げ棚】
つりさげた棚。
さげ‐タバコぼん【提煙草盆】
把手とってをつけ、さげて持ち運ぶようにつくったタバコ盆。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「肩荷の端に―折々休む道草の」
さげ‐づえ【下げ杖】‥ヅヱ
大田植おおたうえの総指揮者さげの携える竹杖。
さけ‐づくり【酒造り】
⇒さかづくり
さけ‐づけ【酒漬け】
酒に漬けること。また、その漬けたもの。
さげ‐づつ【提げ筒】
携帯できる鉄砲。小銃の旧称。
さげ‐づと【下げ髱】
女の髪の結い方。髱たぼを下げて結うもの。江戸時代、奥女中の使番つかいばん以下の間に行われた。
さけ‐どころ【酒所】
酒の生産地として有名な所。さかどころ。
さげ‐どまり【下げ止り】
物価・相場などが下がり続けて、これ以上下がらない水準になること。
さげ‐なわ【下げ縄】‥ナハ
①土蔵の木舞こまいに結び下げた縄。これを壁の中に塗り込んでその剥落を防ぐもの。
②(大工の隠語)上方で、うどん。江戸で、そば。
 さげ‐がみ【下げ紙】
公文書などに貼り下げて意見・理由などを書きつけた紙。つけがみ。付箋ふせん。下札さげふだ。
さげ‐がみ【下げ髪・垂髪】
①女の髪型。髻もとどりをたばねて背後に垂れ下げたもの。江戸時代、貴婦人・宮女などが晴れの時などに結んだ。すべらかし。
②少女の髪型。髪を左右に分け、編んで垂らしたもの。おさげ。
③歌舞伎の鬘かつらの一つ。1の形にしたもの。
さけ‐がめ【酒甕】
⇒さかがめ
さけ‐きちがい【酒気違い・酒狂】‥キチガヒ
①酒に酔ってくるい乱れること。また、その人。酒乱しゅらん。
②甚だしく酒を好んで他事を顧みないこと。また、その人。
さげ‐ぎり【下げ斬り】
①上から斬りおろすこと。狂言、朝比奈「古郡が筒抜き・―」
②片手で宙にひっさげ、もう一方の手で斬ること。つるしぎり。提斬り。
さけく【幸く】
〔副〕
(上代東国方言)(→)「さきく」に同じ。万葉集20「もろもろは―と申す帰り来くまでに」
さけ‐くさ・い【酒臭い】
〔形〕[文]さけくさ・し(ク)
酒のにおいがする。
さけ‐くせ【酒癖】
(サケグセとも)酒に酔った時に出るくせ。さかくせ。「―が悪い」
さけ‐くらい【酒食らい】‥クラヒ
おおざけのみ。
さげ‐ごし【下げ輿】
轅ながえを腰のあたりに持ちあげて運ぶ輿。
さけ‐ごと【酒事】
⇒さかごと
さけ‐こわい【酒強飯】‥コハヒ
(サケコハイヒの約)酒造の際、水に漬けておいてから甑こしきで蒸した精白米。
さけ‐さかな【酒肴】
酒と酒のさかな。しゅこう。
さげ‐ざや【提げ鞘】
①(→)「みせざや」に同じ。
②僧の携える小刀・戒刀の類。
③茶人の携える小刀。
さけ‐じ【裂け痔】‥ヂ
(→)「きれ痔」に同じ。
さげ‐しお【下げ潮】‥シホ
(→)「ひきしお」1に同じ。↔上げ潮
さげ‐じきろう【提食籠】
手にさげて持ち歩けるようにした食籠。
さげ‐したじ【下げ下地】‥ヂ
女の髪の結い方。前髪をつくり、鬢びんをふくらませ、髱たぼを左右で二つに割り、髷まげを島田のようにし、髪の余りを笄こうがいに巻きつけたもの。笄を抜けば下げ髪になるのでいう。江戸幕府の奥女中や大名の妻などの髪型。
さげ‐しぶり【下げ渋り】
(取引用語)相場が下落しそうで下落しないこと。
さげ‐しまだ【下げ島田】
(→)「投げ島田」に同じ。
さげしみ【蔑み】
(→)「さげすみ」に同じ。
さげし・む【蔑む】
〔他四〕
(「下げし見る」の意とも、「下墨さげすむ」の転ともいう)
①見くだす。蔑視する。栂尾明恵上人伝記「いやしみ―・み給へば大罪弥いよいよ深し」
②批判する。とやかくいう。傾城禁短気「物日ものびが厭いやさに四の五のといふと、―・まるるが無念な」
さげ‐じゅう【提げ重】‥ヂユウ
①提重箱の略。
②江戸で、明和・安永(1764〜1781)ごろはやった私娼。提重箱をさげて物を売り歩くさまで徘徊し、売淫したもの。
さげ‐じゅうばこ【提重箱】‥ヂユウ‥
さげて携行するようにつくった組重箱。提げ重。
さけ‐ずし【酒鮨】
硬めの飯に土地特有の甘味の強い地酒をたっぷりかけ、山海の幸を取り合わせて鮨桶に数時間漬け込んだ料理。鹿児島の郷土料理。
さげすみ【蔑み・貶み】
さげすむこと。軽蔑。蔑視。さげしみ。
さげ‐すみ【下墨】
(サゲズミとも)
①柱などの傾きを見るために、大工が墨糸を垂直にたらして見定めること。下げ振り。垂準。談林俳諧
さげ‐がみ【下げ紙】
公文書などに貼り下げて意見・理由などを書きつけた紙。つけがみ。付箋ふせん。下札さげふだ。
さげ‐がみ【下げ髪・垂髪】
①女の髪型。髻もとどりをたばねて背後に垂れ下げたもの。江戸時代、貴婦人・宮女などが晴れの時などに結んだ。すべらかし。
②少女の髪型。髪を左右に分け、編んで垂らしたもの。おさげ。
③歌舞伎の鬘かつらの一つ。1の形にしたもの。
さけ‐がめ【酒甕】
⇒さかがめ
さけ‐きちがい【酒気違い・酒狂】‥キチガヒ
①酒に酔ってくるい乱れること。また、その人。酒乱しゅらん。
②甚だしく酒を好んで他事を顧みないこと。また、その人。
さげ‐ぎり【下げ斬り】
①上から斬りおろすこと。狂言、朝比奈「古郡が筒抜き・―」
②片手で宙にひっさげ、もう一方の手で斬ること。つるしぎり。提斬り。
さけく【幸く】
〔副〕
(上代東国方言)(→)「さきく」に同じ。万葉集20「もろもろは―と申す帰り来くまでに」
さけ‐くさ・い【酒臭い】
〔形〕[文]さけくさ・し(ク)
酒のにおいがする。
さけ‐くせ【酒癖】
(サケグセとも)酒に酔った時に出るくせ。さかくせ。「―が悪い」
さけ‐くらい【酒食らい】‥クラヒ
おおざけのみ。
さげ‐ごし【下げ輿】
轅ながえを腰のあたりに持ちあげて運ぶ輿。
さけ‐ごと【酒事】
⇒さかごと
さけ‐こわい【酒強飯】‥コハヒ
(サケコハイヒの約)酒造の際、水に漬けておいてから甑こしきで蒸した精白米。
さけ‐さかな【酒肴】
酒と酒のさかな。しゅこう。
さげ‐ざや【提げ鞘】
①(→)「みせざや」に同じ。
②僧の携える小刀・戒刀の類。
③茶人の携える小刀。
さけ‐じ【裂け痔】‥ヂ
(→)「きれ痔」に同じ。
さげ‐しお【下げ潮】‥シホ
(→)「ひきしお」1に同じ。↔上げ潮
さげ‐じきろう【提食籠】
手にさげて持ち歩けるようにした食籠。
さげ‐したじ【下げ下地】‥ヂ
女の髪の結い方。前髪をつくり、鬢びんをふくらませ、髱たぼを左右で二つに割り、髷まげを島田のようにし、髪の余りを笄こうがいに巻きつけたもの。笄を抜けば下げ髪になるのでいう。江戸幕府の奥女中や大名の妻などの髪型。
さげ‐しぶり【下げ渋り】
(取引用語)相場が下落しそうで下落しないこと。
さげ‐しまだ【下げ島田】
(→)「投げ島田」に同じ。
さげしみ【蔑み】
(→)「さげすみ」に同じ。
さげし・む【蔑む】
〔他四〕
(「下げし見る」の意とも、「下墨さげすむ」の転ともいう)
①見くだす。蔑視する。栂尾明恵上人伝記「いやしみ―・み給へば大罪弥いよいよ深し」
②批判する。とやかくいう。傾城禁短気「物日ものびが厭いやさに四の五のといふと、―・まるるが無念な」
さげ‐じゅう【提げ重】‥ヂユウ
①提重箱の略。
②江戸で、明和・安永(1764〜1781)ごろはやった私娼。提重箱をさげて物を売り歩くさまで徘徊し、売淫したもの。
さげ‐じゅうばこ【提重箱】‥ヂユウ‥
さげて携行するようにつくった組重箱。提げ重。
さけ‐ずし【酒鮨】
硬めの飯に土地特有の甘味の強い地酒をたっぷりかけ、山海の幸を取り合わせて鮨桶に数時間漬け込んだ料理。鹿児島の郷土料理。
さげすみ【蔑み・貶み】
さげすむこと。軽蔑。蔑視。さげしみ。
さげ‐すみ【下墨】
(サゲズミとも)
①柱などの傾きを見るために、大工が墨糸を垂直にたらして見定めること。下げ振り。垂準。談林俳諧 判「蚊柱の―なれや蜘くもの糸」→正直しょうじき3。
②物事をおしはかること。見積もること。甲陽軍鑑10「信玄公御―少しもちがはず候」
さげす・む【蔑む・貶む】
〔他五〕
みくだす。みさげる。軽蔑する。甲陽軍鑑10「信玄公の氏政を―・み給ふと」。「―・んだ目付き」
さげ‐す・む【下墨む】
〔他四〕
(「下墨さげすみ」を動詞化した語)
①下墨をする。測量する。七十一番職人尽歌合「をしなをす工たくみもいさや墨金すみかねに―・む月のかたぶきにけり」
②おしはかる。推察する。見積もる。醒睡笑「何にも余分をおきて―・むべきものなり」
さげ‐ぜに【下げ銭】
(緡ぜにさしや棒などに銭を通して腰にさげたからいう)日雇職人などが身につけているはした銭。誹風柳多留23「―でくどいたを下女憤り」
さげ‐そ【下苧】
漆喰しっくいなどの剥落を防ぐため、木摺きずり下地に打った釘の頭に結び下げて塗り込む麻あさ。さげお。
さげ‐だち【提太刀】
(→)「さげがたな」に同じ。
さげ‐だな【下げ棚】
つりさげた棚。
さげ‐タバコぼん【提煙草盆】
把手とってをつけ、さげて持ち運ぶようにつくったタバコ盆。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「肩荷の端に―折々休む道草の」
さげ‐づえ【下げ杖】‥ヅヱ
大田植おおたうえの総指揮者さげの携える竹杖。
さけ‐づくり【酒造り】
⇒さかづくり
さけ‐づけ【酒漬け】
酒に漬けること。また、その漬けたもの。
さげ‐づつ【提げ筒】
携帯できる鉄砲。小銃の旧称。
さげ‐づと【下げ髱】
女の髪の結い方。髱たぼを下げて結うもの。江戸時代、奥女中の使番つかいばん以下の間に行われた。
さけ‐どころ【酒所】
酒の生産地として有名な所。さかどころ。
さげ‐どまり【下げ止り】
物価・相場などが下がり続けて、これ以上下がらない水準になること。
さげ‐なわ【下げ縄】‥ナハ
①土蔵の木舞こまいに結び下げた縄。これを壁の中に塗り込んでその剥落を防ぐもの。
②(大工の隠語)上方で、うどん。江戸で、そば。
判「蚊柱の―なれや蜘くもの糸」→正直しょうじき3。
②物事をおしはかること。見積もること。甲陽軍鑑10「信玄公御―少しもちがはず候」
さげす・む【蔑む・貶む】
〔他五〕
みくだす。みさげる。軽蔑する。甲陽軍鑑10「信玄公の氏政を―・み給ふと」。「―・んだ目付き」
さげ‐す・む【下墨む】
〔他四〕
(「下墨さげすみ」を動詞化した語)
①下墨をする。測量する。七十一番職人尽歌合「をしなをす工たくみもいさや墨金すみかねに―・む月のかたぶきにけり」
②おしはかる。推察する。見積もる。醒睡笑「何にも余分をおきて―・むべきものなり」
さげ‐ぜに【下げ銭】
(緡ぜにさしや棒などに銭を通して腰にさげたからいう)日雇職人などが身につけているはした銭。誹風柳多留23「―でくどいたを下女憤り」
さげ‐そ【下苧】
漆喰しっくいなどの剥落を防ぐため、木摺きずり下地に打った釘の頭に結び下げて塗り込む麻あさ。さげお。
さげ‐だち【提太刀】
(→)「さげがたな」に同じ。
さげ‐だな【下げ棚】
つりさげた棚。
さげ‐タバコぼん【提煙草盆】
把手とってをつけ、さげて持ち運ぶようにつくったタバコ盆。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「肩荷の端に―折々休む道草の」
さげ‐づえ【下げ杖】‥ヅヱ
大田植おおたうえの総指揮者さげの携える竹杖。
さけ‐づくり【酒造り】
⇒さかづくり
さけ‐づけ【酒漬け】
酒に漬けること。また、その漬けたもの。
さげ‐づつ【提げ筒】
携帯できる鉄砲。小銃の旧称。
さげ‐づと【下げ髱】
女の髪の結い方。髱たぼを下げて結うもの。江戸時代、奥女中の使番つかいばん以下の間に行われた。
さけ‐どころ【酒所】
酒の生産地として有名な所。さかどころ。
さげ‐どまり【下げ止り】
物価・相場などが下がり続けて、これ以上下がらない水準になること。
さげ‐なわ【下げ縄】‥ナハ
①土蔵の木舞こまいに結び下げた縄。これを壁の中に塗り込んでその剥落を防ぐもの。
②(大工の隠語)上方で、うどん。江戸で、そば。
さけ‐きちがい【酒気違い・酒狂】‥キチガヒ🔗⭐🔉
さけ‐きちがい【酒気違い・酒狂】‥キチガヒ
①酒に酔ってくるい乱れること。また、その人。酒乱しゅらん。
②甚だしく酒を好んで他事を顧みないこと。また、その人。
さけ‐こわい【酒強飯】‥コハヒ🔗⭐🔉
さけ‐こわい【酒強飯】‥コハヒ
(サケコハイヒの約)酒造の際、水に漬けておいてから甑こしきで蒸した精白米。
さけ‐さかな【酒肴】🔗⭐🔉
さけ‐さかな【酒肴】
酒と酒のさかな。しゅこう。
○酒に呑まれるさけにのまれる🔗⭐🔉
○酒に呑まれるさけにのまれる
酒を飲んで本心を失う。
⇒さけ【酒】
○酒に別腸ありさけにべっちょうあり🔗⭐🔉
○酒に別腸ありさけにべっちょうあり
[通俗篇飲食]酒量の多少は体躯の大小にはかかわりないこと。また、酒飲みには酒専用の別の内臓がある意。
⇒さけ【酒】
○酒の酔い本性忘れずさけのえいほんしょうわすれず🔗⭐🔉
○酒の酔い本性忘れずさけのえいほんしょうわすれず
酒に酔ってもその人本来の性質はかわらない。生酔なまえい本性たがわず。
⇒さけ【酒】
さけ‐の‐おおすけ【鮭の大助】‥オホ‥
サケの王。東北地方で、陰暦11月15日に、この王が眷属けんぞくを引き連れ、川をのぼって来ると伝える。
さけ‐の‐け【酒の気】
酒に酔った気配。しゅき。宇津保物語俊蔭「皆人―ありて」
さけ‐の‐つかさ【酒司】
(→)「みきのつかさ」に同じ。
さけ‐のみ【酒飲み】
①酒を飲むこと。酒盛り。伊勢物語「夜ひと夜―しければ」
②酒を好んで多量に飲む人。
③酒を飲むのに使う器。歌舞伎、東海道四谷怪談「アイアイと―をいだし」
⇒酒飲み本性たがわず
さけ‐の‐み【酒の実】
酒のもろみ。〈日葡辞書〉
さけ‐の‐け【酒の気】🔗⭐🔉
さけ‐の‐け【酒の気】
酒に酔った気配。しゅき。宇津保物語俊蔭「皆人―ありて」
さけ‐の‐つかさ【酒司】🔗⭐🔉
さけ‐の‐つかさ【酒司】
(→)「みきのつかさ」に同じ。
さけ‐のみ【酒飲み】🔗⭐🔉
さけ‐のみ【酒飲み】
①酒を飲むこと。酒盛り。伊勢物語「夜ひと夜―しければ」
②酒を好んで多量に飲む人。
③酒を飲むのに使う器。歌舞伎、東海道四谷怪談「アイアイと―をいだし」
⇒酒飲み本性たがわず
さけ‐の‐み【酒の実】🔗⭐🔉
さけ‐の‐み【酒の実】
酒のもろみ。〈日葡辞書〉
○酒飲み本性たがわずさけのみほんしょうたがわず
どんな酒飲みでも本性を失うものではない。
⇒さけ‐のみ【酒飲み】
○酒は憂えの玉箒さけはうれえのたまばはき
酒は心配や憂いを除き去り、忘れさせてくれるものだ。酒は憂えを掃う玉箒。
⇒さけ【酒】
○酒は百薬の長さけはひゃくやくのちょう
[漢書食貨志下]適度な酒はどんな薬にもまさる効果があるという意。
⇒さけ【酒】
○酒飲み本性たがわずさけのみほんしょうたがわず🔗⭐🔉
○酒飲み本性たがわずさけのみほんしょうたがわず
どんな酒飲みでも本性を失うものではない。
⇒さけ‐のみ【酒飲み】
○酒は憂えの玉箒さけはうれえのたまばはき🔗⭐🔉
○酒は憂えの玉箒さけはうれえのたまばはき
酒は心配や憂いを除き去り、忘れさせてくれるものだ。酒は憂えを掃う玉箒。
⇒さけ【酒】
○酒は百薬の長さけはひゃくやくのちょう🔗⭐🔉
○酒は百薬の長さけはひゃくやくのちょう
[漢書食貨志下]適度な酒はどんな薬にもまさる効果があるという意。
⇒さけ【酒】
さげ‐はり【下げ針】
糸でつり下げた針。的まととして射あてるのに極めて小さなもの。古今著聞集9「季武は第一の手ききにて、―をもはづさず射ける者なりけり」
さけび【叫び】
さけぶこと。大声をあげること。また、その声。「核実験反対の―」
⇒さけび‐ごえ【叫び声】
⇒さけび‐じに【叫び死に】
⇒さけび‐なき【叫び泣き】
さけび‐ごえ【叫び声】‥ゴヱ
叫ぶ声。大きく激しい声。〈日葡辞書〉。「―を上げる」
⇒さけび【叫び】
さけび‐じに【叫び死に】
叫びながら死ぬこと。
⇒さけび【叫び】
さけ‐びたり【酒浸り】
まるで酒の中にひたっているように、始終酒を飲んでいること。また、その状態。さかびたり。
さけ‐びと【酒人・掌酒】
⇒さかびと
さけび‐なき【叫び泣き】
大声を立てて泣くこと。
⇒さけび【叫び】
さけ・ぶ【叫ぶ】
〔自五〕
①はげしく大声をあげる。万葉集5「立ち踊り足摩すり―・び」。「助けを求めて―・ぶ」
②比喩的に、世間に向かってある意見を強く主張する。「政界の浄化を―・ぶ」
さけ‐ぶぎょう【酒奉行】‥ギヤウ
①室町時代、将軍が大名の邸に赴いたとき、その家で当日の酒宴の事をつかさどらせた臨時の職。
②江戸幕府の職名。賄方まかないかたに属し、酒の出納をつかさどった。
→さかぶぎょう
さげ‐ふだ【下げ札】
①(→)下紙さげがみに同じ。
②年貢割付ねんぐわりつけの通称。
さけ‐ぶとり【酒太り・酒肥り】
飲酒のために身体が肥え太ること。
さけ‐ぶり【酒振り】
⇒さかぶり
さげ‐ふり【下げ振り】
①振子ふりこのこと。
②錘重すいじゅうの俗称。
③(→)下墨さげすみ1に同じ。
さげ‐まえがみ【下げ前髪】‥マヘ‥
少女などの前髪を額に垂れさげたもの。
さげ‐まく【下げ幕】
内部が見えないよう下げた幕。垂幕。「―があがる」
さけ‐ます‐ぎょぎょう【鮭鱒漁業】‥ゲフ
サケ・マス類を獲る漁業。北太平洋で母船式・独航船方式等で国際条約に基づいて操業していたが、1992年以降全面停止。鮭鱒けいそん漁業。
さけ‐め【裂け目】
①物のさけた所。われめ。
②馬の名所などころで、馬の口のさけたところをいう。くつわがかり。
⇒さけめ‐ふんか【裂け目噴火】
さけめ‐ふんか【裂け目噴火】‥クワ
(→)「割れ目噴火」に同じ。
⇒さけ‐め【裂け目】
○酒を煮るさけをにる🔗⭐🔉
○酒を煮るさけをにる
冬・春に作った酒を、5月に入って、殺菌するために火入れをすることをいう。〈[季]夏〉
⇒さけ【酒】
さ‐けん【左券】
(→)左契に同じ。
さ‐けん【左験】
[漢書楊惲伝]かたわらで見た者の証言。証拠。証左。また、証人。
さ‐けん【査験・査検】
とりしらべ。検査。
さ‐けん【差遣】
使者をさしつかわすこと。派遣。
さ‐げん【左舷】
船尾から船首に向かって左の方のふなべり。↔右舷
さ‐げん【瑣言】
ちょっとした言葉。取るに足りない言葉、または文章。
さこ【谷・迫】
(関西・九州地方などで)谷の行きづまり、または谷。せこ。
さ‐こ【左顧】
①左をふりむくこと。「―右眄うべん」
②[漢書宣元六王伝、淮陽憲王欽](昔、中国で、目上の者は右、目下の者は左にいたからいう)目下の者に目をかけること。転じて、目上の者の来訪。
さ‐ご【さ子】
鹿・猿の胎児。黒焼にして用いると、血の道の妙薬という。
サゴ【sago オランダ・沙穀】
(マレー語saguより)サゴヤシの樹幹の髄から採った白い澱粉。食用。セーゴ。〈本草綱目〉
ざ‐こ【雑魚・雑喉】
①種々入りまじった小魚。小さい魚。こざかな。梁塵秘抄「大津の西の浦へ―漉すきに」
②転じて、大物に対する小物。「捕まったのは―ばかり」
⇒雑魚の魚まじり
ざ‐ご【座五】
俳句で、第3句の5文字。
さ‐こう【左降】‥カウ
(→)左遷させんに同じ。
さ‐こう【作興】
⇒さっこう
さ‐こう【査公】
(明治期に用いた語)巡査の俗称。おまわり。親しみ、あるいは軽蔑の意をこめていう。斎藤緑雨、小説詳註「其頃は警察の事務整はず密行しのびの―もなければ」
さ‐こう【砂鉱】‥クワウ
河床・湖底・海底に砂礫されき状をなして沈積している鉱床。砂鉄・砂金・砂錫の類。漂砂鉱床。
さ‐こう【鎖肛】‥カウ
肛門または直腸の内腔が閉鎖しているもの。先天的な奇形。
さ‐こう【鎖港】‥カウ
①港をとじること。
②外国船の入港・交易を禁ずること。
ざ‐こう【座功】
連歌などの一座に参加して、経験を積み重ねること。連理秘抄「堪能に練習して―を積むより外の稽古はあるべからず」
ざ‐こう【座高・坐高】‥カウ
椅子に腰をかけ、両脚を平行に揃え、大腿が水平に、下腿および上体が垂直になるようにしたときの、座面から頭頂までの高さ。
ざ‐こう【麝香】‥カウ
⇒じゃこう。宇津保物語初秋「―、ぢん、丁子」
ざ‐ごうしゃく【座講釈】‥ガウ‥
講釈師が宴会などに招かれてする軍談・講釈。
さこ‐うべん【左顧右眄】
(→)右顧左眄うこさべんに同じ。
さこう‐ほう【砂耕法】‥カウハフ
きれいな砂に培養液を加えて植物を培養する方法。植物の栄養生理研究に利用し、また施設栽培に用いる。砂栽培。
さ‐こく【鎖国】
(1801年志筑忠雄がケンペル「日本誌」を抄訳し、「鎖国論」と題したのに始まる語)国が外国との通商・交易を禁止あるいは極端に制限すること。江戸幕府は、キリスト教禁止を名目として、中国・オランダ以外の外国人の渡来・貿易と日本人の海外渡航とを禁じた。↔開国。→海禁。
⇒さこく‐れい【鎖国令】
さ‐ごく【左獄】
平安時代、京都左京に置かれた獄舎。東獄。↔右獄
ざ‐こく【雑穀】
⇒ざっこく。〈日葡辞書〉
さ‐こく‐し‐かん【左国史漢】
春秋左氏伝と国語と史記と漢書。中国史書の代表的なもので、日本では平安朝以来、文章家の必読書とされた。
さこく‐れい【鎖国令】
江戸幕府が鎖国体制をつくるために出した一連の法令の通称。特に1635年(寛永12)の海外渡航禁止令と、39年のポルトガル船来航禁止令をいう。
→文献資料[鎖国令]
⇒さ‐こく【鎖国】
さござい
(サアゴザイの約)江戸中期、明和・安永(1764〜1781)の頃、江戸で正月に街頭で宝引ほうびきをして子供などを相手にかせいだ商売。→辻宝引
さごし【青箭魚】
サワラの小さいもの。白身で、疝癪せんしゃくによいとされた。〈[季]春〉。西鶴織留6「食物も朝は白粥に飛魚・―のほかは毎日改め」
さ‐こそ【然こそ】
①まったくそのように(は)。あんなに。源氏物語夕顔「―強がり給へど、若き御心にて、いふかひなくなりぬるを」
②(推量の表現を伴って)さだめし。さぞ。どんなにか。徒然草「向かひゐたりけむありさま、―異様ことようなりけめ」
③いくら(…でも)。平家物語灌頂「―世を捨つる御身といひながら」
⇒さこそ‐いえ【然こそ言へ】
さこそ‐いえ【然こそ言へ】‥イヘ
そうはいうものの。伊勢物語「女をほかへ追ひやらむとす。―まだ追ひやらず」
⇒さ‐こそ【然こそ】
さこ‐だ【迫田】
山の谷間にある田。
さ‐こつ【鎖骨】
胸部上方の体表近くに水平にある棒状の骨。内側は胸骨と、外側は肩甲骨の肩峰と連結してそれぞれ関節をつくる。→骨格(図)。
⇒さこつか‐どうみゃく【鎖骨下動脈】
ざ‐こつ【坐骨・座骨】
寛骨かんこつの後下部を占め、閉鎖孔を後方と下方から囲む骨。腸骨・恥骨と癒合して寛骨をつくる。→骨格(図)。
⇒ざこつ‐しんけい【坐骨神経】
⇒ざこつ‐しんけいつう【坐骨神経痛】
ざ‐こつ【挫骨】
骨をくじくこと。また、くじいた骨。
さこつか‐どうみゃく【鎖骨下動脈】
上肢に血液を送る動脈の本幹。右は腕頭動脈、左は大動脈弓から起こり、鎖骨の裏側を通り抜け、腋窩動脈につながる。脳に向かう椎骨動脈、前胸壁に向かう内胸動脈などの枝を出す。
⇒さ‐こつ【鎖骨】
ざこつ‐しんけい【坐骨神経】
下肢の運動・知覚をつかさどる、人体内で最長の神経。仙骨神経叢から出て大坐骨孔を通り臀部でんぶから大腿後面をほぼ垂直に下行、下肢の筋・皮膚に分布。膝窩のやや上方で総腓骨神経と脛骨神経とに分かれる。→神経系(図)。
⇒ざ‐こつ【坐骨・座骨】
ざこつ‐しんけいつう【坐骨神経痛】
坐骨神経の経路に沿って感じる疼痛。臀部、大腿後面から下腿後面、さらに足部にかけて圧痛点がある。腰椎下部の椎間板ヘルニアなど脊椎の障害によるものが多い。
⇒ざ‐こつ【坐骨・座骨】
ざこ‐ね【雑魚寝・雑居寝】
①雑魚のように入りまじって寝ること。
②年越しの夜その他一定の日に、神社などに男女が集合して、枕席を共にした民間習俗。山城の大原、大和十津川その他に伝えがある。
③上方の花街で、客と芸娼妓などが打ちまじって、一室に寝るのをいう。歌舞伎、五大力恋緘「―するは芸子の習ひ」
さ‐このえ【左近衛】‥ヱ
⇒さこんえ
ささ【酒】🔗⭐🔉
ささ【酒】
(「さけ」の「さ」を重ねた語。一説に、中国で酒のことを竹葉というのに基づくとする)酒をいう女房詞。好色一代男1「少し―などこれよりたべまして」
ささ‐きげん【酒機嫌】🔗⭐🔉
ささ‐きげん【酒機嫌】
酒に酔った時の機嫌。さかきげん。
ささ‐ごと【酒事】🔗⭐🔉
ささ‐ごと【酒事】
さかもり。酒宴。さかごと。
ささ‐のみ【酒飲み】🔗⭐🔉
ささ‐のみ【酒飲み】
⇒さけのみ。狂言、貰聟「わらはがつれやひ、何ともかともならぬ―でござるが」
ささ‐の‐み【酒の実】🔗⭐🔉
ささ‐の‐み【酒の実】
(女房詞)酒粕。〈日葡辞書〉
しゅ【酒】🔗⭐🔉
しゅ【酒】
さけ。さけをのむこと。平家物語8「若宮の拝殿にして、泰定やすさだに―をすすめらる」
しゅ‐いん【酒淫・酒婬】🔗⭐🔉
しゅ‐いん【酒淫・酒婬】
酒と色事。酒色。
しゅ‐えん【酒宴】🔗⭐🔉
しゅ‐えん【酒宴】
さかもり。うたげ。「―を催す」
⇒しゅえん‐ぼん【酒宴盆】
しゅえん‐ぼん【酒宴盆】🔗⭐🔉
しゅえん‐ぼん【酒宴盆】
足のない円形の広蓋ひろぶた。
⇒しゅ‐えん【酒宴】
しゅ‐か【酒家】🔗⭐🔉
しゅ‐か【酒家】
①さかや。酒店。酒舗。浮世床初「酒をのむものを酒客、酒屋を―」
②酒のみ。酒客しゅかく。上戸じょうご。
しゅ‐かい【酒戒】🔗⭐🔉
しゅ‐かい【酒戒】
飲酒のいましめ。
しゅ‐かい【酒海】🔗⭐🔉
しゅ‐かい【酒海】
①酒を入れるのに用いた容器。狂言、鎧「祝ひの家の塵取りて一家一族内の人、大筒―を据ゑ並べ」
②本願寺の元旦の行事で、法主ほっす自ら宗祖親鸞の像の前に酒肴を供えること。
しゅ‐かく【酒客】🔗⭐🔉
しゅ‐かく【酒客】
酒のみ。酒好き。上戸じょうご。浮世床初「酒をのむものを―、酒屋を酒家」
しゅ‐き【酒気】🔗⭐🔉
しゅ‐き【酒気】
①酒のかおり。さかけ。
②酒に酔った気味。「―を帯びる」
⇒しゅきおび‐うんてん【酒気帯び運転】
しゅ‐き【酒旗】🔗⭐🔉
しゅ‐き【酒旗】
酒屋の看板としてたてた旗。酒旆しゅはい。さかばた。
しゅ‐き【酒器】🔗⭐🔉
しゅ‐き【酒器】
酒を飲み、また、酒を酌むのに用いる器。ちょうし・さかずきの類。
しゅきおび‐うんてん【酒気帯び運転】🔗⭐🔉
しゅきおび‐うんてん【酒気帯び運転】
呼気中のアルコール濃度が一定量を超えた状態で車両を運転すること。道路交通法で禁止されている。
⇒しゅ‐き【酒気】
しゅ‐きょう【酒狂】‥キヤウ🔗⭐🔉
しゅ‐きょう【酒狂】‥キヤウ
酒に酔って常軌を失うこと。また、その性癖。酒乱。さかぐるい。
しゅ‐きょう【酒興】🔗⭐🔉
しゅ‐きょう【酒興】
酒に酔い、興に乗ること。酒宴の座興。尾崎紅葉、不言不語「―の上にもあらねば、いつもの洒落にもあらず」。「―を添える」
しゅ‐こ【酒戸】🔗⭐🔉
しゅ‐こ【酒戸】
①律令制で、造酒司みきのつかさに属する品部しなべ。さかへ。
②さかや。さかみせ。
③飲酒の量。
しゅ‐こ【酒庫】🔗⭐🔉
しゅ‐こ【酒庫】
酒を入れておくくら。さかぐら。
しゅ‐こう【酒肴】‥カウ🔗⭐🔉
しゅ‐こう【酒肴】‥カウ
酒と酒のさかな。
⇒しゅこう‐りょう【酒肴料】
しゅ‐ごう【酒豪】‥ガウ🔗⭐🔉
しゅ‐ごう【酒豪】‥ガウ
酒に強く、飲酒の量の多い人。大酒飲み。
しゅこう‐りょう【酒肴料】‥カウレウ🔗⭐🔉
しゅこう‐りょう【酒肴料】‥カウレウ
酒肴のための金銭。人に招待されたりした時などの包み金。
⇒しゅ‐こう【酒肴】
しゅこし【酒胡子】🔗⭐🔉
しゅこし【酒胡子】
①雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの曲。舞は廃絶。すこし。酒公子。酔公子。
②「起上り小法師」の別称。〈倭名類聚鈔4〉
しゅ‐し【酒資】🔗⭐🔉
しゅ‐し【酒資】
さかだい。さかて。酒銭。
しゅ‐しつ【酒失】🔗⭐🔉
しゅ‐しつ【酒失】
酒のうえでの過失。
みき‐の‐つかさ【造酒司・酒司】🔗⭐🔉
みき‐の‐つかさ【造酒司・酒司】
①律令制で、宮内省に属し、皇室の用に供する酒・醴あまざけ・酢などの醸造をつかさどった役所。さけのつかさ。
②⇒しゅし(酒司)
[漢]酒🔗⭐🔉
酒 字形
 筆順
筆順
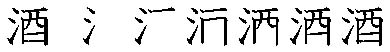 〔水(氵・氺)部7画/10画/教育/2882・3C72〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕さけ・さか=
[意味]
さけ。アルコール飲料。さかもり。「酒量・酒精・飲酒・酒色・酒豪・果実酒」
[解字]
もと、酉部3画。会意。「水」+「酉」(=さけつぼ)。
[下ツキ
淫酒・飲酒・火酒・禁酒・葷酒・豪酒・御酒・卮酒・旨酒・新酒・清酒・節酒・粗酒・濁酒・置酒・斗酒・美酒・銘酒・薬酒・洋酒・老酒ラオチュー・乱酒・緑酒・冷酒・神酒みき
〔水(氵・氺)部7画/10画/教育/2882・3C72〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕さけ・さか=
[意味]
さけ。アルコール飲料。さかもり。「酒量・酒精・飲酒・酒色・酒豪・果実酒」
[解字]
もと、酉部3画。会意。「水」+「酉」(=さけつぼ)。
[下ツキ
淫酒・飲酒・火酒・禁酒・葷酒・豪酒・御酒・卮酒・旨酒・新酒・清酒・節酒・粗酒・濁酒・置酒・斗酒・美酒・銘酒・薬酒・洋酒・老酒ラオチュー・乱酒・緑酒・冷酒・神酒みき
 筆順
筆順
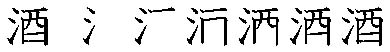 〔水(氵・氺)部7画/10画/教育/2882・3C72〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕さけ・さか=
[意味]
さけ。アルコール飲料。さかもり。「酒量・酒精・飲酒・酒色・酒豪・果実酒」
[解字]
もと、酉部3画。会意。「水」+「酉」(=さけつぼ)。
[下ツキ
淫酒・飲酒・火酒・禁酒・葷酒・豪酒・御酒・卮酒・旨酒・新酒・清酒・節酒・粗酒・濁酒・置酒・斗酒・美酒・銘酒・薬酒・洋酒・老酒ラオチュー・乱酒・緑酒・冷酒・神酒みき
〔水(氵・氺)部7画/10画/教育/2882・3C72〕
〔音〕シュ(呉)
〔訓〕さけ・さか=
[意味]
さけ。アルコール飲料。さかもり。「酒量・酒精・飲酒・酒色・酒豪・果実酒」
[解字]
もと、酉部3画。会意。「水」+「酉」(=さけつぼ)。
[下ツキ
淫酒・飲酒・火酒・禁酒・葷酒・豪酒・御酒・卮酒・旨酒・新酒・清酒・節酒・粗酒・濁酒・置酒・斗酒・美酒・銘酒・薬酒・洋酒・老酒ラオチュー・乱酒・緑酒・冷酒・神酒みき
広辞苑に「酒」で始まるの検索結果 1-80。もっと読み込む