複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (41)
どく【毒】🔗⭐🔉
どく【毒】
①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」
②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」
③わざわい。
④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」
⇒毒にも薬にもならない
⇒毒を食わば皿まで
⇒毒を以て毒を制す
どく‐あく【毒悪】🔗⭐🔉
どく‐あく【毒悪】
非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」
どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】🔗⭐🔉
どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】
イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。
どく‐いみ【毒忌】🔗⭐🔉
どく‐いみ【毒忌】
主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。
どく‐うつぎ【毒空木】🔗⭐🔉
どく‐うつぎ【毒空木】
ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。
どくうつぎ


どく‐え【毒荏】🔗⭐🔉
どく‐え【毒荏】
〔植〕アブラギリの異称。
どく‐えき【毒液】🔗⭐🔉
どく‐えき【毒液】
毒をふくんだ液体。
どく‐えん【毒焔】🔗⭐🔉
どく‐えん【毒焔】
①有毒ガスを発散するほのお。
②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。
どく‐が【毒牙】🔗⭐🔉
どく‐が【毒牙】
①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。
②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」
どく‐が【毒蛾】🔗⭐🔉
どく‐が【毒蛾】
①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。
②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。
どく‐がい【毒害】🔗⭐🔉
どく‐がい【毒害】
①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。
②甚だしくそこなうこと。残害。
どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ🔗⭐🔉
どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ
①毒を飲ませること。
②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」
どく‐ガス【毒ガス】🔗⭐🔉
どく‐ガス【毒ガス】
毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。
⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】
どくガス‐だん【毒ガス弾】🔗⭐🔉
どくガス‐だん【毒ガス弾】
(→)ガス弾に同じ。
⇒どく‐ガス【毒ガス】
どく‐ぎょ【毒魚】🔗⭐🔉
どく‐ぎょ【毒魚】
毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」
どく‐ぐち【毒口】🔗⭐🔉
どく‐ぐち【毒口】
毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。
どく‐げん【毒言】🔗⭐🔉
どく‐げん【毒言】
他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。
どく‐ささこ【毒笹子】🔗⭐🔉
どく‐ささこ【毒笹子】
担子菌類の毒きのこ。秋に竹林内に多数群生する。傘の表面は茶褐色で、中央部がくぼみ、全体が漏斗ろうと形。茎は中空、縦に裂けやすい。食べると、数日後に中毒症状を引きおこす。ヤブシメジ。
どく‐さつ【毒殺】🔗⭐🔉
どく‐さつ【毒殺】
毒薬で人を殺すこと。毒害。「―犯人」
どく‐し【毒死】🔗⭐🔉
どく‐し【毒死】
毒薬によって死ぬこと。
どく‐しつ【毒質】🔗⭐🔉
どく‐しつ【毒質】
有毒な性質。毒の成分。
どく‐じゃ【毒蛇】🔗⭐🔉
どく‐じゃ【毒蛇】
毒腺を持つヘビの総称。毒牙により、咬んだ動物に毒液を注入する。毒腺の発達に伴いマムシ・ハブなどは頭部が三角形またはスプーン形をしているが、コブラ類では他のヘビと同じ。体は太く尾部は短いものが多い。どくへび。
⇒どくじゃ‐の‐くち【毒蛇の口】
どく・する【毒する】🔗⭐🔉
どく・する【毒する】
〔他サ変〕[文]毒す(サ変)
そこなう。害する。性格・気風などに、悪い影響を与える。「世を―・する」
どく‐ぜり【毒芹】🔗⭐🔉
どく‐ぜり【毒芹】
セリ科の多年草。水辺・池沢に自生。高さ1メートル。地下茎は筍状を呈する。夏から秋に白色の小花を密生。全草、殊に地下茎に猛毒がある。この地下茎を万年竹・延命竹・長命竹などと称し、盆栽として観賞。オオゼリ。漢名、野芹菜花。
どくぜり


どく‐ち【毒血】🔗⭐🔉
どく‐ち【毒血】
病毒を含んだ血。悪血。
どくどく‐し・い【毒毒しい】🔗⭐🔉
どくどく‐し・い【毒毒しい】
〔形〕[文]どくどく・し(シク)
①毒を含んでいるようである。
②悪意を含んでいるさまである。にくにくしい。「―・い言い方」
③淡泊でない。しつこい。くどい。「―・い化粧」
○徳とするとくとする
ありがたいものとして、感謝する。「好意を―」
⇒とく【徳】
○毒にも薬にもならないどくにもくすりにもならない🔗⭐🔉
○毒にも薬にもならないどくにもくすりにもならない
害もなく益もない。さわりにもならないが、ためにもならない。
⇒どく【毒】
とく‐にん【特任】
特にその官職に任ずること。また、その任務。
とく‐にん【特認】
特別に承認すること。
とく‐にん【徳人】
①有徳な人。
②富んでいる人。金持。今昔物語集26「財に飽き満ちて、あさましき―にて」
どく‐にん【独任】
一人の人にもっぱらまかせること。一人の人に職務を行わせること。
⇒どくにん‐せい【独任制】
どく‐にんじん【毒人参】
セリ科の越年草。ヨーロッパの原産。地下に蕪かぶ状の根茎を有し、茎は管状で表面に紫色の斑点がある。葉は羽状複葉。夏、茎頂に白色の小花を開く。全草に猛毒を含み、ギリシア時代から毒薬として用いた。ソクラテスが飲んで死んだという。ヘムロック。コニウム。
どくにん‐せい【独任制】
合議制に対し、政府または公共機関の組織上、一人の者を以て構成されるもの。日本の行政官庁1は独任制であるのが通例。単独制。
⇒どく‐にん【独任】
とく‐のう【篤農】
熱心で研究的な農業者。篤農家。
とく‐の‐しま【徳之島】
鹿児島県奄美あまみ諸島の島。面積248平方キロメートル。海岸部は隆起珊瑚礁が発達。アマミノクロウサギの生息地。サトウキビを産する。
とく‐は【特派】
特別に派遣すること。
⇒とくは‐いん【特派員】
どく‐は【読破】
(難解な、または大部の書物や書類を)すべて読み通すこと。「万巻の書を―する」
とく‐はい【特配】
①特別の配当。
②特別の配給。「援助物資を―する」
とく‐ばい【特売】
①競争入札によらず随意契約により特定の人に売り渡すこと。
②特別に安く売ること。「夏物を―する」「―品」
とくは‐いん【特派員】‥ヰン
①特にその地に任命派遣された人。
②新聞社・雑誌社・放送局などから外国に特派されて報道の任に当たる記者。
⇒とく‐は【特派】
どく‐はく【独白】
①劇で、ある役が心中に思っていることなどを観客に知らせるため、相手なしで語ること。また、そのせりふ。モノローグ。「ハムレットが―する」
②ひとりごと。
とく‐はつ【禿髪】
毛髪がぬけて頭がはげること。はげ。
とく‐はつ【特発】
①臨時に特別に出すこと。「―電車」
②病気が、伝染などによらず、原因不明で突然に起こること。
⇒とくはつせい‐しっかん【特発性疾患】
⇒とくはつせい‐しんきんしょう【特発性心筋症】
とくはつせい‐しっかん【特発性疾患】‥クワン
外界からの作用によらず、また原因も明らかでなく起こる病気。特発性気胸・特発性脱疽だっそ(バージャー病)など。
⇒とく‐はつ【特発】
とくはつせい‐しんきんしょう【特発性心筋症】‥シヤウ
「心筋症」参照。
⇒とく‐はつ【特発】
どく‐はみ【毒蝮】
マムシの別称。〈日葡辞書〉
とく‐ばん【特番】
テレビ・ラジオの放送などで、特別番組のこと。
とくび‐こん【犢鼻褌】
ふんどし。たふさぎ。〈下学集〉
とく‐ひつ【禿筆】
①さきのすり切れた筆。ちびふで。
②転じて、自分の文章の謙譲語。「―を呵す」
とく‐ひつ【特筆】
特にとりたてて記すこと。殊に目立つように書くこと。多く、強調してほめる場合にいう。「―に値する」「―すべき長所」
⇒とくひつ‐たいしょ【特筆大書】
どく‐ひつ【毒筆】
人を中傷する目的で書くこと。悪辣あくらつな書きぶり。また、その文章。
とくひつ‐たいしょ【特筆大書】
ことさらに目立つように書きしるすこと。
⇒とく‐ひつ【特筆】
とく‐ひょう【得票】‥ヘウ
選挙で投票を獲得すること。また、獲得した票数。「各地で―する」「―率」
どく‐ふ【毒婦】
腹黒く、悪事を働く女。奸婦。広津柳浪、河内屋「―め、早晩いまに面の皮を引剥ひんむかれるな」
どく‐ふ【独夫】
①独身の男。
②[書経泰誓下]悪政を行い国民に見放された君主。
どく‐ふ【読譜】
楽譜・棋譜などを読みとること。
とく‐ふう【徳風】
[論語顔淵「君子の徳は風也。小人の徳は草也。草これに風を上くわうれば、必ず偃ふす」]徳が人を感化するさまを草が風になびき伏すさまにたとえていう語。道徳の教化。仁徳の感化。
どく‐ふく【独服】
茶などを一人で点たてて飲むこと。
どく‐ふく【独幅】
対ついになっていない、ただ一幅の掛物。
とく‐ぶつ【得仏】
(→)成仏じょうぶつに同じ。
どく‐ぶつ【毒物】
毒性のある物質。狭義には、毒物及び劇物取締法に毒物として掲げられるもので、医薬品・医薬部外品以外のものをいう。
⇒どくぶつ‐がく【毒物学】
どくぶつ‐がく【毒物学】
毒物の作用、中毒の予防と治療の方法を研究する学問。
⇒どく‐ぶつ【毒物】
どくふつ‐せんそう【独仏戦争】‥サウ
(→)普仏戦争の別称。
とく‐ぶん【得分・徳分】
①分けまえ。とりだか。義経記5「五つをば某が―にせん」
②得た分。もうけ。利分。利益。義経記4「安房・上総、畠多く田は少なし、―少なくて不足なり」
③荘園の領主・荘官・地頭などがその権利に応じて収得する収益。
どく‐ぶん【独文】
①独逸ドイツ語で書いた文章。
②独逸文学の略。「―研究室」
とく‐べつ【特別】
普通一般とちがうこと。特に区別されるもの。格別。「―な感情」「―に許可する」「―変わったこともない」
⇒とくべつ‐あつかい【特別扱い】
⇒とくべつ‐いいんかい【特別委員会】
⇒とくべつ‐いにん【特別委任】
⇒とくべつ‐おうせんこぎって【特別横線小切手】
⇒とくべつ‐かいけい【特別会計】
⇒とくべつ‐かつどう【特別活動】
⇒とくべつ‐かんちょう【特別官庁】
⇒とくべつ‐きてい【特別規定】
⇒とくべつ‐きゅうこう【特別急行】
⇒とくべつ‐きょうしつ【特別教室】
⇒とくべつ‐く【特別区】
⇒とくべつ‐けいほう【特別刑法】
⇒とくべつ‐けつぎ【特別決議】
⇒とくべつ‐げんけい【特別減刑】
⇒とくべつ‐こうあつ【特別高圧】
⇒とくべつ‐こうげきたい【特別攻撃隊】
⇒とくべつ‐こうこく【特別抗告】
⇒とくべつ‐こうとうけいさつ【特別高等警察】
⇒とくべつ‐こっかい【特別国会】
⇒とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】
⇒とくべつ‐さいばんせき【特別裁判籍】
⇒とくべつ‐しえん‐がっきゅう【特別支援学級】
⇒とくべつ‐しえん‐がっこう【特別支援学校】
⇒とくべつ‐しえん‐きょういく【特別支援教育】
⇒とくべつ‐しょうきゃく【特別償却】
⇒とくべつ‐じょうこく【特別上告】
⇒とくべつ‐しょく【特別職】
⇒とくべつ‐せいさん【特別清算】
⇒とくべつ‐たんぽ【特別担保】
⇒とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい【特別地方消費税】
⇒とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】
⇒とくべつ‐にんよう【特別任用】
⇒とくべつ‐はいとう【特別配当】
⇒とくべつ‐ふきん【特別賦金】
⇒とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
⇒とくべつ‐ほう【特別法】
⇒とくべつ‐まるゆう【特別マル優】
⇒とくべつ‐もくてき‐がいしゃ【特別目的会社】
⇒とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】
⇒とくべつ‐ようしせいど【特別養子制度】
⇒とくべつ‐よぼう【特別予防】
とくべつ‐あつかい【特別扱い】‥アツカヒ
他のものとは区別して大事に扱うこと。「社長だからといって―しない」
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐いいんかい【特別委員会】‥ヰヰンクワイ
国会の常任委員会以外に、特別の案件のために、そのつど設置される委員会。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐いにん【特別委任】‥ヰ‥
〔法〕特別の事項について訴訟代理権を与えること。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐おうせんこぎって【特別横線小切手】‥ワウ‥
(→)特定線引せんびき小切手に同じ。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐かいけい【特別会計】‥クワイ‥
国および地方公共団体において、特別の事情・必要に基づいて、一般会計から切り離して、その収入・支出を経理する会計。国には、道路整備・外国為替・食糧管理・厚生保険などの各特別会計がある。↔一般会計。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐かつどう【特別活動】‥クワツ‥
小・中・高等学校で、各教科、道徳と並ぶ教育課程の一領域。教師の指導のもとに児童・生徒の自発的・自治的な活動を主とする領域で、児童会・生徒会・クラブ活動・学級会活動・学校行事など。特別教育活動。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐かんちょう【特別官庁】‥クワンチヤウ
普通官庁または一般官庁に対し、その権限が特殊の事務に限定された官庁。国税局・経済産業局の類。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐きてい【特別規定】
ある特定の事項にのみ適用する規定。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐きゅうこう【特別急行】‥キフカウ
普通の急行よりも速く、停車数の少ない列車またはバス。特急。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐きょうしつ【特別教室】‥ケウ‥
理科・図画工作・音楽などのため特別の設備をもつ教室。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐く【特別区】
東京都の区。特別地方公共団体の一つで、原則として、市に準じた取扱いをうける。区議会を置く。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐けいほう【特別刑法】‥ハフ
刑法典の規定外の犯罪に対して適用する刑罰法規。軽犯罪法・「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の類。↔普通刑法。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐けつぎ【特別決議】
株主総会において定款変更・減資など特に重要な議案の決議方式。出席議決権株の3分の2以上の賛成を要する。↔普通決議。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐げんけい【特別減刑】
恩赦の一種。個々の処分により刑の言い渡しを受けた特定人の刑またはその執行を減軽すること。↔一般減刑。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐こうあつ【特別高圧】‥カウ‥
電線相互間または電線と大地間における電位の差が7000ボルトを超過するような送配電線の電圧。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐こうげきたい【特別攻撃隊】
(→)特攻隊とっこうたいに同じ。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐こうこく【特別抗告】‥カウ‥
〔法〕不服申立てのできない決定または命令に対して、違憲を理由に最高裁判所に対して行う抗告。刑事事件では判例違反の場合にも認められる。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐こうとうけいさつ【特別高等警察】‥カウ‥
旧制で、思想犯罪に対処するための高等警察。内務省直轄で、社会運動などの弾圧に当たった。第二次大戦後廃止。特高。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐こっかい【特別国会】‥コククワイ
衆議院の解散により行われた総選挙の日から30日以内に召集される国会。特別会。特別議会。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】
特殊の人・事件について裁判権を行使する裁判所。明治憲法の下で認められた軍法会議・行政裁判所のようなものがこれに当たるが、日本国憲法はこれを認めない。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐さいばんせき【特別裁判籍】
普通裁判籍に対し、特別の場合に規定された裁判籍。財産権上の訴訟は、その義務履行地の裁判所に提起することができる類。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐しえん‐がっきゅう【特別支援学級】‥ヱンガクキフ
小・中・高等学校において特別支援教育を行うために設けられる学級。2006年、特殊学級から改称。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐しえん‐がっこう【特別支援学校】‥ヱンガクカウ
特別支援教育を行う学校。盲学校・聾学校・養護学校の総称。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐しえん‐きょういく【特別支援教育】‥ヱンケウ‥
種々の障害のある児童・生徒に、その種類・程度に応じた支援を行う教育。2006年学校教育法等の改正により特殊教育から改称。障害児教育。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐しょうきゃく【特別償却】‥シヤウ‥
租税特別措置の一つ。普通償却(定額法や定率法など)に対して、早期に多額の減価償却費を計上する。損金計上が前倒しされる分だけ課税延期の効果をもつ。加速償却。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐じょうこく【特別上告】‥ジヤウ‥
民事訴訟において、高等裁判所が上告審としてした判決に対し、憲法違背を理由になされる上告。本来の上告ではない。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐しょく【特別職】
国家公務員の職のうち、国家公務員法が指定し同法の適用外とされる一定の職。内閣総理大臣・国務大臣・大臣秘書官・副大臣・大臣政務官・人事官・会計検査官・大使・公使・裁判官などがこれに属する。地方公務員にも特別職がある。↔一般職。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐せいさん【特別清算】
解散後の株式会社に債務超過の疑いがあるときなどに、裁判所の関与のもとに債権者の利益を保護しながら行われる特別の清算手続。破産手続よりも簡易で迅速。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐たんぽ【特別担保】
抵当権や質権など特定の財産を目的物とする担保権。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい【特別地方消費税】‥ハウセウ‥
料理飲食店・旅館等の利用者を対象とし、利用料金を課税標準とする道府県税。2000年廃止。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】‥シウ
地方税徴収方法の一つ。納税者から直接徴収せず、徴収便宜をもつ者を指定して税を徴収させること。給与所得者の住民税はこれによる。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐にんよう【特別任用】
旧制で、特別の官職について経験ある者を一定の資格または条件によらないで任用したこと。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐はいとう【特別配当】‥タウ
①営利会社が普通配当以外に、剰余の利益金を一定の割合で株主に配当すること。
②保険会社が契約に従って、保険金が一定時に一定額に達した時に行う割戻し。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ふきん【特別賦金】
(→)受益者負担金に同じ。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
弁護士でない者で、特に裁判所の許可を得て、弁護人に選任された者。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ほう【特別法】‥ハフ
特定の地域・人・事項に適用される法。一般法との関係では、特別法は一般法に優先するという原則がある。↔一般法。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐まるゆう【特別マル優】‥イウ
少額公債特別非課税制度。公債購入による利子所得に対し、マル優とは別枠で、元本の一定額まで非課税扱いとするもの。障害者などの利子所得に適用。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐もくてき‐がいしゃ【特別目的会社】‥グワイ‥
(special purpose company)限定された目的のために設立された会社。特定の資産を担保に有価証券を発行して資金調達する会社など。SPC
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】‥ヤウ‥ラウ‥
老人福祉施設の一つ。認知症などの心身の障害のため常時介護を必要とし、また在宅介護が困難な65歳以上の老人が入所する。介護保険法上の名称は介護老人福祉施設。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ようしせいど【特別養子制度】‥ヤウ‥
〔法〕1987年の民法改正で新設された制度で、家庭裁判所の審判によってのみ成立する養子縁組。養親は25歳以上の夫婦、養子は6歳未満を原則とし、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する一方、養子は戸籍上も実子に準じた扱いを受ける。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐よぼう【特別予防】‥バウ
犯罪者に刑罰を科す目的は、その犯罪者が再び犯罪に陥るのを予防することにあるとする考え方。教育刑はその例。↔一般予防
⇒とく‐べつ【特別】
どく‐べにたけ【毒紅茸】
担子菌類のきのこ。高さ約5センチメートル。傘は直径約5センチメートル、表面平滑で紅色または淡紅色。柄は白色。全体はもろく辛味があるが毒性はない。山林・芝生に発生。ベニタケ。
どく‐へび【毒蛇】
⇒どくじゃ
とく‐ほう【特報】
特別の報道。特別のニュース。「―を流す」
とく‐ほう【得法】‥ホフ
禅などの、奥義を会得すること。風姿花伝「天下に許され、能に―したりとも」
とく‐ぼう【徳望】‥バウ
徳が高く、人望のあること。「―が高い」「―家」
どく‐ぼう【独房】‥バウ
一人だけを入れる監房。独居監房。
とく‐ほん【読本】
①絵本に対して、読み物の本。
②もと学校で、国語科の講読教授に用いた教科書。国語教科書。正岡子規、筆まかせ「―の挿画の如きは心底に印して一生忘るゝ能はざる者なれば」
③転じて、広く教科書、あるいは入門書など。「文章―」「人生―」
ドグマ【dogma】
①〔宗〕教義。教条。
②独断。独断的な説・意見。
とく‐まい【得米】
田地の持主がその小作人から取り立てた米。小作米。
ドグマチズム【dogmatism】
独断論。教条主義。
ドグマチック【dogmatic】
独断的。教条主義的。
どく‐み【毒味・毒見】
飲食物を人にすすめる前に、まず自分が食べて毒の有無を確かめること。特に、貴人に食を供する際行われた。転じて、料理の味加減を見ること。泉鏡花、小春の狐「もし其の茸きのこをめしあがるんなら、屹きっとお―を先へして」
とくみ‐どいや【十組問屋】‥ドヒ‥
江戸時代、江戸で組織された各種の問屋の組合。1694年(元禄7)、江戸・大坂間の海上輸送の不正や遭難による損害を防ぐために、荷主を塗物店・内店(繊維関係)・通町(小間物など)・薬種店・釘店・綿店・表店(畳表など)・川岸(油)・紙店・酒店の10組に分けて結成したのに始まる。→二十四組問屋にじゅうよくみといや
とく‐む【特務】
特別の任務。特に、特務機関およびその要員を指すことがある。
⇒とくむ‐かん【特務艦】
⇒とくむ‐きかん【特務機関】
⇒とくむ‐しかん【特務士官】
⇒とくむ‐そうちょう【特務曹長】
とくむ‐かん【特務艦】
海軍で、艦艇の活動に必要な助力をする艦船で、工作艦・運送艦・砕氷艦・標的艦・測量艦・給油艦などの総称。
⇒とく‐む【特務】
どく‐むぎ【毒麦】
イネ科の一年生帰化雑草。ヨーロッパ原産。茎は直立して高さ約50センチメートル。葉は線形で、葉脈に沿って縦溝があり、葉鞘は赤紫色。春から夏、茎頂に緑色の小穂を疎に互生。果実に寄生した菌が分泌するアルカロイドが家畜に有毒。
とくむ‐きかん【特務機関】‥クワン
①諜報活動や特殊工作を担当する特別の軍事組織。
②旧陸海軍で、軍隊・学校・官衙以外の特別の任務を持つ機関。元帥府・軍事参議院・侍従武官府・皇族付武官などがあった。
⇒とく‐む【特務】
どく‐むし【毒虫】
①毒を持ち、人を害する虫。ムカデ・サソリ・イラムシなど。宇治拾遺物語3「そこらの―ども出て」
②転じて、忌み嫌われる人物。
とくむ‐しかん【特務士官】‥クワン
下士官から任官した海軍士官。
⇒とく‐む【特務】
とくむ‐そうちょう【特務曹長】‥サウチヤウ
陸軍の准士官。後の准尉。
⇒とく‐む【特務】
とく‐めい【特命】
①特別の命令。
②特別の任命。「―を帯びる」
⇒とくめい‐ぜんけんこうし【特命全権公使】
⇒とくめい‐ぜんけんたいし【特命全権大使】
とく‐めい【匿名】
[北史尓朱世隆伝]実名をかくして知らせないこと。「―批評」
⇒とくめい‐くみあい【匿名組合】
⇒とくめい‐せい【匿名性】
とくめい‐くみあい【匿名組合】‥アヒ
商法の規定する契約によって組織される営業のための組合。当事者の一方(匿名組合員)が、相手方(営業者)の営業のために出資し、相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約するもので、独立法人ではない。
⇒とく‐めい【匿名】
とくめい‐せい【匿名性】
匿名であること。その行為をなした人物が特定できないこと。
⇒とく‐めい【匿名】
とくめい‐ぜんけんこうし【特命全権公使】
特命全権大使に次ぐ外交使節。職務と特権は大使と同じ。
⇒とく‐めい【特命】
とくめい‐ぜんけんたいし【特命全権大使】
外交使節の最上級。外国に駐在し、自国元首の名誉と威厳とを代表し、本国政府の訓令に基づいて駐在国との外交および在住自国民の保護・監督に携わる。
⇒とく‐めい【特命】
とく‐めん【特免】
①特に罪をゆるすこと。
②特に免除すること。
とく‐もく【徳目】
忠・孝・仁・義など、徳を分類した名目。道徳の細目。儒教では五倫・五常を指す。
どく‐もみ【毒揉み】
辛皮からかわ流しの別称。
どく‐や【毒矢】
やじりに毒を塗った矢。毒箭どくせん。
とく‐やく【特約】
特別の条件を付帯した約束。また、特別の便宜または利益のある契約。
⇒とくやく‐てん【特約店】
どく‐やく【毒薬】
毒性のある薬物。人体に摂取・吸収、また外用した場合、微量でも致死量となるため、生命の危険を誘発する医薬品。日本霊異記中「其の子孫に―を服せ令めて」
とくやく‐てん【特約店】
製造元または販売元と特約をした販売店。
⇒とく‐やく【特約】
とくやま【徳山】
山口県周南市の地名。毛利氏の支藩徳山藩の城下町。
⇒とくやま‐いし【徳山石】
とくやま‐いし【徳山石】
山口県周南市の黒髪島に産出する花崗岩の石材。やや黒っぽく粗粒。土木・墓石用。
⇒とくやま【徳山】
とく‐ゆう【特有】‥イウ
そのものだけが特に備えていること。「―の匂い」
⇒とくゆう‐ざいさん【特有財産】
⇒とくゆう‐せい【特有性】
とく‐ゆう【特融】
金銭などを特別に融通すること。
とくゆう‐ざいさん【特有財産】‥イウ‥
夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産。戸主制度のあった旧制では、家族の各人の有する財産についても、この語を用いた。
⇒とく‐ゆう【特有】
とくゆう‐せい【特有性】‥イウ‥
その物に限って有する性質。特性。
⇒とく‐ゆう【特有】
とく‐よう【特用】
①特別に使用すること。
②特殊の用。
⇒とくよう‐さくもつ【特用作物】
⇒とくよう‐りんさんぶつ【特用林産物】
とく‐よう【特養】‥ヤウ
特別養護老人ホームの略。
とく‐よう【徳用】
①有徳で応用の才能があること。源平盛衰記1「汝は坐道場の―を備へたり」
②徳より発する作用。功徳くどくの力。謡曲、海人「この経の―にて」
③用いて利益の多いこと。値段の割に役に立つこと。「お―なセット」「―品」
④利得。得分。浮世草子、日本新永代蔵「凡そ二十五六匁なり、是れを手代の―にして」
とくよう【徳陽】‥ヤウ
(Deyang)中国四川省北部の都市。中国四大リン鉱の一つがあり、化学工業や機械工業が盛ん。人口62万9千(2000)。
とくよう‐さくもつ【特用作物】
食用以外の特定の用途に供する農作物。煙草・桑・茶・麻・藍・棉・藺いの類。→工芸作物。
⇒とく‐よう【特用】
とくよう‐りんさんぶつ【特用林産物】
森林でとれる木材以外の産物。キノコ類・クリ・クルミ・漆・松脂・樟脳など。
⇒とく‐よう【特用】
どく‐よけ【毒除け】
中毒を予防すること。また、そのためのもの。
と‐くら【土倉】
⇒どそう
と‐ぐら【鳥栖・鳥座・塒】
(「くら」は人・動物が居る所、また物を乗せておく所)鳥の夜寝る所。ねぐら。とや。万葉集2「―立て飼ひしかりの子巣立ちなば」
とぐら‐かみやまだ‐おんせん【戸倉上山田温泉】‥ヲン‥
長野県千曲市、千曲川の両岸にある温泉。泉質は硫黄泉。
どく‐らく【独楽】
①ひとり楽しむこと。〈日葡辞書〉
②⇒こま
とく‐り【徳利】
①陶製・金属製もしくはガラス製の、細く高く、口のすぼんだ器。酒・醤油・酢などを入れておくもの。特に、酒を入れ、杯に注ぐ器。とっくり。銚子。〈易林本節用集〉
②(水中に入れれば沈むからいう)水泳のできない者をあざけっていう語。
⇒とくり‐つばめ【徳利燕】
とく‐りつ【特立】
①衆にぬきんでていること。
②他にたよらないこと。
どく‐りつ【独立】
①それだけの力で立っていること。
②個人が一家を構え、生計を立て、私権行使の能力を有すること。「―して店を構える」
③単独で存在すること。他に束縛または支配されないこと。ひとりだち。特に、一国または団体が、その権限行使の能力を完全に有すること。「司法の―」
⇒どくりつ‐えいよう【独立栄養】
⇒どくりつ‐かおく【独立家屋】
⇒どくりつ‐きかん【独立機関】
⇒どくりつ‐ぎょうせい‐ほうじん【独立行政法人】
⇒どくりつぎょうせいほうじん‐とう‐こじんじょうほうほご‐ほう【独立行政法人等個人情報保護法】
⇒どくりつぎょうせいほうじん‐とう‐じょうほうこうかい‐ほう【独立行政法人等情報公開法】
⇒どくりつ‐けん【独立権】
⇒どくりつ‐ご【独立語】
⇒どくりつ‐こく【独立国】
⇒どくりつ‐こっか‐きょうどうたい【独立国家共同体】
⇒どくりつさいさん‐せい【独立採算制】
⇒どくりつ‐じえい‐のうみん【独立自営農民】
⇒どくりつ‐じそん【独立自尊】
⇒どくりつ‐じゅうり【独立重利】
⇒どくりつ‐しん【独立心】
⇒どくりつ‐ぜい【独立税】
⇒どくりつ‐せんげん【独立宣言】
⇒どくりつ‐とう【独立党】
⇒どくりつ‐とうじしゃ‐さんか【独立当事者参加】
⇒どくりつ‐どっこう【独立独行】
⇒どくりつ‐どっぽ【独立独歩】
⇒どくりつ‐の‐ほうそく【独立の法則】
⇒どくりつ‐びじゅつ‐きょうかい【独立美術協会】
⇒どくりつ‐ふき【独立不羈】
⇒どくりつ‐プロ【独立プロ】
⇒どくりつ‐へんすう【独立変数】
⇒どくりつ‐めいれい【独立命令】
どくりつ‐えいよう【独立栄養】‥ヤウ
「栄養形式」参照。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐かおく【独立家屋】‥ヲク
(もと軍隊用語で、付近に家がなく、目標となる家のこと)一戸建ての家。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐きかん【独立機関】‥クワン
憲法上の原則や三権分立の理念に基づき、裁判所・会計検査院のように特殊の地位を認められた官庁。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐ぎょうせい‐ほうじん【独立行政法人】‥ギヤウ‥ハフ‥
1999年国の行政組織を縮小し外部委託を図るために国から独立させて法人格をもたせた機関。そのうち、役職員の身分を国家公務員とするものを特定独立行政法人という。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつぎょうせいほうじん‐とう‐こじんじょうほうほご‐ほう【独立行政法人等個人情報保護法】‥ギヤウ‥ハフ‥ジヤウ‥ハフ
独立行政法人等の保有する個人情報について行政機関個人情報保護法に準じて定められた法律。対象機関は独立行政法人・国立大学法人・特殊法人・認可法人。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつぎょうせいほうじん‐とう‐じょうほうこうかい‐ほう【独立行政法人等情報公開法】‥ギヤウ‥ハフ‥ジヤウ‥ハフ
独立行政法人等の情報公開について行政機関の情報公開に準じて定められた法律。対象は独立行政法人・国立大学法人・特殊法人・認可法人。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐けん【独立権】
国家が外国に支配されずに国内的および対外的決定をなし得る国際法上の権能。一国が他国の干渉拘束を受けないで内政・外交を処理する権利。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐ご【独立語】
文の成分の一つ。感動・呼びかけ・応答・接続などを表す語句で、他の成分との関係が希薄で、独立的な機能の強いもの。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐こく【独立国】
完全な主権を有する国家。国際法上の能力を有する完全な国際法主体。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐こっか‐きょうどうたい【独立国家共同体】‥コク‥
(→)シー‐アイ‐エス(CIS)に同じ。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつさいさん‐せい【独立採算制】
同一企業内の各部門が、他の部門とは独立に収支調節を図る経営法。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐じえい‐のうみん【独立自営農民】
封建的土地所有の解体の中から生まれ出た独立かつ自由な中小の土地所有農民。→ヨーマン。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐じそん【独立自尊】
独立して世に処し、自己の人格と威厳を保つこと。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐じゅうり【独立重利】‥ヂユウ‥
延滞した利息を元本に組み入れず、これを独立の元本としてさらに利息を付すこと。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐しん【独立心】
他人に依存せず、自分の力でしようとする気概。「―旺盛」
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐ぜい【独立税】
都道府県・市町村が国税とは別に、独立して課する租税。旧地方税法において、付加税に対する語。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐せんげん【独立宣言】
(Declaration of Independence)アメリカの独立に際し、ジェファソンが起草した宣言。1776年7月大陸会議で可決。ロックの自然法思想に立脚して自由・平等・幸福の追求を天賦の人権として主張した。→アメリカ独立戦争。
→文献資料[独立宣言]
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐とう【独立党】‥タウ
朝鮮の開化派の別称。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐とうじしゃ‐さんか【独立当事者参加】‥タウ‥
甲乙間に係属中の民事訴訟の結果により、丙の権利が侵害されるか、訴訟の目的に丙の権利があると思われる場合に、丙が当事者としてその訴訟に参加すること。権利者参加。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐どっこう【独立独行】‥ドクカウ
他人に頼らず、自力で自分の信ずるところを行うこと。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐どっぽ【独立独歩】‥ドク‥
①(→)独立独行に同じ。
②他に並ぶもののないこと。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐の‐ほうそく【独立の法則】‥ハフ‥
「メンデルの法則」参照。
⇒どく‐りつ【独立】
とくり‐つばめ【徳利燕】
コシアカツバメの別称。
⇒とく‐り【徳利】
どくりつ‐びじゅつ‐きょうかい【独立美術協会】‥ケフクワイ
美術団体。1930年、二科会系の洋画家を主体として、新時代の美術確立を宣言して創立。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐ふき【独立不羈】
他からの束縛・制約を受けることなく、自分の思うところに従って行動すること。「―の精神」
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐プロ【独立プロ】
独立プロダクションの略称。大手映画会社に属さず、自主的に資金を集めて映画を製作する組織。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐へんすう【独立変数】
〔数〕ある変数が他の変数とは無関係に独立に自由に変化し得るとき、その変数を独立変数という。自変数。↔従属変数。→関数。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりつ‐めいれい【独立命令】
明治憲法下、法律とは独立に広範な事項について規定することができた大権による命令・勅令。
⇒どく‐りつ【独立】
どくりゅう‐しょうえき【独立性易】‥リフシヤウ‥
黄檗おうばく宗の僧。浙江省杭州の人。1653年(承応2)来日し隠元に師事。能筆家で詩文に長じ、医学にも精通。著「永陵伝信録」「有 別緒自剡分宗」など。(1596〜1672)
どく‐りょう【毒竜】
毒気ある竜。祟たたりをなす怪物の意、また、もの恐ろしいもののたとえ。〈日葡辞書〉
どく‐りょう【読了】‥レウ
すべて読み終えること。
どく‐りょく【独力】
自分一人の力。自力。「―で成し遂げる」
とぐ・る
〔自四〕
(芸人社会の隠語)通言を使う。語呂合せをする。隠語を使う。転じて、一風変わっている。浮世風呂前「タロクと―・る男あれば」
トグル【toggle】
操作のたびに、二つの状態が交互に現れる機構。「―‐スイッチ」
と‐ぐるま【戸車】
引き戸の上または下につけ、開閉を便にする小さい車輪。
とくる‐よし【解くる由】
「解由げゆ」の訓読。日本紀竟宴歌「四年の間―なし」
と‐ぐるわ【外郭】
⇒そとぐるわ
とく‐れい【特例】
①特別の例。特別に設けた例外。「―を認める」
②特別の典例。「教育公務員―法」
⇒とくれい‐こうさい【特例公債】
⇒とくれい‐こくさい【特例国債】
⇒とくれい‐し【特例市】
とく‐れい【督励】
仕事・任務を進めるため、監督し励ますこと。「部下を―する」
とくれい‐こうさい【特例公債】
歳入の不足を補うために、財政法によらず特例法によって発行される公債。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐こくさい【特例国債】
(→)赤字国債に同じ。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐し【特例市】
人口20万人以上の市で、申出により政令で指定されたもの。政令指定都市と中核市に加えて、市町村への事務権限移譲を進める観点から1999年創設。
⇒とく‐れい【特例】
とく‐れん【得恋】
(「失恋」に対する造語)恋愛関係になること。
とぐろ【塒・蜷局】
蛇などが体を渦巻状に巻くこと。また、その巻いた状態。
⇒塒を巻く
どく‐ろ【髑髏】
されこうべ。しゃれこうべ。〈日葡辞書〉
とくろう‐ほう【特労法】‥ラウハフ
特定独立行政法人等における団体交渉の手続を規定し、職員およびその労働組合の争議行為を禁止する法律。正式名称は「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」。
別緒自剡分宗」など。(1596〜1672)
どく‐りょう【毒竜】
毒気ある竜。祟たたりをなす怪物の意、また、もの恐ろしいもののたとえ。〈日葡辞書〉
どく‐りょう【読了】‥レウ
すべて読み終えること。
どく‐りょく【独力】
自分一人の力。自力。「―で成し遂げる」
とぐ・る
〔自四〕
(芸人社会の隠語)通言を使う。語呂合せをする。隠語を使う。転じて、一風変わっている。浮世風呂前「タロクと―・る男あれば」
トグル【toggle】
操作のたびに、二つの状態が交互に現れる機構。「―‐スイッチ」
と‐ぐるま【戸車】
引き戸の上または下につけ、開閉を便にする小さい車輪。
とくる‐よし【解くる由】
「解由げゆ」の訓読。日本紀竟宴歌「四年の間―なし」
と‐ぐるわ【外郭】
⇒そとぐるわ
とく‐れい【特例】
①特別の例。特別に設けた例外。「―を認める」
②特別の典例。「教育公務員―法」
⇒とくれい‐こうさい【特例公債】
⇒とくれい‐こくさい【特例国債】
⇒とくれい‐し【特例市】
とく‐れい【督励】
仕事・任務を進めるため、監督し励ますこと。「部下を―する」
とくれい‐こうさい【特例公債】
歳入の不足を補うために、財政法によらず特例法によって発行される公債。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐こくさい【特例国債】
(→)赤字国債に同じ。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐し【特例市】
人口20万人以上の市で、申出により政令で指定されたもの。政令指定都市と中核市に加えて、市町村への事務権限移譲を進める観点から1999年創設。
⇒とく‐れい【特例】
とく‐れん【得恋】
(「失恋」に対する造語)恋愛関係になること。
とぐろ【塒・蜷局】
蛇などが体を渦巻状に巻くこと。また、その巻いた状態。
⇒塒を巻く
どく‐ろ【髑髏】
されこうべ。しゃれこうべ。〈日葡辞書〉
とくろう‐ほう【特労法】‥ラウハフ
特定独立行政法人等における団体交渉の手続を規定し、職員およびその労働組合の争議行為を禁止する法律。正式名称は「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」。
 別緒自剡分宗」など。(1596〜1672)
どく‐りょう【毒竜】
毒気ある竜。祟たたりをなす怪物の意、また、もの恐ろしいもののたとえ。〈日葡辞書〉
どく‐りょう【読了】‥レウ
すべて読み終えること。
どく‐りょく【独力】
自分一人の力。自力。「―で成し遂げる」
とぐ・る
〔自四〕
(芸人社会の隠語)通言を使う。語呂合せをする。隠語を使う。転じて、一風変わっている。浮世風呂前「タロクと―・る男あれば」
トグル【toggle】
操作のたびに、二つの状態が交互に現れる機構。「―‐スイッチ」
と‐ぐるま【戸車】
引き戸の上または下につけ、開閉を便にする小さい車輪。
とくる‐よし【解くる由】
「解由げゆ」の訓読。日本紀竟宴歌「四年の間―なし」
と‐ぐるわ【外郭】
⇒そとぐるわ
とく‐れい【特例】
①特別の例。特別に設けた例外。「―を認める」
②特別の典例。「教育公務員―法」
⇒とくれい‐こうさい【特例公債】
⇒とくれい‐こくさい【特例国債】
⇒とくれい‐し【特例市】
とく‐れい【督励】
仕事・任務を進めるため、監督し励ますこと。「部下を―する」
とくれい‐こうさい【特例公債】
歳入の不足を補うために、財政法によらず特例法によって発行される公債。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐こくさい【特例国債】
(→)赤字国債に同じ。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐し【特例市】
人口20万人以上の市で、申出により政令で指定されたもの。政令指定都市と中核市に加えて、市町村への事務権限移譲を進める観点から1999年創設。
⇒とく‐れい【特例】
とく‐れん【得恋】
(「失恋」に対する造語)恋愛関係になること。
とぐろ【塒・蜷局】
蛇などが体を渦巻状に巻くこと。また、その巻いた状態。
⇒塒を巻く
どく‐ろ【髑髏】
されこうべ。しゃれこうべ。〈日葡辞書〉
とくろう‐ほう【特労法】‥ラウハフ
特定独立行政法人等における団体交渉の手続を規定し、職員およびその労働組合の争議行為を禁止する法律。正式名称は「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」。
別緒自剡分宗」など。(1596〜1672)
どく‐りょう【毒竜】
毒気ある竜。祟たたりをなす怪物の意、また、もの恐ろしいもののたとえ。〈日葡辞書〉
どく‐りょう【読了】‥レウ
すべて読み終えること。
どく‐りょく【独力】
自分一人の力。自力。「―で成し遂げる」
とぐ・る
〔自四〕
(芸人社会の隠語)通言を使う。語呂合せをする。隠語を使う。転じて、一風変わっている。浮世風呂前「タロクと―・る男あれば」
トグル【toggle】
操作のたびに、二つの状態が交互に現れる機構。「―‐スイッチ」
と‐ぐるま【戸車】
引き戸の上または下につけ、開閉を便にする小さい車輪。
とくる‐よし【解くる由】
「解由げゆ」の訓読。日本紀竟宴歌「四年の間―なし」
と‐ぐるわ【外郭】
⇒そとぐるわ
とく‐れい【特例】
①特別の例。特別に設けた例外。「―を認める」
②特別の典例。「教育公務員―法」
⇒とくれい‐こうさい【特例公債】
⇒とくれい‐こくさい【特例国債】
⇒とくれい‐し【特例市】
とく‐れい【督励】
仕事・任務を進めるため、監督し励ますこと。「部下を―する」
とくれい‐こうさい【特例公債】
歳入の不足を補うために、財政法によらず特例法によって発行される公債。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐こくさい【特例国債】
(→)赤字国債に同じ。
⇒とく‐れい【特例】
とくれい‐し【特例市】
人口20万人以上の市で、申出により政令で指定されたもの。政令指定都市と中核市に加えて、市町村への事務権限移譲を進める観点から1999年創設。
⇒とく‐れい【特例】
とく‐れん【得恋】
(「失恋」に対する造語)恋愛関係になること。
とぐろ【塒・蜷局】
蛇などが体を渦巻状に巻くこと。また、その巻いた状態。
⇒塒を巻く
どく‐ろ【髑髏】
されこうべ。しゃれこうべ。〈日葡辞書〉
とくろう‐ほう【特労法】‥ラウハフ
特定独立行政法人等における団体交渉の手続を規定し、職員およびその労働組合の争議行為を禁止する法律。正式名称は「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」。
どく‐べにたけ【毒紅茸】🔗⭐🔉
どく‐べにたけ【毒紅茸】
担子菌類のきのこ。高さ約5センチメートル。傘は直径約5センチメートル、表面平滑で紅色または淡紅色。柄は白色。全体はもろく辛味があるが毒性はない。山林・芝生に発生。ベニタケ。
どく‐み【毒味・毒見】🔗⭐🔉
どく‐み【毒味・毒見】
飲食物を人にすすめる前に、まず自分が食べて毒の有無を確かめること。特に、貴人に食を供する際行われた。転じて、料理の味加減を見ること。泉鏡花、小春の狐「もし其の茸きのこをめしあがるんなら、屹きっとお―を先へして」
○毒を食わば皿までどくをくらわばさらまで🔗⭐🔉
○毒を食わば皿までどくをくらわばさらまで
(毒を食う以上は、その皿までもなめてしまおうの意で)一度罪を犯した以上は、ためらわずに最後まで悪に徹しようとすることをいう。また、いったん面倒なことに関わってしまったからには、最後まで関わり抜く。
⇒どく【毒】
○毒を以て毒を制すどくをもってどくをせいす🔗⭐🔉
○毒を以て毒を制すどくをもってどくをせいす
[普灯録]悪事をおさえるのに、悪事をもってすること。
⇒どく【毒】
とげ【刺・棘】
①堅くて先のとがった突起物で、触れると痛みを感じるもの。
㋐生物体に生じる針状の突起物。植物では、サイカチのように枝の変形したもの、サボテンのように托葉の変形したもの、バラのように表皮の変形したものなどがある。また動物では、ウニ類やエビ・カニなどの体表に顕著。刺毛。
㋑竹・木などのとがった細片の人の肌につき立ったもの。好色五人女4「左の人さし指に有るかなきかの―の立ちけるを」
㋒魚骨などが飲食の際、人の咽喉に立ったもの。
②比喩的に、人の心を刺すような感じのもの。「―のある言葉」「―を含んだ目つき」
とけ‐あい【解合】‥アヒ
取引所で不時の事変、その他買占め・売崩しなどで相場が急変した場合、それに基づく混乱を防止するため、売方と買方とが協議妥協して一定の値段を定めて差金決済し、売買契約を解くこと。
とけ‐あ・う【解け合う】‥アフ
〔自五〕
①互いにへだたりがなくなる。互いにうちとける。「心が―・う」
②示談で取引の契約を解く。→解合とけあい
とけ‐あ・う【溶け合う】‥アフ
〔自五〕
2種類以上の物質がとけて入りまじり、一つになる。
と‐けい【時計・土圭】
(もと「土圭(周代の緯度測定器)」を日本で中世に日時計の意に用いた。「時計」は当て字)時刻を示しまたは時間を測定する器械。日時計をはじめ水時計・砂時計・火時計などから水晶時計・原子時計に至るまで種類が多い。機械時計は振子または天府てんぷの振動の等時性を利用して歯車を動かし、指針を等時的に進ませる装置から成る。時辰儀。ウォッチ。クロック。日葡辞書「スナノトケイ」。与謝野寛、鉄幹子「車がまはれば―もまはる。―がまはれば世界もまはる」
⇒とけい‐ざ【時計座】
⇒とけい‐ざら【時計皿】
⇒とけい‐じかけ【時計仕掛】
⇒とけい‐しんかん【時計信管】
⇒とけい‐すうじ【時計数字】
⇒とけい‐そう【時計草】
⇒とけい‐だい【時計台】
⇒とけい‐の‐ま【土圭の間】
⇒とけい‐まわり【時計回り】
と‐けい【徒刑】
①(→)徒ずに同じ。
②旧刑法で重罪に科した刑。男は島に送って女は内地で、強制労働につかせた。有期と無期がある。「―場」
③(→)懲役ちょうえきに同じ。
とけい‐ざ【時計座】
(Horologium ラテン)エリダヌス座の東にある南天の小星座。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐ざら【時計皿】
懐中時計の蓋の形をしたガラス皿。少量の物質の蒸発・秤量・反応などに使用。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐じかけ【時計仕掛】
時計の働きによって、一定時刻に作動するようにした仕組み。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐しんかん【時計信管】‥クワン
ぜんまいで動く時計装置を利用した時限信管。高射砲弾丸などに使用。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐すうじ【時計数字】
(時計の文字盤に多く用いることから)ローマ数字。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐そう【時計草】‥サウ
(花の構造が時計の文字板を思わせるからいう)トケイソウ科の常緑多年草。ブラジル原産。茎は蔓状で巻ひげがある。夏、葉腋に大形の花を開く。萼片は白色、花弁は薄桃色、多数の糸状の副花冠が、2列に並ぶ。中央は白色、先端は紅紫色。球形黄色の液果を結ぶ。観賞用に温室で栽培。パッション‐フラワー。
とけいそう
 トケイソウ
提供:OPO
トケイソウ
提供:OPO
 クダモノトケイソウ
撮影:関戸 勇
クダモノトケイソウ
撮影:関戸 勇
 ⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐だい【時計台】
上部に巨大な時計を設けた建物や塔。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐の‐ま【土圭の間】
江戸城内、御用部屋の北方、廊下を隔てて老中・若年寄の部屋に接し、時計が置かれ、坊主が詰めて時刻報知の任にあたった部屋。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐まわり【時計回り】‥マハリ
時計の針がまわる方向にまわること。右まわり。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とげ‐うお【棘魚】‥ウヲ
トゲウオ科の硬骨魚の総称。淡水産。イトヨ・トミヨなど。背びれ・腹びれ・臀しりびれに強いとげがあるからいう。巣を作ることで知られる。
トミヨ
提供:東京動物園協会
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐だい【時計台】
上部に巨大な時計を設けた建物や塔。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐の‐ま【土圭の間】
江戸城内、御用部屋の北方、廊下を隔てて老中・若年寄の部屋に接し、時計が置かれ、坊主が詰めて時刻報知の任にあたった部屋。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐まわり【時計回り】‥マハリ
時計の針がまわる方向にまわること。右まわり。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とげ‐うお【棘魚】‥ウヲ
トゲウオ科の硬骨魚の総称。淡水産。イトヨ・トミヨなど。背びれ・腹びれ・臀しりびれに強いとげがあるからいう。巣を作ることで知られる。
トミヨ
提供:東京動物園協会
 とけ‐こ・む【溶け込む】
〔自五〕
①溶けて、液体や気体の中に入って一つになる。
②自然環境の中や人々の組織の中に入って、その雰囲気になじんで一体となる。「風景に―・む」
ど‐げざ【土下座】
相手に恭順の意を表すため、地上に跪ひざまずいて礼をすること。「道端に―する」「―してあやまる」
とけし‐な・し
〔形ク〕
もどかしい。じれったい。待ちどおしい。好色五人女5「三十五日の立つを―・く」
とげ‐だ・つ【刺立つ】
〔自五〕
①とげが立つ。
②いらだつ。かどだつ。とげとげしくなる。
ど‐けち
(ドは接頭語)非常にけちであることをののしっていう語。
と‐けつ【吐血】
口から血を吐くこと。また、その血。多く消化管の出血についていう。→喀血かっけつ
と‐けつ【兎欠】
(→)兎唇としんに同じ。〈伊呂波字類抄〉
とげつ‐きょう【渡月橋】‥ケウ
京都市右京区の嵐山の麓を流れる保津川に架かる橋。
渡月橋
撮影:山梨勝弘
とけ‐こ・む【溶け込む】
〔自五〕
①溶けて、液体や気体の中に入って一つになる。
②自然環境の中や人々の組織の中に入って、その雰囲気になじんで一体となる。「風景に―・む」
ど‐げざ【土下座】
相手に恭順の意を表すため、地上に跪ひざまずいて礼をすること。「道端に―する」「―してあやまる」
とけし‐な・し
〔形ク〕
もどかしい。じれったい。待ちどおしい。好色五人女5「三十五日の立つを―・く」
とげ‐だ・つ【刺立つ】
〔自五〕
①とげが立つ。
②いらだつ。かどだつ。とげとげしくなる。
ど‐けち
(ドは接頭語)非常にけちであることをののしっていう語。
と‐けつ【吐血】
口から血を吐くこと。また、その血。多く消化管の出血についていう。→喀血かっけつ
と‐けつ【兎欠】
(→)兎唇としんに同じ。〈伊呂波字類抄〉
とげつ‐きょう【渡月橋】‥ケウ
京都市右京区の嵐山の麓を流れる保津川に架かる橋。
渡月橋
撮影:山梨勝弘
 とげっ‐ぽう【吐月峰】
①静岡市丸子付近の地。連歌師宗長が草庵を営み吐月峰柴屋軒と命名したという。
②(1に産する竹で製したものが多く世に行われたことによる)煙草盆の灰吹。
ドケティズム【Docetism】
イエス=キリストの神性のみを認め、その人間的生(誕生や十字架での死など)は仮象であるとし、受肉を否定するグノーシス思想。仮現論。
とげ‐とげ【刺刺】
①多くのとげ。また、一面にとげ立っているさま。
②言動・態度がきつく近づきにくいさま。「―した物言い」
とげとげ‐し・い【刺刺しい】
〔形〕[文]とげとげ・し(シク)
①とげ立っている。森鴎外、青年「器械刈にした頭の、筋太な、―・い髪には」
②態度や言葉つきが意地悪で角立っている。「―・い目つき」
とげ‐な・し【利気無し】
〔形ク〕
しっかりした所がない。賢い様子がない。竹取物語「これを聞きてぞ―・きものをばあへなしといひける」
とげ‐ぬき【刺抜き】
肌にささったとげを抜くこと。また、それに用いる具。
⇒とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】
とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】‥ヂザウ
東京都豊島区巣鴨にある曹洞宗の寺、高岩寺の俗称。本尊の延命地蔵菩薩は諸病に霊験があるとされる。毎月4の日が縁日。
⇒とげ‐ぬき【刺抜き】
とげ‐ねずみ【棘鼠】
ネズミ科トゲネズミ属の哺乳類。奄美大島・徳之島・沖縄だけにすむ。奄美産は体長15センチメートルほど、沖縄本島産は少し大きく別種とされる。背は黒く、体側から腹面は橙色となる。荒い刺し毛をもつ。天然記念物。
と・ける【解ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
結ばれていたり、固まったり、閉じたり、不明だったりしたものが、ゆるめほぐれた状態になる意。
➊結ばれていたものがばらばらになる。
①結び目がほどける。万葉集14「昼―・けば―・けなへ紐のわが背なにあひ寄るとかも夜―・けやすけ」。「帯が―・ける」
②しこりになっていた気持がさっぱりする。万葉集2「磐代の野中に立てる結び松情こころも―・けず古思ほゆ」。「誤解が―・ける」
③心がゆるむ。安心する。万葉集17「よろづ世と心は―・けて吾がせこがつみし手見つつしのびかねつも」。源氏物語空蝉「心―・けたる寝いだにねられずなむ」。「警戒心が―・ける」
④制約や契約などの束縛が除かれる。「禁が―・ける」
⑤警備などで固められていた態勢がゆるむ。「包囲が―・ける」
➋職などから離れる。解任される。源氏物語関屋「その弟の右近の尉―・けて御供にくだりしをぞ」。「任が―・ける」
➌不明のものが明らかになる。
①答が出る。「問題が―・ける」
②納得がゆく。解釈がつく。「疑義が―・ける」
と・ける【溶ける・融ける・熔ける・鎔ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
①融解する。固体・固形物が液状になる。源氏物語末摘花「朝日さす軒の垂氷は―・けながら」。「雪が―・ける」
②液体に他の物質がまざって均一な液体になる。「食塩は水に―・ける」
◇「解ける」とも書く。「熔」「鎔」は、金属の場合に使う。
と・げる【遂げる】
〔他下一〕[文]と・ぐ(下二)
①はたす。成しおえる。成就させる。万葉集3「思へりし心は―・げず」。「本懐を―・げる」
②最後にそういう結果になる。「悲壮な最期を―・げる」
ど・ける【退ける】
〔他下一〕[文]ど・く(下二)
その場所からほかへうつす。どかす。「石を脇へ―・ける」
と‐けん【杜鵑】
〔動〕ホトトギスの漢名。文華秀麗集「―の啼序春将に闌けむとし」
⇒とけん‐か【杜鵑花】
ど‐けん【土建】
土木と建築。「―屋」
とけん‐か【杜鵑花】‥クワ
〔植〕サツキツツジの別称。〈元和本下学集〉
⇒と‐けん【杜鵑】
とこ【床】
①1段高く設けた平らな所。ゆか。新撰字鏡7「
とげっ‐ぽう【吐月峰】
①静岡市丸子付近の地。連歌師宗長が草庵を営み吐月峰柴屋軒と命名したという。
②(1に産する竹で製したものが多く世に行われたことによる)煙草盆の灰吹。
ドケティズム【Docetism】
イエス=キリストの神性のみを認め、その人間的生(誕生や十字架での死など)は仮象であるとし、受肉を否定するグノーシス思想。仮現論。
とげ‐とげ【刺刺】
①多くのとげ。また、一面にとげ立っているさま。
②言動・態度がきつく近づきにくいさま。「―した物言い」
とげとげ‐し・い【刺刺しい】
〔形〕[文]とげとげ・し(シク)
①とげ立っている。森鴎外、青年「器械刈にした頭の、筋太な、―・い髪には」
②態度や言葉つきが意地悪で角立っている。「―・い目つき」
とげ‐な・し【利気無し】
〔形ク〕
しっかりした所がない。賢い様子がない。竹取物語「これを聞きてぞ―・きものをばあへなしといひける」
とげ‐ぬき【刺抜き】
肌にささったとげを抜くこと。また、それに用いる具。
⇒とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】
とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】‥ヂザウ
東京都豊島区巣鴨にある曹洞宗の寺、高岩寺の俗称。本尊の延命地蔵菩薩は諸病に霊験があるとされる。毎月4の日が縁日。
⇒とげ‐ぬき【刺抜き】
とげ‐ねずみ【棘鼠】
ネズミ科トゲネズミ属の哺乳類。奄美大島・徳之島・沖縄だけにすむ。奄美産は体長15センチメートルほど、沖縄本島産は少し大きく別種とされる。背は黒く、体側から腹面は橙色となる。荒い刺し毛をもつ。天然記念物。
と・ける【解ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
結ばれていたり、固まったり、閉じたり、不明だったりしたものが、ゆるめほぐれた状態になる意。
➊結ばれていたものがばらばらになる。
①結び目がほどける。万葉集14「昼―・けば―・けなへ紐のわが背なにあひ寄るとかも夜―・けやすけ」。「帯が―・ける」
②しこりになっていた気持がさっぱりする。万葉集2「磐代の野中に立てる結び松情こころも―・けず古思ほゆ」。「誤解が―・ける」
③心がゆるむ。安心する。万葉集17「よろづ世と心は―・けて吾がせこがつみし手見つつしのびかねつも」。源氏物語空蝉「心―・けたる寝いだにねられずなむ」。「警戒心が―・ける」
④制約や契約などの束縛が除かれる。「禁が―・ける」
⑤警備などで固められていた態勢がゆるむ。「包囲が―・ける」
➋職などから離れる。解任される。源氏物語関屋「その弟の右近の尉―・けて御供にくだりしをぞ」。「任が―・ける」
➌不明のものが明らかになる。
①答が出る。「問題が―・ける」
②納得がゆく。解釈がつく。「疑義が―・ける」
と・ける【溶ける・融ける・熔ける・鎔ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
①融解する。固体・固形物が液状になる。源氏物語末摘花「朝日さす軒の垂氷は―・けながら」。「雪が―・ける」
②液体に他の物質がまざって均一な液体になる。「食塩は水に―・ける」
◇「解ける」とも書く。「熔」「鎔」は、金属の場合に使う。
と・げる【遂げる】
〔他下一〕[文]と・ぐ(下二)
①はたす。成しおえる。成就させる。万葉集3「思へりし心は―・げず」。「本懐を―・げる」
②最後にそういう結果になる。「悲壮な最期を―・げる」
ど・ける【退ける】
〔他下一〕[文]ど・く(下二)
その場所からほかへうつす。どかす。「石を脇へ―・ける」
と‐けん【杜鵑】
〔動〕ホトトギスの漢名。文華秀麗集「―の啼序春将に闌けむとし」
⇒とけん‐か【杜鵑花】
ど‐けん【土建】
土木と建築。「―屋」
とけん‐か【杜鵑花】‥クワ
〔植〕サツキツツジの別称。〈元和本下学集〉
⇒と‐けん【杜鵑】
とこ【床】
①1段高く設けた平らな所。ゆか。新撰字鏡7「 、止己」
②寝るために設ける所。ねどこ。寝台。また、寝具。万葉集5「明星の明くる朝は敷
、止己」
②寝るために設ける所。ねどこ。寝台。また、寝具。万葉集5「明星の明くる朝は敷 しきたえの―の辺去らず」。「―を敷く」
③畳のしん。↔畳表。
④川の底。かわどこ。
⑤苗を育てるところ。なえどこ。
⑥「床の間」の略。
⑦髪結床。床屋。
⑧鉄床かなとこの略。
⑨牛車ぎっしゃの屋形。くるまばこ。
⑩犂すきの底部。いさり。
⑪和船の櫓床ろどこ・舵床かじどこなどの総称。特に、舵床。
⑫船床、また船床銭・船税のこと。
⇒床に就く
⇒床離る
⇒床旧る
⇒床をあげる
⇒床をとる
とこ【所】
①「ところ」の俗語。浮世風呂2「おめヘン―のおかみさんも」
②(「が」に続けて)…ぐらい。…ほど。「千円が―買う」
と‐こ【独鈷】
⇒とっこ。枕草子25「―や数珠などもたせ」
とこ【常】
〔接頭〕
いつも変わらない、永遠であるの意を表す語。古事記上「常を訓みて―といひ」。拾遺和歌集恋「己がつまこそ―めづらなれ」
と‐ご【都護】
①都護府の長官。前漢の宣帝の時の西域都護に始まる。
②按察使あぜちの唐名。
ど‐こ【土戸】
平安時代における地方の農民。京都に住むものを京戸というのに対する。地戸。
ど‐こ【土鼓】
周代の古楽器。瓦または土製の胴の両面に革を張った鼓。草を結んでつくった桴ばちで打つ。
ど‐こ【何処・何所】
〔代〕
(イドコの約)場所・所在・位置をはっきり定めずに表し、または問うのに使う語。将門記承徳点「何トコにか往ゆき何にか来りて、誰が家にか宿る」。「―の人」「―まで話したっけ」→どれ(何)
⇒何処の馬の骨
⇒何処の烏も黒い
⇒何処吹く風
⇒何処方量も無い
⇒何処を押せばそんな音が出る
ど‐ご【土語】
①その地の土着の住民が使用することば。
②その地に特有のことば。方言や俗用語。
とこ‐あげ【床上げ】
長い病気が全快して、また産後の体が回復して、寝床をかたづけること。また、その祝い。床払い。「―を祝う」
とこ‐あしらい【床あしらい】‥アシラヒ
遊女などの閨中けいちゅうでの客あしらい。
とこ‐い【常井】‥ヰ
水が常に絶えることのない井戸。新撰六帖2「絶えぬ―のゐづつなりけり」
とこ‐いた【床板】
床の間に張る板。
とごい‐ど【詛戸】トゴヒ‥
人をのろうのに用いた物。呪詛の品物。古事記中「その―を返さしめき」
どこ‐いら【何処いら】
〔代〕
どのあたり。どのへん。
とこ‐いり【床入り】
①寝所に入ること。
②婚礼の夜、新夫婦が初めて床を共にすること。
と‐こう【杜康】‥カウ
中国の伝説で、最初に酒を造ったとされる人物。また、酒のこと。
と‐こう【杜衡】‥カウ
〔植〕カンアオイの漢名。〈伊呂波字類抄〉
と‐こう【徒行】‥カウ
歩いてゆくこと。歩行。
と‐こう【都講】‥カウ
①塾生の長。塾頭。
②(→)尚復しょうふくに同じ。
と‐こう【渡口】
渡し場。
と‐こう【渡航】‥カウ
船や航空機で海をわたること。海外へ行くこと。「アメリカへ―する」
⇒とこう‐めんじょう【渡航免状】
と‐こう‥カウ
〔副〕
(「兎角」と当て字)トカクの音便。
⇒とこう‐して
と‐ごう【兎毫】‥ガウ
筆の別称。日葡辞書「トガウニアタワズ」
とご・う【詛ふ】トゴフ
〔他四〕
のろう。雄略紀「刑つみせらるるに臨みて井を指して―・ひて曰く」
ど‐こう【土工】
①築堤・道路工事など、土砂を取り扱う土木工事。土功。
②土木工事に従う労働者。
⇒どこう‐し【土工司】
ど‐こう【土公】
土公神の略。
⇒どこう‐じん【土公神】
ど‐こう【土侯】
土着の諸侯。部族・藩・地方王国などの首長。
⇒どこう‐こく【土侯国】
ど‐こう【土貢】
(トコウとも)土産どさんのみつぎもの。田租のこと。平家物語7「土宜―万物を押領す」
ど‐こう【土寇】
土民の一揆。土匪。
ど‐こう【土窖】‥カウ
あなぐら。
ど‐こう【土壙】‥クワウ
(「壙」は穴・墓穴の意)地表面を掘りくぼめて造られた墓穴。「―墓」
ど‐ごう【土豪】‥ガウ
その土地の豪族。
⇒どごう‐れっしん【土豪劣紳】
ど‐ごう【怒号】‥ガウ
①いかりさけぶこと。また、その声。「―が乱れ飛ぶ」
②風・波などがはげしい音を立てるさまをいう。「荒海が―する」
とこうえん【都江堰】‥カウ‥
(Dujiangyan)
①中国四川省中部の都市。人口62万2千(2000)。
②1の西部、岷江中流にある古代以来の水利施設。秦の昭王の代、蜀の大守であった李氷が築造。現在も成都平原の治水に利用。世界遺産。
都江堰
提供:JTBフォト
しきたえの―の辺去らず」。「―を敷く」
③畳のしん。↔畳表。
④川の底。かわどこ。
⑤苗を育てるところ。なえどこ。
⑥「床の間」の略。
⑦髪結床。床屋。
⑧鉄床かなとこの略。
⑨牛車ぎっしゃの屋形。くるまばこ。
⑩犂すきの底部。いさり。
⑪和船の櫓床ろどこ・舵床かじどこなどの総称。特に、舵床。
⑫船床、また船床銭・船税のこと。
⇒床に就く
⇒床離る
⇒床旧る
⇒床をあげる
⇒床をとる
とこ【所】
①「ところ」の俗語。浮世風呂2「おめヘン―のおかみさんも」
②(「が」に続けて)…ぐらい。…ほど。「千円が―買う」
と‐こ【独鈷】
⇒とっこ。枕草子25「―や数珠などもたせ」
とこ【常】
〔接頭〕
いつも変わらない、永遠であるの意を表す語。古事記上「常を訓みて―といひ」。拾遺和歌集恋「己がつまこそ―めづらなれ」
と‐ご【都護】
①都護府の長官。前漢の宣帝の時の西域都護に始まる。
②按察使あぜちの唐名。
ど‐こ【土戸】
平安時代における地方の農民。京都に住むものを京戸というのに対する。地戸。
ど‐こ【土鼓】
周代の古楽器。瓦または土製の胴の両面に革を張った鼓。草を結んでつくった桴ばちで打つ。
ど‐こ【何処・何所】
〔代〕
(イドコの約)場所・所在・位置をはっきり定めずに表し、または問うのに使う語。将門記承徳点「何トコにか往ゆき何にか来りて、誰が家にか宿る」。「―の人」「―まで話したっけ」→どれ(何)
⇒何処の馬の骨
⇒何処の烏も黒い
⇒何処吹く風
⇒何処方量も無い
⇒何処を押せばそんな音が出る
ど‐ご【土語】
①その地の土着の住民が使用することば。
②その地に特有のことば。方言や俗用語。
とこ‐あげ【床上げ】
長い病気が全快して、また産後の体が回復して、寝床をかたづけること。また、その祝い。床払い。「―を祝う」
とこ‐あしらい【床あしらい】‥アシラヒ
遊女などの閨中けいちゅうでの客あしらい。
とこ‐い【常井】‥ヰ
水が常に絶えることのない井戸。新撰六帖2「絶えぬ―のゐづつなりけり」
とこ‐いた【床板】
床の間に張る板。
とごい‐ど【詛戸】トゴヒ‥
人をのろうのに用いた物。呪詛の品物。古事記中「その―を返さしめき」
どこ‐いら【何処いら】
〔代〕
どのあたり。どのへん。
とこ‐いり【床入り】
①寝所に入ること。
②婚礼の夜、新夫婦が初めて床を共にすること。
と‐こう【杜康】‥カウ
中国の伝説で、最初に酒を造ったとされる人物。また、酒のこと。
と‐こう【杜衡】‥カウ
〔植〕カンアオイの漢名。〈伊呂波字類抄〉
と‐こう【徒行】‥カウ
歩いてゆくこと。歩行。
と‐こう【都講】‥カウ
①塾生の長。塾頭。
②(→)尚復しょうふくに同じ。
と‐こう【渡口】
渡し場。
と‐こう【渡航】‥カウ
船や航空機で海をわたること。海外へ行くこと。「アメリカへ―する」
⇒とこう‐めんじょう【渡航免状】
と‐こう‥カウ
〔副〕
(「兎角」と当て字)トカクの音便。
⇒とこう‐して
と‐ごう【兎毫】‥ガウ
筆の別称。日葡辞書「トガウニアタワズ」
とご・う【詛ふ】トゴフ
〔他四〕
のろう。雄略紀「刑つみせらるるに臨みて井を指して―・ひて曰く」
ど‐こう【土工】
①築堤・道路工事など、土砂を取り扱う土木工事。土功。
②土木工事に従う労働者。
⇒どこう‐し【土工司】
ど‐こう【土公】
土公神の略。
⇒どこう‐じん【土公神】
ど‐こう【土侯】
土着の諸侯。部族・藩・地方王国などの首長。
⇒どこう‐こく【土侯国】
ど‐こう【土貢】
(トコウとも)土産どさんのみつぎもの。田租のこと。平家物語7「土宜―万物を押領す」
ど‐こう【土寇】
土民の一揆。土匪。
ど‐こう【土窖】‥カウ
あなぐら。
ど‐こう【土壙】‥クワウ
(「壙」は穴・墓穴の意)地表面を掘りくぼめて造られた墓穴。「―墓」
ど‐ごう【土豪】‥ガウ
その土地の豪族。
⇒どごう‐れっしん【土豪劣紳】
ど‐ごう【怒号】‥ガウ
①いかりさけぶこと。また、その声。「―が乱れ飛ぶ」
②風・波などがはげしい音を立てるさまをいう。「荒海が―する」
とこうえん【都江堰】‥カウ‥
(Dujiangyan)
①中国四川省中部の都市。人口62万2千(2000)。
②1の西部、岷江中流にある古代以来の水利施設。秦の昭王の代、蜀の大守であった李氷が築造。現在も成都平原の治水に利用。世界遺産。
都江堰
提供:JTBフォト
 どこう‐こく【土侯国】
従来からの首長や実力者の支配する国家。主としてイギリスの保護下にあるものをいった。→藩王国
⇒ど‐こう【土侯】
どこう‐し【土工司】
律令制で、宮内省に属し、壁塗・製瓦・石灰焼などをつかさどった官司。つちたくみのつかさ。
⇒ど‐こう【土工】
とこう‐して‥カウ‥
あれこれして。かろうじて。平治物語(金刀比羅本)「―馬にのせられ」
⇒と‐こう
どこう‐じん【土公神】
⇒どくじん
⇒ど‐こう【土公】
とこう‐めんじょう【渡航免状】‥カウ‥ジヤウ
(→)旅券に同じ。
⇒と‐こう【渡航】
どごう‐れっしん【土豪劣紳】‥ガウ‥
中国で、官僚や軍閥と結んで農民を搾取した大地主・資産家の蔑称。
⇒ど‐ごう【土豪】
と‐ごえ【と声】‥ゴヱ
「とほ(遠)声」の略か。また、「と(利)声」「と(外)声」「と(常)声」の意か。曾丹集「よそ耳に鹿の―を聞きしより」
とこ‐おおい【床覆い】‥オホヒ
水分の放散または温度の低下を防ぐため、苗床に筵むしろなどの覆いを施し、苗を保護する装置。
とこ‐おとめ【常少女】‥ヲトメ
とこしえに若い女。いつもかわらぬ若々しい少女。万葉集1「常にもがもな―にて」
ド‐ゴール【Charles de Gaulle】
フランスの軍人・政治家。自国の対ドイツ降伏後、1940〜44年ロンドンに自由フランス政府を作り、本国の抵抗運動と提携。44〜46年共和国臨時政府主席。47年右派を糾合してフランス国民連合を組織。一時引退したが、58年アルジェリアをめぐる危機に際し政府を組織、新憲法により第五共和制初代大統領。62年アルジェリア危機を収拾。核兵器保有などの自主外交を展開。68年五月革命後、国民投票に失敗し辞任。(1890〜1970)
どこ‐か【何処か】
①はっきり特定できない場所、不定の場所を指す語。「―へ遊びに行こう」
②はっきりとはいえないが、何となく。どことなく。「―すっきりしない」
とこ‐がえり【床反り】‥ガヘリ
眠れないで床の上で寝返りをすること。
とこ‐かざり【床飾り】
床の間の装飾。床に掛物をかけ挿花・置物などをおくこと。また、その掛物・置物など。
とこ‐かため【床固め】
河床や橋脚が掘り返されないように、石やコンクリートで河床を強化すること。
とこ‐がまち【床框】
床の間の前端の化粧横木。かまち。とこぶち。
とこ‐かみゆい【床髪結】‥ユヒ
取りたためる簡単な仮店を作って営業している髪結屋。橋台や川岸に多かった。浮世草子、御前義経記「―の目をすりて暖簾かけるを見て」
とこく【杜国】
⇒つぼいとこく(坪井杜国)
とこ‐げいしゃ【床芸者】
芸者を名のりながら、芸よりも床をつとめるのをもっぱらとする一種の私娼。誹風柳多留8「―ずるにかけてはにちうなり」
とこ‐ことば【床言葉】
遊女などが閨ねやに入る前にする決り文句の挨拶。好色一代女2「大かた仕掛定まつての―あり」
と‐ごころ【利心】
するどい心。しっかりした心。万葉集12「わが胸は破われてくだけて―もなし」
とこ‐さかずき【床盃】‥サカヅキ
婚礼の夜、新夫婦が寝所で盃をとりかわす儀式。
とこ‐ざし【床挿し】
挿木法の一つ。挿穂を苗床に挿すこと。
ドコサヘキサエン‐さん【ドコサヘキサエン酸】
(docosahexaenoic acid)不飽和脂肪酸の一種。分子式C21H31COOH マグロ・サバなどの魚油に多く含まれ、血栓・動脈硬化の予防などの効果が研究されている。DHA
とこ・し【常し・長し・永久し】
〔形シク〕
(「常とこ」の形容詞形)永久である。常にある。万葉集7「いや―・しくにわれかへり見む」
とこし‐え【常しえ・永久】‥ヘ
永くかわらないこと。いつまでも続くこと。とこしなえ。万葉集18「―にかくしもあらめや」。「―の愛を誓う」
とこ‐しき【床敷・褥】
①座席などに敷く物。しとね。天武紀下「氈おりかもの―」
②船床に敷く板。
とこし‐なえ【常しなへ・永久】‥ナヘ
(→)「とこしえ」に同じ。
とこ‐しばり【床縛り】
牛車ぎっしゃの屋形を車軸に縛る縄。落窪物語2「一の車の―をふつふつと切りてければ」
とこ‐しめ【床締め】
水漏れを防ぐため、水田の床に粘土などを入れること。
とこ‐じもの【床じもの】
(ジモノは接尾語)床のように。万葉集5「―打ち臥こい伏して」
とこ‐じょうず【床上手】‥ジヤウ‥
床あしらいのうまいこと。また、その人。
とこ‐じらみ【床蝨】
カメムシ目トコジラミ科の昆虫。体長約5ミリメートル。円盤状で扁平、翅はねは退化して小さく、全体赤褐色。アジア南部の原産で、室内に生息し、夜行性。人畜から吸血し、激しいかゆみと痛みを起こさせる。南京虫。鎮台虫。
とこじらみ
どこう‐こく【土侯国】
従来からの首長や実力者の支配する国家。主としてイギリスの保護下にあるものをいった。→藩王国
⇒ど‐こう【土侯】
どこう‐し【土工司】
律令制で、宮内省に属し、壁塗・製瓦・石灰焼などをつかさどった官司。つちたくみのつかさ。
⇒ど‐こう【土工】
とこう‐して‥カウ‥
あれこれして。かろうじて。平治物語(金刀比羅本)「―馬にのせられ」
⇒と‐こう
どこう‐じん【土公神】
⇒どくじん
⇒ど‐こう【土公】
とこう‐めんじょう【渡航免状】‥カウ‥ジヤウ
(→)旅券に同じ。
⇒と‐こう【渡航】
どごう‐れっしん【土豪劣紳】‥ガウ‥
中国で、官僚や軍閥と結んで農民を搾取した大地主・資産家の蔑称。
⇒ど‐ごう【土豪】
と‐ごえ【と声】‥ゴヱ
「とほ(遠)声」の略か。また、「と(利)声」「と(外)声」「と(常)声」の意か。曾丹集「よそ耳に鹿の―を聞きしより」
とこ‐おおい【床覆い】‥オホヒ
水分の放散または温度の低下を防ぐため、苗床に筵むしろなどの覆いを施し、苗を保護する装置。
とこ‐おとめ【常少女】‥ヲトメ
とこしえに若い女。いつもかわらぬ若々しい少女。万葉集1「常にもがもな―にて」
ド‐ゴール【Charles de Gaulle】
フランスの軍人・政治家。自国の対ドイツ降伏後、1940〜44年ロンドンに自由フランス政府を作り、本国の抵抗運動と提携。44〜46年共和国臨時政府主席。47年右派を糾合してフランス国民連合を組織。一時引退したが、58年アルジェリアをめぐる危機に際し政府を組織、新憲法により第五共和制初代大統領。62年アルジェリア危機を収拾。核兵器保有などの自主外交を展開。68年五月革命後、国民投票に失敗し辞任。(1890〜1970)
どこ‐か【何処か】
①はっきり特定できない場所、不定の場所を指す語。「―へ遊びに行こう」
②はっきりとはいえないが、何となく。どことなく。「―すっきりしない」
とこ‐がえり【床反り】‥ガヘリ
眠れないで床の上で寝返りをすること。
とこ‐かざり【床飾り】
床の間の装飾。床に掛物をかけ挿花・置物などをおくこと。また、その掛物・置物など。
とこ‐かため【床固め】
河床や橋脚が掘り返されないように、石やコンクリートで河床を強化すること。
とこ‐がまち【床框】
床の間の前端の化粧横木。かまち。とこぶち。
とこ‐かみゆい【床髪結】‥ユヒ
取りたためる簡単な仮店を作って営業している髪結屋。橋台や川岸に多かった。浮世草子、御前義経記「―の目をすりて暖簾かけるを見て」
とこく【杜国】
⇒つぼいとこく(坪井杜国)
とこ‐げいしゃ【床芸者】
芸者を名のりながら、芸よりも床をつとめるのをもっぱらとする一種の私娼。誹風柳多留8「―ずるにかけてはにちうなり」
とこ‐ことば【床言葉】
遊女などが閨ねやに入る前にする決り文句の挨拶。好色一代女2「大かた仕掛定まつての―あり」
と‐ごころ【利心】
するどい心。しっかりした心。万葉集12「わが胸は破われてくだけて―もなし」
とこ‐さかずき【床盃】‥サカヅキ
婚礼の夜、新夫婦が寝所で盃をとりかわす儀式。
とこ‐ざし【床挿し】
挿木法の一つ。挿穂を苗床に挿すこと。
ドコサヘキサエン‐さん【ドコサヘキサエン酸】
(docosahexaenoic acid)不飽和脂肪酸の一種。分子式C21H31COOH マグロ・サバなどの魚油に多く含まれ、血栓・動脈硬化の予防などの効果が研究されている。DHA
とこ・し【常し・長し・永久し】
〔形シク〕
(「常とこ」の形容詞形)永久である。常にある。万葉集7「いや―・しくにわれかへり見む」
とこし‐え【常しえ・永久】‥ヘ
永くかわらないこと。いつまでも続くこと。とこしなえ。万葉集18「―にかくしもあらめや」。「―の愛を誓う」
とこ‐しき【床敷・褥】
①座席などに敷く物。しとね。天武紀下「氈おりかもの―」
②船床に敷く板。
とこし‐なえ【常しなへ・永久】‥ナヘ
(→)「とこしえ」に同じ。
とこ‐しばり【床縛り】
牛車ぎっしゃの屋形を車軸に縛る縄。落窪物語2「一の車の―をふつふつと切りてければ」
とこ‐しめ【床締め】
水漏れを防ぐため、水田の床に粘土などを入れること。
とこ‐じもの【床じもの】
(ジモノは接尾語)床のように。万葉集5「―打ち臥こい伏して」
とこ‐じょうず【床上手】‥ジヤウ‥
床あしらいのうまいこと。また、その人。
とこ‐じらみ【床蝨】
カメムシ目トコジラミ科の昆虫。体長約5ミリメートル。円盤状で扁平、翅はねは退化して小さく、全体赤褐色。アジア南部の原産で、室内に生息し、夜行性。人畜から吸血し、激しいかゆみと痛みを起こさせる。南京虫。鎮台虫。
とこじらみ
 とこ‐すき【床犂】
床すなわち底のある犂。日本の従来の犂は多くこれである。
とこ‐すずみ【床涼み】
夏の夜、床ゆかを屋外に設けて涼むこと。特に、京都四条河原辺で床を設けて納涼すること。ゆかすずみ。
とこ‐ずれ【床擦れ】
(→)褥瘡じょくそうに同じ。
どこ‐そこ【何処其処・何所其所】
〔代〕
(「どこ」と「そこ」を重ねた語)具体的にそこと示されない場所。「―のだれと名乗るほどの者でない」
とこ‐だたみ【床畳】
床の間に敷く畳。雨月物語4「板敷の間に―を設けて」
とこ‐だな【床棚】
床脇にある棚。
とこ‐つ‐くに【常つ国】
死の国。よみのくに。黄泉。雄略紀「謂おもはざりき…―に至るといふことを」
とこ‐つち【床土】
床の間の壁などを塗る上等の土。
とこ‐つ‐み【床つ身】
病床についている身。〈色葉字類抄〉
とこ‐つ‐みかど【常つ御門】
永久に変わらない宮殿。永久の御所。万葉集2「よそに見し檀まゆみの岡も君ませば―ととのゐするかも」
とこ‐づめ【床詰め】
①いつまでも病床についていること。また、その身。
②(→)褥瘡じょくそうに同じ。
とこ‐とこ
①足早に狭い歩幅で歩くさま。「幼児が―歩く」
②電車が遅いスピードでつかえながら進むさま。「登山電車が―と走る」
どこ‐と‐なく【何処と無く】
どこと定まったことはないが、そう感じられて。なんとなく。「―愁いをふくんだ顔」
どこ‐とも‐なし【何処とも無し】
①どこと定まったところがなく、たよりにならない。平家物語10「下臈はどこともなき物なれば」
②どこが出所ともわからない。浄瑠璃、傾城反魂香「―の取り沙汰」
とこ‐とわ【常・永久】‥トハ
(平安時代までトコトバ)
①永久にかわらないこと。とこしえ。万葉集2「わがみかど千代―に栄えむと」
②いつも。つね。〈類聚名義抄〉
とこ‐とん
①(副詞的にも使う)どんづまり。末の末。最後の最後。また、徹底的に。「―まで頑張る」「―話し合う」
②日本舞踊で足拍子の音。転じて踊りの意に用いる。
とことんやれ‐ぶし【とことんやれ節】
明治初年の流行歌。1868年(明治1)、官軍東征の際に歌われた。「とことんやれとんやれな」という囃子詞はやしことばを添える。一説に品川弥二郎作詞、大村益次郎作曲という。
とこ‐なか【床中】
ねどこのなか。また、ねどこの中央。古今和歌集雑「枕よりあとより恋のせめくればせんかたなみぞ―にをる」
とこ‐なつ【常夏】
①いつも夏のようであること。「―のハワイ」
②㋐(春から秋にわたって咲くからいう)セキチクの一変種。分岐した枝頂に濃紅色の五弁花を四季を通じて開花。〈[季]夏〉
㋑ナデシコの古名。〈[季]夏〉。源氏物語紅葉賀「―のはなやかに咲き出でたるを」
③襲かさねの色目。(→)「なでしこ」に同じ。
④紋所の名。(→)「なでしこ」に同じ。
⑤源氏物語の巻名。
⇒とこなつ‐づき【常夏月】
⇒とこなつ‐に【常夏に】
とこ‐なつか・し【常懐かし】
〔形シク〕
いつまでも変わらず親しみやすい。源氏物語常夏「なでしこの―・しき色を見ば」
とこなつ‐づき【常夏月】
(常夏の花の盛んな月の意)陰暦6月の異称。
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなつ‐に【常夏に】
夏の間ずっと。万葉集17「立山に降り置ける雪を―見れども飽かず」
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなみ【床次】
姓氏の一つ。
⇒とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】
とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】‥ラウ
政治家。鹿児島生れ。東大卒。官界より政友会に入り、その領袖となる。原・高橋内閣の内相など。政友本党総裁・民政党顧問を経て政友会に復帰、のち除名。(1866〜1935)
⇒とこなみ【床次】
とこ‐なめ【常滑】
①岩にいつも生えている水苔。また、水苔でいつもなめらかな岩床。万葉集1「見れど飽かぬ吉野の河の―の絶ゆることなくまた還り見む」
②河床の平らな岩の上を、少量の水が静かに流れている所。
とこなめ【常滑】
愛知県南西部の市。知多半島の西岸に位置し、常滑焼・土管・タイルなどの窯業が中心。海苔のりの養殖が盛ん。中部国際空港がある。とこなべ。人口5万1千。
⇒とこなめ‐やき【常滑焼】
とこなめ‐やき【常滑焼】
常滑市を中心にその付近一帯で作られる炻器せっき質の陶器。草創は平安末期で、中世には甕かめ・壺・鉢を量産。江戸後期からは茶器も焼き、明治以降は急須などの朱泥しゅでい製品で知られる。土管・タイル・植木鉢なども産出。とこなべやき。
⇒とこなめ【常滑】
とこ‐すき【床犂】
床すなわち底のある犂。日本の従来の犂は多くこれである。
とこ‐すずみ【床涼み】
夏の夜、床ゆかを屋外に設けて涼むこと。特に、京都四条河原辺で床を設けて納涼すること。ゆかすずみ。
とこ‐ずれ【床擦れ】
(→)褥瘡じょくそうに同じ。
どこ‐そこ【何処其処・何所其所】
〔代〕
(「どこ」と「そこ」を重ねた語)具体的にそこと示されない場所。「―のだれと名乗るほどの者でない」
とこ‐だたみ【床畳】
床の間に敷く畳。雨月物語4「板敷の間に―を設けて」
とこ‐だな【床棚】
床脇にある棚。
とこ‐つ‐くに【常つ国】
死の国。よみのくに。黄泉。雄略紀「謂おもはざりき…―に至るといふことを」
とこ‐つち【床土】
床の間の壁などを塗る上等の土。
とこ‐つ‐み【床つ身】
病床についている身。〈色葉字類抄〉
とこ‐つ‐みかど【常つ御門】
永久に変わらない宮殿。永久の御所。万葉集2「よそに見し檀まゆみの岡も君ませば―ととのゐするかも」
とこ‐づめ【床詰め】
①いつまでも病床についていること。また、その身。
②(→)褥瘡じょくそうに同じ。
とこ‐とこ
①足早に狭い歩幅で歩くさま。「幼児が―歩く」
②電車が遅いスピードでつかえながら進むさま。「登山電車が―と走る」
どこ‐と‐なく【何処と無く】
どこと定まったことはないが、そう感じられて。なんとなく。「―愁いをふくんだ顔」
どこ‐とも‐なし【何処とも無し】
①どこと定まったところがなく、たよりにならない。平家物語10「下臈はどこともなき物なれば」
②どこが出所ともわからない。浄瑠璃、傾城反魂香「―の取り沙汰」
とこ‐とわ【常・永久】‥トハ
(平安時代までトコトバ)
①永久にかわらないこと。とこしえ。万葉集2「わがみかど千代―に栄えむと」
②いつも。つね。〈類聚名義抄〉
とこ‐とん
①(副詞的にも使う)どんづまり。末の末。最後の最後。また、徹底的に。「―まで頑張る」「―話し合う」
②日本舞踊で足拍子の音。転じて踊りの意に用いる。
とことんやれ‐ぶし【とことんやれ節】
明治初年の流行歌。1868年(明治1)、官軍東征の際に歌われた。「とことんやれとんやれな」という囃子詞はやしことばを添える。一説に品川弥二郎作詞、大村益次郎作曲という。
とこ‐なか【床中】
ねどこのなか。また、ねどこの中央。古今和歌集雑「枕よりあとより恋のせめくればせんかたなみぞ―にをる」
とこ‐なつ【常夏】
①いつも夏のようであること。「―のハワイ」
②㋐(春から秋にわたって咲くからいう)セキチクの一変種。分岐した枝頂に濃紅色の五弁花を四季を通じて開花。〈[季]夏〉
㋑ナデシコの古名。〈[季]夏〉。源氏物語紅葉賀「―のはなやかに咲き出でたるを」
③襲かさねの色目。(→)「なでしこ」に同じ。
④紋所の名。(→)「なでしこ」に同じ。
⑤源氏物語の巻名。
⇒とこなつ‐づき【常夏月】
⇒とこなつ‐に【常夏に】
とこ‐なつか・し【常懐かし】
〔形シク〕
いつまでも変わらず親しみやすい。源氏物語常夏「なでしこの―・しき色を見ば」
とこなつ‐づき【常夏月】
(常夏の花の盛んな月の意)陰暦6月の異称。
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなつ‐に【常夏に】
夏の間ずっと。万葉集17「立山に降り置ける雪を―見れども飽かず」
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなみ【床次】
姓氏の一つ。
⇒とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】
とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】‥ラウ
政治家。鹿児島生れ。東大卒。官界より政友会に入り、その領袖となる。原・高橋内閣の内相など。政友本党総裁・民政党顧問を経て政友会に復帰、のち除名。(1866〜1935)
⇒とこなみ【床次】
とこ‐なめ【常滑】
①岩にいつも生えている水苔。また、水苔でいつもなめらかな岩床。万葉集1「見れど飽かぬ吉野の河の―の絶ゆることなくまた還り見む」
②河床の平らな岩の上を、少量の水が静かに流れている所。
とこなめ【常滑】
愛知県南西部の市。知多半島の西岸に位置し、常滑焼・土管・タイルなどの窯業が中心。海苔のりの養殖が盛ん。中部国際空港がある。とこなべ。人口5万1千。
⇒とこなめ‐やき【常滑焼】
とこなめ‐やき【常滑焼】
常滑市を中心にその付近一帯で作られる炻器せっき質の陶器。草創は平安末期で、中世には甕かめ・壺・鉢を量産。江戸後期からは茶器も焼き、明治以降は急須などの朱泥しゅでい製品で知られる。土管・タイル・植木鉢なども産出。とこなべやき。
⇒とこなめ【常滑】
 トケイソウ
提供:OPO
トケイソウ
提供:OPO
 クダモノトケイソウ
撮影:関戸 勇
クダモノトケイソウ
撮影:関戸 勇
 ⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐だい【時計台】
上部に巨大な時計を設けた建物や塔。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐の‐ま【土圭の間】
江戸城内、御用部屋の北方、廊下を隔てて老中・若年寄の部屋に接し、時計が置かれ、坊主が詰めて時刻報知の任にあたった部屋。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐まわり【時計回り】‥マハリ
時計の針がまわる方向にまわること。右まわり。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とげ‐うお【棘魚】‥ウヲ
トゲウオ科の硬骨魚の総称。淡水産。イトヨ・トミヨなど。背びれ・腹びれ・臀しりびれに強いとげがあるからいう。巣を作ることで知られる。
トミヨ
提供:東京動物園協会
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐だい【時計台】
上部に巨大な時計を設けた建物や塔。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐の‐ま【土圭の間】
江戸城内、御用部屋の北方、廊下を隔てて老中・若年寄の部屋に接し、時計が置かれ、坊主が詰めて時刻報知の任にあたった部屋。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とけい‐まわり【時計回り】‥マハリ
時計の針がまわる方向にまわること。右まわり。
⇒と‐けい【時計・土圭】
とげ‐うお【棘魚】‥ウヲ
トゲウオ科の硬骨魚の総称。淡水産。イトヨ・トミヨなど。背びれ・腹びれ・臀しりびれに強いとげがあるからいう。巣を作ることで知られる。
トミヨ
提供:東京動物園協会
 とけ‐こ・む【溶け込む】
〔自五〕
①溶けて、液体や気体の中に入って一つになる。
②自然環境の中や人々の組織の中に入って、その雰囲気になじんで一体となる。「風景に―・む」
ど‐げざ【土下座】
相手に恭順の意を表すため、地上に跪ひざまずいて礼をすること。「道端に―する」「―してあやまる」
とけし‐な・し
〔形ク〕
もどかしい。じれったい。待ちどおしい。好色五人女5「三十五日の立つを―・く」
とげ‐だ・つ【刺立つ】
〔自五〕
①とげが立つ。
②いらだつ。かどだつ。とげとげしくなる。
ど‐けち
(ドは接頭語)非常にけちであることをののしっていう語。
と‐けつ【吐血】
口から血を吐くこと。また、その血。多く消化管の出血についていう。→喀血かっけつ
と‐けつ【兎欠】
(→)兎唇としんに同じ。〈伊呂波字類抄〉
とげつ‐きょう【渡月橋】‥ケウ
京都市右京区の嵐山の麓を流れる保津川に架かる橋。
渡月橋
撮影:山梨勝弘
とけ‐こ・む【溶け込む】
〔自五〕
①溶けて、液体や気体の中に入って一つになる。
②自然環境の中や人々の組織の中に入って、その雰囲気になじんで一体となる。「風景に―・む」
ど‐げざ【土下座】
相手に恭順の意を表すため、地上に跪ひざまずいて礼をすること。「道端に―する」「―してあやまる」
とけし‐な・し
〔形ク〕
もどかしい。じれったい。待ちどおしい。好色五人女5「三十五日の立つを―・く」
とげ‐だ・つ【刺立つ】
〔自五〕
①とげが立つ。
②いらだつ。かどだつ。とげとげしくなる。
ど‐けち
(ドは接頭語)非常にけちであることをののしっていう語。
と‐けつ【吐血】
口から血を吐くこと。また、その血。多く消化管の出血についていう。→喀血かっけつ
と‐けつ【兎欠】
(→)兎唇としんに同じ。〈伊呂波字類抄〉
とげつ‐きょう【渡月橋】‥ケウ
京都市右京区の嵐山の麓を流れる保津川に架かる橋。
渡月橋
撮影:山梨勝弘
 とげっ‐ぽう【吐月峰】
①静岡市丸子付近の地。連歌師宗長が草庵を営み吐月峰柴屋軒と命名したという。
②(1に産する竹で製したものが多く世に行われたことによる)煙草盆の灰吹。
ドケティズム【Docetism】
イエス=キリストの神性のみを認め、その人間的生(誕生や十字架での死など)は仮象であるとし、受肉を否定するグノーシス思想。仮現論。
とげ‐とげ【刺刺】
①多くのとげ。また、一面にとげ立っているさま。
②言動・態度がきつく近づきにくいさま。「―した物言い」
とげとげ‐し・い【刺刺しい】
〔形〕[文]とげとげ・し(シク)
①とげ立っている。森鴎外、青年「器械刈にした頭の、筋太な、―・い髪には」
②態度や言葉つきが意地悪で角立っている。「―・い目つき」
とげ‐な・し【利気無し】
〔形ク〕
しっかりした所がない。賢い様子がない。竹取物語「これを聞きてぞ―・きものをばあへなしといひける」
とげ‐ぬき【刺抜き】
肌にささったとげを抜くこと。また、それに用いる具。
⇒とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】
とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】‥ヂザウ
東京都豊島区巣鴨にある曹洞宗の寺、高岩寺の俗称。本尊の延命地蔵菩薩は諸病に霊験があるとされる。毎月4の日が縁日。
⇒とげ‐ぬき【刺抜き】
とげ‐ねずみ【棘鼠】
ネズミ科トゲネズミ属の哺乳類。奄美大島・徳之島・沖縄だけにすむ。奄美産は体長15センチメートルほど、沖縄本島産は少し大きく別種とされる。背は黒く、体側から腹面は橙色となる。荒い刺し毛をもつ。天然記念物。
と・ける【解ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
結ばれていたり、固まったり、閉じたり、不明だったりしたものが、ゆるめほぐれた状態になる意。
➊結ばれていたものがばらばらになる。
①結び目がほどける。万葉集14「昼―・けば―・けなへ紐のわが背なにあひ寄るとかも夜―・けやすけ」。「帯が―・ける」
②しこりになっていた気持がさっぱりする。万葉集2「磐代の野中に立てる結び松情こころも―・けず古思ほゆ」。「誤解が―・ける」
③心がゆるむ。安心する。万葉集17「よろづ世と心は―・けて吾がせこがつみし手見つつしのびかねつも」。源氏物語空蝉「心―・けたる寝いだにねられずなむ」。「警戒心が―・ける」
④制約や契約などの束縛が除かれる。「禁が―・ける」
⑤警備などで固められていた態勢がゆるむ。「包囲が―・ける」
➋職などから離れる。解任される。源氏物語関屋「その弟の右近の尉―・けて御供にくだりしをぞ」。「任が―・ける」
➌不明のものが明らかになる。
①答が出る。「問題が―・ける」
②納得がゆく。解釈がつく。「疑義が―・ける」
と・ける【溶ける・融ける・熔ける・鎔ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
①融解する。固体・固形物が液状になる。源氏物語末摘花「朝日さす軒の垂氷は―・けながら」。「雪が―・ける」
②液体に他の物質がまざって均一な液体になる。「食塩は水に―・ける」
◇「解ける」とも書く。「熔」「鎔」は、金属の場合に使う。
と・げる【遂げる】
〔他下一〕[文]と・ぐ(下二)
①はたす。成しおえる。成就させる。万葉集3「思へりし心は―・げず」。「本懐を―・げる」
②最後にそういう結果になる。「悲壮な最期を―・げる」
ど・ける【退ける】
〔他下一〕[文]ど・く(下二)
その場所からほかへうつす。どかす。「石を脇へ―・ける」
と‐けん【杜鵑】
〔動〕ホトトギスの漢名。文華秀麗集「―の啼序春将に闌けむとし」
⇒とけん‐か【杜鵑花】
ど‐けん【土建】
土木と建築。「―屋」
とけん‐か【杜鵑花】‥クワ
〔植〕サツキツツジの別称。〈元和本下学集〉
⇒と‐けん【杜鵑】
とこ【床】
①1段高く設けた平らな所。ゆか。新撰字鏡7「
とげっ‐ぽう【吐月峰】
①静岡市丸子付近の地。連歌師宗長が草庵を営み吐月峰柴屋軒と命名したという。
②(1に産する竹で製したものが多く世に行われたことによる)煙草盆の灰吹。
ドケティズム【Docetism】
イエス=キリストの神性のみを認め、その人間的生(誕生や十字架での死など)は仮象であるとし、受肉を否定するグノーシス思想。仮現論。
とげ‐とげ【刺刺】
①多くのとげ。また、一面にとげ立っているさま。
②言動・態度がきつく近づきにくいさま。「―した物言い」
とげとげ‐し・い【刺刺しい】
〔形〕[文]とげとげ・し(シク)
①とげ立っている。森鴎外、青年「器械刈にした頭の、筋太な、―・い髪には」
②態度や言葉つきが意地悪で角立っている。「―・い目つき」
とげ‐な・し【利気無し】
〔形ク〕
しっかりした所がない。賢い様子がない。竹取物語「これを聞きてぞ―・きものをばあへなしといひける」
とげ‐ぬき【刺抜き】
肌にささったとげを抜くこと。また、それに用いる具。
⇒とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】
とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】‥ヂザウ
東京都豊島区巣鴨にある曹洞宗の寺、高岩寺の俗称。本尊の延命地蔵菩薩は諸病に霊験があるとされる。毎月4の日が縁日。
⇒とげ‐ぬき【刺抜き】
とげ‐ねずみ【棘鼠】
ネズミ科トゲネズミ属の哺乳類。奄美大島・徳之島・沖縄だけにすむ。奄美産は体長15センチメートルほど、沖縄本島産は少し大きく別種とされる。背は黒く、体側から腹面は橙色となる。荒い刺し毛をもつ。天然記念物。
と・ける【解ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
結ばれていたり、固まったり、閉じたり、不明だったりしたものが、ゆるめほぐれた状態になる意。
➊結ばれていたものがばらばらになる。
①結び目がほどける。万葉集14「昼―・けば―・けなへ紐のわが背なにあひ寄るとかも夜―・けやすけ」。「帯が―・ける」
②しこりになっていた気持がさっぱりする。万葉集2「磐代の野中に立てる結び松情こころも―・けず古思ほゆ」。「誤解が―・ける」
③心がゆるむ。安心する。万葉集17「よろづ世と心は―・けて吾がせこがつみし手見つつしのびかねつも」。源氏物語空蝉「心―・けたる寝いだにねられずなむ」。「警戒心が―・ける」
④制約や契約などの束縛が除かれる。「禁が―・ける」
⑤警備などで固められていた態勢がゆるむ。「包囲が―・ける」
➋職などから離れる。解任される。源氏物語関屋「その弟の右近の尉―・けて御供にくだりしをぞ」。「任が―・ける」
➌不明のものが明らかになる。
①答が出る。「問題が―・ける」
②納得がゆく。解釈がつく。「疑義が―・ける」
と・ける【溶ける・融ける・熔ける・鎔ける】
〔自下一〕[文]と・く(下二)
①融解する。固体・固形物が液状になる。源氏物語末摘花「朝日さす軒の垂氷は―・けながら」。「雪が―・ける」
②液体に他の物質がまざって均一な液体になる。「食塩は水に―・ける」
◇「解ける」とも書く。「熔」「鎔」は、金属の場合に使う。
と・げる【遂げる】
〔他下一〕[文]と・ぐ(下二)
①はたす。成しおえる。成就させる。万葉集3「思へりし心は―・げず」。「本懐を―・げる」
②最後にそういう結果になる。「悲壮な最期を―・げる」
ど・ける【退ける】
〔他下一〕[文]ど・く(下二)
その場所からほかへうつす。どかす。「石を脇へ―・ける」
と‐けん【杜鵑】
〔動〕ホトトギスの漢名。文華秀麗集「―の啼序春将に闌けむとし」
⇒とけん‐か【杜鵑花】
ど‐けん【土建】
土木と建築。「―屋」
とけん‐か【杜鵑花】‥クワ
〔植〕サツキツツジの別称。〈元和本下学集〉
⇒と‐けん【杜鵑】
とこ【床】
①1段高く設けた平らな所。ゆか。新撰字鏡7「 、止己」
②寝るために設ける所。ねどこ。寝台。また、寝具。万葉集5「明星の明くる朝は敷
、止己」
②寝るために設ける所。ねどこ。寝台。また、寝具。万葉集5「明星の明くる朝は敷 しきたえの―の辺去らず」。「―を敷く」
③畳のしん。↔畳表。
④川の底。かわどこ。
⑤苗を育てるところ。なえどこ。
⑥「床の間」の略。
⑦髪結床。床屋。
⑧鉄床かなとこの略。
⑨牛車ぎっしゃの屋形。くるまばこ。
⑩犂すきの底部。いさり。
⑪和船の櫓床ろどこ・舵床かじどこなどの総称。特に、舵床。
⑫船床、また船床銭・船税のこと。
⇒床に就く
⇒床離る
⇒床旧る
⇒床をあげる
⇒床をとる
とこ【所】
①「ところ」の俗語。浮世風呂2「おめヘン―のおかみさんも」
②(「が」に続けて)…ぐらい。…ほど。「千円が―買う」
と‐こ【独鈷】
⇒とっこ。枕草子25「―や数珠などもたせ」
とこ【常】
〔接頭〕
いつも変わらない、永遠であるの意を表す語。古事記上「常を訓みて―といひ」。拾遺和歌集恋「己がつまこそ―めづらなれ」
と‐ご【都護】
①都護府の長官。前漢の宣帝の時の西域都護に始まる。
②按察使あぜちの唐名。
ど‐こ【土戸】
平安時代における地方の農民。京都に住むものを京戸というのに対する。地戸。
ど‐こ【土鼓】
周代の古楽器。瓦または土製の胴の両面に革を張った鼓。草を結んでつくった桴ばちで打つ。
ど‐こ【何処・何所】
〔代〕
(イドコの約)場所・所在・位置をはっきり定めずに表し、または問うのに使う語。将門記承徳点「何トコにか往ゆき何にか来りて、誰が家にか宿る」。「―の人」「―まで話したっけ」→どれ(何)
⇒何処の馬の骨
⇒何処の烏も黒い
⇒何処吹く風
⇒何処方量も無い
⇒何処を押せばそんな音が出る
ど‐ご【土語】
①その地の土着の住民が使用することば。
②その地に特有のことば。方言や俗用語。
とこ‐あげ【床上げ】
長い病気が全快して、また産後の体が回復して、寝床をかたづけること。また、その祝い。床払い。「―を祝う」
とこ‐あしらい【床あしらい】‥アシラヒ
遊女などの閨中けいちゅうでの客あしらい。
とこ‐い【常井】‥ヰ
水が常に絶えることのない井戸。新撰六帖2「絶えぬ―のゐづつなりけり」
とこ‐いた【床板】
床の間に張る板。
とごい‐ど【詛戸】トゴヒ‥
人をのろうのに用いた物。呪詛の品物。古事記中「その―を返さしめき」
どこ‐いら【何処いら】
〔代〕
どのあたり。どのへん。
とこ‐いり【床入り】
①寝所に入ること。
②婚礼の夜、新夫婦が初めて床を共にすること。
と‐こう【杜康】‥カウ
中国の伝説で、最初に酒を造ったとされる人物。また、酒のこと。
と‐こう【杜衡】‥カウ
〔植〕カンアオイの漢名。〈伊呂波字類抄〉
と‐こう【徒行】‥カウ
歩いてゆくこと。歩行。
と‐こう【都講】‥カウ
①塾生の長。塾頭。
②(→)尚復しょうふくに同じ。
と‐こう【渡口】
渡し場。
と‐こう【渡航】‥カウ
船や航空機で海をわたること。海外へ行くこと。「アメリカへ―する」
⇒とこう‐めんじょう【渡航免状】
と‐こう‥カウ
〔副〕
(「兎角」と当て字)トカクの音便。
⇒とこう‐して
と‐ごう【兎毫】‥ガウ
筆の別称。日葡辞書「トガウニアタワズ」
とご・う【詛ふ】トゴフ
〔他四〕
のろう。雄略紀「刑つみせらるるに臨みて井を指して―・ひて曰く」
ど‐こう【土工】
①築堤・道路工事など、土砂を取り扱う土木工事。土功。
②土木工事に従う労働者。
⇒どこう‐し【土工司】
ど‐こう【土公】
土公神の略。
⇒どこう‐じん【土公神】
ど‐こう【土侯】
土着の諸侯。部族・藩・地方王国などの首長。
⇒どこう‐こく【土侯国】
ど‐こう【土貢】
(トコウとも)土産どさんのみつぎもの。田租のこと。平家物語7「土宜―万物を押領す」
ど‐こう【土寇】
土民の一揆。土匪。
ど‐こう【土窖】‥カウ
あなぐら。
ど‐こう【土壙】‥クワウ
(「壙」は穴・墓穴の意)地表面を掘りくぼめて造られた墓穴。「―墓」
ど‐ごう【土豪】‥ガウ
その土地の豪族。
⇒どごう‐れっしん【土豪劣紳】
ど‐ごう【怒号】‥ガウ
①いかりさけぶこと。また、その声。「―が乱れ飛ぶ」
②風・波などがはげしい音を立てるさまをいう。「荒海が―する」
とこうえん【都江堰】‥カウ‥
(Dujiangyan)
①中国四川省中部の都市。人口62万2千(2000)。
②1の西部、岷江中流にある古代以来の水利施設。秦の昭王の代、蜀の大守であった李氷が築造。現在も成都平原の治水に利用。世界遺産。
都江堰
提供:JTBフォト
しきたえの―の辺去らず」。「―を敷く」
③畳のしん。↔畳表。
④川の底。かわどこ。
⑤苗を育てるところ。なえどこ。
⑥「床の間」の略。
⑦髪結床。床屋。
⑧鉄床かなとこの略。
⑨牛車ぎっしゃの屋形。くるまばこ。
⑩犂すきの底部。いさり。
⑪和船の櫓床ろどこ・舵床かじどこなどの総称。特に、舵床。
⑫船床、また船床銭・船税のこと。
⇒床に就く
⇒床離る
⇒床旧る
⇒床をあげる
⇒床をとる
とこ【所】
①「ところ」の俗語。浮世風呂2「おめヘン―のおかみさんも」
②(「が」に続けて)…ぐらい。…ほど。「千円が―買う」
と‐こ【独鈷】
⇒とっこ。枕草子25「―や数珠などもたせ」
とこ【常】
〔接頭〕
いつも変わらない、永遠であるの意を表す語。古事記上「常を訓みて―といひ」。拾遺和歌集恋「己がつまこそ―めづらなれ」
と‐ご【都護】
①都護府の長官。前漢の宣帝の時の西域都護に始まる。
②按察使あぜちの唐名。
ど‐こ【土戸】
平安時代における地方の農民。京都に住むものを京戸というのに対する。地戸。
ど‐こ【土鼓】
周代の古楽器。瓦または土製の胴の両面に革を張った鼓。草を結んでつくった桴ばちで打つ。
ど‐こ【何処・何所】
〔代〕
(イドコの約)場所・所在・位置をはっきり定めずに表し、または問うのに使う語。将門記承徳点「何トコにか往ゆき何にか来りて、誰が家にか宿る」。「―の人」「―まで話したっけ」→どれ(何)
⇒何処の馬の骨
⇒何処の烏も黒い
⇒何処吹く風
⇒何処方量も無い
⇒何処を押せばそんな音が出る
ど‐ご【土語】
①その地の土着の住民が使用することば。
②その地に特有のことば。方言や俗用語。
とこ‐あげ【床上げ】
長い病気が全快して、また産後の体が回復して、寝床をかたづけること。また、その祝い。床払い。「―を祝う」
とこ‐あしらい【床あしらい】‥アシラヒ
遊女などの閨中けいちゅうでの客あしらい。
とこ‐い【常井】‥ヰ
水が常に絶えることのない井戸。新撰六帖2「絶えぬ―のゐづつなりけり」
とこ‐いた【床板】
床の間に張る板。
とごい‐ど【詛戸】トゴヒ‥
人をのろうのに用いた物。呪詛の品物。古事記中「その―を返さしめき」
どこ‐いら【何処いら】
〔代〕
どのあたり。どのへん。
とこ‐いり【床入り】
①寝所に入ること。
②婚礼の夜、新夫婦が初めて床を共にすること。
と‐こう【杜康】‥カウ
中国の伝説で、最初に酒を造ったとされる人物。また、酒のこと。
と‐こう【杜衡】‥カウ
〔植〕カンアオイの漢名。〈伊呂波字類抄〉
と‐こう【徒行】‥カウ
歩いてゆくこと。歩行。
と‐こう【都講】‥カウ
①塾生の長。塾頭。
②(→)尚復しょうふくに同じ。
と‐こう【渡口】
渡し場。
と‐こう【渡航】‥カウ
船や航空機で海をわたること。海外へ行くこと。「アメリカへ―する」
⇒とこう‐めんじょう【渡航免状】
と‐こう‥カウ
〔副〕
(「兎角」と当て字)トカクの音便。
⇒とこう‐して
と‐ごう【兎毫】‥ガウ
筆の別称。日葡辞書「トガウニアタワズ」
とご・う【詛ふ】トゴフ
〔他四〕
のろう。雄略紀「刑つみせらるるに臨みて井を指して―・ひて曰く」
ど‐こう【土工】
①築堤・道路工事など、土砂を取り扱う土木工事。土功。
②土木工事に従う労働者。
⇒どこう‐し【土工司】
ど‐こう【土公】
土公神の略。
⇒どこう‐じん【土公神】
ど‐こう【土侯】
土着の諸侯。部族・藩・地方王国などの首長。
⇒どこう‐こく【土侯国】
ど‐こう【土貢】
(トコウとも)土産どさんのみつぎもの。田租のこと。平家物語7「土宜―万物を押領す」
ど‐こう【土寇】
土民の一揆。土匪。
ど‐こう【土窖】‥カウ
あなぐら。
ど‐こう【土壙】‥クワウ
(「壙」は穴・墓穴の意)地表面を掘りくぼめて造られた墓穴。「―墓」
ど‐ごう【土豪】‥ガウ
その土地の豪族。
⇒どごう‐れっしん【土豪劣紳】
ど‐ごう【怒号】‥ガウ
①いかりさけぶこと。また、その声。「―が乱れ飛ぶ」
②風・波などがはげしい音を立てるさまをいう。「荒海が―する」
とこうえん【都江堰】‥カウ‥
(Dujiangyan)
①中国四川省中部の都市。人口62万2千(2000)。
②1の西部、岷江中流にある古代以来の水利施設。秦の昭王の代、蜀の大守であった李氷が築造。現在も成都平原の治水に利用。世界遺産。
都江堰
提供:JTBフォト
 どこう‐こく【土侯国】
従来からの首長や実力者の支配する国家。主としてイギリスの保護下にあるものをいった。→藩王国
⇒ど‐こう【土侯】
どこう‐し【土工司】
律令制で、宮内省に属し、壁塗・製瓦・石灰焼などをつかさどった官司。つちたくみのつかさ。
⇒ど‐こう【土工】
とこう‐して‥カウ‥
あれこれして。かろうじて。平治物語(金刀比羅本)「―馬にのせられ」
⇒と‐こう
どこう‐じん【土公神】
⇒どくじん
⇒ど‐こう【土公】
とこう‐めんじょう【渡航免状】‥カウ‥ジヤウ
(→)旅券に同じ。
⇒と‐こう【渡航】
どごう‐れっしん【土豪劣紳】‥ガウ‥
中国で、官僚や軍閥と結んで農民を搾取した大地主・資産家の蔑称。
⇒ど‐ごう【土豪】
と‐ごえ【と声】‥ゴヱ
「とほ(遠)声」の略か。また、「と(利)声」「と(外)声」「と(常)声」の意か。曾丹集「よそ耳に鹿の―を聞きしより」
とこ‐おおい【床覆い】‥オホヒ
水分の放散または温度の低下を防ぐため、苗床に筵むしろなどの覆いを施し、苗を保護する装置。
とこ‐おとめ【常少女】‥ヲトメ
とこしえに若い女。いつもかわらぬ若々しい少女。万葉集1「常にもがもな―にて」
ド‐ゴール【Charles de Gaulle】
フランスの軍人・政治家。自国の対ドイツ降伏後、1940〜44年ロンドンに自由フランス政府を作り、本国の抵抗運動と提携。44〜46年共和国臨時政府主席。47年右派を糾合してフランス国民連合を組織。一時引退したが、58年アルジェリアをめぐる危機に際し政府を組織、新憲法により第五共和制初代大統領。62年アルジェリア危機を収拾。核兵器保有などの自主外交を展開。68年五月革命後、国民投票に失敗し辞任。(1890〜1970)
どこ‐か【何処か】
①はっきり特定できない場所、不定の場所を指す語。「―へ遊びに行こう」
②はっきりとはいえないが、何となく。どことなく。「―すっきりしない」
とこ‐がえり【床反り】‥ガヘリ
眠れないで床の上で寝返りをすること。
とこ‐かざり【床飾り】
床の間の装飾。床に掛物をかけ挿花・置物などをおくこと。また、その掛物・置物など。
とこ‐かため【床固め】
河床や橋脚が掘り返されないように、石やコンクリートで河床を強化すること。
とこ‐がまち【床框】
床の間の前端の化粧横木。かまち。とこぶち。
とこ‐かみゆい【床髪結】‥ユヒ
取りたためる簡単な仮店を作って営業している髪結屋。橋台や川岸に多かった。浮世草子、御前義経記「―の目をすりて暖簾かけるを見て」
とこく【杜国】
⇒つぼいとこく(坪井杜国)
とこ‐げいしゃ【床芸者】
芸者を名のりながら、芸よりも床をつとめるのをもっぱらとする一種の私娼。誹風柳多留8「―ずるにかけてはにちうなり」
とこ‐ことば【床言葉】
遊女などが閨ねやに入る前にする決り文句の挨拶。好色一代女2「大かた仕掛定まつての―あり」
と‐ごころ【利心】
するどい心。しっかりした心。万葉集12「わが胸は破われてくだけて―もなし」
とこ‐さかずき【床盃】‥サカヅキ
婚礼の夜、新夫婦が寝所で盃をとりかわす儀式。
とこ‐ざし【床挿し】
挿木法の一つ。挿穂を苗床に挿すこと。
ドコサヘキサエン‐さん【ドコサヘキサエン酸】
(docosahexaenoic acid)不飽和脂肪酸の一種。分子式C21H31COOH マグロ・サバなどの魚油に多く含まれ、血栓・動脈硬化の予防などの効果が研究されている。DHA
とこ・し【常し・長し・永久し】
〔形シク〕
(「常とこ」の形容詞形)永久である。常にある。万葉集7「いや―・しくにわれかへり見む」
とこし‐え【常しえ・永久】‥ヘ
永くかわらないこと。いつまでも続くこと。とこしなえ。万葉集18「―にかくしもあらめや」。「―の愛を誓う」
とこ‐しき【床敷・褥】
①座席などに敷く物。しとね。天武紀下「氈おりかもの―」
②船床に敷く板。
とこし‐なえ【常しなへ・永久】‥ナヘ
(→)「とこしえ」に同じ。
とこ‐しばり【床縛り】
牛車ぎっしゃの屋形を車軸に縛る縄。落窪物語2「一の車の―をふつふつと切りてければ」
とこ‐しめ【床締め】
水漏れを防ぐため、水田の床に粘土などを入れること。
とこ‐じもの【床じもの】
(ジモノは接尾語)床のように。万葉集5「―打ち臥こい伏して」
とこ‐じょうず【床上手】‥ジヤウ‥
床あしらいのうまいこと。また、その人。
とこ‐じらみ【床蝨】
カメムシ目トコジラミ科の昆虫。体長約5ミリメートル。円盤状で扁平、翅はねは退化して小さく、全体赤褐色。アジア南部の原産で、室内に生息し、夜行性。人畜から吸血し、激しいかゆみと痛みを起こさせる。南京虫。鎮台虫。
とこじらみ
どこう‐こく【土侯国】
従来からの首長や実力者の支配する国家。主としてイギリスの保護下にあるものをいった。→藩王国
⇒ど‐こう【土侯】
どこう‐し【土工司】
律令制で、宮内省に属し、壁塗・製瓦・石灰焼などをつかさどった官司。つちたくみのつかさ。
⇒ど‐こう【土工】
とこう‐して‥カウ‥
あれこれして。かろうじて。平治物語(金刀比羅本)「―馬にのせられ」
⇒と‐こう
どこう‐じん【土公神】
⇒どくじん
⇒ど‐こう【土公】
とこう‐めんじょう【渡航免状】‥カウ‥ジヤウ
(→)旅券に同じ。
⇒と‐こう【渡航】
どごう‐れっしん【土豪劣紳】‥ガウ‥
中国で、官僚や軍閥と結んで農民を搾取した大地主・資産家の蔑称。
⇒ど‐ごう【土豪】
と‐ごえ【と声】‥ゴヱ
「とほ(遠)声」の略か。また、「と(利)声」「と(外)声」「と(常)声」の意か。曾丹集「よそ耳に鹿の―を聞きしより」
とこ‐おおい【床覆い】‥オホヒ
水分の放散または温度の低下を防ぐため、苗床に筵むしろなどの覆いを施し、苗を保護する装置。
とこ‐おとめ【常少女】‥ヲトメ
とこしえに若い女。いつもかわらぬ若々しい少女。万葉集1「常にもがもな―にて」
ド‐ゴール【Charles de Gaulle】
フランスの軍人・政治家。自国の対ドイツ降伏後、1940〜44年ロンドンに自由フランス政府を作り、本国の抵抗運動と提携。44〜46年共和国臨時政府主席。47年右派を糾合してフランス国民連合を組織。一時引退したが、58年アルジェリアをめぐる危機に際し政府を組織、新憲法により第五共和制初代大統領。62年アルジェリア危機を収拾。核兵器保有などの自主外交を展開。68年五月革命後、国民投票に失敗し辞任。(1890〜1970)
どこ‐か【何処か】
①はっきり特定できない場所、不定の場所を指す語。「―へ遊びに行こう」
②はっきりとはいえないが、何となく。どことなく。「―すっきりしない」
とこ‐がえり【床反り】‥ガヘリ
眠れないで床の上で寝返りをすること。
とこ‐かざり【床飾り】
床の間の装飾。床に掛物をかけ挿花・置物などをおくこと。また、その掛物・置物など。
とこ‐かため【床固め】
河床や橋脚が掘り返されないように、石やコンクリートで河床を強化すること。
とこ‐がまち【床框】
床の間の前端の化粧横木。かまち。とこぶち。
とこ‐かみゆい【床髪結】‥ユヒ
取りたためる簡単な仮店を作って営業している髪結屋。橋台や川岸に多かった。浮世草子、御前義経記「―の目をすりて暖簾かけるを見て」
とこく【杜国】
⇒つぼいとこく(坪井杜国)
とこ‐げいしゃ【床芸者】
芸者を名のりながら、芸よりも床をつとめるのをもっぱらとする一種の私娼。誹風柳多留8「―ずるにかけてはにちうなり」
とこ‐ことば【床言葉】
遊女などが閨ねやに入る前にする決り文句の挨拶。好色一代女2「大かた仕掛定まつての―あり」
と‐ごころ【利心】
するどい心。しっかりした心。万葉集12「わが胸は破われてくだけて―もなし」
とこ‐さかずき【床盃】‥サカヅキ
婚礼の夜、新夫婦が寝所で盃をとりかわす儀式。
とこ‐ざし【床挿し】
挿木法の一つ。挿穂を苗床に挿すこと。
ドコサヘキサエン‐さん【ドコサヘキサエン酸】
(docosahexaenoic acid)不飽和脂肪酸の一種。分子式C21H31COOH マグロ・サバなどの魚油に多く含まれ、血栓・動脈硬化の予防などの効果が研究されている。DHA
とこ・し【常し・長し・永久し】
〔形シク〕
(「常とこ」の形容詞形)永久である。常にある。万葉集7「いや―・しくにわれかへり見む」
とこし‐え【常しえ・永久】‥ヘ
永くかわらないこと。いつまでも続くこと。とこしなえ。万葉集18「―にかくしもあらめや」。「―の愛を誓う」
とこ‐しき【床敷・褥】
①座席などに敷く物。しとね。天武紀下「氈おりかもの―」
②船床に敷く板。
とこし‐なえ【常しなへ・永久】‥ナヘ
(→)「とこしえ」に同じ。
とこ‐しばり【床縛り】
牛車ぎっしゃの屋形を車軸に縛る縄。落窪物語2「一の車の―をふつふつと切りてければ」
とこ‐しめ【床締め】
水漏れを防ぐため、水田の床に粘土などを入れること。
とこ‐じもの【床じもの】
(ジモノは接尾語)床のように。万葉集5「―打ち臥こい伏して」
とこ‐じょうず【床上手】‥ジヤウ‥
床あしらいのうまいこと。また、その人。
とこ‐じらみ【床蝨】
カメムシ目トコジラミ科の昆虫。体長約5ミリメートル。円盤状で扁平、翅はねは退化して小さく、全体赤褐色。アジア南部の原産で、室内に生息し、夜行性。人畜から吸血し、激しいかゆみと痛みを起こさせる。南京虫。鎮台虫。
とこじらみ
 とこ‐すき【床犂】
床すなわち底のある犂。日本の従来の犂は多くこれである。
とこ‐すずみ【床涼み】
夏の夜、床ゆかを屋外に設けて涼むこと。特に、京都四条河原辺で床を設けて納涼すること。ゆかすずみ。
とこ‐ずれ【床擦れ】
(→)褥瘡じょくそうに同じ。
どこ‐そこ【何処其処・何所其所】
〔代〕
(「どこ」と「そこ」を重ねた語)具体的にそこと示されない場所。「―のだれと名乗るほどの者でない」
とこ‐だたみ【床畳】
床の間に敷く畳。雨月物語4「板敷の間に―を設けて」
とこ‐だな【床棚】
床脇にある棚。
とこ‐つ‐くに【常つ国】
死の国。よみのくに。黄泉。雄略紀「謂おもはざりき…―に至るといふことを」
とこ‐つち【床土】
床の間の壁などを塗る上等の土。
とこ‐つ‐み【床つ身】
病床についている身。〈色葉字類抄〉
とこ‐つ‐みかど【常つ御門】
永久に変わらない宮殿。永久の御所。万葉集2「よそに見し檀まゆみの岡も君ませば―ととのゐするかも」
とこ‐づめ【床詰め】
①いつまでも病床についていること。また、その身。
②(→)褥瘡じょくそうに同じ。
とこ‐とこ
①足早に狭い歩幅で歩くさま。「幼児が―歩く」
②電車が遅いスピードでつかえながら進むさま。「登山電車が―と走る」
どこ‐と‐なく【何処と無く】
どこと定まったことはないが、そう感じられて。なんとなく。「―愁いをふくんだ顔」
どこ‐とも‐なし【何処とも無し】
①どこと定まったところがなく、たよりにならない。平家物語10「下臈はどこともなき物なれば」
②どこが出所ともわからない。浄瑠璃、傾城反魂香「―の取り沙汰」
とこ‐とわ【常・永久】‥トハ
(平安時代までトコトバ)
①永久にかわらないこと。とこしえ。万葉集2「わがみかど千代―に栄えむと」
②いつも。つね。〈類聚名義抄〉
とこ‐とん
①(副詞的にも使う)どんづまり。末の末。最後の最後。また、徹底的に。「―まで頑張る」「―話し合う」
②日本舞踊で足拍子の音。転じて踊りの意に用いる。
とことんやれ‐ぶし【とことんやれ節】
明治初年の流行歌。1868年(明治1)、官軍東征の際に歌われた。「とことんやれとんやれな」という囃子詞はやしことばを添える。一説に品川弥二郎作詞、大村益次郎作曲という。
とこ‐なか【床中】
ねどこのなか。また、ねどこの中央。古今和歌集雑「枕よりあとより恋のせめくればせんかたなみぞ―にをる」
とこ‐なつ【常夏】
①いつも夏のようであること。「―のハワイ」
②㋐(春から秋にわたって咲くからいう)セキチクの一変種。分岐した枝頂に濃紅色の五弁花を四季を通じて開花。〈[季]夏〉
㋑ナデシコの古名。〈[季]夏〉。源氏物語紅葉賀「―のはなやかに咲き出でたるを」
③襲かさねの色目。(→)「なでしこ」に同じ。
④紋所の名。(→)「なでしこ」に同じ。
⑤源氏物語の巻名。
⇒とこなつ‐づき【常夏月】
⇒とこなつ‐に【常夏に】
とこ‐なつか・し【常懐かし】
〔形シク〕
いつまでも変わらず親しみやすい。源氏物語常夏「なでしこの―・しき色を見ば」
とこなつ‐づき【常夏月】
(常夏の花の盛んな月の意)陰暦6月の異称。
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなつ‐に【常夏に】
夏の間ずっと。万葉集17「立山に降り置ける雪を―見れども飽かず」
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなみ【床次】
姓氏の一つ。
⇒とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】
とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】‥ラウ
政治家。鹿児島生れ。東大卒。官界より政友会に入り、その領袖となる。原・高橋内閣の内相など。政友本党総裁・民政党顧問を経て政友会に復帰、のち除名。(1866〜1935)
⇒とこなみ【床次】
とこ‐なめ【常滑】
①岩にいつも生えている水苔。また、水苔でいつもなめらかな岩床。万葉集1「見れど飽かぬ吉野の河の―の絶ゆることなくまた還り見む」
②河床の平らな岩の上を、少量の水が静かに流れている所。
とこなめ【常滑】
愛知県南西部の市。知多半島の西岸に位置し、常滑焼・土管・タイルなどの窯業が中心。海苔のりの養殖が盛ん。中部国際空港がある。とこなべ。人口5万1千。
⇒とこなめ‐やき【常滑焼】
とこなめ‐やき【常滑焼】
常滑市を中心にその付近一帯で作られる炻器せっき質の陶器。草創は平安末期で、中世には甕かめ・壺・鉢を量産。江戸後期からは茶器も焼き、明治以降は急須などの朱泥しゅでい製品で知られる。土管・タイル・植木鉢なども産出。とこなべやき。
⇒とこなめ【常滑】
とこ‐すき【床犂】
床すなわち底のある犂。日本の従来の犂は多くこれである。
とこ‐すずみ【床涼み】
夏の夜、床ゆかを屋外に設けて涼むこと。特に、京都四条河原辺で床を設けて納涼すること。ゆかすずみ。
とこ‐ずれ【床擦れ】
(→)褥瘡じょくそうに同じ。
どこ‐そこ【何処其処・何所其所】
〔代〕
(「どこ」と「そこ」を重ねた語)具体的にそこと示されない場所。「―のだれと名乗るほどの者でない」
とこ‐だたみ【床畳】
床の間に敷く畳。雨月物語4「板敷の間に―を設けて」
とこ‐だな【床棚】
床脇にある棚。
とこ‐つ‐くに【常つ国】
死の国。よみのくに。黄泉。雄略紀「謂おもはざりき…―に至るといふことを」
とこ‐つち【床土】
床の間の壁などを塗る上等の土。
とこ‐つ‐み【床つ身】
病床についている身。〈色葉字類抄〉
とこ‐つ‐みかど【常つ御門】
永久に変わらない宮殿。永久の御所。万葉集2「よそに見し檀まゆみの岡も君ませば―ととのゐするかも」
とこ‐づめ【床詰め】
①いつまでも病床についていること。また、その身。
②(→)褥瘡じょくそうに同じ。
とこ‐とこ
①足早に狭い歩幅で歩くさま。「幼児が―歩く」
②電車が遅いスピードでつかえながら進むさま。「登山電車が―と走る」
どこ‐と‐なく【何処と無く】
どこと定まったことはないが、そう感じられて。なんとなく。「―愁いをふくんだ顔」
どこ‐とも‐なし【何処とも無し】
①どこと定まったところがなく、たよりにならない。平家物語10「下臈はどこともなき物なれば」
②どこが出所ともわからない。浄瑠璃、傾城反魂香「―の取り沙汰」
とこ‐とわ【常・永久】‥トハ
(平安時代までトコトバ)
①永久にかわらないこと。とこしえ。万葉集2「わがみかど千代―に栄えむと」
②いつも。つね。〈類聚名義抄〉
とこ‐とん
①(副詞的にも使う)どんづまり。末の末。最後の最後。また、徹底的に。「―まで頑張る」「―話し合う」
②日本舞踊で足拍子の音。転じて踊りの意に用いる。
とことんやれ‐ぶし【とことんやれ節】
明治初年の流行歌。1868年(明治1)、官軍東征の際に歌われた。「とことんやれとんやれな」という囃子詞はやしことばを添える。一説に品川弥二郎作詞、大村益次郎作曲という。
とこ‐なか【床中】
ねどこのなか。また、ねどこの中央。古今和歌集雑「枕よりあとより恋のせめくればせんかたなみぞ―にをる」
とこ‐なつ【常夏】
①いつも夏のようであること。「―のハワイ」
②㋐(春から秋にわたって咲くからいう)セキチクの一変種。分岐した枝頂に濃紅色の五弁花を四季を通じて開花。〈[季]夏〉
㋑ナデシコの古名。〈[季]夏〉。源氏物語紅葉賀「―のはなやかに咲き出でたるを」
③襲かさねの色目。(→)「なでしこ」に同じ。
④紋所の名。(→)「なでしこ」に同じ。
⑤源氏物語の巻名。
⇒とこなつ‐づき【常夏月】
⇒とこなつ‐に【常夏に】
とこ‐なつか・し【常懐かし】
〔形シク〕
いつまでも変わらず親しみやすい。源氏物語常夏「なでしこの―・しき色を見ば」
とこなつ‐づき【常夏月】
(常夏の花の盛んな月の意)陰暦6月の異称。
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなつ‐に【常夏に】
夏の間ずっと。万葉集17「立山に降り置ける雪を―見れども飽かず」
⇒とこ‐なつ【常夏】
とこなみ【床次】
姓氏の一つ。
⇒とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】
とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】‥ラウ
政治家。鹿児島生れ。東大卒。官界より政友会に入り、その領袖となる。原・高橋内閣の内相など。政友本党総裁・民政党顧問を経て政友会に復帰、のち除名。(1866〜1935)
⇒とこなみ【床次】
とこ‐なめ【常滑】
①岩にいつも生えている水苔。また、水苔でいつもなめらかな岩床。万葉集1「見れど飽かぬ吉野の河の―の絶ゆることなくまた還り見む」
②河床の平らな岩の上を、少量の水が静かに流れている所。
とこなめ【常滑】
愛知県南西部の市。知多半島の西岸に位置し、常滑焼・土管・タイルなどの窯業が中心。海苔のりの養殖が盛ん。中部国際空港がある。とこなべ。人口5万1千。
⇒とこなめ‐やき【常滑焼】
とこなめ‐やき【常滑焼】
常滑市を中心にその付近一帯で作られる炻器せっき質の陶器。草創は平安末期で、中世には甕かめ・壺・鉢を量産。江戸後期からは茶器も焼き、明治以降は急須などの朱泥しゅでい製品で知られる。土管・タイル・植木鉢なども産出。とこなべやき。
⇒とこなめ【常滑】
どっ‐き【毒気】ドク‥🔗⭐🔉
どっ‐き【毒気】ドク‥
①毒を含んだ気。毒性。古今和歌集著聞集7「―治すべき由」
②⇒どっけ
どっ‐く【毒鼓】ドク‥🔗⭐🔉
どっ‐く【毒鼓】ドク‥
〔仏〕毒を塗った鼓。これを打てば聞く者みな死ぬという。涅槃経に出て、その教えが衆生しゅじょうの煩悩を殺害することをたとえていう。日蓮宗では、折伏しゃくぶくの方法として毒鼓結縁の談が盛んに行われる。↔天鼓てんく
どっ‐け【毒気】ドク‥🔗⭐🔉
どっけつ‐しょう【毒血症】ドク‥シヤウ🔗⭐🔉
どっけつ‐しょう【毒血症】ドク‥シヤウ
ジフテリア・破傷風・ガス壊疽えそなどで、細菌毒素が血液中に入り、全身に種々の障害をおこすもの。毒素血症。
○毒気に当てられるどっけにあてられる🔗⭐🔉
○毒気に当てられるどっけにあてられる
相手の気張った、または、ずうずうしい言動に意気阻喪する。
⇒どっ‐け【毒気】
とっけ‐も‐な・い
〔形〕
途方もない。とんでもない。浄瑠璃、一谷嫩軍記「やれやれ―・い」
とっけり
〔副〕
(「とっくり」の転か)ゆっくり。落ちついて。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「―夜の目も寝ねえせえだ」
○毒気を抜かれるどっけをぬかれる🔗⭐🔉
○毒気を抜かれるどっけをぬかれる
対抗心や気負った気持がそがれてくじける。どぎもを抜かれる。
⇒どっ‐け【毒気】
とっ‐けん【特権】トク‥
特定の身分や階級に属する人に特別に与えられる優越的な権利。
⇒とっけん‐かいきゅう【特権階級】
とつ‐げん【訥言】
①重苦しくしぶりがちなことば。
②どもることば。
どっ‐けん【独見】ドク‥
自分一人の見解。自分独特の見識。
とっけん‐かいきゅう【特権階級】トク‥キフ
優越権や支配権を有する人々または身分・階級。ヨーロッパ中世の貴族および僧侶や、今日の資本家・高級官僚・財産家など。
⇒とっ‐けん【特権】
とっこ
詐欺さぎ。かたり。盗人。「とっこの皮」とも。浄瑠璃、柏崎「―共につけられ迷惑に及び候」
とっ‐こ【独鈷】トク‥
(独鈷杵しょの略。ドッコとも。「鈷」は「股」の借字)
①両端が分岐していない金剛杵こんごうしょ。とこ。
独鈷
撮影:関戸 勇
 ②縦縞状に多くの独鈷1の形を連ねた文様を織り出した厚地の琥珀こはく織や博多織の称。また、その文様。→一本独鈷。
③僧家で鰹節かつおぶしの隠語。
⇒とっこ‐いし【独鈷石】
⇒とっこ‐しょ【独鈷杵】
⇒とっこ‐れい【独鈷鈴】
どっこい
〔感〕
(「何処どこへ」の転)
①(→)「どっこいしょ」に同じ。
②相手の行動などをさえぎり止める時に発する語。「―そうはさせぬ」
③民謡などの囃子詞はやしことば。からめ節「お山繁昌と啼く烏、ハァ――」。「やっとこ―ほいさっさ」
⇒どっこい‐しょ
⇒どっこい‐どっこい
とっこ‐いし【独鈷石】トク‥
(ドッコイシとも)縄文時代後期・晩期の磨製石器の一種。形が独鈷1に似る。初めは一種の斧、のちには祭祀用となる。東日本で出土。雷鈷らいこ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
どっこい‐しょ
〔感〕
①力を入れる時、または大儀な時の掛け声。「―と立ち上がる」
②民謡などの囃子詞はやしことば。「草津よいとこ一度はおいで―」
⇒どっこい
どっこい‐どっこい
(「どっこい」の畳語)力や勢いがほぼ互角なさま。「―の力量」
⇒どっこい
とっ‐こう【特功】トク‥
特別にすぐれたいさお。
とっ‐こう【特効】トクカウ
特に著しいききめ。
⇒とっこう‐やく【特効薬】
とっ‐こう【特高】トクカウ
特別高等警察の略称。
とっ‐こう【特講】トクカウ
特別講義の略。
とっ‐こう【徳行】トクカウ
道徳にかなったよいおこない。「君子の―」
とっ‐こう【篤行】トクカウ
①篤実なおこない。人情に厚いおこない。「―の人」
②まじめで忠実なおこない。
とっ‐こう【篤厚】トク‥
人情にあついこと。懇切で実意のあること。
どっ‐こう【独行】ドクカウ
①自分一人で行くこと。みちづれなしに行くこと。
②他人の力を借りずに自分の力だけで行うこと。「独立―」
どっ‐こう【独航】ドクカウ
艦船が船団などに属さず、ただ1隻で航行すること。
⇒どっこう‐せん【独航船】
どっこう‐せん【独航船】ドクカウ‥
北洋の母船式サケ・マス漁業、カニ漁業などで、母船会社と買魚契約または傭船契約を結んで、母船に随伴し直接漁獲を行なった漁船。
⇒どっ‐こう【独航】
とっこう‐たい【特攻隊】トク‥
特別攻撃隊の略称。特に、太平洋戦争中、体当りの攻撃を行なった日本陸海軍の部隊。「神風―」
とっこう‐やく【特効薬】トクカウ‥
ある病気に対して著しくききめのある薬。
⇒とっ‐こう【特効】
とっこ‐しょ【独鈷杵】トク‥
(→)独鈷1に同じ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐こつ【突兀】
①山・岩などのけわしくそびえるさま。
②他にぬきんでて高いさま。
とっこ‐れい【独鈷鈴】トク‥
金剛鈴のうち、一端の把手とってが独鈷1の形をした法具。密教の修法で用いる。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐さ【咄嗟】
①舌うちして嘆くこと。また、息をはくこと。
②ちょっとの間。たちどころ。瞬間。易林本節用集「―、即時出来之義」。「―の間」「―の機転」「―に身をかわす」
とっさか【鶏冠】
(→)「とさか」に同じ。温故知新書「鶏坂冠、トツサカ」。狂言、鶏聟「紅葉にまがふ―蹴られては叶はじと」
⇒とっさか‐のり【鶏冠海苔】
とっ‐さか
心のとげとげしいさま。意地悪いさま。浄瑠璃、心中宵庚申「気の―な姑にせりせりいぢりたでられて」
とっさか‐のり【鶏冠海苔】
(→)「とさかのり」に同じ。
⇒とっさか【鶏冠】
とっ‐さき【突先】
突き出た先端。とがった端。
とっ‐さま【父様】
(トトサマの転)父の尊敬語。
どっさり
〔副〕
①数の多いさま。たくさん。花暦八笑人「おかかを―かいてくだつし」。「お土産―」
②重い物が落ちたり倒れたりするさま。どさり。どさっと。浮世風呂前「あふむけに―転ぶ」
ドッジ‐ボール【dodge ball】
二組に分かれてボールを投げ合い、相手の投球に当たらないようにしながら、より多くボールを相手側に当てた方を勝ちとする球戯。コートは円形と方形とがある。
とつ‐しゅうごう【凸集合】‥シフガフ
〔数〕平面または空間内の集合において、その集合の任意の2点を結ぶ線分がその集合に含まれるような集合。
とっ‐しゅつ【突出】
①突き破って出ること。また、だしぬけに飛び出すこと。「地下ガスの―」
②高く鋭く突き出ること。「―部」
③ほかのものよりいちだんと行動や状態が目立つこと。「―した軍事費」
とつ‐じょ【突如】
突然なさま。だしぬけなさま。「―立ち上がる」「―として現れる」
ドッジ‐ライン【Dodge's line】
1949年、GHQ経済顧問として来日したアメリカの銀行家ドッジ(Joseph Morrell D.1890〜1964)が日本経済の安定と自立のために与えた指示。また、その指示に従ってなされた財政金融引締め政策。
どっしり
①重くて据わりのよいさま。「―した家具」
②おもおもしく落ちついたさま。「―と構える」「―した態度」
とっ‐しん【突進】
勢いよくまっしぐらにつき進むこと。「ゴール目掛けて―する」
ドッジング【dodging】
サッカー・ラグビーなどで、相手をかわしながら前進すること。ドッジ。
とつ‐ぜん【突然】
にわかなさま。だしぬけ。不意。突如。「―の出来事」「―変心する」
⇒とつぜん‐し【突然死】
⇒とつぜん‐へんい【突然変異】
⇒とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
⇒とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
とつぜん‐し【突然死】
健康に見える人が突然死ぬこと。心臓・中枢神経・呼吸器などの疾患によるほか、乳幼児突然死症候群、青壮年のぽっくり病、特発性心筋症など原因の明らかでないものもある。急死。頓死。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜん‐へんい【突然変異】
(mutation)親と明らかに異なった形質が、突然、子孫や枝葉に出現、または親の形質が消失し、それが遺伝する現象。遺伝子の変化に起因する。広義には染色体の変化によるものも含める。放射線の照射などで人工的に起こしたものを人為突然変異という。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
生物の進化を説明する学説の一つ。1901年、ド=フリースによって提唱された。突然変異による新種の出現を認め、自然淘汰には重きをおかない。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
(mutant)突然変異した遺伝子をもつ個体または細胞。ミュータント。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつ‐たかっけい【凸多角形】‥カク‥
すべての内角が凸角(180度よりも小さな角)をなす多角形。↔凹多角形
とっ‐たり
(大声で「捕とったり」と怒鳴るからいう)
①捕手とりての役人。とりかた。「とった」とも。
②歌舞伎で、大勢出てくる捕手の役。転じて、下級役者の称。
③(2が常に演ずるからいう)とんぼがえり。
④相撲の手の一つ。両手で相手の片腕を抱え込むようにし、同時に足を踏み込み、肩を相手の腕のつけ根に押し当てて捻ひねり倒すもの。→逆とったり
とったり
とっ‐たん【突端】
つき出たはし。とっぱな。「岬の―」
どっ‐ち【何方】
〔代〕
(ドチの促音化)どちら。
⇒どっち‐つかず【何方付かず】
⇒どっち‐みち【何方道】
⇒何方へ転んでも
⇒何方もどっち
どっち‐つかず【何方付かず】
いずれとも定まらず、あいまいなこと。「―の態度」
⇒どっ‐ち【何方】
②縦縞状に多くの独鈷1の形を連ねた文様を織り出した厚地の琥珀こはく織や博多織の称。また、その文様。→一本独鈷。
③僧家で鰹節かつおぶしの隠語。
⇒とっこ‐いし【独鈷石】
⇒とっこ‐しょ【独鈷杵】
⇒とっこ‐れい【独鈷鈴】
どっこい
〔感〕
(「何処どこへ」の転)
①(→)「どっこいしょ」に同じ。
②相手の行動などをさえぎり止める時に発する語。「―そうはさせぬ」
③民謡などの囃子詞はやしことば。からめ節「お山繁昌と啼く烏、ハァ――」。「やっとこ―ほいさっさ」
⇒どっこい‐しょ
⇒どっこい‐どっこい
とっこ‐いし【独鈷石】トク‥
(ドッコイシとも)縄文時代後期・晩期の磨製石器の一種。形が独鈷1に似る。初めは一種の斧、のちには祭祀用となる。東日本で出土。雷鈷らいこ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
どっこい‐しょ
〔感〕
①力を入れる時、または大儀な時の掛け声。「―と立ち上がる」
②民謡などの囃子詞はやしことば。「草津よいとこ一度はおいで―」
⇒どっこい
どっこい‐どっこい
(「どっこい」の畳語)力や勢いがほぼ互角なさま。「―の力量」
⇒どっこい
とっ‐こう【特功】トク‥
特別にすぐれたいさお。
とっ‐こう【特効】トクカウ
特に著しいききめ。
⇒とっこう‐やく【特効薬】
とっ‐こう【特高】トクカウ
特別高等警察の略称。
とっ‐こう【特講】トクカウ
特別講義の略。
とっ‐こう【徳行】トクカウ
道徳にかなったよいおこない。「君子の―」
とっ‐こう【篤行】トクカウ
①篤実なおこない。人情に厚いおこない。「―の人」
②まじめで忠実なおこない。
とっ‐こう【篤厚】トク‥
人情にあついこと。懇切で実意のあること。
どっ‐こう【独行】ドクカウ
①自分一人で行くこと。みちづれなしに行くこと。
②他人の力を借りずに自分の力だけで行うこと。「独立―」
どっ‐こう【独航】ドクカウ
艦船が船団などに属さず、ただ1隻で航行すること。
⇒どっこう‐せん【独航船】
どっこう‐せん【独航船】ドクカウ‥
北洋の母船式サケ・マス漁業、カニ漁業などで、母船会社と買魚契約または傭船契約を結んで、母船に随伴し直接漁獲を行なった漁船。
⇒どっ‐こう【独航】
とっこう‐たい【特攻隊】トク‥
特別攻撃隊の略称。特に、太平洋戦争中、体当りの攻撃を行なった日本陸海軍の部隊。「神風―」
とっこう‐やく【特効薬】トクカウ‥
ある病気に対して著しくききめのある薬。
⇒とっ‐こう【特効】
とっこ‐しょ【独鈷杵】トク‥
(→)独鈷1に同じ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐こつ【突兀】
①山・岩などのけわしくそびえるさま。
②他にぬきんでて高いさま。
とっこ‐れい【独鈷鈴】トク‥
金剛鈴のうち、一端の把手とってが独鈷1の形をした法具。密教の修法で用いる。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐さ【咄嗟】
①舌うちして嘆くこと。また、息をはくこと。
②ちょっとの間。たちどころ。瞬間。易林本節用集「―、即時出来之義」。「―の間」「―の機転」「―に身をかわす」
とっさか【鶏冠】
(→)「とさか」に同じ。温故知新書「鶏坂冠、トツサカ」。狂言、鶏聟「紅葉にまがふ―蹴られては叶はじと」
⇒とっさか‐のり【鶏冠海苔】
とっ‐さか
心のとげとげしいさま。意地悪いさま。浄瑠璃、心中宵庚申「気の―な姑にせりせりいぢりたでられて」
とっさか‐のり【鶏冠海苔】
(→)「とさかのり」に同じ。
⇒とっさか【鶏冠】
とっ‐さき【突先】
突き出た先端。とがった端。
とっ‐さま【父様】
(トトサマの転)父の尊敬語。
どっさり
〔副〕
①数の多いさま。たくさん。花暦八笑人「おかかを―かいてくだつし」。「お土産―」
②重い物が落ちたり倒れたりするさま。どさり。どさっと。浮世風呂前「あふむけに―転ぶ」
ドッジ‐ボール【dodge ball】
二組に分かれてボールを投げ合い、相手の投球に当たらないようにしながら、より多くボールを相手側に当てた方を勝ちとする球戯。コートは円形と方形とがある。
とつ‐しゅうごう【凸集合】‥シフガフ
〔数〕平面または空間内の集合において、その集合の任意の2点を結ぶ線分がその集合に含まれるような集合。
とっ‐しゅつ【突出】
①突き破って出ること。また、だしぬけに飛び出すこと。「地下ガスの―」
②高く鋭く突き出ること。「―部」
③ほかのものよりいちだんと行動や状態が目立つこと。「―した軍事費」
とつ‐じょ【突如】
突然なさま。だしぬけなさま。「―立ち上がる」「―として現れる」
ドッジ‐ライン【Dodge's line】
1949年、GHQ経済顧問として来日したアメリカの銀行家ドッジ(Joseph Morrell D.1890〜1964)が日本経済の安定と自立のために与えた指示。また、その指示に従ってなされた財政金融引締め政策。
どっしり
①重くて据わりのよいさま。「―した家具」
②おもおもしく落ちついたさま。「―と構える」「―した態度」
とっ‐しん【突進】
勢いよくまっしぐらにつき進むこと。「ゴール目掛けて―する」
ドッジング【dodging】
サッカー・ラグビーなどで、相手をかわしながら前進すること。ドッジ。
とつ‐ぜん【突然】
にわかなさま。だしぬけ。不意。突如。「―の出来事」「―変心する」
⇒とつぜん‐し【突然死】
⇒とつぜん‐へんい【突然変異】
⇒とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
⇒とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
とつぜん‐し【突然死】
健康に見える人が突然死ぬこと。心臓・中枢神経・呼吸器などの疾患によるほか、乳幼児突然死症候群、青壮年のぽっくり病、特発性心筋症など原因の明らかでないものもある。急死。頓死。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜん‐へんい【突然変異】
(mutation)親と明らかに異なった形質が、突然、子孫や枝葉に出現、または親の形質が消失し、それが遺伝する現象。遺伝子の変化に起因する。広義には染色体の変化によるものも含める。放射線の照射などで人工的に起こしたものを人為突然変異という。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
生物の進化を説明する学説の一つ。1901年、ド=フリースによって提唱された。突然変異による新種の出現を認め、自然淘汰には重きをおかない。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
(mutant)突然変異した遺伝子をもつ個体または細胞。ミュータント。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつ‐たかっけい【凸多角形】‥カク‥
すべての内角が凸角(180度よりも小さな角)をなす多角形。↔凹多角形
とっ‐たり
(大声で「捕とったり」と怒鳴るからいう)
①捕手とりての役人。とりかた。「とった」とも。
②歌舞伎で、大勢出てくる捕手の役。転じて、下級役者の称。
③(2が常に演ずるからいう)とんぼがえり。
④相撲の手の一つ。両手で相手の片腕を抱え込むようにし、同時に足を踏み込み、肩を相手の腕のつけ根に押し当てて捻ひねり倒すもの。→逆とったり
とったり
とっ‐たん【突端】
つき出たはし。とっぱな。「岬の―」
どっ‐ち【何方】
〔代〕
(ドチの促音化)どちら。
⇒どっち‐つかず【何方付かず】
⇒どっち‐みち【何方道】
⇒何方へ転んでも
⇒何方もどっち
どっち‐つかず【何方付かず】
いずれとも定まらず、あいまいなこと。「―の態度」
⇒どっ‐ち【何方】
 ②縦縞状に多くの独鈷1の形を連ねた文様を織り出した厚地の琥珀こはく織や博多織の称。また、その文様。→一本独鈷。
③僧家で鰹節かつおぶしの隠語。
⇒とっこ‐いし【独鈷石】
⇒とっこ‐しょ【独鈷杵】
⇒とっこ‐れい【独鈷鈴】
どっこい
〔感〕
(「何処どこへ」の転)
①(→)「どっこいしょ」に同じ。
②相手の行動などをさえぎり止める時に発する語。「―そうはさせぬ」
③民謡などの囃子詞はやしことば。からめ節「お山繁昌と啼く烏、ハァ――」。「やっとこ―ほいさっさ」
⇒どっこい‐しょ
⇒どっこい‐どっこい
とっこ‐いし【独鈷石】トク‥
(ドッコイシとも)縄文時代後期・晩期の磨製石器の一種。形が独鈷1に似る。初めは一種の斧、のちには祭祀用となる。東日本で出土。雷鈷らいこ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
どっこい‐しょ
〔感〕
①力を入れる時、または大儀な時の掛け声。「―と立ち上がる」
②民謡などの囃子詞はやしことば。「草津よいとこ一度はおいで―」
⇒どっこい
どっこい‐どっこい
(「どっこい」の畳語)力や勢いがほぼ互角なさま。「―の力量」
⇒どっこい
とっ‐こう【特功】トク‥
特別にすぐれたいさお。
とっ‐こう【特効】トクカウ
特に著しいききめ。
⇒とっこう‐やく【特効薬】
とっ‐こう【特高】トクカウ
特別高等警察の略称。
とっ‐こう【特講】トクカウ
特別講義の略。
とっ‐こう【徳行】トクカウ
道徳にかなったよいおこない。「君子の―」
とっ‐こう【篤行】トクカウ
①篤実なおこない。人情に厚いおこない。「―の人」
②まじめで忠実なおこない。
とっ‐こう【篤厚】トク‥
人情にあついこと。懇切で実意のあること。
どっ‐こう【独行】ドクカウ
①自分一人で行くこと。みちづれなしに行くこと。
②他人の力を借りずに自分の力だけで行うこと。「独立―」
どっ‐こう【独航】ドクカウ
艦船が船団などに属さず、ただ1隻で航行すること。
⇒どっこう‐せん【独航船】
どっこう‐せん【独航船】ドクカウ‥
北洋の母船式サケ・マス漁業、カニ漁業などで、母船会社と買魚契約または傭船契約を結んで、母船に随伴し直接漁獲を行なった漁船。
⇒どっ‐こう【独航】
とっこう‐たい【特攻隊】トク‥
特別攻撃隊の略称。特に、太平洋戦争中、体当りの攻撃を行なった日本陸海軍の部隊。「神風―」
とっこう‐やく【特効薬】トクカウ‥
ある病気に対して著しくききめのある薬。
⇒とっ‐こう【特効】
とっこ‐しょ【独鈷杵】トク‥
(→)独鈷1に同じ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐こつ【突兀】
①山・岩などのけわしくそびえるさま。
②他にぬきんでて高いさま。
とっこ‐れい【独鈷鈴】トク‥
金剛鈴のうち、一端の把手とってが独鈷1の形をした法具。密教の修法で用いる。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐さ【咄嗟】
①舌うちして嘆くこと。また、息をはくこと。
②ちょっとの間。たちどころ。瞬間。易林本節用集「―、即時出来之義」。「―の間」「―の機転」「―に身をかわす」
とっさか【鶏冠】
(→)「とさか」に同じ。温故知新書「鶏坂冠、トツサカ」。狂言、鶏聟「紅葉にまがふ―蹴られては叶はじと」
⇒とっさか‐のり【鶏冠海苔】
とっ‐さか
心のとげとげしいさま。意地悪いさま。浄瑠璃、心中宵庚申「気の―な姑にせりせりいぢりたでられて」
とっさか‐のり【鶏冠海苔】
(→)「とさかのり」に同じ。
⇒とっさか【鶏冠】
とっ‐さき【突先】
突き出た先端。とがった端。
とっ‐さま【父様】
(トトサマの転)父の尊敬語。
どっさり
〔副〕
①数の多いさま。たくさん。花暦八笑人「おかかを―かいてくだつし」。「お土産―」
②重い物が落ちたり倒れたりするさま。どさり。どさっと。浮世風呂前「あふむけに―転ぶ」
ドッジ‐ボール【dodge ball】
二組に分かれてボールを投げ合い、相手の投球に当たらないようにしながら、より多くボールを相手側に当てた方を勝ちとする球戯。コートは円形と方形とがある。
とつ‐しゅうごう【凸集合】‥シフガフ
〔数〕平面または空間内の集合において、その集合の任意の2点を結ぶ線分がその集合に含まれるような集合。
とっ‐しゅつ【突出】
①突き破って出ること。また、だしぬけに飛び出すこと。「地下ガスの―」
②高く鋭く突き出ること。「―部」
③ほかのものよりいちだんと行動や状態が目立つこと。「―した軍事費」
とつ‐じょ【突如】
突然なさま。だしぬけなさま。「―立ち上がる」「―として現れる」
ドッジ‐ライン【Dodge's line】
1949年、GHQ経済顧問として来日したアメリカの銀行家ドッジ(Joseph Morrell D.1890〜1964)が日本経済の安定と自立のために与えた指示。また、その指示に従ってなされた財政金融引締め政策。
どっしり
①重くて据わりのよいさま。「―した家具」
②おもおもしく落ちついたさま。「―と構える」「―した態度」
とっ‐しん【突進】
勢いよくまっしぐらにつき進むこと。「ゴール目掛けて―する」
ドッジング【dodging】
サッカー・ラグビーなどで、相手をかわしながら前進すること。ドッジ。
とつ‐ぜん【突然】
にわかなさま。だしぬけ。不意。突如。「―の出来事」「―変心する」
⇒とつぜん‐し【突然死】
⇒とつぜん‐へんい【突然変異】
⇒とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
⇒とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
とつぜん‐し【突然死】
健康に見える人が突然死ぬこと。心臓・中枢神経・呼吸器などの疾患によるほか、乳幼児突然死症候群、青壮年のぽっくり病、特発性心筋症など原因の明らかでないものもある。急死。頓死。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜん‐へんい【突然変異】
(mutation)親と明らかに異なった形質が、突然、子孫や枝葉に出現、または親の形質が消失し、それが遺伝する現象。遺伝子の変化に起因する。広義には染色体の変化によるものも含める。放射線の照射などで人工的に起こしたものを人為突然変異という。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
生物の進化を説明する学説の一つ。1901年、ド=フリースによって提唱された。突然変異による新種の出現を認め、自然淘汰には重きをおかない。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
(mutant)突然変異した遺伝子をもつ個体または細胞。ミュータント。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつ‐たかっけい【凸多角形】‥カク‥
すべての内角が凸角(180度よりも小さな角)をなす多角形。↔凹多角形
とっ‐たり
(大声で「捕とったり」と怒鳴るからいう)
①捕手とりての役人。とりかた。「とった」とも。
②歌舞伎で、大勢出てくる捕手の役。転じて、下級役者の称。
③(2が常に演ずるからいう)とんぼがえり。
④相撲の手の一つ。両手で相手の片腕を抱え込むようにし、同時に足を踏み込み、肩を相手の腕のつけ根に押し当てて捻ひねり倒すもの。→逆とったり
とったり
とっ‐たん【突端】
つき出たはし。とっぱな。「岬の―」
どっ‐ち【何方】
〔代〕
(ドチの促音化)どちら。
⇒どっち‐つかず【何方付かず】
⇒どっち‐みち【何方道】
⇒何方へ転んでも
⇒何方もどっち
どっち‐つかず【何方付かず】
いずれとも定まらず、あいまいなこと。「―の態度」
⇒どっ‐ち【何方】
②縦縞状に多くの独鈷1の形を連ねた文様を織り出した厚地の琥珀こはく織や博多織の称。また、その文様。→一本独鈷。
③僧家で鰹節かつおぶしの隠語。
⇒とっこ‐いし【独鈷石】
⇒とっこ‐しょ【独鈷杵】
⇒とっこ‐れい【独鈷鈴】
どっこい
〔感〕
(「何処どこへ」の転)
①(→)「どっこいしょ」に同じ。
②相手の行動などをさえぎり止める時に発する語。「―そうはさせぬ」
③民謡などの囃子詞はやしことば。からめ節「お山繁昌と啼く烏、ハァ――」。「やっとこ―ほいさっさ」
⇒どっこい‐しょ
⇒どっこい‐どっこい
とっこ‐いし【独鈷石】トク‥
(ドッコイシとも)縄文時代後期・晩期の磨製石器の一種。形が独鈷1に似る。初めは一種の斧、のちには祭祀用となる。東日本で出土。雷鈷らいこ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
どっこい‐しょ
〔感〕
①力を入れる時、または大儀な時の掛け声。「―と立ち上がる」
②民謡などの囃子詞はやしことば。「草津よいとこ一度はおいで―」
⇒どっこい
どっこい‐どっこい
(「どっこい」の畳語)力や勢いがほぼ互角なさま。「―の力量」
⇒どっこい
とっ‐こう【特功】トク‥
特別にすぐれたいさお。
とっ‐こう【特効】トクカウ
特に著しいききめ。
⇒とっこう‐やく【特効薬】
とっ‐こう【特高】トクカウ
特別高等警察の略称。
とっ‐こう【特講】トクカウ
特別講義の略。
とっ‐こう【徳行】トクカウ
道徳にかなったよいおこない。「君子の―」
とっ‐こう【篤行】トクカウ
①篤実なおこない。人情に厚いおこない。「―の人」
②まじめで忠実なおこない。
とっ‐こう【篤厚】トク‥
人情にあついこと。懇切で実意のあること。
どっ‐こう【独行】ドクカウ
①自分一人で行くこと。みちづれなしに行くこと。
②他人の力を借りずに自分の力だけで行うこと。「独立―」
どっ‐こう【独航】ドクカウ
艦船が船団などに属さず、ただ1隻で航行すること。
⇒どっこう‐せん【独航船】
どっこう‐せん【独航船】ドクカウ‥
北洋の母船式サケ・マス漁業、カニ漁業などで、母船会社と買魚契約または傭船契約を結んで、母船に随伴し直接漁獲を行なった漁船。
⇒どっ‐こう【独航】
とっこう‐たい【特攻隊】トク‥
特別攻撃隊の略称。特に、太平洋戦争中、体当りの攻撃を行なった日本陸海軍の部隊。「神風―」
とっこう‐やく【特効薬】トクカウ‥
ある病気に対して著しくききめのある薬。
⇒とっ‐こう【特効】
とっこ‐しょ【独鈷杵】トク‥
(→)独鈷1に同じ。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐こつ【突兀】
①山・岩などのけわしくそびえるさま。
②他にぬきんでて高いさま。
とっこ‐れい【独鈷鈴】トク‥
金剛鈴のうち、一端の把手とってが独鈷1の形をした法具。密教の修法で用いる。
⇒とっ‐こ【独鈷】
とっ‐さ【咄嗟】
①舌うちして嘆くこと。また、息をはくこと。
②ちょっとの間。たちどころ。瞬間。易林本節用集「―、即時出来之義」。「―の間」「―の機転」「―に身をかわす」
とっさか【鶏冠】
(→)「とさか」に同じ。温故知新書「鶏坂冠、トツサカ」。狂言、鶏聟「紅葉にまがふ―蹴られては叶はじと」
⇒とっさか‐のり【鶏冠海苔】
とっ‐さか
心のとげとげしいさま。意地悪いさま。浄瑠璃、心中宵庚申「気の―な姑にせりせりいぢりたでられて」
とっさか‐のり【鶏冠海苔】
(→)「とさかのり」に同じ。
⇒とっさか【鶏冠】
とっ‐さき【突先】
突き出た先端。とがった端。
とっ‐さま【父様】
(トトサマの転)父の尊敬語。
どっさり
〔副〕
①数の多いさま。たくさん。花暦八笑人「おかかを―かいてくだつし」。「お土産―」
②重い物が落ちたり倒れたりするさま。どさり。どさっと。浮世風呂前「あふむけに―転ぶ」
ドッジ‐ボール【dodge ball】
二組に分かれてボールを投げ合い、相手の投球に当たらないようにしながら、より多くボールを相手側に当てた方を勝ちとする球戯。コートは円形と方形とがある。
とつ‐しゅうごう【凸集合】‥シフガフ
〔数〕平面または空間内の集合において、その集合の任意の2点を結ぶ線分がその集合に含まれるような集合。
とっ‐しゅつ【突出】
①突き破って出ること。また、だしぬけに飛び出すこと。「地下ガスの―」
②高く鋭く突き出ること。「―部」
③ほかのものよりいちだんと行動や状態が目立つこと。「―した軍事費」
とつ‐じょ【突如】
突然なさま。だしぬけなさま。「―立ち上がる」「―として現れる」
ドッジ‐ライン【Dodge's line】
1949年、GHQ経済顧問として来日したアメリカの銀行家ドッジ(Joseph Morrell D.1890〜1964)が日本経済の安定と自立のために与えた指示。また、その指示に従ってなされた財政金融引締め政策。
どっしり
①重くて据わりのよいさま。「―した家具」
②おもおもしく落ちついたさま。「―と構える」「―した態度」
とっ‐しん【突進】
勢いよくまっしぐらにつき進むこと。「ゴール目掛けて―する」
ドッジング【dodging】
サッカー・ラグビーなどで、相手をかわしながら前進すること。ドッジ。
とつ‐ぜん【突然】
にわかなさま。だしぬけ。不意。突如。「―の出来事」「―変心する」
⇒とつぜん‐し【突然死】
⇒とつぜん‐へんい【突然変異】
⇒とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
⇒とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
とつぜん‐し【突然死】
健康に見える人が突然死ぬこと。心臓・中枢神経・呼吸器などの疾患によるほか、乳幼児突然死症候群、青壮年のぽっくり病、特発性心筋症など原因の明らかでないものもある。急死。頓死。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜん‐へんい【突然変異】
(mutation)親と明らかに異なった形質が、突然、子孫や枝葉に出現、または親の形質が消失し、それが遺伝する現象。遺伝子の変化に起因する。広義には染色体の変化によるものも含める。放射線の照射などで人工的に起こしたものを人為突然変異という。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐せつ【突然変異説】
生物の進化を説明する学説の一つ。1901年、ド=フリースによって提唱された。突然変異による新種の出現を認め、自然淘汰には重きをおかない。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつぜんへんい‐たい【突然変異体】
(mutant)突然変異した遺伝子をもつ個体または細胞。ミュータント。
⇒とつ‐ぜん【突然】
とつ‐たかっけい【凸多角形】‥カク‥
すべての内角が凸角(180度よりも小さな角)をなす多角形。↔凹多角形
とっ‐たり
(大声で「捕とったり」と怒鳴るからいう)
①捕手とりての役人。とりかた。「とった」とも。
②歌舞伎で、大勢出てくる捕手の役。転じて、下級役者の称。
③(2が常に演ずるからいう)とんぼがえり。
④相撲の手の一つ。両手で相手の片腕を抱え込むようにし、同時に足を踏み込み、肩を相手の腕のつけ根に押し当てて捻ひねり倒すもの。→逆とったり
とったり
とっ‐たん【突端】
つき出たはし。とっぱな。「岬の―」
どっ‐ち【何方】
〔代〕
(ドチの促音化)どちら。
⇒どっち‐つかず【何方付かず】
⇒どっち‐みち【何方道】
⇒何方へ転んでも
⇒何方もどっち
どっち‐つかず【何方付かず】
いずれとも定まらず、あいまいなこと。「―の態度」
⇒どっ‐ち【何方】
[漢]毒🔗⭐🔉
毒 字形
 筆順
筆順
 〔毋部4画/8画/教育/3839・4647〕
〔音〕ドク(呉)
[意味]
①生命や健康を害する物質。人の生命を奪うための薬物。「毒にも薬にもならぬ」「毒を以もって毒を制す」(悪を用いて他の悪を除く)「毒素・毒殺・服毒・中毒・解毒げどく」
②人の心をきずつける。わざわいをもたらす。「世間を毒する」「毒舌・毒筆・毒婦・害毒」
[解字]
会意。「生」(=めばえる)の変形+「母」(=子をうむ)。強精の作用のある薬草の意。刺激が強く害もあることから、ひどい害を及ぼす薬草・薬物の意となる。
[下ツキ
煙毒・鉛毒・害毒・劇毒・解毒・鉱毒・抗毒素・死毒・消毒・身毒・瘡毒・胎毒・丹毒・中毒・蠹毒・尿毒症・黴毒・梅毒・病毒・服毒・防毒・無毒・猛毒・薬毒・有毒・余毒・淋毒
〔毋部4画/8画/教育/3839・4647〕
〔音〕ドク(呉)
[意味]
①生命や健康を害する物質。人の生命を奪うための薬物。「毒にも薬にもならぬ」「毒を以もって毒を制す」(悪を用いて他の悪を除く)「毒素・毒殺・服毒・中毒・解毒げどく」
②人の心をきずつける。わざわいをもたらす。「世間を毒する」「毒舌・毒筆・毒婦・害毒」
[解字]
会意。「生」(=めばえる)の変形+「母」(=子をうむ)。強精の作用のある薬草の意。刺激が強く害もあることから、ひどい害を及ぼす薬草・薬物の意となる。
[下ツキ
煙毒・鉛毒・害毒・劇毒・解毒・鉱毒・抗毒素・死毒・消毒・身毒・瘡毒・胎毒・丹毒・中毒・蠹毒・尿毒症・黴毒・梅毒・病毒・服毒・防毒・無毒・猛毒・薬毒・有毒・余毒・淋毒
 筆順
筆順
 〔毋部4画/8画/教育/3839・4647〕
〔音〕ドク(呉)
[意味]
①生命や健康を害する物質。人の生命を奪うための薬物。「毒にも薬にもならぬ」「毒を以もって毒を制す」(悪を用いて他の悪を除く)「毒素・毒殺・服毒・中毒・解毒げどく」
②人の心をきずつける。わざわいをもたらす。「世間を毒する」「毒舌・毒筆・毒婦・害毒」
[解字]
会意。「生」(=めばえる)の変形+「母」(=子をうむ)。強精の作用のある薬草の意。刺激が強く害もあることから、ひどい害を及ぼす薬草・薬物の意となる。
[下ツキ
煙毒・鉛毒・害毒・劇毒・解毒・鉱毒・抗毒素・死毒・消毒・身毒・瘡毒・胎毒・丹毒・中毒・蠹毒・尿毒症・黴毒・梅毒・病毒・服毒・防毒・無毒・猛毒・薬毒・有毒・余毒・淋毒
〔毋部4画/8画/教育/3839・4647〕
〔音〕ドク(呉)
[意味]
①生命や健康を害する物質。人の生命を奪うための薬物。「毒にも薬にもならぬ」「毒を以もって毒を制す」(悪を用いて他の悪を除く)「毒素・毒殺・服毒・中毒・解毒げどく」
②人の心をきずつける。わざわいをもたらす。「世間を毒する」「毒舌・毒筆・毒婦・害毒」
[解字]
会意。「生」(=めばえる)の変形+「母」(=子をうむ)。強精の作用のある薬草の意。刺激が強く害もあることから、ひどい害を及ぼす薬草・薬物の意となる。
[下ツキ
煙毒・鉛毒・害毒・劇毒・解毒・鉱毒・抗毒素・死毒・消毒・身毒・瘡毒・胎毒・丹毒・中毒・蠹毒・尿毒症・黴毒・梅毒・病毒・服毒・防毒・無毒・猛毒・薬毒・有毒・余毒・淋毒
大辞林の検索結果 (50)
どく【毒】🔗⭐🔉
どく [2] 【毒】
(1)生体,特に人体に有害な物質。特に,少量でも人命にかかわる作用を及ぼし得る物質。「―入りの饅頭(マンジユウ)」「―を盛る」「―を呷(アオ)る」
(2)健康・生命をそこなうおそれのあるもの。「勉強ばかりしていては,体に―だ」
(3)ためにならないもの。わざわいとなるもの。害悪。「目の―」「この本は子供には―だ」
(4)人の心を傷つけるもの。悪意。「―を含んだ言葉」
どく=にも薬にもならない🔗⭐🔉
――にも薬にもならない
害にもならないが,かといって役に立つわけでもない。
どく=を食らわば皿まで🔗⭐🔉
――を食らわば皿まで
〔いったん,毒を食らうからには,それを盛った皿までなめるという意〕
一度罪悪を犯したからには,徹底的に罪悪を重ねる。毒食らわば皿まで。「もうこうなったら,―だ」
どく=を以(モツ)て毒を制する🔗⭐🔉
――を以(モツ)て毒を制する
悪いことをなくすために,他の悪いことを利用する。悪人を除くのに,他の悪人を使うようなこと。
どく-あく【毒悪】🔗⭐🔉
どく-あく [0] 【毒悪】 (名・形動)[文]ナリ
はなはだしく害をなす・こと(さま)。「―な眼を張て凝視(ミツ)め/罪と罰(魯庵)」
どく-いみ【毒忌み】🔗⭐🔉
どく-いみ [4][0] 【毒忌み】
主として服薬のとき,差し障りがあるものを飲食しないこと。
どく-うつぎ【毒空木】🔗⭐🔉
どく-うつぎ [3] 【毒空木】
ドクウツギ科の落葉低木。日当たりのよい山地に自生。高さ1メートル内外。葉は広披針形で三脈が目立つ。雌雄同株。春,葉に先立ち黄緑色の小花を総状花序につける。果実は球形で赤く,紫黒色に熟し多肉質多汁で甘いが猛毒を含む。イチロベゴロシ。
毒空木
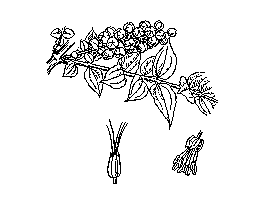 [図]
[図]
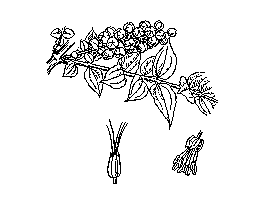 [図]
[図]
どく-え【毒荏】🔗⭐🔉
どく-え [2][0] 【毒荏】
植物アブラギリの別名。
どく-えき【毒液】🔗⭐🔉
どく-えき [2][0] 【毒液】
毒を含む液体。毒汁。
どく-えん【毒煙】🔗⭐🔉
どく-えん [0] 【毒煙】
有毒物質を含んだ煙。毒ガス。
どく-が【毒牙】🔗⭐🔉
どく-が [1] 【毒牙】
(1)毒蛇などがもつ,かみついた時に毒液を出すきば。
(2)悪だくみを含んだむごい手段。悪辣(アクラツ)な企て。毒手。「悪の―にかかる」
どく-が【毒蛾】🔗⭐🔉
どく-が [0][2] 【毒蛾】
(1)ドクガ科に属するガの総称。ドクガ・チャドクガ・マイマイガなど。
(2){(1)}の一種。開張約4センチメートル。全身濃黄色で前ばね中央に褐色帯がある。七月頃出現して灯火に飛来する。幼虫はサクラ・クヌギなどを食害する毛虫で,黒色の地に橙色の紋がある。幼虫・成虫とも毒毛をもち,これに触れると激しいかゆみに襲われる。日本全土と東アジアに分布。
どく-がい【毒害】🔗⭐🔉
どく-がい [0] 【毒害】 (名)スル
毒を飲ませて殺すこと。毒殺。「ひそかに王妃を―する」
どく-ガス【毒―】🔗⭐🔉
どく-ガス [0] 【毒―】
人体または動植物に対して毒性を有し,戦争の手段として用いられる気体物質,または気化あるいは霧状にして散布しやすい物質。その毒性から,窒息性・糜爛(ビラン)性・神経性・催涙性・嘔吐性などに分類される。第一次大戦でドイツ軍が塩素ガスを用いたのが最初とされる。
どく-ぎょ【毒魚】🔗⭐🔉
どく-ぎょ [1] 【毒魚】
毒をもつ魚。フグのように体の一部に毒のあるもの,エイ・ゴンズイ・オコゼのように毒のとげをもつものなどがある。
どく-ぐち【毒口】🔗⭐🔉
どく-ぐち [2] 【毒口】
毒舌。悪口。悪たれ口。「―をたたく」
どく-げきぶつ【毒劇物】🔗⭐🔉
どくげきぶつ-とりしまりほう【毒劇物取締法】🔗⭐🔉
どくげきぶつ-とりしまりほう ―ハフ 【毒劇物取締法】
「毒物及び劇物取締法」の略称。
どく-げん【毒言】🔗⭐🔉
どく-げん [0] 【毒言】
毒舌。毒口(ドクグチ)。
どく-さ【毒砂】🔗⭐🔉
どく-さ [0] 【毒砂】
硫ヒ鉄鉱の俗称。
どく-ざい【毒剤】🔗⭐🔉
どく-ざい [0] 【毒剤】
「毒薬(ドクヤク)」に同じ。
どく-ささこ【毒笹子】🔗⭐🔉
どく-ささこ [3] 【毒笹子】
担子菌類ハラタケ目のきのこ。傘の直径5〜10センチメートル。柄の長さ5〜8センチメートル。傘はやや漏斗状に凹み,表面は淡橙黄色,後に橙褐色。裏面は密に褶(ヒダ)を生じ,帯黄色であるが胞子紋は白い。食べると,数日して四肢の先端がはれ火傷のような激痛が一か月も続くため,ヤケドキン・ヤイトタケの別名がある。
どく-さつ【毒殺】🔗⭐🔉
どく-さつ [0] 【毒殺】 (名)スル
毒薬で殺すこと。「―事件」「奸臣に―される」
どく-し【毒死】🔗⭐🔉
どく-し [0] 【毒死】 (名)スル
毒薬によって死ぬこと。
どく-しば【毒柴】🔗⭐🔉
どく-しば [0] 【毒柴】
アセビの異名。
どく・する【毒する】🔗⭐🔉
どく・する [3] 【毒する】 (動サ変)[文]サ変 どく・す
悪い影響を与える。そこなう。「青少年を―・する悪書」
どく-ぜり【毒芹】🔗⭐🔉
どく-ぜり [2][0] 【毒芹】
セリ科の多年草。水辺に自生。若苗はセリに似るが大形で香りがない。茎は高さ約80センチメートルで,二回羽状複葉。夏,多数の白色の小花を複散形花序につける。全草,特に根茎に猛毒がある。また,根茎は竹の根に似,延命竹・万年竹などの名で盆栽にする。
毒芹
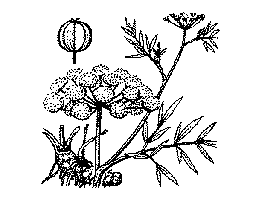 [図]
[図]
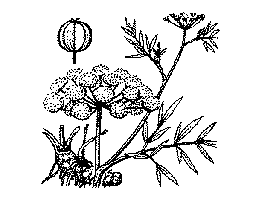 [図]
[図]
どく-ち【毒血】🔗⭐🔉
どく-ち [0][3] 【毒血】
病毒を含んだ血。悪血。
どく-べにたけ【毒紅茸】🔗⭐🔉
どく-べにたけ [3][4] 【毒紅茸】
担子菌類ハラタケ目のきのこ。林地の地上に孤生する。傘は径4〜10センチメートルのまんじゅう形,または浅い漏斗形で紅色。ひだ・柄は白色でもろく,辛みがあるが毒性はない。
毒紅茸
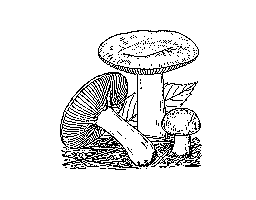 [図]
[図]
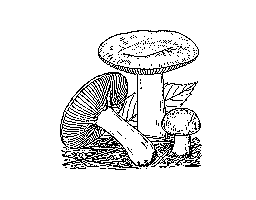 [図]
[図]
どく-へび【毒蛇】🔗⭐🔉
どく-へび [0] 【毒蛇】
有鱗目ヘビ亜目の爬虫類のうち,毒腺を有し毒牙をもつヘビの総称。毒には神経系に作用する神経毒と,血液組織を破壊する出血毒とがある。コブラ・アマガサヘビ・ウミヘビなどは神経毒成分が多く,マムシ・ハブ・ガラガラヘビなどは出血毒成分が多い。日本に生息するものではマムシとハブ。どくじゃ。
どく-み【毒味・毒見】🔗⭐🔉
どく-み [3][0] 【毒味・毒見】 (名)スル
(1)飲食物を他人にすすめる前に,毒のあるなしをみること。「前もって―する」「―役」
(2)飲食物の味加減をみること。
どっ-き【毒気】🔗⭐🔉
どっ-き ドク― [0] 【毒気】
(1)毒になる気体。毒を含んだ気体。
(2)「どっけ(毒気)」に同じ。
どっき=を抜か れる🔗⭐🔉
れる🔗⭐🔉
――を抜か れる
⇒どっけ(毒気)を抜かれる
れる
⇒どっけ(毒気)を抜かれる
 れる
⇒どっけ(毒気)を抜かれる
れる
⇒どっけ(毒気)を抜かれる
どっ-く【毒鼓】🔗⭐🔉
どっ-く ドク― [0] 【毒鼓】
〔仏〕 毒を塗った太鼓の意で,その音を聞く者はみな死ぬという。仏の教えが人々のもつ煩悩(ボンノウ)を完全に打破することにたとえる。
どっ-け【毒気】🔗⭐🔉
どっ-け ドク― [0][3] 【毒気】
〔「どくけ」とも〕
(1)毒となる成分。毒を含んだ気。どっき。「―の多い植物」
(2)他人の気持ちを傷つけるような心。悪意。
どっけ=に当て られる🔗⭐🔉
られる🔗⭐🔉
――に当て られる
相手の人を食ったような言動を目前にして唖然(アゼン)とする。
られる
相手の人を食ったような言動を目前にして唖然(アゼン)とする。
 られる
相手の人を食ったような言動を目前にして唖然(アゼン)とする。
られる
相手の人を食ったような言動を目前にして唖然(アゼン)とする。
どっけ=を抜か れる🔗⭐🔉
れる🔗⭐🔉
――を抜か れる
相手をやり込めようと勢い込んでいた人が,予想外の出方をされたために気勢をそがれ,おとなしくなる。どっきをぬかれる。
れる
相手をやり込めようと勢い込んでいた人が,予想外の出方をされたために気勢をそがれ,おとなしくなる。どっきをぬかれる。
 れる
相手をやり込めようと勢い込んでいた人が,予想外の出方をされたために気勢をそがれ,おとなしくなる。どっきをぬかれる。
れる
相手をやり込めようと勢い込んでいた人が,予想外の出方をされたために気勢をそがれ,おとなしくなる。どっきをぬかれる。
どっけつ-しょう【毒血症】🔗⭐🔉
どっけつ-しょう ドクケツシヤウ [0] 【毒血症】
「毒素血症」に同じ。
どく【毒】(和英)🔗⭐🔉
どく【毒】
(a) poison;→英和
harm (害).→英和
〜する[である]poison;doharm;be bad.〜がまわる The poison takes effect.〜のある poisonous;→英和
harmful (有害な).〜を飲む take poison.〜を盛る(った) poison (poisoned).‖毒をもって毒を制す Like cures like.
どくが【毒牙にかかる】(和英)🔗⭐🔉
どくが【毒牙にかかる】
fall a victim.→英和
どくガス【毒ガス】(和英)🔗⭐🔉
どくガス【毒ガス】
(a) poison gas.〜でやられる be gassed.
どくさつ【毒殺する】(和英)🔗⭐🔉
どくさつ【毒殺する】
killby means of poison;→英和
poison.
どくじゃ【毒蛇】(和英)🔗⭐🔉
どくじゃ【毒蛇】
a venomous snake.
どくする【毒する】(和英)🔗⭐🔉
どくする【毒する】
⇒毒.
どくづく【毒づく】(和英)🔗⭐🔉
どくづく【毒づく】
⇒毒舌.
広辞苑+大辞林に「毒」で始まるの検索結果。もっと読み込む